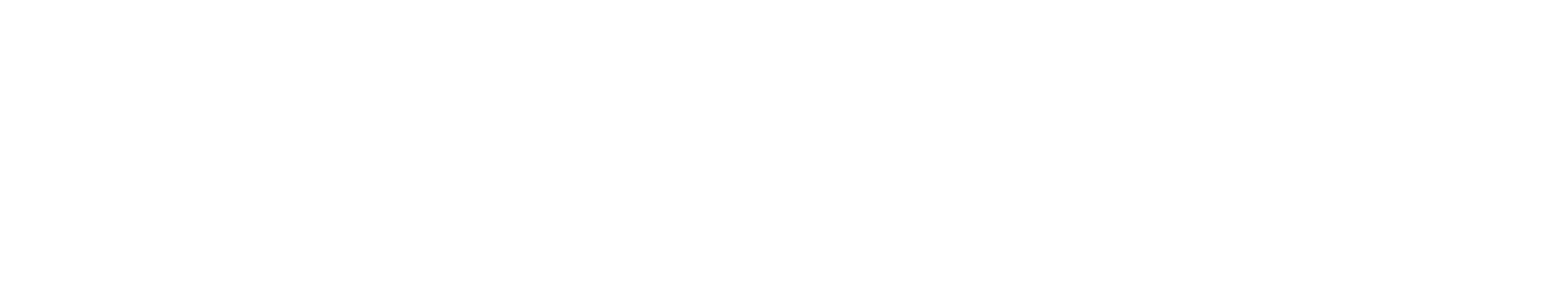院内通信 過食の問題
過食の問題-その1 2007年3月29日
注釈:以下はAさんのお話をそのままではなく、話の筋道は残したまま架空の物語にアレンジしたものです。
30代の主婦、Aさんが、「この何週間か過食が止まっています、こんなことは、はじめてです」といいます。
過食がはじまったのは、17歳のときです。
当時、両親の仲が険悪で、別れ話も持ち上がっていました。母親が家を出て行ったらどうしよう、父親と二人になったらどうしよう、と悩んでいました。そういう折に、甘い物が無性に欲しくなりました。そして、甘いものを口にすると、そのあいだは不安を忘れていられるのです。過食は、そのときからの問題です。
Aさんは、過食をしなくなった後の心を、次のように説明してくれました。
前々から、寂しさ、悲しみ、孤独感、虚しさ・・・という感情に悩まされ、そういう心があるのは、十分すぎるくらい分かっているつもりでした。 でも、いまにして思うのですが、それは頭だけの理解でした。
喩えていえば、冷たい水に手を入れて「冷たい」と感じていたけれど、それはビニール手袋をした手で、「冷たい」と感じていたのに似ていたと思います。いまは、素手で冷たさをじかに感じることができています。そのように実感するようになってから、自分がいとおしく、抱きしめてやりたい気持ちになるのです。また、それと共に、いままでは治療者にずいぶん頼っていたのが分かってきました。そんなふうに考えているつもりはなかったけれど、無意識のうちに、「治してください」という気持ちだったと、いまは分かります。そして、それはおかしい、これは自分の問題で、解決をはかる主体は自分ではないかと、いまは思えるようになっています。いまでも、甘い物が欲しくなります。でも、それを我慢することができます。できてしまえば当たり前のことと思うのですが、過食をやめられなかったころを思えば、不思議な気がします。
こういうふうに、心に重大な変化が起こってから、自分が、何だか、私自身の母親であるように感じています。そして、過食をしていたころの私は、自分に対してひどいことをする母親だったのかと、改めて思います。そう思うのは、何故ともなく、次のようなイメージが浮かんでくるからです。
心に地下室があって、そこに何か大切なものを、自分でも気づかずに閉じ込めてしまっているというイメージです。
その部屋の内情をうすうす感じていたのですが、それを知るのが怖いので、見て見ぬふりをしていたように思います。その理不尽さに、恐怖と後ろめたさがあり、それを知りたくないと無意識的に思っていたような気がしています。さきほど、ビニールの手袋をはめた手で触れた、冷たい水の感触のようなといったのは、地下室の扉ごしに感じていた感情のことだったのかもしれません。そして、扉が開き、直接、そこに閉じ込めていた感情たちに触れることができたような感じです。
私が扉を開けたつもりはないのですが、私以外にそれをできる人はないですよね。誰か助けてくださいと思っているあいだは、私は哀れな被害者の気分でいたのが、自分を助けることができるのは私自身なのだと気がついたときに、扉を開ける勇気が出たのかもしれません。そのように連想が働いて、結局、地下室に閉じ込めていたのも、それを解放したのも私なんだと得心ができます。そして、そういうことをした私が親で、地下室に閉じ込めてしまっていた感情たちは、私の子ということになるのでしょうか。そう考えると、その子たちを救い出していとおしく思っているのも、納得がいくのです。閉じ込めて、いってみればネグレクトしていたのも、救い出して抱きしめてやりたくなったのも、おなじ私なんですね。そう考えてみて一応の納得はできたのですが、何のために可哀想な子供たちを地下室に閉じ込めるようなことをしたのか、何のために自分で自分を苦しめるようなことをしてきたのか、それが分かりません。宝物のような子供たちをひどい目に遭わせて、それをよしとしていた私って、何なのだろうと不思議に思います。
過食の問題-その2 2007年4月14日
過食の悩みは、真に悩みを悩めないでいる人の悩みです。だから、その悩み方がつづくかぎり、過食は繰り返されると思います。真に悩んでいないなどといえば、地獄の苦しみの中にいる過食症者に、とんでもなくひどいことをいう奴だと思われるかもしれません。
しかし、苦しむことと悩むこととは違います。やはり、真正に悩めないでいる悩みだと、私は思います。そういう悩み方からは、希望の光がほとんど見込めません。逆にいえば、真正に悩まれた悩みであるときに、その果てに希望の光が見えてくると、かなりの確度で保証されるのです。これら二つの違いは、問題の核心を直視しようとしているか、避けようとしているかというところにあります。過食症の治療が難しい理由は、ここにあります。核心から眼をそらして食に取りすがっているのが過食なので、ここに見られるのは問題の隠蔽と、代理満足への回避とです。つまり問題のすり替えが起こっています。そして、そのことへの自覚が、当然ながらありません。
いくらかはあるとしても、それを隠蔽しようとする気持ちが上回るのです。過食は、より大きな問題から眼をそらす(悩みを悩まない)代理満足ですけれど、それも満足の一つには違いありません。刹那的ではあっても、それなりの満足が得られます。しかし、核心から眼をそらしている代償として、本来もとめているはずの満足には、決して至り得ないのです。また、過食によって得られるのは身体的な満足に過ぎません。そして、本当は、もっと精神的に意味のある満足を希求しているので、「いくら食べても満足できない」し、「満腹感が得られない」のです。そもそも人の満足は、健全なものであれば、精神的?身体的なものです。知的な満足であっても、身体的な興奮を伴い、単純に精神的な満足に留まるものではありません。その精神的?身体的なものの一方が欠落する場合は、必ず病的な問題が起こっていると考えなければなりません。
そして、欠落するとすれば精神的なそれであり、病的な満足の形態は、身体的な満足に偏する場合にかぎります。それは、必ず非社会的なものか、反社会的なものといえます。セクハラ、痴漢は犯罪ですし、人にいえない恥ずかしいことである過食は、非社会的な行動です。それらには、共に精神性がありません。心には、表と裏(無意識の領域)とがあり、前者は社会的な心で、後者は非社会的な心です。そして、社会性と精神性、非社会性と非精神性とは、それぞれ一対の関係です。非社会的な心である裏の人格は、自我によって抑圧され、受容されなかった心です。過食は非社会的な行動なので、「人にいえない」性格を持っています。一般には、過食をした人は、「卑しい大食漢」という汚名を、他でもなく、自分で自分自身に着せるものです。
その罪悪感が、また、大きな苦しみになります。しかし、ここには自我が抑圧した心たちの反作用である、という反省がありません。それは見方を換えれば、自我はそれらの分身たちの反攻に遭って、それを受け止める能力を欠いているということです。罪悪感は、一つには、不当な抑圧をしたことへの、自我の無意識的態度に起因しますが、もう一つは、「人に見せられない行動が現に起こっている」ことに、責任を取れないところにあります。過食症者は、一般に、人への気遣いがつよく、人の批判的態度を過敏に怖れるので、「表に現われてしまっている人に見せられないこと」を、まるで大勢から一斉に非難されているかのように恥じ入るのです。
過食の問題-その3 2007年5月8日
「いつも、いつも、ここ(クリニック)に来るたびにおんなじことばっかりいって、・・・少しも進歩しない・・・」と、Aさんがいいます。そして、「過食をやめようと思えばできるのに、やろうとしない」と、涙ながらに語ります。こういう気持ちはAさんだけのものではなく、多かれ少なかれ、過食に悩む人たちに共通しているのではないかと思います。
「おんなじことばかりいって、・・・少しも進歩しない・・・」という言葉には、怒りが込められています。その怒りは、二つの方向に向かっていると思われます。一つは過食をやめる意志を持とうとしないAさん自身へのものでしょうし、もう一つは、「治す力を示せない」治療者へのものでしょう。
過食に向かうエネルギーは、とても大きなものです。心を、馬(無意識)にまたがる騎手(自我)と比喩的に捉えると、過食は無力な騎手を後目に、馬が勝手に行動を起こしている姿になります。人馬一体を理想として、騎手が馬をコントロールするのが心の問題の鉄則ですから、馬が騎手を無視した行動に出るのは、あってはならないことです。過食では、そのような、あってはならないことが起こっています。この比喩でいえば、あってはならない行動に出ている馬は、怒っているに違いありません。
そして、騎手がまったくの無力であることは、それとの相対関係で、馬の怒りを怖れている姿でもあるのです。過食の行動は、怒った馬が恐れをなしている騎手を後目に、暴走している図式になります。以上のことは比喩に過ぎませんが、心の問題は抽象的になりがちなので、比喩的な絵として捉えてみるのは意味があることです。また、比喩的な絵は直感に訴えるので、冗長になりがちな説明を補足する意味を持ちます。
過食は、ふつうの意味での食への欲求の強さと、その反映ではありません。ふつうの意味でなら、旺盛な食欲は否定されるべきものではありません。それは、いうならば、生きる意志の強さの現われです。しかし、過食においては旺盛な食欲というものではなく、精神的に満たされない鬱憤が溜まっているために、そして、それが満たされる希望が見えないために、当てにならない騎手を後目に、馬が鬱憤のはけ口を求めた行動に出ているというような出来事です。
つけ加えれば、自我である騎手が、満足や希望や安心をもたらす役目を担っているにも拘わらず、長期にわたって主体性を発揮する様子が見えず、その見込みも持てないので、業を煮やした馬が暴走しはじめたということになります。旺盛な食欲が生きる意志の強さを現していることに対応して、過食は死への斜傾を意味します。それは以下のような事情によります。
そもそも、生きることは死ぬことを含んでいます。単純な生はなく、死があればこその生です。赤ん坊の誕生は、生命の誕生です。赤ん坊が犬の子でもなく、猫の子でもなく、人間の子であるのを証明するのは、自我によってです。自我は人間を特徴づけるものですが、そのために他の動物たちが自然のものであるのに対して、唯一人間が反自然の性格を合わせ持っています。
反自然的性格とは、一つには本能の命じるままに生きるわけにはいかないという意味がありますが、それは自我が本能に従う装置ではなく、本能を引き受ける主体であることに由来しています。換言すると、自我は本能への従属者ではなく、本能を引き受け、改めて本能をいかに生きるかを主題化する主体であるということです。ことは本能にとどまらず、心にとって自然的なものを、自我はすべておなじ扱い方をします。
しかしながら、このように自我はひとまずは自然のしもべではないのですが、めぐり巡って結局は自然のしもべであるのを思い知るしかないという不可思議な役割を与えられている、と考えるしかありません。そのことを忘れると、人間は(自我に拠って)自然から解離した独自の存在者である、という趣きが人間を驕らせ、災いをもたらします。それは、あたかも、孫悟空が大暴れをして、三蔵法師とは独立した力を発揮しているつもりが、気がつくと三蔵法師の手の内で暴れていたに過ぎなかったというのに似ているように思えます。昨今、異常気象が問題になり、地球環境の危機が叫ばれています。それは、自然に対する人間の驕りが、自分自身への災いとなって跳ね返っている一つの表われ、と要約できるような出来事です。
過食の問題-その4 2007年5月14日
無意識の層は、二種に分かれます。第一のものは、大自然が心に及んでいる層です。大自然といういい方には、ふつうでいう自然ではないという意味が込められております。
それは名状し難いものです。ふつうでいう自然、すべての動物、植物、生きとし生けるもの、あの山、この山、地球、星々、宇宙などなど、知覚できるあらゆるもの、想像できるかぎりのものなど、どこまでと限定できないあらゆること、あらゆるもの、というようなことです。一言でいえば、全です。別ないい方をすると、無です。全と無とは、両極端にあるもののようですが、我われ人間には、両者の区別をつけることができません。そのような意味での大自然が心に及んでいるのが、第一の無意識層です。大自然という、茫漠を通り越した名状し難いものが心に及んでいるものを、いうならば大海が陸地に及び、囲われて湾となったような、と比喩的に捉えておきます。ということは、(第一の)無意識は大自然そのものではなく、心という限定を受けたもので、いうならば大自然の意向を受けつつ、心にそれを繋いでいく性格を担っていると考えてよいと思います。そう考える根拠は、精神の病理現象を理解しようと努める過程で、それが合理的であるということです。
ひとり一人の自己は、有限の生命を担っています。その限定は、身体に拠っているように見えます。身体が朽ち、滅びたときに、それぞれの自己は終焉にいたります。それは自我も同様で、人の誕生は自我の誕生であり、人の命の終焉は自我の終焉です。このことから自我は、身体的な基盤の上にあると推測されるのです。また、一方で、心には個々人の限定を超えたものがあると判明しております。例えば、ユングによる元型は、そういう性格のものです。また人間が持っている信仰心は、自己を超えた存在、いうならば全なるものを崇敬するという形での心的な連携、といえるのかもしれません。しかし、それは心にとっての外的な関係、つまり心に内的な根拠がない関係、としては理解ができません。
崇敬する対象が外的なものであるにせよ、ないにせよ、心の内部に感受するものがなければ、生きた関係になることはできないだろうからです。それぞれの自己の内奥にこそ、全なるものに感応する心が潜在しており、それによって、はじめて何か外的な超越者との連携が可能になるに違いありません。この想定される内的な根拠が、大自然が心に及んでいるものに関連していると考えられるのです。
そのように、心には個という限定を超越したものが入り込んでおります。そのようなことから、身体と心という関連だけでは、心の諸現象を解いていくことができないのです。身体は、先の比喩でいえば陸地に似ています。そもそも、心とか精神とかいうものは、無形状で、掴み所がありません。しかし、人間は身体的存在でもあります。
そのために、心を身体的、形状的な側面から見ることは、ある程度可能です。例えば、喜怒哀楽を、それらの人物像として、絵に描いて表現することは可能です。身体的実体のない幽霊でさえ絵に描かれます。心の諸現象を、何らか知覚的に表現することは可能なので、次のようにいうことが許されるのではないかと思います。
精神は限定化、実体化されることで精神であることが可能になるが、その限定化、実体化するのは身体に拠ってである、と。
自我は、意識化が可能なかぎりでの世界の、あるいは意識できるかぎりでの世界の主宰者です。更にいえば、意識は、何ものかについての意識である、といえます。その何ものかという意識の対象が、限定化と実体化とを保証し、意味と充実と意識を繋ぎとめる安心とをもたらします。
過食の問題-その5 2007年5月27日
先に述べた比喩的モデルをまとめると、以下の通りです。
①大自然である全なる大海がある。
②大海に浮かんでいる島がある(自我、身体)。
③その島には湾がある(無意識)。
①は全または無の世界です。それぞれの自己は、「かのような存在」と名指しできる、限定化された有の存在です。自己は意識で捉えることができるかぎりでの世界、つまり現象的世界の住人です。全と無とは、「かのような存在」である現象的実体としては存在していません。それは、「かのようにと名指しできるものは何もない」ので、いわば一者性の性格のものです。②と③は有機的な関連を持ち、心という総合体を形成しています。心は身体という衣装を身にまとっているかぎり、明確に限定化されています。
それは、「何もない」無(または全)から生じた「かのようにと名指しできる」有の存在です。その有の世界は、湾である無意識を抱え持っています。つまり心は、身体と自我とによって限定化されていますが、大自然のものである全(または無)の性格をも併せ持っています。結局、心は有と無との二項が対立する二者性の性格を持っていることになります。
以上のことは、広義の心理学が蓄積してきたものと、精神の病理現象を理解する努力と、その理解が治療的に還元された事実との上に成り立つ仮説を、比喩的に図式化したものです。
それぞれの自己の誕生は、全なる大海のただ中に、湾を持つ島が生まれることと、比喩的にいうことができます。その島を宰領するのが自我であり、島と湾とを合わせた全体がそれぞれの自己ということになります。
全なる大海から自己という有の存在が生まれ、それはいわば島と湾との出現です。そして自己という有の存在が消滅する(無に帰する)とき、島と湾とは全なる大海に回収され、姿を没し去ります。
島を宰領するのは自我です。そして湾を宰領するものは、大自然の意向を心に繋いでいく役目を持っています。大自然の意向が何であるかは、人間にはうかがい知ることができません。しかしながら、自我なる島の母体は、大自然以外にはありません。大自然の意向が何であるかは不可知である、というのはその通りで、論を待ちません。しかし、精神の病理現象を理解しようとすると、不可知のものをも可知としなければなりません。
「知らないものは知らない」というのは謙遜のようですが、精神を病む人の前では、それで済ませるわけにはいかないのです。人の心には、無意識という不可知の世界が、否定し難くあります。無意識の世界は、それがなくては心が成立しないものです。そのような重要なものがある以上は、それをも問題化しないかぎり、精神現象を理解することはできません。それをはじめて主張し、無意識の問題を精神医学に持ち込んだのがフロイトです。この無意識の問題を不問に付し、自我の領域のことに限定しようとするのは、「群盲、象を評す」という行為に他なりません。
それで不可知の問題についても、「かのように考える」試みが必要です。その試みに合理的な意味があるかどうかは、治療上の有効性にかかっています。
「かのように考える」のは、自我の能力を超えている領域について、敢えて合理的な準拠を仮定的に措定し、自我が宰領者であるのを可能とさせようとする試みです。
過食の問題-その6 2007年6月2日
前章に述べた意味を込めて、無意識に当たる湾を宰領するものを、内在する主体と呼んでおきます。人は、あるいは、それぞれの自己は、自我に拠って存在可能です。その、自我に拠る自己が誕生したときに、大自然の意向を伝えるべく心に及んでいる無意識の首座にあるのが、内在する主体です。
全(または無)である大自然には、全(または無)であるが故に首座にあたる中心はなく、有の存在である心には、有限であるが故に中心があります。従って、湾に当たる心の無意識の領域は、全の性格を担いつつ、有限の性格をも併せ持っているといえます。そういうわけなので、内在する主体は、全の世界の意向を有の世界に橋渡しする使命を持っていると考えることができます。
この主体との関係における自我を、特に主我と呼んでおきます。主我は主体との関係における自我ですが、自我のもう一つの要員は客我です。客我は、他者との関係における自我です。主我と主体、客我と他者とのそれぞれの関係は、いわば心の縦軸と横軸として心を支える機軸です。このことは、心の病理現象を解く上で、あるいは治療の上で、すこぶる重要な意味を持っています。
問題を先取りして結論的にいえば、主我の機能が欠陥状態にあれば、心は病気です。そして、主我の機能が損なわれていなくても、客我に支配される心的状況があれば、主我は自由を奪われ、心の自立性が損なわれています。こうなると、主我と共に、心は機能的な不全状態に陥ります。この場合も治療者の関与が必要になります。しかし、病気という言葉は妥当でありません。主我が客我の支配を受けている心の構造が、主我の自律性を奪い、社会的な自立心を封じているので、この構造を改変して主我の自由を回復させるのが治療上の課題になります。
人生を無限に高い山を登ることになぞらえると、自分からそれを引き受け、自分の意志で登る精神が必要です。そうでなければ強いられた山登りになり、無意味で虚しい苦行になります。
人生には課せられたという側面が色濃くあります。人の誕生自体がそういう意味合いを持っていますし、躾も教育もそういうものです。ですから、強いられた山登りではなく、自ら引き受ける山登りであることが、人生が意義深いものであるための要件です。心に課して来るのは、社会であり、他者であり、そして客我です。その課して来るものを引き受けるのは、主我の役目です。心にとって外的なものが心に課してくるとき、客我がそれに連動します。
例えば、ある小学生が母親に、「遊んでいないで勉強しなさい」といわれるとき、母親は外的な他者ですが、その子の心の、内的な他者である客我がそれに連動するのです。母親のいい分に連動する客我が課してきたときに、主我が客我から自由であれば、「勉強しなさい」という言葉が、この子の心を強制することはありません。
例え母親が命令的にいったとしても、主我は状況を読んで、勉強をするかどうかは自分で決めることができます。先ほどの例に戻れば、主我がこのように活きていることが、自ら引き受ける山登りであるための必須の条件になるのです。
主我が客我から自由であるときに自立心があるということになるのですが、その条件が満たされているときは、自分自身と他者とへの信頼が基本的に備わっているといえます。
上に述べたように、主我が客我に支配されているときは、何らかの心の障害をもたらしますが、その治療の要点は、強いられる心から、引き受ける精神への改変ということになります。従って、それは治療者が外側から加える‘治療’ではなく、本人自身が自らその意味と必要とを察知して取り組む、主体者意識が鍵になるのです。しかしながら主体者意識を持つのも主我の役目なので、当の主我が機能不全に陥っている心の状況では、簡単なことではありません。そうではあっても、心の不全状態を解いていく主役は主我であり、本人自身であり、治療者は介助者ということになるのです。心が病気であれば、治さなければならず、治療者の積極的な介入が必要です。
心の自立性が問題であれば、求められているのは、主我が客我から自由になっていくことであり、それは取りも直さず、心の成長が課題であるということになります。治療上の困難は、前者の場合、治療者の介入を拒否することです。そして後者についての困難は、本人が、「治してほしい」という受身的な依存の姿勢のままでいることです。それは潜在する無意識的な強い恐怖があるために、主我が客我に取りすがっている姿です。その様子は、恐怖に怯える幼い子が、母親に取りすがっているのと酷似しています。「治してほしい」という受身でいるかぎりは、治療が難航しても不思議はありません。
過食の問題-その7 2007年6月10日
過食症にかぎらず、心の障害とは何かといえば、「心が囚われていること」と考えてよいと思います。その方が、具体的で、分かり易いかもしれません。それは言葉を換えると、主我が客我に、あるいは何らかの強い感情(具体的には恐怖と怒りとそれに伴う不安)に支配されているということです。
例えば、癌の宣告を受けると、大多数の者が「心が囚われる」ことになります。このときは、御し難い恐怖に主我が支配されて、不安に駆られたり、落ち込んだりします。その恐怖は、いうまでもなく死の恐怖です。恐怖は怒りを伴います。(一般に、「心が囚われる」場合、無意識下にある恐怖が「元凶」であろうと思われます。この問題は後で取り上げるつもりですが、恐怖は怒りを必ず伴うと考えられます。例えば暴力男の前では恐怖が目立ちますが、怒りも伴います。その怒りは抑圧されて意識されないのです。怒りは、相手へのものと自分自身へのものです。抑圧された怒りは不安を引き起こします。怒りは関係を破壊しかねません。他へ向かえば人との関係が破壊されるかもしれませんし、抑圧されると自分自身との関係、つまり心が危機に瀕します。このような怒りの扱いは、その人の性格を表します。また怒りの扱い方によって、心の成長が図られもし、あるいは鬱屈した心の持ち主になって行きもし、ということでもあります)
ひとしきり怒り(「何故、自分が?」という怒り)を顕わにし、やがて、「避けられない運命であれば従おう」という落ち着きと平安が心に訪れるプロセスを、癌の臨床に長年携わってきたスイス出身の精神科医、キューブラ・ロスが、「死ぬ瞬間」で、述べております。
そのことは、主我が恐怖と怒りという強い感情から自由になり、与えられた状況を受け止めることができるようになった、と説明することができます。
癌の恐怖に「囚われる」のも心の障害に順じる問題です。しかしこれは誰もが陥ることであり、従ってそれを理解するのが容易で、共感もできることなので、この場合は「心の障害」とはいわれません。しかし、その恐怖への囚われが、常識を越えて長期にわたるようであれば、「心の障害」ということになります。後者については、癌の罹患という直接的な脅威を越えて、元々何らかの理由で無意識下に潜在していただろう恐怖のエネルギーが大きかったと推測されるのです。その潜在していただろう恐怖が、癌という具体的、かつ現実的な脅威に直面したために一気に活性化され、いつまでもそのことに心が囚われるのです。しかし、元々、怯え易い性格の人が、癌を宣告されて、意外にも落ち着き払っていることが珍しくありません。ですから、一様にいま述べたようなことが起こるわけではありません。死への直面という強烈なインパクトが、ある人の主我をゆさぶり、しかしある人の主我は、いわば「背中をどやされてシャンとなった」といえるのかもしれません。
そのことに関連して、精神病院に長く入院していた統合失調症の、ある患者さんのエピソードを思い出します。その患者さんは重症の自閉と緘黙の状態にあり、何年ものあいだ誰とも一言も口をきかないまま、入院生活が長期化していたのです。そして、その上に重い身体病に罹患しました。死期が近づいたあるとき、トイレで主治医と一緒になりました。たまたま、二人だけだったそうです。そのときに、「お世話になりました」と主治医に挨拶をしたのです。そんなことを口にするとは信じていなかった主治医は、大変驚いたといいます。
このエピソードからは、凝固したように動かなかった患者さんの主我が、死への直面という特別な事態を向かえて、「背中をどやされた」ように、瞬時、「我に返った(自由が回復した)」のかという印象を受けます。
上に述べた例では恐怖が主我を支配しているのですが、以下は客我が主我を支配している例です。
ある男性(A)は、会社で重要な仕事を任されています。しかし毎日が苦痛でなりません。自分がしていることが、人に認められるものとは、どうしても思えないからです。上司はといえば、Aさんの仕事振りを、「何も問題がない」といいます。しかし、それは上司がよく分かっていないから、甘いからだとAさんは思うばかりです。自分を信頼し、評価してくれている上司が信じられないのです。つまり、Aさんは自分も人も信じられません。
こういうAさんを、「自分に厳しい」といういい方は当たらないと思います。「自分に厳しい」というのは、自己否定感に囚われている人を指した言葉ではないからです。Aさんの場合、問題になるのは自己否定感への囚われです。
よりレベルを下げて、転勤させてほしいとAさんは望むのですが、何人もの上司が、Aさんに、「無理はさせないから自分のところに来て欲しい」といいます。上司たちはAさんを十分に評価し、好意的なのに、Aさんは、まるで厳しい上司に仕事ぶりを否定されつづけているかのように自信を持てないのです。仮に、上司が厳しい人であったなら、おそらくAさんの主我が心を持ちこたえることはできなかっただろうと思います。他者である上司とAさんの客我とが連動して、主我を脅かすからです。そのことは、主我が客我から独立していれば、例え他者である上司が過酷な人であっても、心がつぶれることはないという意味でもあります。
つまり、心にとって重要なのは、他者がどうであるか以上に、他者と連動して攻撃、非難をする客我と、それに支配されている主我なのです。(いじめに遭って学校に行けなくなった子の場合も同様です。いじめをする者たちもさることながら、それに連動する客我に支配されている主我という心の状況が問題です)
Aさんのような状況にあっても、社会的な地位に固執する人もあります。そのような場合は、自己否定感の塊のようになったまま、「超低空飛行」を強いられることにもなります。Aさんは、レベルを下げてほしいと転勤願いを出している分、まだしも柔軟といえます。
過食の問題-その8 2007年6月29日
前の項で述べたAさんの場合、問題の中心にあるのは、自己否定感に囚われていることです。自分が自分を否定するというのは、心の内部に「他者の眼」があることを意味します。というのは、何かについての評価が成立するためには、評価するものと、されるものとが必要で、評価をするのは「他なるもの」であるからです。
それらの関係は、既に述べた客我と主我の関係に他なりません。
心の執行権は主我にあります。客我は主我に対して、社会的なこと、対人的なこと、人生のことなどについて標準的な意向を伝え、主我はその上に立って行為し(執行権を行使する)、そして改めて客我がそれを評価することになります。客我は、「客観的な観点」から意向を伝え、かつその観点から評価を加えるのですが、その「客観的な観点」には、人さまざまに主観が入ります。この「客観的な観点」は、帰属する集団の文化や民族性などによって異なります。国民性、国や地方の文化、職場の特性、学校の校風、それぞれの家庭の内情などによって「客観的な観点」は異なるので、集団への新参者は適応力が問われることになります。人生の新参者である赤ん坊は、生まれた家庭の家風に適応しなければなりません。家風は、良かれ悪しかれ家長を中心に醸し出されます。
家長は、具体的には父親ということになります。関白型の父親、影のうすい父親、恐妻家の父親、妻の尻に敷かれる夫、仕事人間の父親等々、父親はさまざまに、意識的、無意識的に家風を演出します。
そのように、それぞれの家庭の状況の下に赤ん坊が誕生するのですが、それ以前に、赤ん坊の誕生は何に拠っているのかという問題があります。赤ん坊を生んだのは母親であるにしても、母親が赤ん坊を創り出したわけではありません。では、赤ん坊は、何に拠って創り出されたのでしょうか?この問題に、「科学的に」答えることは不可能です。卵子と精子の合体があったのは紛れもなく、それは「科学的な」事実です。しかし、赤ん坊が創出された理由が、それにとどまるわけもありません。
無数の卵子が生まれ、無数の精子が誕生し、その中のA卵子とB精子が、偶然に合体するに至った、という問題、この卵子、この精子の最初の萌芽があり、やがて一つひとつが成熟して完成へと至るプロセスの問題、そうしたあれやこれやの複雑極まりないプロセスが何に拠って導かれているのか、といった類いの疑問は果てしなく起こります。これらの疑問に「科学的に」回答するのは不可能というしかありませんが、敢えていうのであれば、「無数の偶然が積み重なった結果である」とでもいうことになるのでしょうか。しかし、それは大雑把過ぎる投げやりないい方で、回答といったものではありません。「何がなんだか分からない理由で・・・」というのと五十歩百歩です。
つまり、「赤ん坊が創出された」のは、分かり得ない理由に拠っている、それを合理的に説明するのは不可能である、というしかないのが実態です。それは言葉を換えると、赤ん坊の誕生は無限性のものに由来しているということになります。逆にいえば、科学的に解明可能なのは、対象が限定され、有限化されているときだけということです。例えばバラの研究家は、一本のバラの木を相手に、一生を送ることができます。
というより、一生をかけてもバラの木を解明し尽くすことはできません。仮にバラの木の全体が科学的に解明されれば、バラの木という生命体を、人間が合成することができることになります。それが不可能なのは、錬金術とおなじことです。つまり、生命体は無限性の性格を持っています。ましてや、「人間を合成する」わけにはいかず、人間が作れるのはせいぜいロボットです。
以上のように、「赤ん坊の創出」は、「過食の問題(5)」で説明したような、無限性の性格を持つものに拠っている、と比喩的にいえます。比喩的にというのは、「無限性の性格のもの」という表現が、具体的に捉えることが不可能なものを、敢えて現象的実態になぞらえて呼べばそうしたいい方になるという意味です。
以上のことをふまえて、「赤ん坊の創出問題」を敢えて定式化していえば、次のようになります。
赤ん坊は、無限性の性格のものに拠って、有限性の性格が付与されて創出されたと、比喩的に、仮定的にいえるようであるが、創出された赤ん坊(人間)の象徴性と実効性とは自我に集約されている。
赤ん坊を創出したのは、無限性の性格の、名づけ得ないものによってです。その名づけ得ないものに拠って赤ん坊は創り出されたが、先の項で説明した「内在する主体」が、創出者のいわば代理人として心に宿っている、といえます。
では、母親はどういう役割を持っているのかといえば、いうならば現実界の代理人です。母親は、名づけ得ないものによって名指しされて、いってみれば天与のものとしての赤ん坊を託されたという構図になります。そういう事情を前提にすると、赤ん坊は最大限に丁重に扱われて然るべきです。そのようにして、ともかくも、然々の家風の家の、然々という母親の全面的な庇護の下に、赤ん坊は「この世の新参者」として人類の一員になります。
赤ん坊にとって、客我を形成する直接的な状況は「家風」です。そして、「家風」の下で、絶対的な庇護者である母親は、客我形成に影響を与える最大の他者ということになります。母親が、何らかの意味で欠落している場合には、「あるべき者がない」という致命的な影響を与えます。赤ん坊にとって、母親は、いわば第二の主体です。内在する主体が真の主体であり、現実的な代理人である母親が第二の主体という構図になります。
過食の問題-その9 2007年7月11日
第一の主体である内在する主体は、無意識界に鎮座して、一般に意識されることがありません。それは、いわば深い沈黙の内に、悠揚として不動のままに、自我の仕事を見守っていると仮定的に考えることができます。そのように考える合理的な理由は、繰り返しになりますけれど、精神の病理現象の理解と治療的還元とを通じて、その有用性が確かめられるというところにあります。
それらの仮説は、当然のことながら固定されたものではありません。新しい病理現象が、その仮説と矛盾する可能性は、常にあります。そのときには、それらをも統合した新たな仮説に赴く必要があります。現象的実体として、客観的に対象化できない心理現象に関しては、仮説を用いることは、不可避、不可欠です。そして、それらの仮説は、常に改変されていくべきものです。
そういうことが前提ですが、ここで仮定されている内在する主体は、指図せず、批判せず、しかし自我にとって一切であると考えられます。一切というのは、第一に、主体は、それぞれの自己が創出された母体であるということです。それぞれの自己、あるいは人間を象徴し、実効的な主動力を担っているのは主我です。
人は、自我に拠って人であることが可能です。主我は、客我と共に、その自我の一員ですが、主体との関係において生命的世界を展開する執行権を委ねられています。主我と主体との関係は、自己の生命線といえるものです。つまり、この関係がうまくいっていれば、心は豊かな生気感情にひたされますし、そうでなければ人生は負担の重い、暗澹たるものになります。
それぞれの自己が創出された母体は、無限性のものからであるのは、先に述べたとおりです。無限性のものによって自我が授与され、有限性の性格を持つに至ったもの、それがそれぞれの自己であり、人間です。自我に拠る心の世界は有限のものですが、心の無意識界には無限性のものである主体が鎮座しているので、結局、心は、あるいは自己は、有限のものでありながら無限性の性格を併せ持っています。有限である人の命は、いずれ終焉にいたります。
つまり、それぞれの自己は、無限性のものから創出され、無限性のものの下に回帰します。その軌跡が人生であり、その人生を自己の展開という形で演出する執行権を担っているのが主我ですが、人は社会的存在でもあるので、その観点から主我を補佐するのが、客我の本来あるべき姿です。本来あるべき姿というのは、実際には往々にして客我が主我を支配し、執行権の行使を阻害するからです。内在する主体は、無限性のものを、有限であるそれぞれの自己につなぐ役目を持ち、自己の展開の執行権を自我に委ねつつ、それを見守るという関係にあります。
では、自我は、どのようにして沈黙する主体の意向を引き受けるのでしょうか?
その前に、次なる問題は、自我が主体との関係である他に、他者との関係をも司る役目を負っているということです。自我の中で、他者との関係を司るのが客我です。先に述べたように、赤ん坊にとって、他者の中でも特別の他者である母親は、いわば現実界の代理人、第二の主体です。
赤ん坊は、自我に拠って自己であることを引き受けた(主体の命を引き受けた)という体裁になるのですが、その赤ん坊をこの世の代理人として引き受ける立場にあるのが、母親です。母親も、また、主体の命を受け、それを引き受けて母親となったという体裁です。この「体裁」は、しかしながら、意識されることがありません。母親は、主体の命を受けた特別に名誉ある代理人であるという位置づけが可能ですが、実際には、母親はその意識を欠いているので、赤ん坊にとって、自分が第一の主体であるという漠然とした意識を持つとしても不思議はありません。ここに、大きな錯誤が起こる余地があります。赤ん坊は名誉ある大切な授かり者、という意識が母親にあれば、赤ん坊は丁重に扱われるでしょう。しかし、その意識が欠落していれば、母親は赤ん坊にとって第一の主体になります。それは、良くも悪くも第一位の権力者に他ならないので、愚かな母親であればあるほど、「自分が生んだ者」という意識を、容易に「自分のモノ」に変換してしまうのです。「名誉ある代理人」の自覚があれば、「自分の都合のいいように育てたい」という意識は、無意識的にであれ滅多には働かないと思います。
そういう自覚があれば、自ずから「真の愛情」を模索することになるはずです。その「真の愛情」が、「自分が生んだ者」という意識の下では、大いに歪むのです。子供への愛情の名の下での、実質的な迫害は、軽微なものまで入れれば、これを免れることができる母親はいない、と断言できます。それは、二心(ふたごころ)が人間の心理的特性であるためです。人を愛することは自分を愛することであり、人を憎むのは自分への憎しみと無縁でないのは、良くも悪くも、人間心理の特徴です。
赤ん坊は、生まれてしばらくのあいだは幻想の中にまどろんでいます。そのまどろみは、有限と無限の入り混じった繭にくるまれているような、あるいは半ば主体のふところに抱かれているような、といったふうなことで、この世とこの世以前の世界との混淆された準備状況に置かれている標章、と考えることが可能です。その幻想の状況は、まだ母親と名指しできない「この世の代理人」が、大きな満足と大きな安心とを保証してくれるはずだから何も案じることはない、と主体に囁かれているといったふうなことであろうかと、仮定的に想定されます。
こうした「お話」は、誰もが直接は確かめることができないものなので、ばかばかしいと思えば思えます。しかし、単なるお話ではなく、そこには一定の合理性があると認められる「お話」というべきです。それは昔話が単なるお話ではなく、古今東西の人間の在り方の骨格とでもいうべきものが込められていることに通じています。