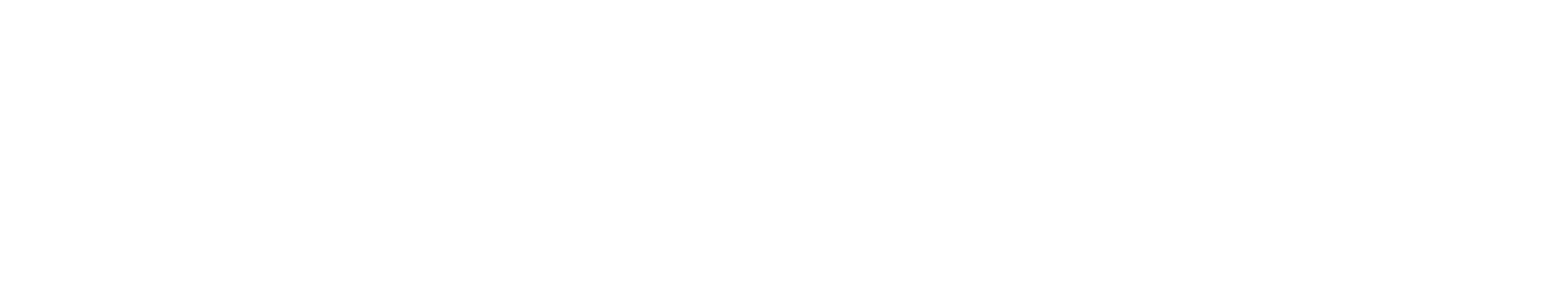院内通信 断片集
断片集-その1
■子育てについて
私が直接経験した範囲にかぎっても,子育ての悩みを持つお母さんは,とても多いです。
子供をどうしても叱ってしまうと,あるお母さんはいいます。「そんなことぐらいで叱らなくてもいいのではないか」と夫にいわれたりします。しかし,ふだん夫のサポートが少ないという思いがあるので,かえって反発を感じます。いらいらしたり,気が滅入ったりするだけで,励みになりません。自分でもそんなふうにはしたくないのです。もっと穏やかにいってやれるようにと思うのです。しかし,できないのです。
お母さんの怒りと悩みは二つの方向に向かいます。叱り過ぎる自分と,いうことを聞かない子供と。子供がお母さんのいうことをきちんと守ってくれさえすれば,お母さんも目くじらを立てることはなくなるのです。そういう思いがあるので,自分の怒りが正当化されます。そして正当化されているかぎりは,このジレンマはつづくと思います。
お母さんが,我が子にいい子になってほしいと願うのは,一見すると無理がないように思えます。しかし,いい子とはどういうことなのでしょう。親の願いどおりの子になるということでしょうか,それとも子供が自分の幸せをつかみ取る,そういう能力を身につけるということでしょうか。いうまでもなく両者のあいだには,天と地ほどの差があります。
子供の幸福を願わない親は,ふつうに考えればいないでしょうが,親の側に盲点があれば,実際上,子供を不幸にしてしまいます。そういう例は決して少なくないのです。親の側で,自分の大人性に問題をかかえたままでいると,自分の未熟さに補いをつけようとするかのように,子供に大人性を無意識的にもとめるようになるのです。それで,子供の未熟なところ,よその子に劣っているように感じられるところに神経質になります。お母さんが,自分の未熟なところを自分で認め,受け止めるることができていれば,「私がこんなだから」と笑って我が子の未熟さに寛大になれるかもしれません。そういう態度自体が立派に大人の姿勢だと思います。未熟であるのは善悪の問題ではなく事実の問題です。子の未熟は親の未熟の反映という側面もあるかもしれません。いずれにしても親子の共通の課題です。叱ってすませるのはお門違いということになるのではないでしょうか。
問題があれば,まずは受け止める。それが原則です。解決の第一歩です。
おとなしく親のいうことを聞く子より,反抗的な子のほうが問題の解決にいたりやすいものです。親としても叱って解決できることではないので,真剣に問題を受け止めようとするしかないからです。子供がおとなしくいうことを聞いてくれれば,親は反省する機会がなかなか持てないので,子の犠牲(我慢に我慢を重ねるのが性分となるような)において,親の満足があるということになりかねません。親はもちろんですが,子もうまくいっていると思おうとしたり,いっても聞いてもらえないとあきらめる癖が身についていたりします。
子供は自分の力で伸びていきます。親が手を引っ張って伸ばすのではありません。ずいぶん幼くても,自分の中に伸びる芽があり,自分の力で伸びていくと考えて間違いがないと思います。問題が起こるとすると,親がしてはならない介入をしたときです。子供の伸びる芽を邪魔しない環境を作ってあげるためには,親の本物の愛情と信頼が欠かせません。そしてそれは容易なことでもありません。むしろ甘すぎたり,厳しすぎたり,環境破壊をしてしまうことの方が多いだろうと思うべきです。親はなんといっても子に対して権力者です。権力を持つものは力をふるいたくなるものです。力にものをいわせようとするときに,たぶん環境破壊をはじめていると思います。
H14/02/27
断片集-その2
■患者さんは先生です
医者は患者のみなさんから,先生といわれるのが慣わしのようになっております。ですから,先生と呼ばれても特には違和感はないのですが,考えてみると,この言葉に安住してはいけないように思います。
いつも人の悩みを聞いていて疲れないかと,訊かれることがあります。いわれてみて,仕事とはいえ,来る日も来る日も人の悩みを聞いているのは確かだと,いまさらのように思います。しかし,疲れるかといえば,そうでもありません。うまく自分の感情をコントロールできなくて,患者さんにいらいらしながら対応してしまったとか,後悔するようなことが起こると,確かに疲れます。ですから,平常心を保つように心がけ,自分なりに最善をつくすのが疲れない最良のことと思っています。
しかし,なぜ疲れないかというと,医者と患者の関係が,一方的に指導したり,教えたりということではないからだと思います。つまり両者の関係は,持ちつ持たれつだからです。一方向的だと,いわばエネルギーは放出されるばかりなので,疲れると思います。相互交流的であれば,医者も患者さんからエネルギーをもらえるということだと思います。患者さんが元気になっていけば,医者も元気になれるわけです。
患者さんが自分の悩みを打ち明ける,医者はそれを受け止める,医者としての考えを返す,患者がそれに対して意見をいう,医者が新たに考えを返す…という交流が両者のあいだに起こります。両者が信頼でつながれていなければ,この交流は円滑に進行しません。最終的に,医者の対応が正しかったかどうかを決めるのは,患者のみなさんです。元気になったという結果が出るか,出ないかということが,すべてを物語ります。
こびるつもりはありませんが,こんなふうに考えていくと,患者さんが先生という図式になるようです。
ところでジェイムズ・ヒルマンという人は,癒す心と病む心とが元型としてだれにでもあると考えています。これに従えば,病む心をたずさえて患者が医者を訪れ,癒す心をたずさえて医者が患者を向かえるということになります。そして医者は病む心があればこそ患者の病む心を理解することができ,患者は癒す心があればこそ癒そうとする医者の心と協同できるということになると思います。
そういうことは確かにいえると私も思います。
H14/02/27
断片集-その3
■騎手と馬
意識と無意識の関係を,騎手と馬の関係にたとえると分かりやすいのではないかと思います。競馬に,障害レースというのがありますが,柵や水溜りを次々と飛び越えてゴールを目指します。騎手が馬のパワーを最大限に引き出してレースをする様子が,意識という騎手が無意識という馬のパワーをうまく引き出して,人生の関門をクリアする様子に似ているのです。
馬はなかなか利口な動物らしく,騎手がどういう能力を持っているか,愛情と信頼を豊かに向けてくれているか,おそらく敏感に察知していると思われます。騎手と馬との関係が十分で,いわゆる人馬一体になれば,馬は持っている力を最大限に発揮できるのでしょう。逆に馬の心を知らない駄目な騎手は,まともには相手にしてもらえないわけです。
無意識という馬は,ほんものの馬よりはるかに利口です。自我という騎手よりはるかに利口です。というより,自我がなにを考え,どういう方向へ導こうとしているのか,それは正しい判断なのか,すべて見抜かれていると考えてよいようです。つまりこの馬のほうこそが本来の主体なのです。ですから,自我―騎手は,無意識―馬にうかがいを立てつつ,指揮をとる必要があります。この馬は,沈黙したままでなにもいいませんが,指揮のとり方(判断)が正しければ,勇気,元気,やる気が出てくるでしょう。逆に見当違いであれば,不安,おじけ,暗澹,あせりなどの感情に悩まされるでしょう。しばしば人は,この馬にうかがいをたてる(自分自身との内的な対話を心がける)よりは,親の顔色をうかがい,人や世間に気を使い,占いにかけ,あるいはどうだって勝手だろうとばかりに,やけくそな行動に走ります。
そんなことなら無意識ー馬が直接に人生行路の指揮を取ればいいようなものですが,実際には自我に人生が託されているのです。無意識はいわば自然そのものですが,自我は人間が人間である理由,あるいは根拠のようなものといえるでしょうか。
無意識―馬の奥深い知恵は,夢を通じて示されることがあります。古代人は夢占いを重視しました。占い師は高い地位をあたえられ,国家的な命運を託されました。占いは,現代では科学的な根拠を欠いているとして,当たるも八卦当たらぬも八卦とうさんくさい目で見られがちです。たしかにそういう側面は大いにあるので,眉に唾をつけてかからねばなりませんが,すべてがそうだとはいい切れないようです。占いの技術を通じて,無意識の心を直感的に読み取る特殊な才能の持ち主がいるとしても,不思議はないと思います。
夢に無意識の叡智が示されることがあります。一見すると,夢は“わけのわからないもの”ですが,よく見ると,透かし絵のように深い意味が現われてくることがあります。それは人生劇場を演出している自我の仕事のゆがみを,夢という別次元の舞台での演出家(無意識界の主体―内在する主体)が,それとなく教え,補償し,あるべき自己に導こうとしているように見えます。ただし,禅問答の導師のように,自我の姿勢のいかんにより態度を変えてきます。真剣に教えを請う姿勢が継続されれば(人生や自分の問題に本気で取り組もうとしているか,夢の意味を真剣に読み取ろうとしているか),夢の内容もしだいに変わっていき,まともな対応をしてくれるけれど,あいまいであればそれに相応した対応しかしてくれません。
自我―騎手は,社会的な存在である人間のコントロールタワーです。置かれている状況の全体の見渡し,的確な判断,行動がもとめられております。前線での指揮官が判断ミスをすれば部隊が全滅するかもしれません。オーケストラの指揮者が楽団員の信頼をもらえないでいると,よい演奏ができません。自我―騎手も社会という舞台で演じる人生劇場で,よい演出をしなければ惨憺たる人生になってしまうわけです。
人生の航海で方向を見失い,途方にくれることもあるでしょう。空が曇っていると,星を頼りにすることもできません。しかし,あわてないのが肝要です。羅針盤(内在する主体)は心の内,無意識―馬に備えられております。見えるまでは見えませんが,そのあいだは不安に満ちるでしょうが,なくなることはありません。そういうことですから,自分を信じてください。信じつづけるかぎりは,やがては羅針盤が作動しているのがわかるときが来ます。あきらめずに,やけを起こさずに,自分のためによいと思われることを,一日一日,少しずつ,少しずつ継続することが大切です。こういうときは,あまり遠い過去も,遠い将来も見ないほうがいいと思います。その日その日を,足元を見つめるように生活することが大切です。
H14/03/26
断片集-その4
■病気がなかなか良くならないのは何故ですか?
たとえば「本に,うつ病は三ヶ月で治ると書いてありますが,なかなか良くなりません。何故ですか?」という質問を,時に受けることがあります。
うつ病は薬が合えば,それだけで速やかに回復していく代表的な心の病気です。
心と身体は密接不可分の関係にあるので,心の現象には正常と異常とに関わらず,それに相応する身体的側面の理由があることはいうまでもありません。ですから薬が効いて治ることもありますし,薬だけではうまくいかないことがあっても不思議ではありません。
うつ病は薬だけで治ることが珍しくない一方で,神経症や人格障害は薬で治ることはできません。
こういうことがあるので,うつ病は何らかの生物学的な原因があると考えられていますが,先にも述べたように,うつ病といっても各人各様で,薬がまったく効かない場合もあります。
それでは薬が十分には役に立たない場合,どのように考えればよいのでしょう?
結論的にいえば,自我が鍵を握っています。自我が自由で独立していれば心の病気になることはありません。逆にいえば自我の機能を回復させるのが治療の目的です。
自我は専門用語なので,あまりなじみがない言葉だと思います。
心にはその気になれば自分でも分かる世界と,分からない世界とがあります。言い換えると意識の世界と無意識の世界ということになります。
簡単にいえばこのようになりますが,実際は意識できる世界といっても,いうならば薄暗すぎて手探りで見つけることができるかどうかという困難や,複雑に入り組んでいたり,対立しあったりなど,幾重にも錯綜しているので容易には捉えることができません。ましてや無意識となると,意識化ができないということですから,見ようとしても見ることができないものが存在していることになるのです。自我というのは意識の世界の中心にあるものです。そして自己形成の中枢でもあります。その時々の状況的な課題を担い,超克することによって自己形成が計られます。それは無意識の領域へ分け入る心の作業でもあります。つまり意識化するのが不可能なものをまで問題にしなければなりません。これは大変矛盾した話ですが,克服し得ない矛盾を内包していることこそ人間存在の特徴です。いうならば人間存在は無意識という深淵を内に持っています。
では,意識化できない無意識なるものが存在しているといえるのは,何故なのでしょうか?
その理由の一つは夢の存在です。夢も意識化されたからこそ目覚めた後で想起できるのです。日中の意識の活動は多くは能動的です。つまり,「私が見ている」,「私が聞いている」というふうに,それぞれの私の意識が意志的に対象に向っています。一方で夢については意識が受身です。「見ている」という能動性はなく,「見たのを覚えている」という受動性の中にあるのです。そうすると夢を意識に向けて創出しているのは,意識自体ではあり得ません。
このことを定式化すると,「夢は疑いなくある。それは意識が受動的に活動していることを表している。しかし夢を送り出しているものは何か?それは確実に存在しているが,意識できない以上はその存在様態を知ることはできない」ということになるかと思います。
その目で見てみると,日中の意識が覚醒した状態の下でも,夢とおなじように意識が受動的になっていることがあるのが分かると思います。
そのようなことを考えると,我々が意志的に意識しているように感じられることも,むしろそうではなく受動的な活動に支配されているらしいことに気がつきます。
たとえば意識とは何かといったことを考えるとすると,それは能動的な意識活動のように見えます。その活動の拠り所は自我にあるのですが,自我は意識についてこれまでに学習したことを思い出す心の作業をしていきます。その記憶を取り出す作業は能動的な意識活動といえるでしょう。しかしそれが全てであれば,我々人間は全てを知っている,あるいは少なくても知ることができることになります。言い換えると人類の最高の知者がいるとして,我々はその知者から学び取っていけば,全てを知ることができることになるでしょう。ではその知者はどのようにして,誰も知らないことを知ることができたのでしょう?その知者は人間の中の最上位にあるとして,我々は彼から学びつくすと,それで全てということになります。換言すると,その知者は人間らしく有限の存在であるらしいので,我々の全てが知識に関して一定の限界に到達して,そこで終わる・・・といった妙なことになります。ではその限界の外を知りたければどうなるのかと考えれば,答えが行き詰るのは明らかです。
いま述べたように,考えるという心の作業は,知識や記憶の集積だけでは済みません。言い換えると意識の能動作業は,一定の限定つきで可能であり,意味もあるのですが,どうやら受身で受け取る作業の方により大きな意味があるらしいということになってきます。
そのことは意識の存在は心の全てではなく,意識できない力の存在を認めないわけにはいかないことを示しています。何かを考えるという創造的な行為は,意識が無意識から立ち上がってくる意味のある信号を受け取る作業であるといえます。
こういうことをくだくだしくいうまでもなく,我々人間は,心の内外の現象の全てを知ることは不可能であるのは誰でも知っていることです。つまり意識できないものが存在しているのは自明のことです。
このように意識化が可能なものが現象的実体で,有限の世界ということになります。そして意識化が不可能なもの,つまり無限の世界が存在し,これらを現象的実体として捉えることは人間にはできません。
生きるということは有限の世界でということになりますが,その心の営為の中心に自我があり,それは無意識的世界に包囲されているともいえます。そしてこのように考えていくと,無意識といえども単に茫漠としたものではなく,自我との有意味な関連があると考えるのが合理的です。その有意味な関連がある無意識側にも,自我に匹敵する中心があると考えるのが自然な思考の流れというものです。その中心にあるものを,内在する主体と呼んでおきます。
それは現象的実体ではありませんが,現象的実体を意味の連鎖で繋ごうとすると,そのような仮説が浮かんでくるということです。それは現象的実体に準じるものであるといってもいい過ぎではないと思います。
結論的にいえば,自我がこの主体との関係の筋を探り当てることができているとき,自我は良い仕事をしていることになります。そういう心の状況にある証は,充足感,高揚感などとなって表れると思います。それはいうならば最上位者に認められた満足感と高揚感であるともいえるでしょう。
目前の欲求に駆られて行動する動物は,いわば自然のものであるといえます。人間はどうかといえば,いま述べた意味では自然のものではありません。
人間は自我に拠る存在です。そのために精神性と社会性とを追求する特異性を持っています。そのことと,人間が他者との関係を欠かせない存在要件としていることとのあいだには,密接な関係があります
このようにいえますので,人は自然そのものからは乖離して,精神的に上昇していく形で自己形成を計らなければならない宿命の下にあります。宿命というのは,自我の特徴である両極分離化が,ここでは上昇には下降,あるいは頽落がセットになっているという意味が含まれているからです。また精神性と社会性との二つの柱において,それぞれ上昇と下降が問題になります。
躾けは主に社会性の涵養であるといえます。それは原初の他者である母親,そして父親を中心として計られます。
他者の介入,あるいは関与は,人間には不可欠,不可避であり,自我の機能には先験的にそれらのことが含まれているように思われます。つまり他者は外なるものであるだけではなく,内なるものとして自我の機構に内包されているように思われます。他者は内なるものと外なるものとのあいだで,いわば阿吽の呼吸で一体化できるものであれば,あるいは人間もまた,動物一般と等しく自然のものといえるのかもしれません。しかしながら,現実には外なる他者は,独自の個性として存在主張をします。そのために親の躾けといえども,子の個性の尊重が踏みにじられ,親の価値観の押しつけ,侵入というものになりがちであるのは避けられません。それが子の心の自然が撹乱される理由です。
ここで重要なのは自我の境界機能です。
境界機能というのは,以下のようなものです。
生まれて間もない赤ん坊は,意識と無意識,あるいは自己と他者との分離ができていず,渾然としています。長ずるにつれて,それらが分離していきます。境界機能というのは,これらを分かつ機能的な隔壁と考えればよいでしょう。
幼い自我ではこの機能が未発達なので,母と子はいわば一体の関係で子の心が護られます。
境界機能は愛と信頼とによって健全に形成されていくもののようです。乳幼児期に見捨てられる恐怖に圧倒されそうになった幼い自我は,境界機能の形成が不確かなまま成長するように思われます。良い子であろうとする心は,母親の自我に従おうとする心でもあるでしょう。そのようにすれば,母親に見捨てられる(無論,心理的に)恐怖を最小にすることができるからです。それは母親を支配して,安心と満足とを万全なものにしたいという小児に特有の心理(この欲求は,それを充足するために,強い怒りを従えています)を押し殺し,いうならば意識の地下室に閉じ込める無意識的な試みを伴わないわけにはいかないと思われます。そして母親の自我に取りすがるのは,逆に母親の支配を受けることになったのと同じことになります。意識下に押し込められて沈黙していた,そのような小児心性が,既に成人の域に達したあるときに表面化して,母親またはその代理者に向けられることがあります。特別に乳児にのみ許される安心と満足との万全な要求を,怒りにまかせて突きつけることになるのです。強い怒りを伴ったそれらの要求や感情を抑圧し,意識下に潜在させたのが,良い子が支払わなければならなかった代償です。
境界機能は例えば次のように作用します。
2歳の子が友達の家に遊びに行って,玩具を持ってきたとしても,泥棒呼ばわりされることはありません。しかし5歳の子であれば少々問題になるかもしれません。これは2歳の自我では境界機能が未成熟であり,5歳ではある程度の成熟が求められているということを意味します。
AがBに怒りを込めて抗議したとします。Aに,客観的な正当性がある場合,怒りは適応的なものといえます。そのときAの自我は,怒りを引き受けた上で行為しているといえます。抗議されたBの自我が,受けた抗議を引き受けることができたときに,自分が取るべき態度を判断できます。つまり両者共に自我が正当に仕事をしているのですが,それは境界機能がうまく作動していることとパラレルな関係にあるといえます。
Aの抗議にBが反射的に怒りを以って応えたとき,あるいは恐れをなして単に意気消沈したときなどは,境界機能がうまく作動していません。従って自我は,引き受けるという自我の仕事の前提のところでつまずいていることになります。
自我の強さは,どうやら境界機能の強さ如何であるようです。自我の役割のうちで最も重要と思われる引き受ける機能は,境界機能を根拠としているように思われるからです。
以上の考えを基にして,’心の病気がなかなか治らない’理由は,自我が問題を引き受けようとしていないところにある可能性が最も高いといえるでしょう。角度を変えてみると,それは自我が小児心性に支配されているという見方にもなるでしょう。ごく幼いころの問題が未解決で,そこに今も留まって心が動けないのかもしれません。暗黙の内に,自分がこんなに辛いのは,自分のせいではない・・・という心理が働くのかもしれません。そして,それらの心の最奥には強い怒りがあると考えられます。当然といえば当然ですが,この怒りの存在に気がついている人はあまりありません。
人間は動物一般のようには自然のものでないと先に述べましたが,結論的には自然の摂理とでもいうべきもの(内在する主体の意向)に沿うのでなければ,人生の無意味感に囚われてしまうかもしれません。人生の意味の問題は理性が追求すべきものですが,理性自身に解決能力があるわけではありません。自我が主体との関係を肯定的に保つことができているときに,人生について何かを会得することが可能になるといえるのでしょう。それは自我に内属する理性が,無意識から浮上してくる主体の意向を受け止めることができたことを意味すると思います。
その主体の意志を受け止める重要な心の作業は,人格形成の最早期の諸欲求をどう護るかであるように思われます。
幼い子の心には,様々な欲求が浮かびます。それらの欲求のすべてが主体から送り出されてきたもののように思われ,従ってそれは,いわば神の子です。自我には神の子を護る使命があると考えて然るべきもののようです。
欲求に駆られる乳幼児の行動は,暴力的であったり,危険であったりもします。欲求を護るというのは,それらをそのまま満たすことではありません。それらを護るのは自我の役目ですが,幼い子の未熟な自我だけではできないことなので,実際には母親を中心とした親の補助が必要になります。
欲求自体には善も悪もなく,幼い子のあらゆる行動は自然のものです。善悪の問題が生じるのは,他者が関与することによってです。欲求に駆られた幼い子の行動を捉えて,善悪の問題や危険から身を守ることなどを教えるのが躾けです。親の愛情が確かなものであれば,それが適切に行われます。確かな愛情の下での自我は,境界機能が活きているので,幼い子の人格も尊重されるのです。そして’世間体を気にする’親は,この適切さに疑問符がつくことになります。危険に過敏な親も同様です。これらの場合は,親の自我の境界機能に問題があります。更にいえば境界機能が不確かな自我の下では,潜在する怒りが問題を惹き起こすと思われます。親といえども子の領域に侵入すれば,親が子の人格を否定しているのと同じことになります。たいていは躾けの名のもとに正当化されますが,相手の心の領域への侵入には,必ず怒りが一役買っていると考えて間違いはないと思います。子供の行動に過度に危険を感じて介入する場合などのときは,一見すると怒りと無縁のように見えます。しかし親の心に,抑圧された強い怒りが潜在していると思います。
このように,境界機能の確かな自我の下にある親の躾けであれば,基本的に子の心に生じる欲求が護られると思いますが,そうでないときには護られない度合いが高まるでしょう。主体から送り出されてきた諸欲求は,自然のもので傷つきやすく,いわば白い子です。そして護られなかった白い子は(幼い自我が受け取りを拒否したことになります),怒りによって黒い子になり,無意識界の勢力になっていきます。また自我の後見人ともいえる超自我といわれているものは,白い子(神の子)を護れなかった幼い自我に,いわば怒りを持ちます。白い子が抱えてきたエネルギーが,自我に受け渡すことができなかった分を,黒い子と超自我とに渡すことになり,それは怒りの性格を持つと思われます。
白い子が抱えてきたエネルギーを適正に受け取ることにより,自我は生きる意志を確かなものとしていきます。しかし,他者(親)の介入によって受け取ることができなかったエネルギーは,怒れる黒い子たちと,怒れる超自我を養う結果となります。相対的に自我の力が不足してしまうと,両者の山の狭間に埋没して自由を失います。自我は,それら怒れるものの支配を受けがちになります。
過食症のYさんは,次のように述べています。
「気分の落ち込みがほとんど無くなってから,過食がクローズアップされている。過食が止まらない一方で,自分から求めて何かを食べたいという気持ちが湧かない。だから食事を楽しむことはできない。食べるなという命令に逆らえないということもある・・・」
過食が肥満の恐怖に連動していくので,食べることが恐怖なのは当然です。「食べるな」と命令するのは超自我でしょう。そして過食を惹き起こすのは黒い子たちです。自我はそれらの狭間で無力でいます。この黒い子は,自我が引き受けなかった分身たちです。力を弱めた自我は,この分身たちの支配を受けています。超自我は,黒い子をたくさん作り出した自我に怒りを向けます。超自我は自我を補佐せずに,懲罰的な動きをしています。
白い子をよく護れなかった自我は,自由を保持するエネルギーを確保できなかったといえると思います。それらは生へのエネルギーとなるべきものでしたが,怒りのエネルギーと一体となって負のものに変質したのです。
では,現実にどのような心構えで臨めばよいのでしょうか?
問題の核心は,自我がその時々の心の状況に即して,それなりに仕事をする意志を持てるかというところにあります。そのためには,「生きていこう・・・元気になりたい・・・」という心が必要です。言葉を換えれば,当事者意識を持ち,問題を引き受ける意志を確かめなければなりません。自我がそれなりに仕事をすれば,それなりに満足感を味わえるはずです。
「引き受ける精神」があるかないか,それがすべてといっても過言ではないと思います。その精神が基本的に備わっているか否かによって,心の内と外とに深淵(無限または無)を含む個々人の世界は,恐るべき貧困に陥るか,(命のあるかぎり)自己超克という豊穣を手に入れるかということになるのでしょう。
断片集-その5
■引き受ける精神-1
Aさんは友達に頼まれると,努めて明るく,「いいよ」という人でした。人に親切で,ある意味では「引き受ける人」です。しかしここでいう引き受ける精神というのは,このような意味ではありません。
Aさんは,「断ると,バイバイっていわれそうで怖い」といいます。喜んで引き受けるというのではなく,本当は断りたいのです。しかし人に見離されるのが怖いので,その友人に内心では腹を立てていることさえ気がつかなかったのです。
怒りは何かを破壊する力を持っています。Aさんが友人に怒りを向ければ,友人との関係が壊れるかもしれません。怒りを我慢すると,心や身体に支障が出るかもしれません。事実Aさんは,激しい過呼吸発作に,しばしば死の恐怖を経験しました。その原因は怒りであるといっても間違いではありません。そういう意味では,怒りというのは厄介な存在です。しかし怒りは無意味なものかといえば,そんなことはありません。
動物では,怒りは生きていく上で重要な意味を持っています。動物は一般に本能として満足と安全とを求めます。それを脅かす侵入者には,怒りを向けて撃退しようとします。
人間ではどうでしょうか。人間の場合は,他者との関係が動物一般とは違った重要な意味があります。動物でも群を作って行動するなど,他との関係は生存の上で重要であるのはいうまでもないでしょうが,人間の場合は自我に拠る存在であるという点で,特殊な意味を持つのです。
自我というのは難しい概念ですが,植物での胚珠になぞらえられるでしょうか。人間が身体的のみならず,精神的な存在として成長していく上での情報がぎっしりと詰まった自我機構が,植物における胚珠に相当するといっておきます。ですから身体は物質ではなく,精神性と切り離して捉えることはできません。身体の痛みは心の痛みであり,身体への陵辱はそれ以上に精神への陵辱になるのです。
このように物質としての身体を,精神から切り離して捉えることができないように,自我に拠る人間にとって,あらゆる対象が主観的であり,かつ客観的であるという体裁になり,両者を切り離して捉えることができません。ですから人間にとって,世界の一切が現象として存在します。
主観と客観とがそうであるように,あらゆる現象を二極に分化して捉えるのが,自我の能力的な特徴です。
白と黒もその一つです。純粋の白はなく,純粋の黒もありません。かぎりなく白に近い黒が白であり,かぎりなく黒に近い白が黒です。それは自我が全体を全体として捉える能力がないことを表しています。全と無は両極に分かれているようですが,自我はかぎりなく全にちかづく,あるいはかぎりなく無にちかづくことができるばかりで,全そのもの,無そのものには至り得ません。全と無の二極分化には,自我の観点からという限定がつくのは,当然といえば当然のことです。
男と女,自己と他者も然りです。それぞれは歴然と異なるように見えますが,現象的な客観としてそのように存在していると認識しているということであって,それらは純粋客観ではありません。男はかぎりなく男に近い女であり,女はかぎりなく女に近い男なのです。他者も同様に,かぎりなく他者に近い自己であり,他者はかぎりなく他者にちかい自己といえます。
事実,心理学が蓄積した知見によれば,男は女を心の内景として持ち,女は男を心の内景に持っています。他者と自己の関係も同様です。いうならば男と女は合体してはじめて完全であり,自己と他者もそのような関係にあります。
’05/08/15
断片集-その6
■引き受ける精神-2 (雄雄しさと女々しさ)
「雄雄しさと女々しさ」というのは,いささか気になる言葉です。男は立派で,女はそうではないといっているように聞こえるからです。この言葉は男についていっているようです。女について,こういういい方はあまりしないようです。これらの語感のあいだには,明らかに価値の上下があるように思われるので,言葉の由来を知りたいと思いました。しかし私が調べたかぎり,ある辞書に,「雄雄しさらしいこと」,「女々しさは女らしいこと」と書いてあっただけです。
いずれにせよ,雄雄しさは男があるべき立派な態度であり,女々しさは男としては情けない態度ということになるのでしょうか。
ちなみに英語では,例えば,HeisAneffeminAtefellow(女々しい男だ),Don’tbewomAn!(女々しい真似をするな)などというようです。やはり男が優位に立った表現です。
このいい方は女性蔑視の姿勢から出たものと取られても仕方がないようですが,ここではそのことを問題にしようというのではありません。
これらの言葉を私流に言い換えれば,雄雄しさとは引き受ける精神であり,女々しさは引き受けない精神ということになります。そのように捉えると,雄雄しさと女々しさとは重要な意味を持ちます。引き受ける精神(雄雄しい精神)は心の病気から最も遠く,引き受けない精神(女々しい精神)は最も近いといえるからです。
60代のある女性,Aさんは10年以上にわたって頭痛に苦しんできました。頭が鉛を詰め込んだように絶えず重く,しばしば蒲団針で刺されるような鋭い痛みに見舞われます。このときはのた打ち回るほどといいます。脳外科や神経内科などで診てもらいましたが,異常はありません。
発端は交通事故だったようです。10年以上も前に受けた事故ですが,*年*月*日*時ごろに,と具体的に記憶しております。加害者は20歳未満の女性でした。「相手はまだ子供だし」と自分に言い聞かせて,示談に応じたそうです。しかし訊いてみると,「こんな身体にされて・・・家族も台無しにされた・・・考えるとはらわたが煮えくり返るほど・・・」といいます。
10年経っても昨日のことのように被害者意識が残っています。そして激しい怒りが一向に収まらず,心内を駆け巡っていたといういきさつがありました。
Aさんは,そういう問題が頭痛の素であったとは夢にも思いませんでした。そして,そこに理解がおよんだときから,痛みがうすらいでいきました。
Aさんは被害者です。Aさんが考えていたように,「こんな目に遭わなければ何事もなかった」のはある意味ではその通りです。しかしAさんの問題は,女々しさ(引き受けない精神)にありました。それが向けようのない怒りがいつまでも収まらなかった主因です。Aさんの怒りが本格的に加害者に向かえば,自分が蒙ったのとおなじ目に合わせなければならなかったでしょう。しかし目には目をという行為は,社会的人格を備えているAさんにはしてはならないことでした。
それでは怒りはどのように扱われるべきだったのでしょう?加害者に向けるわけにはいかないとすれば,いわば怒りの引き受け手がなく,Aさん自身の心の中をいつまでも駆け巡るしかありません。実際にそうなっていました。怒りはAさん自身が引き受けなければならなかったのです。
しかし怒っているのがAさんなら,それを引き受けるのもAさんというのは,どういうことでしょうか。
これは心が多重構造であることを示唆している問題です。Aさんは一人であって,一人ではありません。
これが動物であれば,話は単純です。危害を蒙れば生きるか死ぬかの戦いになるか,尻尾を巻いて逃げるかだけです。恐怖心を持つ動物はあっても,いつまでも怒っている動物はおそらくないでしょう。
動物と人間の違いは精神性の有無にあります。そして精神性の拠り所は自我にあります。自我こそ,引き受ける精神を本分としています。自我は自分にふりかかる一切を引き受ける役目を持っています。
Aさんに即していえば,怒りは自我よりも深い心の層である無意識から発しています。自分に危害が及んで,差し当たりは怒るのが当然です。それは無意識の世界からの本能を含んだ反応です。その怒りを自我が引き受けなければ,場合によっては犯罪にもなるでしょう。しかし自我が引き受けるならば,それは潔く,雄雄しいことです。災厄をものともしない潔さは,文字通り,災いを転じて福となすことになります。
身体性と精神性とを併せ持つ人間は,結局は精神性が問われるのです。ただし身体的な欲求にも耳を貸さなければならず,心身の問題の葛藤に大いに悩むべきです。その中から自分の力で精神の勝利を生み出すことが重要です。そうでなければ精神性の問題は,上からの説教が胡散臭く,偽善的に感じられる素にもなるものです。
‘05/09/07
断片集-その7
■引き受ける精神-3 (死にたがるあなたへ)
Cさんは,絶えず死にたいという気持ちに悩まされています。それなりのいきさつもあって,薬の効果にも限界があります。Cさんは,どうしたらよいのでしょうか?
繰り返しになりますが,人を人として特徴づけるのは,自我といわれているものです。このあたりの事情は比喩をまじえていえば,次のようになります。
人の誕生は,いわば神様が,「これ(自我)を授けるから,この先は自分の力で生きていきなさい」といっているような出来事です。自我はいうまでもなく人間が創り出したものではなく,われわれの知恵のおよばない理由で人間に備わっています。人知を超えた理由ですから,それを例えば神という言葉で表しておくのも,荒唐無稽ということはないだろうと思います。
この契約はしかしながら一方的で,赤ん坊の方は引き受けたつもりがないという事情があります。しかし相手が人間であれば不当な契約ということになるのですが,神であればそうはいきません。とにもかくにも人間であれば,自我による私という現実は歴然としてあるので,「授ける」ということに対して,「分かりました,引き受けます」というしかないのです。引き受けるというのは,自分にふりかかる一切をという意味です。これが雄雄しい精神です。
そのようにして人間としての心の旅路がはじまるのですが,自我を授けた神はどうするかといえば,心の無意識の領域に座して,沈黙のうちに自我の仕事を見つめることになります。
ところで先ほども述べたように,一方では引き受けたつもりがないという事実があります。そして引き受けないというのはどういうことかといえば,死ぬということです。神に向かって文句もいえないので,母親に向かって,なぜ生んだのかなどと食って掛かることも起こります。ところが母親としては,全責任を負うという立場にはありません。父親としても同様です。それぞれの責任はあるにしても,本人が自分の責任において引き受ける精神がなければ,この問題の根本解決は望めません。引き受けない心は,いわば神に対しての異議申し立てということになり,神罰としての死があることになるといえるでしょう。だから死は容易ならぬ問題であり,恐るべきものという性格を持ちます。引き受けないわけにはいかないものを引き受けたくないというのは,女々しい精神です。
引き受けるかぎり自我は仕事をします。そして引き受けたくないかぎり自我は機能しません。無意識に座する神は,自我が神の意志を体現しつつある様子を見守ります。それは公正無私で,ある意味で呵責ないものにもなります。
引き受けない自我は次のようにして問題を抱えることになります。
例えば2歳の子(D)が兄(姉)になったとします。甘えたい盛りで母親を奪われたことになります。弟(妹)が眠っているときにDが母親の膝に乗ろうとします。ところが疲れている母親にうるさがられます。何度かそういう目にあっているうちに,Dは甘える心を断念します。それは2歳の自我が甘える心を引き受けなかったことを意味します。いうならば自我が,甘えたがる心を無意識という牢屋に閉じ込めてしまうのです。年齢を考えれば責められないのですが,理不尽なことをしたことになります。自我に引き受けられなかった心は,死ねといわれたのに等しいのです。
このような分身たちは,誰の場合でも作り出されます。それは自我に拠る人間の宿命です。これらの影の分身たちが一大勢力になると,自我の自立性自体があやしいものになります。それを内在する神なる主体の視点からすれば,自己の達成が由々しいことになり,見離されることになっていきます。自分自身が自分を見離すともいえるでしょう。言葉を換えれば,人生の大道で自分を見失うことになります。
死にたくなるときには,必ずこのような(引き受けられない)心の状況ができていると思います。そしてこのような心の状況では,さまざまな形で母親,ないしは父親に大きく気を取られていると思います。それらの親子関係での何らかの重圧のために,自分のために生きる,という当然のことができなくなるともいえるでしょう。
こういうときにどうするべきかといえば,答えは常に一つしかありません。自我が引き受ける以外に手はないのです。なにを引き受けるのかといえば,影の分身たちをです。 分身たちは,死ねといわれたのに等しいものたちなので,怒りとともに死を志向しているのです。自我はもはやそれに対応する力を持てないと感じたときに,死を意識すると思います。そのような状況にある自我はほとんど機能が固化しています。いわば自由な自我が不在になるのです。この機能が賦活しなければならないので,さしあたり力をふりしぼって,「死ぬわけにはいかない,いまはその力がないが,あなたたち分身を引き受けるつもりだ,しばらく待ってほしい」と影の分身たちに言明してほしいと思います。そして,死を志向する心の動きを見張り,可能なかぎりそれを排除する仕事が求められます。心が生きていこうとする精神で統一されるにつれ,自我の機能が回復されていくでしょう。そうであれば,自ずから生きるために有用な心の動きがはじまるはずです。そうすることで,一旦は知らずに死ねといってしまったものたちを,改めて救い出す決意を固めることになります。
‘05/09/14
断片集-その8
■白い満足,黒い満足-1
満足感と安全(安心)感の追求は,動物一般に共通します。それは生きていく上で不可欠のもので,本能的な欲動に基づきます。
動物の行動は本能的で,従って身体的な行動に終始します。動物は欲求が生じたときに,あるいは危険が迫ったときに行動し,後は寝そべるなり,ぶらぶらするなりして過ごしているように見えます。哲学者のショーペンハウエルは,動物が目の前のことにだけ関わりを持つ傾向を称して,直前存在といっています。
動物の中で人間だけが本能的な行動にとどまらず,精神的な満足を追求します。その拠り所となるのが自我と呼ばれているものです。人間を特徴づけ,人と動物とを分けるのがこの自我です。
何であれ,行動をするときには意志が働きます。意志は心の親(自我)が計画を立て,それに呼応する心の子と協調して成立します。心の子は,親の呼びかけに応じて無意識の海から生まれる欲動ないしは欲求です。
自我には心の頭としてのエネルギーはありますが,実際に行動を進めるエネルギーは持っていません。行動するエネルギーは,そのたびに無意識の海から呼び出すことになります。心の親と子の関係は騎手と馬のそれに似ています。
心の親には,呼びかけに応じて生まれてきた心の子に責任があります。この子は無意識から生まれてきたばかりの自然のものですから,大変傷つき易いのです。親は一定の計画に基づいた行為をしているあいだ,この心の子を護り通せるかどうかが問題になります。
どのようにして護るかといえば,現在の行動(行為)を共にしてくれているものへ感謝の念を持ち,それを喜べることによってです。
行為ないしは行動は意志に基づき,必ず目標を持っています。その目標へ向っていくということは,大きいか小さいかは別として,希望に向っていくということに他なりません。そうでなければ行動への意欲が湧きようがないのです。意欲があるかぎり,それは希望に向っている以外の何ものでもありません。
たとえば身体に異変を感じて病院へ行くときに,何か悪い病気が予感されると,希望など,かけらほども見えないかもしれません。
しかし希望が皆無であれば,行動することができるものではありません。病気の性格を知り,治りたい希望が根底になければ病院に行く気になることはないでしょう。
何か行動をするときには必ず目的があり,希望がありますが,理想をいえば一直線にその目標へ突き進みたいのは山々でしょう。病院に一刻も早く着き,理想的な人格と技量とを備えた医師に出会い,納得のいく治療をしてもらいたい,そう思うのが人情というものです。
ところが道路が渋滞する,応対した受付の人が気が利かない,長々と待たされる,ようやく診てくれた医師がなんだか頼りないなどなど,目標はさまざまな障害に行く手を阻まれます。怒りや不安や不満で一杯になれば,希望などはかけらもないことになります。
しかしそれは行動の裏に目的,希望がなかった理由にはなりません。不安に圧倒されている自我が,行動の協働者である心の子を護れなかった姿なのです。
満足には白いものと黒いものとがあります。
食事を例にとると,気の知れた仲間と楽しむ食事は白い満足です。そして過食症者の過食は黒い満足です。白い満足としての食事は,心の親である自我に活気があります。その親に呼び出された心の子である欲動も活力を発揮します。活気のある親の下では力を出し,無気力な親の下では力を出さず,親しだいで子の活力が変わります。(格闘技の選手が,試合前に顔や手足を叩いて気合を入れているのは,心の親のやる気を心の子に伝えようとしているのです)
心の親と子の役割分担は,前者が社会性や精神性にあり,後者は身体性にあります。両者は一体となって機能するので,明確に区別をつけるわけにはいかないでしょうが。
白い満足である食事は,人と共に分かち合うことができる満足で,つまり社会性があります。このとき心の子は,味覚や嗅覚,視覚などを動員して満足感の舞台裏を支えます。
一方,過食に耽っている人は,その姿を人に見せたくないと強く思っています。そして太っているので人前に出たくないと考えるものです。たとえ客観的には肥満していると見えなくても,過食症者は太っていて醜いと大変気にします。
人目を忍ぶ過食に社会性がないのは,自我の関与がないからです。自我は機能不全に陥っているのです。自我に拠るのが人間であり,自我は社会性や精神性を追求する拠り所でもあるので,身体的な満足に偏る過食は動物に類似した姿といえ,屈辱的なのです。太っていて醜いと考える本当の理由はここにあります。過食は精神的に満たされていないことと大いに関係があり(自我の機能不全化と黒い子をおびただしく作り出すこととの間には,相関関係があります。黒い子たちの支配を受けている自我は白い満足を得るのが困難で,黒い子が傀儡化した自我を無視して黒い満足を取りに行きます),黒い満足の一つである過食は刹那的な満足は得られても,精神性を欠いているためにいくら食べても満たされることがありません。それどころか自我が不甲斐ないと,繰り返し,改めて後悔する理由になり果てしない悪循環に陥ります。
一方で,逆にいえば精神性や社会性が身についている人であれば,少々太っていても自分が病的に醜いとは思わないものです。
’05/10/26
断片集-その9
■「頑張る」ということ
「頑張ってください」というのは,日常的に多くの人が何げなく使う言葉です。
何かの折に,信頼する誰かに,「頑張れよ」,「頑張ってね」といわれて悪い気がする人はあまりいないでしょう。
しかし場合により,人によっては,「分かっているよ」と内心でうるさく感じることがあると思います。
うつ病では,「頑張れ」といわない方がよいといわれています。多くの人がそのように理解してもいるようです。それは,「頑張れ」ということが励ましにはならないからです。励ましているつもりが,逆に圧力をかけることになりかねないからです。
うつ病者はそもそも「頑張る人」が多いので,その挙句にいまの不調があるともいえます。「頑張れ」といわれると,「まだまだ頑張りが足りない。いまの自分は駄目なのだ」という否定的な意味に受け取ることになりがちです。
それは「頑張る」というのが,元々は,他から課せられたもの(義務教育なので学校に通うとか,小学生の宿題とか)について,期待に応えていくという意味があるからだと思います。
何かをするときに動因となるのは,心の内から湧き出る意欲と,他から課されたものとの混淆であるといえるでしょう。
天分といえば,自然に才能が開花することかといえば,むしろそうではなく,親をはじめとした周囲の大人の厳しい管理的指導が欠かせないようです。関与の厳しさが才能の芽をつぶさないで済むのは,本人の意欲の強さ,才能への自信の強さがあってのことのように思われます。
いかなる行為にも他から課されたという側面が必ずあるからには,すべての行為に他者の眼差しが入っているといえます。その眼差しに応えようとするのが,頑張るということです。
最近はあまり目にしなくなりましたが,うつ病に陥る典型的な病前性格があるといわれてきました。時代と共に心の病気の様相も変わっていくので,現代では,うつ病といっても一様には論じかねるのですが。
この伝統的なうつ病の病前性格は,昭和時代の初期から中期に活躍した下田光造によって執着気質と命名され,概念化されています。
下田が活躍した当時の日本では,第二次大戦前のことで,国威発揚が声高に叫ばれていました。そういう時代ですから,批判的精神より滅私奉公型の精神が尊重されたのは当然といえば当然です。
この時代,思想や言論の統制,取り締まり,町内会を通じての意志の統制など,国家権力の下に国民が一途の規制を強いられ,扇動され,一丸となって全体主義国家へとなだれこんでいきました。自由精神は圧殺される時代でした。
人間の弱さ,悲しさは,時代の風潮に逆らうのが困難なことです。
自由な判断が許されているのなら,従ってはならないことに逆らうのが良心です。
外部から巨大な圧力がかかったときに,その良心を保つのは至難といえます。自我が保身に向けて動き出すときに,意識の欺瞞化が容易に起こります。それは平時であれば卑怯ということになりますが,欺瞞化であるゆえんは,心の痛みを伴わないことです。つまり卑怯を卑怯と思わないのです。
そのようにして,国家権力によって課せられたものが,いつか自分からすすんで(国のために)引き受けるという意識になり,国民の大方が疑問を持たなくなります。
そうでなければ戦争などは成り立たないともいえるでしょうが。
人間に一番大切なものは何かといえば,自由と答える人が多いのではないでしょうか。自由が圧殺される状況は,平和な時代であれば犯罪的なものといえるでしょう。
だからこそ戦争には大義名分が重要です。
本当に自由を守るための戦争であれば,それは正義であり立派な名分になります。進んで,情熱的に,個人の自由を国のために捧げることも人は厭わないでしょう。
’命あっての物種’で,命があってこその自由ですが,場合によっては,自由を守るために一命を捨てることも辞さないということも起ります。
戦争では,必ず何らかの名分が掲げられます。その名分はいつも何らかの自由を守るためということになります。それは大抵は権力者たちの自由を守るためのものといって過言でなさそうです。そして自由に判断できるのであれば首をかしげるものであっても,戦争というほどの事態になると,多くの場合,国民の大勢はそれに従うほうへ雪崩を打つのが歴史的事実です。
いうことを聞かない小国を罰するのは,しばしば大国の正義になります。大国の市民の大勢がそれを支持するのが現実です。大国の国民の自由が,小国の国民の自由を踏みにじることで成り立つのであれば,それは自由の名に値いしないのですが。
力が強い者の自由の前に弱い者の自由が無視され,踏みにじられることは,個人的レベルから国家的レベルにいたるまで,いたるところに見られる現象です。個人的レベルでは,母と子のあいだで起こりやすく,そのために,子供が大きくなってからさまざまな精神の病理性に悩むという現象は,診療場面ではおなじみのものといえます。
自由というのは,いうまでもなく容易な問題ではありません。
精神性は身体性と切り離して存在することはできません。自由もその例外ではありません。
高度に純化された自由の精神とは,身体性が理想的に克己されたさまといえるでしょう。
おなじ理由から,不純なものを内に含む自由とは,身体性を無視し難く内に含んでいるということになるのです。
自由の精神が理想的に高くなれば,職業に貴賎はないとか,万人が等しく自由であり,平等であるとかということになるのでしょうが,現実の人間はこの理想からはるかに遠いところにいるので,これらの美しい理念は空々しい響きを持っています。
現実的な自由にば,個人的な利得,欲求などの身体性を色濃く内に含み,結局は力の強さの順番に,その種の自由は享受されるのです。
権力者の自由とは,しばしば,自分の利得のために他人の自由を奪って憚らない,自由の名に値いしないものというべきものでしょう。
私心を最大限に払拭した純化した高邁な自由精神の持ち主であれば,政治などに携わろうという意志を持たないだろうと思いますが,このように高邁なといえるほどに純化された自由の精神を具現している人は,極めて稀なことでもあるに違いありません。
一般的に自由というのは,甚だ不純な代物であることになります。
そのようなことがいえるので,自由の意識は,容易に欺瞞化されます。
執着気質者は,良かれ悪しかれ滅私奉公型であるのを特長としますが,滅私奉公という美風が,そのようなわけで権力者にとって甚だつごうのよいものであるのは否めません。
しかし以上の論旨でいけば,この気質の美風を不当にこき下ろしたことになりかねないので,補足が必要です。
滅私奉公型の精神にはそのような問題がはらまれているといえるものの,精神にかかわる多くのことがそうであるように,身体性のほうに偏るおぞましいものから,精神性の方向に浄化され,高邁というレベルに達している人に至るまで,十把一絡げというわけにはいきません。
滅私奉公型の中でも,下は力を持つ者に媚び,利得を狙い,狡賢く,濁った目つきの者たちがある一方,上はそれらの身体性が純化され,愛他精神といったものに浄化されている人々があります。執着気質と呼ばれる場合は,後者の意味合いが込められているといえます。
権力者に利用されないかぎり,この気質の人たちは有徳の持ち主です。歴史的にも,虐げられる民衆のために一命を賭して行動する人もあったと思います。
精神の高邁の中心にあるのは,自由の精神が健在であることといえるでしょうが,この観点から,対立する二つの典型的な気質を上げることができます。
一つは分裂気質者,一つは執着気質者がそれです。
両者を分けるのは,それぞれの自己が拠り所としているものの相違です。
人は自己自身との関係であり,同時に他者との関係でもありますが,それらを総合して心の中軸に何が位置しているかという問題です。
前者は自己自身,つまり内在する主体にあり,後者は集合体としての他者,つまり外なる主体とでもいうべきものにあると考えられます。その集合体としての他者というのは,内在する主体の外在化とでもいうべきものです。前者の自己の主な拠り所が内部(主体)にあり,後者のそれは外部(集合的他者)にあるという違いが,前者を超俗的にさせ,後者を世俗的にさせる理由と考えることが可能です。
前者は孤高の人として人々の輪から離れたところに存在し,後者は輪の真ん中に存在します。前者は冷ややかに,後者は暖かに,周囲の人には感じられ,前者は隣人愛よりは人類愛に,後者は人類愛よりは隣人愛に傾きます。
ところで頑張るというのは,先にも述べましたが,他から課せられたものを引き受けて,こなしていく努力というふうにいえると思います。
一般に何かの行為をするときに,内発的な欲求と,他者から課せられたものとが混淆して意志となり,動機となるといえるでしょう。両者は合い携えて何らかの行為を可能にするといえますが,そのどちらにより多く比重があるかによって,「熱中する」のと,「頑張る」のとの比重の違いとなってきます。
人は何ものかに依存しつつ存在可能ですが,個々の他者の存在を欠かせない拠り所としているのであれば,それは個としての確立が未熟,不確定ということになります。
自己がそれなりに確立されているとき,自己自身との関係,つまり主体との関係が計られているか,あるいは集合体としての他者との関係が計られているかのどちらかであるといえるようです。
前者は自己の拠り所がより内的なので,「熱中する」でしょうが,後者はそれがより外的なので「頑張る」ことになるといえます。
つまりは頑張るというのは,人の期待に応えようとするさまであるといえるでしょう。
自己の拠り所が‘より外的’であれば,それに生真面目に応えるためには,いわば‘あらゆる人の目に適う’ものでないかぎり,安心できない,申し訳が立たないということになります。どうしても完璧であろうとします。それが執着という意味になると思います。