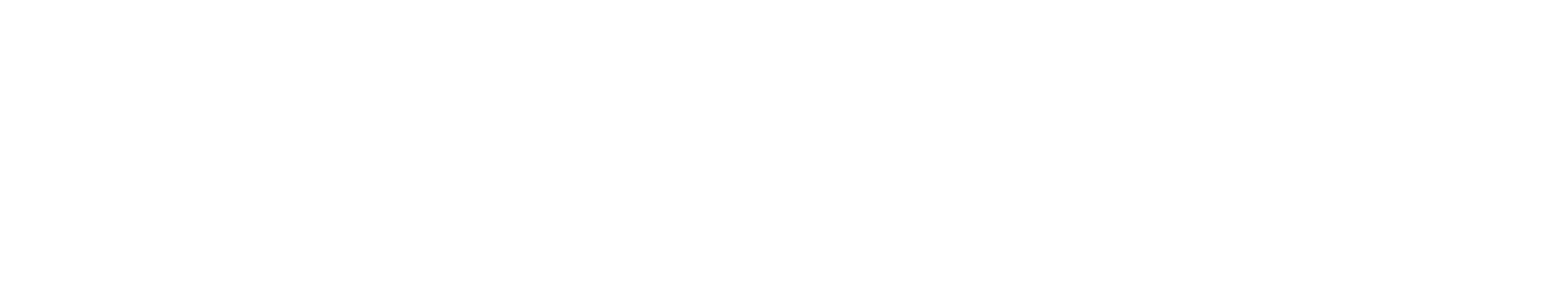院内通信 性格形成に与える母親の影響(摂食障害の症例を通して) H14.2.27
性格形成に与える母親の影響-その1
■人格と性格(外国の症例)
M子さんが治療を受けることになったのは,19歳のときでした。母親は若いころに多数の美人コンテストで優勝するという経歴の持ち主でした。娘にその夢を託そうとしたのでしょうか, M子さんが3歳になると早くも美人コンテストに参加させました。そしてコンテストに出すために,M子さんの体型をスリムに保つように仕向けました。
一方,幼い娘は美人コンテストなどには関心がなく,母親の期待をとても負担に感じておりました。また幼いころは病気がちでもありましたが,それはM子さんには好都合な面がありました。というのは,病気になれば美人コンテストなどには出なくてもいいからです。それに病気になれば優しくしてもらえるからです。とはいっても母親は,身体を心配してくれるよりは,コンテストに出られないことのほうを気にしました。それはM子さんにとっては腹の立つことでしたが,母親に怒りを直接ぶつける勇気はありませんでした。
M子さんは,母親の期待にこたえられないことにつよい自責の念を持ちました。自分がだめな人間であり,生きる価値がないと思い続けてきました。そして過食と拒食に加え,自傷行為を繰り返してきたのです。
この症例に即して,問題をどうとらえ,どう考えればいいのか検討してみます。
M子さんの主訴は,母親の期待にこたえられないことへの自責の気持ち,自分が生きるにあたいしないだめな人間であると考える自己評価の低さ,自傷行為,摂食障害などです。
この問題を考えるに当たっては,発病したときの状況はどうか,状況の病理性はどの程度かが重要です。これらは心にとって外的な事情ということになります。
それから本人の側のストレスへの耐性が問題になります。こちらは心の内的な事情ということになりますが,具体的には,生まれたときからの人格形成の歴史を知ることが参考になります。
心の病気は,身体の病気とはだいぶ違います。身体の病気では,人格とは無縁とはいえないものの,たいていは局所の所見だけを診て解決します。一方,心の病気ではそういうわけにはいかず,本人も気がつかないでいる心理的理由を探っていく必要が出てきます。
人間はすべてなにがしか神経症的であるといわれるように,人格は,相当に無理を重ねて形成されます。というのは,人格は,人との関係での影響をつよく受けて作られるからです。人の中でも,特に両親の影響を受けます。それらの影響の下で,心がしだいに成長し,しかし,ときにはさまざまに傷つきます。それら傷ついた心は,幼なすぎるものには解決するすべもなく,その体験と,怒りや,恐怖や,落胆やの耐えられない感情とを,そのまま無意識の心に預けることになります。それらは未解決の問題として堆積され,沼のように無意識の心にたまります。これが人格に影を落とします。あの人は暗いなどといわれるのはそのためですが,この沼のように広がる不気味な気配のものはだれにでもあります。ふだんは意識にのぼることはないでしょうが,過去を振り返るときに,無意識的にそこに触れることがあります。そういうときは,不安,恐怖,苛立ち,落胆などのネガテイブな感情が,乳幼児期に体験したのとおなじようによみがえり,湧き起こって来るかもしれません。沼の情景は暗く,不気味なので,近寄りたくない気持ちになると思います。明るいといわれる人も例外ではありません。それが人格に宿すかげりが,暗い人として他人から敬遠される理由になることがある一方で,人間的な魅力を深める理由になる場合もあると思います。また,明るさが沼の気配を忘れていたいがための反動であるかもしれません。そのために軽薄な印象を人に与えることもあるかもしれません。だれにでもある犯罪への暗く,根強い関心も,この沼の存在に起因するといえると思います。
この一文では人格形成にあたえる母親の影響を取り上げます。もちろん父親の影響も考えないといけないのですが,この症例報告では父親のことに触れておりませんので,いまは割愛します。
人格という言葉を使いましたが,むしろ性格のほうが的確かもしれません。人格といえば「あの人は人格者だ」,「彼は人格ができていない」,「人格が破綻している」などなどといわれるように,人間のあるべき姿に即しているとか,道徳的に正しいとか,そのような価値意識がこめられているように思います。一方,性格という言葉には,そういう価値意識が入っておらず,現にある,良くも悪くもそのままの,事実としてのその人の人間の姿とでもいえばいいのか,そんな感じがこめられているのではないでしょうか。そういうわけで,ここでは性格と呼び直すことにします。
性格は,一つには生物学的に規定された,もって生まれた気質という面があります。そのほかにもう一つ,生まれたあとに形成された面があります。後者については,特に人間関係の影響が大きいといえます。植物でいえば根っこの部分,建物でいえば基礎の部分がしっかりしているかどうかが肝心なのとおなじように,人の心も,幼いときほど環境がおよぼす影響が大きいのです。また人間関係といっても,父親,母親以上に大きな影響力を持った人物はありませんから,事実上,親の影響が基本といえます。(このあたり,たとえば不登校の子について,学校に問題があるのか,家庭に問題があるのかという議論がしばしば起こりますが,これは台風で建物が被害を受けたときに,台風が原因か,基礎に問題があったかというのと似ているようです。要するに基礎をしっかりさせて,台風が来ても被害を受けないように対策が講じられている必要があるのです)
母親が三歳の子を美人コンテストに出すなどということは,日本では極端に過ぎる例だと思います。しかし,たとえば幼い我が子を受験競争に駆り立てるというおなじみの現象は,それに似ているものがあります。
性格形成に与える母親の影響-その2
■愛情の問題
M子さんの母親がしたことは,娘への愛情なのでしょうか。これが問題です。母親は愛情と信じているかもしれません。「娘に素敵な体験をさせて上げたいと考えるのが,どうして愛情でないといえるのでしょう」と彼女はいうかもしれません。あるいはそうかもしれません。将来,娘が,母親がしてくれたことを感謝する場合だって考えられないわけではありません。
そうすると,この母親の行為が愛情に値するものかどうか,誰がどのようにして決めるのでしょう? また仮に,この母親の行為が愛情とはいえないということが判明すると,どういう問題が生じるのでしょう。M子さんの場合は,摂食障害や自傷行為という痛ましい問題が起こっているわけですが,それとどんな関係があるのでしょうか?
他人には,それぞれの意見があっても,誰であれ裁判官のような権限で判定する力はもちろんありません。ただ,誰か周囲の人が,母親の行為に危惧の念をいだき,M子さんの将来を心から心配して説得するということはあり得るでしょう。その人を母親が信頼していれば,説得が実を結ぶかもしれません。母親が,心の迷いを正してもらえたことを感謝するかもしれません。それはそれでいいことです。人間の関係としては,そのようでなければならないともいえると思います。しかし,そういう場合でも,母親の行為が迷妄であり,真の愛情ではないと言い切れるかどうかは別問題です。さらに母親が自分の正当性をあくまでも主張するとき,どちらが正しいかは,なおのこと一概には決められなくなると思います。
そうしてみると,M子さんの母親が愛情に基づいた行為であると主張することの当否を,誰か人間が判定するのは,煎じ詰めると不可能ということになると思います。
なぜこういうことが問題になるのか,それ自体も問題です。
親が子に愛情を注ぐのがしばしば難しいのはなぜでしょう。そうすることが当然であり,よいことであり,必要であり,仕合せな心でいられる理由になると誰もが容易に分かるはずのことなのに,実際には,その実践がむしろ難しいのは不思議なことです。 愛情を注ぐどころか,憎みさえするのも珍しいことではありません。憎むとまではいかなくても,愛情という観点からすると問題のあるしつけをしてしまうのは,残念ながら,普遍的な現象だといえるでしょう。
愛情に似て非なるものの典型は,親の考えや価値観の押しつけです。言葉を換えれば,愛情の名を借りた侵入です。それは乳児が,母親に全面的に依存する母子一体の時期を経験することとも関係があるでしょう。母子の蜜月時代の体験は,それ自体が母子双方にとって素晴らしいものであるでしょうが,乳児の成長の基盤の形成という観点からも大いに意味のある大切なことです。
自分が生んだ赤ん坊によって与えられたその素晴らしい体験は,母親のみに許された,余人には味わい得ない稀有なものであろうと思われます。赤ん坊は母親にとって,俗にいわれるように,天から授けられた宝物という趣きを持っているといえるのでしょう。
そうした体験もふまえて,生まれてきた赤ん坊の将来に,母親が一定の好ましい期待イメージを持つことはむしろ当然です。その仕合せが継続するように,豊かな未来が待っているようにと,心に願いを抱くのは,もちろん不思議なことではありません。
ただし,この体験に即して,母親には二通りの願望が生まれるのではないでしょうか。一つは,愛すべき我が子の将来の仕合せへの願いと,もう一つは,母親自身がこの稀有の仕合せを失いたくない願いと。これら二つの願いは,母親にとっては,分離して考えることが容易にはできないものであるように思われます。「あなたのためなのよ」といいながら,その実,母親自身の仕合せのために然々のようでありなさい,というメッセージが向けられるのは,ありがちなことだと思います。
二通りの願望のうちの後者が優っているとき,母親はなかば無意識的に子供を操作しようとします。ターゲットになるのは,子供たちの中でも母親思いの反抗心の少ない子です。子供も母親の言葉の矛盾になかば気がつきながらも,母親を怒らせたくない,悲しませたくないという恐れから同調することになるのです。
子供が成長するにつれ,母親の期待に即することが窮屈になり,不満にもなるのは必然です。それは成長の証でもあるのですが,それに対応できない母親(父親も無縁ではあり得ません)には,期待イメージどおりに育たない子供への愛情に曇りが生じ,憎しみの感情が賦活してきてもおかしくないのです。裏切り,忘恩といった感情も持つかもしれません。
このように,愛情というものの性格をはきちがえる母親は,子供を自分の支配下に置くために,意識的,無意識的に手段をつくすものです。母親によっては,自分自身が満たされない心のままで大人になり,母親になり,母子一体の蜜月時代の仕合せな感覚が,ほとんど唯一生きるに値した体験である場合もあるだろうと思います。そうであれば,それを永久に封印したいと無意識が考えることにもなるのです。極端な場合には,表層の意識はともかく,子供の幸福などはまるで念頭になくなってしまうのです。こうなるとほとんど犯罪的といえるほどの心的状況になってしまうといっても過言ではないでしょう。事実,いわゆる虐待は,この意識の延長線上で起こる問題です。
人はどうかすると幸福であるよりはむしろ不幸です。人が自分自身を愛しているかといえば,むしろ,しばしば愛していません。自己愛と他者愛とは一対の関係にあります。愛情と信頼も一対のものです。自分自身を愛し,信頼する心が希薄であれば,他人(子供も含めて)を愛し,信頼する心も希薄になります。逆に人に疑いの念を持ち易く,恐怖心をいだきやすく,怒りの感情が内向します。
また,愛は単独で愛であることはなく,憎しみと対をなし,背中合わせにつながっているのです。つまり愛があれば,その裏に必ずなんらかの形で憎しみがあります。人間の本性としてそのようなことがいえるので,親がかけがえのない我が子に対して,憎しみ,怒りの感情を持つとしても必ずしも不思議なことではありません。
愛と憎しみとが,一方が存在するためには他方の存在を必要とする関係にあるということは,人間の心の構造的な問題であり,人の心を考える際には重要なことです。
愛している心の裏に,必ずなんらかの憎しみがあります。かつては愛していた人に裏切られれば,陰に潜んでいた憎しみが表に出ます。そして,また,憎しみの情に苦しむとすれば,その裏切り者を愛する心がいまも失せていない証拠です。その人への愛がなくなったためではありません。愛する心が強いのに,その対象を所有することが不可能になってしまったからです。
怒り(憎しみ)は破壊的な力を持っています。愛していた人に裏切られて憎しみの情が長く続くと,怒りがなにものかを破壊するかもしれません。裏切った相手との関係を破壊する動きをするか,あるいは内向する怒りが心を破壊(心の何らかの不調となって表われます)するかということが考えられます。
こういうときに自我が主導的な動きをできるかどうかが,肝心です。憎しみを持っている相手との関係を修復する見込みが立たなければ,その関係は終わらせなければなりません。怒りは相手に向かうのですが,自我にも向けられています。怒りは自我に所属するものではありません。いわば自我の不始末に伴って生じるもので,無意識のものです。
怒りを向けられて自我が立ちすくみ,それを受け止めることができなければ,怒りが直接に相手に襲い掛かり,関係を破壊し,混乱に陥れます。怒りには,事態を収める能力はありません。それは自我の仕事です。破壊と混乱の後に怒りが鎮まると,改めて相手への恋慕の情が残っているのを知り,その感情を扱いかねることにもなります。また,本人の人格,品性が疑われることにもなります。怒りには,正当性があっても,分別がありません。
自我が怒りを受け止めることができれば,相手との関係を終わらせる心の作業に取り掛かることになり,やがては最終的な決着が図られるでしょう。
この問題の根本は,おそらく,出生に関連したものです。生まれたばかりの赤ん坊は,恐怖と驚愕と怒りの中にあると想像されます。母親の子宮の中で身体と心が形成されていく過程が,出生へのそれなりの心の準備期間ではあっても,いうならば’いきなり人間にさせられてしまった’驚きと怒りがあるに違いありません。そのように仮定的に考えるのが自然ではないでしょうか。それをなだめ,慰めて,人としての心構えのようなものを整えさせていく役割を担っている中心人物が母親です。赤ん坊は母親を頼りとする以外にありませんが,今度はその母親に置き去りにされる恐怖に耐えなければなりません。絶対依存の身では,そういう恐怖と無縁であるのは,ほぼ不可能です。母親の’愛’は絶対ではないからです。
赤ん坊の怒りは,人間以前のものに返せということかもしれません。ということは,既に人間の身である以上は,死の要求という意味を持ちます。赤ん坊は生を受けることにより,死をも生きなければならない身なのです。また,自我の活動が未分化である赤ん坊の代理自我は母親のそれなので,怒りは母親へも向けられます。それは空腹やおむつの汚れの不快なども含めた,情緒的に満たされていないことに伴うものではないでしょうか。拡大して考えれば,死をかけて情緒的に満たされたいと怒っているといえるのではないかと思います。
怒りを向けられたことによって,代理自我である母親がその意味を汲み取り,満たして上げることができれば,怒りは自我に解決を求め,自我がそれに応じたことになり,それは人間の心のあり方として望ましいことです。ところが母親が,何らかの事情で赤ん坊の怒りの意味を汲み取れなければ,赤ん坊の怒りは,母親との関係も自分自身の心も破壊することになるかもしれません。つまり母親との関係がいびつになり,赤ん坊自身の心もまたいびつになり,将来が案じられるということです。この場合怒りは,受け止める自我の不在によって,単なる破壊者になります。
こうした原初の事情があって,人は一般に,自分が他人に受け入れられないのではないかという不安を持ちますし,信じていた者が遠ざかろうとする気配を感じると,不安や悲しみや怒りを持つのです。特に乳幼児の段階で,いま述べたような意味で外傷体験といえるほどの傷を心に負うと,長じて,他人に受け入れられることに自信を持てず,関わりのある人に置き去りにされるのではないかという不安が耐え難いほどになります。そのために人に対して恐怖を持ち,回避的になったり,被害感情を持ちやすかったりということにもなるのです。
ある女性は,同棲している男性に,一時間に五回も六回も,「愛している?」と訊いてしまうといいます。
愛と憎しみとが一対のものであるというのは,自我に拠る人間の心の構造に基づくといえます。自己が存在することの原基は自我機構にあると思われます。そして自己の存在構造には,他者が組み込まれていると考えられます。愛と憎しみとは,このような原理に基づいており,他者の存在が前提となっています。
また,以上のことを前提に,自己愛と他者愛とは一対のものであり,自己および他者への不信も一対のものといえます。
自我は,愛を追求します。そして,憎しみが心を苦しめれば,それを受け止めるべきものです。自我が憎む心を受け止めることができれば,問題の解決の基盤ができたことになります。そして,苦しい体験を克服することによって,心の成長がはかられます。
例えていえば,次のようにいえます。
愛は主人公の自我と共にあります。自我が力強ければ,愛は健やかです。憎しみ(怒り)は主人公の無意識なる海の中にあります。憎しみは愛が憎いわけではありません。その証拠に愛が健やかであれば,海は穏やかです。海が荒れるとき,怒りが姿を現すのです。そして海が荒れるのは,愛が危殆に瀕したときです。怒りは愛の後見人であるかのようです。
自我が愛の世界を豊かに保持できるとき,無意識なる海は生の豊穣の源であるといえます。自我が愛の世界の貧困を招いたとき,海は怒りによって荒れることになります。無意識なる海は,愛の枯渇に比例するように,熱い怒りと,それにつづく凍りつく静寂の様相を濃くします。それは死の世界の様相です。
自我は生のものであり,自我の不首尾は,その影響を蒙ったものを無意識に葬り去る意味を持ち,その場合の無意識は死の性格を持ちます。
愛は生きる方向で発展します。憎しみは愛の破壊者です。前者の場合,自我は無意識との関係を尊重し,調和させることができていることによって,無意識は生の拠り所となります。そして,生を切り開く使命を持つ自我の働きによって,心が豊かになっていくでしょう。ところが自我が愚かにも無意識との協調を撹乱するように動いてしまえば,自我は生を切り開くよりは,無意識の恐るべき相貌である死の方向に引きずられる結果を生み出すことになるのです。自我の拙い介入によって,無意識の自然をいわば人為的に歪めるようなことになれば,心は貧困に傾くでしょう。これらの意味で,愛は自我と共に生の世界にあるものであり,憎しみは自我の不始末と共に死の世界に属するものです。
信と不信についてもおなじことがいえます。愛と信とは一対のものです。
ある中年男性が,次のような内容の夢を報告してくれました。
一つは「底なし沼に落ちて,もがいている。水面には無数のあぶくが泡立っている」 もう一つは「仔犬と遊んでいる。急に仔犬が怒り出し,足に噛みついてくる。犬に引きずりまわされる」
二つとも恐怖夢です。
この男性は,人との関係をなによりも大切にし,争いを嫌います。人には明るくて,協調性があり,気の置けない人という印象を与えていると思うといいます。そのように見られたいとも思っています。争いは嫌いなので,昇進は望んでいません。しかし,旧友と会って,管理職になったとか,会社を立ち上げたなどという話を聞くと,自分は結婚もしていない,これでいいのかなと動揺します。秋口には,退社時間が憂鬱です。外はちょうど日暮れ時で,寂しくなるのです。夏はまだ日が高く,冬は日が既に落ちているので,平気でいられます。
この男性は長男で,唯一の同胞である妹は結婚しています。父親は無口で,いつも機嫌が悪かったそうです。酒が好きですが,飲んで帰ると,すぐに寝てしまうそうです。母親には,いつも怒られていたといいます。
二つの夢は,無意識の領域に大きな問題があることを示しているようです。他人への配慮がいき過ぎたためでしょうか,情緒的な欲求が満たされることが少なかったようです。おそらく両親との関係に発端があったと思われますが,そうした欲求は,抑圧する習慣ができてしまっているのだろうと思わせます。
仔犬が噛みつくというのは,そのあたりのことが夢に現れているのだろうと思います。この男性は情緒的なものを求めている(子犬と遊ぶ)のですが,抑圧されつづけてきた情緒的なものは怒りと共にあるのです。怒りは,本来あるべき望ましい働きをしてこなかった自我に向けられています。
泡立つ底なし沼は,怒りによって荒れる無意識です。怒りは,自分自身のために生きようとするところが少なかった自我に向けられ,自我は沼に引きずり込まれそうになっているのです。
他人との協調に気を遣い過ぎて,その分,無意識との協調を怠った様子が,この夢からうかがわれます。
愛情に満ちていると信じていた人の顔の裏に,それとは似ても似つかない憎しみの心が潜んでいるかもしれないと考えるのは恐ろしいことです。(そういう疑念に取りつかれると,神経的な病気になってしまう危険もあります。妄想は,信と不信,愛と非愛といった心の二極構造が,何らかの理由で固化してしまい,信頼の極が機能しなくなった様相と考えることができます)
M子さんには,母親との関係で,幼いころにそういうことが起こっていると考えることが可能です。もっとも自覚的ではないだろうと思われます。むしろ,母親の愛情を信じようとしているのではないかと思います。M子さんが母親に逆らわない様子があり,一方で心を病んでいる様子があるところから,このようなことがいえるのです。心の表と裏には,甚だしい矛盾,乖離があるだろうということが窺われます。
こういう問題は,年齢が進んでから起こり始めるということは,ほぼ考えられません。心の障害が表面化しているということは,自我が受け入れようとしない,あるいは受け入れる力がない,そういうものを自我に代わって,あるいは自我を無視して,無意識の心がなにものかをアピールしようとする試みであると考えることができます。そういうものの中で,いわゆる外傷体験といわれるものであれば,自我が事の大きさに衝撃を受けて,受け止めることができなかった体験ということになります。自我は,そのとき大急ぎで抑圧機能を行使したのです。あたかも機能麻痺に陥ったかのような事態でも,自我はそのような働きをして,自分のキャパシティを護ったのです。そして時間が立てば,自我はおもむろに回復して,記憶の空白となっているそのことを想起することができるようになります。つまり,原則的に想起可能なのです。ところが摂食障害のような問題については,その意味での外傷体験が原因であるとは,およそ考えられません。それは食に関わる人間の本能的,原始的な行動異常であり,著しい退行現象という側面があるからです。そして,それが極めて激しい欲求であり,それが世界の一切であることを示そうとしているかのようであり,生きるエネルギーの激しさでありながら死を賭してでもやめるわけにはいかないという死の色が表われていることでもあり,大人である病者が,必死に訴えようとしているのは,乳児の渇望と捉えることで,なんとか納得がいくことのように思われます。そして,そうであれば,情緒的な満足への激しい渇望ということなるのです。そういうところからどうしても生まれて間もなく,母親との関係で,何らかの恐怖体験をしたに違いないということだと思われてくるのです。そのために幼い自我は,自分を抑制(情緒的なものを抑制するのと同じことです)するのが習慣になり,要するによい子となって母親との関係を保とうとしたのではないでしょうか。ですから,母親が大好きと信じてしまうのが安全でもあるのです。それは,先に上げた男性の例のように,他に配慮しすぎて,自が疎かになるということです。
母親への怒り,憎しみもあるはずです。自傷行為や摂食障害には,内向する怒りが関与するものであるからです。それらは無意識の世界に収めてしまい,自覚的には母親を信じ,愛しているつもりになっているということではないでしょうか。
そのように見ていくと,M子さんが幼いころから病弱だったのも,同様に内向する怒りと,それを招いただろうと思われる情緒的な欲求の抑圧がからんでいると考えるのが自然ではないかと思います。そして,M子さんは,それらの病気を利用していたようです。病気というのは辛いものです。それをよしとする心は尋常ではありませんから,そういうことが起こっているということは,病気以上に辛い現実があったということだと思います。
その辛い現実を,母親に向かって言葉で訴えることができなかったのは,M子さんの気の弱さからでしょうか,それとも母親への恐怖が強すぎたからでしょうか。もしかすると,自分でも辛い現実であるとは思っていないかもしれません。そういう思いを持ちつづけるのは苦しいことですし,エネルギーを必要とします。そういう本音のようなものは,すっかり無意識に預けてしまって(自我の不始末),意識的には,母親の愛情を信じ,自分も母親を愛していると思っているかもしれません。その方が気が楽のはずですし,また,実際にそのようなものへの憧れがあるはずでもありますので,いうならば嘘であっても信じていたいというふうに,心が動いてもおかしくはありません。しかし無意識に溜め込まれた不満は増大していることは明らかで,それを考えれば意識の欺瞞というものがあるのも明らかでしょう。そして,それらの無意識の反攻が身体の病気という形を取っていると考えられるのです。
M子さんの自我が恐怖にめげずに,勇気を奮い起こして母親に立ち向かうことができていれば,それは自我が立派に役割を果たしたことになり,無意識との調和を保つことができただろうと思います。そういう姿勢で臨んでいれば,母親の対応の仕方も違っていたかもしれません。
ともあれそのようなことが起こり得るのが,人間の心の真実です。信じていた人に,あるとき不信の念が生じるとしても不思議はないのです。むしろそういうふうに,信と不信が交錯するのが人間です。いずれにしても,”ほどほどの満足”というのが人間の分ですから,信頼もほどほどのものであるしかないのです。誰か重要と考えている人に絶対的な信を置いているとすると,そこには何らかの無理,自己への虚偽,背信が隠れているかもしれないと考えてみる必要があります。
カエサルが暗殺されたときに,「ブルータス,お前もか」と叫んだという有名な逸話があります。信頼している人にひどい裏切られ方をすると,受けた心の衝撃は,その人の人格を変えてしまうほどのものでしょう。カエサルのブルータスへの信頼が絶大なものであった分,裏切られた絶望の大きさも察しられるわけです。
しかしこのエピソードには,信頼しきることの心根の美しさというよりは,権力者の驕りがうかがえるのではないでしょうか。ブルータスは裏切り者であったかもしれませんが,絶対の忠心という隷属を拒否したと考えることも可能です。ここにはカエサルの自己過信と,傲慢とが招いた悲劇の様相が現れているように思います。
権力者は,周囲の者に高い要求を持ちやすいものだと思います。人への高い要求は,一般的には恋人同士や夫婦や親子などに見られますが,要求を高くする背景には怒りがあります。そして他人(そして自己自身への)一般への不信と恐怖があります。
カエザルのブルータスに対する絶対的な信頼は,心の裏面に,不信と恐怖と怒りが強いエネルギーと共にあったことを示していると思います。
母子の関係にも,これに類似するものが見られることがあります。それは決して珍しいことでもありません。子供を自分に隷属させておきたいと考える母親は,無意識レベルをも含めると,普遍的とさえいえるほどおびただしく存在しているでしょう。一見すると仲がいい親子であることも多いので,母親も子供も無自覚になりがちな問題でもあります。しかしそういう関係に無力に依存する子供は,生涯にわたり,自分らしく生きることが難しくならざるを得ないでしょう。無力な依存よりは,ブルータスのように隷属を拒否する反抗心が,むしろ人間としての心を育てるのです。
ある青年は母親が100パーセント好きだといいます。母親は君のことをどう思っているだろうと訊くと,恐らく100パーセント好きだというと思うと,自信たっぷりにいうのです。家で下着でくつろいでいると,母親は,性器のことをしばしば口にするそうです。青年もそれを不快に思うことがありません。二人はほとんど近親相姦の関係にあるようで,青年もそれを認めています。しかしそれが問題だという実感はないのです。
彼の問題は社会性が育っていないこと,自分が社会人としてなにをすればいいのか見当がつかないことなどですが,母親との関係で自足している面があり,いまのままでも特には困らないのです。単に母親が長生きしてくれればいいと思うだけです。
「どうしたら友達を作れますか?」と質問しておきながら,「別に欲しくはないんですけど」とつけ足します。せっかく入った大学を,合わないような気がすると,あっさりやめてしまいました。万事に切実感がありません。
母親が息子との赤ちゃん時代の蜜月関係を手放したくなかったのかと思われます。息子の成長を阻止し,自分に隷属させることに成功したというふうに見られなくもありません。本人が問題視しないかぎり,他人がとやかくいう筋合いのものではないともいえるのでしょうが,青年が母親の身勝手な愛玩物に仕立て上げられてしまっているのは明らかなように思われます。母親の愛情のあり方に,ブルータスのような怒りを向けることができていれば,彼の人生への悩みは,もっと実のあるものではなかったでしょうか。彼の人間としての自尊心も,より高度なものではなかったかと思います。
愛する者を愛しつづけるためにも,憎しみの心が正当に扱われなければなりません。あってはならない関係を断ち切るために,怒りを向けることも必要です。母親がどんな魔術を使って息子の怒りを封じ,いつまでも幼子のように母親の許にとどまることを可能にしたのかは分かりません。しかし,そこに性的なものが介在しただろうことは,容易に察せられることです。性のエネルギーは強力であるだけに,それをほどよく満たしつづければ,息子をいつまでも自分の許にとどめて置くことも可能になるのでしょう。残酷さをはらんだこのような愛も,愛の形態の一つです。しかしながら,子供の心を思うように支配しようとする欲求は,表面はどんなに優しく見えても,子供自身がある種の満足をしているとしても,自分本位で残酷な心に基づくものといわざるを得ません。
”ほどほどの”というのが人間の分としては大切なところです。愛に関しても,それを徹底させようとすると,いつしか憎しみに変貌しかねません。憎しみの心は,それを反省する余裕がなければ,力づくで相手を支配しつくそうとする心の動きにつながるでしょう。自分が望むように相手を支配することができなければ,自分自身が限りなく不幸で,可哀想なのです。その要求を押し通すために,愛の仮面を躊躇なく身につけることも力の行使の有力な手段です。反省する心がなければ,それを相手への愛情と信じこませてしまう欺瞞化する意識が,いわば無垢の心のように,手つかずにとどめ置かせることになるのは必至です。 先にも述べたように,母親は赤ん坊に対して,特別の位置にあります。それは,時によっては特権的な立場と錯覚させるものです。母親が心に満たされないものがあり,依存欲求が強いときに,夫の理解と協力が足りなかったり,あるいは夫を見下すような夫婦関係であったりすると,赤ん坊は危険な状況にあるといえるでしょう。母親の恰好の依存の対象とされるという意味でです。そういう心的状況にある母親は,自分でも意識していないレベルで,怒り,不信の感情を強く持っている可能性があります。場合によっては怒りを振りかざし,あるいは愛情の仮面で怒りを巧妙に隠蔽し,子供を支配しようと,あの手この手と策を弄するとしても不思議はありません。もちろん,自分に悪意があるという自覚はないでしょう。子供のために努力していると思うのではないでしょうか。子供に対して,特権的な立場にあると感じているとすれば,子供が服従するのは理の当然で,なんの疑問もないのです。母親自身が子供時代にその母親からおなじような扱いを受けてきたとすれば,ますます,それは気分的に正当化され易いと思います。母親が自分の間違いに気づく機会は,ほぼ絶望的にないのと同様に,子供も母親の自分への支配的な依存の片棒をかつぐ関係から脱することも絶望的に困難になるでしょう。それを脱する唯一の可能性は,子供が怒りを持ってそういう母子関係を切断する力を持つときです。
愛の真実についてあまりに理想を求めるとき,それは,愛の欠乏に耐えてきたことの反面の姿といえるでしょう。その心の裏には,強い不満や怒りが潜んでいるものです。母親が子供を相手に愛情についての錯覚に陥るのは,真実の愛情というものにこだわる心が災いしたと,場合によってはいえるのかもしれません。そういうものを求める心の根については,同情されるものがあるに違いありません。しかし,それは必ず新たな災いの火種を作り出さずにはおかないでしょう。ほどほどの愛に自足できなければ,ある程度以上のことは笑って許せるほどの寛容と遊びの精神がなければ,この世はどうしても地獄化することになるようです。
心の病理的な問題を扱う立場にある治療者は,患者さんの心の形成過程を見ていかなければなりません。その際の中心的な問題は親子関係です。親の子に対する愛情が,適切かつ豊かであることが仮に証明できれば,目の前にいる患者さんの心の障害がなぜ生じたのか,ほとんど手がかりを失うに等しいといえます。ですから一般的に,問題がないかのように見えても,なにかが隠蔽されていると考えないわけにはいきません。そして,事実,治療の進展に伴って問題が語られ,明らかにされていくのがふつうです。その場合,親の子に対する養育姿勢の理想が,適切かつ豊かな愛情にあるとするのが前提とすると,自ずから親の子に対する愛情の希薄,歪み,悪意,憎しみが問題になることになります。
親のあからさまな子供への攻撃が見られることは,稀にはあるにしても,一般には少ないと思います。しかし,表面に現われている様子がおおむね穏やかであっても,愛情とは別種のものが裏面で暗躍していることは珍しくはありません。それは子供の心に暗い影響を与えることになるでしょうが,子供自身もそれを深く隠蔽して問題視しようとしないことが少なくありません。問題があるのが明らかなのに,子供本人は心を語ろうとしないとき,治療上の進展が得られようがありません。その様子を見ていると,人間の不思議を思います。それはもしかすると,「治りたくなんかない」という表現かもしれません。いずれにしても,怒りがエネルギーを蓄えて潜在しているのは確かだと思います。怒りに言葉を与えるとすれば,「治ってなんかやるものか」ということになるのかもしれません。その種の恨みを自我が取り扱う気がなければ,それは自爆に向かうか,周囲を攻撃するか,どちらかになるしかない危険があります。
ここで注意を要するのは,いうまでもないことでもありますが,親の養育姿勢に関する客観的事実と,子供のイメージとして生じている主観的な現実とのあいだには,一般的にかなりの隔たりがあるということです。
本人の心に,自分のために,自分らしく生きるための基盤がそれなりに形成されているかどうかが問題です。それが現に形成されているのであれば,そもそも受診の必要がなかったでしょう。
ある患者さんは自分でも認める”いい子”で,母親に過度に依存的でした。あるとき,「母親とは価値観が違うと分かった。もう相談しても仕方がないと思っている」というのと同時に,「私の中に中心ができてきたような気がする」と自分から述べています。この感覚が大切です。そういうことが地に足が着くように確かなものとなっていくのが,治療的な目標です。
この方の場合,母親の現実は,「口では分かったようなことをいっていて,実際はまったく変わっていない。今も,昔も,私を支配しようとしている」と本人がいうように,以前と何ら変わっていないようです。そういう母親に見切りをつけることができた本人が,母親イメージを変容させることができつつあるということのようです。このようにイメージが変容していくことが心理治療の要点になりますが,母親なり他の家族なりが協力的に姿勢を変容させていくことが,治療環境を整えることになります。周囲の人は直接的に手を貸すことはできませんが(そういうことは余計なお節介,干渉になるのがおちです),望ましい姿勢で見守ることにより,患者さん本人が自己の回復に向けた心の作業を行い易くなることが期待できます。
家族という関係の中で心理力動が働き,家族成員個々の性格形成に影響を与えます。
家族の中で影響力が強い立場の者(ふつうは父親,母親ということになります)は,権力者に特有の盲点がある場合があります。常識があれば容易に分かりそうなことが,本人には不思議なほどに意識できない心があり,子供たちに被害的な影響を与えていることがあります。時には,特定のスケープゴートを作り出したりもします。
個々人の心は,家族という関係の中で良くも悪くも変容しますので,心理的な治療とはいえ,本人一個の問題ではなく,家族(更に学校や会社などの生活状況の全体も問題になります)という単位で考えなければならないものでもあります。
ある男性は,両親の愛情が一心に兄に傾いていると信じています。そして彼自身も,兄は学業でもスポーツでも,あるいは人に愛される好ましい性格においても,あらゆる点で自分より優れていると思っていたのです。ですから両親が兄を評価し,自分を評価しないのは仕方のないことと考えてきました。それで兄のような人間であること,兄のように生きることが両親の願いであり,意志であると信じてきました。それで不承不承ながらもその願いに沿うように努力してきました。ある程度は彼の努力は成功しました。兄とおなじ大学,おなじ学部になんとか入ることができたのです。大学を出て一流企業に就職しました。世間的な常識では彼はエリートということになるのですが,彼自身は人生になんの希望も持てず,自分には何ひとつ取り柄がないと感じ,虚しく無気力な日常を送ってきたのです。
彼の心の中には怒りが充満していると,私にははじめから感じられていましたが,彼自身はそういう感情の存在にほとんど無自覚でした。しかし,ある時期から両親への怒りを口にするようになりました。
自分はずっと叱られてばかりいた,両親はそんなことはないというかもしれないが,少なくても自分の記憶では愛されたということはまったくない,一方,兄が叱られるのは見たことがない,私が生まれたときに両親が望んだのは,私ではなくもう一人の兄だったのに違いないと思う,なぜ私を生んだのか,なぜ中絶してくれなかったのか,云々と激しい怒りの表明がある時期ひとしきりつづきました。そして自分の人生を歪めたのは両親だというのです。
そういうある時,彼はそうした認識が間違っていたと,ふと気がついたのです。兄そのものになりたいと考えていたのは自分だった,両親がそんなことを強制したわけではなかったと思う,なれるわけがない馬鹿げた考えに取りつかれていたものだと思う,そういうことに気がついてみると,両親が自分を思っていってくれたこともいくつか思い出した,それに伴って両親への怒りも静まった,なぜ生んだかということも考えなくなった・・・というのです。そして心が軽くなり,力が湧いて来るのが感じられたそうで,仕事に向かう気力が出てきたのです。
重要な要素は怒りの感情でした。幼少期から長年にわたり,両親の愛情が自分に向けられていないと感じ,怒りを持ったのは明らかです。そういうものがあるのは,言葉の端はしからうかがわれ,ある時期には直接的に言葉で表現しました。しかし,彼は怒りをむしろ打ち消しながら成長してきました。兄と比較して自分が劣った人間という認識が強固にありました。そうであれば,怒りを持つことは不当なことであり,許されないことになるのです。それは彼のイメージにある両親の考えと符号するものです。客観的にどうであったかはともかく,彼が両親が考えるだろうように自分を否定し,兄を肯定的に評価してきたのは疑いありません。
しかし,自然な心が自己否定に陥るということはあり得るでしょうか? それぞれの自己が自然なものであれば,良いも悪いもなく,価値に順位をつける気になるとは考え難いことです。誰が好んで自己を否定し,他を肯定するでしょうか?
そういうことが起こるのは,必ず他者,それも最も頼りとする他者の評価に影響されてのことに決まっているといって間違いはないでしょう。自分の価値を他者によって決められて怒りを覚えない者はないでしょうが,その評価に本人自身が同調してしまえば,誰に向かって怒りを向ければいいのでしょう? 自己が独立して自己であれば,自己評価に怒りを持つ理由がなく,怒りがあるとすれば,自己が強く依存する他者による有無を言わせないものにであり,怒りが向かう先はその他者と,その他者に同調している自我以外にありません。怒りのあるところ必ず依存があり,そして人間は依存から自由になることができない存在です。
怒りは他者への依存の目印です。自分が自分のために何をしなければならないか,その手がかりを与えてくれるのです。
彼は怒りの感情を抑圧しました。それに伴って,劣った自分という自己イメージを受け入れました。それは,イメージとしてある両親の考えと同一のもので,彼自身のものと区別がつかなくなっています。つまり,そこには両親に迎合する心があり,彼自身がどこに存在するのか分からないほどに支配されている様子があるのです。それをしているのはイメージとしての両親であり,それを許しているのは彼自身です。彼は怒るに怒れない状況にあるといえます。
恐らく両親は,彼にとって権威的,権力的な逆らい得ない存在だったのでしょう。両親に迎合し,支配を受け入れる自我によって,怒りが封じられ,怒りによって生じる親子関係の危機を回避したということであったと思います。それに伴って,愛されない自分,価値のない自分という強固な自己イメージが,固定的に形成されたということでもあります。
そして抑圧された怒りを意識がとらえはじめたときに,彼の自己イメージは変容の兆しを見せはじめたのです。それは自我が活性化し,機能を回復しかけている様子でもあります。それに伴って,自分を愛さず,無価値な存在と決めつけている性格を持つ両親のイメージに対抗し,怒りを覚えるという動きがありましたが,イメージの変容が進むにつれ,それは両親の考えそのものではなく,両親の態度への過剰反応だったことに気がついてきました。つまり,怒りを捉えた自我は自分自身の問題を問題とする気配を見せ始めたのです。そして,また,人生そのものを否定するほどの怒りを両親に対して持つたことの行き過ぎを,訂正する自由な心を得たのです。
M子さんの美人コンテストの問題について,愛情という観点から見てどうかというのがこの一文の最初の設問でした。それはいま述べた事例についても共通していえることですが,親が子の立場をどのように尊重したかということになるようです。親が自分の気分的な価値意識で,事実上子供に強制したのであれば,いうまでもなくそれは子供を個として尊重したことにはなりません。いくら将来のためといってみたところで,子供の領域に侵入し,強制したのであれば,それは愛に値しません。芸術やスポーツの領域では,親のスパルタ訓練が子供の才能を開花させるということはあると思います。子供は親のおかげで今日の自分があると思うかもしれません。親も成功した我が子の姿に,感無量の涙を流すかもしれません。確かに親が子供の立場を尊重して自由に任せていたとすれば,才能の開花はなかったかもしれません。しかしながら,親の冷酷や身勝手が子供の才能を開花させる場合があるとしても,親が賞賛されるわけにはいきません。子供の才能によって,親がむしろ助けられたのです。子供の才能がなければ,子供は押しつぶされて心の荒廃を招いたかもしれず,親は非難されるところでした。そして,実際には子供の才能は開花せずに終わることがどれほど多いことでしょうか。大多数は荒涼たる精神の破れた姿が残ることになるのです。その荒野に咲く徒花が,心の障害であるとっても過言ではありません。
M子さんの自傷行為や摂食障害は,なにを表現しようとするものでしょうか? 自我が心の中軸として指導性と統合力を保っていることができていれば,心の障害といえるようなことは決して起こらないことです。自我は,自己を形作り,自己を護るべきものであるからです。自己を破壊してまで,他人に何事かを伝えなければならないのは尋常なことではありません。いかなる行為にも,他人へのメッセージ性があります。自分を表現するということは,何に向けてかといえば,他人に向けてに決まっているのです。日記は自分だけのものです。他人が見ることを前提としておりません。しかし,それは他人に見られるかもしれないということを排除できません。他人には見られたくないものを自分は持っているということは,眼差しの彼方に他人があるということです。人にはいえない秘密も同様で,彼方に他人の眼差しがあるからこその秘密です。見られる(知られる)ことを拒否するというのも,他人へのメッセージです。
心の障害ー症状というものにも,同様に何らかのメッセージ性があります。
自傷行為は,秘め事の行為ですが,それをを知って欲しいという心が,むしろ働いている行為でもあると思います。無人島に長年のあいだ一人で暮らしている人が,自傷行為をするかどうかは疑問です。おそらくしないように思います。自殺もないのではないでしょうか。身体の美に神経を使う若い女性が,腕に隠しようもなく残っている傷痕を,夏場などの軽装のときに,隠そうとしない人が少なくありません。どこか誇らしげに,これ見よがしというふうにも見えます。夫に「隠せ」といわれて,「私は別に気にしないんですけどね」と不満そうにいっていた女性がありました。この心理は,「普通の人」への挑戦的な気分の反映だろうと思います。
身体を切りたいという衝動は不可解なほどに強い欲求です。苦痛を恐れるとか,苦痛に耐えるとかという意識はないかのごとくです。本人にも,「どうしても切りたいから」としか説明できない強い要求のようです。そこには悪魔的な力が働いているように思われます。切ったときに流れる血を見て,血肉が踊るという感覚になる人が少なからずあります。殺人鬼の快感に似ているという印象を受けます。それはすさまじい怒りが介在した悪魔的な行為であるようです。その怒りを他人に向ければ凶悪犯罪になりますが,自分自身に向けるので,命までは奪おうとはしません。「久しぶりに切ったので,加減が分からなかった」と,血を滴らせながら外来に来た人がありました。「他の人が怖がるから,これからは切ってしまったときは遠慮してね」といったところ,「え? 怖がりますか」といっていました。そして,その後は約束を守ってくれています。
自傷行為というのは,実は行為ではないと思います。行為というのは意志が働き,判断が働きます。つまり自我の営為です。自傷というものは,自我の営為とはいえません。つまり本人には責任が取り難い問題です。
では,誰の意志による行動なのでしょうか? 私はその意志の主体を,裏の自我と呼びたいと考えています。
裏の自我というのは,以下のようなことです。
自我は,生物学的な基礎を持つ自我機構の上に機能するものであると考えられます。それは植物の種の内部に,将来のその植物の形態が,既に,あらかじめ仕組まれているのに似ていると思います。その自我構造の中に,構造的に他者や境界機能などが内属していると考えられます。自我は自己を形成していく上での中核といえますが,とりわけ生まれて間もない人生の最早期の自我は未発達で,他者(母親)に絶対的に依存します。他者の存在を抜きにしては自己の存在はあり得ないのが人間です。その原型的他者は母親です。
他者は,人生での不可欠のパートナーですが,それは他者が常に有益な存在であることを意味しません。逆に,なにかとそれぞれの自我を混乱させ,人生を迷走させる最大の理由ともいえるのです。原型的他者である母親といえども例外ではありません。むしろ母親が他者の原型であるだけに,それぞれの自我を混乱させる原点にあるといえます。
絶対依存という赤ん坊の身を考えれば,他者なる母親の保護は,生死に関わる意味を持ちます。母親は常に有り難く,優しい存在と単純に考えるわけにはいきません。絶対的なものを必要とするということは,そもそも危険な状況といえるのです。絶対を保証することなど,人間にはできないことだからです。そのようなことから,他でもなく,最も頼りとする母親によって,恐怖(赤ん坊にとっては死につながるものだと思います)する瞬間は,どんな赤ん坊でも避けられないだろうと思います。赤ん坊にとっては母親との関係を保つことは,生死に関わる重要なことですから,場合によっては母親を怒らせたり,困らせたりしないようにすることの必要を,半ば本能で感じ取るのではないでしょうか。具体的には,甘える心を母親に向けることに神経質になる場合があると思います。甘えるということは,赤ん坊にとっては自己の主張であり,それが主張であるからには,相手の拒絶にあう可能性があるのです。拒絶には怒りが含まれます。赤ん坊の未熟な自我は,母親の怒りをおそれて自己主張を控えることになると思います。そのときに発動するのが,境界機能です。境界機能というのは,自己と他者とのあいだ,意識と無意識とのあいだにおいて,相互の関係を画然とさせる役割を持ちます。そして他者との関係で,境界機能を強化して,自我の混乱,破壊を護ろうとするのが,抑圧と呼ばれている心的過程です。
甘える欲求を満たすことは自我の役割であり,心の成長のためには重要なことなのですが,他者なる母親との関係に危険なものを感じれば,そちらを優先させて身を守ろうとするのです。生きるために必要なことであっても,生死をかけた問題の方が優先されるということです。
赤ん坊という頼りない身を考えればやむを得ないことが起こるのですが,抑圧された甘えたい心からすると,理不尽な,認め難いことを自我がしていることになります。その角度からいえば自我の不始末といえ,自己の形成の過程で,自我は自己に対していわば借りを作ってしまうことになります。そういうことが繰り返されることになるとすれば,気弱な自我ということになり,多難な人生を切り開くには問題が大きいといえるでしょう。
自我の強さは,生まれつきの素質によるところが大きいと思いますが,幼い子の自我は両親によって守り育てられなければなりません。自我の機能の中でも重要なものが自律機能と思われます。それが心が成長するための拠り所になります。植物の種を蒔いたあとに,注意深く手をかけて大地に根が下りるのを助けるように,傷つき易く,混乱し易い自律機能の根を,母親と父親が大切に護り育てるのが,つまり愛情というものです。
心の病気には,自我の自律機能の混乱と境界機能の不全化という側面があります。われわれ治療者の目標は,これらの機能を回復させることにあり,話をしっかりと聞く(受け止める),落ち着かせる(混乱を鎮める)ということが欠かせません。一般的にも,混乱し,不全化しているこれらの機能を鎮めることができるのは,人の優しさ,愛情です。誰であれ,人の優しさに触れることがあれば,心が落ち着き,癒されるものです。そういう手助けによって,病者の自我が受け止める力を回復することができれば,即ち自己の回復ということになります。
子供が反抗的で,親に怒りをぶつけてくるとき,親はそれを受け止めることが必要です。怒っているという事実はまず受け止めることです。親のその姿勢を確かめることができれば,怒っている子供は,心の裏で求めていた愛情欲求について語り始めるかもしれません。怒りは認められなかった愛情の裏面だったということが明らかになってくるに違いありません。
親に逆らわない子は,何か不自然なものがあってのことと考えてみる必要があります。親の側に,何らか怒りを封じるものがある可能性があるからです。よい子というのは,自己犠牲なしには済まないのです。いわば自分を殺して,親の気持ちを優先させる強固な癖がついてしまったのです。その大元は,赤ん坊のころにあります。親への恐怖があり,生きる本能が親に取り入る手段を教えたのです。それが強固なものであるので,自我が親の自我を内在化させ,両者はほとんど区別がつかなくなっています。そのために,四六時中親の監視と支配の下にあるのと同然になっているのです。よい子というのは,親にとっては有り難いことなので,自分の子に問題があるとは考えにくくもあります。ですから,親たる立場の者は,この問題に関心を持つべきであると,特に強調しなければなりません。よい子というのは,いわば心が発育不全なのですから。
良い子の穏やかなたたずまいの中には,実は心の奥底に親への恐怖が潜んでいると考えなければなりませんが,もしかするとこの二層性の心は,母親の無意識(半ばは意識的と思います)的な操作によるものです。母親は子供を愛しているというメッセージをたえず送っていると思いますが,子供の様子をうかがうもう一つの目があると考えてみるべきである理由があります。子供がおとなしいのを良いことに,そのまま放置しておけば,後々,子供がさまざまな逸脱行為をはじめたり,心の何らかの障害に陥ったりということで,親のこれまでの操作的な干渉が攻撃されるということにもなるのです。
子供を愛していると思っているとき,怒り,憎しみがどういう形で心の奥に存在しているのか,一応は内省してみるのが賢明です。愛があるところ,必ず裏面に憎しみがあるのです。それが見つかれば幸いです。ないわけがないのですから。そして愛と怒りが対決するとすれば,結構なことです。それは新たな心の統合の動きの始まりなのですから。きっと更に深い愛情が生まれ出ることになると思います。
光と闇,白と黒,愛と憎しみなどのように,対立する二つが,一方が存在するためには,他方の存在を絶対的に必要とするのが人間の心の特徴です。自己と他者,男と女の関係についても,おなじことがいえます。古来,男女が合体して完全になるという元型的思想があります。
このように互いに相容れない対立する二つのものが,相互に他を必要とする絶対的な依存関係にあること,従って,心の出来事はおしはなべて相対的関係にあること,それが人間の心に固有なあり方です。そして人間にとって存在するものは,あらゆることが心の出来事という様態で存在します。
人間には白そのものは存在しません。黒そのものも存在しません。限りなく白に近い黒,限りなく黒に近い白という様態で,白と黒があります。光と闇も,愛と憎しみ,善と悪も同様です。 それらはすべて人間固有の二極構造をなしています。善人は全身的に善人であることはなく,悪人の自覚があるときに本物の善人に近づきます。僧侶は人の心を善導する立場にあります。だからこそ,坊主憎けりゃ袈裟まで憎いだの,生臭坊主だのと揶揄されるのです。本当に偉い僧侶があるとすれば,自分の心に潜む悪について知っている僧侶です。善と悪とはシャム双生児の関係にあり,切り離せないからです。それらのことは自然から乖離して,人として生きることを運命づけられていることに関連していると思われます。つまり絶対というものは,自然ならぬ人間の心の世界にはないということです。その意味で人間は不完全で,完全(自然)を目指すべく宿命づけられた存在です。
人が経験するのは,おしなべて有限で,従って相対的なことに限られます。絶対,無限,無というものを自我が具体的に捉えることは原理的に不可能ですが,宇宙に思いをはせているときに感じるめまいは,宇宙の無限あるいは無に触れたということではないかと思います。
自然はそれ自体で完結し,充足する完全なものに見えます。完全,絶対,無限,無というものは,自然の属性であり,人間が直接体験できる範疇を越えています。
愛は生きようとする力です。憎しみは滅びようとする力です。愛と憎しみとが心の内部で,あるいは人と人との間で激突し,愛が勝利を収めるか,憎しみが勝利を収めるか,それによって方向が定まっていきます。しだいに愛が優勢になれば,心の光がまします。しだいに憎しみが優勢になれば,心の闇がまします。人はしばしば地獄を生き,時に天国を垣間見ます。
人は対立するものを止揚することでより高次の段階にいたるか,あるいはその闘争に敗れて低次の段階に転落するかです。
いずれにしても,人はやがて闇そのものに覆われ,人としての終焉を向かえ,自然に帰ります。もともと生まれ出てきたところへ戻るのです。終焉を向かえるまでのそれぞれの個の心の様態の軌跡には,光りの方向に上昇しているのか,闇の方向に下降しているのか,あるいは気晴らしをしながら待機しているのか,それぞれです。
先に上げた,母親に小児的に依存している青年の場合,母親が人生の終焉を向かえたあと,どういう人生が待っているのでしょう。彼を支えるものが彼自身の心の内部になければ,彼は人生の拠り所を失うでしょう。母親との密着した関係が青年の心の発達を阻止している要因である可能性は,小さくはありません。そうであれば母親の息子への愛情は,彼を本当の意味で助けるものではなかったどころか,大変残酷なことをしていることになるといわざるを得ません。
愛情の当否を判定する能力と権限は人間にはないといいましたが,母親の愛情が本物であれば,愛を受けた子供の心の内部に心の中心が生起するのを助けると思います(母親だけがこの鍵を握っているわけではありませんが)。自分の心の中に,自分を支える拠り所が確かなものとして感得されていることは,人生を地獄化させないための要件です。それがあれば,ダルマのように,何かのストレスでぐらりと傾いても,ほどなく起き上がれるのです。人生の難所でつぶれるか,たくましく乗り越えるかを分けるものが,いま述べた意味での心の中心です。
依存心が度外れに強ければ,その子の親は,愛情において欠けるものがあるかもしれません。
性格形成に与える母親の影響-その3
■内在する主体
心には無意識の領域があります。人間の認識能力は,意識の届くかぎりという制約の下にありますから,無意識という意識の届かない領域のことが,なぜ認識可能なのかという疑問が起こるかもしれません。
たとえば私という人間が現に存在していることは事実問題です。これは否定のしようがありません。しかし私がなぜ存在するに至ったのかという疑問については,私は答えることができません。私は知り得ない理由によって存在しているとしか答えられません。この例によれば,私が存在していることは意識できるが,存在の根拠については無意識であるということになります。換言すると,私にはとうてい認識できない(意識できない)ものがあるということを,認識(意識)することができているということになると思います。
自分の心の世界について,むしろ知らないことがいくらでもあるのは,誰もが知っているとおりです。たとえば過食という本人にとっての深甚な苦しみは現実そのものですが,なぜそのような心の障害に見舞われたのか,さしあたり心的な理由が不明です。過食という事実は認める(意識する)しかないが,心の深部で起こっているに違いないなんらか心的な理由(何かが起こっているのは明らかです)は認識(意識)できません。それは意識の光が届かない無意識の領域があることを意味しています。
そして心理的な治療がうまくいって,その心的な理由を本人が認識(意識)できるときが来れば,おそらく過食地獄から解放されるでしょう。つまり無意識の領域に潜んでいる問題を意識が探り当てることは,ある程度可能なのです。そのことは意識と無意識との領域は,相互の境界が不明瞭で,従って相対的であることを示しています。
このように無意識の世界にも,意識化可能な領域がありますが,それが不可能な領域もあります。前者は個人的なある種の体験を,自我が自我組織に組み込むのを拒否し,無意識下に抑圧したものの集合体から成る領域です。
後者については,たとえば「私が存在していることは否定できないが,存在するに至ったいきさつについては認識不可能である」というとき,私には知り得ないが,何らかの根拠,プロセスが存在しているのは否定し難いという形で,その領域の存在を知ることができ,しかし存在の様態については認識することは不可能であるということになります。ここでは意識と無意識とのあいだに,絶対的な境界が存在しています。従って個人的な体験を超えた(理性的,合理的には説明ができない)ものの存在がここにはあると認められるのです。
C・Gユングは前者を個人的無意識,後者を集合的無意識と呼んでいます。
医学の基本には自然科学があります。あらゆる病気は何らかの身体因によるという理念が,現代医学を築き上げてきました。この思想は医学のみならず,現代文明そのものを築き上げてきたものでもあります。
精神医学にも医学一般の流れの中で,科学としての学問的な体裁を整えてきた歴史があります。その考えを敷衍すると,精神も自然科学的,合理的に理解されるのでなければ当てにならないことになります。事実,19世紀以降の精神医学の本流では,「精神疾患は脳の病気である」という志向が理念のようになっていたといえるでしょう。
しかしながら,そのような身体主義が身体医学では赫々たる成果を上げてきた一方で,精神医学の領域では見るべき成果が上がらないまま19世紀後半を向かえたといえます。精神医学の歴史はギリシア時代にまでさかのぼりますが,神や悪魔や迷信などの超自然的な解釈を排除して,自然的な疾病理解を追求したこの時代の観点は,それら超自然的なものに支配されがちだった当時としては,卓越した精神によって初めて可能だったといえるでしょう。事物の現象に忠実に即しようとするこの現象学的な姿勢は,現代でも尊重されている心理科学的な精神です。そしてその眼差しを歪ませたものは,かつては超自然的なものだったわけですが,現代では自然科学主義であるといっても過言ではないでしょう。「精神病は脳の病である」とする脳神話が,一時期ロボトミー手術を生み出して社会問題化したのはその一例です。これは,医学者たちが自然への忠実な僕という精神を投げ捨て,自然科学主義に囚われた忌むべき事態です。人間そのものをより,学問的な立場を盲目的に上位に置く姿勢は,専門家の陥りがちな愚かで傲慢な姿という他ありません。自然科学は人間が考え出した偉大な方法論であるのは確かであっても,自然を読み解く一つの方法であり,自然そのものはそれに従属するものではあり得ないという単純な事実が,奢った精神には見えなくなってしまうのでしょう。
それはともあれ,自然科学が精神医学領域では見るべき成果を生み出せなかったこともあり,18世紀後半までの100年間というもの,治療に関しては,はかばかしい進展がなかったということになります。精神病院に囚人のようにつながれていた病者ともども,打開策のない難問になす術がなかった精神科医たちも,希望も誇りも持てない囚人のような境遇にあったといえるようです。そういう境遇を自ら選んだ医師たちの多くが,患者たちと共に精神病院で寝起きして生活を共にしてきたのは歴史的事実です。有効な治療的方法を持たない医師たちは,そのようにして医師としての誠意や良心を示すしかなかったのかもしれません。
ギリシア時代に,医聖の誉れ高いヒポクラテスが活躍しましたが,彼の名声が世に知られたのは,むしろ死後のことです。学問の中心がエジプトのアレキサンドリア(プトレマイオス朝の首都)に移ってから,ヒポクラテスを中心とする諸家の医学思想が文書として編纂され,改めて脚光を浴びることになったのです。
ヒポクラテスの思想は,「ヒポクラテスの誓い」と呼ばれている文書に集約されていますが,医師の倫理的なあり方を説いたこの誓いは,神に向けて立てたられたものです。神々が人々の心に生きていたこの時代であるからこそ可能であったのですが,高度に人道的で,倫理的な姿勢が高らかに謳われております。
ヒポクラテスは「神聖病について」という一書で,てんかんを神の意向に基づく神聖な病気とするのが間違いであると断じております。この病気を現象に即してつぶさに診ていけば,自然現象のレベルで理解可能であるとして,神を持ち出すことを非難しております。この病気を神聖化したのは妖術師,祈祷師の類で,彼らは神を持ち出すことでいかにも神を崇めているようだが,その実,自分を優れた者に思い込ませ,祓い清めたり妖術を施したりするまやかしの施術に利用しているというのです。そして処置に窮したときには,神を隠れ蓑に利用しているといっております。それは敬虔な態度とは無縁の,むしろ涜神行為であると断じているのですが,神々が生きていたこの時代には,多くのいかがわしい者たちが,もっともらしく病人達を食い物にしていたことがうかがわれます。
ヒポクラテスが述べているように,神という正体不明の一者への信仰は,それを邪悪に利用しようとする不敬な輩もはびこる余地が大いにあるということですが,ヒポクラテス自身のように,高度に人間的,倫理的な拠り所でもあり得たといえるのでしょう。所詮は人間の所業です。神そのものがどうであれ,それを前にした人間の心が浅ましいものであれば,自分の都合のよいように利用するのも人間ですし,心根の優れた者であれば,高度に真摯に敬虔になれるのも人間です。神が心に生きている時代では,人の心は豊穣に満たされることが可能であり,一方では腐敗,堕落に傾くことも大いに起こりえたということのようです。
ドストエフスキーが,大きな善をなすことができる者は,それに相応して悪人でもあるといっております。ヒポクラテスのような高度な倫理性を持っていた医師たちが存在するためには,それに相応する堕落した精神の存在を必要とするということでしょうか。
ヒポクラテスの時代では,医師は神の前で特別な存在だったということです。
神の側から,「特別に悩みを持つ人たちのために,あなたの能力を使う意志があるか?」という呼びかけがあり,その啓示に感応した者が,それに応じ,誓約するという体裁があったようです。重要なのは,神の側に,人間の自由意志を尊重するという建前があったことです。それが前提であったので,それに応じた人間の側には,神に選ばれた者という意識がありましが,憑かれた者ではなかったわけです。ですから当時の医師たちには,通俗的な野心や名誉欲を超越した高い倫理性が備わっていたといえるのでしょう。
医師と弁護士と僧侶とは,このように神との契約という意味を持つ特別な存在で,単なる職業人ではないという歴史的な由来があるようですが,自然科学の申し子である 現代の医師たちの倫理性はどうでしょうか。
ヒポクラテスがあやしげな施術師たちを,神を隠れ蓑にしているとして非難していますが,現代の隠れ蓑は自然科学といえるでしょう。現代では,医師は,生きるための方便としてその職業を選んだとしても,表立って非難するわけにはいきません。
ヒポクラテスの精神は,「神を拠り所にするが,これを隠れ蓑にするまやかしは排除する」ということでした。現代では,自然科学が拠り所になっていますが,この学問は精神的なものを排除することで成り立っているので,医師の倫理の問題は,まったく個々人の人間性に委ねられているといえます。人間性の怪しげな医師であっても,定められた方法的な手続きに基づいて仕事をしていれば問題はないことになります。医療事故が起きれば,定められた注意義務に怠りがなかったかが問題とされます。人間が人間の行為の是非を判定するのですから,それが公平というものでしょうが,良くも悪くも人間の精神の問題は不在です。
精神論を云々することは,神々が人の心に生きていない現代では,しばしば胡散臭くもあり,誤解を招き易いものでもありますが,現代の精神的な貧困を考えると,ヒポクラテスの時代の神の現代版はなにかという問いは切実なものがあるように思われます。その意味で,ヒポクラテスの精神が生きていた時代と較べると,現代の医師の倫理的な基盤は,文字通り地に落ちてしまっているといわざるを得ない状況にあるというべきでしょう。 現代において神の問題をどう考えるかは特別に難しいことですが,この問題は,神々が心に生きていた時代の精神の豊饒と,自然科学を金科玉条とする時代の精神の貧困とに,如実に反映されているように思われます。
現代においてヒポクラテスの精神をどのように回復できるのか,それは不可能なのかという問いは,医師の倫理問題を超えた人類的な課題であるように思われます。
精神医療が新たな発展を開始したのは,1900年に近づくころでした。しかしながら治療的な閉塞状況に風穴を開ける試みを始めたのは,残念ながら精神科医たちではありませんでした。精神病院の中で,重篤な病人ばかりを前になす術を知らなかった精神科医たちは,赫々たる成果を上げてきた身体医学的な手法が,精神医療に関しては何らの光明ももたらさないことで更に治療的なペシミズムに陥ったままでした。その一方で,神経内科医たちが別な角度から心の病を見つめていました。彼らの外来には,内科的な神経疾患とはいい難いおびただしい数の患者たちが訪れていました。彼らは現代でいうところの神経症者たちでした。内科医たちは,これらの人々のために,何かをしなければならない状況に置かれていたのです。医学の王道である生物学主義の呪縛にかかっていた精神科医たちとは対照的に,彼らは,目の前の神経症者たちを,自由な眼で診る立場にいたといえます。これらの病者の悩みの多くは,「了解不能」というほどのものではなく,健常人と較べても五十歩百歩と映ったでしょうから,一足飛びに「脳の障害」と考える事もなかったのです。
精神医療が生物学的根拠をもとめて,見るべき成果を上げられないでいたこの時代に,それと平行して,メスメリズム(動物磁気説)が一世を風靡していました。これは従来は,医学的本流からすると,いかがわしく,不真面目なものでした。しかし治療的な効果が広範に認められ,熱心な信奉者たちがいたのは否定し難い事実でした。そこに大学教授であったベルネームが注目し,心理療法として導入するにいたり,催眠療法が再認識されることになったのです。催眠療法はそれまでは軽視されていたのですが,ベルネームが学問的に評価したことによって,無意識の領域への扉を開く鍵を,いわば公的に手にすることができたといえます。そして,やがてはフロイトに代表される精神医療の本流への流れができたのです。フロイトの精神分析への発展は,無意識という自然科学の手法の及ばない心の領域に,心理的ー科学的な新たな観点をもたらしたことを意味します。これは精神医療の歴史にとって画期的なことです。
このように自然科学の呪縛から解き放たれたときに,精神医学は,新たな治療的な展開を大々的に開始する方法を得たのです。
そもそも人間は自我を持つ存在です。自我の機能の主要なものの一つが論理性です。自我は合理的精神の砦ともいえますが,その骨子となるものが因果律であり,自然科学においてそれが純粋化されたといえるでしょう。自然科学は自我の能力を模範的に,最も高度な形で示したので,現代人がこの合理的な精神に魅せられ,大きな価値を置くことになったのは,自然な成り行きでもあります。
人間の人間たる所以は自我にあるので,可能なかぎり自我による支配を確立したいと考えるのは,人間であれば当然の欲求といえます。
宇宙には無数の未発見の星体があると思われます。その存在が直接的には証明されていない段階で,科学的類推によって存在を確信する理由が与えられることがあります。これは自然科学の理にかなっていると認められたことを意味し,自我の支配が宇宙に向けて拡張されたことを意味します。
無意識の世界では,個人的無意識の領域に関するかぎり,原理的には自我の光が届くことができます。精神分析的精神療法では,治療者が患者さんの自我と協働して無意識の暗闇に向けて意識を操作するのですが,そのことを通じて,自我が自我組織に組み込むことを拒否していたものを,改めて回収し再統合することになります。
精神的な何らかの不調は,自我が無意識との相対的な関係で,有効に力を発揮できなくなっていることに起因するといえます。ですから自我が健全であれば,精神の不調は原則的には起こり難いといえるでしょう。あるいは起こったとしても,ダルマのように素早く姿勢を元通りに正すことができるといえるでしょう。
自我の機能が生来的に弱い人もあると思います。それは自我が生物的な基盤の上に成り立っていることを示唆しています。また繊細過ぎたり,気が弱かったり,父親や母親の養育姿勢の問題が大きかったりで,抑圧的な態度が習い性になっているなどすると,自我が持てる力を思うように発揮することが,多かれ少なかれ難しくなるかもしれません。
いずれにせよ,これらのことは相対的な問題で,だれにでもそれなりに起こって当然というようなことでもあります。 このように自我が好ましい状態にないことと,精神の不調とのあいだには密接な関連があります。心の治療は,方法的にはさまざまであっても,この関係を調整し,自我の姿勢を正すというところに行き着くといえるでしょう。自力でこの作業をするのが難しいときには,治療者によって自我を支えてもらう必要があるのです。そして両者の関係が十分に信頼の絆で結ばれて行くにつれ,治療という心理的作業を通じて,自我の成長,強化が果たされていくものです。
心の治療では,治療者が心の障害を取り除くのではありません。患者さんが治療者の協力によって自我の姿勢を正し,その能力を回復させることによって,おのずから自分の問題を克服していけるようになるのです。言葉を換えれば,無意識の領域にある問題(従来は受け止める能力を持てず,抑圧するしかなかった)に眼を向ける力を取り戻すことができるのです。このように心理的な治療がうまくいけば,自我の支配圏が拡張されたことになります。それはただちに人間として成長したことを意味します。
以上のように,心にとって内側と外側とに向けて自我の力がおよび,支配圏を拡張していきますが,どの範囲までと限定するのは不可能であっても,自ずから限界があるのも,また,明白です。意識の光が届き得ない絶対的境界が存在しているのは,経験的に自明のことといえると思います。
この絶対的境界で隔てられた無意識と宇宙の無限とは,自我の機能が及び得ない世界です。従ってそれらを科学的に証明するのは,等しく不可能です。言葉を換えれば,「人間には人間的な理性では,その存在の様態を理解することができないものがある,しかし,存在していること自体は認識できる」ということができると思います。更に言葉を換えれば次のようになります。「これら超越的なものの存在を,直感が捉え,自我に訴えかけることがあるが,その実態的な様相について自我が認識的に捉えることは不可能である」
ところが,以上のようなことは自明ではなく,人間の理性はあらゆることを解決可能だと信じる人もあるようです。こうした自我万能の信奉者にかかると,結局,人間自身が神になるしかなくなるのです。そして地球規模で危機的な状況におかれてしまっている現代のもろもろの問題は,実際に人間が神に取って代わろうとした結果であるという趣を持っています。神を放逐した人間的な偉業は,一方ではとんでもない愚行に直結する性格を,元々はらんでいました。
人間がそのまま神になってしまうのは,必ずしも珍しいことではありません。現人神,天子などはそういう趣きを持っていますし,独裁者は,「朕は国家なり」という言葉で代表されるように,それに類する者といえるでしょう。神に匹敵する力を持っていると,事実上意識している人間は,恐ろしい存在です。傲慢は常に罪ですが,その中でも特別な罪だと思います。独裁者とはいえなくても,強力な武力を持つ国の最高権力者が,自分に敵対的な国に実質的な侵略戦争をしかけるのは,文字通り神を恐れぬ所業です。たった一人の人間を殺すのさえ大それたことです。侵略戦争という大量殺戮行為をしかけることができる人間が,どうして存在し得るのでしょう。彼は正義という光り輝く名分を求めて,殺戮者の黒い凶悪な精神を覆い隠そうとします。その程度には,狡猾ながら恐れを知っているといえるのかもしれません。そして彼が最高権力者であるがために,それはほとんど必ず成功し,国民によって支持されるという体裁が出来上がるのです。人間が人間を殺戮してよい理由は,どんな人間も持っていません。それは,いついかなるときでも憚られることです。それを,堂々と遂行する権利を主張できる者は,もはや人間ではありません。彼はある意味で神になってしまっているのです。そして国民はそれを承認するのです。侵略戦争を仕掛けようとして国民の反発にあい,思いとどまった例は,歴史上のどこにもないのではないでしょうか。
人間は一切のものの最上位者ではあり得ません。そんなことは自明だと思います。人間より上位にあるもの,それは自我の力の及ばないものです。そういうものは経験的にいくらでも存在していることで,こと改めて証明してみせるなどということは必要もないことです。自我の力の及ばない超越的な存在を神と呼ぶかどうかは,あまり問題ではありません。さまざまな信仰が活発に生きている時代では,神と呼んだ歴史的過程はあるのでしょう。そして実態のあいまいな,非科学的なその種のことを,ことごとく剥ぎ取って来た歴史的過程もあるのでしょう。
宇宙の無限は存在するというのとおなじ次元で,神が,意識にとって外的に存在するとはいえません。しかし信仰というものは,人間があるところいたるところに存在してきました。科学万能の現代でも例外ではありません。現代では現代の信仰である科学的な風潮のおかげで,信仰の形態は随分いびつになることもあるようです。極端になるとカルト的,反社会的という性格を持つものもあると思います。しかしどんなにいびつなものに見えようと,それらの集団がなくなることは考え難いことです。それは奇怪な心の持ち主がたくさん居るということを証明するものでしょうか。しかし,彼らにいわせれば,逆に,現代社会こそが歪んでいるというに違いありません。それら両者の関係は,自我と無意識のそれに似通っているようでもあります。つまり時代を主導する自然科学的なものの見方を自我とみなせば,カルト的な宗教団体は無意識に相当します。自我が歪めば,相対的に無意識も歪んで,悪しき様相を帯びるものです。それらは相対的で,相互に関連し合うのです。
現代の大問題は心の砂漠化が進んでいることです。その影響は思春期にある者たちに,特に先鋭に表われていると思われます。彼らの心を支える精神的な拠り所が不在なのです。そういうものは思春期にあるものには,特に必要です。親離れがはじまる年頃になって,飛び立てない子たち,逆に早々と親に見切りをつけてしまった子たちの姿が,精神医療を求める子供たち,あるいは親たちの様子から,現代的な様相としてうかがえるようです。
とりわけ早々と親に見切りをつけ,精神の漂流を始めてしまっている子供たちは,世の大人達を右往左往させる悪のにおいのする行為に快感を覚えるようになるようです。彼らには親たちは,単に”うざったい”存在でしかなく,その許を離れることの恐れよりは,解放される心地よさの方に魅かれるのかもしれません。子供に見切りをつけられそうになっても,親自身が自分が畏れを持って助力をあおぐような心の上位者を持たないのです。
自由というものは魅力的なものです。そして大いに不安なものです。真に自由を享受するためには,高度な精神性が必要です。早々と精神の漂流を始めた者は,自由を求めたつもりかもしれませんが,この意味で自由の享受者とは到底いえません。畏れるに値しない上位者の束縛が意味を持たないので,その絆を破ることに,ためらいや罪悪感を持てなかったというのはありそうなことです。将来が不安でないかといえば,大いに不安なのだと思います。しかしその不安をなにかによって繋ぎ止められる不自由に敵意を持つ者が,束縛を破って漂流を始めるのだと思います。それは親子関係の反映という側面はあるでしょうが,時代そのものが精神的な支柱を持っていないことが,更に大きな理由になっていると思います。精神的に満たされることの少なかった子供時代を経験すると,拠って立つ心の基盤を,人的なものを含めて社会的な資産に求めることが難しく,自分自身の幼い心に求めるしかなくなる場合も珍しくはないでしょう。頼りにするのは自分だけ,自分の気分だけということになるのではないでしょうか。自由とは似て非なる身勝手な行動に走って何がいけないのか,気分に従って行動しようとする者たちには,答えを知りたいとさえ思わないかもしれません。
生きたいように生きて何が悪いかのという反問になんと答えればいいのでしょう。極端になれば,人を殺してなにが悪いのかということにもなりかねません。彼らを納得させるような答えは,さしあたりは難しいように思います。彼らの自我は既に自由を失っているように思われるからです。自我が健全でなければ(健全な自我は,必ず無意識の力に対して一定の自由を保持しています),無意識の勢力は反社会的な,あるいは非社会的な色合いを活発化させます。もともと無意識は社会的な存在ではありません。自我がその役割を担っているので,自我が無意識を指導的に従える必要があるのです。自我を騎手に,無意識を馬に例えてみると,人間にとってのこの馬は全てを見通す叡智を持っていますが,人生という障害物レースを戦うにあたっては,一切を自我に委ね,沈黙したまま,しかし一切を知り,一切を見抜きながら,自我の指揮ぶりを見ているのです。騎手が自分の役割に責任を持って,目の前の障害物にどう対処するべきかを機敏に判断するとき,馬は騎手を評価して,それに従って行動するエネルギーの源泉となります。しかし指揮を取る騎手の能力が不満足なものでしかなければ,馬は騎手のために働く気にはならないでしょう。いわば騎手を見捨てるのです。その代わりに,評価するに値しない騎手に対して,社会的な存在として滅亡するのをお構いなしに,あれやこれやの気分的な満足を与えようとします。それは既に悪の彩のある動きなのです。社会的な存在として,いわばやる気をなくし,無責任化した自我に相応して,無意識は悪のたくらみをはじめ,滅びの誘いを始めるように思われます。自我はそういう無意識に盲従してしまうのです。そうなると自我は自由と主体性を失い,事の是非を判断するのが難しくなるのです。 心の砂漠化が進行して,精神の漂流を始めてしまった者たちも,時代の被害者です。彼らに,彼らが生きてきた社会の規範的な価値意識を説いても,それによって犠牲を強いられてきたと感じているだろう彼らは耳を貸そうとしないでしょうが,彼らも何かを求めてはいるのです。そういう彼らに,たとえばカルト集団が一つの答えを出しているということは,大いにありそうに思います。
人が生き生きと人であるためには,精神的な拠り所が不可欠です。自我は無意識によって成り立ちます。自我の機能が及び得ないものが自我の上位者である資格を持ち,自我に力をもたらす源泉である理由を持ち得ます。その上位者が無意識の世界であり,自我との有機的連関があって心が存在するのです。 自我が一切の理由であるとするのは,根拠を持たない張りぼてを不当に高く評価するようなものです。自我への信仰が時代の主調となり,自然科学が一世を風靡しました。それが物質文明の隆盛をもたらし,そして一方では,おそるべき心の貧困,心の病気,犯罪を招き寄せてきたといわなければなりません。
人間が自我の能力を絶対的に超越しているものの存在を認めることは,好みの問題ではありません。人間が置かれている心の様態を素朴に捉えるかぎり,それ以外に選択の余地がないといえます。それを考えると,自我にとっての超越的なものを現代において捉えることは不可能であるとは思えません。
これらの自我の能力を超えたものについて,人間がその存在様態を知ることは不可能です。しかし存在自体は,自我に直感として訴えかけるなにものかという形で,察知できますし,認めないわけにはいきません。
その存在は自我には所属しません。自我を超えたなにものかであるそれは,無意識界,それも絶対的な境界を超えた領域にあるもの,ユングのいう集合的無意識の世界に存在すると考えるしかありません。この領域は自我の上位にあります。自我は自我の支配し得ない上位のものに依存しつつ存在可能なのです。人間の意識活動が存在するためには,無意識の存在を前提とするといえると思います。
自然科学は,その対象となるものを,完璧に人間の能力のコントロールの下に置こうとする志向性を持ちます。
自我は社会的な存在としての人間の心の中核の位置にある組織体ですが,先にも述べたように,自我の主要な機能の一つは論理性です。その骨子となる因果律を,最も洗練された形で方法化されたのが自然科学です。
自然科学においては,対象となっているものに隈なく光を当てるように自我が機能し,意識が操作されます。そのようにして,対象をまったくの自我の支配下に置く試みが純粋化された学問が自然科学です。ここでは対象を見つめている主観が問題にされることはありません。たとえば感染症のように,原因菌と病症との因果律が明快であるときは,主観性を排除した観点は有効であり,なんら問題はないように見えます。これは鍵と鍵穴の関係,機械の修理の問題といえるでしょう。
しかし,感染症の征服は可能かといえば,そうはいかないようです。原因菌やウイルスは姿を変え,抵抗力を高め,改めて人間を攻撃する力をとめどなく蓄えているようです。新手の感染症が続出するのは,どうやら人間が自然の生態系を破壊したことにもよるようです。自然との調和を無視して,人知が自然に破壊的な手を加えると,自然の側からの手ごわい反撃を覚悟しなければならないように思われます。そういうことを考え合わせると,一見すると単純な感染症の問題も,人間と自然との調和,ないしは闘いの様相があり,この戦いに人類が究極的に勝利する可能性はないように思われます。そう考えると感染症の問題も,単に原因菌を確定するという自然科学的営為に,なにか重大な問題が残されていると考えなければならないようです。たとえば森林破壊が新たな感染症を招き寄せたということがあるのなら,感染症対策はしかるべき抗菌剤の開発だけでは解決しないでしょう。むしろ自然との調和を問題にするほうが,より根本的な解決策になるのではないでしょうか。輝かしい自然科学の勝利は,個々の感染症を征服したという限定的なものにとどまっているといわなければなりません。
ましてや精神疾患となると,更に問題は複雑です。E・クレペリンは,現代でいう統合失調症を分類整備した人ですが,厳密な現象学的姿勢で,観察者の立場の偏見を慎重に排除したはずでした。ところが彼が観察した精神病者たちは,劣悪な環境に長期的に入院していた人たちで,それは大いに人為的な影響を受けた病像であり,病気の自然な姿ではなかったといわれています。こうなると病気あるいは病人というものは,見る立場の主観を排除して観察し,実態を把握することは不可能になります。このことを考慮に入れないと,クレペリン自身が陥ったように,「精神疾患は,観察する立場の反映から独立したなんらかの純粋に客観的な疾病プロセスに起因する」という科学的な偏見を生む出すことになります。それは「精神疾患は脳の病気である」ということにほかならず,病を病む者という自然な現実に対して,本来は仮説であるべきものが,いつのまにか科学的な真実となってその上位に据えられることになるのです。科学が自然現象の上位に位置するのは本末転倒であり,危険な事態です。
たとえば原子爆弾には自然科学の功罪が示されています。
核爆弾の親物質である天然ウランは,地球上に広範囲に見られるものです。それらは分子的に安定しており,そのままではエネルギー源にはなりません。そこに膨大なエネルギーがはらまれているのを発見したのは科学者です。それを純粋化し,巨大なエネルギーを取り出す手続きを発見したのも科学者です。これは科学者としては胸を躍らせるような発見だったに違いありません。ここまで来れば,そのエネルギーが類を見ない巨大兵器の開発に行き着くのは時間の問題です。当時,アメリカを中心とした科学者たちは,ナチスドイツがこの兵器を開発しつつあるということで,それに先んじようと力を合わせたのです。これを作り出した科学者の能力は,大きな戦争の渦中にあった当時としては,大いに賞賛される事情があったといえます。兵器として類を見ないものを完成させるという行為は,携わった科学者を興奮させたに違いありません。
兵器が完成された段階で,その使用が検討された相手国は日本でした。そのころ日本国は,既に戦争の相手としては恐れるに値しなくなっていました。この新型兵器を使用する意味を知っていた多くの科学者が,熱心に反対運動を展開しましたが,抑止する力にはなりませんでした。
自然界にある石油を採掘してエネルギー源とするのと,天然ウランから純粋ウランを取り出してエネルギー源とするのと,どこが違うのでしょう。それは単にエネルギーとしての規模の違いなのでしょうか?
石油タンクが燃え始めたとしても,問題とされるのは責任者の不注意です。それらタンクが存在すること自体に疑問を持ち,反対する人はあまりいないでしょう。しかし原子力施設で故障が起きると,人は単に責任者の不注意に対してにとどまらず,そういうものが存在していること自体に素朴に疑問を覚えるのではないでしょうか。
両者の違いはどこにあるのでしょうか。原子力の場合は,どこか禁断の火といった趣があるということかもしれません。天然ウランは,そのままにしておけばおとなしく人間と共存しているが,それに人間が手を加えたばかりに,人間の手に負えない性情がむき出しになるという恐れが人にはないでしょうか。
科学者の好奇心は,天然ウランから巨大なエネルギーを取り出せるかもしれないという見込みが立てば,どうしてもその可能性を確かめたくなるでしょう。こうした知的好奇心は,科学者であればなくてはならないものでしょう。しかし人間としての立場を離れて,純粋に科学者であることはできません。それはどうしても一体のものです。
この研究に危険なものを感じて,消極的な姿勢に終始した科学者は,むしろ大勢いたようです。そうすると時代の風にも影響されたとはいえ,積極的な姿勢を貫いた科学者たちは,人間としてやはり特殊な人たちだったといえるのかもしれません。 破壊や暴力は人間の悪に由来するものです。人間であれば,誰にでもこういう性情はあると考えなければなりません。人を分けるのは,この種の悪を悪として退ける精神が確かであるか,悪と認めつつも,無意識の領域に巣食うこの勢力に密かに魅かれているかの違いではないでしょうか。一介の庶民であれば,悪をなすことへの恐れに敏感です。そうでなければ自分自身が危険な状況に置かれることになるからです。しかし権力者になればなるほど,こうした恐れを持たなくなるようです。彼らにつきものの支配欲求が,彼らを高い立場に押し上げるためではないでしょうか。自我肥大を起こすと,人は必ず傲慢になります。自分が一切の価値の中心になります。正義は常に自分にあり,敵対者は不埒な者として退けられるのが当然になります。人間は権力に近づくことにより,ほとんど必ず悪に傾くといっても過言ではないように思います。
人間のこうした悪魔性と関連するのが,原子力の兵器への応用です。そういう魔力をこのエネルギー源は秘めているように思います。そのにおいがあるからこそ,人は原子力発電に,特別な危険を感じるのではないでしょうか。しかし本当は人が密かに恐れるのは,原子のエネルギーを含んだ物質へというよりは,むしろ人間の持つ悪の影に対してではないでしょうか。
実際に核兵器の研究開発に携わった科学者は,光に満たされた兵器が完成に向かうにつれ,彼らの心もまた光に満ちたことでしょう。対象に関わっている科学者の心から,影の領域に属するものが排除されなければ,仕事を進めるのは困難だと思います。兵器を使用する側は敵国を殲滅させる覚悟です。相手国は悪なる影の集団という意識が働かなければできない覚悟です。そして使用する側は,対照的に正義の見方,光につつまれた恥じることのない集団という意識にならないわけにはいかないと思います。巨大殺戮兵器で勝利する側の意識は,光につつまれていることでしょう。攻撃をする側は,攻撃を正当化するために,心から影を排除しなければならないだろうからです。そして攻撃される側は,この切り離された影によって殲滅されようとするのです。しかしいうまでもなく,攻撃をする側もされる側も,等しくおなじ人間です。一人の人間の心とおなじように,一つの国という単位にも光と影との二つの領域があります。二つの国のあいだで光と影の分離と対立が際立ったときに,戦争が避けられなくなるのです。
このように自然科学は一方で物質文明の隆盛をもたらし,他方で人類に被害をもたらす可能性を持っています。人間の心には光と影との両面があり,影の領域への敬意を忘れると,自然科学者はおのれの分をわきまえない傲慢さを露呈することになるでしょう。言葉を換えると,自然への畏敬の念を失ったときに,人類は危険な挑戦を始めていると考えなければならないと思います。
自然は,本来,人間が自由に扱えるものではあり得ません。心についても同様です。それらのことはいうまでもないことですが,換言すると自然や心は,意識の光が届かない影の領域を持っているということです。意識は対象を捉える人間的な武器で,人間の偉大な力を示しますが,とうてい手には負えないものがあります。
その意識にとっての越え難い存在は,心の外側と内側とに存在します。意識の領域は先にも述べたように,人間の知性的な理解が可能な範疇にあるので,当然有限の世界です。これに対して影の領域にあるものは無限の世界です。光の世界のものである意識は,その世界についてはすべてにわたって操作することが,原則的に可能です。しかし意識が存在する理由については,自我に与えられている能力の範疇を越えており,知ることができません。言葉を換えると,意識はその存在の根拠をそれ自体の内に持っていず,自己完結的な存在ではありません。 そのことは,自我はその基盤を,自我ではないもの,つまり無意識の世界に拠っているということを意味します。
人間の意識活動は,その能力を超越した無意識的な心の存在を前提として,はじめて理解可能になるのです。
無意識の世界は,自我の拠り所ですが,自我に与えられている能力ではうかがい知れない超越的上位者です。従ってそれは,まるごと認め,受け入れる以外にはなく,自我に固有の能力である疑いの眼を向ける余地がない存在です。これが,人間があくまでも謙遜でなければならない根本理由です。ですから謙遜であることは,人間に対する根源的な要請であると,私は思います。卑屈は精神の堕落ですが,謙遜は精神の崇高な姿です。このことの実践は,いうまでもなく容易いことではまったくありません。人は力を持てば,謙遜どころか,むしろ傲慢になりがちです。力を失えば,卑屈になり,狡猾になり,妬み,恨みの虜になります。いずれにしてもそれらは精神の堕落した姿です。
人が心の救済を真に求めたければ,唯一の可能性は謙遜に徹することでしょうが,これを人に勧めること自体が傲慢の謗りを免れないでしょう。人類の中でも類まれな人だけが,そういう精神を求めて自分を厳しく律することにより,可能的な彼方が眼差されるということなのでしょうから。
それを考えると,多くの心の病も,また,謙遜の精神からの転落という側面があるのは確かでしょう。
それらの意味で,人間には大きなものがあるといえると思います。そこへの道を妨げるのは実に人間自身です。この大きなものの前では,この人間自身は,実に矮小です。そして,この人間自身の中で人は迷子になるのです。それを脱して大きなものへ近づくには,心の,ある澄んだものが必要なようです。
このような自我と無意識の関係は,信仰を持つ人と神の関係とほとんど区別がつけ難いと思います。ただし前者の場合は,経験的な事実の上に立って自然に見えてくることなので,信仰ではありません。自我の超越的上位者の存在は,その実相を知ることは不可能とはいえ,ほとんど事実問題です。そして,また,信仰という人類に根深い問題も,それぞれの心の内部に,このような超越的上位者が存在するために成立することができるのです。人がしばしば思うように,信仰が馬鹿げた空疎なものへの胡散臭い信奉というのは,人間の心の実態に即して公平な見方ではないと思います。
自我の超越的上位者の存在は事実問題といえると思いますが,それは,はるか遠くに望見される形態の不確かな山のようなものと例えていえるでしょうか。幻にも似て形状が不確かとはいえ,幻が人間が作り出した幻影であるのに対して,このものは人間の存在に関わる一切の根拠であり,死と共に消滅するという意味で人間の存在に関わる一切の現象という幻影を作り出しているものです。この不確かな形状のものを確かめるために,もっと近づいて観察しようとしても近づくことは不可能です。幻は不意に消滅しますが,このものは決して消滅することはありません。従って,このものの存在は事実問題であるとはいえ,超人間的な世界のことなので,あくまでも自我を拠り所とする人間的な推理,解釈をすればという前提があってのことになると思います。人間的な世界は,完全に意識と共に存在します。睡眠によって自我の活動が休止したときに,人は意識と共に人としての存在を休止させます。休止しているあいだは無と区別がつけ難く,死と区別がつけ難いといえます。そして再び覚醒したときに,再び意識活動が開始され,自分が昨日までの自分と連続したものであることに疑いを持ちません。意識を中断させ,それはしかし死ではなく,意識の休止である,一つの人格としては一連のものであり,統合されたものであるという安心保証は,意識に拠るものではなく,従って無意識に拠るものです。
意識が捉えた様相が人間的な世界の一切です。従って人間的な世界は,終始,現象として存在します。その存在は意識の消滅と共に消滅するのですが,睡眠あるいは意識障害という意識の休止(意識が直接は捉えられない世界への陥没),それらをも含み一個の人格の存在を保証しているものは,無意識の世界以外には考えられません。それは同時に,現象として存在する人間的な世界に秩序を与えているものでもあります。 このように,現象として存在する人間的な世界に秩序をもたらしていると想定される超越的上位者を,内在する主体と呼んでおきたいと思います。
Fさんは企業人の妻です。夫が某国の支店に駐在することになり,Fさんのその国での生活がはじまりました。Fさんは夫人達の親睦会の人々が開いてくれた歓迎会に招かれ,会の一員となりました。しばらく経って,すっかり信じていた何人かの人たちが,いつのまにか誹謗,中傷の噂を撒き散らしていることに気がつきました。Fさんばかりでなく,夫もおなじような噂にさらされました。そういう目にあう人は他にもいて,嫉妬がからんだ独特の陰湿なものがあったようです。
Fさんは気が弱い人ではありませんが,人と対立的にならないように気を使う抑制的な性格です。反撃や詰問をせずに黙って耐えているうちに,激しい動悸,呼吸困難の発作に悩まされるようになりました。日本に帰国してからも,それらの症状はつづき,受診しました。
受診後,それら症状的なものは速やかに収まりましたが,しばしば当時の生活が夢に出ます。常に悪夢です。外国での外傷体験がいかに深刻なものであったかがうかがわれますが,単に当時のことが夢の上で再現されているだけではないらしいということに,Fさんもしだいに気がつくようになりました。外傷となった体験は隅々まで想起可能なのです。ということは自我はそれらの体験のあらかたは受け止めることができているので,それらが悪夢となって自我をおびやかす要因にはならないと考えていいのです。Fさんを悩ませている悪夢の内容は某国での体験なのですが,悪夢という形でFさんの自我をおびやかしているのは,自我がまだ気がつかずにいるなんらかの問題が無意識界に横たわり,解決を迫っていると考えていいと思います。ですからそれらの夢の内容は,某国の体験そのものではなく,それに関連する,より根深いものの所在を暗示しているのです。自我がそれを捉えることに成功すれば,夢の役割は果たされることになります。自我にとって受け止め難かったものを受け止める力を得たのですから,端的に自我のキャパシティが大きくなったことを意味します。それは一応の解決が図られたことになります。そういうことを前提にして考えると,某国の体験が繰り返し夢に現れる理由は,それらの体験そのものではないことになるのです。事実Fさんが母親との関係その他について,夢が何を伝えようとしているのか,芋ずる式に推理を重ねていくにつれ,悪夢は消失しました。それはそれらの推理が,大筋で的を射ていたことを意味すると考えていいと思います。
気分がよい日がつづいているある日,Fさんは封印していたCDを取り出しました。それは,その某国の英雄的な作曲家の名前を冠したコンクールの決勝の演奏を収録したものでした。Fさん自身や誹謗,中傷の噂を撒き散らした夫人たちも,コンサート会場にいました。国民的な英雄である作曲家のその曲は,町中にいつも流されているものでもありました。Fさんは当時を思い出したくないので,曲を聴かないようにしていたのです。 演奏が始まる前に拍手の音が鳴り響きます。自分のもあれば,許し難い仕打ちをしていた者達のものも混じっているはずです。演奏を聴いているうちに,動悸とともに全身から汗が吹き出してきました。Fさんは,問題の根の深さに暗然となりました。
外界からの,あるいは無意識界からの刺激を受け止め,それに対応するのが自我の機能です。
Fさんの自我は,某国での生活の証である音楽を聴くことに耐えられなかったのです。その理由は,一つにはいうまでもなく外傷体験によるものです。しかし先にも述べたことですが,Fさんはその体験の隅々までを把握しているのです。それは過ぎ去ったことでいまさら仕方がないことでもあります。Fさんもそう思っています。自我としてはそれに関しては隠し持つ何物もないはずなので,Fさんを震撼させるほどの大きな理由になるとは考え難いことです。どうしても他に理由があるはずです。なぜ自我が凍りついてしまうほどのことが起こったのかが問題です。それは自我がまだ知らないでいる体験群があることを示しています。それらはできれば知りたくない理由があり,従来は意識の地下に封印することで問題がなかったのですが,いまや件の外傷的体験によって一撃され,活性化されてしまったのです。外傷体験に何らかの意味で連関するような性格を持っているそれらの体験群は,いまとなっては自我が知らないふりをして済ませることを許さないほど活力を帯びてしまっているのです。
Fさんは聡明な人で,果敢な精神の持ち主でもあったので,以上のような意味合いを理解し,臆せずに自分に立ち向かっていきました。そうすることで,彼女を苦しめ,脅かしているものをむしろ手がかりにすることができたのです。つまり自我に圧力を加えてきていたものに対して,立ち往生することがなく,いわば心の扉を開くことができたのです。それに伴って意識の地下に封じ込めることに費やしていたエネルギーを回収することに成功したのです。それは自我の勝利です。同時にFさんの人間としての成長を意味するものです。
このように述べると簡単なことのように思えるかもしれませんが,自我が抑圧していたものの存在は,自我にとって脅威の素なのです。いわば自分を犠牲にして,自分以外の誰か(親といってもいいでしょう)との関係を重視したといういきさつがあるはずなので,いわば人生を左右するほどの無意識的な選択だったといえるだろうからです。比喩的にいえば,自分の国を守るために,強い隣国に助けを求め,その代償に主権をそれなりに放棄してしまっていたものを,今になって取り戻そうとするようなものです。当然,隣国は,少なくても主観的には恐ろしい存在なのです。
Fさんの恐慌発作に伴って明らかになったのは,一見すると原因となっているように思われる外傷的な体験が,実は根本的な要因ではなく,きっかけになっているに過ぎないということです。むしろ容易には把握し難い意識の深部に潜む問題があり,それは直接のきっかけをなした出来事と心的に関連する一連の過去の体験群であると考えられるのです。それらは,自我によって負の烙印を押され,受容するのを拒まれたものたちです。その結果,無意識下の負の集積場に蓄えられ,平生はその存在が忘れられているという性格のものです。それだけに,怒りや怨念の感情を伴い,自我をおびやかす潜在的な勢力となっているのです。またいつかは自我に認められたいと願ってもいるのです。このようにいうと,いわば隠し子のような趣がありますが,実際それに類似することが無意識の世界で起こっているのです。。
このような無意識的な自我の選択的抑圧は,多かれ少なかれ誰にでも起こることです。否,むしろ起こらないわけにはいかないというべきでしょう。人は他人との関係で生きることが,人間が人間であることの条件となっているからです。他者の中でも,特に両親との関係が人間関係の基本です。そういうことがあり,抑圧は一般に他者との関係を重視し,その分,自己犠牲を強いるという意味合いがあるといえるでしょう。社会的な存在を免れるわけにはいかないのが人間ですから,良くも悪くも抑圧は人間に必須の心的機能です。
自我が十分に強力になっていれば,抑圧は,いわば自我の責任において自我の価値規範に反するという心的形態の下に起こります。それは自己にとってなんら問題はないといえるでしょう。問題が生じるのは,自我が十分には強くないときです。それは相対的に他者への恐れが強いことの反映といえるでしょう。そのために人格形成の上で好ましくはない選択を無意識的にしてしまうのです。いわば他人に気兼ねして自己を抑圧してしまいがちになるのです。 抑圧されるのはその都度の個々の体験ですが,それは単なる記憶の封入というレベルを超えて,臆病になっている自我(他人との関係で)が受け入れるのを拒否している一連のものであり,一定の傾向の自己を自我が受け入れるのを拒否しているのと等しくなります。
自我(ここで問題になっているのは,他人に気兼ねをして,選択的に抑圧する自我)が受け入れている自己を表のそれと考えると,受け入れを拒まれているそれらは,裏の(あるいは影の)自己ということになりなります。ですからそれらは,自分の分身ともいえるものです。それら分身は,自我によって認知を拒まれ,意識の地下牢に幽閉されている弟(妹)分ともいえるのです。
これは比喩的な表現を超えて,現実の事実問題といえるほどのことです。いわゆる多重人格という病的な現象がありますが,これは人格の分裂を意味しており,無意識下に別様の人格が潜んでいることを示しています。そのような病的な現象にとどまらず,そもそも人格というものは,強固に統一されたものではなく,いわば複合的な諸人格が統合された姿といっていいでしょう。いわゆる自我といわれているものは,それらの中の公的な人格の形態といえるでしょう。人格とはそういう性格のものなので,時によっては,自分がばらばらに砕けそうだという恐怖を持つこともあるのです。
このような事情の下にあるのが人間といえますので,自我がほどほどに強固であり,健全であることは大変重要です。そうでなければ,場合によっては病的な自己に陥る危険も出てきます。
人生には何度も節目となる出来事がありますが,そのときに自我の強さが試されます。自我が問題を克服していかなければ,更に自我の衰弱を招くことになります。それらの問題が解決されずに長く放置されていると,いつか自我が機能不全に陥りかねません。あえて病的といえないまでも,生きる目標を見失い,活力を失ってしまうことになるかもしれません。
自我が受容できないものがあるということが,そもそも自我の脆弱なところです。つきつけられた問題には,自我は何らかの解答を出さなければなりません。たとえそれが自分の手には負えないというのが解答であるとしても,そこに客観的な根拠があれば立派な解答です。しかし自我が然るべき態度を取れず,問題を回避しつづけていると,そういう自我に業を煮やし,意識の地下牢に幽閉されていた分身たちが力を蓄えはじめる危険があります。自我は生きるという方向性を担っていますが,生きることの対極にある死への方向性を担った破壊的な力が無意識界に潜在しています。人の心には一般に対立する二極があるのです。自我が衰弱すると,この力が活性化し,意識の地下で日の目を見る機会を奪われつづけている分身たちと結託する危険があるのです。いわば母屋を乗っ取り,自我を傀儡化しようとする動きが出て来ることになるのです。そうなると,いうならば自我の根っ子が腐り始めたようなもので,人間として,人格として問題が生じてきます。具体的には無気力になったり,卑屈になったり,さまざまですが,場合によっては目先のことには抜け目がなく,狡猾になったりもするかもしれません。いずれにしても,自我が無意識との相対的な関係で指導力を発揮できず,持てる力を極めて不十分にしか活用できていないという心的状況に陥ります。基本的に能力がないというのではなく,持っている力がありながら宝の持ち腐れ状態になってしまうのです。こうなると将来について,なんの希望も持てなくなってしまいます。そして指導力に不満を募らせた無意識の諸勢力が跳梁し始めるのです。
これらの意識の地下にある勢力は,比喩的にいえば,人里離れたところにある不気味で,近づくのがためらわれるような雰囲気を持つ沼に潜む魑魅魍魎という趣があります。そういう意味を込めて,意識下に収束されている負の意味を帯びた体験群の棲息する様相を,私は個人的に”心の沼”と呼んでみています。
”心の沼”と私が呼んでいるのは,自我にとっての弁慶の泣き所のようなものです。それはおそらくは生まれて間もないころの人生の最早期に端を発していると思います。つまりおそらくは母子の関係で恐怖する何らかの体験があり,それが核となっていると想像されます。そういうことは単なる想像ではなく,児童心理の研究者の蓄積や,日常の臨床からうかがわれるものです。直接確かめることはできないけれど,そのように考えないと理解が難しいということです。そうしたものが核となって,そのことに近似する新たな体験をすると,幼い自我は受け止める力を持てないのです。それは改めて無意識の領域に抑圧されることになると思います。人生の道程でその種のことが繰り返されて,無意識下で一つの勢力となります。
それら一連の体験に関しては,自我は機能できず,いつまでも未熟なままでいるしかなくなります。この”沼”の存在と,相対的に脆弱な自我との関係が,外傷体験といわれるものを生じ易くさせる素地となります。
自我は固有の問題に弱点を持っています。もともとその種の問題は,意識が回避的な態度を取ってきたものです。自我は責任を回避しつづけてきたそれらの問題をつきつけられると,臆病に立ちすくんでしまうのです。そういういきさつがあるので,自己の回復をはかるためには,無意識の領域にある”沼”に立ち向かう勇気を必要としているのですが,自我としてはそもそも気が重い課題なのです。いわゆる抵抗といわれる形で,自我が自分の作業を妨害するという一見不可解なことが起こる所以でもあります。
しかしながら,そういうことではあっても自我の役目は,心の内側と外側の問題を捉えて受け止め,自己に取り込み,新たな統合を図るということです。困難であっても本来あるべき自分でありたいと考えれば,勇気を出して立ち向かっていくしかありません。
自我は,人間が社会的な存在として生きることに関わる中枢的な機能を担っています。しかしこのような作業が円滑に行われているのか,見当違いのことをしているのか,それを決める基準は自我自身にはありません。なにかの問題に直面して,それを解決して充足感を味わったり,逆に自分の無力に悩んだり,落ち込んだりするのは,自我が拠り所としている何かがあることを間接的に証明しています。それは無意識以外にはあり得ないことでもあり,この領域にある自我の拠り所を内在する主体と呼ぶことが許されるのではないかと思います。
母親の胎内で卵子と精子とが合体し,人間の身体の諸器官が形作られていく過程の胎生期にあっては,意識と自我の機能はまだ開始されていず,活動への準備期間にあります。その時代は自然と一体の人間以前の特別な生命体として存在しています。人間存在へと向けた生命の始まりと成長は,自然のプロセスの中にあります。そこにどういう意志が働いているのか,人間の知恵のおよぶところではありません。しかし我々人間には永遠に解明不能であるにしても,現にしかじかの特徴を持った驚嘆に値する合理的な機能を備えた身体と精神とが存在しているのは,厳然とした事実です。そこに何らかの意志が働いたと考え,それを自然の摂理と呼ぶのは,不当とはいえないでしょう。
複雑極まりなく,かつ精妙な身体と精神を持ち,しかし存在する目的と理由を明らかにされていない人間は,自然の摂理とでも呼ぶ以外にないものによって存在していると考えるしかありません。人間は自然から乖離される形で存在を得,いずれ自然の懐に帰還するのです。
自然の中にあり,自然をつかさどり,運行するものの意志によって統率されていると考えるしかない人間が,自らの内部にその意志がこめられている具体的な領域は,無意識のそれです。この領域に現われている自然を統率する意志を,特に内在する主体と呼んで区別したいと思います。そのように呼ぶことによって,精神のさまざまな病理現象について理解を深めることができ,かつ治療上の重要な手がかりが得られるのです。
会社の人間関係などの重圧に負けてうつ病を発症し,休職している30代の男性Hさんの例です。Hさんの目は専ら会社に向けられており,家族,両親との関係で問題を深めるのが難しい経過がありました。
会社への拒否感が強く,転職も考えますが,それも具体的には進展しません。そういうことを考えると不安になり,抑うつ感が深まるのです。いたずらに休職期間が長引いてしまっていました。
あるとき他人との関係は重要だが,それ以上に自分自身との関係が重要だという話をしました。
その内容は以下のようです。 他人から見離されるのも辛いものだが,自分自身に見離されると,比較にならないほど深刻な事態になる。心にとっての生命の拠り所は,他者をはじめとした外的な状況にではなく,それぞれの自分自身の内部にある。つまり無意識の世界に心が拠り所としているものがあると考えていいと思う。それとの関係が断絶すると人生は地獄になる。例えば小学生が3人のいじめっ子の標的にされていると仮定して,その子が不登校になるときは,その子自身が4番目のいじめっ子になるときである。そのように自分で自分を攻撃し,見離したときに問題は決定的になる。本当は自分を助ける考えを探し出さなければならない肝心のときに,逆に自分を見捨てるようなことをすると,役にも立たない他人であるいじめっ子に心を寄せ,何よりも頼りとするべきである自分自身の中にある拠り所をないがしろにすることになる。それは自分から求めてその重要な関係を断ってしまうのと同然である。
そのようなことにならないための方法は,気分まかせの生活ではなく,頭を使って考えること,つまり判断することである。たとえば無気力感から横になるとしても,気分まかせでそうするのはよくない。それが必要なことか,考えて判断をしてそうするべきである。結果としてはおなじことでも,前者と後者とでは全く違う。判断をすれば自我が仕事をしたことになる。その判断が不適切なこともあるだろう。しかし自分が考えてしたことであれば,責任を取ることができる。それを生かすことができる。なによりも自分のためになるように,自我が仕事をする姿勢が大切である。そういうふうに自分の問題に責任を持って生活することが継続されれば,無意識的に拠り所としているはずのものに接触し,支持を受けることが出来てくるだろう。
そういう話をしましたが,聞いているHさんの様子に手ごたえのようなものを感じました。その後,彼はどこか腰の座った人に見えるようになり,目に見えて頼もしげな雰囲気に変わっていきました。会社のことも前向きに考えはじめるようになりました。ともかくも復帰しよう,その上で転職するかを検討したいといい,同僚から会社のよからぬ情報をもらっても動揺しなくなりました。
内在する主体は,無意識の領域にある人知を超えた存在です。たとえば発見,発明,創作などのインスピレーションはここから発せられる叡智です。夢を通じてベンゼン核が発見されたという逸話は有名ですが,行き詰まりを感じて悩んでいるとき,不意にアイデアがひらめいて解決してしまうという経験はだれもがすると思います。そういうときの一気にみなぎる力も,主体の叡智と接触したためと考えられます。いわゆる火事場の馬鹿力,危急時にみなぎる力もおなじです。夢には補償作用があるといわれていますが,意識の偏った志向性を本来あるべき方向に導こうとするのも,ここに由来していると考えられます。この内在する主体は,表には顔を出さないものの,意識がする仕事を黙って見つめているもののようです。
我々は,自分のことは自分が一番よく知っているなどといいますが,それはちょっとあやしいと思います。自分や他人を意識的にか無意識的にか,しばしば騙し,欺くのが人間です。しかし内在する主体だけは,絶対に騙せません。
他人との関係は大変重要です。両親,配偶者,親友など,大切な人と良好な関係にあるか否かで,人生そのものが大きく変わるといっても過言ではないでしょう。ですから精神医学は,対人関係を大変重要なものと考えています。
しかしながら,他人との関係以上に重要で,難しくもあるのが,自分との関係なのです。言葉を変えれば,主体との関係です。
内在する主体は,無意識界にある特別な超越的な独立体というようなものではないと思います。人間は自然から乖離,独立した特別の存在といえるかもしれませんが,自然の一部を構成しているものでもあります。
人間がこのような身体,このような心として存在しているのは,いかなる意志によってであるのか不可知です。隈なく身体や心を調べても,その謎を解くのは不可能です。そのような形で自然の摂理が働いているとしかいいようがありません。我々はそういう事実を受け入れるばかりです。
人間には自由があります。しかしまったくの自由は無と区別がつきません。拠り所がなにもない自由!それは空恐ろしいことです。無人の荒野に一人放り出された幼児にしても,まだしも生きる方法を見つけることができるかもしれません。それ以上に途方もないことです。自由を勝手気ままにやってよいという意味と考え違いをして,人生を地獄化させてしまうのは,むしろありふれたことです。といって親が子の自由に足枷をはめるのは越権行為というもので,これもまた子供をだめにしてしまう典型でさえあります。
自由は自我にともなって授けられたもののようです。「お前に任せるから,思うように人生を生きてみなさい」というのが,人間に与えられた命題のようです。それが自由ということです。そして授けられたものが人間なら,授けたものがあるということです。授けたものがなにか,それは不可知です。人知を超えた意志です。自然の摂理です。その自然の摂理が,人間を無言のうちに,しかし絶対的に支配しています。自由を生きる生き方で,人生が満ち足りたものとして終わるか,地獄化してしまうかが左右されます。
自由は,この主体の無言の制約を受けていると思います。主体から見離されると,他人に見離されるのとは比較にならない深刻な事態を招きます。人生の地獄化は,常にそういう事態です。
自我と自由という特権を与えられた人間は,実にしばしば傲慢の罪に陥ります。大小の専制君主は,いたるところにいると思います。人間にとっての最大の敵は人間かもしれません。敵と身方もまた裏と面の関係で,相互に切り離せないものの一つです。人がにわかには信じ難いのも無理からぬ所以です。
これらに関連がある例を二つ上げてみます。第二の例はある時期,新聞等で話題になった話です。
過呼吸発作を起こして緊急で受診された方がありました。仮にMさんとしておきます。Mさんは30代の主婦で,子供はありません。結婚して数年になります。受診の前々日,夫が浮気を告白しました。それも一人や二人ではないというのです。寝耳に水でパニックになりました。ところが夫は,翌日,あれは嘘だったといい(それはMさんも信じられるそうです),しかし寝室を別にしたいといいました。どうやらMさんが夫の世話をこまめに焼きすぎたのが負担になっていたようだといいます。その後ももめごとがつづき,家を飛び出しました。三日目に帰宅する途中,二度目の受診をしました。実は,初回のときに,状態が悪いにもかかわらず服薬も診療の継続もしぶる気配がありましたので,心配していました。
事態は急展開となり,一ヶ月ほどのあいだに別居の話が決まってしまいました。夫は自分が依存的で妻に頼りすぎていたと自覚し反省していて,このままでは互いによくないので分かれようというのだそうです。Mさんも自分の性格が依存的なのは分かっていますが,別居しなくても改善できるのではないかと思っています。しかし夫の意志は固いそうです。
Mさんはこういう経過について話をしたついでに,「それに,私以外の女性とつき合ってみたいらしいですよ」と,くったくなく笑っていたのが印象的です。ふつうはこういう話は深刻になるものです。ましてMさんは依存的な性格ですし,考えるいとまもないほどの急転直下という展開でもあるので,落ちついている様子は不思議なほどのことです。
この過程で,実母と電話で連絡をとりました。夫のいい分を伝え,自分がずっとよい子で,自分のいいたいことをいえない性格だったという話もしました。母親は,「そうね,あんたはいい子だったわね」とあっさりといい,「そう,そんなに我慢していたとは知らんかったわ」といったそうです。母親のあっけらかんとした様子で,Mさんは肩の力がぬけ,急に気分が軽くなったといいます。自分で思っていたほど母親がこだわっていたわけではないと分かったからです。
M子さんはふっ切れたように明るくなりました。初診のときは,見る影もなく打ちしおれていたので,別人のようです。
転機は初診のときにあったそうです。そのとき服薬にも診療にも積極的になれないでいました。その気持ちを訊かれ,夫がいやがると思うと返事をしたところ,あなたの気持ちはどうなのかと問い返されました。更につづけて,それはご主人に依存しているということでしょうかといわれて,ハッとしたということでした。
依存の問題に思い当たり,それは目から鱗が落ちるような体験だったそうです。そして母親と夫とそれぞれのあいだの依存の関係を,自分の立場で問題にできたといいます。それに伴っていろいろとしたいことが見えてきたというのです。かつてなかったことです。通常は深刻な悩みになる別居,離婚という問題が,Mさんの場合はむしろ自分を回復する方向で心が動きました。
ある人(A氏と呼んでおきます)は,某有名企業で,安定した会社員生活を送っていました。中年期にさしかかり,会社でも中堅の役どころを無難にこなしていたA氏が,ある日,突然申し出て,会社を辞めました。彼の意志は強固でした。辞めてどうするつもりかというと,北極まで一人で橇を引き,走破する計画ということでした。真意を測りかねている周囲の者を後目に,計画を実行に移しました。人生に嫌気がさして,あとは野となれ山となれというやけくそ半分の行動であれば,なんといえばいいのか分かりません。しかし,A氏の場合は内面からの要請で,やむにやまれぬ静かな熱情に駆られてのことであったようです。彼には,日常の生活があきたらなかったのかもしれません。昨日までの友人,大切に思っていただろう妻や子,それらの人々の心配や反対を押し切って命がけの孤独な難行に立ち向かいました。A氏の冒険行に要するエネルギーは,並大抵のものでないことは容易に想像できます。一体どういう熱情がA氏を駆り立てたのか,おそらく言葉で説明するのは難しいのではないでしょうか。
この情熱は,純粋で,妥協の余地がないように思われます。頑固で,協調性がない者とか,傲慢で,強圧的な権力者とかの場合とは,いうまでもありませんが,正反対といっていいぐらい意味が違います。A氏のそれは何事にも代えがたい,ゆるぎない価値として妥協できないものだっただろうと思います。彼にはなによりも自分自身との関係が大切だったのではないでしょうか。それは,ガリレイが宗教裁判にかけられたときに,「それでも地球はまわっている」とつぶやいたことにも通じるでしょう。
内なる主体としっかりとした関係ができているとき,A氏のように命をかけることができるのだと思います。分からず屋たちの中で孤立したときなどに,平然とおのれを保つことができるでしょう。
これに対して単に頑固なだけの者は,心を凝固させることで身を守っているように見えます。何から身を守るのかといえば,第一に無意識界に潜む抑え難いほどの怒りからだと思います。強権的で容易に人の意見に耳を貸さない者は,しばしば,権力という鎧で身を守らなければならない弱さを秘めているように見えます。
前者と後者とを決定的に分けるのは,謙遜の精神です。自然の摂理の前に,人は畏敬の念に打たれないわけにはいきません。自然に頭を垂れ,謙遜であるしかありません。それが人に品性や節操を与えます。
頑固者や権力者に最も望まれるのは,これらの精神です。
性格形成に与える母親の影響-その4
■自立と依存
自立は理念です。現実に到達されることはないものです。
人はそれぞれの人生をどこへ向かって進めて行こうとしているのでしょうか。動物は目先のことに,欲求に従って行動しているように見えます。人間は動物の中でも特別な存在のようで,目先のことに欲求にだけ従って生きていけばよいというわけには,到底いきません。できれば自分らしく,充実した日々を送りたいと誰もが思うでしょう。人間の場合,生きる指針は,本能として身体に刻印されたものとしてあるようには思われません。では指針はどこに,どういう形であるのでしょう?
子供には躾けや教育が必要です。大人になって自分一人の力で生きていけるように,大人たちが人生の先輩として,必要と考える知識や,人との関わりの大切さを身をもって教えます。それらは欠かすことのできない重要なことですが,彼ら大人たちの誰もが,人生そのものの指針を伝授することはできません。
では,自立の理念とは何でしょうか?
依存からの完全な脱却であるというのは,どうでしょうか。同語反復のきらいがありますが,間違いではなさそうです。言葉を換えれば,自立とは,自己がそれ自体で自足することであり,あらゆる関係性から自由になるということであるといえるようです。
それでは依存とは何でしょうか。
それぞれの自己は,何ものかとの関係において存在しています。何ものかとの関係においてしか存在し得ないという方が,より適切です。
私がこの一文を書いているということに即して具体的にいえば,持っているペン,紙,向かっている机,椅子,暖房機,電気スタンド,書斎,家,家族,近隣の住人,家々,街,道路,などなど無数の物や人が,つぎつぎに私の意識的視界に入ってきます。それらのすべてが私との関係において存在し,私の世界を構成しています。それらは私の所有に属しているともいえます。それらのものは,私との関係において主観的,かつ客観的という性格を持っています。従って,たとえばAさんの世界に属するそれらのものと,わたしのものは,主観的というかぎりでまったく別個のものですし,客観的というかぎりで同一のものです。我々は互いになにものかを共有することができますし,しかし,なおかつ共有することができません。
私がいま使っているペンは,しかじかという会社の製品で,しかじかという名前の物であり,どこの文具店でも手に入るありふれた物です。Aさんもおなじ物を持っているとします。Aさんのも私のもおなじ物といえますが,しかし,まったく別の物ともいえます。つまり,私が持っているそのペンは,「私のペン」であり,「Aさんのペン」とはまったく異なります。仮にその関係性を無視して,私がAさんのペンを勝手に使えば,私は泥棒ということになります。このように,私はそのペンとの関係性の中にあり,私がそのペンに依存することにより,それは私に固有のものとなるのです。
私がそのペンを使ってみて,書き心地がいいから試してみてとAさんに勧めたとします。Aさんがそれに応じて試し書きをしたとすると,そのペンは共有されたことになります。Aさんも同感しておなじ物を買ったとすれば,ますます共有性を深めたことになります。あるとき何かのきっかけにAさんが私に対して著しく気分を害することがあれば,そのペンを捨てるかもしれません。Aさんがペンを買ったときと捨てたときとでは,おなじペンが対立する意味を持つものとなります。
このように見ていくと,私はおびただしい物や人との依存関係の上に生きているのが分かります。私はそれらによって人生を支えられており,それらが必要であるかぎり,どれ一つとして欠けてはならないものです。
また,不要の物はゴミとして捨てることになりますが,不要でありながら私が捨て切れないでいるものたちもあります。それらの物との関係においても,私の性格的特性が表われているのです。
隣の芝生がきれいに見えるという諺があります。
人をうらやむ心は誰にでもあるものでしょうが,度が過ぎると心を制御するのに苦しむことになります。自分が所有するものは,それを大切にする心がなければ,依存している当の物や人によって,ある意味で逆襲されることになります。
隣の芝生がきれいに見える精神は,満たされていない精神です。
私が貧乏であり,隣の家が裕福であるとしても,私の心が満たされていれば,羨ましく感じることはあって妬むことはないでしょう。しかし心が満たされていなければ妬むかもしれません。
私の心がある程度満たされているとすれば,私に本来与えられている自然的な精神の諸力が,過不足なく実践できている場合です。そのとき,それなりに他人の評価がもらえていることも,必要条件になるでしょう。
逆に心が満たされない思いをしているときは,本来自分が持っているはずの潜在的能力が実践されていないときです。
つまりは心が自然的であればおおよそ問題はないのです。そして人の心が自然的に成長するのが難しいのは,人間が他者との関係を必須のものとしているからです。
結論的にいえば,本来持っているはずの潜在的諸力を実践できないのは,自我の不始末ということになります。結論だけをいえば自業自得ということになるのですが,自我自身がその自然的な機能を他者によって歪められるので,ことは単純ではありません。自我の未発達は,悪しき依存関係の一側面です。それは何よりも,原初の他者であり,人格形成の根幹に関わる立場にある母親との関係において生じます。
このあたりを具体例に即して見てみたいと思います。
A氏は,画家です。ある農村の離農した農家の家と田畑を借り受け,自給自足の生活をしながら絵の修行に励んでいます。彼は元精神科医でした。私は彼の二十代後半から三十代前半にかけてと,その十数年あとの二年ほどをおなじ職場で仕事をしました。最初の職場でのA氏は,将来を嘱望される有為の青年医師でした。患者さんを診る能力は,周りが一目置いていたと思います。その能力は,何よりも柔らかな受容力にあったように思います。患者さんの立場からすると,受け入れられているという安心感と,理解されているという信頼感を得やすかっただろうと思われます。そういうセンスは,天性のものだったでしょう。精神科医は多くのものを学び取らなければならないのはいうまでもないとしても,学習によっては得られない何かが要求されています。それは一つには,病者の問題を他人事にしてしまわない共感力ですが,A氏にはそれがありました。病者と関わり,問題を共有するためには,治療者がその問題を自分自身の問題とする能力が必要です。それが共感能力というものですが,微妙なものも過たず感じ取るには,天性のセンスが要るように思います。病める心の人は,いわば全身で治療者を見ていると思います。相性のこともあるので各人各様ですが,一般論としては治療者の共感能力を感じ取ることができたときに,一応の安心が得られるものだろうと思っています。
心を病んでいるということは,自我の機能的能力が衰退しつつあるということです。人は自我に拠る存在です。自我は光の世界のものです。人は自我を持つことによって人となったのですが,自我によって光を知ることになったのです。そして光を知ったがために闇をも知ることになったのです。光は生きようとする世界のものであり,闇はその裏面の世界です。そして闇は,死に通じるものです。光は闇を前提とし,生きるということは死を前提とするのです。光と闇,生と死は,人間が自我を持つ存在であることで必然化された,人間ならではの遠大な矛盾です。
赤ん坊のか細い自我は,それを護るものがなければなりません。光を知る者として生を受けた赤ん坊は,必然的に闇に怯えるものでもあります。自我の機能を駆使して自らを生きる力を獲得できるまでは,他者の保護を絶対のものとする理由があります。
自我に拠る存在ということが,必然的に闇の世界の存在を前提としているというところに,人が依存的な存在であることの一義的な意味があります。
絶対的な保護を必要とする赤ん坊の未熟な自我が,しだいに力をつけて闇の世界のエネルギーを活用していくことになりますが,それに伴って絶対的な依存から自立の方向に向かうものの,闇の世界を凌駕することが結局は不可能なのも自我の一面です。従って,自立は単なる理念にとどまるのです。
そのようなわけで,人は人生の最早期に他者への依存を不可欠なものとし,結局,他者との依存関係を脱することはできません。
自我は強力な能力を与えられていますが,闇の力の前には何ほどのものでもありません。闇には意識を無化する力があります。それは場合によっては自我を滅ぼすことになるものです。ですから自我を共有する他者との関係は,なにを置いても重要な意味があります。しかし,それだけに他者は諸刃の剣です。自分を元気づけてくれる最たるものであるということは,逆に当てが外れるとひどい目に合うことにならざるを得ません。
小児のころ緘黙症であったある女性は,テレビなどのニュースで人が死んでもなんとも感じないが,犬や猫が死んだらとても悲しいといっています。頼りとする人間たちに,いかに傷つけられてきたかが察せられます。
犬や猫は自然のものです。犬にかまれても,犬を憎んだり,恨んだりする人は滅多にないでしょう。ふつうは飼い主に抗議するだろうと思います。犬は人の身体を傷つける力を持っていますが,心を傷つけることはありません。心を傷つけるのは人間ばかりです。心の傷は外部からの力によるのではなく,受け止める側の内部的な問題として生じるのです。このことは他者が,外なる存在者の中で,特別な意味を持っていることを示しています。つまり自己という存在は,構造として他者を内に含んでいるのです。それがいかなる外部的な状況に置いても,他者との関係が途絶えることがない理由です。犬は経験的に,学習としてそれぞれの個人の世界に外部から入ってきたものですが,他者は,経験以前のものとして存在しているのです。人と人とのあいだでは,言葉を交わさなくても相通じるものがありますが,犬の気持を察するには,人間的な類推をするしかありません。
それにしても他人に心の傷を負わせる人は,人の心の自然の性としてそうした行為におよぶのではありません。その人自身がかつて他人たちから傷を負わされ,いわば心の自然を撹乱されたために,怒り,憎しみが無意識のレベルに解消されずに残っているからです。
他者は,自我を共有するものとして最も頼りとするべきものであるだけに,最も傷つけられるものでもあります。人間の最大の敵である可能性を,人間は持っているといっても過言ではありません。それは人間の存在構造から,原理的にいえることなのです。
自己の存在条件として,他者の助けを絶対的に必要としているのが人間であるということは,親といえども赤ん坊を十分に守り育てる力を持っている保証がないということでもあります。つまり親にしても他に助けを求めたい心があっても,おかしくないどころではないのです。その相手が年端もゆかない赤ん坊であっても不思議はありません。むしろ心にわだかまりを抱える母親には,恰好の相手になります。動物に似て自然のものである赤ん坊は,どんな母親にとっても愛らしいかぎりではないでしょうか。滅多には味わえないであろう愛らしいものとのあいだでの至福の感情は,程度の差こそあれ,あらゆる母親がいつまでも封印しておきたいほどのものではないでしょうか。母親によっては,あの手この手と意識的,無意識的な策を弄し,自分の思うように育てようとするかもしれません。自分の望ましいイメージに沿って育児に励むとき,それが愛情と信じやすい心的状況ができるだろうと思います。ときによっては,投網にかける漁師のように我が子をからめとろうとする母親も,珍しくはありません。いずれにせよ,最良の母親も含めて,母親が赤ん坊に悪しき依存をしてしまう側面があるのは,避けられないことです。
そのような事情が,赤ん坊の自我を混乱させ,自然的な機能を守り通すのが困難になる主要な理由です。母親が第一番の頼りであるということは,母親によって人生を狂わされる最大の理由になり得るということでもあります。
ある中年女性は,離婚の経験者です。小学生の長女と暮らしています。年の暮れに,再婚している元夫から連絡があり,正月に長女を預かるといわれました。相談ではなく,要求であったのも神経を逆なでされることでしたが,長女が喜んで父親のもとへ去ったあとの寂しさは,言葉ではつくせないほどのものでした。そして元気で帰ってきた娘に,「おかあさん,淋ししかった?」と訊かれて,大丈夫だったから安心してね,とはいえませんでした。幼い娘に,母親自身が幼い子のように寄り添って,いつまでも離れたくないと思っていました。娘は母親を気遣って,あれこれと世話を焼いてくれるのです。親子の関係はまったく逆転していたそうです。
繰り返しになりますが,人間は依存的な存在であり,その依存の原初の関係は,母親とのあいだで体験されると考えて間違いないと思います。原初の他者である母親への絶対依存からしだいに自立していくことになりますが,それにはまずは母親の助けが必要です。そのためには母親が,それなりに自立していなければなりません。しかしながら先にも述べたように,母親の自立性には個々に問題があるのです。赤ん坊が頼りとするに値するかは疑問であるほど母性を欠く母親が少なくないのが,精神科の臨床現場からうかがえる現実です。子供の虐待報道さえ日常的というのが,昨今の状況です。まして子育てに悩み,自信を失くしている母親は無数にあると考えなければなりません。そこには時代の反映という側面もあると思います。
価値観が多様化している現代ですが,どうやら母親たちにとって,母性も多様化しているかのようです。
それは心の豊かさの表れでしょうか?価値観の多様化が,それぞれの自由の発露に基づいているのであれば,そこには精神の豊かさがあって然るべきです。そして,豊かさのしわよせとして,母性が希薄になるという事態はあり得ることでしょうか?私には,とてもそういうふうには考えられません。母親が個々の価値観に基づいて行動するのは個人の自由でしょうが,それが母性の希薄さを弁明することになるとは到底考えられません。そういうことは個人の問題だと思う人もあるかもしれません。しかし,それは間違いです。子供には自分を守る術があまりないのです。そういう子供の立場を,社会的に擁護する規範が要ると思います。
人間の精神が豊かであるとき,それは必ずその個性が自然的に解放されているはずだと考えます。母親にとって自然的であるとは,何を置いても母性が豊かであるということではないでしょうか。母性を欠く母親!これほどに矛盾したものは滅多にありません。
「私は母親になどなりたくなかった。しかしなってしまった」という人もあるでしょう。その人はどう生きればよいのでしょう。荷の重い育児に,全精力を奪われるのは耐えられないと思うかもしれません。その気持は分からなくはありません。そして自分のかけがえのない人生を精一杯生きる自由があると考えるのも,理解はできます。その女性は,社会的に成功するかもしれません。そのために家事や育児が疎かになってしまうのはやむを得ないと考えるかもしれません。
彼女たちが人生を自由に,豊かに生きる権利を否定することはできません。しかし,われわれ精神科医は,このような母親の下で呻吟する子供たちの例を,いくらでも挙げることができます。もし自分がよりよく生きる自由を追求するためには,やむを得ない犠牲だったという母親があるとすれば,なんといえばいいのでしょう。これが精神の恐るべき貧困の表れでなくして,どういう貧困があるのでしょう。
矛盾を生きる宿命の下にある人間には,まるごとの充実,豊かさはあり得ません。
ソクラテスは,アポロンの託宣により,最も知恵のある者とされました。ソクラテス自身は,自分が人に勝っているとすれば,自分が無知であることを知っていることにおいてであるという意味のことをいっております。
この例にならっていえば,ある母親が精神の豊かさを追求していくつもりがあれば,自分の心の貧困をこそ知る必要があるといえるでしょう。そうでなければ,恐るべきエゴイストと区別がつかないことになってしまいます。
望まない子を生んでしまった母親は,同情に値する面があるかもしれません。育児に煩わされることが,かけがえのない人生をより自分らしく生きる上で障害になると考えていたとすれば,大きな難題を抱え込むことになったといえるでしょう。彼女が考える自由な生き方,自分らしい生き方が,精神の豊穣を意味するものであり,精神の貧困を排除したいという意味であるのなら,不幸にして母親になってしまった現実を真剣に悩む必要があります。あっさりと’不幸の素’を切り捨てるやり方は,忌むべき自己本位,恥を知らない傲慢といわれても仕方がないことです。せめて自分がしていることは,そういう意味を持つのだという自覚を持つべきです。そうであれば,’不幸の素’を切り離すなどという結論には,滅多にいたらないでしょう。人は悩むべきことをしっかりと悩むべきです。真剣に悩むことができれば,やがて大きな解答が出てくるものだろうと思います。そして,そのとき,まったく別の人物になっていることでしょう。
彼女が自分の心の貧困に思いをはせる勇気を持つのなら,’望まなかった出産’に,自己の再生の重要な契機を見出すことでしょうし,そのときこそ精神の豊穣に一歩近づくのではないでしょうか。
現代の母親たちの母性の希薄化は,人間が心の自然から遠ざからざるを得ない時代的な潮流にも関係があると思います。人々の心はより世知辛くなり,小賢しくなり,心の飢えに人知れず悩まされているのが現代精神の潮流です。それに伴って現代人の精神の成熟が阻まれているようであり,それが母親たちにおいては,母性の未成熟化となって表われているということだと思われます。
また,人が依存の対象を絶対的に必要とし,それは必ず悪しきものを排除できないことを含むという問題の根本には,自我に拠る人間の存在条件があります。つまり,人間存在の一つの特徴は,諸矛盾をはらむということです。生きるということには,死ぬことが含まれ,自己であるためには,他者性を含み,良い依存を目指すべきであるということは,悪い依存を含むからこそである等々です。絶対的な良い依存というものは存在しないのです。諸矛盾の果てしない止揚(二つの矛盾,対立する概念を,一段高い段階に統一,発展させること)が,人間精神に許されている自己実現への王道です。人は矛盾を引き受け,矛盾に悩み,そして新たな高みへと進むことができるのです。
このように依存は相互的なものであり,母親と赤ん坊との関係も例外ではありません。かつ依存には,良い形態と悪い形態とがあります。いずれにせよ,どんなに母性に恵まれた母親であっても,悪しき依存の混在は避けられないことです。
母子のあいだでの依存関係では,力を持つ母親の側からの侵入,干渉が特に避け難く,悪しきものの典型です。それに伴って赤ん坊は,自然的な心性をさまざまに混乱させられます。それは悪しき影響ということになりますので,善悪の問題ではありますが,どうしても避けることができないのが人間の宿命的現実です。
話をA氏に戻します。
私が二度目の職場でA氏と再び仕事を共にすることになったのは,たまたまA氏と会ったときに,私が誘ったのがきっかけでした。A氏はすぐに応じてくれました。それは私が予想していないほどのことだったので,私は少々あわてました。施設長に頼まれて声をかけたわけではなく,そのときの話の勢いで私が勝手に誘ったからです。それから施設長に話を持って行ったところ,幸いに退職予定者が一人いるというのです。話が意外にも上首尾に運んでしまいました。私は再びA氏と仕事を共にすることが,素直にうれしかったのを覚えています。
しかし再会したA氏は,かつてのA氏ではありませんでした。
一言でいえば,A氏は影に呑み込まれていました。暗い無表情や,陰鬱な雰囲気から一目でそう感じました。しばらくぶりに再開したときに私が誘ったのは,一つには変わり果てたA氏の様子にあったと思います。あの有為の青年が一体どうしてしまったのかと驚いたのです。もともとA氏は外向的な性格ではありませんでした。人に媚びず,本物だけを大事にしようとする精神がありました。いうまでもなく,それは精神科医としては欠点ではありません。A氏には,自分の信じることだけをするという好ましい頑固さがあり,私はそういう彼が好きでした。患者さんを大切にし,仕事を誠実に,熱心にこなし,しかし小心ではなく,どこか人生を高括るようなところがありました。自分の才能を信じていました。しかし医者として認められ,それなりの地位を得て世間的に成功することなど,およそ念頭にないように見えました。それだけにどういう風にでも生きていける人のように思えていました。彼に見られた表情の翳りのようなものも,むしろ人格に深みを与えていました。
再会したときに,一体どうしたんだと私は心で叫んでいましたが,言葉には出せませんでした。彼がかかえている問題が重過ぎるように思えたためでした。そのとき,私はどこか保護者のような気分になりかけていたと思います。彼が私の誘いにあっさりと乗ってくれたときにも,彼が私に救いを求めているように思われたのです。そしてかつての彼を知る私には,共に仕事をするうちに,きっと回復するはずだという確信のようなものがありました。
しかし,二度目の職場に現れたA氏は,ひどく尊大でした。世の中も人間も憎んでいるように見えました。仲間たちへの最低限の礼儀もなく,あらゆるものを軽蔑しているようでした。なりふり構わず,人を人と思わないかのような態度に,仲間たちは最も善意のものも含め,一人として彼と口をきこうとするものはなくなりました。そういうことも一向に意に介する様子もないのです。
一番問題なのは,治療者としての自信も意欲もすっかり失せているらしいことでした。
彼がかなり深刻に人格を病んでいるのはほとんど明白でしたが,そのことで悩んでいるようには見受けられず,人生そのものを捨てている気配が感じられました。
私に対しても,不機嫌以外には何の感情も見せないに等しいのです。彼とのあいだで,まともに意見が交わされるということもおよそなかったのです。彼と心を分かち合う何ものもありませんでした。彼はいつまでたっても,単にそこにいるだけの,厄介な人物であるに過ぎませんでした。そうなると彼にとっては,医者の立場は,単に生活のためでしかないのです。彼は患者さんのために存在しているのではなく,患者の皆さんは彼のために存在しているに等しいのです。もはや彼は治療者ではありません。それを苦にしているようにも見えません。治療者としては,最も堕落した姿としかいえない有様でした。
私がA氏の例を上げるのは,心についての治療者とはどういうことか,心を病むということは,ひいては人間であるということはどういうことか,そうしたことを考えてみるためでした。
若い時代の精神科医としてのA氏は,治療者として機能している自己を感じていたと思います。しかし彼は,治療者としての自分を重視し,大切にしているようには見えませんでした。医者は働き口には恵まれています。そのためもあったでしょうか,彼は思いつくままに,いわば人生を彷徨していたように思われます。それは才能を持つ者にはありがちなことかもしれません。何かを模索していたのかもしれません。しかしながら,後年の彼の著しく変貌した様子をも合わせて想像すると,彼の世界を中軸として支えていたものは,なんといっても患者さんとの関係であっただろうと思われます。結果から見れば,その関係を疎かにしたことになるように思われ,真剣に人生に対峙することを回避してきたようでもあり,それは自我の不始末,力不足を意味すると思います。
それぞれの自己は,おびただしいものたちとの関係において存在可能です。自分をより良く生きるためには,それらの関係性をより良く生きなければなりません。そうでなければ糸の切れた凧になります。根絶やしになります。才能に溺れるものが陥る罠は,そういうところにあるといえます。大切なものを大切にしないと,その大切な依存の対象に,いわば復讐されてしまいます。
自己とは,主観的ー客観的な存在です。純粋な主観も純粋な客観も存在しません。それぞれの世界における客観的なものたちは,無限という様相を持っています。たとえば一本のバラの花には無限なものが秘められています。画家が納得のいく作品を描こうとすると,何枚ものバラの絵を描かねばならないでしょう。それでも,なおかつ納得できないかもしれません。他の画家は,またまったく別なバラの花の絵を描くでしょう。そもそも対象が無限の様相で表われているので,芸術家が作品にする意欲を持てるのです。
バラを素材にする植物学者は,いわば一本のバラの花と共に一生を送れるかもしれません。人が対象としっかりと向き合おうとすれば,対象は無限の様相を表すのです。逆にいえば,それら大切なものを大切に扱う心がなければ,心は貧困化するのです。
統合失調症に見られる世界没落体験をはじめ,自己を失う脅威は,関係が途絶える脅威であるといえます。一切の関係が途絶えたときに,人は身体的にか精神的にか,死に直面するのです。大切な関係は,それを疎かに扱えば,関係によって滅びるともいえます。
A氏にとって,患者さんとの関係は生命線であったように思われます。それを疎かにしてきたために,その関係の希薄化と共に,A氏の精神の後退が起こっていたのではないかと思っています。
A氏の自我がそのようであったのは,自我の自然的なものが人為的に撹乱されたためと考えるべきことです。そういう力を持つ他者は,人生の最早期の他者である両親をおいてなく,なかんずく母親の影響によるものと考えて間違いはないだろうと思います。その意味で,A氏は,悪しき依存の中にいたのだと考えられます。
若い時代のA氏は,有能ではあっても治療者として確立された何かがあったわけではありません。しかしおそらくは,自分が人並み以上に優秀な医者であるという無意識的な自負心があっただろうと想像されます。
後年の彼を見ていると,治療者としての自信も自負心も実質的に失っていたように思われますが,一方では人並み以上の評価をもとめる無益で,虚しく,不快なばかりの自負心が見えていました。それが実体を欠いた要求であるのを,他でもない彼自身が知っていたはずです。
しばしば驚かされたのは,人を出し抜いたときのはしゃぎぶりです。ふだんが暗鬱で,不機嫌なので,その様子は異様でした。また,いたるところに顔を出す羨望の色がありました。そういうものから察すると,彼の内部には並々ならぬ自負心が虚しく潜んでいたのだろうと思われるのです。
そうした実体を欠いた自負心というおぞましい姿は,しかしながら別な意味で実体があったといえるのでしょう。火のないところに煙は立たないのです。彼の内部には,日の目を見ない分身たちが,宝の持ち腐れ状態で埋没していたに違いないのです。それら分身たちは,A氏が自分に自信を持っていた時代には,無意識下でおとなしくしていたはずの者たちです。というのは,自我がそれなりに力を発揮していることは,それら影の分身たちにも好ましい,望みを持てることだからです。いつかは自分たちも,自我によって日の目を見る期待が持てるからです。
しかしそういう期待が裏切られると,無意識下にある分身たちは怒りと共に勢力を強めていきます。それは自我の衰退とパラレルの関係にあります。そして自我は傀儡化されるに等しい心的状況が生まれます。
それらの分身たちは,幼いころにおそらくは主として母親との関係で,自我によって抑圧されたものたちです。自我が中年期にいたっても悪しき依存から脱していない様子から察すると,自我は母親(と思われます)の自我によって支配されたままであることを,直接的に意味していると考えてよいと思います。そしておそらくは母親の自我による支配の代償に,母親の過保護があったのではないかと思われます。
無気力に傀儡化されている自我の下で,A氏はほとんど傲慢,不遜な小児でした。他者への配慮など,社会性は極めてあやしいものになっていました。自我の無力化に伴って,小児的に退行していたといえるのでしょう。
他に依存するA氏の自我は,虚しく,実体を欠いてしまった自己のありように対して,いたって無責任なのは当然といえば当然なのです。そうした自我の下にある無意識下の分身たちは,いまや日の目を見る当てもなく,勢力を拡張してしまっていたと思います。
A氏がおそろしく客観性を欠いている様子に,しばしば驚かされたものです。どう考えても,あきれるほどの現実のすりかえとしか思えないことを口にしたりもするのです。そういう自己本位そのものといったところは,かつてのA氏にはなかったことです。それを見ると,彼の自我は完全に傀儡化され,影の思考に支配されていたのだと考えるしかありません。自我を傀儡化しているのは,影の分身たちです。それら影の分身たちの首座にあるものを,私は裏の自我と呼んでいます。それは直接は表に出ないで,表の自我を操って欲求を満たそうとするのです。裏の自我は人生を生きようとするものではありません。生の世界のものを憎悪し,目先の欲求を自我をそそのかして手中に収めようとするのです。人生と他人と,そしておそらくは自分自身を憎悪しながらも,なにかのきっかけに,A氏が見せた上機嫌の中にはそのような色が見えていました。他人を出し抜くことで,してやったりと小躍りする黒い笑いは,裏の自我の下にある裏の世界の感情です。自我が果たせなかった満足を,まるで他人のせいであるかのような意識のすり替えが起こるのです。他人への悪意,憎悪をこめて腹いせをしようとするかのような様子は,かつてのA氏にはもちろん見られなかったことです。
本当は彼の自我が,内心に潜むそれらの諸欲求を満たすべく,何らかの研鑽,努力をする必要がありました。ところが現実には,彼は’蟻とキリギリス’のキリギリスだったのではないかと想像されます。
キリギリスには,バイオリンを奏でる才能がありました。蟻にはとりたてて才能がありません。しかし蟻には生きるために,せっせと餌を集めて冬に備える地道さと謙虚さがありました。キリギリスは,夏のあいだは才能にまかせていれば,満足のいく生活ができたのです。蟻もキリギリスが奏でる音楽に,仕事の合間に耳を傾けて賞賛しました。そして冬がやってきました。蟻はキリギリスが心配でした。外に出てみると,よろめき歩くやつれきったキリギリスがいました。肩を貸そうとする蟻を,キリギリスは振りほどき,巣に呼んで手当てをしてあげようという蟻の親切を断りました。そして死んでしまいました。別の蟻たちが見つけて,食糧にするために運んでいきました。
もしキリギリスに,冬のあいだにも蟻が音楽を聞きたがるほどの才能があれば,生きていけたかもしれません。ところが蟻は音楽を懐かしむのではなく,キリギリスの無力を助けようとしたのです。キリギリスにバイオリンの才能があるといっても,他から見ればその程度のものなのです。助けてあげなければ生きていけない哀れな生き物に過ぎないのが,客観的な現実です。他なるものである蟻によって支えてもらえなくても,キリギリス自身が己の演奏能力を信じることができていれば,蟻が差し伸べてくれた援助の手を断ることはなかったのではないでしょうか。キリギリスにも,夏のあいだも冬への不安があったはずですが,自立性に欠けるものがあったに違いない彼は,自分のバイオリンの演奏能力を評価してくれる他者の存在が必要だったようです。そして他でもなく,自分で自分の能力を信じきれていなかったに違いありません。なにものかを信じることができていれば,他との関係も保つことが難しくはないのです。自分を信じていなかったに違いないキリギリスは,他なる蟻も信じていなかったと思います。あらゆるものとの関係の薄弱なキリギリスには,他なるものの関心を惹きつける当てがない現実を,直視する勇気もなかったのです。そして誇り高いキリギリスには,演奏者としての自分を評価することによってではなく,自分の力では生きていけない哀れな者であるがために支えようとする親切は,とうてい受け取るわけにはいかなかったのでしょう。そういうふうに考えると,夏のキリギリスも既に絶望していたのだろうと想像されます。
キリギリスの自我は,バイオリンを奏でることに依存しています。それは夏のあいだは意味を持ちます。周りのものたちには,夏の気候の恵みによって,キリギリスのバイオリンを楽しむ余裕があるのです。しかしその自我は,冬の厳しさには何らの力も持っていません。つまりバイオリンは,冬の厳しさにも耐えるだけの依存の対象ではありませんでした。
A氏にとっての夏は,若さだったと思います。若さの勢いが,彼に,能力の暗示を垣間見せたのかと思います。そして彼はいつまでも若くはないということに気がつかなかったというよりは,高を括ったのではないでしょうか。
その盲点は,彼の自由意志,自主の精神を混乱させたに違いない悪しき依存関係に起因するものだろうと思われます。悪しき依存関係を克服できないままでいる自我の頼りなさの反映として,彼は恐れ入るほどの幼稚な心に陥っていたと思います。それに伴って,人間としてのあらゆる美点が消滅してしまったかという事態に立ち至ったのではないでしょうか。それはまさしく冬のキリギリスさながらに,「だれも俺に構わないでくれ,俺の価値を認めようとする気がある者を除いては・・・」というふうな,絶望的でなりふり構わない自己主張であったように思われます。自己を支える根拠が空洞化しているときに,それを補うかのように自負心だけが更に誇大的になっているらしいのも,人間関係的な状況を更に悪化させることになります。そこにも自我の後退に伴う社会性の喪失,影の性格の現前,幼児的退行といった様相が表われているといえるようです。
一般に,心の病理現象は,幼児心性が意識の表舞台に姿を表している様相といっても過言ではないようです。
J.Fマスターソンは,自己愛性の人格障害に関して,次のように述べております。
「自己愛パーソナリティ障害の子供を持つ母親の中には,基本的に情緒が冷ややかで利己的に他人を利用する人たちがいる。そういう母親は自分自身の完全主義的な情緒的欲求を正当化するためのちょうどよい対象となるように子供たちを型にはめ込み,子供の分離・固体化欲求を無視する。子供の真の固体化欲求は,母親の理想化投影に子供が共鳴するにつれて損なわれていく。母親の子供に対する理想化に子供が同一化すると,子供の誇大自己は保存されるようになり,・・・」
この論旨に従うと,A氏の幼児心性である誇大自己と万能感とを,母親が功利的に巧みに利用して,A氏を通じて母親自身の誇大的な欲求を満たそうとしたということなります。A氏は母親の干渉に気がついていたと思われ,母親への不快感,反発を強める一方,自己の誇大感を母親によってくすぐられることには大いに満足していたといえるのかもしれません。
彼の無意識は他者の賞賛を強く求めるものがあり,それに見合う実質を欠いてしまった後にも,虚しさと一体となった誇大感に相応する自負心を捨てることができなかったように思います。
彼の気分は当てのない賞賛をそれとなく他に求めていたように思われ,いまや他人は滅多なことでは彼を賞賛する理由もないので,彼は常に不機嫌に’愚かな他人ども’が不愉快で仕方がなかったのでしょうか。
夏のキリギリスは光の思考が可能でした。そのとき無意識の闇の世界に葬られている分身たちも息をひそめて自我の働きぶりを見守ります。いつかは自我が自分たちにも目を向ける力を持つかもしれないからです。
冬のキリギリスは影の思考に支配されてしまいました。心の世界全体が影に支配され,世界を構成するものたちとの関係が生気を失ってしまいました。それは一途に無気力になっている自我と,相対的な関係にあります。影の世界のものである怒り,憎しみ,怨念などの暗い情念が,冬のキリギリスのように滅びを志向しようとします。
冬のキリギリスの世界は病者の世界です。世界がすっかり影に覆われたときに,自我の世界である社会性が後退し,幼児性が露わになります。幼い時代に満たされなかった心たちが,頼りにならなくなった自我に見切りをつけ,自分たちの姿を露骨に表すのです。
精神科医は,影の専門家であるといえると思います。自我の気弱さが影の勢力増大を招き,ますます自我が力を衰退させることになるのを,精神科医は病者の自我に代わって病者の心を力づける役目を持っています。
影というのは,先ほど述べた闇に通じるものです。影が支配的になると,意識が無化されていきます。自己の世界の関係性を剥奪する力を,闇は持っています。自我の機能不全が回復不可能なレベルに及ぶと,闇による自我の回収,つまり死への直面ということになっていきます。
自我の活力が不十分であれば,自我は自分の影を扱うことができません。影は他者の介入によって,自我が懼れをなして身売りをしてしまったというような心的過程に伴って生じたものです。自分が思わずしてしまった無意識的な不始末を,衰弱した自我が改めて回収することはほとんど困難です。他者の利を優先させて自己の不利益を我慢するというのは美談にもなり得ますが,自我の気弱さのなせる業であれば,大きな禍根を残すことになるのです。
自己の世界を支える諸々のものたちとの関係が無化されているときに,治療者が介入することで,治療者とのあいだに新たな関係が生じます。それが信頼関係といえるほどのものになっていけば,それだけで病者の世界は活気づくきっかけを持つことになります。
A氏が画家として再生しかけているのは,A氏の自我に潜勢力があったということになるのでしょう。彼は画家として外的対象の無限性に関わることになったといえますが,それは同時に彼の影や闇の世界である無意識の無限性との関わりが新たに始まったことをも意味するでしょう。心を無化する力を持つ闇は,自我が力を回復させると,自我の拠り所となって大きな活力の源泉になるのです。
精神科医をやめ,画家に転向したことはよいことでした。
精神科医は,自分の影の世界に精通していなければなりません。精通とまでもいかなくても,そこに関心を向けつづけなくてはなりません。というのも患者の皆さんは,影に呑み込まれそうになって医者を求めるからです。医者が自分の影に無関心で,無神経でいるかぎりは,心の治療者の資格がないといってよいでしょう。さもなければ患者さんの影に直面して,医者は間違った反応,対応をしてしまうのが避けられないのです。影に反応して,自分の影である鬱屈したものを相手にぶつけることになれば,攻撃的,拒否的,敬意の要求という傲慢など,してはならないことを防ぐ手立てがありません。また影を共有しあうことで,悪しき依存関係が形成される場合もあるでしょう。それは患者さんを利用して,「傷のなめあい」をしていることになるのです。
心の治療者は,心を病む人の指導者です。一歩上にいる必要があります。それは知識があるとか,地位があるとかということでは勿論ありません。患者さんの影に呑み込まれず,その影を見つめつつ,治療者本人の心の影の動きを見張ることによって成り立つ類のセンスと技術に関わるものです。
それぞれの自己はおびただしいものたちとの関係を持ち,それぞれの自己の世界が構成されています。私が日々の生活でどの程度満たされているかということは,それら私の世界を構成しているものたちとのあいだで,生きた関係を保つことができているかどうかにかかっています。その中でも主柱となるものたちとの関係が,とりわけ重要です。それらとのあいだに生きた関係が保たれていれば,私の世界は親和的な相貌で表われるでしょう。しかしそれらとの関係が親しみを欠いていれば,世界は寒々としたものであるでしょう。何か特別に悲しいできごとに見舞われれば,そういう事態になります。
H.テレンバッハが提示した「メランコリー親和型」という性格類型は,内因性メランコリーへの親和性を持つものとして提唱された概念です。この概念は,下田光造が提唱した「執着性格」との類縁性が指摘されており,日本的な性格類型であるといわれております。その要旨をかいつまんで翻案すると以下のようになります。
日常の生活は,有形無形の規則で秩序立てられています。日本には日本的な暗黙の生活習慣というものがあります。個々の会社や学校には,それぞれの社風なり,校風なりがあります。家庭には家風があります。自分が置かれている組織や集団などの秩序に基づいて,忠実に,几帳面に,自己を捧げようとするのがこの性格類型です。彼らは,所属する集団の中で感じ取った期待されている役割を敏感に感じ取って,それを高いレベルで忠実に守り通そうとする生来的な気質を持っています。彼らは与えられた立場において,その立場を主体的に生きようとするよりは,要求されている秩序の中に自らを主体的に投げ入れるのです。主体者として行動するよりは,忠実な僕であろうとすることに主体的に関わるのです。彼らの仕事ぶりは,几帳面,勤勉,堅実,綿密です。非の打ち所なく役目を果たすことに,彼らは使命感を見出します。仕事はすべて人との関わりを持ちますから,人に対して誠実,律儀,世話好きな性格が好都合に働きます。
彼らの厚い愛他的な性格と確かな仕事ぶりは,人に信頼され,敬愛されることになるのは当然といえば当然です。
それらは立派な処世の術となっているのですが,彼らが狡猾に見えることは決してないでしょう。人にそのように見られるとすれば,彼らには耐え難いことだと思います。行為の無償性が,彼らのもう一つの美徳といえます。だから人を出し抜いたり,争ったりということは決してないだろうと思います。誰の目もないところではずるく立ち回るなどということは,およそなさそうです。
彼らの自分への高い要求は,何に基づいているのでしょうか?
彼らの性格の根本問題は,個々の他者の眼ではなく,公共の眼のごとき高次の他者の眼を畏れ,敬うところにあるように思われます。それは個人的な他者への依存ではないので,確固としたものへの依存ということになり,彼らは容易には動揺しないのです。
彼らの思考や感情や行動の原理は,そのように公共的な他なるものへの高度の依存といえるものなので,身の回りのあらゆるものに優しく心を配り,場合によっては他人のために命をも惜しまないほどのものだと思います。
♪ しばしも休まず槌打つ響き,飛び散る火花や走る湯玉,ふいごの風さえ息をもつかず,仕事に精出す村の鍛冶屋・・・。
これは明治時代の小学校唱歌の一節ですが,ここには執着性格の特徴が表されているように思います。
明治時代は封建的支配から脱し,近代的統一国家への体裁を整える大激動の中にありました。文明開化の気運や自由民権運動の高まりなどがある一方で,政府の富国強兵策が浸透していきます。開発途上にある国家は,軍部による支配を目指すのは必然のようです。人民の不満の噴出をはじめ,激動期のエネルギーを抑え,かつ利用するためには,軍の力は欠かせないものでもあるのでしょう。日本国の富国強兵策は,モデル的な成果を上げたといえるようです。短期間に欧米列強と肩を並べる軍事力を育成し,産業革命を成し遂げました。産軍の興隆と人民の支配とが切り離せない統治策であったと,明治史は語っているように思われます。
小学校唱歌は,欧米の先進国に追随しようとする,当時の為政者の施策の一端でもあり,為政者にとって望ましい日本人像が,唱歌を通じて働きかけられているという色合いの濃いものだったと思います。
このような時代に,執着性格は,模範的な美質としてとりわけもてはやされた一面があります。公共的な意志とでもいうものに依存する「執着性格」の人たちは,為政者にとっては都合がいいという面もあると思います。
ところで執着性格が云々されたのは,うつ病の病前性格という観点からでした。
その性格特徴が,与えられた秩序の枠の中の規範的な価値を最大限に追求するというものなので,彼らが危機に陥る状況は,大きく分けて二つあります。
一つは,与えられた課題が大きすぎるということです。比喩的にいえば,負わされた荷物の重さにつぶされてしまうのです。
たとえ不寛容な心を持つ上司であっても,この性格的特長を持つ人たちには,上司は上司なのです。命じられた仕事は,家庭を犠牲にし,休日を返上してであっても応えなければならないのです。責任感が強い彼らには,役目を果たせないことは何よりも申し訳ないことです。その罪悪感は,例えていえば,最も頼りとする父親の期待に背いて顔向けが出来なくなっている様といえます。拠り所が自己の中にではなく,内なる公共的な他者(イメージ的に父親に通じるものです)にある彼らには,職責を果たせないということは,弁解の余地なく許されないことです。外なる他者は許してくれても,彼らの内なる他者は過酷です。そもそもが,その過酷さが彼らに規範的な価値への高い忠誠を要求したのです。彼らが自分の意志で,決意して自分に高い要求を出したのであれば,それは責任を取れる話です。しかし要求を出したのが,自己ならざる自己である内なる他者であれば,挫折したときに責任の取りようがありません。言葉を換えれば,問題を受け止める主体が不在であるに等しいのです。
いかなる場合でも,問題は受け止められないでいるときに,心は乱調の中にあります。そして更に乱調に陥ります。
危機的な状況のもう一つは,全身全霊を込めて奉仕をしてきた秩序体が,別種のものに変わるという事態です。具体的には,転居,昇進,転勤などです。折角作り上げたものを捨て,また一からやり直すのは,途方もない精神力が必要と感じるのです。
オリンピックで三連覇を成し遂げた柔道選手が,テレビの番組で,「四連覇を狙いますか」と質問されていました。それに対して彼は,次のように答えていました。
「監督に,練習の再開は年が明けてからするようにといわれている。今は練習を何もしていない。練習を再開してから身体の様子を見て決めることになると思う。三連覇に向けた二年間の練習の苦しさを考えると,年齢のこともあり,今は狙いますとはとてもいえない」
この選手はオリンピックの二年前の世界選手権で不覚を取っています。その口惜しさがばねになって,激しい練習に耐えてきたのです。
一流選手が目標を定めたあとの日常生活は,執着性格の人の完璧を目指す忠勤ぶりに似ているように思われます。
ただし,この選手が,「四連覇を狙うかどうかは自分が決める」と明言しているかぎり,うつ病に悩むことはなさそうです。執着性格の人は,「自分が決める」といういい方はできないように思います。
30代のある男性は,外出恐怖の悩みを持っています。外出中に不穏感が出てくる恐怖があるのです。ある日,薬を持たずに外出してしまいました。用心深くなっているので,外出するときには薬を携えるのが習慣でした。しかしこのときはどうしたことか,忘れてしまったのです。しかし,「まあ,いいや」と思い直しました(何かのときに,「まあ,いいや」と思えることは案外重要なことです。それは問題を受け止める気になっているという意味があるからです。不安に見舞われるかもしれないが,それはそれで仕方がないという気持がこめられています。ほどほどの感覚ではなく完璧な安全を求めるようであれば,その時点でパニックに陥ってしまうでしょう。多少の不安でも耐えられそうにないと感じれば,完璧な保証を求めたくなるのです。それがないかぎり,安心はないことになります。ほどほどのことは許そうという心が大切なのです。人間に完璧はないので,完璧を求める心は常に病的です。それらの心理を集約している言葉が,「まあ,いいや」です)。
「まあ,いいや」と思えたことが,薬ではなく,自分の力を信じようという気持に傾くきっかけになったようです。そのときから,外出の恐怖が和らぎはじめました。
近くに,結婚している妹が住んでいます。甥と姪がいて,彼は彼らに慕われています。妹に,兄の外出訓練を助けようという気もあってか,兄にその相手をしてやってほしいと頼まれていました。行けるときもあれば,行けないときもあります。行けるときでも,ウオークマンで武装するようにして,まっしぐらに,脇目も振らずに歩くのが習いでした。しかし薬に頼るのをやめてから,周囲の景色が自然に目に入るようになっていました。子供のころに遊んだときの情景が浮かんで懐かしんだり,民家のクリスマスの電飾をきれいだと感じたりしながら,歩けるようになったのです。
この話は,’元気になる’ということについて示唆するものがあります。
先にも述べましたが,それぞれの自己は,それぞれの固有の世界と共にあります。世界は,もろもろの物や人との関係で構成されています。この男性の例でいえば,妹さんのところへ歩いていく道すがらの歩いている道,周囲の景色,これから会うことになる妹や甥や姪,妹の家,周辺の民家,などなどが彼との関係において存在し,彼の世界を構成している様子が語られています。
不調の彼は,道も野原も小山も樹木も民家も,ほとんど心から排除されて,それらとの間で生きた関係にないという心的状況にあるといえます。それらの道や野原などからすると,主人公の自己から存在を無視されているに等しいことになりますし,心の側からいえば,闇の無化作用を受けて,それらとの関係が疎遠なよそよそしいものになっているともいえると思います。それに相応して,彼の心は不安に脅かされていました。関係があいまいになり,途絶化,あるいは無化することにより,彼の心は繋ぎとめるものを失って危うくなるということだと考えられます。
そして心が回復してくると,それらのものが一斉に彼の世界に戻ってきたといえるのです。それらとの関係は生きたものとなり,親しみを持つものとなり,そうした関係に繋ぎとめられて心が落ち着くことができたのです。
このように心が不調のときは,自己と自己の世界を構成するものたちとの間の生きた関係が損なわれているといえます。逆にそれらとの関係が改善されれば,心の回復が図られることになりますので,あえて自分の世界を構成し,支えているものたちに意識的に目を向けることは意味のあることです。それらは自分が存在し,生きていく上で大切なものであるのは明らかですから,生きた関係が保たれているときは,自ずから感謝の心が,特に意識はしなくても,それとなく流れているのではないでしょうか。健康なときに,暖かな心でいられるのは,そういうことの反映であるといえると思います。「物を大切にしなさい」といえば,現代ではうさんくさく思われるかもしれませんが,自分にとって大事なものを大事に扱わなければならない意味があるのは明白です。プロ野球の落合監督は,現役時代にバットを常に磨いて大切に扱っていたと聞いたことがあります。
自分の世界を構成している物や風景や動物については,それらとの関係を改めて確かめてみることで,心の世界の活力を導き出す意味を持つと思います。しかし人の場合は特別に複雑です。それだけに重要な意味があり,両親を中心とした鍵を握る人たちとのあいだの関係改善をはかることが,精神療法の要件です。
中年のある女性は,長年のあいだ,さまざまな程度のうつ状態がつづいております。
彼女にとって重要な関わりがある人が三人います。一人はおなじ敷地内に住む高齢の母親,一人は夫,一人は既に嫁いでいる一人っ子の長女です。
母親はおなじ敷地内に住んでいます。その母親に,亡父の墓参りに誘われました。その日,起きたののはお昼ごろでした。母親は,「一人で行くからいい」と怒って行ってしまいました。
母親には,すぐ近くに住んでいることでもあり,食べるものを持って行ったり,身の回りの世話をやいてあげたり,できるだけのことをしようと努めてきました。しかし母親は一向に有り難がらないのです。持って行ったものを,「要らない」と突っ返されることもあります。夜中に目覚めたときに,母親が無事かどうか,しきりと気になった一時期がありました。それは母親を思う情に違いないのですが,その裏返しの感情も潜んでいるかという趣がありました。母親に認められたい心が強く,それがいつかな適えられないので,怒りが潜在していてもおかしくありません。妹と母親との関係もあり,母親はたぶんに操作的,支配的で,母親との間の歪んだ依存関係が根本問題の一つといえるでしょう。
夫に対しては,結婚早々から不満が内向しています。会社が倒産したとき,保証義務がおよんで大きな経済的損失を余儀なくされました。夫はいま困難な病気と闘う身です。始終辛そうにしている夫に気疲れします。怒りをぶつけることもできません。特別食をいつも考える負担も耐え難いものがあります。
長女には手を焼いてきました。いいたい放題,したい放題の娘だったと思っています。いまは結婚し,子供も生まれました。たまに帰ってきたときは,母親の都合は念頭になく,子供を預けて夜中まで遊んでいます。
母親との墓参の約束を寝坊して果たせなかったあと,夕方まで眠りました。そして目が覚めたとき,無性に死にたくなったのです。死のうと思い,身の回りの物を整理し,遺書をしたためました。
しかし長女のことが目に浮かんできました。そして身勝手なことはできないと思ったのです。
彼女が自殺を考えるほどに追い詰められたとき,彼女の世界を支え,彼女を世界に繋ぎとめておく一切のものとの関係が途絶えかけたといえます。その背景には強い怒りが潜在し,それが一切の関係を断ち切ろうとする勢いを示したともいえると思います。自殺に走るのは,このように自己の世界を支え,自己を世界に繋ぎとめているもろもろとの構成的関係が終焉を向かえ,関係が死滅するときであるといえるのでしょう。
そういうときに,彼女の場合,長女との関係が蘇ったのです。そして,それによって生きる力が回復したのです。
統合失調症では,世界が貧困化します。誇大感を持つある患者さんは,芸術や学問の世界で超一流の力を発揮する夢のような話をしばしば語ります。その夢は決して実現されることはないでしょうが,それによって生きる支えを得ているのも確かでしょう。
統合失調症では,現実吟味力が問題にされます。どのくらい客観的な認識力が保たれているかという意味です。この力は,自我の機能の一つです。現実の上にしっかりと立っていないと,自己を正しく保つことができません。現実吟味力が病的に損なわれているとき,自我の機構に深刻な障害が生じている端的な表れであると考えなければなりません。現実に立脚することが困難であることと,関係性が広範囲に損なわれているということとは,おなじことの二つの表現です。それは,言葉を換えれば,世界が病的な変容をきたしているということになります。
これらのことを考えると,人や物など客観世界のもろもろのものとの間で生きた関係にある心は,文字通り生きているのです。個々人それぞれの世界は,主観的=客観的という性格のものであるといえます。
まったくの客観的な世界というのは,それ自体で自足する世界です。まったくの主観的な世界というものは,たぶん存在しないでしょう。こうしたことは,おそらく人間が自我を持つ存在であることに起因します。人間の誕生は客観的世界からの乖離という意味があり,そのときに自我が付与されたというふうに考えることが可能です。付与したのは何ものかというのは,人間の理性を越えた問題であるとしかいいようがありませんが。ともあれ人間を特徴づける最たるものは何かといえば,自我を持つものであることといえるでしょう。そしてその由来は,おそらく永遠の謎だと思われます。そしてまた,人は自我によって主観的な存在であり,かつ客観世界との関係を必須のものとしているといえるのです。心の内部の客観世界は無意識の世界です。比喩的にいえば無意識は海であり,自我はその上に浮かぶ小舟の船頭です。もっともこの海は,無限大の広さと深みを持っています。船頭の操船にあやしいものがあれば,船頭に期待されている予定調和が乱され,怒りが海を荒れさせます。それで更に船頭が操船に自信を失うと,海はますます荒れて子舟を呑み込もうとします。それが無化作用です。
客観的世界との関係を保ちつつ,自我に拠り自己自身であらんとする存在者,それが人間です。まったくの主観的世界は存在しませんが,自己自身であらんとすることに難渋すると,客観世界との関係が途絶に瀕することになります。その極端な様態が統合失調症というものです。そこでは主観的=客観的という関係に,さまざまなほころびが生じ,著しく主観に傾くのです。主観的自己が客観世界のものとの関係に繋がれていないと,自己はかぎりなく貧困化します。その病的過程では,自己がバラバラになりそうだという強い不安が訴えられますが,このような深刻な事態が進行していることに伴う不安であると考えられます。
客観的世界との生きた関係が確固としていることが,もう一方の主観的世界が充実しているためには不可欠です。それは人間という独自の存在者が目指すべき自立理念が,客観的世界への合流であることを示唆しているように思われます。そして客観的世界に属するものの性格は,汲めども尽きない豊穣性と,冷酷ともいえる沈黙であるように思われます。
心と世界が充実し,温かくなるのは,心が,この客観的世界の豊饒性に触れているということであり,心と世界が寒々として貧困化するのは,その接触が希薄化し,冷酷なものが前景に表われているということであるように思われます。
自我の出現以前の自然が,人間的に理解すれば,全(豊饒性)または無(冷酷性,沈黙性)であり,自我とともに自然から乖離された人間存在は,それ自体で自足する存在ではなくなったということになると考えられます。自我に拠る存在として,人間は主観的であり,かつ客観的であるという独自の存在構造を持つにいたったと考えることができると思います。
そもそもの自然は,その全体性という性格から全という豊饒性であり,かつ無という性格から冷酷性ないしは沈黙性でもあり,自我との関係においてはそれらのいずれもの様相が,さまざまな形で現前するということではないでしょうか。
さきほど,自己の世界を構成するものの中で,自己と物や動物との関係はシンプルなので,それらについて意識的になることで,ある程度の心の化粧直しが可能だが,人については複雑で別格であると述べました。
そのことを具体例に即してみて見ます
長期間,うつ状態から脱せないでいるある女性が,母親と激しい口論をしている夢を見たと報告してくれました。現実にはそういうことは起こったためしがないそうです。つまり彼女の意識では,「子供じみたところがあり,あまり母性的とはいえないとは思いますが」と控えめに批判しますが,母親との関係は穏やかなのです。
こういうときに,心の化粧直しは,より手の込んだ方法が必要です。つまり,意識はしばしば己をも欺くものなので,意識が捉えている母親や父親をはじめとした他者のイメージが,心にとっての真相を必ずしも表していないのです。意識が真相を隠そうとするのは,それが心にとっての影に所属するものだからです。
彼女の場合,怒りを強く抑圧していることがうつ状態の遷延につながっていると推測されます。意識的な心の内景は,母親との関係が穏やかなものということになります。そのかぎりではよい関係にあるということになりますし,物や動物との関係であれば,それで十分といえます。しかし人との関係ではまったく十分ではありません。
仮にこの女性の意識が,それなりの心の準備を抜きにして怒りの存在を捉えてしまったとすれば,心は大混乱に陥ると思います。自我が激しい怒りを受け止める勇気を持てないので,抑圧の手を緩めることができないでいるのです。それが生きている気がしないほどの抑うつ感の理由と思われるのですが,抑圧の手を緩めることができない自我は,おそらく自立には程遠いのです。父親ないしは母親の自我の支配を強く受けているので,彼女の自我は自分を助ける独自の働きを封じられているといえます。
彼女の場合,いわゆる対人関係の改善は,内的な両親との関係をあるべき姿に改変しなければ果たせないといえます。意識の上では穏やかな関係をひと掘して,彼女の自然の自我の機能を大いに混乱させられたことの怒りを,意識が明るみに取り出さなければ解決しません。それは必然的に親への怒りを表に現わすことになります。その筋の心理的作業を貫徹するには,自我の強化が果たせなければできない相談ですが,その勇気を持ち始めたときに,心の大混乱の彼方に新たな心の平衡が待っているといえます。
自立が理念であるというときに,その方向を指し示すのはどうやら自我ではありません。
自立の概念が成立するのは何を根拠としているのかといえば,人間は究極的にどこへ向かおうとしているのかという問いに発すると思います。人生は死によって終焉を向かえます。生と死のあいだには連続性がありません。そして死は人生の到達ではなく,生の回収です。生は自我の世界のものですが,死は自我の力のおよばない世界のものです。そのように考えると人生に究極的な到達点はなく,未完のままで終わる宿命の下にあります。死は自我の力を超えた世界のものであり,自我を無化し回収する力を持つものとして,自我を超越した,上位にあるものです。そうしてみると,自我が回収され,生が終焉を向かえるときに,人は,「人生は結局は虚しい」と考えるか,「これでいい」といいおおせるかの両極に分かれると思います。前者は闇に包まれてしまっている者がする影の思考であり,後者は自我が生きている光の思考であるということができます。
生に到達点がないことと,生が回収によって終焉を向かえるのは同じことのようですが,生があるべき到達点に向かおうとしつつ終焉を向かえるときには,「これでいい」という肯定的な気分になれるのです。この’あるべき’到達点への到達が自立というものであり,それは実際にそこに到達することはできませんが,指し示される朧な光として感じ取ることが,人によっては可能のようです。
はるか遠方に,朧にかすんで定かには捉え難い光を捉えるのは自我です。その発光体は,矛盾したことをいうようですが,自我の内部にあるといえるのでしょう。つまり自我が拠り所とする自我機構のうちに存在していると考えられます。自我は機能であり,自我機構を拠り所としますが,機構そのものは自我が作り出した作品ではありません。
結局,自立は自我の直感に訴える何かとして感じ取られることは可能ですが,現実には到達不能の理念であるということになります。
人間に可能なことは,自我が意識という光を機能させて目下の問題を探索することです。そして,その極限に達したときに闇の世界がはじまり,そこは人間の世界であって人間の世界を超えています。朧な光につつまれた自立の理念は,自我を通じて発光させる闇の世界のなにものかの意志であるようにも思われます。
その朧な光の根拠,ないしは自我機構の存在根拠は,自我と直接的に関わりつつ自我を超越しているものという性格のものであり,それを前章で述べた内在する主体と呼ぶことができるのではないかと考えます。
自立は自然に通じるものがあると思います。自然とは,自ずから然りということです。つまりそれ自体で自足しているということです。自立もまた,それ自体で自足しているということですから,両者には共通するものがあると思います。
自立は自我に与えられている課題です。自我は内なる自然である無意識に拠り所を持ちつつ,外なる自然に関わる諸々の現象としての自己の世界を構築していきます。そしてやがては自然そのものに合一するべく自己を導く使命を帯びています。それは果たしえない目標であり,ついには死によって人生は切断されることになりますが,精一杯生きるというのはそのように生きることだと思われます。何事も精一杯生きることはいわば理想です。何らかの目標があり,それにかなう能力への信頼があるときに,そうした最善の生きる姿勢が得られるのです。自分を信じていなければ,目標があっても行動は伴いません。自分を信じていられるときは,自分の自然に触れているときです。何事によらず,自然が一番よいのですが,自然そのものを生きることができないのが人間です。自然的に生きるのは難しい課題です。しかしそれを求める心があれば,そこに近づくことは可能で,そのときにたぶん満足のいく充足感があることでしょう。
人が自然的な生き方ができる拠り所は,内なる自然にあります。関わりを断ち切るわけにはいかない重要な意味を持つ他人たちによって,一途に心の自然を混乱させられるのは皮肉以上の不可思議ですが,それが現実です。その不自然となった心を,内なる自然を拠り所に,改めて自然に立ち返るのが人生です。そのことの手がかりは夢が与えてくれるかもしれません。夢には内なる自然の叡智が表われる可能性があるのです。そのことからも闇の世界である無意識の領域は,自然そのものが心に関与しているものであると考えられ,そこには人知を越えた叡智が沈黙のうちに存在していると考えてよいようです。
自立が自然の特性である完全性を持っているのに対して,自我に拠る人間は不完全な存在です。であればこそ,完全なものである自立を理念とするのです。,
人間存在の不完全性は,心の二極構造として表われています。自己が存在するためには他者の存在を不可欠のものとしていますが,他者は外的な存在にとどまらず,自己の構造に内的に含まれているのです。
私が男として存在しているということは,自己の構造として他者を内に含み,異性を内に含んでいることになります。完全なるものを希求するものであるらしい自己存在は,自己の構造に他性を含み持ち,それによって外的な他者,および異性との関係が不可欠なものとなっていると考えられます。かつまたその一方で,それら外的な他者,異性と結局は一体のものとなることは不可能であり,自己は不完全性を克服し得ない存在なのです。
自己の内的な構造として異性や他者が含まれていることにより,外部に存在する彼らが,外部からの観察と学習によって初めて理解可能な異星人のごときものではなく,経験以前にそれらの存在を了解しているといえます。
それらのことの根本には,人間が自我を持つことによって人間であることに伴い,自我と無意識との二極に分離して心が成立している存在であることに関連していると思います。つまり人間の誕生というできごとは,自我と無意識との二極に分裂した存在として,自然から乖離したものが世界に登場することであると考えられますし,死によって自我と無意識の両者が再び合体したときに,自然に帰還することになるというふうに考えられのです。
ともあれ,いかなる叡智が人類を生み出したのかは知るよしもありません。しかしたとえば夢において,日常の思考系列からすると啓示のような考えが現に見られるのであり,それは自然の叡智とでも呼びようがない思考のひらめきです。そのことからしても,人間は無目標のまま放り出されたというようなものではないように思われます。人生は難解そのものであり,その生誕と終末との謎を解き明かす力は人間にはないといわざるを得ません。漂流するかのような人生があります。極悪人も存在します。病気という心の破綻もあります。人生の舵取りはしばしば困難を極めますが,それでも心の奥底に耳を傾ければ,意味深いつぶやきが聞こえてくることも可能です。それが生きる方向を指し示す力として感じ取られたときに,自立の方向が朧に感じられたということであるのかもしれません。それは分かる者にだけ分かることなのでしょう。
いずれにせよ自我の認識能力がすべてではないと思います。それを超えたものがあるのは明白ですから,自我万能主義は愚かな迷妄というしかありません。そこからは,「人生は結局は虚しい」というつぶやきが聞こえるばかりだろうと思います。自我を超越したものが存在しているのは論を待たないので,その前に頭を垂れる謙遜こそが人間にふさわしいといえるのではないでしょうか。自分よりゆるぎのない上位のものが存在することを認めることは,その前に自然に頭を垂れることが含まれるはずで,これ以上の豊かさ,喜びはないといって決していい過ぎではないでしょう。
自立理念は,それに向けて現在の自己を脱し,より好ましい自己に改変していく方向を示すものです。好ましい自己の方向とは,いうならばダルマへの道です。自己の重心が自己の真ん中にある感覚です。なにか痛切な出来事があって,自分を保つのが危うくなっても,ほどなく傾きかけた心の態勢を立て直すことができるための拠り所が,自己の内にあるという感覚です。
現実に,人は何事かに依存しつつ存在します。自己があるということは,同時に,それは何事かとの関係で存在するということです。その関係の連鎖の先には,他者との関係があります。自己が存在するということは,結局,他者との関係として存在するということです。
人間を特徴づける自我は無意識の力に依存しています。それが,自我に拠る人間が,基本的に依存的な存在であることの根本理由かもしれません。依存は一般には相互的なものですが,自我と無意識に関してはそうではないと思います。無意識の中でも,個人的無意識(ユング)と自我の関係は相互的です。しかし集合的無意識は人間の心の内部にある自然であり,全という性格を持つものなので,自我が一方的に依存する関係にあると考えるべきだと思われます。
先に述べたダルマ的な心の中心という意味は,拠り所としている無意識の力と接触している感覚であるように思われます。人は他人との関係に依存しますが,それは必ずしも他人が信頼に値するという意味ではありません。それは,また,別問題です。他人は力を貸してくれることもあり,しばしば裏切りもします。ですから他人との関係に自己の命運そのものをかけてしまうのは,大変危険です。自己の重心がむしろ他者にあるときに,精神は病的に不安定になりがちです。他人の裏切りにあえば,ひとたまりもなく自己は傾きかねません。いうならば他人しだいの人生になってしまっている人は,現実に決して少なくないように思います。彼らは,他人によってわずかな打撃を心に受けるだけでも,しばしば深刻なダメージが残り,容易には回復しないのです。
しかし自己の重心が自己自身の中にあれば,心に打撃を受けても,ダルマのように態勢を立て直すことができるのです。
自己の重心の本来的なものは,心の内なる自然である集合的無意識にあると考えてよいと思います。その自然が自我の機構に及んでいると考えられ,それとの関係に自我が直接的に拠り所とする首座があると考えることが可能だと思います。その自己の本来的な拠り所と思われるものを,内在する主体と呼びたいと考えます。
この主体との関係が好ましくはかられている状況にある自我の下にあるとき,心はダルマ的に安定し,関係が好ましくないときに心はダルマ不在,もしくは他者への悪しき依存ということになると考えられると思います。
Pさんは40代後半の主婦です。夫と長男,長女との4人家族ですが,長男は一人暮らしをしています。地方都市で大きな割烹料理店を営む両親の下で育ちました。母親は優しい性格といいますが,夜遅くまで店の仕事があるので,朝は遅くまで寝ているのが日常でした。当然のように,幼いときから,毎朝幼い弟の分と二人分の弁当を自分で作って学校へ行っていました。家には住み込みの従業員が大勢いて,いつも賑やかでした。弟は寂しい思いをして可哀想だったといいますが,本人自身は大勢の人に可愛がられて仕合せに暮らしていたそうです。
ずっとよい子だったといいます。母親が忙しい姿を見ていたので,たいていのことは自分でしていました。気分がすぐれないときも,面には出さず,元気そうに振舞っていました。
高校を卒業した年に,東京の大学に入りました。寂しい日々で,寮の自室に閉じこもりがちだったようです。
20代前半で,学生のころから交際していた男性と結婚しました。夫は優しい性格で,これ以上いうと嫌われるかなと思いながら,思いのたけをぶちまけることもしばしばでしたが,常に優しかったそうです。その夫より自分が上位にいるような気分もあったといいます。夫には社会的な地位があるので,その妻である自分が誇らしくもあり,惨めなようにも感じていましたが,「私がいないと家庭がまわっていかない」という自負心を持っていました。
育児は生き甲斐を与えてくれました。元々手を抜けない性質ですが,常に良い母親でありたいと考えつつ,我ながら一所懸命にやったと思っています。しかし子育てが終わり,子供たちが成長していく姿を見ていると,自分だけが取り残されていく焦りと不安を感じるようになりました。
舅が死んだあと,姑を引き取り10年間生活を共にしました。最後の2年間は痴呆症になり入院しましたが,毎日のように見舞いに通いました。夫に負担をかけたくないと思い,休日も,「いいから休んでいて」といっていました。
難しい性格だった姑が死んで,数ヵ月後に初診となりました。そのころはしばしば落ち込み,何につけ自信がなく,夫に八つ当たりしがちになっていましたが,発端と思われる問題は,姑が亡くなる2ヶ月ほど前に起こりました,帰宅した夫の顔を見たとたん,居ても立ってもいられない気分に襲われたのです。
Pさんの通院は数年におよびます。一進一退ながら徐々に動じなくなる方向に向かっているといえます。
Pさんの問題は表面を見ればうつ病ということになりますが,依存的な性格がより根本の問題です。つまりPさんはダルマ性に程遠い性格といえます。Pさんを支えるのはPさん自身ではなく,夫と長女です。なかんずく夫であり,夫を支配しつくさないと安心できないのです。
育児と姑の看病は,Pさんにとって頑張りどころでした。自分の価値を示すよい機会でした。模範的な良い母親,良い妻というのがPさんに与えられた課題です。その課題を与えたのは,おそらく母親と父親です。実際には両親がそういう指示をしたわけではないのですが,Pさんが両親の覚えを確かなものとするために必要な,無意識的な戦略であったようです。夫の帰りが遅く(接待が多いのです),長女もまだ帰宅していない一人でいる時間に,見捨てられたような不安,寂しさがあったと,あるとき述べております。
芸妓もまじえた大勢の人がのべつ出入りする環境の中で,Pさんは実際にみんなに可愛がられていたようです。Pさんはずっと良い子だったと思うと述べています。そういう事情を見ると,一見なに不自由なく恵まれた環境に育ったようであり,Pさん自身がそのように認識しております。両親が家業で忙しいのを目の当たりにしているので,我慢して当たり前という生活状況でした。それだけに,いっそうPさんには両親を困らせないようにする理由がありました。しかし良い子というのは,大きな自己犠牲を払わずには成り立たないものです。幼い子の心の自然の欲求が満たされなかったと思われるのですが,それがPさんの心に残った寂しさと依存心と支配欲の源泉と考えられます。どんなに大勢の人に大切に扱われても,両親は別格です。両親,なかんずく母親に見捨てられる不安は,すべての赤ん坊に共通する本源的なものといえます。それを甘えによって和らげていくことが心の成長には必須といえます。Pさんは,大いに恵まれた環境に育ったともいえますが,肝心な一点で欠けるものを持っていました。
「なんでも一番でないと気がすまないところがある」と控え目なPさんが何度か述べております。幼いころに自宅が新築されたときに,弟の部屋の方が大きかったのが口惜しかったということです。元気だったころには,夫を下に見ていたといっておりますし,夫が昇進すると誇らしく感じる一方で,自分が置いてきぼりにされるようで不安だともいっております。夫が接待で女性の多い場所に出入りすることが多いようですが,若い子の話をされると,嫉妬とともに自分は不要といわれているように思えます。私がいるとどうせ邪魔なんだろうと,家族旅行をキャンセルしたこともあったといいます。
Pさんの性格は,明るく,穏やか,優しく,親切といったふうな好ましいものだと思います。特に無理をしてそのようにしているとは思えません。それがいわば表の人格です。一方,裏の性格には,人に認められ,受け入れられないという大きな不安があります。そこには裏の性格につきものの大きな怒りが潜在していて,その怒りが,当然の欲求を満たされることがなかった理不尽さにからんできます。それは母親には私が可愛くないのか,不要な子なのかという不安と不満でもあるはずです。
夫は優しく,受容的な人のようで,依存する相手が切実であるPさんには,自分を託すにはこの上もなかったようです。その夫を,Pさんの無意識は支配しようと考えたようです。自分が受け入れられない不条理と,それに伴う怒りとが裏の性格を彩っています。従来は,そのつもりがなかったでしょうが,抑制に抑制を重ねてきたので,大きな怒りと不満とが,お門違いともいえる夫に向けられたのだと思います。その不条理も知っているので,Pさんはしばしば懊悩し,落ち込みもします。それが表の性格をリードする自我の悩みであり,力不足でもあるのです。そして内心の不満と怒りとに煽られる裏の性格が,安心のできる夫に,いわば完璧で,全的な受け入れを求めるのです。
このような表の自我の力不足が,裏の自我の強い要求を引き起こしているのですが,両者のあいだの葛藤がPさんの病態を招いているといえるでしょう。両者の綱の引き合いで,ときには気分が晴朗になり,ときには不安と憂鬱と苛立ちになるのです。
悪しき依存には怒りが介在します。それはしばしば無意識です。怒りをつよく抑圧した依存(本人には怒りは意識されません)の状態にあるとき,依存する相手に絶対的な忠誠心を持つことがあります。その極端な例は,昨今問題になっている虐待に見られます。命が危ないほどの目にあっている子が,第三者が救助の手を差し伸べようとしても,十人が十人,放って置いてほしいというそうです。
子供の方が怒りをあらわにし,親に暴力的になる形の依存もあります。この問題もしばしば深刻ですが,怒りを表せない依存は問題視されにくいことが多く,こちらも同様に深刻です。怒りを出せないのは,当然,恐怖や不安からです。恐怖や不安を持ったために”物言わぬ子”になってしまうのは,ごく幼いときに問題の発端があったからでしょう。心身がある程度成長し,それなりに力を自覚するようになってからは,いわゆるPTSDにつながるような特殊な状況下ではともかく,滅多には”物言わぬ子”にはならないだろうと思います。
人間の誕生は,自我に拠る世界の幕開けです。何によってか,人となるということは,自我が付与されることによってということです。自我は,それぞれの個の世界を切り開き,構築していく上で必須のものです。また,自我が付与されたということは,自分の責任で生きなさいという意味が含まれています。赤ん坊にはそんなことは分かりようもないでしょうが,しかし,無意識のどこかで地獄のような人生を背負わされたと感じているかもしれません。胎児以前の自然の一部であった時代は,苦楽はもとより,一切の意識が存在せず,従って永遠の沈黙の中にあったともいえるのでしょう。それがいかなる理由によってか,永遠の沈黙の世界から乖離されたのです。それが自我に拠る人間の誕生です。生まれ出るものは,人々に喜びをもたらします。それは人間が自我によって生を切り開く使命を帯びており,自我は光の世界の演出家であるからです。光をもたらすものは,自我の世界への参入だからです。そして生まれ出た赤ん坊はどうでしょうか。光を知るものとして歓喜するでしょうか?それはおそらく違うと思います。光を知ることは闇を知ることでもあるからです。赤ん坊に光も闇もないかもしれませんが,人間の誕生ということは,光と闇の世界の始まりということですから,赤ん坊が何も感じないと考える根拠はありません。赤ん坊が驚愕と怒りの中にいるとしても不思議はないと思います。後々,そういう記憶が感覚として残っていないという証拠もないと思います。
人間の誕生はいずれにしても並大抵のものではありません。
児童心理学の研究者でもあったイギリスのメラニー・クラインによると,生れ落ちた赤ちゃんは激しい怒りを持っているということです。おそらくは安全で心地よかったはずの母親の胎内からいきなり放り出されるのですから,途方もないことといって過言ではないでしょう。いずれにせよびっくりもし,怒ってもいて当然のように思います。
出産とは,赤ん坊に成り代わって想像的に大人の言葉で表すと,不安,恐怖,猜疑,怒り,寄る辺なさといった大きな感情を伴う体験ではないでしょうか。
そのように激しく傷つく心は,万能感といわれているものによって守られていると考えられています。「大きな力で守られているのだから大丈夫」という感覚です。それを満たす立場にあるのが,誰よりも母親です。しかしいうまでもなく母親の力は万能ではありません。ですから胎内にあったときに匹敵する安全感と満足感を求めるだろう赤ん坊の激しい欲求は,たえず裏切られないわけにはいかない宿命の下にあるのです。その欲求を母親が満たしてくれるときには至福の感情を味わい,満たされないときには激しい怒りの虜になるのです。
赤ん坊の恐怖は,闇を感覚的に意識するからではないでしょうか。それは自我という光のものを持つことに伴う必然です。そして光は生世界のものであり,闇は死の世界のものです。生まれたばかりの赤ん坊にして,生と死を過敏に感じ取るのではないかと想像されます。
赤ん坊の不安は,闇または死を感受することにあるように思われます。その恐怖を和らげ,安心保証をする役目を持っている母親が,赤ん坊の欲するものを与えてくれていないと感じるときに,赤ん坊は激しく恐怖し,怒りを持つと思います。怒りは保証を求める叫びでしょう。そして赤ん坊が自分の怒りの投影を,母親の表情の上に見たとき,母親が世にも恐ろしいものに見えることがあると思います。場合によっては悪鬼のように見えることもあると思います。そういうときには怒りが麻痺し,恐怖であらゆる感情が抑えられるかもしれません。
そのようにしてよい母親とわるい母親とが交互に現われ,それがやがて一人の人物として統合的に認知できるほどに自我が成長していきます。
乳児はまったくの依存の中にいます。絶対的な依存の対象を必要とします。胎内にいるある時期までは,自然の特性であるそれ自体という存在形態でしょうが,生れ落ちると同時におぼつかない自我を保護し助けるものが必要です。依存の絶対的な対象を必要とするということになります。母親の胎内での安全感に匹敵するものが求められ,それが先ほど述べた万能感という幻想です。ここに依存の原型があります。
万能感が満たされたときによい母親が体験され,満たされず怒りに駆られるときにわるい母親が体験されるというふうに考えれば,依存にもよい形とわるい形とがあることになると思います。よい依存は,自分が愛され,認められているという自我意識の形成に寄与することでしょう。それは自分は自分を愛している,認めているという健全な自己愛の形成にも寄与するはずです。そして自立へと向けた心の動きにつながります。わるい形の依存は,自分は愛されてはいないのかもしれない,認められていないらしいという恐怖,猜疑を伴う感覚的意識で,自分でも自分を愛せない,認められないという自我意識に発展すると思います。そうであれば人間に必須である自己愛の健全性が傷つけられることにもなると思います。それは自立するための基盤を危ういものにすることになると思います。
これらのことはだれもが程度の差はあれ置かれている,あるいは置かれざるを得ない人間の宿命的な姿ともいえるでしょう。強い自我に恵まれた人であれば,こうした心の逆境(悪しき依存に伴って,それを助長する体験が集積されて,心の暗部に得体の知れないものが沼のようにたまります。それは心の内側からおびやかされる原因になります)に悩まされながらも,立ち向かっていく力を発揮することがあります。大きな仕事をなしとげる人は,むしろいま述べたような心の重圧をかかえていた人たちといえます。自分の内部に鬱屈した問題を抱えてしまったために,真剣に人生と対峙し,人生を模索する人は強い自我の持ち主です。しかし多くの人の自我はむしろ弱く,人生と対峙するよりは回避する傾向が強くなるのは否めません。
ある不登校の高校生の例です。
新学期になれば学校に行けると思うといっていましたが,実際には行けていません。学校に行かないことを除けば,何事もないかのように過ごしています。友達とディズニーランドへ遊びに行ったりもします。
しかし朝は,蒲団をはいでも起きようとしません。母親には理解ができず,苛立ちがつのります。
学校に行けないはっきりした理由は,本人にもよく分かりません。積極的に行きたくない理由が学校にはありません。
学校という管理された社会と個人の自由な世界とで,この子は別な顔を持っています。母親の苛立ちは,人としての義務を遂行せず,わがまま勝手に生きているという類の怒りに発しているようです。そんなことでは大人になって落伍者になるという不安でもあるでしょう。確かに,それぞれが大人になったときに,自立的な人生を送ってもらわなければ困ります。母親の不安を解消するには,自立した大人に向けてのプログラムが見えたときといえるかもしれません。
この子の母親が安心する自立とは,依存から脱出しつつある傾向が見えるということでなければならないでしょう。しかし実際には,母親が心からそういうことを望んでいるかは疑問です。ふだんは元気にしていて,なぜ学校に行けないのかという母親の思いが間違っているとは思いません。ただ,ふだんの気楽そうな生活ぶりに幻惑されてか,学校へ行くか行かないかというレベルで苛立っているのは問題です。というのは,なぜという問いを,子供の心に即して発していないからです。母親は自分自身の常識の中から出ようとせず,その常識の高みから子供の行動を批判的に見ているのでは,依存の中にいるからこそであるに違いない不登校問題の核心は見えないだろうと思います。自立が問題であれば,依存の形を見なければなりません。それは子供の行動を,批判的に見ることによって得られるものではないはずです。それが問題であれば,母親は子供の問題に関して,自分自身を見つめる必要があるのです。それはたぶんに母親自身の問題だろうからです。そういう発想ができていないことが,そもそも母親の養育姿勢が,自分の思考や感情から子供の行動を批判的に見,かつ指導する体のものだっただろうことを暗示しています。つまりそれは,母親一般が実にしばしば陥るものである,子の世界へのぶしつけな侵入であり,干渉であるだろうということになります。そしてまた,それは子供が持っている力を信じようとしなかったということにもなるのです。子供の立場からすると,母親が望むようになるしかないのです。それは悪しき依存の形を作る典型です。
そうして見ると,母親の苛立ちは,自分の思い通りにいかない子供に対して腹を立てている以外のなにものでもありません。
子供は心の根っ子のところで,母親に信じてもらっているという安心を得られなかったと思います。これは不登校児にかぎりませんが,なんらかの心理的なつまずきに至っている子に,共通して見られる問題といえます。
乳幼児期に母親から母親本位のではない愛情を受けることができず,従って信頼を受けていなければ,自分は人に信じてもらえないという基本的な不安をかかえることになっても不思議はありません。そうすると自分は駄目な子で,人に受け入れてもらえない性格だという考えに直結することになります。
この子の場合も,級友たちに受け入れてもらえない不安が強いのです。本人もそう思っています。
本人の問題を解決するには,母親自身が変わらなければなりません。
この子の場合も,乳幼児期にどんな体験をしてきたかは誰にも知ることはできませんが,以上のように見ていくと,おそらく母親の養育姿勢は自分本位ではなかったかと想像するだけのものがあると思います。母親が子供の自然な能力を大切にしようとせずに,母親の思い込みどおりであってほしいと望んで育てたとすると,子供の心の自然は混乱させられるのは必至です。母親の介入によって混乱させられた心的状況では,乳幼児期の自然な欲求は,自覚がないままに無意識界に抑圧する以外に,母親との関係は保てないことになるのです。そしてその分母親の自我に従うことになり,本人の自我の成長は阻害されることになるのは避けられません。それは悪い形の依存ということになり,それに伴い,抑圧された影の分身たちがしだいに大きな勢力になっていきますし,いつまでも日陰者のように抑圧されたままでいるしかないことにもなります。それは影の性格とでもいうべきものとなり,表の自我を脅かすことになっていきます。
これらの日陰者たちが勢力をつよめることになったそもそもの理由は,自我が本来求められている指導性を発揮するに足りる力を示すことができなかったところにあります。そしてそうなったことについては母親の干渉があったので,母親に依存する分,自我は無責任にもなるのです。その結果として影の分身たちが裏の性格といえるほどに勢力を増すのを許してしまっている今となっては,ますます自我の手には負えるものではないのです。自我は無責任に,触れずに済ませたいという態度になるしかないといえます。
この子に即していえば,学校に行こうとするのは表の自我の役目です。その力が自律的に伸びるのを奪ったのは,どうやら母親のようです。本人は,学校へ行けないのは反抗もあるといっております。自我の力不足が学校へ行けない直接の理由ですが,そこには母親の関与が大きく働いているので,反抗という側面はあっておかしくないのです。
母親は,良い子を求めてきたということになりますが,それが仇となって,表の人格形成の成り行きとして,学校へ行けない’悪い子’にしてしまう結果を招いてしまったことになります。また,「学校へ行きもしないで平気で遊んでいる」というのも,母親の観点からすると悪い子ということになります。これは裏の性格によるということになると思います。本人の場合,悪というほどのものではないので,友達との関係,明るい遊びという’逸脱行為’にとどまっているのですが,裏の性格に基づいたものの中には,悪の性格の色が見える場合も少なくありません。
断っておきますが,一般論として子供が学校へ行かないのが悪い子というわけでは,勿論ありません。
ここで事例として上げたお子さんについて,母親の価値観からすると悪い子になってしまっているということですが,母親が自分の望みどおりに子供をしつけようとすることも,悪いことといえるのです。
それにしても,社会性がないと将来が案じられるという現実があります。学校に行かない「悪い子」であっても,芸術的な才能なりがあれば,あまり問題になることもないでしょう。要は,その子が一生を託すにあたいする拠り所を持つことができればいいのです。特殊な才能に恵まれることは稀なので,一般には自分の力を信じることができているのが望ましい拠り所になるのです。そのためには,学校へ行けないでいる現実を,母親が容認する必要がまずはあるでしょう。
かつて作家の野坂昭如氏が,「子供は生きていてくれればそれでいい」と語っていました。この言葉につきるのではないでしょうか。現にある我が子のありようは,良いも悪いもないのです。それはそっくり容認されるのが原点であり,出発点です。親が容認することは,本人が自分の現実を認め,受け入れていくのを助けることになるのです。いずれにせよ,自分を助けることができるのは,自分自身しかありません。親はそれを側面援助できるばかりです。本人の自助の努力に水を差すようなことをしなければいいのです。
自分の力を自分自身が信じることができれば,他人は怖くなくなるでしょう。学校へ行こうが行くまいが,他人が怖いという理由は排除されるでしょう。
悪しき依存は心の障害の欠かせない前提のようなものです。それは精神を試練に立たせます。克服して自立の方向へ向かうことができるか,さもなければ様々な形でつぶされてしまうか,あるいはいやな気分を紛らわせるために気晴らしの日々を送るか,人生を分けるものでもあるでしょう。
性格形成に与える母親の影響-その5
■見捨てられる恐怖
見捨てられる恐怖は,「境界性人格障害」に固有の病理といわれることがありますが、この問題は、むしろすべての乳児が経験する心理特性であるというべきです。つまり、いうならば、人間が人間以前の存在形態から、人間存在へと移行する過程での通過儀礼ともいえるものです。
人間は誕生という形で、あるとき、いきなり個の人間として世界に登場するのですが、人間存在の著しい特徴は、生の個的な開拓者として、既に死を背負う宿命の下にあるということです。後にも述べることになりますが、死は無意味の代名詞ではなく、生の欠かせない対立軸と考えることができます。
つまり力強く生きるためには、意志によって限定化された可能性と、それを阻み、空無化しようとする不可能性とが対立し、せめぎ合う必要が欠かせません。
喩えていえば、算数の苦手な小学三年生にやる気を出させるには、容易に解ける二年生の問題をさせつづけるのも、初めから無理と分かる六年生の問題をさせるのも愚かしく、出来るか、出来ないかというところでせめぎ合わせることに意味があるのとおなじです。
この意味で、生を受けた者の必然として死を背負うので、赤ん坊にしてもその矛盾に満ちた現実に立たされるのです。
そして母親は、赤ん坊にとって‘全’の役割を担っています。
赤ん坊は、次のような気分的なメッセージを母親に向けて発するでしょう。
「あなたは完全な満足と完全な安心とを与えてくれる力を持っているはずです。そうでなければ私の存在は成り立ちません」
ある意味での臨床場面では全員に共通して見られる根本問題の一つです。診療に訪れる患者さんが直接この恐怖を意識していること はむしろ稀ですが,症状的なものが表面化する理由の根本のところにこの問題が関与しているのです。もっとも,この問題は心の病理的なものに悩むことになってしまった一部の人にだけあるのではなく,心の成長過程の最早期に,この恐怖を経験しない乳幼児はないといえる性格のものだろうと思います。ですから人間に普遍的にある心性といって間違いではないと思います。
一般的にも,日常心理のいたるところにこの恐怖は顔を出します。人に会うときの緊張もそうです。親しく信頼のできる人に会うときは,あまり緊張はしないでしょうが,目上の人,密かに思いを寄せる異性,嫌いな人,あるいは自分が嫌われている人などなどに会うときは,たいていは緊張を強いられます。
自分が愛されているか,受け入れられているかということに,多くの人がこだわりを持つものです。
この問題の基本概念を,E.Hエリクソンが「基本的信頼感」と呼んで提唱しています。エリクソンは,この概念は大人の精神病理学から学んだものだと述べております。その論旨は次のようです。
他人や自分自身とうまくいかなくなると,自分の中に閉じこもってしまう。自分の部屋のドアを閉め,食事や慰めを拒否し,交友関係を没却してしまう。彼らが根底的に欠如しているもの,それは,彼らに精神療法を施すときにはっきりしてくる。つまり,我々は彼らを信頼していることを信じてよいのだということ,および自分自身を信頼してもよいのだということを確信させる意図を持って彼らに接近しなければならない・・・そのように退行している患者の最も幼児的な深層部に接しているうちに,我々は基本的信頼というものを,活力的なパーソナリティの隅石とみなすようになった・・・そういう観点から逆照射して,病的に退行している人の心が,基本的信頼の根底において損傷しており,基本的不信感に陥っている・・・。
基本的信頼感は,赤ん坊が生まれて間もない原初の段階で,母親とのあいだで,母親主導で確立されることになるものです。安心と満足とを貪欲に求める赤ん坊とのあいだで十分な信頼感が醸成されるためには,母親の安定した愛情が頼りです。育児にかかわるこの過程で,母親の愛情に不安定なものがあれば,あるいは赤ん坊の側に特別に過敏で混乱し易い生物学的な事情があれば,赤ん坊の満足と安心は脅威にさらされることになるでしょう。見捨てられる恐怖が体験されるのはこのような母子の関係においてですが,完璧な母親があり得ない以上は,多かれ少なかれすべての赤ん坊が脅威にさらされることにならざるを得ないと考えられます。
ですから基本的信頼感といっても,その程度は個々にさまざまなのはいうまでもないことです。
人と自分とを信頼し,愛することができるための一定の礎の上に,人は成人として社会の一員に足りるように両親に躾けられ,学校で集団的な訓練を受けます。社会の中でときどきの集団の一員としての地歩を占めることができるためには,なかんずく他者との関係を円滑に営める能力の開発が必要です。他者愛と他者を信じる能力が一定程度そなわっていれば,更に重要な意味を持つ自己愛と自己を信じる力も,ひとまずは,それなりにそなわっていると考えてよいと思います。
いま述べた世間向けの顔ともいうべきものは,ペルソナと呼ばれているものです。ペルソナという対人的な一種のテクニックを身につけるための基礎が,基本的信頼感であるといえるのでしょう。
ペルソナの命名者であるC.Gユングは,このことについて次のように述べております。
非常な苦労の末にようやく実現されるこの集合的心(個人の特徴を離れた一般的,普遍的に見られる心)の一切を,私はペルソナと名づけた。・・・ペルソナは,もともと役者がつける仮面で,役者が演ずる役を表している。・・・個人と社会とのあいだに結ばれた一種の妥協である・・・。
つまりペルソナという仮面を身につけることと,それを形成する礎である基本的信頼との確かな醸成がなければ,人は社会的存在として危ういものになるのですが,一方ではそれは本音を隠すものでもあります。その意味での本音とは,社会性とは相反する性格を持つものに違いありません。
おびえ,ひるみ,恐怖,不安,怒り,敵意,妬み,恨みなどなどの感情は,ペルソナによって覆い隠されることになるものですが,これらの対人関係を不安定にさせる感情の根底に見捨てられる恐怖があると考えられます。この恐怖には強い怒りも伴いますので,仮に日常的に’本音で’人と対さなければならないとすると,いわば血みどろの闘争の日々になることでしょう。それでは人間社会そのものが成立しなくなってしまいます。
ペルソナは建前であり,本音を隠すものでもあるのですが,本音は滅多なことでは人に明かせませんし,滅多なことでは明かしてはいならないものでもあります。
見捨てられる恐怖が母親との早期の関係で緩和されていなければ,ペルソナによって装われた自己は内側から脅かされ,自己を保つことが危うくされかねないのです。そうなると自我は防衛のためにペルソナの仮面性を過度に強化し,場合によってはいわゆる心の硬い人ということになるかもしれません。
ペルソナを身につけることの主要な意味は,一般的な人々に受け入れられ,それなりに愛されるに値する性格の形成です。「私は社会でのしかじかの役割と責任を負っています。それをまっとうする力を培った人間です」というメッセージがペルソナに彫琢されます。また彫琢されるべく日常生活を励む必要があります。それは社会の一角に自分を位置させるために不可欠な努力であり,人を安心させるためのものです。しかしペルソナの出来栄えに神経質すぎる人は,ペルソナの仮面性が逆に面に表われてしまうでしょう。それは仮面が心を隠すという意味があるからです。感情を過度に押し殺すと,「能面のような顔」になってしまいます。そこには自己というものの表出が見えなくなっているのです。人に見せられない自己というものは誰にでもあります。意識下に抑圧されている影の分身たちはそういう性格のものです。しかし他人が,なぜそんなことが人に知られたくないのかといぶかしむようなものまで影の分身としてしまっている人は,「何を考えているのか分からない人」,「感情のない人」として敬遠されることになりがちです。ペルソナの彫琢が神経的に過度にわたると,魂が見えない顔になってしまいます。
ペルソナの完成は,自己の完成ではありません。それはまったく別な次元の話になります。それは人を安心させるため,見ようによっては人を欺くための仮面ですが,自分自身を本来的に満たしていく心の作業は,仮面の影に隠れているものを自らあばきたてることによって可能となるのです。いわば仮面の持っている嘘にあきたらず,あるいは偽りの自分であることに不安をかき立てられる人には,真実の自己の探索へと向けた心の旅が現実の目標になるかもしれません。これは大きな行為です。この心の作業,あるいは行為をまっとうするには,強い自我が要求されます。自我が弱ければ,あるいは自我の機能が衰弱すれば,自己と人生とを見失う危険がはらまれています。ですからペルソナに安住している大方の人は,見て見ぬふりをすることになるものです。その意味でペルソナの達人は,ごまかしの達人でもあるのです。
心の病は,いわば偽りの自己と真実の自己とのあいだの矛盾,葛藤の緊張に耐えられず,心にほころびが生じたものといえなくもありません。自己を創出するための演出者は自我ですから,自我が,演出者としての能力を無意識界にある身内から批判されて立ち往生してしまった図ともいえます。そして真実の自己を追究する心の旅に出る人にとっても,その先導者はやはり自我ということになります。この大仕事をするためには,自我が十分に力をつけていなければ出来ない相談です。
また,心の病に悩む人はペルソナの達人とはいえない人たちです。自我が強いとはいえず,ごまかしが利かない人が心の病に陥る危険があるといえると思います。
心が病んでいるとき,必ず自我が機能不全に陥っています。両者はほとんど同義語です。これといった外部的な理由が見当たらず,いわば平地で遭難してしまったかのように発病する場合,自我が自己欺瞞に陥って見るべきものを見ようとしないか,衰弱した別種の様態に陥っているかということになると思います。それとの相対関係で,勢力を強めている無意識界の分身(影と呼ばれるものです)たちによって,機能不全化して無気力になっている自我が実質的に支配されるのです。
健康な精神では,自我が常に主導力を保持しています。悪を働く心は悪人にだけあるのではありません。人間であればだれにでもないわけがありません。悪人と善人とを分けるのは,前者の自我が無意識界にある悪なる影の支配を受けているのに対して,後者の自我は影の上位者であることができていることの違いです。
PTSDといわれる心の病気の場合は,事件として扱われるほどの外的できごとの下で,平均的な強さを持つ自我が機能不全化する心的病理現象です。この場合は大方の人の理解と同情が容易に得られます。この場合も機能不全に陥っている自我との相対関係で,無意識の心が荒れるのです。自我にとっては外的な負荷という前門の虎と,荒れる無意識という後門の狼とに対処が迫られるという事態です。
このように心を病むにいたった人の自我の機能が,自然に回復することも稀にはあるでしょうが,それはかなり難しいことです。ですから一般には,心理治療が必要になりますが,心理的な治療者は,心を病んでいる人の自我がひとり立ちできるほどに回復するまでのあいだの,指導的な伴侶ということになります。
心をいったん病んだ人に,ペルソナ,ないしは自我の強化策を勧めるのが,いうならば認知療法といわれているものです。これに対して自我の機能の不全化に伴って勢いを強めている無意識界の影たちを扱い,影たちの存在を捉え,そのいい分に耳を傾け,いずれはそれらを意識に統合する(影たちを救い出すといっていいでしょう)作業の試みが,精神分析的なアプローチということになります。この試みも自我の仕事ですから,治療者に支えられつつ,機能不全に陥っている自我の強化が図られることになるといえます。認知療法が自我の強化を目指すことによって,無意識の世界のものを相対的に改変させる試みといえるのに対して,分析的な試みは直接無意識を操作することによって,自我の姿勢の本来化を目指すということもできると思います。
繰り返しになりますが,心の病理的な現象は,幼児心性が意識の表舞台に顔を出している側面が色濃くあるといえます。自我を支配するほどの勢力を失うことなく,病理的な意味を持つほどのものである幼児心性が認められる背景には,原初の他者である母親との関係がからんでいる可能性が高いのです。そしてそれが自我の自律性を混乱させ,劣等化させるという連鎖があります。
これらの一連の病理的な連鎖の淵源にあるのが見捨てられる恐怖です。
このように,日常にある対他心理の根本のところに潜んでいる見捨てられる恐怖と呼ばれる幼児心性が,どのように克服されていくかがそれぞれの自己の課題であり,克服の仕方がそれぞれの自己の性格の上に反映されていきます。その克服に向けた最初の努力目標は,まずは両親,なかんずく養育の中心である母親によって掲げられることになります。人間の集団の最小単位であり,人間関係の基本を修練する場所でもある家庭の中が,最初の重要な人生の演習と実践の舞台となります。ここでは指導者としての母親の能力,そして当然父親の能力とがまずは問われることになります。その指導能力は,結論的にいえば愛情と信頼との質にかかっているといえます。そしてそのことがいかに難問であるかということも,精神科の臨床という窓口に立てば痛感させられることです。愛情と信頼が誰が見ても欠落している家庭がたくさんあるわけではないと思います。むしろ傍目にはもちろん,当の両親と子供たちの多くでさえ,自分たち親子のあいだで本物の愛情と信頼とが機動しているか正確な認識を持つことが困難なのです。それは人の心がそれぞれの無意識の心の影響を強く受けるために,自分の認識力が歪曲されていても気がつかないか,気がつきたくないということが起こるからです。
煎じ詰めれば心の病は対人関係に行き着き,その原型は親子関係に行き着くといっても過言ではありません。ここに問題がなければ,機能的な精神障害の過半は問題化されることはないでしょう。
家庭という人生の最初の舞台の上で修練されるものの中で,最も重視されるべきものは他人の心が分かる心の育成ではないかと思います。しかしこれは大きな問題です。人の心が分かるということは,自分の心が分かるということであり,人間について,ひいては人生について分かるという広がり方をする性格のものでもあるように思われます。そうなるとそれが十分に出来ている人は,少ないどころではなくなります。無論,私自身もよく分かっていない一人です。問題が大きく,たいていの大人にも手に負えないほどのものであるので,たじろぎもしますが,しかしやはり子供の心の育成上,大切な問題です。
人の心は,ある意味では分かるわけがないものです。そして,ある意味では一挙に分かることができるものです。これらは互いに矛盾していますが,矛盾こそがこの問題の特質なのです。
それは自我の機構に拠っていると思われる,自己の構造に由来するのです。他者は犬や猫とおなじように,他なるものとして意識にとって外部に存在しています。赤ん坊が成長していく過程で,犬や猫をしだいに認識していきます。それらは物と違って動くもの,命があるものとして,生物体である自分との類縁性において理解をすすめていきます。そしてそれらが何を感じ,何を考えているのか,そういうことも理解できるようになっていきます。そしてそれらの理解や認識は,外部からの学習と研究によって獲得されるのです。それは人間の心と絶えず比較されながらの理解ということになるでしょう。人間の理解とは,人間的な理解以上ではあり得ないのです。
ところで他者はこれらの動物たちとは違った認識のされ方をします。
生まれたばかりの赤ん坊について,M.Sマーラーは,「乳児はあたかも自分と母親とが全能の組織(共通した境界を持つ二者単一体)であるかのように行動し,機能する。・・・母子単一体という共生球を形成している」と述べております。
このように生まれたばかりの赤ん坊は,原初の他者である母親を,他なるものとして捉えていないのです。この段階の赤ん坊の自我はまだ機能を開始しはじめたところで,いたって未熟で自律性がありません。ですから母親の自我に絶対的,全面的に依存しています。人間には,あるいは自我には,絶対とか全部という存在形態はなく,赤ん坊のこの段階での母親依存が特別の例外といえるでしょう。
対自意識と対他意識とが渾然として一体になっていると考えられる生まれたばかりの赤ん坊は,簡単にいうとすべてが主観的である世界の住人なのです。そうした状態にある意識の黎明期にあっては,赤ん坊は誇大感と万能感の中にあると考えられております。つまりあらゆることが可能な力を持っているという感覚的意識と,大きな力によって護られているという感覚的意識の中にいるということです。
それは赤ん坊が人間になる以前の存在形態を暗示しているようであり,自我に拠る人間存在への最初の移行を安全に遂行させる役目を持つものであると思われます。
生まれたばかりの赤ん坊は,自然の中にまだまどろんでいるかのように思われますが,意識活動が開始される以前の沈黙の様相がうかがえます。そして沈黙は自然の特性の一つです。自然の特性は全ないしは完全というふうに考えられます。そして人間は,というよりは自我の能力はいうまでもなく不完全です。
人間は自我に拠る存在です。その活動がまだ不十分な意識の黎明期にある赤ん坊の自我機能は,母子一体の機能的な空間の中で,すべてが可能であるという幻想の中に保護されているようです。そして,また,その自我機能は,完全なもので護られているという幻想の中にもあるようです。つまり自我機能の能動性と受動性とがもろともに完全であるという幻想の中に,赤ん坊はまどろんでいるだろうと想像されます。しかしそれらは分離しており,従ってそのどちらもが不完全であるという不安があればこその誇大感と万能感の共存であるといえると思います。かつ,その存在形態は自然にかぎりなく近く,しかし自然から決定的に分離しているのです。つまり未成熟とはいえ自我の機能は最初の活動を開始しているのす。ということは自我の活動によって光(生)を意識し,従って闇(死)を感覚的に意識しないわけにはいかないはずなのです。
マーラーによれば,生後3ヶ月までの赤ん坊は,「正常な自閉」の中にあります。それはフロイトの,「閉じられた精神体系の見事な例としての鳥の卵」に相応するものです。その状態にある赤ん坊は,「刺激防衛壁に護られて外部刺激に対して反応しない」のです。そのように胎児期に近い状態で,過度な刺激から,活動を開始したばかりの未熟な自我の機構を護っているのです。
もっとも自我心理学の立場に立つマーラーのこの見解に対して,D.Nスターンが独自の乳児観察の経験に基づき,根本から否定的な見解を述べています。マーラーが,生後間もなくのあいだは,刺激防護壁に守られながら恒常的な平衡状態を維持する生物学的過程が優勢であると述べたのに対して,スターンは母子相互の関係性を無視してはならないという趣旨のことを主張しています。この対立は,本家フロイトに端を発する古典的精神分析を受け継ぐ自我心理学と,コフート以降の自我心理学への異議申し立ての一連の流れとの対立に伴うものです。
自我心理学の立場は,他なるもの,外なるものとの関係を考慮することなく,専ら病者個人の内的空間のみに限局して,起こっている歪曲を問題化しようとします。分析者は,自身をまったくの客観的立場に位置させ,あたかも外科医が外側から患部を調べ,病巣を摘出しようとするのに似て,治療者と病者との関係性は問題外なのです。これに対して,コフート以降の流れをくむスターン他の分析医たちは,それぞれ別個に存在する自己と自己とのあいだの関係性において問題を捉えようとします。
スターン他が主張する,関係性の視点で問題を捉えるべきであるというのは,改めて主張するのが奇妙に感じられるほどに当然のことと思われます。それはアメリカの地に根をおろした古典的精神分析の発展の歴史が,いかに重たいものであったかということの裏返しになるのでしょう。いまや教条主義に陥っているというしかないものに対する挑戦が,コフートの勇気と決断によって口火が切られたという形になっているのです。
スターンの主張によれば,生まれたての赤ん坊が専ら生物学的な過程の中にいるわけではないということですが,とはいえマーラーの観察が無意味だったということにはならないと思います。そこで観察されていることの理解と解釈の立場の相違はあるでしょうし,スターンの主張にその意味では分があるように思われますが,赤ん坊が生物学的な保護を必要としていることに異議を申し立てる根拠はあまりないようにも思われます。
スターンがいうように,生後間もなくから母子相互の関係で何かの感覚的意識のうごめきがあるとしてもまったく不思議はないでしょうし,大いにありそうなことです。であればこそ,赤ん坊の感覚的な意識は大きな脅威の中にあると考えないわけにはいかないのです。何らかの意識が活動するということは,繰り返しになりますが,闇の圧倒的な脅威を意識しないではすまないはずのものです。その脅威に対抗するために,赤ん坊の自我は,母親の自我とほとんど一体化するほどに密着している生物学的な理由を必要としていると思います。つまり生まれたての赤ん坊の自我は,母親の自我の中にまどろむように一体化して守られているのでなければ,無化する闇の脅威の前にひとたまりもなく粉砕されてしまうだろうと想像されるのです。
人間は人間以前の全なるものから,自我に拠る存在として生誕することに伴って,意識という光の世界と無意識という闇の世界に二分割された存在者であり,それら二つの存在形式のあいだに横たわる埋め得ない非連続的な深淵を,赤ん坊は前経験的な感覚的意識において通過しなければなりません。この経過の原初の存在形態として赤ん坊の自我は,他者なる母親の自我とほとんど渾然として一体であると考えるのが合理的であるだろうと思われます。
以上に述べたことによっても,自己は構造的に他者を内に含んでいると考えることができるのではないでしょうか。従って,他者は内なるものと外なるものとがあることになります。ここに犬や猫との関係と,人間相互の関係との存在形態が根本的に異なっている理由があります。
外部にある他者は,他性として結局は不可知の存在であり,しかし内なる他者との関連において一挙に会得されることが可能な存在でもあるという両面を持っているといえます。
そしてしだいに赤ん坊の自我が機能を進化させていく過程で,母親を他なるものとして認識することができていくのです。このことは,生まれたばかりの赤ん坊の自我が未熟すぎて,他なる存在である母親を他者として認識できないと考えることも可能だと思いますが,とはいえ,母親を自分の一部,内なるものとして捉えている事実を否定する理由にはなりません。赤ん坊の未熟な自我が,母親の自我をほとんど自分自身のものであるとする存在構造上の理由があって,はじめて母子一体の共生球が存在できると考えるのが合理的ではないでしょうか。それは赤ん坊の錯覚というようなものではなく,母親が内なる他者として自己と一体で区別がつかないところから,赤ん坊の自我の機能の進化に伴って,おもむろに外部にある他なる母親を認識的に捉えることができるようになっていくと考えられるのです。
犬や猫は学習と研究によって,いわば外部から認識できるのですが,他者についてはあらかじめ内的な会得があり,その投影が外部にある他者におよぶので,あらゆる存在者の中でも,他者は特別に親和的な存在であるといえます。外部にある他者は,外的な自己でもあるのです。
見捨てられる恐怖が根源的な意味を持つ理由は,以上のような人間に宿命づけられている存在構造にあると思います。
つまり自然の一部であったものが,どういう理由によってかあるとき自然から乖離され,自我に拠る特殊な存在として人間の生誕があったと考えるのは,なんら突飛なことではないと思います。人間以前の存在形態が何であるかは不可知ですが,不可知であることが,既に人間の知性,認識力を超越したものの存在を指し示しているのです。そのような超越的な存在をどのように命名するかは個々によるでしょうが,ここではそれを自然と呼んでおきたいと思います。
自然の特性は,一つには全または無といえます。これは矛盾したいい方のようですが,自我の能力が有限であることからくる必然です。全も無も,自我が捉え得ないものです。自我はかぎりなく全を目指すが全にいたることはなく,究極において自我の消滅という無に帰するのです。
人間の精神の内部にある自然が無意識の領域です。その領域には自我の光は限定的にしか届きません。そして人間を人間たらしめている自我は,無意識の世界,無意識の力とのあいだに有機的な関連を持っています。いうならば内なる自然である無意識の力を拠り所とする自我は,無意識の意向を受けているはずです。しかし無意識の意向をそのまま実践するだけのものであるのなら,あえて自我が存在する意味があるとは考えられません。自我は無意識に拠りつつ,無意識から独立したものでもあると考えるのが妥当だろうと思います。
自我の無意識との関係でのそのような依存性と独立性が,人の一生を,個々に大きく分ける理由だろうと考えられます。
いわゆる自己実現とか真の自己と呼ばれる人生行路をたどる人は,特別に恵まれたたくましい自我の持ち主ということになると思いますが,彼らの自我は,自然に通じる無意識の力の意向に忠実に即して人生の舵取りをすることができるのだろうと思います。
そして大方の人間の自我は,広大無辺である上にしばしば荒れ狂う海を,いわば自力で小舟を操って航海し通す自信と勇気とを持てません。危険に満ちた,なにが起こるか分からない人生という海路を,人と助け合って航海するにしくはないのです。
無意識という自然から独立しているものでもある自我の能力の寄る辺なさが,特別に親和的な関係にあるもの,他者の存在を必要とし,事実,他者を自己の構造の内に含み,’全’の性格に一歩近づいた存在形態となっています。そうすることで,恐ろしい孤独を慰めることが可能となっていると考えることができるように思います。
しかし一方で他者は外なるものです。他者とのあいだの親和性は,単に有力な可能性にとどまります。他者は頼りになりますが,人間の常として絶対の保証はありません。それは自我に拠る人間の宿命です。
赤ん坊のとりわけ寄る辺のない自我は,寄る辺がないだけに貪欲に安心と安全の保証を要求します。それに母親がどう応えるかが,いわば赤ん坊の一生の命運を担っています。赤ん坊は内なる母親との一体感の中にあり,それを拠り所にして万能感と誇大感が存在しているのだろうと考えられます。これら二つの誇大な感情は,赤ん坊が自我を付与される以前の全である自然に匹敵する代理的な防具としての意味があると思います。その幻想的な感情は生得的なものに基づくものに違いありません。そしてその原基の所在は,赤ん坊の自我の機構以外には考えられないと思います。いうならば赤ん坊を,自然のものから自我に拠る人間存在へと,ソフトランディングさせるための装置として原基があるのだろうと想像されます。
しかしながら先ほど述べたことと関連しますが,内なる母親との一体感の中にある赤ん坊といえども,母親の他性は感覚的意識に映じないわけにはいかないだろうと思います。内なる母親との関係で成立している全を要求する赤ん坊の貪欲さに,他なるものである母親が応えることができる能力は,いうまでもなく限定的です。自然の中にまどろむようにして存在していた赤ん坊の全的な安心と満足への期待と要求と,現実の母親の能力とのあいだには,埋めきれない深淵があるのです。この深淵は無を予感させます。これが見捨てられる恐怖が存在する根源的理由であり,人間には等しく避け難いものである理由です。この恐怖の深淵性が,あるとき母親の表情に投影されて映し出される瞬間がいくらでもあるだろうと思います。そういうときの母親体験は,母親が冷酷な他人に匹敵するほど遠方に感じられ,無の深淵の渦中にただ一人取り残された恐怖を感じる体験でもあるのではないかと想像されます。母親との関係でのその種の恐怖体験は,一種の外傷体験として刻印されることでしょう。それはさまざまな程度で,おそらくはすべての赤ん坊が体験するに違いないと思われます。
成人してからの病理性である完全癖,’全か無か思考’の心的傾向は,この幼児心性が克服されず,自我を支配し脅かしている様相です。人間の人間らしいところは,ほどほどの満足で自足することです。それをもたらすためには,先にも述べたように母親が一貫した愛情で応える必要があります。赤ん坊が求める,不安と恐怖と怒りに裏打ちされた全的な安心と満足への要求に対して,母親にできることはこの程度のことでしかないということを,精一杯,身をもって教えることが必要です。全的な要求をする赤ん坊は,しばしば不満と怒りで一杯になることでしょう。しかしやがては一貫した愛情を示す母親に,感謝の感情を持つようになります。それは現実を認め,受け入れる気になったということです。全的な安心と満足を要求する心から,現実的なほどほどの安心と満足で我慢する心に移行することで,母親との関係が落ち着くことができるのです。母親としては首尾一貫した愛情を,精一杯示してあげるのが,真の愛情ということになります。
母親の気分が不安定であったり,病気で入院するなどして愛情の剥奪,中断があったりすると,赤ん坊は大いに混乱するでしょう。幻想的な主観世界の中にある赤ん坊は,当然のこととして客観的にできごとを捉えることができません。混乱させられ,不安と恐怖とを鎮めてもらえない心的環境にあっては,いつまでも全的な安心と満足とをもとめつづけることになるのです。そういう折に強く叱られるなどすると,赤ん坊によっては更なる恐怖で沈黙するでしょう。そのときもとめつづけていた全的な要求は引っ込められますが,それは母親の怒りを恐れての非常手段であり,問題が解決したわけでは勿論ありません。問題は自我によって抑圧,封印されて,意識下で幼児心性としてのエネルギーをいつまでも温存されることになります。この抑圧する自我は,怖い親の自我に密着して傀儡化すると共に,自己の自然な欲求を不当に扱ったことになります。親との関係において無力であるしかなかった自我は,恐怖をもたらした親に怒りを向けることができません。
心的なエネルギーは大きく分けて,生の方向に作動するか,死の方向に作動するかだと思われます。自我が主導的に機能しているかぎり,エネルギーは原則的に前者のものであり,機能不全化すると後者のものになると思います。そして後者のそれは,怒りの形で表われます。幼い子が親に恐怖をいだいたために満足をもとめる欲求を抑圧するとき,自我が主導する力を示せなかったことになります。主体性を欠いた自我は親の自我の支配を受けて傀儡化してしまいます。その自我によって,親に向けられるはずであった怒りが抑圧されます。満足を求める欲求は,本来は自然のものとして自我によって受け入れられ,生の方向に自己を発展させていくものであり,かつ発展させていく力を増強するはずのものです。それができるためには,自我が親のしたことへの反応として生じた適応的な怒りの正当性を認め,自我の主導の下で親に対してアピールをする必要があります。ところが生へのエネルギーが,やむを得ずとはいえ自我によって阻まれ,そぎ落とされることになるときは,親に向けられて然るべきであった怒りもまた,自我によって抑圧されることになります。生の世界に羽ばたくはずであったそれらのエネルギーは,一転して心の闇に内向して怒りのエネルギーに姿を換えるのです。このときの怒りは,最初に親に対して向けられるべきであった適応的な怒りとは違う性格を持ちます。それは生の世界の開拓者である自我に対して,自己の中の異分子となった抑圧された分身たちと共に異議申し立てをし,やがては自我の世界の破壊者になる可能性を持っています。自我は不自然な,無理のある解決策を講じてしまったことになります。それに伴ってエネルギー論的にも自我は弱く,抑圧を蒙っている分身たちは強い負のエネルギーを抱え持つという歪んだ配分となります。そして歪んだ自己の構造に基づく圧力を,たえず無意識から受けることになる弱い自我は,ますます親の自我の傀儡でありつづけることで機能を守るしかなくなるのです。こういう自己の構造の下にある自我は,親の自我の支えを失うと無意識の圧力に抗し切れない不安を強く持つことになります。
H.コフートが次のように述べております。
・・・女性性器を目にした少年が見せる戦慄は,体験全体のうちで最も深い層ではない。その背後に,それに隠されてさらに深く,もっと恐ろしい体験が横たわっている。それは顔のない母親の体験,我が子を見てもその顔の輝くことがない母親を体験することである・・・。
生まれて早々に,あるいは生まれて早々であるからこそ,このように激しい他者への恐怖と不信との基になりかねない過酷な体験を強いられる赤ん坊を,両親,なかんずく母親は,人の心が分かる子供に躾けていかなければならないのです。それは何といっても,原初の他者である母親自身とのあいだで,根源的であるこの恐怖を癒していく心の交流がもとめられるのです。その決め手は母親の愛情と信頼が,真正のものにどれだけ近いかということです。いわばごまかしの愛情,愛情に似た母親の欲求充足などは,赤ん坊には通じないと考えるべきです。そのような偽りの愛情は,母親には理解できない形で赤ん坊の心をいびつにさせてしまうと考えなければなりません。赤ん坊も,成人となってからも,自分にそういう問題が起こっているという認識を持てません。たとえていえば,気がつかないうちに何らかの被害にあい,しかし実際にはその事実は知らないままでいるのにいくらか似ているかもしれません。これらのことについては,母親自身がその母親からどの程度質の良い愛情を注がれていたかに,かなりの程度左右されることになると思います。そういう前提の上に立って,いずれにせよ母親自身が自我の姿勢を好ましく整えていなければ,母親の自我は無意識の潜勢力の悪しき影響を受けることになるのは必至で,それが育児に反映されるのも避け難いでしょう。よい母親であろうと知性的にいくら注意を払っても,盲点はできてしまうと思います。
賢い母親とは知性的に高い人ということではなく,赤ん坊という自然のものであるが故に無垢である存在者に,母親自身も母性の自然の発露で応じることができている人ということになるのではないでしょうか。そういう母親であれば,赤ん坊と一体となって自然的な心の充足感の中にいると感得し,至福の感情にひたることがことができるのだろうと思われます。それは母親にだけ与えられた特権です。そういう役割と立場を与えられていることを喜べる母親は,賢いという名に値するのではないでしょうか。
母親である人が母性的でないことは不幸なことです。神経症に類する心の不自然化の表れであると考えることもできます。しかし他人がとやかくいうことではないかもしれませんし,人がさまざまに神経症的であるといわれていることでもあり,何も母性だけが問題でないのも確かです。
しかしながらここでのテーマは,性格の形成の基盤に当たる乳児期の問題に関してです。赤ん坊の命運を母親が担っているというのは,大げさないい方ではないと思います。問題の性格から母親の責任論という側面があり,母親によっては不愉快かもしれません。しかしそのことは,見方と受け取り方を少し変えれば,母親が赤ん坊にとって余人には変えがたい,唯一最大の拠り所であるという名誉ある問題についての議論です。一人の人生を左右するほどに大きな役割を与えられた立場に置かれて,それを誇りと感じない精神は貧困であり,不幸です。そしてそれは母性の欠落を即座に意味するものです。ですからこのテーマは母親の仕合せ論でもあると思います。人の問題について,特に不幸かどうかについて,他人がいうことではないのも確かですが,そういう客観的な性格を持っています。また母性に関しては母親個人の問題にはとどまらないことなので,別格なものとして議論されてしかるべきです。ともあれ大きな役割を与えられるときに,それを名誉であり,誇りであると捉える精神は豊穣であるといえます。しかし物事にはすべて裏と面があるように,母親が余人には味わえない豊穣と至福の感情を持つことができる立場にあるということは,逆に一転してストレスと被害感の源泉にもなる可能性があるということになるでしょう。母親が子供に対して愛情の名を借りて過干渉になるのは,後者の精神においてです。
それにしても人の心を知るというのは大きなことです。生易しいことではないと思います。そしてそれは,自分自身の心をどのくらい深く知ることができているかということと,パラレルな関係にあると思います。自己を知ることは,他者を知ることであり,人との関係性を知ることです。それはそれぞれの自己の世界を知ることであり,ひいては人生や人間についての理解を深めていくということでもあると思います。
汝の敵を愛せという言葉があります。この言葉の内に含まれている精神は上質すぎて,大方の人の笑いものになりかねないほどのものです。だれにもそんなことが出来るわけがない,言葉だけだ,偽善者のたわ言だということになりかねない言葉です。
端的に,「あなたの子供が殺されたとして,犯人を愛せますか」という反問があるときに,「愛せます」という心境になるのはほとんど困難です。偽善的な響きになりそうなそういうことより,「犯人を殺したいと思うかもしれない」と感情を表す方が共感を呼ぶのかもしれません。
問題は理念と実際との違いということだと思います。’汝の敵を愛する’精神は理念です。その極致にまで到達するのはおそらく困難でしょうが,実践が困難なほどのものでなければ理念にはなりません。
理念は自我がおのれに課す,到達されることのない到達目標です。理念は,自我がそれに向けて現実的な行為を編み出す力をもたらします。ですから理念は自我に内在するものではなく,自我を超越するものです。従ってそれは無意識に係属するものであり,自我がそれによって啓発されおのれに課したものという正確を持っています。理念はいわば自我に提示された光であり,その光の照射を受けて,自我が心の内外の暗部をあからさまにしていく力を得るのです。
人に向かってこれ見よがしにする’善行’の実践はいただけません。それはほとんど愚行です。人から揶揄され,謗られても仕方がないでしょう。しかし’汝の敵をどこまで愛せるか’と密かに自己に沈潜する精神は,理念によって照らし出されるものに向けて,可能なかぎり自分の暗部を探り,最奥にまで至ろうとする行為を導きます。その沈潜する行為の過程で,他者への激しい怒り,憎しみに遭遇するかもしれません。というより遭遇しないわけがありません。心の内部の闇の帝王の手先である怒りに遭遇したとき,自我がそれをどう受け止めるかは,自我の器の大きさが試される正念場です。早々に蓋をして退散しなければ,自我が粉砕されかねないほどのものであるかもしれません。怒りは弱気の自我にとっては,自我が演出者として構築する,自己の世界を世界たらしめている心の内外の諸対象との関係を破壊しかねない,悪なるものです。しかし立ち向かい,受け止める自我にとっては,怒り,憎しみは,もはや闇の帝王の手先ではありません。闇の帝王として自我を脅かすかぎりは悪として潜行するものですが,自我の手の中にあり,既に光の中に取り出されたそれは,善に衣替えしたのも同然のものです。
怒り,憎しみの力を恐れ,自我がそれによって支配されているとき,それらの感情は自我を傀儡化して悪性の働きをします。心の外にあっては他人に対してさまざまな形態の悪を働きますし,内にあっては健康をさまざまに害します。しかし自我が怒りの上位に立ち,それを従えているとき,怒りは悪の牙を抜かれたも同然です。場合によっては人に向けて怒りを露わにすることもあるでしょうが,それは防衛的,適応的な怒りで,自我が怒りを利用したことになり,つまりは自我に主体性があるのです。
自分を深く知るということは,自分の暗部にある悪をより深く知ることです。自分の内部の悪をおそれず捉えたとき,悪は既に悪ではありません。もっとも,それで心の深部に潜む悪の全貌を捉えたことにはなりません。人が善であろうとすること,自己自身であろうとすることを心がけるかぎりは,その前進を阻む力である悪は立ちはだかりつづけるでしょう。つまり悪の存在がなければ善もないのです。
自我が下位にあるものを捉えることは,常に可能です。捉えたかぎりで自我は上位に立ちます。まだ正体のはっきりしない怒りについては,自我は上位にはありません。それを意識し,捉えようという意志があれば,少なくても自我は下位にはありませんが,その意欲を失くしている自我は,本来は下位のものとしなければならないものの下位につくことになります。そのような状況にある怒りは悪の性格を持ちます。これは病理的な心的状況といえます。
怒りは悪の手先です。自我は怒りと,怒りをもたらしたものを捉えてその上位に立たなければなりません。それをあきらめて自我が怒りの下位に甘んじるとき,怒りの根源にあり悪の支配下に置かれます。悪は闇の帝王であり,自我の姿勢によっては自我の世界の破壊,回収を使命とするものであるように思われます。
自我はより上位にあるものは捉えることができません。怒りは自我がその上位に立たなければならないものですが,怒りの根源(悪)は捉えることができません。つまり怒りは必ず無意識の中に存在し,悪性のものとなる可能性を持っています。そしてそれらの根源となっている悪そのものにまでは,自我の追求が及ぶことができません。従って根源にある悪は上位に立つものです。そしてそれは善と区別がつかないものでもあると思います。つまり自我の上位者は一つであり,自我の姿勢によって悪が現前化するのでしょう。悪の尻尾を捕らえようと極限まで追求することができるとすれば,そこには善と区別がつかないものの存在があったということになりそうです。つまり善と悪は二律背反の関係にあるのだと思います。
以上のように自己に沈潜する行為を揶揄したり,非難したりする者はないはずです。第一,最初から他人の眼は問題外なのです。自己自身との関係で悪は真に問題とされることが可能であり,’汝の敵を愛せ’という設問が意味を持つのです。ですから悪をなす者は,自分の悪を知らない者のすることです。あるいは自我が悪によって支配しつくされた者のすることです。「俺は悪人だ,それがどうした」と,そのとき彼らはいうでしょう。
パニック障害を病むある女性が,次の内容の夢を報告してくれました。
どこかのホテルのロビーにいる。私がパニック障害で悩んでいるのを知っているらしい女性が,それを治す方法を教えてくれるという。別室に連れて行かれ,しつらえてある仏像に向かって鈴を振れば治るという。鈴を振ると,脇のところから大きな身体の相撲取りが出てきて,私の方に向かってくる。その眼がとてもこわい。たちまち投げ飛ばされる・・・。
そして,「私を案内していた女性に,力士の身体を押さないといけないといわれていたように思う」という補足がありました。しかし相手が大きすぎて押すどころではありません。
彼女は薬の助けもあって,症状的なものは一応は収まっています。しかし薬に頼っているかぎりは,ふつうの人ではない,と感じています。はたして薬をやめることができるのかという不安もあります。占いや祈祷の類に関心を持っている彼女は,魔術的に治ることはできないかというほのかな希望を持ってもいるようです。
夢に現れた巨大な身体と力を持つ力士は,彼女のパニック障害をもたらしている何ものかのようです。
夢によるかぎり,たちどころに投げ飛ばされる無力な彼女の自我が,巨大な怒りでもあり,彼女にとっての悪でもあるらしい力士に対抗する力を持つのは,現時点では到底無理なようです。一見すると案内した女性は,彼女をだましたことになります。何か悪辣な意図をいだいて彼女に接近したように見えます。これは夢の特性のようです。つまり立ち向かう意志を持っていない自我に対しては,このようにいいかげんなことをいってあしらうのです。しかし,夢の意図はそれにとどまらないものがあります。この夢では,夢を見ている主人公に,その夢舞台に現れた女性が,「力士の身体を押しなさい」といっているようです。つまり自我が対抗するようにといっているのです。ところが端からそんな力が自分にあるとは信じていない本人は,祈祷によるマジックを期待するしかない気分なのかと思われます。そういう意味合いでいえば,案内した女性はいい加減なことをいっていることになります。
この場合,本人の自我は自分の問題と対決する勇気も意志もないかぎり,夢舞台の女性は,本人にとっての悪の手先であるらしい力士と一連の者であるようです。しかし本人が夢の意味するところに気がついて,力士と対決する姿勢を見せれば,一転して夢の舞台の演出者の真の意図が汲み取れるのです。そのように自分の問題と正対しようとする自我に対しては,演出者が差し向けた女性は悪の手先ではなく,問題を解決する方法を教えようとするものの使いということになります。つまり夢の演出者は本人にとって善をほどこすものでもあり,悪をなすものでもあり,それは自我の姿勢によって変わるということになります。
この女性の母親は,結婚したときから夫の実家に住み,気難しい舅,姑に黙々と仕えてきました。夫は自分の両親に頭が上がらない人で,妻の苦労を見てみぬふりをしていたようです。そして夫自身が妻に依存的な性格です。母親の辛そうな顔をいつも見ながら女性は成長しました。祖父母や父親には,強い不快感を持っています。外出しようとすると後ろから黙って見ている視線をしばしば感じ,気味の悪い思いをしてきました。このごろでこそ,「何か,用?」と怒りを表すことができますが,最近まで何もいえずにいたのです。
女性の夢に現れた力士は,祖父母,父親,母親などとの関係があるようです。
案内した女性が,「力士を押すように」ということに促されて夢のイメージを見据えると,それらの家族の人たちとの関係が表われてくるかもしれません。夢のイメージを解剖してそれらの人たちを客観的に捉えることができれば,彼らに対して嫌悪感はあるかもしれませんが,もはや恐れるに足らないものになるでしょう。そうして見ると,彼女の夢に現れた力士の恐ろしげなイメージは,彼女の感情の彩色によるものが大きかったということになると思います。人が恐怖するイメージを持つときは,大いに主観的になっているものです。
夢は多重構造になっていて,一見すると卑近な日常の些事が現れているのに過ぎないように見えても,掘り下げていくと日常の意識のおよばない叡智が現れてくることがあります。夢というイメージは,現実の世界にあるものから無意識の深部にあるものにまでおよぶ広がりを持ちます。
童話には元型的なものが表われているといわれますが,「眠れる森の美女」というドラマは童話をもとにして創られています。このドラマでは王子が,悪魔によって100年の眠りに就かされているお姫様を救い出すことになっています。その過程では悪魔の手先と戦わなければなりません。このドラマを夢の舞台に置き換えると,王子は夢を見ている神経症的な苦悩を持つ本人の自我であり,それを癒すためには無意識下に我知らず追いやってしまった命の源泉であるお姫様を救い出さなければなりません。お姫様は心に生気をもたらす力です。そのお姫様を100年の眠りに就かせてしまったのは,王子自身の臆病だったでしょう。悪魔の存在を忘れてしまった父王の臆病が悪魔を怒らせたということになっていますが,王子にはその父王との関係でそれと類似の臆病があったために,かけがえのないお姫様を失ってしまったのです。王子である自我は,発奮して死を恐れずに悪魔と戦う気構えを見せました。その勇気があるかぎり勝利は王子のものです。王子は次々と繰り出してくる悪魔の手先を撃退し,最後には悪魔自身と戦い勝利を収めます。
自我の臆病は,してはならない抑圧をして無意識下に分身たちをとじこめます。それら分身たちは自我の価値規範に合わないということですから,自我に敵対するもの,つまり怒りと一体となった悪という性格を帯びることになります。ドラマではかけがえのないお姫様を意識の地下に幽閉してしまいました。悪魔とその手先たちは,お姫さまの怒りと悲しみとを受けて自我に敵対するのです。自我は不始末をしてしまった理由である不安や恐怖に改めて立ち向かわなければなりません。その不安は,基本的には母親や父親との関係で生じてくるものでしょう。そういう不安に負けてかけがえのないお姫様を抑圧してしまったのです。
王子である自我に起死回生の勇気を与えたのは,イメージの際深奥にある内在する主体です。先の女性の夢で,女性にパニック障害の治し方を教えようとした女性は,もしかするとこの主体に使わされた者かもしれません。彼女が王子のような勇気を持てば,悪である力士と戦って勝利することができるでしょう。
イメージの最深奥には,このように,自我の世界の歪みをただしたり,指針を与えたり,叡智を示したりという可能性をたたえて自我の様子を見守っている,無意識の世界の王である主体の存在があると思われるのです。
Sさんは,他人との意志の疎通がしばしばうまくいかない悩みを持っています。彼女は母親に大変依存的です。母親が少しでも自分が望んでいるような対応をしていないと感じると,大いに感情が乱れます。
彼女は,「関係のあるあらゆる人を大事に思っており,そのように対している」と自分では信じています。
しかし彼女は,家族や他人の言葉や態度を受け止めることがしばしばできないのです。自分が望んでいるような反応がないと,「どうして!」と動揺します。「私がよかれと思って出来る限りのことをしてきたのに,どうしてなの?」と思うばかりです。
この心を要約すると,私はあなたが大事なので,しかじかの努力をしてきました,ですからあなたも私を同等に大事に扱ってくださいということになるかと思います。この姿勢は相手側から見ると,私を大事にしてくださいというところに主眼があり,その心が満たされないかぎり不満を持たれることになります。そんな不満を持つのなら,あなたに気を使ってもらう必要がありませんということになりがちで,相手が去っていく十分な理由になり得ます。事実,友人たちが次々と去っていくのです。彼女にはその理由が分からず,不安が募ります。去って行った友人たちは,彼女の気遣いをむしろ要求がましく,自分本位と取っていることになるのでしょう。そういうことでは人との関係を大事にしていることにはならないのですが,その分,その理由が分からない彼女の心には大きな盲点があることになります。
子供は親の助けを必要とします。基本的に親の支持があって安心できます。大人は,大人といえる心は,自分を支える力は基本的に自分自身であるのが前提です。そういう意味での大人でない人は,一般的にいって少なくないように思います。Sさんも,本当の意味で自分を助けることができるのは自分自身でしかないということが理解できません。「私はとても寂しく,一人で居られる人間ではありません,だから分かってください,私を助けてください・・・」という心が切実すぎて,他人のことが念頭になくなるのです。一人ではいられないほどに孤独感と寂しさが強い彼女は,人の心が分からなくなるのはもとより,被害的な気分にすらとらわれがちになります。それはほとんど幼い子供の心です。安心と満足の全的な要求を持つ赤ん坊の心性が,そっくり残っているといえるようです。無意識下に強く布置していると思われるその幼児心性のほかに,見捨てられる恐怖もそれと並存していると考えられます。彼女の自我はそれらの力に支配され,自我としての自律性,主体性がほとんど奪われているのです。そのために人との関係を安定して保つ主体が不在であるに等しく,必死に人にしがみつこうとしては疎んじられることを繰り返しているように思われます。
幼児心性に支配されている彼女には,人から疎んじられ,陰口をたたかれる現実的な理由が皆目見当がつかず,しばしば死にたくなるほど落ち込みます。
では彼女はどうすればよいのでしょうか?
うつ状態に落ち込んでいる人に,私は,「私は元気になりたいの?と自問してみてください」と問いかけてみています。この問いかけは一見愚問です。元気でいたくない人があるはずがないと,誰もが思って当然です。通院するという行為は,元気になりたい心があってこそといえるでしょう。
しかし実際はそれほど単純ではありません。少なからぬ患者さんが,「そういわれてみると・・・」と首をかしげるのです。遷延しているうつ状態の患者さんには,決してこれが愚問でないことが珍しくありません。
この問いが意味を持つとすれば,それによって自我の自律機能が賦活され,活性化しはじめたときです。首をかしげるとき,自我はうなだえたまま立ち上がる力を感じていないことになると思います。自我の機能が途絶えたはずはないのですが,幼児心性が活性化してその支配を受けつづけている自我は,他の助けによってこれまで’元気でいれた’ために,苦境をはね返す力が自分自身の内部にあるとは信じられないでいるのです。他の圧倒的な助けがなければ立ち上がれないという気分は,幼児心性の支配を受けている姿そのものですが,そのことは自我が自律性を抑圧しつづけてきた性格形成のプロセスを物語っているのです。
発病という形で露呈した性格形成上の大きな問題に,自律性を欠いた自我は対処の仕様がないと感じているのだと思います。
繰り返し,「私は元気になりたいの?」と問いかけることによって,自我の自律性を鼓舞したいところですが,人生の重たい問題に押しつぶされそうになっているときに,自我の奮起よりはあきらめの方が先に立つことになりがちのように思います。
初診以来長期にわたってしまっているある主婦は,反復的に再発を繰り返しています。結果としての病状はうつ病の相ですが,根本の問題は,’自分の問題’として問題をとらえることができない性格的な特性が関与しています。再発すると常に焦っています。子供をせかし,家事に急き立てられる思いがし,病気を即座に治してほしいと焦ります。
通院をはじめて間もないころに,人の勧めもあって祈祷師にみてもらったことがあります。魔術的な解決を期待できないと分かっていながら,常に望んでいるところがあります。
この方の場合,「元気になりたいですか」という自問は,二重に意味をなしません。一つには「元気になりたい」と常に焦っているので,それはいうまでもなく,愚問です。一つには「治してほしい」という意識が強すぎるように,自分の問題としてとらえるという意味がどうしても理解できないのです。といっても知的な問題があるわけではありません。心の盲点がそうさせているのです。
彼女は自分の苦しみは親の悪影響の結果であると考え,恨んでいます。受容的な義母を頼りにし,常にそれと比較して実の両親に攻撃的な気分を持ち,実際に電話等で怒りをぶつけるのです。おそらくはこの被害的気分が,’自分の問題’としてとらえることを阻んでいるのです。病状が悪化するといつもそうであるように,子供を急かし,時間に追われ,家事をふつうにやっていれば問題がないと分かっていながら気がかりで仕方がなく,結局は何もしないで寝てしまいます。そして自己嫌悪に陥ります。
「治してほしい」という被害者心理をはらんだ要求的な気分は,大人の心性とはいえません。自我の力の一つが受け止めることであり,責任を持つことです。病的になったときに,そういうものが影を潜め,幼児心性が自我を支配するようです。
治療者に治してほしいという希望があるのは当然のこととして,患者さん本人の中に治りたい意志がなければ心理的な治療は空転します。もっとも幸いにして薬が奏効してくれれば話は少々別になりますが。
ユング派の論客であるJ.ヒルマんは次のような意味のことを述べています。
「治療者と病者との双方の心の無意識層に,癒す心と病む心とがある。治療者は自分の心に潜む病む心によって病者の心を共感的に理解することができ,病者は自分の中にある癒す心で癒し手である治療者に反応する・・・この無意識にある病む心と癒す心とは元型である・・・」
元型とは生得的なものであり,個人的に経験によって体得したものではないというような意味です。
いま述べた,「元気になりたいですか?」という質問に対して,「そういわれてみると疑問がある」とする場合,遷延しているうつ状態の患者さんには重要な意味が含まれているのです。つまり,「元気になりたい」ということの中には,いま述べたように,患者さんの無意識にある癒されたい心がある程度は活性化されていることになり,自分を助ける意志があるという意味が含まれているのです。そういう意志があれば,治療者との協力関係がより進展するはずですし,日常の生活の中の工夫や,考え方の転換などの対策も心に浮上してくる下地ができていると考えてよいと思います。
もっともそうした意志がしっかりしていれば健常の心であるわけで,何らかの程度にその意志が薄弱化しているのも明白ではあると思います。その薄弱な意志を掘り起こし,励ますことが大切なのだと思います。
私は,「仮に,そうは思わないという反応が心内から返ってくるようであれば,いまの状態はつづくと思ってください」ということにしています。そのように伝えて,「突き放された」と感じる人はいないようです。
Sさんの場合も,「元気になりたいですか」という問いに,「私はよくなりたいと思っていないかもしれません」という返事が返ってきました。彼女の説明によれば,「よくなると心配してもらえなくなるから」ということでした。彼女の自我は,幼児のようにしがみつく自我なのです。無意識下に強力に布置していると考えられる見捨てられる恐怖に支配されて,自我はほとんど自由に活動できていないように思われます。人に見放されないようにとしがみつく自我は,この恐怖の虜になっているのです。
彼女が,「私は人の助けを当てにしすぎていたようだ」という反省をすることができるまでは,苦境から抜け出ることは難しいのではないでしょうか。現状の心理構造で’元気になる’というのは,彼女が望む通りに周囲の人たちが応えてくれるのでなければ難しいのです。そういうことは不可能です。
彼女が時間をかけてでも,ある意味であきらめて(ほどほどの満足を受け入れて),人を当てにすることの間違いに気づいたときに,自我の機能が動き出すことになると思います。心内の手ごわい恐怖が彼女の自我を圧倒しているあいだは,彼女は幼い社会人として社会恐怖の心を免れることができないでしょうが,恐怖をともかくも従えることができたときに,彼女は自己の回復と,社会人としての新たな出発がはじまることになります。
問題は受け止められたときに,解決への第一歩を踏み出したことになります。いわば人にしがみつく自我から,受け止める自我への変貌は,それだけで子供の心から大人のそれへと脱皮しはじめたことを意味します。受け止める自我は大人のものです。そしてしがみつく自我は子供のものです。
自我がそのように本来化して自律性を回復すれば,人の気持ちをも捉えることが可能になっていきます。いたずらに主観的に問題を捉えるのは,幼児の心の世界でのことです。大人の自律的な自我は,客観的に存在しているものとの関係が確かなものとしてあるのです。
人の心が分かるというのは,このように自己の世界の関係性が豊かに保たれているという総体的な枠組みの中にあるときに,自ずから可能になるといえるだろうと思います。それが可能であるためには,自我の力が十分に強いということが必要であり,かなりの程度素質が要求されるかもしれません。一般的には性格発達の早期に,乳児の自我を好ましく守り育てることで過重な負荷がかからないようにすることが望まれます。資質として強い自我であれば,負荷(主に母親の愛情提供に何らかの問題,歪みによって生じるものです)によって苦しみながらはね返すことも可能でしょうが,資質として弱い自我であれば負荷によって機能不全化します。いうならば前者の自我は鍛えられて更に強くなることも可能ですが,後者の自我はさまざまにつぶされてしまいます。
要するに一般論としては,両親が子供の心の自然な成長(それは親自身とは独立した個の確立を目指す心の成長ということになります)を望み,喜べるという意味で,真実の愛情と信頼とに値する育児姿勢の中から,子供の自我の歪みの少ない発達が得られるといえます。逆にいえば,子供の心の自然な成長を喜べない親が,さまざまに介入して子供の自我の自律性を混乱させるのです。
しかしながら穏やかに成長した自我は,無意識との相克に悩まされない分,おおむね日常の生活に満たされるので,創造的な大きな仕事をするには向いていないようです。
このあたりのことを比喩的に説明すると,以下のようになります。
人生を無意識という海の上を行く自我という小舟の船頭になぞらえると,次のようにいえるかと思います。
いわゆる健康な心の人の場合は,暗黙のうちにどことなく定められている海路の航海です。そこかしこに小舟の姿があり,みな一様におなじ方向に進んでいます。海はおおむねおだやかで,空はたいていは晴れています。ときに空模様が怪しくなると波が荒くなりますが,仲間のベテランの船頭が小舟の操り方を教えてくれるので安心していられます。
一方,混乱しがちな自我なる船頭に操られている小舟は,いわば安全海域を離れてしまった海路を進むのを余儀なくさせられます。そういう海路を選んだ理由は,海なる無意識にあります。無意識の力が,船頭に安全な海路を取ることを許さなかったのです。そのために船頭は,自分が船団を組むようにして航海する多くのものたちの仲間の異分子であると感じるのです。船団を組む者たちによって,その仲間になる資格がないと拒絶されているように感じられるのです。いつの間にかはぐれたしまった海路は,独自のものです。天候はおおむねわるく,海はしばしば荒れ出します。操船術を授けてくれる信頼できる人もありません。暗い空の下の,荒れる海の,どこへ向かおうとしているのかも分からない果てしない航海を,無事にしとおせる見通しを持てません。なんとか確保した入り江に避難したとしても,人生は航海です。ひと休みはいずれ航海に乗り出すためにのみ許されるのです。入り江でのひと休みは,それなりに安心で気楽ではあっても,多くの仲間たちからはぐれてしまった,それに匹敵する独自色を出すことは不可能だという船頭の気持ちは自分を助ける力を持てません。人とのあいだで信頼関係を築けなかったからには,自分で自分を助ける以外には道はないのですが。
本当は船団を組む者たちにとっても,どこへ向かおうとしているのかは謎なのです。それを考え出すと船団の一員であることが怪しくなるので,考えない方が身のためともいえます。ともかくも天気は晴朗で,波は静かで,仲間たちと共にある安心は保証されています。
一方,独自の海路を取らざるを得なかった人の中には,あえてその独自の人生を引き受けようとする人も出てきます。そういう人は,船団を組む人たちが難路にさしかかったときに相談するだれかがいるわけではないので,いわば自分自身に相談する以外にありません。自分で自分を助ける以外にありません。そういう力を発揮できた人は,いわば人生の開拓者としての立場に立ち,一種の英雄として船団を組む人たちに対しても指導的な立場に立つことになります。いうならば一旦は船団を組むものたちからはぐれ,改めてそこへ別格な形で回帰したことになります。
ボクサーはハングリーでないと強くなれないといいます。作家は日常に満足してしまうと作家である理由がなくなるといいます。そういえばドストエフスキーや太宰治は,いつも金に困り借金をしていたということです。
人間は自我に拠る存在として,最も特徴づけられています。自我は人生を切り開き,自己を形成していく上での拠り所です。自我は自己と人生の光の世界の演出者といえます。そしてそれは話の半分です。残りの半分は(半分以上です),自己と人生の闇の世界の話になります。闇は,無,沈黙,死に通じるものです。光の世界のものである自我ないしは意識の力がとうてい及ばない世界です。
人間は光を知ることになった者として,必然的に闇を意識する者となったということでもあるのです。闇がなければ光もないのです。闇は光を無化する力を持っています。自我が力強く機能しているかぎりは,自己と人生は自我のものですが,機能が不全化すると自己と人生に翳りがさしていきます。
人が自我に拠って光の世界を切り開くことができているかぎりにおいては,人生は喜びです。自己は誇りに値するものです。そして自我の衰弱に伴って光の世界が翳りはじめると,不安,暗鬱,無力などの重苦しい気分に傾き,それは闇の無化作用が意識に及んでいる証拠です。自我がなんとか力の回復をはかれないかぎり,自己と人生は絶望とあきらめの境地に追い込まれていきます。
それらの意味で人生は過酷です。生まれたばかりの赤ん坊は,自然のものから自我に拠る人間への移行形として,自然の特徴といえる全ないしは完全の様相に準じるものを身にまとっているかのようであり,その具体的な防具が誇大感と万能感といわれているものであるようです。赤ん坊は母親との共生関係(母親と共に「共生球」の中に自閉するが,母親を他として意識しない)を機軸にして,おもむろに自我の機能が活動していくことになりますが,しばらくのあいだは誇大感と万能感とで移行期の不安が生物学的に保護され,緩和されると考えられるのです。
赤ん坊の自我は未熟とはいえ光の世界のものです。その発光体の存在根拠であり,後見人でもある無意識は闇の世界のものです(意識の力がおよばないという意味です)。闇にすっかり捉えられると光のものである自我は消滅するように,闇には無化作用があります。生まれたばかりの赤ん坊の心もとない自我が闇を意識するときに(意識しないわけにはいかないはずです),その無化作用によって粉砕されかねないほどの怯えを持つと思われます。ですからとりわけ時間をかけて,慎重に馴化させる必要があるでしょう。しばらくのあいだは,生物学的な装置によって,本能のレベルで自分で自分を護らなければなりません。そしておもむろに母親の助けを借りて自我の活動がはじまっていくことになりますが,心の発達,成長の過程で,誇大感や万能感の基となる心の防護装置は取り除かれていかなければなりません。成人になってもそういう心理が色濃く残っていれば,明らかに病的です。
病的な心は空虚感や無価値感に悩まされますが,誇大と万能の幼児心性の支配を受けていると,怒りと羨望と被害者意識とに捉えられます。自分は誉められてしかるべきだという気分があり,一方ではそんな人間は一人も居ないという絶望感と被害感と怒り,憎しみを覚えるのです。
被害感,怒り,憎しみは,周囲の人たちが,自分の中にある誇大感を認めようとしない,するわけがないという感情と,それと関連しますが自分が賞賛に値する人間であることを認めようとしない,するわけがないという感情に端を発するものです。どことなくそれが満たされることを当てにする気分の中にいるために,あたかも周囲の者が当然のものを自分に与えてくれないという被害者意識になってしまうのです。
自我を支配するほどの勢力を持つ幼児心性は,病的な心の孵卵器なのです。それらは対人関係を損なうもとになるものです。
万能感に応える立場にあるのが母親です。母親に課せられている役割は,赤ん坊の欲求の高さと母親が現実に応えることができる能力とのあいだの落差を埋めることです。赤ん坊が母親の助けによって,誇大感と万能感とを要求することが現実的でないことを体得し,それらの旗を撤去する気になったときに,一定の安心感と共に母親の現実的な愛情を受け止め,感謝する心が形成されていきます。それは母性が十分に機能したことを意味します。しかし貪欲な要求をする赤ん坊に対応しようとする代わりに,母親が自分の都合に赤ん坊を従わせようとするときに,赤ん坊の自我の形成は危機的な状況に置かれることになります。
このような意味で赤ん坊の期待と母親の受容力とのあいだに隔たりがあれば,赤ん坊は大いに混乱することになると思います。赤ん坊の自我はしがみつく自我になり,自律機能を自然的に発達させることができません。そして赤ん坊は,誇大欲求と万能欲求とを手放せず,いつまでもそれらを要求しつづける子であるか,表面はおとなしく,しかしながら無意識の中にこれらの欲求を保持したまま大人になってしまうということが起きるのです。
このように大人になって心の病気に苦しむときに,その人の幼いころの問題が表面化していると考えられる具体的な事例が大変多く,それは少なくても機能的な心の病気については,一般的にいえると考えてほぼ間違いがないように思われます。大人が人に見捨てられる恐怖を持つというのは,どこか不可思議な感じを与えるかもしれません。見捨てられるという言葉には,人間の上下の関係が込められており,生殺与奪の権力を持つ者によって人生を切断されるというふうな強い表現があります。この言葉は,幼い子と親の関係にこそふさわしいのです。乳幼児にとって,親に見捨てられるというのは,生死に関わる恐怖です。子を守る力を持っているはずの親と,その親の力を当てにする子との関係は,一方的なものです。ですから子供の立場では,いうならば絶対的に確かな信頼感がなければ,危ないのです。信頼の感覚が怪しくなったときに,この恐怖感情に強力に見舞われることになると思います。
実際に親に嫌われた幼い子は,悲惨なことになります。どこにも助けを求めようもありません。捨てられたり,虐待されたりということも現実に起こります。それほどでなくても,幼い子が愛されず,嫌われると感じると,精神的に抹殺される恐怖を持つと思います。
Tさんは50歳を過ぎた主婦です。子供はありません。高校を卒業してすぐに結婚しました。夫は,学校で相談に乗ってもらっていた教師です。家庭の事情をよく知っている男性と,助けを求める形で結婚しました。
夫は大変優しく,よくできた方です。Tさんにはこの上もない伴侶といえるでしょう。
結婚して十年ほど経ったころに,うつ状態を伴う強迫性障害を発症しました。入院も経験しました。私のクリニックに転じてきたのは,発症して15年ほど経ったころです。火の元,鍵などの確認行為や,トイレに一度入ると10分ほども手洗いをするなどの強迫行為があり,家事は夫の手助けなしには不可能でした。「料理,洗濯,掃除などは苦手という以上に,嫌なものは嫌なんです」と強い口調でいいます。一人でいることの寂しさに耐えられず。といって出かけるところもあまりありません。荒れる無意識と無力な自我の反映として,無為に寝て過ごす日々がつづきました。
一番の問題は以前からあった買い物依存でした。安い物には関心がなく,高価な洋服を買いつづけ,一室が洋服で一杯になっているということでした。「欲しいものは必ず買ってしまう。我慢することはできない。お金がなくなると万引きするかもしれない。いつもは家にこもっているが,外出すると必ず買ってしまう」といっています。そのときの心理は,「駄々をこねている子供とおなじ。後でまずいと思うが,そのときは家計のことは考えない」ともいっています。一方では老後のことも含め不安で一杯といい,死にたい気持ちが波のように襲ってくるといいます。夜中にパジャマのまま飛び出したことがあります。車に当たって死ねばいいと考えていたそうです。薬を過量に飲み,救急車で運ばれても胃洗浄を拒否するということもありました。
ある時期夫に対して攻撃的になり,「この人(と傍らにいる夫をそう呼びます)と一緒にいると我慢しなければならない,それを脅かされる,逃げるしかない・・・」などといいます。後々落ち着いてからのTさんには信じられない口の利き方ですが,当時は夫に何か不満があるのかという雰囲気でした。やがて幻覚,妄想が現れ,夜中に雨の中を戸外に飛び出し,連れ帰ろうとする夫から逃れようと大声を出すなどするようになりました。夫と別れたいともいいます。しかし夫はいかなるときも冷静に対処しているようでした。
Tさんは親子関係に大変問題がある家庭で育ちました。幼いころに,母親と外出すると,母親はどんどん先に行ってしまうのが当たり前のようでした。学生のころには鞄の中をチェックされたり,何かと干渉されたと思っています。「母親が死んだときに涙が出なかった,義母のときは泣いたけど」といいます。
父親のことは自分勝手,嘘つきといいます。両親は喧嘩ばかりしていたそうで,早く家を出たい一心で結婚したといいます。
一方,夫はゆるぎなく受け止める人でした。それに助けられて,Tさんは最悪の危機からしだいしだいに脱していきました。初診のころは生理的に無理といっていた家事全般も,ほぼこなせるようになっています。夫としばしば旅行を楽しみ,旅先で知り合った人の生き方に接して心を動かされたり,自宅を訊ねてくる夫の友人たちとの語らいを楽しんだりしています。
そういう現在でも,夫が毎朝仕事に出かけるときは不安になります。毎朝,毎朝,「今夜は帰って来ないのではないか」という不安と猜疑に悩みます。理性の上ではそんなことはないと分かっているのですが,どこか信じ切れないのです。夫に,「今夜,帰ってくる?」と何度となく訊いてしまいます。夫は,「他に行くところがないよ」とその都度返事をします。
夫は教師としての仕事のほかに,講演やボランティアなどで忙しい人です。自宅でも何かと仕事をしています。Tさんはそういう夫が羨ましく思います。夫と比較して,自分には何にもないという気持ちになり,しばしば落ち込みます。焦りも感じます。羨望し,僻む心が夫との関係にひびを入れかねないという客観的事実があり,それが更に夫に見捨てられるのではないかという不安を増幅するのです。そのように最も信頼し,頼りとする夫にすら,関係破壊的な心がしばしば頭をもたげます。関係を切断しかねないのは潜在する強い怒りですが,その原点は,母親に見捨てられるのではないかと怯えていた幼児心性にあります。その恐怖が強い分怒りも強いのですが,Tさんは直接的に怒りを表す性格ではありません。怒りは意識の奥深くに潜行して,吐き気,過食,買い物依存などを,抑えがたく引き起こす動力となっています。
人を信じることの基本のところで,身をもって教えられるものが希薄だったTさんの心を,支え,励ました夫の助けによって,Tさん自身の心に癒す力がすこしづつ賦活してきたといえると思います。
人を信じる能力は自我のものです。Tさんの自我は,人を信じるという一点においても,発育不全だったといえるのでしょう。荒れる海に打ち破られる防波堤のように,発育不全の弱い自我が,無意識の圧力に抗しきれずに破壊された様相が,Tさんの統合失調症に類似した心の病理現象です。この上もない支え人である夫にすら怒りと不信感を露わにしたのは,そういう事態においてでした。そのような強い怒りと不信を抱え持つ無意識の圧力の下で,自我の力は相対的に心許ないものがあります。ずいぶん穏やかになった現在でも,夫が帰ってこない(見捨てられる)のではないかという不安が拭い切れないのは,そのような事情に基づいています。
正月に実父の家に行きました。実家には父親が一人で住んでいます。Tさんは父親から父親らしいことは何もしてもらっていないと思っています。それなのに父親は,当然のように世話をやいてほしがるのです。高齢とはいえ,自分でできることがいくらでもあるのに,子供たちを呼び寄せようとします。姉を通じて声がかかると,できるだけ断るようにしていますが,いつもというわけにもいきません。なんといっても父親だから,できることはしてあげないといけないとも思っています。しかし父の所へ行くたびに,嘔吐感に悩むのです。
正月の集まりは,四人の姉妹とその家族も含むので,かなりの大人数になりました。きつい性格という妹二人は途中で帰り,姉もしばらくは他用がありました。一人で山となった汚れた食器を洗っているうちに,ひどい吐き気に襲われました。Tさんには,こころに障害を持っている事情を姉が知らないわけではないのにという怒りがあります(この姉と会って話しをしたいという私の申し出は,「親でもない私が何のために行かなければならないの?」と拒否されました)。夫が口添えをしてくれなかったことにも怒りを覚えます。無意識に潜行する怒りがそもそも相当なエネルギーを持っていると思われ,いわば火薬庫に点火されたような心的状況が生まれてしまいました。
翌日から過食と買い物依存が激しくなりました。過食はふだんもあります。買い物依存もときどき起こります。しかしこの正月のあとは,なりふり構わずといった買い物依存になってしまいました。夫への不満,怒りも,意識にのぼってくるのです。
そういう折に,「無性に母親が欲しいんです」といいます。そしていまは亡き母親を求めているという意味ではないと,あえてつけ加えるのです。それを夫に求めているように思うといいます。
この言葉からは,過食も買い物依存も,幼いときの情緒的に満たされなかった心と密接な関係がある様子が窺われます。
信頼と愛情との観点から,ほとんど唯一といえるほどに重要な夫との関係は,夫のふところの深い愛情によって保たれているといえるでしょう。しかしいま述べたように,心が怒りで荒れると,その夫との関係も不確かになってしまいます。そういうときに心を繋ぎとめるのが,過食であり,買い物への依存なのです。
これらの病理的な心理現象は,対他者関係が自己を正常に保つ上でいかに重要であるかを示しています。Tさんの例を通じても窺われるように,病的な心理と行動化が表われるのは,対他者関係が危殆に瀕しているときです。最も重要である夫との関係さえもがTさんの心を現実世界に繋ぎとめる力を失いかけたときに,無意識なる海は波高く荒れ,自我なる海に浮かぶ小舟の船長は,自己と人生とを支え,かつ創出する操船術に著しい困難を覚える状況に置かれるのです。漂流しかねない小舟を操る能力(自我の機能)が凝固し,不全化したときに,満足と安心とを激しい怒りを込めて求め,無意識なる荒れる海の破壊的な圧力を前にして,自我がせめても自己を現実世界に繋ぎとめようとする窮余の策が,過食であり,買い物依存であったと思われます。
TさんをTさんの世界に繋ぎとめておくのは,ふだんはなかんずく夫との関係です。一般に安定した心情でいる人の心の世界では,両親をはじめとした重要な人たちとの関係がゆるぎなく成立しているといえます。Tさんの場合,人格発達の早い時期に,両親との関係が不確かでした。典型的な悪しき依存の関係でした。見方を換えると,見捨てられる恐怖が和らげられることがないまま成長し,その強力なものは無意識の世界に布置しつづけたことになります。それは自我が,心を世界に繋ぎとめるための最大の拠り所を欠いたがために,世界から転落し,あるいは世界を粉々に砕かれてしまいかねない脅威を内に抱え込んでしまったということを意味します。そしてそれは,無化される意識,闇の恐怖,死の恐怖といったものにつながるものでもあります。
実家での正月の集まりでのTさんの経験は,見捨てられる恐怖を活性化させるものでした。たった一人で山と積まれた汚れた食器を洗う作業は,そういう経験でした。受け入れ難い父親のための集まりで,Tさんは孤立無援の心的状況に置かれたといえるのでしょう。幼児心性が一気に賦活したTさんの心は,小児的,主観的な世界に埋没してしまったのです。夫さえもTさんを刺激したことになるほどに強力な怒りは,Tさんの客観世界とのあらゆる関係を破壊しかねないほどのものでした。それはTさんを発病に導くことになった,心の原風景(幼児心性)であったといえると思います。
活性化した見捨てられる恐怖は激しい怒りを伴い,Tさんの心的世界を粉砕しかねないものであり,世界を保持するために自我が取った窮余の策が,過食であり,買い物依存であるといいましたが,それらのものに必死に助けを求めなければ,世界は粉々に砕けそうな恐怖,一切のものとの関係が失せる恐怖(統合失調症に見られる世界崩壊への恐怖),あるいは無化する闇へとまっさかさまに転落していく恐怖といったものに対処できなかったといえるのでしょう。
依存の対象へのTさんの激しい没入は,母親を強く求めているというTさんの言葉とも符号するものです。Tさんは,実際の母親を求めているという意味ではないとわざわざいうのですが,母なるものの不在形として実際の母親との関係があったということであり,それは見捨てられる恐怖と直結するものです。そして夫がいくら母親的な存在であっても,母なるものへの欲求が夫によって満たされるのは無理というものです。そうしてみると,Tさんの心が望ましく満たされることは相当に難しいといわざるを得ないことにもなります。ですから唯一,最大の良い依存の対象である夫にさえ怒りを向けたのです。これまでに,夫に助けられて徐々に自己の回復がはかられてきたといういきさつもありますが,Tさんの心の飢えが活性化すると,夫の存在すらが無意味化する危機に立たされるのです。
いま述べたような耐え難い心的状況では,心の飢えを封じられていた幼児心性が,強い怒りとともに意識の表面に浮上してくることによって,客観世界との関係が粉砕されかねない恐怖を持つことになると思います。それはまた,それによって心の病理現象の原点を明らかにするという意味合いを持っています。それは幼い時代の自我の自律性の根の保護を,当然してもらえるべきであった両親によってしてもらえなかった強い怒り,悲しみ,口惜しさ,虚しさなどが抑えようもなく表明されているということでもあります。
Tさんは家庭から逃れるように,高校を卒業すると同時に結婚しました。家庭がTさんには安心できる場所でなかったのは明らかですが,見捨てられる恐怖から逃れるための結婚というのとは,少し違う側面もあるようです。
乳幼児が母親の愛情を期待し,要求するのは自然なことです。それが適えられなければ怒りを覚えて当然です。赤ん坊の怒りは自然的,適応的なものと考えられるので,見捨てられる恐怖に捉えられ,それが母親の愛情によって緩和されなければ,その怒りは撤回され,意識の上から引っ込められることになると考えられます。それが生存本能に即した適応的な心の動きといえるからです。それは自分の,生存にかかわる正当な主張を犠牲にし,母親に取り入ったことを意味します。自我は自律性を犠牲にし,母親の自我の支配の下に入るのが安全という選択をしたことになります。
見捨てられる恐怖という強力な脅威の下で,そのような策を講じた自我は,母親の自我にしがみつくことになるのです。それは母親にとっても,かなりの程度望むところだろうと思われます。赤ん坊がおとなしくなり,聞き分けの良い子になるのは,家事や育児に追い回される母親にとっては悪いことではないだろうからです。更に,それ以上に,半ば意図的に赤ん坊の怒りを緩和せず,沈黙させた母親は,母親自身が脅かされつづけてきただろう見捨てられる恐怖を抱え持っている可能性があります。そうであれば母親自身が心の奥深く,情緒的に満たされない思いを持つ分身を抱え持っていることになります。そしてそういう場合には,もう一つの分身である赤ん坊によって情緒的に満たされ,見捨てられる恐怖を緩和させたいという強い要求を,内々で正当化させる理由を持つことになるのです。
赤ん坊が自己の自然に即して成長していくことは,母親の下から離れていくことを意味します。それを喜べる母親であれば,赤ん坊の怒りを受け止める愛情を持つことができるのでしょうが,それを喜ばない母親もいて不思議はありません。そのような母親は,赤ん坊をいわば道具にして,母親自身の見捨てられる恐怖を恒久的に緩和させようと無意識的な意図を持つことになります。そのような母親の下で,母親から容易には離れられなくなった幼児の心は,母親が望むように機能するしかなくなります。両者は分離しがたい一対の心となり,場合によっては大変仲睦まじく見えさえするのです。
Tさんの場合は,親にしがみつく自我ではありませんでした。内在する強い怒りと共に,Tさんに親元から逃れるように促した心の動力は,別種の恐怖でした。それは母親ないしは父親に呑み込まれる恐怖だったようです。親の都合のいいように利用され,自由が奪われ,呑み込まれてしまう恐怖から逃れたのです。自己が失われる恐怖でもあったと思います。
良い子の姿勢は親の一定の評価が得られて,親子関係がそれなりに安定するのに比べて,呑み込まれる恐怖をも併せ持つ子供の場合には,親の暗黙の要求を拒否する心理力動が働くことになると思われます。それは自主独立の心にも見えますが,内在する強い怒りの支配を受けています。それを克服できていない以上は,怒りと恐怖に支配された行動になり,親から独立した心には程遠いのです。これもまた悪しき依存の一つの形です。つまりTさんの自我は,母親に甘えたい強い欲求と,それを強く拒否する心とを無意識下に潜め,その支配を受けている幼児心性の様態にあるといえるのです。
さきほど述べた父親との関係で生じた感情の乱れと過食と買い物依存とは,Tさんの怒りが,自分を自分の世界に繋ぎとめておくはずの,客観的なもろもろのものとの関係を破壊してしまいかねないほどに強力だった心的状況で起こったことです。これ以上にない伴侶と思われる夫との関係さえ粉砕されかねないほどの,怒りと対人不信が一気に浮上したのです。
彼女を現実世界に健康的に繋ぎとめることができるかぎり,Tさんは大人の心を保つことができます。つまり自我がそれなりに機能しているのですが,父親と姉妹たちとの関係で味わわされた疎外感は,彼らによいように扱われる(呑み込まれる)ことへの強い怒りを浮上させました。それは自我を恐怖させるものでもあり,本来は自我の力の下で,意識の地下にあって人目に触れてはならないはずのものをも浮上させることになりました。信頼と愛情とで与えてくれるはずの安心を,誰もが保証しようとしないことへの怒りに駆られて,なりふり構わずに満足を求めて過食と買い物に走ることになりました。誰もが自分を助けず,見捨てようとしていると被害的な怒りに駆られたときに,Tさんを世界に繋ぎとめることができるのはそのようにしてでしたが,それは幼児の世界への退行という様相になりました。
それは自我の世界で起こることではなく,いわば裏の自我の世界でのできごとです。裏の自我の営為では破壊的な怒りが発動します。そこでは社会性がまったく配慮されることがありません。おもむろに自我の機能が回復されるまでは,他者の支配を被害感に駆られて拒否するTさんは,裏の自我の支配を受けることになるのです。そして時間の経過と共に自我の機能が回復していくことができるためには,夫の動じることのない母親的な愛情が不可欠です。仮に夫がTさんに愛想尽かしをしてしまったとすれば,Tさんの自我の機能の回復のために必要な,現実的な拠り所を見出せなくなる危険性が高くなるでしょう。
呑み込まれる恐怖については,逆に相手を呑み込もうとする甚だしい例がかつてありました。自分の要求をあくまでも押し通そうとするので,地域でのトラブルが絶えないのです。両親は耐え切れずに,行方が分からなくなってしまいました。治療者に対しても,幼児的な万能欲求に裏打ちされているかと思われる期待感を持っているらしく,何かと要求をしてきます。幼児的な誇大欲求を満たすべく,相手を呑み込み,支配しつくそうとする姿勢は,相手にとってこの上もなく厄介で迷惑なものですが,その心理の背景にあるのは,大きな不安と恐怖と怒りです。その幼児心性の根底には見捨てられる恐怖があり,和らげられることのなかった赤ん坊の誇大欲求と万能欲求とに裏打ちされた被害感が,相手を支配しつくす(呑み込む)ことによって,それらの欲求をなにが何でも手に入れようとするのです。その被害感と過大な権利の要求は甚だしく現実感を欠いており,反社会的な行動になってしまいます。
この種の反社会的行動に走る精神病質者について,J.Fマスターソンは次のように指摘しています。
「幼いころに愛情剥奪を経験している子供たちは,対象からすべての情動投資を引き上げ,感情を持たなくなる,病的な自己愛を満たすために,治療者を操ろうとする」と。
40代の男性会社員Yさんの例です。
Yさんは一人っ子です。父親はYさんが十代のときに病死しています。2児の父で,妻と実母との5人家族です。会社には在勤10年になりますが,大学までの学校生活も含め,最近までほとんど元気に過ごしてきました。初診の一ヶ月ほど前から会社をしばしば休むようになり,受診にいたりました。欠勤の理由は,不眠,気分の乱調,食欲不振などですが,その他に会社の上司や同僚への不信感の増幅があり,それがストレスになっているようでした。背景として会社の再編問題があります。一部上場企業に就職したのですが,Yさんの職場は切り離されて別会社に移行することが決まり,本社に残りたければ遠方へ移住しなければならないことになりました。他の多くの同僚が選んだように,Yさんも今までどおりの職場に残ることに決め,受診した半年ほど前に再出発という形になりました。Yさんは社会的な名聞にこだわる傾向がありますので,一部上場企業に見切りをつけるのは,苦渋の決断でした。
診療が始まってしばらくは,会社の問題にだけ目が向き,家族間の葛藤が語られることはありませんでした。そのことに気がつかなかったということになりますが,気がつきにくい心理的な事情もしだいに明らかになっていきます。
初診の数ヶ月前に,母親の名義になっている土地にYさんの金策で家を建て,母親と同居する計画が決まりました。そして実際に同居することになったのは初診の2ヶ月ほど後のことですが,そのころから急激に精神状態が不安定になりました。
診療を重ねるにつれ,母親の問題が主題になっていきました。母親が孫であるYさんの子供に接する様子を見ていて,自分の幼かったころの記憶が蘇りました。母親によく叱られ,勉強を強制され,何かと干渉されたのです。しかし子供のころはそういうことに殊更な意識を持たず,一貫して母親に従う良い子だったといいます。
同居してからは母親の声を耳にするだけで怒りがこみ上げてきます。しばしば衝突もします。荒れ狂うような怒りの他に,母親にそういう態度を取ってしまう自分への怒りも強く,罪悪感に悩まされます。
母親との同居問題が浮上し,現実化することに伴ってYさんの不調がはじまっているのが明白であり,病状の改善には母親と一定の距離を取る必要があると判断されました。妻をもまじえてこの問題を話し合い,母親に近くのマンションに移ってもらうことになりました。このことをYさんが理解し,実行に移すまで相当な逡巡がありました。「母親と一緒に暮らしながら解決できることだし,母親があまりに気の毒だし,世間がどう見るかということもあるし・・・」と抵抗感が強かったのです。しかしなんとか納得して自分で母親に別居を申し出るということになり,実際にそのように行動しました。しばらくはYさん自身は母親と会わないほうがよいと思われ,母親とうまくつき合っている妻が,母親とのあいだの仲介役をすることになりました。
それでもしばらくは気分の動揺がつづきましたが,しだいに落ち着いてきて会社にも行けるようになりました。
しかし妻がしだいに疲れてきました。妻は事情を理解していましたし,姑とのあいだは悪くはなく,気さくな人柄でもありました。しかし本心ではまったく理解していない義母の相手をするのが苦痛になってきたのです。妻はYさんが長期の休職中にも動揺する素振りを見せず,Yさんを支えてきました。その妻の憔悴,苛立ちは新たな難題でした。
妻から伝え聞くかぎり,母親は不満で一杯のようです。「なぜ自分が家を追い出されなければならないのか」と母親は思っているようです。古い土地柄ということもあり,母親は近所の目を気にするのですが,その点はYさんもおなじです。「母親は,自慢の孝行息子となぜ別々に暮らさなければならないのか,近所の人が理解できないだろうと考えていると思う」とYさんはいいます。Yさん自身もそう思うのです。想像される近所の人の目で自分を見,「自分はなんてひどいことをしているんだ」という罪悪感に,しばしば責め苛まれます。「自分がしっかりしていれば,同居しながら母親を困らせるようなことをしないですんだ」とも思います。依存関係にある両者は,一般になにかと似てしまうものです。しかしYさんは,一方では母親が身勝手だとも思うのです。果てしない堂々巡りになってしまいます。
母親はYさんを,「とてもよい子です。しかし心の底がよく分かりません」と評しています。その母親は息子の深刻な事態を前にして,表面的には理解を示して別居生活に踏み切りました。しかし心の底では理解も納得もできずに,強い不満のままでいたようです。そういう母親をYさんの立場でいえば,「母親はよく理解して別居に応じてくれました。しかし心の底ではよく分かっていないと思います」ということになり,両者の関係は相似形になっています。
母親がいう「とてもよい子」というのは,子供時代のYさんのことであり,いまもそういう側面があるということだと思います。そして「心の底が分からない」というのは,結婚してからの息子の様子が少年時代とは違うといっているのだと思われます。それは結婚によって,Yさんの自我が幾分か自由を回復させたということなのでしょう。
一方,少年時代のYさんは,自分自身が「心の底が分からなかった」のです。それは母親に気兼ねをしない,自分自身の自由な感情,思考であり,母親への恐怖によって強く抑圧されていたのです。そのような形で昔からあったものです。そのように抑圧された心の要素は,母親が受け入れるはずのものではなかったので,Yさん自身が幼いころから習慣的に,無意識的に,いわば見捨ててきたのに違いないのです。
母親が「分からない」といっている「Yさんの心の底」は,元々はYさん自身にも「分からない」形になっており,いわば見捨てられる恐怖を仲立ちにして,「良好な親子関係」があったのだろうと想像されます。いうならば母親から見捨てられないために,Yさんはかけがえのない自分自身の重要な分子を見捨てたといえるのでしょう。その意味で依存する母と子は共犯関係にあったといえます。両者の犯意が何に対するものかといえば,無垢なる自然のものであるYさんの分身に対してです。母親に向けた良い子の顔は,一方で,自分自身に対しては無慈悲な顔を持っていたことになります。
Yさんの父親は会社が忙しく,家庭は妻にまかせきりだったようです。母と子の関係は密接になる状況がありました。母親に「心の底が分からない」といわせるようになった現在のYさんには,幼いころは叱られ,何かと強制された思い出だけが残っています。ずっと良い子だったと思うとYさん自身もいっており,怖い母親に取り入るしかなかったことに,今は気がついています。それらのいきさつから,いわば母親の自我に憑依された自我の形成があったと思われます。
極論すれば,母親を安心させ,母親の心を満たすためだけに存在を許されたともいえる幼いYさんは,良い子であることによって安心を手にすることができていたのです。それは一方では情緒的な満足を犠牲にされた分身たちを,無意識下に閉じ込める必要をもたらしたのですが,Yさんが手にした安心は,そこからの圧力に脅威を受けることなく,すっかり意識から遠ざけていられるほどの力を持っていたようです。しかし意識下には強力な恐怖心と満足を求めて怒っている心が潜在していたのです。それらのことは結婚をして,母親から独立した生活をするあいだに,少しずつYさんの意識に上るようになったと思われます。改めて母親との同居問題が持ち上がったときに,Yさんが大いに混乱しはじめたのが,その証拠です。
一方の母親は,半ば無意識ででしょうが,幼い時代のYさんの,そういう弱みを存分に利用してきたといっても過言ではないと思います。自分自身の安心,満足をもとめて息子を巧みに操作してきたといえば,酷ないい方になるでしょうか。しかし「心の底が分からない」という不満は,Yさんの心の一部が,自分が望み,求めてきたものではないという意味以外の何ものでもないだろうと思います。
Yさんを何がなんでも自分に従うように仕向けたと思われる母親の心も,たぶん無意識的な力に操られていたと思われます。無意識下に布置する大きな力の支配を受け,母親の自我は自由ではなかったと見なければ,かけがえのない息子への支配的で身勝手な心のあり方の説明がつきません。自由な自我であれば,他でもない自分の大切な息子に対して,より余裕のある柔軟な心でいられないわけがないのです。そういうふうに考えれば,母親の自我も無意識下にある大きな力に捕捉され,なにものかに憑依されていたということになります。そうであれば自由な自分自身の立場,考えを持つのが困難だったと思います。Yさんの母親は,彼女自身が,おそらく見捨てられる恐怖とそれに伴う怒りとを,強く持っていた人ではないかと思われます。悪しき依存関係にある親子は,互いに似たもの同士という側面を持つのです。
実際に母親に会ったときに,ある種の威圧感と怒りをたたえた表情が感じ取られました。もしかするとそのときの母親の心には,大切な息子を奪い取られる怒りがあったのかもしれません。そのときに感じた迫力は,幼い子を怯えさせ,威圧し,望むように従えるには十分なものでした。
怯えを持った幼い自我が,いわば保護色で身を守るように,母親に取り入るのが安全と感じただろうことが理解できるよう思われました。
母親の支配を受け,憑依された自我にとって,憑依しているものは守り神でもあります。幼い息子の怯える心を利用したのが母親なら,怯える心を鎮めるために幼い子は母親を利用しました。つまり母親を安心させ,少しでも母親の心を満たすように心をくだけば母親の庇護をもらえるのです。まだ子供といえる時代には,母親を必要とする公然の理由もあり,問題は表面化しないのです。
結婚し,頼りにできるよい妻に恵まれ,しばらく母親とは離れた生活がつづきました。この間に,妻との関係でよい依存を体験したことになります。
Yさんの心が荒れ出したのは,母親との同居問題が持ち上がった時期に重なります。従来は無意識だった母親への依存が,こんなにも強かったのかと,Yさんは驚きを込めて何度か語っております。そして制御し難い怒りと罪悪感とが交互に現われ,心の沼が激しく揺れる日々がつづきました。
人間は何ものかに依存しないではいられない存在です。前章でも述べましたが,依存にはよい形とわるい形とがあります。一人一人の中でそれらは入り混じっていると思います。見捨てられる恐怖は,わるい形の依存へと発展していく素地となるものです。わるい依存の形が顕著になると,自我の自律性が育たず,主体性と責任意識も未発達になります。
悪しき依存関係にある親子は,二人組みの内部にあるかぎり問題はないかもしれませんが,共に社会的な自立を果たせない未熟な自我の姿でもあるので,それ自体が心の病理現象といわなければなりません。
Yさんは心理的に紆余曲折しながらも,会社での左遷をも経験しながらも,それにめげない自我の主体性の確保と,社会的な立場の確保とをほぼ自分のものとしています。今後は母親との同居が現実の課題になるでしょうが,自分の心の内部に拠り所を得たYさんは,母親から自由になった主体者としての自己を確立しつつあり,かつてのような混乱に陥ることはないだろうと思われます。
以下は長期にわたり規則的な通院をしているにもかかわらず,病状がまったく改善しない中年女性Wさんの例です。
Wさんは夫とふたり暮らしで子供はありません。もともと仕事や習い事でずいぶん頑張る人です。気力をふるって精一杯励んでいるときは,生きている実感があります。しかし,一段落つくと落ち込みます。そういうことが繰り返されてきました。やれることはやってきたという思いがあり,これ以上はどうすればいいのか,とても虚しいということで受診にいたりました。
両親はWさんが幼いころに別居しています。母親が家を出て行こうとしたときに,夫がとめてくれるかと思っていたのが,別居するのもいいかもしれないといわれて別居になってしまったと,母親から聞かされたといいます。Wさんにとっては,その以前から母親には捨てられたに等しい心理状況だったといいます。それでも後に正式に離婚になったときには,冷静ではいられなかったそうです。離婚をするような夫婦であれば,自分は生まれてくるべきではなかったと改めて考えるのです。
Wさんは父の元に残りました。Wさんは「母親に捨てられたと思っている」といったり,「母親と一緒になるのを拒否した」といったり,「拒否ではなく,どうせ父親が許してくれないと思ったから」といいかけて,「それでは父親に愛情があったことになりますね・・・」と自分で首をかしげていたり,「母子家庭がいやだった」,あるいは「父には経済力があり,自分を扶養する義務がある。将来は大学へ行きたいという計算が働いた」といいます。そのときどきでいい方が変わり,混乱しがちです。
別居後,近くに住む母親のところにしばしば行っていました。母親を求めてではないそうです。義務感からのように思うとも,行くと物や金をくれたからともいいます。いずれにせよ母親は愛情深い人ではないといいます。母親が近所に住んでおり,生殺しにされていると感じていたともいいます。
父親は自分中心の人だったといいます。自分のためにだけお金を使い,母親には十分なお金を渡さなかったのも離婚の理由だったともいっています。
両親は母親がしている仕事が縁で結婚しましたが,Wさんは母親がしている仕事を軽蔑しています。それは母が死んだ今も受け入れ難いといいます。
父親のイメージを絵に描けば般若の顔になるといます。体罰もあったが,それ以上に精神的に怖かったそうです。自分の意見が認められなかったということですが,両親に対する怒り,憎しみ,恨みの感情が激しくあるように見える一方で,具体的に訊いていくと,説明が一貫しない様子がうかがわれます。
母親については,何かのことで自分が有名になったときに,母親がしている仕事が恥ずかしいと一貫して思ってきました。
母親が死んで十数年になります。母が死んだとき落ち込み,立ち直るまで二,三年かかりました。Wさんがいうには,「ふつうの親子関係では母親が死ねば素直に悲しみ,そして悲しみから立ち直るまでにそんなには時間がかからないと思うが,私の場合ははるかに屈折したものだった。母の死後に見た日記で,それまでは自分とまったく性格が違うと思っていたのが,意外と似ているのに気づいた」といいます。
母親が家を出たのは,同居していた父親の妹にそれを促されたからである,あの人に家庭を壊されたともいいます。そして父親と二人の父方の叔母は,それぞれに問題のある性格で,そういう子供を育てた父方の祖父母には会ったことがないが,誰よりも憎しみを覚えるといいます。
父親については,絶対に再婚させてやらないと考えていました。自分だけ仕合せになるのは許せないと思ったそうです。父親への激しい羨望がうかがわれます。父親が肺疾患で死んで数年になります。病床にある父親の様子は苦しそうでした。看病をつづけ死を見取って父親への怒りが和らぎました。そして父親にも認められるものがあると思うようになりました。読書家であること,音楽や絵画への造詣が深いこと,頭がいいことなどです。そして頭がいいのは母親もおなじとつけ加えます。
両親が好きだと思ったことは一度もないといいます。母親に抱かれた記憶がまったくないといい,しかし一人っ子だし,実際にはそんなはずはないとも思っています。
あるとき受診したWさんが沈み込んでいるように見えました。理由を訊ねたところ,「意識にはないのですが,もしかすると両親が死んだことと関係があるかもしれない」といっております。両親はたまたまおなじ月に亡くなっています。
Wさんには生まれてきたことへの根強い恨みがあります。どうしてもその気持ちを払拭できないといいます。初めのころはその理由はなんといっても両親にあるといっていましたが,ある時期からは,死んでしまった両親を恨んでも仕方ない,神様を恨みたい気分といい方に変化がみられます。
小学生のころから,死にたいと思っていました。大人になると,何かの犯罪を犯すことになるかもしれないと考えたこともあります。この時代を振り返っても,信じることができた人の顔も,尊敬できる人の顔も浮かびません。しかし明るく元気に,人に嫌われないようにと心がけていました。同年代の子には,気が強いためか疎んじられるところがあったのですが,大人好きがする子だったと思うといいます。
高校生のときに,夫となった人と知り合いました。Wさんがいうには夫は自己中心の人で,友人がいなかったそうです。「私がいないと彼は人と接点を持てなかった,私によって彼は生きる楽しみ,喜びを知ることができた,その彼が一生かかってでも償えないほど,私を傷つけることをいった,彼はそういうことをよくよく分かって結婚した」といいます。
夫は会社員ですが,自分の世界を大事にし,会社の仕事の犠牲になりたくない人だといいます。Wさんは自分の方をだけ向いていてほしいと思い,夫が会社員として成功してほしいとは望んでいません。二人でしみじみと人生を語って暮らすことができれば,それで満足なのです。その夫がときに,「自分の世界に閉じこもってしまう」のです。Wさんは取り残されてさめざめと泣いてしまいます。夫は見かねて傍に寄り添ってくれます。
そういうところを見ると,「名もなく,貧しく,美しく・・・」といった類の仕合せな生活があってもよさそうに思われますが,隣の空き地に家が建つと分かってから,その種の平和が脅かされ,同時にWさんの不穏な心が表に表われてきます。
Wさんはあふれるばかりの陽光を何よりも大事に思っていました。それが隣の家の建築で奪われることになるのです。まだ会ったことがない隣人に激しい敵意を感じます。建築がはじまるととても大きな家と分かりました。相当な金持ちだろうと思われます。建築中の家を一家で見に来たときに,幼い子供たちの騒ぎ立てる声が聞こえてきます。
Wさんは苦労をして手に入れた我が家が,「この程度のものでしかない」と改めて落胆します。自分たちは子供を望んだことはないが,子供がいるふつうの仕合せを羨む心があるのは否定しません。隣家への怒りは,太陽を奪われたこともさることながら,物心両面での羨望があるのも否めないのです。周りの平凡に生きる人を軽蔑してきたのが,一転して自分が誰よりも惨めで,認めるべきものがなにもないという心に転落してしまうのです。
最近になって夫に変化が生じました。会社での責任が重くなったのです。それに伴って帰る時間が遅くなり,その分,「二人だけの語らい」が犠牲を蒙るのです。遅くまで話したがるWさんに,夫が苛立つようにもなってきました。帰りが遅い夫を詰問して(Wさんには詰問しているつもりはありませんが),夫が怒り出すということもあります。夫を会社に奪われた,夫に裏切られたという思いが,Wさんの理性をしばしば圧倒し,混乱させます。
夫が楽器を手に入れました。元からその種の楽器が好きでした。夫が目をつけたそれは音が外に漏れないように細工してあるもので,インターネット・オークションに出品されていたのです。「金額の提示は高くできないのでたぶん無理と思うが,入札してみたい,どうか」と,事前にWさんの了解を取ってありました。夫にもそういう気晴らしが要るのは分かると思っていたので反対はしませんでした。そして落札はきっと無理だろうという気持ちもありました。
ところが落札してしまったのです。Wさんは,楽器に夫を奪われたと思いました。怒りがこみあげて夫に当り散らしました。自分が理不尽なことをしているのは分かっています。しかし,「私を放っておいてそんなことをしていいのか,許されるのか」という怒りがどうしようもなく立ち上がってくるのです。夫を会社に奪われたという焦りもあったので,怒りに火がつきやすい状況もありました。
夫は唯一理解のある人とWさんはいいます。夫との良好な関係が唯一生きる支えになっているといいます。しかし交際のある友人たちも含め,一人として信頼できないという思いが強く,夫も例外ではないいいます。自分には人を愛する心がないともいいます。Wさんは,表情などから受ける印象は,決して冷淡には見えない人なのですが。
両親を頼りにできなかったWさんは,怒りをこめて両親を心から排除し,幼いころから自分を恃む心が強かったようです。明るく,活発にと心がけ,人に負けないように,人に認めてもらえる(見捨てられない)ようにと,精一杯頑張って大人になりました。一息入れると自分には認めるべきものは何ひとつない,生きている資格も意味もないという気持ちに苦しめられます。ちょっとひと休みというわけにはいかなかったのです。より強く,より正しく,より好ましくと自分自身に鞭打って自己形成に励んできたのですが,その様子には,どこか追いすがろうとする影から逃れようと懸命になっている姿が感じられます。Wさんもそういう捉えかたを否定しません。
生活の中に小さな楽しみ,喜びを見出せるように,いろいろな提案をしましたが,無益です。家事がまったく苦手といって,実際にも夫まかせのようです。なにか大掛かりなことが必要で,「小さなことでは動けない」人なのです。
あるとき,「先生が提案してくれることが,小さなことなのにできない。自分は病気ではないのではないか。ただの怠け者ではないか。こんなことでは通院する意味があるのか,疑問に思うときがあるんです」といいます。このときに,「自分を恃む気持ちが強すぎて,問題を医者に託していないということはないですか」と訊いてみました。彼女はしばらく黙っていました。無言の肯定のように思われました。そして,「人を信じきれないというのは確かにあります。だれであっても私の病気は治せないだろうという気持ちがあるように思います。・・・・・それと,こんなことをいうと見捨てられるのではないかと怖いのです」といいます。
治りたい心がないわけがありません。現に長期にわたり規則的に通院しているのです。しかし一方では,治りたいと本当に思っているのか疑問だといいます。むしろ,この世から消えてしまいたいのだといいます。彼女によると,治ってしまうと怠けている口実がなくなるのです。Wさんは,怠けるという言葉が誰よりも当てはまらない人なのですが,なにかの目標に向かってまっしぐらに進んでいないと,怠けているように感じてしまうようです。いわゆる「全か無か」の人で,「ほどほどの満足」ができません。
実際にWさんもいっておりますが,治療者に自分を委ね切れないのは,見捨てられる恐怖が一因になっているようです。自己不信が強く,しかしおのれを恃む心もそれに劣らず強い彼女は,人を信じることが怖いのです。自分の本心をさらけ出すと(信じると),相手は受け止めかねるほどの厄介な荷物と感じるに違いないという恐怖が湧いてくるようです。彼女自身が,自分の内面には受け止めかねるほどのものがあると感じていることの裏面です。
また根拠のはっきりしない自負心が人一倍強く,一方では現実が伴わないので,逆にそれが無能感を呼び込んでいるようです。おそらく根拠のはっきりしない何らかの能力への感覚があると思われます。そしてそれだけの根拠が,無意識の領域には実際にあるのだろうと思います。
自分の力をそれなりに発揮できていれば,人は自分に納得できるものです。自分はだめな人間だ,何一つ取り柄がないと思っている人は,いわば持てる力をほとんど発揮できていないのです。そして評価の基準点が自己自身にはなく,何らか他なるものにあるのです。
それにしても何を基準にして自分を評価するのでしょう?人の価値を計る客観的な基準が何かあるでしょうか。
個々の価値は人さまざまでしょうが,結局は自分らしく生きているかということになると思います。それはなかなか困難な課題ですが。
Wさんが自分には価値がないと考えるのは,価値の基準点が,万人が感心し,賛美するものという甚だしく高いものだからであるといえるようです。その心理の背景にあるのは,幼児的な誇大欲求です。もう一つの幼児の幻想的欲求である万能感が,現実の両親などによって満たされることがなかったので,いわば万人が認めるほどの大きな価値を手に入れないかぎり,くつろぐのに耐える安心,安全もまた手に入らないという意識が働いたのではないかと思われます。それは両親から見捨てられた感覚と,逆に両親を拒絶した感覚とに起因する幼すぎる自立の試みだったように思われます。
Wさんが隣家に羨望の眼を向けたように,金持ちか,貧乏かということは一般的に小さな問題ではありません。お金はあるに越したことがないと思うのがふつうでしょう。本当にそういうことに恬淡としていられる人は,よほどの人物といえるのでしょう。そういう人であれば,おそらく自分らしく生きている人に違いありません。
Wさんは,お金にとらわれるのは愚かなことだという意識の強い人です。そのWさんがはからずも隣家の住人によって,富への羨望が強いことが暴露されています。しかしだからといってWさんの心が,実際に富によって満たされるものでもないだろうと思われます。Wさんには他人を見下ろす心があります。「その辺にごろごろしている人」といういい方をしてはばかりません。そういう自分を傲慢と認め,たとえようもなく醜い自分といいます。おそらくは富に恵まれているらしい隣人を蔑む心があり,その蔑む理由が精神的な豊かさに関連するものであり,しかしながらその隣人が少なくても自分より富において勝っている,自分にはそれすらないという心が働くのです。Wさんが精神的に満たされていれば,おそらくそういう羨望からは免れることができているはずです。実際にはWさんには,「自分には何もない」感覚があります。全力を出して目標にまっすぐ向かっている自分以外は認められない,という要求を自ら突きつけている人です。自然の意志の発動を喜び,楽しむ精神はなく,誰よりも高く,遠くへという精神性への要求があります。まるで誰かに命じられてそうしているかのように見えます。
自分が掲げた目標であれば,自分の力と相談した目標設定になるでしょう。途中で間違っていることに気がつけば,訂正することもできるでしょう。うまく進まないときに悩むこともできると思います。それは自己の責任において機能している自我の姿です。
Wさんの自我は,何ものかに憑かれた自我です。自我を強いて一途の前進を要求する他なるものがあるのです。
Wさんは人を信じることができないと自分でいいますが,人の評価を大変気にする人でもあります。その一つが母親の仕事を認め難いという,不可解なほどのこだわりように表われています。彼女の自我が自由であり,自律的であれば,好悪はともかく,より柔軟な姿勢でいられるのではないかと思われます。そういうことも含めて,人の全幅の承認を得たいというのが,Wさんが躍起となって自己を飛翔へと駆り立てているように思われます。
ある日,次のような内容の夢を見ました。いま述べたことが象徴的に表われているように思います。
カラフルな玩具のような自転車で,ある家の屋根から空を飛ぼうとしている。周りに人が一杯いて期待して見ている。しょっちゅうトイレに行く。
客観性を著しく欠いた無謀な内容です。Wさんの世界が,いかに客観的なものとの関係が育たないままでいるかということの表れのようです。Wさんはしばしば赤ん坊のように夫に甘えたがるといいます。玩具のような自転車というのは,その心と関係がありそうです。空を飛ぶ,周りで大勢が期待して見ているというのも現実的ではなく,退行的,小児的心性の表れのように思われます。この「期待している大勢の者」というのが,彼女の自我に憑依しているものに通じるように思われます。それによって自我肥大を起こしているようです。心の成長過程で,何らかの無理な心理力動が働いたことに伴うものに違いありません。
この夢からも,Wさんの無意識の領域に,自我を支配するほどの勢力を持つ小児心性が潜んでいることがうかがわれます。それは幼いころの親子関係に端を発するのはいうまでもないことです。
Wさんは幼いころから両親に怒りを持ったようです。「母親は別居をはじめる以前から私を捨てていた,だから別居とその後の離婚によって決定的に確認できたということであって,その流れは一貫している,だからそもそも私は生まれてくるべき者ではなかった」と考えています。おそらく見捨てられる恐怖とそれと関連する誇大感,万能感などが母親によって和らげられる体験を持たなかったのではないかと想像されます。それは愛される体験,信頼される体験の不在の感覚と,そうしたものを求めることへの警戒心とを招いたと思われます。
愛し,愛されること,信じ,信じられることを母親との関係で達成することをWさんは拒否し,空想的な母親に託しました。それらの感情のほかに,和らげられることなく持ち越された誇大欲求,万能欲求なども母親との関係からは怒りをこめて撤収し,空想上の母親に託しました。そのような感情と欲求の撤収と移動の主な動因は怒りでした。
彼女の自我に憑依したものとは,怒りによって呼び出された空想上の母親とその人に託した二大欲求です。憑依され肥大化した自我は,誇大欲求という全的なものに引きずりまわされ,元気で,明るく,正しく,だれもが認める蜃気楼のような人物像に向かって休むことなく疾駆しつづけました。疾駆しているかぎり,彼女は見捨てられる恐怖に端を発する,もろもろの恐怖や空虚感などを意識しないで済むのです。
万能欲求は夫に託されました。この欲求は現実的な対象が必要です。夫は楽器で遊ぶことさえ許されない,完璧な受け手の役割を担わせられています。いつか夫が同席しているときに,「まるでご主人は奴隷のようですね」といったことがあります。後でWさんは,そのことを,「夫はやけに気に入ったみたいです」という形で,半ばその意味を認めながらも不満をいっておりました。
自分としては精一杯頑張ってきた,これ以上どうすればいいのか分からないとWさんは思っています。疲弊した精神を跳ね返す気力がわかない日がつづいています。いくら頑張ってもだめだ,自分にはなんの価値もないという気持ちが支配しています。
Wさんの負の依存は,なにか絶対的なものを追い求めるという形になって現われています。それは両親への依存を拒否する心の裏面です。同時にそれは両親をもとめる心が未処理だということです。人一倍大人であろうと背伸びした子供でしたが,その自我は,本来依存するべきものを見出せず,怒りをこめて拒否し,目に見えない自分の力を信じようとしたように思われます。そこにおのれを恃む心の病理性があります。まだ甘えを必要としている時期にその欲求を封じたことに,心理発達上の無理があったのではないでしょうか。
治療者に自分を託すことができるとすれば,よい依存の対象にかけてみる気になれたということになるでしょう。それは確かに冒険です。治療者が本当によい依存の対象であるか未知であるかぎり,期待が失望に変わる危険への感覚があって当然です。その意識がWさんには人より大きいのでしょう。恃むにあたいしないと分かったときの失望は,Wさんをして自らの意志で治療者を見切らせるように促すのではなく,自分が見放されたと感じさせる人なのです。未発達な自我は再びまずい判断をしたことになります。
性格形成に与える母親の影響-その6
■怒り
怒りは明確に生物学的な根拠を持っています。本能をつかさどる中枢は大脳辺縁系にあり,怒りの中枢もここにあります。動物実験で特定の箇所に電気刺激を与えると,動物はたちまち激しい怒りを表します。そして電流を切ると即座に怒りは鎮まります。いうならば機械仕掛けで怒りは発動します。
動物は,本能的に安心(安全)と満足とを求めようとします。安心を求めて巣を作る場所を選び,あるいはテリトリーを守ろうとします。満足を求めて獲物を捕らえ,異性を得ようとします。安心を脅かし,満足の追求を妨害する相手には,怒りを向けます。ただし動物の場合,同じ種族の中での闘争では,力の優劣がはっきりした時点で,弱いほうは恐れを持ち,尻尾を巻いて引き下がるのです。そうすると強いほうはそれ以上相手を攻撃し,息の根を止めるようなことはしないようです。大脳辺縁系の怒りの座のすぐそばに恐怖の座があります。怒りと恐怖とは,現象的にも相互に素早く入れ替わる類縁関係にありますが,それらはそれぞれ生物学的に個別の根拠を持ちながら近縁関係にあるのは興味深いことです。種の保存が本能的にはかられている動物の世界では,怒りと恐怖とがいわばセットになって,役割を果たしているのが分かります。
種の保存の生物学的な原則を越えて相手に攻撃を加えるのは,動物の中では人間ばかりのようです。怒りは極めて原始的な情緒ですが,人間の怒りは単に本能的,生物学的な現象とはいえません。原始的であることに特有の強力なエネルギーを保持しつつ,人間にあっては,怒りは高度な精神性に寄与する側面と,最も凶悪な忌むべき行為に関与する側面とを持っています。怒りによる攻撃行動は動物一般に認められることですが,相手を殺すこと自体が目標になる凶悪な行為は,人間に固有のものといえます。
動物の世界で見られる怒りは,生きていくために必要な,あるいは種の保存のために必要な適応的なものといえます。人間においても,この意味の適応的な怒りはあります。
動物にとっては,怒りは単純に怒りであり,自然そのものといえます。動物では怒りは他の動物に向かい,自分自身には向かいません。ここでは怒りが持つ意味は関係の破壊ではありません。そもそも動物では関係というものが,人間のようにはっきりしたものではありません。人間になついている動物は人間との関係ができているといえなくもないのでしょうが,そこにあるのは,動物の立場では,人間によって安全と満足とが満たされているということです。それは不快が退けられ,快が確保される動物的な適応的な行動の域を出ないでしょう。動物の行動に’人間的な’情趣を感じ取るのは,大部分が人間の思い入れというものではないでしょうか。
一方,人間の怒りには喜びの反意という性格があります。動物との違いは,人間では他者との,あるいは自己自身との関係の上に怒りが生じるという点です。それはおなじことを角度を変えて見れば,自我を持たないものと持っているものとの違いといえます。人間にあっては動物と違って,怒りには不快への反応にとどまらず,喜びの対極にある感情でもあります。つまり喜びがそうであるように,怒りもまた,精神的な現象です。そしてそれらの精神性の根拠は自我にあり,自我に拠って自己と他者との関係,および自己と自己自身との関係が,人間においては特徴的,かつ重要な意味を持つものとして生じています。
このように怒りの本質的な意味は,人間の場合,関係の破壊です。怒りは他者との関係,あるいは,それとの関連で自己自身との関係で生じます。適応的な怒りでは,怒りによって旧来の悪しき関係を破壊し,新たな関係を再構築する意味を持ちます。
動物の場合は怒りが他へ向かうことがあっても,自分自身へ向かうことがありません。そこが自我に拠らない動物と人間とでは,関係概念が根本的に異な
る所以です。
反抗期にある子が親に怒りを向けるのは,ひとまず適応的です。これまでの親子関係が,子にとっては支配され,抑圧される関係だと子が感じはじめたあるとき,一定のエネルギーの高まりがあって反抗が面に表われるのです。
長年にわたって培われてきた親子の関係は,それなりに強固ですが,親子の関係は,暗黙の合意,暗黙の契約によると考えることができます。そして親と子は,しばしば共犯関係にある,あらざるを得ないともいえます。それは暗黙の合意とはいえ,親の主導によるものなので,子供の立場では多かれ少なかれ不満があっても従わざるを得ない事情に関連します。親は権力的になりやすく,子供は親の権力を恐れるということを前提とした合意ですが,その上に成り立つ親子関係によって,そのかぎりで親子の安心と満足が保証されるのです。しかし親の権力,親の主導ということから明らかなように,親にとっての満足,安心が優位に傾くのは避け難いところです。そういうことを前提に,何に対する犯意かといえば,子供の心の自然的なものに関してであるといえます。これは,しかしながら,なかなか難しい問題です。子供の自然な心といっても,親の関わりがない放任された環境というものは,むしろ不自然なものであるからです。親の保護の下にある子の心の自然というものは,親の介入を人工的と捉えれば,どうしても人工的な心的環境の下でのものになります。たとえば我がままの度が過ぎる場合,あるいは逆に行儀の良い子の場合など,子供の心の自然が何であり,どこまで許容されるべきかというのは,そう簡単なことではありません。しかしながら自然の知恵というのは無視し難く,子供の心の自然の中に,自ずから自己規制を促す能力があるのではないでしょうか。大人の介入が,この自然の自己規制力を混乱させるときに問題が生じ,また,多かれ少なかれ問題が生じざるを得ないのが,人間的な現実であると考えるべきであるように思われます。ここで問われるのは,またしても親の愛情の深さと質とであろうと思います。
親の子に対する愛情は,二つの方向性を持っています。つまり親が子によって自分自身の安心と満足とを得ようとする心と,子供自身がみずから安心と満足とを得ていくのを喜ぶ心とです。前者の比重が高ければ子供の自由はさまざまに阻害され,後者のそれが高ければ子供の自立心と自由とは望ましいものになるでしょう。子供の自由を最大限に尊重する親を一方の極とし,その精神が劣悪な親を他方の極として,親子の共犯関係はそれらの両極のあいだのどこかに位置することになるといえます。その程度に応じて親子の関係は強制的合意,あるいは合意の不在となり,最も望ましくは信頼に裏打ちされた自由の契約ということになるでしょう。
次に上げる女性の夢は,母と子の共犯関係を示しているように思われます。
この女性は母親と性格が似ているそうで,両者の関係はよいという認識を持っています。
第一の夢は,「6歳ぐらいの女の子が施設にいる。母親の面会があり,女の子が喜んでいる。しかし母親は,まだしばらくは引き取れないという」といった内容です。そして,この子は私ではないと思いますとつけ加えました。
この女性は仕事の上では人に当てにされ,自信も持っています。しかし家庭では,しばしば幼い子(男子,2歳)に当たってしまいます。受診を思い立った直接の理由はその問題でしたが,夫の浮気に悩まされてもいるのです。夫は子供の世話はよくやき,子供は父親になついているそうです。彼女は経済的には自立できる自信を持っています。しかし一人で子供を育てていける自信がありません。何日間も家に帰って来ない夫に対して,別居,離婚に踏み切ることも辞さないという強い姿勢を取れないかぎり,彼女の将来は暗澹たるものと思われるのですが,元々争いを嫌う性格のせいもあって,彼女は我慢するしかないと思っているのです。そのような気弱さのために,公然と浮気をし,それがなぜ妻にはストレスなのか分からないという不可思議な感性の持ち主である夫の行動は,黙認されたままでいます。
夢に登場した女の子を,「私ではないと思います」と,質問を受ける前から自分でいっていますが,逆にそのことは,半ば自分と関係があるといっているようなもののように思われます。夢に出てきた施設については,女性の弟が肢体不自由者であるという現実があり,それと関係がありそうです。そして主観面では,女性と母親とのあいだの共犯関係の犠牲となった心内の幼い分身が,いわば心の内部の施設に預けられているというイメージが提示されているように,私には思われます。
第二の夢は,「地震が起こり家が倒壊する。両親と弟が押しつぶされ,私が泣き叫んでいる」というものです。
女性の連想が得られず,夢も断片しか記憶されていないので確かなことはいえません。しかし女性が置かれている状況と,第一の夢とを照らし合わせて,次のように読み取ることが出来るのではないかと思います。
第一の夢に現れた,心内の女の子を救い出すには,女の子の持つ怒り,悲しみ,絶望を,女性が認め,受け止めることができなければなりません。それは共犯関係にある母親への怒りの存在を,彼女が認め,受け入れることとおなじ意味を持ちます。心内の女の子は,肢体不自由者である弟のためもあって,幼い時代の女性が,母親に我がままをいい,自由に甘える心を抑圧し,’健気な大人’であったことに伴う犠牲者として(心内に)幽閉されている,というふうに考えられます。彼女の無意識的な怒りは,家という自我を倒壊させる力を持っています。彼女の心内に幽閉されている幼い子が望んでいるように,彼女自身が母親に甘えたい心を隠し持ち,我慢しているのです。だから現実の我が子を一人で育てるだけの母性がなく,頼りない夫への依存を断ち切る勇気が湧きません。夫は彼女にとっては,母親の代理という意味を持ちます。彼女は母親に依存する心を強く持ちながら,意識上では否定しています。そういう歪んだ意識と無意識との関係が,現実生活の上で夫との不可解な依存関係を生じさせています。
女性は怒りを面に表さない性格ですが,心内には大きな怒りが内向していると思われます。夫によって悩まされることに耐えつづけているのですが,ここにも怒りが内向する大きな理由があります。その怒りが夢の舞台で家を倒壊させたようです。彼女の現在の自我は母親への依存が強いので(意識上では独立しているつもりですが),母親が倒れれば,自我もまた崩壊すると感じているのでしょう。
この解釈がまったくの当て推量で,治療者である私の一人合点に終わるのであれば,私がこうした解釈をもてあそぶことは許されないでしょう。しかし治療関係の上の直感としては,かなりの確度で実態を捉えているように思われるのです。それは今後の治療過程で実証されるものであれば,この解釈は意味を持つことになります。
いま私がここで試みたのは,母と子の共犯関係と,その裏で犠牲となる分身のことと,それを救い出すのが治療上の要点になることと,そのためには怒りが重要な意味を持っていることとを例示することです。
ある父親が次のように語っています。
「息子に,幾つかの学習塾を探してやったが,息子は態度を決めかねている。ふと気がついて,もう息子に任せよう,余計な先回りはやめようと思った。そうするとずいぶん気が楽になった。思えば,これまでいろいろと無意識的に先回りして手を貸してきた。年齢から仕方がない面もあったと思うが,息子のためにも私のためにも良いことだったとは思えない・・・」と。
この父親自身がその母親から浸入的,束縛的な養育を受け,自己の姿勢を正すために多大の時間と苦労とを重ねてきたのです。
親が子を躾けるときに重要な役割を果たすのは怒りです。
心には表舞台と裏舞台とがあります。表舞台とは自我に拠る世界です。裏舞台とはいわゆる無意識の世界ということになりますが,無意識には自我がそこから生まれ出てきた,自我の拠り所となる領域と,自我の価値規範外のものとして抑圧,排除された領域とがあります。そしていずれにせよ,自我の基本姿勢は,それら一切を引き受けるということです。無意識の世界は自我の能力から見れば無限大のものであり,であればこそ自我が拠り所とするに値するのですが,それをも引き受けるのが自我の使命という大いなる矛盾があります。自我に拠る人間は,どうしたって矛盾を生きる宿命の下にあるのです。
自我に拠る心の表舞台は生を志向します。そして心の裏舞台は死を志向します。人の心には日常的に生と死とが入り乱れて表われます。一途に,永遠に生を生きることができない人間は,睡眠という形で死を日ごと経験します。目覚めと睡眠とは,生は単なる生ではなく,死をも含むことの一端であると考えられます。そして健やかな心は,睡眠によって一日の生を閉ざし,翌日,健やかな目覚めとともに再生するのです。
怒りは裏舞台に所属するものです。怒りの指し示すベクトルの最奥にあるのは死であろうと思われます。
動物が怒りを表すのは,生に適応するためでしょうが,怒りを露わに攻撃すれば自分が殺されるかもしれないのです。しかし闘うしかないのです。怒りを表すときに,動物は死を計るようです。勝ち目がないと分かると,怒りに代わって恐れを表し,降伏する自然の知恵を持っています。
親が子を叱るときはどうでしょう。叱るというのは,分別のある態度です。親の権威を背景にして教え諭すのが叱るということです。しかし叱るということと怒るということとは,見分けがつけにくいものです。叱ることは,抑制された怒りであるといえるように思われます。その証拠に,叱っているつもりでも,子供が思い通りにならなければ,いつの間にか怒りそのものに代わってしまうことも,むしろ一般といえるだろうからです。
人間にとって怒りが動物と根本的に違うのは,怒りを自我が加工するということです。子供が怒りのはけ口になっているように見えても,躾けのためだといえなくもありませんし,正義のために命がけで闘うこともありますし,理不尽な相手を黙らせることもできる等々です。
人間をも含めた動物の生を促す動力は,満足と安心との追求ではないかと思われます。本能的な心の要求に自我の加工が入る人間においては,動物よりは複雑ですが,煎じ詰めるとおなじところに落ち着くように思われます。
親が子を躾ける場合にも,親が満足と安心とを追求する基本姿勢に従っているといえます。どんなに愛他的精神に富んだ親でも,子を躾けるときに親自身の満足も追求されないわけにはいきません。親が子について描く期待イメージが,子の心の自然の要求に即したものであれば,素直に子によって受け入れられ,親も子も満足できるでしょうが,子供が反発して親が描くイメージが脅かされると,何らかの怒りが生じるでしょう。そのときに親がその怒りをどのように表現するかは一定の傾向があるものなので,親子関係に強い影響を与えるに違いありません。親たるもの,そのようなときには自分自身の心にある怒りを見つめ,それが与える自他への影響を計らなければなりませんが,実際には簡単なことではありません。気の強い親,気まぐれな親,頑固な親,気弱な親など,さまざまに異なった表現になるのはいうまでもないことですが,怒りの持つ破壊力に親の自我が翻弄されなければ幸いです。子にとって一番ありがたい親の姿勢は,いろいろあっても引き受ける精神が根底にあることではないでしょうか。それがあれば要するに正直な心でいられますし,何よりもそれ自体が親自身にとって満足と安心との源泉になるので,子の助けに依存する度合いも最小にできるからです。
親の価値観の事実上の強制を,子は多かれ少なかれ不満を抑圧して受け入れ,両者の無意識的な暗黙の契約が成立します。それに伴って子供は親によって安心と満足とを与えられることになるのですが,そこには,親に従わなければ安全を保証しないという隠れた威嚇に,子供が多かれ少なかれ屈せざるを得なかったという事情が潜んでいるのです。これらのことには親と子の双方ともに,一般的には無意識だと思います。ここには親と子の共犯関係という意味があります。この関係によって子供の自我が,子供本来の満足への要求,自分の心の自然的なもの(甘える心,羽目を外した遊び,いたずらなど,子供にとってはそれらの満足を満たすことは,その後の成長に大きな意味を持ちます)の要求を抑圧(いわば心の牢屋に拘束する)し,犠牲に供することになります。共犯と呼んだ意味は,これら抑圧され,犠牲となったものを生み出すということです。それらは心の表舞台の価値規範に合わないものとして裏舞台に回されたというふうにも考えられます。それらのものたちは,しだいに影の分身といえるほどの勢力を持つことになります。それは自我が偽りの自己を作り出すことに直接的に関連しますが,これらのことは人間には避け得ないものでもあります。
また生きることの拠点である自我によって受け入れを拒否され,裏舞台に回されたものたちは,生きることの反面である死を志向する性格を持つといえます。自我がこれらの影の分身たちを改めて自己に再統合することができれば,それは自己の成長ということになります。人生の重要な意味の一つは,そのように影の分身たちを再統合しつつ自己の発展を模索することであるということができると思います。
逆に裏舞台のものたちに対して無関心,無気力でいれば,影の分身たちは勢力を強める一方で,相対的に生きるエネルギーは衰微せざるを得ないでしょう。そういう状況では,裏舞台の極北の首座にあるといえる死の影がもたらす極風が,人の心を戦慄させるでしょう。心の諸々の病気は,この戦慄させる極風に吹きさらされることによってもたらされるといえるように思われますが,しばしば心の病気の諸症状は,その戦慄させる北風から身を守る手段ともいえるように思います。
人は何らかの満足と安全とを求めないではいられない存在です。心の表舞台で思うようなそれらが得られないときに,裏舞台のものたちが,いわば凍え死なないように病気というせめてもの隠れ家に身を潜めるという側面があるようです。いうまでもなくそのせめてもの満足は,症状といわれる苦痛に身を切られる思いと引き換えに得られるものです。
一例を上げれば,拒食症は,身体が痩せ細っていくことにのみ満足感が得られるのです。衰弱して死が切迫していると分かっていても,その満足の追求をやめることができません。
心の表舞台と裏舞台とは一定量のエネルギーを分かち持っていると思われます。表舞台が活力を持っていれば相対的に裏舞台が沈静化され,要するに元気でいられます。表舞台を活性化するエネルギーは,満足感によってもたらされ,その根本的な由来は内在する主体にあるものと想像されます。また裏舞台に注がれるエネルギーは怒りによってもたらされ,その根本的な由来は死界(内在する裏の主体)にあると想像されます。
これら表と裏の主体は,結局は一体のものであり,前者を全と呼べば,後者は無と呼ばれるべきもののように思われます。すべてを分割してでなければ認識的に把握できない自我にとっては,生と死とも正対するものとして表れるしかありませんが,いずれもが自我を超越した存在です。それらについて自我に拠る認識を敢えてほどこせば,以上のような意味を見て取ることが可能だというふうに考えるのです。
このように考えることを単なる暇つぶしに終わらせないために必要なのは,ここでは心の領域での臨床上の問題に寄与できるかどうか,臨床上のできごとに符号するかどうかということです。
心身症を病むものの多くが,もともと良い子といわれてきた人たちです。人生の最早期の幼いころに,心根を震撼させる何らかの怯え(死の極風に関連するでしょう)があると,親に捨てられないように(捨てられると生きていけないという心理が働くと思われます),親に満足されるように専心します。それは一方では,子供自身が自らの意志で,本来望んでいた,情緒的に満足したいとする心を断念することになります。それによってそれらの心は,心の暗部に幽閉されることになるのです。言葉を換えれば,自然的には受け入れられて然るべきものが,自我によって不当な拒絶を受けたことを意味します。
以上のことを敷衍すると,子の心根にある怯えが親の介入に対して自我を無気力にさせ,引き受ける精神を放擲させるのです。その結果自我によって裏切られたのも同然の自然の心たちは,心の裏舞台に回されることになります。人生の最早期にそのような心の動きがあれば,その後の心の成長過程において,親の価値観に同調しつづける自我になります。そしていうならば同じ過ちを繰り返すことになり,雪だるま式に増大する影の分身を抱え込むことになります。それらの勢力が増大するにつれ,分身たちの怒りのエネルギーもまた増大していきます。
それら分身たちの怒りの圧力に突き動かされて,子供の自我はそれに同調しないでは済まなくなるか,あくまでも畏怖する自我がそれらの分身たちの圧力を強力に抑圧しつづける(この場合は分身たちの怒りがほとんど意識されません)かということになります。後者は大きな問題を残したまま成長しますが,前者は,これまでの親子関係に異議を申し立てなければ済まなくなります。その心の動きは,旧来の親子の共犯関係を破棄し,分身たちの要求を受け入れた形で改めて契約を結び直そうとするものです。
これらのことを実行に移すには,それ相応のエネルギーの高まりを必要とし,覚悟が要ります。反抗期の反抗は,人間として成長し,力をつけてきた証拠でもあります。そのように,反抗期での怒りは,親との関係で子供自身もその関係維持に加担し,恩恵を蒙ってきた旧来の関係が,一方では自分自身との関係での軋轢が耐え難いほどに大きくなったことに伴うものです。
しかしながら関係の破壊には,それなりの危険は避けられません。それはある意味では忘恩なのです。共犯関係とはいえ,そういう形で親の恩を受けてきたのは事実ですから,世話になってきた親に弓を引く罪悪感も伴います。そして必ずしもその後の保証はありません。関係を破壊しようとすることの重要な意味を,親が理解すれば子の勇気は価値のあるものになります。困難な人生に適応するために,勇気と信頼と愛情とが踏み絵にかけられることになります。
20代の女性,Lさんの例です。
Lさんはしばらく休んでいた仕事に出ることにしました。Lさんは,「心の中にもう一人の子供の私がいる感じがしている」といいます。これは先に述べた’分身’が,自我に脅威を与えるほどに成長し,乖離した存在として意識にのぼり,自己の一体感,統一感が危機に瀕していることを示しています。
この幼い分身が表に出ると,頭がボーっとして思考力がなくなるそうです。しかし,「会社に出れば大人の私がしっかりするので,仕事はこなせる」のです。それが今回はいつもと違い,しばらくぶりに職場に復帰したところ,分身に邪魔をされて,思ったようには仕事をこなせなかったのです。帰宅して,情けなくて号泣しました。そして幼い分身を殺す気持ちで,胸に刃物を向けました。その夜,幼い分身に仕返しをされました。実際には,自分で自分の首を絞めました。その後二日間にわたり手首に傷を負わせました。
このことがあった前日,母親と雑談していた折に,自分の病気のこと,幼い分身のことを母に聞いてもらいました。母親は,「そんな話は私には分からない」といいました。また,「病院に一緒に行って・・・」と頼みましたが断られました。Lさんは,「母親が理解しないだろうということは,期待する部分もあったけれど私には見当がついていた。しかし幼い子供はそのことで傷つき,怒ったみたいだ」といいます。
この話は,要約すると以下のようになります。
母親に認めてほしいと願いつづけているLさんは,母親の願いどおりの子でいようと努めるのが習いでした。それで母親との表面の関係は平和に保たれてきました。しかしLさんの本当の願いは,(二人の関係の犠牲者として)存在が明らかになっている’幼い分身’をも含めた,全身的なLさんの存在の容認です。そのためにLさんは,母親に’幼い分身’について説明し,一緒に病院へ行ってもらいたいと頼みました。それが聞き入れられれば,乖離している分身との和合が可能となり,乖離の解消と自己の統合とが図られると考えたのです。ところが母親はその願いを拒否しました。母親との関係を手放せないLさんは,逆に分身の怒りを活性化させてしまったことになります。自我は混乱に陥り,仕事に支障をきたしてしまいました。従来は,「仕事に出れば大人の自分でいられる」と思い,それが一つの支えになっていたので,このことは二重に心に打撃を与えました。そしてLさんは母親にではなく分身に怒りを向けました。分身が消えれば乖離は消滅するのです。しかしそれはお門違いというものでした。分身を作り出したのは他でもなく,Lさん自身なのです。分身の仕返しにあったとLさんはいいますが,それは起こるべくして起こったといえる出来事です。分身はLさんと一体のものなので,Lさんが引き受ける以外にないものです。分身の立場からすると,Lさんの自我が分身の存在を容認し,自我に統合する意志を持つか,あるいはその可能性があくまでも閉ざされ,もろともに滅びる道を選ぶか,ということになるのです。いうならば母親を取るか,分身を取るかは,死ぬか生きるかということに等しいのです。
このように,生死を賭けてでも手放したくない母親との共犯関係を支えるものは,Lさんの心根にあるだろう,根源的といえるほどの恐怖以外には考え難いことです。
Rさんは男子大学生です。
初診の半年ほど前から,これといった外的な理由がなく,無気力感に囚われるようになり,母親に促されて受診しました。
Rさんの成育史で重要なのは,母親が入院を含む精神科受診歴を持っていることです。
母親はそのことを,自分の病気が子供たちに迷惑をかけたと大変気にかけています。母親自身は最近は一日の中の一定の時間,睡魔に襲われる(そのことを,眠りに逃げ込むように,と表現します)ものの,それ以外は健常状態と変わらず,残遺症候はありません。
Rさんは,小学校以前の記憶はあまりありません。小学校のころが一番楽しかったといいます。家では母親が怖いのでおとなしくしていたといいますが,外では先頭に立って,(幼い子としては)過激ないたずらをしていたということです。
5年生になってから,母親に命じられて塾通いがはじまります。勉強がいやで仕方がなかったそうです。しかし母親には絶対服従でした。目標の学校は中高一貫の有名校で,母親のいうなりに決まりました。受験勉強をはじめてから,2年間にわたり,身体への暴力を含むいじめにあいました。
受験は成功しました。しかし,自分から進んで入った学校ではなく,強制されるばかりだったという思いがありました。合格してしまうと,「もう勉強はしなくていいんだ」と思いました。勉強を怠けているので,成績は下がる一方でした。中学2年のとき,進級が難しいことになりました。そのころ両親の喧嘩が絶えなかったといいます。母親が独断で,学校に行き,退学を決めてきました。Rさんは勉強はいやだと思っていましたが,自分で勝ち取った学校という思いはあり,また学校が嫌いなわけではないという気持ちもありました。この学校に入ったのは母親主導でしたが,やめるときも同様でした。Rさんは逆らえませんでした。
公立中学に転じたあとも’やる気’は起きず,欠席が多かったということです。それでも友人には恵まれました。高校は管理的に行き過ぎていたそうで,1年で中退したRさんは,現在にいたるまで引きこもりがちの生活ですが,遊びに誘い出してくれるのは,そのころの友人たちです。
大学への進学希望は特にはありませんでしたが,通院後,大検を受け某大学に入学しました。Rさんには興味がある学問分野があり,そこを選んだものの,入学が決まったときに何の感動も覚えませんでした。疲労感が絶えずあり,講義への幻滅感もあり,いつか通学の意欲を失くしてしまいました。いまは休学中です。
通院後は,いわば一進一退です。気分がよいときと,乱気流に巻き込まれたように不安定になるときとが交互にやってきます。死を待望する気分にしばしば陥ります。生きようとする心と,死にたいという心と,二つの心が綱を引き合うように交互に表われるのです。
通院をはじめて1年半ほど経ったある日,いつになく険しい表情で受診しました。
母親に,「生んでほしくなかった」とはじめて口に出したといいます。そのあと自殺も考えました。「いままでいわなかったが,物心ついたころから,死にたい,生きていたくないと思ってきた。元気にしているときも,その気持ちを隠していただけだった。口にしなかったのは,そうすることで家庭が壊れるのを心配したからだった」といいます。
深刻な事態であり,深刻な告白です。しかし,新たに困難な局面にさしかかったというよりは,元からあった心の問題が告白されたのです。そのような苦しい胸のうちを明かしてくれたのは,むしろ注目され,評価されてよい局面です。いわば生きようとする心が勝ってきたからこそ,口にすることが出来たといえます。
評価してよいもう一つは,これまで抑圧してきた怒りを,母親に向けて表現したことです。そしてその怒りが,母親のみならずRさん自身にも向けられたものであることを,Rさんはすぐに気がつきました。
従来,母親とのあいだには,母親の意向には逆らわないという暗黙の合意がありました。母親の病気に伴う不安定,怒りっぽさ,入院による不在等々は,幼い幼いRさんには脅威だっただろうと容易に想像されます。幼いRさんは,母親の気持ちに迎合することで母親の怒りを鎮め,母親が(多くは心理的に)遠くへ去ってしまわないように心を砕いただろうことも,容易に想像されます。このように,母親の意向には決して逆らわないという暗黙の合意は,母親を恐れる心を背景にしたものであるのは明らかです。その暗黙の契約は,幼いRさんが自分の内部にある自然の心の要求を無視し,黙らせることなしには済まないものなので,共犯関係といえる性格のものです。
Rさんが母親に向けた怒りは,その関係の不条理性を問い質すものです。怒りを込めた異議申し立ては,両者の関係の犠牲となっている分身たちに端を発するものですが,それをRさんが受け入れたことになります。
一般に怒りは自我に所属するものではありませんが,自我がそれを受け止め,みずからの責任において怒りを利用するときに,怒りは適応的な意味を持ちます。
Rさんの異議申し立ては,「生んで欲しくなかった,無(死)を望む」ということです。「生んで欲しくなかった」というのは母親に向けられたものであり,「無を望む」というのはRさん自身に向けられたものです。
怒りは関係の破壊を志向します。母親との旧来の関係を破壊しようとするRさんの怒りが適応的なものになるかどうかは,一つには母親の姿勢にかかっています。つまり母親が冷静に受け止めることができるかどうかですが,「子供に迷惑をかけて申し訳ない」気持ちで一杯の母親は,悩みながらも受け止めることの意義をよく理解しています。またRさん自身も,自分の中にあるはずの怒りの正当性を認めたからこそ,無意識層深くに潜んでいた怒りを意識の上に浮上することを許したといえるのでしょう。ある程度はそれを口に出しても,母親の病気は悪化しない,親子の関係が破壊されることはないという計算も働いただろうと思われます。いわばそれなりの心理的な準備が整って,かつては考えられなかった自己主張をしたのです。
評価できるもう一つは,治療者に,「いままでいわなかったがずっと死にたいと思っていた・・・」という’告白’です。これは重い荷物を治療者に預けても大丈夫だろうという心理があってのことです。ある意味では治療者へのプレゼントです。また,その告白の意図の重要な要素は,「死にたい気持ちがあるのは事実だが,それを共有してほしい,何とかなるものなら方法を教えて欲しい」という気持ちが無意識的に働いているだろうと思います。ですからこのことは,治療的な展開といえるのです。
これまでにRさんは,「自分が最も望むのは無です,消えることです。一人になることは何とも思わない。友達は要らない・・・」と繰り返しいっていました。その都度そのことについて話し合われてきました。この’告白’は,そのやり取りの延長線上にあるといえます。
その後何度か母親に向かって,「生んで欲しくなかった・・・」という怒りの表明をしています。そして,母親への怒りの表明が繰り返されることに伴って,乱気流に巻き込まれたかのような気分の乱調は,目に見えて収まってきています。
Rさんが怒りの存在に気がついたのは通院後のことです。それまでは怒りは自我によって強く抑圧され,無意識下に潜行していたのです。それは母親を恐れる自我が,母親の自我に同調したことによるものでしょう。抑圧が強かった分,恐れも強かったと考えるのが合理的だと思います。
(30代のある主婦は,「結婚するまで母親のいうことに疑問を持ったことがなく,ましてや怒りを覚えたことがなかった」のです。ところが結婚してから,夫の家庭や育ち方などが,自分とあまりに違うのでびっくりしました。夫は寒い日に外出しようとすると,「温かくして行けよ」といいます。ところが母親は,「みっともないから一枚脱いで行きなさい」といいます。一事が万事この調子でしたが,「世の中こんなもの」と思っていました。母親は世間体が常に気になる人だといいます。しだいに怒りが収まらなくなりました。いままで溜まっていた怒りが,堰を切ったように意識に上ってくるようになったのです。あるときから電話の連絡も断っています。母親を「心の貧しい人」といってはばかりません。些細なことで苛立ちを覚えると収まりがつかなくなり,しばしば落ち込みもします。そういうことで受診にいたりました。この方の場合は怒りの存在を,幼いときから自分でも気がつかないように抑圧し,その存在を消していたのでしょう。それはいうならば親子の共犯関係に基づくものです。いまは心の中を飛び交うようにして表われる怒りの処理に窮していますが,怒りの存在を過度に抑圧する自我から,その存在を受け入れた自我に移行したということなので,差し当たりは苦しくても彼女の自己の回復過程では重要なことが起こっているのです)
Rさんがうつ状態に陥ったのは,高校を中退してコンピューター関連の仕事を目指していたころです。ある時期からそのことへの意欲を失ったのがきっかけでした。そのことに特別な外的事情があったわけではなく,いわば内的に閉塞状況に陥ったようです。そのころから,いわゆる引きこもりの生活になりました。心のベクトルが生よりも死の方に傾いたといえる状況です。見方を変えれば,心の舞台の重心が表から裏に移行したともいえるでしょう。
通院後,まる2年ほど経ったころに,次の内容の夢の報告がありました。
パラシュートで降下する。綱が切れる。死の恐怖と安堵。しかし山の頂上に落ちてたすかる。「たすかった」と思った。苦労して自力で山を下りる。
Rさんの内的世界では,生きようとする心と滅びようとする心の綱引きが長期にわたってつづいています。夢の内容もそういうことを表しています。パラシュートでの降下は,この夢では生と死を賭けたものです。もし綱が切れなければ死はありません。危険ではあっても,ただのスポーツです。しかしここでは綱が切れてしまいました。そして生きようとする意志がはたらいて,山の頂上に落ちることになります。仮に夢の中で激突死していれば,近い将来に実際に死の危険が迫っていると考えなければならなかったかもしれません。
この夢によって,Rさんの生きようとする心が死を望む心に勝ったことが窺えるのですが,現実にはすぐにはその意志が強化されていく様子が見えません。あるとき自殺を考えて外出し,しかし恐怖心から果たせなかったということも起こっております。それは夢の内容に符号するものです。母親(父親にも)への怒りの爆発はその後も見られました。そしてそれが母と子の旧来の関係を破壊する上で必要であり,有意味でもあったのです。その証拠に,しだいしだいに気分の安定が図られております。
Rさんから,「自分の仕合せを問い詰めていくと,どうしても無を望むことになる。それがなぜ問題なのか,その自由はあると思うが・・・」という問いかけがしばしば見られていました。そして気分の安定化に伴ってそうした問いかけが見られなくなっています。
Rさんの問いかけに,私は,自我に拠るのが人間である所以だから,というふうにこたえております。
自由と死のテーマは,他の方からも提出されています。その方は自死について言及することが多いのですが,次のような夢を見ました。
だれかがステージに立って,「自由を勝ち取ろう!」と演説している。そのとき私自身が空から落ちて行く。
この男性の問いは,自死と自由とは同等だろうかという問いでした。
自由は心の表舞台のものです。死は裏舞台の最奥にあるものです。前者は自我の世界のものであり,後者は自我の範疇の外にあるものです。もし自死が自由に選べる性格のものであれば,それは自我の世界に所属することになるのですが,そうではありません。自死は自我の力の行使ではなく,自由な選択の不能として起こることではないでしょうか。
ここで検討に値するのは,ソクラテスの死です。
ソクラテスは,「悪事をなす者で,若者を堕落させ,国家の神を信じず,自らの何か新しい心霊を奉じている」というかどで告発されたといわれています。彼は刑罰を免れるための一切の弁明をせず,亡命のすすめも拒否して,毒杯をあおって刑死しました。
ソクラテスが裁判にかけられ,死刑の宣告までされるにいたったのは,(「ソクラテスの弁明」におけるソクラテス自身の説明によれば)次のごとくです。
それはソクラテスが自分自身に課した’奇妙な使命’から生じました。あるとき,カフェレオンという彼を信奉する親友の一人がデルフォイへおもむき,ソクラテスより知恵のある人がいるかどうかと,神託を訊ねました。その答えは,ソクラテスより知恵のある人はいないというものでした。
ソクラテスは,それは何を意味するのか知りたいという使命感に駆られたのです。というのは彼自身は,善美のことや徳(それらは魂を世話することを何よりも重視するソクラテスにとって,最深奥にある課題でした)について,自分はむしろ何も知らないと考えていたからです。そうすると神託は,何も知らないことを知っていることが知恵のある者であるといっているのだろうかと考え,それを確かめたいと思ったのです。この答えを知るために,自分より知恵のありそうな者を探し出す必要を感じました。これはと思う者に会って,彼らの知恵に耳を傾け,それを論駁できるだろうかと考えました。結局,彼らの誰一人としてソクラテスより知っている者はいないというのが結論でした。何ほどかすぐれたところがあっても,自惚れることでそれを帳消しにしているということが明らかになるばかりでした。彼らはほとんど知らないか,何も知らないのに,すべてを知っていると思い込んでいるのです。ソクラテスは,結果的には,自惚れる者たちに問いを持ちかけ,自己矛盾に陥らせることで,見せかけの知恵を暴き立てる仕事にのめり込むことになりました。こうして恥をかかされた者たちの激しい敵意を呼び込み,知識の教師を自認する者たちから,「詭弁を弄してアテナイ市が認める神々を認めず,別の新しい神を信じるように促し,若者を堕落させる不埒者」呼ばわりされることになったのです。
こうした問題になった背景には,当時のアテナイ市が国家の存亡をかけた政治的状況にあり,アテナイ市民に与えるソクラテスの立場と影響力の大きさ,加えて多くの市民が彼をソフィスト(神を否定するもの,弱小の問題を強弁して世を惑わす者)と混同していた,などの事情があるようです。
ソクラテスは人類の教師と讃えられていますが,ソクラテス自身は神に仕える者という使命感を持っていたようです。彼は合理的な精神を誰よりも尊重し,身につけてもいた人といえるのでしょうが,一方では親しい関係にある者にとっても,神秘的で不可思議な人という側面を持っていました。それは,「子供のときから何か神からの知らせとか,鬼人からの合図とかいったようなものがよく起こった」と彼自身が述べていたと伝えられているように,’心内の声’に聞き入っている姿がしばしば見られたからです。
当時は,神の定めた圧倒的な運命の前に,人間はいかんとも抗し難く,神託,予言,前兆,夢などを通じて自分たちの運命をさぐり,悪しき運命をできるだけ避けようとする時代精神から,一方で,そのような運命的な必然に対して,人間の自由を主張する合理的な精神の方向へと時代が動いていました。特にアテナイ市民は自由を何よりも誇りとしていました。彼ら市民たちが自由と合理性を謳歌しようとした背景には,神々がまだ生きていた時代であったということがあるでしょう。一方では神々の威力を畏怖し,一方ではそれを非合理なものとする合理的な精神が台頭し,しだいに後者が時代をリードしつつあったといえます。
神々への畏怖を背景として,掟や部族の宗教に縛られる古代人に較べると,アテナイ市民たちは大きな自由を謳歌しつつありました。しかし宗教的な戒律に代わって,今度は市民たちは,ポリスへの全的な服従という戒律に従わなければならなかったのです。いずれにせよ自由という高度な精神は,人間はどう扱ってよいものか分からないものになりがちです。ソクラテスが,「身体は一切の災いの素である・・・・・・魂(精神)ができるだけすぐれたものになるように気を使わなければならない・・・・・・そのことよりも先に,もしくは同程度にでも,身体や金銭のことを気にしてはならない」というように,身体性を持つ人間には,純一の魂と同義であるらしい真正の自由というものは,永遠に理念でありつづけるばかりです。ですから戒律がなければ,人間がそれぞれに勝手なことをはじめる混乱は避け難いことです。
神々の名の下であろうとなかろうと,戒律を定めるのは人間です。自由を与えられると勝手なことをはじめる愚かしさが人間のものであるなら,本当にはその権利も資格もないのに,市民に戒律を押しつけて自由を奪う愚か者もまた人間です。自由を真には謳歌できない人間は,どうしても愚か者以上にはなれないというべきでしょうか。
ソクラテスは,自分自身がそのような意味での愚か者であることを誰よりも承知していました。そして真の賢者は神であると認め,自分は神の助手として,自分の愚かしさをかぎりなく煎じ詰めることによって,人間の分としての賢者でありたいと熱望した人です。そして神の助手であるという自負心と使命感とを持って,アテナイ市民たちを少しでも有徳で謙遜であるように仕向けようとしました。彼は自分自身が神の助手としての資格を本当に持っているのかということを確かめるためにも,世の中の権威者と考えられている人間たちと,ある意味での知恵比べをしたのです。
ソクラテスは自分の使命を,「(神が私を)虻のようなものとして,このポリスに付着させたのではないかと思われる・・・」という比喩を使って表現しています。「・・・ポリスという馬は,素性がよくて大きいが,そのために却ってふつうより鈍いところがあって,目を覚ましているのには,何か虻のようなものが必要だ・・・(諸君は)目を覚まされて怒っているのだろうが,そのような(虻である私のような)人間を軽々に殺してしまうと,後は(諸君は)ずっと眠ってしまうことになるのだから,困るのは自分ではなく諸君の方だろう・・・」といいます。
神の助手を自認するソクラテスを理解するには,内心の声に聞き入った特異の体験の持ち主であることを抜きにしてはできないでしょうが,神々がまだ生きていた時代であればこそ,その特異さが彼を神々しく色づけることに益したのでしょう。彼の時代であれば,「神からの知らせに聞き入っていた」といっても,「それは幻聴というものです」としたり顔にいって聞かせる者などはいなかったのは幸いでした。もっとも内心の声に従ったといっても,声が彼を突き動かしたのではなく,何か間違った考えが浮かぶと声がそこに介入してきたという意味のことを,ソクラテス自身の言葉としてプラトンが伝えています。つまり彼は憑かれた者ではなかったということです。
ソクラテスは一方の足を神の世界にかけ,もう一方の足を人間界にかけていたといえなくはないように思われます。ソクラテスの信奉者たちはそういう彼に神々しいものを見たようです(プラトンは「饗宴」の中で,アルギビアデスの名を借りて次のように語らせています。・・・ソクラテスの話は女,男,少年の区別なく,みな驚嘆してそれに魅入られてしまうようなものであり,・・・ソクラテスと接することで,心臓は激しく動悸を打ち,涙が流れ,奴隷のような状態になって恥じ入るという体験をした)。神の世界に片足をかける存在が許容される時代でなければ,ソクラテスのように,あれこれの誇り高い人物のところにおもむき,その思想の迷妄を確かめ,正そうなどというお節介は,決してまともに相手にされることではなく,許されることでもないでしょう。その意味では現代は神々に対する人間の自由は,完全な勝利を得ています。そしてアテナイ市よりは,社会を律する掟もずっと洗練されたものになっているに違いありません。しかしながら真の自由を謳歌できるほどに人間が洗練され,愚か者であることからも自由になりつつあるかといえば,それは設問自体が愚かしいことになるでしょう。
私がソクラテスに見る最大のものは,引き受ける精神の具現者であるということです。何を引き受けるのかといえば,神命ということになります。つまりソクラテス流に考えれば,自我に拠って人間であるようにというのが神命であり,彼はそれを潔く引き受けたことになります。
自我はまさしく引き受けることを使命としています。そしてソクラテスが耳を傾けた内心の声の発信者こそ,先の章で問題にした「内在する主体」であると考えられます。
これは非科学的な考えでしょうか?
思うに人生とは,ソクラテスが内なる声に耳を傾けたように,内在する主体の意向に耳を傾け,それに即してそれぞれの自分の心の姿勢を整えていくことにより,自己自身になろうとする行為過程であろうというものです。ここでいう自分自身とは,ソクラテスに従っていえば,純一なる魂に到ること,換言すると’囲いの外’へ超え出ることによって神の意志そのものと合一すること,という意味合いになると思います。こうした人間的な知性,認識力を超越したものもまた人間存在の構成要件になっている以上は,想像的に人間的に解釈し,人間的な言葉に置き換える努力は,目下の問題に答える上で欠かせません。問題は全体を包括的に見る視野の上に立たなければ,いかなる理解も本来的なものに近づくことはできないでしょう。
具体的に主体者の意向をどう捉えるのかというのは難題ですが,ソクラテスの愛知の精神,常に最上のものを知りたいとする精神はそういうものです。また我々の日常に即していえば,一つには,’心の障害’といえるほどの心の苦境からどのように脱するのかということに手がかりを与えるものがそういうものである,と考えることができます。実際,「内在する主体」というのは,机上の空論を弄んだ結果の産物ではなく,患者の皆さんとの関わりを通じて経験的に浮上してきた産物であるのは確かです。
ではギリシア時代の神はどこへ行ってしまったのでしょう?宇宙的規模で森羅万象をつかさどる神を擬人的に描いたさまざまな神話は,それが生き生きとた感動を人々に与えていた時代にあっては,それに呼応し,活性化される心の内部の状況があったのでしょう。現代では神話はくだらないお話の域を出ません。それに呼応する心がほとんど死んでしまっているのです。言葉を換えれば自我が至上のものとなり,非合理的なものが意識からほとんど排除されてしまった現代では,神が云々されることは困難になりました。しかし神を征服し,至上者の位置についたかのような自我に拠る現代の人間は,ソクラテスの時代に較べて一段と成長し,賢くなったとも思えません。物質文明が栄え,心が砂漠化している現代は,ソクラテスが魂の世話をせよ,金品や身体を魂に従えさせよと警告を発しつづけていたことに学ぼうとしなかったために,精神の貧困化を必然的に招き寄せたといっても過言ではないでしょう。そしておなじ理由によって,神や自然を畏れる時代には豊かにあっただろう謙遜の心が,現代ではあやしいものになっています。人間にとって自我は最上位のものではないという自明のことから,謙遜の精神は人間にとって最も意味のあるものに違いないのです。
ソクラテスがしたように,内心の声に耳を傾けることは現代でも大きな意味があります。それは人間が拠って立つ自我がその上位のものに依拠しているのは論を待たず,その上位者を内在する主体と位置づけるときに,この主体の意向に耳を傾ける必要があるからです。自我を通じて我々がするべきことは主体の意向を模索することです。C.Gユングは,夢は意識の補償作用の意味を持つといっております。自我が主体の意向の軸に即するように活動しているときに,自我の働きはいわば補償される必要がありません。そして心の障害という事態にあっては,自我の活動の方向性と主体の意向の方向性とが甚だしく合い隔たってしまっているといえ,補償作業が必要になるのです。
内在する主体の意向に耳を傾けるのは,ソクラテス流にいえば,「神からの声」に耳を傾けるのとおなじ意味になると考えられます。現代の神は,内在する主体であるということが可能であり,そのように考えることによって臨床的な問題の理解と,治療上の工夫と有効性とが確かめられていると私は考えています。また,そのような意味のある思考の連鎖を,私は科学的であると主張できると考えます。
ところでソクラテスは,死刑の判決を逃れるための画策や,あるいは,まだ幼い年齢の子供たちを含む家族の苦境も考えて欲しいという弟子達の声に耳を貸そうとしませんでした。彼にとっては最も正しいと考えることを,いかなる理由によっても捻じ曲げることは許されないことでした。神の助手としての自分の崇高な使命を翻し,地上の汚濁にまみれている者たちに媚びるなどは,彼には考慮に値しないことでした。神を信じるソクラテスには,この世で善を生きようとする者は,囲いの外である彼の国ではますます善が喜ばしく遂行されるはずのものでした。
引き受ける精神の具現者であるソクラテスにとっては,死は雄雄しく引き受けるべきものでした。
死に関して彼は次のようにも述べています。
人間というものは,囲いの中に入れられ,その囲いを監視するものにいつも見張られている動物のようなものである。その動物が勝手に自分の命を絶つようなことをすれば,監視するものは当然腹を立てるに違いない。一方,哲学者は無知な大衆によって’死んだ者’と馬鹿にされるが,真の哲学者とはいわば死の練習を日夜しているようなものである。死とは一切の災厄の元である身体を去って,魂そのものとなることなので,それこそ真の哲学者の望むところである。(死は)知の探求の究極の姿である・・・。
ソクラテスにとって哲学者とは知の探究者であり,知を探求することは,人間にとって最も重要な徳や善,美を求めようとするかぎり必須のことです。そして知を極めた者が死を正当にまっとうできると考えているようです。ソクラテスにとっては,知の探求は人間が魂を最高,最善なものになるように世話をするための王道です。その道は囲いからの解放と,監視者の監視からの解放への道でもあります。それが達成されたとき,人は既に人間存在ではなく,それを超越した存在です。人はそのような死を理想的な目標と考えることが可能で,哲学者たるもの,日夜そのための練習をしているというわけです。
一方で,人間は身体的存在であるのを免れず,それはどうしても災厄の素になるので監視者が要る,とソクラテスが述べているのも頷けることです。いわば煩悩から解脱しないかぎり人は災厄から逃れるわけにはいかないが,解脱をもとめる心があるかぎり,彼方に理想としての死が微笑んでいるということでしょうか。
ソクラテス流に考えると,魂はこの世を超越した世界のものです。そして身体はこの世のものです。この世を超越した性格のものと,この世的なものそのものの性格のものとが混交しているのが人間存在に他ならない,ということになるようです。
魂はこの世のものであるかぎり身体と連れ添うしかない羽目にあるのですが,それらの関係から不可避的である矛盾,葛藤に耐え,超克していく強い自我があれば,やがては対立的な諸矛盾の最終的な止揚という形態で究極の境地に到ることができる,そのようなものとして死は求められるべきものであるというふうに考えることができるようです。そして自我のそのような仕事に,内在する主体が暗黙の内に指針を与えていると考えることは何かと有益です。
死へと到るこの道は,いうまでもなく容易なものではありません。だから我々は日夜死の練習をしているのだよと,ソクラテスはほくそ笑むようにいっているように見えますが,’哲学者’ならざる我々は死の練習をするほどの余裕はありません。絶えず煩悩にさらされ,傍目からは日常の平坦な道と見える路上で遭難しかけることも珍しくはありません。この世的な煩悩を超克して純一な魂の完成に到る,などという大層なことなどはおぼつかないことであり,荷厄介な身体を捨て去りたいというほどに疲れ果てることも起こります。
我々一般にとって,死は囲いの中から覗き見る非日常的な問題です。それは到底手に負えるものではないものとして,ふつうは寿命がつきる,病に落ちるという形で訪れます。それは囲いの中で迎える死といえるかもしれません。
そしてソクラテスが述べる死は,囲いの外へ出ようとする意志を持った者に訪れる死です。そのような意味での死は,生きることが確かに「死ぬ練習」といえるのでしょう。ソクラテスが人生の道半ばで死を甘受したのは,監獄という囲いの監視者の目よりも,人間存在のあり方そのものの監視者の目の方を躊躇なく尊重したことによります。
死はいずれにしても訪れるとして,彼我を分ける決定的なものは,生きる姿勢ということになるのでしょうか。より良く生きたものは,死を自ら引き受けることができるということなのでしょう。
先にあげたRさんの問いは,身体を捨て去ることによる死と,人生をかけた葛藤を超克して純一な魂になり得たのと,一体どこが違うのかという問題であるように見えます。
死に関する問いは重いものなので,どのように答えても安易の謗りは免れないように思いますが,自我が十分に引き受ける精神をまっとうした意味を持つソクラテス的な死は,この問題を考える基準を与えているように思われます。
魂と身体という二極分化は,人間が自我に拠るものであることに伴う必然です。自我そのものが矛盾し,対立しあうものの交点です。先に,ソクラテスは一方の足を魂のふるさとの世界にかけ,一方の足を身体の存在理由となっているこの世的な世界にかけているといいましたが,自我についても同様なことがいえます。つまり自我の機構は生物学的な根拠を持っていると思われますが,これと名指しするのは不可能でしょう。仮にそれが可能であるとすると,生物学的なという限定によって,自我は明瞭に’この世的なもの’以上のものではなくなります。しかし自我に拠るのが人間であるという前提が正しければ(他のものを前提としたとしても,結局おなじことになります),人間に関する一切の問題を自我は引き受けなければなりません。つまり自我は,’この世的なもの’以上のものも自己の課題とすることを含んでいます。換言すれば自我は,人間が’この世的に’存在する理由であり,かつ’この世的なもの’を超えたものをも引き受ける使命を持っているということになるだろうと思います。ソクラテス流にいえば,自我は神意を受けてこの世のものであるべく存在しているということになるだろうと思います。
自我は光の世界のものです。人間が何を目指して生きるのかといえば,ソクラテスに従えば,純一の魂を目指してということになります。この場合の魂とは,真の自己,自己自身,自己実現といった概念と等しく,実際には到達できない理念としての自己の目標,あるいは超越的自己の存在様態ということができます。ソクラテスは,純一の魂となることは身体から自由になることであり,哲学者がそうありたいと努めてきた理想の実現であるといっております。つまり人間が生きているかぎり手中に収めることは決してできないが,死という到達点に向けて,満足の行く自己形成の歴史を追及するにあたっての目標であるということになると思います。
具体的には,ソクラテスに従えば,身体性を歩一歩克服していく心的なプロセスということになるでしょうか。
しかし克服するべき身体性とは,どういうことでしょうか?
人間の心には,光(正)の世界と影(負)の世界とがあるといえます。その心の負性のものは,心の自然的な発展過程というものを想定したときに,他者によって歪められることになった心たちによって構成されるといえると思います。
例えばAという人物が3歳のときに次のような経験をしたとします。
まだ1歳に満たない弟を,母親がまたとない慈愛に満ちた顔をしてあやしています。Aはそれが羨ましいと思っています。母親が寝ついた弟をベビーベットに寝かせています。Aは母親の膝の上に乗りたくてたまりません。先ほど弟にしていたように,慈愛に満ちた顔で抱いて欲しいと思っています。しかしつい先日も含めこれまでに何度も,母親の膝に乗ろうとしたら厳しい声で叱られたのを思い出します。
Aは母親に甘えるのをあきらめました。ぼくは(わたしは)お兄ちゃん(お姉ちゃん)だから,そんなことをしてはいけないんだと思いつつ。
この例によると,母親に甘えたい心は自然のものです。そして母親との関係で,その自然のものを歪めたということになります。
いうまでもなく,こうしたことは誰の場合でも多かれ少なかれ起こることです。つまり自然の心を歪めないですませることは不可能なのが人間です。
この例のAの場合,甘えられなかった甘えたい心が負性のものです。
Aが純一の魂を目指す使命を持つとして,長じてこの負性のものをどのように扱えばよいのでしょう。また,Aのこの負性と身体性とはどんな関係にあるのでしょう。
このように心を不自然に歪めるときに働くエネルギーは主に怒りです。Aがいわゆる良い子であるとすれば,怒りを抑圧して自分では気がつかないことになるでしょう。可能なら怒りを母親に向けて抗議するとよかったかもしれません。母親がその正当性を認めてくれれば,Aは甘えたい心を抑圧する必要がありません。つまりAの自我は,心の自然を護ることができたことになります。この場合の怒りは,Aの自我によって適応的に作用したといえます。
長じて,Aがこの問題を解くことができるとすると,Aが幼いころのこれらの経験を意識が探り当てたときです。言葉を変えると自我がかつては抑圧したものを,改めて自我の表舞台に引き上げ,再統合を図ることが出来たときです。このあたりの自我の作業を,フロイトは遺跡の発掘作業になぞらえています。
こうした心の作業を困難にさせる理由の一つは,強力な怒りの存在です。怒りは元はといえば,甘えたい欲求が理不尽に満たされなかったことに伴うものですが,それが理不尽であればあるほど,抑圧しなければならなかった母親との関係の問題が大きかったことになるでしょう。それとの相対的な関係で,自我が気弱にならざるを得なかったのです。意識下の闇に葬ったものに長年にわたり悩まされて,長じて改めて意識の光を当てる気になった自我は,既に気弱ではないことを証明したことになります。そしてこのときに,暗々裏に感じていた怒りのエネルギーに恐れをなしていた心に,打ち克ったことを意味するでしょう。その怒りのエネルギーは,抑圧されていた体験群と共にあっただろうと思われます。そして心に屈するものを解決する決意を持った自我が無意識界を探索し始めるとき,自我は怒りと共にある過去の体験群を受け入れる気になっているのです。その心の作業に伴って怒りが意識の上に浮上してきて,自我を脅かします。しばらくのあいだは心は不安定であることを免れないでしょう。しかしやがては怒りのエネルギーは,自我の意味のある仕事によって心の表舞台を支えるエネルギーに姿を変えることになります。裏舞台のものであった怒りのエネルギーは,表舞台のものである生のエネルギーに変換されたのです。
この場合,ソクラテス流に見れば,’災いの素である身体的側面’を,魂の世話をすることで克服したということになりますが,それを具体的に見てみます。
Aが羨望したのは母親の愛情のことです。
母親の愛情は身体の愛撫を通じて表現されます。母親に愛されなかった自分とは,愛されるに値しない身体を持つ自分といっても過言ではないでしょう。怒りも介在して母親を怖れたAは,母親の怒りを招かないために,本来は心の表舞台にあるべきものとして認知しなければならなかったもの(甘えたい心)を,裏舞台に回してしまいました。その自我の汚点は,自分の身体が認めるに値しないという歪んだ認知を招きます(思春期にある者が,身体に病的なこだわりを持つことはしばしばありますが,その由来はこのようなものであると思われます)。
このように人間の悩みは,総じて身体的なものへのこだわりであるといえるようですが,それは身体に発するさまざまな欲望,欲求といったものが満たされていないところに帰着し,人間の宿命としてそれらのものがことごとく満たされることは不可能であるというところに帰着します。
これら本能に由来する身体的な諸欲求のエネルギーが強力であることが,’地を這うもの(鳥は空を飛びますが)’である動物たち一切が,たくましく生存していく上で不可欠といえるでしょう。そして動物達の中で人間だけが,魂を持っています。ソクラテス流にいえば,身体に由来する強力なエネルギーによって確固として’地上のもの(この世のもの)’であるが,一方で神の直系である魂によって,この世的であることからの超越的飛翔(身体から離脱し,自由になる)を目指すものであるといえるように思われます。
Aが後々,先ほどのように意識下に埋没させていた自分の分身を救い出したことは,それ自体が自我が有意義な仕事をしたという満足感につながります。そして甘えたい,身体的に愛撫されたいという潜在欲求が,それなりに解決し,解放されることになります。その分密かにあった母親への依存心からも自由になり,ある意味で母親を許すことになるでしょう。身体に発する欲求に制縛されていた心が,そこから解放されることに応じて,魂はその分の飛翔を果たしたといえます。
この種の満足はいわば白い満足です。言葉を換えれば魂が飛翔する感覚の満足です。それは内在する主体の意向を捉えた心の動きといえ,その分の自我の勝利です。
一方,自我が相変わらず気弱なままであれば,甘えたかった心は依然として怒りと共に心の裏舞台に据えられたままです。そうした折々に,これらの心たちは,例えば過食という問題を起こします。これはいわば黒い満足です。つまり魂の飛翔のない満足です。見方を換えれば,’地を這いずる満足’ということになり,動物的なレベルでの満足です。いずれにしても満足の追求はしないわけにはいかないのが人間です。そして魂性を欠いた黒い満足は,結局は人間としての満足としては虚しいのです。過食など,黒い満足に束の間の愉楽をもとめる者は,それと引き換えに人間としての尊厳,満足という点からは見放されているのです。
人間の人間たる所以である自我の機構的な構造は自然のプロセスの中にあると考えるべきですが,自我の機能はその自律性によって,人間独自の反自然的な世界を切り開く能力を持っているように思われます。その自律性は自然からの乖離,魂の飛翔という特性があるようですが,しかし絶えず自然の支配の中にあると考えられます。自然の大きなプロセスの中にありながら,反自然的な世界を構築するべく宿命づけられているのが,人間の偉大と卑小,あるいは幸福と地獄の理由といえるのかもしれません。人間は自我によって特別な存在者となったといえるもののようであり,一方で自然の全的な大きさの前に,しばしば震撼させられる存在でもあります。その自然の大きさに包囲されているかのような自我は,例えていえば無限の宇宙に浮かぶ一個の星のような存在に見えます。宇宙の大きさの前では,星に例えられる人間はほとんど無に等しく,事実人間の心は絶えず自然の無化作用に脅かされるのです。しかし星が強い光に満ちているかぎりは,自身が無限大の闇に包囲されていることは忘れていられるのです。それほどの光を放つ力を人間は持っています。
こうした人間的特性が,他者との関係,そして自己自身との関係を,欠かせない存在要件としています。つまり自我はそれ自身で自足するものではなく,全的な存在であろうとする可能性を生きるべく宿命づけられています。他者との関係,自己自身との関係は,既に自我の機構の内部に自然そのもののプロセスとして所持していると考えられます。言葉を換えれば,現実の他者および自己自身との関係の可能態を,それぞれの自我は既にあらかじめ所持しているのです。それらを根拠として,現実の他者との関係を生き,あるいは自己自身との関係を模索すると考えることができます。
自我の自己自身との関係とは,言葉を換えれば自我と無意識的自己との関係ということになるでしょう。しかし生まれて間もない自我は,その成長のためには他者の助けを必須のものとしています。とりわけ特別な他者である母親とは,全面依存という関係です。赤ん坊と母親とは全面的に助けられ,助けるという依存関係であり,しかしながら人間の能力として完全な相互依存ではありません。原初的な関係において,赤ん坊のもとめる絶対的な依存欲求が不完全にしか適えられないということの中に,自己は自己自身との関係が確立されていかなければならない理由の根本があります。赤ん坊の自我は母親に全面的に依存しつつ,しかし不完全であり,不完全であればこその依存なのです。この不安定な依存関係が,赤ん坊の心に,信頼と不信,満足と不満足,安心と不安という満たし尽くされない空隙をもたらし,それが自我の発達を促す原動力になります。それらのこともまた,自我の機構的な構造に含まれていると考えてよいと思います。しかし他なる他者としての母親が母性を欠いている場合は,信頼よりは不信,満足よりは不満足,安心よりは不安ということになり,いわば後天的に自我の機構に破壊的な影響を与えると思われます。逆に母親の愛情がいかにも自然的に子に注がれれば,一般の動物とおなじように人間の心もまた自然な発達をしていくに違いありません。しかしご承知のように,人間の心はどうしてもさまざまに自然から遠ざかり,その観点からすると個々に歪んでいるのです。こうした他者による介入,なかんずく母親の介入は人間の精神を反自然的にさまざまに歪めさせるのは必定です。それを改めて自我が引き受けることがもとめられています。歪められた心を引き受ける雄雄しい自我が,その歪みを徐々に解除しつつ,本来もとめられているであろう自己の姿勢を追求していく自己の回復のプロセスが,いわば人生です。
以下は,両親の理想的な愛情の下にあったと思われる方の例です。
患者さんは70代後半の女性です。うつ状態が長くつづき,涙にくれる日々ということで受診しました。うつ病の発症は,初診の1年ほど前になりますが,かつての恋人の訃報に接したことがきっかけとなりました。その男性と別れたのは,50数年も昔のことになります。
彼女の父親は名のある政治家でしたが,歴史的に著名な何人もの学者たちと懇意にしていた人でもあったそうです。その父親は,家庭にあっては自由の精神を尊重し,音楽,絵画などの素養を持ち,子供たちにもそうした素養を身につけることができるように,時間を惜しまず機会を与えました。
子供時代は第二次大戦前のことであり,海外の統治国で過ごしました。大きな邸宅に大勢の男女の使用人が同居して,身の回りの世話をやいてくれました。母親は,「大和撫子の鑑といわれていた」といいます。あらゆる人に分け隔てなく愛情を注いだそうです。
彼女は女子の入学が許された草創期に大学に入りました。「夢子ちゃんといわれていました」というように,「本があれば何も要らない」といったふうでしたが,一方ではダンス,テニスなどのスポーツを好み,ピアノの練習,料理など多方面にわたって生活を楽しみました。留学も経験しています。
大学を卒業するころ,同窓の恋人から,突然,「これ以上つきあえない」といわれたそうです。理由は何も知らされず,また,「訊いてみようとさえしない子供でした」ということです。いわば何不自由のない生活をしてきた彼女は,生活臭といったものがない人です。「二人でいさえすればどんな暮らしでもよかった」という言葉に嘘はなかったでしょう。どんなに貧乏をしたとしても,それを嘆く姿が想像しにくい方です。どういう生活状況であれ,いわば自然に生きていたのではないかという印象があります。彼女の伴侶となるべき人はその彼氏以外には考えらないといい,実際にもその通りでした。何故そう思うのか,言葉で表現するのはほとんど困難でしたが,彼氏が常識的な意味での生活力があるかどうかは問題外のようです。彼女がそのようにいい,実際にその通りだろうとうなづくしかないのですが,そのことは彼女の伴侶となるべき人が,客観的に語れる人格の持ち主というものではなく,彼女自身のもう一つの半分の像をその男性に投射して見ているように思われました。いわば彼女は自分自身に恋したと考えて,ようやく理解がいくのです。
彼女の失恋は周囲の者たちには知れ渡っていたようで,その一人の男性が恋人としての名乗りを上げたのです。彼女はまったくの受身で交際していたようで,「気がついたら結婚していた」のです。
この夫も一流大学で然るべき地位にあった方です。しかし学者然として人を近づけないという感じの人ではなく,浮世離れをした妻の忠実な伴侶といった雰囲気を持っています。この夫なしには,浮世を渡るのがはなはだ難しいように思われるのですが,いつかな夫との結婚を肯定的には見ようとはしないのです。夫を見下しているともいえるのですが,彼女は決して高慢ではなく,自分の感情に単に自然に従っているだけなのです。夫もまた,妻のそうした態度を不快にも,不満にも思わないようで,常に笑みを浮かべながら妻の心情を観察して私に伝えてくれるのでした。
彼女が心を許せるのは,今は亡き両親と,子供たち,孫たちと兄など,血縁関係にある人ばかりのようです。そして肉親以外の唯一の例外は,50数年前に分かれたかつての恋人なのです。
子供たちを育てているあいだは,一途に育児に打ち込みました。そしてそれぞれが独立し,両親も他界したあとは,過去の恋人との思い出だけが心を支えているかのようでした。その男性の訃報に接したあとは,まるで昨今分かれたばかりの恋人の死を嘆くように,時空を超越して涙に暮れるのです。そして生きる理由のほとんどが失われたという気配です。
一日の生活は,「本さえあれば何も困らない」というように,手許にある馴染みのある本を繰り返し読むことで費やされているようです。それは読書三昧というものではなく,既に生きる実質的な理由を失って,形式化されたものであるように思われます。そしてときに縁側に座って庭の樹木や花に見取れます。食欲があるときは,「食べ過ぎて太ってしまった」と気にすることはありますが,食事も気分のおもむくままです。
通院はしていますが,意志的に元気になりたいなどとはまったく考えません。仮に薬などによって元気になったとすれば,それもまた拒むものではないでしょうし,辛い人生という意識も殊更にはありません。自殺という意志的な考えも起こりません。人生の終焉として死が訪れるのであれば,それもまた自然に従おうとする心があるばかりです。
ことごとくに自然の感情に従い,それに逆らうという様子が,この方には見えません。彼女を気遣う夫や子供たちに応えて,少しは生きる努力をして安心させようとする心の動きもありません。それはしかし頑固というものには程遠いのです。外国に住む子供たちから,毎日のように電話がかかるのですが,彼女から電話をかけることは決してありません。しかし子供たちを何よりも愛しています。
生きるため,生活するために,意志的な努力をしない彼女に対して,夫は忠実なしもべのように黙々と必要な役割を果たしています。かなり長期にわたる通院になりましたが,必ず夫が付き添っていました。うつ状態のためということ以上に,電車を乗り継いでの通院が,一人ではほぼ不可能でした。どの駅で降り,どの電車に乗り換えるのか,夫の助けがないと不可能なのです。
この症例の方は,現実にはあり得ない,おとぎ話の世界の主人公のような印象を受けます。子供のころから不安とか不満とかの感情に悩まされた記憶がなく,いわば何一つ不自由のない育ち方をしているといってよいように思われます。それは甘やかされたとか,過保護だったとかという以上に,両親の稀有な愛情の下で成長したというべきことのようです。そしてこの方の心のありようは,考えられるかぎりの自然流というふうに見えます。
この方は両親の保護が物心両面にわたり理想的に行き届いていたために,自然的に生きることが可能だったという稀な例のように思われます。そして一方では,社会性という観点からすると著しく欠けるものがあるといわなければなりませんが,それを意識し,問題視しようとする心の動きはありません。
自然的に生きていくしかないこの方は,確かな関係を持ち得る具体的な他者の存在が失せてしまってからは,ほとんど生きる理由を失ってしまったかのように見えます。両親の死後,両親の霊魂のようなものが彼女の周辺に絶えず漂っているといいます。それは実態的な雰囲気を持つ,守護者です。そうしたことが客観的に実在するものか,それとも主観的,心霊的な現象なのかなどということは,彼女には問題ではありません。単にそういう事実があるばかりなのです。
稀に見る自然流の心を持つこの方には,自我の確立,自立心の涵養といったこととも無縁のようです。
このことから考えると,たくましく自己であろうとすると,他者の歪んだ介入をむしろ必要としているといわなければならないように思います。その他者の歪んだ介入は,まさしく,先ほど述べた偽りの自己の源流となる影の領域の心を作り出すものでもありますが,社会的人格を形成するためには,心内での対立,葛藤が欠かせないもののようです。
いかにも自然流の心でいるこの女性には,影の自己といったものが希薄です。彼女の無意識を探ると第二の自己が表われて問題が回復に向かう,ということはほとんど信じ難いことです。何よりも抑圧されている個人的無意識といったものがあまり問題にならないことが,彼女の場合,むしろ稀有な特徴になるのではないでしょうか。
そのように考えると,影の自己の存在は人間にはむしろ欠けてはならないといえます。そういうものがあるために,それを解決する自我の責任意識のごときものが必要とされるのです。自己が当面している(心の)内外の問題を引き受けるのが自我の本分です。影の自己は他者(特に人生最早期の,最も重要であり,原初的な他者である母親)の介入によって生起するとはいえ,その不可避的に関与してしまっているものを,自我は己の課題として引き受けていかなければなりません。それら影の分身たちによって悩まされながらも,それを引き受ける雄雄しい自我だけが自己を助ける力を持つのです。
影の分身たちを引き受ける雄々しい自我がある一方には,引き受けない自我もあります。影の分身に悩まされていることを意識したがらない自我は,分身たちが存在しないかのような不誠実な姿勢に終始します。そうした欺瞞化する自我を持つ自己を,偽りの自己と呼ぶことは妥当だろうと思います。
逆に真のあり方を志向する自己とは,自分自身が作り出した分身たちの存在に悩まされながら,意を決してそれらの分身たちを引き受けようとし,責任を持とうとする自我に拠る場合といえます。
このあたりの問題は次に上げる男性の例に端的に表われています。
男性は30代です。身分保障に恵まれた職場で専門的な仕事をしています。いわゆる’現場’で対人的な関わりをするのが本来の職分ですが,請われる形で現在の事務職に就いています。彼を招いた先輩が転勤で去り,新しく上司となった人との関係がうつ病を発症したきっかけとなりました。その上司は,彼によればよく怒鳴るのだそうです。男性は上司に認められるとよく仕事ができる人ですが,高圧的な上司の下では怒りが内向して,気力が萎えてしまう傾向があります。職場の問題の他に家庭の問題も重なり,長期間の休職となっています。
男性は旅行を好みます。海外にも何度も行っています。最近,十日ほどの予定で計画を立てましたが,出発の直前まで無気力でほとんど自宅から出られない日々でした(彼は一人暮らしです)。そういう状態で海外旅行など出来るだろうかと思いましたが,何とか飛行機に乗り込みました。そして旅行中はいつになく元気でいられたのです。
男性によれば,十日のあいだに七カ国を回ったのですが,それらの旅行の計画や,不自由な言葉の問題などを,当然のことながら自分一人の責任でやらなければなりません。誰かを当てにすることができず,一切を自分が引き受けなければなりません。何が起こっても自分の責任において解決を図らなければなりません。そういうことが元気を取り戻すことができた理由のように思うといいます。
それでは,そのあたりのことがふだんはどうなっているのか,なぜ不調なのかという問いに対して,職場を含めた生活全般に,誰かが何とかしてくれるだろうといった甘えが,どことなくあると思うといいます。
男性のこの経験は,私流に解釈すると次のようになります。
外国旅行中は,男性がいうように,自分以外の誰をも当てにできない生活状況に自ら身を置くことになります。そういう状況では,自我が一切を引き受ける以外にありません。自我が自己に関わるすべてを引き受ける姿勢に入ることにより,彼が所有しているエネルギーを十分に動員することができたと考えることができます。
一方,日常はどことなしの依存があり,漠然と誰かのたすけによって意欲が保たれ,あるいはたすけがないときは意欲が阻喪されてしまうと考えられるのです。言葉を換えれば自我が自己と生活全般を引き受ける意志を持たず,だれかのたすけを漠然と当てにしているのです。そういうときには,自我は必要な仕事をしていないので,エネルギーは自我の負債ともいえる意識下の分身たちに取られてしまうのです。これら分身たちは自我の力によって救い上げられるのを待っているのですが,自我は当事者意識が希薄で,分身たちを引き受ける心になれないのです。
また別の男性の例では,もともと他に気を使う性格で,与えられた仕事を断ることができず,人一倍頑張る方です。うつ状態で休職になり,やがて復職しました。会社は鷹揚なところがあり,本人が望む限り負荷はかけてこないので,しばらくは人より負担の軽い仕事をしています。会社からの圧力は何もないのですが,男性が仕事をふやさないと申し訳ないと気にします。しかし,「しばしば心にもやもやしたものを感じる」という形で分身たちがその存在を誇示しているのです。この方の場合も,他に気を使うことも大事とはいえ,引き受ける(気を使う)べきものは第一に分身でなければなりません。そうでなければしばらくは持ちこたえることができても,やがてうつ状態が高じる懸念を否定できません。
これらの男性の例に見たように,光の世界を切り開く使命を持つ自我は,不可避的に影の世界(意識下の分身たち)をも作り出す宿命の下にあります。自我はいわば自ら作り出した影に怯え,悩まされつつ,それを超克していく使命を持っています。全的な存在ではないという性格のものである自我は,影ないしは闇をその内に持ちつつ,それらによって自我自身を超えたものの存在を意識します。そのことは,自我が畏怖の念を抱くことができるための内的で根源的理由にもなっています。それは不安と恐怖の根源となるものですが,永遠なるものに対して畏敬の念を持つことを可能にするものでもあります。
偽りの自己と真の自己とを考えるために,万引きを例にしてみます。万引き行為は悪に違いないとはいえ,精神科の臨床で問題にされることが珍しくありません。これは犯罪の中でも悪性度が比較的低く,その問題を治療者と共有できる自我の健全性がそれなりに保たれていることが多いからだと思います。この他者と共有できる自我の健全性の程度が,犯罪の悪性度に大いに関係があると考えてよいでしょう。そして悪性度の低い犯罪は,悪しき依存の一つの形として精神科の臨床の問題となり得るのです。
依存の心の病的な表現である万引きが,悪そのものであるのは論を待ちません。その論拠は法律にあり,また常識的な倫理観にあるとひとまずはいえると思います。しかしそのような人為的な取り決めごとにとどまるものでもありません。そこに更に人為的なものを超越した理由がなければ,説得力も不確かなものになるでしょう。
その超人為的な論拠は,少なくても一つには,自我の境界機能に求められます。この機能の一つに,自己と他者とのあいだに一線を画すということがあると思われます。それが自他を弁別し,それぞれの自己を独立したものとして保証する原理的な理由であると考えられます。(したがって親,特に母親が自分の子の世界に干渉,侵入するのは,誇張的にいえば人権侵犯になります。一般に母親がこの過ちを侵しがちなのは,子が赤ん坊のころに母子密着の時期を経験するからでしょう)
自我機能の基盤をなすと考えられる自我機構は,自然のプロセスの内部にあると考えられます。法律という公共的な規則,規制が揺るぎのないものであるためには,人間の知性が超知性的な根拠の上に成立することが必要ですが,自我機構にはそのような性格があると仮定的に考えることができます。
このように考えると,万引きという行為が悪であるのは,自我がその本分に基づいた仕事をしていないところに問題の一端があることになります。
偽りの自己についても,これとおなじことがいえるでしょう。つまり偽りの自己とは,自我が影の分身たちに対して,本来あるべき役割を果たそうとしていない場合といえます。そのように見ていけば,悪の問題と偽りの自己の問題とは近縁の関係にあることが分かります。
悪性度の低い段階での万引き行為では,人の目を盗む一方で,場合によっては人の目に触れることを望んでいるように見受けられます。そこには,悪性の行為とはいえ,何らかの意味のあるメッセージが込められていると考えられます。
悪の特性に即したメッセージということになれば,望ましい形の否定,いやがらせ,挑戦,脅しなどなどの影の自己の要求を受け入れた行動の形を取ることになるでしょう。それは従来の自己が偽りのものであること,その自己が「(親である)あなたとの関係で生じている」ことを暗に主張しているということになると思われます。
「私はあなたが望んでいるような良い子ではありません。むしろ悪い子です」,「私が家のお金を盗むのは,私がもらうべきものだったもの(愛情,信頼など)をもらっていないからです」,「みんなが一家の主として私を尊敬しないのであれば,私は盗人となって転落します。そうするとみんなは私の存在を少しは認識することになるかもしれない」,「あなたは会社で偉い人かもしれませんが,夫として私のことを疎かにし過ぎていませんか。私が転落するとあなたはうれしいですか,それとも私に少しでも目を向けるつもりがありますか」等々・・・。
メッセージ性のある悪性の行為では,健全な関係が,歪んではいても壊れてはいないことが認められます。そのときに自我の意識は,半ばは関係者に向けられ,半ばは分身たちに向けられています。分身たちのたくらみは,目先の利得,満足の要求です。自我の意図は,分身たちの意向を行動に移すとすれば,関係者との関係に与える影響がどの程度破壊的であるかを計ることです。その程度には分身たちの力に押され,その程度には分身たちを抑える力を残しています。強力な力を持たない自我は,分身たちが求める目先の欲求充足に身を任せる責任回避と,そのような事態をもたらしたと考える関係者を窮地に追いやることの意趣返しとで,暗く危険な愉楽にふけるという側面も持ちつつ,関係者に助けを求めているのです。やがて自我が目を覚ますときは,関係者への愛情と信頼とが回復されているでしょう。そのときに危険な愉楽の試みは,一定の成果を手にしたことになります。
このように,悪は,自我が社会的責任を回避することと,刹那の愉楽に身を任せようとする無責任とで,社会的な位置を危うくさせることになりますが,重要な位置にある関係者に助けを求めているかぎり自我の力が回復する可能性があるといえると思います。そのかぎりでは治療的な介入が意味を持ちますが,刹那の愉楽をもとめて止まない心が大きな障害になります。一般に犯罪は,悪性の依存的行為であるといえる所以です。
幼い心としては,たとえ他人の物であれ自分の物としたい心があって当然です。それを考えると幼い心が盗みを働くのが,なぜ真実の自己の行為とはいえないのかということにもなるかもしれません。その点は先に述べたように,他者との関係で相互の境界が自我の機能に内在しているからというのが根本的な理由といえるでしょう。つまり盗みはいけないという指導は,内的な自然のプロセスに即した理由を持っているといえるのです。
ここに表われているのは二つの側面です。一つは親(という他者)との関係であり,もう一つは自然のプロセスの中にある無意識的自己との関係です。欲しい物を自分の手許に置きたいというのは,そもそもは本能的な自然のプロセスによるものです。そして他者の介入により,その行為の善悪が問題になります。その根拠は介入する他者の恣意によるものであってはならないでしょう。つまり自我の機構に内在すると思われる境界機能に即した他者の介入であれば,恣意によるものではありません。それは正しい指導であり,納得がいくはずのものです。
この自然のプロセスに基づく二つの要求は互いに矛盾します。子供は葛藤に悩むことになります。そして親との関係は幼い子にとっては何ものにも優先させなければなりません。子供は原則的に親に従うしかありませんが,親子の関係が愛情と信頼とで満足できるものであれば,その葛藤の解消は一般に困難ではないでしょう。
ところが親が体罰を加えるなど,度の過ぎた育児指導をしたり,両親の不和,母親の神経質や病気,等々によって,乳幼児期に過度に不安や怯えを経験したりすると,子供の心は親への不満,反感を密かに強めるのは避け難いでしょう。そのような心理にあるとき,他者とのあいだの境界を侵してはならないという自然の心に従うよりも,満足を得たいという自然の心に従おうとするとしても不思議はありません。このような場合にはいずれにせよ幼い心には,満たされない思いの分身たちが大きな勢力を占め,それに伴って強い怒りが内向していると考えなければなりません。
強い怒りが内向するときには,必然的に,不当に満たされるべきものを満たされなかったという思いと,護られるべき安全が不当に無視されたという思いが交錯して内在すると思います。それらは自己が自己らしく生きる上で,是非とも適えられなければならない思いといっていいでしょう。それを果たさなければならないのは自我です。自我がこの苦境を引き受ける雄雄しい態度を取るときが来ないかぎり,分身たちの怒りと不満とによって内側から蝕まれていくことになります。蝕まれかけた心が悪を表現します。それは表の心の営為の中心である自我が不甲斐なく,裏の心の営為に主導権が渡りつつあることの表現です。
この険悪な心的状況をはね返すには,強い自我の力が必要です。
私が,「盗みはしない」と意識し,行動するように努めているかぎり,私は光(正)の世界の住人です。しかしそれは私の正を保証するものではありません。負があればこそ正があるのです。私が行動として負に落ちないためには,自分の正を信じるよりは負の存在について深く思いを馳せる必要があるでしょう。もしかすると,盗みを働いた人に憎しみの情を持つことは,まだまだ心が負に傾く危険があることを知らなければならないのかもしれません。自分の内面に潜む盗人の心を一掃することは不可能である以上(人間である以上は不可能です),盗人を憎むことは自分を憎むことです。考えの中にあることと実際に行動することとは,まったく次元が違うともいえますが,「絶対に私は人の物を盗みません」と断言できる理由にはなりません。むしろ,「その可能性を一掃できないので,よくよく注意したいと思います」という方が自分に忠実といえるのかもしれません。そう考えることで盗みという悪行を許す理由にはなり得ないでしょうし,盗みという犯罪に対して,人間的な態度を取ることができるかもしれません。
盗みはともかく,自己の負性に苦しめられることは多かれ少なかれ避けられず,それを克服するべく引き受けるか,気晴らしをして問題を回避するかということになります。一般的には,そういう意識に囚われていると日常の生活に支障をきたすでしょうから,回避的態度になると思います。
ここでいう偽りの自己に悩まされる意識というのは,それを引き受けたときに意味のある問題になり得るのです。それは人間が何を目指して生きるのかという問いを,自分に対して立てるのとおなじ意味を持ちます。
偽りの自己とは,自我の臆病ないしは自我の欺瞞の犠牲になっているものたちの存在をかかえる自己といえます。
光の世界のものである自我によって影の世界に追いやられたものたちに対する自我の態度には,二通りあります。
一つは雄雄しく引き受ける自我です。一つは女々しく,引き受けない自我です。
前者と後者との自我の営為に対する評価は,自己自身との関係に与える影響如何ということになります。つまり前者への評価は自己の充足感,生気感情の高揚という結果をもたらします。後者への評価は,それとは逆に,自己の不充足感,生気感情の低落という結果をもたらします。
自我の仕事を評価する力を持つのは,自我を超越したものでなければならず,従ってそれは無意識界に内在するはずの超越者といえるものです。それは仮説の域を出ることがない問題ですが,精神現象を論理的に理解しようとすれば,自ずからそれが指し示されているともいえるのです。
偽りの自己とは,その本分に基づいた仕事をしない自我によって影の世界に追いやられたものたちの存在が生じ,なおかつそれらの存在に自我が目を向けようとしないままでいる自己のことです。それは仮説的に述べた内在する主体によって,評価されることがない自我に拠る自己です。そして人間は常に何ほどか偽りの自己であり,そうあらざるを得ない存在であるといえます。人間のあるべき姿は,そのことを絶えず悩み,絶えず問い,そしてそれを克服することといえます。そうすることで一歩ずつ真実の自己へ近づくのです。しかしまた,最終的に真実の自己に合一するところまで自己を克服するのは不可能なのも人間です。そのような自己を人間は生きているといえると考えられますが,自我は’真実なる自己という絶対的な光’に向けて,時々の偽りの自己を克服していく根拠となるものです。そのように,光の世界の演出者という性格を持つ自我が,あえて死を志向するということは考えられないことです。死は自我の無力化,無効化に伴って姿を表すものです。自我は無限または無,あるいは絶対という性格を持つ自然によって無化されるものです。それが死の意味であると考えられます。
敷衍すると,自我が無力化するにつれ,相対的に個人的無意識(C.Gユングによる)が勢力を強めます。個人的無意識は,自然そのものが心に及んでいると考えられる普遍的無意識(ユングによる)と,相互に交流していると仮定的に考えられます。自我が衰弱していくと,自我の負性の特徴を持つ個人的無意識を介して,場合によっては自然の無化作用が自我に及ぶと考えられるのです。
自然自我ととの関係は,宇宙の無限空間とそこに浮かぶ星体に比してみると分かり易いように思います。自我なる星体は,自然なる無限空間の中で,マクロ的に見ればいかにも頼りなげで,ミクロ的に見れば,無限の深みを持つ周囲の暗黒をはね返すほどに力強い光を持っている,というふうに見えます。自我なる星体と自然なる宇宙とは,対立して相互に交わることがないというものではなく,自我の生物学的根拠と仮定される自我機構の中に,自然そのものの特性が及んでいると考えられます。
生まれたばかりの赤ん坊の心は,自然そのものである普遍的無意識と,自然そのものの中にあって自然から乖離する方向性を持った,萌芽的な自我とから成ると仮定的に考えられます。萌芽の状態にある自我は,母親の自我との協働でしだいに機能を高めていきます。この母親との関係は,明確に自然から乖離した次元の上に成り立ちます。母親との関係を最優先とする乳幼児の自我が,無意識から生起する自然のものである心たちを抑圧,排除して,母親が望むような自己形成に励むことになりますが,この抑圧,排除された無垢の心たちが個人的無意識の層を作っていくことになります。
また自我と無意識の関係について,私はしばしば次のような比喩を引き合いにして説明を試みています。
無意識は海であり,自我は小舟の船頭です。日常がとりたてて問題がない人の場合,天気晴朗で,海は凪いでいます。近くには多くの小舟が浮かんでいるのが見えます。天候が怪しくなり,海が荒れても,仲間同士で励まし合い,助け合ってなんとか乗り切れます。仲間たちとの関係で支えられている自我なる船頭は,孤独になったときに容赦なく突きつけてくる’航海の意味’という難題に悩まされることがなく,念頭に浮かべる必要がなく,目前の困難を仲間と共に乗り切ることだけを考えていればいいのです。それは自我の力で何とか乗り切れる見通しの下での困難といえます。こういう自我の下では,海は過激な荒れ方はしないものです。
しかし死が問題となっている自我の下では,天候は不良で,海は荒れがちで,あたりに仲間の船影がありません。荒れる海にもまれて,どこへ向かうとも知れない航海になんの意味があるのかという懐疑が船頭を捉えます。その種の懐疑はもっともなものでもありますが,心細いかぎりの思いでいる船頭が,孤独に船を操る意味を悟るのは至難の業です。実人生のさ中での問いは絶望をもたらすだけです。そういう問いは,実人生から距離を置いた哲学的,心理学的なものでなければならないでしょう。
そのような意味不明の難儀な航海に耐えるよりは,いっそのこと海に飛び込んで航海を終わりにしたいと考えるのも,無理からぬことです。しかしそうすることが船頭の自由かといえば,そうはいえません。それが船頭の意志であるといえるためには,自我がそれなりに自由であり,健全であることが前提になります。つまり航海について創意工夫をこらす自由はあっても,航海そのものをやめるのは,自我が自由にできる範疇の問題ではありません。死は自我の終焉,自我の最終的な挫折です。自我を超えた力,海なる無限,全,あるいは無という性格のものによって,自我は終焉に導かれる可能性を持っています。つまり力尽きた自我が終焉を向かえたときに,死があるのです。死は自我の終焉と同義です。そして無限,または無という性格を持つ自然によって,自我は無化され,回収されます。それは自我が自ら意志してではなく,自我の無効に伴ってはじまる回収作業です。死は自我の意志,自我の決定により自由に選べるというものではなく,抗し得ない成り行きというものです。「死にたい,なぜそうしてはいけないのか?」と問いかける人は,そのような回収作業に取り込まれかけているのかもしれませんが,むしろ生きる意志を持っており,助かる可能性はあるだろうかと反問しているように思われます。より深刻な事態に陥って,死が避けられないと感じている場合は,むしろこのような問いは向けてこないのではないでしょうか。
それでは死を志向する心の中心には何があるのでしょう。
Lさんの例では,首を絞めたり,刃物を突きつけたり,手首に傷を負わせたりしていますが,そこにはもちろん怒りが絡んでいます。首を絞めたのと手首に傷を負わせたのとは,Lさんの言葉によれば,「子供の仕返し」です。子供というのは先に説明したように,母親とのあいだのいわば共犯関係によって犠牲にされ,抑圧された自然的な心たちです。それは理不尽な目にあっている分,当然,怒りと共にあります。内向する怒りに火がついて,自分たちの存在の元凶ともいえる自我に襲いかかったといえます。また自分の胸に刃物を当てることで,「子供を殺そうとした」のは,混乱に陥っている自我の仕業です。
Lさんの取るべき唯一の方法は,怒りを母親との関係に向けることです。それは自我が分身の怒りを受け止めることをも意味します。それが果たされないかぎり幼い分身は,自我によって受け入れられる見込みを持てないのです。自我はまた,それらの分身を受け入れることで,本来もとめられている力を発揮できたことになります。逆に母親との共犯関係を手放そうとしない自我は,怒りと共にある分身を意識下に封じ込めるために多大のエネルギーを費やし,かつ分身が意識下で暗躍するために,多大なエネルギーを奪われることになります。その結果,自我が自己の世界を拡大,発展させていくエネルギーが削がれることになります。
それだけの犠牲を払ってでも旧来の母親との関係を失いたくない自我は,そもそもがよほど怯えているのです。それは見捨てられる恐怖に由来する怯えだと思います。怯える自我はしがみつく自我です。このような事情がありますので,母親との強固な関係の下にあるLさんにはかなり困難な課題ですが,それでもその関係を破壊し,清算しなければ,幼い分身を救い出す手立てがありません。些細といえる刺激で混乱する自我の下では,人生は多難を極めます。どうしても困難な内外の心的状況を,ともかくも自我が引き受ける気勢を示すことは,人生の軌道をただすためには必須です。
このあたりの問題の解決の鍵は,治療者との関係がしっかりとした信頼でつながれるかどうかにあります。それができれば,自我はその姿勢をただすためのひとまずの根拠を得ることができます。
Lさんの母親との関係が現状のままであれば,幼い分身は救われません。自我が勇気を出して内外の状況を引き受けることがないまま,やがて母親との関係も活力を失うと,事態は更に悪化します。自我が更に無気力となると,人間そのものが内部から蝕まれることにもなりかねかせん。そのような成り行きになると,幼い分身が心の主導権を握ることになると思います。自我に分身を引き受ける力も意志もないのがはっきりすると,影の存在である分身たちは闇の世界のもの,死の世界のものの性格を強めていくことでしょう。それは社会性を引き受ける自我が,もはや機能しなくなっているに等しいということでもあります。人生の意味が見失われ,直接に死が志向されるか,闇のものの特徴として悪の色合いを深めていくかということになるでしょう。
その闇のものの中心にあるのは,自我が光の世界の中核であるのと正反対に,裏の自我ともいうべきものです。それは悪をなすものです。悪とは破壊そのものが目的である破壊です。非適応的な破壊ともいえます。他者との関係での一途の破壊は,暴力ないしは犯罪です。自己自身との関係での破壊は,自死が志向されます。
現実的な心の中心である自我が力を失えば,幼い分身たちは生きる方向で日の目を見る機会が永遠に奪われてしまいます。そうなると闇の世界のものである分身たちに,エネルギーの過半が移行します。強力なエネルギーを持った幼い分身たちは,自我を傀儡化して目先の欲求を満たすために自我をあやつり,他者との関係を毀損して傷む心を持たないことにもなっていきます。
この人格全体の主導権を握った闇のものは,社会的に未熟で,対人配慮に欠け,いたって自己本位になります。生きる方向での希望を絶たれたものが持つ恨み,怒り,絶望,羨望といった黒い感情を身にまとい,人品を著しく欠いたものになります。
自我が分身たちとの好ましくない長期にわたる相対関係で衰弱し,分身たちが自我に統合される可能性が事実上絶たれてしまうと,怒りを蓄えた分身たちが悪の性格を帯びるようになり得るのです。そこにあるのは,自己と他者との関係の,そして自己と自己自身との関係の実質的な破壊です。いわば人に迷惑をかけることなど眼中になく,その悪行に悩む自己がありません。
(付言すると,Lさんは彼女を慕っていた年下の女性の死という事態に直面しました。その死は避け難く,予期されたものでした。しかしLさんは,その悲報によって雄雄しい精神になることができました。「彼女はもっと生きていたかったに違いありません。それを思うと私が死を云々することは許されないと思います」とLさんはいいます。人によっては,更に落ち込むこともある状況です。死によってかけがえのない友人を失うという状況で,Lさんの自我はむしろ決然と生きる意志を確かめたのです)
いま述べたように自我が自己形成の表舞台の演出家であるとすれば,挫折した自我の下では,自我のネガである悪の様相を帯びた裏舞台の演出家もあることになります。前者が生または光を志向し,後者は死を志向します。そして後者は,本来は表の自我によって表舞台への登場が見込まれていたものたちを統合するものです。
自己の表舞台の演出家である本来の自我を表の自我と呼び,悪の性格を持つ裏舞台の演出家を裏の自我と呼んで区別したいと思います。裏の自我は,表の自我の衰弱に伴って,永遠に表舞台への登場が阻まれてしまったものたちの怨念を携えて,影の世界での暗躍を画策します。
表の自我と裏の自我とは,ポジとネガの関係にあります。前者が生きることの肯定系であり,後者は否定系といえます。
このように性格形成に関して,二つの首座があると考えるのは,日常の臨床を通じて表われてきた病理的現象に導かれたものです。ですからそれは病理的現象の理解にとって有用なのはいうまでもなく,治療的な手がかりとなるものでもあります。患者さんにそのような理解を伝えることで,患者さんが自分を悩ませていた問題に一定の見通しを持つことができれば,不安のかなりの部分が解消されることになります。またそのことにより,治療者との信頼関係もより安定したものになり,その後の診療を進めやすくなります。
多重人格という病理現象は,裏の自我の演出によると考えられる具体的な例です。明確に多重人格を語る患者さんは,一も二もなく以上の見解に理解と同意を示します。またそれ以外の大方の患者さんも,自分の心の深部でうごめく何ものかの感覚があり,以上のような説明に対して,直感的な理解を示すことが多いのです。
70代のある女性は,神経質症の気味があります。軽度の抑うつ感があり,アモキサンという抗うつ剤をごく少量使って改善しました。本人の判断で,ある時期からは気分が不安定になりそうなときだけ,10ミリグラムを服用しています。それでほとんど問題はありませんでした。
ある受診時に,「アモキサンはたくさん残っているから,今回は不用・・・」ということで処方はしませんでした。ところが家に帰ってみると,いくらもないことに気がつきました。律儀な性格のためか,決められた受信日以外に薬をもらいに行くことにためらいがあったそうです。この間,「うつ病がひどくなって入院することになるのではないか,一生だめになるのではないか」というふうに,良からぬことばかり考えてしまいました。そして明るく考えるよりは,暗く考えるほうがなぜか楽なのだといいます。
アモキサンは,薬理作用としては,たまに服用することで効果が得られるとは考え難く,おそらく気分的な効果だったと思われます。薬が手許にないということで,気持ちが動揺し,抑うつ感にかられたのだと想像されます。「暗く考えるほうがなぜか楽だった」というのは,どう解釈すればいいのか安易にはいえませんが,裏の自我の力に従うのが自然だったというふうに,私には思われました。葛藤に耐え,それに打ち克つのは相当なエネルギーを要しますので,この方は,そんなことよりも自然に従ったほうが楽だったと感じたのではないでしょうか。
Rさんの例に即して考えれば,怒りが母親(との関係)に向けられたことに大きな意味がありました。しかしそれは,一般に怒りが外に向けられることが有意義であるということではありません。Rさんの場合は,自我が怒りを受け入れる準備ができていたので有意味だったのです。怒りは母親に向けられましたが,本人は無自覚だったものの,Rさん自身にも向けられました。Rさんの自我は,自分自身がその怒りによって粉砕される恐怖に耐えることができると踏んだのでしょうし,母親の自我もその怒りによって粉砕されることはないだろうと踏んだのに違いありません。事実Rさんは,「自分の人生を目茶目茶にしておいて,母親面をして欲しくない・・・」と怒りを込めて語っておりましたが,やがては,「その一方では,母親を恋い慕う気持ちもある・・・」と述べております。
この怒りがRさんの意識にのぼる以前は,Rさんにとって怒りは存在しないも同然でした。しかし実際には無意識の世界に潜行していたのはいうまでもありません。そしてRさんが,「ものごころが着いたころから,死を望んでいた」といいます。そのことは裏の自我という’反自我連合’を統合する中核が早々と形成され,勢力を強めていたことを意味すると思います。Rさんの幼いころに母親の気分は特に不安定で,気分まかせに(理不尽に)怒鳴られることがあったようです。手厚い保護が必要であった年代の幼い自我は,母親の自我に必死にしがみつくことで精一杯だったのではないかと推測されます。安全感と情緒的な満足とが保証されることが特に必要な年代で,他でもなくそれらを保証する立場であるはずの母親によって脅かされ,剥奪されつづければ,脅威にさらされる幼い自我は,何を頼りにすればいいのか分からないでしょう。過酷で悲惨な心的状況だったと思います。年端のいかない年齢では,幼い心を引き受けるのは,幼い自我ではなく,主に母親なのです。引き受けられないと感じている幼い心が死を待望するとしても,何の不思議もありません。それでも幼い心は親とのあいだで密着した依存関係にあるので,自我はまだ未発達で,死を志向するほどには分身たちが勢力を強めていないといえるでしょう。幼い子の自死が比較的少ないのは,そのためではないかと考えられます。
これらの表と裏の自我の綱の引き合い(生きるか死ぬか)は,Rさんにとどまらず,臨床場面の随所に見て取れます。
これらのことをエネルギー論の観点から見ると,次のような仮説が考えられます。精神エネルギーの問題は,実証的に証明することは不可能なので,精神科の臨床をはじめ我々の日常の体験を合理的に考えればこのようになるという仮説にとどまるしかありません。そのような仮説を立てることは,精神の構造を措定する作業を補完する意味を持ちます。精神構造についても,自然科学的な意味での実証は不可能です。いわば一つのことを二つの局面から,可能なかぎりで合理的に考察するとこのようになると仮定的に考えることができるということです。
各人の精神的なエネルギーは定量であると思われる。言い換えると,集合的無意識に属するエネルギーと自我に属するエネルギーとはそれぞれ一定量である。前者は身体的なエネルギー,ないしは本能に属するエネルギーと相互に交流をはかりつつ,定量のエネルギーを保っていると推定される。また後者と前者とのあいだにもエネルギーの交流がはかられつつ,それぞれに定量のエネルギーが保持されていると推測される。
自我に属するエネルギーは,個人的無意識を養うために分与されると思われるが,個人的無意識層と普遍的無意識層とのあいだにもエネルギーの相互的な交流があると考えられる。しかしながら個人的無意識層のエネルギーは,本来は自我に留まるべきものであると想定される。つまり自我と個人的無意識層とのエネルギーの総和は定量であると考えられる。そのエネルギーは自我の活動いかんによって,双方に容易に移動すると推測される。
日常的には,自我に付与されているエネルギーが自我によっていわば運用されるが,特別な心的状況では,集合的無意識層にあるエネルギーが一時的に自我に向かって流れ込むことがあると思われる。
たとえば研究者や芸術家のインスピレーションがそういうものであり,いわゆる’火事場の馬鹿力’といわれている危急時の興奮のときにそういうことが起こる。あるいは統合失調症の病的な興奮や躁的興奮状態などの精神病性興奮,もしくは境界性人格障害などの興奮状態などのときにも,そのようなことが起こる。
前者のいわば適合的なエネルギーの移動は,強い感動をもたらします。それは自我が十二分に活動していることに伴うことのように思われます。逆に後者の病的興奮でのそのような現象は,自我に回るエネルギーが極端に少ない状態がつづいているときに起こるように思われます。そうした心的状況では自我が必要な働きができていず,相対的に無意識層の活動が活発化するために,ますます自我は破壊的な圧力を受けることになるのです。そのような状況で自我機構に非日常的な圧力がかかり,何らかの機能的,あるいは器質的な不具合が生じるのではないかと推測されます。それに伴って,自我と集合的無意識層とのあいだの境界機能が一時的にダメージを受け,後者のエネルギーが前者へとなだれ込むのではないかと想定されます。
統合失調症の中核群では,自我の機構に何らかの器質的欠陥が生じていると考えられます。そのために自我の境界機能に不都合が生じ,エネルギーの適量を確保する能力自体に問題が生じていると推測されます。
また統合失調症の中にもさまざまな移行形があります。健常な心とのあいだ,うつ病,神経症,人格障害などとのあいだにも相互に移行する病態があります。
それらすべての問題の中心にあるのは自我であるといえます。自我こそ人間の標章であり,自我の機能的,器質的なざまざまなレベルの様態が,さまざまな病的様態を惹き起こすといえます。
このあたりの問題を二つの例に見てみます。
Mさんは40代の主婦です。
診断名は「うつ病」で,通院歴は10年ほどになります。発病のきっかけの一つは,転居した先の主婦たちが,どれも賢そうに見えたことといいます。私のところには5年ほど通院していますが,初診の半年前に急性妄想状態で入院しております。
Mさんは女ばかりのきょうだいの次女で,一児の母です。彼女は夫を頼りにしており,娘が生まれたときに夫を取られると思ったといいます。子供に愛情を感じず,子煩悩な夫に不満を持ち,夫婦仲は険悪になりました。離婚の危機もあったようです。そもそもMさんは子供を持たないキャリアウーマンが理想と考えていました。実際,子を生まずに海外旅行などを楽しんでいる女性が羨ましくてなりません。結婚後に妊娠したときに,子供よりも仕事を取りたかったといいます。しかしそのことで夫との仲がおかしくなり,やむを得ず退職しました。
Mさんによれば,父親がことあるごとに,もっと勉強してキャリアウーマンになりなさいといっていたそうですが,その父親の一番のお気に入りは,’一番できの良い’妹だといいます。妹は研究者です。両親は将来この妹と一緒に暮らしたいと思っているそうです。長女である姉は,父親とおなじ医療系の専門職についています。姉と妹は頭が良く,美人で,子供のころから仲が良かったそうです。Mさんは孤独感をかみしめていました。家族全員が集まる席で,父が,「お前だけが母親似で,うまくいっていない」といったといいます。しかし両親の仲は大変よいといい,父親が母親を蔑視している節が感じられません。父親がいったというこの言葉がどこまで客観性があるのか疑問があります。
Mさんは仕事を持っていないことに異常に劣等感を持っていました。
娘が6歳になったころに,子供が誘拐される夢を見ました。夢の舞台のRさんは,誘拐されても構わないと思い,娘を捨てて家を出ました。いつかヤクザの世界に迷い込んでいました。その朝,気を失っているのを夫に発見されました。覚醒したMさんは,妄想の世界にいました。興奮が収まらず緊急の入院となりました。妄想の内容は,妹夫婦が加入している某宗教団体に家を乗っ取られる,義弟は学歴詐称をしているというものでした。義弟は国内の有名大学を卒業し,外国の有名大学に留学しています。ちなみに夫も,世間的に有名という意味では弟以上の大学の出身者です。Rさん自身は,私立の有名大学の出身です。Rさんも留学を望んでいました。姉妹たちは共におなじ高校(進学校として有名)を卒業しています。Mさんと母親とは資質的に文系で,他のきょうだいは父親とおなじ理系の大学を卒業したことを,Mさんは偶然以上のものとしてこだわりを持っていました。母親の家系には,知的で自由な職業についている人が多いそうです。そして母親自身は大学を出ていません。Mさんによれば大変頭が良い人で,全国的に有名な進学校の卒業生です。大学に進学しなかったのは,「女に学問は要らない」という父親の考えのためといいます。母親の学歴コンプレックスの犠牲にされたと考え,子供時代を,「下らない受験勉強に終始した」ことを悔やんでいる様子を垣間見せたこともあります。しかし別な機会には,母親は物事に囚われず,明朗闊達でスポーツを好み,感性が豊か・・・と称揚します。Mさんが語る父親,母親像には,一貫性が欠けているように感じられます。Mさんはむしろ聡明な人のように思われますので,このような混乱は無意識下のコンプレックスの影響を受けているのだろうかと想像されます。自分の子にも,下らないといって憚らないMさんの過去の人生の軌跡を,そのままたどらせようと躍起になっているところがありました。この矛盾については,父親の意向に抗せなかったと説明します。また,子供のころは父親を疎んじていたが,母方の親族の女性問題を軽蔑し,父親を高く評価するようになったといいます。また別な機会には,父親の生活姿勢には,何一つ問題のないしっかりした人と子供のころから思っていた,ともいいます。
Mさんの娘は,「私と対照的な能天気で,勉強などは気にかけずに,テレビを見て笑い転げるような性格」です。ある時期までは,「受験勉強に打ち込もうとしない・・・成績が伸びないのに平気な顔をしている・・・」と苛立ち,落ち込んで,娘の成績に振りまわされている様子が顕著にありました。しかしその様子に変化が見られ,受験に駆り立てる母親に,「おかあさんは,どうしてそんなに心配するの?私は何にも心配していないのに」と不思議そうにいうと,娘の立場を理解する様子が見えてきました。
Mさんが自分で嫌っている人生コースに,躍起となって幼い娘をはめ込もうとしている様子からは,Mさん自身の子供時代の母子関係が表れているように思われます。Mさんがいうように娘は能天気であるらしく,それは娘とMさんのために,喜ばしいことといってよいでしょう。またMさんの夫は,「お前みたいな下らん奴が出た学校に,娘を入れようとするな」というそうです。それをMさんは忌々しいとは捉えていない様子です。
結局は娘は公立の学校に進むことになりました。私立校への強かったこだわりを捨てることができたのは,一つには母親の苛立ちを一向に気にかけずに,’能天気’であるらしい娘に助けられたといえるのかもしれません。そしてこのごろのMさんは,キャリアウーマンへのこだわりも少なくなったといい,さばさばしているように見えます。日常の生活が結構楽しいと,かつては聞かれなかった感想をもらします。
先に上げた夢は,Mさんの葛藤を表現しています。
Mさんは他を羨み,自分にないものにあこがれる傾向が顕著でした。母親とは,「きょうだいのような仲」といいます。これは一見すると微笑ましい親子関係の表現のように見えますが,母親とのあいだに強い相互的な依存関係があることを暗示しているように思われます。言葉を換えれば母親を母性豊かなものとして尊重していない表現のように見えます。母親にMさんと共通するものがあるのは確かかもしれませんが,Mさんの自律的でない自我は,母親に同一視する(母親の自我にしがみつく)ことで平衡を保っているように見えます。
「きょうだいのように(母親と)仲がよい」というのは,若い女性からしばしば聞かれる言葉です。ここに共通しているのは,母親から独立し,自由になっていない心です。そしてそれが問題であるとは考えたくない様子が見えます。いわば母親にしがみつき,それを手放すと自分が立ち行かないという気分であるように思われますが,そういう認識の言葉を聞いた記憶が希薄です。このことには母親自身も一役買っているように思われます。そこにはかつて幼いころに得られなかった母親との蜜月関係がようやく実現できたという気配があります。(一般に,摂食障害や自傷行為が仲立ちになって,このような母親との蜜月関係が形成されることが珍しくありません)
母親に同一視(自律性を欠いた自我が母親の自我にしがみつく)するMさんの心を支配するのは,父性原理とでもいうべきもののようです。「父親は非の打ち所がなかったので,父親のいうことに逆らうことができなかった」といいますが,Mさんがイメージとして描いている父親からは,父性としての豊かさが感じられません。むしろひどく幼稚な身勝手な父親に感じられます。Mさんには懲罰的で恐ろしく,到底逆らえないものとして父親イメージが屹立しているようです。そのイメージの父親は,Mさんに怒りを持っていて,子供たちの中で最低位に価値づけされ(ということは無価値に等しい感覚になります),駄目な奴と思われているというふうなものです。それへの反作用として,それに相応してMさんの心にも強い怒りがあると考えられますが,父親を美化して心を護っているMさんにはそういう認識はありません。その父に認められることは到達困難な理想という形で,父親に拝跪する姿勢で内外の怒りを和らげようとしているように見えます。
客観的に父親は暴力的でもなければ威嚇的でもなかったようです。Mさんが自我の自律性を捨てざるを得なかったのは,記憶の届かない早期に体験した恐怖があったからに違いありませんが,それはむしろ母親との関係でのことではなかろうかと想像されます。幼い時代のMさんの自我がとった防衛的戦略は,一方では母親との同一視で,一方では父親の理想化ではなかったかと思われます。何を防衛したのかといえば,むしろMさん自身にある強い怒りと,それと恐らくは関連するだろう見捨てられる恐怖とに対してではなかろうかと推量されます。そのように内在する強い恐怖と怒りとの投影をまじえて,畏怖する父親像が生じ,「きょうだいのように仲のよい」母親像が生まれたのではないかと思われます。このようにMさんの自我は,父親と母親の自我のまったくの支配を受けています。子供のころは父親に反抗的な気分を持ったといいますが,ある時期から自我は自立と自由への途を断念し,父親に迎合する方向に転換しました。主体性を放棄した自我は,自分を助けるものを他に求めなければならなかったのです。
助けを求めたのは,一つには母親です。「きょうだいのように仲がよい」という形で,母親との依存関係を絶えず確かめる途を進んできました。それが,「勉強に明け暮れして,他の楽しみを知らない下らない人生」を選んだ理由の一つで,一方では,「母親の学歴コンプレックスの犠牲にされた」という密かな思いです。これも母親との関係を壊すわけにはいかないので,声高には叫ぶことができません。感性を共有すると信じているMさんは母親をコンサートに誘うなどしますが,そういう折に母親がMさんの姉妹たちのことを話題にするとたちまち不安に駆られます。
一つには夫です。夫にはMさんが描いている理想を託しているところがあります。しかし夫は実家の方に心が斜傾しているようで,Mさんには少々遠い存在です。Mさんが自分の両親と一緒に暮らしてくれる気があるかと訊いたときに,断られました。夫は世間的に有名な学歴の持ち主です。しかし義弟は留学をしているので,そちらの方が一等高いものとしてMさんを脅かします。そして義弟の妻であるMさんの妹は,「美人で,頭が良くて,羨ましい職に就いていて,父親の大のお気に入り」なので,Mさんにとっては何から何まで敵わない人なのです。義弟は学歴詐称ではないかと妄想の中でこき下ろしにかかっています。そして密かに第一等でありたいという野心を抱いている(Mさんは,「白雪姫」のお妃に自分はそっくりだといっています)Mさんの自我は,かれら夫妻への羨望で破壊されそうなのです。それが義弟たちが入っている宗教団体に家を乗っ取られるという妄想になって表れています。
一つには娘です。Mさんは母親の特権をふるって,娘を自分の写し絵にしようとしました。娘を自由に支配することは,支配を受けないでは立ち行かない自我の歪んだ戦略といえます。歪ませたのは無意識界に膨れ上がっている負の分身たち(コンプレックス)といえるでしょう。自律性と主体性を欠いた自我は,外では父,母の自我の傀儡となり,内では怒れる分身たちの傀儡にならざるを得ないのです。分身たちによって傀儡とされた自我は,娘に対しては黒く彩られています。それは父,母に対しては拝跪する姿勢(よい子)で,あくまでも白い彩を演出(黒い欲求を隠す)しているのと好一対です。
自我を傀儡化している分身たちの要求は,「世界で一番美しい(女性として価値がある)のは私であるべきだ」というものかと思われます。それは自己愛が怒りと恐怖によって病的に肥大化して,意識下の潜勢力となったものです。人に認められるものは私には何もないというのが表の意識ですが,誰よりも高い価値を持っていると認められないのは不当だ,というのが裏の意識です。自律性と自由とを欠いている自我が描く理想的な自己像は,Mさんがたどった人生の軌跡の正確な再現でしかないのです。意識下の潜勢力が,傀儡化した自我を操って,そのように自分が果たせなかった(父親の)期待通りの人生コースを娘によって実現させようと企てたのです。それは娘の人格と人権とを無視した冷酷で,愚かしく,悲しいイメージ図に娘をはめ込もうとしたのです。
一般に自我の自律性と自由とが失われて,無意識の潜勢力の傀儡となっているときの特徴は,社会性と精神性の欠落です。
Mさんを助けたのは夫と娘だったでしょう。娘はMさんが躍起になって従属させようとしても,一向にへこたれない’能天気な’強さを持っていたようです。そしてその娘を夫が支えています。娘に対してあまり無理なことをすると,夫との関係にひびが入りかねません。夫に対しても理想化要求があるのですが,元は他人であるという事情のために父親に対してのような理想化には至ることはありません。頼りにしつつ現実的な距離があるので,Mさんの自我は夫との関係では自由になるのです。また思い通りにいかなかった娘に対しても,結局,一個の独立した人格として認めざるを得ませんでした。娘の自我を自分の自我の傀儡に仕立てようと躍起となったのですが,幸いにして娘は自由になりませんでした。結果的に娘に対しても,娘の助けによってMさんの自我は自由になることができたのです。
かつて妄想状態に直結した夢を見たころのMさんの自我は,このように自由ではありませんでした。
夢の世界で,誘拐された娘を捨てて家を出たのは,自由を求めるという意味があったと思われます。しかし夢が提示するMさんの自由とは,到底その名に値しないものでした。粗野で暴力的なカオスの中に身を投じる映像が,夢が提示したMさんの自由のイメージでした。それはMさんの自我が到底受け入れることができる代物ではありません。傀儡化したまま固化した自我には,自由を描く術がありません。自由という高度な精神性は,自我が自由であることと一対のものであるだろうからです。Mさんの自我が夫と娘とに助けられて,おもむろに自由を回復させていく過程で,Mさんの精神の自由が現実のものになるでしょう。そのときに夢が提示する自由のイメージは,まったく別種の,Mさんの目を開かせるプレゼントといったものになるのではないでしょうか。
中年の主婦であるNさんは,両親への依存心,攻撃心を強く内向させている人です。夫の両親である義父母は,Nさんを終始温かく見守っているようで,特に義母を頼りにしております。不安に駆られると,毎日でも義母に電話をしているようです。Nさんの話を聞いていて,義母の根気のよさには頭が下がる思いがします。そして義父母と絶えず比較して,実父母への怒りを抑えきれなくなるのです。
あるときに憑き物が落ちたように平静になり,一定期間,それが保たれます。
繰り返しうつ状態が訪れ,そして一定期間それが回復します。その過程で,統合失調症と区別がつかない状態になり,それが長期化するということも一度ならずありました。
彼女は,「すぐに治してほしい・・・」という姿勢を一貫して変えられません。心の治療は外科医のようにはいかない,本人が自分を助けるのを助けるのが,われわれ心の治療者の役目ですと,いくら説明しても,「先生のいうことは難しくて分からない」とうまく理解してもらえません。Nさんが望むのは,魔術的な治療なのです。実際,祈祷師を訪れたことがあったようです。
「こんなに辛い気持ちで長年通ってきているのに,いつまで経っても治らない,ここに来るのがいやになる」と焦る彼女は口癖のようにいいもします。実際,長年にわたり堂々巡りが繰り返されているので,何度か転医を勧めました。しかしそれに応じることもありません。
ようやく回復が確かなものとなったように見えたあるとき,「自分の力を信じるということがどういうことか,やっと分かりました。先生のおかげです」というのです。彼女は,「夫に,おれは精も根も尽き果てた,離婚したいといわれた,それがきっかけだった」と明るくいうのです。
「離婚のことはしょっちゅういわれていたが,どこか高を括っていた。しかし今度はヤバイと思った」といいます。つまり他の力を当てにしつづけてきたが,今度こそは自分が引き受ける以外にないと決意したというのです。
Nさんのこの他の力を当てにする基本性格は,心に潜む幼児性の影響を受けたもののように思われます。これはごく幼いころに,満足感を得られなかった何らかの心的状況があったことに起因していると予想されます。そのような小児心性は,乳児期の幻想的な全能感,全能要求に由来し,それらの約束を母親(父親も)が履行していないという怒りと不満とがあっただろうこと,しかしそれを上回る恐怖心が働いて,幼い自我がそれらを意識下に抑圧し,潜在させたまま成長したことによるのではないかと想像されます。母親(父親)への不満,怒りよりも恐怖感が優先するときに,幼い自我は親の自我に迎合して共犯関係に入るので,満たされなかった自然的な欲求が,怒りや不満と共に抑圧,排除されて心の裏舞台に追いやられることになります。
それらの全能幻想は乳児の自我に内属していると,仮定的に考えることができます。それは母親の胎内にあるときの充足性と,出生後の不充足性との落差を埋めるものです。
出産に伴ういま述べた落差は,’1000メートルの降下’と比喩的に考えてみると分かり易いように思います。つまり赤ん坊が生まれるときに経験するのは,まったくの充足である母親の胎内という洞窟から出るように促されて,1000メートルの高みに立たされるようなものではないかと想像されます。まともに落ちればショック死があるのみなので,それを回避するためには,現実を引き受け,直視する力が身に着くまでのあいだ,何らかの幻想的なクッションが不可欠であろうということです。その幻想は,十分な満足感と安心感とが与えられると約束された感覚であるように思われます。それは母親の胎内にあるときの充足感に匹敵するものを保証するものです。
満足感の追求は動物一般に認められる本能的な欲求(フロイトをはじめ精神分析的には欲求という言葉は使われず,欲動といわれることが多いようです。欲動の方がより身体的であり,欲求には精神的ニュアンスが込められているからかと思いますが,あまり厳密に言葉に捉われる意味はないようにも思われ,日常見慣れた欲求をここでは使います)ですが,人間の場合も同様です。人間が動物と違うのは,’自己満足’という言葉があるように,他者と共有できる満足,換言すると精神性と社会性とを携えた満足の追求がもとめられることです。それが自我の主要な仕事であり,かつ人生の主題であるといっても間違いではないでしょう。このように他者とのあいだで共有できる満足の追及が重要であることは,逆に他者によってその追求が困難にされるということでもあります。
他者は自我が仕事をしていく上での欠かせないパートナーです。しかし他者の介在を不可欠とすることが,自我が自分の仕事を遂行することを混乱させる要因です。
このことを敷衍すると,以下のように考えることができます。
生まれたばかりのときは,心の全体が自然のものです。自我の役目は,これら自然の心たちをいかに護っていくかということです。しかし一個の自我が独立して機能することは不可能なのが人間の現実で,自我が機能していく上で,他者の関わりを不可欠なものとしています。それは外部的な他者の助けを必要としているという以上に,自我の機構に他者および異性が内属していて,自己の無意識層に内なる他者または異性を構造的に含んでいると考えられます。そのために自己の内と外とで,他者または異性が呼応し合える関係にあります。そして一方で外なる他者は,自己と異なる存在であり,いわば何を考えているのか計り知れない存在でもあります。ですから他者はいかに善意の持ち主であっても別個の存在であり,当人の自我が自己のために最善を尽くすような意味では,当人のために他者が最善を尽くすのは不可能です。自己の内と外の他者の呼応性というかぎりで,他者は頼りになりますが,外なる他者が不可知であるかぎり,時によっては悪意の他者でもあり得ることになります。そのような他者の意向を受けて,とりわけ幼い自我は葛藤し,混乱するのを避けることはできません。つまり自我が自分の内部の自然な心たちを自然のものとして護り切ることは不可能です。
以上のような事情から,自我は心の自然な欲求を護ることができたときには,いわば白い子を生み出し,護り切れなかったときには,いわば黒い子を生み出します。黒い子を生み出すのは,自我の不始末ということになります。
このあたりのことを以下の例によって見てみます。
ある家にぶどう棚があるとします。秋になると美味しいぶどうがなります。その家の幼い子(A)が友達を連れてきてぶどうをご馳走します。Aは友達に満足を与え,自分も満足します。それが得意でもあります。ところがあるとき母親に見つかり,叱られます。Aは友達の前で叱られて恥をかき,自分の威厳が下がったような気がします。
母親に見つかる前は,Aは美味しいぶどうを友達と分かち合う楽しみを味わいます。そのとき一人で食べるよりも,更に大きな満足を得られたに違いありません。Aはその場の主人公であり,ぶどうという満足をもたらす力を自分のものとしています。この場合Aは小さな権力者です。ところが母親に見つかってしまえば,ぶどうの本当の持ち主は自分ではないことが暴露されてしまいました。権力者の座から失墜したのです。このときからAは少々元気がなくなりました。
母親の関与がある前は,Aは美味しいぶどうを友達と分かち合う満足を得ました。ここには社会性を帯びた白い満足を,幼い自我が引き出した意味があります。しかし母親の関与により,本来は自分のものではないものを自分のものとしたことが暴露されました。そのとたんにAがしたことは,社会性を失い,黒い満足になってしまいました。
Aの自我が試みた仕事は,美味しいぶどうを仲間と食べたいというかぎりで,自然な欲求を充足しようとしたことです。しかし人間社会の掟では,他者(ここでは母親)への配慮を抜きにすることは許されないという理由で,Aは心を護ることに失敗したのです。
これが自我が単独で機能することができないという具体的な例です。そして敢えてそれを試みると,未熟な自我という汚点を残すことになります。つまり自我が社会性を帯びた成熟性を発揮するためには,他者の関与を踏まえないわけにはいかないのですが,それは自然の心の欲求との激突を避けられないものでもあります。
それではAはどうすればよいのでしょうか?
Aのテーマはぶどうを仲間に振る舞い,喜んでもらいたいということです。そしてそれとは別の意図が入っていた可能性があります。Aは功を焦るあまり,自分のものではないものを自分のものであるように振る舞ってしまったように見えます。Aの目論見は,「自分の力によって仲間たちと共に満足することを演出する」ということのようです。Aは自分の力を示したい,人に認めさせたいと,少々権力的になってしまっているようです。Aが内心で望んでいるのは,母親にもっと認められるべきだという不満足の解消だったかもしれません。「ぶどうを好きなように食べていいよ,ぶどうはAのものだよ」,と母親にいってもらいたかったのかもしれません。その心はもっと幼いころに母親に十分に甘え,自分が愛される価値があることを母親に認めて欲しかったという不充足感に発したのかもしれません。母親に十分に甘えることは,その後のあらゆる満足感の源泉であり,基礎になることのように思われます。Aはそういう意味で母親に不満があり,ぶどうは僕の物だという隠れた意識を持っていたかもしれません。そうであればぶどうを仲間に振舞ったのは,母親への挑戦であったという面を持つことになります。Aは母親に叱られ,ぶどうはAの物ではないといわれました。権力者の座を目指したAの面目は丸つぶれです。Aは口惜しい思いをし,腹を立てたことでしょう。
このように見てみると,Aはこれでよかったのだということもできます。何故ならAは,自分の分身である母親に甘えたい心を見捨てなかった(抑圧しなかった)からです。幼い時代に甘えたい心が満たされなかった不満をいだき,改めてその不満の表明と解消とをもとめる心が,仲間とぶどうを食べるという行動の隠れた意味ではなかったかと考えることが可能です。そして再びその目論見を母なる他者によって封じられたことは,自我の不始末ということになります。しかし自我は常に即座に成功を収めることは無理であり,必要でもありません。いつか成功を収める機会を得ればよいのです。怒りと共に心に内在している満たされなかった甘える心が自我を圧迫し,苦しめるでしょうが,それを持ちこたえる強さが自我にあれば,いまは負であるそのエネルギーは,機が満ちたときに一気に自我の仕事を支える正のエネルギーに変換されるのです。そのときに意識の下部で自我に圧力をかけて催促していた欲求が,自我によって満たされることになります。母親によって失墜させられたAの野心は,その後のAの人生への取り組み方しだいによって,むしろ使えるエネルギーなのです。大きな負荷をかけられて撓んだバネが,あるとき一気に反撥するように。
以上のように,自我の目論見が他者によって退けられたときに,自我は無意識からの圧力を受けることになります。自我はその圧力に耐えなければなりませんが,耐え難く傀儡化する自我と耐える自我との差は小さくありません。無意識の力の傀儡となった自我は,未熟で社会性を欠いた思考や行動になることが避けられません。耐える力を維持することができる自我は,次の機会に備える能力を温存しているといえます。
いまの例でいえば,幼い自我が母親をおそれて甘えたい心を満たせなかったとき,自我は二つのものに捕捉される,あるいは傀儡化されてしまう可能性があります。一つは母親で,一つは無意識の世界に抑圧,排除した分身たちです。母親をおそれて取り入る自我は,いわば傀儡自我であり,主体的,自立的であることをあきらめています。傀儡自我の下では,自然のものである心の諸欲求(白い子)を護りとおすことは困難で,引き受けを拒んで無意識の世界に抑圧,排除することになりがちです。自我が護ってあげられなかった無垢の欲求は,自我によって死の宣告を受けたのに等しいことになります。言葉を換えれば,白い子を黒い子にしてしまったことになります。黒い子を作り出したのは自我の不始末ということになり,黒い子たちをおびただしく作り出してしまった自我の下では,自ずから不甲斐ない,自分は駄目な人間だという思いにかられがちになると思います。そして黒い子たちが強力化すると,自我はそれらの勢力に捕捉されて,再び主体性と自立性を放棄するしかなくなります。このような事情にある自我の下では,Aのように仲間を集めてぶどうを食べるよりは,人目を盗んで一人で食べることになるでしょう。
人に認められる,愛される,信頼される,受け入れられる等々のことは,他者との関係での要点ですが,その原型となるのは(主に母親によって)甘えが十分に満たされることではないかと思われます。精神の未発達な赤ん坊が母親との関係を通して得られる満足感は,身体的なものです。甘えることの原型は,抱かれる,愛撫されるなどの身体的な接触を通じた満足感です。それへの欲求は身体的なものであるだけに,強いエネルギーを秘めたものであるといえるでしょう。そういうことが基礎になり,長じて愛される,信頼される,認められる,受け入れられる等々の,より精神性の高い満足をもとめることになります。
甘えることの原型は,身体的な満足感(フロイトの快感原則)をAがBに求め,Bがそれを満たしてあげるという関係で成立します。それが本能的なものである証拠の一つに,動物も人に甘えることを上げることができます。
動物の場合は,心地よさを人に求め,満たしてもらうという身体的な次元での満足に留まっているように見えます。しかし動物の側で人を信じることがなければ,甘えることはありません。人間の側でも噛まれるなどの怖れを持たないので甘えを受け入れることができます。人は動物を可愛いと感じ,もしかすると可愛がられているという感じが動物の側にもあるかもしれません。このように人と動物とのあいだでも信頼とか愛とかの精神性の萌芽があるように思われます。
母親と赤ん坊の場合も,甘えの原型としては本能レベルで赤ん坊が身体的な接触を求め,母親も半ば本能的に赤ん坊の身体を抱き,愛撫します。両者はその身体的な触れ合いの満足感に没頭します。イギリスの精神分析医であるW・ウイニコットは,このことをマターナル・プレオキュペーションと呼んでいます。この両者の関係で,母親の助けの下に赤ん坊は甘えを満たすことができます。すべての満足感の基礎と思われる甘える満足は,母子の特別な二者関係において成立し,そこには両者のあいだに,身体的な強い満足感と信頼と愛情という精神的な強い満足感とが体験され,それは母子共々に至福のときではないかと思われます。動物も人に甘えることがあるようですが,赤ん坊が動物と決定的に異なるのは,自我に拠るものとそうでないものとの違いです。赤ん坊の甘えも,生まれて間もないころは動物と同じように身体的なレベルに限局したものです。それが自我の機能の発達に伴い,徐々に精神的な様相を深めていきます。そのことは甘えを求め,それを受け入れられ,満たされるという受身的に見える満足追求の行動が,実は主体的なものであるという意味につながっていくことでもあります。母親によって身体的に心地よい満足感を与えられることが,実は赤ん坊の心の親ともいえる幼い自我が,母親の協力を取りつけることに成功し,自分で心の子である甘えを求める欲求を満たすことができたといえるのが重要であるように思われます。つまり満足感を得たのは,赤ん坊自身の自我によってであるという意味が大切であると思います。母親は欠かすことが出来ない重要な役割を果たしていますが,赤ん坊の甘えるという満足感を獲得する主体者ではなく協力者に過ぎないのです。つまり赤ん坊が母親に十分に甘えることができたということは,人間の満足感の追求が身体レベルにとどまらず,精神的な満足への広がりをみせ,それは他者との関係での満足感と密接不可分であり,将来,一切の満足感を得る上での基礎になります。
赤ん坊が甘える満足を満たされたとき,母親によって自分が価値ある者,大切な者等々として受け止められているという満足感を諸共に経験することになります。そのとき両者のあいだには,信頼と愛情が共有されています。
赤ん坊が母親から信頼され,愛されているのを体得するのは大変重要なことですが,それは幼い自我が甘えるという満足感を自分の力で得る上で欠かせないことであったからともいえます。この重要な心の作業を(母親が)理解し,協力してくれたのは,信頼と愛情とによってであるに違いないからです。仮に母親にネグレクトされるなどのことがあれば,赤ん坊は恐怖と不満足感とで恐慌状態に陥るでしょう。何よりも母親の助けを得られないと甘える欲求を満たす術がありません。ここには愛情と信頼との欠落があります。最も頼りとする母親から何がしか見捨てられた体験を持つと,その後の人間関係に強い影響を与えます。自分は人に受け入れられないかもしれないという怯えが生じやすく,自我は心の子であるさまざまな欲求を無意識的に,自動的に抑圧することになるでしょう。当然それは性格形成の上で大きな問題を残すことになります。
心の親である赤ん坊が,心の子であり,自然のものである甘えたい欲求(白い子)を満たすことができれば,白い子を白い子として護り通すことができたことになります。そして母親の協力が得られず,甘えるのを断念したとすれば,幼い自我は白い子を護れず,意識の裏舞台に追いやったことになります。自我は心の子である甘えを求める欲求を護ることができず,いわば死の宣告を与え,黒い子にしてしまったことになります。
母親に愛されていない(幼い心は,きょうだいたちの中で,第一等の愛を要求します。それが得られていないと感じると,愛されていないのに等しい感じを抱くのです)と感じる子は,甘えを満たすことが更に難しくなるでしょう。それは母親への不信感に直結するでしょうし,一般に対人不信に陥る十分な理由になります。愛されていないと感じている子の一番の問題は,対人不信に陥りがちであるために,自我が甘えを満たす術を失うところにあります。それは自我が不始末を繰り返す意味を持つ上に,自分が愛され,信頼される価値がなく,人に認められない駄目な人間であるのを絶えず確認していくことにもなり,心が転落していく理由になります。
幼い時代に甘える欲求が満たされる体験をしていれば,自我は白い子を護ってきたという自負心を持つことができているので,後々,対人的にストレスに見舞われても回復は速やかでしょうが,甘える満足に欠けるものがあれば,次々と黒い子を生み出してしまう悪循環に陥ることになるかもしれません。
このように人間も含めて動物一般の基本的な欲求は満足感の追求です。動物と異なって人間は,本能的,身体的なものの他に精神的な満足の追求が欠かせません。動物体としての人間が,動物としていわば地に根を張った存在でありつづける上で,肉体的,本能的な満足への欲求は強力である必要があり,事実そのとおりです。そして一方では,成長するにつれ精神的な満足の追求が不可欠の要請になっていきます。身体性と精神性とのあいだでの相克,葛藤は,とりわけ思春期にあって甚だしく,しばしば内的に深刻な問題になります。
いずれにしても自我の役割は,身体的,本能的欲求と精神的な満足との相克に悩まされながらも,身体的な満足からしだいに精神的な満足へと比重を変えていくところにあるでしょう。
自我は満足感の追求の履行者の立場にあります。何であれ行為するときは自我が方針を決め,欲求の協力を促します。両者の協力関係の下に意志が確かめられます。意志の根底には欲求があり,何かを始めようとするとき,自我は自動的に欲求に呼びかけると考えることができます。欲求はその都度新たに生まれるものです。そういうふうに考えると,いわば心の親である自我が,子供である欲求を大切に護っていくことが重要です。邪念に駆られていったん始めようとしたことを中断するようなことになれば,欲求の立場からすると,要請されたり不要とされたり,いわば迷惑な話になります。このような頼りない自我の下では,自我自身が自信を失くしているでしょうし,気まぐれにもなるでしょう。欲求もまた,容易には生じにくい状況といえ,要するに無気力になっていきます。
ソクラテスは,身体の心配をするよりは魂の世話をすることが肝心だといっています。また愛知の精神を尊ぶ彼にとって,哲学は人間の仕事の最上位にあるものですが,「我々は日夜死ぬための練習のために哲学をしているようなものだ・・・」といっています。また,「人間は囲いの中に囲われているようなもので,当然,囲いの番人はいる。人間の究極の目標は身体を去ることで囲いを超えることだが,囲いの中で勝手に死ぬようなことは,番人にとっては許し難いことだろう・・・」といいます。
この考えに組するかどうかはともかく,人間の存在様態を端的に捉えている一つの典型といえるのではないでしょうか。
そのことを煎じ詰めると次のようになるかと思います。
人間が生まれたときは,満足感の源泉は身体的なものにある。しだいに成長するにつれて精神的なものに比重が移り,身体と精神との満足追求の対立が激しくなっていく。自我がうまく成長するときには,この対立を止揚して新たな統合を達成していくことができる。見方を換えると,対立に伴う強いエネルギーに一定の意味のある方向性を与えることに成功する。そして最終局面に達して死を向かえるときに,身体が滅び精神のみの存在となる。それはソクラテスのいう囲いを越えることであるが,囲いの向こうに何があるのかは,人間の窺い知れない問題である。
精神的に満たされることが人間の場合は決定的に重要ですが,身体性の裏づけを欠いた精神性というものはありません。身体的に満たされる体験を,乳幼児期にしているかどうかは重要です。自我の未発達な赤ん坊の安心と満足とは,母親とのボデイコンタクトを通じて得られます。それに従って,愛されるという精神的な満足を受動的に経験します。愛されるに値する自分とは,まずは身体的に満たしてもらうという経験に由来します。そういうことを経験して,自我の機能が発達していきます。
以上のような意味で自我が健全な発達をしていないと,過食症やアルコール症のような黒い満足の追求に向かうことになるかもしれません。心の病的な現象は,大多数が幼いころに満たされなかった心に由来しており,それは同時に身体を通じて愛された体験が希薄であることを意味しているように見えます。
過食症は,満たされない心を代理的に食べ物で満たそうとする病的心理現象です。これは乳幼児期に甘えが満たされなかったことに関係があるようです。幼い自我が母親との関係で何らかの恐怖心を抱き,甘える心を護れなかったことに起因すると思われます。この幼児心性がことごとく過食に向うというものではありませんが,自我によって抑圧された甘える欲求は,いわば見捨てられて死の宣告を受けたことになります。自我に護られることで心の表舞台に乗せられ,精神性と社会性とを備えることになります(白い子)が,護られなかった欲求は心の裏舞台に退けられて(黒い子),精神性と社会性とに無縁となります。怒りのエネルギーを蓄えている黒い子が一定以上の勢力になると,自我を捕捉し傀儡化するようにもなります。何らかの満足を求めないわけにはいかないのが人間であり,そういう心の状況では黒い満足の追求になります。それが食物に向うとき,黒い満足は小児心性ということでもあり,虚しい心を埋めるために怒りを込めて貪り食うことになります。黒い満足としての食事は,自我の関与を欠き,精神性と社会性とを欠いているので,いくら食べても虚しいのです。また拒食症者にとっては,食べずにやせることが満足の一切です。身体性を否定し,精神性だけの存在になろうとしているように見えます。それは幼いころに身体を通じて満たされる体験が希薄だったことの,過食とは違った一つの表現です。食べ物を貪るのは身体への固執であり,食べ物を拒否するのは身体性の拒否ということになります。両者は両極に分かれていますが,共通するのは幼い時代に心が不十分にしか満たされなかったこと,恐らくは甘える満足が十分に満たされなかったことが主因となって,心の成長過程にあっても内心の空虚さが満たされないままでいたのです。過食症者は,太っていることをとても恥じます。それは精神性を欠いているが故の食行動の結果だからでしょうし,激しいエネルギーの黒い子の下で無力だった自我が,我に返って,情けなさに打ちひしがれている姿でもあるのでしょう。また骸骨のようにやせ細っても,ある意味では恥じない拒食症者は,身体性を拒否することに精神性を見出そうとしているように見えます。いずれにしてもそれらは心の裏舞台にある黒い子たちが求める満足で,生きる方向での行動ではなく,死の方向での行動なのです。ですから常識的な意見は通用しません。
ある女性は次のように述べております。「健康な心が健康な身体を望むというのは分かる。私の中にもそれがなかったとはいえない。しかしずっと以前から私にとっての美とは,死に化粧だった。グロテスクといわれると思うが,そのようなメイクをし,痩せこけるのが私のもとめる本来の美だった。そこには悪魔がいて,私を誘っていた・・・」
人の不幸を喜ぶ心も黒い満足です。犯罪も然りです。黒い満足を演出する究極には,影の帝王ともいえる死があるといえるでしょう。その手先が先の女性が述べているような悪魔の誘惑といったものです。死は恐るべきものである一方で,魅惑するものでもあります。
ちなみに人間の誕生は,O.ランクが出産外傷と表現し,後々の不安反応の原型となるといっています。
人間が生まれるということは,無限定なものから限定されたものへの移行であると考えられます。それは母親の胎内以前のものから,以後のものに移行するというのとおなじ意味です。生きることは限定されているということ,つまり’囲いの中’に限定されて満足を享受する自由が与えられているといえます。その生の享受は,限定されているが故の不安を排除できません。囲いの中が生の世界であれば,外は死の世界に違いありません。
無限定なものから生という限定されたものへ移行し,再び無限定なものへと移行する宿命の下にあることの無意味感は,我々にとって厄介過ぎる問題ですが,それは,所詮,生という囲いの中のもののボヤキに過ぎません。ソクラテスのように,人知を超えたものの意志に対してひたすら服従する精神があれば,ボヤク無意味から一転して,謙遜の精神を手に入れることになるように思われます。謙遜の精神とは,引き受ける精神と表裏一体の関係にあるものです。
母親の胎内から出て,そこへと回帰するというふうにも取れる人生の道筋を,人間的に生きる主要な手がかりが満足感の追求ではないでしょうか。いわば全の世界からこの世という限定の世界へと突き落とされて,全に匹敵する満足感を飽きることなく追求することをやめるわけにいかない人間は,どこか蟻に似ていなくもありません。満足感の追求が不首尾に終われば,たちまち生の世界に翳りが生じます。生は自我による光の世界であり,光の源泉は有限の彼方である全であろうかと思われます。そして翳りは無であるものといえるだろう死の気配です。それら全と無とは無意識の世界にいわば存在し,自我に光と影をもたらすようです。自我が上首尾に自己を導きとおすことができれば,限りなく全に向けて飛翔するようであり(ソクラテスのいう囲いを越えること),自我が不始末の悪循環に陥れば光の世界にあって翳りの色を強めることになるのでしょう。
とりわけ生まれて間もない赤ん坊は,全を要求します。母親の胎内にあって,人間となるどんな修行を積んできたのか知る術もありませんが,限定された世界であるが故に死を含み持つ生を,赤ん坊単独の力で引き受けることはできません。幸か不幸か,母親は赤ん坊の絶大な期待に応える義務を帯びた立場にあります。母親に誰がそのような義務を負わせたのか,母親自身が不満を持つことも可能な状況です。母親はソクラテス流の引き受ける精神が要求されています。であればこそ,母性豊かな母親は祝福された人といえるのでしょう。
母親の大きな役割は,全を要求してやまない赤ん坊に,生きる上での欠かせない知恵である,この世の限定のことを身をもって教えることです。つまり,ほどほどの満足が人間の分というものであることを分からせるのが,母親にできる最上の愛情です。この大仕事を委ねられた母親の名誉は,どんなに頑張っても,全を求めてやまない赤ん坊によって悪魔の烙印を押される不名誉に転落する怖れを内に持っています。赤ん坊が全を求めてやまないのは,この世のものになったがために,宿命として死を垣間見ることが避けられないからです。その恐怖は,全を提供してくれるはずの母親と一体のものとして映じるでしょう。つまり母親は,赤ん坊にとって,死をもたらす存在でもあり得ることが不可避なのです。この母親の全と無のイメージが,大母と魔女とに他ならないといえるでしょう。
そのようにして,全ならざる人間は,飽きることなく,蟻のように満足を求めて生きつづける宿命の下にあります。
しかしいずれにしても赤ん坊の心は,全の世界から全ならざる世界へ移行していくのでなければなりません。言葉を換えれば幻想的世界から,現実的,客観的世界に移行していかなければなりません。
以上のような事情の下で,生まれたばかりの赤ん坊が母親から心理的に分離して,独自の個として生きていく上での拠り所となる自我の機能が,ひとまずは確保される(3歳ごろ)までのあいだは,いわば’1000メートルの下降’が穏やかに果たされる必要があります。この危険な下降,着地が理想的に穏やかに果たされたとしても,人間は絶対的な受身として存在が開始されたという事実は否定できません。つまり危険を賭して’1000メートルの下降’を強いられるということの意味は不明であり,絶対的な不条理を生きる宿命の下にあります。この不条理性を余儀ないものとする人間は,光のものであり,意味を紡ぎ出すものである自我によって存在可能となるのですが,それは同時に,人間の心は自我による光がおよび得ない闇と無意味の領域とを併せ持つことになります。かつまたこの闇の領域は,自我の価値規範によって否定され,隔絶,排除された意味を持つ領域と,自我が拠り所とする領域とを併せ持つものです。
自我に拠る光の領域を白の世界とすると,自我の価値規範によって否定された領域は黒の世界ということになります。そして白の世界の帝王は前章で述べた内在する主体ということになると考えられます。一方黒の世界の帝王は,死であると考えられます。しかしながらこのように両極に分離して現象を捉えるのは,自我の機能の宿命的特性です。白と黒のそれぞれの主体そのものは全であり,かつ無であるといったものであるだろうと考えられます。そしてその一者の観点からは,白と黒との分離はなく,白でもなく黒でもなく,あるいは白であり同時に黒であるといったことになるのではないでしょうか。
いずれにせよ,自我に拠る人間の理解がおよぶのは,主観と客観の総合である現象的世界にかぎられます。それは「意識という光が及ぶ限りの世界」と同義であり,つまりいうまでもないことですが有限の世界です。そのことは必然的に意識の光が及び得ない「無限界が存在する」ことを含んでいます。いうならば「無限の世界」は現象的世界とおなじように,「その存在}は明証的で,疑いようがありません。
自我は意識に拠る現象的世界の中心にあり,その世界を司っています。しかし自我が存在するにいたった理由は,自我の能力を超えています。そのことは一見すると合理的理解が不可能であるということになりそうですが,しかし自我が存在する理由はいま述べたように明証的です。そのことを結論的に言い表せば,次のようになるかと思います。
人間にとって明証的なのは意識が捉えるかぎりの世界(現象的世界)についてである。意識は自我に拠るものである。しかし自我自身の存在理由を自我は知らない。それは自我が一切の最上位にあるものではないことと同義である。つまり自我の上位にあるものに拠って自我が存在するにいたったことは疑いようがない。その上位にあるものを,現象界にあるものとおなじような意味で実体的に理解することは不可能であるが,それと名指しできないにせよその存在自体は疑いようがない。現象とは意識がそれと指し示すものの存在のことであり,その意識の連鎖を認証することが合理性ということである。このように,自我の存在理由となったものの存在を認めることは合理的である。
自我の上位にあるものは原則的に無限界に属するものです。ですから具体的に現象的実体として捉えることは不可能で,自我の能力を超えた問題です。「それは存在する,しかしどのような様態で存在するかは知り得ない」ということになります。
個々の自己が自分にも知り尽くせない自己であるのは,改めていうまでもないことです。それは自己が自我に拠りつつ,自我を超えたものの存在(「無限界に属する存在」ということになります)にも拠っていることを,明証的に示しています。そのことを敢えて考慮する必要があるのは,精神科の診療で心の問題を考えるときです。人間が絶えざる可能態として存在していることは,希望の源泉を確認することになるからです。自我の上位にあるものの存在様態は,現象的実体として捉えることはできないのですが,だからといって煙のごときもののように漠然としたままでいるのでは説得性が希薄です。それをともかくも措定する必要があります。それはどうしても擬似有限態として仮説的に措定するしか手がありません。
そのような試みは,心の治療の体験から自ずから導き出され,その有用性を診療の上で訂正されつつ確かめられることで容認され,意味を持つだろうと思います。
自我の存在と存在様態の問題は,生と死という人間の最も根源的なものと直接関わるものです。この問題を不問にして人間の心の問題を考えることは不可能です。
生は自我の誕生と共にあり,死は自我の終焉と共にあります。自我の存在以前には生も死もありません。つまり生と死とは,有限と無限の問題でもあります。
それにしても死とは何でしょうか?現象としては物化した屍体がそこにあります。それは死の動かし難い事実の一面です。しかしそれが死でしょうか?精神は,魂はどうなったのでしょうか。
死によって我々の前で明らかなのは,物化した身体ばかりです。精神は煙のように消えてしまい,それがそもそもどこに帰属するものなのか,手がかりがありません。生きているあいだは身体と精神とは一体のものであり,精神の活動は身体性と切り離すことができません。
人間の一生をたどれば,幼いころは身体に傾き,年をとるにつれ精神に傾くのが理想のようでもあります。生涯に3度結婚したソクラテスは,60歳を過ぎて再婚し,子供をもうけました。そして幼い子を残し,その気があれば免れることができた死刑を甘受して死を選びました。そのソクラテスは,身体に固執する愚を説き,魂を磨くことを説いています。
身体は成熟のピークを向えた後は,時間を経るにつれて衰えていきます。最後に物化して死を向えます。滅び行く伴侶と共にある精神は,共に滅びるのか,遊離するのか不明です。ソクラテスは,哲学は死の練習だといいます。哲学する精神は,滅び行く身体を慮り,自分自身の行く末を慮るという意味かも知れません。
死は精神の所在を謎に包みます。差し当たりは無に帰したというしかありません。身体もまた物化して残りますが,やがては腐敗して無に帰します。いずれにしても死によって人間は無に帰するので,ここでも厳然と「有限態であったもの」と「無の存在」とが明らかになっているようです。
自我が自我以上のものによって存在可能となったと考えるしかないのとおなじ理由で,死によって無に帰した精神は,そもそも「無の世界のもの」であると考えるのは可能であるように思います。有限態である自我の観点から,有限の彼方にあるのは無限に違いありませんが,無限即ち全は無と区別がつきません。
自我至上主義は虚無の精神に他なりません。それは死は本人の自由に扱ってよいものかという問いに対して,いうまでもなく本人の自由であるという結論を導きます。またそれは,謙遜である根本理由を欠くことになるので,ドストエフスキィーの「罪と罰」の主人公が考えたように,場合によっては他殺も許されることになります。更に自然破壊,環境破壊など人類の危機をもたらしているのもおなじ理由によります。
自我の機能は,第一に自由で自立的な自我,第二に社会的な自我,第三に非社会的な自我と,便宜的に三つの階層に分けて考えることができます。そして存在するものは必ず滅びます。自我の機能もまた崩壊する可能性を秘め,実際に崩壊します。その様態が統合失調症と呼ばれているものです。です。
自由で自立的な自我が保たれていれば,病的な心理に陥ることはないといえます。芸術家や研究者など,創造的な仕事に携わる人,あるいは人間の身体能力の限界に挑戦する才能のあるスポーツマンなどは,このレベルが最も望ましく機能している必要があります。このレベルでは内在する主体との関係が良好に保たれていると考えられます。何にせよ行為するためには意志が働きます。意志というのは,心の親である自我が働きかけ,それに即応する欲求が心の子として生まれ出て,両者が協働することで形作られます。自由な自我の機能のレベルにあっては,自我とそれに即応する欲求とがいわば阿吽の呼吸の関係にあり,同時にそれは内在する主体との関係も良好に保たれていると考えることができると思います。
この機能レベルは,下位レベルにある社会的自我機能を,監視し調整する役目があります。ですからこのレベルがそれなりに活発でなければ,考えが窮屈で,融通の利かない人ということになります。
第二の社会的な自我機能は社会的な存在である人間が是非とも身につけていなければならないものです。
第二のレベルを保つことができなくなったときに,第三の非社会的機能のレベルに後退します。このレベルでは自我は無意識の黒い分身たちに対して優位の立場を保てず,それらに支配されることになります。この場合,何らかの心身の不調は避けられません。
第四に自我が崩壊した場合,決定的な異常心理である統合失調症の世界に陥ります。このレベルには機能的なものと器質的なものがあります。器質的なものでは,人格の何らかの欠損状態が永続的なものとなります。
例として上げたMさん,Nさんに即していえば,自我の自由な機能は活発ではなく,第二と第三の階層を行き来していると考えることができます。そしてあるときに自我の機能的崩壊が一時的に起こったと考えられるます。
自我の自由で自律的な機能が失われて,固化した状態が長期にわたっていたことが第一に問題になると思いますが,二つの例に共通していて,しかし対照的なのは怒りの存在です。Mさんの場合は怒りの所在についてはむしろ無意識です。その存在は子供に対する支配的態度から容易にうかがえるのですが,Mさんにはそういう自覚もありません。それを明確化,直面化させようとしても,するりと交わされてしまいます。仮に無理にそれを迫るとすると,激しい怒りが噴出する怖れがあります。治療関係の破綻はもとより,自我の崩壊をもたらす怖れもあります。Nさんの場合は,逆に絶えず怒りが意識に上り,Nさんを苦しめます。
両者ともに怒りのエネルギーが大きいと考えられますが,怒りは自我が本来の機能を果たしているときには問題になることはありません。怒りの布置は自我の機能が弱体化している証拠なのです。それは分別のある人の怒りも同様です。思わず怒りを顕わにして,周囲の者にもその理由が十分に分かるとしても,自我がうまく機能しない隙をついて怒りが顕わになったのです。いかなる場合でも決して怒りを表さない人格円満な人は,自我の機能が常に安定しているのでしょう。
Mさんの自我は怒りを強く抑圧しているために,無意識からの圧力にひたすら耐えることで精一杯のように見えます。Nさんの自我は怒りを含む影の分身たち(黒い子)に取り囲まれ,支配されているように見えます。両者に共通しているのは,それぞれの自我が自立性と自由とに欠け,引き受ける能力を失っていることです。
無意識界に大きな勢力となっていたと思われる負の分身たちによって,Mさんの自我は固化され傀儡化されていたと考えられますが,Mさんが急性精神病状態に陥ったとき,潜勢力のエネルギーがついに自我の耐用力を凌駕して崩壊させたと思われます。このとき崩壊しつつも,自我は二つの対案を示しているように見えます。一つは置かれている客観的な状況から逃れて自由になること,もう一つは義弟は実は学歴を詐称していて留学はしていないと合理化することです。両者共に自我が無意識の力をある意味で利用しているともいえます。
しかし崩壊に瀕している自我には,現状況を再建的に克服する力を示すことはできず,非現実的で,機能を失っていることが明らかになるばかりであることに変わりはありません。
自我が機能を発揮するとき,生の方向にエネルギーが動きます。何らかの活力のある現実策が展開されるのです。そして機能を発揮できないとき,死の方向にエネルギーが動きます。Mさんの場合は,悪夢となって表れたように,暴力と無秩序のカオスの世界に突き進むしかなく,あるいは実の妹にあらぬ疑いをかけることにより,姉妹の関係を破壊するしかなく,それらはいずれもMさんを自滅の方向に向かわせるものです。
Nさんについてはどうでしょうか?
Nさんの生活状況は,むしろ恵まれたものです。夫と小学生の子供との3人家族ですが,夫は特に不理解でもなく,自分本位ということもないようです。何かと不調を訴える妻を,夫は病気というよりは性格の問題とみていたようで,突き放すような態度があったようですが,Nさんが精神病状態に陥った時には,よく世話を焼いてくれています。会社員としては高収入ではないかと思われ,経済問題もありません。さきほども述べたように,夫の母親はNさんをよく助け,嫁姑問題については大変恵まれています。
Nさんは一日の家事の手順に,強いこだわりがます。そのために絶えず時間に追われ焦っています。掃除,洗濯,買い物など,すべて決められた時間に済ませたいのです。夕食を作る時間,子供を入浴させる時間,食事させる時間,寝かせる時間なども然りです。そこへ夫から電話が入り,迎えの車を頼まれたりすると,それらが乱されることになります。夫はゴルフ好きで,休日には出かけることが多いのは仕方がないとしても,車を持っていかれるのが不便です。そういうことでも小競り合いが絶えず,日常的に波風が立っているのは確かです。それらのことは家族関係に起因するというよりは,Nさんの性格的特性に端を発しているといわなければならないようです。言葉を換えると,会社の仕事がある夫にもストレスの解消策が必要でしょうし,もっと奥さんの身にもなってと要求するとすれば,夫のストレスが更に高くなる危険があります。
Nさんによれば,夫は,「お前のは病気でないよ・・・」としばしばいっているようです。それは言外で性格の問題だといっているのでしょう。それに間違いはないのです。Nさんが性格を変えて行くつもりにならなければ,繰り返されている発病に歯止めをかけられません。
先にも述べたように,Nさんの治療者への姿勢は,「治してください」というものです。これは他を当てにする以上に,問題の一切を外部に預けることになります。これは外科医の治療を求めるのとおなじです。心の問題は,どんな医者であれ,「外側から治す」のは不可能です。Nさんの心の問題はNさんにしか分かり得ないのは,いうまでもないことです。そのことをどうしても理解できないNさんの心は,それ自体がどこか病的といってよいでしょう。心の病気の治療には,{頭が良い」ことが決定力を握っていますが,それは知能の良し悪しの問題ではありません。
Nさんが取るべき望ましい姿勢は,「これは私が引き受けるべき問題ですが,どう考えていけばよいのか見当がつきません。このことに治療者として協力してもらえますか?」といったことです。このような心の姿勢になれることが,心理治療の上では「頭がいい」ということになります。やはり問題は引き受ける精神に行き着きます。一般に,引き受ける精神になれる人が,「頭がいい」と言い換えても間違いではないでしょう。
この意味では残念ながらNさんは,心が硬かった,固化した自我の下にあった,といえます。
Nさんの自我を固化させていた主役は怒りです。Mさんの場合も同様ですが,Mさんの自我は怒りをひたすら封じ込め,表面では,「親に逆らわない良い子」というのが意識の構えです。自我が影の分身たちを引き受ける気配を見せないので,影のものたちからすると救いがありません。それで影の者たちの怒りのエネルギーは無視し難いものになってたと思われ,自我は必然的にその圧力を受けつづけています。そしてそのエネルギーのはけ口が娘に向かったことになったのです。怒りを込めた黒い分身たちを引き受ける気のない自我は,娘に問題を転嫁しようとしました。仮にそれが上首尾に運んだとすると,得られたのは黒い満足ということになります。そして娘はその犠牲者に供されることになります。
NさんはMさんとは逆に,怒りを両親に向けつづけました。義母に模範的な良い母親像を見出した一方では,まるで義母が焚きつけたかのように実の母親(父親にも)への怒りが収まりません。Nさんの自我が引き受ける精神を機能させていれば,事情は変わっていたでしょう。そのときには義母の優しさによって得られる満足は,自我が獲得した白い満足ということになるのです。ところが自我が引き受ける意志を持てないままでの義母の優しさは,Nさんの実の親への怒りを助長させることになりました。その黒い分身たちの怒りは,Nさんの自我が黒い分身たちを生み出した原状況である幼い時代の親子関係に問題が持ち込まれ,実父母への怒り,攻撃がとどまることがないのです。
Nさんの固化した自我は,日常の問題に対応できずに機能的崩壊(精神病の発病)を何度か来たしました。その度に夫の優しさ,頼もしさを経験しました。結果的にそれは夫を試すことになりました。うがち過ぎかもしれませんが,発病は,自我が夫の力を図る無意図的意図の一面もなくはなかったかもしれません。何度も離婚問題が取りざたされながら高を括っていたといい,しかし,「今度はヤバイと思った」と笑顔交じりでいうNさんの様子から,そういう印象も持つのです。自我が,「今こそ引き受ける気にならなければ離婚はあり得る」と踏んだともいえ,それが,自我が自律性と自由とを回復させるきっかけになったと思われるのです。それはMさんの自我が,動かし難い夫と娘の独立性によって,(ある意味であきらめて)自律と自由とを回復させたように見えるのと似ています。
(このあたりのことに共通するものとして,50代の主婦の例を上げておきます。この方は,幼いころから気分や行動が乱調だった息子さんの世話をやいてきました。ところが息子さんが,心霊的なあるセミナーで知り合った女性と懇意になり,いわゆる洗脳された気配になりました。そして,突然,激しい別離の言葉を浴びせられ,息子さんは家を出て行きました。連絡は一方的な形で金銭等の依頼があるものの,母親から連絡を取ることはできません。それから年余の歳月が経っております。夫は以前からそうであったように,連夜のように飲酒して深夜に帰宅します。夫のサポートもなく,孤独感と寂しさに悩まされておりました。そういう折に,老いた母親の入院の知らせを受けました。高齢なので覚悟はできていました,「しっかりしなくちゃ」と思いました。それを機に,本当にしっかりして心が屈することがなくなっております)
エネルギー論的に見ていくと,自我と無意識との関係は次のように考えられます。
自我は海のような無意識から浮かび出てくる小島のように見えます。生まれて間もなくは,代理自我ともいえる母親の全面的な助けを必要とします。母親の愛と信頼とに助けられて,赤ん坊はしだいに自分に固有の小島が大海のただ中に生み出ていく喜びを,大きな不安を持ちながらも知っていきます。それは母親が与えてくれた愛と信頼とを,赤ん坊自身が自分に与えることでもあり,同時にそれは母親への愛と信頼との印でもあります。やがて生まれつつある小島が自分のものであり,それを経営していく喜びが将来を保証しているように感じられます。いつか囲んでいる大海が怖れるに足らないもののように思われていきます。そして,いつか大海は姿を消し,小島は既に小島ではなく,揺るぎない大地の感覚になっていきます。
海は小島を呑み込む怖れを持っていますが,敵対するものではありません。それは母親が護り,助けてくれた大きな力によって,自分の小島を経営していく喜びと自信とが大きくなるにつれ,身についていきます。
海はいつか小島の内部に身を隠します。
このように比喩的に見ていくと(自我や無意識は現象的実体ではないので,我々が通常しているように,見たまま,聞いたまま伝えるというようなわけにはいきません。そういう形に似せて語る以外にないのです),自我が小島を未知なる大地に向けて発展させていくためには,自ら計画を立てるほかに,無限に通じる海のエネルギーの助けが必要です。
どうやら海は二層に分かれているようです。一つは小島に固有の海,もう一つはいわば人類のものであり,いうならば公海です。自我も含めてそれら三者は互いに境を隔て,かつ交流をはかっていると思われます。
これら三層のうち,自我と自我に固有の無意識層とでは,それぞれ一定量のエネルギーが固定されていると思われます。そして公海にあたる無意識のエネルギーは,いわば無限定です。
これら三層のあいだに境界があり,機能的な定めに従ってエネルギーの移動があると思われます。それは日常の心理の動きから推測すると,次のようではないかと思われます。
自我が使用可能のエネルギーはおおむね一定量と思われます。それは大よそ,自我が無意識層に対して上位に立ち,自由で自律的であるのを保つためです。
何かの行為をするときに,自我は自我固有の無意識に働きかけをして,それに応える形で欲動,あるいは欲求と呼ばれているエネルギーの供与を受けます。それは精神活動の一つの形式となり,必要に応じてパターン化して活動します。それが意志と呼ばれているものです。このときに自我に向けて,自我に固有の無意識から一定のエネルギーが移動します。自我が本来的な機能を果たせば,自我の子ともいえる欲求を護りとおすことができます。それは一定の満足感となり,供与されたエネルギーが適正に消費されたことになります。そして自我の機能の自由と自律性とが護られ,自我は活気のある状態を保つことができます。それに伴い自我に固有の無意識層に向けて,消費されたエネルギーが公海に当たる無意識層から補給されます。これら三層の一方向的なエネルギーの移動が起こっているかぎり,精神状態は健全です。
このことを,母親に甘える子を例にして見てみると次のようになります。
母親の助けによって甘えることができた場合は,幼い子の心の親である自我が,生まれてきた心の子である甘える欲求を護ることができたことになります。甘えを満たすことができたのは,母親によってというよりは幼い心の親である自我によってです。当然,母親の助けはなくてはならないものです。本来の役目を果たすことができた幼い子の自我は,エネルギーを蓄えて生まれてきた心の子である甘える欲求から,そのエネルギーを受け取ることになります。そのときに甘えが満たされた満足感を味わうことができます。その満足感は,母親から愛されている,信頼されているという喜びと共にあり,自分が価値ある存在であるという喜びと共にあるのです。そしてそのような体験を重ね,自信を得た幼い自我は,次々と生まれてくる欲求を押し殺さずに護り通そうとすると意志を持つことになるでしょう。それは自我の成長であり,活気のある自己の育成につながります。自我がエネルギーをうまく消費し,無意識の海から自我へと向けたエネルギーの移動が,滞りなく進んでいることになります。
一方,母親に甘えるのが難しい何らかの状況で甘えを断念したとき,次のようになると推測できます。
幼い自我は,心の海から生まれ出てきた自然のものである欲求(白い子)を護れず,見捨てることになります(黒い子を生み出す)。このとき自我は移動してきたエネルギーをもう一度押し返すことになります。それは自我が,生まれてきた欲求が蓄えているエネルギーを受け取ることができないばかりか,逆にそのエネルギーを自我に固有の無意識層に押し返すことによって,反自我の勢力(黒い子たち)を作り出すことになります。それに伴って,自我へと向う無意識層からのエネルギーの流れに,混乱と停滞が惹き起こされます。
そのようにして自我は不活性化し,かつ無意識層にある黒い子のエネルギーである怒りの圧力を受けることになり,二重に自我の活動を鈍らせることになります。
治療的な関わりが必要になるのは,以上のように自我の負債が増大したときといえます。治療的な介入がうまく進み,再び活性化しはじめた自我によって,黒い子の存在が改めて認められ,受け入れられるようになれば,それは既に黒い子ではなく,自我へと向けたエネルギーの移動が正常化することになります。
上に述べたことを別のいい方をすれば,次のようになります。
心には表舞台と裏舞台とがあります。表舞台には自我が仕事をした成果が乗せられ,生きる方向を指向しています。裏舞台には自我によって受け入れを拒否されたものが乗せられています。それら受け入れを拒まれた影の分身たちは,本来は自然のものであり,理不尽な目に合わされていることになります。また,人が人として生を開拓していく拠り所である自我が受け入れを拒否し,表舞台に上げるのを拒んだのですから,それは死の宣告に等しい意味があります。つまりそのようにして裏舞台に回された影の分身たちが志向するのは生ではなく,従って死ということになります。そのようなことが起きるのは,自我が機能する上で他者との関係を不可欠なものとしているからです。他者の助けがなければ,とりわけ幼い自我は立ち行くことができません。そして他者の助けは,幼い自我が真に必要としているものとは異なる宿命の下にあります。そのような事情から,自我の不始末(影の分身たちを心の裏舞台に回してしまう)が雪だるま式に拡大してしまうのは,多かれ少なかれ避けられません。自分を助けてくれるはずの他者によって,自我が不始末をはたらくのを余儀なくされ,結果として他者によって心が貧困化していくことは,大いにあり得ることといえます。
これら裏舞台の分身たちは死を志向するので,その勢力を一定程度以上作り出した自我は,作り出したことの不甲斐なさで力を衰弱させることに加えて,作り出された影の分身たちに取り囲まれ,支配を受けることになるかもしれません。そうなると主体性を失った自我の機能は固化して本来の生を志向する働きが鈍くなり,心全体が死の影に覆われることにもなるのです。
「死にたい」,「死んだ方がましだ」と考えるのは,自我が受け入れを拒否した心の分身たちの支配を受け,自由と自律性とを失ったことの表れです。
自我は,敢えて心の親であると意志的に意識する必要と責任とがあります。親であればこういう折に,「一緒に死のう」ではなく,「一緒に死ぬわけにはいかないよ,いまは助けてあげる力がないけれど,そのうちに助けてあげることができるようになるから・・・」というべきです。
このように心の裏舞台にある分身たちに言明するのは意味のあることです。そもそも自我の本分は,自己と人生とを引き受けることであり,いかに生きるかというところにあります。死を引き受けることはあっても,死を選択する余地は自我にはないのです。その本分に立ち返って,死への要求を排除していくことは,理にかなったことです。
ちなみに精神医療では,患者さんが死にたがっているときに,「死なないと約束してください」と提起するのが治療者が試みる定石です。その約束は,自殺を防ぐ有効性を持っています。この場合,衰弱している病者の自我を,治療者の自我が代理して補っているといえるでしょう。
なにはともあれ心の問題に解決が求められたときに,自我の介入が必須です。怒りは裏の自我に仕えるものです。
何であれ行為するときは意志に基づきます。意志は自我が相応する欲求(欲動)に呼びかけ,欲求が無意識の領域から生まれて来ることで成立します。その欲求はエネルギーを蓄えており,自我と協調して行為の達成を図ります。自我がしっかりと欲求を護り,励ますことができていれば,自我は活性化され意欲的に取り組むことになります。それは自我の呼びかけと相応する欲求の生起とが,いわば阿吽の呼吸の関係にあることになり,自由な機能が活発である自我の下に,次なる行為が速やかに展開され易い状況であるといえます。
一方,挫折を繰り返してきた自我は,呼び出した欲求を中途で無意識界に追い返すことを繰り返すことになります。自我によって見捨てられた形の欲求は,エネルギーを蓄えたまま生まれてきた心の海に押し返されて,いわば黒い子となります。それらは怒りと共にあります。自我に反逆するものとなり,死への志向を持つことになります。
以上のことを心の全体の整合性において考えると,以下のように描くことが可能ではないかと思います。
まず心の真の主体は何かという問題があります。意識的心の主体は自我と呼ばれています。自我は人間的なあらゆる営みの中心です。自我は意識活動の拠り所で,意識が及ぶかぎり知性的理解が精密に行われることができます。それが極限にまで推し進められたのが自然科学的なアプローチです。自然科学的達成に関しては,人は一切の上位に立つ支配者です。しかしながら自然科学以外の科学については,簡単ではなくなります。たとえば人の心理に関する学問は,自然科学のようには一様でありません。自然科学の威力は,意識の光が隈なく行き渡るので,ほぼ完璧に因果律的な論理の下に対象を従えることができることです。そしてその限界は,物的な対象に厳密に限られるところにあります。心理学は当然その範疇に収まりません。そこでは意識の光が隈なく及ぶことができないものを対象とします。つまり生きている全体を合理的に理解しようとすれば,意識の光が届き得ないものをも対象化することになり,その対象には無意識のものが入り込んでいることになります。ところで無意識と合理性とは全く相容れない関係にあります。合理的理解は意識化が可能であるのが前提になるからです。自然科学は合理的理解の究極のものであるので,心の科学もそれを援用することになりますが,意識が物的な実体として捉えることが不可能であるものを飛び越える形で,意識を繋ぎ合わせることになります。ですから推理や仮説は不可欠になります。仮説は物的な実体に凝らして行われるしかありません。
このように,そしていうまでもなく意識可能の世界が心の全体ではありません。つまり無意識の世界があり,これを大海になぞらえると,意識の世界は大海に浮かぶ小舟の船頭以上に頼りなげです。というよりは両者はそもそもそうした比較が不可能なのです。
心には無意識の世界があるのは疑えません。しかし意識の光が及ぶのはそこまでです。「それは疑いもなく存在する。しかしどのような様態で存在するのかは不可知である」ということになります。
意識できないものの存在を何故意識できるのかといえば,意識の光が届く世界が有限であるのが明らかだからです。しかしどこまでと限定すること自体が不可能です。たとえば100メートル走の世界記録を考えてみると,人間の能力に限界があるのは疑いありません。しかし世界新記録が限界に到達することもないでしょう。それは必ず新たな記録で破られるためにあるようなものです。それでも5秒以内で走るのは不可能に違いありません。「限界は必ずある。しかし人間の能力でそれをあらかじめ知るのは不可能である」ということになります。明らかにある限界に向けて,無限に近づくというのが実際です。このように明らかな有限性の中にも無限性が入り込んでいるのです。
つまり有限性は無限性があって初めて成り立つのです。そしてその両者のどちらが上位にあるかは論を待ちません。
そのことを定式化していえば,「我々は人間のことを意識できるかぎりで知っている。そのかぎりで人間は一切である。その拠り所を自我と呼んでいるが,それでは自我は何に拠っているのか?そのことを意識が捉えることは不可能である。しかし自我が存在する以上はそれをあらしめた存在もまた存在しているのは明らかである。その存在が自我の上位にあるのは論を待たない」ということになります。
自然科学の呪縛の下にあると,例えば,「死は一切の消滅である。それ以上の存在仮説を弄ぶのは愚かなことである」と考えます。しかしこの考えもまた,自然科学に論拠を置いた仮説に過ぎません。死の問題には無の問題があり,全の問題があります。それは無意識に通じるものでもあります。これらの問題が厳然としてあるかぎり,人はそれを問わなければ生きている全体を問うことができません。「死は無である。ただそれだけのことだ。それ以上のことを考えるのは無意味なことだ」と悟りすますのは,一見は謙遜に見えます。しかし真の謙遜は,自分の上位者の存在を認めることです。そうであれば,「死について,身体が無に帰する以上のことは,私には何も分からない」となるべきです。そしてその留保の態度が謙遜であるとすれば,暗黙の内に「何も分からないものの存在」を認めていることになるのです。「私には何も分からないのだから,それは存在しないということだ」といっているに等しい唯物論者の論は,粗暴に過ぎるというべきでしょう。
ここでその上位者を,内在する主体と呼んでおきます。この主体が心全体の上位者であり,統括者です。それは自我という有限の能力からは無限のものです。
自我という限定されたものには,それ自体を養う力はありません。言葉を換えると,自我が有限体である以上は,自我が抱えるエネルギーは有限のものです。つまり他から補給されなければ枯渇することになり,他というのは無意識の世界以外にはありません。このエネルギーは行動(行為)に伴ってもたらされると考えられます。何か行動(行為)を起こすとき,自我は計画を立てます。そして行動のエネルギーをもたらすものを呼び出す必要があります。その呼びかけに応じて内在する主体が,エネルギーを抱えた,いうならば神の子を送り出してきます。神の子は自然から生まれたばかりの無垢のものです。いわば白い子です。大変傷つき易くもあるでしょう。
呼び出した神の子を自我は護る義務があります。それは何といっても神の子で,送り出した子を自我がどのように扱うか,主体は見守っているともいえるでしょう(それぞれの個はどのように生きようが自由でしょうか。地獄化する人生があります。創造的な人生を送る人があります。それぞれの個が自分らしく生きていくのは,誰もが等しく願っていることではないでしょうか。それがどのようにしてというのが困難なのです。それを予め知っている人はいないというべきでしょう。しかしながら道を間違えると人生は地獄化します。やはり道はあるのです。我々には予め分からないが,それぞれの道は必ずあるということになるのだと思います。そうであればそれを知っているのは自我の上位者以外にはありません。自分らしく人格形成をしていく上での青写真は,主体にあると考えることができると思います。我々は手探りで自分の筋を辿っていくことになりますが,それは送り出された神の子を自我がどのように扱うかにかかっているように思われます。そしてその筋を曲げざるを得なくなり,自己を見失うことになる最大の理由は,他者との関係を必須のものとしているところにあります。換言すると他者の介入にあります)。
自我が神の子をどのように護るかといえば,目的(希望)に向って進む上での欠かせないパートナーですから,第一に呼びかけに応じてくれたことを感謝すること,そして第二に共に行動することを喜ぶことによってです。その行動のあいだ他のことに気をとられるようであれば,白い子は傷つくと考えるべきです。それで首尾よく目的を果たせば(自我が白い子を守り通せば),自我は白い子が抱えていたエネルギーを受け取ることになります。そのように逐一の行動を通じて,自我はエネルギーの補給を受けていると考えられます。
仮に予定された行動が,気が変わって取り止めになると,求めに応じた神の子は無用のものとされます。捨てられた神の子は怒りでいわば黒い子になります。自我に渡されることがなかったエネルギーを抱えたまま,黒い子は行き先を失います。送り出された主体の元に戻ることはなく,自我の世界の一隅にうずくまることになります。それは自我と無意識との中間領域で,ユングが命名した個人的無意識の世界です。この世界のものは,ふだんは意識の光が届かないので無意識ですが,自我がその気を出せば意識化が可能です。
このようにして元々は神の子であったこの黒い子たちは,悪魔の手先になっていきます。
これら黒い子たちを作り出す自我は,特有の状況でおなじことを繰り返す傾向を持つものです。それで黒い子は雪だるま式に肥大化します。それら黒い子たちの中核にあるのを,仮定的に裏の自我と呼んでおきます。
黒い子たちの抱えている怒りのエネルギーは自我に見捨てられたことによるので,怒りは,本来,自我に向けられたものです。それを受け止める気勢を示さない自我が,そもそも黒い子たちを作り出してきたのです。そういうときには,表の自我が裏の自我に支配されたまま無力でいるので,怒りは外的な状況に向けられるのです。黒い子をおびただしく作り出した自我の下では,人生そのものが面白くなく,道で石につまずくと腹を立てて石を蹴飛ばしたりといったことになります。
機能を回復した自我が与えられた使命をめざましく果たすことになれば,自我は裏の自我に仕える怒りのエネルギーを引き上げ,生へのエネルギーに転換する可能性があります。表の自我が力を回復させると精神のエネルギーは自我に集まり,力が衰弱すると,精神のエネルギーは裏の自我の方へ移行し,怒りを蓄えることになります。精神のエネルギーは無定形であり,生(光)への方向と死(闇)への方向といずれのものにも姿を換えるもののようです。一切を破壊するほどに蓄積された怒りは,死そのものと一体化します。死は一切の破壊であり,心の裏舞台の首座にあると考えられます。
Rさんの例で見れば,分身たちを抑圧しつづけてきた自我は,母親の自我の支配を受け,母親との共犯関係に囚われていました。その様子があるとき変わり,母親に怒りを向けることになりました。それはRさんの自我が母親の自我から距離を取り始めることに伴って起こったことです。それは同時に影の分身たちの存在に目を向け始めたことを意味します。母親の自我にへばりつくように依存していたRさんの自我は,おびただしく黒い子を作り出すことが避けられなかったはずです。そして怒りが意識に上ってきたことは,自我が本分に目覚める力を回復した兆しが表に表れたことを意味します。しかしまだ十分に機能を回復していないRさんの自我は,強力な怒りのエネルギーを蓄えている影の分身たちに捉えられたということができます。自我が機能を回復した分,母親から離れる自由を得たものの,今度は分身たちに捕捉されてしまったのです。その分身たちは,母親と共犯関係にあるあいだに,自我が心の表舞台に乗せることを拒否し,見捨ててきた(死の宣告に等しい扱いになります)ものたちです。
そのような局面を向えて,Rさんは大変困難な状況に身を置くことになったといえます。母親の自我の代わりに影の分身たちの支配を受けるかぎり,自我は傀儡の立場であることを免れません。それは死を賭した自立の希求という意味を持ちますが,自我が影の分身たちの上位に立ち,自由と自立とを確かめることができるまでは,自傷,自死を含めたあらゆる黒い満足の危険の只中にあることになります。いつか気がつくと自我が上位に立ち,影の分身たちの支配から自由になることができるでしょう,しかし裏の自我が蓄えていた怒りのエネルギーの総量は大きなものと予測され,自我によるそのエネルギーの回収作業はゆっくりとしたものである必要があります。慎重を欠けば,自我が粉砕される怖れがあるからです。その後の人生上の節目において,自我が衰弱するときもあるに違いなく,その度に分身たちのエネルギーが活発化して気分が不安定になり,あるいは屈するときもあることでしょう。それでもめげずにいるかぎり,やがて自我は引き受ける力を回復するでしょう。
怒りは身を守るものでもあり,身を滅ぼすものでもあります。身を守る怒りは,自我の後ろ盾を必要とします。身を滅ぼす怒りは,自我のそれを欠いています。
怒りは他者との関係,あるいは自己自身との関係を破壊しようとするものです。自我によって正当に支えられた怒りが他者に向かうのは適応的で,自己を護り,助けようとするものです。自我の支えを欠いた怒りが他者に向かうとき,対人関係を損なう危険が高まります。また自我の支えを欠いた怒りが自己自身に向かうとき,心と身体の健康を損ねる理由になります。
ある小学生は,夜,寝るときに,母親がいなくなる恐怖で眠れなくなります。母親が死ぬのではないかという恐れもあります。母親に叱られると,自分は嫌われているのか,可愛がってもらえていないのかと思います。年の離れた弟がいますが,弟ばかりが可愛がられると思い,怒りを覚えます。
弟はまだ1歳半ほどですが,小学生の兄が寝ているときに,いきなり頭を叩くなどします。小学生は,みんながいる居間で寝たいのですが,危険な弟がいるので,仕方なく別室で一人で寝ます。弟は宵っ張りで,夜中の1時ごろまで起きています。兄は不安と不満と怒りを胸に,眠りに入れません。兄も弟に仕返しをしたいのですが,なんといっても1歳半なので我慢するしかありません。学校から帰ると笑顔を向けてくる弟が,可愛くもあるのです。
この子は,率直な様子で話をする明るくも見える性格です。屈折した感じが見られません。「そうなんだよ,腹が立ってたまらないんだよ」といわば明るく怒りを表現します。怒りを露わにするという感じではありません。しかしそれらは表面のことで,心の裏面は明るいはずはなく,相当に深刻だと思います。明るく語る表情の裏には,はちきれんばかりの口惜しさがうかがわれます。
この明るく表現する怒りは,少年の自我の精一杯の努力といえるようです。自我が成熟している大人であれば,自我の精一杯の仕事はそれだけで十分に報われる意味を持ちます。しかし年齢が幼すぎるために自我が未成熟であるあいだは,幼い自我の仕事は親の支えによって報われる必要があります。両親の姿勢から,少年の怒りはいかにももっともなものなのです。それだけに少年の自我がしている精一杯の努力は,両親によって受け止められる見込みがなく,無効化されるのです。自我の精一杯の仕事によっても報われることがないので怒りが溜まり,心の潜勢力になります。その内向する怒りが,チックや不慮の災害への過剰の恐れという問題を引き起こしているのです。
怒りが心に充満し,母親の死を願うことさえあるようです。そういう怒りを持つために,母親が自分を捨ててしまうのではないかと恐れているのです。通学路の行き帰りに,変質者に連れ去られる不安を持っていますが,変質者は怒り(自分が母親へ向けた,あるいは母親が自分に向けた)の投影でもあると思われます。
母親によれば夜鳴きの激しい子だったそうです。
この子の怒りが母親に向けられたとき,もっと自分に愛情を向けてほしいという欲求を従えています。それは正当な要求であり,自我の仕事に基づくものといえます。そのとき怒りは満たされない欲求の従者でもあり,護衛でもあります。
しかしほどほどにしないと危険です。母の怒りの反撃に遭うかもしれませんし,場合によっては怒りが母との関係そのものを破壊するかもしれません。
親との関係の改善をもとめ,身を守るために怒りが表現されていますが,少年への優しさが足りないように見受けられる両親は,その意味を知ろうとしないのです。自我は本来の働きを精一杯しているのに,それが無効であるのは恐るべき現実です。子にとって,その存在を正当に認めようとしない親の下にあるのは,この上もなく残酷なことです。幼い自我の仕事は,親の支持がなければ無効になるのです。意識下の分身たちにとっては,自我が無力であるのと区別がつかないのです。業を煮やした分身たちの護衛である怒りが,実力行使に走り,心身の症状をもたらしているといえるでしょう。
親子の関係,特に乳幼児期の関係は,性格形成に決定的な意味を持ちます。幼い子の自我は,親との関係を通じて自分の仕事の意味を確かめていきます。生まれて間もないあいだの幼い自我は,身体的,生物学的な欲求の充足をもとめます。自我の仕事であるそれらの要求を,母親が満たして上げることが必要不可欠ですが,本当は満たしているのは母親ではなく,幼い自我が自分の仕事の有効性を母親を通じて確かめているのです。母親のサポートが得られたときに,幼い自我は大いに満足し,それを母親と分かち合うことになります。ここに自我の重要な役目である満足の追求と,母なる他者との関係が良きものであることとが,分かち難い関係の中で確かめられたことになります。このような母子関係の下では,自我は安定した機能活動に確信を持つことができます。逆に母親のサポートが不十分であれば,赤ん坊の自我は混乱することになります。
このように,親に感謝をする理由も,不満や怒りを持つ理由も,恐れる理由も,かなりの程度に親しだいです。
幼い子の怒りは,親のサポートが不適切であるという表明であり,改めて適切に対処して欲しいという合図です。
怒りをあらわにする子に対しては,親が真剣に取り組まざるを得ないだけに,解決に向けた努力が払われ易いといえます(体質的に怒りの度が過ぎる場合もありますので,うまくいくかどうかは一概にいえませんが)が,怒りを表に現さず,従順に見える子は,その傾向が災いして周囲の大人たちも問題視し難くなりがちです。表の従順は裏の不従順の表れであるとすれば,それは親を恐れる心からであると知っておく必要があります。
親に従順な子の場合,その親密さは見せかけのものであり,欲求の不充足感と怒りとを幼い自我が抑圧している可能性があるのです。そうであれば性格形成の上で難点を残すことになります。親としてもそれで満足したり,場合によっては子供のそういう傾向に乗じたりするのですが,子供の心には,抑圧が生み出した影の勢力が増大している可能性のことを考えなければなりません。
後々,心に障害が生じて医療の介入が必要になったときに,怒りは問題の在り処を指し示すセンサーのような役目を果たします。この感情に注目することで,隠蔽されていた負の体験を明らかすることが可能です。怒りの所在に注目することは,心の障害を取り除く上でも重要なものです。
心の障害を,治療者が親子の関係の側面から見る必要は大いにあり,それは鉄則であるといっても間違いではありません。
親子の関係を問題にするにせよ,しないにせよ,目的とするところは,障害をかかえている本人の利益にあるのはいうまでもありません。それはその母親,父親についても同様で,親子関係に問題があるのではないかと疑われるのは親の立場では不愉快でしょうが,親に対しても利益が還元されないはずがありません。障害を受けている子供だけがその利益を受け,親はそうではないなどということはあり得ないことです。もしそう考えて不快に思う親があるとすれば,それは親としては大いに問題であることを自ずから示していることになるでしょう。
残念ながら,この種の問題提起に,不快,不満を持つ親は少なくないどころではありません。むしろ一般だといっても過言ではありません。
明快な拒否感を持つ親は,そもそも治療者の前に現われることがありません。一見は協力的な場合でも,問題の根にまで理解を深めることは容易ではありません。親子が負の依存でつながっているからだと思います。親子の負の依存関係は,元はといえば親の側に,自我が処理し切れなかった負債ともいえる分身を意識下に蓄えていることによる可能性があります。それらの分身が要求するものを,自我が引き受けなければならないのですが,引き受けない(弱い)自我が他によって分身の不満を満たさせようとするのです。そのような自我の下にある母親にとって,赤ん坊は恰好の相手になります。赤ん坊は母親にとってはある時期まで自分の一部のように相互に密着した関係にありますので,意識的にか無意識的にか赤ん坊が自分を助けるように仕向けることが可能です。そのようなことが母親に起こりやすいのは,赤ん坊に対して特権的な立場にあるからです。ですから無自覚でいると,母親は赤ん坊に依存し,赤ん坊を助けるよりは自分を助けるように仕向けることになりやすいのです。母親が抱える意識下の負債が大きければ大きいほどこのようなことになりがちで,その依存の対象にされた赤ん坊もまた,自我の自律性が損なわれて,いずれ意識下に負債を抱え込まざるを得なくなります。
Wさんは主婦です。子供はいません。初診は29歳の夏でした。過呼吸状態で一人では歩けず,父親に背負われての受診でした。一週間ほど微熱がつづき,胃に熱感があり,食べ物を口にすると吐いてしまい,内科で栄養失調といわれていました。
初診の3年ほど前に結婚しました。初診の数日前に,夫婦二人の生活から両親が住む実家へ住居を移しております。父親が,「子供はまだか」と気にするので,「家が狭いから」とかわしたつもりが,実家に引越しをする羽目になってしまいました。父親に家を改造するからといわれると断れなかったのです。Wさんは自分の意見,意志を明確に出来ず,相手がだれであっても,「いやです」といえない性格です。夫が気を使うだろう,自由がなくなり申し訳ないといいますが,その後の経過から,この心配はWさん自身のものでもあるのは明白です。受診の動機となった心身の不調は,この転居と大いに関係があります。
Wさんは一人っ子です。過呼吸発作が始まると,いつも父親が手を握ってくれます。母親は決してそういうことはしません。この一事からもうかがわれるように,母親は母性に問題があるようです。Wさんは,幼いころから母親に罵られながら大きくなりました。何事につけ,役立たず,お前にはできっこないよなど否定的な言葉を投げつけられ,ほめてもらった記憶は皆無です。あんたなんか生まなきゃよかったと何度となくいわれました。赤ちゃんのときお湯を使わせたことがなかったとか,泣いても放っておいたとかわざわざいって聞かせるのです。2歳ほどのとき食べものを喉につまらせて,吐いたものが母親の顔にかかりました。いきなり平手打ちされたのを覚えています。
そのように育てられたのですが,父方祖母(この人には可愛がられました)に母親のことを悪くいわれ,あんなふうになるんじゃないよなどといわれると,おかあさんが好きだと,母親を庇うように心でつぶやきました。母親が身体の具合をわるくしたり,悲しそうな顔をしていたり,そのようなことがしばしばありました。母親を,怖いと思うのと可哀想と思うのと両方の気持ちが交錯するといいます。また両親の仲がわるいので(母親が一方的にののしる),Wさんは意識して笑顔を作っていたといいます。実際,Wさんは笑顔を絶やさない人です。その表情からは推し量れませんが,こんなことをいっていいのかなとつぶやきながら,心の奥に潜んでいる殺意を打ち明けることもあります。対象は母親と夫です。夫のことは尊敬しているし愛してもいるのですが,いつも仕事で帰宅が遅いので,しばしば私がいやなのか,私が負担なのかと気になるのです。しかしながらWさんがそのような激しい心を打ち明けることができたのは,心が回復してきている証拠です。
友達にも,頼まれると断ることができませんでした。常に機嫌よく引き受けてしまいます。しかし自分の問題を客観的に見る力がついてくるにつれ,自分の意志を表すことができるようになってきました。相手がどういう態度に出ようが恐れないという気持が芽生えてきました。これまでの優しさが,見せかけの仮面であったこと,自分がほんとうは怒っていたことに気がついてきました。本当は好き勝手なことばかりいう友人など,友人ではないとひそかに思っていたのです。そういうこともいえるようになってきました。従来は,ひそかにあった怒りは醜い心で,あってはならないことに思えていました。そういう心が自分にあることを意識したくなかったのです。しかしいまは違います。怒るだけの理由があるので優しいふりをする必要がないのも分かってきました。
Wさんは人に優しくしていないと,自分が意地悪に思えて不安になります。しかし意地悪なところがあるとしても,それはそれで受け止めるしかありません。事実は事実です。知らないでいるよりは知っているほうがよほどましです。意地悪なところがない人などあるわけもありません。自分に意地悪なところがあると知っていることが,それを克服するための最良の態度ではないでしょうか。Wさんはそういうことを理解するようになってきています。それにつれて母親に対しても以前のようには気を使わなくなりました。
怒りは重要な感情です。つよいエネルギーをはらんでいるので,怒りが爆発すると人との関係を破壊しかねません。内向すると自分自身を打ち砕きかねません。そういう不安を覚えることは誰にでもあると思います。
怒りのエネルギーが強いと,自分に対しても(重要な)他人に対しても,要求の水準が高くなります。要求が高くなると,望ましいイメージどおりでなければ納得できず,苛立ちを隠せなくなります。
怒りは”心の沼“の守護者のような働きをするように思われます。”沼“は意識が受け入れなかったものの負の集積所といえるでしょう。自我が怒りの活動に応えるときに,怒りが守護者であった意味が現実のものとなります。しかし自我が怒りに対して恐れをなすようであれば,怒りは黄泉路の国からの使いになりかねません。強い怒りによって機能不全化された自我は,心全体の指揮を取り,自己を指導する資格がないのです。
負の活動は生まれたときからはじまります。思えば誕生という祝福されるはずの出来事が,そもそも負の体験そのものである節があります。母親の胎内という安楽境にまどろんでいるときに,いきなり外へ放り出されるのが出産です。新生児は驚きもし,怒り狂ってもいるようです。児童心理の研究者によってその種の指摘がされています。
赤ちゃんは安楽境に匹敵する大安心,大満足を要求して猛り立ち,時には満ち足りた気分にもなり,そういうことを繰り返しながら母親に助けられて,しだいに現実的な,ほどほどの満足を受け入れていくことになります。
人間の誕生は自我の授与でもあります。人間の人間たるゆえんは,自我に拠るということです。
自我は人間自身が自分の力で身につけたものではあり得ません。生まれるときに備えられたものです。それを授けたのは誰かといえば,あまりに人間的な問いということになるでしょう。しかしながらそれは不可知の力によって,人知のおよばない力によってというのは明らかです。その超越的な力を表す主体は,無意識の世界に内在して自我の後ろ盾になっていると仮定的に考えることができます。
それは科学的という観点から実証不能ということで,荒唐無稽であると考えることも可能でしょう。しかし歴然として人知を超えたものの存在をどう扱えばよいのでしょう。それは科学では証明できないから留保するしかないというのであれば,それはそれでよいでしょう。しかしそうした留保は,超越的なものの存在を認める姿勢と何ら変わりがありません。
また科学的に証明できるもの以外は認められないというのであれば,それは科学至上主義ということになります。いわば科学ないしは人間の理性を,最上位に据えることに他なりません。これがいかに謙遜を欠いた態度であるかは,地球環境をまるごと危機に追いやった現実を見れば明らかです。自我に拠る人間は,その上位に立つものの存在を認め,怖れを知るべきです。
このように考えると,自我に拠る人間の存在理由は,自我を授与した超越者の意志を引き受けるものということになります。
かつてソクラテスが実践したのは,このことでした。彼は神の助手を自認し,神の意志(彼によれば子供のころから,鬼人か何かからの合図があるといい,何事かに心を奪われ,没入する様子があったといいます。その様子は,彼を信奉する人にも神秘的,奇異と映ったようです。現代の科学万能の時代であれば,ソクラテスは幻聴に聞き入っていたということになりかねません。また時代が違うと一蹴されてしまいかねませんが,それはソクラテスを時代の迷妄の産物といってのけるのに等しいことです。人間を取り巻く状況は,今も昔もおなじです。ソクラテス的な神が,現代においてどのように扱われるかは重要です。その存在の実体が何であるかは,今も昔も,我々人間の認識能力を超えたものであることに変わりがありません)をアテナイ市民に伝えるのを使命としていました。ソクラテスの愛知というのは,神命を引き受ける精神というところに行き着きます。
それにしても,大満足をあきらめて小満足に甘んじる仕方を習得していくのが人生だとすれば,一体人間とはなんなのでしょうか。幸福の追求とはなんなのでしょう。
この問いに答えるには,幸いにして人の心には無意識という広大で,不可知な世界があるというところに行き着くでしょう。この世界も人間の持ち物です。そしてソクラテス的な神は,いわば主体として無意識の領域に内在すると考えることが可能です。それは自我に拠る人間に,測りがたい力を秘めた後ろ盾となっていると考えてよいように思われます。
赤ちゃんの大安心,大満足の現実の提供者は,主に母親です。自然な母性に従う母親は,赤ん坊に一体化して没入することでそれに応えているのです。そして母親にできるのは,大安心,大満足の提供ではなく,ほどほどのものでしかないのだということを,身をもって赤ちゃんに教えることです。赤ん坊の心に潜む大安心と大満足への要求とは,母親の胎内にあった充足に匹敵するものの要求と思われるので,この世の現実を生きるためには,ほどほどの満足,ほどほどの安心(安全)に甘んじる必要があると教えることは,何よりも大切なことです。言葉を換えれば,母親の愛情とはこの程度でしかないということを教えることができるのは,豊かな母性のみであるということです。母親がこの役割を良く果たすことができなければ,赤ん坊のこれらへの要求は,約束の不履行の感覚として,意識下にいつまでも残ることになるのです。それはこの世を地獄化する大きな理由になります。
たとえば授乳について,母親は赤ちゃんが望むときにするのではなく,決めた時間にするとき,赤ちゃんの感覚は混乱し,安全感が危うくなるとイギリスのウイニコットという児童精神科医が述べております。たとえていえばこのように,母親は,知識に拠ってではなく,自らの本能的な知恵で育児に当たらなければならないのでしょう。赤ちゃんの人生の生殺与奪の権限が,母親に託されているといっても過言ではないと思います。大きな責任と大きな喜びとが母親に特権的に与えられているといえますが,それを喜び,誇りに思うか,迷惑千万と思うかは,人間の幸福と不幸の問題です。
それはともかく乳幼児の負の体験は,のちのち記憶としてとどまることはないでしょうが,その事実は消滅することはなく,無意識が預かることになると思います。そのようにして,”心の沼“が形成されていくのです。沼を構成するものは,感情の面では,恐れ,おびえ,寂しさ,虚無感,抑うつ感,疎外感,孤独感などで,またそれらの感情の基となった体験群であろうと思います。そしてそれらの辛い体験は自ら望んでしたものではなく,押しつけられたと感じたものです。それは理不尽と感じられ,怒りを伴います。これらの問題を捉えて解決に当たるのが自我なのですが,問題が大きすぎると,自我は回避的な態度を取ります。そういうときに,怒りは,”沼”を構成するものの,いわば守護者のような動きをするようで,主君である自我を脅かす勢力になるのです。
母親に叱られたときの乳児の恐怖は,母親が意識するものを超えている場合があります。乳児に愛情と信頼とが十分に伝わっているときには,母親の叱責は彼女の意識するレベルにとどまるでしょう。しかし,彼女が意識する以上の恐ろしさを乳児が感じるとき,それは乳児自身が大きな怒りを持つていたためかもしれません。自分の怒りが母親の上に投影されて,母親が鬼のように恐ろしい顔で怒っていると感じられることはあり得ることです。
あるいは母親が持つ“心の沼”に潜む怒りが,赤ん坊に感じ取られることも起こり得るでしょう。怒りをはらんだ“沼”には元型的なエネルギーが入り込んでいると思います。それは常識的な理解を超えたエネルギーが怒りに蓄えられていることを意味します。そのために場合によっては鬼のような怒りになるのです。
無意識の根底に,動物でいえば本能に相当する心の元型があると,ユング心理学ではいわれております。これは人類の長大な歴史を越え,民族格差を越えて,だれもが経験し,あるいは経験し得るものとして,人から人へ受け継がれてきた普遍的な心理現象の基となっているものです。人が個別的に学習して獲得するための原基となるもの,学習以前の生得的なもの,本能のように刻印されているもの,そういうものが心の深層にあるとユングが確信して,命名したのです。この元型には強力なエネルギーが込められています。
元型の一つに悪元型があります。それは文字通り悪に通じるものですが,一般的には,古い心の体制を破壊して,新しく心の組織をよみがえらせる上で,大切な役割を果たすと考えられております。いわゆる死と再生に関わるのです。この悪元型には怒りのエネルギーが強力に布置されております。この元型が賦活された状態にある人を前にすると,おのずから緊張を強いられるかもしれません。
虚無や孤独や寂しさや恐れなどが,「底なしの」とか,「途方もない」とか,「奈落に落ちるような」とかの言葉で形容されるのが,“沼“を構成する感情の特徴といえます。それらの感情は,人間の言葉では捉えがたい無限定なもの(死にも通じると思います)に触れたために生じているようでもあります。つまり,人間は有限の存在ですが,それら限定できないものに包囲されている存在でもあることを,ふとしたときに感じ取ることがあるものです。
星の群れがきれいに輝いている夜空を見上げるとき,ふとめまいを覚えたことはないでしょうか。そのとき宇宙の無限に触れたといえるかもしれません。そういう折の,途方もない無限感覚が,日常のありふれた体験の中にも入り込むことがあると思います。どこか空恐ろしげな気分に悩まされるとき,”心の沼”が活性化していると考えられます。
性格形成に与える母親の影響-その7(Updated 07/10/06)
■自我の形成 その1
#1 心の指導者(主我と客我)
心が成長するためには指導者が必要です。
心にとっての指導者は、心の内と外に存在しています。
母親がほとんどすべてである乳児期においては,母親は絶対的な指導者の立場にあります。
心の指導者が心の内部に存在せず、外部にのみ存在する乳児期は、乳児と母親とは絶対依存の関係にあります。
それは乳児のみならず、母親もまた乳児に絶対的に依存しているというべきです。
何故なら、そうした状況での母親と乳児の関係は一体のものである上に、そもそも依存というものは、相互的な関係であるからです。
しだいに長じるにつれ、母親のみならず、父親や祖父母などなど、周辺の重要な関わりを持った大人たちが、躾や教育などの指導をします。
それらは外的な指導者です。
そして、それにつれてしだい次第に、心の内部にも指導者が育っていきます。
このように影響力のある他者を取り込みつつ、他者イメージが育成されていくのですが、それを可能とする根拠は自我にあります。
心の中核にある自我の機構には、内的な他者の原基があると思われます。
それが受け皿となって外的な他者と協働し、他者イメージが育成されていくのです。
その内的な他者が、内的な指導者になります。
この内的な他者も自我の構成員ですが、その指導を受け、かつ受けた指導を再構成しておのれ自身のものとする構成員もあり、こちらがいわば真の指導者の立場にあります。
これらの自我の二つの構成員を、それぞれ客我と主我と呼んでおきます。
客我は内的な集合的他者で、主我は自己本来の主張を導くものである、と想定されます。
この関係を画家を例にして図式的に示すと、以下のようになります。
幼いあいだは、心がおもむくままに「お絵描き」を楽しみます。
この場合、幼児の無意識の心から、欲動が生まれてきます。
この欲動を引き受けて、絵を描くという行為に導くのが幼児の自我です。
その自我は、心の自然の要求に従っているので、主我ということになります。
やがて、絵の教師が指導者として現れ、お絵描き(主我による描画)を批評します。
教師の批判的指導を受けて、独りよがりだったことに気がつき、受けた指導に従おうとします。
自我は、この外部にある指導者を心の内部に取り込み、外的な教師がいないときでも、教えられたとおりに絵を描こうとします。
心に取り込んだ、この内的な教師が、客我の構成員になります。
これら心の内外の指導者が、仮に過度に厳しいとしても、画家の名に値するものであれば、主我は常に客我に屈することはありません。
主我は、いかなる場合でも、客我の支配から自由でなければ、「自分の絵」は描けないのです。
従って、おなじ理由から、心の構造が、客我が主我を支配する形になっているのであれば、絵は模写の域を出ることはできません。
一般的な日常の生活では、客我が心を主導していると考えるのが実際的であるといえます。
日常の行動は、いちいち考えながら推し進めるのではなく、パターン化されています。
エネルギー効率の上でも、パターン化されている方が合理的ですし、日常の行動はそれで足りるのです。
仮に、日常の個々の生活で、逐一「独創を意識する」とすると、エネルギーのロスが大きい上に、「個性的」というよりは、「変わった人」の印象を人に与えるだけのことでしょう。
日常は、常に変わらない姿が、周囲の人に安心を与えます。
しかし、こうした客我にいかなる場合でも従っていると、「退屈な人」、「変わった人」、「融通が利かない人」などなどといわれかねません。
当の本人にとっても、マンネリ化した日常では、退屈に悩まされることになるので、主我はそれなりに自由(柔軟)でなければなりません。
だから、「日常の中の非日常」は必要です。
「日常の中の非日常」では、心の柔軟性が問われています。
それは、主我が客我から自由であるという意味を持ちます。
例えていえば、ふだんは「自動運行装置」に任せておき、ここぞというときに「手動」に切り替えるのに、いくらか似ているでしょう。
主我が客我に支配され、自由が極端に束縛されると、人の目が過剰に気になります。
客我は客観的な他者と連動するのです。
客我に支配され、自由を束縛されている主我の下にある心は、自己を評価する基準が抽象的、集合的他者になります。
それは、客観的な外部の他者に認められるかどうかが、自己の存在意義にかかわることになることを意味します。
こういう心の状況では、客我が威嚇的、高圧的になるので、いわば100点を取って当たり前になります。
仮に上司が高圧的であっても、それは具体的で客観的な他者との個別の関係なので、主我が自由であるかぎり心が屈することは滅多にはないでしょう。
しかし、客我が主我を凌駕する心の構造があれば、例え上司が理解のある人であっても、100人もの過酷な上司に囲まれているに等しい気分状態になります。
このような状況では、主我は無意識から立ち上がってくる恐怖に圧倒されます。
いわば恐怖の色眼鏡で外的な他者を見るので、個々人を個別に、客観的に見ることができなくなります。
個々人への対処ではなく、いうならば、周囲の100人が100人ともが恐怖の対象になるので、社会的な役割の全般にわたって、すべての他者から無理難題を押しつけられるのに等しくなります。 (主我が恐怖によって破壊的な影響を受けて機能不全に陥ると、周囲の者に迫害されたり、監視されたりという妄想、幻聴に発展します)
そういう心的状況では、常に100点満点を強迫的(脅迫的ともいえます)に要求されるに等しいことになるので、義務を果たすばかりの、喜びのない、頑張りつづけるしかない日常になります。
こうした状況が長期に渡れば、やがては弾性限界に達したバネのように、心の弾性がくず折れるとしても不思議はありません。
一般に、困難な状況に置かれると、主我の動きが鈍くなり、相対的に客我が心を支配します。
それは、いってみれば、伸るか反るかの分岐点に心が立たされることになり、不安の増大は避けられません。
不安の大素には、恐怖があります。
その状況を越えることができなければ、挫折という心の崩壊が待っています。
それを免れることができない予感が、恐怖をもたらします。
こういう状況では、動きの鈍い主我に対して、客我が威嚇的にもなるので、主我が試練にさらされることになります。
そして、置かれた状況が客観的にも困難なものであれば、主我が客我を凌駕する力強さがもとめられます。
それが力強く発揮されたとき、天才的であるということになるのでしょう。
一方で、発育不全(親の躾けなどに耳を貸さないのが、習い性になっているなどで)の客我と共にある主我の下では、天才気取りの自称芸術家か、いずれにしても独りよがりの人間になります。
この場合は、社会への適応が難しくなります。
主我は、客我の影響を受けつつ、刻々と無意識層から贈られてくる新しい生命(欲動)を引き受けて、行動化する使命を持っています。 (無意識界には二つの層があります。一つは意識化が可能なA層、もう一つは意識化することが不可能なB層で、このB層は大自然が心に及んでいるものです。欲動はB層から贈り出されてきます)
自己に固有の生命的世界は、そのように展開されていきます。
主我は、客我の意向と、このB層から送られてくる新たな生命の誕生(大自然の贈り物)とを引き受ける立場にあるので、両者の意向が矛盾するときに、主我は選択を迫られて葛藤します。
それは、例えば次のようになります。
友達と遊びに行く約束をして帰宅したところ、母親に、「遊んでいないで勉強しなさい」といわれたとすると、母親の意向と客我とが連動し、遊びに行くことの動因として生起している生命とのあいだで、主我は葛藤に苦しみます。
客我が有力で、母親の意向に逆らえないときには、新たに生起した生命は抑圧されます。抑圧されたその生命は、怒りと共にA層に留まります。
しかし、改めて母親の意向を客我の意向と連動させてその意義を認めなおすと、「勉強をする」ことは、新たに主我が引き受けたことになり、自分自身の問題とすることができます。
そして、それに相応してB層から新たな生命が送り出され、主我との協働で勉強をする確かな意志になります。
しかし、母親の意向を理不尽と感じながらも、母親と客我の権勢に押されて盲従するとき、主我は客我の傀儡となり、自分を護れない臆病者になります。
つまり、B層から生起しているもっともな生命の誕生を無視することになりますが、それは母親の意向を理不尽と捉える明確な心が欠落していたのと並行して、主我が自分自身に理不尽なことをすることになります。
主我が、正当にも、生起している生命を護ろうとすると、母親と衝突します。
客我は、それなりに強くなければなりません。
それは主我の独りよがりを補い、社会一般の常識を教えます。
その上で主我が客我に対して自由であるのが健全な心です。
主我と客我が対立し、しかし補い合い、その上で主我が心を主導するとき、心は自立しています。
その母親が気弱であれば、あるいは幼い子の怒りが強く、聞く耳を持とうとしないなどの傾向があれば、客我の育ちがわるくなるかもしれません。
気弱な客我の下では、主我は生起する新たな生命を無批判に受け入れるので、勝手気ままな幼稚な心になります。
その場合は、社会性が怪しいものになり、場当たり的な行動を繰り返すことになるかもしれません。
いずれにしても主我によって抑圧された生命たちは、A層に終結します。
A層に終結している生命たちは、主我に受け止められなかった恨み、虚しさ、寂しさ、悲しみなどなどと、そしてその理不尽さへの怒りと、それらの感情と共にあることになります。
客我に支配された主我の下では、A層の生命たちは、不当に抑圧されたことになり、逆に主我を支配、拘束することにもなります。
それは、治療を要する病的な心の状況です。
A層の生命たちは、いわば、生きる喜びのために生まれてきたものが、「受け取れない。死んでちょうだい」と、主我に拒絶されたものたちに等しいのです。
実際、A層の分身たちは、死の極を目指すことになります(心には、生命の極と死の極との対立があると考えられる合理的理由があります)。
大自然の力と人間の浅知恵との力較べは、本来は比較にならないことであるので、客我が主我を支配しつづけるほどに強大であるときは、心はいかにも不自然な状況になると共に、豊かな人間性から程遠いものになります。
乳幼児の主我が、必要以上に母親との関係を優先させざるを得ない何らかの事情の下に置かれれば、母親との関係を護ろうとしないわけにはいかない(見捨てられないように、母親に盲従しようする)ので、大自然からの贈り物を不当に拒否することになります。
そうしたことが起こりがちであれは、乳幼児は、自縄自縛に陥る途を選んでいるのに等しくなります。
それは、自らを窮地に追いやることになります。 (母親との関係を優先させざるを得ない事情が傾向的に大きくなるのは、次のような場合が考えられます。母親の健康に問題があるとき、父親が家庭を省みない何らかの事情があるとき、両親が不和であるとき、母親の心が未熟、幼稚であるとき、幼い子が過敏であるとき、などなど)
他者との依存関係を存在条件としている人間の心の構造の中心にあるのが自我ですが(唯一の中心ではありません。自己の中で、生命的世界を展開する心の中心です)、この自我を、先に述べたように客我と主我とに分けることは、精神の問題を理解する上で合理的な意味があります。
そして外部に存在する他者と連動する客我と、真の指導者の立場にある主我とが、対立し、補完し合う様相によって、性格のパターンが決まります。
依存は依存であっても、主我と客我とのそれぞれの強さの程度や、両者の相対関係によって、自己の自立性の程度に、違いが出てくるのです。
赤ん坊に最も必要なのは、安心と満足です。その両者は、それぞれが別なものではなく、共にあるものです。
安心がないところに、満足はなく、満足がないところに安心はありません。
そして、赤ん坊は無邪気に育っていくだけのものではなく、大安心と大満足とを母親に要求しつつ育っていくのです。
ということは、赤ん坊は、安心と満足とを脅かされがちであるということです。
赤ん坊は、安心が‘全’でなければ、いわば立命できない気分でいると思われますが、現実にそれが理想的に適えられることはありません。
母親が、赤ん坊に、安心、満足をもたらす役目を持っているのは当然として、何らかの事情で不安感、不満足感を与えてしまうのは避けられません。そういうときに、赤ん坊の疑いに、現実的な理由を示すことになります。
母親は、欠けることのない愛情を注ごうとするよりは、‘全的な存在’ではないことを伝えるのが、むしろ愛情であるのは明らかです。
母親が‘全的な存在’ではないのが明らかだからです。
自立心に欠ける母親の中には、赤ん坊に、「すべてを注ぎたい」と考える場合もあるかもしれません。
そういうときに、甘やかしすぎて赤ん坊の自立性を奪うことになるかもしれません。
それは愛情が大きいのではなく、母親の不安が大きいからに違いありません。
母親自身の満たされていない心を、赤ん坊をいわば利用して満たそうとするに等しいので、実質は愛情に似て非なる自己本位のものといわなければなりません。 (ある境界性人格障害の患者さんは、「母親が欲しいものを全てあたえてくれた。そういうふうにして、子供である自分を支配しようとしてきた」といいます)
良かれ悪しかれ、二心(ふたごころ)を持っているのが人間です。
どんなに優しい母親でも、赤ん坊に注ぐ愛情は、赤ん坊に対するものである一方で、母親自身の利得を無意識のうちに意図するものです。
それは良い、悪いの問題ではなく、人間の特徴であり、事実問題です。
この意味で無私の愛情はあり得ないので、‘全’を要求する赤ん坊に疑惑を与えるのは避け難く、不安、不満足を覚えさせないようにするのは不可能です。
‘全’であってほしいほどに頼りとする母親であるがために、その裏返しとして、母親は大不信の発信源になる理由を持っているのです。
そういう折々に、赤ん坊が、心を震撼させるような大きな恐怖経験に見舞われても不思議はありません。
それが全面依存の身である赤ん坊に不可避な、見捨てられることへの恐怖の意味です。
見捨てられる恐怖は、生死を賭けた恐怖です。
このように見捨てられる恐怖は、人間であるが故の根源的なものであり、あらゆる恐怖の起源です。
それは無意識的な恐怖であり、しばしば得体が知れない恐怖感をもたらします。
いうならば心理的な意味で、見捨てられる恐怖は「諸悪の根源」で、さまざまな、というよりはあらゆる病理的現象を惹起させます。
人前での過度の緊張、過度な明るいふるまい(無意識界にある恐怖、孤独感などを隠すふるまいです)、過食、拒食、買い物、アルコール、ギャンブル、自傷、盗み、等々の依存症などなどをはじめ、すべての精神疾患の根底に、見捨てられる恐怖が潜んでいます。
見捨てられる恐怖は、人間であれば誰であれ、例外なく意識の根底に存在していると考えなければなりませんが、その度合いが強いときに、主我は生きる本能を優先させて、母親を怒らせないように、迎合する戦略に走るのです。それは同時に、自動的にB層から生起してくる(大自然の贈り物である)新たな生命を抑圧することになります。そういう傾向が優勢になると、客我が主我を支配する構造が出来てしまいます。客我に依存する主我は、いわば自由を放擲して、よい子になります。
以上のような事情がありますが、最善の母親とは何かといえば、自然の心を豊かに保っている母親ということになると思います。
それは高学歴であるとか、知能指数が高いとかとは、直接の関係がありません。
むしろ、「頭でっかち」の母親は、自然の心の豊かさに問題があるかもしれません。そういう母親は、赤ん坊に(育児に)専心するのが難しいのではないかと思います。
前者の母親であれば、二心についても、自然に身についた知恵が働くでしょうが、育児に専心できない後者では、関心がそがれている分、知的に理解しようとするでしょう。そういう母親は、当然ながら、赤ん坊の心に敏感になるのが困難だろうと思います。
そういう事情があるので、母親は、自分が赤ん坊に愛情を注ぐのは、赤ん坊が可愛いからだけではなく、赤ん坊の成長によって母親自身が仕合せになりたくもあるからだということを、知っている必要があります。このことに鈍感な母親は、母親自身が無意識界に何らかのコンプレックスを持っているに違いありません。
見捨てられる恐怖は、精神の病理現象を招く元凶といっても過言ではないと思いますが、否定的な性格をしか持っていない、というものでもありません。
肯定的な意味は、まさにこの否定的な意味の隣にあります。
つまり、見捨てられないように、対他的な何らかの行為を試みることによって、他者との関係を計る理由があり、それは必要なことです。
そのことによって他者に認められ、他者に認められることを通じて、自分が自分自身を認めることができ、いつか自己肯定感が育っていきます。
いうならば不足感があるがために、充足をもとめる理由が生じることが可能になるのです。
見捨てられる恐怖は、心のさまざまな病気を招く諸悪の根源であるといういい方をしましたが、その恐怖の存在自体が問題なのではなく、それが過度にわたるときの話です。
先に、自我は心の中心であるが、唯一のものではないと述べました。
もう一つの中心は、B層にあります。
B層は大自然が心におよんでいる領域で、心の無限性を保証するものです。つまり、この層は、全であり、無であるという性格を持っていて、自我(と、それによる有限の世界)はここから生まれ出てきたとも考えられるのですが、いずれにせよ、自我を根底で支える拠り所です。
この層の存在と死(無)の存在とによって、自我の有限性は補完されています。
つまり、そのときどきの志向対象との関係で、そのつどの自己を刻々と超克し、生命的世界を展開する主体である自我は、そのときどきの志向対象との関係にかぎっていえば、有限のものであり、目的に到達するたびに潰えます。それは、そのつど無(死)の無化作用を受けるということです。
一仕事を終えて、その充足感の余韻に浸りつつひと休みしているうちに、虚無の気配が忍び込み、不安に駆られることになります。それは次なる行為を促します。自我が健全な状況にあれば、改めてB層から新たな生命が送り出されてくるので、自我はそれを受け止めて新たな志向対象へ向かうことになります。
そのように自我は、死に由来する無化作用と、B層に由来する大自然から生まれ出てくる生命との、二つの無限性のものとの関係において補完されています。
つまり有限のものである自我は、逐一の行為が(死の別名である)無の無化作用によってそのつど潰え、B層との関係によって、そのつど新たに蘇るのです。
いわば人の心は、日常的に、生まれ、そして死んでいるといっても過言ではありません。例えば、夜が来て眠りに着くのは死と区別がつけにくい面がありますし、健やかな気分で朝を向かえるのは、新たな生命の生起といってもおかしくありません。
結局、自我は有限のものですが、無限性のものである死とB層とによって補完され、いわば「生きているかぎり無限の性格を持っている」ことになります。
死は自我にとって超えることができない壁です。
しかしながら、死は、いま述べたように、生を単に阻むもの、無意味化するものではありません。
生を主宰する自我にとって、死は超克することができない壁である一方、生と死の相容れることのない対立が、希望を生み出す根拠になります。
希望が成立するためには無限性が必要ですが、それを保証するのが死と、B層にあたる無意識界です。
繰り返しになりますが、自我は、生命の誕生(B層からの贈り物)と死との狭間にあって、死の超え得ない壁に挑みつつ、B層からの新たな生命の誕生を受けて、いわば生と死とを日常的に演出していると考えることが可能です。そこには、明瞭に有限のものでありながら、内に無限性をはらんでいるという、自我の特有の性格がうかがえます。
自我は、そのつど何ものかを志向します。
疲れてぼんやりとしているときであっても、自我が放つ光りである意識は、虚空を無意味に漂うのではなく、志向されている何ものかをぼんやりとまさぐっていると考えるべきです。そして、志向され、課題化されている何ごとかを超克したときに、意識はふたたびぼんやりとした状況に置かれます。それは、しかしながら、課題を超克したことへの満足感の余韻と共にあるでしょう。そして、また、しだいに死に由来する無の無化作用を受けて、不安、寂寥、虚無などの感情に悩まされることになります。そのように(死に)挑発されて、次の志向対象へと向かう意志をしだいに明確にしていきます。
そのようにして、「生きているかぎり、可能態としての希望が保証されている」といえるのです。つまり自我による生命世界の展開は、明瞭に有限のものですが、しかしながら、内に無限性を潜ませているといえます。
「生きているかぎり無限性を生きる」というのは論理的に矛盾しているように見えますが、矛盾こそが人間の本質であり、可能態としての「生きる無限性」が生み出される理由です。
生命的世界、有限の現象的世界を主宰するのが自我であるのに相応して、人間の心の内なる大自然の中にも心を主宰するものがあると考える合理的理由があります。
その主宰者を、内在する主体と呼んでおきます。
内在する主体は、心全体の主宰者です。
自我は意味を紡ぎ出す役目を持っていますが、主体は、沈黙のうちに心全体を統括しています。
自我が、沈黙する主体の意向を探り当てる方向で世界を展開できるときに、揺るぎない充足感、「これでよいという安心感」が心全体を覆うでしょう。それが沈黙のうちに存在する主体の答えです。自我の仕事への肯定的評価です。
そのような心は、主我が主導性を確保できている自立的な心です。それはいわば自由な心なので、精神が病理性といえるほどの事態に陥ることは考えられません。
そうした主我の育成には、幼い時代に母親に甘える体験を十分にすることが大きな意味を持ちます。
それは内在する主体からの贈り物を、幼い主我が受け止めている姿だからです。
それは、躾の中心にいる母親が(不当な)介入をせずに、従って客我がいまだ未成熟なので、主我が存分に自分の力を楽しむことができているからです。また、それは、内在する主体との関係が純粋に近い形で営まれているので、それを尊重して見守っている母親の態度に大きな意味があります。そのことは、内在する主体との関係で幼い主我が活動することが、もう一方の主体である母親に是認されている意味を持ちます。それは、即ち、母親の愛と信頼とに他ならず、人間関係一般に重要な意味を持つそれらのものに、基礎を与えることでもあるのです。
以上、述べたように、赤ん坊が置かれている心理的状況を推察することから、人間の精神の重要な問題の一端が、垣間見えるように思われます。
それらを列挙すると,以下のようになります。
嬰児は,全なるものの世界から,全ならざる世界への移行を果たさなければならなかったらしいということが第一の要点です。換言すると,赤ん坊は生まれる以前は,全なる世界の住人であったと仮定されます。
母親に絶対的に依存し、全であることを要求しているらしいということから,逆に、母親が全なるものではない予感を持っていると思われるのが第二の要点です。
何らかの不快感にとらわれているときに示す激しい怒りの表出から、赤ん坊が母親を支配しようとしている様子が窺えます。そのことから,「欠けるものがある存在者」であるが故の不安の脅威から、「満たされている存在者」への移行を、「全なるものである母親」に要求しているという推論が成立するように思われます。そして、それと共に、「欠けるものがある存在者」であることを受け入れる準備をしているらしい、と推論することが可能です。
全ではない者が受ける脅威とは,「欠けるものがある存在者」が、既に部分的に、無の無化作用にさらされていることを示していること、その無化作用が存在の全面におよぶことの予感(死の脅威に直面することに他なりません)から来るのであろうということが第三の要点です。それは、母親に見捨てられる恐怖といい換えることができます。
補足 人間の誕生は、自我の誕生です。自我は生を展開する首座にありますが、生はその裏面に死を併せ持つことによって存在可能です。このことから、自我の誕生は二項対立の世界の誕生といえます。事実、心は、自己と他者、男と女、善と悪、愛と憎しみなどなど、いたるところに二項対立があり、その最奥に生と死の対立があります。 そして、自我が終焉を向かえて自己が無に帰するときに、二項対立の世界である現象的世界という舞台の照明が暗転し、唯一性の世界に入るということができます。
また、例えば、「純粋に白い(あるいは純粋に黒い)」ものは現象的実体としては存在しないが、かぎりなく白に近い黒、(あるいはかぎりなく黒に近い白)」は、現象的実体として存在するといえるので、純粋に白い、あるいは純粋に黒いという全なるもの、あるいは無なるものは、単に概念的に存在するだけではなく、現象的実体の内部に含まれている」といえます。
いずれにしても、現象的世界の諸問題を合理的に理解しようとすると、人間的な理解の範疇を超えた超現象的世界のことどもが視界に入ってきます。現象的世界が有限のものであるといっても、内に無限性の性格をも含み持っているので、両者を截然と区分することはできません。従って、超現象的性格のものについても命名し、概念化する必要が出てきます。それは実証性を持たないので、何らかの仮説を設ける以外にはありません。その仮説の作業は、現象的世界についての概念を援用し、かつ命名する以外には方法がありません。
嬰児は母親に「全であること」を要求しつつ,そうではない予感を現実のものとして受け入れていく必要があります。それは全という「満たされている存在者」、あるいは自己完結態ではないという現実を承認することに他なりませんが、そういうことが可能となるためには、それに準じる存在形態を不可欠の要点としているといえます。現実を受け入れるとは、全をあきらめ、不十全に甘んじる心になることに他なりません。
つまり個としての存在であるそれぞれの自己は,「欠けるものがある存在者」として、他者との依存関係を欠かせない要件としています。それによって、他者との望ましい関係が得られれば、「満たされている存在者」に準じること、つまり不十全に甘んじる心になる基礎を得ます。また、更には無限性を帯びた人生を歩みつつ、自己の発展的達成に向かうことを通じて、「満たされている存在者」に限りなく近づくことができます。そのように、「満たされている」心そのものに到達することはできないが、そこへかぎりなく近づくことに甘んじることが、有限の「欠けるものがある存在者」の分であるといえます。そして有限の「欠けるものがある存在者」であるが故に、限りなく有限性を越え、無限性に近づこうとすることが可能であり、そのような意味で人間は無限性を生きているといえます。
自己がそれ自体で完結しているのではなく、いわば自己と他者とに分裂している「欠けるものがある存在者」であって、それが改めて自己と他者との合体によって、「満たされている存在者」に準じるものとなることが可能であるための前提条件は、他者を予め自己の構造(その原基である自我の機構)の内部に含んでいることです。つまり、他者は自己の外部に客観的に存在すると同時に、自己の内部に主観的に存在することによって、自己は他者との関係性において、「満たされている存在者」に近づくことができるのです。恋愛と、それに伴う熱情とは、「満たされている存在者」であることが現実に適えられることはないものの、いわば瞬間的に類体験していると考えることができ、従ってそれは、人間存在がその可能態を内に含んでいることを証明していると考えることができます。
母親とのかかわりを通じて,乳児は自分の幻想的な欲求(生後2ヶ月ほどになると,母子一体の感覚が乳児に芽生えます。その時期,乳児の母親への愛情欲求は絶対的なものであるといわれます)が満たされたり,満たされなかったりしながら,しだいに自分とは別個の他者が存在することを知っていきます。
現実の母親は,乳児がもとめるような絶対的な存在ではないので,乳児の幻想は,始終やむを得ず破られないわけにはいきません。幻想が破られたときに味わう乳児の苦痛は,大変なもののようです。そういうときにはどんなに愛情深い母親も,悪い存在として激しい攻撃を向けられます。ある時期には,乳児はあらゆる人や物を我が物にしようと攻撃的になるのです。場合によっては、悪鬼に殺されるとでも感じるかのように激しく泣き叫ぶことも起こります。そのようにしてしだいに現実を受け入れていくのですが,その過程では激しい苦痛と恐怖を経験しないではすまないということなのでしょう。
この人は本当に自分を守る力を持っているのか,持っているとしても,自分にその力を与える気があるのかといった猜疑や疑惑の(認識ではなく感じ取る)虜になるときに,乳児の全能欲求が反転して,母親は悪いものをもたらす張本人に見え,欲求が満たされたときには,母親は願わしいものを具現する者になって見えるようです。人生の最早期のある時期までは、母親は、そのように良い母親と悪い母親とに分裂した別種の者として存在し、良い母親だけが母親であるという全能欲求が護られます。そしてやがては良い者も悪い者も,おなじ一人の母親として,統合的に捉えていくことができるようになります。絶対者ではない母親は,一貫し,安定した愛情を示しつづけることで,乳児が現実を受け入れていけるように手助けをしてあげなければなりません。
この世に生を受け,自己を形成していくにあたり,人は人生の入り口の段階で最初の,そして最大の関門に直面します。すでに容易ではない試練にさらされているといえます。母親の胎内で安らいでいるある時期までは,胎児は自然と一体です。それが誕生という形で自然から乖離され,自分の力で生きていく使命を負わされたのが人間です。その人間に,人生という難路を旅するために授けられた武器が,自我といわれているものです。自然から乖離されて,人間として人生を旅する第一歩が,どれほど不安に満ちたものか,いうまでもないことです。激しい不安や恐怖や怒りの渦をはらんだ闇夜の中に,人生の黎明が訪れます。自分の力でこの世を生きていく喜び,希望もしだいに芽生えていくことになります。
人生がどれほど過酷なものであるか,たとえばソクラテスが次のような趣旨で述べています。死刑の宣告を受け入れる心境の一端を語った言葉です。
「死は深い眠りと区別をつけ難く,深い眠りに勝る安らかな経験がはたしてあるだろうか」と。
この言葉は,人生に懐疑的というのではなく,死の否定的な意味をもういちど否定しているのだと思いますが,人類の教師ともいわれるソクラテスが,生きることの困難を語っているのが興味深いことです。
生まれる間もなく,過酷な苦痛が待ち構えている宿命のもとにあるのが人間です。それを耐え抜くためには,母親の安定した豊かな愛情による養育が不可欠です。
逆にそこに問題があれば,人生の第一歩にして,将来の多難が早くも予測されるといっても過言ではないでしょう。
人生は一幕の芝居であるといわれることがありますが,このたとえでいえば,人生の早期に台本を書き,演出するのは父親と母親です。そこには両親の願い,考え,感情,価値観などが込められています。成長するにつれ,両親以外の人が意図せずに台本に別の筋を書き加えます。そうした経験を重ね,両親が書いた台本や演出に疑問を持つようになります。そして,やがては自分の手で自分のために台本を書いてみたいと思うようになります。人生を自分の演出のもとにしたがえたいと考えるようになります。これは自然な願いです。
幼い心で考えたことですから,未熟なのは仕方がありません。両親の愛情のあり方に問題がなければ,幼い我が子の未熟な主張を成長の証ととらえ,その主張の中に無視してはならないものがあるのを見逃さないと思います。そういう余裕があれば,ひきつづき子供を正しく指導することができますし,実際にまだまだ指導が必要なのです。自分の手で台本を書きたい,演出したいという意識の芽生えは大切なことなので,それを育てるのは両親の重要な課題です。
心の指導者が,他者から自己自身へと移行する過程では反抗は必至であり,なくてはならないものです。
#2 自律機能と抑圧機能
幼く,未熟な自我の代行を母親が中心となってするに当たり,第一に重要なのは、幼ない自我の自律機能を護ることです。それは乳幼児の感情をコントロールするのではなく、感情を全面的に許容する心の姿勢を貫くことによって得られます。それにつづいて指示や禁止など、感情をコントロールすることで躾をすることになりますが、それは自我の抑圧機能に働きかけることを意味します。
「自我の自律機能」の提唱者であるハルトマンは,この機能を,「自我という生物学的ー心理学的構造体が,超自我,無意識,外界などとの相互的な葛藤,関係性から自由であるべく保証されている」という意味で用いています。 あ また抑圧機能は,フロイトによれば,例えば生物学的な本能のほしいままに任せるわけにはいかないため,などといった自己の防衛策ということになります。
ここではそれらのことをふまえた上で,自律機能を,生の欲動(フロイト)の一切を意識にもたらすものという意味で用いています。そして抑圧機能は,他者への配慮の無意識的態度という意味で用いています。
一例を上げると以下のとおりです。
欲しい物を獲得するのは,自律機能によります。他人の所有になるものを,欲しくても我慢するのは,抑圧機能によります。
従って,自律機能はより生得的であり,抑圧機能は後天的です。後者は,人間存在が他者との関係を必須のものとしていることと密接な関連があり、本能的、欲動的なものとのあいだを調整する役割を担っています。抑圧機能の発動は,他者への配慮,社会性の尊重という意味を持っているのです。従って、躾は抑圧機能の発動を促すことになりますので、たとえば母親が神経質で、注意を与えることが必要以上に多くなると、幼児は、却って身勝手な行動に走ったり、抑制的になって子供らしくなくなったりします。母親は、幼い子には十分に甘えさせることが重要です。それは、幼児が無意識の心の泉から湧き出てくる力を体験していることの邪魔をしない、という意味を持つからです。そしてそれは、幼児が母親に認められている、必要とされている、愛されているという肯定的な感情を育てていく上で重要な意味があります。
心の無意識層から生まれてくる欲動群は、すべて生命的なエネルギーを蓄えています。あらゆる行動は、これらの欲動に促されて可能になります。あらゆる行動には対象があり、これらの欲動は、目的とする対象をおのれのものとして関係づける動因になります。対象を自己化して所有し、それとの関係をいわば傘の骨として、自己の世界を発達させていきます。対象となるものが人の場合は、欲動は愛という性状になります。対象となるのが自己自身であれば、自己愛ということになります。自己愛というものが存在していることが、愛の性状を持つ欲動が自分の心の内部から生起し、自分の心の内部のどこか外的なものへ向かうことを示しています。自己は自己自身との関係でもあるのです。
これらの欲動群がどこから生起してくるのかは謎です。無意識層からには違いありませんが、それは、心の内部にあって我われには理解し得ないところから、という意味になります。従ってそれを生み出し、意識へともたらすものは、人間が意識できる範疇を超えているものによって、というしかありません。
人間であることの証明は、自我にあるといえます。人間は自我に拠って、自己を発展的に展開していくと考えることができます。では、この自我を授与したものは何かということになりますが、それもまた、解き得ない謎です。しかし自我を授与したものと、生命的である欲動を送り出すものとの主体者は同一であると考えるのは、精神の諸現象を統合的に考える上で有意味です。欲動群は生命の源であり、自我は生命を司るものです。欲動群は、自我の自律機能に即して生起し、それを受けて自我は、改めて抑圧機能によって他者との関係に配慮します。自我は、両者を調節し、統合する首座となるものです。
欲動群を送り出すものと、自我を授与したものを、ここでは内在する主体と呼んでおきます。それは自我の拠り所であり、心全体の首座をなすものです。
つまり自我は個々の自己の首座となるものであり、内在する主体は個々の自我の拠り所であると同時に、個々の人間存在を超えた普遍的なものです。それは心の内における無限性を保証するもので、全でもあり無でもあるという性格のものです。
自我の自律機能は,内在する主体との関係性において,欲動群が主体から送り出されてくることに直接関わるものであるのに対して,抑圧機能は多かれ少なかれ(意識的にか無意識的にか)自我の判断機能と密接な関係があります。
自我が自由で自立していれば,状況に応じた適切な判断が可能なので,自己を適切に護り,他者との関係も適切に護るために抑圧機能を発動させることができます。
しかし後の項で述べるように,集合的他者に従属させられている自我の下では,他者への配慮が優先されるので,過剰に抑圧機能を発動させることになります。言葉を換えれば,不当に自律機能を抑圧し,自己を護り,発展させる上で好ましくない心的状況が生まれます。
このような意味で,自律機能よりも抑圧機能の方が強力であるかぎりにおいて,自己は発展的であるよりは閉塞的になります。
心的状況がそのままに置かれると,自己の展開は困難になるので,自己否定の方向に傾くことになると思います。
再びそうした心の閉塞状況を打破するためには,心理的な治療の介入か,あるいは自律機能が自ずから発奮して巻き返しにかかるかすることが必要です。
結局,自我の抑圧機能の本来の役目は,自律機能を護ることにあります。
自律機能は動物一般に通じる自然のものですが,抑圧機能は人間に固有のものです。精神性と社会性とを要求されている人間は,他者の存在を尊重する上で自律機能がもたらしたものに修正を加える必要があります。
動物的な自然の要求と他者への配慮とを理想的に統合するのが,それぞれのあるべき自己の実現であると集約的にいえると思います。
自我はこの二つの主軸の機能を活動させるにあたり,思考,判断等の知性的な機能を駆使することになり,それらが精神性を自己にもたらすことになります。
他者との関係はすこぶる重要であり,取り分け原初の他者である母親は,乳幼児期には絶対依存の対象になるので,特別に重要な他者といえます。母親への絶対依存の関係にある自我の未成熟な時代の乳幼児は,客観世界の展開がまだ始まっていないので,まったくのイメージの世界の住人です。とはいえ客観世界の展開がそれとなくは予感されていないはずはなく,それを勘案すれば母親は絶対者であるのではなく,絶対者であることの要求であり,願望であると考えるべきです。
乳幼児の幻想的絶対者である母親が,実はそうではないかもしれないという予感は,受け入れ難い不安を伴うのではないかと推測されます。
赤ん坊が置かれている心的状況には,絶対性と非絶対性とのあいだの埋めることが出来ない懸隔が避け難く存在しています。その奈落への転落を免れるには,依存の対象である母親が,幻想としてであれ絶対者である必要があります。
この克服不能の懸隔が,赤ん坊をどうしても脅かします。その恐怖は,母親が絶対者ではないかもしれないという疑いがあってこそ生まれるでしょう。
その疑いは,母親が自分を見捨てるかもしれないという恐怖に直結するでしょう。それは,生死のかかった恐怖です。従って人間の根源にある恐怖です。そして,また,他者への不信の起源をなすものでもあると考えられます。
人はよりよく自分である以前に,自己の保全をはかる必要があります。
成人してからは,場合によっては両者の関係が逆転することもあるでしょう。
「肉体の自由は奪われても,精神の自由は渡さない」とか,「身体への拷問より精神的な拷問の方が耐えがたい」とかいわれます。
作家のドストエフスキーは著作の中で,労役刑の苦痛の中でも,Aの場所にある土砂の山をBに運び,再びAに戻し,果てしなくAからBへ,BからAへと無益に移動させつづける刑罰ほど耐え難いものはなかったと述べております。
しかしながら親の保護の下にある年齢では,精神よりも身体の保全の方が優先されて当然です。
そのような意味から,見捨てられる恐怖は,幼い子にとっては精神の問題というより全存在に関わる問題なので,親を怒らせないために自我の抑圧機能を活性化させる,強力な意味を持っていると思われます。
従って,しばしば抑圧機能は自律機能に優先するのです。
しかし「角を矯めて牛を殺す」の喩えのように,抑圧機能が自律機能を護るという本来の使命を超えてそれに優先するのが習いとなると,自己の発展はさまざまに阻害されます。
いずれにしても自律機能が健全に発展していける心の状況にならなければ,人生は「強いられた山登り」になります。
人生は無際限に高く,深い山を登るのに似ています。その時々に遭遇する人生の難所は,いわばその時々の難路です。その都度その難所を切り抜けることに山登りの喜び,希望があるように,置かれた状況がいかに困難であれ,そこに希望の光りの筋を見出して,その状況を克服していくところに人生の喜びがあります。そしてその中心に自我の自律性があります。
希望のない山登りは無意味です。自ら意志してはじめた山登りであれば,必ずそこに希望を見ているはずです。
人生という山登りは,自ら意志して開始されるわけではありません。その意味では強いられたものといっても過言ではないでしょう。
それを改めて自ら意志して,というふうな主体者意識を,まずは母親,そして父親が導き出すべく育てる必要があります。
何事も最初が肝心です。大人びた幼児のように,早すぎる社会性はむしろ弊害があります。抑圧機能を早々と活動させる以前に,努めて好きなようにさせておく(自律機能の発露を喜び,自己の力を知る)ことが,親の愛情というものです。それが十分であれば,この世も捨てたものではないという重要な意味を持ったウォーミングアップになります。
比喩的に登山と希望との関係を人生に当てはめてみると,次のようになります。
エベレストはいかに高い山であっても,それが客観世界のものであるかぎり,征服してしまえばそこで希望は潰えることになります。
その対比でいえば,人生の高山には限りがありません。つまり人生の山登りの山は,客観的ー主観的という性格を持っています。
この主観的性格には無限性があります。つまりこの山は,ここでお仕舞いという終点がありません。
「強いられた山登り」は希望のない山登りです。これほど虚しいものはなく,どこかで絶望するに決まっています。
子供のうちは親に認められ,褒められるという喜び,楽しみがあるので,「強いられた山登り」であっても,我慢をする理由があります。
しかし長じるにつれて,「強いる者」が外なる他者ではなく,内なる他者である集合的他者となると,自律機能が抑圧されつづけるので,人生という山登りは希望のない,強いられたものになります。それは,棒の先に括りつけられた鼻先の人参を追いかける馬のたとえに,どこか似ています。そこにも希望があるといえばあるのでしょうが。
フロイトはその欲動理論において,生と死の二大欲動の存在を仮定しています。生に関しては,その根源的な欲動の存在はうなずけるものです。しかし死については欲動といえるものかに疑問があります。
場合によっては死の衝動が存在しているのは厳然とした事実です。精神科医であれば,誰でも知っていることです。しかしそれが生への欲求とおなじレベルで,対抗的な欲求であることを意味するかどうかは別問題です。
死の衝動は一義的なものではなく,生への欲求が挫折したときに表面化する二義的なものとしては是認できます。
生へのエネルギーは,プラトンが述べているエロス的(身体的なレベルから高度に精神的なレベルにいたるもの)なものであり,それがすなわち生の欲動という大河に即していると考えられます。
別の箇所で述べた「表の自我」は,この生の大河の首座にあるものと考えることができます。従ってここでいう自我の自律機能は,この大河に即して機能する方向性を持っており,内発的であるが故にエネルギーを抱え持っている,といい換えることができます。
生の欲動というのは無目的に無闇に何らかの欲動が生起してくるというものではなく,一定の方向性があると考えるのが合理的です。
その方向性とは,心全体の主体(内在する主体)と生の大河の主体である自我とを軸にして,内在する主体が自我に向けて欲動を送り出してくるといったもので,それがここでいう自我の自律性です。
それは内発的で,心の自然な発露といえるもので,つまり生(エロス)のエネルギーをもたらすものです。
動物には一般に,このような内発的なエネルギーの発露があると考えられますが,人間には,この心の自然な発露に’待ったをかける’抑圧機能が備わっているのが動物一般と違うところです。
本能に従う動物の場合は,例えば縄張りを守るために生死をかけて戦うところを,人間は自我に内属する抑圧機能によって,他者の立場を配慮,尊重するのです。
繰り返し述べていることですが,人間の証明は自我にあります。人間には社会性と精神性とがあり,それらの根拠が自律機能と抑圧機能とにあり,それらが適正に運用されることで適正な自己の展開が可能となります。
動物一般は,いわば自然そのものを生きているのに対して,人間は自我によって,自然そのものを生きつつも,しかしながら自然から乖離している存在であるという特徴を持っています。
それは人間には克服不能の矛盾ですが,人間がその存在の根本において,あるいは存在構造として,そうした矛盾を抱え持っていることが特徴であり,それが人生の苦悩と希望との源泉でもあります。
このように,自我が生の有限の世界の主宰者でありながら,自我機構が存在する由来が自我を超えたもの,つまり無限の世界のものという性格でもあるということは,人間の存在構造は,「有限であり,しかしながら無限性の性格をも合わせ持っているという矛盾を内包させている」ということになります。
人間が,この甚だしく錯綜し,解き難い世界の住人であることが,人生のさ中で迷子のようになったり,絶望したり,希望を見出したりする理由です。
人生は希望に満ちているといえば安易すぎるいい方でしょうが,「人生は克服不能の高さと深さとを持つ山に登るようなものである。だからこそ希望は常にあり得る」というのは真実ではないでしょうか。
身近にいるかけがえのない人の死は,痛恨の極みでしょう。
我われ人間への要求,「いかに生きるか?」という問いは,しかしながらこのような状況でさえ,「そこから希望の光を見出せ」と要求しているように見えます。その難問の前に生きる希望を見出せないでいるのはもっともであるとしても,「立ちはだかる目前の絶壁」を登らないわけにはいかないのが人生です。
それは,「いまは無理だが,そのうちに登ってみせる」ということになるのでしょう。そう考えるとき,既にかすかであっても希望が見えているはずです。そして,’そのうち’がやって来たときには,そそり立っていた絶壁は,より穏やかな勾配に変わっているに違いありません。
究極の課題は,「死について希望を見出す」ということになるのかもしれません。生を生きる人間には,死は最大の難問です。死はすべてを無意味化しかねないものです。しかし,いま述べたように,この解き難い問いがあるからこそ,可能態としての希望の光が絶えることがないというのは確かでしょう。
人間が自我によって自然から乖離し,独自の途を進む宿命の下にありながら,自然に内包されたものでもあるために,自然の無化作用の脅威を受けています。
自我が自己の展開の主宰者であることは,他者との関係を不可欠のものとすることで成り立っているのは,その脅威に対抗する意味があると思われます。
抑圧機能は,エロス的エネルギーの源泉である自律機能の発動を抑圧します。それは「生のエネルギー」を「死のエネルギー」に変換する意味を持ちます。
他者との関係を不可欠の前提としている自己の存在は,こうしたエネルギーの変換を避けることができません。
変換されたエネルギーは,喜び,満足をもたらすものから,怒りをもたらすものになります。
死の衝動は,内向した怒りのをエネルギーの強さを物語っています。
自我は二分化して機能し,そのように現象を形成します。
自律と抑圧もその一つです。
自我によって,人生は喜びを追求します。しかし,怒りを背後に隠し持たない喜びはありません。
前章で取り上げた小学校2年の男子の例です。
少年は,はきはきと物をいい,素直な性格の子です。その年頃らしい可愛さも持っています。
少年にはチックがあります。通学路で,怖い男になにかされるのではないかという恐怖があります。学校は友達がたくさんいるし,楽しいそうです。しかしこのごろ学校に行きたくないといいます。不意に胸のあたりがもやもやして気持ちが悪くなるからです。
父親は職人です。野球が上手です。そういう父親をかっこいいと思っています。将来は父親とおなじ仕事もしたいが,それよりも整体士になりたいそうです。父親や母親の身体を楽にさせてやりたいのです。少年も野球チームに入っています。もと父親が入っていたのとおなじチームです。「君は親孝行をしたい,よい子なんだね」というと,「そうだよ,よい子なんだよ」と答えます。しかしよい子の心の底には,それとは矛盾した激しいものが渦巻いています。
最近見たという次の夢がそれを物語っています。
人間がロボットを作っている。うまくいかなくて爆発しそう。怖いので逃げた。
父親は,「別に怖くないじゃないか」といったそうですが,少年には怖い夢でした。
ロボットにされそうなのは少年自身です。ロボットに仕立てようとしているのは両親でしょう。爆発しかねないほどの怒りがたまっているようです。爆発するのは少年にとっては,勿論恐ろしいことです。大好きな父親や母親をひどい目に合わせてしまうからですし,どんな反撃をされるかも分かりません。自分の心が破壊されてしまう恐怖もあります。
少年には1歳の弟がいます。可愛い弟だよと彼はいいます。その言葉に嘘はありません。彼は大変素直で,率直な性格に見えるのです。当然のことながら,母親は弟にかかり切りです。弟が寝ると,「起きると困るから,外に行ってなさい」といわれます。祖父母が近くに住んでいて,「泊まりに行ってきなさい」といわれることがあります。それをいわれると不安になります。学校に行きたくないと言い出したのも,母親の姿を見ていないと不安にかられるからでもあるようです。
この不安は,少年の年齢からすると理解し難いものです。客観的に見て,母親が少年を捨ててしまうことは考えられません。少年にもそれは分かっています。
そうすると母親の側に絶えずいなければ,母親が自分の前から姿を消す(捨てる)のではないかという不安は,心理的なものに違いありません。ということは,少年は,無意識的な心によって脅かされていると考えてよいでしょう。つまり想起できないほどに強い恐怖体験があったか,あるいは記憶をたどるのが不可能な早期(誕生後,自我の活動が未成熟な時期)に,何らかの恐怖をもたらすエピソ-ドがあったかということになると思います。
見捨てられる恐怖に怯える少年の自我は,自分の意志を押さえてでも,両親に忠実な子になりなさいというイメージの支配を受けています。それに伴って,親孝行をするよい子でなければ,愛される資格もないし,価値を認められることもないという恐怖心にかられているようです。
少年が求めているのは,分け隔てのない安定した愛情です。両親の思いはともかく,チック等の”症状”は,少年の心の沼から立ち上がってくる叫びでもあるのです。少年の自我が両親の支配から脱するためには,夢に現われている爆発しそうな怒りに,言葉を与えることができるようにならなければなりません。それを助けるのが治療者です。治療者の介入と援助がなければ困難な心の作業です。そして,また,子供の幼さを考えると,それは両親,とりわけ母親の協力なくしては難しいテーマです。
幼い子なので女性カウンセラーにも協力してもらうことになり,診療が開始されました。本人に起こっていると思われることを母親に説明し,今後の方針を伝えました。母親は涙ながらに,「私が怒りすぎたものですから・・・」と問題を受け止めてくれました。
5回ほど面接を重ねたところで,母親の伝言が入りました。子供の習い事の関係で,次回の予約は取り消したい,また連絡するということでした。相談ではなく通告です。母親の不信を買ったとは思えない状況です。カウンセラーは50分ほどの時間を空けて待っているのですが,あまりにもあっさりしています。習い事以上に重要視してもらえなかったのは残念です。母親のセンスに不安を覚えることでもあります。子供はその母親の指導を受けなければならず,現に指導のまずさが,大きな怒りを蓄積させ,恐怖の虜にさせてしまっているのが問題なのです。特別な事情があるのかもしれませんが,この子が心を回復させるまで,母親が忍耐強く診療に協力できるのか,気になります。
この母親の場合はともかく,一般的に,親の”ちょっとした”配慮の欠落,子供の心への鈍感などが積み重なって,子供の自我の形成によからぬ影響を与えるのは論を待たないでしょう。そういうことが起こるのは,親の側の盲点でもあると思います。自然な心でさえいれば,どんな親にでも気がついて訂正する機会はいくらでもあるだろうと思います。それを考えると,親の側の盲点が意味するものは,恐らく親自身が,自然な自我の形成を歪められた生育過程の下にあったということだろうと思います。その影響で硬直した自我が,哀しみと怒りをたたえて,子供に対して独善的な構えを取るのです。それは当然,固執的になり,優しさとは無縁のものになるでしょう。親自身がその親から蒙ってきた有形無形の被害的なものを背景に,子を相手に復讐をしている趣さえどこか感じ取られる場合もあります。自分が不幸だったという思いがあれば,子供の幸福を無条件に望むのが,しばしば難しくなります。子の側でいえば,意識するかしないかは別としても,当然,不満,怒りがたまる理由になり,その処理に苦しむことになるのです。
まことに人は人によって,自然の心から遠ざけられるのです。
このように見てくると,少年の自我の形成は相当に歪められていると考えざるを得ないと思います。
集約していえば,親との関係で少年は,見捨てられる恐怖に支配されています。そのために少年の自我は抑圧機能を過度に作動させつづけるしかありません。それに伴い潜行する怒りのエネルギーが勢力を強めていきます。自我はそのために自縄自縛に陥る一方です。
母(父)と子の関係は,特に子供が幼いほど,同盟関係にある強国(P)と弱小国(S)のそれに似ています。
PとSは同盟を結んでその他の国(H)と外交交渉をし,あるいは戦います。そのかぎりでSにとってPは心強い存在です。
しかしPとSは対等ではありません。Pがよほど大らかであっても,自国の利益を優先させるのは自明でしょう。
このことに先ほどの用語を当てはめていえば,PとSとの自律機能と抑圧機能の関係は,Pは前者に偏り,Sは後者に偏ることになります。
P国の安定はS国の犠牲の上に成り立っているのだが,S国の安定のためにはP国の力を必要としているので,国王は自国が不利益を蒙っているとは考えない・・・S国は国民の不満を黙らせることでP国との友好を維持できる・・・不利益を蒙っているのを知っているのは,S国の市民たち(C)である等々ということになります。。
事例の少年にこれを当てはめると,S国王は少年の自我,P国は母(父)親で。S国王は善政を敷きたいと願いつつ,P国に従わなければ国が成り立たないので,涙を飲んで不満分子であるCたち(自律機能によるもの)を地下牢に幽閉(抑圧機能による)しているということになります。
横暴なPに依存するSは,国王として自立的でないので,意識の地下から突き上げてくるCの抗議の気配に脅かされ,ますますPに取りすがろうとします。Pはそれを疎ましく思い,Pは見捨てられまいとして更に取りすがろうとします。
Cの怒りは,無力な国王のために国づくりが怪しくされているS国を破壊しかねない(ロボットが爆発する)ほどですし,S国王を恐怖で痙攣させてもいる(チック)と考えることができます。また,無力な国王を捕捉する(暴漢に襲われ,拉致される恐怖)たくらみもあるようです。そしてその怒りをP国に察知されると見放される,という恐怖(母親の側を離れることができない)も強いようです。
#3 内なる他者
自己の存在にとって,他者の存在は欠かせない構成要件です。
それは自己の存在構造の内に他者が含まれていることを示しています。そしてそのことは,自己と他者はそれぞれに独立しつつ,相互に絶対依存の関係にもあることを意味しています。
精神医学は,人間関係の学であるといわれることがあるように,人間関係は重要です。それぞれの自己が他者と絶対依存の関係にあることは,ほぼ必然的に利害の上で矛盾,葛藤が生じる理由になります。
他者の存在は有り難く,多大の恩恵を受ける一方で,少なからず迷惑で,不利益を蒙ることになるのです。従って対人関係は,しばしば人を大いに悩ませ,時によっては心の病理現象を惹き起こす要因にもなります。
それらのことは,以上に述べた理由,自我に拠る人間に特有の解き難い矛盾に起因するといえます。
結論的にいえばこのように考えることができますが,しかしながら,人間嫌いや,孤独を好むもの,ジャングルに置き去りにされた旧兵士,動物に育てられた子供などなど,いわゆる人間関係と無縁に等しい境遇で生活している人もないわけではありません。
また例えば人と猫や犬との関係,あるいは猫同士,犬同士の関係,あるいは未知の異星人と遭遇したとしてそれとの関係などなどは,人間同士の関係と質的な相違はあるのかといった問題があるかと思います。
人間の証明は自我にあると述べましたが,犬や猫,あるいはチンパンジーに,自我に類するものはないのかという問いもあって当然でしょう。
ある女性(A)は,「ニュースなどの報道で,人が殺されたと見聞きしても何とも思わないが,動物が虐待されたときは許せない気持ちになる」といいます。
このことは人間には二心があるが,動物にはないことに関連しています。その意味では動物は純粋であり,悪の性格を持たない(罪がない)のです。
これを敷衍すると,悪は善と裏表の関係にあり,つまり自我に拠る人間の二心の問題であるということになります。
自己と他者とが絶対依存の関係にあるということは,心が二分割されていることに通じます。
つまり自己が存在するためには他者の存在が不可欠であるということは,男と女,愛と憎しみ,善と悪,正義と不義,表と裏,本音と建前,全と無,生と死等々とおなじように,全一なるものを自我が二分割して捉えるということを示しております。それが自我の一大特徴なのです。
Aさんは母親と二人で暮らしていますが,母親は重い悩みを持っているAさんに関心を示しません。人間関係に疲れ果てるAさんは,かつては職場に向かうのが容易なことではありませんでした。しかし仕事をしないでいると,母親は冷淡な態度になります。誰それとのことでの悩みを聞いて欲しくても,相手方の立場でAさんが批判されます。
そういう母親に対して,Aさんも批判的ないい方になりがちでした。
しかし,あるときAさんが母親を行楽地に誘い,そのときの様子を報告するAさんの表情には,ふだんは見せない明るさがありました。
その様子から,母親への日ごろの怒りは,Aさんが母親に認められたい,愛されたい心と裏腹の関係にあるのが分かります。
Aさんは乗馬の練習をしています。「馬さんに会いに行く」のは,何よりの楽しみです。
Aさんにとって,母親と馬とのそれぞれの関係の違いは,といえば奇妙な比較ともいえますが,結論的にいえば,前者には二心があり後者にはそれがないことといえます。
それを前提にいえば,Aさんが人間を憎むのは,人間(自己および他者)を愛したいがためであり,他者から愛されたいがためであると結論づけられるでしょう。また人間への正義の要求が満たされていないために,人間の悪に過敏であるともいえます。
一方,動物との関係では,動物には二心がないので,彼らを愛らしいと感じる心は純一であり,人間を襲う熊は悪ではないのです。むしろ熊を怒らせた人間の方に悪があることになります。
この比較から,自己と他者との関係と,人と動物との関係とのあいだには,決定的な違いがあるのは明らかです。
Bさんは不妊治療も受けましたが,子供がありません。それで養子(C女)をもらうことになりました。その数ヶ月後,実家が改築された折に両親に請われて同居することになりました。しかしBさんは,もともと両親に対して屈折した心を持っています。
C女はみんなに可愛がられています。Bさんは,可愛がるだけではいけないと思っているので厳しくもします。いつかC女はBさんになつかなくなってしまいました。
Bさんは母性に疑問も持っています。C女を可愛いと思えないのです。
両親は,C女を可愛がることのどこがいけないのかと,Bさんの不満,疑問を理解せず,受けつけません。
この問題はさまざまに深刻です。C女はペットになっているからです。養母であるBさんが両親に対して気が弱いだけではなく,養女に愛情を持てないからです。
この状況で,本気で養女に責任を持つ気があれば,両親の家から出る覚悟がいると思います。「私が母親なのだ,私が責任を持って育てる」という覚悟がBさんには必要です。
ペットであれば,家族のみんなが単純に可愛がってやればよいのです。
しかし(人間の)赤ん坊であれば,躾が要ります。
この両者を較べてみると,動物と人間との心の在りようの違いが見えてきます。
つまり動物にも心があると仮定すると,それは単一のもので,人間のそれは,いわば二心であるということです。
動物は可愛がるとなつきます。なつかれると悪い気はしません。飼い主が望む通りに,ほぼ応えてくれます。だからこそペットなのです。その心の状況は,母親が赤ん坊にしてあげ,赤ん坊が母親にそのお返しをするという状況に似ています。
どうやらペットを可愛がる人は,母親と赤ん坊との蜜月時代の心を感じ取っているように見えます。
自我の発達が未成熟な赤ん坊は,動物に似て二心がありません。
母性は赤ん坊の単一の心を包み込む心性であるといえます。
母性を感じられないというBさんは,養女が(Bさんの)両親に可愛がられているのを見て,嫉妬しているともいいます。このことはBさんが,幼い時代に両親にうまく甘えられなかった何らかの心的事情があったことを示していると思います。
つまりBさんが幼女を包み込む心を持てないのは,幼い時代のBさん自身が,思うようには母親に甘えられなかったからで,未済の感情があるのだろうということです。
ペットが人の心を癒すのは,甘えたい,甘えてほしいという心の葛藤をなぐさめてくれるからのように思われます。
母親が赤ん坊に甘えてほしい,甘えさせてあげたいと思うのは,母親自身が甘えたい心を持っているからに違いありません。仮に甘えたい心が充足しきっていれば(現実にはあり得ません),甘えさせてあげたいなどとは思わないでしょう。赤ん坊に甘えられて仕合せな気分でいる母親は,部分的に自分自身が赤ん坊の心でそれを分かち合っていると思われます。
赤ん坊が甘えるのをわずらわしいと感じる母親は,自分自身が幼いころに甘えを極端に封じられていた可能性があります。そういう心的状況では,甘えるという生へのエネルギーが怒りのエネルギーに変換されます。内向する怒りと共に,甘えたい心が意識の地下に封じ込められていると,「甘えたいー甘えさせてあげたい」という心の流れが阻まれてしまいます。
赤ん坊は動物に似て単一の心の状態であるとはいえ,やがて成長して二心の持ち主になるのが分かっているのが動物と違うところです。
そこにペットは可愛がることができても,母性が湧かない心の事情があると思われます。
躾は,単に可愛がるだけでは済まないことになります。
ペットのように扱われた子は,自分の責任において行動する主体者意識が育ちません。
結局,二心は自我の自律機能と抑圧機能に関連します。
#4 自我の傀儡化
自我の活動は意識の活動に他なりませんが,両者の関係は発電機と電気の関係に似ています。
自我は何もの(何ごと)かとの関係において機能します。それは意識は何もの(何ごと)かについての意識である,というのとおなじ意味になります。
自我は意識活動の中心であり,根拠です。何ものかについての意識であるというとき,その何ものかは自我との関係における対象ということになります。
これらの一切の対象との全関係を統合する位置にあるのが自我であり,統合された全関係が自己であるということになります。
意識がとらえた何ものかについて,統合された全関係に即して,合理的な意味の連鎖を探り当てる知的作業も自我の仕事です。
生後間もないころは,自我は組織体として未分化で,機能的に未熟です。
それを補う役目を,母親(そして父親)を中心とした,重要な関わりを持つ大人たちが負っています。
乳児の自我が最初にする重要な仕事の一つは,「よい乳房」と「わるい乳房」(メラニー・クライン)の存在に関して進められると考えられます。
赤ちゃんがお腹を空かしてむずかっているのを母親が的確に察知し,授乳することで赤ん坊が満足できれば,即ちそれは「よい乳房」です。
母親が何らかの事情で機敏な行動ができなかったり,母乳の出がわるかったりすると,それは「わるい乳房」になります
成熟した自我であれば,空腹を感じたときにどうするかを知っています。つまり自分の意志で空腹を満たす(必要なものを自分で獲りにいく)ことができます。
自我が未熟な赤ん坊は,自分から「よい乳房」を獲りに行くことができません。母親がそれを助けることになります。
自他の弁別がまだついていない赤ん坊にとっては,母親は自己の一部です。言葉を換えれば,この時期の赤ん坊は主観ー客観の融合した世界の住人です。そこでは全てが思い通りに運ばれなければならないのです。つまり万能感が支配する自己愛の世界の住人でもあります。
「よい乳房」がそこにあるとき,それは赤ん坊が魔法で呼び出したように,望みどおりに存在するので,万能感が満たされ,自己愛が満たされることになります。
そして「わるい乳房」によって赤ん坊の万能感と自己愛とが傷つくのです。
あるときは「よい乳房」によって満たされ,あるときは「わるい乳房」によって傷つけられることが,やがて自他の弁別がつきはじめることに重要な意味を持ちます。
そもそも自我が未熟であるとはいえ,「よい」と「わるい」とに二極分化していることが,赤ん坊の自我が活動している証拠です。混沌とした主観的世界にありながらも,他者の存在,客観的なものの存在が姿を現し始めていることの証なのです。
「よい」の’一極化’がいわば赤ん坊の理想でしょうが,「よい」と「わるい」との二極化が避け難いのがこの世の原理と知るのが,’自我に拠って生きる’のを受け入れることに通じます。
「わるい乳房」の存在は,万能感や自己愛に翳りをもたらします。そして,それは全的には肯定されていないという根源的な恐怖を生み出す理由になり,投げ出されたもの,という被害感の起源にもなるでしょう。そして,また,それは万能感や自己愛が完璧ではないことを受け入れるしかなく,自己の一部であった母親が,客観的に外界に存在する他者であることを自覚し,受け入れるしかないことを促しています。
自己意識は,次のような心の動的なプロセスを受け入れ,それに即することによって形成されていくと考えられます。
万能感と自己愛とを完璧に保証するはずのものであるがために,絶対的依存の対象であった母親は,自己に内属しているのでなければならなかった。しかしそのことに疑問があるので,繰り返し母親を支配しようと試みる必要があった。そういうことを必要としたこと自体が,既に問題を明らかにしているのだが,やがて,母親を支配し切れないことが明白になった。
支配し切れない以上,母親は相対的依存の対象に過ぎない。そしてそれは,自己に内属する存在ではなく,外部に,独立して存在するものであることを示している。つまり母親は,他者であると認め,受け入れるしかないことである。
そうであれば,結局は自己を肯定する根本原理は自己自身にしかないことになる。そして,そこにも絶対性はないので,繰り返し自己を自己自身にもたらすのが,自己形成と自己の自立化の原理になる。
このように生まれて間もないあいだの赤ん坊は,母親との一体化の中にある主観世界の住人です。そしてやがて母子分離を経験する時がやってきます。
別の見方をすれば,母親に絶対的に依存している赤ん坊は,やがて相対的依存の関係に移行していきます。それは母親なる他者が自己に内属するのではなく,自己とは別個に独立した外部的な存在であると認識していくことを示しています。
(更に別ないい方をすれば,いうならば一者の世界のものが,既にそうではない世界のものに変貌を遂げようとしている,ということもできそうです)
母子の一体化現象と呼ぶとき,あるいは絶対的依存というとき,そこには両者の分離が内包されています。つまりそこには動的,発展的な分離の動きが既に予定されているのです。
赤ん坊は,心のこの動きを単純に喜ぶことはできません。
母子の分離の気配を感じ取るときに,その動きに抵抗しようとしているように見えます。自分が魔法使いのように,母親を思い通りに動かそうとしているように見えます。
それがうまくいったときに,例えば「よい乳房」を手に入れることができたのです。しかし,「わるい乳房」が繰り返し表れます。
繰り返し,繰り返し,「よい乳房」が手に入ることを確かめながら,その合間に,これもまた繰り返し味合わされる「わるい乳房」の,不愉快で不安な存在に悩まされ,脅かされながら,やがてそれへの対処の仕方を覚えます。
つまり,赤ん坊にとって,本来は「よい乳房」のみが存在しているべきなのです。それが万能感の本来あるべき姿です。それが自己愛の本来の形です。
従って,不愉快な「わるい乳房」の存在は,万能感や自己愛に翳りを与え,それらを揺るがすものです。それは’一者の世界’にはあるまじきもの,であるに違いありません。
やがて赤ん坊は,一つの結節点に立ち会うことになり,未知の経験をすることになります。
それが他者の発見です。既に一者の世界の住人ではないことの発見です。
その他者は,よい乳房とわるい乳房の提供者です。
他者であれば,「よい」のも「わるい」のも,その理由が外部にあるので,気分がよくても,わるくても我慢しなければなりません。自分は既に万能の世界のものではなく,自己愛だけの世界のものではなく,他者愛と共存,共立させなければならないと感じ始める時が訪れるのです。
’一者の世界’といういい方をあえてしましたが,このような形而上学的なものを,精神医学という学問を論じる場所に持ち込むのは言語道断といわれる向きがあると思います。
確かに,論のための論であれば,これは虚しい議論になります。
しかし,ここでは精神科の病理現象の蓄積の上に立って問題を整理し,統合的に理解する可能性を探ることが唯一の関心事です。精神病理をどう理解し,治療的に有効な形でどう還元するかがすべてです。
「客観的な学問の体裁」が求められているのはいうまでもありません。
その客観性の理想的なモデルは自然科学にあります。しかしそれを心の現象に適応しようとすれば,いわば穴だらけになるのは避けようがありません。それを徹底排除して,自然科学に準じようとすれば,脳の科学になるでしょう。
心理的な議論では,幾つかの里程標のような事実問題があり,それら相互の間隙を繋ぐには推論以外にはありません。そしてその「科学性」とは,その推論の説得性,合理性にあります。
人間存在の問題は,生誕以前の世界と死後の世界とを含んでいます。これらの巨大な謎は,自然科学の手に負えるものではないのは論を俟ちません。
しかしそれらは厳然とした人間の事実問題です。
この超え難い謎は,人間の心理を’科学的に’理解しようとするときに立ち会う謎(里程標のような現象的諸事実のあいだに横たわる間隙,自然科学的な光が及ばない深淵)と連関するものです。ですからそれらのすべてを仮説をもって繋がなければ,統合的で合理的な理解を得ることはできません。
形而上学的であるといえば,人間存在はそうしたものなのです。
人間存在にかぎりませんが,問題は統合的な視野の下に置かなければ,それを問うことはできません。
この問題を,自我に内属する理性の支配下に置くことは不可能です。いわば人間の手に負えないものを学問的に理解しようとすれば,仮設を用いて,我われにも了解可能な一種の体系を仕立て上げる以外になく,その有用性は,治療的な還元によって確かめられることになります。
誕生以前の自我の存在様態は永遠の謎です。
一般に目下の謎を解いていくのは,理性とか知性などと呼ばれる能力によってですが,それらは自我に内属するものです。自我は自我自身について対象化することはできず,従って自我自身を問うことはできません。
換言すると,現象的世界に現れている現象的実体に関してはこれらの能力の範疇にありますが,自我そのものの存在様態,存在の由来などは,その能力の範疇外です。ということは自我の力が及ぶかぎりの現象的世界が有限界であるのに対して,及び得ない世界は無限界ということになります。それを自然界といい換えることができます。
自我は,以上の意味で,自然から乖離されたものであると考えることは許されると思います。つまり自我は自然に内属しながら,自然そのものではなくなったものという性格を持っています。自然そのものは全なるものであり,無限であり,無であり,それ自体で自足するものです。それらは自我に拠る人間の能力では捉え得ないものです。
その上で改めて自然を対象化することによって,自我は自然を我が物にすることが可能ですが,そのように対象化したものは,もはや自然そのものとはかけ離れたものです。人間である我々の前には,自然そのものは決して姿を表すことはありません。人間にできることは自然を限定化し,対象化することですが,その心的な作業は自我に拠ります。そして全である自然と,限定的な力をしか持たない自我とは,いうまでもありませんが対等の関係ではありません。
自我が捉え,自己のものとしようとする試みは,全であり無である自然の前に,絶えず無化の脅威にさらされているといえます。
とりわけ生まれて間もない未熟な自我は,「世界を自己化する」力はとうていありません。
人生の最早期の乳児の精神世界を,イギリスの児童精神科医であるメラニー・クラインは,妄想的,分裂的であると特徴づけました。クラインは,母親の乳房との関係を軸に,乳児が精神的な世界を切り開いていく煩悶,苦痛と至福,満足とのあいだを激しく揺れ動く心性について詳しく論じております。目の前に現れる母親をはじめ,さまざまな対象を統合的に捉えていくのは自我の役目ですが,生まれて間もない自我は,自然による無化作用という乱気流にもまれて,一貫した姿勢をとれません。
それを保護するのが,なによりも母親の愛情ということになりますが,母親の力でも補い切れないものがあります。しかしながら,赤ん坊のこうした激しい心の混乱も自然のプロセスの中にあります。母親にもまた,そういう赤ん坊にどう対処したらよいか,自然の力とでもいうべきものがあると思います。ですから良い母親というのは,言葉では捉え難い自然の情愛深さを,誰に教えられたわけではなくても身につけている人なのでしょう。このような意味での良い母親の保護の下であれば,多かれ少なかれ幼い自我が傷つけられるのは避け難いにしても,やがては自然的なプロセスの流れとして,赤ん坊の自我は統合機能を整えていくことになります。
このような流れの中にあって,赤ん坊の側に持って生まれた過敏なものがあれば,あるいは母親の側に何らかの不都合があれば,混乱は更に深みを増すことにもなるでしょう。この場合は母親の保護を十分に受けられず,最も重要な立場にある母親によって傷つけられ,混乱させられるに等しいことになります。
もともと傷つき易く,混乱しがちな赤ん坊の自我が,いわば不自然に母親によって何らかの恐怖体験をしたとすると,自我は自然のプロセスに従うことができず,身を避けるために生まれて初めての対人的な策を弄することになります。つまり,母親の自我の傀儡と化すことによって身を守り,心の自然を犠牲にするのです。その動機は恐怖と不信であったにもかかわらず,そうしたものを緩和するために,母親が大好きという偽装を凝らすことになる場合があります。疑いを持つことは危険なので,あくまでも友好の姿勢で取り入ろうとするのです。しかし,その根にある恐怖と不信は,対人不信と自己不信の核になるでしょう。その程度がはなはだしければ,将来,妄想的でさえある猜疑心に囚われる下地となるかもしれません。
自我は自己を形成していく中核ですが,いま述べたように,乳幼児の段階では母親の自我がその代理を勤めることになります。母親の愛情により至福の感情に浸されれば,赤ん坊の自我は母親のそれに助けられる形で,自己愛と他者愛とを同時に経験することになり,自我の成長に寄与することになるでしょう。また母親に恐怖を感じたとすると,怒りをもって応じるかもしれません。それが母親の愛情を改めて引き出す結果をもたらすことになれば,赤ん坊は,やはり自我の成長となる礎を得るかもしれません。しかし,恐怖の度が強ければ,赤ん坊の自我は母親のそれにしがみつき,恐怖をもたらしたものを懐柔しようとすることもあるでしょう。それらは本能的な自我の動きだろうと思いますが,後々の対人的な駆け引きにつながるものでもあると思われます。
このように(赤ん坊の)自己なる存在構造には,母なる他者が密接不可分に入り込んでおります。
そのようなことが可能であるのは,その存在構造に内なる他者が(構造的に)含まれているからであろうと想定されます。そして,また,自己の存在構造は,原基としての自我の機構に組み込まれいると考えられます。
生まれて間もない赤ん坊は,自他の区別がつきません。そして客観的には厳然として他者が存在します。赤ん坊は外なる他者である母親の世話を受けつつ,やがて自他の区別がつくようになります。
それに応じて外なる他者である母親とは別に,自己の内部に他者が生起してくると考えられます。つまり自我の機構に組み込まれていた自己の存在構造としてある内なる他者が,外なる他者である母親との関係に刺激されて機能を顕かにしていくと思われます。
この過程で重要なのは,境界機能です。自我に内属すると仮定される境界機能が,自己の内なる他者の生起に寄与していると思われます。
つまりこの意味での自己の内なる自己と,内なる他者とは関連しつつ独立しており,両者のあいだは境界機能によって隔てられていると仮定されます。
自我は全であり無である自然から乖離されたものです。自我に拠る光の世界は,無限定な闇に包囲された限定的なものです。人間はそれぞれの自己として存在し,意識の光によって世界を現象させます。その世界は意識と共にあり,意識の消滅と共に消滅します。そのような現象的な世界の演出者であり,住人であるそれぞれの自我は,包囲している闇といずれは一体化する宿命の下にあります。そしてそのときに限定的であった自己ならびにその世界は,無限の中に溶出します。その意味では,自己は自己自身の中に’全’を含んでいます。自己はそれだけでは全体の半分に過ぎず,他の半分を内に含むことにより’全’となるのです。そのように他者を自己の構造の中に,内なる自己として包含しています。そして同様に外部にある’半分に過ぎない’他人の内部に,他なる自己を包含しているのです。それは現実的な他者との関係にとどまらず,心的現実としてさまざまに現象されているのです。
自己と他者の関係は大変重要ですが,それはいま述べたような理由によるものです。ですから,たとえ嫌人癖が甚だしく,人里はなれて孤独に生活する人であっても,他者との関係から無縁になることはできません。
生まれたばかりの自然的な傷つき易い自我は,最重要の他者である母親が,基本的に自我の護り手であったか否かということに大きく左右されることになります。
自我の重要な機能の一つは自律性です。樹木の種が大地に落ち,しっかりと根を下ろせば,あとは種に組み込まれた自律性によって成長していくのとおなじように,自我の自律性の根は,母親の保護を受けて大地に根を下ろすことができるでしょう。根が伸びていくのは,心の大地である無意識の領域です。その領域の主体にまで根がおよび,しっかりとした接触が図られれば,自我の自律性はそれなりに健全性を保つことができるものと思われます。そのようにして,自己がおのずから自分らしい自己に向けて,成長していくことができるのだろうと考えられます。
逆に,原初の他者である母親によって自我が護られず,自律性が混乱させられる体験をすれば,自我の健全な自然性が傷つけられることになるのでしょう。
人間にとって他者が重要なのは,自然的な自我の機能を護る上で,他者が絶対的な前提となっているということです。しかし他者は,むしろしばしば脅威になります。絶対に必要な存在であることは自然的な要請ですが,現実の外なる他者は,むしろこの自然的なものに脅威を与えるものでもあります。
従って人間の最も大きな矛盾と困難は,自我の自然性を他者との関係でいかに護っていくかということにあり,それはしばしば難問であるということです。
母親への恐怖から,いわば母親の自我の傀儡と化した幼いそれは,自我本来の善導する姿勢から,一転して過酷なものに転身します。この幼い自我は,母親を怒らせる元凶が甘える心と認識するので,甘える心を片端から捉えて無意識の牢屋に封じ込める途をとることになるのです。そのようにして母親に媚を売り,よい子を無意識的に演出することで,母親の怒りをかわすことができると考えるのです。そして甘える心を封じたままでいるので,その後の心の成長に大きな難点を残すことになります。
なによりも自我が,傀儡化することによって,その自律性を犠牲にしたことが問題です。母なる他者への恐怖によって乱された自我の混乱は,長じて,一般的に他者に対して恐怖心や不信感を抱き易くなる可能性がありますし(不登校や対人恐怖症などの心の障害に関連します),自己不信のもとにもなるでしょう。更にそうした不安定な他者への感情のまま,他者へ依存しないではいられないということにもなります。何歳になっても,年齢とは無関係に依存心が心の大勢を占めることになるかもしれません。そして,それに相応して無意識の領域に,先の例に即していえば,「甘えられなかった分身たち」を抱え込むことになります。この分身たちは,悲しみ,虚しさ,恨み,怒りなどと共にあるでしょう。そして表の自我が生きる方向に向かうべく機能する性格を持つのに対して,この自我に受け入れを拒否された分身たちは,裏の自我とでもいうべきものを主柱とした勢力になり,表の自我への反逆を志向することにならざるを得なくなります。それは,やがては死へのエネルギーと一体化して,ただでさえ困難な人生をいっそう難しいものにしてしまうのです。
他者への度の過ぎた依存は大変危険です。他人しだいの人生に,満足も,充足も,安心も望めるはずがありません。おまけに他者への度を過ぎた依存を求める心は,表の自我が基本的に劣弱であるという事情があります。そういう心の状況であれば,日常の生活の諸々のストレスに対応が難しい上に,内側(無意識)にも意識を脅かす勢力を持つことになるのです。まさに前門の虎に,後門の狼という心的状況といえるでしょう。
#5 表の自我と裏の自我
40代後半のYさんが,「私の中に悪魔がいる」とあるときいっていました。
Yさんが10代のとき,母親が幻覚,妄想状態でした。Yさんの目の前で縊首自殺を試みようとしたこともありました。現在は,通院は継続していますが,いわば’健常人と変わらない’程度に回復しています。
Yさんの一人娘も,中学生のころに幻覚,妄想状態となりました。いまは大学生ですが,しばしば感情が嵐のように激しく揺れます。そういうときは母親を罵倒します。手に負えない幼児のような行動に走ります。
Yさん自身は,長女が発病したころに気分が不安定になり,通院が開始されました。
長女は祖母(Yさんの母親)に似ているので,病気がよくなるとしても祖母のような年齢になっているのではあまりに不憫だと,しばしば悲観的になります。そしていっそのこと自分の手で・・・と思いつめることがあります。実際に行動に出たこともあります。
「私の中に悪魔がいる」というのは,そういう状況でのことです。「もう,いいかな」と悪魔がしきりとそそのかすといいます。
Yさんの絶望は,長女の将来を悲観する気持ちと一体になっています。
長女は鬱屈した感情を激しく母親にぶつけますが,自分に手を掛けようとした母親の行動には,怒りも恐怖も覚えないように見えます。両者は密着した依存関係にあるように思われます。
30歳のWさんは二児の母親です。この夏に第二子を出産しました。
あるとき,「(4歳の)上の子の足をへし折ろうとするイメージが湧いてきて,怖くなった」といいます。
一年ほど前,状態のよくない日がつづいていました。
ある日,一人で帰すのが心配で母親に来てもらいました。ベッドに寝ているWさんの肩を抑えている母親の手を,「・・・るせーな・・・」といって払いのけようとします。「ハサミ・・・カッター・・・」とうめくようにいいます(自傷行為は数知れずといった過去があります)。動物そのもののような唸り声を発します。
いまにも暴れ出しかねない様子なので,弟にも来てもらいました(夫は仕事で,呼ぶのが困難でした)。
小一時間後,人が変わったように自分から起き上がり,きちんと挨拶をして帰って行きました。
20歳のZさんは,そのWさんの紹介で二年前に受診しました。
初診のとき,真夏ということもあり,無数の切創痕が露出された腕の全面に見えていました。
手首,腕への自傷行為は,高校に入学して間もなくからつづいています。始めは興味本位でしたが,やがては幻聴にそそのかされるようになりました。「切っちまえ」という声が聞こえ,切ると,「よくやった」と聞こえたりします。
外出中などに急に怖くなり,泣きたくなり,死にたくなり,身体を切りたくなることがあります。そういう折に,「死んだら」とか,「切ったら楽になるよ」とかいう声が聞こえたりします。
電車の中で,「切れ!・・・誰も見ていないから大丈夫だ」という声が,リアルに聞こえたこともあります。
初診のころに,「将来がとても不安・・・ちょっとしたことで無闇に涙があふれてくる・・・私は駄目だとすぐに思ってしまう・・・しばしば死にたくなる,そういうときに手を切る衝動が湧く・・・高校に入ったころから<自殺マニュアル>の本に興味がある・・・ゾンビーを殺すゲームに夢中になる・・・」と述べています。
「腕に目立っている傷痕は,人に見られるのが嬉しいと思う,何故か隠そうとするより誇りたい気分・・・」ともいいます。
鼻翼と口唇へのピアス,’ゴス調’の黒装束を好み,当然目立ちます。そういういでたちをしていると自信が湧いて,みんなに見て欲しいと思います。一方で,’ふつうの’服装をしていると,人の目が気になります。私がおかしいから見ているのかと思い勝ちです。
紹介者のWさんが,「様子がおかしい,いつもと違う,ある人と自殺の計画を立てている。そういうときの顔は怖い」と,相談に来たことがあります。
十代の患者さん(K)が,「犯罪者の気持ちって分かりますか?」と,あるとき訊いてきました。この質問は,昨今,十代の子の重大犯罪のニュースが続発していることに関していたと思いますが,実は彼自身の不安でもあるようでした。
彼は生い立ちに,ある事情があり,しかしながら母親を助けるよい子として成長しました。その’ある事情’が,彼の心に潜在している怒りをもたらしたと思われるのですが,彼自身はそのことに無意識でした。治療がはじまって,うつ状態が晴れるにつれて,制御し難い激しい怒りに苦しむことになったのです。
彼の自我は,怒れる分身たちを抑圧することで自己を保ってきました。彼が抑うつ感と無気力感に囚われることになったのは,母親を助けようとする心に無理があり,その一方で自分を押し殺さずにはすまなかったからです。
母親は強い人ではありません。幼い彼が母親を助けることに腐心したのは,心根の優しい彼としてはそれ以外にはできないことでした。そしてその代償をも背負わされることになったのです。
過度に抑圧された怒りは,憂鬱と無気力の十分な理由になります。
それは自己を切り開いていくはずのエネルギーが,自己を閉塞させる方向に流れているからです。
母親を助けることが何故このような意味を持つことになったかといえば,母親に大いに助けられなければならない年代に,幼い彼の怯える心は孤独に耐えるしかなかったということがあります。
また強い依存関係にある母親が危機的状況にあるので,母親を支え,助けることが自分を保つ上で,不可欠の要請でした。
それは,そうしたいというよりは,そうしなければならなかったのです。つまり自発的である意志に基づいたというより,他から強いられたという性格を持っているのです。
大人の分別で母親を何らか助ける場合には,どういう場合であれ一定の満足が得られるでしょう。それは強いられたものではなく,自ら意志してする行為だからです。しかし幼い子であれば,自分を助ける立場にある母親が窮地に陥っていること自体が一大事です。更に,母親の窮地を助けるのは,幼い自分ではなく,誰か大人,特に父親でなければなりません。しかし幼い彼は孤立無援に等しかったようです。大人たちからそれらが得られないときに,母親を助ける役割を,いわばそれら不在の大人たちによって強いられたに等しいことになるのです。
事実,殺意をも秘めた彼の怒りは,不特定の他者と父親とに向けられています。
これらの症例に共通しているのは,自我の世界の分裂が公然化することによって,社会性と精神性との活力が著しく低下するのと,それに反比例して破壊性を内に秘めた孤立性のさまざまな様相です。
以上の四例を上げた理由は,心の病理現象が,本来は影に隠れているはずの心の裏舞台のものたちが,表舞台に躍り出て公然化している(しようとしている)ことを示すためです。
心が裏舞台と表舞台の二重構造になっているのは一般的なことで,心とはそういうものです。
その二分化は,繰り返しになりますが,自我に拠るもの(つまり人間)の必然です。ですから潜在的に,人間は二重人格といえます。
心が健康であれば,社会的人格がしっかりと確立されているので,その人格の別称ともいえる表舞台が安定した活況を保っています。そして裏の世界は,影に回って縁の下を支えているといってよいでしょう。
この場合の表と裏の舞台の統括者,演出者が自我です。とはいえ,いま述べたように,心は裏と表に二分割されているので,それぞれの世界がそれなりに統合されていると考える方が理解を進める上で便利です。それでここでは,前者を統合するものを裏の自我と呼び,後者を統合するものを表の自我と呼んでおきます。
ちなみにC.Gユングは,心の全体をコンプレックスの複合体とみなしています。ユングによれば,自我はその気になれば意識化が容易な心の世界の中核であり,意識化が可能ではあるが,原則的に無意識である世界を個人的無意識と呼んでいます。また,この個人的無意識の世界は,多数のコンプレックスから構成されています。そして自我もまたその一つで,自我コンプレックスと呼ばれています。
ユングによれば,このように意識化が容易である心の領域の中核が自我であるので,彼がいう個人的無意識の領域は非自我の世界ということになります。
私が裏の自我と呼んでいる領域は,ユングの個人的無意識に相当しますが,なぜ敢て自我と呼ぶかといえば,ユングのいう個人的無意識の世界は,いわば自我の負の遺産だからです。自我の関与があってこその存在であるからです。
心の世界で自我の関与が及ばないのは,ユングがいう普遍的(または集合的)無意識の領域です。言葉を換えれば,この領域は自我を超越した世界です。時間的,空間的に,自我に拠る世界は有限性のそれですが,心の内なる普遍的無意識界は,無限性の性格を持っています。
人間が人間たるゆえんは,自我に拠ってです。つまり自我の領域こそが人間的世界ですが,人間を超越した世界をそれぞれの自己が心の内に抱え持っているところに,自己が永遠に現在の自己を否定的に超え出て,新たな地平を求めつづける時間的存在である理由があります。
そして普遍的無意識の存在は,人間が超人間的である自然に内包された存在であること,人間の存在由来をそれぞれの自己の心の内部に抱え持っていること,を暗黙の内に示していると考えることができます。
以上の意味での自然は純一であるのに対して,時間的性格を持っている自我は,果てしない自己否定の階梯をスパイラル状に上昇していくのを理想としています。つまりその都度の自己は否定を内に含んでいます。
純一なる善,正義,愛,公正などなどを追求するのは人間であればこそというわけですが,それは内に,悪,不義,憎しみ,不正などなどを常に抱え持っている証拠で,それが人間です。
敷衍すると,例えば純一なる善を追及するとして,それは理念としてのみの概念的存在で,実際には善の否定,つまり不善が尽きることなくついてまわればこその追求です。ここにもまた,人間が有限の存在でありながら無限性を生きている様が現れています。
人間は人生を追及しようとするかぎり,自我に拠って,以上のように人生の階梯をスパイラル状に登っていくことになりますが,それは別な角度から喩えていえば無限につづく負債の返却です。つまり自我は,仕事をすれば,必ず何らかの負債をも背負い込む宿命の下にあるといえるのです。
’追求する自我’であるかぎり,精神性と社会性との追求ということになるでしょうが,人間についてまわる身体性と他者性とがそこに干渉してきます。これらの属性があるかぎり,人間はたえず煩悩に引きずり込まれないわけにはいきません。
十歩前進,九歩後退といったところが,うまくいっても人間の現実ではないでしょうか。
まことに死によって,人間はようやく本物の自由になることができるようです。
解脱,悟り,などによって得られる解き放たれた感覚,真に自由であるという感覚は,その根拠を死から得ているように思われます。
このように自我は自己の開拓者であり,同時に,やむを得ず自己を貶めるものでもあります。
開拓された自己の全体の中核にあるものを表の自我,貶められて陰の領域に追いやられた自己の中核にあるものを裏の自我と,ここでは呼んでおきます。
ユングが述べているように,無意識の領域はいくつものコンプレックス群から成り立っています。その中で自我コンプレックスと呼ばれているものだけが,一定の恒常的体裁を保っています。そのために,誰それという固有名詞で呼ばれることが可能になります。つまり,それぞれの自分がそういう体裁で存在しています。
心のこの世界が自我の仕事の正のものです。そして正を生み出そうとする自我の仕事の背後に,負の遺産がいわば量産されていきます。
この負の遺産の中で問題になるのは,他者への過度の配慮から,その過度にわった分の自己犠牲です。それは簡略化していえば,外面がよすぎる自己における自我の不始末です。
これら無意識界に存在しているコンプレックス群のそれぞれには,自我コンプレックスのような恒常的体裁はありません。
それぞれのコンプレックスには,それを刺激する特定の体験があり,そういう折に思いがけない激しい感情状態に囚われることによって,その存在が顕かにされます。
例えばふだんは落ち着いている大人が,子供が騒ぐ声を耳にするときに限って,その場に居たたまれない強い不安に駆られるとすると,幼い時代に甘えを満たされなかった体験をしている可能性があります。
この場合のコンプレックスは,幼い時代に母親に甘えられなかった数々の体験群の無意識的記憶と,それに伴う悲しみ,寂しさ,虚しさ,怒りなどの強い感情群とから成り立っています。
(20代のある女性(S)が,退職した職場に用があって顔を出しました。元の同僚達に,「思ったより元気・・・」とか「綺麗になった・・・」といわれて悲しかったといいます。彼らは上辺だけを見て,心内にある強い悲しみ,寂しさに日夜悩まされているのを察してくれなかったからです。
幼いころに母親に甘えたいのに甘えられないでいる心を,母親に気づいてほしいという願いが元々あったと思われます。しかし,それは果たされないまま成長し,いわば未済のままでいるのです。その心が無意識的に他者に向かうとき,その他者は母親代理ということになります。虚しく期待してしまう様子がここに現れています。
何もいわなくても分かって欲しいという気持ちは,甘えの変形です。大人のいまでも,幼児のころと少しも変わらず,母親代理の他者が気づいてくれるのを虚しく待っている心が,ここに現われているのです。
中には,寂しがりやであるのを見抜いてくれた友人もありましたし,それなりに努力もしてくれましたが,彼女の心が癒されることはありません。「私は甘え方を知らないのかしら・・・確かに強がって甘えたりしないと思うけど・・・」といいます。しかしながら,彼女が望むように甘えると,幼児そのもののようになるに違いなく,それは手に負えない病的な行動になりかねません。
(このような行動化は,境界性人格障害に典型的にみられます)
心にある欲求を他者が気づき,解決を図ることができるのは,乳幼児と母親との関係における母親だけといってよいでしょう。この関係での両者は一体の関係にあり,未熟な乳幼児の自我を母親が代理しているからです。この関係においては,乳幼児の心の要求を,母親はほとんど自分の心の要求とおなじように扱うことになります。
成人においては,阿吽の呼吸とか,腹を探るとか,勘で分かるなどというように,人の心を直感で察することは可能であるにしても,乳幼児のように扱えば,ふつうは余計なお節介ということになります。
従って自分の内部問題であるこれらのことを解決できるのは,本人以外にはないのですが,人はしばしば,「黙っていても意を察してほしい」と思うものです。キリスト教文化の影響の下にある欧米人にくらべて,日本人にはこの傾向が強いのは,かねてからいわれていることです。それは屹立する自我と,より相互依存的である自我との違いといえるでしょう。そのことは集団行動を得手とすることや,公衆道徳のありようなどにも表れています。
たとえばかつての国家統制の行き渡っていた時代の日本では,二宮尊徳型の忠義者が公衆道徳を率先して黙々と実践すれば,社会の大勢が自然にそれに見習うことになるのがふつうです。
これがなぜ幼児心性かといえば,個々人の自我が,良かれ悪しかれ自立していないからです。この場合の主体的自我は,いわば外在する集合的他者ということになり,それは天皇を頂点とした権力機構であるといえます。個々人の自我は,幼い子が母親の自我に依存するように依存しているのです。
ですからこの権力機構が崩壊した’民主国家日本’では,自立していない個々の自我が解放されて,幼児のように’やりたいようにやる’人種がここかしこに見られるようになり,公衆道徳は一転して地に落ちることになるのです。
自立していない自我の下での個人主義は,幼児的自由がまかり通ります。それは真の自由とは似て非なるもので,いうならば’勝手にやる心’といったものです。そしてまじめな心の持ち主は,集団に依存します。かつての強力な国家的集合体ではなく,個々の大小の集合体に依存します。ここでは集団に帰依することによって,自我は主体者である困難(自由と責任等々)を免れる代わりに,自己自身を追及する機会をも捨て去ることになります。こうした状況では,責任の主体があいまいになり,欺瞞的精神に傾かざるを得ません。集団の秩序に従うのが前提になるので,秩序を乱すものは排除されます。そこでは,時として正義が踏みにじられ,偽善がまかり通ることになります。
土居健郎氏は,日本人の心理特性を甘えという鍵概念で捉えています。
本来,甘える心はまさしく小児のものです。それが日本人一般の心理的特性であるのは,キリスト教的な唯一神による民族の支配がなじまない何らかの風土的な事情があり,個々の自我が,より人間臭のただよう現実的な集合体に依存したからに違いありません。超越的なものへの依存であれば,それは個々の問題になるのですが,人間的な集合体への依存であれば,自我はさまざまに移ろうことになるのです。
先のK,Sの二例は,心の無意識にある幼児心性が強い勢力を持っていることを顕かにしているのです。
言葉を換えれば,心の表舞台を司る自我をおびやかすほどに裏舞台の勢力が大きいといえるのですが,冒頭に上げたY,W,Zの三例では,いうならば表に出てはならない裏舞台のものが表に出てしまっている様子が現れているといえます。
ここでは自我の統率力が破綻を来たし,心の表と裏の舞台がそれぞれ独立しているように,人格が二分裂している様相になっているのです。
三例に共通するのは,自我の統合力が衰微して破れが生じているという点です。そのために,裏舞台にあるはずのものたちが,自我の統率から逸脱して自律性を持ってしまっているのです。そのために自我の世界の二分裂が公然化したともいえ,分裂したそれぞれの世界の統合者を,一つには表の自我であり,そして一つには裏の自我であると呼ぶのが現実的であり,それなりに意味があるのです。
これまでに述べてきたことの繰り返しになりますが,自我に拠る現象的世界は,意識・光・生きる・有限・・・ということで特徴づけられるものです。そして無意識・闇・死・無限・・・といった世界が,それら現象界を包囲しています。
それは,心の表層はそれら光の世界のものであるが,闇の世界をも含み,両者は密接不可分の関係にあるということを,そしてまた,光の世界は独立を志向しながらも闇の世界に依存していることであると言い換えることができます。
つまり人間は自我に拠っているので,自我のものである前者の性格を持っているのはいうまでもないのですが,自我を超越している後者の
無数にあるともいえるコンプレックス群が正の意味を持つのは,自我がその存在に気づき,自我コンプレックスの一員と認め,表舞台に引き上げるときです。こういうときには,裏舞台に流れていた負のエネルギーが正のものに賦活されるので,一見して元気になります。さまざまな精神療法,心理療法がうまくいけば,必ずこのようなことが起こっているといってよいでしょう。
しかし自我との接触が図られないままでいると,それらのコンプレックスは,さまざまに負の力を現すことになります。
両者の利益の矛盾に直結するのです。
ところで自我はなにを拠り所に存在しているのでしょうか?
自我は,人間に固有のものです。人間は自我に拠るものです。人間の認識能力は,自我の機能に属します。自我は意識という光の世界の核であり,光は生きる意志と共にあります。
自我の誕生の由来,意味は,人間の理解を超越しています。つまり自我の光や認識能力のおよばない問題です。自我は意識という光の世界を演出しますが,自我が自我自身の根拠であることはできません。従って自我が存在する所以は,心の闇の領域,つまり無意識の世界以外にはありません。それは仮説以上のものです
ですから自我の実体的な根拠を名指しすることは不可能です。人間の身体をつぶさに調べても,自我の根拠についての具体的な答えは見つかりそうにありません。しかし身体のいたるところに,その兆候があるようでもあります。
繰り返しになりますが,自我は人間の意識活動が存在する根拠です。身体的,精神的な全ての現象は意識活動に伴うものです。自我を実体的な存在として名指しすることができず,自我に拠る意識活動として世界を現出させている人間には,世界は実体的にではなく,現象的なものとして存在します。
換言すると,もろもろの精神現象が存在する以上は,然々の原基的な起源がないはずはないが,それを実証することは不可能であるということになります。
自我はそういう性格のものです。それはいたるところに姿を現しているが,それ自体は決して意識に映じることはないといえます。
つまるところ,自我を拠り所に意識による光の世界を生きる人間は,意識の消滅によって世界は闇に溶け去ります。死は自我の終焉を意味します。
以上のように,「自我は,その存在様態を人間が知り得ないものの,何か原基的なものに拠って存在していると考えなければ,精神現象の一切が説明できない」というのは,合理的な仮定です。一定の仮説を立てて合理的な理解を目指すのは,必要なことです。
それはやがては実体的に証明することができるという性格のものではなく,永遠に仮説にとどまるでしょう。ですから,それぞれの分野でそれぞれの仮説を立てることになるのは当然です。そしてそれぞれの仮説は,それぞれの分野に現象として存在しているものを,合理的に説得する力を持つかという意味が問われることになります。
このように,自我のような,そもそもの存在根拠を,人間的な理性の及ばないところに求めるしかないものは,その実体性においてあいまい極まりないものです。そして精神の現象には,その類のことがずいぶん多いのです。
人間の理性的な理解を超越したものの全体を,仮に’自然’と呼ぶとすれば,自然の意志が人間の心の内部に及んでいるのが無意識の領域であると考えられます。意識界の首座にあるのは自我です。そしてそれに相応して,無意識界にも首座があると考えるのが合理的です。そうしたものが存在すると仮定することは,精神の病理現象を統合的に理解する上で意味があります。
その無意識界の首座にあるものを,ここでは「内在する主体」と呼んでおきます。それは自我の拠り所となるものです。自我がその意志を探り当てることによって,人間の精神を造形していくものと考えることができます。
自我は,喩えていえば大海を行く小舟の船長ですが,船長が操る羅針盤に映じるのが主体の意志です。あるいは星を読み取って航路を定めるのが船長であれば,星々の運行をつかさどるのが主体です。いずれにせよ船長の恣意で小舟を動かすことはできません。それは漂流に他なりません。
人生はどのように生きてもよいとはいえません。「自由に生きる」ことには,主体の意志を探り当てるという意味があるでしょう。これに対して,「どう生きようと勝手だろう」という考えは,自由とは似て非なるものです。それは自我が自分を引き受けようとしない姿です。ですから基本的なところで無責任なのです。たとえ漂流しようが構わないでほしいということは,確かに他人の与り知らぬこととはいえ,他人との関わりを欠いた行為というものはありません。いずれにせよ,主体の意志にお構いなしの生き方は,いわば心の内部の法廷で有罪判決を受けることになるのは必定です。それは他人に対しても,何らかの迷惑が及ばさないわけにはいかないでしょう。
以上のような考えは,人間が存在するのは何かの偶然に過ぎない,あるいは生物の進化の連鎖の過程にあるに過ぎない,等々という疑問ないし反論にあうのは必然でしょう。そうした疑問が起こるのは,自然科学的な合理的思考が行き渡っている現代ではもっともなことです。
しかし,それは自我を首座に置いた思考によるものです。いま,ここで述べてきたことは,自我を最上位に据えることは不可能であるということでした。
さまざまな観点から考察を加えることは必要なことであり,そうしなければ済まないものでもあります。それぞれの立場によって,現象の読み解き方がそれぞれに違ってくるのは避けられないことです。しかし,自我を最上位に置く自然科学的思考が,精神現象を統合的に解明することができると考えるのは不可能です。
これまでに述べてきたことがどういう意味を持つかということについては,臨床的な有用性がどの程度かということにかかっていると思います。事実,それらは診療を通じて自然的に浮かび上がってきた考えです。病気の成り立ちや自己が改善されていく様子などに考察を加え,それらは更に臨床の上で検証され,強化されてきたといういきさつがあります。それに伴って,その仮説に基づいて治療に当たることに,一定の確信を持つことができているということでもあります。
無意識界にあるとする人間の精神の直接的な母体を,内在する主体と呼ぶのは仮定の命名ですし,自我は,人間が自然そのものではない存在として乖離されたときに,この主体から生み出されたものであろうと想定するのも同様に仮定のことです。そうした前提の上に立って,臨床上の有用性がそれなりに確かめられたときに,それらの仮定は一定の意味を持つと考えるわけです。
結論的にいえば私が果たさなければならないのは,以下のことです。
治療者に対して患者の皆さんは問題を提起し,治療者としての私には,それを受け止め,有効性のある治療的な展開と還元とをもって応える義務と役割があるということです。更につけ加えれば,患者の皆さんは,教師としての性格の一面を持っています。教師が問いを出し,生徒である治療者がそれに対して一定の答えを出す,その当否を決めるのは教師であるというわけです。
この場合の教師の役割は患者さんの自我にではなく,内在する主体にあるといえます。患者さんが発する問いは自我によるものですが,治療者の自我がそれを受けて,双方の意志を通じ合うことになります。それらのやりとりの結果,患者さんが納得でき,それに伴って心に力が湧いてくるときに,生徒である治療者は,教師である双方の主体から合格通知を受け取ったことになるといってよいように思われます。
診療というものは,本来的にそのように展開されるものと考えてよいと思います。
幼い子の自我の自律性を守り育てる,唯一といっていい立場にある母親(と父親)の存在の重要性は,いくら強調されてもされ過ぎることはないでしょう。それはいうまでもないことですが,程度の差はあっても虐待する親が決して少なくないのが実情でもあります。子供は,親の前で逃れようがない立場にあるので,虐待される子供の絶望は察するに余りあります。それは,どんな犯罪よりも犯罪的であるといってもいい過ぎではないと思います。親から受けた心の傷は,一生を決定づけるほどのことなのですから。
虐待とまではいかなくても,子供は親から様々な干渉を受けるのが現実です。それは,人間の宿命といえるでしょう。他人の’要らぬ節介’は避け難い問題です。
赤の他人のお節介はともかく,親のそれは性格形成に大きな影響を与えます。
性格の健全な形成には自我の自律性が鍵を握ると思われます。その自律性が両親によって護られる必要があります。そのためには,親の自我の境界機能が確かなものである必要があります。そうでなければ,親は当然のように子の心の領域に侵入することになるでしょう。
自我の自律性は,境界機能と密接な関係があると想像されます。親が子の領域に無分別に侵入するのが当たり前になっていると,子供の自我の境界機能が混乱し易く,境界機能に護られない自律機能も混乱すると想定されるのです。
強い不安と硬直した自我を持った親ほど,子供への干渉が甚だしくなると思います。両親の干渉が過剰になれば,先に上げた少年の例のように,ロボットにされる恐怖を持つようなことも起こるのです。
以下は,甚だしい干渉をしてしまっている母親の例です。しかしこの母親は,劣等感が大変つよい人であるにもかかわらず,柔軟な心と子を思う優しさとを失ってはおらず,自分がおかした過ちをすぐに認めることができる人でもありました。
この方は,小学生の一人娘が,最近になって不登校になったという悩みを持っています。彼女は夫と離婚し,一人娘と実母と三人で暮らしています。娘が不登校になったことについて,甘やかせ過ぎがよくなかったのかという悔いを交えた反省をしています。愛情ならたっぷり与えている,むしろそれが行き過ぎているのではないかというのです。
しかし実際には,’愛情’の裏側には,大きな不安が潜んでいるのが明らかです。娘はごくごく幼いときから,喧嘩ばかりしている両親の仲裁役をしていたようです。母親が落ち込んで黙りこくっていると,「何か話して」といって母親を励ましました。「こんな駄目な親の私に,どうしてあんなよい子ができたのかと思ってきました」と彼女はいいます。勉強もできるし,手伝いもしてくれるし,申し分がなかったのだそうです。
この母親と幼い子の祖母(本人の実母)とは,良好な関係ではありませんでした。祖母が支配的,強権的で,母親に育児の自由さえ許さなかったようです。幼い子は,母親と祖母とのあいだの板ばさみにもあっていたと思われます。そして母親は,「こんな醜い私のような大人になってほしくない」というのです。けがらわしい大人になるくらいなら,ずっとこのまま子供でいてほしいと願ってきたそうです。テレビの番組や読書など,’大人のにおいがする’ものは,ことごとく規制し,排除しました。愛情と信じた過度の干渉が繰り返されてきたようです。このごろ,「なんでもお母さんには話をしてね」という母親の願いに応えてくれないことが多くなりました。母親は焦りと孤独感と不安を感じるのです。
これまでにも述べてきたように,自我の重要な機能の一つは自律性です。自然から乖離された人間は,自分の力で人生を切り開いていかなければなりません。それは小舟で大海を渡ろうとするような途方もないことです。そのための拠り所が自我の自律性です。先の比喩でいえば,自我は小舟の船長です。船長は自由に,主体的に操船しなければなりませんが,その自律性に根拠を与えているのが内在する主体です。船長が幼くて,操船術が未熟なあいだは親に依存して技術を見習います。そして,しだいに依存から脱して自由になり,直接に主体との関係を探り当てていきます。それが順調に進むときに,自我は自律性を発揮できます。
他者,とりわけ両親の望ましい援助と協力と指導があれば,または他者の干渉が自我の眼を眩ませなければ,その自律的な機能は,かなり自然に遂行されるのではないかと思われます。しかし実情は,両親を含めた他者の干渉が,無意識的なレベルをも含めると,無視し難いものがあるのが一般です。また,自我自身のそれぞれの能力の問題もあります。それらの事情から,自我が本来の自律性を保ち,適切に自己を導き抜くのは,むしろ困難だといわざるを得ないと思います。
幼い自我が自分のためになる仕事をしたいと思っているときに,権力者である親の干渉によってどのような影響を受けるか,先に述べたの二つの例に即して見てみたいと思います。
男児の例では,母親の愛情が弟に傾いていると感じ,母親に気に入られるように,活発にアピールしている様子がうかがわれます。しかし,その努力は一向に報われず,望むような反応が得られません。かえってうるさがられている印象もあります。父親はそのような母子関係と,息子の悩みに鈍感なようです。こういうときに少年はどうすればよいのでしょう?男児の自我は精一杯の仕事をしているように思われます。それが無効なので,怒りが充満しています。自我は役割を果たしているのですが,両親の協力が得られないので,結果としては無駄な努力になってしまっているのです。愛されたい,認められたいというもっとも過ぎる欲求には切実なものがあり,しかし,それらの欲求は,母親の協力を得られないので,自我はやむを得ず無意識の牢屋に押し込めるしかない(抑圧する)状況です。それは親の不理解,愛情の欠落によって,自我が無能力なのと何ら変わらないことになるのです。自我は大変に混乱しやすい状況です。不当な抑圧を強いられて,無意識の領域には怒りが充満しています。自我がそれらの不満の代弁者として,姿勢を変える必要があるのかもしれません。つまり反抗的な姿勢に転じるのです。しかし,よい子路線を取る少年の自我は,親に見捨てられる恐怖がもともと強かったと思われます。愛されたい,認められたいという自然で,当然の要求を,自我は精一杯すすめるのですが,両親には通じません。自我は両親の更に恐ろしい拒絶を回避するために,甘えたい心を涙を飲んで押さえ込まなければならない状況です。親の自我に迎合しなければ,存在そのものが危うく感じられるのです。押さえ込まれた甘えたい心たちは,傀儡化せざるを得なかった自我と両親に対して,悲しみや,虚しさや,恨みなどと共に怒りを充満させています。それら充満する怒りが,チックを呼び,夢の絵の中で,爆発しそうなロボットとして表現されています。ロボットの意味は,言葉によっても,行動によっても,意志を伝える力を持てないということかもしれません。
また,学校への通学路で,誘拐されるのではないかという恐怖があります。学校には友達がいて,学校生活そのものは問題がないようです。この恐怖は,母親との関係が遮断されてしまう不安のようです。母親が自分を捨てて,どこかへ行ってしまうという類の恐れは,意識上はありません。彼の自我は,母親がそんなことをするはずがないという認識を,精一杯保っているといえるでしょう。しかし内心の不安は打ち消し難く,無意識の世界にあるそれらの感情が,彼の自我を捕捉し,飲み込んでしまう恐怖を持つのでしょう。それが,誘拐という外部的な事件への恐れの形になって現れているようです。
彼は,将来,父親のような職人になるのもいいが,それ以上に整体師になりたいと考えています。その職業が両親の身体を癒して上げるのに役立つと思うからだといいます。もしかすると,その他に,両親の心にも整形を加えたいという隠れた願いがあるのかもしれません。
女児の母親の例では,女児はごく幼いときから,喧嘩の絶えない両親の関係と,自分をも含めた家族の関係との危機を救おうとしています。幼い自我の必死の願いと行動とに応えることができなかった両親は,少なくても子供の立場からは,幾重にも非難されても仕方がありません。女児の願いは叶えられなかったというべきか,半ばは叶えられたというべきか,両親は離婚しました。しかし離婚後,今度は母親と祖母とのあいだの板ばさみになりました。少女の自我は,本来は大人たちがするべきである関係の調整の役目を強いられました。幼いときから大人の自我の強さを求められたのです。親に愛されたい,励まされたい,甘えたいという子供本来の自然の欲求は,ここでも無意識の牢屋に押し込めるしかなかったのです。「私はなんで生まれたの?なぜ私を生んだの?」という疑問に応えるのが親の義務といえるでしょう。子供の側に,愛されている,信頼されている,大切にされているという肯定感があれば,それが答えです。
女児を母親は大切にし,愛情を傾けたつもりです。しかし母親自身に自己肯定感がなければ,それなりの健全な自己愛がなければ,子供に満足感を与えるのは,ほとんど難しいことでしょう。むしろ子供にそれとなく依存してしまうものだと思います。こういう依存は,穏やかな言葉や態度でカムフラージュされて,一見は仲のよい親子の図になるかもしれません。しかし,実質的に強制的な侵入になっていくと思われます。依存の対象になるのは,いわゆるよい子です。よい子というのは,そもそも(母親の)期待や要求に,無理をしてでも応えてくれるからです。「親が望むなら,そのようにして上げたい」と考えるよい子としては,母親が苦しむと分かっていながら,無視はできないのです。
母親の’苦しみ’にも,半ばは無意識的にでしょうが,よい子をそのように仕向けるための演技が入っているのではないかと想像されます。母親の半意識的な誘導によって,母親が悲しんだり,苦しんだりするのは,自分のせいと感じる癖が子供にはできていると思われます。そこには母親が,’愛情’を隠れ蓑に,もう一つの意図を隠し持っている姿が見え隠れしているように思われます。このあたりの事情は,子供もうすうすとは分かっていると思います。しかし,よい子であるかぎりは,母親の仮面を剥ぎ取ってしまうような考えは,到底できない相談でしょう。それは’愛情’の背後には,恐ろしい怒りが潜んでいる(母親が,幼い娘の気を引くために悲しそうな顔をするときにも,その心の奥には怒りが潜んでいます)のを感じ取っているからだと思われます。母親の怒りについては,どうすれば自分に向けて炸裂する(怒りの炸裂は,見捨てられる恐怖に直結します)のを防げるか,半ばは生存本能から分かっていると思います。恐らく,母親が大好きなのだという自己欺瞞にも陥っているのではないでしょうか。母親が愛情の仮面の裏に怒りを潜ませているのと,女児がつけている「お母さんが大好き」という仮面の裏に恐怖と不信とを潜ませているのと,母子それぞれが対をなして,演技的な関係にあると考えられるように思います。
こうした恐れを背景に,少女は母親に強く依存しているので,その関係が壊れることは,自己が破滅するに等しい恐怖感を持つのです。母親との間をつなぐ危うさをはらんだ絆を手放すと,無人の荒野に一人放り出されるのに等しい恐怖を持つのではないかと想像されます。
母親が望むように,という女児の自我の姿勢は,生きるための必死の戦略です。生存本能に駆られてのことといえると思います。そして一方では,自律性を犠牲にするという高価な代償を支払うことになったのです。それに伴い,’自分らしく生きようとする’意志のほとんど全てをあきらめるしかなくなります。それはかけがえのない人生を虚しいものにする,過酷な犠牲を強いることにもなるのです。
人間は自然から生まれ,自然に即することを最善とするものであるように見えます。それが損なわれるのは,他者との避けられない関係によってです。最も頼りとする母(そして父)なる他者によって,人生の塗炭の苦しみを味わいかねない不条理劇の幕が切って落とされるということが起こり得ます。そのように極端でなくても,子は親によってそれなりの被害を蒙らないわけにはいきません。それが人間です。人は,「親から受けた被害によって歪んだ心を,一生かけて自然的なものへ整え直す,それが人生である」という不可解な存在です。そして,それらの苦しみを招いてしまうのが自我であれば,改めてそこから脱出して自己を回復させるのも自我です。
この女児の幼い自我も,母親の愛情に守られているという安定した安全感が得られなかったと推測されます。おそらくそれとは正反対の母親への恐れ,恐怖,,不信感に,ごく幼いころに直面しただろうと思われます。それが自我の自律性を混乱させ,母親の自我への密着を促したと思われます。それらのことは,生死をかけたといえるほどの切迫した心理状況の下で起こることです。
幼い時代に経験したと思われる恐怖心や不信感などは,抑圧されて滅多には意識されることはないでしょう。それは年齢的に幼すぎるためではあるでしょう。しかし抑圧であるからには自我が関与し,抑圧されたものは無意識界にエネルギーを抱えたままいつまでも留まることになります。それは傷ましい心の出来事です。親が与えた心の傷ということになります。
このように幼い自我が自然の欲求を抑圧するのは,大人が何かを我慢するのとは比較にならないもので,いうならば心的外傷とでもいうべき出来事に直面したからであるに違いありません。それはよくよくの恐怖体験があったからに違いないのです。
それらの傾向,幼い自我が抑圧に走る傾向があるとすれば,その大元には,恐らく甘える心の抑圧があっただろうと想像されます。それは次のような事情によります。
乳幼児の幼い自我が,無意識界から送り出されてくる諸欲求を護るためには,母親との関係を抜きにしては考えられません。その最重要の他者とのあいだの関係が良好である証は,甘える心が満たされていることです。
母親への甘えが満たされている関係があれば,乳幼児は母親に受け入れられている,信頼されている,愛されているなどのことに確信を持て,満足感と安心感に浸ることができます。そういう関係であれば,何か不満足なことが生じたときには,恐れることなく不満や怒りも表現できるのです。そしてそういう関係の下では,それは基本的に,改めて母親によって受け入れられるはずです。
逆にいえば,母親への甘えを抑圧して満たされない思いをしている乳幼児の場合は,母親に受け入れられていない,愛されていない,信頼されていないという思いに駆られがちになるのは必然でしょう。そして子供の方も,母親への愛や信頼の確かさに自信を持てないことにならざるを得ません。そういう関係状況では,新たに不満が生じると,激しい怒りを向けるか,恐怖によって沈黙するかになりがちだろうと思います,それを受けて,母親の方が力で対抗したり,無関心になったり,悪循環に陥る可能性を否定できません。
甘える心が充足される度合いは,自己愛と他者愛との確かさの礎石に関わる問題なのです。
例示したこの女性の幼い子について見れば,底深い恐怖心がいわば仲立ちとなって,女児の自我は母親の自我に密着し,その上で母親への愛着という体裁に変質したのでしょう。換言すると,(自己の本心から見て)偽善的な装いをこらして自分をも母親をも欺くのです。母親を愛している,母親が大好きだというふうに信じ込むことで,母親との関係をはかろうとするのですが,一方で意識下に抑圧されている甘えられなかった分身たちは,その心の嘘にだまされることはありません。それらは表の自我と母親との一種の取引の犠牲になっているので,両者に対する怒りや恨みなどの感情と共にあります。ですから,どんなに表面上は母と子の関係が蜜月のように見えても,裏の自我に率いられる分身たちが心を許すことはありません。
(よい子の装いを偽善的というのは,代償として支払う自己犠牲が大きすぎるのを考えると酷な表現のようにも思いますが,非難をしてそのように呼ぶわけではないのはいうまでもありません。偽善というのは,悪意を隠し持って他人に親切を施すというようなことになると思います。よい子の仮面の裏には,一般的な意味での悪意があるわけではないのはいうまでもありません。しかし外側(親,他者)への配慮が過ぎて,内側(自己自身)を疎かにし過ぎるのは,自分自身に悪をなしていることになるのです。よい子がいじめに合うのは,そのような’嘘’が感じられるからかもしれません)
心から母と子の和解的な結合が起こるとすれば,唯一,表の自我が母親から距離を取り,無意識下に潜む分身たちの恨みや怒りに目を向けるときです。そうすることができるためには,表の自我が本来の力を回復させていることが前提になります。それは自我の自律性の回復をも意味します。
そのような心の転換を生じさせるのが,心理的な治療の目標になります。
これら二つの例に見られるように,自我の基本姿勢は,両親の影響を決定的に受けながら形成されます。生まれて間もない人生の最早期に情緒的に満たされることが,他者との関係を円満に保つことができる性格を形成する基礎になるはずです。
男児の例では,自我の自然的な機能が両親によって無効化されました。女児の例では無効化を恐れ,母親への盲従の途を選びました。両者とも,それぞれの自我は,いわば親の自我の傀儡になるしかなかったといえます。
幼い自我が脅威を受けてすくみ上がり,母親の自我に密着するのはやむを得ないことです。しかしながら,内在する主体との関わりから見れば,許し難い堕落という意味になる危険があるのです。自我の自然の機能を,自我自身が根本から歪める動きをしたことになるからです。これは幼い子の罪というわけには勿論いきません。しかし罪を犯したのに等しい罰のような人生が待っています。主体との関係をあやまたず確立することを目指すのが,何よりも自然的な要請だからです。
このことは,ダルマになるのが自己形成の理想といういい方で言い表すことができます。
心の軸が自己の中心にあれば,何かのストレスによって心がぐらつくとしても,過度にぶれることがなく,やがて心は平静を取り戻すことができます。しかし母親,あるいは母親代理の他者,あるいは(人間との関わりから脱落して)何ものかに,悪しき依存をしている自我の下では,心の軸は自己の中心から遠く離れるので,ストレスがかかって心がぐらつくと,態勢を容易には整えられないのです。それに加えてそういう心の状況では,自我がうまく機能しないので,心はしだいにエネルギーの枯渇感に囚われていきます。
ダルマ的な心の軸は,自我が主体としっかりと結合しているときに生じるといえます。そういう自己を目指すのが,それぞれの人生の理想的課題であると考えられます。
このように他者の介入によって,自我の主導性を損ねてしまう危険があります。母なる他者の影響が殊更に大きいのは,人生早期の未成熟な自我が,他者の保護を絶対的に必要としているからです。それを護る第一の立場に母親があるからです。あたかも神に対するかのように,赤ん坊は母親に全能者を要求するのです。
赤ん坊は人間の心の形成の歴史の中で,自己愛という自足態の中に満ち足りる,特別に理想的な時代にあるとする考えがあります。しかしそれは間違いであるように思われます。逆に,生を受けたが故に,必然的に死に怯えるものとなったのが赤ん坊であると思われます。そうであればこそ,幻想的な絶対者によって護られなければ存在できないのでしょう。わずかな闇の気配に怯えるだろう赤ん坊は,母なる全能者のふところにまどろむことを希求するのでしょう。そのふところは,つまり母親の愛情ということになり,そこには(広義の)性愛的な彩りがあるに違いありません。絶対的な上位者に護られていたいということは,言葉を換えれば甘えたいということになります。甘える欲求は,生死を賭けたものにふさわしい強力なエネルギーを持っていると考えられます。ところが,母親がこのようにかけがえのない立場にあるだけに,逆に,一転して恐怖をもたらす者になる危険性を払拭することはできません。全能幻想はいつかは綻びるのです。その綻びた隙間から垣間見る闇が与える恐怖が,赤ん坊に,母親への全能要求をためらわせるのではないかと考えられます。その恐怖は,母親その者への恐怖と区別がつかないだろうからです。生きるために母親に甘えることが重要ですが,垣間見た闇(死)の恐怖が更に大きなエネルギーを持っているために,その希求を制御するのです。母親への全能要求を恐怖によってあきらめ,現実的な関係の模索がはじまります。
人は巨大な矛盾の中に存在します。その最たるものが,生と死です。つまり,生とは究極のところ死の主題化である,という難題を人は負っています。赤ん坊にとって,全能要求は,生が主題であるかぎり死の存在を排除できないという現実原則が受け入れ難いという意味を持つのでしょう。そして赤ん坊にして,全生命の要求が,はからずも死の恐怖を否定し得ない現実によって打ち砕かれたときに,生と死とを本能的な知恵によって止揚しなければならなくなるのです。そしてそれが果たされたときに,人間存在として自立する第一歩を踏み出す基礎を得ることができます。
しかし,この激しい対立を止揚できないときには,母親への全能要求も,母親への恐怖(死の恐怖に通じます)も無意識下に収めて,いわばなかったことにしてしまうようです。それらの要求も恐怖も克服されないまま,いわば意識の地下に冷凍保存されることになります。
このように畏怖する自我は,自立を断念した自我でもあります。母親を畏怖する心は,死を畏怖する心に通じるものです。時によって母親は,半ばは意識して,半ばは無意識的に,幼い子のこうした畏怖する心に乗じます。時によって,巨大な不安を潜在させる母親は,子を自分を助ける道具にしようとします。
このようなことになれば,罪を問えないものに罪を科し,罰を受けているかのような多難な人生にしてしまいます。そうはならいように,親をはじめとした周辺の大人たちは,よくよく心をつくす必要があります。
母親の胎内にあり,まだ意識の活動が始まる以前には,心が存在していません。それは光もなく,従って闇もない世界です。それは全であり,かつ無でもある世界です。そして意識が芽生え,心が生まれることにより,光と闇の世界が始まります。赤ん坊は光を意識することにより,闇を知るのです。光は自我の世界のものであり,従って有限の世界のものです。闇は自我の光がおよばない世界のものであり,無限ないしは無の性格を持ちます。
言葉を換えれば,自我に拠る人間の世界は,それが存在する以前には全であり無であった世界が,いわば二分割されて現れます。つまり意識による光の世界のものとして存在することに伴って,生の世界が生じ,従って必然的に死の世界が生じたのです。生と死と,二極に分化した世界を生きるのが人間の宿命です。
生を受けたばかりの赤ん坊も例外ではありません。生まれる前には光も闇もない世界にあったものが,生を受けることにより,赤ん坊は,早速死におびえる者であらざるを得ないのです。生という光を意識するものにとって,闇という無限,無,死は絶大な脅威になります。赤ん坊は光の世界を享受するいとまもなく,怯えているのです。
闇に怯える赤ん坊の心の光を支え,育てる唯一最大のものは,母親の愛です。それに支えられて,赤ん坊の自我に備えられていると考えられる愛の原基に,ようやく活力が与えられるのです。しかしそれは圧倒的である無の感覚の前に怯えやすく,他でもない最も頼りとする他者なる母親によって怯えを刺激されたときに,著しい恐怖を味わうことになるだろうと想像されます。それに伴って,幼いとはいえ心の形態は既に備わっている赤ん坊は,襲い掛かる脅威に対抗するために母親の自我にとりすがるという原初の対人駆け引きを行い,かつ心を抑圧するという防衛手段を講じるだろうと思われます。必然的に,赤ん坊の無意識界には,自我の不当な抑圧を受けた無垢の心たちが集合体を作るのです。そこには不当な扱いを受けたものたちの怨嗟の声が満ちているといえるでしょう。それらの死の世界に追いやられたに等しい分身たちには,いつか自我によって改めて認められ,受け入れられる願いを持つもっともな理由があるのです。長期にわたってそれがかなえられないでいると(幼い子がこの作業をできるためには,両親の反省,手助けが欠かせないでしょう),これらの分身たちは,まとまりのある一つの勢力になります。それは心にできた怨嗟に満ちた沼のような趣があります。自我としては近づくと危険な雰囲気を持つのです。その沼の中心にあるのは,裏の自我と呼ばれるにふさわしいものです。表の自我と裏の自我の関係は,正と邪,善と悪,生と死,明と暗というふうに,真っ向から対立するものです。
表の自我は,生へと向かうエネルギーを司ります。裏の自我は死へと向かうそれを司ります。心には表層の生へと向かうエネルギーの河の流れがあり,深層には死へと向かう河の流れがあります。
人が何かの行為,行動をするときに,それに伴って無意識界からエネルギーが動員され(内在する主体によって送り出される),自我がそれを護ったかぎりで生へのエネルギーが受給され,護れなかったかぎりにおいてエネルギーは死への流れに合流します。一つの行為(行動)に伴って,二様のエネルギーの流れが生じると考えられます。
仕事で無理を重ねて心の病気になるのは,日ごとの仕事が自我に活力を与える(自我が引き受けているかぎり満足感が得られます)よりは,自我が受け入れ難く感じている度合いが甚だしいということになります。そのときに,仕事をするときに動員されたエネルギーは,より多く負の方に回ることになります。こういうときには休養が意味を持ちます。逆に無用に怠惰にしていると,自我はエネルギーを受給されないままになり,活力を失うばかりです。
自我が生まれてきたエネルギーを護り切れるとき,興奮に満ちた歓喜が起こるでしょう。科学者が待望の発見を目の当たりにしたとき,芸術家が霊感に触れたとき,競技者が力を出し切ったとき,恋する男女が恋を交わすときなどがそれに当たると思われます。
小学生のA君は,一時期,学校へ行けませんでした。最近は行けるようになっていますが,時には休みます。あるとき,学校で,広島の被爆者の戦争体験を聞く機会がありました。悲惨な話を聞いたあと,大好きだった肉を食べられなくなってしまいました。食べようとすると吐き気がするのです。
夜になると,お化けが怖くて一人で寝つけません。そんなものはいないと思っても,寝つくまで母親に傍にいてもらわないと安心できません。爆弾を投げつけられる悪夢に悩まされたりもします。
母親がやむを得ない会合があったとき,家で過ごすことができず,父親につきそってもらい,会合場所の近くで待つ必要がありました。
父親と母親が喧嘩をすると,母親に抗議します。父親にはできません。元々は,両親の口論が激しかったのですが,最近では母親も落ち着いて,自制することができるようになっています。
一般に,小学校に通うのは,まず社会から課せられた通過儀礼の一つという意味があります。課せられた学校状況を引き受けるのは,自我の役目です。自我が成熟して引き受ける意志を持つことができるようになれば,課せられたものという受身の姿勢から,自分が自分自身に課していくという能動的姿勢に転じていきます。このような心的状況であれば,母なる他者から与えられる満足感を,自分で自分自身にもたらすという重要な経験をすることになります。
自我が未熟な,より幼いレベルでは,幼児の満足感は主に遊びを通じて得られますが,それは(主に)母親によって補佐される必要があります。つまり未熟な自我は,母親のそれに依存して補強してもらう必要があります。無心に遊びに没頭しながらも,母親にその喜びを共有してもらうことが意味を持ちます。敢て母親を困らせることもするでしょうが,それは母親に喜んでもらう満足を求める要求と考えるべきです。それらのことは,母親への甘えの欲求を主軸とした行動といえます。原初の人間関係は,母親との関係であり,それは甘える満足をめぐってのことといえるでしょう。
小学生が学校に通うのは,自我がある程度成熟した年齢に達したときです。従って通学は欲求ではなく意志に基づきます。
欲求は無意識という心の内部の自然から送り出されてくるものです。自我がそれを受動的に受け入れるのです。一方,意志は,自我の主体性に力点があります。つまり自我がある計画を持ち,それに伴って個々の行動に必要な欲求(方向性を持ったエネルギー)を呼び出します。求めに応じて送り出されてきた欲求を,自我が護りとおすことで行為が成立します。それに伴って満足感が得られ,自我に活力が与えられると考えることができます。元気があるというのは,自我に(欲求を護ることにより)エネルギーが補充され,活力が保たれているということです。
意志に関して,ある行為の計画を立てるのは自我の役目ですが,いま述べたように幼い自我は両親をはじめとした大人たちの助けを必要とします。学校に通うことについては,本人の自我に任せるというわけにはいかないといえるでしょう。義務教育といわれるように,義務として課されたものであることが意味を持ちます。つまり多かれ少なかれ,意志的な心の仕事には苦痛が伴います。本人がしたいようにさせていたのでは,つまり意志の弱い子になってしまいます。天分も本人の気ままな欲求に任せていたのでは開花しないと思います。そのように他者によって義務として課されたものを,改めて積極的に引き受ける自我であれば,最も好ましいことになります。
躾けも含めて,教育には,以上のように,上位者である他者の関与が重要な意味を持ちます。
A君の不登校については,誰もが理解できるほどの問題が学校状況で発生したからというわけではありません。最近,午後から登校したときに,先生に,午前中は登校できなかった理由をきかれ,「鼻水が出たから」と返事をしました。すると先生に,「そんなことで休む子はいないよ」といわれました。A君としては,先生の言葉は心無いことになり,傷つきもし,怒りも覚えました。しかし,A君は答えに窮してそのような返事をしたのでしょうが,本当の理由はA君にも分からないのです。何か分からない理由で意志がくじけたのです。
これを先ほどの図式に当てはめてみると,学校へ行く意志を持つたのは表の自我です。そしてその意志を打ち砕いたのは裏の自我です。A君は裏の自我に引きずられて,心の沼に落ち込んだのです。
A君の夢からは,強いエネルギーを持った恐怖と怒りが,心の沼に渦巻いている気配が窺われます。母親から片時も離れられない不安の様子と重ね合わせると,それは見捨てられる恐怖に由来するもののようです。
(自我に拠って生きることを宿命とされる人間は,即座に闇(死)に怯えるものであることをも宿命づけられています。
心には生と死と,二つの極に向かうエネルギーの流れがあると考えられます。自我は専ら生の世界を切り開くものですが,その仕事を助けるために他者の関わりが不可欠です。そしてその欠かせない他者の介入が,自我が節を折る理由にもなるのです。
自我が正当に仕事をしたときには,生へのエネルギーが勢いを増し,他者の介入によって自我が節を折ったときに生へのエネルギーは供与されず,そのエネルギーは自我が護れなかった分身(黒い子)を作り出し,心の沼が広がります。この沼からは,死の極へと向かう流れがゆるゆると形成されることになるように考えられます)
A君は,自覚的には,母親がまさか自分を見捨てるなどとは考えていません。しかし内心では強く疑っているのです。その恐怖と不信とは,無意識界に抑圧されている幼児心性がもたらすものといえるでしょう。幼児心性としては,自己愛と自己を信じることとは母親を経由して可能になります。つまり未熟な自我は母親の自我を頼りにして,幼児的な判断をするのです。
幼児心性とは,ごく幼いころに,母親への恐怖心から自我が護れなかった欲求たちです。とりわけ満たされなかった甘えの欲求が,護ってもらえなかった不満,不信,悲しみ,虚しさ,恐怖などと共に,怒りと一体になって意識下に現に潜在しているものたちのことです。
それらは裏の自我とでもいえるものを首座として,強い勢力となって表の自我に圧力を加えます。その影響を受けて,生の世界を司る表の自我は機能不全に陥りがちになります。
見方を換えれば,傷ついた自己愛ということになります。自己愛という自我機構に内属すると考えられる(自己愛は習得されるものではなく,生まれ持ったものです。自己愛の健全な成長は,つまり心が健全に成長しているということです。しかし,生まれたばかりの自然のものは傷つき易いのです)ものが傷つけば,自己を正当に愛することができません。信頼する(自信を持つ)ことも困難になります。自己がそういう状況に置かれると,当然,他者愛も他者を信じることも難くなります。
先生に訊かれて,「鼻水・・・」の口実を考え,先生に,「そんなことで休む子はいない・・・」といわれて傷ついたのは,(表の)自我が引き受ける能力に欠けるものがあることを示しています。先生の自我は,その点,健全な状況にあるので,鼻水が出たくらいでは学校を休むとは信じ難いのです。一方,A君は,得体の知れないことに悩まされているのを察してほしいと思っているのでしょう。更にいえば,幼い子の自我が母親のそれに取りすがるように,先生の自我にも取りすがりたかったのだろうと想像されます。甘えといえば甘えですが,小児心性の支配を受けているのですから,ふつうの意味での甘えとはいえません。心の構造が病的になっている心的状況下での言葉にならない叫びが,甘えに似ていることのように思われます。
母親に十分には甘えることができなかったことに起因する幼児心性が,先生に母親代理の役を期待したようです。そこに介入できなかった自我は,先生の質問にあって,答えにならない答え方を探し出したということでしょう。それで引き受ける意志を示せず,頼りにならない自我を差し置いて,裏の自我に拠る幼児心性が怒りを表したのだと思われます。
A君が気になるのは,裏の自我が主宰する,不気味な’心の沼’の存在です。それは死の恐怖につながります。夜になると気になる幽霊は,その沼から立ち上がってくる名状し難い不気味なものが,イメージ化されたものといえるようです。
’心の沼’は死へと斜傾する心の川の流れにつながると考えると,病的な心理の理解に役立ちます。この沼の首座にあるものを裏の自我と呼ぶことは,同様に人間の心を理解する上で有意味です。
表の自我を彩る感情が生気感であるとすれば,裏の自我を彩るそれは怒りです。
たびたび述べてきたように,人の誕生は自我の誕生です。人は自我に拠って存在可能となるといえます。
誕生以前の世界を,自我に拠る人間が遠望するかぎり,全または無に見えると思います。そして自我に拠るかぎり,世界は生と死に二分されて現前します。自我は世界を二分法で捉えるのが特徴です。生と死をはじめ,全と無,自己と他者,男と女,条理と不条理,愛と憎しみなどなどというように。
自我の誕生によって生の方向が目指され,それは即座に死の方向が打ち出される必然の下に人はあります。このように心の川には,対立し,相互に相容れることなく矛盾し合うふた筋の流れができます。一つは生へと向かう流れで,一つは死へと向かう流れということになりますが,この川筋ができる心の形成の歴史の発端に母親が大きく関わっています。つまり甘える欲求を赤ん坊が満たされているかぎり,生の流れが勢いを持ちますが,それが満たされなかったかぎりで死への流れが形成されるのです。甘える欲求は生の方向での源流を形成するといえるようです。それだけにその欲求は強力なエネルギーを持っています。しかし二分法の原理の下にある人間の心には,それとは反対の流れができないわけにはいきません。それを形成するのは怒りと恐怖です。つまり心の川の死の流れがはじまる発端には,甘える欲求を上回るエネルギーを持った恐怖と怒りに竦み上がる体験があったに違いありません。それは甘える欲求を満たしてくれる母親その人によって惹き起こされるのです。それはつまり,見捨てられる恐怖です。この根源的な恐怖は,赤ん坊が全生命を要求することが,人間的な現実の原則に反することであるのを教える意味を持ちます。そして恐怖の陰にある怒りを抑圧することに伴って,死へと向かう川筋が形成されることになります。
このように人が生きる方向で可能性を切り開き,自己形成をはかろうとすれば,死へと向かう心の川の流路の存在を必要としているという甚だしい矛盾をも受け入れていかなければなりません。そしてその相容れ難い矛盾をもたらす源流のところに,原初の他者である母親が介在しています。それは心を形成していく上で,複雑に矛盾するものを抱え込む理由になり,悩み多き人生を作り出す理由となるものでもあります。人は単に優しくあることはできません。人が人と関わることによって,原初の恐怖と怒りとが刺激されるのは,いかなる場合でもむしろ避け難い話です。絶えざる矛盾,絶えざる葛藤を乗り越え,乗り越えしながらでなければ,人は人を深く愛することはできません。
心の病理的な諸現象は,表の自我の衰弱に伴ってのことであるのは論を待ちません。それは自我が白い子を護り切れなかった度合いの多寡と関係があり,死へと斜傾する心の川の流れが勢いを増していることを意味するでしょう。そしてついに表の自我が主導権を裏の自我に譲り渡すにいたったときに,心の病理現象が問題になります。その病理性は,社会性や精神性に欠けるものがある心の状況と同義です。いずれにしても人は,生きているかぎり表の自我に拠ります。裏の自我はこれを無視することはできません。社会性と精神性とを欠いている裏の自我は,表の自我を傀儡化して社会性の体裁を保つことになるといえます。
(犯罪者の心理となると,「人の衣装をまとった獣」といわれるように,裏の自我が積極的に表の自我を操っている様相と考えられます。そのようにして社会をあざむき,自己の欲得に積極的にかまける心の態勢が作り出されているのが,犯罪者の心理的特性といえるだろうと思います)
A君は,先生に,「鼻水が出たぐらいで休む子はいない」といわれて傷つきました。翌日,学校を休んだのはその証拠のようなものです。先生のこの言葉に,A君は怒りを覚えたに違いありません。その怒りは先生とA君自身とに向かったと思われます。先生に対しては,A君にも説明がつかない’本当の理由’を察知してもらえなかったためです。それは母親に分かって欲しいのに分かってもらえなかった,甘えたい欲求の存在がかつてあっただろうことをも暗示しています。また,答えにならない答えをした自分自身にも腹を立てたと考えて間違いはないでしょう。
結局,怒りは無力な自我に引き受けられることがなく,抑圧されたのです。そして自我によってまたしても引き受けられることがなかった怒り(それは,はるか昔,見捨てられる恐怖体験によって抑圧された怒りに淵源を持つものでしょう)が,改めて怒りの沼を刺激して,A君を押し流そうとしたのです。学校に行くというのは,生きる方向での心の川の流れに乗らなければなりませんが,逆の動きをする川に引きずられたといえるのです。
怒りをどう扱うかは,すこぶる重要な問題です。怒りは,いわば黒い子たちのものなので,自我の介入がなく表に出れば,つまり憤怒ということになります。対人関係を破壊する動きになります。抑圧すれば怒りの川の勢いをつけることになり,意気消沈することになります。
自我が介入(引き受ける)するのでなければ,いずれにしても自己を窮地に追いやることになります。自我が介入するということは,いうならば黒い子たちを代弁する意味を持ちます。つまり,その存在を自我が認めたことを意味します。それは自我がしなければならない仕事なのです。そして自我が仕事をするかぎり,心は健全であるといえます。
更にいえば,怒れる川が勢いを増している心の状況では,自我は,その流れの始原にある見捨てられる恐怖(と潜在する怒り)に怯えた記憶を蘇えさせたように,凝結してしまう傾向を持つようです。
A君に先んじて受診したのは母親でした。母親の両親の問題があり,そのころ母親は怒りに駆られる人でした。そのあおりで夫婦喧嘩がしばしばあったといいます。恐らく,幼い時代のA君は恐怖心に怯えていました。満足感と安心感が不足していたのに違いありません。それは甘えを通じた母と子の関係が望ましいものではなかったことを意味するでしょう。
表の自我は生を志向し,裏の自我は死を志向すると先に述べました。
A君についてこのことを見てみると,赤ちゃん時代の母との関係が第一に問題になります。持って生まれた気質はともかく,養育環境としては母親がすべての時期がしばらくつづきます。それは赤ちゃんといえども,人間として生を受けたからには,死の問題に無縁であり得ないということに関係します。
先にも述べたように,人間は自我に拠って存在可能であり,その自我は世界を二分割して捉える特徴を持っています。その淵源は,人間の存在以前の世界を,自我は生と死との二つに分割して現前化するところにあるように思われます。
赤ん坊は人間として生を受けたときに,死を垣間見て怯える者でもあらざるを得ません。そのために赤ん坊は,母親に全を要求するのです(生誕以前の状態への回帰の要求ともいえるのでしょう)。それは母親を支配しようとするのとおなじ意味を持ちます。赤ん坊は怒りくるって泣き叫び,母親に要求を呑ませようとすると思われます。そうすることによって,万全の安心を手に入れようとするのです。安心がなければ満足はありません。満足感と安心感とは一体のものです。
しかし母親は全なるものではありません。母親には赤ん坊にそれを教える役目もあります。それは無意識的にであれ,死の存在を教える意味を潜ませることになるのです。
意識的には母親は,赤ん坊に死の存在を理解させようなどとは夢にも思わないでしょう。一所懸命に赤ん坊に愛情を注ぎ,可能なかぎり赤ん坊を怯えから護り切りたいと願うと思います。しかし,母親は全なる存在であるのを教えるしかありません。それは母親が,赤ん坊に死の存在を教えないわけにはいかないのとおなじ意味になるのです。そのことは,むしろ母親にも意識されていないはずです。母親自身もそのようなおぞましいものは見たくもないのです。しかし,いわば心の自然のプロセスとして,思わずそれを教えてしまうのです。それは避けるわけにはいかないものであり,避けてはならないものでもあります。
死の存在を赤ん坊に教えるのは,母親の怒りによってです。全的な存在ならぬ母親が,赤ん坊に対してといえども,怒りを一掃してしまうことは不可能です。そしてそういうあるときに,全を要求する赤ん坊の激しい怒りが,母親の顔に投影されて跳ね返ってくることがあるだろうと想像されます。それを感じたときに赤ん坊は,死を垣間見ることになるだろうと思われます。そういう折に,母親の顔が悪鬼の表情に見えるのかもしれません。実際は悪鬼のように怒っているのは赤ん坊の方なのですが,母親の顔にそれが投影されるのです。赤ん坊が見捨てられる恐怖を持つのは,そのときだろうと推測されます。そうなると怒りが恐怖に変わり,今度は母親を怒らせないように要求を自制するようになるでしょう。全生命というものはない,従って生きることには死が含まれていると身をもって知ることはどうしても必要なのです。そのことは人間が人間の現実世界を生きる上では,どうしても受け入れなければならないのです。しかしこの恐怖の度合いが強いと,必要以上に甘えることを断念してしまうようになるかもしれません。恐怖の度が強ければ,幼い心の自我は母親を怒らせないために,生まれてくる諸欲求を抑圧する傾向を強めることになるでしょう。それはいうならば心の負債を大きすぎるものにしてしまう理由になります。誰であれ心の成長過程でこの意味での負債を負います。それは程度の差はあっても避けることはできません。そしてその心の負債を自我が返済していくことが,いわば人生の目標であるとさえいえます。そのようにして人は成長していくのです。しかし負った負債が甚だしいものであれば,よほど強靭な自我でなければ,返済は困難になります。返済が困難であるということは,その重荷に押しつぶされる可能性が高まるということでもあります。そのままでは自我が無力になり,生命感情を豊かに育てていく上で大きな困難を持つことになるだろうと推測されるのです。
甘えがどの程度満たされているかは,母親との関係の良し悪しを占う道標になります。そしてその後の人間関係をも占う道標となります。甘えられない母親との関係では,自分は愛されていない,嫌われている,価値がないといった考えに囚われることになり,それは自己愛が傷ついていることを意味します。そして他者についても疑い深くなり,愛情を持ち難くなると懸念されます。
幼児期には活発に欲求が生まれてきます。それは内在する主体が送り出してくる,いわば神の子と考えることができます。自我はそれを護る使命を帯びています。それらのことは自然のものとして起こるでしょう。しかし幼い自我が諸欲求を護るためには母親の協力を欠かせません。すべては乳幼児と母親との関係の基調である甘えに還元されるのです。つまり甘えが満たされている関係であれば,幼い子の心に生じたさまざまな欲求は,おおむね自我に受け入れられ,護られるでしょうが,満たされ方に問題があれば自我によって抑圧される傾向が強くなりがちでしょう。
いたずらなり何なり,幼い子が何かをするときは,母親に認めてほしい心が付随します。それは甘えに他なりません。自我が発達した年齢であれば,何らかの行為を楽しみ,評価するのは自己自身でなければなりませんが,自我が未発達な幼児としては,母なる他者によって支えてもらう必要があるのです。
このようにして,護られなかった神の子は,自我に生気感をもたらすはずだったエネルギーを,怒りのそれに換えて無意識の世界のものとなります。そういう影の分身たちが,無意識界に不気味な沼のようなものとなって勢力を張ります。それは自我によって受け入れを拒否されたものであり,従って生の世界のものとしては認められなかったものたちです。つまりそれらは死を志向する勢力です。そして生を志向する心の首座にあるものを表の自我と呼び,死を志向する心の首座にあるものを裏の自我と呼ぶことが,心の病理的現象を理解する上で有益です。
裏の自我は,既に証明されている脳中枢にある怒りの座に,一つの根拠を持つだろうと推測されます。
A君は,他人に対して過敏です。人と争うのを好まず,誰とでも仲良くしていたいと思っています。母親によれば,友達は男女を問わず大勢いるそうです。しかしA君は,’真の友達’はいないと思っているようです。
A君が望む’真の友達’とは,「揺るぎのない心の支えになってくれる友人」,といったもののように思われます。そのような友人に出会える可能性はあるでしょうか?ない,というのが私の答えです。
A君がもとめる’真の友人’というのは,恐らく’全’をもとめる乳幼児の心に通じるものです。つまり乳幼児が,母親に対して持つ支配欲求に通じる心性といってよいだろうと思います。その心性は乳幼児に特有のものです。言葉を換えれば,心の成長過程で克服していなければならない心性です。この支配欲求は,闇(死)への怯えを一掃したいという願いです。母親にはそれを可能とする力があるという幻想を,赤ん坊は持っているようです。つまり赤ん坊にとって,母親は’全なる者’なのです。誕生したばかりの自我は,生を引き受けるべきものですが,生(光)の裏面である闇(死)に過敏に脅かされると想像されます。赤ん坊の萌芽でしかない自我は,その脅威によって破壊されかねないので,防護装置として万能感が備えられていると想定されます。それは自我に拠って世界が二つに割れたこと(生の世界と死の世界),自我の誕生以前の世界が’全’であることを暗示しています。万能感とは,全的な存在への幻想であるということができます。
ところで母親と一体の関係にある赤ん坊には,自分に’全なる力’があるのと,母親に’全なる力’があるのと区別がつきません。赤ん坊に,自分が’全なる力の持ち主である’という大安心を保証してくれるのは,’全なる力’を持っているはずの母親です。そして一方では,闇に絶えず脅かされることによって,母親が自分を護る気がないのではないかという猜疑心に囚われると思われます。赤ん坊は怒りをこめて,母親を支配しようとすると想像されます。全面的な支配を欲するのは,それが可能であるとする幻想があるからに違いありません。そして全的な大安心を提供する力があると幻想するからこそ,’未だ与えられていない’ことに激しい怒りを持つのです。そしてまたそこには,相手方である母親にそういう力はないのかもしれないという予感もどこかしら働いているに違いありません。あるに違いない,あるはずだという要求は,既に半分は疑惑なのです。疑惑がなければ要求は起こりません。そしてその疑惑の一部は,(母親が)持っているはずなのにくれようとしないというものでもあるだろうと思われます。それは自分が大切に扱われていない,愛されていないということに直結します。生死がかかっているこの要求は,ほどほどのものでは満足されることはありません。ですからきょうだいの中でも,自分が第一等でなければならないのです。そして,それは相手方(母親)が全なるものではないという恐怖に満ちた予感と,一体感の破綻の予感とに脅かされてのことのようにも思われます。
いずれにしても相手(母親)を完璧に支配しないかぎり,真の安心はありません。そしてその大安心幻想があるかぎり,小安心に甘んじることができません。その幻想の下では,全部でなければ無に等しいのです。つまり人間は小安心に甘んじることができなければ,無の感覚に脅やかされることから逃れることができません。
これらの恐怖は,母子分離の恐怖でもあります。
小安心に甘んじることが出来るようになるには,大安心幻想を捨て去ることが不可欠です。それは母親が全的な存在ではないことを受け入れることによって可能となります。その意味のある諦めは,見捨てられる恐怖をうまく克服できたときに生じるでしょう。この根源的な恐怖は,人間が人間であろうとするときの最初で最大の関門です。それを克服できれば,母親を現実的なものとして受け入れることができます。つまり,互いに小安心に甘んじなければならない頼りない身分であること,従って互いに助け合うことが必要である(信頼と愛情とによって)こと,大安心はないと知ることによって,自分で自分に小安心を提供しつづけることが求められていること,母親と自分とは支配ー被支配によって全的に一体化するべきものではなく,相互に分離ー独立した存在であること,従ってそれぞれが人格という個的な存在であり,それぞれに自由であること,などなどが自然のものとして受け入れられることになります。
そして一方,この恐怖をうまく克服できなかったとすると,母親が永遠に全なる人であるとする幻想から逃れることができません。その幻想に依拠することによってのみ存在可能なので,もらえるはずの大安心を当てにして母親にしがみつくことになります。それは,当然,母親を信頼している姿ではありません。信頼しきれない姿です。その不信の根源にあるのは,見捨てられる恐怖です。
大安心を諦めきれないでいる心と,小安心に甘んじることができている心とを分けるのは,おそらく見捨てられる恐怖を幼い自我がどう扱ったかの問題です。前者の自我はこの恐怖を克服する術がなく,一途に抑圧したと仮定されます。そのとき母親は死に匹敵する巨大な恐怖をもたらすものです。その恐怖はそれに匹敵する怒りの存在(当然与えられるはずである大安心を与えられない怒り)に関連するでしょう。自分の怒りの巨大さに恐怖を持つともいえるだろうと思います。そしてその怒りの巨大さは,一対の相手である母親の怒りと区別がつかないのです。それらの恐怖と怒りは,無力な自我が引き受けられるものではないときに,強力にそれらを抑圧して母親の自我に拝跪するのです。そのようにして,巨大な恐怖をもたらすものの怒りを鎮めようとするのです。
大安心幻想は乳幼児のものです。長じてなおこの幻想の支配を受けている自我は,個の確立が不確かであることになります。その幼児心性の下では,勝手な行動は取っても,自由に行動することは困難になります。そもそも自由に生きるという意味が感覚的に分からないという人が珍しくありません。この幼児心性の下では,他者の自由は脅威でありつづけるのです。別ないい方をすると,どうしてみても闇の脅威におびやかされるのです。
自由の精神とは,自分自身の自由のみならず,あれこれの他者の存在をそれぞれの個として,それぞれに自由であると尊重することができているときに可能です。それは大安心幻想をあきらめ,小安心を受け入れることができている個性に対する別な呼び方といえます。
A君が友達たちの些細な悪意に脅威を覚えるのは,友達の自由を尊重することができないためといえます。人の自由を’真に尊重’できないかぎり,人を’真に信用する’ことはできないはずです。母親をさえ信用できません。というよりは母親との関係で個の確立が不確かであること,それは同時に母親の自由を尊重することができていないことに,この問題の核心があります。
母親が自分を捨てるとは考えられなくても,不慮の事故に遭わない保証はありません。病気で命を落とすことになる可能性を排除できません。それらの不安を一掃するためには,赤ん坊のように母親と一体化するしかありません。否,赤ん坊もこの不安から免れることはできません。赤ん坊以前,自我に拠る世界が現出する以前の世界のものになるしかありません。それは絶望して死を望む心に他なりません。
見捨てられる恐怖の克服に失敗して,完璧な他者,全なる他者を求める大安心幻想の支配を受けているかぎり,心の平穏は困難です。
A君の’すべての人と仲良くしていたい’という願いには,このような心理的な意味が隠れていると思われます。だからA君が心の平穏を獲得するためには,友達たちの個と自由とを容認することができなければなりません。それは,死の存在を容認できることとおなじ意味になると思います。つまり生の裏面は死であり,対立し相容れない矛盾である両者を共に許容できなければなりません。死という現実問題を受け入れることができるときに,ようやく生と死との矛盾を生きる力を得るのです。そのときに,相容れない矛盾を止揚する心のダイナミズムが生まれてくるのです。
人間の意識は有限のものです。しかし人間は無限性を生きる存在です。仮に有限性を生きるのが人間であるとすると,生きる意味はほとんど失われるでしょう。ある有限の時空にいたって人生が,あるいは自己の形成が,完成し,自足するという事態は想像できません。
無限性を生きるというのは,生と死という相容れることのない永遠の対立が,姿をさまざまに変えて現れ,そして超克されていく意識のダイナミズムを生きるということです。それは生があるかぎり死があり,それが対立し合うかぎり,無限定に上昇しつづけることが可能な意識のダイナミズムといえます。
ここにこそ人間精神の自由の実態があり,それは幾分か比喩をまじえていえば,人間精神が無限の時空間を縦横に飛翔する姿であるといえます。
精神の自由の問題は,次のように考えることが可能です。
赤ん坊の生みの親は,いうならば二人います。
一人はいうまでもなく母親です。そして’もう一人’は,人間に自我を授ける力を持ったものです。それは人間以上の存在と考えないわけにはいかないものです。自我を授与した人間の上位に立つものは,以下のような意向を示していると考えることができます。
「自我に拠って思うように生きてみよ」と。
そしてこの上位者は心の無意識界に鎮座(内在する主体)して,沈黙のうちに自我の活躍ぶりを注視していると考えられます。
一方,母親はこれに対して,「お母さんを安心させるような子になりなさい」という暗黙のメッセージをもって育児に当たるだろうと思います。そしてそれは愛情といえる面と,母親の私心といえる面とがあって当然でしょう。
自我は生に奉仕するものですが,赤ん坊が生まれて間もない早期の段階では,母なる他者の絶対の補佐を必要とします。自我の生誕は光の世界の幕開けです。しかし,赤ん坊の未熟な自我は自ら活動する力を持ちません。母親の補佐(愛情)を受けて,自我の原基が刺激され,徐々に自ら光を発する力をつけていくのです。このような光の黎明期(乳児期)では,闇(死)の存在に殊更に脅かされると思われます。自我が自律機能を活発化させて人生を切り開く力を得るまでは,母親の愛情によって保護されるのでなければ,自我は立ちすくみ,いわば凍りついてしまうことでしょう。
自我は自律機能によって生を志向しますが,抑圧機能によって自律性を阻害します。前者は主体の命に基づこうとする機能であり,後者は他者の意向を重んじようとするときに働く機能といえます。抑圧機能は他者を前提としたものです。つまり自我には他者への配慮が構造化されています。
自我がそれなりに成熟して自律機能が活動しはじめてからも,いうならば無化される脅威に対抗するために,自我は他者との関係を不可欠なものとしています。自我の機構には,他者のイメージを生み出す機能が内属していると考えられるのです。そのために,他者は客観的に外部に存在するだけではなく,内なる他者として自己の内部の無意識界にも存在しています。
ですから他者との関係を必須のものとしている自我には,抑圧機能は,(自己を護るために)欠かせないものです。それは生死を分ける問題に関わるものでもあるので,自律機能以上に重要ともいえます。しかし自律機能が不十分であれば,自己の好ましい育成は望めないことになります。自己は他者に見放されても,自己自身に見放されても立ち行かなくなるという難しい問題をかかえているのです。
自己の自己自身との関係が好ましい形になっていれば,それは主体との関係が良好ということになります。そのことは誰もが目指すべき理想でしょう。そしてその関係を混乱させる元凶は,他者の介入,他者への行き過ぎた配慮です。それは主体との関係を中心にしてみると,巧まざる自我の堕落といえるものがあります。幼い自我にそのような要求をするのは無意味ですけれど,心の内部の事情を主体の観点からするとそのような意味になるように思われます。それは自己形成の上で犯罪的ともいえる結果をもたらしかねないのです。心の内部の法廷で有罪判決を受けたかのように,人生が地獄化することは決して珍しくはありません。
自我は,あちらを立てればこちらが立たずという難しい舵取りをしなければなりません。生誕につづく原初の段階では,全面的な他者(母親)の補佐を必要としているといういきさつから,自我が不始末を起こす状況的素地は十分過ぎるほどにあるのです。それは避けることができない人間の宿命であるといえます。そしてその幼い自我の避けられない不始末によって,’心の沼’が生み出されるのです。
’心の沼’は,,破壊的な力を蓄えた影の分身たちが,いうならば跳梁跋扈する闇の世界です。自我に脅威を与えるほどに,怒りを伴う破壊的な力を蓄えてしまっている’心の沼’がそのままに放置されていれば,ストレスに大変弱くなります。場合によっては,さまざまに由々しい人間の不幸,悲惨を招き込む,心的事態に陥ることにもなります。
自然的な自我が,内在する主体との接触を妨げられ,節度が曲げられるのは他者の介入によってです。
主体との関係を見失うのは,他者の介入による自我の不始末といえる側面があります。しかし圧倒的な力を持つ闇(死,無限,無であるものに繋がるものです)に包囲されている自我は,あまりに頼りなげな存在です。たちどころに無の闇に飲み込まれ,無化されてしまいそうな脅威の前に,自我は他者の力を当てにするしかありません。このような事情があるので,人間を頽落させるのはしばしば人間自身であるという無残な悲喜劇が,人生のここかしこに見られるのです。
自我が抱える難題は以上のようですが,総括的にいえば次のような問題があります。
自我に拠って生の世界が始まり,それは同時に死の世界の始まりであると繰り返し述べました。それは,自我の使命が,「死を課題化せよ。死に向って希望の光を掲げつづけよ」という難解極まりないものであることを意味します。人間の常識では理解不能の課題を,自我は負っています。禅問答の極みのような話です。
患者さんはしばしば,「何のために生きていなければならないのか?何故死んではいけないのか」という問いを持ちます。
それに対する答えは,「人間は自我に拠る存在だから。自我は引き受けるのが使命だから」ということになるのでしょうが,難問であることには変わりありません。
自我の使命は人生を切り開くことであり,自己を形成することであり,生きていくことです。ですから死は自我の終焉とともにあります。死によって生が終わるという意味では生は有限です。しかし生は単純に生ではなく,絶えず死をはらんでいます。
失敗の危険のない試みはありません。必ず成功すると決まっている試みはありません。成功は自我の勝利,つまり生の世界での営為です。失敗は自我の不始末,つまり死の世界への斜傾ということになります。
大冒険は死の危険と隣り合わせの行為です。スポーツ選手の新記録は,身体を極限まで鍛え上げる(身体を壊しかねない)ことなしには得られません。芸術作品は心の闇の表現です。科学者の大発見は失敗すれば一切が瓦礫化する怖れと共にあります。
死を賭けない成功は大したものではありません。そして大成功があっても,すぐに虚無の影が忍び寄ってきます。
精神の充実は自我によってもたらされますが,それは死(無)による意識の無化作用を一時的に沈黙させることができたに過ぎないともいえるでしょう。それは永続するものではなく,充実の獲得と共にすぐさま無の無化作用に脅かされるので,自我はひと休みしたあとは次の仕事に取り掛からなければなりません。
癌に侵されるなど死期の迫った人については,先に述べた「死に向かって希望の光を掲げよ」という主題はどうなるでしょうか。しだいに優勢になっていく死の無化作用は,自我の回収作業ともいえ,自我自身は従容として身を任せるしかありません。それは最終的な生と死の合一に向かっての回収作業といえるのでしょう。
臨終に当たって,「これでいい,これでいい・・・」という言葉を残した偉人の逸話が伝えられています。「これでいい」かどうかの判定者は誰かという問題があります。仮につぶやいた人自身であるとすると,単なる自己満足の域を出ず,強がりと区別がつけられません。しかし内在する主体の支持にもとづくものであれば,それは人生の達成というものに等しいかもしれません。そしてそれは自我の回収作業に携わる主体でもあるかもしれません。
いずれにしても死は人間の手に負えるものではありません。そこから先は,人間の上位者に任せるしかないというのは自明のことです。死刑,自死,安楽死などの問題の根本にはこのことがあります。
人間が存在する根拠は人間自身にはありません。つまり人間が最上位者ではないのが明らかである以上は,最上位者の存在を認めないわけにはいかないでしょう。自我がその者の存在に拝跪するのは当然のことです。その姿勢が,つまり,引き受ける精神です。謙遜は引き受ける精神の別称といえます。
自我に拠らない人間の上位者が,自我に拠る人間に向けて立てた問いが,人間の眼には先に上げた究極の矛盾のようなものに映るといえるのでしょう。
また,この解き得ない矛盾のような問いを負うのでなければ,人生はひどく詰まらないものになるでしょう。解き得ない矛盾に見えるからこそ,人に与えられた可能性は無限なのです。矛盾し合う二つのものを止揚しつづけることが未来を開くのです。それは生きているかぎり終わりのない展開です。そういうものを想像するのも困難ですけれど,仮に一切が有限の世界であるとすると,人生は永遠の退屈になるしかありません。
自我は自立を理念としています。しかし自我は内在する主体に絶対的に依存しています。主体が自然の属性を色濃く持っているのに対して,自我は人間を人間たらしめるものであり,人間が自然から乖離され,独自の存在形式を許された象徴ともいえるものです。従って自我の自律性は,自己を保ち,世界を切り開くために欠かすことができないものですが,それが健全に機能するのは,主体との依存関係が良好に保たれていることがあってのことです。
また,自己は他者とのあいだでも絶対的な依存関係にあります。それぞれの自己は,現実界の他者を排除して孤独に生きることは可能ですが,心の構造には内なる他者が構成要件の一つとして存在しています。そうでなければ,他者は異星人のように不可解な存在であることになるでしょう。内なる他者が心の構造に生まれつき組み込まれているので,他者を外なる自己として,異星人に対してであれば感じないであろう親しみの情をもって容認し,理解することができるのです。
また,それぞれの自己は,そのときどきの対象との関係において存在しています。その関係の連鎖の先には,他者が介在してきます。
要するに自我に拠る自己は自立を目指しますが,それはなにものかとの依存関係においてであるというのが,人間存在の特徴です。人は,本質的に依存的な存在です。
依存には好はましいものと好ましくないものとがあります。好ましい依存は,主体との関係が良好であるというところに行きつきます。それがあれば,いわば自己の軸は心の中心を貫くことになり,いってみればダルマ的な存在になることができます。つまり,何かのストレスに負けて心がグラリと傾いても,速やかに心の姿勢を回復させることができます。そうであれば他者との関係も自由になります。主体との関係がしっかりしていれば,孤独であることが脅威にはならないからです。
好ましくない依存とは,逆に主体との関係が危うい場合です。先の比喩に従えば,心の軸が中心を大きく外していること,換言すると,(主に)母親への隠れた依存が無視し難いことを表しています。それに伴って’心の沼’が強いエネルギーを抱えていることを表しています。
自我の抑圧機能が過度に働けば,自律機能を歪めることになるので,’心の沼’が勢力を強めることになります。そうであれば他者への依存が過度になるか,逆に拒否的になるかということになるでしょう。他者にも,自己にも信頼がうすくなります。孤独であることに耐え難いか,シェルターに避難するかのような孤独になるか,いずれにしても他者に対して自由になれません。
そもそもが,表の自我による人格は精神性と社会性とを備えています。これに対立する形である裏の自我は死を志向します。表と裏との相対関係で前者が劣勢になれば,それに相応して,虚無感に囚われ,あるいは非社会的ないしは反社会的という性格が色濃くならざるを得ないといえます。
過食症は好ましくない依存の一つです。つまり裏の自我に支配された表の自我の依存的な営為です。こういう問題が起こるのは,人格形成の最早期に,情緒的な満足が得られなかった何らかの事情があったためではないかと推測されます。想起するのは不可能であるほどの人生の初期に何があったかは分からないのですが,情緒的な満足が得られなかった理由は,主に養育の中心である母親との関係に求められるだろうと考えるのが自然というものです。情緒的な満足は,自我の根が無意識という大地にしっかりと下りていない乳児には,欠かしてはならない大切な肥料です。それを求めるのは本能的なものと思われますが,一方で乳幼児には見捨てられる恐怖というものがあります。これは他者への絶対的な依存を必要とするかぎり,生き死ににかかわるもので,根源的といえるほどに強力なものだろうと思われます。
生まれたばかりの赤ん坊は,なにはともあれ人間の誕生です。その意味は,これからは自分の力で生きていきなさいということです。赤ん坊は極度に感覚的な存在だろうと思われますが,その意味は分からなくても感覚でそれを捉えるのではないでしょうか。母親のお腹の中にいるときの自然的な状況から,あるときいきなりお産という形でまったく異なる環境に放り出された驚愕は(大人の感覚での類推になりますが)並大抵のものではないだろうと思われ,その恐怖は甚だしいものだろうと推測されます。その恐怖を和らげるお守りが万能感と呼ばれているものです。それは母親のお腹の中にいたときの安全感覚を,保障しようというものでしょう。
万能感と呼ばれているものは,E・ノイマンが次のように述べていることに通じるものがあると思います。
「人類の生まれつつある自我意識の最初の何段階かは,ウロポロスの支配下にある。これは自我意識の幼児期であり,もはや胎児ではなく,すでに独自の存在となってはいるが,なお円の中にいて,まだ円から出ておらず,ようやく円から自らを区別しはじめた段階である。・・・世界は周りを取り囲んでいるものとして体験され,人間はその中でとぎれとぎれに,瞬間的にのみ自らを自らとして体験する。・・・幼児の自我が,ほんの一瞬無意識の薄明の中から小島のように浮かび上がったかと思うと再び無意識の中に沈んでしまうように・・・偉大な母なる自然に守られ,抱かれ,支えられ,あやしてもらい,そして善きにつけ悪しきにつけ彼女に身をまかせきっている。
・・・世界が保護し,養うのであって,彼・人間が意志し,行為することはほんの稀にしかない。無為,無意識の中に抱かれていること,すなわち必要なものがすべて偉大な養母(原母)から絶えずこんこんと湧き出してくるような尽きざる薄明の世界,これこそ原初の’至福’状態なのである。・・・ウロボロス近親相姦における一体化は心地よさと愛を特徴とするが,これは能動的なものではなく,むしろ溶け込み吸い込まれようとする試みである。・・・快楽の海と愛による死の中で消滅することである。・・・死は・・・すなわち母との一体化というウロボロス近親相姦の特徴をおびている。・・・人間の意識が自らをこの原深淵の子とみなすのは正しい。・・・そしてこの意識は毎晩眠りの中で太陽と共に死んで,母なる無意識の深淵へと沈み,帰っていく。そして翌朝再生し,昼の運行を新たに始めるのである]
胎児の段階と赤ん坊として生まれる段階とのあいだの落差には甚だしいものがあり,その激しさを和らげる何らかの機構がなければ生存に耐えないだろうと推測されます。その機構が万能感といわれるものであり,具体的にはE.ノイマンが記述するようなことではないかと思われます。
この万能感を具体的に保証する役割を担うのが母親です。しかしいうまでもなく母親は,ほどほどの満足をしか与えることができません。赤ん坊は,万能欲求をしばしば裏切られ,失望する宿命の下にあります。「この人は,本当に凄い力を持っているのだろうか」とか,「この人は凄い力を持っているのに,なぜ私にそれを与えてくれないのだろう」といった不信,疑惑に,怒りと共に囚われることでしょう。それらが見捨てられる恐怖の母体となるのだと想像されます。
そういう折も折,過敏な赤ん坊が,何らかの御し難い恐怖に捉えられるということがあれば,情緒的な満足を求める生きる本能(自律機能を育てるために重要です)よりは,捨てられることの死の恐怖の方に圧倒されるのではないかと思われます。赤ん坊は,いわば沈黙して,母親の自我にしがみつくことで,危機を回避しようとするのではないかと考えられます。母親の自我の傀儡となることで,見捨てられる恐怖を鎮めようとするのです。それに伴って情緒的な満足は抑圧されることになります。
これらのことは,あらゆる乳児に起こる心的過程だろうと思います。自然ならざる人間は,このようにして他者の介入を必要とし,それによって,程度の差はあれ自然性を歪められることになるのです。
あまりに幼いときは母親は絶対者ですから,乳幼児たちは服従する以外にありませんが,成長するにつれ,しだいに自己主張がはじまるのが自然です。それは親子の関係で蓄積されてきた,いうならば歪みエネルギーが,いずれどこかで放出されずには置かないという意味合いを持つ自己解放の動きです。それによって親子関係の是正,修復が目指されるのです。
これまでに述べたことから,人間の誕生にはいわば’二人の親’が関わっていると考えることが,精神構造を理解する上で有用です。第一の親は,自我を授ける力を持った’人間の上位にあるもの’です。そして第二の親は,ふつうの意味での母親です。このような考えが可能であるという前提に立てば,真の親は前者であるのはいうまでもなく,後者はいわば前者から仮託されていると考えることが可能です。
前者は,「自我に拠って自由に自己を導くように」という意向を示し,内在する主体として,無意識的な心の世界で沈黙のうちに自我の営みを見守っていると考えられます。
後者は,二つに分離,対立する特徴を持つ自我に拠るものの宿命として,二心を禁じ得ません。つまり,立派に成長してほしいという当然の願いを母親は持ったとして,そこにはそれが赤ん坊に対する愛情である一方,母親自身を安心させて助けるようにという私心も入らないわけにはいかないのです。
前者が沈黙のうちに見守るとすれば,後者は良くも悪くも有形無形の口出しをすると考えてよいと思います。無形の口出しというのは,超自我の関与ということになるでしょう。
先にも述べましたが,自我領域にはいわば三つの山(立場)があります。
中央に位置するべきものが自我です。この自我と重要な他者(性格形成の初期ほど重要な意味を持ちますので,この重要な他者とはほとんど母親であるといえます)との関係で,必然的に派生されてくるのが,一つには超自我の山であり,一つには黒い子たちの山ということになります。そして無意識界にある沈黙する主体の沈黙する関与があります。
(過度によい子と,非社会的,ないしは反社会的な行動を取る子とは,対照的な心の病理現象と考えることができます。前者は無力な自我が超自我に絶対的に服従する心的構造下にあると考えられます。一方,後者の自我も無力であるのは前者とおなじですが,違うのは超自我もまた不在であるかのように未発達でいるらしいということです。そして後者の自我は黒い子たちの支配を受けていると考えることができます。
このことは,両者の自我が共に主体の意向に即することができないままでいること,そのために自己形成が病的なレベルになっていることを示しており,前者の超自我がいびつに大きなエネルギーを持つに至っていること,後者では黒い子たちがいびつに大きなエネルギー持ってしまっていることを示しているように思われます。これらの三つの山のどれが勢力を持っているかが,人格構造の基本的枠組みを決定的にしているといえるでしょう)
前者の命に沿うときに自我の自律機能が機軸になり,後者の命に沿うときに自我の抑圧機能が作動することになります。
赤ん坊にとっては母親はいわば神に匹敵します。その神なる母親は,赤ん坊には,自分に向けられた愛情に関しては何よりも心強く,しかし母親の私心に関してはそむくことの許されない恐るべき者といえます。
そのような事情から,幼い子の自己形成は,主体による第一の命題(自由に生きる)から大いに遠ざけられることにならざるを得ません。それぞれの心は,大いに歪まされながら自己形成が進行する宿命の下にある,それが人間である,といえます。
Bさんは50代の主婦です。近くに80代の母親,妹,二児の親である別居中の一人娘がそれぞれ住んでおります。Bさんは癌に侵されている夫と二人で暮らしています。酒好きの夫はあまり家庭を顧みなかったようで,夫婦の関係は以前からうまくいっているとはいえません。夫が勤めていた会社は倒産しました。取締役であったために保証金を差し出してあり,それが返ってこない上に,当然ということになりますが退職金はありません。夫への不満が高い一方で,夫は病気のためもありかなりわがままで,愚痴も多く,その相手をすることは容易ではないようです。
長女は十代から我がままのし放題というふうでした。実はそもそもは,当時十代だったこの長女が私のところに通院しており,途中から母親も通院することになったいきさつがあります。
長女が夫と別居生活に入った当時は,Bさんは,母親(父親は既に他界しています)が暮らす実家の敷地にあった小さな古屋に住んでおりました。
Bさんは,最近にいたるまで,母親のいいなりになってきたようです。母親は世間体を重んじる人のようで,Bさんが自分の家を持っていないこと,婿が失職していること,貧困であること,長く通院をして薬を飲んでいること,長女が婚家から帰ってきていることなど,ことごとく気に入らないようです。次女も母親のいいなりのようで,母親の命を受けて何かと言い募ります。そしてしばしば母親自身が罵倒します。Bさんが顔を出さないからといって腹を立て,夕方に雨戸を閉めに行くと,余計なことをするなといって怒ります。夕食のおかずを持っていっても受け取ってくれず,持ち帰ることもしばしばです。
家を出て行けと何度もいわれました。しかしBさんは母親の側を離れるのが不安でした。自分が困るというのではなく,母親が心配だと思えたのです。それでもようやく母親と別れて暮らす決心をしました。夫がまた,そこを離れて住まいを探すことに反対しつづけていたのですが,何とか説得しました。
マンションの一室に移り住んで一息ついたころ,孫達が騒ぐのがうるさいと苦情がきました。また引越しをしました。長女は当然のように一緒に住むと決めていましたが,今度は部屋が狭くてとても無理でした。それに30歳に近い年齢で,親に寄りかかって気ままに暮らそうとするのを黙認するのも問題です。強くいって,可能な援助はして,住居を別にすることになりました。そして悪態をついていた長女も,何とか仕事をする気になりました。しかし幼い孫の面倒をみてあげなければなりません。長女にとってはそれは当たり前で,感謝することでは決してありません。機嫌がわるいと,手伝いに来ている母親を激しく罵倒します。
マンションに移ってからも,相変わらず母親と,母親の手先のようになっている妹に責め立てられます。長女が婚家に帰ろうとしないのは親の責任だから,何とかしろといわれます。
Bさんは,もともと依存的な性格の上に,まったくの孤立,無縁の状況に置かれて,何度も絶望的な気持ちになり,死を待望するかのような日々でした。
そういうBさんに残されている唯一の可能性は,自分自身との関係を強化することでした。Bさんはその意味を理解しました。
敢て自由ということを意識するように心がけました。母親の,妹の,長女の,夫の,そしてBさん自身の自由をです。母親がいかに支配的な人であろうと,母親が何を考えようと,何をいおうと,さしあたりそれは母親の自由といえます。そしてその母親はBさんの自由などまるで配慮しません。Bさんは自分自身の自由を護らなければなりません。そのような甚だしい性格の母親が相手では,関係を断ち切る覚悟がなければ自由は護れません。Bさんは,非難,攻撃する妹に静かに耳を貸し,そして静かに,「縁を切ってもらって結構です」といいました。
母親との依存関係が殊更に強かったBさんにとって,「縁を切る」というのはいかに困難な課題だったか察するに余りあります。しかしBさんはぎりぎりの状況でそれを果たしたのです。
あるとき,晴れ晴れとした顔で,Bさんが次のように述べてくれました。
先日,娘の所にいたときに妹が来た(長女の叔母である妹は,Bさんの孫に会いたいのです)。Bさんが,「私はできることは精一杯やったわ。自分を褒めてあげたい気分よ」といったところ,妹は,「ほんとにその通り。よくやったよ」といっていた,と。
無論,皮肉ではなかったようです。
Bさんが試みた自分自身との関係の強化というのは,逃れようのない厳しい現実状況を,敢て引き受けることが,重要で,欠かせない出発点になります。Bさんにとっての救いは,幼い命を護りたい願いが,理屈ぬきの使命感につながったことでした。幼い子は,二度,三度と肺炎を起こして入院しました。それを助けたいという願いには,自分の命と引き換えにしてでもという切なるものが篭っていました。
現実を引き受けたことにより,それは押しつけられた(厄介な)ものが,(他でもなく)自分自身のものであるという意味に変換されることになります。押しつけられた意識感覚のままであれば,解決の主体は自分自身にあるとはいえません。現在の辛い状況は誰かのせいという被害的気分の中にいることにもなり,当てに出来ない何者かを当てにしつづけることになります。その場合は,不承不承「頑張る」しかありません。
「頑張る」ことには,他から課せられた問題に向かうという意味が込められています。
一般に何か行為をするときに,内発的な欲求と他者から課されたものとの混淆によって動機と意志が形成されると考えられます。
それは自我の自律性が内在する主体との関係において生じること,その自律性に即して主体から送られてくるエネルギーが欲動といわれるものであること,そして自我は自足態ではなく不十全な存在であるために,他者によって補完されるのが不可欠の要件であること,自律性が自我の生命線でありながら,他者の厚い協力がなければ,(無の無化作用の脅威に絶えずさらされている)有限なる自我の機能が存立の危機に瀕すること,他者の補佐は避け難く二心に基づくために不十全であり,かつ脅威ともなること,そのために自我は抑圧機能を不可欠のものとしていること,それは自律機能に対して優先的に働くものであるので,自己の形成,成長にとって阻害的であることなどなどの問題をはらみつつ形作られます。
煎じ詰めると,他者の関与のそれぞれの様態と主体との関係の健全性とが,結論的に,課されたもの(本質的に他者性です)を自我が望ましく引き受けることができているか否かに直結するといえます。このような他者とは,元々は母親を中心とした具体的な個々の誰かですが,しだい次第に抽象化されて集合的他者という体裁になります。それは超自我と呼ばれているものに相当するものです。
幼い時代に家庭環境に恵まれ,母親の安定した愛情の下に育まれた子の自我にあっては,集合的他者との関係も穏やかで,それはいわば心内における先人の知恵者との関係といった趣のものになるのではないかと思われます。しかし母(父)親が自分の二心に無自覚で,子への愛情以上に自分自身の役に立つようにという無意識的意識が優勢であれば,子に対して支配的,浸入的な育児となります。そういう関係で育まれた集合的他者は,自我に対して威嚇的,支配的なものになるだろうと思われます。
以上のような事情から,いかなる行為にも他者の眼差しが入っています。そして内発的な欲求は,内在する主体と関係があると思われます。この文脈で集合的他者が,自我に対して威圧的,支配的なものであれば,後者との関係が不確実なものである傍証といえるものでもあるので,自我は,相対的に他者の眼差しに依存的になります。つまり人の目が気になるのです。
(個々の自由は,自我の自律性が健全であるのを前提とします。しかしこの機能の危うさが他者の補完を不可欠とするので,取り分け人生の早期(自我がまだ未成熟な時代)には,他者(母親が中心になります)への怖れが抑圧機能を自律機能に優先させることになります。その度が過ぎると,他者の支配,侵入を受けるに等しいことになるので,自己の自由は危機に立たされます。つまり他者の眼が殊更に気になり,脅威になります。自己の自由が失われた極致に,諸々の妄想があります)
他者に行為の評価の基準点があるともいえるこのような心理的状況では,かぎりのない疑念に囚われざるを得ません。他者が何を考えているのか,結局のところ分からないのです。そういう状況では,生真面目な性格の人は,’完璧’であろうとする以外にないという心理状況に陥りかねません。
他者不信は,自己への不信と並行する関係にあります。
自己への信頼が揺らいでいないということは,主体との関係がうまくいっていることを意味します。そうであれば自己を支える機軸は自己自身の内部にあるので,他者に対する自由が確保されています。いたずらに人の心を気にすることはないのです。
(以上のように,行為には,一つには他者との,一つには内在する主体との関係が欠かせない契機です。そのいずれもがあやふやな心的状況では,いわゆる’勝手な行動’になります。それは眼差しの中にある重要な他者に(悪しき)依存していながら,それを認めるのを拒否するというひねくれた意識の下にある行動です)
Bさんは,できることを精一杯やりつつ,「これでよいですか?」と尋ねました。尋ねる相手は自分自身,つまりBさんの意識を超えた力を持つ主体です。そういう行為は,一人だけの信仰ともいえることです。
Bさんは,いまもおなじ生活状況にありますが,一定程度の自信を持っています。それが表情に表れています。そういうふうであれば,やがては親子関係の修復も可能でしょう。そのときは過去への回帰ではありません。かつてのBさんは,支配的な母親に従う一方でした。Bさんの主体者は母親だったといっても過言ではありません。いまやBさん自身が自己の主体者であるという,当然のことを自覚しつつあります。そうであれば,母親が従来のように支配者として振舞おうとするかぎり,親子のあいだには断絶があるばかりです。
必要とあらば関係の断絶も辞さないという強く,揺るぎない心の姿勢があれば,自己の自由を護ることができます。それは関係の正常化をはかる基盤を得たことを意味します。やがては,母と子が対等の関係で,それぞれの自由を尊重することで成り立つ,しみじみとしたものに変わる可能性も出てきたといえるのです。
自由は当然のことながらそれぞれのものでなければなりません。そういう理屈は誰もが知っていますが,実際には,個人のレベルであれ,国家のレベルであれ,強者には弱者を支配する自由があるという暗黙の了解があるかのようです。
親が子を支配し,子が親に支配され,そういう関係に依存している親子がなんと多いことでしょう。
膠で貼り付けたように,この依存関係は実に強力です。それを何とかしないかぎり,「病気がよくなる」可能性がないのですが,当然のことながら依存し合う双方共にさまざまに無自覚です。治療者がことを急いで,無理に膠をはがしにかかると,それはいわば自由の侵害になり,治療関係の拒否に合うことになります。母親の方は怒りをもって,子供の方は怖れをもって,共々に治療者の下を去っていくことになります。
何はともあれ自由は尊重しなければならないのです。依存し合う両者が,内側から,不自由な自由に疑問を持つ力を蓄えるしかありません。
このような局面では,治療者も困難な立場に立たされます。
何故なら,「病気がよくならない」からです。そしてよくならない理由を説明することが困難だからです。無理に分からせようと試みると,たったいま述べたように膠をはがす作業になり,痛みに耐えかねるあまりに不信と不興を買うことになりがちだからです。
そういう事情の下にあるとはいえ,問題を解決に向かわせるには,問題が正当に受け止められたとき以外にはありません。
膠で貼り付けたようなと,少々度が過ぎたいい方になりましたが,親子の強固な(悪しき)依存関係の悪しき意味を受け止めなければならない立場にあるのは,いうまでもなく第一には親の方です。
親の姿勢に好ましい変化があれば,子供は自分が自由になることが許されるという,当然で,重要な意味を知るきっかけを得ることになります。しかしそれは不安に満ちたことでもあり,半信半疑でだろうと思います。
何故ならそれは重要であり,そうでなければならないとはいえ,心の組織の破壊でもあるからです。
変革のためには破壊が必要ですが,自分で克ち得たものでないかぎり,破壊はあくまでもしばらくは破壊に留まります。
親に従うことで親に護られていた自己組織を,急に本人自身の自由に任されても,どうしてよいのかすぐには分かりません。むしろ突き放された,見捨てられた,親を怒らせたという恐怖に耐え難い思いをするだろうと想像されます。
しかしながら親の側のそのような意味のある理解の仕方は,子への愛情に違いないでしょうから,それは子の心を安心させる大いなる理由になります。
愛情と信頼とに勝る贈り物はありません。今度は子供の方で,その素晴らしい贈り物に自然な心でお返しをすることになるでしょう。本物の愛情と信頼に応えない子はないはずです。そのように親子の心の交流が進展すれば,心の自然を歪めてしまった人間の介入が,改めて人間の介入によって是正され,修復されることになるでしょう。
■自我の形成 その2
#1 集合的他者
いわゆる良い子の多くは,以上に述べた自己の自由の意味を感覚的に理解できません。
それは心の中軸であるはずの自我が,自立性を保つことができていないからといえます。
自我が自立性に問題がある場合,それに換わって首座にあるのは集合的他者とでもいうべきものになります。
この心の内部の他者が中心的な位置を占めると,人の目が気になって仕方がないことになります。
ここでいう集合的他者というのは,個々の他者ではないだけに,この勢力が大きくなると,あらゆる他者のおめがねに叶おうとすることにもなります。そうなるといわゆる完璧主義者になるしかありません。常に100点を取りつづけないと許さない親のような心の内在化といえます。いわば全か無かということになり,80点を取っても零点と変わらなくなります。自我が健全に機能しているのであれば,「80点は零点ではない」と主張することができるのですが。
それを心の法廷に見立てると,鬼検事ばかりがいて弁護士不在のようになっています。そうであればいつも有罪宣告されるに等しい心的状況になるのです。
鬼検事ですから,攻撃性が強く,怒りのエネルギーを強力に蓄えています。自我によって不当に抑圧された心の分身たちの,潜行する怒りが,命令的,懲罰的な集合的他者を作り出すのです。
以上のことを,具体的な例で説明してみます。
友達(B)の家で遊んでいた二歳の子(A)が,玩具を家に持ち帰りました。その玩具を欲しい,自分の物にしたいというのは自然の欲求です。それは幼い子の端的な自己表現であるといえます。
言葉を変えると,この素朴な自己表現は,自我の自律機能によって促されたものであると考えることができます。
幼い子がこのような表現をすることは,決定的にといってよいほど重要です。
つまり自己表現は人間にとって基本的に重要なことですが,幼い子は他人の干渉を受けずに,素朴にそれを表現し,それができている自分を喜ぶ(遊ぶ)という経験ができる年代にあるからです。
そして幼い子の自己表現が親をはじめとした大人たちの干渉を受けないということは,幼児が自分の力を感じ取るのを大人(主に母親)が是認すること,つまり共に喜ぶことを意味します。
未熟な自我は,ひとしきり素朴に自我の自律性の発露を味わい,楽しむことにより,自己表現の原体験をすることになります。それは母親を中心とした重要な大人たちの愛情によって保護されることにより,豊かで意味深い経験になります。
その経験は,後々,必要とすることを自分で取りに行く意志を持つことが正当化されることに通じ,与えられた人生,ないしは自己を自ら引き受ける意志を持つことに通じるのです。
その表現の仕方は,しかしながら,いずれ母親によって否定されます。「それはBちゃんの物です」と。
Aは不快感を味わいます。しばらくは元気がなかったり,不機嫌だったりするでしょう。母親に認めてもらえないことは,一種の危機なのです。
自分がすることが母親に認められたり,認められなかったりしながら,やがて母親に叱られないように気をつけるようになります。母親が側にいなくてもいいつけを守ることができるのは,母親を無意識的に心に取り込む(内在化)ことによってです。それによって自我は,自律機能の他に抑圧機能を働かせることになります。
ある程度成熟した自我がこのように母親の介入を受けることになり,それによって,素朴な自己表現から,より高次のものが求められることになります。
換言すると,素朴なレベルでは,’あらゆることが許される’のですが,新たな次元では,他者との関係をも配慮に入れることが要求されます。
母親との関係が確かな信頼と愛情とで結ばれていれば,「人の物は取ってはいけない」という禁止は容易に内在化されるでしょう。心に内在化されるのは,この例に従えば母親ということになりますが,一般的には誰とは特定できない抽象的他者になります。
このように内在化された集合的他者との関係で,自我が時によっては抑圧機能を働かせて,自律機能に優先させるのです。それによって,勝手気ままな行動は慎まれることになり,社会性を身につけることになります。そしてそれに伴って,自己表現の喜びには,他者に認められる喜びが含まれていることが明らかになります。
しかし一方では,このような集合的他者が内在化され,心の指導者になっていくと,幼児に許されるような内発的な自己表現が貧困化していく理由になります。つまり発達した社会性は,自己表現の本来の喜びを奪う側面があります。
例えば幼稚園児の’お絵描き’はそれぞれの内発性によるもので,この場合の集合的他者は,「自由に描いてごらん」という姿勢になると思います。また大人たち(外的な集合的他者)も余計な干渉をしないので,’それぞれの絵’があり,優劣は問題になりません。しかし中学生,高校生になると,教師が指導的干渉をします。この場合の(内的な)集合的他者は,一定のあるべきイメージを提示します。これら集合的他者なる指導者に従っているかぎり,優劣の差ができることになります。つまり自己表現の喜びは大幅に減じ,集合的他者が提示するイメージに従って絵を描き,それを教師が等級をつけて評価することになります。
このように,(内的な)集合的他者に従うかぎりは,(外的な)集合的他者によって優劣の等級がつけられることになります。
(真の芸術家は,世に受け入れられなくても,集合的他者にではなく,幼児のように自己の内発性による自己表現にこだわるので,孤独の中でも自己を追求しつづけるのです。そして’真の芸術家’には,(幼稚園児のように)作品に優劣はなく,それぞれのものがあることになります)
一般的には,それぞれの人生はそれぞれのものというほどに個性的,独創的ではありません。むしろ集合的,没個性的といえるでしょう。洗練された芸術家の自我は自律機能に従おうとする一方,一般市民のそれは,抑圧機能を発達させていると思われます。それによって,自己自身であろうとするよりは,人間集団の中で確固とした立場を得ようとします。この場合の野心は,人に抜きん出ることです。
他人より秀でたいという野心によって社会的な成功者になることができた人は,一方では,本来の個性的自己からは遠ざかることになるかもしれません。内在化された集合的他者の下に成功した人は,仲間同士の語らいで時を忘れることができます。うまくいくと一生をそのようにして送ることもできるかもしれません。しかし,例えば会社を辞めたあとに,虚無感に陥る危険がないとはいえません。
また先に上げた例の母親が,心配性で,子供が不始末を仕出かしていないか,絶えず監視の眼を光らせるようであれば,子供の心に内在化された集合的他者もまた監視的,命令的になり,幼い自我は過度に抑圧機能を働かせることにならざるを得ず,子供らしい自己表現(いたずら,泥んこ遊び,喧嘩などの遊び)が封じられることになっても不思議はありません。
このような心的状況では,心の表舞台から封じられた幼児的な自己表現の欲求が,社会性を剥奪された裏舞台のものとして潜航しつつ勢力を蓄え(必ず強い怒りを伴います)ることになるでしょう。場合によっては長じてから,それらが自我の眼を盗んで,万引き,過食,買い物依存等々の黒い満足に走る独立した動きを起こすことがあります。
幼児の心を失わず,素朴な自己表現の欲求を失っていない芸術家たちは,いま述べた心の裏舞台を作品として表現することがあります。成功者が心の表舞台を描いても,それは下らない自慢話になるだけで人の共感は得られません。芸術家が作品の上に描き出すのは,世間的な達成から疎外されている生活者の不安,不幸,あるいは悪とされるものです。世間的な成功者の驕りの陰で虐げられているもの,世間が眉をひそめる性的なこと,人生の惑い,悲しみ,怒りなどの中に,より強く人間のにおいがあることなどが,人の共感を呼びます。それらは世間的な成功から疎外された心の叫びともいえます。それはあたかも,意識上の世界だけが心のすべてではなく,無意識の世界の中にこそ生命の源があることを教えているかのようです。
心に裏面が存在しているのは,人間の真実です。それを何らか表現することは極めて重要なことでもあります。
ある中年女性は,人前では過緊張で字が書けなかったり,歯科治療のときに喉をごくんと鳴らすのではないかということを過度に怖れたり,「人は人を殺すことがある」という強迫的観念に脅かされたりします。
もし彼女が芸術家であれば,これらの衝動をもたらす心の裏舞台にあるものを抑圧しつづける代わりに,作品に取り上げることができるかもしれません。そうするとそれらのものは自我が承認したことになり,もはや意識の地下活動で自我を脅かすことはなくなるはずです。
彼女がこれらの衝動の突き上げにあって悩むのは,彼女が過度に社会性を身につけて,いうならば不条理な抑圧をしつづけてきたからに違いありません。
集合的他者というのは,体験された他者たちといったものではありません。
生まれて間もない赤ん坊は,いわば純粋主観の世界の住人です。それは自我がまだ機能を開始していないか,未成熟な機能でしかない時代の話です。その時代では,母親が自我の代行をしていると考えてよいでしょう。
そして客観的,外的世界は,自我の成熟と共に乳幼児の世界に取り込まれていきます。
このように自我に拠る人間は,主観的ー客観的である現象的世界の存在者であるといえます。
そのために,確かに経験したはずのことが夢のようにも思われたりします。確かである保証が純粋客観に求められるのであれば,人間にはそういうものは存在しないことになります。
人間に純粋客観はないが,純粋主観はある,それは嬰児の世界であるといえるように思われます。
ただし,このことを経験的,実証的に確かめる術はありません。いわば理論的推測ということになります。
この,存在すると思われる純粋主観の心理的世界が,人類に普遍的な無意識の世界であり,自我の能力を超えているという意味で無限界であるといえます。
心理的なエネルギーの源泉は,所在不明です。
身体にエネルギーがあるのは,実証的に明らかですが,身体と精神とは密接不可分の関係にあるのもまた明らかです。しかし,最初に身体があって,ついで精神の方にエネルギーが移行するといったふうに割り切って考えることは困難です。それは「精神の原因は身体にある」といった類の考えが,割り切り過ぎて,説得性を持たないのと同様です。
このような筋で人間の問題を考えると,「人間の原因は人間である」という奇妙な,悪ふざけになってしまいかねません。
それではこの問いに何と答えればよいのかは,自明といえるほどのことのように思われます。
つまり人間の存在は,不可知の理由によるとしかいい様がありません。
その上で,身体にエネルギーがあるのは明らかなのと,精神的エネルギーの捉えどころのなさと,一人の人間が持っているエネルギーの総量が一定範囲の中にあるらしいのと,それらを拠り所に,次のように仮定的に考えることが可能です。
自我は,無限界へとつながる無意識界(純粋主観の世界)と,身体をも含む外的客観的世界(意識化可能の世界)との接点にあり,主観的ー客観的である現象的世界を演出する主宰者の位置にある。
自我の存在根拠は不可知である。従ってそれは,先に述べたような意味で純粋主観の世界に根拠を持っていると考えるしかないが,身体的な根拠をも持っていると考えられる。それによって,主観的ー客観的な世界の演出が可能となる。それぞれの人間存在は,まだ自我の機能が開始されていない嬰児の段階で,定められた定量のエネルギーが与えられている。それが精神と身体の未分化な純粋主観の世界と,機能開始以前の自我機構とを養っている。
そして自我の機能が開始されると,主観性に客観的側面の根拠を与え,客観的,身体的なものに主観性(精神性)をもたらし,心に外形と内実とをもたらして統合する・・・。
自我が健全に機能すれば,外的客観とこの純粋主観との円滑な協働が果たされることになります。エネルギーは順調に循環することになります。
ここで問題にしている集合的他者というのは,いま述べたような意味で,主観的ー客観的な性格のものです。意識と無意識との中間にあるものでもあるので,それはイメージとして存在するといえます。
過食症者の多くは’よい子’です。自分でそう思っている場合もあり,むしろよい子ではないと思っている場合もあります。後者の方が自己がより多く抑圧され,「完璧ではない」という意味でよい子ではないと感じているのです。
一般的によい子の路線を取っている過食症者は,表面はにこやかにしながら,内面では人間不信や激しい孤独感,虚しさ,寂しさに打ちひしがれています。それらの激しく,ネガティブな感情と共にある彼らは,他人がどんなに優しくしてくれても,容易には情緒的な満足に浸ることができません。
彼らの自我は,母親のそれに密着していわば傀儡化しています。
権力者である母親の自我に過剰にすがるとき,自我は自律機能よりは抑圧機能を優先させる傾向が顕著になります。そうすると子供らしく甘える心は,抑圧されつつ成長していくことになります。それは自律機能に関係する子供らしい諸欲求(内在する主体から送り出されてくるもので,一定の方向性を持ったエネルギーを帯びています。それを自我が受け止め,護ることによって生気感情が育まれていきます)が不当に抑圧されることを意味します。無意識の領域から生まれてきた分身たちが,自我に受け入れを拒否される(母親への怖れ,気兼ねなどから)ことに伴って,寂しさ,悲しさ,虚しさ,怒り,恨みなどと共に,裏の人格を形成していくことになるのです。それは表の自我の無力を意味します。いつまで経っても(無力な)自我に受容される見込みが立たないままでいると,いつか裏の人格が支配的となり,死を志向する力と一体化していくことにもなりかねません。
このような傾向がつよい自己の心の内界は,中心にあるべき自我が無力である代わりのように,集合的他者とでもいうべきもの(外界にある母親に対応するものでもあるでしょう)が支配的な力を持つことになります。
これは他人の眼を過度に気にする基となるものです。
そして,それに相応して自我によって受け入れを拒否されたものたちが,影の分身たちの勢力となります。
自我領域には,いうならば自我の山と集合的他者の山と影の分身たちの山があると考えると,心の病理現象を理解する上で有益です。
それらの山の中で自我の山が主力であれば,自我は自立していることになり,自己形成へと向けた心の体制が整っているといえるでしょう。
過食症者は,しばしば死を希求します。
それはいま述べたような事情によるのですが,表の自我が自立していないために,有益な仕事をして自分で自分に満足をもたらすことができない傾向があるからです。集合的他者の支配を受けている自我が,自分自身よりも母親(あるいはそれに準じるもの)が満足するように仕事をしようとする傾向があるからです。
それに伴い,自我が自律機能をよりは抑圧機能を優先させるために,無意識の領域から生起してくる諸欲求を自我が受け入れ,護ることができないために,得られるはずの生命的なエネルギーを,怒りのエネルギーに変換させてしまうからです。それは生命的な心の表舞台に活力を与える代わりに,死への志向を持つ裏舞台にエネルギーを注ぎ込むことになるのです。
自律機能を十分に働かせ,自己を表現することの喜びを十分に経験するべき時期に,母親の意識的,無意識的な干渉によって抑圧機能が発達すると,大人びた子供になるかもしれません。それはもしかすると,周囲の大人たちに,「よくできたお子さん」と見られるかもしれません。いわば早すぎた社会性を身につけた子供は,周囲の大人たちの目にはよい子に映る一方で「自己の無力」に苦しむことになる可能性があります。
しかしながら乳幼児の場合,目的は,いずれにせよ母親によって自分の全存在が認められることです。
乳幼児に特徴的な重要な心性の一つは,揺るぎない全存在の保全をもとめて,母親を支配しつくそうとすることです。
完全に母親に依存している乳幼児の段階では,母親は神のごとき存在であるといっても過言ではないでしょう。事実,乳幼児は,母親が全能であるという幻想を持っていると思われます。母親と一体の関係にある赤ん坊は,全能なる母親を支配することで自分自身が全能の者となれるのです。
それを裏返せば,赤ん坊はこの全能幻想に疑いを持っていることになり,だからこそそれを要求するのです。あるはずのもの,持っているはずのもの,それらが与えられていないという不安,不満,苛立ち,怒りをもって母親に要求する(これらの疑惑,不満足は,長じて,自分は愛されていない,愛される価値がない等々の自己否定感の源泉になります)ことが,即ち支配欲求です。
しかしその原始的で,強力な欲求は,強力であるがためにカウンターパンチをもらう理由になります。いま述べたように,その要求が強力である分,強い怒りをはらみます。現実に満たされることが不可能な欲求と,満たされないことへの怒りが,母親のカウンターパンチを招く理由になります。母親自身にはそのつもりがなくても,ふとしたときに赤ん坊は自分の怒りを母親の顔に投射して,恐怖を持つことになります。
その恐怖は,赤ん坊が幻想的な全能感を必要とする現実と,それを要求することの非現実性とのあいだの懸隔が,赤ん坊が生まれる以前と以後との存在形態のあいだに横たわる超え難い深淵そのものであるといえ,そのような事情に由来しているように思われます。
しかしながら,いずれにしても,人間の現実世界では通用しないこのような支配欲求は,取り下げられなければなりません。何はともあれ人間として生を受けたからには,この世の現実を受け入れなければなりません。
見捨てられる恐怖には,あきらめて人間的現実を受け入れさせるための役割もあります。
「そんな分からず屋は,おかあさんの子ではありません」というわけで,全の要求をあきらめて,ほどほどの満足と安心とに甘んじる気にさせなければならないのです。そうしなければ,頼りとする母親との関係が保てなくもあるのです。
乳幼児にとっては,母親に見捨てられないようにするのは最優先の課題です。
この見捨てられる恐怖は,母親が赤ん坊に対して持つ怒りではむしろありません。そうではなく,赤ん坊が持っている怒りの逆照射に主因があるといってよいでしょう。しかし母親側の問題も無論小さくはないと考えなければなりません。というのは,支配欲求というのは小児心性の特徴として強いエネルギーを持っているので,母親自身が満たされない思いを潜在させていると,赤ん坊に苛立ちをぶつける十分な理由になるからです。それどころか,苛立ち易い母親,支配的な母親でさえ,珍しいどころではありません。
良い子として抑圧機能を優先的に働かせるのは,自我の戦略としては勧められたものではありませんが,母親に認められたいという目的はそれなりに達成されます。それに相応して,自律機能も護られることにはなるのです。
このように,よい子という自己犠牲の精神で生き残りを図ろうとする問題が生じる発端には,人格形成の最早期での避け難く,宿命的な見捨てられる恐怖があると考えられます。
いかに生きるかという以前に,ともかくも生きようとするのが自然ともいえるでしょう。
根源的に二律背反の原則に従わされている人間存在にとって,見捨てられる恐怖は生と死の分水嶺となるものです。
生を受けた赤ん坊は,残酷にも早々に死の存在を突きつけられ,やがては受け入れていかなければならないのです。
死を,自我が引き受け難いものであるかぎり,生もまた耐え難いものになります。
20代前半のある女性(Cさん)は,姉が’おばあちゃん子’であったのに対して,「この子は私の子」と母親にいわれながら成長しました。大学を卒業後,勤めた会社で否定的に扱われたこともあって,職に就いていません。母親の観点からすると,「昔はよい子だった」ということになります。そのついででいえば,「今はわるい子」ということになりま
あるときCさんが冷蔵庫の中を見ていると,母親が,「やめなさい」といいました。
Cさんによれば,いまも太っている(さほどではありません)のだし,仕事もせずに家でごろごろしているのだから,間食をするともっと太るというのが理由だと思うということでした。Cさんも,その母親の考えに同感しています。
その直後,母親が出かけたときに,菓子パンを2個食べました。食べてから,大変なことになったと思いました。あわててゴミを捨てに外へ出たときに,帰ってきた母親に出会いました。「殺される!」と思い,走って逃げました。電車に乗って遠くまで逃げたそうです。
いくらなんでも実際に殺される心配は皆無です。
支配的なCさんの母親を怒らせると,Cさんは見捨てられると感じたのです。Cさんにとっては,母親が支配的であるということは,圧殺者ではなく護られている者という感覚です。恩義を与える者と受けている者との関係です。そういう意識の下で,圧殺される,侵入される,自由を認めてもらえないといった心と,それに伴っているに違いない怒りとを無意識下に封じているのです。
そのことは集合的他者の山が,自我の山よりも高いことを,従って母親との関係で,自律機能より抑圧機能を優先させていることを物語っています。
間食など許される身分か,というのが母親の気持ちであり,Cさんも同調しているのですが,この同調する考えが集合的他者によるものです。そして母親がいない隙に盗み食いをしたのは,影の分身たちの仕業です。
自我はといえば,いずれにしても主体性を示せないでいます。
集合的他者の山が自我の山よりも大きくなるのは,怒りによってです。
その怒りは影の分身たちの山のものでもあります。
つまり自我が母親の自我に傀儡化するようにして自律機能を抑え,抑圧機能を働かせることに伴って,自我に受け入れを拒否された諸欲求が,生命感情を育成するはずだったエネルギーを,怒りのエネルギーに転換させたといえるのです。その怒りのエネルギーは影の分身たちを養い,集合的他者をも大きくします。
見捨てられると生きていく術を失うのは,幼い子の問題です。Cさんの心の中でそうした幼児心性がつよい勢力を張っていたことを,このエピソードは如実に物語っています。
殺されると恐れたのは,部分的には,もしかすると圧殺されているCさんの怒りが自我を脅かしたからかもしれません。その怒りはCさん自身の心を破壊しかねない(自我に向けられた怒りに自我が耐え難く感じている)ものであろうと推測されます。また,その怖れは母親に向けられた無意識的怒りへのものであったかもしれません。
集合的他者はすべての人の心にあるものです。
幼いときからピアノの天分が認められた子に,その父親が極端なスパルタ教育をして,ついには人格破壊をもたらし,しかしピアノ演奏の才は大いに開花したという映画があります。
この場合は,内在化された集合的他者は命令的,懲罰的で,自我を打ち壊すほどの勢力を持っていますが,自我の自律機能は,ピアノによる自己表現に関するかぎり,それに抗する力を失わなかったと考えられます。
むしろ圧力を加えてくる集合的他者に押し潰される代わりに,それを凌駕するようにピアノに立ち向かう力を自我は持っていました。
一般には,集合的他者は,より穏やかなものです。それは自我と対立,拮抗するよりは,穏やかな教師のように忠告します。その忠告は,おおむね,世間的に認められた人生の途についてのものでしょう。創造的,個性的な途については,自我の自律性の役目になり,集合的他者はその意味では抑制的に自我に働きかけることになると思われます。
Cさんの集合的他者は,支配的,命令的,懲罰的なもので,自我はひたすら抑圧機能を働かせるしかなかったようです。
つまり集合的他者(その中核には母親,そして父親がいます)に圧倒され,従属させられている自我の下では,’自己否定の人’の人生を歩むことになるのが避けられません。こうした場合は,いわば人生レースの敗者になります。
画家を目指す者であれば,集合的他者の介入に抗する内発力を発揮できないかぎり,二流以下の凡庸な画家に甘んじるしかないでしょう。あるいはその道の敗者になれば,絵をあきらめればよいだけのことです。しかし人生そのものとなればそうもいきません。しかし絵と違って,それぞれの性格,それぞれの人生は,本来は出来の良し悪しではありません。自分らしいかどうかです。
問題は心の指導者の立場を,集合的他者が握っていることにあります。そのために自我の自律性が抑圧を受け,機能不全化するのが習いになっていると,人生レースの敗者となり,自己を見失い,虚無と絶望の淵に立たされることにもなります。
そういう心的状況では,改めて,「自由にやっていいのだよ」という’幼稚園児のお絵描き’の精神に立ち返ってみるのも一方でしょう。
「かくあらねばならない」という絵の(集合的他者としての)教師は極力排除して,「自由に描いてごらん」という教師に置き換える努力をするのです。途方に暮れ,打ち倒されるようにして無為に過ごすのではなく,「いまできる自由な絵は思い浮かばない,強いていえば寝ている絵しか描けない」というのであれば,「それでよい」とする精神です。
何をしてよいか分からず,途方に暮れて寝ているとしても,強いられた絵が描けなくて寝ているのと,自分の意志で描く絵がいまは寝ていることでしかないのとの違いは,大きいはずです。
前者であれば一日中でも寝て過ごすかもしれませんが,自分の意志でとなると一日中寝ているのは苦痛になるでしょう。苦痛は不足感でもあるので,たとえば「掃除をするという絵」を描こうという気が起こるかもしれません。
そのように,「かくあらねばならない」という精神から,「何が出来るか」という精神に移行していくこと,強いられた精神から自ら意志する精神へと換えていくことができれば,徐々に自分らしい生活が見えてくるかもしれません。
何もする気になれなくて一日中寝て過ごしたとしても,それがいま自由に描ける精一杯の絵であれば,良しとしてよいのです。それは,旧来の厳しいばかりの集合的他者の指導の下にあれば,「そんなものは作品であるものか」ということになるでしょう。そういう状況では,おなじ寝ているだけの生活にしても,「絵を描けない」という絶望と内向する怒りと共にあることになります。しかしそういう集合的他者の指導に従ってきたので,現在の無気力な姿があるのですから,いまは差し当たりそれでよいのです。寝ていることも,自由に描いてよいという指導者の下であれば,「いま描ける精一杯の絵」といえるのです。
要は,一日を精一杯生きるということになるでしょうか。
強力に支配的な母親に従属していたある女性は,近く家を出て一人暮らしをすると決意を固めています。彼女には,母とのあいだの依存関係を清算するのは容易ならぬことでした。そのように心の状況が変化していくにつれて,無力に見えていた表情が引き締まってきました。この女性が描いた「家を出る」という絵は,立派な作品です。
#2 二人の母親
自我の抑圧機能が過剰に働くのは,母親を核とした他者への過度の気遣いとパラレルな関係にあり,それは集合的他者と影の分身たちとの勢力を増大させ,自我の無力化を招くことになると述べました。そしてそれは死へと斜傾する方向性を持っています。
一方,生気感情を豊かにさせるのは,自我の自律機能によってです。
これまでに繰り返し述べてきたことですが,自我の誕生は光の世界の誕生です。そして自我の誕生は死の誕生でもあります。
自我の誕生以前の世界は,自我に拠るわれわれ人間にはうかがい知ることができません。
自我による世界は,誕生によってはじまり,死によって終焉する有限のものです。自我による意識という光が届く範囲は限られたもので,これを有の世界とすると,自我の誕生以前の世界は意識が届く範疇の外になるので,それは無(または無限,または全)の世界ということになります。
そして先に述べましたが,自我の機能開始の黎明期にある嬰児の世界には客観的な外形はいまだなく,主観と客観とが渾然と一体化している,いわば純粋主観の世界であるように思われます。それはユングのいう普遍的無意識の世界ともいえるかもしれません。外形によって限定化されていないその純粋主観の世界には,無限性の性格があるように思われます。
自己と人生とが,誕生と死によって外側から明瞭に限界化されていながら,それでもなおかつ自己と人生とが目標とするある到達点を持ち,そこに到ってそれらが終結するといったことはなく,その意味では無限性を生きているのが実態といえます。それは嬰児の世界である純粋主観が無限性の性格を持ち,それが他でもなく我われ人間の一大特性であることに関係があるのではなかろうかと思われます。
また,明瞭に有限のものである身体性と,無限性に通じる精神性との総合である人間存在は,永遠の二律背反(生と死の互いに相容れず,しかし相互に絶対依存の関係にあるのがその最たるものです)を生きているのを特徴としています。その永遠の矛盾の対立が新たな統合をもたらし,人間の精神の無限性が保証されていると考えることができます。
つまり,この論旨に従えば,自我の誕生以前の世界は全または無であり,誕生後の世界は,その主宰者である自我によって二分割され,不完全なものの複合体になるといえます。
自我に拠る世界は現象的世界です。つまり主観と客観とが総合された世界で,両者は独立して存在することがなく,相互に絶対的依存の関係にあります。
現象的世界にあって,諸現象を二つに分割して捉える(自己と他者,男と女,善と悪,愛と憎しみ等々は,相互に他を不可欠のものとしています)のが自我の特徴です。その根源には,相互に他の存在を不可欠なものとしつつ,しかし相反するものの関係にある生と死と,あるいは光と闇との分割された対立があると考えられます。
自我による生の世界は,死という終焉にいたる有限のものです。
しかし生と死の対立の永遠性が,生の無限性を生み出すのです。つまり希望は無限定なものでなければ希望の意味をなしませんが,生と死との終わりのない矛盾,対立があるかぎりは,その都度それらが止揚されることが可能であり,それは次々と新たな希望が生み出されることを意味します。そして死という終焉にいたって,人は人間存在としての役目をはたし,自分の全存在を,それをそもそも生み出した不可知の上位者に返還することになると考えることが可能です。
そのように考えると,限られた能力をしか持っていない我々ではあっても,日常の意識の中に無限性をも持ち込みつつ生きているといえます。
ところで,それぞれの私の母親はだれでしょうか?
それぞれの私を生み落としたのは,それぞれの母親,というよりは,父親との合作によってであるとひとまずはいえます。
しかしそれが全てでしょうか?
その答えは,たったいま述べたことの中に含まれていると思います。
常識的な意味での母親を地上の母と呼ぶとすると,もう一人の母親は上位者なる母ということになります。
人間が人間であるゆえんは自我にあるといえますが,自我を授けたのは父親でも母親でもないのは明らかです。その自我を授与する力を持ったものが上位者なる母です。人間は,人間に似せたロボットを作り出すことができますが,あるいは人間を生むことはできますが,人間そのものを作ることはできません。
自我を授ける力を持っているのは,人間以上のものであるのは明らかであっても,誰と名指しするのは不可能です。名指しはできないが,自我によって人間は存在可能であるという事実問題があるかぎり,上位者の存在もまた明白といわなければなりません。
自我至上主義者は,例えば次のようにいうかもしれません。
人間は生命連鎖の極致にある,動物が進化した究極の存在である・・・と。
それもまた一つの仮説です。
しかし動物の存在形態のあいだに進化論的移行系が見出されているにしても,それが単純に物質的ないしは生命科学的な発展であると証明するのは不可能です。簡単にいえば人間の知恵をいくらこらしても極めることができない難題であることに変わりはありません。
この論法によっても,つまりは我われには知り得ない理由によって動物間の進化があることになり,その知り得ない理由を知っているのは人間以上のものであるということになります。
結局,どのような仮説を立てようが,,自我を最上位に置くことが不可能なのは自明です。
そもそも知性は自我の僕であり,自我は有限の世界での自己の中核です。そして自己ないしは人間存在には,無限的世界も含まれています。自我はこの無限領域に関わる能力を持っていないのですから,知性が人間存在の全般を網羅的に究明し,理解するのはどだい無理な話です。
そのように考えると,以下のような仮説が可能です。
人間の誕生は,第一に自我の授与によってである。それを授ける力を持つものは,自我に拠ってはじめて存在可能となる人間自体ではありえない。それは人間には不可知の上位者であると考える以外にない。
不可知の上位者とは,意識による人間にとっては’全なるもの’と言い換えることができる。
そして全なるもの(天)を母とする赤ん坊は,天からの授かり者ということができる。
自我を授与された赤ん坊は,意識せずにそれを引き受けたものとなる。つまり不可知の上位者(主体と呼んでおきます)の命を引き受ける者として地上の者となったと考えることが可能である。
主体の命とは,「自我によって自由に自己を導け」というふうに考えることができる。
そして地上の者となった人間の無意識世界に,主体は鎮座して沈黙のうちに自我がいかに自己を導くかを見守る。自我が自己を導く道筋を,主体は沈黙の内に指し示している。
人間の誕生は,第二に(地上の)母親によっている。母親は意識せずに主体の命を受け,仮託されたと考えることが可能である。
いうならば父親と母親とはそれぞれに二分割された二分の一以下の存在で,その母親が新たに一人の人間の親であることができるためには,他の二分の一の存在である父親と合体して’完全’にならなければならない。そうなることで子供が二分の一の存在として生み落とされる。
有限の世界を生きるそれぞれの自己は,二分の一以下の存在として心の内に他者を構造化し,外なる他者との関係を不可欠なものとしている。そのようにして全に準じる存在形態となり,人間の現象世界を包囲している全(自我に拠る人間には無と区別がつかない)の無化作用に対抗している。
第二の母親が第一の母親と決定的に違うのは,前者には二心があり,後者にはそれがないことである。
第一の母は,無意識世界の主体となって,個々の人生,個々の自己の途を無言のうちに指し示している。
第二の母は,人間的な大道を志向する。つまり,この世的な達成を志向する。それは勢い,他に負けないことが要点になる。
二心というのは,例えば,子供の成長を親が喜ぶのは子供への愛情である,と同時に,親自身の安心,満足でもあるということです。
二心それ自体は良くも悪くもなく,人間に固有のものです。
善心と悪心もまた人間に固有のものであり,二心です。その存在自体にはよいも悪いもありません。しかし悪がどういうものかを知らない者はないので,この場合の二心はある意味ではあまり問題ではありません。
人間に善心があるかぎり悪心は必ずある,しかし社会性と精神性とが欠落している悪心は,裏の自我による世界のものであり,公然と心の表舞台に乗せることは許されない・・・ということになります。
育児上の二心は,子のためを思ってしているつもりの躾が,実は親自身の不安や不満の解消を子に求めていること,それが意識されることがないこと,という形で問題になります。
以上の仮説に基づくと,躾は,主体が指し示す自己の途を探り当てる自我の仕事を,親が助ける形が望ましいことになります。
しかし躾や教育は,人生の大道の歩き方といったものにならざるを得ません。
個々人の真に個性的な達成などというものは,もし分かる者があるとすれば本人以外にはあり得ません。しかも幼いうちからそういう道筋をたどろうとするのは,ごく稀な芸術的天才だけでしょう。一般的には社会性を身につけさせる努力以外には,躾であれ教育であれできない相談です。
「世間体を気にする親」といったこともいわれたりします。世間体を気にしない人間もまたいないはずですが,このようにいわれるときには,子供の方で親の二心に敏感になっているということなのでしょう。
Sさんが,父親が乱暴にドアを叩き続けている,といった内容の夢を見ました。
実際に父親は怒りっぽく,母親も負けていないので両親の口喧嘩が絶えません。非は父親の方にあるとSさんは思い,両親のあいだに立って家庭の空気を和らげる役目を負いつつ成長しました。しかしSさんが仕事をすぐに辞めてしまうので,それが両親の頭痛の種になってしまいました。
常々,Sさんは母親の意向に従っていましたが,この夢を見て,乱暴にドアを叩き続ける父親も可哀想だと思いました。夫を閉め出している母親の方が問題ではないかと思ったのです。
Sさんと両親の三者との何度目かの面談の席で,Sさんをはさんで両親が声高にいい合いをはじめました。母親が夫の態度を責め続ける状況で,私がこの夢の話を持ち出しました。「Sさんも,母親に対してこのような批判的な気持ちを暗に持っているようだ」といったことを伝えました。
これはかなり乱暴な介入だったと思います。事前にSさんの同意を取りつけないままにしてはならないことでした。しかしSさんと母親との強固な依存関係が変わらないかぎり,通院を必要としているSさんの問題は改善される見込みがないのも確かです。どの段階でかこうした介入は必要ですが,その場の成り行きで,いわば賭けのような介入をしてしまったのは危険なことでした。
果たせるかなSさんの足がしばらく遠のきました。そしてしばらくぶりで受診したSさんは,言葉が少なく,不満の様子が見て取れました。
しかしその後気を取り直した様子が見え,私は改めてSさんの基本問題の説明をした上で,「あなたの意志を伝えることができるようになるのが課題です。おかあさんに,今後はそのようにするつもりがあるといってみてはどうですか?治療上の必要があるのでそうするようにいわれたと,話されてもよいかと思いますが」と提案しました。
Sさんはうなずいていました。
その数日後に母親がやって来ました。
母親は,Sさんが「逆らいなさいといわれた」といっているが,どう対応したらよいものか相談に来たといいます。そして最近辞めた会社の元上司と個人的な交際をしていて,彼は父親ほどの歳だが何もいわない方がよいのかといいます。
「逆らいなさい」というのはSさんの取り違いと思います(「意志は伝えるように」というアドバイスをしてあります)が,年上の男性との交際は初耳でした。
母親の困惑は当然です。
恐らくは感情を抑圧しつつ成長してきたSさんは,情緒的なものに飢えていたのだろうと想像されます。
しかしこの交際が正しいかどうかには疑問があり,母親が心配するのはもっともなことです。しかしながら,良くも悪くもこれもまた母親の二心であることに違いないのもたしかです。
仮に母親の強い介入があり,二人が分かれることになったとして,やがてはSさんも自分の迷妄に気がつき母親に感謝をすることになったとして,母親は自分の二心をよく承知している必要があります。
本当のところはSさん自身の問題であるのはいうまでもないからです。Sさんが当事者能力を欠いているほどに幼いとすれば,その責任の過半は親が負うべきものだからです。この時点で未熟な心のSさんに代わって,母親が善処策に走るのも愛情の形でしょうが,両者の依存関係はSさんの未熟な心と共に手つかずになってしまうでしょう。
二心を母親が十分に理解すれば,容易には手出しができないはずです。
このように母親(に限りませんが)が子供を思ってすることが,子供の身を護るためだけではなく,親の安心のためでもあるのは当然なのです。そもそも親の安心がなく,子の満足だけがあるなどということはあまりないことでしょう。親と子は強い関係としてあるので,一方の幸福は他方の幸福です,一方の不幸は他方の不幸です。子供を虐げる親は,何らか不幸であるからに決まっています。親の安心が薄ければ,子を安心の道具としがちなのです。
先に上げたBさんの例のつづきです。
Bさんは,「自分の狭い部屋に一人いて,何か牢獄にでもいるような感じがしていました。自由って何だろうと考えましたが,どうしても分かりません」といいます。
Bさんは支配的な母親からも,その手先のような妹からも,怒りをぶちまけるようにして支配してかかる一人娘からも,いまは距離を取っています。Bさんが本気で怒っているのを知っているためと思われますが,母親からも娘からも連絡はありません。
Bさんはいまは怒りの存在と,それが蓄積されてきた長い心の形成の歴史と,母親のまったくの支配の下にあったこととをよく理解しています。だからこそ母親から距離を取ることができています。気に入らないと怒り,罵ることでBさんを従えて来た母親にとって,Bさんは手であり足であり,道具であるに過ぎなかったといえるようです。だから何も連絡を取ってこないというのは,怒りの表現とはいえません。むしろBさんの真剣な怒りに怖れをなしているのだろうと想像されます。
Bさんは幼い時代に,母親への強い恐怖を体験しているだろうと推測されます。
その恐怖心が,母親の二心に対する怒りを徹底して抑圧しただろうと思われます。そのために母親のいかなる態度も,子である自分への愛情に基づくものという意識態度が強固に形成されたのだろうと想像されます。
それは自我が怒りを抑圧することに伴って必然化された,意識の欺瞞化でもあります。
そのような意識構造の下では,母親はいわば全なるものです。
母親への絶対服従の呪縛から解かれるきっかけとなったのは,他でもなく母親自身の更に激しい怒りでした。
Bさんは母親が何といって罵ろうが,自分の使命は母親の側にいて下女のように仕えることでした。
しかし夫のことや娘のことも重なって,Bさんが打ちひしがれているときに母親が放った痛罵に,さすがに怒りを覚えました。そして,「ここ(実家の敷地の一角にある古家)を出て行け」といわれたときに,Bさんは転居の決心を固めました。
母親への怒りの存在を認めたBさんは,ようやく母親の二心に注意を向けることができたのです。いわば全なるものが,自分と等身大の哀れな存在に過ぎなくなりはじめたのです。
自由とは,自我に拠る自由と考えてよいと思います。換言すると自我の自律性に従うということになります。これはいわば自我を付与したもの,人間の上位にあるものの意志に基づくものと考えることができ,内在する主体との関係において展開される性格のものといえます。
一方,現実の母親は,全面依存する赤ん坊には事実上の神といえるほどの存在で,生殺与奪の権利が委ねられているといえます。
先にも述べたように,見捨てられる恐怖から,母親の自我に同一化することによって自我の自律性を犠牲にしたところにあると考えられます。自我が自律性を失い,抑圧性を手放せないままでの人格形成の歴史ということになり,自我は衰退し機能不全化していくのです。それは相対的に裏の自我が力を強めることを意味し,やがては衰退した自我を支配することになります。母親の自我の傀儡であった自我は,裏の自我の傀儡になるしかなくなる必然性をも持っているといえます。
裏の自我は社会性と精神性とを欠いています。その自我が求める満足とは身体的,刹那的であるのを特徴とします。
食物に代理満足を求めます。それは決して満たされることがない欲求であり,常軌を逸した激しさで,餓鬼そのものの姿になるのです。
自己を善導する役割を持つ表の自我に対して,死への志向性を持っている裏の自我は,目先の利欲にかまけたり,狡猾であったりということはあっても,自己の将来などはおよそ念頭にありません。
よい子であった彼らが,強く依存している母親に怒りを向けることがあります。’よい子’によっては決して怒りを人に向けないことも少なくありません。怒りの感情の存在さえないかのような人もあります。しかし怒りの感情がないなどということは考えられないことなので,抑圧の強さの問題と考えるべきです。怒りを向けないという意志的なことではなく,怒りを表出できないのが実情だと思います。いずれにしても,’よい子’は(恐怖心から)感情の抑圧をするのが習い性になっているということなので,怒りのエネルギーはむしろ意識の下層に蓄積されていると考えるべきです。
’よい子’が母親に向ける怒りは,悪しき依存の枠の中にいる衰退した自我が,怒りを強めている裏の自我の支配を受けてのことです。そうすることにより母親を支配してしまうこともあり,これも裏の自我の営為といえるでしょう。怒りを表現することは大切なことですが,彼らのこうした行動は,表の自我の無力を反映したものなので,たんなる怒りの奔出という現象にとどまり,心の成長にはつながりません。
それが表の自我の仕事であるなら,大いに意味を持つことになるでしょう。それは抑圧してきた意識下の分身たちの感情に自我が眼を向けたことを意味します。いわばそれらの分身たちを意識下から救出するという意味があるのです。
しかし裏の自我の営為であれば,単なるうっぷん晴らしの域を出ず,表の自我の無力が浮き彫りになるばかりです。感情が鎮まれば,更に落ち込むことにもなるのです。
不登校の子を持つある母親は,母親自身の子供時代の親子関係の反映もあって,子供に支配的,浸入的な育児をしてきました。それを反省した母親は,不登校に陥った子の理解者であるよう努めるようになりましたが,父親や学校の先生たちは,不登校の子をかばう母親が理解できません。あくまでも’よい子’を求めるのです。かつて母親自身がそうであったように,学校に行ったか,家でだらだら過ごしていないか,親のいうことを素直に聞くか,などなどといったことにばかり注目して,それを守らせるのが本人のためであると信じているのです。それができないのは悪い子なのです。
かつてはこの子も,これらの大人たちの基準によるよい子でした。そのよい子の自我は,親の基準に従う傀儡自我にほかならず,’悪い子’を抑圧してきたのです。その基準の下での’悪い子’は,実はそれほど悪くはなかったはずです。先にも上げたように,単に甘える心を持つことが,抑圧という形で悪い子にさせられてしまうということが起こります。子供らしいいたずら,わがまま,反抗は,いわば子供の自然といえる程度のものが大半でしょう。それを抑圧する’よい子’の傀儡自我は,本来はあってはならない抑圧をすることで,無駄なエネルギーを使いつづけることになります。
しかも自我の自律性が犠牲にされているので,主体との接触がうまくいかず,いわばエネルギーの元を自ら絶ってしまっていることになります。必要なエネルギーの供給を思うように受けられないでいると,表の自我は無気力のままでいるしかなく,悪循環になります。それはすべて傀儡自我が招いた災いです。社会的な存在であることに無気力になってしまった表の自我は,いまや裏の自我の傀儡になってしまったといえるでしょう。主導権はこちらに移った結果としての不登校なので,’悪い子’といえばいえるのです。しかし,その子に’よい子’を求めてどうなるというのでしょう。仮に学校へ行くということが目標であるとすれば,表の自我が,’悪い子’のいい分に耳を傾ける力をつける必要があります。そのためには,周りの大人たちが,この子の自我の仕事に協力していかなければなりません。つまり自我が親の自我の傀儡にならざるを得なかった事情を汲み取って上げる必要があります。そのためには,学校へ行けない事情を理解しないわけにはいかないでしょう。傀儡化してしまっている自我には,自らを省み,問いただす力はないのです。
そもそも’悪い子’が実は悪かったわけではなく,大人の態度にこそ子供の自我を無力化してしまった理由があるのだということを,大人たちが改めて理解しなければなりません。それが行き渡れば,いずれ子供の自我の自律性は息を吹き返すのではないでしょうか。
このようによい子というのは,見方を変えれば,情緒的な満足を断念した子ということになります。それはずいぶん理不尽な話です。幼い子らしく駄々をこねたり,甘えたりしたいと思う心が,母親への恐れを持つ自我によって,片端から意識下の牢屋に閉じ込められるという残酷なドラマが,幼い子の心の舞台で密かに起こっていたに違いありません。
これらのよい子たちの,母親や他人の前でするにこやかで礼儀正しい笑顔の演出は,傀儡自我によるものです。そしてその一方で表面化してくるのは,意識の暗部に閉じ込められてきた分身たちの侮れない勢力です。それらは裏の自我の下に,満たされなかった情緒的な満足を求めて,役に立たない表の自我に公然と反旗を翻すことになっていくのです。
自己を導き,社会的な顔を育成する使命を帯びている自我としては,裏の自我の支配を受けるのは,恥ずかしく,屈辱的な事態です。それは,そのまま自己の喪失,人生の形成の失敗という意味があるからでもあると思います。
過食症の治療の困難は,依存症一般がそうであるように,依存の対象を容易には手放したくないという強固な心理が働いているからです。そのような強い依存欲求の存在は,それだけで小児心性を表していることを証明しているだろうと思います。依存の方向を間違えているとはいえ,激しい力を秘めている裏の自我にいわば捕捉されている表の自我は,本来の依存対象に自らを引き戻す力は既にあきらめかけているようにも見受けられます。治療的に必要なのは,依存の対象を手放しても安心できるほどの治療関係ということになるでしょうが,依存症者の心を現に捉えているのは,悪魔的に魅了する力と破壊力とを併せ持った何ものかであるようです。
人前でのにこやかな笑顔を持つ人格と,一人で過ごすときのなりふり構わない人格と,表と裏に極端に分裂した姿は,表の自我の力の弱さの反映です。餓鬼と化したかのような圧倒的なエネルギーを,裏の心は秘めています。
自我は受け止める力を持つときに,機能の回復が開始されます。餓鬼と化したといえるほどの激しい力を持つ裏の心を受け止めるのは,容易なことではないでしょう。衰弱している自我は,母親との依存関係に殊更の愛着を持っています。それは愛着というよりは,恐怖を媒介とする同盟関係という方が当たっているかもしれません。愛は人と人とのあいだで緩やかな関係を保ち,恐怖は強固な関係を必要とするでしょう。
恐怖心が一役買っている母親とのあいだの強い依存関係に楔を打ち込むためには,どうしても治療的介入が必要だと思います。それができるためには,患者さんの側の’求める心’がそれなりに強くなければなりません。それがなければ,母親との関係にしがみつく患者さんは,治療関係を築く間もなくあきらめてしまうでしょう。治療者との関係がしっかりしていけば,恐怖が愛に置き換わる可能性が出てくると思います。治療関係とは,愛と信頼の一つの形です。それがある程度進行したときに,これは自分の問題だ,このままでは自分に申し訳が立たない,という自己への責任感と贖罪の気持が芽生えるかもしれません。
問題を受け止めることができれば,最初の第一歩が踏み出されたのに等しいといえます。そうすれば,過食行動をさしあたっては承認する気力が湧いてくるかもしれません。たとえ当面は太る恐怖があるとしても,治療関係を通じて愛と信頼との力が回復することができれば,’太っている自分’を許せるのではないでしょうか。自己愛が回復すればそれは可能です。そして他人を信じてよい気力も回復するはずです。他者愛が回復すれば,他人の眼もさほどには気にならなくなるはずです。そういう心が育っていけば,何よりも,心の成長という得がたいものを手にすることができるのです。
自我のもう一つの重要な機能は,境界です。とりわけ意識と無意識とのあいだと,自己と他者とのあいだを分ける境界が重要です。
自我は人間を特徴づける最たるものです。その自我の機構の中核的な位置にあるのが自律性であると考えられ,その機能が健全に保たれることが人間的な自由を謳歌する条件です。自我の機構には,境界機能も含まれていると想定されます。自律性が健全な状態にあれば,境界も健全に機能すると思われます。
境界が意識にとって外界にあるもの,とりわけ他者とのあいだで,そして意識にとっての内界である無意識とのあいだで,有効に機能しているかぎり,自我の自律性が保たれると想定され,これらは互いに相補的な関係にあると考えられます。
男子大学生の例です。
予備校生だったある時期に,幻聴と被害妄想がはじまりました。予備校に入って間もなく,見かけた女性に好意を持ち,接近を試みたことがあり,それが関連してのことです。受診したのは大学に入ってからですが,その大学に,かつて噂を流した’張本人’がいると信じています。’彼とその取り巻き’に恐怖を持ち,大学を辞めようかと思いつめました。薬が奏効したこともあり,危機を乗り越えることができました。しかし,ふとしたときに,妄想的な疑惑が頭をもたげます。その’噂’が核になって,他の人の耳に入ったのではないかというふうに拡充します。また,将来の進路について迷いに迷い,決められないこと,母親になんでも相談し,判断をしてもらうことなどが顕著なときもありましたが,そういうこともしだいに自分で解決できるようになっています。
本人の受診以前に,父親が会社の問題でうつ状態となり通院しておりました。その父親は会社の要職にある人でしたが,妻を大変頼りにしておりました。夫の診療が終結した後に,その妻が,「実は・・・」と長男の相談に訪れたのですが,彼女は自分の対応がまずいのではないかと気にしておりました。夫につきそって来ていたころは,頼もしい妻という印象でしたが,実は大変に不安と混乱に陥りやすい性格のようでした。
本人(大学生)の母親観は,「怒ると怖い。もともと神経質でヒステリックになる。顔色をうかがう癖がついてしまった。・・・こうしなさいと何でもパッパと決めてしまう。それに従ってきた・・・」ということです。唯一の同胞である姉は,対照的に,自分で考えて行動する性格ということです。
母親が長女よりも長男の方を,依存のターゲットにしてしまったという印象を受けます。心根が動揺し易く,不安に駆られ易い母親が,長男によって安定を図ろうとしたようです。自分を助けることができる大人になるように,むきになって仕向ける母親のイメージが浮かびます。それがどうやら仇になったという印象を受けます。どうすれば母親が望むような息子でいられるか,’怖い母親’に,いちいち確認しなければならないほど,自立性を欠いてしまったのでしょうか。
幻聴や妄想が活発な時期がありましたが,経過から見て,統合失調症ではありません。この病的な問題は,境界機能が混乱し易いことを示していると思います。境界機能には,内外の問題を受け止める役割があると考えられます。無意識の勢力を受け止め,意識の領域との境界を画然とすることで,心の秩序が保たれます。自我が心の秩序を保つために,自我のときどきの価値規範に合わないものを抑圧するのは,境界機能を利用していると考えられると思います。
幻聴,妄想に関連して,誰かが自分の悪口をいっているように感じられるとき,外界の他者と自己との境界を画然とさせる機能も混乱しています。(ある女性が,最近,母親が身勝手なことを言い出して父親を困らせるというエピソードを語っていました。一時的にそのことで憂鬱になりましたが,「私は,私だ,お母さんとは独立しているんだ」と思い返して心の安定を回復させることができました。もともとは,こういう状況では混乱して自分を失うことが受診の動機だったのを考えれば,自我の境界機能が有効に働くようになったといえるのです。それは成長の証です)
境界機能が混乱するときは,必ず自律機能も混乱します。この大学生の場合は,関係念慮に苦しんでいたときは,将来の進路を決められず,一途に混乱していました。彼の自我がこのように混乱し易いのは,たぶんに母親の影響があります。母親の自我の混乱の影響を受けつつ成長したためであろうと思われます。
なお,統合失調症の中核型は,人格が恒常的に後退してしまいますが,これは自我が機能不全のレベルを越えて,自我機構自体(生物学的な根拠があると思われます)が何らかの破壊を受け,不可逆的な変化が生じたと考えられます。
自我の破壊という意味では,先の大学生が述べていることが参考になります。病的体験が活発なころに,殺される夢を繰り返し見たというのですが,これは自我が無意識の高波を受けきれず,破壊されかけているという意味に取れるように思います。
心理的な治療では,全人格的なものが,あるいは人間そのものが問われる側面があります。それは,治療者は病者を診る立場ですが,病者の問題を通じて自分自身を問う姿勢が要求されるという意味を持ちます。この心の作業には,問題を解く方程式もあります。いろいろある中で,たとえばフロイトを始祖とする精神分析はその一つです。この’方程式’の価値が他を凌駕するのは,人間の心への洞察の深さにあるでしょう。しかし我々がするべきことは,フロイトの真似ではありません。学ぶべきことは,その精神です。目の前の患者さんにフロイトの方程式を当てはめようとする治療者があるとすれば,彼は反フロイト的な行為をしていることになります。生きている現実に,’方程式’を当てはめて検討してみるのは意味があるでしょうが,’方程式’に患者さんを押し込めようとするのは,治療者がすることではありません。’自分の眼’を持たない心理治療者は,その名に値しません。しかし,’方程式’を無視する無手勝流も排除されるべきです。心を白紙にして臨むことと,学ぶ精神とは別個のことではないからです。学ぶ精神と白紙で臨む精神とを共に持つことが,病める心を前にする治療者の,理想とするべき’方程式’です。
心の問題に,万人が納得する永遠の真理といったものはあり得ないことなので,先達に学ぶ心を持ちつつ,なおかつ心が白紙であるときに,新たな里程標のようなものが立ち上がって見えて来るかもしれません。
人間の心理の問題は果てしなく奥が深く,そこに分け入ろうとすると,終わりのない探索行為になります。心理的な治療はそうした土俵の上ですることになるので,これまた果てしなく深く,複雑で,難解です。そうした困難に耐えて探索行為が続けられるうちに,心的現象の連鎖として,里程標のごときものが自然に見えて来ることがあると思います。やがては,現象的なものを超越したものも視界に現れてくることがあると思います。それらは実証されることはなく,仮説にとどまりますが,一定の意味を持ち,探索行を続けていく上で,勇気をもたらします。症例を積み重ねることによって,それらが無効化されることもあるでしょうが,有用性が更に確信されることもあると思います。
そのようなことを前提にして,主体との好ましい接触が出来ているときに,自我の自律性が健全に機能するものと仮定的に考えることができます。逆に自律性が傷つけられたり,混乱させられたりしがちなときに,自我の主体への接触が不良であると考えられます。
そもそも自我の起源の胚種である段階で,機構的に自律性や境界などが組み込まれていると考えられます。育児の主力である母親によって,自然的な自我の機構がほどほどに保護されつつ成長すれば,いい方を変えれば母親によって著しく擾乱されなければ,自我の中核である自律機能を育てる根が,到達目標である主体にまで伸びていくと仮定的に考えられます。
このように自我の自律性の根が,心の発達,成長につれて主体に向かって伸びていくと想定されますが,主体との接触が好ましいものであれば,親からの自立は順調に進行するといえるでしょうし,接触が著しく不調であれば,何歳になっても幼児のように親の助けを必要とするでしょう。
20代のある女性は,一人でいる時の不安,恐怖が著しく,その心の様子を,「幼いままの自分が,まるで一人で荒野に取り残されている感じ・・・」と表現しております。
自我の自律性の根は自然的に成長していくのがよいはずですが,原初の段階では自我はそれ自身で機能する力はなく,母親による愛情で保護されることが,絶対的に必要です。このことが,人間の心を育てる上で大きな矛盾を引き起こすのです。他者の介入は,赤ん坊の自我の自然的な機能を護るには,’あまりに不自然’にならざるを得ません。自然が全的な存在であるとすれば,人間は能力的に二分の一以下的な存在です。どう転んでも赤ん坊の自我は混乱させられるのです。それに相応して,自我の主体との関係はなにがしか接触不良に陥るのが,人間存在の宿命的現実です。そして,その不良の程度に応じて自我の自律性に混乱が生じ,それに伴って裏の人格が勢力を持つことになります。裏の人格の中核にあるのは,主体との関係を欠いた裏の自我ともいえるものですが,こちらは死に関わるエネルギーと一体化します。死に関わるものの中核にあり,裏の自我の拠り所となるだろうものを,裏の主体と呼ぶことができるのではないかと思います。
表の自我の自律機能の主要な役割は,自己の善導にあるだろうと想定されるのに対して,裏の自我の機能は,自己の善導の破壊,否定という性格を持ちます。従って,悪という性格を帯びています。
これら表と裏の自我の拠り所もそれぞれに違うということですが,それは別個に存在するというよりは,一つの主体の中の二つの機構とでもいうべきものではないかと思われます。つまり生と死は,生命体にはすべて起こることですが,中でも自我を持つ人間の特徴は,
単に生物学的に生と死があるのにとどまらず,精神的な意味をも併せ持つというところにあります。
心の外界には自然がありますが,これは宇宙にもおよぶ無限大の広がりを持ちます。また限りある人の命という観点からすると,永遠の時間と共にあるといえます。これら無限というものは,人間には概念と感覚の対象としてのみあり,人の身体にも心にも実態としては存在しません。
心の内界にも同様の無限の属性を持つ無意識界があり,これも外界の自然と一体のものと考えて然るべきです。どうやら無限の属性を持たない人間の精神に特有なものとして,現象として現前する事実や観念は,二つの極性に分離して現れる傾向があるといえるようです。外界の自然と内界の’自然なる無意識界’もその一つです。それは自我に拠る人間存在ならではの現象的な事実です。そのような特性を持つ人間の自我に対応して,自我の母体である’自然なる無意識界’にも,生と死に関与する二つの機構が存在すると仮定することができます。それらは人間にこそ別種のものとして存在しているように見えるものの,自然の様態としては一体のものに違いありません。
生と死は本来は一体のものと思われますが,自我を持つ人間に特有のこととして二極に分化し,互いに逆方向のベクトルを持つものとして現前しています。生は自我の誕生であり,意識という光の世界のはじまりです。そして,それは自然からの乖離でもあります。死は,意識という光の消滅であり,世界の暗黒化です。それは同時に自我の終焉ないしはお役ご免を意味します。そして,それは自然への帰還です。生は明るい光の中にあり,死は暗黒の中にありますが,それはあくまでも意識の存在が前提となっていえることです。
人間の誕生は自我の誕生です。自我が生まれることによって光が生まれました。そして光が生まれたことによって闇が生まれたのです。光は生の世界です。そして闇は死の世界です。人間は生きながらにして,死を併せ持っているといえます。
自我の誕生と共に自然から乖離したのが人間です。自我は生きる方向に向けて光の世界を構築する拠り所です。そして光を得ることによって,生の対極に死が布置することになったのです。生きるという方向で自己を形成していくのが,いわば人間の自然的な使命であると思われますが,そのことの裏面である死は,生きる機能に不具合が生じれば生そのものを回収しようとするもののようです。
寿命がつきかけたときに,「これでいい,これでいい」とつぶやいたという哲学者の話がありますが,回収作業を開始した死に自己を差し出す心を語る言葉として,人間の生き様の理想を見る思いがします。つまり死もまた,人間にとっては一つの目標です。いかに生きるかということは,いかに死ぬかというのとほとんど同義です。死は,単なる生の否定ということではないと思います。死は生に既に内包されており,いかに死ぬかが人間の課題です。自我が人間的な事態そのものであるとすれば,死は自然そのものの人間的な事態です。そういう意味で,死は裏の主体といえるのだと思います。
身近な者の死が悲しいのは,生を否定する力としての死が,生きよう,行きたいとする人の心を日常的に脅かすものであり,その直接的な事実の現前に立ち会うからです。死は生の脅威です。生きるためには喜びが必要です。それは意識という光の下でくりひろげられる祭典です。その喜びを意識と共に永遠に回収されてしまうのが死です。それが悲しくないわけがありません。生きる喜びをそれなりに楽しんできたあるとき,「もう,そろそろいいだろう」と,意識という舞台上の照明を一挙に消されてしまうのは残酷な話です。回収する側は,「そんなことは初めから承知していたはずだ」というでしょう。それは確かにそうなのです。回収する側が,舞台の照明の点灯をも含め,一切の権限を握っているのですから,文句をいってもはじまりません。人間としては,いずれにせよ与えられたことを受け止める以外に手はありません。人の力を超越しているなにものかが,こういう意味不明の舞台を提供しているのですから,なにか我々には及びもつかない深い思慮が働いているのだろうと考えるのが関の山です。どうやら人間が第一等に偉いわけではないのは確かですから,そうであれば,安んじてその第一等者に身を任せるのが分というものです。
それとおなじ理由から,つまり第一等者によってよりよく生きよと命じられているのですから,あれこれいわずにおのれの分に従って,謙遜に,よかれと信じる日々の営みを大切にし,自分らしい人生の創出に励むのが最善ということになるのではないでしょうか。
ということで,自我と意識の光を頼りに生きる我々としては,意識の否定である死の影は大変な脅威ですが,死というものの存在も生と同じくらい重要であるのは疑いありません。ですから潔く死の意義を積極的に評価するに越したことはありません。
そういうわけですから,自然のものである死が人間の脅威であるにしても,人間の敵というわけではありません。人間の敵は他でもなく人間自身のようです。人間は人間によって,相互に自然的な素地を混乱させ合い,それぞれの自己が,自己ならざる自己に迷い込むように仕向けあっているかのようです。困難な人生を,共に生きるものとして相互に助け合うのが筋というものでしょうが,不幸の渦中にあるものがしばしば意地悪であるように,大小の意地悪を,かけがえのない我が子に対してさえしてしまうのが,残念ながら我々人間の愚かな性であるようです。そのように,悲喜劇を繰り返しつつ一生を過ごそうとしているかのように見えます。
迷妄の渦に巻き取られる程度が甚だしいときに,生よりも死が関心事になっていきます。つまり,よりよく自分自身でありつつあるとき,生は大きく途を開けてくれますが,自己ならざる自己に迷い込んでしまうと,死が手招きしはじめるのです。前者が表の主体と表の自我の蜜月がはかられているのに対して,後者は裏の自我が表のそれを圧倒する力を持ち,裏の主体との接触を深めてしまっていることの表れといえるでしょう。そうなると,いわば死の極北から吹きつける風が,心のさまざまな不調,病気をもたらし,あるいは悪化させ,あるいは生きる意欲を失わせたりということも起こるのです。
人間が,自己の存在条件に他者の存在を前提としていることは,自我に拠る人間の完全性(自然の属性)の欠如を表していると考えられます。それは先にも述べたように,もろもろの事実や観念が二極に分化して現前するのが,人間の認識機能の大きな特徴であり,その一つの表われということです。自己と他者が合体して完全になるのが,自然的完全を志向する人間の理念といえるようです。そのように考えるのは,人間には,自他が互いに相手を求め合う無意識的な心の叫びがあるように思われるからです。その心の叫びは自然的な合体を求め合うようであり,現実に恋愛関係にある男女において,そういうことが垣間見えているように思われます。それを志向する心は,純度の高いものなので,実際には,むしろ他者は幻滅を与えるだけになるのでしょう。
他者は,自己の存在にとって必要不可欠な存在です。それは外部にある他人との関係が不可欠ということでもありますが,それにとどまらず,その根拠として自己の存在構造に他者が組み込まれているということでもあります。
自己の存在構造は,自我機構を拠り所としていると思われます。従って自己の存在構造の原基は,自我機構にあると考えられます。それらを敷衍すると,自己の中に内なる他者があり,それは当然,他者の中に外なる自己があることを意味します。それがあるために,現実に外部に存在する他者への親しみを持つことが可能になるのです。しかし一方では,他者は自己ならざる者でもあるので,疎隔感を持つことにもなります。人は孤独であり,孤独でないという一見矛盾した存在ですが,それは人間が全ではない存在であることの一端といえるでしょう。
自己愛と他者愛は相互的なひと組の関係にあります。自己愛が健全であれば,他者愛も健全のはずです。自己を愛する心の原基は,自我機構に備わっていると考えられますが,それを賦活し,機能的に発達させるのは,他者の中の特別な他者である母親の愛情によってです。私なる乳児を愛情をもって認めてくれている母親の受容力が,乳児の自己愛を育みます。そして,そういう豊かなものを与えてくれている母親に愛情のお返しをするのです。そのような相互的な力動関係が自我の自律性の根を護り育て,内なる主体へと根が伸びていく素地を作るのです。
逆に,このような豊かな愛情の関係で結ばれなかった親子の場合,乳児の心の自己愛は屈折したものになり,他者に対しても屈折した心を持つことにならざるを得ません。
恵まれた自己愛を持つ心の持ち主が,他者の中に他なる自己を感じたときに,他者への愛情と信頼が生まれるでしょう。自己の内部の他者(内なる他者)と外部にある他者の内部の自己(外なる自己)とが,それぞれに活性化され,結合的になったと考えられるのです。そして他者が単なる他性であるに過ぎないとき,他者は無縁の存在です。それらは状況によっても違うはずです。異郷の地で心細い思いをしているときに同胞を見かけると,日常の世界では味わえない親愛の感情を持つこともあるでしょう。道端で転んで怪我をしたときに,かけつけてくれる人があれば,恩人のように感じられるでしょう。
また,屈折した自己愛の持ち主が,他者の中に自己を感じたとき,容易には心を開けないと思います。自己愛の光りがとばりの中にあるように感じられている人は,他者に対して一様に距離を保ち,周囲の人には冷淡に感じられることもあるでしょう。
孤独であることを,人は一般的に嫌います。実際,一人遊びが多い幼い子は,将来が案じられる理由があるのは確かでしょう。
子供の場合,遊びを楽しむことが大変重要です。子供は生のエネルギーにあふれているので,元気がふさわしいのです。そして遊びを通じて自分を全身で表現することができるからです。時には喧嘩もするでしょう。喧嘩にも自己主張,自己表現の重要な意味があります。動物は,仲間との戦いを通じて群の中の自分の力,位置を知ることができ,仲間とうまくやっていく知恵を得ます。人間もおなじです。遊びの中の喧嘩で,人との関係の中での自己調整をはかることができます。そこで何を会得するかは,個々の問題ではありますが。いずれにせよ喧嘩という真剣な行為を通じて,自分を知り,他者を知り,怒りを体験し,対立する緊張を知り,断裂を味わい,和解する感動を覚えます。それらは大人になっていく上で,得難い体験になることでしょう。
まだ自分で自分を支える力を持たない子供にとって,孤独には危険な厳しさがあると思います。というのは,孤独には,死の極北から吹きつける風にさらされるという意味があるように思われるからです。心を凍りつかせるほどの力を持つ孤独は,子供には耐え難いものがあるでしょう。それは心を育てるよりは,破壊する方向に仕向けるかもしれません。
また他の元気な子供たちは,これらの孤独な子の理解者になるよりは,迫害者になる可能性があります。生きるエネルギーにあふれている子に,死の北風に震えている仲間への同情を要求するのは,一般に無理なことだろうと思います。しかし,これらの元気にあふれた子供たちにも,死の予感がないとはいえないはずです。それがあるからこそ,その気配に憤りを覚え,叩き潰すか,無視するかしたくなるのではないでしょうか。もっとも大抵の元気にあふれた子供たちの口から,その通りだという言葉は得られそうにありませんが。
いじめられっ子たちを護るのは大人の役目です。生きるエネルギーにあふれた子達に,そういう役割は期待できないように思います。大人たちが役目を果たしている姿があれば,それでいいのではないでしょうか。
孤独な子供たちは危険な状況にあると考えるべきですが,注意を要するのは,彼らを危険に追いやるのは,”元気な子’たちの悪意です(それ以上に親の不理解が問題ですが)。それは無意識的なものかもしれませんが,悪意の根底には死への恐怖が潜んでいると思われます。’元気であること’は子供にとって大切ではあるでしょうが,そこには生の裏面である死を意識しないで済ませるという意味もあると思われます。’元気な子’の悪意は,恐らく元気を沮喪させる影を持つ子に向けられます。それは本能的なものだと思います。影は死の領域に属するものです。それは’元気’を挑発するのです。そして彼らの悪意によって疎外される孤独な子は,自分自身の中に新たに燃え上がる心の炎が生まれ出て,自分自身を励ます力となることができるのでなければ,更に一層,死の極風が心を凍りつかせることになる可能性があります。そうなると,著しい悪しき依存から抜け出すのは容易なことではなくなると思います。
幼い時に情緒的な満足を覚えることは,その後の性格形成に重要な意味がありますが,しかし,それだけでは足りない何かがあります。人とうまくやれるということは,集団の中で生活をしていくことになる子供たちにとって,是非とも身につけていなければならないものでしょう。’集団の中にいる仕合せ’といったものは,大多数の者が理想とするものだと思います。そこには,しかしながら,’集団への逃避’という別な側面があります。何からの逃避かといえば,死の脅威ということになると思います。そういうことは意識にのぼることがあまりないでしょうが,集団依存的な一般的な市民の盲点だと思います。そうであるとすれば,先に述べた乳幼児期の情緒的な満足が性格形成の上で重要だというのは,括弧つきでということになるのでしょう。つまり市民一般のもう一つの顔である集団依存は,守りの姿勢を変えるのを難しくさせる要因になります。この意味での保守性は,特に日本人では個性の否定に傾きます。世間体を気にするということにもつながると思います。これらは育児の上での干渉にも通じる問題です。
これは,いわゆるペルソナの問題です。
C.Gユングは,次のような意味のことをいっています。
人間は,誰もがしっかりとペルソナを身につけていなければならない,しかし,それは自己ならざる自己の世間向けの顔である,それが発達し過ぎると,自己の実体が形骸化するだろう,中年期以降に,それが問われることになるだろうと。
このことは,社会的な存在である人間は,社会の中で人と調和してやっていけるための人格的な修練を欠かすわけにはいかないが,しかしそれは自己本来のあるべき姿とはまったく別問題であるということです。
世間的な成功を収めた人は,会社なりの組織にいるかぎり他人から評価され,それに助けられて自分の価値を支えることができるでしょう。しかし定年退職になって会社を離れると,いわば支えを失うことになります。それをどこに求めるかが問われます。しかしどこにもそれが見当たらないとすると,晩年が過酷なものになります。
ペルソナを鍛える一方では,自己と人生について思いをめぐらせて,集団の中で調和していることの意味と限界を理解しているに越したことはありません。そうすることで,集団への依存から,ある程度自由でいられることが可能だと思います。それは自己自身との関係をしっかりさせ,重心の移動を図る心の用意をはかっておく意味を持ちます。
集団の中で平和に過ごすことができる穏やかな心は,何よりも人間にとっての極限的なものを回避していられるという意味があると思います。それはそれで必要なことでもあるでしょうが,回避という姿勢は問題をはらんでいるのは確かでしょう。後々,いま述べたような自己の実質の空洞化に悩むということもあるでしょうし,他者に対しては無意識的に同族的,均質的なものを求め,排他的にならざるを得ないという別の顔を持っているのも否定できません。どんなに’良い人’でも,疎外されて傷ついている部外者には,結局のところ冷淡,非情であるしかないのです。
人生を創造し,人生の大問題に取り組むことになるのは,’元気な子’たちに疎外され,辛い時代を過ごした子供たちであるように思われます。彼らには,死の極風にもまれ,’人生に遭難する’危険を切り抜けてきた力への自負があると思います。人生そのものを受け止め,直視しようとすることがなければ,芸術も思想も成立しません。彼らは孤独であることを恐れないと思いますし,’明るく群れる’ことに価値を求めることはないでしょう。孤独を恐れない者には嘘は通用しないのです。逆にいえば,一般には,人間にとって重たすぎるものは回避するという,一種の嘘があるといえると思います。
彼らにとっては,自己自身との関係が最も重要になるので,他者との関係は,それぞれの仕事を通じた間接系になるだろうと思います。偽りの関係は無意味なので,真の友人以外は不要なことかもしれません。彼らにふさわしいのは人類愛ということになるのでしょうか。主体との関係がしっかりしていれば,自我の自律性もしっかりしているので,極風にたじろぐこともないように思われます。
こうしたことを考慮に入れると,先ほど述べた乳幼児期の母子の好ましい愛情関係について,つけ加えなければならないものがあることになります。
母親の愛情が重要な意味を持つことは強調されて然るべきですが,これには例外があります。俗に,「天才と狂気は紙一重」というように,長じて大きな才能を個性的に開花させることができるのは,むしろ幼少時に母子関係に恵まれていたとはいい難く,何かと問題があった生い立ちの子であるようです。「艱難汝を玉にす」という諺があります。幼いころに集団になじめない’変わった子’が,孤独の中で極風にもまれて,創造的な自己を創出する場合があります。それは本来的な自己の達成ともいえることです。そういうことが可能であるためには,孤独に耐える強い自我に恵まれている必要があると思います。彼らは,人生の早い時期に自我の自律性が危機に瀕したものを,自力で取り戻すことができたといえるのでしょう。このような場合に,自我は主体と最も望ましい関係にあるといえると思います。
このことは人生の難しさを教えてくれます。いわば’人生に遭難しない’ために,幼いころに母親を中心とした近親者たちから,豊かな愛情を与えられることが望ましいのですが,それは一面では,’集団への依存’という日常のぬくもりの中に人を安住させがちです。それがいけないということもないでしょうが,人生を回避している姿といえるのも確かでしょう。人が自己を本来化させるためには,孤独を引き受ける力が必要です。
一般的な市民にとっては,隣人愛が最も価値があり,美しいものでもあります。極風にさらされることから身を守るために,他者は重要なパートナーです。愛情の親密な関係で結ばれた他者があれば,日常はどんなに救われ,励まされることでしょう。災厄や不幸に見舞われれば,みんなが協力して助けてもくれるでしょう。それで十分だともいえるのかもしれません。
平凡な市民と非凡な個性派を分けるのは,他者への依存の仕方の違いといえます。他者への依存の比重が高くなれば,その関係に縛られて自由度が低下せざるを得ません。その分,いわば自己の重心は自己自身の中にはなく,何かの都合で自己の軸が傾いたときに,態勢を回復させるのに難渋することもあると思います。
一方,非凡な個性派は,他者との関係が比較的ゆるやかで,それだけに自由度が高いと思います。自己の重心がいわば自分の中心にあるので,ストレスで軸が揺らいでもダルマのように容易に姿勢を回復させることができるようです。
それは,極風にもまれてきた人と,それを回避してきた人との違いともいえるでしょう。
しかしながら,場合によっては命がけで人を救おうとするのも,隣人愛に富んだ人たちのようです。人間の価値の基準は簡単にいえるものではありません。
隣人愛の性格の一つの例を,シェクスピアの戯曲,「オセロ」に見てみます。
ムーア人の将軍であるオセロ(黒人)は,貞淑な妻,デズデモーナ(白人)を大変愛しています。美しい妻に満足しているオセロは,仕合せな日々を送っています。ところが忠臣と信じている部下のイアーゴー(白人)が,デズデモーナが不貞を働いていると吹き込みます。妻を信じようとして懊悩するオセロにとどめを刺したのは,一枚のハンカチーフでした。それは二人のあいだを繋ぐ愛のしるしとして,オセロが妻に,「決して失くさないように」と念を押して渡したものでした。それをイアーゴーが盗み取り,動かぬ証拠としてオセロの心を揺さぶります。嫉妬の激情にかられたオセロは,ついに最愛の妻を殺してしまいます。そして,やがて真相を知り,自らも命を絶ちます。
オセロが妻を愛する心情は一途なものであり,生きる喜びそのものです。しかし当然のことながら,貞操を疑ったときに暗転します。そのように仕向けたのは,悪魔的な心を持つ者です。暗転したオセロの心は,死の方向になだれ込んでいきます。そして最愛の人を殺し,自らも絶望して死を選びます。
オセロにとってデズデモーナは生きる意味のすべてに等しいものでした。高い愛と信頼への代償のように,絶対的な貞淑を求めました。表の心がそのようなものであるとき,心の裏面がどうであったかといえば,悪魔であるイアーゴーがつけ入る隙があったということが証明しています。つまり心の闇には,猜疑,不信など非愛の心が拭い難く潜んでいたということです。山が高ければ谷も深いのです。デズデモーナの気高い心を信じようとした分,一方ではそれを疑う心が意識を悩ませていました。それ自身が悪魔と手を携えて出番を待っているといえます。イアーゴーは,この無意識の中に潜むもの,そのものです。そして悪魔は黄泉の国の住人です。
デズデモーナへの愛の光が,オセロに生きる喜びを与えていました。しかし愛という光を求める心が強すぎたことが,オセロの心の闇の深さを物語っています。この戯曲で,黒人であることが白人へのオセロのコンプレックスを,象徴的に表しているようです。
隣人愛は,オセロのように純度の高いものの要求であるとき,自ら崩れ去るしかないのです。デズデモーナは貞淑の化身として描かれています。このドラマは観念的に過ぎるきらいがあるのですが,デズデモーナが生きた魂の持ち主であれば,オセロ的な愛の要求に耐えられないでしょう。離別するか,浮気でもするしかなさそうに思われます。オセロは滅びるべくして滅びたのです。滅ぼすべく誘ったのは外部にあるイアーゴーですが,それを可能にさせるほどに,オセロの内なるイアーゴーは勢力を強めていたのです。
隣人愛は人類愛のように純度が高いものであっては,ある意味ではならないのです。それは戦略的でなければならないといっていいと思います。不貞や欺きや裏切りや不公平などが,少々のことなら認め合わなければ成り立たないと思います。程度の問題でしょうが,そういうものを内に秘めて,なおかつ仲間として肩を組み合えるのでなければ仲間にはなれないでしょう。愛は少々のことは許すということも含んでいます。
生と死,愛と非愛の二者関係の両極の中間にあるのが人間存在です。従って愛は自然発生的であり,かつ世俗的,打算的でもある相対関係の中にあるといえます。
生と死の両極は,しかしながら,同等,同格ではありません。人間は生の極と全的な結合をすることは決してありませんが,死の極への全的な結合は,必ず起こるのです。死には,生という意識の光を回収する役目があるようです。あたかも人生は一つの作品のようであり,魂のこもった作品の制作が見込めないと分かったときに,人生そのものを回収する作業が始まるかのようです。それは同時に,主体との関係がほぼ断たれたことを意味すると思います。その撤収作業の主役が悪魔的な力です。言葉を換えれば,この悪魔は裏の主体ということになるのでしょう。
人間は,死を決意して自死にいたることができるでしょうか?寿命がつきたような自然的な死は別として,死を決意したときに,悪魔の回収作業が最終段階まで進んでいるようにも思われます。ですから死は決意してできるというよりは,回収作業に身を任せるというほうが事実に近いのではないのでしょうか。自死の気配を強めている人に,人の愛がどうしても届かないときには,そのようなことが起こっているのかもしれません。
表と裏の心のあいだの境界は,いうならば関所のようなものと考えるのが合理的なように思われます。裏の心は無意識界に勢力を張っていることになるのですが,表の自我は関所を通じてそれとの交流をはかっているというふうに考えることができます。
無意識の世界では,最下層で身体との直接的な関わりを持っていると考えられます。精神のエネルギーの源泉は身体にあると思われますが,精神と身体の関係は相補的です。一方的に心が身体からエネルギーを補給されているということではなく,心が健全に機能していれば身体にも影響が及び,身体も健やかでいられるわけです。
身体と接する層を最下部に,自我の層を最上部に置くのが,心の機能的ー構造的なヒエラルヒーです。そのような構造が仮定的に想定されるので,境界もまた,それらのあいだにあると仮定するのが合理的ではないでしょうか。
C.Gユングによって,身体と接する無意識の最下層を普遍的(あるいは集合的)無意識と呼ばれ,その上層の自我の領域と接する無意識層を個人的無意識と呼ばれております。それらのことは十分に説得的だと思います。
精神の力動総体は,自我の働きに決定的な影響を受けます。自我は,自己を指導する立場にあります。そして社会的,対人的な関わりの直接的な責任者の立場にあります。しかし自我は心の全体の主体ではありません。自我の働きがどう評価されるかは,内在する主体を拠り所とするに足りる働きをしているかによって決定されるでしょう。自己に対して責任を負う自我が十分な働きをすれば,主体との関係が良好に保たれていることになるので,いわば全身にエネルギーが行き渡るのです。そのように自我が望ましい働きをしているとき,境界での検閲は柔軟であると考えていいと思います。つまり現状のままで殊更の問題はなく,仮に,たとえば夢を通じて無意識からの何らかのメッセージがあれば,それを受けて前向きに検討することができる等々という意味でです。
自我の検閲が厳しくなるときは,自我が何らかの脅威を受けているときでしょう。それが外部に問題があってのことであっても,無意識が活性化するので,緊張を強いられます。自我に余裕がなければ,無意識の圧力を受けることになりますので,不安やいらいら感などに苦しむかもしれません。そういうときは,一時的に無意識との関わりを停止しようとするのも自我の仕事です。
自我の機能が衰退していると,無意識の支配を受けます。社会との関わりを持つのは表の自我の役目なので,衰退した自我は相対的に勢力を強めている裏の自我の傀儡と化し易くなります。
また自我の混乱と衰弱が甚だしいと,裏の自我が表のそれを無視して,直接的な行動に出ることがあります。解離性障害といわれるのは,そういう心の現象です。
更に自我の機能が不全化すると,境界機能も不全化して,深い層の無意識の内容が意識の中に侵入するという事態にもなります。精神病といわれる諸相は,そのような問題です。
関所がまったく封鎖されることはないでしょう。そういうことが必要なほどに無意識の力が増大しているときは,自我の境界機能はむしろ破壊されてしまう危険が増大するだろうと思われます。統合失調症のような事態が,一時的に現実化することは,状況によっては誰にでもあり得ることです。いずれにしても自我が柔軟な強さを失うと,境界の検閲機能も頑なになり,無意識の圧力を封じようとすることはあると思います。そういう時は,感情が表に現われなくなります。
関所での検閲を厳重にする必要があるのは,個人的無意識層にあるものが,単なる過去の体験群の集積にとどまらないからです。抑圧という心的活動は自我の価値判断に伴うものですが,それは自我に与えられている能力が限定的であることに帰着します。自我が抑圧するものには一定の傾向があります。自我がいわば神経質になっているものが抑圧の対象になり,その傾向の原点は乳幼児期にあると思います。人間が自我に拠る存在であるということは,自然的に心を形成することが不可能であるという意味を持ちます。しかも自然的であることが常に目標になるという矛盾した性格を強いられております。自然的であることが不可能である最大の理由は,自己なる存在が他者の存在を前提として可能であるということです。他者の介入によって自然的な心の営為が混乱させられ,それを改めて自分の力で自然的な方向に自己を整え直す,それが人生の目標であるという観があります。ここに人生の意味と無意味が交錯しており,人間が存在する理由の不可解さがありますが,これらのことは,あくまでも我々人間が人間的に答えていく以外にないことです。そもそも,なんといっても人間が存在する理由を人間自身が持っていないのですから,その根本理由をいくら詮索してもどうなるものでもありません。
自我による抑圧という心的行為には,他者の介入によって強いられたという側面があります。その始原的なものの過半は,原初の他者であり,最も関わりの深い母親との関係において生じると考えていいと思います。
たとえば性的な行動は,動物ならば自然なものとしてあるのですが,人間は抑圧します。それは自我を持つものと,持たざるものとの違いのようです。それは少なくとも一つには,自我に係属していると考えられる自己と他者とのあいだの境界によるのではないでしょうか。性的行動には,攻撃という側面があります。人間は人格的な存在なので,性行動が人格への攻撃という側面を持つのは否めません。境界を護るということは,自他の人格を尊重する意味を持ちます。自我機構に係属すると思われる境界機能は,生物学的な根拠を持っていると思われるので,性行動の抑圧は単なる文化的なモラルの要請以上のものがあると思います。しかし強すぎる性への拒否感は,他者(多くは親)の何らかの介入による自我の反自然的な性格傾向によると思います。
性がタブーになりがちなのは,その欲動の強さと攻撃性に関係すると思います。それは他者との関係を結びつける力にもなり,関係を破壊する力にもなります。従って,その本能の無原則的な発動は自我によって制限されます。そのときに自我の境界機能が意味を持つのです。その欲動の強さは結びつける作用の強さでもあるので,愛し合う男女のあいだでは好都合にはたらく一方,男女それぞれが異性を支配する本能的な手段にもなります。他人の性行動が気がかりになったり,不快感を持ったりするのは,欲動の魔力を扱いかねる複雑な心の動きがあるからでしょうか。
乳幼児が甘えを抑圧するのは,性の問題とは異なった意味があります。幼い子の甘えが母親の怒りを誘うのは,どういうときでしょうか?母親が情緒的に満たされているときに,幼い子の甘えに不快感を持つということはなさそうに思います。むしろその逆に,満たされていない情緒が拒否感を持つ理由になるのだと思います。自分の幼い子の甘えに怒りを覚える母親は,特別な状況にいるのでなければ,自分自身がおそらく乳児のように甘えたいのです。幼いころに甘えを満たされなかったという感情が働くのです。無意識にある満たされなかった情緒的諸欲求が自我を支配して,我が子の甘えを拒否するように,怒りをこめて要求するのでしょう。母親自身が幼いころにその母親からされたのと同じことを,我が子にすることになります。
全面依存の身である幼い子の自我は,ときによっては生き死にに関わる恐怖で母親の怒りを恐れると思います。
幼い子の甘えが,性的な欲求のように,母親に対して攻撃的な側面を持つとは考えられないことなので,この問題に関して自我が境界機能を必要とする意味はなく,一般的に甘えがタブーになることはありません。
甘えなどの情緒的なものが母親によって満たされることは,健全な自己愛と他者愛の育成に重要です。自律性の涵養という意味でも同様です。それは自我の自然的な機能が,母親によって護られたことにもなります。甘えを封じられることは,これらの意味がまったく逆になります。自然的な自我の機能が母なる他者の介入によって混乱させられ,自我が自律的な機能を捨てて母親に取り入ったという心の動きが抑圧と呼ばれています。幼い者の自我がそのような非常手段を取らなければならなかったのは,必ず恐怖と不信が働いたからだろうと思います。間違っても,母親が大好きだから母親に取りすがったなどということではありません。
このとき自我は母親の怒りを恐れたと思います。そして,自分が大切なものではなく,愛情に値しないと考えているのではないかという恐れと不信を持ったと思います。乳児にはそれに対して怒りを持つ理由がありますが,母親に向けるわけにはいきません。その怒りは,母親を怒らせる理由になるとおそれた甘えたい心に向かうのです。怒りをこめて,甘えたがる心を抑圧するのです。
このように,抑圧には,抑圧を蒙る側からすると不当であるという性格があります。ですからこれらの分身たちは,怒りによって抑えられるのですが,怒りを蓄えつつ無意識下に抑圧されているともいえるでしょう。
抑圧には,自我による死の宣告という性格があります。それは,自我は生の方向で機能するものですが,その折々の自我の判断が,ある種の体験が受け入れ難いとして無意識の闇に葬ったということを意味するからです。怒りはそれに伴って生じる感情です。つまり怒りは,死の方向で活動するエネルギーです。
自我のよい働きは生の方向で,わるい働きは死の方向で,心を動作させるといえます。また自我は,どう頑張ってみても半分しかよいことをできないともいえます。それは,自我には自然的な機能を大切に護るようにという大命題があり,それを達成するために他者の介在を必須のことして与えられているというふうに見えるということです。しかし自己と他者は合わせて’全’となるのは理念の上でのことで,現実には’全’どころか,他者は自我の破壊要因にさえなりかねません。どう転んでも’全’になりようがない人間は,それは永遠に彼方にあり続ける命題です。そして現実には自我の仕事としてではなく,自我の終焉として,死という’全’の世界に回収されるのです。自我の仕事は永遠に未完であり,悔いを残すことなく終焉を向かえるのは,すこぶる難しい話です。しかし’第一等者’ではない人間は,人間の知恵のおよばない’第一等者’にすべてを委ねるのが分というものでしょう。
母親との関係で,甘える心が自我によって抑圧されるとすると,甘えを封じる力が怒りです。それは母親の怒りが自分に向けられるのを恐れる自我が,扱いの厄介な甘えに対して怒りを持つということでもあります。本来は甘える心を自我が受け入れることで情緒的に満たされ,生のエネルギーを増幅させることができるはずですが,いわば母親の怒りに迎合するように,怒りをもって無垢の分身たちを葬り去るのです。受け入れられなかった分身たちは,悲しみ,寂しさ,虚しさなどの感情と共にあるでしょうが,そのエネルギーが強いだけに,境界を超えて自我に圧力を加えてくることになります。更にそれを強く抑圧することによって,自我は硬直したものになっていきます。これらのことは,エネルギーの流れの自然法則に反した,人工的なともいえる動きです。他者が介入することによって,心の自然な流れが乱されるのです。
怒りは,この例に即していえば,甘えを封じるために動いたのですが,意識の地下に封じられているものたちに所属する感情ともいえるでしょう。
破壊的なエネルギーである怒りは,死の方向で奉仕するものです。そして意識の地下に葬られているものたちは,怒りによって地下に繋ぎとめられているといえます。これらの分身たちは,自我が自由になり,自律機能を回復させて,改めて救い出されるのを待っています(それを実践するのが,分析的精神療法です)。しかし救出されないでいる状態が長期化すると,分身たちは怒りのエネルギーと一体化して,理不尽,不当な目にあっているものらしい恨みや羨望の感情に変質していきます。
抑圧は,すべての人に起こる人間に必須の心的過程です。そして常になにがしか不当であり,自然の心的機能を歪めます。その矛盾は人間に苦悩を与えます。不当な抑圧の比重が高くなっていくとすると,それは自我の弱さの反面ということでもあり,ますます自我の衰弱を招きかねません。しかし自我に強さがあれば,自分が知らずにしてしまった過度の抑圧が招いた,いわば不祥事を悩む力を持つことも可能です。意識の地下の分身たちの反攻を受けて,矛盾と苦悩に耐えながら,いつか,それらのエネルギーを己のものとしてしまうことも可能です。芸術作品には,このような心の過程が働いていると考えていいと思います。
分析的治療の経過中に,不用意に抑圧が解除されると,封印されていた怒りが,意識の表面に躍り出てくるような混乱が起こります。それが治療者に向けられるとき,治療者が抑圧,迫害の張本人であるかのような一種の取り違えが起こるのですが,やがてその怒りが治療者によって受容されるときに,患者さんの自我が抑圧者から受容者に変貌することができるのです。自我は更に自由になり,自律性が回復することになります。こういうことも考え合わせると,怒りは封印のために機動しただけではなく,受け入れを拒否された無垢のものたちと共にあるという側面があるのが分かります。治療者に向けられた怒りも,破壊的に作動しています。治療者が思わぬ怒りを向けられてあわてるとすれば,治療者は怒りの犠牲になるかもしれません。具体的に暴力を受けるとまではいかなくても,治療関係の破壊の危機に立ち至っているといえます。治療者が治療者としての節度を護れない困難な状況では,治療者・患者の関係は,迫害者・被害者の関係に変貌します。
しかし治療者が冷静さを失わず,治療者の立場を護ることができれば,怒りをもって破壊的な動きをした分身たちが,自我に受容されたに等しいことになるのです。それに伴って患者さんの自我も,自律性を回復する方向で動くはずです。それは既に生の動きです。死への志向性を持つ怒りに充当されていたエネルギーは,生の方向に志向する自我の自律性に所を換えることになります。つまりエネルギー自体は同一のものであり,自我の動きに伴って生と死とどちらかの方向に動くのです。怒りは死への志向を持つものの,生への方向で自我が力を回復させたときに,お役御免になるのです。
このことを考え合わせれば,怒りには自我の姿勢を「どやしつける」意味があるのが分かると思います。自我に,「受けて立つ」気があれば,怒りによって自我がよい仕事をすることができるのです。
一般に,つよい感情を潜在させてしまっている抑圧する自我は,特定の人や物へのしがみつき的な依存が強くなっています。それは必ずよくない依存です。過食症もその一つですが,依存症一般にそういうことがいえます。
依存症の異常なところは,食べることなり,飲酒なりが,人生の関心事のほとんどすべてと化していることです。そういうことは一般の人には理解に苦しむことです。
それらはいうならば死をかけた依存ともいえます。そうすることで必死に生につながっているのです。それは自我が,裏の自我にまったく支配されている姿ともいえます。その依存の手を放すと,死の世界にまっさかさまという恐怖が支配しています。
過食地獄に長年のあいだ苦しんでいるある女性に,次のような意味の問いかけを試みました。
「過食は自我が著しく衰弱して,裏の自我に支配されていることに伴うものと考えられます。言葉を換えれば,過食は,死の世界に属しています。一方で,会社へ行っていることや,めげずに診療に通い続けていることなどは,生の世界に属しています。いわば生死をかけた戦いといえますが,死の世界に引きずられかけているといっても過言ではありません。だから,食べることがすべてであるかのような事態になっているのです。しかし,こういう話はなんのことか訳が分からないと感じますか?」」
それに対して,彼女は首を振って,「いいえ,よく分かります」と明快に答えてくれました。
彼女は,過食のために異様に腹が膨らんでいると信じています。それは,もちろん,そんなふうには見えないといって上げたところでなんの意味もないほど,激しい恐怖です。それを人が見ると,異常な人だと思うだろうと恐れます。
それで私は,つづけて次のように問いかけました。
「異常なのは太っていることではなく,事実を認めようとしない気持ちです。たとえ醜かろうが,どうだろうが,事実は事実です。それは認める以外にないことです。しかし,あなたはそれを認めようとしない。それができるまでは,あなたの地獄は止むことはできないでしょう。逆にいえば,それができたときに,克服するきっかけをつかめるのです。癌と宣告されたとすると,すぐには受け容れられないと思います。そして受け入れることができるまで,平穏はあり得ないでしょう。事故で視力を失った人が不幸であるかどうかは,その事実を受け止めることができるかどうかにかかっています。失明が即座に不幸を意味するものではないと思います。そういうことと同じことで,事実としてあることは認める以外にありません。しかし,認め難い問題に直面することはあります。そして,認めることができないあいだは心に平穏はないのです。ところで,あなたは過食と癌か失明か,どちらかと差し替えることがでえきるとすると,どうしますか?」
彼女は少しのあいだ考えて,小さな声で,「眼です」と答えました。私が,「しかし,失明は治りませんが,過食は治ることが可能ですよ?」といったところ,「そうですね」と答えてくれました。
過食と肥満の恐怖とは,自己愛(と他者愛)と自己不信(他者不信)と直接の関係にあります。醜い身体の私という恐怖は,ありのままの自己を受け入れられないという自己不信と恐怖に帰着すると思います。それは密接不可分の関係にある他者不信(と恐怖)にも直結するのはいうまでもありません。
克服の第一歩は,’醜い私の身体’を,’ありのままの事実’として認める勇気を持つことです。それができた後で,やはり「私は醜い身体をしている」と思うかどうかは疑問です。たぶん,そうは思わないでしょう。
繰り返しになりますが,過食という依存を手放せない背景に,死につながる強い恐怖があり,それは依存症一般にいえます。
アルコール依存症者は,しばしば,会社や家庭など,持っているもの一切を失います。命と引き換えにしてでも酒瓶を手放さない人も少なからずあります。普通に考えると理解しがたことですが,アルコールという依存の対象を手放すと死の世界にまっさかさまに転げ落ちる恐怖があるからといえるだろうと思います。アルコールを飲みつづけることで心も身体も蝕まれていくので矛盾しているようですけれど,いずれにしてもいわば死の影に捉えられている心的状況でのことで,身体が緩徐に蝕まれて受動的に死を向かえるのは仕方がないと思うのかもしれません。
抑圧されている分身たちの欲求不満が長期にわたると,それは自我が無気力で当てにならないということでもあり,怒りと一体化して,いわば自我の根がしだいに腐っていくかのような印象もしばしば受けます。
破壊的なエネルギーを持つ裏の主体と一体化するに至ったと考えられる犯罪者たちにも同様なことがいえるようですが,こちらは裏の自我が強力化して,生きる理由が悪であると,裏の自我に迎合する形で自我が完全に傀儡化してしまうことにより,ある意味で活性化している様相であるように思われます。
他者との関係を自己の存在要件としている人間には,他者が自然的な自我の機能にさまざまな程度に破壊的に作用し,自律的な機能を歪め,混乱させるおそらく唯一の理由なので,他者はある意味でおそるべき強敵です。そして最も頼りとする最重要の立場にある母親が,他者の脅威を左右する鍵を握っているといえるでしょう。
しかしながら,精神の涵養の問題を安易に定式化することはできません。それぞれの持って生まれた自我の性状にもよるので,他者の脅威を受けつつ,それをやがては跳ね返していく力を導き出す子もあるでしょう。
自我の自律性は,個々人を,真の意味で個性的で人間的な達成に導くために欠かせないものと考えられます。その独自の人生行路を歩もうとすれば,どうしても孤独であることを免れないでしょうし,それを引き受ける覚悟,勇気,自分自身を信じる強い力などを必要とするでしょう。また,自然にそのような人生行路を歩み出すというよりは,何らかの決意と共に始まるものだと思います。というのも,将来を保証してくれる具体的な手がかりは特にはなく,自己を信じる曇りのない眼だけが頼りだろうからです。芸は身を助けるという諺があります。この独自の途を進む人には,なんらかの’芸’が手がかりを与えてくれると思います。
このように考えるのは,人間が生涯かけてまっとうしようとするのは,人間に与えられた自然的な自我の機能が,なかんずく自律的な機能が,他者の介入によってさまざまに混乱させられ,自己を失い,それをもう一度自然的な機能に修復することであるらしく見えるからです。
他者の問題は,すこぶる重要です。人間が自然そのものから乖離し,自己という存在者として誕生したとき,感覚的な存在である赤ん坊は,恐らく強い驚愕と恐怖の中にあるのではないでしょうか。周囲の大人は目出度いこととして祝福しますが,赤ん坊自身が自分の誕生を喜ぶ気分になれるか,甚だ疑問です。そういうものが皆無ということもないでしょうが。
赤ん坊にとって,生まれてきたことが目出度いと感じられるとすれば,それは母親が自分の存在を慈しみ,喜んでくれるのを知り,改めて自分の存在を愛でる気になったときだと思います。そういうことが可能であるためには,赤ん坊自身の中に,誕生をよしとし,自己を肯定する心の原基がなければならないといえるでしょう。伸びる芽がなければ,何事も伸びようがないのです。
いずれにせよ,自分の存在を大いに喜んでくれる他者なる母親の存在は,心の成長のためには不可欠です。自然児ならぬ人間の子は,母親の愛情に最初に触れて最初の安堵を知り,それから先は,その母的な愛情に絶対的な安心を求めると思います。生の方向に向けて自己を導くためには,なくてはならないと思われる自我の自律機能が萌芽の状態にある赤ん坊は,自己の内部に自己を支える力を持っていません。そうした心的状況では,おそらく絶対孤独の不安にさらされることになると想像されます。それは死の不安に包囲される脅威といっていいだろうと思います。その赤ん坊に大いなる光りをもたらすのは,なんといっても母親の愛情に違いありません。
赤ん坊の母親との関係での原初的な愛情体験は,心の成長のためには欠かせないものですが,赤ん坊が希求する愛情への欲求は絶対的なものがある激しいものです。それは人間以前だった全的な存在から,人間という不完全な存在への移行に伴う恐怖と驚愕と怒りをまじえた希求,というふうに考えることも可能ではないかと思います。そうした全的なものへの要求は,どうしても現実の前に失望に変質せざるを得ません。
愛というものを感じ取ったときに,全能欲求への期待はふくらむと思われます。しかし,それが満たされることは決してありません。期待が高いレベルでつづくかぎり,現実は冷酷です。赤ん坊はどうしてもそのことに気づく必要があります。それができたときに,人間として生きていくための第一条件をクリアしたことになります。自我に拠る人間は,能力的にいわば二分の一以下の存在です。人間には完璧はなく,ほどほどの満足が分というものです。強迫性障害などに見られる完全への要求には,原初のこうした問題がからんでいるのかもしれません。乳児が’二分の一の存在’であることを体得できるためには,母親の安定し,一貫した愛情が欠かせないでしょう。絶対的というものではなくても,自分を護る力を持っていることを理解し,許容する気になれるときに,心が落ち着いていくと思います。そして愛されている自分に気がつき,それに値する自分の価値を知り,生きている喜びを味わうことができるでしょう。また,自分を慈しみ,大切に思っていてくれる他者なる母親に,感謝と共に愛情のお返しができるようになるのです。ただし繰り返しになりますが,これらの肯定的な満足感は限定的であり,つまり不満,不信,怒りなどが一掃されることは決してありません。それが自我に拠る人間が,’二分の一以下の存在’であるという意味です。心が光の面と影の面とを持つということでもあります。
それはそれとして,日常生活の一般的な特徴は,反復です。来る日も来る日も,おなじような生活が繰り返されます。退屈は平和の証でもあります。
それに対して,気慰めをしつつの人生を送っていいものか,それは人の頽落態ではないかという議論も起こるかもしれません。それはもっともな議論だと思います。しかし凡庸な精神をしか持っていない我々の大方にとっては,それは厳しすぎる,場合によっては危険な問いかけです。
反復的な退屈な日常に,不意に不安が顔を出すという経験を,誰もがしていると思います。そうしたときに,急いでなじみのある日常に逃げ込み,胸をなでおろすかもしれません。たとえ退屈であっても,なじみの深い日常はこうした得体の知れない不安から身を守ってくれるので,贅沢なことはいえないのです。
退屈だが平和だった日々のあるとき,得体の知れない強い不安に見舞われ,それが執拗につづくとき,心の病かもしれません。それは平和だった反復的,日常的な世界の相貌が,もはや親和的ではなくなったということでもあるでしょう。
反復的な日常世界に安住できるためには,安定した自己愛と他者愛とを備えていることが必要のようです。それは,繰り返し述べてきたように,乳幼児期の母親との関係で情緒的に満たされる体験をしている(E.Hエリクソンの「基本的信頼」に相当すると思います)ことが基盤になります。。それによって,ある意味でバランスのよい性格を身につけることができ,いわゆる隣人愛の精神を発達させることができるのです。これらは,いわば平均的な市民感覚が発達している人たちです。彼らは,著しい不安に悩まされることがあまりないと思います。しかし,それが人間の模範的なあり方かといえば,それは疑問です。そこには,死の脅威(無意識的な)に対抗する愛の同盟という趣があり,そのかぎりでは自分たちの’健全な’市民感覚にほとんど疑問を持たないのです。危なっかしい生き様に見える肌合いの異なる他人たちに,隣人として優しい気遣いを示すことがあっても,所詮は理解しがたい世界の住人の域を出ることはないでしょう。彼らは自分の眼差しの優しさに,かなりの程度自足するのです。そして,また彼らの心配と忠告どおりに,’危なっかしい連中’は,人生の泥沼にはまり込むことが多いのも確かでしょう。これら市民的な健全さをしっかりと身につけている人たちは,隣人への優しく,愛情のある眼差しを持ち,決して無理をせず,突然見舞われた災厄にも従容として従う謙虚さと穏やかさを失わず,持って生まれた美質のために人の支援を得やすくもあり,ある意味で生き方の手本といえるでしょう。しかし,それにもかかわらず,死の脅威から目をそらす欺瞞化の才に富んでいるという趣は否定できません。
これらの’才能のある市民感覚’の持ち主ほどには,その種の才に恵まれていないものたちには,不意に顔を出す不安は,時によっては御し難いものがあると思います。それは一気に孤独を突きつけられるということでもあるでしょう。拡大視すれば,そこには死の影が漂っているといえるように思います。
影があるということは,光があるということです。心にとって光は自我の力を示すものであり,影は自我の無力を示し,死に所属するものです。自我はどうしても影を一掃できないものでもあります。
影は,それに捉えられると自我の滅亡を招きかねません。その予感が不安となって現れるのです。不安に見舞われたときに,自我がどういう姿勢を取るかが問われます。自我の解決能力が問われているのです。最も望ましいのは,他者との関係の途絶の不安,一切を無化する恐怖,等々であるこの死の影に,恐れずに立ち向かう勇気を持つことです。それがあれば,人を日常への頽落から脱出させるきっかけになるかもしれません。真に個性的な独自の途を開拓しようとすれば,’死’との戦いを抜きにしてはできない相談であるといえるのではないでしょうか。
しかしそういうことが可能であるのは,強い自我の持ち主であることが条件になると思います。それは先に述べた’健全な市民感覚の才能’の人とは,別種の才能ということになるでしょう。これら真の意味で個性的な人生を送る人は,’才能のある市民感覚’ということを基準とすれば,いびつな,バランスの悪い人格の持ち主ということになるようです。
以上に述べたように,なじみのある日常世界は,’死’に包囲されている現実を忘れていることができるという効用があります。そうした日常の世界に自足することができるのは,’健全な市民感覚’を身につけている人たちです。当然,彼らが人間社会の中心にいることになりますが,その特徴は良くも悪くも世俗的ということです。これらの集団依存的な生き方がうまくいっている人たちは,どことなく人生の勝利者という顔を持っています。人があるところ,いたるところに様々な集団がありますが,リーダーとなるのは,当然といえば当然ですが,人を上手にまとめたり,操ったりする能力に長けた人です。そういう人を中心に,その力を当てにする多くの仲間が集まって集団が形成されますが,肌合いの異なる者は巧妙に排除されることにならざるを得ないでしょう。偏狭といえばそうなりますが,集団の輪というものが要の意味であれば,それはやむを得ないことです。ですから,どうしても世俗的です。
人と仲良く暮らすことができるのはいいことです。それに異論はありません。それができれば人生はひとまず安泰といえるのでしょう。しかし,一方では,諸々のクラブから,排除され,疎外された人たちも必ずいることになります。クラブとしては,そんなことは知ったことではないということになるでしょう。それはやむを得ないこととはいえ,人間の偏狭が人間の不幸を生み出すという側面は否定できません。
そういうわけですから,そうした性格を持つ集団を,小市民的であるとして忌避する人がいるのもうなずけることです。他者に対して不信と恐怖と猜疑を払拭できないでいる人たちは,そういう拒絶感を持つでしょう。そこには,元々がそれらのクラブ的な人間の偏狭さの犠牲になり,心に傷を負ったといういきさつもあるだろうと思われます。
それらの人の中で,なにか秀でる一芸があれば,それは確かに,「芸は身を助ける」ことになるのでしょう。それらの恵まれた人たちは,自分自身の中に拠り所を持ち,自己を評価する基準を持つことになるので,他人の直接的な助けを必要としません。それだけに欺瞞的なものに敏感でもあるでしょう。従って彼らは,集団に対して批判的,否定的になるでしょう。孤独でもあるかもしれません。しかし他者との関係は,自己との関係同様に,内的に安定しているといえます。それは主体との接触がうまく図られるているということでもあると思います。
これらの独自の途を行くのは,いうまでもありませんが生易しいことではありません。自我がよほどしっかりしていないと,集団から離れて暮らすのは,やはり危険です。自分では個性的に生きているつもりでも,いつか途が見えなくなり,自分を見失う危険は,むしろ高いでしょう。そのときに死の極北から吹きつける冷たい風にさらされ,人間がいわば立ち枯れてしまうということも起こり得ると思います。死につながる意味を持つ孤独の彩の濃い生活は,精神を蝕むことになる危険があります。独自の実りある途を行く少数の人間エリートと,世間のクラブ的な社会に安住する常識派とのはざまに置かれると,どうしても危険な状況にあるといわなければなりません。
自我の自律性が確固としたものであるとき,自我に内属すると思われる境界機能もしっかりとした礎を得るでしょう。そして不幸にして,その好ましい心の作業に乱れが生じると,自我の根の主体との関係が不安定になると考えられます。そうなると自我は混乱しやすく,境界機能も不安定になるのではないかと思われます。
親,特に母親は,子に対して,心の境界をしばしば無視して侵入します。その極端なものは虐待する親です。虐待する親の下では,子の自我の自律性は失われます。そして甚だしい依存の仕方をしがちです。脅威を与えている親から逃れようとするよりは,その親への依存を手放せなくなるのです。それは死(乳幼児にとっては,親に見捨てられると,死の脅威にさらされることを意味します)をかけた必死の依存になるのではないかと思われます。
親の虐待に関するテレビの報道番組がありました。虐待されて命さえ危ぶまれる状況で,第三者が援助の手を差し伸べようとしても,虐待される子の十人が十人とも,「構わないでほしい」と述べたという内容でした。
境界を甚だしく無視して子の心の領域に侵入する親の養育を受けた子は,親への甚だしい依存を手放すことができません。それは自我の境界機能の欠落と自律機能の欠落を意味します。
そのような親子関係にある十代の患者さんがありました。社会性が大変低く,未熟な人格の人で,自分の問題を適切に表現する力もありません。しかし診療には通いつづけておりました。手前味噌のようになりますが,「ここへ来るとほっとする。私の聖域です」といったことを口にしておりました。そして,あるとき母親が訪ねてきました。ごく普通の母親のように見えました。診療への協力をお願いしたところ,こころよく聞いてくれました。しかしそれを最後に,その患者さんはクリニックを訪れることはありません。そのまま通院しつづけたからといって,’良くなる’ということも難しいと思いますが,私は,「回収されてしまった」と感じました。私の勝手な思い込みで,実はどこか別の医療機関に母親が連れて行ったというのであればまだしもと思うのですが。
こうした甚だしい依存関係(そうしたものは必ず悪しき依存です)では,自我の主体との関係は極めてよくないはずです。
自我の境界の問題は,隣り合う二つの国の関係によく似ています。両者に力の差があれば,強国がもう一つの国の主権を尊重するのはむしろ難しい問題です。強国が浸入して併合したり,植民地支配したりというのが歴史的現実です。
それと似たような事情にあるのが,親と子,特に母親と子供の関係だと思います。母親は胎児を宿し,お産の後も母子一体の時期を経験するので,余人には計り難い特有の感情を子供に持つと思います。そういうことと関係があると思いますが,母親がおかす一般的な間違いは,子供の領域への侵入です。それは子供の心の成長を阻み,心の障害をもたらす要因となる危険性もはらむことになるのですが,母親には容易には理解しにくい問題でもあるようです。母親自身が多かれ少なかれ依存の対象を必要としているので,恰好の相手を手放したくないというのが,むしろ一般ではないかと思います。そこには隠れた悪意さえうかがわれることもあります。母親は,子供のためを思ってしていると考えがちですが,意識の欺瞞というべき側面があることが決して少なくないと考えるべきです。
国境と異なるのは,強いはずの侵入する親が,実は強くはないがための侵入であるという点です。そういう弱さを自覚し,見据えることで心が成長するのでしょうし,子供の心の成長も助けることになるはずです。弱さは,それを自覚するときに,もはや弱くはないのです。
心の境界は,自他の存在をそれぞれ別個のものとして承認し,尊重するという意味を持ちます。国境が,相互にそれぞれの独立を尊重するものであり,それを護らなければ紛争になるのと似ています。
余計なお節介をされると腹が立つのは,境界を無視されたと感じるからです。親子といえどもおなじことで,親は子の存在を独立したものとして承認し,尊重しなければなりません。親が子の領域に侵入的になりながらその自覚を持たないのは,かつては自分自身がその親からおなじことをされてきたためであるかもしれません。これは好ましくない依存につながり,悪循環に陥りがちです。そして心の沼を広げる理由になります。
親は,特に母親は子供に依存しがちです。依存には良い形のものと悪い形のものがあります。前者は相互の人格を独立したものとして,それなりに認め合い,尊重し合っている場合で,いわば対等の関係で信頼と愛情を分かち合えるのです。後者は,親の力を子に対して行使するという体裁になります。あからさまに,あるいは暗黙のうちに,子供を従えてしまうのです。子供のころに親にされたことを,無意識のうちに取り込んで性格の一部にしてしまうのが人間です。そして自分では意識せずに,当然のように,子に対して,自分自身が子供であった時代にされたことを押付けていくのです。人はそういうことを繰り返し,まずいことをしているという自覚を持たないのです。人間は,代々このように苦しみの元をつないでいく不思議な一面を持っています。
境界機能がしっかりしていれば,他人が脅威に感じられることもあまりないでしょう。逆に,他人の脅威におびえる人は,境界機能が不確実なのです。それは隣国の侵入を受けてきた小国のおびえに似ています。そのことをYさんの例に見てみます。
Yさんは30代の男性です。彼は父親を大変恐れています。家族のだれもが父親には逆らえず,母親も夫に従って,Yさんはいわば放置されて幼児期を過ごしたと思っています。それは問題の一端で,長じては,勉強,進学,就職,友人との交際など,一事が万事,父親は激しい罵声をまじえて干渉しました。
父親は家族の全員が覚えているそれら昔のことを,ほとんど想起できません。しかし治療に非協力というわけではありません。出来ることがあれば力を惜しまない姿勢が見えています。被害を蒙った家族が覚えていることを,与えたらしい本人は記憶していないというのは,被害を与えたつもりがなかったからでしょうか。それとも都合のわるいことは忘れてしまう心の知恵なのでしょうか。
Yさんは成人し,結婚もしてから発病しました。職場で配置換えがあり,しばらくして年上の女性上司に恐怖心をいだくようになりました(客観的には人を恐怖させるような人ではなさそうです)。Yさんは,年上のその女性に取り入ろうとしたようです。父親を取り込み,内的な支配を受けている彼の自我は,取り入ることで身の安全を図ろうとしたのかと想像されます。しかし人とのあいだの距離の取り方がよく分からない(人の心が分からないのとおなじことです)Yさんの試みは,逆効果になりました。相手の女性には,しつこくつきまとう困った人と映ったようです。強い口調でたしなめられたYさんの心は,一気に崩れてしまいました。そして女性上司に依存することでおのれを保とうとした自我が,対象を見失って混乱に陥りました。Yさんは上司への恐怖心から,自分の席に座っていることができなくなりました。当然,仕事を満足にできず,欠勤することも目立つようになりました。
表の自我の主要な役割の一つは,社会的な立場を築き上げることです。それは自我の自律機能と境界機能が成長,強化されることによって可能になります。境界機能の重要なものは,問題を受け止める力です。
上に述べたことは,Yさんの自我が役割を果たすことができていないことを示しています。それと平行して裏の自我が勢力を強めていることになるはずです。
Yさんは,女性上司におそらく母親的なものを求めたと思われますが,拒絶されたと感じたときに,女性は拒否的,威嚇的,浸入的な支配の人に変貌したのです。女性は父親と同列の人になったということだと思います。彼女が出張などで不在のときはまだしも,ふだんは五分と席に座っていられないのです。
Yさんには退行しやすい幼児心性が色濃くあります。それは一つには母親的なものに甘えたい,頼りたいということです。また,拒否的,威嚇的なものに怯えを持ちやすいということでもあります。それらのことは自我の自律性が混乱しやすく,頼りないということと,自己の主観世界が他者の客観世界との混同が生じやすく,境界機能の受け止める力,侵入的にならない力が未分化であることを示しています。
父親への恐れと共に怒りも持っているYさんには,自分がこうなったのは父親のせいだというつよい思いがあります。しかしその父親を取り込み内在化しているのは,父親に対抗する力がない自我が,取り入る道を選んだということだと思います。父親の内的な支配を許し,依存した無気力な自我は,父親が期待したような自分ではないことについて,常に罪悪感に責めさいなまれる代償を支払わされているのです。自分の意志は,父親によってことごとく踏みにじられてきたと思っている一方で,内的な父親と一体になって,自分を不甲斐ない奴と内心で罵っているのです。内在する父親に依存し,Yさん自身の自由意志が不在であるかぎりは,心が晴れる日がないのは,当然といえば当然です。
妻は優しい人です。夫を気の毒に思い,受容的,母親的な姿勢で助けようと努めています。しかしそれが仇となって,著しく退行的(いわゆる幼児がえり)になる時期がありました。その姿は,幼い子が保護者の下に安らごうとしているのに似ています。それに伴って自他の区別がつかなくなったように,仕事がある妻の心を気遣うこともなく,朝方まで時間かまわず心の内を語りつづけます。Yさんは,他者を客観的に見るのが難しく,極めて主観的に,主観世界を外界にある他者に投影して見てしまうのです。
これはまさしく乳幼児の世界で起こることです。それら幼いものたちと同じように,心の境界機能が極めて未発達なレベルに後退していると考えられます。幼いころに母親に甘えたかった心を剥奪されたと思われ,早々に自我が父親に取り入ったと想定されます。それによって幼い時代は,むしろ大人びたませた子であったかもしれません。そして,それに伴って情緒的な満足を求める心は,自我によって抑圧されたと思われます。それに相応して,自我の自律性は未発達に終わらざるを得なかったのではないでしょうか。
学生時代のある時期まで,Yさんは学業成績が優秀でした。そのころまでは父親の支配を受けているYさんの自我は,学校の成績を重視する父親との協調が出来ていたということだと思います。そして,子供とはいえない年齢にさしかかったころに,息切れがして,成績が振るわなくなりました。高校生のころに,Yさんは勉強をしなくなり,見た目には怠惰な生活をするようになったのです。自我の目覚めといったものでもあったのか,消極的ながら反抗の意識もあったようです。自我の自律性が問われる年頃になって,問題が表面化したということでしょう。
いずれにしても,父親の支配を受けてきた無気力な自我は,子供の時代のままの父子関係に耐えられなくなったのだと思います。とはいえ,自分の価値を自分自身で支える力がありません。反抗ということが親の自我の傀儡であることを意志的に拒否し,自己の独自性の宣言という意味であるとすれば,Yさんのそれは,曖昧なところがあったように思います。つまり自我が明瞭に無意識の分身たちと一体になろうとしたというよりは,その圧力に効し切れず,機能不全に陥ったという印象を受けます。その筋で見れば,父親の価値規範から見て失格という状況に立ち至ったということです。選んだ大学は,父親が望んでいる(と信じています。父親は,「そんなつもりはなかった」と否定しますが)’超一流’ではありませんでした。自己の主張の萌芽ともいえると思いますが,父親の期待に即せなかったことへの罪悪感も並大抵のものではなかったようです。’超一流’を目指すことをあきらめたのは,明快に反抗したというより,荷が重過ぎるという一面もあったのだろうと思います。それは単に学力的な問題という単純なものではなく,父親との関係の長年にわたる重圧に耐えられなくなったということでもあるのでしょう。
発病は結婚後のことです。それは結婚によって情緒的なものに触れたことと関係がありそうです。というのは,無意識界に潜んでいたと思われる情緒的なものへの欲求が活性化したと思われますが,Yさんの自我は,それを受け止めるだけの力がなかっただろうということです。自我がそれをできたのは,幼児的に退行すること,妻を母親に見立てることによってです。無意識下の欲求の強さは,乳幼児の貪欲なそれに等しいものだろうと想像されます。その分身たちの勢力に支配された自我は,客観的に妻を見る力はなく,分身たちの眼差しで,つまり投影によって妻を見ることになったのです。妻の受容的な人柄も,そういうものを助長させたのではないでしょうか。自我は,無意識の力に押されて,妻をほとんど母親と見立てたと思います。
退行せざるを得なかった弱い自我によって,自律と境界の機能においても幼児的に退行したと考えるのが妥当でしょう。従って,錯覚し,混乱してもいる退行した自我は,受容的な妻に対して感謝の気持ちを持つことはほとんどありません。むしろ当然のように,’わがままに甘える’ばかりです。
発病は,意識の姿勢が崩れるということでもあります。Yさんの自我は,もともとは情緒的なものを抑圧して父親と協調しようとするものでしたが,思春期にいたってその姿勢があやしくなり,結婚をしたことによって崩れたといえます。
崩れるということは一巻の終わりですが,新たな出発の始まりである可能性も秘めています。その破壊作業は,死につながる裏の自我の営為であると考えられますが,破壊の次に再生があるか,単なる崩壊かは,表の自我にどんな力が秘められているかにかかっているでしょう。
Yさんの自我は,少しずつですが,再構築の作業に取り組んでいます。その証拠に,最近はほとんど欠勤しなくなっており,同僚たちへの過度の恐怖も少なくなってきています。その背景には,妻の根気のいい支えと,会社の度量ある態度にも大いに助けられているということをつけ加えなければなりません。
自我の重要な機能のひとつは判断力です。未熟な自我は,自分ではどうすればいいのか分からないので,外部的な頼れるものに依存します。親や権力者や友人に依存します。
いま上げたYさんは,恐怖をもたらした父親に取り入り,依存しました。どこかミイラ取りがミイラになってしまった趣です。この過程で自我が主体性を保つことができていれば,何らかの判断が働いたことでしょう。判断の機能が生きていれば,その後のことに責任を持てます。ミイラ取りがミイラになることはないと思います。父親との関係で無気力なままでいる自我は,幼い子が母親にするように,外的なものに過度に依存するしかない状況に置かれているようです。
退行しているYさんには,妻が困っているのが理解できません。「どうして怒っているの?」と悲しそうに訊ね,すねるように黙り込んだりします。自分の気持ちでしか他人をはかれないのです。
ところで判断力は自我の機能として重要であるといいましたが,判断をするということは,当面している問題を,まずしっかりと受け止めるということが前提になります。その上で自立的に考えをめぐらし,一定の結論を出すということです。そのようなことですから,判断という心的活動を支えているのは,境界機能の’受け止める力’と自律機能であるといえます。これらの機能が,人間の心的活動には,基本的に重要であるのが分かると思います。
女子大生のIさんが,次のような夢を報告してくれました。Iさんはおかあさんが大好きなのですが,夢の中でそのおかあさんに追われ,殺されそうになったのです。
もちろん現実にはこういうことはあり得ません。夢の舞台でなぜこのようなことが起こっているのでしょうか。
Iさんの主訴は,パニック発作や人前での異常なほどの緊張でした。
この夢について,本人の連想から次のような意味が汲み取れました。
殺されるというのは,母親の望むように生きなければ見離される,そうすると自分は生きていけない,精神的に抹殺されるという恐れです。
実際の母親は,Iさんが必要な意見を臆せずいうようになったこともあって,最近ではあまり口出しをしません。しかし内心では何を望んでいるか,Iさんにはよく分かるような気がするのです。それは,やはり無視しがたい圧力になります。また,Iさんの場合,母親を取り込み内在化している度合いは人より強いといえます。その’内なる母’は,直接的にIさんの自我を監視しています。かつては傀儡自我といえるほどだったのが(パニック発作や,人前での過度の緊張の要因です。母親の仮想的な要求に完璧に即さなければならないという強迫観念と,ロボット化している自我による抑圧された怒りなどが,関与していたと思われます),このごろでは大分自由になったとはいえ,十分ではありません。このような内的状況で,自我の自由はしばしば脅威にさらされるということが,’母親に追われて殺されそうになるというふうに解釈できると思います。
Iさんはいわゆるよい子です。夢の舞台ででも,母親に対抗する怒りが見えていません。抑圧がずいぶん強いのでしょう。人前での過度の緊張は,侵入される恐怖だと思います。それは母親から侵入されてきた養育過程と,それに対抗するだけの自由な自我が育っていないこと,境界機能が不十分であることを意味していると思います。
母親の侵入,支配を受ける形の上に,母と子のあいだの強い依存関係が成り立っています。Iさんは知性的で,問題を理解する能力は基本的に高い人です。解決を要する基本的な問題への理解が進むにつれ,症状的なレベルのものはしだいに解消していきました。ということは,その分自我が力をつけてきているということです。事実,こういう夢を見て報告をする気になったのは,自我が成長した証です。診療に協力する姿勢の現われでもあると思います。
患者さんにとって無意識的だった問題を,治療者が感じ取って,タイミングよく解釈という形で還元してあげれば,患者さんの方では思いもよらぬ収穫を手にすることになります。それは患者さん自身が半ば気がついていたからこそ可能なのですが,本当に知ることには抵抗があったので,気がつかないままで済ませていたのです。治療者との信頼関係が進展すれば,自分の中の扱いが厄介だった問題を預ける気になれます。それに伴って抑圧して無意識だったものを,ようやく認める気になれるのです。
夢のこのメッセージに注意を向ける気になったのは,自我が,おそるおそるながら従来の母親への姿勢に懐疑を抱くようになったからですが,それでも,いままでの恐れが強力なので,自分が持っていた母親のイメージに異を唱えるのは,やはり容易ではないのです。
Iさんは薬をほとんど必要としなくなってきており,やめようと心に決めました。しかし,バイトに行くときなど,特別なときは服薬をしています。これが本人には問題なのです。薬は飲まないと決めた以上は,それをまっとうしたいのです。新たな混乱が生じました。
薬はやめるべきだということ,一度決めたことはまっとうしたいということは,母親への同一化を示しているようです。強迫的なこの不自由な思いは,’囚われている自我’の姿です。母親の思いとしては,Iさんが’心の弱い子’であってはならないのです。
「その葛藤は,お母さん的な考えから自由になっていないからですかね」という問いかけに,Iさんは,「そう思います」とすぐに肯定しました。そして実際に母親が,服薬を快く思っていないとつけ加えました。
母親の支配を受けているIさんの自我が,もがき苦しんでいるという様相です。
Iさんの心の世界と,Iさんが対処してきた様子を比喩的に述べると,次のようになります。
それぞれがそうであるように,Iさんは小舟の船長です。小舟には母親も乗っています。小舟は心の世界で,Iさんが自我です。小舟には他にも同船者がいますが,それらは常に姿が視界にあるわけではありません。しかし母親は絶えず視界の中にいます。それを考えると,母親は特別な同船者のようです。おそらく船長としてのIさんの腕前を信用してはいません。Iさんは母親が口を出さなくても,なにをいいたいか分かっています。常に傍にいるので一心同体も同然なのです。
海が荒れています。船長はパニックに陥りそうです。船長はまだ半人前の腕前なので自信がないのです。母親にどうしても頼りたくなります。いままで母親がいう通りに小舟を操ってきました。それなのに海の荒れ方がひどくなってきたのはどうしたことかと,分からなくなってきました。
このごろ少し分かってきたのは,自分の舟なのに,まるで母親自身が船長であるかのようになっているのと関係があるようだということです。そのために,知らず知らず荒れる海の方に舟を導いてしまっているのではないかと考えてみたのです。
しかし母親に舟から下りてもらうわけにはいきません。そんなことをいえば母親が怒るに決まっているし,下りられてしまえば舟をどう操ればいいのか見当がつきません。それで母親が眠っているときに,母親にいわれたことを無視して自分流にやってみることにしました。それなら危険な状態になったとしても母親に助けを求められるのです。いかしいざとなると動悸がします。それで病院で相談したときにもらった安定剤を利用してみました。医師がIさんの考えに賛成してくれたことも心の励みになります。薬を飲むと心が落ち着きます。しだいにそういうやり方に自信が出てきました。薬を飲むと安心することができ,自分が舟をどう操ればいいのか,落ち着いて考えることが多少はできます。
Iさんは友人達に,自分にパニック障害があるとはいえませんでした。うかつなことをいえば,自分がよほどおかしな人間であると思われるのではないか,彼女たちが遠ざかってしまうのではないかと恐れたのです。それはIさん自身がパニック障害という問題を,自分のこととして受け止めることができないでいることも意味しています。やがて彼女は,それはおかしいと気がつきました。それは辛い問題ではあっても,恥ずかしいこととはいえないと気づいたのです。思い切って友人たちに話してみたところ,彼女たちはあっさりと受け止めてくれました。理解し,共感してくれました。一番の問題ともいえることを友人たちと共有できたのは,大きな収穫でした。
これらのことは,自我の境界機能と自律機能の混乱と回復とを示しています。
あるとき,母親が口出しをしてきたときに,自分の意見をいえるようになりました。初めのうちは母親は怒っていました。それを見て恐れをなしたのも事実です。しかし,だんだん負けないようになりました。それにつれて,母親もむきになってIさんを服従させようとするのを控えるようになりました。一目置くようになったのです。
小舟に同船していたがる母親に,下りてもらう勇気はまだありません。一部は母親が可哀想だからです。Iさん自身が,独立した船長であるといえるだけの自信がついたとはいえないからでもあります。しかし,どういう問題があり,どうしなければならないかということは理解ができていると思っています。
小舟の運命は,船長にかかっています。どうしたらよいのか分からずに,右往左往しているようでは舟を守れません。ともかくも船長の自覚を持ち,船長としての仕事をすることです。自分のためによいと思うことを考え,それを実行に移すべく判断をすることが求められています。それが間違いであると気がつくこともあるでしょう。それはそれでいいのです。判断をすることが,船長が仕事をしたことになるのです。そうすれば責任を取れます。次にどうすればいいのかが見えてきます。
この舟の船長は私である,母親は相談の相手ではあっても,最終判断を下すのは船長である私だという自覚を持つことが大切です。
診療への協力云々ということを書きましたが,診療のために通っている現実があるのに,変ないい方だと思えたかもしれません。それは患者さんの側に,一般的に治療への抵抗が潜んでいるといえるからです。そのために,場合によっては,治療が成功するのを阻む無意識の心の動きさえあり得るのです。
ある人が次のようにいっておりました。
3ヶ月で治る・・・と書いてある本を見た。私は良くなっているのだろうかと疑問を持った。もしかして私は治りたくないのかもしれない。治るとお母さんが心配しなくなると思う・・・。
このように’心の病気’にはコミュニケーションの一つの形という面があります。自我が解決できないでいる問題を,病気が部分的に救う面があるのです。疾病利得といわれているのは,そういう意味です。’自爆テロ’と呼んだ人がありました。自宅で暴れたことや,薬の過量服用を指しているのですが,言葉でいくらいっても通じない両親への暴力的なアピールという意味です。
自我が無力である状態が長くつづいているとき,身体が答えを出してしまうことがあります。たとえば過眠症にはそういう意味があります。学校や会社に行きたくないときなどに,それを解決するのが自我の役目です。(自我が)判断をするという形が必要ですが,それをせずに気分まかせにしておくと,身体が答えを出してしまうのです。自我が責任を取らずに回避しているという図になるといっていいでしょう。
メラニー・クラインが,羨望の心理の強い患者さんの中には,治療者の成功を妬み,治療の成功を妨害する心理力動が見られると述べております。
患者さんは,誰にも話せないでいる自分の問題を,治療者であるがために打ち明ける気になれます。しかしそれも程度の問題です。意識的にもさることながら,本人にも気がつかないレベルで重要な問題を隠蔽してしまうのは,なんら不思議なことではありません。治療関係の信頼度には,現実にはさまざまな程度があるのはいうまでもありません。治療者の能力に足りないものがあれば,患者さんの方で,ある程度以上のものを打ち明ける気にはなれないでしょう。
相手が誰であれ,自分の心をさらけ出すに値しないという心を誇りにしている人もあります。それでも一般には,自分が理解されたい,心の地獄絵を解決に導きたいという心があるからこそ通院するのに違いありません。例外的には,心の回復をほとんど信じていないで,治療者に対する何らかの悪意から通院する場合もあり得ると思いますが。
心の根底に絶望的なものがあるからこその心の障害です。そうであるからこそ,治療者がその難解なものを解決する能力を持っているかどうか,容易には疑問を拭えないと思います。治療妨害,治療抵抗の一面は,治療者の力量をテストする心の動きともいえるでしょう。
治療者は,そうした治療的な難問をかかえていると感じられる患者さんを,自分の手に負えるかどうか判断しなければなりません。その上で引き受けることになった場合は,さまざまなレベルの治療抵抗を,むしろ治療的な手がかりにできるかどうかが鍵を握るでしょう。一つ一つそれらの関門を克服していくのは,心の治療そのものです。
自我は無意識の心に依存しつつ,なおかつ自立した,主体的な存在であることが求められています。実質的に,心全体の主体は,内なる自然である無意識に,言葉を換えれば内在する主体にあります。しかし自然界のものである主体自身は,人生を直接生きることはありません。その役割は自我に与えられているのです。
無意識の上層部は,人為的な手が加わることによって混乱させられた自然界であるといえるかと思います。その混乱の責任は自我にあり,しかし自我にはありません。自我が未熟すぎて,責任の取りようがない時代の話におよぶものがあるからです。その上で自我の責任において,これらの人為的に混乱させられた自然を,元の自然へ回復させる作業をしなければなりません。それは主体との関係を確立する方向で進められなければならないと思います。その作業が首尾よく進んでいるかどうかは,心の全体が充実し,豊かになっていく感覚が答えになると思います。
自我の機能は,便宜上三つに分けることができます。一つは自由な機能,一つは社会的な機能,一つは非社会的な機能です。
自由な機能は,なにものにも囚われない高度な自我のものです。この機能が活発なときは,内在する主体との関係がしっかりしているので,自分の価値を信じることができています。それだけに他者への依存から理想的に自由になっています。これが健全に機能しているときに,内外の状況に主体的,自立的に柔軟な対応ができるのです。自我は一個の組織体ですが,自由な機能は組織体を改善していく上で重要なものです。
非日常的な状況に置かれたとき,自由な機能の発動が必要になります。一例を挙げれば次のようになります。
小学校の一年生が交差点で信号を待っているとき,幼児が車道に入ったとします。小学生は先生に,「赤信号では止まりましょう」と教えられています。一年生はどうするでしょうか。
法規を守って信号で立ち止まるのが,社会的な機能に依ってということになります。幼児が車道に出たとき,とっさに車道に飛び出して(法規を無視する)幼児をたすけようとするのが,自由な機能の発動ということになります。
社会的な機能は,主に日常の行動に関するものです。いちいち考えながら行動するのでは,ぎくしゃくして,日常生活が円滑に営まれないでしょう。人間関係もぎこちないものになります。無駄なエネルギーを使うことになり,疲れもします。そういうことがないように,日常の生活行動は,組織的,自動的に行われるのが望ましいのです。またこの機能には,その人の社会的な顔という側面もあります。
非社会的な機能は,上にあげた二つの機能が固化して不全状態に陥ったときのものです。生活状況のストレスが耐え難いほどに感じられ,人間関係にうまく対応できないでいると,このレベルに後退する場合が出てきます。身を守るために人を避け,いわゆる引きこもりの生活に入ることになります。このレベルになると無意識の影響をつよく受けるようになります。心の沼の勢力が大きくなっているので過敏になり,ストレスを受け易くなります。それが活性化しないように刺激を避ける必要があり,他人との関係を遮断する方向に向かいます。
自我の以上の区分は,いうまでもなく便宜上のものです。実際には非社会的な機能といい,社会的な機能といっても固定的なものではなく相互に移行する関係にあります。それら自由な機能の下位にあるものは,日常の思考や行動をパターン化し,それぞれの個人の特徴を表すものです。そして自由な機能が随時,それらの下位の自我の営為を監視し,修正する指令を発します。自由の機能が活発であるときは,内在する自我との関係が望ましい状況にあり,自我は与えられているエネルギーを十分に駆使することができます。
自由な自我は,内在する主体との関係が保たれているかぎりにおいて機能すると考えられます。主体は超人間的な存在であり,自我は人間に固有のものです。両者が自我の機構において接点を持ち,主体の意志を自我が人間的に変換して一定の指令を発すると仮定的に考えることができるように思われます。そのかぎりでは人間の力の源泉が主体にあり,かつ無限な可能性が秘められているともいえるように思われます。人間の可能性が無限であるという感覚がなければ,人生はすべて自我の範疇に収まることになり,閉塞球の中に閉じ込められた存在であるしかありません。人間の有限性は現実問題ですけれど,不可知な無限感覚もまた人間のものです。
非社会的な機能に陥っている自我は,自由な自我の機能がほとんど見られなくなった心的環境に自己を置きますが,この状況では内在する主体の意志は,自我を通じて人間的に有意味のメッセージを伝えることができません。エネルギー的にも枯渇する自我である非社会的なそれは,生きる意味を紡ぎ出す根拠を欠いているに等しいといえるようです。
また,この自由の自我の活況如何が,自己感を表すと考えられるように思われます。
自我を騎手に,騎手がまたがる馬を無意識にたとえてみると,自由な機能が健全に働いているとき,両者の関係は良好です。そのとき騎手は馬の力を巧みに引き出して,いわば人馬一体の状況にあるといえます。馬である無意識には,内在する主体が存在します。賢明な騎手は,その意向を探り当てることができているといえます。
これに対して非社会的な機能のところまで後退するとき,騎手がまたがっている馬は気まぐれで,しばしば不機嫌です。おまけに騎手は自分の力を信じていないので,人生行路が二重に難しくなるのです。このとき騎手は,自分がどこへ行こうとしているのか,なにをすればいいのか見当がつきません。いわば馬まかせになってしまいます。自我の主体性は発揮されず,主従の関係は逆転してしまいます。
馬が不機嫌なのは,自我が自分の役割をきちんと果たしていないからと考えるべきです。
すべては主体との関係に帰着します。その関係に問題があれば,いわば自分の筋を離れて迷子になってしまいます。自分がなんだか分からないという気持ちに悩まされることになります。
状況に応じて,自我の様態は変化します。自由自我が健全であれば,状況に柔軟に対応できるので,人間性がますます豊かになっていくと思います。しかしそうでなければ,悪い形のさまざまなものに依存します。
非社会的なところまで自我が後退している状況では,自我は無力化し,それに反比例して裏の自我が勢力を拡大するという事態になります。強いエネルギーを蓄えた内向する怒りが,長期的に滞留することになります。主体性を失った自我は傀儡化され,いわば裏の自我の虜になってしまいます。裏の自我に率いられる無意識界の勢力は,いつしか悪魔的,破壊的な彩りを深めていくかもしれません。
人間が犯罪者になっていくのは,そうした心の変質が起こってのことだと思います。アルコールで身を滅ぼしていく姿も然りです。過食症者が過食にふけっているときも,拒食症者が命の危険を省みないのも同様です。そこには悪魔的な心に捉えられ,引きずられていく様相が表れていると思います。 拒食症の患者さんが,夢の報告をしてくれました。
暗い道を通って家に帰ると,見知らぬ中年男が来て,荷物を差し出す。「これはあなたのものだ」という。荷物を開いて中身を見ると,ミイラ化した死体が入っている。「これは私のではない」という。相手は自分の主張を繰り返し,私はむきになって否定する。
むきになるのは確かに変だ,自分のものでなければむきになることはないですからと,夢の報告者はいいます。
いうまでもなくミイラ化した死体は,患者さん自身でしょう。やせることに囚われていると,こういう結末が来るだろうということ,あるいは心が身体を否定しようとするかのような行為は,既に精神的な死をもたらしているということ,そういう意味が見て取れるように思います。
では荷物を突きつける見知らぬ男はどういう素性の者でしょうか?彼は実際には見たことのない男です。現実の人物ではないらしいということは,無意識の世界から浮上してきた,なんらかの使命を帯びた不気味な者と考えられると思います。死を予告する冥界からの悪魔的な使者のようでもあります。 患者さんがあくまでも受け取りを拒めば,使者は冥界にいざなう役目を帯びてやって来た危険なものの姿を剥き出しにするかもしれません。しかし荷物を自分の物と認め,受け止めれば,その危険を回避するのを助ける使命を帯びてやって来た者ということになるでしょう。
荷物の受け取りを拒んだ前者は,自我が機能しなかったことを,受け取った後者は,機能したことを意味します。
夢を見た人の受け取り方一つで,夢の意味が変わり,次に見る夢に影響を与えます。夢は無意識の世界にある意味を伝達する機能を持つことがあるので,それを正しく受け止めることができれば,それ自体が自我の力の証明になります。提出された問題を受け止めることは,常に重要な意味を持ちます。それは心の世界全体が好ましく変容していく上で欠かせないことです。
Updated 07/10/06
性格形成に与える母親の影響-その8
■終章
「院内通信」の当初の目的は,摂食障害の外国の症例に即して,私がこの問題をどう考えるかを提示することでした。そうすることで,診療を受けていただいている皆さまに少しでも益するものがあればよいと考えていました。ですから当初は,パンフレットの類の簡単な解説文のようなものを念頭に置いていたと思います。しかし始めてみると,簡単には済まないことになってしまいました。というのも,少し考えればいうまでもないことですが,改めて思い至ったのは,心の問題は大変に複雑で,奥が深く,我々のような専門的な立場にある者にとっても,容易に扱えるものではないことです。
心の問題は人間存在そのものに関わります。心の病気はそのことと無縁であるはずがありません。従って心の病気を考えるに当たっても,人間存在の全体を視野に置かなければ,「群盲象を評す」の喩えのとおりになってしまいます。
考えてみれば,いかなる場合でも「簡単な解説」というのはむしろ難しい作業です。その問題に精通している上位者でなければできないことです。
学問一般についてみると,問うものと問われるものとはひとまず分離しています。つまり研究者が,外在化されている何らかの対象について問いを立てます。どの研究分野であれ,学問的に解明されつくすという事態はほとんど考えられないことなので,誰が第一人者かというのはそう簡単な問題ではありません。しかし一般論でいえば人間の営為には違いないので,ある研究領域に最も精通している人といういい方は可能です。人間の営為というのは,問う者としての人は,問われている事象の外部に位置しているという体裁の下での行為という意味です。この体裁の下では,人は,問われている事象に対して,それらの全体を知ることが可能であるという原則の上に立っていることになります。
ところが人間が人間自身を問う場合,誰が上位者かという問いには,これとは別種の困難があります。
この場合は,問う者としての人は,問われているものの外部に位置していません。喩えていえば,自分の尻尾を噛んでいるウロポロスの蛇のように,問題に食らいついても,終わりのない円環から抜け出せないことになりかねません。つまりウロポロスの尻尾をつかもうとするのがウロポロスの頭であれば,出口のない迷路をさまようだけということにもなるのです。
かつて哲学者のソクラテスが,彼の信奉者が受けた「ソクラテスより賢い者はいない」という神託の真意を知りたいと考えました。彼は,人間が人間らしく生きるためには,その根本知が必要であるが,自分はそのことに関して無知であると自覚していました。当時のアテナイ市民は,成人はすべて立派な市民であるための徳を身につけていなければならないと考えていました。その徳は人間社会が作り出した規範的なもので,その意味ではソクラテスは,いうならば落ちこぼれでした。神託を受けてソクラテスは,当時の知者として名高い者を尋ね歩き,彼らの考える徳についての根拠である知を問い質しました。結論的には,ソクラテスの反問によって,彼らの全てが空虚な知にしがみついていたに過ぎないことが暴露されただけでした。それでソクラテスは,神託の意味する賢者とは,「無知であるのを自覚している者」ということであり,真の知者は神のみであるという結論を得ました。
この例は,人間の上位者は存在するかという問いに対する一つの答えを提示しています。つまり人間の問題を熟知している人間はあり得ない,人間の問題に関するかぎり,敢て上位者を名指しするなら神とでもいうしかないということになるかと思います。
ですから,心の問題を語ることは根本的に難解です。そういう事情を考えれば,心の病気についての「簡単な解説」などというのは初めから無謀なことでした。
とはいえ,心の病気の専門家はいますし,私もその端くれの一人です。この問題は難解すぎて何も分からないというのでは,笑い話になりかねません。ともかくもそういう仕事をしているのですから,責任もあります。それで,一旦始めた以上は止めるわけにはいかないのですが,私にできるのは,日ごろの診療を省みて,そこから意味がある(と思われる)糸筋を慎重に引き出してみることのように思われます。そういう思いで作業を試みているうちに,いつしか自己研鑽の場になっていきました。それを「院内通信」という形のままで敢えて残したのは,一つには私に関わりを持たれた方に私の考えをお伝えしたいということです。そしてもう一つには,どなたが読んだとしても読むに値するものでなければ意味がないので,公開という形で一定の緊張の持続が保たれるだろうと考えたことです。
気になるところを直し直ししているうちに,思いのほかに大きくなってしまいました。それどころか永遠の工事現場のような気配で,これでお終いということがないだろうという果てしもないことになっております。
また当初の’M子さんの症例’に即するつもりが,まったく変化してしまいました。自己研鑽ということですから,症例の検討が欠かせません。症例を通じて浮かび上がって来るものを,可能なかぎり論理の糸で繋いでいくのが生命線といえます。症例を記載するに当たっては,ご迷惑をお掛けしないように出来るだけの配慮をしているとはいえ,全くの作り物では客観性という観点からあやふやなものになると考えますので,どうしてもご本人の目に入れば自分のことだと分かると思います。そこで最も怖れたのは,不快感を持たれたり,抗議を受けたりすることです。いちいち予め了解をいただくのが筋ですが,それは大切とは承知していても,なにせ多数にわたり,全ての方のご了解をいただくのは現実的ではありませんでした。ご本人が読まれたとしてもご不快のないようにという姿勢には注意しました。ご本人から,「読んだ」といわれたことも少なくありませんが,幸いにして抗議の類はいまのところ一件もありません。
ここに上げる症例は,いうまでもなく興味本位ではなく,あくまでも問題を掘り下げて一般化していくための素材です。私自身の自己研鑽という意味があるものの,患者の皆さまに益するものと信じて作業を続けています。何かご不快があればお話いただきたくお願いいたしますが,趣旨をご理解いただけると有り難いことです。
いま述べたように,心の病気の問題は人間存在そのものと切り離すことができません。従って,問題の捉え方が人によって異なり,一様ではないのが当然といえます。
医学は自然科学の方法論で進歩,発展してきました。心の病気も医学の一分野ですが,自然科学をそのまま適用できるものではありません。自然科学は’物’を扱う方法論で,’生きている全体’から不透明なものを排除して,意識の光が隈なく行き渡るように物を純化していくことで成り立つものです。その方法は厳密で,科学であることの見本ではあります。心の科学も科学であるからは,それを手本にする必要があります。その際,取り分けて難点になるのは,心には無意識の世界があるという問題です。自然科学が隈なく意識の光を当てていくことであるという原理からすると,意識の光を当てることは不可能であればこその無意識に対して,自然科学は全く歯が立たないことになります。
それにしても無意識の世界があると分かる(意識できる)のは何故でしょうか?
その答えは,(自我に拠る)意識の世界が有限であるということです。つまり有限の世界があるということは,無限の世界があることが前提となって可能なのです。無意識の世界とは,自我の光が届かない心の領域があるということであり,その存在は自明であるといえます。
このことを定立化していえば,「無限の世界は存在する。心に関しては無意識の領域が無限の世界である。その存在は自明である。しかしその存在様態を意識が捉えるのは不可能である」ということになります。
あらゆる対象は意識に映じるかぎりで存在しています。つまりあらゆる対象は,現象として存在するのです。それが自我に拠って意識と共にある人間の実相です。たとえ物理学の対象が’純化された物’であるとしても,意識に映じているかぎりの存在(現象的存在)であることに変わりがありません。換言すると,「純粋の物とは何か」という類の問いは,人間にとっては何のことか分からないのです。そして客観性の保証は,我々が意識が正常であるかぎりは,誰もが同一の体験が可能であるというところにあります。物理学的に’純化された物’の純粋性は,意識が正常な者なら,万人がその対象についての体験を等しく共有できるのは勿論のこと,因果律という純粋論理として定式化が可能であるというところにあります。それは当の対象を見ている科学者の眼から,無意識的心を徹底排除することで成り立つものでもあります。対象に意識の光が隈なくおよぶというのは,そういう心の動きがあって可能なのです。
ところで心を自然科学者の真似をして捉えようとするとき,心のいたるところに無意識が入り込んでいるのが難点になります。
例えば100メートルの競争という単純な行為であっても,無意識が入り込んでいるのです。この競技の新記録の限界値をいい当てることができる科学者はいないでしょう。誰であれ5秒以内で走るのは無理だと思うでしょう。限界があるのは明らかなのです。しかし具体的な数字で予想するのは不可能です。現在の新記録は少しずつ破られていくに違いありません。つまり,意識の光が隈なくおよび,この問題に最終決着が与えられることはあり得ないでしょう。仮にそれが可能であるとすると,100メートルの新記録を狙う者などいなくなるでしょう。競争をすること自体がばかばかしいことになるに違いありません。無意識という無限定なものがあるからこそ,人間は絶えず目標を持ち,挑戦的に生きていけるのです。
このように自然科学者の思い通りにならないことが,この世を生きていく上で大切なことであるという皮肉が,学問的にはある意味では人間を悩ませます。この場合,「群盲象を評す」という喩えに即してみると,群盲は自然科学者であり,象は無限的なもの(無意識)ということになります。それで心を科学的に見ていく上で,自然科学の手法に見習いながらも,群盲であることから脱する試みが求められます。そのためには,心の全体を俯瞰する立場を求めなければなりません。それはどうしても心の上位者の措定という問題にならないわけにはいきません。
そういうことをふまえて,心の科学が自然科学者の真似をしようとすれば,意識が捉えることができたものを里程標のようにみなし,それらを繋ぎ合わせていくことになります。心の病気の場合,患者さんが苦痛な体験を語る言葉が里程標ということですが,さまざまな患者さんがさまざまな表現をするので,それらをどう解釈するかはそれぞれの治療者が自分の心に意識の光を当ててみる作業が不可欠です。確かなことがいえるとすれば,この作業を通じてです。そしてそれを再び患者さんの語るところとつき合わせて整合性を図るのです。それでも心の問題ですから不確かさが絶えず残るでしょう。継続的に患者さんの言葉に耳を傾けて訂正したり,確信したりすることになりますが,洞察が深ければ,そういう過程で旧来の確信がそのまま残ることになります。そして決定的に重要なのは,得られたものが治療の上に反映され,有効性が確かめられることです。
心についてのこうした作業を難しくもさせ,意味深くもさせているのは,心の内なる無意識の問題があればこそです。心という生きている人間の全体に関わるもののいたるところにあり,生きていることの源泉でもあるのが無意識です。これを避けて心を語ることはできません。その上に無意識の問題を語るとき,自然科学者の手法を借りて,可能なかぎりの科学的客観性を確保しなければなりません。科学的な説得性が内包されていなければ意味を持ちません。しかしながら無意識という海であるが故に,里程標はいたって不確かです。そういう状況でのこの作業では,人為的な里程標を打ち込んでいくしかありません。
その作業は以下のようになります。
現象世界に現れている心的事象を理解しようとするときに,無意識の世界の存在様態を知る必要がどうしても出てきます。しかし実際にはそれを確かめる手がかりが希薄なので,日常の現象的な実在になぞらえて,比喩的に,仮定的に命名し,仮に実在させる必要が生じます。それは我々が知りたいと考えている現象世界に生じている謎に,仮説を建てることで自然科学者に準じようとする作業と考えることができます。それらの仮説は,自然科学者がするようには実証する術がありません。それらは永遠に仮説の域を出ることはありませんが,是非とも知りたいと考えている現象的事実の謎に対して,それなりに首肯させる力を内包させていれば,ひとまずの収穫というべきです。そしてそれ以外には打つ手がないのです。
それらの仮定的な里程標の中で,最大のものが心の上位者の措定です。それを内在する主体と,ここでは呼んでおきます。内在する主体は,心的世界の,あるいは一切の現象的世界を統括するものです。また,自我がどのように自己を導けばよいのかを知っている唯一者です。自我は精神活動の中枢に位置します。換言すると精神活動の頭にあたります。そして精神活動が生じているかぎりは,いわば足となるものの力を借りなければなりません。それは主体が送り出してくる欲動といわれているものです。いわば神の子(白い子)を護りとおすことにより,自我は主体の意向を自ずから尊重し,実践する意味を持つと考えられます。
病的な心理現象を扱う上で,以上の仮説を掲げることの有効性は,心を悩ませている患者さんの大方に,いかに理解され,共感されるかにかかっています。そしてそれらの説明は,少なくはない患者さんの共感と理解とが得られており,自分を悩ませている問題への理解が進むことに伴って,かなりの治療的効果が認められています。
以上のことを前提として,私が描いている心の見取り図は,以下のようになります。
心には二つの中心があります。
C.Gユングは自我を意識の中心と呼び,自己(セルフ)をこころ全体(意識と無意識)の中心と呼んでいます。
自我は(人間的な)世界を切り開いていく拠り所であり,(現実的な)精神活動の一切の中心です。人間の活動には,いかに身体的なものであれ,精神性の関与をまったく欠いているものはないといえるでしょう。仮にあるとすれば,自我の機構に何らかの故障が生じたときです。このことは,裁判で責任能力が問われるのと関係があります。心神喪失と認定されるときには,自我機構の決定的な不具合が生じているのです。
摂食障害やアルコール依存など,依存症といわれるものが病的であるゆえんは,その行動に溺れながら精神性の欠落感に苦しむところにあります。苦しんでいるくらいですから,精神的に満たされることへの渇望があり,しかしそれが適えられる希望がまるで見えないのです。それは自我の機構的な不具合ではなく,自我が機能不全に陥っている姿です。
自我が超自我と無意識界にある分身たち(黒い子たち)から自由であり,自立しているかぎり,精神は健全です。そして自我が機能不全に陥っているときには,超自我が自我の上位に立ち,黒い子たちもそれに連動して自我の上位に立っています。それらの勢力の狭間に埋没する自我は,著しい苦境に置かれることになります。
このように自我が機能不全化するのは,次のような過程があってのことであろうと思われます。
幼い時代には,心にさまざまな欲求が生まれてきます。それらはすべて大切に扱わなければなりません。例えば2歳の子であれば,遊びに行った友達の家の玩具を黙って持ち帰ることもあるかもしれません。2歳の子がしたことであれば,それを泥棒と呼ぶ者はいないでしょう。しかし5歳の子が同じことをすると問題になります。だからといって2歳の子のそうした行動は咎められるべきではありません。むしろそうした行動は自然のことであると捉え,その上で事の善悪を教えていかなかればなりません。生まれてきた欲求自体は善悪の問題ではなく,自然のものです。その上で人が成長していくには,他人との関係を教える必要があります。善悪の問題は他者との関係が前提になって問題化するのです。他者との関係は,内なる他者として自我の機構に内在していると思われ,親が子に善悪の問題を教えるのは,そういう前提があってのことで,親の恣意による教育というわけにはいきません。
他者との関係を自我が課題化することにより,心は社会性と精神性を獲得していくことになります。それは人の心が豊かになっていくための要点になります。
他者との関係は決定的に重要な意味を持ちますが,無意識の自然から生起してくる白い子たちを,自我が護れなくなる理由になります。他者との関係において,白い子を自我がいかに護っていくかが問われることになり,そのことを教えてくれる立場の中心にあるのが,父親と母親です。しかし彼らは部分的に正しく,部分的に間違っているのが一般です。すべて正しい親はあり得ません。
親の指導が間違っているときに,子供の自我は白い子の扱いに失敗して,黒い子にしてしまいます。
親の指導は,正しいことも間違っていることもひっくるめて,子供の心に主観的に取り込まれ,一定のイメージとして内在化します。これが,超自我と呼ばれている自我の後見人ということになります。一方,自我が護ることができなかった黒い子たちも,心の一角を占めることになります。
心はこのように自我を中心として超自我と影の分身といえる黒い子たちによって,そして心の最奥に在る主体とによって構成されます。超自我と影の分身たちとは半ば無意識の世界にあり,主体は完全な無意識の世界のもので,我々にはその存在様態は知る術がありません。
そのような構成の中で,自我が自由と自立性とを保っているときには,主体との関係はうまくいっていると考えられます。このことを見方を換えて説明すると,以下のようになります。
自我が何かの行為を主導するときに(精神活動が営まれるときに),主体が行為の足となる白い子(神の子)を送り出してきます。その白い子を自我が護りとおせば,白い子が抱えていたエネルギーは自我に渡され,活力が高まります。それは主体のおめがねに叶ったことを意味するでしょう。
逆に親との関係で,幼い自我が白い子を護ることが出来なかったときに,白い子は怒りと共に黒い子に変化します。神の子は,一転して,いわば悪魔の手先に変わることになります。
白い子の中でも,取り分け甘える欲求が封じられる何らかの事情があるときに,この問題が重大化するでしょう。その欲求は強力なエネルギーをはらみ,諸欲求を満たす基礎ともなるものです。それだけに,それを封じる力を持つことができたのは,根源的な恐怖だけであろうと考えるべきです。
こういう状況では自我は怒りを抑圧しつづけることになります。抑圧された怒りは黒い子と共にあり,それは超自我とも連動します。いわば黒い子をおびただしく作るような自我に対しては,超自我も怒りを持つともいえます。怒りのエネルギーの蓄積が大きくなると,超自我は優しさを減じ,命令的で懲罰的になります。いわば怒れる後見人になります。自我は相対的に地盤の沈下を来たし,超自我と影の分身たちとが上位に立ちます。自我は物いえぬものとなり,絶えず超自我に威嚇され,責め立てられ,黒い子達の嘲りを受け,という事態になります。
(例えば強迫性障害といわれている病理的な現象では,とりわけ超自我は苛烈な懲罰者の姿を表しているように見えます。超自我は自我に,安全の完璧な確認を求めるかのごとくです。完全性を求められても応える術がないのが人間ですから,自我は確認行為という完璧の真似をしてみせることになります。それは内容を欠いた悲痛な演技のようであり,儀式以上の意味を持ちません。それは超自我の苛烈な要求に従って見せているようであり,懲罰を受けている姿のようでもあります)
自我に拠る世界は光の世界です。精神の活動には,無意識という暗闇のものの関与がさまざまにあるので,陰翳の彩りがありますが,自我の機能が活発なかぎりは光の強さは強力です。それは比喩的にいえば,無意識という暗黒は無限大の広がりがあると想像されるので,これを暗黒の宇宙とすると,自我はその宇宙に浮かぶ一片の星です。その星は,包囲している暗黒の無限からすると,いまにも呑み込まれてしまいそうな頼りない存在に見えます。しかし星が力強く光を放っているかぎり,圧倒的な闇は存在しないかのようです。そして闇の力をいずれ知らされることになります。一つには心の何らかの病のときに,そして決定的には死期が近づいたときに。
この光が満ちているとき,自我は一切の上に立つ勢いがあります。それは自然科学が大掛かりに実践してみせてくれました。自然科学の勝利は,自我に拠る人類の勝利です。人は光をもとめ,光の世界を切り開いて行くものなので,そのかぎりで自我は最上位のものです。そして心の内部の暗黒を探るのも,自我です。しかしこの世界を隈なく光で満たすのが不可能であるのは,最初から誰にも分かることです。自我には手に負えないものが確実にあると認めるしかありません。
自我の活動に限界があるのが明らかであるように,自我が存在している理由そのものも不可知の闇に包まれています。自我は自我自身を知ることはできません。
自我が我々が知ることができない事情によって,自らの存在を自らに与えるべく意志したのかもしれないと考える人があるでしょうか。あるいは自我が存在するのは単なる偶然だという人がいるでしょうか。あるいは自然のサイクルの中の説明できないいきさつがあってのことだという人があるでしょうか。そしていつか人間の科学する力が,それらの謎を解き明かす時が来ると信じている人があるでしょうか。
いっそのこと,人間が存在しているのは神の意志によるというふうに考える人はいないでしょうか。合理主義精神が隅々まで行き渡っている現代において,神の問題はどこかタブーの趣があります。信仰を持っている人たちは,仲間内ではともかく,どこか肩身が狭そうにしているように見えます。ですからこういうことを考える人がいるとしても,滅多には口に出せない時代的な雰囲気があると思います。実際,神が云々といい出せば,たいていは一笑にふされるだけでしょう。
しかし私にいわせれば,以上に挙げたどれもが五十歩百歩です。合理主義精神は自我の責任範囲に関しては有意味ですが,自我は無意識という海に浮かぶ小舟のような存在なので,無意識の世界のことを自我がどう捉えるかは手に余るとはいえ,そこを無視すると精神が干からびてしまいます。それなりに捉える工夫はむしろ欠かせないはずです。
そんな人はいるとも思えないのですが,人間の存在理由を科学的に証明できると信じている人がいるとすれば,それこそ笑いものという気がします。
自我が人間の心の最上位者ではあり得ないのは,厳然たる事実として認めるしかないはずです。言葉を換えれば,光のものである自我の力が及び得ないものがあるのは,改めていうのも気が引けるほどに明証的です。その最上位にあるものをどのように命名するかは,あまり問題ではありません。自我の存在が単なる偶然であるといってみたところで,それで何かを証明したことになるわけではありません。我々には何か分からない理由があるといっているのと同じことです。
我々には理解し得ないものがある,自我の存在理由もその一つであるというのは明証的なものであるにもかかわらず,それを敢えて認めようとしないことが,自然科学の影響に置かれている現代の迷妄というべきではないでしょうか。科学の言葉で捉えることができないという理由から,自我の上位にあるものの存在を認めないことに,どんな意味があるのでしょうか。
ここではこの最上位にあるものを,内在する主体と呼んでおきます。それは自我の光が届かない無意識の世界の最奥にあるものと,仮定的に里程標を打っておきます。
我々が知り得ない理由によって自我がもたらされ,人間の存在が可能になったと考えることに,何か重大な見当違いがあるでしょうか?
そのように考えると,自我の最も大きな使命は,引き受ける精神です。
私は以上のことの恰好の実例をソクラテスに見ます。
ソクラテスは神の助手を自認し,公言していました。つまり神の意志を引き受けることに最大の使命感を持った人のようです。彼の時代のアテナイ市民は,合理主義精神に活路を見出し,活気づいていましたから,ソクラテスが奇妙な神(ソクラテス自身が,「子供のときから鬼人の類からの合図があった」といい,ぶつぶつ独り言をいいながら心内の声に聞き入っていたといいます)を信奉し,世を惑わすことは,為政者には看過し難いことでした。彼は為政者などの権力者に媚びないという点で,傲慢な人物と見られました。彼は誰が何といおうと,自ら信じていること(神の助手としての勤め)を実行しつづけました。
権力者たちの前では傲慢だった彼は,神の前では敬虔であり,あくまでも謙遜であったといえるようです。それは彼が人間である自分の上位者の存在を認めていたからです。彼は神の声に一心に聞き入り,その意志を引き受けようとした人のように思われます。
自分の上位者を持たない者は謙遜である根本理由を欠きます。そして謙遜とは,人間の最も崇高な精神の一つだと私は思います。
自我を最上位に置く自然科学は,干からびた威力をもたらします。それは大きな仕事を成し遂げてきた一方で,救い難い傲慢の罪を犯してきたともいわなければならないようです。
魂に潤いを与えるのは無意識の力です。その力を自然科学が,自分の上位に置くことができていれば,人類はまったく別様の文明を持ったに違いありません。
ソクラテスが心内の声に聞き入っていたといわれますが,その声の主こそが内在する主体であると,私には思われます。このことは,C.Gユングが述べていることとも符号します。
彼は次のように述べています。
「いま自分(の心)に起こっているのは何か教えてほしいと,心内のアニマに向けて問いかけた。問いかけるその姿勢が不確かであれば,反応はいい加減なものだった。しかし真剣になればなるほど,意味深い反応があった・・・」
自我の役割の最大のものは,引き受ける精神だと思います。引き受けるというのは,ソクラテス流にいえば,’神の意志’をです。ここでは主体の意志をということになります。ソクラテスやユングのように,心の内奥に在る主体の声に聞き入ることが必要です。自己を形成するというのは,主体の意志を実践することであると考えることができます。主体は,自我がどのように人生を切り開き,自己の達成に向けて導く働きをしているか,沈黙のうちに見守っていると考えられるのです。
実際にどうすればそれが可能かというのが問題です。
このことの仮定的な考えの一つは以下のようです。
自我のエネルギーは自我の位置を保つためのものと考えられます。自我は心の司令塔の役割を担っています。いわば心の頭であり,行動を実践する力は持っていません。何か行為(行動)をするときに,自我は計画(目標)を立てます。それを実践するためには自我のほかに,行為の足となるものの協力が必要になります。
日常の精神活動は,その眼で見てみると,個々に何らかの目的を持った行為(行動)群から成り立っているのが分かると思います。それらの個々の行為(行動)について,自我は自動的に無意識に呼びかけると考えることができます。それに応じて主体が行為の足となるものを送り出してきます。それはいわば神の子です。自然から生まれてきたばかりの無垢の子(白い子)です。自我は必要があって呼び出したのですし,行為の欠かせないパートナーであり,無垢であるが故に傷つき易くもある白い子をしっかりと護りとおすことが大切です。何せ神の子ですから丁重に扱わなければならないということでもあります。
スポーツ選手や囲碁などの勝負師,あるいは思索している人,研究に打ち込んでいる人などが,心の集中に極力努めているのは,自我が白い子との協働作業に没頭しようとしている姿です。
我々はすべての行為(行動)をまっとうできるわけではありません。言葉を換えれば常に神の子を護ることは不可能です。それは人間が,動物的な自然を生きるのではないことに伴うものです。そういう意味では,刻々と黒い子を生み出しているとも考えられます。しかし行為の価値には軽重があります。それぞれの分に応じて,現実的,かつ意味深い仕事を自我が成し遂げることができれば,それで十分といえます。
精神の充実は,つまるところ自我がどの程度の仕事をしたかということにかかっています。幸いにして大きな充実感の中にいることができているとき,自我は大筋で神の子を護ったことを意味すると考えられます。それは主体の意向に即することができたという意味です。
白い子を護るためには,行動の目的を敢えて確認してみるとよいと思います。そうすることで,白い子に意志を伝え,共に行動してくれるのを感謝するのです。首尾よく予定の行動が終われば,白い子は抱えてきたエネルギーを親である自我に渡したことになります。自我はエネルギーの補給を受けることになり,一定の満足感や充足感を得ることができます。
逆にいえば無為に過ごしていると,自我のエネルギーはしだいに枯渇していきます。
以上に述べたように,心の病は自我が機構的にか機能的にか,何らかの不具合が生じたときに起こるといえます。つまり自由と自立性が損なわれている自我は,与えられた状況的な課題を担えない,引き受けられないということが起こっているのです。
最初に提示したM子さんの過食と拒食,自傷行為は,いずれも臨床場面で日常的に見られる病態です。
過食にふけっているときの様子は,餓鬼道に落ちた亡者を連想させるものがあります。人目を避けて一心不乱に獲物に向かう悲しい姿がそこにあります。そのことに関して自我は機能せず,いわば無意識の仕事を無気力に傍観するばかりです。
摂食障害の治療は,依存症一般がそうであるように,易しくありません。
人は何かに依存しつつ生きています。人はまったくの自由,まったくの自立を生きることはできません。いうならば何かに掴っていなければ,押し流されてしまうのです。どこへかといえば,死へです。不安の根源には死があります。しっかりとした拠り所に掴っているのでなければ,不安に脅かされます。その度合いがひどければ,頼りないものにすがっていることの意味が分からなくなります。いっそのこと,当てもなく耐えるよりは,すがる手を放してしまった方が楽になれると考えることにもなります。
食べることにこだわる(すがる)のは,彼方に死の影が見えるからともいえ,それを見たくないばかりの必死の行動ともいえるように思います。見方を変えると,自我がこれほどまでに無気力なのは,おびただしく黒い子を作り出してきたいきさつがあるからです。黒い子は,神の子(欲求ー白い子)として主体から送り出されてきたものを,自我が護れなかったものたちです。それは主体の意向に即せなかったことになります。引き受けるべきである自我がそれを拒否したことになり,白い子,あるいは主体の側からすると不当,不埒という意味を持ちます。
自我が引き受けず,見捨てることになった産物である黒い子は,怒りのエネルギーを抱えることになります。そのエネルギーは,元は白い子が抱えていた生きるためのものです。自我はそれを受け取らなければ,エネルギーの補給を受けることができないのです。
神の子であった白い子が,一転して怒れる黒い子に変じて,悪魔の手先になったと考えることが可能です。
とはいえ,黒い子もまた,自我の子です。その関係は非行少年と親とのそれに似ていると思います。黒い子はいつか親である自我によって,改めて引き受けられる時が来るのを待っています。
(全(無限)と無とは正反対のようですが,それは有限性を生きる人間にはそう思えるということです。全とは限りない広がりのイメージから来るものであり,無とは限りなくゼロに近づくというイメージから来るものです。そして全そのもの,無そのものは,現象的実在として捉えることは不可能です。それらは有限性を超えたものであるがために,人間の意識の光が遠く及ばないものです。そういうことから全が良きものの最高のもので,無が悪しきものの最悪のものというイメージを持つことになります。最高のものとは,例えば神であり,最悪のものとは,例えば悪魔というわけです。全(無限)と無との分離は,人間の能力を超えたものについての人間的な把握の仕方といえます。
自我は心に関して二分化して捉えるのが特徴です。心には内なる他者,内なる異性などがあり,それは外なる他者,外なる異性と合体して完全な一者ということの内的な意味のように思われます。有限性を生きる人間は,この意味で二分の一以下の不完全な存在です。実際には起こり得ない他者との合体は,永遠なる一者,完全な自立など,無限なるものへの憧憬としてあるのだと思われます。そのようなことが前提になって,現実世界の人間は,他者を深く愛するときに至福の感情に浸ることができるのではないでしょうか)
黒い子を作り出すのは,人間には避けられないことです。
たとえばこの黒い子の存在がなければ,芸術活動は成り立ちません。白い子たちのエネルギーを受け取ることができた証である心の表舞台を,芸術家が表現する意味はまったくありません。そんなことは下らない自慢話の域を出ないからです。芸術家が意欲を掻き立てられるのは,黒い子たちの要求があってのことなのです。心には人に見せられない裏舞台があります。そこは黒い子たちの世界です。黒い子の勢力が大きくなると人の目が気になるのは,自我が,それらの存在を人に気づかれるのは恥と捉えるからです。それはいわば自我の不始末(お粗末でもあります)の証拠であり,黒い子をたくさん作ってしまった自我は,怒れる超自我をも意図せずに作り出してしまっているからです。
芸術家が一般の人と違うのは,欺瞞を潔しとしない自我を持っていることでしょう。彼らは黒い子たちの存在主張から眼をそむけずに,それを取り上げようと意志する心を持っています。芸術家が黒い子の存在に眼を向け,自らを暴き立てようと意志したときに,黒い子は自我によって引き受けれらたことになります。それは自我が知らずに犯した不始末を,自ら意志して取り返したことを意味します。
このように意図して,あるいは意図せずに,黒い子を引き受ける自我が,独自の人生を創っていくのです。黒い子はそれぞれの人生の起爆剤でもあります。つまり黒い子たちをたくさん作り出してしまった自我は,それに押しつぶされるか,それともそれを起爆剤に変える力があるかということになります。
心の病気は自我の不全化と密接な関係がありますが,自我が黒い子をたくさん作り出す不始末を働くことになった根本には,人間の誕生の問題(出産外傷といわれることがあります)と,それを補う立場にある母親との関係(取り分け,生まれて間もない最早期の関係)があると考えなければなりません。
出産という人間の誕生は,「自我に拠って,限られた時空間を思うように生きてみよ」という意味を持っているように思われます。自我を付与したのは,当然,自我の上位者です。
限られた時空間を生きるということには,死の問題が必然的に付帯しています。元気に生きるというのは分かりますが,一歩踏み込むと死に向って元気に生きよという設問になります。死という巨大な壁に阻まれて,元気に生きるという設問は,難解極まりありません。
(誕生という)人生の出発点でも,死の問題は立ちはだかります。
生まれるということは,喩えていえば,無のまどろみから起こされて,1000メートルの高みに立たされるに等しいことのように見えます。原初の段階にある自我機構には,「大きな安心と大きな満足がもらえるから何も心配は要らない」という幻想をかもし出す装置が取り付けられているかのようです。それは無であった世界に準じるものを保証しようとするものであるように思われます。その幻想に基づいて,赤ん坊は完璧な安心と満足とを要求します。要求する相手は母親以外にはありません。
有限の時空間を生きる人間にとっては,全とか無とかは現象的実在ではありません。しかし生まれて間もない赤ん坊には,直接的に全と無とが問題になっているように思われます。というのは,赤ん坊が自我に拠って有の存在になったということは,全または無の存在があることを間接的に示していることになるからです。そして有の存在としてはあまりにも頼りない赤ん坊は,母親に全面的に依存するしかありません。つまり母親は,赤ん坊にとって全の存在に等しいのです。その対比において,赤ん坊は無の存在に等しいといえるでしょう。赤ん坊は無の感覚において全にすがるといえるでしょう。
赤ん坊が人間として存在する出発点の段階で,1000メートルの高みの恐怖に耐えて,いわば無事に着地するためには,心の緩衝装置が不可欠です。満足と安心との十全な供与を約束されている幻想は,そういう意味を持ちます。母親にはそんな大それた力はないという意味では,それはまやかしです。そもそも人間は,その存在理由が永遠の闇の中にあるという点からして,壮大なまやかしの中にいるといえなくもありません。赤ん坊が,巧妙なまやかしを甘受することから人間としての第一歩を踏み出すことになるのは,人間存在の宿命的な何かを暗示しているようでもあります。
このように,いわば全,あるいは無限,または無の世界から,有限の世界に降りる甚だしい不条理のドラマが開始されるのが,赤ん坊の誕生です。
不条理劇の存在理由は,永遠の謎です。しかしともかくも幕は上がったのです。赤ん坊は不承不承であれ何であれ,与えられた運命を引き受けるしかありません。およそ3年ほどの歳月をかけて,1000メートルの降下を,母親に助けられながら果たさなければなりません。3年ほど経てば,自分と人生とを引き受ける役目を帯びた自我のひとまずの基盤ができるのです。赤ん坊はこの間に,完璧な要求の旗を降ろし,ほどほどのもので我慢できるようにならなければなりません。ほどほどの満足,ほどほどの安心で妥協する気にさせるには,母親の愛情が鍵になります。それができたときに,ようやく,この世を生きていくのも満更ではないという喜びを知る基礎を手に入れたことになるのでしょう。
過食は意志と判断が働いて起こっている行動ではありません。つまり自我の仕事ではありません。自我が機能できなくなった原初的な理由があってのことです。自我が機能できなくなった裏には,黒い子たちがおびただしく作り出されてしまった事情があるはずです。黒い子は,自我が受け入れるのを拒否したために,精神性と社会性とから無縁となった存在です。黒い子をおびただしく作り出す自我は,幼いころの母親との関係に問題があったと考える理由があります。そのような自我は白い子を護ることができた満足が得られず,白い子が抱えているエネルギーの補給も受けられず衰弱します。一方で黒い子たちが自我を支配するほどに勢いを増すと,いわば黒い満足を取りにいきます。その黒い満足の一つが過食です。
人は,あるいは心は,何らかの満足を追求します。そこに自我の関与がないかぎり,満足の追求に精神性も社会性も望めません。それらが欠落したものが黒い満足で,それは決して心を満たすことはありません。
拒食と過食とを繰り返してきたある患者さんに,自我(親)と超自我(後見人)と(黒い)子とから成る心の見取り図を示してみました。その図では自我が上位に立たなければなりません。上位にある自我は自由と自立性とを確保できているのです。ところが黒い子たちをおびただしく作り出した自我の下では,抑圧された怒りが超自我を大きくさせます。怒りをはらんだ超自我は,命令的,支配的,懲罰的になります。これら超自我と黒い子たちとは,パラレルの関係にあり,一方が増大すると他方も増大するのです。そしてこれら二つの山に囲まれて埋没した自我は,自由と自立性とを失います。
そのような自我の下で,超自我が活発なときには拒食に走ります。懲罰的な超自我の支配下での食行動は,それが極端になると身体性が否定され,精神性のみの追求が要求される観があります。この患者さんは,瘠せの極限で,死んでも構わないと思いました。身体性の全否定は,当然,死につながります。しかしやがて生きたいという意志が発動して,食事を摂りはじめ,元気を回復しました。そしてひとしきり経って,今度は過食にふけるようになりました。それは黒い子の仕業です。
超自我の勢いが収まると,一旦は自我が力を回復したものの,やがて黒い子たちが勢いを増し,自我を支配したといえるようです。このとき自我は,黒い子の動きを傍観するばかりです。
この患者さんの例から窺えるように,自我の機能は固定されたものではなく,あるときは自由を得,あるときは超自我の支配を受け,あるときは影の分身である黒い子の支配を受けるといえるようです。
患者さんは,以上の仮定的な説明に,まったくの同意を示しています。
乳児の精神的な満足は,授乳を通じて得られます。
フロイトは生の本能と死の本能とに言及していますが,生の本能はエロスともいわれます。一方プラトンは,愛の形態には肉欲から始まってしだいに上昇していく諸段階があり,その最高位にあるのが純粋な愛,つまり美のイデアへの希求であるとしました。そして真善美に到達しようとする哲学的衝動を,エロスと呼びました。
このように,生きる喜び,満足には,高度に精神的なものも含めて,その機軸となるエネルギーが性的であるというニュアンスが多分にあります。そして精神分析では,このエロス的な満足の身体的根拠がいくつかあり,心の成長に伴ってそれらの発達段階をたどるとしています。そのプロセスを精神性的発達と呼び,その最初の拠点は口唇にあるといわれています。これらの身体的個所は,erogenousuzoneと呼ばれていますが,日本語では「性的に敏感な」という意味です。
つまり生後間もなくからおよそ1歳半までの口唇期は,最初の性本能が満たされる時期ということになります。欲求一般を受け止めて,護る,あるいは満たすという心の作業は,自我の重要な役目ですが,とりわけ性本能(広義の)は強い欲求で,それをどのように満たしたかということは,精神的発達に大きな影響を与えます。
母親による授乳には,赤ん坊に口唇によるエロス的な満足とそれに伴う安心とをもたらす特別な意味があります。それは栄養の補給に勝るとも劣らない意味を持つでしょう。
自我に拠って有限化され,二分の一以下の存在となって個々に孤立している自己なるものに,エロス的な満足は,他者との完全な結合によって一者となる幻想をもたらすもののように見えます(自己と他者とが一体化して一者となるのは,人間の情念的な理念であるように見えます)。それだけに,エロス的なエネルギーには強大なものが秘められているのです。
そうした意味を持つ授乳は,信頼と愛情とを保証する基になります。それらは相互的なので,授乳によって満足と安心とを保証された赤ん坊は,愛されている,信頼されていると感じると共に,母親を愛し,信頼する基盤を得ます。
逆に,強大なエネルギーを秘めたエロス的な満足であるがために,授乳による継続的な満足が欠落する何らかの事情があれば,赤ん坊の心は不満足と共に,不信,不安,恐怖,怒りなどによって脅かされることになるでしょう。それは愛されていないと感じる大きな理由になります。そして愛されていなければ,信頼されていないと感じるでしょう。そうであれば母親を愛し,信頼するのも難しくなります。
摂食障害は,この時期のそうした心が意識下に潜行していたのが,あるとき病理現象という装いで浮上したもののように思われます。
なぜ意識下に潜行することになったかといえば,見捨てられる恐怖からです。そして摂食障害の患者さんたちは総じて’良い子’なのです。つまり内心のネガティブな心を,自我が笑顔でカムフラージュするのです。その葛藤は容易に解けないほどに,自我は笑顔の欺瞞性を,滅多には自ら認めようとはしません。
これは自我が母親への強い恐怖心から,自分を捨てて母親の自我にしがみついた,あるいは傀儡化してしまったともいえます。
こうした人生を賭けた心の欺瞞化構造を招いた根本にあるのが,人間に根源的な見捨てられる恐怖です。それは以下のように考えることができます。
先ほど述べた1000メートルの降下は,有の存在となったがために無に怯える赤ん坊の心を,比喩的に描いたイメージです。この降下を助けるのが母親です。母親の助けは,絶対不可欠です。絶対というのは,有の存在が無に帰する怖れに遭遇したときに意味を持ちます。赤ん坊にとって母親は全に等しい存在です。赤ん坊は無に怯えるものであるがために,全なるものを必要とします。
つまり全なる母親は,場合によっては無をもたらすかもしれず,その可能性を否定する術はないのです。1000メートルの降下中に,母親が赤ん坊を支える手を放せば,それでお仕舞いです。
無論,それは身体的な虐待の話ではありません。心理的に見放されることへの恐怖の話です。乳児にとって母親から見放される感覚を覚えるのは,死に等しい恐怖につながるといえるでしょう。それが見捨てられる恐怖であり,この心性が根源的な恐怖である所以です。
摂食障害という心の病理の形成過程の端緒には,以上のような,本人も知り得ない人生の最早期の問題が潜んでいると思います。
この時代の乳児の要求は,大人の想像を絶した激しいものであるようです。生きるか死ぬか,そのぐらいの大きなものがかかっていると思います。心の成長の原初の段階で,生きるために欠けてはならないエロス的な強力な満足の要求が適えられなかったとすれば,その理由は,それを上回る恐怖があったからに違いありません。それが適えられなかったことへの不満と怒りとは,それだけに極めて大きなもののはずですが,それを上回る(見捨てられる)恐怖のために抑圧され,意識の上にのぼることはなかったと考えられます。問題は欺瞞化されたまま,一応は収められた形になります。しかし消えたわけではなく,ほとんど生涯にわたって心に影響をおよぼします。表面の明るい笑顔とは裏腹に,真の生きる喜びが欠けたまま年齢が重ねられていることも多いのです。
親子の関係は重要で,精神医療ではことあるごとに問題視されます。それだけのことがあるのは間違いないところですが,その他に,自然と人類という更に大きな問題があります。
胎児の段階までは,人間が自然の一部でいられた特別のものです。そして出生という新たな段階を向かえるのですが,おめでたいはずのこの出来事が,どこか楽園追放という趣もないではありません。誕生という形で胎児は自然から切り離されて,なんのためとも知れず,人として人生の難路を旅する宿命を負わされます。その際,自然が授けた人間への武器が,自我といわれるものです。自然から乖離され,胎児は人間として独自の道を切り開くことになります。その営為の中心的な役割は自我に委ねられています。そのように自我は人間になくてはならない特有のものですが,自我自体はいうまでもなく人間が自らの意志で手に入れたものではなく,授けられたものです。換言すると,それを授けたものの存在があるのが明白だということです。ですから人間は自然から独立した存在とはいえ,自然のしもべの立場でもあり,自然の支配を受けています。
比喩的にいえば,自我は海に浮かぶ小舟の船頭です。海はもちろん無意識の世界です。
心に障害といえるほどの問題が生じれば,しばしば激しい感情が自我を翻弄します。その様子は荒れる海に浮かぶ小舟のように危うく,時には,立ちすくむ自我を後目に,怒りに駆られた阿修羅のような行動に駆り立てます。
高校時代に不登校の経験を持ち,中途退学をしたK子さんは,難関の大学に入りました。失恋がきっかけで発病しました。診断は境界性人格障害です。ふとしたことで怒り,憎しみがこみ上げてくると,行動を抑制できません。時間かまわず相手の男性に電話をかけたり,直接押しかけたりしてしまいます。自殺衝動が強く,相手を殺すか,自殺するかしなければ収まらないという気持ちになります。過呼吸発作が頻繁に現われます。何日か気分が落ち着いている日もあります。しかし急に別人のように激しい感情が心を席巻します。自分から求めて入院となりました。
無意識の海が荒れると,小舟の船頭である自我はなす術がありません。エネルギーの中心には怒りがあります。阿修羅のようなその激しさが分別を打ち砕き,行動に駆り立てます。なぜ人生のこの時期に,この激しさで,怒り狂う感情が心を席巻するのか,共感を持って理解するのは困難です。人の心理としては共感も理解もできないという異常な事態は,心理的理解を越えた出生に伴うなんらかの障害ということになるのかもしれません。
せめて海が荒れてひどい事態にならないように,我々ができることは,子供に正しい操船術を教えることです。どうしてみても難しい場合もあると思いますが,できることをするしかありません。
ふつうは,親が子に正しい指導をすることで,心の海が不自然に荒れるのを防げるでしょう。自我がそれなりにしっかりとした操船術を身につけていれば,困難極まりない航海も,満更でもないものになります。
自我の操船術は,主に両親から教えられます。危険や困難を乗り切るための有能な先達が身近にいるのは,心強いものです。しかしそれでも遭難の危険はなくなりません。海が荒れれば,やはり自分の力で切り抜けるしかありません。人はどうしても孤独な存在なのです。
この比喩のついでにいえば,小舟には船長のほかに,その親(実際の親ではありません。内的な親です。超自我と呼ばれることがあります)と(黒い)子が同船しています。無難な航海をしている舟は,船長が中心的な役割を保っています。それでも黒い子(幼い自我が親との関係で引き受けることができなかった諸欲求=内在する主体が送り出してきた神の子=)たちは必ず同船しています。それは船長が自然の要求を完璧に護りとおすことが不可能なためです。同船している内的な親は何かと口を出し,それが船長を助けるよりは足を引っ張ることも少なくないからです。黒い子をたくさん作り出した船長は,内的な親との相対関係で,間違った操船を何かとしてしまったことになります。どこかで船長が反発して自由と責任とを取り戻す力を示さないかぎり,いつか内的な親が事実上の船長になってしまいます。そして扱いの厄介な黒い子たちがとかく騒ぎ立てます。小舟はあくまでも船長が責任を負うべきものなので,内的な親と黒い子たちとに主権が移ってしまった舟は,迷走し,大海の只中で目標を見失ってしまいます。それは死への漂流になりかねません。
操船術の本当の教師は,自然の摂理です。信頼できる人生の先達から受け取るべきものは,技術ではありません。精神です。自然の摂理を読み取る謙遜な無私の精神です。処世の技術は世俗的な意味があっても,人生の航海の目をくらまし,しばしば有害です。それは無私ではなく,謙遜でもないからです。目先の利得になにほどの意味があるでしょうか。処世の楽しみに飽き足らず,虚しさを覚える人があって当然です。生きる理由について,確かな手ごたえのある何事かを会得したいと考えるのであれば,海なる無意識そのものの力に注目する以外にありません。
乳児は,母親に全面的に依存する形で,人間としての第一歩を踏み出します。目標は母親からの自立です。
自立を妨げる要因は二つあります。怒りと恐怖です。これら二つの感情は,主に原初の他者である母親との関係で生じ,一種の外傷体験になります。そして黒い子を生み出す理由になります。母親との関係は原初の人間関係であり,そこで生じた外傷体験は,抑圧されて意識下に潜行することになります。それはいわばアキレス腱となって,後々,人間関係一般でそれに類似する体験状況の下で,新たに怒りと恐怖とを惹き起こしがちになります。そしてその都度,黒い子を生み出すことになります。
激しい怒りは,完璧な保全の要求をする乳児に特有のものと思われます。いわば人間であることを強いられたものが持つ,その要求と怒りは,自己を保存しようとするもので,本能に基づきます。それはその反面に,人間であることの拒否を含むといえます。自己保存の要求が本能に基づくように,その要求の裏面には死の本能があると考えるのが自然です。文字通り,生死を賭けた要求といえるほどの激しいものが,乳児にはあるのではないかと想像されます。
怒りと恐怖は双子のきょうだいです。
「人間として生きよ」と命じられたものが,生の反面に死があるのを意識せざるを得ず,それを大きな脅威と感じないわけにはいきません。その解き難く,超え難い矛盾は,怒りを持つ十分な理由になると思います。生きるという光の世界の温かさは,死の極風にさらされ,凍りつく裏面を持ちます。生へのエネルギーはエロス的な満足と共にありますが,死へのエネルギーは,その満足が剥奪される怖れと怒りです。
しかしいま述べたように,自己保存と死という形での二分法となっていることが,既に人間の特徴です。つまり,自我に拠って生を切り開くのが人間である一方には,その挫折もまた含まれており,それは死への斜傾ということになります。
人間が生まれる前の存在形態は永遠の謎です。それは人間の目には,現象的には実在しない無または全の性格を持つもの,とでもいうしかないようです。それは死後の存在についても同様です。
人は無から生じたのか,全から生じたのかという議論は意味をなしません。しかし自我に拠って有限の時空間を生きる人間には,自我を授与したものは無であるというのは,何だか妙な感じを受けます。やはり全によって授けられたという方がしっくりします。どこか偉い人に認められた,選別されたというような気分にもなります。人間には,赤ん坊の誕生はおめでたいことでもありますし,生まれるというのは喜ばしいことに間違いはありません。だからこそ死はかぎりなく不吉なものです。死によって人間の存在はどんなふうになるのかは闇の中ですが,人間の語感では全より無の方が死にはふさわしいようです。つまり人は全によって生を受け,やがては無に帰するということになるようですが,実際のところ,全と無との区別は人間にはつけられません。
貪婪な欲求の持ち主である乳児がひとしきり騒ぎ立てるのは仕方がありませんが,母親の愛情に支えられて,自我がしだいに人生を引き受ける力をつけていかなければなりません。
しかしながら自我は幾重にも自立を阻まれていると考えなければなりません。母親の愛情が鍵を握るといっても,母親を取り巻く内外の事情や,赤ん坊の側の過敏さなど,一様には論じられません。結果として幼い自我がどのように怒りを扱ったかが問題ですが,それは個々に複雑な心のプロセスとでもいうしかありません。
怒りを母親の助けによって鎮めることができず,母親への恐怖から抑圧するしかななかった幼い自我は,黒い子をたくさん作ってしまうことになります。そして黒い子をたくさん作ってしまった自我は,それに応じて依存的であらざるを得ないといえます。親にあからさまな怒りを持ち,家出同然に独立した生活をはじめたとしても,心が依存から脱したとはいえません。依存から脱した証は,心が親からどの程度自由になったかによるでしょう。それなりに自由である自我は,黒い子たちを引き受け,その怒りのエネルギーを回収すろことに成功しているはずです。ですから激しい怒りが潜在しているあいだは,自立に似て非なるものといえます。
依存に関して,問題は黒い子たちにあります。それが大きな勢力を持っているかぎり,自我はその支配を受けます。怒りに駆られて家出同然の独立をはかるのは,とりあえずは黒い子たちに促された行動と考えるべきです。黒い子に取り囲まれて,親から離れることができない依存する自我とは別種の,依存する自我の下での行動です。怒りを抑圧し,内向させている後者よりは,怒りを前面に出している前者の方が本格的な自立への可能性が高いかもしれません。しかしその後のことは本人しだいであり,予断は許されません。
乳児は,母親に向けて完璧な自己保存を求める,いわば生死を賭けた激しい戦いを挑むと考えることができると思います。言葉を換えれば,母親を支配しつくそうとする戦いということになるのでしょう。それが激しいものであればあるほど,母親の態度に過敏に反応し,反転して著しい恐怖に陥ることがあるのではないでしょうか。恐怖は死を垣間見るときに起こります。それが現れたときに,乳児は怒りの鉾を収めて沈黙するのでしょう。
まだ人間らしい中庸の精神が発達していない段階では,エロス的満足を求めて,あるときは天使の笑顔になり,あるときは悪鬼の相を顕わにし,至福と怒りの両極の間で激しく揺れるのです。そしてあるときに死の恐怖を垣間見たときに,幼い自我が怒りを強力に制して沈黙し,時によっては親の自我に取りすがるようにしてよい子の路線を取ることで,身を守ることになるのでしょう。
そのように母親を支配しつくそうとして,反転して母親の支配を受けることになったときに,依存の病理的な一つの形ができるのではないかと思われます。
(怒りは関係を破壊しようとする力であり,死と関係します。動物の怒りは専ら外へ向かい,何らかの脅威となるものを攻撃する力になります。人間の場合は外へ向うこともあれば,内へ向うこともあります。外へ向えば他者との関係を破壊しようとする動きになりますし,内へ向えば自己自身との関係が破壊される動きになります。赤ん坊の怒りは,不快を快に転換するように求める適応的なものでしょうが,その怒りには,それが適えられないのであれば相手の破壊をも辞さないという構えもあると思います。であればこそ,反転して相手(母親)に恐怖を抱き,沈黙することにもなるのでしょう。それは自分の怒りが,いわば逆照射された恐怖といえるでしょう。他に死をもたらす力を持つものは,自分にも死をもたらす力を持っています。
相手に向う怒りが相手への恐れによって撤収されるのは,自己保存の本能が発動してのことですが,収められた怒りは逆照射して自分自身に向けられ,相手への恐怖が更に強められます。それを自我が持ちこたえられないときは,強力に抑圧して表面上は問題が収められます。しかし問題は内向する怒りとなって,今度は自分自身との関係を破壊する力となります。それはそのまま拡大してしまえば,精神的に滅びてしまうことにもなりかねないものです。
そういう事情の下で何が必要かといえば,自我の介入です。怒りを引き受けて,適切に扱うのは自我の役目です。それがあれば怒りの持つ死をももたらすエネルギーは,いつか自我によって鎮められて,生へのエネルギーに転換されることになることが可能です)
完璧な自己保存の要求は,具体的には,愛情と信頼とで満たされることを求める欲球に基づくものだと思います。そしてそれを要求したばかりに味わわされた恐怖があまりに大きいと,一転してそれは撤収され,今度は母親の気分を損ねないことに全神経を使うことになるのです。そのときに支払わされる代償が,寂しさ,不安,孤独などの程度の強い感情です。そしてそれらの感情の奥には強い恐怖と怒りが潜んでいます。それでも母親によい子と認められるのが嬉しいので,子供である間はそれで満足できてもいるのだと思います。しかし支払わされた代償は,大人の年齢になりつつある過程で,しだいに制御し難いものになります。それにもかかわらず早期に経験した恐怖が著しいと,抑制の手が緩められることはありません。その内面の激しいドラマとは裏腹に,あくまでも明るく優しげな仮面は強固であるとすれば,それは人に見捨てられたくない恐怖が強いためといえるでしょう。そして,その一方では自我によって解放される見込みが立たない怒りのエネルギーが,内側から心を破壊することになります。もっとも,外傷体験のように外部からダメージを受ける経験をしたとしても,心が破壊されるのは内側からであるといえるのですが。いずれにせよ強力な見捨てられる恐怖のために,その仮面を取り去って素顔を面に出すのは,容易なことではありません。そのことに伴う潜行する恐怖と怒りとは,人の理解を越えた激しいものだと思われます。それらの強い感情の下では,自我はほとんど機能不全に陥ることになるでしょう。凍える自我の下での理性は,自分の心の問題を形式的に理解はできても,洞察といえるほどの能力を発揮することはほとんど望めません。本心を知るくらいなら死を望みさえするほどに慄く自我は,恐怖と怒りとを抑圧する手を緩めようとしないのです。
この慄く自我は,母親との授乳を媒介とした心の会話がうまくいかず,好ましい形の依存が封じられたままでいるあいだに,いつしか懲罰的な怒れる超自我と,受け入れを拒否された怒れる黒い子たちとの狭間で,無力化しているともいえます。
このように無力化した自我は,自由と自立性とを欠いているので,さまざまに依存する自我であることが避けられません。
拒食症者である女性(Aさん)が,妹さん(Bさん)を診てほしいと連れてきたことがあります。妹があまり食べなくなったというのです。Aさんは自分のことは心配しないのに,妹であるBさんの心配はするのです。Bさんは,「いまはいらいらし易く,食べたくないのは事実だが,そのうちに食べ出すと思っている。私は姉と違って,明るく,社交性があり,物をはっきりいう。割り切りもいいので,姉のようにはならないと思う」といいます。また,「両親と暮らしているあいだは気分が常に不安定で,しょっちゅう吐いていた。2年ほど前に家を出て,同棲をはじめた。それから吐かなくなった」といいます。Aさんの話では,酒乱だった父親によって,家の中の物が壊されて目茶目茶だったということですが,Bさんによれば父親の暴力は更に激しいものでした。Bさんは以下のように語ります。
「幼いころから殴る,蹴るという目に遭ってきた。姉は我慢してよい子でいようとするが,私は口ごたえするからだと思う。父親は酔っているときに暴力的になったが,素面のときでもあった。中学生のときに,父と二人になった。包丁で刺されそうになったが,理由がいまでも分からない。その他にも,包丁を持った父に追い回されたことがある。いつ殺されてもおかしくないと思っていた。父は勿論,庇おうとしなかった母も決して許せないと思う。その一方で,許さないと・・・という葛藤がある。姉と違うのは,私は両親とのあいだに境を置いたことと思う。私が両親に怒りを持つのを許し,その一方で,私と両親とは人格が別だと考えた。そうすると気が楽になった。姉は両親の前でよい子でいつづけたと思う。いつか両親の面倒を見ないといけないと思っている。どうしてもその心を変えられないでいる・・・」
ずっとよい子で,いずれ両親の世話をやかなければならないと考えているAさんは,Bさんより度の強い拒食症者です。Bさんは甚だしい暴力を受けながら成長しましたが,自分の心にある度の強い怒りをしっかりと受け止めています。その上で,怒りの扱いに腐心した様子がうかがえます。それは自由な自我にでなければできない仕事です。一方,Aさんは,暴力をふるいつづけてきた父親と,無力だった母親とを,ある意味ではあくまでも庇おうとしています。Bさんは,それはよくないことだという認識を持っていますが,Aさんの心には届きません。姉妹を較べると,Bさんの自我はかなり自由のようですが,Aさんの自我はまったくそうではありません。
Bさんは重要なことを自ら会得しています。
一つは度の強い怒りに自我が支配されず,介入する自由を保つことができたことです。もう一つは,心の境界を敢えて意識したことです。母子一体の関係の中にある母親と乳幼児とのあいだでは,心の境界が曖昧です。母親は,必要であれば自分自身にするように幼い子の心に介入できます。そして幼い子にはその助けが不可欠です。そして心(自我)の成長と共に,親子のあいだに心理的な境界が形成されていきます。それは幼い子が母親から自立していくために必要なことです。幼い心が成長していくことと,心の境界が明確に備わっていくこととは,パラレルな関係にあります。それによって心の自由と自立とが得られるのです。
人格障害の患者さんの中には,他者に完璧な助けを求める場合があることが珍しくありません。このことは境界機能の発達が不十分であることを示しています。乳児と母親との関係では,母親の心にも乳児のそれに対応して心の境界が取り払われていると考えられます。ところが大人の年齢になってしまえば,本人の心の境界が曖昧であっても,周囲の人の心には明確に境界があります。そのために,母親が乳児にするようには助けられないのです。比喩的にいえば,相手が乳児の場合は,母親は家の中に入って助けることができますが,大人になってしまえば,母親(あるいはそれに準じる立場の人)といえども,家の外から助けることができても,子供の家の中に入って助けるのは不可能です。
このように完璧な助けを求めるのは,得られないものを得ようとすることで,周囲の者も疲れ果ててしまいます。自我がこのことを理解する力を回復したときに,自分の問題として自ら引き受ける気になることが可能になります。そのときに問題は収束に向うのです。
Aさんは,自分のことより妹を心配する優しい心の持ち主です。Aさんの心の優しさ,穢れのなさには疑問の余地はありません。しかし両親の世話をやかなければならないと思っていることについては,姉思いのBさんが疑問を投げかけています。何よりもAさんの拒食の心には,死への志向が色濃く紛れ込んでいるのが問題です。これは親孝行というより,苛烈な要求をつきつけ,懲罰的な超自我の下で機能を破壊されかけている自我が,必死に両親に取りすがるのをやめられない(依存している)様相というべきものです。これらの心の深部には,内向する強い怒りがあるはずですが,Aさんは強力に抑圧してその存在に気がついていません。あるいは気がつくのを徹底して避けているともいえるでしょう。それはもしかすると,抑圧する手を放すと,制御し難い怒りが両親に襲い掛かると,意識できないレベルの心で感じているからかもしれません。それよりも,自己の死を選ぼうとしている無意識的な心の動きがあるのかもしれません。Aさんが妹さんのように,両親とのあいだに心の境界を置くことができれば,超自我に屈しない自我の自由があると思われます。そしてそのときに,必要であれば親孝行が可能になるのです。
Rさんは40代の主婦です。
20歳で結婚し,共働きをしていましたが,30歳のころに動悸と全身倦怠感などがあり,某クリニックを受診しました。強迫神経症とうつ状態と診断され,仕事を辞めるようにいわれました。その3ヵ月後に勧められて入院しました。家事から解放されて落ち着きましたが,家に帰ると’旧の木阿弥夫’で,入退院を4,5回繰り返しました。
私のところの初診は45歳のときです。その当時は不安が強く,家事をする意欲がなく,強迫行動(観念も)があり,過食と買い物依存がありました。「鍵があいて誰かが入ってくる」という夢を繰り返し見るといいます。「自由な身(お金に困らず,子供に束縛されず,何人かの友人がいるなど)なのに,ひどく不自由・・・」と述べています。
強迫行動は,手洗い,洗顔,歯磨き,入浴,洗濯物の取り込み,調理,食器洗い,火の元,鍵など多岐にわたります。買い物は,高価の衣類にかぎられ,「昨日は5万円,一昨日は12万円・・・」などと,欲しいと思うと我慢が効かないのです。家中に衣類があふれ,お金がなくなると万引きをするかもしれないともいいます。夫によれば,スーパーに入ると様子が変わる,駄々をこねる子供とおなじになるということです。
夫は高校時代に身の上相談をしていた人で,父親的な優しさと包容力のある方です。Rさんと夫とは一回り以上歳が離れています。子供はいません。Rさんは,初診のときに夫を評して,「こういう私と長年連れ添ったのだから,優しくて,辛抱強い,120点あげます」と述べております。
毎朝,夫が家を出るとき,「帰ってくるのかしら」と不安になります。夫は笑って,「他に行くところがないよ」といいます。分かっていても不安は取れず,繰り返しおなじことを夫にいってしまいます。
夫は専門の分野で幅広く活動をしています。それが羨ましくもあり,自分の虚しさを教えられる理由にもなります。それに較べると自分には価値がないと思えてしまいます。十分に夫を信じ,尊敬しているのですが,夫に置き去りにされる不安が根深くあります。
初診から間もないころに,パジャマのまま夜中に外へ飛び出したことがあります。車道に出てはねられて死のうと思ったといいます。その後,夜中に薬の過量服用をして救急入院しましたが,胃洗浄を拒みました。その際,夫が,「数ヶ月前から,私が出かけたあとに,人の気配があって刃物で追い回される,刃物で切れと命令する声が聞こえるといっていた」といいます。本人から離婚話が出たこともあるといいます。しかし夫は,「見捨てるつもりはありません」といっています。この時期は,統合失調症と区別がつかない状態でした。
父親が自分本位の人のようです。母親は仕事を持っていて,いつも忙しそうにしている人でした。日記を覗き見られたり,鞄の中を調べられたりしました。両親はいつも喧嘩ばかりしていたといいます。
母親と共に出かけたとき,「置いて行っちゃうよ」としばしばいわれました。あるとき,幼いRさんのはるか前(母親と出かけるときは,いつも母親が速足で,先へ,先へと行ってしまいます)を速足で歩いていた母親が,本当にバスに乗って行ってしまいました。置き去りにされたRさんは,「ああ,やっぱり」と思いました。
子供は欲しいとは決して思わないそうですが,母親のような母親には絶対にならないと思ってきました。母親は交通事故で亡くなりましたが,涙が出ませんでした。
父親も母親も,いまでもどうしても受け入れることができません。そして,寂しさ,虚しさ,孤独,怒りの感情が常に心を支配しています。
母親の行動は恐怖をもたらしました。幼いRさんは,叱られないように,見捨てられないように,認めてもらえるように,ひたすら母親に注意を奪われつつ成長しました。自分が存在する価値がなく,両親に必要とされていないという意識が,いつか心の支配原理になりました。自己本来のさまざまな欲求は,強い見捨てられる恐怖の下にある自我によって抑圧されつづけたと思われます。母親の傀儡となっている自我によって抑圧されたものは,無意識の世界で黒い子となって勢力を蓄えることになります。黒い子たちが大きな勢力になると,破壊的で悪魔的な力になっていきます。Rさんの買い物依存や過食はその現れの一つです。
また黒い子をおびただしく作り出した自我は,強い怒りを強力に抑圧することになり,内向する怒りが,超自我を支配的で威嚇的,懲罰的なものにしてしまいます。それが強迫行動を生み出します。
Rさんはふだんは怒りを面に出す人ではありません。しかし妄想の渦中で夜中に外へ飛び出し,追いかけてきた夫に激しい怒りを向けたことがあります。冷静になれば,Rさんにとって夫はほとんど非の打ち所がない人です。その夫にさえ,毎朝出かけるたびに,もう帰ってこない(見捨てられる)のではないかと,いわば不信を持つのです。
Rさんの結婚は,何としても家を出たいという気持ちに端を発し,夫がそれを理解し協力したという形だったようです。単なる愛情からの結婚ではなく,たぶんに同情心が働いてのことでした。愛情は相互的ですが,同情は上下の関係での一方向的な行為になるでしょう。それは同情される側から僻みを受ける可能性を,そもそも持っています。そこにも怒りが介在する余地があるのです。Rさんは夫を尊敬していますし,悲惨な境遇から救い出されて感謝もしていますが,負い目がどうしても残ります。
自我が比較的自由である状態のときは,Rさんは夫に感謝と尊敬の念を持つのですが,自我が力を弱めた状態のときに,夫に対する羨望の念に苦しみます。
羨望は,そもそもは幼いころに,母親などから当然もらえるはずの愛情と信頼とがもらえていないと感じる不満と怒りに端を発するのでしょう。乳幼児期の満足と安心とを求める心には,強いエネルギーが込められているので,これを更に強いエネルギーで抑圧する理由があるとすれば,それは見捨てられる恐怖以外には考えられません。この激しい不満と怒りとが,親代理でもある夫に向けられても不思議はありません。
羨望は激しく傷ついた自己愛の問題でもあります。自己への愛情と信頼とは,健全な自己愛の下に育まれます。それは人格形成の最早期に,母親との関係でその基礎が築かれなければならないものです。健全な自己愛と健全な他者愛とのあいだには,相関関係があります。Rさんの夫は,安定した自己愛の持ち主のように思われます。Rさんに対する父親的な愛情に,不信の眼を向ける余地がない人のように見えます。Rさんの夫としては,これ以上に望めない人のように思われ,Rさんもそのように考えております。それだけにその夫を怒りを込めて羨むことの葛藤,苦痛には深甚なものがあるでしょう。
自殺衝動,妄想などのことは,超自我と黒い子たちとの狭間で苦しみつづけた自我が,ついに機能麻痺に陥り,黒い子達が心を主導している様相といえるでしょう。
Rさんが夫に救いを求めて家を出た主要な理由の一部に,内向する怒りがあったと思われます。その怒りは自我が受け止めたのではなく,依存の対象を親から夫へと移し変える動力になっていたと思われるので,恩を受けた負い目の下に,怒りは相変わらず内向しつづけたのです。夫の助けは貴重なものではあっても,それに支えられてRさんの自我が自らを助ける仕事をして,夫と対等の立場に立たないかぎり解決できないものでした。最近は家事をこなしていますし,夫と旅行をしたり,生活をそれなりに楽しめるようになっていますが,寝る前の薬をのんだあとに過食にふけり,その記憶がまったくないなどのことは今もあります。人生の最早期に傷ついた病理的な自己愛の修復は,理想的なパートナーによっても容易なことではないのです。
このことには,先に述べた自我の境界機能が関係しているように思われます。
母親と赤ん坊との関係では,自我の境界機能は特殊な様相になるように思われます。つまり,繰り返しになりますが,赤ん坊の自我の境界が未成熟であることに相応して,赤ん坊との関係における母親の自我の境界機能もいわば撤去されると考えられます。それによって,赤ん坊と母親とは,いわば特殊な二人組みの関係になるように思われます。それがあって,母親が自分にするように直接的に赤ん坊の心の世話をやくことが可能になるのです。そして赤ん坊が成長すると,この境界が明確になっていくために,他者(母親も含めて)は母親が赤ん坊にするようにして直接に助けることはできないのです。
人格障害の患者さんの中には,幼い子が助けを求めるような激しい情動を示す人があります。このことからは,自我の境界の機能がしっかりしていないということが暗示されます。
冒頭に上げたM子さんの症例は,美人コンテストで成功する夢を母親に託された娘の問題でした。日本には子供のこうしたコンテストがないので,馬鹿げた,グロテスクな話に見えます。しかし,日本の現実には受験の問題があります。それが母親の理性をどれほどおかしくさせているか(父親も同列です),実例に事欠きません。そこにはM子さんの母親がしたことと,さほどの相違がないように思えます。
そもそも親が子を信じ,愛情にも確かなものがあるとき,幼い子を受験などに駆り立てるものでしょうか。
親の側に,自分の不安が強く,そのために子供の将来も不安になるのだという正直な認識があれば,害は少ないと思います。そうであれば,自分の心に潜む,悪辣なもののへとつながりかねない心の傾向を知っていることになるからです。そこに嘘が介在していないからです。辛く,苦しい気持ちを持つことはなんら罪ではありませんが,自分の問題を子供の問題に転嫁するときに,子供の領域への無反省な侵入が始まると思います。それは,国境を越えて侵入すると紛争になるのとおなじく,親子の間で紛争が始まったと考えなければなりません。
強い自我(境界機能がしっかりしている)を持った子であれば,親も無闇と子の領域に侵入できません。弱い自我(境界機能が不確か)の子がその種の被害を蒙ることになります。それを考えると,おかしなことをしようとしているのが,親自身もどこかで分かっているというべきなのでしょう。子の領域に侵入すれば,強い自我の子であれば親子のあいだでの紛争になります。しかし侵入しようとする自我は,本来的には弱い自我なので,そういう紛争は回避して,弱い子に向うのです。これは卑劣というものです。
元はといえば,親の心の中が紛争状態なのです。それを自分で解決するほどの強さがないので,弱い立場の子の心を支配する形で問題を収めようとするのだろうと思われます。弱い自我の子が,親に対してしっかりとした態度を取れないために,表立った問題が起きていないだけなのです。そして,親の心の内紛が転嫁された子供の心は,表面はともかく,内面での葛藤に苦しむことになるとしても不思議はありません。
不安に悩む母親が,子供を信じるという善を施せずに,不信という悪にかられるときに侵入が始まります。子供を信じることができている母親が,子供の領域に侵入する理由はありません。子供を信じられない母親は,自分自身も信じられないのです。
侵入する心には,常に怒りが護衛のように従えられているように思われます。「あなたのために良いことをしている」という思いが単なる正当化に過ぎないのは,’良い子’がそれに従わなかったときに,親の心が穏やかではないことがそれを証明しているでしょう。
親が自分本位の毒念を持ち,しかし無神経な心がそれをカムフラージュしたとき,子供は厄介な状況に置かれます。親の心の奥に潜む悪意を子は敏感に感じ取ると思います。怒りを覚えるだろうと思います。しかし(弱い自我の)子も親に似て,その心を隠して親を信じた気になります。そういう親子の関係ができているとき,子の固有の意志は,怒りとともに意識の奥深くに潜行し,心の破壊活動がやがて始まることになりかねません。
一児の母であるSさんが,子供が可愛いと思ったことがないと口を滑らせたようにいったことがあります。ふだん子供の受験問題にことさら熱心な人なのですが,そうならざるを得ない子供の側の問題を常々述べておりました。子供が受験勉強に不熱心なので口やかましくなることはあるが,それを別にすると親子の仲はとてもよいということでもありました。しかしそれはにわかには信じ難い思いがありました。そういう折に,冷酷な心が一瞬だけ表に現われてしまったように感じられ,それは注目に値することでした。というのは,心が本音を隠蔽したままでいるかぎり,Sさんの本格的な治療が望めないからです。
残念ながら,この折角の話は深められないままになってしまいました。私も瞬間的に息を呑み,タイミングを逸したということですが,いずれ問題にできると思っていました。しかしその周辺のことに話が及んでも,再びその心が語られることはないままです。
母親自身が幼いころは勉強一筋の人でした。そうすることで両親に取り入ってきました。裏を返すと,両親に認められない怯えを持つ子でした。自分の子供時代の不毛をしきりと悔やみながら,子供が望むので応援しているという口実で勉強を強いているのです。意識の表面では子供への愛情からということであっても,影に冷酷な心が潜んでいます。幼い娘が,母親であるSさん自身がかつて夢見たように,学校生活でも,社会人としても,誰にも自慢できるような赫々たる成功者になり,母親を助けなさい(それはSさんが,内的な親によって命じられていたことでもあります)という暗黙の意志が働いてのことであるのはほとんど明白です。母と子の関係が良好であるという認識に裏があるのと同様に,娘としての自分と母親との関係が良好であるという認識にも,裏があるのも明白です。つまりは自分がされたのとおなじことを(世の成功者にならないと娘として認められないという強迫的な観念),まるで復讐でもするように一人娘にしていながら,その自覚を持たないのです。
Sさんの場合,野心とその影に潜む冷酷さは一体のものです。野心が自分の力を当てにするのではなく,子供の力を当てにする形を取っているからです。だから子供を独立した人格と認めていません。それは冷酷な心です。そこには子供じみた強制が働いていると考えなければなりません。いうことをきかなければ,おかあさんは承知しないよというメッセージが込められているに違いないと思います。
冷酷な心は,自我が認知しないことによって,無意識の中で毒素となって暗躍します。しかし認知する気になったときに,もはや冷酷な心ではなくなる第一歩を踏み出しています。それが容易なことではないSさんは,内向する強い怒りを恐れていると思います。
悪意が善意に変われば,みんなが仕合せです。そういう自明のことが難しく,秘めた悪意を捨てようとしない心は奇妙なものですが,それはどこにでも見られるありふれた心の出来事です。その理由は,それだけ内向する怒りが強いからだと思います。強い怒りを秘めた心はしばしば怨念となります。場合によっては,無力な主人公である自我を傀儡化して,第二の人格を無意識の領域に仕立て上げようとします。それがさまざまな依存症を引き起こします。場合によっては周囲を驚かせるような危険な行動をも引き起こします。
自我が,自分の盲点となっていることに眼を向けていくのは,二重に困難な作業です。それはそもそも自我が引き受けることができなかった体験に発しています。いわば幼い心の外傷体験ともいえるものがあり,それに類似する体験に直面するたびに,自我は抑圧,排除する傾向を持ちます。いわば自我が最も苦手としている問題に,改めて眼を向け,立ち向かっていこうとするには,大きなエネルギーを必要とします。
自我はそういう認識姿勢を持つこと自体を,できれば避けようとするでしょう。そうであればこその盲点なのです。しかしそれを克服して自分の仕事という自覚を持つのが,本来の自我の使命です。
そういう事情がありますので,黒い子たちの勢力に悩む自我が,改めて黒い子たちを引き受ける力を回復させられるまでのあいだ,その自我を補助するのが,我々,心の治療者の役目です。
外科の病気のように,自分はベッドに横たわっているあいだに治れるものなら治してもらいたいでしょうが,心の病気はそうはいきません。治すための主役は本人自身であり,治療者の存在は重要ですが,協力者以上であることはできません。
このことは先に述べた自我の境界機能に関係します。つまり心を病む人の自我と治療者の自我との領域は,境界機能によって画然と隔てられています。治療者は病者の心の内部に入り込むことはできません。いわば境界の外から,患者さんの自助努力に協力するのが心の治療者の役目です。ですから患者さん本人が,自分に立ち向かっていく意志の強さが鍵を握っています。
「あなたは病気を治したいと思いますか?」というと,馬鹿な質問と思うかも知れません。しかし,心の治療に関しては馬鹿な質問とはいえません。
幼い時代に抑圧,排除されたものである黒い子たちは,心の深部で,凍りつくほどにおびえている幼い弟,あるいは妹(つまり過去の自分自身)と見なすことができます。
というのは,主体から送り出されて来た白い子を,幼い自我が護ることができた(母親の協力が不可欠です)ときに,自我がエネルギーを得,満足感と安心感とを心にもたらすことができるのです。そのとき,白い子は心の表舞台に上げられたといえます。そして心は力を得て,その分の成長を果たすことになります。
しかし自我がそうした仕事が出来ずに,白い子を黒い子にしてしまったときに,自我はエネルギーを受け取ることに失敗し,心は不満足と怒りと恐怖とを抱え持つものを心の裏舞台に留め置くことになると考えることができます。つまり黒い子たちは,その時々の年齢のレベルに,凍結されるように留め置かれるのです。
心の治療は,それらの分身たちを救出する作業という意味合いを持ちます。具体的にその仕事ができるのは自我ですが,治療者の補助を受けて,その意味での弟(妹)の存在に眼を向ける勇気を持ち,それらの分身たちの心を言葉で捉えるということです。現実にも,そういう弟(妹)がいれば,兄あるいは姉が,弟の心をよく分かってあげるのが,何よりの励みになると思ます。それとおなじことです。これは自己の回復のためには,是非とも必要なことですが,自我の仕事としては最大級の難作業です。
他人との関係は重要ではあっても,一般には周辺的な問題です。他人との関係も依存的なそれであり,関係に無理が生じると壊れます。心もそれなりのダメージを受けます。しかしそのときは大きな問題であっても,やがては癒されます。切れてしまえば,他人の場合は,多かれ少なかれそれで問題は終結するのです。
なかなか終結しないとすると,その背後で,より核心的ななにかが連動していると思います。それを探って行くと,心の形成の歴史をはるかに遡った親との関係にたどりつくことになるでしょう。
勇気を持って自分の本心に立ち向かおうとすると,必然的に(母親との)旧来の依存関係に波及するのは避けられません。自我のその仕事は,威嚇的な超自我に支配されている心の体制を破壊し,再構築する一種の革命です。心の体制が覆るのは恐ろしいことです。統合失調症の中に,世界没落体験という深刻な病的現象がありますが,それに見舞われるときは,恐怖に満ちた体験になると想像されます。いま述べた心の再編も,それに準ずるような恐怖を伴うと思います。そういう勇気を持てない理由は,幼児のときに母親を恐れたのと同じ心で恐れるからといえるでしょう。幼いときに大きな否定的感情を体験すると,自我は無力なままで,いつまでも成長できなくなることがあるのです。恐怖心の底にある怒りが激発するような事態には,自我はとうてい耐えられないと感じるのです。鍵を握るのは自我の強さです。治療者に助けられて,自我が徐々に力をつけていくことができるかどうかです。
人は何ものかに依存しつつ存在しています。
中には死に依存する人さえあります。いざとなれば死ねばいいと思いつつ現実に耐えている人は,決して珍しくはありません。このタイプの人は,自分自身を引き受ける覚悟を持てないのです。誰かの助けは欲しいと思っても,自分の力で生きていくのは途方もないことのように感じられるのです。
一部のうつ病は薬が奏効して比較的短期間に治癒にいたります。この場合は外科医のような治療ということになります。しかし,うつ病といっても個々に背景が違います。単純なうつ病は,薬によっていわば体質が改善され,治癒にいたるのですが,心の病気は,一般に性格の傾向と切り離して考えることはできません。そしてそれに関連して,人生問題を抜きにして考えることはできません。
生きるということの反面に,死の問題があります。治療者に,’治してほしい’と思い,自分の問題として捉えることができない人の場合には,背景にこの問題があるかもしれません。何故なら,引き受ける精神がそもそも薄弱であるとすれば,それは幼児的な依存する自我の下にあるといえるだろうからです。自己と人生とを自ら引き受ける意志を持つことができなかったのは,無意識的にであれ死の恐怖にさらされているために,他に取りすがるのを止められないのでしょう。そういうときは,治療は難航します。
院内通信 性格形成に与える母親の影響(摂食障害の症例を通して) H14.2.27
性格形成に与える母親の影響-その1
■人格と性格(外国の症例)
M子さんが治療を受けることになったのは,19歳のときでした。母親は若いころに多数の美人コンテストで優勝するという経歴の持ち主でした。娘にその夢を託そうとしたのでしょうか, M子さんが3歳になると早くも美人コンテストに参加させました。そしてコンテストに出すために,M子さんの体型をスリムに保つように仕向けました。
一方,幼い娘は美人コンテストなどには関心がなく,母親の期待をとても負担に感じておりました。また幼いころは病気がちでもありましたが,それはM子さんには好都合な面がありました。というのは,病気になれば美人コンテストなどには出なくてもいいからです。それに病気になれば優しくしてもらえるからです。とはいっても母親は,身体を心配してくれるよりは,コンテストに出られないことのほうを気にしました。それはM子さんにとっては腹の立つことでしたが,母親に怒りを直接ぶつける勇気はありませんでした。
M子さんは,母親の期待にこたえられないことにつよい自責の念を持ちました。自分がだめな人間であり,生きる価値がないと思い続けてきました。そして過食と拒食に加え,自傷行為を繰り返してきたのです。
この症例に即して,問題をどうとらえ,どう考えればいいのか検討してみます。
M子さんの主訴は,母親の期待にこたえられないことへの自責の気持ち,自分が生きるにあたいしないだめな人間であると考える自己評価の低さ,自傷行為,摂食障害などです。
この問題を考えるに当たっては,発病したときの状況はどうか,状況の病理性はどの程度かが重要です。これらは心にとって外的な事情ということになります。
それから本人の側のストレスへの耐性が問題になります。こちらは心の内的な事情ということになりますが,具体的には,生まれたときからの人格形成の歴史を知ることが参考になります。
心の病気は,身体の病気とはだいぶ違います。身体の病気では,人格とは無縁とはいえないものの,たいていは局所の所見だけを診て解決します。一方,心の病気ではそういうわけにはいかず,本人も気がつかないでいる心理的理由を探っていく必要が出てきます。
人間はすべてなにがしか神経症的であるといわれるように,人格は,相当に無理を重ねて形成されます。というのは,人格は,人との関係での影響をつよく受けて作られるからです。人の中でも,特に両親の影響を受けます。それらの影響の下で,心がしだいに成長し,しかし,ときにはさまざまに傷つきます。それら傷ついた心は,幼なすぎるものには解決するすべもなく,その体験と,怒りや,恐怖や,落胆やの耐えられない感情とを,そのまま無意識の心に預けることになります。それらは未解決の問題として堆積され,沼のように無意識の心にたまります。これが人格に影を落とします。あの人は暗いなどといわれるのはそのためですが,この沼のように広がる不気味な気配のものはだれにでもあります。ふだんは意識にのぼることはないでしょうが,過去を振り返るときに,無意識的にそこに触れることがあります。そういうときは,不安,恐怖,苛立ち,落胆などのネガテイブな感情が,乳幼児期に体験したのとおなじようによみがえり,湧き起こって来るかもしれません。沼の情景は暗く,不気味なので,近寄りたくない気持ちになると思います。明るいといわれる人も例外ではありません。それが人格に宿すかげりが,暗い人として他人から敬遠される理由になることがある一方で,人間的な魅力を深める理由になる場合もあると思います。また,明るさが沼の気配を忘れていたいがための反動であるかもしれません。そのために軽薄な印象を人に与えることもあるかもしれません。だれにでもある犯罪への暗く,根強い関心も,この沼の存在に起因するといえると思います。
この一文では人格形成にあたえる母親の影響を取り上げます。もちろん父親の影響も考えないといけないのですが,この症例報告では父親のことに触れておりませんので,いまは割愛します。
人格という言葉を使いましたが,むしろ性格のほうが的確かもしれません。人格といえば「あの人は人格者だ」,「彼は人格ができていない」,「人格が破綻している」などなどといわれるように,人間のあるべき姿に即しているとか,道徳的に正しいとか,そのような価値意識がこめられているように思います。一方,性格という言葉には,そういう価値意識が入っておらず,現にある,良くも悪くもそのままの,事実としてのその人の人間の姿とでもいえばいいのか,そんな感じがこめられているのではないでしょうか。そういうわけで,ここでは性格と呼び直すことにします。
性格は,一つには生物学的に規定された,もって生まれた気質という面があります。そのほかにもう一つ,生まれたあとに形成された面があります。後者については,特に人間関係の影響が大きいといえます。植物でいえば根っこの部分,建物でいえば基礎の部分がしっかりしているかどうかが肝心なのとおなじように,人の心も,幼いときほど環境がおよぼす影響が大きいのです。また人間関係といっても,父親,母親以上に大きな影響力を持った人物はありませんから,事実上,親の影響が基本といえます。(このあたり,たとえば不登校の子について,学校に問題があるのか,家庭に問題があるのかという議論がしばしば起こりますが,これは台風で建物が被害を受けたときに,台風が原因か,基礎に問題があったかというのと似ているようです。要するに基礎をしっかりさせて,台風が来ても被害を受けないように対策が講じられている必要があるのです)
母親が三歳の子を美人コンテストに出すなどということは,日本では極端に過ぎる例だと思います。しかし,たとえば幼い我が子を受験競争に駆り立てるというおなじみの現象は,それに似ているものがあります。
性格形成に与える母親の影響-その2
■愛情の問題
M子さんの母親がしたことは,娘への愛情なのでしょうか。これが問題です。母親は愛情と信じているかもしれません。「娘に素敵な体験をさせて上げたいと考えるのが,どうして愛情でないといえるのでしょう」と彼女はいうかもしれません。あるいはそうかもしれません。将来,娘が,母親がしてくれたことを感謝する場合だって考えられないわけではありません。
そうすると,この母親の行為が愛情に値するものかどうか,誰がどのようにして決めるのでしょう? また仮に,この母親の行為が愛情とはいえないということが判明すると,どういう問題が生じるのでしょう。M子さんの場合は,摂食障害や自傷行為という痛ましい問題が起こっているわけですが,それとどんな関係があるのでしょうか?
他人には,それぞれの意見があっても,誰であれ裁判官のような権限で判定する力はもちろんありません。ただ,誰か周囲の人が,母親の行為に危惧の念をいだき,M子さんの将来を心から心配して説得するということはあり得るでしょう。その人を母親が信頼していれば,説得が実を結ぶかもしれません。母親が,心の迷いを正してもらえたことを感謝するかもしれません。それはそれでいいことです。人間の関係としては,そのようでなければならないともいえると思います。しかし,そういう場合でも,母親の行為が迷妄であり,真の愛情ではないと言い切れるかどうかは別問題です。さらに母親が自分の正当性をあくまでも主張するとき,どちらが正しいかは,なおのこと一概には決められなくなると思います。
そうしてみると,M子さんの母親が愛情に基づいた行為であると主張することの当否を,誰か人間が判定するのは,煎じ詰めると不可能ということになると思います。
なぜこういうことが問題になるのか,それ自体も問題です。
親が子に愛情を注ぐのがしばしば難しいのはなぜでしょう。そうすることが当然であり,よいことであり,必要であり,仕合せな心でいられる理由になると誰もが容易に分かるはずのことなのに,実際には,その実践がむしろ難しいのは不思議なことです。 愛情を注ぐどころか,憎みさえするのも珍しいことではありません。憎むとまではいかなくても,愛情という観点からすると問題のあるしつけをしてしまうのは,残念ながら,普遍的な現象だといえるでしょう。
愛情に似て非なるものの典型は,親の考えや価値観の押しつけです。言葉を換えれば,愛情の名を借りた侵入です。それは乳児が,母親に全面的に依存する母子一体の時期を経験することとも関係があるでしょう。母子の蜜月時代の体験は,それ自体が母子双方にとって素晴らしいものであるでしょうが,乳児の成長の基盤の形成という観点からも大いに意味のある大切なことです。
自分が生んだ赤ん坊によって与えられたその素晴らしい体験は,母親のみに許された,余人には味わい得ない稀有なものであろうと思われます。赤ん坊は母親にとって,俗にいわれるように,天から授けられた宝物という趣きを持っているといえるのでしょう。
そうした体験もふまえて,生まれてきた赤ん坊の将来に,母親が一定の好ましい期待イメージを持つことはむしろ当然です。その仕合せが継続するように,豊かな未来が待っているようにと,心に願いを抱くのは,もちろん不思議なことではありません。
ただし,この体験に即して,母親には二通りの願望が生まれるのではないでしょうか。一つは,愛すべき我が子の将来の仕合せへの願いと,もう一つは,母親自身がこの稀有の仕合せを失いたくない願いと。これら二つの願いは,母親にとっては,分離して考えることが容易にはできないものであるように思われます。「あなたのためなのよ」といいながら,その実,母親自身の仕合せのために然々のようでありなさい,というメッセージが向けられるのは,ありがちなことだと思います。
二通りの願望のうちの後者が優っているとき,母親はなかば無意識的に子供を操作しようとします。ターゲットになるのは,子供たちの中でも母親思いの反抗心の少ない子です。子供も母親の言葉の矛盾になかば気がつきながらも,母親を怒らせたくない,悲しませたくないという恐れから同調することになるのです。
子供が成長するにつれ,母親の期待に即することが窮屈になり,不満にもなるのは必然です。それは成長の証でもあるのですが,それに対応できない母親(父親も無縁ではあり得ません)には,期待イメージどおりに育たない子供への愛情に曇りが生じ,憎しみの感情が賦活してきてもおかしくないのです。裏切り,忘恩といった感情も持つかもしれません。
このように,愛情というものの性格をはきちがえる母親は,子供を自分の支配下に置くために,意識的,無意識的に手段をつくすものです。母親によっては,自分自身が満たされない心のままで大人になり,母親になり,母子一体の蜜月時代の仕合せな感覚が,ほとんど唯一生きるに値した体験である場合もあるだろうと思います。そうであれば,それを永久に封印したいと無意識が考えることにもなるのです。極端な場合には,表層の意識はともかく,子供の幸福などはまるで念頭になくなってしまうのです。こうなるとほとんど犯罪的といえるほどの心的状況になってしまうといっても過言ではないでしょう。事実,いわゆる虐待は,この意識の延長線上で起こる問題です。
人はどうかすると幸福であるよりはむしろ不幸です。人が自分自身を愛しているかといえば,むしろ,しばしば愛していません。自己愛と他者愛とは一対の関係にあります。愛情と信頼も一対のものです。自分自身を愛し,信頼する心が希薄であれば,他人(子供も含めて)を愛し,信頼する心も希薄になります。逆に人に疑いの念を持ち易く,恐怖心をいだきやすく,怒りの感情が内向します。
また,愛は単独で愛であることはなく,憎しみと対をなし,背中合わせにつながっているのです。つまり愛があれば,その裏に必ずなんらかの形で憎しみがあります。人間の本性としてそのようなことがいえるので,親がかけがえのない我が子に対して,憎しみ,怒りの感情を持つとしても必ずしも不思議なことではありません。
愛と憎しみとが,一方が存在するためには他方の存在を必要とする関係にあるということは,人間の心の構造的な問題であり,人の心を考える際には重要なことです。
愛している心の裏に,必ずなんらかの憎しみがあります。かつては愛していた人に裏切られれば,陰に潜んでいた憎しみが表に出ます。そして,また,憎しみの情に苦しむとすれば,その裏切り者を愛する心がいまも失せていない証拠です。その人への愛がなくなったためではありません。愛する心が強いのに,その対象を所有することが不可能になってしまったからです。
怒り(憎しみ)は破壊的な力を持っています。愛していた人に裏切られて憎しみの情が長く続くと,怒りがなにものかを破壊するかもしれません。裏切った相手との関係を破壊する動きをするか,あるいは内向する怒りが心を破壊(心の何らかの不調となって表われます)するかということが考えられます。
こういうときに自我が主導的な動きをできるかどうかが,肝心です。憎しみを持っている相手との関係を修復する見込みが立たなければ,その関係は終わらせなければなりません。怒りは相手に向かうのですが,自我にも向けられています。怒りは自我に所属するものではありません。いわば自我の不始末に伴って生じるもので,無意識のものです。
怒りを向けられて自我が立ちすくみ,それを受け止めることができなければ,怒りが直接に相手に襲い掛かり,関係を破壊し,混乱に陥れます。怒りには,事態を収める能力はありません。それは自我の仕事です。破壊と混乱の後に怒りが鎮まると,改めて相手への恋慕の情が残っているのを知り,その感情を扱いかねることにもなります。また,本人の人格,品性が疑われることにもなります。怒りには,正当性があっても,分別がありません。
自我が怒りを受け止めることができれば,相手との関係を終わらせる心の作業に取り掛かることになり,やがては最終的な決着が図られるでしょう。
この問題の根本は,おそらく,出生に関連したものです。生まれたばかりの赤ん坊は,恐怖と驚愕と怒りの中にあると想像されます。母親の子宮の中で身体と心が形成されていく過程が,出生へのそれなりの心の準備期間ではあっても,いうならば’いきなり人間にさせられてしまった’驚きと怒りがあるに違いありません。そのように仮定的に考えるのが自然ではないでしょうか。それをなだめ,慰めて,人としての心構えのようなものを整えさせていく役割を担っている中心人物が母親です。赤ん坊は母親を頼りとする以外にありませんが,今度はその母親に置き去りにされる恐怖に耐えなければなりません。絶対依存の身では,そういう恐怖と無縁であるのは,ほぼ不可能です。母親の’愛’は絶対ではないからです。
赤ん坊の怒りは,人間以前のものに返せということかもしれません。ということは,既に人間の身である以上は,死の要求という意味を持ちます。赤ん坊は生を受けることにより,死をも生きなければならない身なのです。また,自我の活動が未分化である赤ん坊の代理自我は母親のそれなので,怒りは母親へも向けられます。それは空腹やおむつの汚れの不快なども含めた,情緒的に満たされていないことに伴うものではないでしょうか。拡大して考えれば,死をかけて情緒的に満たされたいと怒っているといえるのではないかと思います。
怒りを向けられたことによって,代理自我である母親がその意味を汲み取り,満たして上げることができれば,怒りは自我に解決を求め,自我がそれに応じたことになり,それは人間の心のあり方として望ましいことです。ところが母親が,何らかの事情で赤ん坊の怒りの意味を汲み取れなければ,赤ん坊の怒りは,母親との関係も自分自身の心も破壊することになるかもしれません。つまり母親との関係がいびつになり,赤ん坊自身の心もまたいびつになり,将来が案じられるということです。この場合怒りは,受け止める自我の不在によって,単なる破壊者になります。
こうした原初の事情があって,人は一般に,自分が他人に受け入れられないのではないかという不安を持ちますし,信じていた者が遠ざかろうとする気配を感じると,不安や悲しみや怒りを持つのです。特に乳幼児の段階で,いま述べたような意味で外傷体験といえるほどの傷を心に負うと,長じて,他人に受け入れられることに自信を持てず,関わりのある人に置き去りにされるのではないかという不安が耐え難いほどになります。そのために人に対して恐怖を持ち,回避的になったり,被害感情を持ちやすかったりということにもなるのです。
ある女性は,同棲している男性に,一時間に五回も六回も,「愛している?」と訊いてしまうといいます。
愛と憎しみとが一対のものであるというのは,自我に拠る人間の心の構造に基づくといえます。自己が存在することの原基は自我機構にあると思われます。そして自己の存在構造には,他者が組み込まれていると考えられます。愛と憎しみとは,このような原理に基づいており,他者の存在が前提となっています。
また,以上のことを前提に,自己愛と他者愛とは一対のものであり,自己および他者への不信も一対のものといえます。
自我は,愛を追求します。そして,憎しみが心を苦しめれば,それを受け止めるべきものです。自我が憎む心を受け止めることができれば,問題の解決の基盤ができたことになります。そして,苦しい体験を克服することによって,心の成長がはかられます。
例えていえば,次のようにいえます。
愛は主人公の自我と共にあります。自我が力強ければ,愛は健やかです。憎しみ(怒り)は主人公の無意識なる海の中にあります。憎しみは愛が憎いわけではありません。その証拠に愛が健やかであれば,海は穏やかです。海が荒れるとき,怒りが姿を現すのです。そして海が荒れるのは,愛が危殆に瀕したときです。怒りは愛の後見人であるかのようです。
自我が愛の世界を豊かに保持できるとき,無意識なる海は生の豊穣の源であるといえます。自我が愛の世界の貧困を招いたとき,海は怒りによって荒れることになります。無意識なる海は,愛の枯渇に比例するように,熱い怒りと,それにつづく凍りつく静寂の様相を濃くします。それは死の世界の様相です。
自我は生のものであり,自我の不首尾は,その影響を蒙ったものを無意識に葬り去る意味を持ち,その場合の無意識は死の性格を持ちます。
愛は生きる方向で発展します。憎しみは愛の破壊者です。前者の場合,自我は無意識との関係を尊重し,調和させることができていることによって,無意識は生の拠り所となります。そして,生を切り開く使命を持つ自我の働きによって,心が豊かになっていくでしょう。ところが自我が愚かにも無意識との協調を撹乱するように動いてしまえば,自我は生を切り開くよりは,無意識の恐るべき相貌である死の方向に引きずられる結果を生み出すことになるのです。自我の拙い介入によって,無意識の自然をいわば人為的に歪めるようなことになれば,心は貧困に傾くでしょう。これらの意味で,愛は自我と共に生の世界にあるものであり,憎しみは自我の不始末と共に死の世界に属するものです。
信と不信についてもおなじことがいえます。愛と信とは一対のものです。
ある中年男性が,次のような内容の夢を報告してくれました。
一つは「底なし沼に落ちて,もがいている。水面には無数のあぶくが泡立っている」 もう一つは「仔犬と遊んでいる。急に仔犬が怒り出し,足に噛みついてくる。犬に引きずりまわされる」
二つとも恐怖夢です。
この男性は,人との関係をなによりも大切にし,争いを嫌います。人には明るくて,協調性があり,気の置けない人という印象を与えていると思うといいます。そのように見られたいとも思っています。争いは嫌いなので,昇進は望んでいません。しかし,旧友と会って,管理職になったとか,会社を立ち上げたなどという話を聞くと,自分は結婚もしていない,これでいいのかなと動揺します。秋口には,退社時間が憂鬱です。外はちょうど日暮れ時で,寂しくなるのです。夏はまだ日が高く,冬は日が既に落ちているので,平気でいられます。
この男性は長男で,唯一の同胞である妹は結婚しています。父親は無口で,いつも機嫌が悪かったそうです。酒が好きですが,飲んで帰ると,すぐに寝てしまうそうです。母親には,いつも怒られていたといいます。
二つの夢は,無意識の領域に大きな問題があることを示しているようです。他人への配慮がいき過ぎたためでしょうか,情緒的な欲求が満たされることが少なかったようです。おそらく両親との関係に発端があったと思われますが,そうした欲求は,抑圧する習慣ができてしまっているのだろうと思わせます。
仔犬が噛みつくというのは,そのあたりのことが夢に現れているのだろうと思います。この男性は情緒的なものを求めている(子犬と遊ぶ)のですが,抑圧されつづけてきた情緒的なものは怒りと共にあるのです。怒りは,本来あるべき望ましい働きをしてこなかった自我に向けられています。
泡立つ底なし沼は,怒りによって荒れる無意識です。怒りは,自分自身のために生きようとするところが少なかった自我に向けられ,自我は沼に引きずり込まれそうになっているのです。
他人との協調に気を遣い過ぎて,その分,無意識との協調を怠った様子が,この夢からうかがわれます。
愛情に満ちていると信じていた人の顔の裏に,それとは似ても似つかない憎しみの心が潜んでいるかもしれないと考えるのは恐ろしいことです。(そういう疑念に取りつかれると,神経的な病気になってしまう危険もあります。妄想は,信と不信,愛と非愛といった心の二極構造が,何らかの理由で固化してしまい,信頼の極が機能しなくなった様相と考えることができます)
M子さんには,母親との関係で,幼いころにそういうことが起こっていると考えることが可能です。もっとも自覚的ではないだろうと思われます。むしろ,母親の愛情を信じようとしているのではないかと思います。M子さんが母親に逆らわない様子があり,一方で心を病んでいる様子があるところから,このようなことがいえるのです。心の表と裏には,甚だしい矛盾,乖離があるだろうということが窺われます。
こういう問題は,年齢が進んでから起こり始めるということは,ほぼ考えられません。心の障害が表面化しているということは,自我が受け入れようとしない,あるいは受け入れる力がない,そういうものを自我に代わって,あるいは自我を無視して,無意識の心がなにものかをアピールしようとする試みであると考えることができます。そういうものの中で,いわゆる外傷体験といわれるものであれば,自我が事の大きさに衝撃を受けて,受け止めることができなかった体験ということになります。自我は,そのとき大急ぎで抑圧機能を行使したのです。あたかも機能麻痺に陥ったかのような事態でも,自我はそのような働きをして,自分のキャパシティを護ったのです。そして時間が立てば,自我はおもむろに回復して,記憶の空白となっているそのことを想起することができるようになります。つまり,原則的に想起可能なのです。ところが摂食障害のような問題については,その意味での外傷体験が原因であるとは,およそ考えられません。それは食に関わる人間の本能的,原始的な行動異常であり,著しい退行現象という側面があるからです。そして,それが極めて激しい欲求であり,それが世界の一切であることを示そうとしているかのようであり,生きるエネルギーの激しさでありながら死を賭してでもやめるわけにはいかないという死の色が表われていることでもあり,大人である病者が,必死に訴えようとしているのは,乳児の渇望と捉えることで,なんとか納得がいくことのように思われます。そして,そうであれば,情緒的な満足への激しい渇望ということなるのです。そういうところからどうしても生まれて間もなく,母親との関係で,何らかの恐怖体験をしたに違いないということだと思われてくるのです。そのために幼い自我は,自分を抑制(情緒的なものを抑制するのと同じことです)するのが習慣になり,要するによい子となって母親との関係を保とうとしたのではないでしょうか。ですから,母親が大好きと信じてしまうのが安全でもあるのです。それは,先に上げた男性の例のように,他に配慮しすぎて,自が疎かになるということです。
母親への怒り,憎しみもあるはずです。自傷行為や摂食障害には,内向する怒りが関与するものであるからです。それらは無意識の世界に収めてしまい,自覚的には母親を信じ,愛しているつもりになっているということではないでしょうか。
そのように見ていくと,M子さんが幼いころから病弱だったのも,同様に内向する怒りと,それを招いただろうと思われる情緒的な欲求の抑圧がからんでいると考えるのが自然ではないかと思います。そして,M子さんは,それらの病気を利用していたようです。病気というのは辛いものです。それをよしとする心は尋常ではありませんから,そういうことが起こっているということは,病気以上に辛い現実があったということだと思います。
その辛い現実を,母親に向かって言葉で訴えることができなかったのは,M子さんの気の弱さからでしょうか,それとも母親への恐怖が強すぎたからでしょうか。もしかすると,自分でも辛い現実であるとは思っていないかもしれません。そういう思いを持ちつづけるのは苦しいことですし,エネルギーを必要とします。そういう本音のようなものは,すっかり無意識に預けてしまって(自我の不始末),意識的には,母親の愛情を信じ,自分も母親を愛していると思っているかもしれません。その方が気が楽のはずですし,また,実際にそのようなものへの憧れがあるはずでもありますので,いうならば嘘であっても信じていたいというふうに,心が動いてもおかしくはありません。しかし無意識に溜め込まれた不満は増大していることは明らかで,それを考えれば意識の欺瞞というものがあるのも明らかでしょう。そして,それらの無意識の反攻が身体の病気という形を取っていると考えられるのです。
M子さんの自我が恐怖にめげずに,勇気を奮い起こして母親に立ち向かうことができていれば,それは自我が立派に役割を果たしたことになり,無意識との調和を保つことができただろうと思います。そういう姿勢で臨んでいれば,母親の対応の仕方も違っていたかもしれません。
ともあれそのようなことが起こり得るのが,人間の心の真実です。信じていた人に,あるとき不信の念が生じるとしても不思議はないのです。むしろそういうふうに,信と不信が交錯するのが人間です。いずれにしても,”ほどほどの満足”というのが人間の分ですから,信頼もほどほどのものであるしかないのです。誰か重要と考えている人に絶対的な信を置いているとすると,そこには何らかの無理,自己への虚偽,背信が隠れているかもしれないと考えてみる必要があります。
カエサルが暗殺されたときに,「ブルータス,お前もか」と叫んだという有名な逸話があります。信頼している人にひどい裏切られ方をすると,受けた心の衝撃は,その人の人格を変えてしまうほどのものでしょう。カエサルのブルータスへの信頼が絶大なものであった分,裏切られた絶望の大きさも察しられるわけです。
しかしこのエピソードには,信頼しきることの心根の美しさというよりは,権力者の驕りがうかがえるのではないでしょうか。ブルータスは裏切り者であったかもしれませんが,絶対の忠心という隷属を拒否したと考えることも可能です。ここにはカエサルの自己過信と,傲慢とが招いた悲劇の様相が現れているように思います。
権力者は,周囲の者に高い要求を持ちやすいものだと思います。人への高い要求は,一般的には恋人同士や夫婦や親子などに見られますが,要求を高くする背景には怒りがあります。そして他人(そして自己自身への)一般への不信と恐怖があります。
カエザルのブルータスに対する絶対的な信頼は,心の裏面に,不信と恐怖と怒りが強いエネルギーと共にあったことを示していると思います。
母子の関係にも,これに類似するものが見られることがあります。それは決して珍しいことでもありません。子供を自分に隷属させておきたいと考える母親は,無意識レベルをも含めると,普遍的とさえいえるほどおびただしく存在しているでしょう。一見すると仲がいい親子であることも多いので,母親も子供も無自覚になりがちな問題でもあります。しかしそういう関係に無力に依存する子供は,生涯にわたり,自分らしく生きることが難しくならざるを得ないでしょう。無力な依存よりは,ブルータスのように隷属を拒否する反抗心が,むしろ人間としての心を育てるのです。
ある青年は母親が100パーセント好きだといいます。母親は君のことをどう思っているだろうと訊くと,恐らく100パーセント好きだというと思うと,自信たっぷりにいうのです。家で下着でくつろいでいると,母親は,性器のことをしばしば口にするそうです。青年もそれを不快に思うことがありません。二人はほとんど近親相姦の関係にあるようで,青年もそれを認めています。しかしそれが問題だという実感はないのです。
彼の問題は社会性が育っていないこと,自分が社会人としてなにをすればいいのか見当がつかないことなどですが,母親との関係で自足している面があり,いまのままでも特には困らないのです。単に母親が長生きしてくれればいいと思うだけです。
「どうしたら友達を作れますか?」と質問しておきながら,「別に欲しくはないんですけど」とつけ足します。せっかく入った大学を,合わないような気がすると,あっさりやめてしまいました。万事に切実感がありません。
母親が息子との赤ちゃん時代の蜜月関係を手放したくなかったのかと思われます。息子の成長を阻止し,自分に隷属させることに成功したというふうに見られなくもありません。本人が問題視しないかぎり,他人がとやかくいう筋合いのものではないともいえるのでしょうが,青年が母親の身勝手な愛玩物に仕立て上げられてしまっているのは明らかなように思われます。母親の愛情のあり方に,ブルータスのような怒りを向けることができていれば,彼の人生への悩みは,もっと実のあるものではなかったでしょうか。彼の人間としての自尊心も,より高度なものではなかったかと思います。
愛する者を愛しつづけるためにも,憎しみの心が正当に扱われなければなりません。あってはならない関係を断ち切るために,怒りを向けることも必要です。母親がどんな魔術を使って息子の怒りを封じ,いつまでも幼子のように母親の許にとどまることを可能にしたのかは分かりません。しかし,そこに性的なものが介在しただろうことは,容易に察せられることです。性のエネルギーは強力であるだけに,それをほどよく満たしつづければ,息子をいつまでも自分の許にとどめて置くことも可能になるのでしょう。残酷さをはらんだこのような愛も,愛の形態の一つです。しかしながら,子供の心を思うように支配しようとする欲求は,表面はどんなに優しく見えても,子供自身がある種の満足をしているとしても,自分本位で残酷な心に基づくものといわざるを得ません。
”ほどほどの”というのが人間の分としては大切なところです。愛に関しても,それを徹底させようとすると,いつしか憎しみに変貌しかねません。憎しみの心は,それを反省する余裕がなければ,力づくで相手を支配しつくそうとする心の動きにつながるでしょう。自分が望むように相手を支配することができなければ,自分自身が限りなく不幸で,可哀想なのです。その要求を押し通すために,愛の仮面を躊躇なく身につけることも力の行使の有力な手段です。反省する心がなければ,それを相手への愛情と信じこませてしまう欺瞞化する意識が,いわば無垢の心のように,手つかずにとどめ置かせることになるのは必至です。 先にも述べたように,母親は赤ん坊に対して,特別の位置にあります。それは,時によっては特権的な立場と錯覚させるものです。母親が心に満たされないものがあり,依存欲求が強いときに,夫の理解と協力が足りなかったり,あるいは夫を見下すような夫婦関係であったりすると,赤ん坊は危険な状況にあるといえるでしょう。母親の恰好の依存の対象とされるという意味でです。そういう心的状況にある母親は,自分でも意識していないレベルで,怒り,不信の感情を強く持っている可能性があります。場合によっては怒りを振りかざし,あるいは愛情の仮面で怒りを巧妙に隠蔽し,子供を支配しようと,あの手この手と策を弄するとしても不思議はありません。もちろん,自分に悪意があるという自覚はないでしょう。子供のために努力していると思うのではないでしょうか。子供に対して,特権的な立場にあると感じているとすれば,子供が服従するのは理の当然で,なんの疑問もないのです。母親自身が子供時代にその母親からおなじような扱いを受けてきたとすれば,ますます,それは気分的に正当化され易いと思います。母親が自分の間違いに気づく機会は,ほぼ絶望的にないのと同様に,子供も母親の自分への支配的な依存の片棒をかつぐ関係から脱することも絶望的に困難になるでしょう。それを脱する唯一の可能性は,子供が怒りを持ってそういう母子関係を切断する力を持つときです。
愛の真実についてあまりに理想を求めるとき,それは,愛の欠乏に耐えてきたことの反面の姿といえるでしょう。その心の裏には,強い不満や怒りが潜んでいるものです。母親が子供を相手に愛情についての錯覚に陥るのは,真実の愛情というものにこだわる心が災いしたと,場合によってはいえるのかもしれません。そういうものを求める心の根については,同情されるものがあるに違いありません。しかし,それは必ず新たな災いの火種を作り出さずにはおかないでしょう。ほどほどの愛に自足できなければ,ある程度以上のことは笑って許せるほどの寛容と遊びの精神がなければ,この世はどうしても地獄化することになるようです。
心の病理的な問題を扱う立場にある治療者は,患者さんの心の形成過程を見ていかなければなりません。その際の中心的な問題は親子関係です。親の子に対する愛情が,適切かつ豊かであることが仮に証明できれば,目の前にいる患者さんの心の障害がなぜ生じたのか,ほとんど手がかりを失うに等しいといえます。ですから一般的に,問題がないかのように見えても,なにかが隠蔽されていると考えないわけにはいきません。そして,事実,治療の進展に伴って問題が語られ,明らかにされていくのがふつうです。その場合,親の子に対する養育姿勢の理想が,適切かつ豊かな愛情にあるとするのが前提とすると,自ずから親の子に対する愛情の希薄,歪み,悪意,憎しみが問題になることになります。
親のあからさまな子供への攻撃が見られることは,稀にはあるにしても,一般には少ないと思います。しかし,表面に現われている様子がおおむね穏やかであっても,愛情とは別種のものが裏面で暗躍していることは珍しくはありません。それは子供の心に暗い影響を与えることになるでしょうが,子供自身もそれを深く隠蔽して問題視しようとしないことが少なくありません。問題があるのが明らかなのに,子供本人は心を語ろうとしないとき,治療上の進展が得られようがありません。その様子を見ていると,人間の不思議を思います。それはもしかすると,「治りたくなんかない」という表現かもしれません。いずれにしても,怒りがエネルギーを蓄えて潜在しているのは確かだと思います。怒りに言葉を与えるとすれば,「治ってなんかやるものか」ということになるのかもしれません。その種の恨みを自我が取り扱う気がなければ,それは自爆に向かうか,周囲を攻撃するか,どちらかになるしかない危険があります。
ここで注意を要するのは,いうまでもないことでもありますが,親の養育姿勢に関する客観的事実と,子供のイメージとして生じている主観的な現実とのあいだには,一般的にかなりの隔たりがあるということです。
本人の心に,自分のために,自分らしく生きるための基盤がそれなりに形成されているかどうかが問題です。それが現に形成されているのであれば,そもそも受診の必要がなかったでしょう。
ある患者さんは自分でも認める”いい子”で,母親に過度に依存的でした。あるとき,「母親とは価値観が違うと分かった。もう相談しても仕方がないと思っている」というのと同時に,「私の中に中心ができてきたような気がする」と自分から述べています。この感覚が大切です。そういうことが地に足が着くように確かなものとなっていくのが,治療的な目標です。
この方の場合,母親の現実は,「口では分かったようなことをいっていて,実際はまったく変わっていない。今も,昔も,私を支配しようとしている」と本人がいうように,以前と何ら変わっていないようです。そういう母親に見切りをつけることができた本人が,母親イメージを変容させることができつつあるということのようです。このようにイメージが変容していくことが心理治療の要点になりますが,母親なり他の家族なりが協力的に姿勢を変容させていくことが,治療環境を整えることになります。周囲の人は直接的に手を貸すことはできませんが(そういうことは余計なお節介,干渉になるのがおちです),望ましい姿勢で見守ることにより,患者さん本人が自己の回復に向けた心の作業を行い易くなることが期待できます。
家族という関係の中で心理力動が働き,家族成員個々の性格形成に影響を与えます。
家族の中で影響力が強い立場の者(ふつうは父親,母親ということになります)は,権力者に特有の盲点がある場合があります。常識があれば容易に分かりそうなことが,本人には不思議なほどに意識できない心があり,子供たちに被害的な影響を与えていることがあります。時には,特定のスケープゴートを作り出したりもします。
個々人の心は,家族という関係の中で良くも悪くも変容しますので,心理的な治療とはいえ,本人一個の問題ではなく,家族(更に学校や会社などの生活状況の全体も問題になります)という単位で考えなければならないものでもあります。
ある男性は,両親の愛情が一心に兄に傾いていると信じています。そして彼自身も,兄は学業でもスポーツでも,あるいは人に愛される好ましい性格においても,あらゆる点で自分より優れていると思っていたのです。ですから両親が兄を評価し,自分を評価しないのは仕方のないことと考えてきました。それで兄のような人間であること,兄のように生きることが両親の願いであり,意志であると信じてきました。それで不承不承ながらもその願いに沿うように努力してきました。ある程度は彼の努力は成功しました。兄とおなじ大学,おなじ学部になんとか入ることができたのです。大学を出て一流企業に就職しました。世間的な常識では彼はエリートということになるのですが,彼自身は人生になんの希望も持てず,自分には何ひとつ取り柄がないと感じ,虚しく無気力な日常を送ってきたのです。
彼の心の中には怒りが充満していると,私にははじめから感じられていましたが,彼自身はそういう感情の存在にほとんど無自覚でした。しかし,ある時期から両親への怒りを口にするようになりました。
自分はずっと叱られてばかりいた,両親はそんなことはないというかもしれないが,少なくても自分の記憶では愛されたということはまったくない,一方,兄が叱られるのは見たことがない,私が生まれたときに両親が望んだのは,私ではなくもう一人の兄だったのに違いないと思う,なぜ私を生んだのか,なぜ中絶してくれなかったのか,云々と激しい怒りの表明がある時期ひとしきりつづきました。そして自分の人生を歪めたのは両親だというのです。
そういうある時,彼はそうした認識が間違っていたと,ふと気がついたのです。兄そのものになりたいと考えていたのは自分だった,両親がそんなことを強制したわけではなかったと思う,なれるわけがない馬鹿げた考えに取りつかれていたものだと思う,そういうことに気がついてみると,両親が自分を思っていってくれたこともいくつか思い出した,それに伴って両親への怒りも静まった,なぜ生んだかということも考えなくなった・・・というのです。そして心が軽くなり,力が湧いて来るのが感じられたそうで,仕事に向かう気力が出てきたのです。
重要な要素は怒りの感情でした。幼少期から長年にわたり,両親の愛情が自分に向けられていないと感じ,怒りを持ったのは明らかです。そういうものがあるのは,言葉の端はしからうかがわれ,ある時期には直接的に言葉で表現しました。しかし,彼は怒りをむしろ打ち消しながら成長してきました。兄と比較して自分が劣った人間という認識が強固にありました。そうであれば,怒りを持つことは不当なことであり,許されないことになるのです。それは彼のイメージにある両親の考えと符号するものです。客観的にどうであったかはともかく,彼が両親が考えるだろうように自分を否定し,兄を肯定的に評価してきたのは疑いありません。
しかし,自然な心が自己否定に陥るということはあり得るでしょうか? それぞれの自己が自然なものであれば,良いも悪いもなく,価値に順位をつける気になるとは考え難いことです。誰が好んで自己を否定し,他を肯定するでしょうか?
そういうことが起こるのは,必ず他者,それも最も頼りとする他者の評価に影響されてのことに決まっているといって間違いはないでしょう。自分の価値を他者によって決められて怒りを覚えない者はないでしょうが,その評価に本人自身が同調してしまえば,誰に向かって怒りを向ければいいのでしょう? 自己が独立して自己であれば,自己評価に怒りを持つ理由がなく,怒りがあるとすれば,自己が強く依存する他者による有無を言わせないものにであり,怒りが向かう先はその他者と,その他者に同調している自我以外にありません。怒りのあるところ必ず依存があり,そして人間は依存から自由になることができない存在です。
怒りは他者への依存の目印です。自分が自分のために何をしなければならないか,その手がかりを与えてくれるのです。
彼は怒りの感情を抑圧しました。それに伴って,劣った自分という自己イメージを受け入れました。それは,イメージとしてある両親の考えと同一のもので,彼自身のものと区別がつかなくなっています。つまり,そこには両親に迎合する心があり,彼自身がどこに存在するのか分からないほどに支配されている様子があるのです。それをしているのはイメージとしての両親であり,それを許しているのは彼自身です。彼は怒るに怒れない状況にあるといえます。
恐らく両親は,彼にとって権威的,権力的な逆らい得ない存在だったのでしょう。両親に迎合し,支配を受け入れる自我によって,怒りが封じられ,怒りによって生じる親子関係の危機を回避したということであったと思います。それに伴って,愛されない自分,価値のない自分という強固な自己イメージが,固定的に形成されたということでもあります。
そして抑圧された怒りを意識がとらえはじめたときに,彼の自己イメージは変容の兆しを見せはじめたのです。それは自我が活性化し,機能を回復しかけている様子でもあります。それに伴って,自分を愛さず,無価値な存在と決めつけている性格を持つ両親のイメージに対抗し,怒りを覚えるという動きがありましたが,イメージの変容が進むにつれ,それは両親の考えそのものではなく,両親の態度への過剰反応だったことに気がついてきました。つまり,怒りを捉えた自我は自分自身の問題を問題とする気配を見せ始めたのです。そして,また,人生そのものを否定するほどの怒りを両親に対して持つたことの行き過ぎを,訂正する自由な心を得たのです。
M子さんの美人コンテストの問題について,愛情という観点から見てどうかというのがこの一文の最初の設問でした。それはいま述べた事例についても共通していえることですが,親が子の立場をどのように尊重したかということになるようです。親が自分の気分的な価値意識で,事実上子供に強制したのであれば,いうまでもなくそれは子供を個として尊重したことにはなりません。いくら将来のためといってみたところで,子供の領域に侵入し,強制したのであれば,それは愛に値しません。芸術やスポーツの領域では,親のスパルタ訓練が子供の才能を開花させるということはあると思います。子供は親のおかげで今日の自分があると思うかもしれません。親も成功した我が子の姿に,感無量の涙を流すかもしれません。確かに親が子供の立場を尊重して自由に任せていたとすれば,才能の開花はなかったかもしれません。しかしながら,親の冷酷や身勝手が子供の才能を開花させる場合があるとしても,親が賞賛されるわけにはいきません。子供の才能によって,親がむしろ助けられたのです。子供の才能がなければ,子供は押しつぶされて心の荒廃を招いたかもしれず,親は非難されるところでした。そして,実際には子供の才能は開花せずに終わることがどれほど多いことでしょうか。大多数は荒涼たる精神の破れた姿が残ることになるのです。その荒野に咲く徒花が,心の障害であるとっても過言ではありません。
M子さんの自傷行為や摂食障害は,なにを表現しようとするものでしょうか? 自我が心の中軸として指導性と統合力を保っていることができていれば,心の障害といえるようなことは決して起こらないことです。自我は,自己を形作り,自己を護るべきものであるからです。自己を破壊してまで,他人に何事かを伝えなければならないのは尋常なことではありません。いかなる行為にも,他人へのメッセージ性があります。自分を表現するということは,何に向けてかといえば,他人に向けてに決まっているのです。日記は自分だけのものです。他人が見ることを前提としておりません。しかし,それは他人に見られるかもしれないということを排除できません。他人には見られたくないものを自分は持っているということは,眼差しの彼方に他人があるということです。人にはいえない秘密も同様で,彼方に他人の眼差しがあるからこその秘密です。見られる(知られる)ことを拒否するというのも,他人へのメッセージです。
心の障害ー症状というものにも,同様に何らかのメッセージ性があります。
自傷行為は,秘め事の行為ですが,それをを知って欲しいという心が,むしろ働いている行為でもあると思います。無人島に長年のあいだ一人で暮らしている人が,自傷行為をするかどうかは疑問です。おそらくしないように思います。自殺もないのではないでしょうか。身体の美に神経を使う若い女性が,腕に隠しようもなく残っている傷痕を,夏場などの軽装のときに,隠そうとしない人が少なくありません。どこか誇らしげに,これ見よがしというふうにも見えます。夫に「隠せ」といわれて,「私は別に気にしないんですけどね」と不満そうにいっていた女性がありました。この心理は,「普通の人」への挑戦的な気分の反映だろうと思います。
身体を切りたいという衝動は不可解なほどに強い欲求です。苦痛を恐れるとか,苦痛に耐えるとかという意識はないかのごとくです。本人にも,「どうしても切りたいから」としか説明できない強い要求のようです。そこには悪魔的な力が働いているように思われます。切ったときに流れる血を見て,血肉が踊るという感覚になる人が少なからずあります。殺人鬼の快感に似ているという印象を受けます。それはすさまじい怒りが介在した悪魔的な行為であるようです。その怒りを他人に向ければ凶悪犯罪になりますが,自分自身に向けるので,命までは奪おうとはしません。「久しぶりに切ったので,加減が分からなかった」と,血を滴らせながら外来に来た人がありました。「他の人が怖がるから,これからは切ってしまったときは遠慮してね」といったところ,「え? 怖がりますか」といっていました。そして,その後は約束を守ってくれています。
自傷行為というのは,実は行為ではないと思います。行為というのは意志が働き,判断が働きます。つまり自我の営為です。自傷というものは,自我の営為とはいえません。つまり本人には責任が取り難い問題です。
では,誰の意志による行動なのでしょうか? 私はその意志の主体を,裏の自我と呼びたいと考えています。
裏の自我というのは,以下のようなことです。
自我は,生物学的な基礎を持つ自我機構の上に機能するものであると考えられます。それは植物の種の内部に,将来のその植物の形態が,既に,あらかじめ仕組まれているのに似ていると思います。その自我構造の中に,構造的に他者や境界機能などが内属していると考えられます。自我は自己を形成していく上での中核といえますが,とりわけ生まれて間もない人生の最早期の自我は未発達で,他者(母親)に絶対的に依存します。他者の存在を抜きにしては自己の存在はあり得ないのが人間です。その原型的他者は母親です。
他者は,人生での不可欠のパートナーですが,それは他者が常に有益な存在であることを意味しません。逆に,なにかとそれぞれの自我を混乱させ,人生を迷走させる最大の理由ともいえるのです。原型的他者である母親といえども例外ではありません。むしろ母親が他者の原型であるだけに,それぞれの自我を混乱させる原点にあるといえます。
絶対依存という赤ん坊の身を考えれば,他者なる母親の保護は,生死に関わる意味を持ちます。母親は常に有り難く,優しい存在と単純に考えるわけにはいきません。絶対的なものを必要とするということは,そもそも危険な状況といえるのです。絶対を保証することなど,人間にはできないことだからです。そのようなことから,他でもなく,最も頼りとする母親によって,恐怖(赤ん坊にとっては死につながるものだと思います)する瞬間は,どんな赤ん坊でも避けられないだろうと思います。赤ん坊にとっては母親との関係を保つことは,生死に関わる重要なことですから,場合によっては母親を怒らせたり,困らせたりしないようにすることの必要を,半ば本能で感じ取るのではないでしょうか。具体的には,甘える心を母親に向けることに神経質になる場合があると思います。甘えるということは,赤ん坊にとっては自己の主張であり,それが主張であるからには,相手の拒絶にあう可能性があるのです。拒絶には怒りが含まれます。赤ん坊の未熟な自我は,母親の怒りをおそれて自己主張を控えることになると思います。そのときに発動するのが,境界機能です。境界機能というのは,自己と他者とのあいだ,意識と無意識とのあいだにおいて,相互の関係を画然とさせる役割を持ちます。そして他者との関係で,境界機能を強化して,自我の混乱,破壊を護ろうとするのが,抑圧と呼ばれている心的過程です。
甘える欲求を満たすことは自我の役割であり,心の成長のためには重要なことなのですが,他者なる母親との関係に危険なものを感じれば,そちらを優先させて身を守ろうとするのです。生きるために必要なことであっても,生死をかけた問題の方が優先されるということです。
赤ん坊という頼りない身を考えればやむを得ないことが起こるのですが,抑圧された甘えたい心からすると,理不尽な,認め難いことを自我がしていることになります。その角度からいえば自我の不始末といえ,自己の形成の過程で,自我は自己に対していわば借りを作ってしまうことになります。そういうことが繰り返されることになるとすれば,気弱な自我ということになり,多難な人生を切り開くには問題が大きいといえるでしょう。
自我の強さは,生まれつきの素質によるところが大きいと思いますが,幼い子の自我は両親によって守り育てられなければなりません。自我の機能の中でも重要なものが自律機能と思われます。それが心が成長するための拠り所になります。植物の種を蒔いたあとに,注意深く手をかけて大地に根が下りるのを助けるように,傷つき易く,混乱し易い自律機能の根を,母親と父親が大切に護り育てるのが,つまり愛情というものです。
心の病気には,自我の自律機能の混乱と境界機能の不全化という側面があります。われわれ治療者の目標は,これらの機能を回復させることにあり,話をしっかりと聞く(受け止める),落ち着かせる(混乱を鎮める)ということが欠かせません。一般的にも,混乱し,不全化しているこれらの機能を鎮めることができるのは,人の優しさ,愛情です。誰であれ,人の優しさに触れることがあれば,心が落ち着き,癒されるものです。そういう手助けによって,病者の自我が受け止める力を回復することができれば,即ち自己の回復ということになります。
子供が反抗的で,親に怒りをぶつけてくるとき,親はそれを受け止めることが必要です。怒っているという事実はまず受け止めることです。親のその姿勢を確かめることができれば,怒っている子供は,心の裏で求めていた愛情欲求について語り始めるかもしれません。怒りは認められなかった愛情の裏面だったということが明らかになってくるに違いありません。
親に逆らわない子は,何か不自然なものがあってのことと考えてみる必要があります。親の側に,何らか怒りを封じるものがある可能性があるからです。よい子というのは,自己犠牲なしには済まないのです。いわば自分を殺して,親の気持ちを優先させる強固な癖がついてしまったのです。その大元は,赤ん坊のころにあります。親への恐怖があり,生きる本能が親に取り入る手段を教えたのです。それが強固なものであるので,自我が親の自我を内在化させ,両者はほとんど区別がつかなくなっています。そのために,四六時中親の監視と支配の下にあるのと同然になっているのです。よい子というのは,親にとっては有り難いことなので,自分の子に問題があるとは考えにくくもあります。ですから,親たる立場の者は,この問題に関心を持つべきであると,特に強調しなければなりません。よい子というのは,いわば心が発育不全なのですから。
良い子の穏やかなたたずまいの中には,実は心の奥底に親への恐怖が潜んでいると考えなければなりませんが,もしかするとこの二層性の心は,母親の無意識(半ばは意識的と思います)的な操作によるものです。母親は子供を愛しているというメッセージをたえず送っていると思いますが,子供の様子をうかがうもう一つの目があると考えてみるべきである理由があります。子供がおとなしいのを良いことに,そのまま放置しておけば,後々,子供がさまざまな逸脱行為をはじめたり,心の何らかの障害に陥ったりということで,親のこれまでの操作的な干渉が攻撃されるということにもなるのです。
子供を愛していると思っているとき,怒り,憎しみがどういう形で心の奥に存在しているのか,一応は内省してみるのが賢明です。愛があるところ,必ず裏面に憎しみがあるのです。それが見つかれば幸いです。ないわけがないのですから。そして愛と怒りが対決するとすれば,結構なことです。それは新たな心の統合の動きの始まりなのですから。きっと更に深い愛情が生まれ出ることになると思います。
光と闇,白と黒,愛と憎しみなどのように,対立する二つが,一方が存在するためには,他方の存在を絶対的に必要とするのが人間の心の特徴です。自己と他者,男と女の関係についても,おなじことがいえます。古来,男女が合体して完全になるという元型的思想があります。
このように互いに相容れない対立する二つのものが,相互に他を必要とする絶対的な依存関係にあること,従って,心の出来事はおしはなべて相対的関係にあること,それが人間の心に固有なあり方です。そして人間にとって存在するものは,あらゆることが心の出来事という様態で存在します。
人間には白そのものは存在しません。黒そのものも存在しません。限りなく白に近い黒,限りなく黒に近い白という様態で,白と黒があります。光と闇も,愛と憎しみ,善と悪も同様です。 それらはすべて人間固有の二極構造をなしています。善人は全身的に善人であることはなく,悪人の自覚があるときに本物の善人に近づきます。僧侶は人の心を善導する立場にあります。だからこそ,坊主憎けりゃ袈裟まで憎いだの,生臭坊主だのと揶揄されるのです。本当に偉い僧侶があるとすれば,自分の心に潜む悪について知っている僧侶です。善と悪とはシャム双生児の関係にあり,切り離せないからです。それらのことは自然から乖離して,人として生きることを運命づけられていることに関連していると思われます。つまり絶対というものは,自然ならぬ人間の心の世界にはないということです。その意味で人間は不完全で,完全(自然)を目指すべく宿命づけられた存在です。
人が経験するのは,おしなべて有限で,従って相対的なことに限られます。絶対,無限,無というものを自我が具体的に捉えることは原理的に不可能ですが,宇宙に思いをはせているときに感じるめまいは,宇宙の無限あるいは無に触れたということではないかと思います。
自然はそれ自体で完結し,充足する完全なものに見えます。完全,絶対,無限,無というものは,自然の属性であり,人間が直接体験できる範疇を越えています。
愛は生きようとする力です。憎しみは滅びようとする力です。愛と憎しみとが心の内部で,あるいは人と人との間で激突し,愛が勝利を収めるか,憎しみが勝利を収めるか,それによって方向が定まっていきます。しだいに愛が優勢になれば,心の光がまします。しだいに憎しみが優勢になれば,心の闇がまします。人はしばしば地獄を生き,時に天国を垣間見ます。
人は対立するものを止揚することでより高次の段階にいたるか,あるいはその闘争に敗れて低次の段階に転落するかです。
いずれにしても,人はやがて闇そのものに覆われ,人としての終焉を向かえ,自然に帰ります。もともと生まれ出てきたところへ戻るのです。終焉を向かえるまでのそれぞれの個の心の様態の軌跡には,光りの方向に上昇しているのか,闇の方向に下降しているのか,あるいは気晴らしをしながら待機しているのか,それぞれです。
先に上げた,母親に小児的に依存している青年の場合,母親が人生の終焉を向かえたあと,どういう人生が待っているのでしょう。彼を支えるものが彼自身の心の内部になければ,彼は人生の拠り所を失うでしょう。母親との密着した関係が青年の心の発達を阻止している要因である可能性は,小さくはありません。そうであれば母親の息子への愛情は,彼を本当の意味で助けるものではなかったどころか,大変残酷なことをしていることになるといわざるを得ません。
愛情の当否を判定する能力と権限は人間にはないといいましたが,母親の愛情が本物であれば,愛を受けた子供の心の内部に心の中心が生起するのを助けると思います(母親だけがこの鍵を握っているわけではありませんが)。自分の心の中に,自分を支える拠り所が確かなものとして感得されていることは,人生を地獄化させないための要件です。それがあれば,ダルマのように,何かのストレスでぐらりと傾いても,ほどなく起き上がれるのです。人生の難所でつぶれるか,たくましく乗り越えるかを分けるものが,いま述べた意味での心の中心です。
依存心が度外れに強ければ,その子の親は,愛情において欠けるものがあるかもしれません。
性格形成に与える母親の影響-その3
■内在する主体
心には無意識の領域があります。人間の認識能力は,意識の届くかぎりという制約の下にありますから,無意識という意識の届かない領域のことが,なぜ認識可能なのかという疑問が起こるかもしれません。
たとえば私という人間が現に存在していることは事実問題です。これは否定のしようがありません。しかし私がなぜ存在するに至ったのかという疑問については,私は答えることができません。私は知り得ない理由によって存在しているとしか答えられません。この例によれば,私が存在していることは意識できるが,存在の根拠については無意識であるということになります。換言すると,私にはとうてい認識できない(意識できない)ものがあるということを,認識(意識)することができているということになると思います。
自分の心の世界について,むしろ知らないことがいくらでもあるのは,誰もが知っているとおりです。たとえば過食という本人にとっての深甚な苦しみは現実そのものですが,なぜそのような心の障害に見舞われたのか,さしあたり心的な理由が不明です。過食という事実は認める(意識する)しかないが,心の深部で起こっているに違いないなんらか心的な理由(何かが起こっているのは明らかです)は認識(意識)できません。それは意識の光が届かない無意識の領域があることを意味しています。
そして心理的な治療がうまくいって,その心的な理由を本人が認識(意識)できるときが来れば,おそらく過食地獄から解放されるでしょう。つまり無意識の領域に潜んでいる問題を意識が探り当てることは,ある程度可能なのです。そのことは意識と無意識との領域は,相互の境界が不明瞭で,従って相対的であることを示しています。
このように無意識の世界にも,意識化可能な領域がありますが,それが不可能な領域もあります。前者は個人的なある種の体験を,自我が自我組織に組み込むのを拒否し,無意識下に抑圧したものの集合体から成る領域です。
後者については,たとえば「私が存在していることは否定できないが,存在するに至ったいきさつについては認識不可能である」というとき,私には知り得ないが,何らかの根拠,プロセスが存在しているのは否定し難いという形で,その領域の存在を知ることができ,しかし存在の様態については認識することは不可能であるということになります。ここでは意識と無意識とのあいだに,絶対的な境界が存在しています。従って個人的な体験を超えた(理性的,合理的には説明ができない)ものの存在がここにはあると認められるのです。
C・Gユングは前者を個人的無意識,後者を集合的無意識と呼んでいます。
医学の基本には自然科学があります。あらゆる病気は何らかの身体因によるという理念が,現代医学を築き上げてきました。この思想は医学のみならず,現代文明そのものを築き上げてきたものでもあります。
精神医学にも医学一般の流れの中で,科学としての学問的な体裁を整えてきた歴史があります。その考えを敷衍すると,精神も自然科学的,合理的に理解されるのでなければ当てにならないことになります。事実,19世紀以降の精神医学の本流では,「精神疾患は脳の病気である」という志向が理念のようになっていたといえるでしょう。
しかしながら,そのような身体主義が身体医学では赫々たる成果を上げてきた一方で,精神医学の領域では見るべき成果が上がらないまま19世紀後半を向かえたといえます。精神医学の歴史はギリシア時代にまでさかのぼりますが,神や悪魔や迷信などの超自然的な解釈を排除して,自然的な疾病理解を追求したこの時代の観点は,それら超自然的なものに支配されがちだった当時としては,卓越した精神によって初めて可能だったといえるでしょう。事物の現象に忠実に即しようとするこの現象学的な姿勢は,現代でも尊重されている心理科学的な精神です。そしてその眼差しを歪ませたものは,かつては超自然的なものだったわけですが,現代では自然科学主義であるといっても過言ではないでしょう。「精神病は脳の病である」とする脳神話が,一時期ロボトミー手術を生み出して社会問題化したのはその一例です。これは,医学者たちが自然への忠実な僕という精神を投げ捨て,自然科学主義に囚われた忌むべき事態です。人間そのものをより,学問的な立場を盲目的に上位に置く姿勢は,専門家の陥りがちな愚かで傲慢な姿という他ありません。自然科学は人間が考え出した偉大な方法論であるのは確かであっても,自然を読み解く一つの方法であり,自然そのものはそれに従属するものではあり得ないという単純な事実が,奢った精神には見えなくなってしまうのでしょう。
それはともあれ,自然科学が精神医学領域では見るべき成果を生み出せなかったこともあり,18世紀後半までの100年間というもの,治療に関しては,はかばかしい進展がなかったということになります。精神病院に囚人のようにつながれていた病者ともども,打開策のない難問になす術がなかった精神科医たちも,希望も誇りも持てない囚人のような境遇にあったといえるようです。そういう境遇を自ら選んだ医師たちの多くが,患者たちと共に精神病院で寝起きして生活を共にしてきたのは歴史的事実です。有効な治療的方法を持たない医師たちは,そのようにして医師としての誠意や良心を示すしかなかったのかもしれません。
ギリシア時代に,医聖の誉れ高いヒポクラテスが活躍しましたが,彼の名声が世に知られたのは,むしろ死後のことです。学問の中心がエジプトのアレキサンドリア(プトレマイオス朝の首都)に移ってから,ヒポクラテスを中心とする諸家の医学思想が文書として編纂され,改めて脚光を浴びることになったのです。
ヒポクラテスの思想は,「ヒポクラテスの誓い」と呼ばれている文書に集約されていますが,医師の倫理的なあり方を説いたこの誓いは,神に向けて立てたられたものです。神々が人々の心に生きていたこの時代であるからこそ可能であったのですが,高度に人道的で,倫理的な姿勢が高らかに謳われております。
ヒポクラテスは「神聖病について」という一書で,てんかんを神の意向に基づく神聖な病気とするのが間違いであると断じております。この病気を現象に即してつぶさに診ていけば,自然現象のレベルで理解可能であるとして,神を持ち出すことを非難しております。この病気を神聖化したのは妖術師,祈祷師の類で,彼らは神を持ち出すことでいかにも神を崇めているようだが,その実,自分を優れた者に思い込ませ,祓い清めたり妖術を施したりするまやかしの施術に利用しているというのです。そして処置に窮したときには,神を隠れ蓑に利用しているといっております。それは敬虔な態度とは無縁の,むしろ涜神行為であると断じているのですが,神々が生きていたこの時代には,多くのいかがわしい者たちが,もっともらしく病人達を食い物にしていたことがうかがわれます。
ヒポクラテスが述べているように,神という正体不明の一者への信仰は,それを邪悪に利用しようとする不敬な輩もはびこる余地が大いにあるということですが,ヒポクラテス自身のように,高度に人間的,倫理的な拠り所でもあり得たといえるのでしょう。所詮は人間の所業です。神そのものがどうであれ,それを前にした人間の心が浅ましいものであれば,自分の都合のよいように利用するのも人間ですし,心根の優れた者であれば,高度に真摯に敬虔になれるのも人間です。神が心に生きている時代では,人の心は豊穣に満たされることが可能であり,一方では腐敗,堕落に傾くことも大いに起こりえたということのようです。
ドストエフスキーが,大きな善をなすことができる者は,それに相応して悪人でもあるといっております。ヒポクラテスのような高度な倫理性を持っていた医師たちが存在するためには,それに相応する堕落した精神の存在を必要とするということでしょうか。
ヒポクラテスの時代では,医師は神の前で特別な存在だったということです。
神の側から,「特別に悩みを持つ人たちのために,あなたの能力を使う意志があるか?」という呼びかけがあり,その啓示に感応した者が,それに応じ,誓約するという体裁があったようです。重要なのは,神の側に,人間の自由意志を尊重するという建前があったことです。それが前提であったので,それに応じた人間の側には,神に選ばれた者という意識がありましが,憑かれた者ではなかったわけです。ですから当時の医師たちには,通俗的な野心や名誉欲を超越した高い倫理性が備わっていたといえるのでしょう。
医師と弁護士と僧侶とは,このように神との契約という意味を持つ特別な存在で,単なる職業人ではないという歴史的な由来があるようですが,自然科学の申し子である 現代の医師たちの倫理性はどうでしょうか。
ヒポクラテスがあやしげな施術師たちを,神を隠れ蓑にしているとして非難していますが,現代の隠れ蓑は自然科学といえるでしょう。現代では,医師は,生きるための方便としてその職業を選んだとしても,表立って非難するわけにはいきません。
ヒポクラテスの精神は,「神を拠り所にするが,これを隠れ蓑にするまやかしは排除する」ということでした。現代では,自然科学が拠り所になっていますが,この学問は精神的なものを排除することで成り立っているので,医師の倫理の問題は,まったく個々人の人間性に委ねられているといえます。人間性の怪しげな医師であっても,定められた方法的な手続きに基づいて仕事をしていれば問題はないことになります。医療事故が起きれば,定められた注意義務に怠りがなかったかが問題とされます。人間が人間の行為の是非を判定するのですから,それが公平というものでしょうが,良くも悪くも人間の精神の問題は不在です。
精神論を云々することは,神々が人の心に生きていない現代では,しばしば胡散臭くもあり,誤解を招き易いものでもありますが,現代の精神的な貧困を考えると,ヒポクラテスの時代の神の現代版はなにかという問いは切実なものがあるように思われます。その意味で,ヒポクラテスの精神が生きていた時代と較べると,現代の医師の倫理的な基盤は,文字通り地に落ちてしまっているといわざるを得ない状況にあるというべきでしょう。 現代において神の問題をどう考えるかは特別に難しいことですが,この問題は,神々が心に生きていた時代の精神の豊饒と,自然科学を金科玉条とする時代の精神の貧困とに,如実に反映されているように思われます。
現代においてヒポクラテスの精神をどのように回復できるのか,それは不可能なのかという問いは,医師の倫理問題を超えた人類的な課題であるように思われます。
精神医療が新たな発展を開始したのは,1900年に近づくころでした。しかしながら治療的な閉塞状況に風穴を開ける試みを始めたのは,残念ながら精神科医たちではありませんでした。精神病院の中で,重篤な病人ばかりを前になす術を知らなかった精神科医たちは,赫々たる成果を上げてきた身体医学的な手法が,精神医療に関しては何らの光明ももたらさないことで更に治療的なペシミズムに陥ったままでした。その一方で,神経内科医たちが別な角度から心の病を見つめていました。彼らの外来には,内科的な神経疾患とはいい難いおびただしい数の患者たちが訪れていました。彼らは現代でいうところの神経症者たちでした。内科医たちは,これらの人々のために,何かをしなければならない状況に置かれていたのです。医学の王道である生物学主義の呪縛にかかっていた精神科医たちとは対照的に,彼らは,目の前の神経症者たちを,自由な眼で診る立場にいたといえます。これらの病者の悩みの多くは,「了解不能」というほどのものではなく,健常人と較べても五十歩百歩と映ったでしょうから,一足飛びに「脳の障害」と考える事もなかったのです。
精神医療が生物学的根拠をもとめて,見るべき成果を上げられないでいたこの時代に,それと平行して,メスメリズム(動物磁気説)が一世を風靡していました。これは従来は,医学的本流からすると,いかがわしく,不真面目なものでした。しかし治療的な効果が広範に認められ,熱心な信奉者たちがいたのは否定し難い事実でした。そこに大学教授であったベルネームが注目し,心理療法として導入するにいたり,催眠療法が再認識されることになったのです。催眠療法はそれまでは軽視されていたのですが,ベルネームが学問的に評価したことによって,無意識の領域への扉を開く鍵を,いわば公的に手にすることができたといえます。そして,やがてはフロイトに代表される精神医療の本流への流れができたのです。フロイトの精神分析への発展は,無意識という自然科学の手法の及ばない心の領域に,心理的ー科学的な新たな観点をもたらしたことを意味します。これは精神医療の歴史にとって画期的なことです。
このように自然科学の呪縛から解き放たれたときに,精神医学は,新たな治療的な展開を大々的に開始する方法を得たのです。
そもそも人間は自我を持つ存在です。自我の機能の主要なものの一つが論理性です。自我は合理的精神の砦ともいえますが,その骨子となるものが因果律であり,自然科学においてそれが純粋化されたといえるでしょう。自然科学は自我の能力を模範的に,最も高度な形で示したので,現代人がこの合理的な精神に魅せられ,大きな価値を置くことになったのは,自然な成り行きでもあります。
人間の人間たる所以は自我にあるので,可能なかぎり自我による支配を確立したいと考えるのは,人間であれば当然の欲求といえます。
宇宙には無数の未発見の星体があると思われます。その存在が直接的には証明されていない段階で,科学的類推によって存在を確信する理由が与えられることがあります。これは自然科学の理にかなっていると認められたことを意味し,自我の支配が宇宙に向けて拡張されたことを意味します。
無意識の世界では,個人的無意識の領域に関するかぎり,原理的には自我の光が届くことができます。精神分析的精神療法では,治療者が患者さんの自我と協働して無意識の暗闇に向けて意識を操作するのですが,そのことを通じて,自我が自我組織に組み込むことを拒否していたものを,改めて回収し再統合することになります。
精神的な何らかの不調は,自我が無意識との相対的な関係で,有効に力を発揮できなくなっていることに起因するといえます。ですから自我が健全であれば,精神の不調は原則的には起こり難いといえるでしょう。あるいは起こったとしても,ダルマのように素早く姿勢を元通りに正すことができるといえるでしょう。
自我の機能が生来的に弱い人もあると思います。それは自我が生物的な基盤の上に成り立っていることを示唆しています。また繊細過ぎたり,気が弱かったり,父親や母親の養育姿勢の問題が大きかったりで,抑圧的な態度が習い性になっているなどすると,自我が持てる力を思うように発揮することが,多かれ少なかれ難しくなるかもしれません。
いずれにせよ,これらのことは相対的な問題で,だれにでもそれなりに起こって当然というようなことでもあります。 このように自我が好ましい状態にないことと,精神の不調とのあいだには密接な関連があります。心の治療は,方法的にはさまざまであっても,この関係を調整し,自我の姿勢を正すというところに行き着くといえるでしょう。自力でこの作業をするのが難しいときには,治療者によって自我を支えてもらう必要があるのです。そして両者の関係が十分に信頼の絆で結ばれて行くにつれ,治療という心理的作業を通じて,自我の成長,強化が果たされていくものです。
心の治療では,治療者が心の障害を取り除くのではありません。患者さんが治療者の協力によって自我の姿勢を正し,その能力を回復させることによって,おのずから自分の問題を克服していけるようになるのです。言葉を換えれば,無意識の領域にある問題(従来は受け止める能力を持てず,抑圧するしかなかった)に眼を向ける力を取り戻すことができるのです。このように心理的な治療がうまくいけば,自我の支配圏が拡張されたことになります。それはただちに人間として成長したことを意味します。
以上のように,心にとって内側と外側とに向けて自我の力がおよび,支配圏を拡張していきますが,どの範囲までと限定するのは不可能であっても,自ずから限界があるのも,また,明白です。意識の光が届き得ない絶対的境界が存在しているのは,経験的に自明のことといえると思います。
この絶対的境界で隔てられた無意識と宇宙の無限とは,自我の機能が及び得ない世界です。従ってそれらを科学的に証明するのは,等しく不可能です。言葉を換えれば,「人間には人間的な理性では,その存在の様態を理解することができないものがある,しかし,存在していること自体は認識できる」ということができると思います。更に言葉を換えれば次のようになります。「これら超越的なものの存在を,直感が捉え,自我に訴えかけることがあるが,その実態的な様相について自我が認識的に捉えることは不可能である」
ところが,以上のようなことは自明ではなく,人間の理性はあらゆることを解決可能だと信じる人もあるようです。こうした自我万能の信奉者にかかると,結局,人間自身が神になるしかなくなるのです。そして地球規模で危機的な状況におかれてしまっている現代のもろもろの問題は,実際に人間が神に取って代わろうとした結果であるという趣を持っています。神を放逐した人間的な偉業は,一方ではとんでもない愚行に直結する性格を,元々はらんでいました。
人間がそのまま神になってしまうのは,必ずしも珍しいことではありません。現人神,天子などはそういう趣きを持っていますし,独裁者は,「朕は国家なり」という言葉で代表されるように,それに類する者といえるでしょう。神に匹敵する力を持っていると,事実上意識している人間は,恐ろしい存在です。傲慢は常に罪ですが,その中でも特別な罪だと思います。独裁者とはいえなくても,強力な武力を持つ国の最高権力者が,自分に敵対的な国に実質的な侵略戦争をしかけるのは,文字通り神を恐れぬ所業です。たった一人の人間を殺すのさえ大それたことです。侵略戦争という大量殺戮行為をしかけることができる人間が,どうして存在し得るのでしょう。彼は正義という光り輝く名分を求めて,殺戮者の黒い凶悪な精神を覆い隠そうとします。その程度には,狡猾ながら恐れを知っているといえるのかもしれません。そして彼が最高権力者であるがために,それはほとんど必ず成功し,国民によって支持されるという体裁が出来上がるのです。人間が人間を殺戮してよい理由は,どんな人間も持っていません。それは,いついかなるときでも憚られることです。それを,堂々と遂行する権利を主張できる者は,もはや人間ではありません。彼はある意味で神になってしまっているのです。そして国民はそれを承認するのです。侵略戦争を仕掛けようとして国民の反発にあい,思いとどまった例は,歴史上のどこにもないのではないでしょうか。
人間は一切のものの最上位者ではあり得ません。そんなことは自明だと思います。人間より上位にあるもの,それは自我の力の及ばないものです。そういうものは経験的にいくらでも存在していることで,こと改めて証明してみせるなどということは必要もないことです。自我の力の及ばない超越的な存在を神と呼ぶかどうかは,あまり問題ではありません。さまざまな信仰が活発に生きている時代では,神と呼んだ歴史的過程はあるのでしょう。そして実態のあいまいな,非科学的なその種のことを,ことごとく剥ぎ取って来た歴史的過程もあるのでしょう。
宇宙の無限は存在するというのとおなじ次元で,神が,意識にとって外的に存在するとはいえません。しかし信仰というものは,人間があるところいたるところに存在してきました。科学万能の現代でも例外ではありません。現代では現代の信仰である科学的な風潮のおかげで,信仰の形態は随分いびつになることもあるようです。極端になるとカルト的,反社会的という性格を持つものもあると思います。しかしどんなにいびつなものに見えようと,それらの集団がなくなることは考え難いことです。それは奇怪な心の持ち主がたくさん居るということを証明するものでしょうか。しかし,彼らにいわせれば,逆に,現代社会こそが歪んでいるというに違いありません。それら両者の関係は,自我と無意識のそれに似通っているようでもあります。つまり時代を主導する自然科学的なものの見方を自我とみなせば,カルト的な宗教団体は無意識に相当します。自我が歪めば,相対的に無意識も歪んで,悪しき様相を帯びるものです。それらは相対的で,相互に関連し合うのです。
現代の大問題は心の砂漠化が進んでいることです。その影響は思春期にある者たちに,特に先鋭に表われていると思われます。彼らの心を支える精神的な拠り所が不在なのです。そういうものは思春期にあるものには,特に必要です。親離れがはじまる年頃になって,飛び立てない子たち,逆に早々と親に見切りをつけてしまった子たちの姿が,精神医療を求める子供たち,あるいは親たちの様子から,現代的な様相としてうかがえるようです。
とりわけ早々と親に見切りをつけ,精神の漂流を始めてしまっている子供たちは,世の大人達を右往左往させる悪のにおいのする行為に快感を覚えるようになるようです。彼らには親たちは,単に”うざったい”存在でしかなく,その許を離れることの恐れよりは,解放される心地よさの方に魅かれるのかもしれません。子供に見切りをつけられそうになっても,親自身が自分が畏れを持って助力をあおぐような心の上位者を持たないのです。
自由というものは魅力的なものです。そして大いに不安なものです。真に自由を享受するためには,高度な精神性が必要です。早々と精神の漂流を始めた者は,自由を求めたつもりかもしれませんが,この意味で自由の享受者とは到底いえません。畏れるに値しない上位者の束縛が意味を持たないので,その絆を破ることに,ためらいや罪悪感を持てなかったというのはありそうなことです。将来が不安でないかといえば,大いに不安なのだと思います。しかしその不安をなにかによって繋ぎ止められる不自由に敵意を持つ者が,束縛を破って漂流を始めるのだと思います。それは親子関係の反映という側面はあるでしょうが,時代そのものが精神的な支柱を持っていないことが,更に大きな理由になっていると思います。精神的に満たされることの少なかった子供時代を経験すると,拠って立つ心の基盤を,人的なものを含めて社会的な資産に求めることが難しく,自分自身の幼い心に求めるしかなくなる場合も珍しくはないでしょう。頼りにするのは自分だけ,自分の気分だけということになるのではないでしょうか。自由とは似て非なる身勝手な行動に走って何がいけないのか,気分に従って行動しようとする者たちには,答えを知りたいとさえ思わないかもしれません。
生きたいように生きて何が悪いかのという反問になんと答えればいいのでしょう。極端になれば,人を殺してなにが悪いのかということにもなりかねません。彼らを納得させるような答えは,さしあたりは難しいように思います。彼らの自我は既に自由を失っているように思われるからです。自我が健全でなければ(健全な自我は,必ず無意識の力に対して一定の自由を保持しています),無意識の勢力は反社会的な,あるいは非社会的な色合いを活発化させます。もともと無意識は社会的な存在ではありません。自我がその役割を担っているので,自我が無意識を指導的に従える必要があるのです。自我を騎手に,無意識を馬に例えてみると,人間にとってのこの馬は全てを見通す叡智を持っていますが,人生という障害物レースを戦うにあたっては,一切を自我に委ね,沈黙したまま,しかし一切を知り,一切を見抜きながら,自我の指揮ぶりを見ているのです。騎手が自分の役割に責任を持って,目の前の障害物にどう対処するべきかを機敏に判断するとき,馬は騎手を評価して,それに従って行動するエネルギーの源泉となります。しかし指揮を取る騎手の能力が不満足なものでしかなければ,馬は騎手のために働く気にはならないでしょう。いわば騎手を見捨てるのです。その代わりに,評価するに値しない騎手に対して,社会的な存在として滅亡するのをお構いなしに,あれやこれやの気分的な満足を与えようとします。それは既に悪の彩のある動きなのです。社会的な存在として,いわばやる気をなくし,無責任化した自我に相応して,無意識は悪のたくらみをはじめ,滅びの誘いを始めるように思われます。自我はそういう無意識に盲従してしまうのです。そうなると自我は自由と主体性を失い,事の是非を判断するのが難しくなるのです。 心の砂漠化が進行して,精神の漂流を始めてしまった者たちも,時代の被害者です。彼らに,彼らが生きてきた社会の規範的な価値意識を説いても,それによって犠牲を強いられてきたと感じているだろう彼らは耳を貸そうとしないでしょうが,彼らも何かを求めてはいるのです。そういう彼らに,たとえばカルト集団が一つの答えを出しているということは,大いにありそうに思います。
人が生き生きと人であるためには,精神的な拠り所が不可欠です。自我は無意識によって成り立ちます。自我の機能が及び得ないものが自我の上位者である資格を持ち,自我に力をもたらす源泉である理由を持ち得ます。その上位者が無意識の世界であり,自我との有機的連関があって心が存在するのです。 自我が一切の理由であるとするのは,根拠を持たない張りぼてを不当に高く評価するようなものです。自我への信仰が時代の主調となり,自然科学が一世を風靡しました。それが物質文明の隆盛をもたらし,そして一方では,おそるべき心の貧困,心の病気,犯罪を招き寄せてきたといわなければなりません。
人間が自我の能力を絶対的に超越しているものの存在を認めることは,好みの問題ではありません。人間が置かれている心の様態を素朴に捉えるかぎり,それ以外に選択の余地がないといえます。それを考えると,自我にとっての超越的なものを現代において捉えることは不可能であるとは思えません。
これらの自我の能力を超えたものについて,人間がその存在様態を知ることは不可能です。しかし存在自体は,自我に直感として訴えかけるなにものかという形で,察知できますし,認めないわけにはいきません。
その存在は自我には所属しません。自我を超えたなにものかであるそれは,無意識界,それも絶対的な境界を超えた領域にあるもの,ユングのいう集合的無意識の世界に存在すると考えるしかありません。この領域は自我の上位にあります。自我は自我の支配し得ない上位のものに依存しつつ存在可能なのです。人間の意識活動が存在するためには,無意識の存在を前提とするといえると思います。
自然科学は,その対象となるものを,完璧に人間の能力のコントロールの下に置こうとする志向性を持ちます。
自我は社会的な存在としての人間の心の中核の位置にある組織体ですが,先にも述べたように,自我の主要な機能の一つは論理性です。その骨子となる因果律を,最も洗練された形で方法化されたのが自然科学です。
自然科学においては,対象となっているものに隈なく光を当てるように自我が機能し,意識が操作されます。そのようにして,対象をまったくの自我の支配下に置く試みが純粋化された学問が自然科学です。ここでは対象を見つめている主観が問題にされることはありません。たとえば感染症のように,原因菌と病症との因果律が明快であるときは,主観性を排除した観点は有効であり,なんら問題はないように見えます。これは鍵と鍵穴の関係,機械の修理の問題といえるでしょう。
しかし,感染症の征服は可能かといえば,そうはいかないようです。原因菌やウイルスは姿を変え,抵抗力を高め,改めて人間を攻撃する力をとめどなく蓄えているようです。新手の感染症が続出するのは,どうやら人間が自然の生態系を破壊したことにもよるようです。自然との調和を無視して,人知が自然に破壊的な手を加えると,自然の側からの手ごわい反撃を覚悟しなければならないように思われます。そういうことを考え合わせると,一見すると単純な感染症の問題も,人間と自然との調和,ないしは闘いの様相があり,この戦いに人類が究極的に勝利する可能性はないように思われます。そう考えると感染症の問題も,単に原因菌を確定するという自然科学的営為に,なにか重大な問題が残されていると考えなければならないようです。たとえば森林破壊が新たな感染症を招き寄せたということがあるのなら,感染症対策はしかるべき抗菌剤の開発だけでは解決しないでしょう。むしろ自然との調和を問題にするほうが,より根本的な解決策になるのではないでしょうか。輝かしい自然科学の勝利は,個々の感染症を征服したという限定的なものにとどまっているといわなければなりません。
ましてや精神疾患となると,更に問題は複雑です。E・クレペリンは,現代でいう統合失調症を分類整備した人ですが,厳密な現象学的姿勢で,観察者の立場の偏見を慎重に排除したはずでした。ところが彼が観察した精神病者たちは,劣悪な環境に長期的に入院していた人たちで,それは大いに人為的な影響を受けた病像であり,病気の自然な姿ではなかったといわれています。こうなると病気あるいは病人というものは,見る立場の主観を排除して観察し,実態を把握することは不可能になります。このことを考慮に入れないと,クレペリン自身が陥ったように,「精神疾患は,観察する立場の反映から独立したなんらかの純粋に客観的な疾病プロセスに起因する」という科学的な偏見を生む出すことになります。それは「精神疾患は脳の病気である」ということにほかならず,病を病む者という自然な現実に対して,本来は仮説であるべきものが,いつのまにか科学的な真実となってその上位に据えられることになるのです。科学が自然現象の上位に位置するのは本末転倒であり,危険な事態です。
たとえば原子爆弾には自然科学の功罪が示されています。
核爆弾の親物質である天然ウランは,地球上に広範囲に見られるものです。それらは分子的に安定しており,そのままではエネルギー源にはなりません。そこに膨大なエネルギーがはらまれているのを発見したのは科学者です。それを純粋化し,巨大なエネルギーを取り出す手続きを発見したのも科学者です。これは科学者としては胸を躍らせるような発見だったに違いありません。ここまで来れば,そのエネルギーが類を見ない巨大兵器の開発に行き着くのは時間の問題です。当時,アメリカを中心とした科学者たちは,ナチスドイツがこの兵器を開発しつつあるということで,それに先んじようと力を合わせたのです。これを作り出した科学者の能力は,大きな戦争の渦中にあった当時としては,大いに賞賛される事情があったといえます。兵器として類を見ないものを完成させるという行為は,携わった科学者を興奮させたに違いありません。
兵器が完成された段階で,その使用が検討された相手国は日本でした。そのころ日本国は,既に戦争の相手としては恐れるに値しなくなっていました。この新型兵器を使用する意味を知っていた多くの科学者が,熱心に反対運動を展開しましたが,抑止する力にはなりませんでした。
自然界にある石油を採掘してエネルギー源とするのと,天然ウランから純粋ウランを取り出してエネルギー源とするのと,どこが違うのでしょう。それは単にエネルギーとしての規模の違いなのでしょうか?
石油タンクが燃え始めたとしても,問題とされるのは責任者の不注意です。それらタンクが存在すること自体に疑問を持ち,反対する人はあまりいないでしょう。しかし原子力施設で故障が起きると,人は単に責任者の不注意に対してにとどまらず,そういうものが存在していること自体に素朴に疑問を覚えるのではないでしょうか。
両者の違いはどこにあるのでしょうか。原子力の場合は,どこか禁断の火といった趣があるということかもしれません。天然ウランは,そのままにしておけばおとなしく人間と共存しているが,それに人間が手を加えたばかりに,人間の手に負えない性情がむき出しになるという恐れが人にはないでしょうか。
科学者の好奇心は,天然ウランから巨大なエネルギーを取り出せるかもしれないという見込みが立てば,どうしてもその可能性を確かめたくなるでしょう。こうした知的好奇心は,科学者であればなくてはならないものでしょう。しかし人間としての立場を離れて,純粋に科学者であることはできません。それはどうしても一体のものです。
この研究に危険なものを感じて,消極的な姿勢に終始した科学者は,むしろ大勢いたようです。そうすると時代の風にも影響されたとはいえ,積極的な姿勢を貫いた科学者たちは,人間としてやはり特殊な人たちだったといえるのかもしれません。 破壊や暴力は人間の悪に由来するものです。人間であれば,誰にでもこういう性情はあると考えなければなりません。人を分けるのは,この種の悪を悪として退ける精神が確かであるか,悪と認めつつも,無意識の領域に巣食うこの勢力に密かに魅かれているかの違いではないでしょうか。一介の庶民であれば,悪をなすことへの恐れに敏感です。そうでなければ自分自身が危険な状況に置かれることになるからです。しかし権力者になればなるほど,こうした恐れを持たなくなるようです。彼らにつきものの支配欲求が,彼らを高い立場に押し上げるためではないでしょうか。自我肥大を起こすと,人は必ず傲慢になります。自分が一切の価値の中心になります。正義は常に自分にあり,敵対者は不埒な者として退けられるのが当然になります。人間は権力に近づくことにより,ほとんど必ず悪に傾くといっても過言ではないように思います。
人間のこうした悪魔性と関連するのが,原子力の兵器への応用です。そういう魔力をこのエネルギー源は秘めているように思います。そのにおいがあるからこそ,人は原子力発電に,特別な危険を感じるのではないでしょうか。しかし本当は人が密かに恐れるのは,原子のエネルギーを含んだ物質へというよりは,むしろ人間の持つ悪の影に対してではないでしょうか。
実際に核兵器の研究開発に携わった科学者は,光に満たされた兵器が完成に向かうにつれ,彼らの心もまた光に満ちたことでしょう。対象に関わっている科学者の心から,影の領域に属するものが排除されなければ,仕事を進めるのは困難だと思います。兵器を使用する側は敵国を殲滅させる覚悟です。相手国は悪なる影の集団という意識が働かなければできない覚悟です。そして使用する側は,対照的に正義の見方,光につつまれた恥じることのない集団という意識にならないわけにはいかないと思います。巨大殺戮兵器で勝利する側の意識は,光につつまれていることでしょう。攻撃をする側は,攻撃を正当化するために,心から影を排除しなければならないだろうからです。そして攻撃される側は,この切り離された影によって殲滅されようとするのです。しかしいうまでもなく,攻撃をする側もされる側も,等しくおなじ人間です。一人の人間の心とおなじように,一つの国という単位にも光と影との二つの領域があります。二つの国のあいだで光と影の分離と対立が際立ったときに,戦争が避けられなくなるのです。
このように自然科学は一方で物質文明の隆盛をもたらし,他方で人類に被害をもたらす可能性を持っています。人間の心には光と影との両面があり,影の領域への敬意を忘れると,自然科学者はおのれの分をわきまえない傲慢さを露呈することになるでしょう。言葉を換えると,自然への畏敬の念を失ったときに,人類は危険な挑戦を始めていると考えなければならないと思います。
自然は,本来,人間が自由に扱えるものではあり得ません。心についても同様です。それらのことはいうまでもないことですが,換言すると自然や心は,意識の光が届かない影の領域を持っているということです。意識は対象を捉える人間的な武器で,人間の偉大な力を示しますが,とうてい手には負えないものがあります。
その意識にとっての越え難い存在は,心の外側と内側とに存在します。意識の領域は先にも述べたように,人間の知性的な理解が可能な範疇にあるので,当然有限の世界です。これに対して影の領域にあるものは無限の世界です。光の世界のものである意識は,その世界についてはすべてにわたって操作することが,原則的に可能です。しかし意識が存在する理由については,自我に与えられている能力の範疇を越えており,知ることができません。言葉を換えると,意識はその存在の根拠をそれ自体の内に持っていず,自己完結的な存在ではありません。 そのことは,自我はその基盤を,自我ではないもの,つまり無意識の世界に拠っているということを意味します。
人間の意識活動は,その能力を超越した無意識的な心の存在を前提として,はじめて理解可能になるのです。
無意識の世界は,自我の拠り所ですが,自我に与えられている能力ではうかがい知れない超越的上位者です。従ってそれは,まるごと認め,受け入れる以外にはなく,自我に固有の能力である疑いの眼を向ける余地がない存在です。これが,人間があくまでも謙遜でなければならない根本理由です。ですから謙遜であることは,人間に対する根源的な要請であると,私は思います。卑屈は精神の堕落ですが,謙遜は精神の崇高な姿です。このことの実践は,いうまでもなく容易いことではまったくありません。人は力を持てば,謙遜どころか,むしろ傲慢になりがちです。力を失えば,卑屈になり,狡猾になり,妬み,恨みの虜になります。いずれにしてもそれらは精神の堕落した姿です。
人が心の救済を真に求めたければ,唯一の可能性は謙遜に徹することでしょうが,これを人に勧めること自体が傲慢の謗りを免れないでしょう。人類の中でも類まれな人だけが,そういう精神を求めて自分を厳しく律することにより,可能的な彼方が眼差されるということなのでしょうから。
それを考えると,多くの心の病も,また,謙遜の精神からの転落という側面があるのは確かでしょう。
それらの意味で,人間には大きなものがあるといえると思います。そこへの道を妨げるのは実に人間自身です。この大きなものの前では,この人間自身は,実に矮小です。そして,この人間自身の中で人は迷子になるのです。それを脱して大きなものへ近づくには,心の,ある澄んだものが必要なようです。
このような自我と無意識の関係は,信仰を持つ人と神の関係とほとんど区別がつけ難いと思います。ただし前者の場合は,経験的な事実の上に立って自然に見えてくることなので,信仰ではありません。自我の超越的上位者の存在は,その実相を知ることは不可能とはいえ,ほとんど事実問題です。そして,また,信仰という人類に根深い問題も,それぞれの心の内部に,このような超越的上位者が存在するために成立することができるのです。人がしばしば思うように,信仰が馬鹿げた空疎なものへの胡散臭い信奉というのは,人間の心の実態に即して公平な見方ではないと思います。
自我の超越的上位者の存在は事実問題といえると思いますが,それは,はるか遠くに望見される形態の不確かな山のようなものと例えていえるでしょうか。幻にも似て形状が不確かとはいえ,幻が人間が作り出した幻影であるのに対して,このものは人間の存在に関わる一切の根拠であり,死と共に消滅するという意味で人間の存在に関わる一切の現象という幻影を作り出しているものです。この不確かな形状のものを確かめるために,もっと近づいて観察しようとしても近づくことは不可能です。幻は不意に消滅しますが,このものは決して消滅することはありません。従って,このものの存在は事実問題であるとはいえ,超人間的な世界のことなので,あくまでも自我を拠り所とする人間的な推理,解釈をすればという前提があってのことになると思います。人間的な世界は,完全に意識と共に存在します。睡眠によって自我の活動が休止したときに,人は意識と共に人としての存在を休止させます。休止しているあいだは無と区別がつけ難く,死と区別がつけ難いといえます。そして再び覚醒したときに,再び意識活動が開始され,自分が昨日までの自分と連続したものであることに疑いを持ちません。意識を中断させ,それはしかし死ではなく,意識の休止である,一つの人格としては一連のものであり,統合されたものであるという安心保証は,意識に拠るものではなく,従って無意識に拠るものです。
意識が捉えた様相が人間的な世界の一切です。従って人間的な世界は,終始,現象として存在します。その存在は意識の消滅と共に消滅するのですが,睡眠あるいは意識障害という意識の休止(意識が直接は捉えられない世界への陥没),それらをも含み一個の人格の存在を保証しているものは,無意識の世界以外には考えられません。それは同時に,現象として存在する人間的な世界に秩序を与えているものでもあります。 このように,現象として存在する人間的な世界に秩序をもたらしていると想定される超越的上位者を,内在する主体と呼んでおきたいと思います。
Fさんは企業人の妻です。夫が某国の支店に駐在することになり,Fさんのその国での生活がはじまりました。Fさんは夫人達の親睦会の人々が開いてくれた歓迎会に招かれ,会の一員となりました。しばらく経って,すっかり信じていた何人かの人たちが,いつのまにか誹謗,中傷の噂を撒き散らしていることに気がつきました。Fさんばかりでなく,夫もおなじような噂にさらされました。そういう目にあう人は他にもいて,嫉妬がからんだ独特の陰湿なものがあったようです。
Fさんは気が弱い人ではありませんが,人と対立的にならないように気を使う抑制的な性格です。反撃や詰問をせずに黙って耐えているうちに,激しい動悸,呼吸困難の発作に悩まされるようになりました。日本に帰国してからも,それらの症状はつづき,受診しました。
受診後,それら症状的なものは速やかに収まりましたが,しばしば当時の生活が夢に出ます。常に悪夢です。外国での外傷体験がいかに深刻なものであったかがうかがわれますが,単に当時のことが夢の上で再現されているだけではないらしいということに,Fさんもしだいに気がつくようになりました。外傷となった体験は隅々まで想起可能なのです。ということは自我はそれらの体験のあらかたは受け止めることができているので,それらが悪夢となって自我をおびやかす要因にはならないと考えていいのです。Fさんを悩ませている悪夢の内容は某国での体験なのですが,悪夢という形でFさんの自我をおびやかしているのは,自我がまだ気がつかずにいるなんらかの問題が無意識界に横たわり,解決を迫っていると考えていいと思います。ですからそれらの夢の内容は,某国の体験そのものではなく,それに関連する,より根深いものの所在を暗示しているのです。自我がそれを捉えることに成功すれば,夢の役割は果たされることになります。自我にとって受け止め難かったものを受け止める力を得たのですから,端的に自我のキャパシティが大きくなったことを意味します。それは一応の解決が図られたことになります。そういうことを前提にして考えると,某国の体験が繰り返し夢に現れる理由は,それらの体験そのものではないことになるのです。事実Fさんが母親との関係その他について,夢が何を伝えようとしているのか,芋ずる式に推理を重ねていくにつれ,悪夢は消失しました。それはそれらの推理が,大筋で的を射ていたことを意味すると考えていいと思います。
気分がよい日がつづいているある日,Fさんは封印していたCDを取り出しました。それは,その某国の英雄的な作曲家の名前を冠したコンクールの決勝の演奏を収録したものでした。Fさん自身や誹謗,中傷の噂を撒き散らした夫人たちも,コンサート会場にいました。国民的な英雄である作曲家のその曲は,町中にいつも流されているものでもありました。Fさんは当時を思い出したくないので,曲を聴かないようにしていたのです。 演奏が始まる前に拍手の音が鳴り響きます。自分のもあれば,許し難い仕打ちをしていた者達のものも混じっているはずです。演奏を聴いているうちに,動悸とともに全身から汗が吹き出してきました。Fさんは,問題の根の深さに暗然となりました。
外界からの,あるいは無意識界からの刺激を受け止め,それに対応するのが自我の機能です。
Fさんの自我は,某国での生活の証である音楽を聴くことに耐えられなかったのです。その理由は,一つにはいうまでもなく外傷体験によるものです。しかし先にも述べたことですが,Fさんはその体験の隅々までを把握しているのです。それは過ぎ去ったことでいまさら仕方がないことでもあります。Fさんもそう思っています。自我としてはそれに関しては隠し持つ何物もないはずなので,Fさんを震撼させるほどの大きな理由になるとは考え難いことです。どうしても他に理由があるはずです。なぜ自我が凍りついてしまうほどのことが起こったのかが問題です。それは自我がまだ知らないでいる体験群があることを示しています。それらはできれば知りたくない理由があり,従来は意識の地下に封印することで問題がなかったのですが,いまや件の外傷的体験によって一撃され,活性化されてしまったのです。外傷体験に何らかの意味で連関するような性格を持っているそれらの体験群は,いまとなっては自我が知らないふりをして済ませることを許さないほど活力を帯びてしまっているのです。
Fさんは聡明な人で,果敢な精神の持ち主でもあったので,以上のような意味合いを理解し,臆せずに自分に立ち向かっていきました。そうすることで,彼女を苦しめ,脅かしているものをむしろ手がかりにすることができたのです。つまり自我に圧力を加えてきていたものに対して,立ち往生することがなく,いわば心の扉を開くことができたのです。それに伴って意識の地下に封じ込めることに費やしていたエネルギーを回収することに成功したのです。それは自我の勝利です。同時にFさんの人間としての成長を意味するものです。
このように述べると簡単なことのように思えるかもしれませんが,自我が抑圧していたものの存在は,自我にとって脅威の素なのです。いわば自分を犠牲にして,自分以外の誰か(親といってもいいでしょう)との関係を重視したといういきさつがあるはずなので,いわば人生を左右するほどの無意識的な選択だったといえるだろうからです。比喩的にいえば,自分の国を守るために,強い隣国に助けを求め,その代償に主権をそれなりに放棄してしまっていたものを,今になって取り戻そうとするようなものです。当然,隣国は,少なくても主観的には恐ろしい存在なのです。
Fさんの恐慌発作に伴って明らかになったのは,一見すると原因となっているように思われる外傷的な体験が,実は根本的な要因ではなく,きっかけになっているに過ぎないということです。むしろ容易には把握し難い意識の深部に潜む問題があり,それは直接のきっかけをなした出来事と心的に関連する一連の過去の体験群であると考えられるのです。それらは,自我によって負の烙印を押され,受容するのを拒まれたものたちです。その結果,無意識下の負の集積場に蓄えられ,平生はその存在が忘れられているという性格のものです。それだけに,怒りや怨念の感情を伴い,自我をおびやかす潜在的な勢力となっているのです。またいつかは自我に認められたいと願ってもいるのです。このようにいうと,いわば隠し子のような趣がありますが,実際それに類似することが無意識の世界で起こっているのです。。
このような無意識的な自我の選択的抑圧は,多かれ少なかれ誰にでも起こることです。否,むしろ起こらないわけにはいかないというべきでしょう。人は他人との関係で生きることが,人間が人間であることの条件となっているからです。他者の中でも,特に両親との関係が人間関係の基本です。そういうことがあり,抑圧は一般に他者との関係を重視し,その分,自己犠牲を強いるという意味合いがあるといえるでしょう。社会的な存在を免れるわけにはいかないのが人間ですから,良くも悪くも抑圧は人間に必須の心的機能です。
自我が十分に強力になっていれば,抑圧は,いわば自我の責任において自我の価値規範に反するという心的形態の下に起こります。それは自己にとってなんら問題はないといえるでしょう。問題が生じるのは,自我が十分には強くないときです。それは相対的に他者への恐れが強いことの反映といえるでしょう。そのために人格形成の上で好ましくはない選択を無意識的にしてしまうのです。いわば他人に気兼ねして自己を抑圧してしまいがちになるのです。 抑圧されるのはその都度の個々の体験ですが,それは単なる記憶の封入というレベルを超えて,臆病になっている自我(他人との関係で)が受け入れるのを拒否している一連のものであり,一定の傾向の自己を自我が受け入れるのを拒否しているのと等しくなります。
自我(ここで問題になっているのは,他人に気兼ねをして,選択的に抑圧する自我)が受け入れている自己を表のそれと考えると,受け入れを拒まれているそれらは,裏の(あるいは影の)自己ということになりなります。ですからそれらは,自分の分身ともいえるものです。それら分身は,自我によって認知を拒まれ,意識の地下牢に幽閉されている弟(妹)分ともいえるのです。
これは比喩的な表現を超えて,現実の事実問題といえるほどのことです。いわゆる多重人格という病的な現象がありますが,これは人格の分裂を意味しており,無意識下に別様の人格が潜んでいることを示しています。そのような病的な現象にとどまらず,そもそも人格というものは,強固に統一されたものではなく,いわば複合的な諸人格が統合された姿といっていいでしょう。いわゆる自我といわれているものは,それらの中の公的な人格の形態といえるでしょう。人格とはそういう性格のものなので,時によっては,自分がばらばらに砕けそうだという恐怖を持つこともあるのです。
このような事情の下にあるのが人間といえますので,自我がほどほどに強固であり,健全であることは大変重要です。そうでなければ,場合によっては病的な自己に陥る危険も出てきます。
人生には何度も節目となる出来事がありますが,そのときに自我の強さが試されます。自我が問題を克服していかなければ,更に自我の衰弱を招くことになります。それらの問題が解決されずに長く放置されていると,いつか自我が機能不全に陥りかねません。あえて病的といえないまでも,生きる目標を見失い,活力を失ってしまうことになるかもしれません。
自我が受容できないものがあるということが,そもそも自我の脆弱なところです。つきつけられた問題には,自我は何らかの解答を出さなければなりません。たとえそれが自分の手には負えないというのが解答であるとしても,そこに客観的な根拠があれば立派な解答です。しかし自我が然るべき態度を取れず,問題を回避しつづけていると,そういう自我に業を煮やし,意識の地下牢に幽閉されていた分身たちが力を蓄えはじめる危険があります。自我は生きるという方向性を担っていますが,生きることの対極にある死への方向性を担った破壊的な力が無意識界に潜在しています。人の心には一般に対立する二極があるのです。自我が衰弱すると,この力が活性化し,意識の地下で日の目を見る機会を奪われつづけている分身たちと結託する危険があるのです。いわば母屋を乗っ取り,自我を傀儡化しようとする動きが出て来ることになるのです。そうなると,いうならば自我の根っ子が腐り始めたようなもので,人間として,人格として問題が生じてきます。具体的には無気力になったり,卑屈になったり,さまざまですが,場合によっては目先のことには抜け目がなく,狡猾になったりもするかもしれません。いずれにしても,自我が無意識との相対的な関係で指導力を発揮できず,持てる力を極めて不十分にしか活用できていないという心的状況に陥ります。基本的に能力がないというのではなく,持っている力がありながら宝の持ち腐れ状態になってしまうのです。こうなると将来について,なんの希望も持てなくなってしまいます。そして指導力に不満を募らせた無意識の諸勢力が跳梁し始めるのです。
これらの意識の地下にある勢力は,比喩的にいえば,人里離れたところにある不気味で,近づくのがためらわれるような雰囲気を持つ沼に潜む魑魅魍魎という趣があります。そういう意味を込めて,意識下に収束されている負の意味を帯びた体験群の棲息する様相を,私は個人的に”心の沼”と呼んでみています。
”心の沼”と私が呼んでいるのは,自我にとっての弁慶の泣き所のようなものです。それはおそらくは生まれて間もないころの人生の最早期に端を発していると思います。つまりおそらくは母子の関係で恐怖する何らかの体験があり,それが核となっていると想像されます。そういうことは単なる想像ではなく,児童心理の研究者の蓄積や,日常の臨床からうかがわれるものです。直接確かめることはできないけれど,そのように考えないと理解が難しいということです。そうしたものが核となって,そのことに近似する新たな体験をすると,幼い自我は受け止める力を持てないのです。それは改めて無意識の領域に抑圧されることになると思います。人生の道程でその種のことが繰り返されて,無意識下で一つの勢力となります。
それら一連の体験に関しては,自我は機能できず,いつまでも未熟なままでいるしかなくなります。この”沼”の存在と,相対的に脆弱な自我との関係が,外傷体験といわれるものを生じ易くさせる素地となります。
自我は固有の問題に弱点を持っています。もともとその種の問題は,意識が回避的な態度を取ってきたものです。自我は責任を回避しつづけてきたそれらの問題をつきつけられると,臆病に立ちすくんでしまうのです。そういういきさつがあるので,自己の回復をはかるためには,無意識の領域にある”沼”に立ち向かう勇気を必要としているのですが,自我としてはそもそも気が重い課題なのです。いわゆる抵抗といわれる形で,自我が自分の作業を妨害するという一見不可解なことが起こる所以でもあります。
しかしながら,そういうことではあっても自我の役目は,心の内側と外側の問題を捉えて受け止め,自己に取り込み,新たな統合を図るということです。困難であっても本来あるべき自分でありたいと考えれば,勇気を出して立ち向かっていくしかありません。
自我は,人間が社会的な存在として生きることに関わる中枢的な機能を担っています。しかしこのような作業が円滑に行われているのか,見当違いのことをしているのか,それを決める基準は自我自身にはありません。なにかの問題に直面して,それを解決して充足感を味わったり,逆に自分の無力に悩んだり,落ち込んだりするのは,自我が拠り所としている何かがあることを間接的に証明しています。それは無意識以外にはあり得ないことでもあり,この領域にある自我の拠り所を内在する主体と呼ぶことが許されるのではないかと思います。
母親の胎内で卵子と精子とが合体し,人間の身体の諸器官が形作られていく過程の胎生期にあっては,意識と自我の機能はまだ開始されていず,活動への準備期間にあります。その時代は自然と一体の人間以前の特別な生命体として存在しています。人間存在へと向けた生命の始まりと成長は,自然のプロセスの中にあります。そこにどういう意志が働いているのか,人間の知恵のおよぶところではありません。しかし我々人間には永遠に解明不能であるにしても,現にしかじかの特徴を持った驚嘆に値する合理的な機能を備えた身体と精神とが存在しているのは,厳然とした事実です。そこに何らかの意志が働いたと考え,それを自然の摂理と呼ぶのは,不当とはいえないでしょう。
複雑極まりなく,かつ精妙な身体と精神を持ち,しかし存在する目的と理由を明らかにされていない人間は,自然の摂理とでも呼ぶ以外にないものによって存在していると考えるしかありません。人間は自然から乖離される形で存在を得,いずれ自然の懐に帰還するのです。
自然の中にあり,自然をつかさどり,運行するものの意志によって統率されていると考えるしかない人間が,自らの内部にその意志がこめられている具体的な領域は,無意識のそれです。この領域に現われている自然を統率する意志を,特に内在する主体と呼んで区別したいと思います。そのように呼ぶことによって,精神のさまざまな病理現象について理解を深めることができ,かつ治療上の重要な手がかりが得られるのです。
会社の人間関係などの重圧に負けてうつ病を発症し,休職している30代の男性Hさんの例です。Hさんの目は専ら会社に向けられており,家族,両親との関係で問題を深めるのが難しい経過がありました。
会社への拒否感が強く,転職も考えますが,それも具体的には進展しません。そういうことを考えると不安になり,抑うつ感が深まるのです。いたずらに休職期間が長引いてしまっていました。
あるとき他人との関係は重要だが,それ以上に自分自身との関係が重要だという話をしました。
その内容は以下のようです。 他人から見離されるのも辛いものだが,自分自身に見離されると,比較にならないほど深刻な事態になる。心にとっての生命の拠り所は,他者をはじめとした外的な状況にではなく,それぞれの自分自身の内部にある。つまり無意識の世界に心が拠り所としているものがあると考えていいと思う。それとの関係が断絶すると人生は地獄になる。例えば小学生が3人のいじめっ子の標的にされていると仮定して,その子が不登校になるときは,その子自身が4番目のいじめっ子になるときである。そのように自分で自分を攻撃し,見離したときに問題は決定的になる。本当は自分を助ける考えを探し出さなければならない肝心のときに,逆に自分を見捨てるようなことをすると,役にも立たない他人であるいじめっ子に心を寄せ,何よりも頼りとするべきである自分自身の中にある拠り所をないがしろにすることになる。それは自分から求めてその重要な関係を断ってしまうのと同然である。
そのようなことにならないための方法は,気分まかせの生活ではなく,頭を使って考えること,つまり判断することである。たとえば無気力感から横になるとしても,気分まかせでそうするのはよくない。それが必要なことか,考えて判断をしてそうするべきである。結果としてはおなじことでも,前者と後者とでは全く違う。判断をすれば自我が仕事をしたことになる。その判断が不適切なこともあるだろう。しかし自分が考えてしたことであれば,責任を取ることができる。それを生かすことができる。なによりも自分のためになるように,自我が仕事をする姿勢が大切である。そういうふうに自分の問題に責任を持って生活することが継続されれば,無意識的に拠り所としているはずのものに接触し,支持を受けることが出来てくるだろう。
そういう話をしましたが,聞いているHさんの様子に手ごたえのようなものを感じました。その後,彼はどこか腰の座った人に見えるようになり,目に見えて頼もしげな雰囲気に変わっていきました。会社のことも前向きに考えはじめるようになりました。ともかくも復帰しよう,その上で転職するかを検討したいといい,同僚から会社のよからぬ情報をもらっても動揺しなくなりました。
内在する主体は,無意識の領域にある人知を超えた存在です。たとえば発見,発明,創作などのインスピレーションはここから発せられる叡智です。夢を通じてベンゼン核が発見されたという逸話は有名ですが,行き詰まりを感じて悩んでいるとき,不意にアイデアがひらめいて解決してしまうという経験はだれもがすると思います。そういうときの一気にみなぎる力も,主体の叡智と接触したためと考えられます。いわゆる火事場の馬鹿力,危急時にみなぎる力もおなじです。夢には補償作用があるといわれていますが,意識の偏った志向性を本来あるべき方向に導こうとするのも,ここに由来していると考えられます。この内在する主体は,表には顔を出さないものの,意識がする仕事を黙って見つめているもののようです。
我々は,自分のことは自分が一番よく知っているなどといいますが,それはちょっとあやしいと思います。自分や他人を意識的にか無意識的にか,しばしば騙し,欺くのが人間です。しかし内在する主体だけは,絶対に騙せません。
他人との関係は大変重要です。両親,配偶者,親友など,大切な人と良好な関係にあるか否かで,人生そのものが大きく変わるといっても過言ではないでしょう。ですから精神医学は,対人関係を大変重要なものと考えています。
しかしながら,他人との関係以上に重要で,難しくもあるのが,自分との関係なのです。言葉を変えれば,主体との関係です。
内在する主体は,無意識界にある特別な超越的な独立体というようなものではないと思います。人間は自然から乖離,独立した特別の存在といえるかもしれませんが,自然の一部を構成しているものでもあります。
人間がこのような身体,このような心として存在しているのは,いかなる意志によってであるのか不可知です。隈なく身体や心を調べても,その謎を解くのは不可能です。そのような形で自然の摂理が働いているとしかいいようがありません。我々はそういう事実を受け入れるばかりです。
人間には自由があります。しかしまったくの自由は無と区別がつきません。拠り所がなにもない自由!それは空恐ろしいことです。無人の荒野に一人放り出された幼児にしても,まだしも生きる方法を見つけることができるかもしれません。それ以上に途方もないことです。自由を勝手気ままにやってよいという意味と考え違いをして,人生を地獄化させてしまうのは,むしろありふれたことです。といって親が子の自由に足枷をはめるのは越権行為というもので,これもまた子供をだめにしてしまう典型でさえあります。
自由は自我にともなって授けられたもののようです。「お前に任せるから,思うように人生を生きてみなさい」というのが,人間に与えられた命題のようです。それが自由ということです。そして授けられたものが人間なら,授けたものがあるということです。授けたものがなにか,それは不可知です。人知を超えた意志です。自然の摂理です。その自然の摂理が,人間を無言のうちに,しかし絶対的に支配しています。自由を生きる生き方で,人生が満ち足りたものとして終わるか,地獄化してしまうかが左右されます。
自由は,この主体の無言の制約を受けていると思います。主体から見離されると,他人に見離されるのとは比較にならない深刻な事態を招きます。人生の地獄化は,常にそういう事態です。
自我と自由という特権を与えられた人間は,実にしばしば傲慢の罪に陥ります。大小の専制君主は,いたるところにいると思います。人間にとっての最大の敵は人間かもしれません。敵と身方もまた裏と面の関係で,相互に切り離せないものの一つです。人がにわかには信じ難いのも無理からぬ所以です。
これらに関連がある例を二つ上げてみます。第二の例はある時期,新聞等で話題になった話です。
過呼吸発作を起こして緊急で受診された方がありました。仮にMさんとしておきます。Mさんは30代の主婦で,子供はありません。結婚して数年になります。受診の前々日,夫が浮気を告白しました。それも一人や二人ではないというのです。寝耳に水でパニックになりました。ところが夫は,翌日,あれは嘘だったといい(それはMさんも信じられるそうです),しかし寝室を別にしたいといいました。どうやらMさんが夫の世話をこまめに焼きすぎたのが負担になっていたようだといいます。その後ももめごとがつづき,家を飛び出しました。三日目に帰宅する途中,二度目の受診をしました。実は,初回のときに,状態が悪いにもかかわらず服薬も診療の継続もしぶる気配がありましたので,心配していました。
事態は急展開となり,一ヶ月ほどのあいだに別居の話が決まってしまいました。夫は自分が依存的で妻に頼りすぎていたと自覚し反省していて,このままでは互いによくないので分かれようというのだそうです。Mさんも自分の性格が依存的なのは分かっていますが,別居しなくても改善できるのではないかと思っています。しかし夫の意志は固いそうです。
Mさんはこういう経過について話をしたついでに,「それに,私以外の女性とつき合ってみたいらしいですよ」と,くったくなく笑っていたのが印象的です。ふつうはこういう話は深刻になるものです。ましてMさんは依存的な性格ですし,考えるいとまもないほどの急転直下という展開でもあるので,落ちついている様子は不思議なほどのことです。
この過程で,実母と電話で連絡をとりました。夫のいい分を伝え,自分がずっとよい子で,自分のいいたいことをいえない性格だったという話もしました。母親は,「そうね,あんたはいい子だったわね」とあっさりといい,「そう,そんなに我慢していたとは知らんかったわ」といったそうです。母親のあっけらかんとした様子で,Mさんは肩の力がぬけ,急に気分が軽くなったといいます。自分で思っていたほど母親がこだわっていたわけではないと分かったからです。
M子さんはふっ切れたように明るくなりました。初診のときは,見る影もなく打ちしおれていたので,別人のようです。
転機は初診のときにあったそうです。そのとき服薬にも診療にも積極的になれないでいました。その気持ちを訊かれ,夫がいやがると思うと返事をしたところ,あなたの気持ちはどうなのかと問い返されました。更につづけて,それはご主人に依存しているということでしょうかといわれて,ハッとしたということでした。
依存の問題に思い当たり,それは目から鱗が落ちるような体験だったそうです。そして母親と夫とそれぞれのあいだの依存の関係を,自分の立場で問題にできたといいます。それに伴っていろいろとしたいことが見えてきたというのです。かつてなかったことです。通常は深刻な悩みになる別居,離婚という問題が,Mさんの場合はむしろ自分を回復する方向で心が動きました。
ある人(A氏と呼んでおきます)は,某有名企業で,安定した会社員生活を送っていました。中年期にさしかかり,会社でも中堅の役どころを無難にこなしていたA氏が,ある日,突然申し出て,会社を辞めました。彼の意志は強固でした。辞めてどうするつもりかというと,北極まで一人で橇を引き,走破する計画ということでした。真意を測りかねている周囲の者を後目に,計画を実行に移しました。人生に嫌気がさして,あとは野となれ山となれというやけくそ半分の行動であれば,なんといえばいいのか分かりません。しかし,A氏の場合は内面からの要請で,やむにやまれぬ静かな熱情に駆られてのことであったようです。彼には,日常の生活があきたらなかったのかもしれません。昨日までの友人,大切に思っていただろう妻や子,それらの人々の心配や反対を押し切って命がけの孤独な難行に立ち向かいました。A氏の冒険行に要するエネルギーは,並大抵のものでないことは容易に想像できます。一体どういう熱情がA氏を駆り立てたのか,おそらく言葉で説明するのは難しいのではないでしょうか。
この情熱は,純粋で,妥協の余地がないように思われます。頑固で,協調性がない者とか,傲慢で,強圧的な権力者とかの場合とは,いうまでもありませんが,正反対といっていいぐらい意味が違います。A氏のそれは何事にも代えがたい,ゆるぎない価値として妥協できないものだっただろうと思います。彼にはなによりも自分自身との関係が大切だったのではないでしょうか。それは,ガリレイが宗教裁判にかけられたときに,「それでも地球はまわっている」とつぶやいたことにも通じるでしょう。
内なる主体としっかりとした関係ができているとき,A氏のように命をかけることができるのだと思います。分からず屋たちの中で孤立したときなどに,平然とおのれを保つことができるでしょう。
これに対して単に頑固なだけの者は,心を凝固させることで身を守っているように見えます。何から身を守るのかといえば,第一に無意識界に潜む抑え難いほどの怒りからだと思います。強権的で容易に人の意見に耳を貸さない者は,しばしば,権力という鎧で身を守らなければならない弱さを秘めているように見えます。
前者と後者とを決定的に分けるのは,謙遜の精神です。自然の摂理の前に,人は畏敬の念に打たれないわけにはいきません。自然に頭を垂れ,謙遜であるしかありません。それが人に品性や節操を与えます。
頑固者や権力者に最も望まれるのは,これらの精神です。
性格形成に与える母親の影響-その4
■自立と依存
自立は理念です。現実に到達されることはないものです。
人はそれぞれの人生をどこへ向かって進めて行こうとしているのでしょうか。動物は目先のことに,欲求に従って行動しているように見えます。人間は動物の中でも特別な存在のようで,目先のことに欲求にだけ従って生きていけばよいというわけには,到底いきません。できれば自分らしく,充実した日々を送りたいと誰もが思うでしょう。人間の場合,生きる指針は,本能として身体に刻印されたものとしてあるようには思われません。では指針はどこに,どういう形であるのでしょう?
子供には躾けや教育が必要です。大人になって自分一人の力で生きていけるように,大人たちが人生の先輩として,必要と考える知識や,人との関わりの大切さを身をもって教えます。それらは欠かすことのできない重要なことですが,彼ら大人たちの誰もが,人生そのものの指針を伝授することはできません。
では,自立の理念とは何でしょうか?
依存からの完全な脱却であるというのは,どうでしょうか。同語反復のきらいがありますが,間違いではなさそうです。言葉を換えれば,自立とは,自己がそれ自体で自足することであり,あらゆる関係性から自由になるということであるといえるようです。
それでは依存とは何でしょうか。
それぞれの自己は,何ものかとの関係において存在しています。何ものかとの関係においてしか存在し得ないという方が,より適切です。
私がこの一文を書いているということに即して具体的にいえば,持っているペン,紙,向かっている机,椅子,暖房機,電気スタンド,書斎,家,家族,近隣の住人,家々,街,道路,などなど無数の物や人が,つぎつぎに私の意識的視界に入ってきます。それらのすべてが私との関係において存在し,私の世界を構成しています。それらは私の所有に属しているともいえます。それらのものは,私との関係において主観的,かつ客観的という性格を持っています。従って,たとえばAさんの世界に属するそれらのものと,わたしのものは,主観的というかぎりでまったく別個のものですし,客観的というかぎりで同一のものです。我々は互いになにものかを共有することができますし,しかし,なおかつ共有することができません。
私がいま使っているペンは,しかじかという会社の製品で,しかじかという名前の物であり,どこの文具店でも手に入るありふれた物です。Aさんもおなじ物を持っているとします。Aさんのも私のもおなじ物といえますが,しかし,まったく別の物ともいえます。つまり,私が持っているそのペンは,「私のペン」であり,「Aさんのペン」とはまったく異なります。仮にその関係性を無視して,私がAさんのペンを勝手に使えば,私は泥棒ということになります。このように,私はそのペンとの関係性の中にあり,私がそのペンに依存することにより,それは私に固有のものとなるのです。
私がそのペンを使ってみて,書き心地がいいから試してみてとAさんに勧めたとします。Aさんがそれに応じて試し書きをしたとすると,そのペンは共有されたことになります。Aさんも同感しておなじ物を買ったとすれば,ますます共有性を深めたことになります。あるとき何かのきっかけにAさんが私に対して著しく気分を害することがあれば,そのペンを捨てるかもしれません。Aさんがペンを買ったときと捨てたときとでは,おなじペンが対立する意味を持つものとなります。
このように見ていくと,私はおびただしい物や人との依存関係の上に生きているのが分かります。私はそれらによって人生を支えられており,それらが必要であるかぎり,どれ一つとして欠けてはならないものです。
また,不要の物はゴミとして捨てることになりますが,不要でありながら私が捨て切れないでいるものたちもあります。それらの物との関係においても,私の性格的特性が表われているのです。
隣の芝生がきれいに見えるという諺があります。
人をうらやむ心は誰にでもあるものでしょうが,度が過ぎると心を制御するのに苦しむことになります。自分が所有するものは,それを大切にする心がなければ,依存している当の物や人によって,ある意味で逆襲されることになります。
隣の芝生がきれいに見える精神は,満たされていない精神です。
私が貧乏であり,隣の家が裕福であるとしても,私の心が満たされていれば,羨ましく感じることはあって妬むことはないでしょう。しかし心が満たされていなければ妬むかもしれません。
私の心がある程度満たされているとすれば,私に本来与えられている自然的な精神の諸力が,過不足なく実践できている場合です。そのとき,それなりに他人の評価がもらえていることも,必要条件になるでしょう。
逆に心が満たされない思いをしているときは,本来自分が持っているはずの潜在的能力が実践されていないときです。
つまりは心が自然的であればおおよそ問題はないのです。そして人の心が自然的に成長するのが難しいのは,人間が他者との関係を必須のものとしているからです。
結論的にいえば,本来持っているはずの潜在的諸力を実践できないのは,自我の不始末ということになります。結論だけをいえば自業自得ということになるのですが,自我自身がその自然的な機能を他者によって歪められるので,ことは単純ではありません。自我の未発達は,悪しき依存関係の一側面です。それは何よりも,原初の他者であり,人格形成の根幹に関わる立場にある母親との関係において生じます。
このあたりを具体例に即して見てみたいと思います。
A氏は,画家です。ある農村の離農した農家の家と田畑を借り受け,自給自足の生活をしながら絵の修行に励んでいます。彼は元精神科医でした。私は彼の二十代後半から三十代前半にかけてと,その十数年あとの二年ほどをおなじ職場で仕事をしました。最初の職場でのA氏は,将来を嘱望される有為の青年医師でした。患者さんを診る能力は,周りが一目置いていたと思います。その能力は,何よりも柔らかな受容力にあったように思います。患者さんの立場からすると,受け入れられているという安心感と,理解されているという信頼感を得やすかっただろうと思われます。そういうセンスは,天性のものだったでしょう。精神科医は多くのものを学び取らなければならないのはいうまでもないとしても,学習によっては得られない何かが要求されています。それは一つには,病者の問題を他人事にしてしまわない共感力ですが,A氏にはそれがありました。病者と関わり,問題を共有するためには,治療者がその問題を自分自身の問題とする能力が必要です。それが共感能力というものですが,微妙なものも過たず感じ取るには,天性のセンスが要るように思います。病める心の人は,いわば全身で治療者を見ていると思います。相性のこともあるので各人各様ですが,一般論としては治療者の共感能力を感じ取ることができたときに,一応の安心が得られるものだろうと思っています。
心を病んでいるということは,自我の機能的能力が衰退しつつあるということです。人は自我に拠る存在です。自我は光の世界のものです。人は自我を持つことによって人となったのですが,自我によって光を知ることになったのです。そして光を知ったがために闇をも知ることになったのです。光は生きようとする世界のものであり,闇はその裏面の世界です。そして闇は,死に通じるものです。光は闇を前提とし,生きるということは死を前提とするのです。光と闇,生と死は,人間が自我を持つ存在であることで必然化された,人間ならではの遠大な矛盾です。
赤ん坊のか細い自我は,それを護るものがなければなりません。光を知る者として生を受けた赤ん坊は,必然的に闇に怯えるものでもあります。自我の機能を駆使して自らを生きる力を獲得できるまでは,他者の保護を絶対のものとする理由があります。
自我に拠る存在ということが,必然的に闇の世界の存在を前提としているというところに,人が依存的な存在であることの一義的な意味があります。
絶対的な保護を必要とする赤ん坊の未熟な自我が,しだいに力をつけて闇の世界のエネルギーを活用していくことになりますが,それに伴って絶対的な依存から自立の方向に向かうものの,闇の世界を凌駕することが結局は不可能なのも自我の一面です。従って,自立は単なる理念にとどまるのです。
そのようなわけで,人は人生の最早期に他者への依存を不可欠なものとし,結局,他者との依存関係を脱することはできません。
自我は強力な能力を与えられていますが,闇の力の前には何ほどのものでもありません。闇には意識を無化する力があります。それは場合によっては自我を滅ぼすことになるものです。ですから自我を共有する他者との関係は,なにを置いても重要な意味があります。しかし,それだけに他者は諸刃の剣です。自分を元気づけてくれる最たるものであるということは,逆に当てが外れるとひどい目に合うことにならざるを得ません。
小児のころ緘黙症であったある女性は,テレビなどのニュースで人が死んでもなんとも感じないが,犬や猫が死んだらとても悲しいといっています。頼りとする人間たちに,いかに傷つけられてきたかが察せられます。
犬や猫は自然のものです。犬にかまれても,犬を憎んだり,恨んだりする人は滅多にないでしょう。ふつうは飼い主に抗議するだろうと思います。犬は人の身体を傷つける力を持っていますが,心を傷つけることはありません。心を傷つけるのは人間ばかりです。心の傷は外部からの力によるのではなく,受け止める側の内部的な問題として生じるのです。このことは他者が,外なる存在者の中で,特別な意味を持っていることを示しています。つまり自己という存在は,構造として他者を内に含んでいるのです。それがいかなる外部的な状況に置いても,他者との関係が途絶えることがない理由です。犬は経験的に,学習としてそれぞれの個人の世界に外部から入ってきたものですが,他者は,経験以前のものとして存在しているのです。人と人とのあいだでは,言葉を交わさなくても相通じるものがありますが,犬の気持を察するには,人間的な類推をするしかありません。
それにしても他人に心の傷を負わせる人は,人の心の自然の性としてそうした行為におよぶのではありません。その人自身がかつて他人たちから傷を負わされ,いわば心の自然を撹乱されたために,怒り,憎しみが無意識のレベルに解消されずに残っているからです。
他者は,自我を共有するものとして最も頼りとするべきものであるだけに,最も傷つけられるものでもあります。人間の最大の敵である可能性を,人間は持っているといっても過言ではありません。それは人間の存在構造から,原理的にいえることなのです。
自己の存在条件として,他者の助けを絶対的に必要としているのが人間であるということは,親といえども赤ん坊を十分に守り育てる力を持っている保証がないということでもあります。つまり親にしても他に助けを求めたい心があっても,おかしくないどころではないのです。その相手が年端もゆかない赤ん坊であっても不思議はありません。むしろ心にわだかまりを抱える母親には,恰好の相手になります。動物に似て自然のものである赤ん坊は,どんな母親にとっても愛らしいかぎりではないでしょうか。滅多には味わえないであろう愛らしいものとのあいだでの至福の感情は,程度の差こそあれ,あらゆる母親がいつまでも封印しておきたいほどのものではないでしょうか。母親によっては,あの手この手と意識的,無意識的な策を弄し,自分の思うように育てようとするかもしれません。自分の望ましいイメージに沿って育児に励むとき,それが愛情と信じやすい心的状況ができるだろうと思います。ときによっては,投網にかける漁師のように我が子をからめとろうとする母親も,珍しくはありません。いずれにせよ,最良の母親も含めて,母親が赤ん坊に悪しき依存をしてしまう側面があるのは,避けられないことです。
そのような事情が,赤ん坊の自我を混乱させ,自然的な機能を守り通すのが困難になる主要な理由です。母親が第一番の頼りであるということは,母親によって人生を狂わされる最大の理由になり得るということでもあります。
ある中年女性は,離婚の経験者です。小学生の長女と暮らしています。年の暮れに,再婚している元夫から連絡があり,正月に長女を預かるといわれました。相談ではなく,要求であったのも神経を逆なでされることでしたが,長女が喜んで父親のもとへ去ったあとの寂しさは,言葉ではつくせないほどのものでした。そして元気で帰ってきた娘に,「おかあさん,淋ししかった?」と訊かれて,大丈夫だったから安心してね,とはいえませんでした。幼い娘に,母親自身が幼い子のように寄り添って,いつまでも離れたくないと思っていました。娘は母親を気遣って,あれこれと世話を焼いてくれるのです。親子の関係はまったく逆転していたそうです。
繰り返しになりますが,人間は依存的な存在であり,その依存の原初の関係は,母親とのあいだで体験されると考えて間違いないと思います。原初の他者である母親への絶対依存からしだいに自立していくことになりますが,それにはまずは母親の助けが必要です。そのためには母親が,それなりに自立していなければなりません。しかしながら先にも述べたように,母親の自立性には個々に問題があるのです。赤ん坊が頼りとするに値するかは疑問であるほど母性を欠く母親が少なくないのが,精神科の臨床現場からうかがえる現実です。子供の虐待報道さえ日常的というのが,昨今の状況です。まして子育てに悩み,自信を失くしている母親は無数にあると考えなければなりません。そこには時代の反映という側面もあると思います。
価値観が多様化している現代ですが,どうやら母親たちにとって,母性も多様化しているかのようです。
それは心の豊かさの表れでしょうか?価値観の多様化が,それぞれの自由の発露に基づいているのであれば,そこには精神の豊かさがあって然るべきです。そして,豊かさのしわよせとして,母性が希薄になるという事態はあり得ることでしょうか?私には,とてもそういうふうには考えられません。母親が個々の価値観に基づいて行動するのは個人の自由でしょうが,それが母性の希薄さを弁明することになるとは到底考えられません。そういうことは個人の問題だと思う人もあるかもしれません。しかし,それは間違いです。子供には自分を守る術があまりないのです。そういう子供の立場を,社会的に擁護する規範が要ると思います。
人間の精神が豊かであるとき,それは必ずその個性が自然的に解放されているはずだと考えます。母親にとって自然的であるとは,何を置いても母性が豊かであるということではないでしょうか。母性を欠く母親!これほどに矛盾したものは滅多にありません。
「私は母親になどなりたくなかった。しかしなってしまった」という人もあるでしょう。その人はどう生きればよいのでしょう。荷の重い育児に,全精力を奪われるのは耐えられないと思うかもしれません。その気持は分からなくはありません。そして自分のかけがえのない人生を精一杯生きる自由があると考えるのも,理解はできます。その女性は,社会的に成功するかもしれません。そのために家事や育児が疎かになってしまうのはやむを得ないと考えるかもしれません。
彼女たちが人生を自由に,豊かに生きる権利を否定することはできません。しかし,われわれ精神科医は,このような母親の下で呻吟する子供たちの例を,いくらでも挙げることができます。もし自分がよりよく生きる自由を追求するためには,やむを得ない犠牲だったという母親があるとすれば,なんといえばいいのでしょう。これが精神の恐るべき貧困の表れでなくして,どういう貧困があるのでしょう。
矛盾を生きる宿命の下にある人間には,まるごとの充実,豊かさはあり得ません。
ソクラテスは,アポロンの託宣により,最も知恵のある者とされました。ソクラテス自身は,自分が人に勝っているとすれば,自分が無知であることを知っていることにおいてであるという意味のことをいっております。
この例にならっていえば,ある母親が精神の豊かさを追求していくつもりがあれば,自分の心の貧困をこそ知る必要があるといえるでしょう。そうでなければ,恐るべきエゴイストと区別がつかないことになってしまいます。
望まない子を生んでしまった母親は,同情に値する面があるかもしれません。育児に煩わされることが,かけがえのない人生をより自分らしく生きる上で障害になると考えていたとすれば,大きな難題を抱え込むことになったといえるでしょう。彼女が考える自由な生き方,自分らしい生き方が,精神の豊穣を意味するものであり,精神の貧困を排除したいという意味であるのなら,不幸にして母親になってしまった現実を真剣に悩む必要があります。あっさりと’不幸の素’を切り捨てるやり方は,忌むべき自己本位,恥を知らない傲慢といわれても仕方がないことです。せめて自分がしていることは,そういう意味を持つのだという自覚を持つべきです。そうであれば,’不幸の素’を切り離すなどという結論には,滅多にいたらないでしょう。人は悩むべきことをしっかりと悩むべきです。真剣に悩むことができれば,やがて大きな解答が出てくるものだろうと思います。そして,そのとき,まったく別の人物になっていることでしょう。
彼女が自分の心の貧困に思いをはせる勇気を持つのなら,’望まなかった出産’に,自己の再生の重要な契機を見出すことでしょうし,そのときこそ精神の豊穣に一歩近づくのではないでしょうか。
現代の母親たちの母性の希薄化は,人間が心の自然から遠ざからざるを得ない時代的な潮流にも関係があると思います。人々の心はより世知辛くなり,小賢しくなり,心の飢えに人知れず悩まされているのが現代精神の潮流です。それに伴って現代人の精神の成熟が阻まれているようであり,それが母親たちにおいては,母性の未成熟化となって表われているということだと思われます。
また,人が依存の対象を絶対的に必要とし,それは必ず悪しきものを排除できないことを含むという問題の根本には,自我に拠る人間の存在条件があります。つまり,人間存在の一つの特徴は,諸矛盾をはらむということです。生きるということには,死ぬことが含まれ,自己であるためには,他者性を含み,良い依存を目指すべきであるということは,悪い依存を含むからこそである等々です。絶対的な良い依存というものは存在しないのです。諸矛盾の果てしない止揚(二つの矛盾,対立する概念を,一段高い段階に統一,発展させること)が,人間精神に許されている自己実現への王道です。人は矛盾を引き受け,矛盾に悩み,そして新たな高みへと進むことができるのです。
このように依存は相互的なものであり,母親と赤ん坊との関係も例外ではありません。かつ依存には,良い形態と悪い形態とがあります。いずれにせよ,どんなに母性に恵まれた母親であっても,悪しき依存の混在は避けられないことです。
母子のあいだでの依存関係では,力を持つ母親の側からの侵入,干渉が特に避け難く,悪しきものの典型です。それに伴って赤ん坊は,自然的な心性をさまざまに混乱させられます。それは悪しき影響ということになりますので,善悪の問題ではありますが,どうしても避けることができないのが人間の宿命的現実です。
話をA氏に戻します。
私が二度目の職場でA氏と再び仕事を共にすることになったのは,たまたまA氏と会ったときに,私が誘ったのがきっかけでした。A氏はすぐに応じてくれました。それは私が予想していないほどのことだったので,私は少々あわてました。施設長に頼まれて声をかけたわけではなく,そのときの話の勢いで私が勝手に誘ったからです。それから施設長に話を持って行ったところ,幸いに退職予定者が一人いるというのです。話が意外にも上首尾に運んでしまいました。私は再びA氏と仕事を共にすることが,素直にうれしかったのを覚えています。
しかし再会したA氏は,かつてのA氏ではありませんでした。
一言でいえば,A氏は影に呑み込まれていました。暗い無表情や,陰鬱な雰囲気から一目でそう感じました。しばらくぶりに再開したときに私が誘ったのは,一つには変わり果てたA氏の様子にあったと思います。あの有為の青年が一体どうしてしまったのかと驚いたのです。もともとA氏は外向的な性格ではありませんでした。人に媚びず,本物だけを大事にしようとする精神がありました。いうまでもなく,それは精神科医としては欠点ではありません。A氏には,自分の信じることだけをするという好ましい頑固さがあり,私はそういう彼が好きでした。患者さんを大切にし,仕事を誠実に,熱心にこなし,しかし小心ではなく,どこか人生を高括るようなところがありました。自分の才能を信じていました。しかし医者として認められ,それなりの地位を得て世間的に成功することなど,およそ念頭にないように見えました。それだけにどういう風にでも生きていける人のように思えていました。彼に見られた表情の翳りのようなものも,むしろ人格に深みを与えていました。
再会したときに,一体どうしたんだと私は心で叫んでいましたが,言葉には出せませんでした。彼がかかえている問題が重過ぎるように思えたためでした。そのとき,私はどこか保護者のような気分になりかけていたと思います。彼が私の誘いにあっさりと乗ってくれたときにも,彼が私に救いを求めているように思われたのです。そしてかつての彼を知る私には,共に仕事をするうちに,きっと回復するはずだという確信のようなものがありました。
しかし,二度目の職場に現れたA氏は,ひどく尊大でした。世の中も人間も憎んでいるように見えました。仲間たちへの最低限の礼儀もなく,あらゆるものを軽蔑しているようでした。なりふり構わず,人を人と思わないかのような態度に,仲間たちは最も善意のものも含め,一人として彼と口をきこうとするものはなくなりました。そういうことも一向に意に介する様子もないのです。
一番問題なのは,治療者としての自信も意欲もすっかり失せているらしいことでした。
彼がかなり深刻に人格を病んでいるのはほとんど明白でしたが,そのことで悩んでいるようには見受けられず,人生そのものを捨てている気配が感じられました。
私に対しても,不機嫌以外には何の感情も見せないに等しいのです。彼とのあいだで,まともに意見が交わされるということもおよそなかったのです。彼と心を分かち合う何ものもありませんでした。彼はいつまでたっても,単にそこにいるだけの,厄介な人物であるに過ぎませんでした。そうなると彼にとっては,医者の立場は,単に生活のためでしかないのです。彼は患者さんのために存在しているのではなく,患者の皆さんは彼のために存在しているに等しいのです。もはや彼は治療者ではありません。それを苦にしているようにも見えません。治療者としては,最も堕落した姿としかいえない有様でした。
私がA氏の例を上げるのは,心についての治療者とはどういうことか,心を病むということは,ひいては人間であるということはどういうことか,そうしたことを考えてみるためでした。
若い時代の精神科医としてのA氏は,治療者として機能している自己を感じていたと思います。しかし彼は,治療者としての自分を重視し,大切にしているようには見えませんでした。医者は働き口には恵まれています。そのためもあったでしょうか,彼は思いつくままに,いわば人生を彷徨していたように思われます。それは才能を持つ者にはありがちなことかもしれません。何かを模索していたのかもしれません。しかしながら,後年の彼の著しく変貌した様子をも合わせて想像すると,彼の世界を中軸として支えていたものは,なんといっても患者さんとの関係であっただろうと思われます。結果から見れば,その関係を疎かにしたことになるように思われ,真剣に人生に対峙することを回避してきたようでもあり,それは自我の不始末,力不足を意味すると思います。
それぞれの自己は,おびただしいものたちとの関係において存在可能です。自分をより良く生きるためには,それらの関係性をより良く生きなければなりません。そうでなければ糸の切れた凧になります。根絶やしになります。才能に溺れるものが陥る罠は,そういうところにあるといえます。大切なものを大切にしないと,その大切な依存の対象に,いわば復讐されてしまいます。
自己とは,主観的ー客観的な存在です。純粋な主観も純粋な客観も存在しません。それぞれの世界における客観的なものたちは,無限という様相を持っています。たとえば一本のバラの花には無限なものが秘められています。画家が納得のいく作品を描こうとすると,何枚ものバラの絵を描かねばならないでしょう。それでも,なおかつ納得できないかもしれません。他の画家は,またまったく別なバラの花の絵を描くでしょう。そもそも対象が無限の様相で表われているので,芸術家が作品にする意欲を持てるのです。
バラを素材にする植物学者は,いわば一本のバラの花と共に一生を送れるかもしれません。人が対象としっかりと向き合おうとすれば,対象は無限の様相を表すのです。逆にいえば,それら大切なものを大切に扱う心がなければ,心は貧困化するのです。
統合失調症に見られる世界没落体験をはじめ,自己を失う脅威は,関係が途絶える脅威であるといえます。一切の関係が途絶えたときに,人は身体的にか精神的にか,死に直面するのです。大切な関係は,それを疎かに扱えば,関係によって滅びるともいえます。
A氏にとって,患者さんとの関係は生命線であったように思われます。それを疎かにしてきたために,その関係の希薄化と共に,A氏の精神の後退が起こっていたのではないかと思っています。
A氏の自我がそのようであったのは,自我の自然的なものが人為的に撹乱されたためと考えるべきことです。そういう力を持つ他者は,人生の最早期の他者である両親をおいてなく,なかんずく母親の影響によるものと考えて間違いはないだろうと思います。その意味で,A氏は,悪しき依存の中にいたのだと考えられます。
若い時代のA氏は,有能ではあっても治療者として確立された何かがあったわけではありません。しかしおそらくは,自分が人並み以上に優秀な医者であるという無意識的な自負心があっただろうと想像されます。
後年の彼を見ていると,治療者としての自信も自負心も実質的に失っていたように思われますが,一方では人並み以上の評価をもとめる無益で,虚しく,不快なばかりの自負心が見えていました。それが実体を欠いた要求であるのを,他でもない彼自身が知っていたはずです。
しばしば驚かされたのは,人を出し抜いたときのはしゃぎぶりです。ふだんが暗鬱で,不機嫌なので,その様子は異様でした。また,いたるところに顔を出す羨望の色がありました。そういうものから察すると,彼の内部には並々ならぬ自負心が虚しく潜んでいたのだろうと思われるのです。
そうした実体を欠いた自負心というおぞましい姿は,しかしながら別な意味で実体があったといえるのでしょう。火のないところに煙は立たないのです。彼の内部には,日の目を見ない分身たちが,宝の持ち腐れ状態で埋没していたに違いないのです。それら分身たちは,A氏が自分に自信を持っていた時代には,無意識下でおとなしくしていたはずの者たちです。というのは,自我がそれなりに力を発揮していることは,それら影の分身たちにも好ましい,望みを持てることだからです。いつかは自分たちも,自我によって日の目を見る期待が持てるからです。
しかしそういう期待が裏切られると,無意識下にある分身たちは怒りと共に勢力を強めていきます。それは自我の衰退とパラレルの関係にあります。そして自我は傀儡化されるに等しい心的状況が生まれます。
それらの分身たちは,幼いころにおそらくは主として母親との関係で,自我によって抑圧されたものたちです。自我が中年期にいたっても悪しき依存から脱していない様子から察すると,自我は母親(と思われます)の自我によって支配されたままであることを,直接的に意味していると考えてよいと思います。そしておそらくは母親の自我による支配の代償に,母親の過保護があったのではないかと思われます。
無気力に傀儡化されている自我の下で,A氏はほとんど傲慢,不遜な小児でした。他者への配慮など,社会性は極めてあやしいものになっていました。自我の無力化に伴って,小児的に退行していたといえるのでしょう。
他に依存するA氏の自我は,虚しく,実体を欠いてしまった自己のありように対して,いたって無責任なのは当然といえば当然なのです。そうした自我の下にある無意識下の分身たちは,いまや日の目を見る当てもなく,勢力を拡張してしまっていたと思います。
A氏がおそろしく客観性を欠いている様子に,しばしば驚かされたものです。どう考えても,あきれるほどの現実のすりかえとしか思えないことを口にしたりもするのです。そういう自己本位そのものといったところは,かつてのA氏にはなかったことです。それを見ると,彼の自我は完全に傀儡化され,影の思考に支配されていたのだと考えるしかありません。自我を傀儡化しているのは,影の分身たちです。それら影の分身たちの首座にあるものを,私は裏の自我と呼んでいます。それは直接は表に出ないで,表の自我を操って欲求を満たそうとするのです。裏の自我は人生を生きようとするものではありません。生の世界のものを憎悪し,目先の欲求を自我をそそのかして手中に収めようとするのです。人生と他人と,そしておそらくは自分自身を憎悪しながらも,なにかのきっかけに,A氏が見せた上機嫌の中にはそのような色が見えていました。他人を出し抜くことで,してやったりと小躍りする黒い笑いは,裏の自我の下にある裏の世界の感情です。自我が果たせなかった満足を,まるで他人のせいであるかのような意識のすり替えが起こるのです。他人への悪意,憎悪をこめて腹いせをしようとするかのような様子は,かつてのA氏にはもちろん見られなかったことです。
本当は彼の自我が,内心に潜むそれらの諸欲求を満たすべく,何らかの研鑽,努力をする必要がありました。ところが現実には,彼は’蟻とキリギリス’のキリギリスだったのではないかと想像されます。
キリギリスには,バイオリンを奏でる才能がありました。蟻にはとりたてて才能がありません。しかし蟻には生きるために,せっせと餌を集めて冬に備える地道さと謙虚さがありました。キリギリスは,夏のあいだは才能にまかせていれば,満足のいく生活ができたのです。蟻もキリギリスが奏でる音楽に,仕事の合間に耳を傾けて賞賛しました。そして冬がやってきました。蟻はキリギリスが心配でした。外に出てみると,よろめき歩くやつれきったキリギリスがいました。肩を貸そうとする蟻を,キリギリスは振りほどき,巣に呼んで手当てをしてあげようという蟻の親切を断りました。そして死んでしまいました。別の蟻たちが見つけて,食糧にするために運んでいきました。
もしキリギリスに,冬のあいだにも蟻が音楽を聞きたがるほどの才能があれば,生きていけたかもしれません。ところが蟻は音楽を懐かしむのではなく,キリギリスの無力を助けようとしたのです。キリギリスにバイオリンの才能があるといっても,他から見ればその程度のものなのです。助けてあげなければ生きていけない哀れな生き物に過ぎないのが,客観的な現実です。他なるものである蟻によって支えてもらえなくても,キリギリス自身が己の演奏能力を信じることができていれば,蟻が差し伸べてくれた援助の手を断ることはなかったのではないでしょうか。キリギリスにも,夏のあいだも冬への不安があったはずですが,自立性に欠けるものがあったに違いない彼は,自分のバイオリンの演奏能力を評価してくれる他者の存在が必要だったようです。そして他でもなく,自分で自分の能力を信じきれていなかったに違いありません。なにものかを信じることができていれば,他との関係も保つことが難しくはないのです。自分を信じていなかったに違いないキリギリスは,他なる蟻も信じていなかったと思います。あらゆるものとの関係の薄弱なキリギリスには,他なるものの関心を惹きつける当てがない現実を,直視する勇気もなかったのです。そして誇り高いキリギリスには,演奏者としての自分を評価することによってではなく,自分の力では生きていけない哀れな者であるがために支えようとする親切は,とうてい受け取るわけにはいかなかったのでしょう。そういうふうに考えると,夏のキリギリスも既に絶望していたのだろうと想像されます。
キリギリスの自我は,バイオリンを奏でることに依存しています。それは夏のあいだは意味を持ちます。周りのものたちには,夏の気候の恵みによって,キリギリスのバイオリンを楽しむ余裕があるのです。しかしその自我は,冬の厳しさには何らの力も持っていません。つまりバイオリンは,冬の厳しさにも耐えるだけの依存の対象ではありませんでした。
A氏にとっての夏は,若さだったと思います。若さの勢いが,彼に,能力の暗示を垣間見せたのかと思います。そして彼はいつまでも若くはないということに気がつかなかったというよりは,高を括ったのではないでしょうか。
その盲点は,彼の自由意志,自主の精神を混乱させたに違いない悪しき依存関係に起因するものだろうと思われます。悪しき依存関係を克服できないままでいる自我の頼りなさの反映として,彼は恐れ入るほどの幼稚な心に陥っていたと思います。それに伴って,人間としてのあらゆる美点が消滅してしまったかという事態に立ち至ったのではないでしょうか。それはまさしく冬のキリギリスさながらに,「だれも俺に構わないでくれ,俺の価値を認めようとする気がある者を除いては・・・」というふうな,絶望的でなりふり構わない自己主張であったように思われます。自己を支える根拠が空洞化しているときに,それを補うかのように自負心だけが更に誇大的になっているらしいのも,人間関係的な状況を更に悪化させることになります。そこにも自我の後退に伴う社会性の喪失,影の性格の現前,幼児的退行といった様相が表われているといえるようです。
一般に,心の病理現象は,幼児心性が意識の表舞台に姿を表している様相といっても過言ではないようです。
J.Fマスターソンは,自己愛性の人格障害に関して,次のように述べております。
「自己愛パーソナリティ障害の子供を持つ母親の中には,基本的に情緒が冷ややかで利己的に他人を利用する人たちがいる。そういう母親は自分自身の完全主義的な情緒的欲求を正当化するためのちょうどよい対象となるように子供たちを型にはめ込み,子供の分離・固体化欲求を無視する。子供の真の固体化欲求は,母親の理想化投影に子供が共鳴するにつれて損なわれていく。母親の子供に対する理想化に子供が同一化すると,子供の誇大自己は保存されるようになり,・・・」
この論旨に従うと,A氏の幼児心性である誇大自己と万能感とを,母親が功利的に巧みに利用して,A氏を通じて母親自身の誇大的な欲求を満たそうとしたということなります。A氏は母親の干渉に気がついていたと思われ,母親への不快感,反発を強める一方,自己の誇大感を母親によってくすぐられることには大いに満足していたといえるのかもしれません。
彼の無意識は他者の賞賛を強く求めるものがあり,それに見合う実質を欠いてしまった後にも,虚しさと一体となった誇大感に相応する自負心を捨てることができなかったように思います。
彼の気分は当てのない賞賛をそれとなく他に求めていたように思われ,いまや他人は滅多なことでは彼を賞賛する理由もないので,彼は常に不機嫌に’愚かな他人ども’が不愉快で仕方がなかったのでしょうか。
夏のキリギリスは光の思考が可能でした。そのとき無意識の闇の世界に葬られている分身たちも息をひそめて自我の働きぶりを見守ります。いつかは自我が自分たちにも目を向ける力を持つかもしれないからです。
冬のキリギリスは影の思考に支配されてしまいました。心の世界全体が影に支配され,世界を構成するものたちとの関係が生気を失ってしまいました。それは一途に無気力になっている自我と,相対的な関係にあります。影の世界のものである怒り,憎しみ,怨念などの暗い情念が,冬のキリギリスのように滅びを志向しようとします。
冬のキリギリスの世界は病者の世界です。世界がすっかり影に覆われたときに,自我の世界である社会性が後退し,幼児性が露わになります。幼い時代に満たされなかった心たちが,頼りにならなくなった自我に見切りをつけ,自分たちの姿を露骨に表すのです。
精神科医は,影の専門家であるといえると思います。自我の気弱さが影の勢力増大を招き,ますます自我が力を衰退させることになるのを,精神科医は病者の自我に代わって病者の心を力づける役目を持っています。
影というのは,先ほど述べた闇に通じるものです。影が支配的になると,意識が無化されていきます。自己の世界の関係性を剥奪する力を,闇は持っています。自我の機能不全が回復不可能なレベルに及ぶと,闇による自我の回収,つまり死への直面ということになっていきます。
自我の活力が不十分であれば,自我は自分の影を扱うことができません。影は他者の介入によって,自我が懼れをなして身売りをしてしまったというような心的過程に伴って生じたものです。自分が思わずしてしまった無意識的な不始末を,衰弱した自我が改めて回収することはほとんど困難です。他者の利を優先させて自己の不利益を我慢するというのは美談にもなり得ますが,自我の気弱さのなせる業であれば,大きな禍根を残すことになるのです。
自己の世界を支える諸々のものたちとの関係が無化されているときに,治療者が介入することで,治療者とのあいだに新たな関係が生じます。それが信頼関係といえるほどのものになっていけば,それだけで病者の世界は活気づくきっかけを持つことになります。
A氏が画家として再生しかけているのは,A氏の自我に潜勢力があったということになるのでしょう。彼は画家として外的対象の無限性に関わることになったといえますが,それは同時に彼の影や闇の世界である無意識の無限性との関わりが新たに始まったことをも意味するでしょう。心を無化する力を持つ闇は,自我が力を回復させると,自我の拠り所となって大きな活力の源泉になるのです。
精神科医をやめ,画家に転向したことはよいことでした。
精神科医は,自分の影の世界に精通していなければなりません。精通とまでもいかなくても,そこに関心を向けつづけなくてはなりません。というのも患者の皆さんは,影に呑み込まれそうになって医者を求めるからです。医者が自分の影に無関心で,無神経でいるかぎりは,心の治療者の資格がないといってよいでしょう。さもなければ患者さんの影に直面して,医者は間違った反応,対応をしてしまうのが避けられないのです。影に反応して,自分の影である鬱屈したものを相手にぶつけることになれば,攻撃的,拒否的,敬意の要求という傲慢など,してはならないことを防ぐ手立てがありません。また影を共有しあうことで,悪しき依存関係が形成される場合もあるでしょう。それは患者さんを利用して,「傷のなめあい」をしていることになるのです。
心の治療者は,心を病む人の指導者です。一歩上にいる必要があります。それは知識があるとか,地位があるとかということでは勿論ありません。患者さんの影に呑み込まれず,その影を見つめつつ,治療者本人の心の影の動きを見張ることによって成り立つ類のセンスと技術に関わるものです。
それぞれの自己はおびただしいものたちとの関係を持ち,それぞれの自己の世界が構成されています。私が日々の生活でどの程度満たされているかということは,それら私の世界を構成しているものたちとのあいだで,生きた関係を保つことができているかどうかにかかっています。その中でも主柱となるものたちとの関係が,とりわけ重要です。それらとのあいだに生きた関係が保たれていれば,私の世界は親和的な相貌で表われるでしょう。しかしそれらとの関係が親しみを欠いていれば,世界は寒々としたものであるでしょう。何か特別に悲しいできごとに見舞われれば,そういう事態になります。
H.テレンバッハが提示した「メランコリー親和型」という性格類型は,内因性メランコリーへの親和性を持つものとして提唱された概念です。この概念は,下田光造が提唱した「執着性格」との類縁性が指摘されており,日本的な性格類型であるといわれております。その要旨をかいつまんで翻案すると以下のようになります。
日常の生活は,有形無形の規則で秩序立てられています。日本には日本的な暗黙の生活習慣というものがあります。個々の会社や学校には,それぞれの社風なり,校風なりがあります。家庭には家風があります。自分が置かれている組織や集団などの秩序に基づいて,忠実に,几帳面に,自己を捧げようとするのがこの性格類型です。彼らは,所属する集団の中で感じ取った期待されている役割を敏感に感じ取って,それを高いレベルで忠実に守り通そうとする生来的な気質を持っています。彼らは与えられた立場において,その立場を主体的に生きようとするよりは,要求されている秩序の中に自らを主体的に投げ入れるのです。主体者として行動するよりは,忠実な僕であろうとすることに主体的に関わるのです。彼らの仕事ぶりは,几帳面,勤勉,堅実,綿密です。非の打ち所なく役目を果たすことに,彼らは使命感を見出します。仕事はすべて人との関わりを持ちますから,人に対して誠実,律儀,世話好きな性格が好都合に働きます。
彼らの厚い愛他的な性格と確かな仕事ぶりは,人に信頼され,敬愛されることになるのは当然といえば当然です。
それらは立派な処世の術となっているのですが,彼らが狡猾に見えることは決してないでしょう。人にそのように見られるとすれば,彼らには耐え難いことだと思います。行為の無償性が,彼らのもう一つの美徳といえます。だから人を出し抜いたり,争ったりということは決してないだろうと思います。誰の目もないところではずるく立ち回るなどということは,およそなさそうです。
彼らの自分への高い要求は,何に基づいているのでしょうか?
彼らの性格の根本問題は,個々の他者の眼ではなく,公共の眼のごとき高次の他者の眼を畏れ,敬うところにあるように思われます。それは個人的な他者への依存ではないので,確固としたものへの依存ということになり,彼らは容易には動揺しないのです。
彼らの思考や感情や行動の原理は,そのように公共的な他なるものへの高度の依存といえるものなので,身の回りのあらゆるものに優しく心を配り,場合によっては他人のために命をも惜しまないほどのものだと思います。
♪ しばしも休まず槌打つ響き,飛び散る火花や走る湯玉,ふいごの風さえ息をもつかず,仕事に精出す村の鍛冶屋・・・。
これは明治時代の小学校唱歌の一節ですが,ここには執着性格の特徴が表されているように思います。
明治時代は封建的支配から脱し,近代的統一国家への体裁を整える大激動の中にありました。文明開化の気運や自由民権運動の高まりなどがある一方で,政府の富国強兵策が浸透していきます。開発途上にある国家は,軍部による支配を目指すのは必然のようです。人民の不満の噴出をはじめ,激動期のエネルギーを抑え,かつ利用するためには,軍の力は欠かせないものでもあるのでしょう。日本国の富国強兵策は,モデル的な成果を上げたといえるようです。短期間に欧米列強と肩を並べる軍事力を育成し,産業革命を成し遂げました。産軍の興隆と人民の支配とが切り離せない統治策であったと,明治史は語っているように思われます。
小学校唱歌は,欧米の先進国に追随しようとする,当時の為政者の施策の一端でもあり,為政者にとって望ましい日本人像が,唱歌を通じて働きかけられているという色合いの濃いものだったと思います。
このような時代に,執着性格は,模範的な美質としてとりわけもてはやされた一面があります。公共的な意志とでもいうものに依存する「執着性格」の人たちは,為政者にとっては都合がいいという面もあると思います。
ところで執着性格が云々されたのは,うつ病の病前性格という観点からでした。
その性格特徴が,与えられた秩序の枠の中の規範的な価値を最大限に追求するというものなので,彼らが危機に陥る状況は,大きく分けて二つあります。
一つは,与えられた課題が大きすぎるということです。比喩的にいえば,負わされた荷物の重さにつぶされてしまうのです。
たとえ不寛容な心を持つ上司であっても,この性格的特長を持つ人たちには,上司は上司なのです。命じられた仕事は,家庭を犠牲にし,休日を返上してであっても応えなければならないのです。責任感が強い彼らには,役目を果たせないことは何よりも申し訳ないことです。その罪悪感は,例えていえば,最も頼りとする父親の期待に背いて顔向けが出来なくなっている様といえます。拠り所が自己の中にではなく,内なる公共的な他者(イメージ的に父親に通じるものです)にある彼らには,職責を果たせないということは,弁解の余地なく許されないことです。外なる他者は許してくれても,彼らの内なる他者は過酷です。そもそもが,その過酷さが彼らに規範的な価値への高い忠誠を要求したのです。彼らが自分の意志で,決意して自分に高い要求を出したのであれば,それは責任を取れる話です。しかし要求を出したのが,自己ならざる自己である内なる他者であれば,挫折したときに責任の取りようがありません。言葉を換えれば,問題を受け止める主体が不在であるに等しいのです。
いかなる場合でも,問題は受け止められないでいるときに,心は乱調の中にあります。そして更に乱調に陥ります。
危機的な状況のもう一つは,全身全霊を込めて奉仕をしてきた秩序体が,別種のものに変わるという事態です。具体的には,転居,昇進,転勤などです。折角作り上げたものを捨て,また一からやり直すのは,途方もない精神力が必要と感じるのです。
オリンピックで三連覇を成し遂げた柔道選手が,テレビの番組で,「四連覇を狙いますか」と質問されていました。それに対して彼は,次のように答えていました。
「監督に,練習の再開は年が明けてからするようにといわれている。今は練習を何もしていない。練習を再開してから身体の様子を見て決めることになると思う。三連覇に向けた二年間の練習の苦しさを考えると,年齢のこともあり,今は狙いますとはとてもいえない」
この選手はオリンピックの二年前の世界選手権で不覚を取っています。その口惜しさがばねになって,激しい練習に耐えてきたのです。
一流選手が目標を定めたあとの日常生活は,執着性格の人の完璧を目指す忠勤ぶりに似ているように思われます。
ただし,この選手が,「四連覇を狙うかどうかは自分が決める」と明言しているかぎり,うつ病に悩むことはなさそうです。執着性格の人は,「自分が決める」といういい方はできないように思います。
30代のある男性は,外出恐怖の悩みを持っています。外出中に不穏感が出てくる恐怖があるのです。ある日,薬を持たずに外出してしまいました。用心深くなっているので,外出するときには薬を携えるのが習慣でした。しかしこのときはどうしたことか,忘れてしまったのです。しかし,「まあ,いいや」と思い直しました(何かのときに,「まあ,いいや」と思えることは案外重要なことです。それは問題を受け止める気になっているという意味があるからです。不安に見舞われるかもしれないが,それはそれで仕方がないという気持がこめられています。ほどほどの感覚ではなく完璧な安全を求めるようであれば,その時点でパニックに陥ってしまうでしょう。多少の不安でも耐えられそうにないと感じれば,完璧な保証を求めたくなるのです。それがないかぎり,安心はないことになります。ほどほどのことは許そうという心が大切なのです。人間に完璧はないので,完璧を求める心は常に病的です。それらの心理を集約している言葉が,「まあ,いいや」です)。
「まあ,いいや」と思えたことが,薬ではなく,自分の力を信じようという気持に傾くきっかけになったようです。そのときから,外出の恐怖が和らぎはじめました。
近くに,結婚している妹が住んでいます。甥と姪がいて,彼は彼らに慕われています。妹に,兄の外出訓練を助けようという気もあってか,兄にその相手をしてやってほしいと頼まれていました。行けるときもあれば,行けないときもあります。行けるときでも,ウオークマンで武装するようにして,まっしぐらに,脇目も振らずに歩くのが習いでした。しかし薬に頼るのをやめてから,周囲の景色が自然に目に入るようになっていました。子供のころに遊んだときの情景が浮かんで懐かしんだり,民家のクリスマスの電飾をきれいだと感じたりしながら,歩けるようになったのです。
この話は,’元気になる’ということについて示唆するものがあります。
先にも述べましたが,それぞれの自己は,それぞれの固有の世界と共にあります。世界は,もろもろの物や人との関係で構成されています。この男性の例でいえば,妹さんのところへ歩いていく道すがらの歩いている道,周囲の景色,これから会うことになる妹や甥や姪,妹の家,周辺の民家,などなどが彼との関係において存在し,彼の世界を構成している様子が語られています。
不調の彼は,道も野原も小山も樹木も民家も,ほとんど心から排除されて,それらとの間で生きた関係にないという心的状況にあるといえます。それらの道や野原などからすると,主人公の自己から存在を無視されているに等しいことになりますし,心の側からいえば,闇の無化作用を受けて,それらとの関係が疎遠なよそよそしいものになっているともいえると思います。それに相応して,彼の心は不安に脅かされていました。関係があいまいになり,途絶化,あるいは無化することにより,彼の心は繋ぎとめるものを失って危うくなるということだと考えられます。
そして心が回復してくると,それらのものが一斉に彼の世界に戻ってきたといえるのです。それらとの関係は生きたものとなり,親しみを持つものとなり,そうした関係に繋ぎとめられて心が落ち着くことができたのです。
このように心が不調のときは,自己と自己の世界を構成するものたちとの間の生きた関係が損なわれているといえます。逆にそれらとの関係が改善されれば,心の回復が図られることになりますので,あえて自分の世界を構成し,支えているものたちに意識的に目を向けることは意味のあることです。それらは自分が存在し,生きていく上で大切なものであるのは明らかですから,生きた関係が保たれているときは,自ずから感謝の心が,特に意識はしなくても,それとなく流れているのではないでしょうか。健康なときに,暖かな心でいられるのは,そういうことの反映であるといえると思います。「物を大切にしなさい」といえば,現代ではうさんくさく思われるかもしれませんが,自分にとって大事なものを大事に扱わなければならない意味があるのは明白です。プロ野球の落合監督は,現役時代にバットを常に磨いて大切に扱っていたと聞いたことがあります。
自分の世界を構成している物や風景や動物については,それらとの関係を改めて確かめてみることで,心の世界の活力を導き出す意味を持つと思います。しかし人の場合は特別に複雑です。それだけに重要な意味があり,両親を中心とした鍵を握る人たちとのあいだの関係改善をはかることが,精神療法の要件です。
中年のある女性は,長年のあいだ,さまざまな程度のうつ状態がつづいております。
彼女にとって重要な関わりがある人が三人います。一人はおなじ敷地内に住む高齢の母親,一人は夫,一人は既に嫁いでいる一人っ子の長女です。
母親はおなじ敷地内に住んでいます。その母親に,亡父の墓参りに誘われました。その日,起きたののはお昼ごろでした。母親は,「一人で行くからいい」と怒って行ってしまいました。
母親には,すぐ近くに住んでいることでもあり,食べるものを持って行ったり,身の回りの世話をやいてあげたり,できるだけのことをしようと努めてきました。しかし母親は一向に有り難がらないのです。持って行ったものを,「要らない」と突っ返されることもあります。夜中に目覚めたときに,母親が無事かどうか,しきりと気になった一時期がありました。それは母親を思う情に違いないのですが,その裏返しの感情も潜んでいるかという趣がありました。母親に認められたい心が強く,それがいつかな適えられないので,怒りが潜在していてもおかしくありません。妹と母親との関係もあり,母親はたぶんに操作的,支配的で,母親との間の歪んだ依存関係が根本問題の一つといえるでしょう。
夫に対しては,結婚早々から不満が内向しています。会社が倒産したとき,保証義務がおよんで大きな経済的損失を余儀なくされました。夫はいま困難な病気と闘う身です。始終辛そうにしている夫に気疲れします。怒りをぶつけることもできません。特別食をいつも考える負担も耐え難いものがあります。
長女には手を焼いてきました。いいたい放題,したい放題の娘だったと思っています。いまは結婚し,子供も生まれました。たまに帰ってきたときは,母親の都合は念頭になく,子供を預けて夜中まで遊んでいます。
母親との墓参の約束を寝坊して果たせなかったあと,夕方まで眠りました。そして目が覚めたとき,無性に死にたくなったのです。死のうと思い,身の回りの物を整理し,遺書をしたためました。
しかし長女のことが目に浮かんできました。そして身勝手なことはできないと思ったのです。
彼女が自殺を考えるほどに追い詰められたとき,彼女の世界を支え,彼女を世界に繋ぎとめておく一切のものとの関係が途絶えかけたといえます。その背景には強い怒りが潜在し,それが一切の関係を断ち切ろうとする勢いを示したともいえると思います。自殺に走るのは,このように自己の世界を支え,自己を世界に繋ぎとめているもろもろとの構成的関係が終焉を向かえ,関係が死滅するときであるといえるのでしょう。
そういうときに,彼女の場合,長女との関係が蘇ったのです。そして,それによって生きる力が回復したのです。
統合失調症では,世界が貧困化します。誇大感を持つある患者さんは,芸術や学問の世界で超一流の力を発揮する夢のような話をしばしば語ります。その夢は決して実現されることはないでしょうが,それによって生きる支えを得ているのも確かでしょう。
統合失調症では,現実吟味力が問題にされます。どのくらい客観的な認識力が保たれているかという意味です。この力は,自我の機能の一つです。現実の上にしっかりと立っていないと,自己を正しく保つことができません。現実吟味力が病的に損なわれているとき,自我の機構に深刻な障害が生じている端的な表れであると考えなければなりません。現実に立脚することが困難であることと,関係性が広範囲に損なわれているということとは,おなじことの二つの表現です。それは,言葉を換えれば,世界が病的な変容をきたしているということになります。
これらのことを考えると,人や物など客観世界のもろもろのものとの間で生きた関係にある心は,文字通り生きているのです。個々人それぞれの世界は,主観的=客観的という性格のものであるといえます。
まったくの客観的な世界というのは,それ自体で自足する世界です。まったくの主観的な世界というものは,たぶん存在しないでしょう。こうしたことは,おそらく人間が自我を持つ存在であることに起因します。人間の誕生は客観的世界からの乖離という意味があり,そのときに自我が付与されたというふうに考えることが可能です。付与したのは何ものかというのは,人間の理性を越えた問題であるとしかいいようがありませんが。ともあれ人間を特徴づける最たるものは何かといえば,自我を持つものであることといえるでしょう。そしてその由来は,おそらく永遠の謎だと思われます。そしてまた,人は自我によって主観的な存在であり,かつ客観世界との関係を必須のものとしているといえるのです。心の内部の客観世界は無意識の世界です。比喩的にいえば無意識は海であり,自我はその上に浮かぶ小舟の船頭です。もっともこの海は,無限大の広さと深みを持っています。船頭の操船にあやしいものがあれば,船頭に期待されている予定調和が乱され,怒りが海を荒れさせます。それで更に船頭が操船に自信を失うと,海はますます荒れて子舟を呑み込もうとします。それが無化作用です。
客観的世界との関係を保ちつつ,自我に拠り自己自身であらんとする存在者,それが人間です。まったくの主観的世界は存在しませんが,自己自身であらんとすることに難渋すると,客観世界との関係が途絶に瀕することになります。その極端な様態が統合失調症というものです。そこでは主観的=客観的という関係に,さまざまなほころびが生じ,著しく主観に傾くのです。主観的自己が客観世界のものとの関係に繋がれていないと,自己はかぎりなく貧困化します。その病的過程では,自己がバラバラになりそうだという強い不安が訴えられますが,このような深刻な事態が進行していることに伴う不安であると考えられます。
客観的世界との生きた関係が確固としていることが,もう一方の主観的世界が充実しているためには不可欠です。それは人間という独自の存在者が目指すべき自立理念が,客観的世界への合流であることを示唆しているように思われます。そして客観的世界に属するものの性格は,汲めども尽きない豊穣性と,冷酷ともいえる沈黙であるように思われます。
心と世界が充実し,温かくなるのは,心が,この客観的世界の豊饒性に触れているということであり,心と世界が寒々として貧困化するのは,その接触が希薄化し,冷酷なものが前景に表われているということであるように思われます。
自我の出現以前の自然が,人間的に理解すれば,全(豊饒性)または無(冷酷性,沈黙性)であり,自我とともに自然から乖離された人間存在は,それ自体で自足する存在ではなくなったということになると考えられます。自我に拠る存在として,人間は主観的であり,かつ客観的であるという独自の存在構造を持つにいたったと考えることができると思います。
そもそもの自然は,その全体性という性格から全という豊饒性であり,かつ無という性格から冷酷性ないしは沈黙性でもあり,自我との関係においてはそれらのいずれもの様相が,さまざまな形で現前するということではないでしょうか。
さきほど,自己の世界を構成するものの中で,自己と物や動物との関係はシンプルなので,それらについて意識的になることで,ある程度の心の化粧直しが可能だが,人については複雑で別格であると述べました。
そのことを具体例に即してみて見ます
長期間,うつ状態から脱せないでいるある女性が,母親と激しい口論をしている夢を見たと報告してくれました。現実にはそういうことは起こったためしがないそうです。つまり彼女の意識では,「子供じみたところがあり,あまり母性的とはいえないとは思いますが」と控えめに批判しますが,母親との関係は穏やかなのです。
こういうときに,心の化粧直しは,より手の込んだ方法が必要です。つまり,意識はしばしば己をも欺くものなので,意識が捉えている母親や父親をはじめとした他者のイメージが,心にとっての真相を必ずしも表していないのです。意識が真相を隠そうとするのは,それが心にとっての影に所属するものだからです。
彼女の場合,怒りを強く抑圧していることがうつ状態の遷延につながっていると推測されます。意識的な心の内景は,母親との関係が穏やかなものということになります。そのかぎりではよい関係にあるということになりますし,物や動物との関係であれば,それで十分といえます。しかし人との関係ではまったく十分ではありません。
仮にこの女性の意識が,それなりの心の準備を抜きにして怒りの存在を捉えてしまったとすれば,心は大混乱に陥ると思います。自我が激しい怒りを受け止める勇気を持てないので,抑圧の手を緩めることができないでいるのです。それが生きている気がしないほどの抑うつ感の理由と思われるのですが,抑圧の手を緩めることができない自我は,おそらく自立には程遠いのです。父親ないしは母親の自我の支配を強く受けているので,彼女の自我は自分を助ける独自の働きを封じられているといえます。
彼女の場合,いわゆる対人関係の改善は,内的な両親との関係をあるべき姿に改変しなければ果たせないといえます。意識の上では穏やかな関係をひと掘して,彼女の自然の自我の機能を大いに混乱させられたことの怒りを,意識が明るみに取り出さなければ解決しません。それは必然的に親への怒りを表に現わすことになります。その筋の心理的作業を貫徹するには,自我の強化が果たせなければできない相談ですが,その勇気を持ち始めたときに,心の大混乱の彼方に新たな心の平衡が待っているといえます。
自立が理念であるというときに,その方向を指し示すのはどうやら自我ではありません。
自立の概念が成立するのは何を根拠としているのかといえば,人間は究極的にどこへ向かおうとしているのかという問いに発すると思います。人生は死によって終焉を向かえます。生と死のあいだには連続性がありません。そして死は人生の到達ではなく,生の回収です。生は自我の世界のものですが,死は自我の力のおよばない世界のものです。そのように考えると人生に究極的な到達点はなく,未完のままで終わる宿命の下にあります。死は自我の力を超えた世界のものであり,自我を無化し回収する力を持つものとして,自我を超越した,上位にあるものです。そうしてみると,自我が回収され,生が終焉を向かえるときに,人は,「人生は結局は虚しい」と考えるか,「これでいい」といいおおせるかの両極に分かれると思います。前者は闇に包まれてしまっている者がする影の思考であり,後者は自我が生きている光の思考であるということができます。
生に到達点がないことと,生が回収によって終焉を向かえるのは同じことのようですが,生があるべき到達点に向かおうとしつつ終焉を向かえるときには,「これでいい」という肯定的な気分になれるのです。この’あるべき’到達点への到達が自立というものであり,それは実際にそこに到達することはできませんが,指し示される朧な光として感じ取ることが,人によっては可能のようです。
はるか遠方に,朧にかすんで定かには捉え難い光を捉えるのは自我です。その発光体は,矛盾したことをいうようですが,自我の内部にあるといえるのでしょう。つまり自我が拠り所とする自我機構のうちに存在していると考えられます。自我は機能であり,自我機構を拠り所としますが,機構そのものは自我が作り出した作品ではありません。
結局,自立は自我の直感に訴える何かとして感じ取られることは可能ですが,現実には到達不能の理念であるということになります。
人間に可能なことは,自我が意識という光を機能させて目下の問題を探索することです。そして,その極限に達したときに闇の世界がはじまり,そこは人間の世界であって人間の世界を超えています。朧な光につつまれた自立の理念は,自我を通じて発光させる闇の世界のなにものかの意志であるようにも思われます。
その朧な光の根拠,ないしは自我機構の存在根拠は,自我と直接的に関わりつつ自我を超越しているものという性格のものであり,それを前章で述べた内在する主体と呼ぶことができるのではないかと考えます。
自立は自然に通じるものがあると思います。自然とは,自ずから然りということです。つまりそれ自体で自足しているということです。自立もまた,それ自体で自足しているということですから,両者には共通するものがあると思います。
自立は自我に与えられている課題です。自我は内なる自然である無意識に拠り所を持ちつつ,外なる自然に関わる諸々の現象としての自己の世界を構築していきます。そしてやがては自然そのものに合一するべく自己を導く使命を帯びています。それは果たしえない目標であり,ついには死によって人生は切断されることになりますが,精一杯生きるというのはそのように生きることだと思われます。何事も精一杯生きることはいわば理想です。何らかの目標があり,それにかなう能力への信頼があるときに,そうした最善の生きる姿勢が得られるのです。自分を信じていなければ,目標があっても行動は伴いません。自分を信じていられるときは,自分の自然に触れているときです。何事によらず,自然が一番よいのですが,自然そのものを生きることができないのが人間です。自然的に生きるのは難しい課題です。しかしそれを求める心があれば,そこに近づくことは可能で,そのときにたぶん満足のいく充足感があることでしょう。
人が自然的な生き方ができる拠り所は,内なる自然にあります。関わりを断ち切るわけにはいかない重要な意味を持つ他人たちによって,一途に心の自然を混乱させられるのは皮肉以上の不可思議ですが,それが現実です。その不自然となった心を,内なる自然を拠り所に,改めて自然に立ち返るのが人生です。そのことの手がかりは夢が与えてくれるかもしれません。夢には内なる自然の叡智が表われる可能性があるのです。そのことからも闇の世界である無意識の領域は,自然そのものが心に関与しているものであると考えられ,そこには人知を越えた叡智が沈黙のうちに存在していると考えてよいようです。
自立が自然の特性である完全性を持っているのに対して,自我に拠る人間は不完全な存在です。であればこそ,完全なものである自立を理念とするのです。,
人間存在の不完全性は,心の二極構造として表われています。自己が存在するためには他者の存在を不可欠のものとしていますが,他者は外的な存在にとどまらず,自己の構造に内的に含まれているのです。
私が男として存在しているということは,自己の構造として他者を内に含み,異性を内に含んでいることになります。完全なるものを希求するものであるらしい自己存在は,自己の構造に他性を含み持ち,それによって外的な他者,および異性との関係が不可欠なものとなっていると考えられます。かつまたその一方で,それら外的な他者,異性と結局は一体のものとなることは不可能であり,自己は不完全性を克服し得ない存在なのです。
自己の内的な構造として異性や他者が含まれていることにより,外部に存在する彼らが,外部からの観察と学習によって初めて理解可能な異星人のごときものではなく,経験以前にそれらの存在を了解しているといえます。
それらのことの根本には,人間が自我を持つことによって人間であることに伴い,自我と無意識との二極に分離して心が成立している存在であることに関連していると思います。つまり人間の誕生というできごとは,自我と無意識との二極に分裂した存在として,自然から乖離したものが世界に登場することであると考えられますし,死によって自我と無意識の両者が再び合体したときに,自然に帰還することになるというふうに考えられのです。
ともあれ,いかなる叡智が人類を生み出したのかは知るよしもありません。しかしたとえば夢において,日常の思考系列からすると啓示のような考えが現に見られるのであり,それは自然の叡智とでも呼びようがない思考のひらめきです。そのことからしても,人間は無目標のまま放り出されたというようなものではないように思われます。人生は難解そのものであり,その生誕と終末との謎を解き明かす力は人間にはないといわざるを得ません。漂流するかのような人生があります。極悪人も存在します。病気という心の破綻もあります。人生の舵取りはしばしば困難を極めますが,それでも心の奥底に耳を傾ければ,意味深いつぶやきが聞こえてくることも可能です。それが生きる方向を指し示す力として感じ取られたときに,自立の方向が朧に感じられたということであるのかもしれません。それは分かる者にだけ分かることなのでしょう。
いずれにせよ自我の認識能力がすべてではないと思います。それを超えたものがあるのは明白ですから,自我万能主義は愚かな迷妄というしかありません。そこからは,「人生は結局は虚しい」というつぶやきが聞こえるばかりだろうと思います。自我を超越したものが存在しているのは論を待たないので,その前に頭を垂れる謙遜こそが人間にふさわしいといえるのではないでしょうか。自分よりゆるぎのない上位のものが存在することを認めることは,その前に自然に頭を垂れることが含まれるはずで,これ以上の豊かさ,喜びはないといって決していい過ぎではないでしょう。
自立理念は,それに向けて現在の自己を脱し,より好ましい自己に改変していく方向を示すものです。好ましい自己の方向とは,いうならばダルマへの道です。自己の重心が自己の真ん中にある感覚です。なにか痛切な出来事があって,自分を保つのが危うくなっても,ほどなく傾きかけた心の態勢を立て直すことができるための拠り所が,自己の内にあるという感覚です。
現実に,人は何事かに依存しつつ存在します。自己があるということは,同時に,それは何事かとの関係で存在するということです。その関係の連鎖の先には,他者との関係があります。自己が存在するということは,結局,他者との関係として存在するということです。
人間を特徴づける自我は無意識の力に依存しています。それが,自我に拠る人間が,基本的に依存的な存在であることの根本理由かもしれません。依存は一般には相互的なものですが,自我と無意識に関してはそうではないと思います。無意識の中でも,個人的無意識(ユング)と自我の関係は相互的です。しかし集合的無意識は人間の心の内部にある自然であり,全という性格を持つものなので,自我が一方的に依存する関係にあると考えるべきだと思われます。
先に述べたダルマ的な心の中心という意味は,拠り所としている無意識の力と接触している感覚であるように思われます。人は他人との関係に依存しますが,それは必ずしも他人が信頼に値するという意味ではありません。それは,また,別問題です。他人は力を貸してくれることもあり,しばしば裏切りもします。ですから他人との関係に自己の命運そのものをかけてしまうのは,大変危険です。自己の重心がむしろ他者にあるときに,精神は病的に不安定になりがちです。他人の裏切りにあえば,ひとたまりもなく自己は傾きかねません。いうならば他人しだいの人生になってしまっている人は,現実に決して少なくないように思います。彼らは,他人によってわずかな打撃を心に受けるだけでも,しばしば深刻なダメージが残り,容易には回復しないのです。
しかし自己の重心が自己自身の中にあれば,心に打撃を受けても,ダルマのように態勢を立て直すことができるのです。
自己の重心の本来的なものは,心の内なる自然である集合的無意識にあると考えてよいと思います。その自然が自我の機構に及んでいると考えられ,それとの関係に自我が直接的に拠り所とする首座があると考えることが可能だと思います。その自己の本来的な拠り所と思われるものを,内在する主体と呼びたいと考えます。
この主体との関係が好ましくはかられている状況にある自我の下にあるとき,心はダルマ的に安定し,関係が好ましくないときに心はダルマ不在,もしくは他者への悪しき依存ということになると考えられると思います。
Pさんは40代後半の主婦です。夫と長男,長女との4人家族ですが,長男は一人暮らしをしています。地方都市で大きな割烹料理店を営む両親の下で育ちました。母親は優しい性格といいますが,夜遅くまで店の仕事があるので,朝は遅くまで寝ているのが日常でした。当然のように,幼いときから,毎朝幼い弟の分と二人分の弁当を自分で作って学校へ行っていました。家には住み込みの従業員が大勢いて,いつも賑やかでした。弟は寂しい思いをして可哀想だったといいますが,本人自身は大勢の人に可愛がられて仕合せに暮らしていたそうです。
ずっとよい子だったといいます。母親が忙しい姿を見ていたので,たいていのことは自分でしていました。気分がすぐれないときも,面には出さず,元気そうに振舞っていました。
高校を卒業した年に,東京の大学に入りました。寂しい日々で,寮の自室に閉じこもりがちだったようです。
20代前半で,学生のころから交際していた男性と結婚しました。夫は優しい性格で,これ以上いうと嫌われるかなと思いながら,思いのたけをぶちまけることもしばしばでしたが,常に優しかったそうです。その夫より自分が上位にいるような気分もあったといいます。夫には社会的な地位があるので,その妻である自分が誇らしくもあり,惨めなようにも感じていましたが,「私がいないと家庭がまわっていかない」という自負心を持っていました。
育児は生き甲斐を与えてくれました。元々手を抜けない性質ですが,常に良い母親でありたいと考えつつ,我ながら一所懸命にやったと思っています。しかし子育てが終わり,子供たちが成長していく姿を見ていると,自分だけが取り残されていく焦りと不安を感じるようになりました。
舅が死んだあと,姑を引き取り10年間生活を共にしました。最後の2年間は痴呆症になり入院しましたが,毎日のように見舞いに通いました。夫に負担をかけたくないと思い,休日も,「いいから休んでいて」といっていました。
難しい性格だった姑が死んで,数ヵ月後に初診となりました。そのころはしばしば落ち込み,何につけ自信がなく,夫に八つ当たりしがちになっていましたが,発端と思われる問題は,姑が亡くなる2ヶ月ほど前に起こりました,帰宅した夫の顔を見たとたん,居ても立ってもいられない気分に襲われたのです。
Pさんの通院は数年におよびます。一進一退ながら徐々に動じなくなる方向に向かっているといえます。
Pさんの問題は表面を見ればうつ病ということになりますが,依存的な性格がより根本の問題です。つまりPさんはダルマ性に程遠い性格といえます。Pさんを支えるのはPさん自身ではなく,夫と長女です。なかんずく夫であり,夫を支配しつくさないと安心できないのです。
育児と姑の看病は,Pさんにとって頑張りどころでした。自分の価値を示すよい機会でした。模範的な良い母親,良い妻というのがPさんに与えられた課題です。その課題を与えたのは,おそらく母親と父親です。実際には両親がそういう指示をしたわけではないのですが,Pさんが両親の覚えを確かなものとするために必要な,無意識的な戦略であったようです。夫の帰りが遅く(接待が多いのです),長女もまだ帰宅していない一人でいる時間に,見捨てられたような不安,寂しさがあったと,あるとき述べております。
芸妓もまじえた大勢の人がのべつ出入りする環境の中で,Pさんは実際にみんなに可愛がられていたようです。Pさんはずっと良い子だったと思うと述べています。そういう事情を見ると,一見なに不自由なく恵まれた環境に育ったようであり,Pさん自身がそのように認識しております。両親が家業で忙しいのを目の当たりにしているので,我慢して当たり前という生活状況でした。それだけに,いっそうPさんには両親を困らせないようにする理由がありました。しかし良い子というのは,大きな自己犠牲を払わずには成り立たないものです。幼い子の心の自然の欲求が満たされなかったと思われるのですが,それがPさんの心に残った寂しさと依存心と支配欲の源泉と考えられます。どんなに大勢の人に大切に扱われても,両親は別格です。両親,なかんずく母親に見捨てられる不安は,すべての赤ん坊に共通する本源的なものといえます。それを甘えによって和らげていくことが心の成長には必須といえます。Pさんは,大いに恵まれた環境に育ったともいえますが,肝心な一点で欠けるものを持っていました。
「なんでも一番でないと気がすまないところがある」と控え目なPさんが何度か述べております。幼いころに自宅が新築されたときに,弟の部屋の方が大きかったのが口惜しかったということです。元気だったころには,夫を下に見ていたといっておりますし,夫が昇進すると誇らしく感じる一方で,自分が置いてきぼりにされるようで不安だともいっております。夫が接待で女性の多い場所に出入りすることが多いようですが,若い子の話をされると,嫉妬とともに自分は不要といわれているように思えます。私がいるとどうせ邪魔なんだろうと,家族旅行をキャンセルしたこともあったといいます。
Pさんの性格は,明るく,穏やか,優しく,親切といったふうな好ましいものだと思います。特に無理をしてそのようにしているとは思えません。それがいわば表の人格です。一方,裏の性格には,人に認められ,受け入れられないという大きな不安があります。そこには裏の性格につきものの大きな怒りが潜在していて,その怒りが,当然の欲求を満たされることがなかった理不尽さにからんできます。それは母親には私が可愛くないのか,不要な子なのかという不安と不満でもあるはずです。
夫は優しく,受容的な人のようで,依存する相手が切実であるPさんには,自分を託すにはこの上もなかったようです。その夫を,Pさんの無意識は支配しようと考えたようです。自分が受け入れられない不条理と,それに伴う怒りとが裏の性格を彩っています。従来は,そのつもりがなかったでしょうが,抑制に抑制を重ねてきたので,大きな怒りと不満とが,お門違いともいえる夫に向けられたのだと思います。その不条理も知っているので,Pさんはしばしば懊悩し,落ち込みもします。それが表の性格をリードする自我の悩みであり,力不足でもあるのです。そして内心の不満と怒りとに煽られる裏の性格が,安心のできる夫に,いわば完璧で,全的な受け入れを求めるのです。
このような表の自我の力不足が,裏の自我の強い要求を引き起こしているのですが,両者のあいだの葛藤がPさんの病態を招いているといえるでしょう。両者の綱の引き合いで,ときには気分が晴朗になり,ときには不安と憂鬱と苛立ちになるのです。
悪しき依存には怒りが介在します。それはしばしば無意識です。怒りをつよく抑圧した依存(本人には怒りは意識されません)の状態にあるとき,依存する相手に絶対的な忠誠心を持つことがあります。その極端な例は,昨今問題になっている虐待に見られます。命が危ないほどの目にあっている子が,第三者が救助の手を差し伸べようとしても,十人が十人,放って置いてほしいというそうです。
子供の方が怒りをあらわにし,親に暴力的になる形の依存もあります。この問題もしばしば深刻ですが,怒りを表せない依存は問題視されにくいことが多く,こちらも同様に深刻です。怒りを出せないのは,当然,恐怖や不安からです。恐怖や不安を持ったために”物言わぬ子”になってしまうのは,ごく幼いときに問題の発端があったからでしょう。心身がある程度成長し,それなりに力を自覚するようになってからは,いわゆるPTSDにつながるような特殊な状況下ではともかく,滅多には”物言わぬ子”にはならないだろうと思います。
人間の誕生は,自我に拠る世界の幕開けです。何によってか,人となるということは,自我が付与されることによってということです。自我は,それぞれの個の世界を切り開き,構築していく上で必須のものです。また,自我が付与されたということは,自分の責任で生きなさいという意味が含まれています。赤ん坊にはそんなことは分かりようもないでしょうが,しかし,無意識のどこかで地獄のような人生を背負わされたと感じているかもしれません。胎児以前の自然の一部であった時代は,苦楽はもとより,一切の意識が存在せず,従って永遠の沈黙の中にあったともいえるのでしょう。それがいかなる理由によってか,永遠の沈黙の世界から乖離されたのです。それが自我に拠る人間の誕生です。生まれ出るものは,人々に喜びをもたらします。それは人間が自我によって生を切り開く使命を帯びており,自我は光の世界の演出家であるからです。光をもたらすものは,自我の世界への参入だからです。そして生まれ出た赤ん坊はどうでしょうか。光を知るものとして歓喜するでしょうか?それはおそらく違うと思います。光を知ることは闇を知ることでもあるからです。赤ん坊に光も闇もないかもしれませんが,人間の誕生ということは,光と闇の世界の始まりということですから,赤ん坊が何も感じないと考える根拠はありません。赤ん坊が驚愕と怒りの中にいるとしても不思議はないと思います。後々,そういう記憶が感覚として残っていないという証拠もないと思います。
人間の誕生はいずれにしても並大抵のものではありません。
児童心理学の研究者でもあったイギリスのメラニー・クラインによると,生れ落ちた赤ちゃんは激しい怒りを持っているということです。おそらくは安全で心地よかったはずの母親の胎内からいきなり放り出されるのですから,途方もないことといって過言ではないでしょう。いずれにせよびっくりもし,怒ってもいて当然のように思います。
出産とは,赤ん坊に成り代わって想像的に大人の言葉で表すと,不安,恐怖,猜疑,怒り,寄る辺なさといった大きな感情を伴う体験ではないでしょうか。
そのように激しく傷つく心は,万能感といわれているものによって守られていると考えられています。「大きな力で守られているのだから大丈夫」という感覚です。それを満たす立場にあるのが,誰よりも母親です。しかしいうまでもなく母親の力は万能ではありません。ですから胎内にあったときに匹敵する安全感と満足感を求めるだろう赤ん坊の激しい欲求は,たえず裏切られないわけにはいかない宿命の下にあるのです。その欲求を母親が満たしてくれるときには至福の感情を味わい,満たされないときには激しい怒りの虜になるのです。
赤ん坊の恐怖は,闇を感覚的に意識するからではないでしょうか。それは自我という光のものを持つことに伴う必然です。そして光は生世界のものであり,闇は死の世界のものです。生まれたばかりの赤ん坊にして,生と死を過敏に感じ取るのではないかと想像されます。
赤ん坊の不安は,闇または死を感受することにあるように思われます。その恐怖を和らげ,安心保証をする役目を持っている母親が,赤ん坊の欲するものを与えてくれていないと感じるときに,赤ん坊は激しく恐怖し,怒りを持つと思います。怒りは保証を求める叫びでしょう。そして赤ん坊が自分の怒りの投影を,母親の表情の上に見たとき,母親が世にも恐ろしいものに見えることがあると思います。場合によっては悪鬼のように見えることもあると思います。そういうときには怒りが麻痺し,恐怖であらゆる感情が抑えられるかもしれません。
そのようにしてよい母親とわるい母親とが交互に現われ,それがやがて一人の人物として統合的に認知できるほどに自我が成長していきます。
乳児はまったくの依存の中にいます。絶対的な依存の対象を必要とします。胎内にいるある時期までは,自然の特性であるそれ自体という存在形態でしょうが,生れ落ちると同時におぼつかない自我を保護し助けるものが必要です。依存の絶対的な対象を必要とするということになります。母親の胎内での安全感に匹敵するものが求められ,それが先ほど述べた万能感という幻想です。ここに依存の原型があります。
万能感が満たされたときによい母親が体験され,満たされず怒りに駆られるときにわるい母親が体験されるというふうに考えれば,依存にもよい形とわるい形とがあることになると思います。よい依存は,自分が愛され,認められているという自我意識の形成に寄与することでしょう。それは自分は自分を愛している,認めているという健全な自己愛の形成にも寄与するはずです。そして自立へと向けた心の動きにつながります。わるい形の依存は,自分は愛されてはいないのかもしれない,認められていないらしいという恐怖,猜疑を伴う感覚的意識で,自分でも自分を愛せない,認められないという自我意識に発展すると思います。そうであれば人間に必須である自己愛の健全性が傷つけられることにもなると思います。それは自立するための基盤を危ういものにすることになると思います。
これらのことはだれもが程度の差はあれ置かれている,あるいは置かれざるを得ない人間の宿命的な姿ともいえるでしょう。強い自我に恵まれた人であれば,こうした心の逆境(悪しき依存に伴って,それを助長する体験が集積されて,心の暗部に得体の知れないものが沼のようにたまります。それは心の内側からおびやかされる原因になります)に悩まされながらも,立ち向かっていく力を発揮することがあります。大きな仕事をなしとげる人は,むしろいま述べたような心の重圧をかかえていた人たちといえます。自分の内部に鬱屈した問題を抱えてしまったために,真剣に人生と対峙し,人生を模索する人は強い自我の持ち主です。しかし多くの人の自我はむしろ弱く,人生と対峙するよりは回避する傾向が強くなるのは否めません。
ある不登校の高校生の例です。
新学期になれば学校に行けると思うといっていましたが,実際には行けていません。学校に行かないことを除けば,何事もないかのように過ごしています。友達とディズニーランドへ遊びに行ったりもします。
しかし朝は,蒲団をはいでも起きようとしません。母親には理解ができず,苛立ちがつのります。
学校に行けないはっきりした理由は,本人にもよく分かりません。積極的に行きたくない理由が学校にはありません。
学校という管理された社会と個人の自由な世界とで,この子は別な顔を持っています。母親の苛立ちは,人としての義務を遂行せず,わがまま勝手に生きているという類の怒りに発しているようです。そんなことでは大人になって落伍者になるという不安でもあるでしょう。確かに,それぞれが大人になったときに,自立的な人生を送ってもらわなければ困ります。母親の不安を解消するには,自立した大人に向けてのプログラムが見えたときといえるかもしれません。
この子の母親が安心する自立とは,依存から脱出しつつある傾向が見えるということでなければならないでしょう。しかし実際には,母親が心からそういうことを望んでいるかは疑問です。ふだんは元気にしていて,なぜ学校に行けないのかという母親の思いが間違っているとは思いません。ただ,ふだんの気楽そうな生活ぶりに幻惑されてか,学校へ行くか行かないかというレベルで苛立っているのは問題です。というのは,なぜという問いを,子供の心に即して発していないからです。母親は自分自身の常識の中から出ようとせず,その常識の高みから子供の行動を批判的に見ているのでは,依存の中にいるからこそであるに違いない不登校問題の核心は見えないだろうと思います。自立が問題であれば,依存の形を見なければなりません。それは子供の行動を,批判的に見ることによって得られるものではないはずです。それが問題であれば,母親は子供の問題に関して,自分自身を見つめる必要があるのです。それはたぶんに母親自身の問題だろうからです。そういう発想ができていないことが,そもそも母親の養育姿勢が,自分の思考や感情から子供の行動を批判的に見,かつ指導する体のものだっただろうことを暗示しています。つまりそれは,母親一般が実にしばしば陥るものである,子の世界へのぶしつけな侵入であり,干渉であるだろうということになります。そしてまた,それは子供が持っている力を信じようとしなかったということにもなるのです。子供の立場からすると,母親が望むようになるしかないのです。それは悪しき依存の形を作る典型です。
そうして見ると,母親の苛立ちは,自分の思い通りにいかない子供に対して腹を立てている以外のなにものでもありません。
子供は心の根っ子のところで,母親に信じてもらっているという安心を得られなかったと思います。これは不登校児にかぎりませんが,なんらかの心理的なつまずきに至っている子に,共通して見られる問題といえます。
乳幼児期に母親から母親本位のではない愛情を受けることができず,従って信頼を受けていなければ,自分は人に信じてもらえないという基本的な不安をかかえることになっても不思議はありません。そうすると自分は駄目な子で,人に受け入れてもらえない性格だという考えに直結することになります。
この子の場合も,級友たちに受け入れてもらえない不安が強いのです。本人もそう思っています。
本人の問題を解決するには,母親自身が変わらなければなりません。
この子の場合も,乳幼児期にどんな体験をしてきたかは誰にも知ることはできませんが,以上のように見ていくと,おそらく母親の養育姿勢は自分本位ではなかったかと想像するだけのものがあると思います。母親が子供の自然な能力を大切にしようとせずに,母親の思い込みどおりであってほしいと望んで育てたとすると,子供の心の自然は混乱させられるのは必至です。母親の介入によって混乱させられた心的状況では,乳幼児期の自然な欲求は,自覚がないままに無意識界に抑圧する以外に,母親との関係は保てないことになるのです。そしてその分母親の自我に従うことになり,本人の自我の成長は阻害されることになるのは避けられません。それは悪い形の依存ということになり,それに伴い,抑圧された影の分身たちがしだいに大きな勢力になっていきますし,いつまでも日陰者のように抑圧されたままでいるしかないことにもなります。それは影の性格とでもいうべきものとなり,表の自我を脅かすことになっていきます。
これらの日陰者たちが勢力をつよめることになったそもそもの理由は,自我が本来求められている指導性を発揮するに足りる力を示すことができなかったところにあります。そしてそうなったことについては母親の干渉があったので,母親に依存する分,自我は無責任にもなるのです。その結果として影の分身たちが裏の性格といえるほどに勢力を増すのを許してしまっている今となっては,ますます自我の手には負えるものではないのです。自我は無責任に,触れずに済ませたいという態度になるしかないといえます。
この子に即していえば,学校に行こうとするのは表の自我の役目です。その力が自律的に伸びるのを奪ったのは,どうやら母親のようです。本人は,学校へ行けないのは反抗もあるといっております。自我の力不足が学校へ行けない直接の理由ですが,そこには母親の関与が大きく働いているので,反抗という側面はあっておかしくないのです。
母親は,良い子を求めてきたということになりますが,それが仇となって,表の人格形成の成り行きとして,学校へ行けない’悪い子’にしてしまう結果を招いてしまったことになります。また,「学校へ行きもしないで平気で遊んでいる」というのも,母親の観点からすると悪い子ということになります。これは裏の性格によるということになると思います。本人の場合,悪というほどのものではないので,友達との関係,明るい遊びという’逸脱行為’にとどまっているのですが,裏の性格に基づいたものの中には,悪の性格の色が見える場合も少なくありません。
断っておきますが,一般論として子供が学校へ行かないのが悪い子というわけでは,勿論ありません。
ここで事例として上げたお子さんについて,母親の価値観からすると悪い子になってしまっているということですが,母親が自分の望みどおりに子供をしつけようとすることも,悪いことといえるのです。
それにしても,社会性がないと将来が案じられるという現実があります。学校に行かない「悪い子」であっても,芸術的な才能なりがあれば,あまり問題になることもないでしょう。要は,その子が一生を託すにあたいする拠り所を持つことができればいいのです。特殊な才能に恵まれることは稀なので,一般には自分の力を信じることができているのが望ましい拠り所になるのです。そのためには,学校へ行けないでいる現実を,母親が容認する必要がまずはあるでしょう。
かつて作家の野坂昭如氏が,「子供は生きていてくれればそれでいい」と語っていました。この言葉につきるのではないでしょうか。現にある我が子のありようは,良いも悪いもないのです。それはそっくり容認されるのが原点であり,出発点です。親が容認することは,本人が自分の現実を認め,受け入れていくのを助けることになるのです。いずれにせよ,自分を助けることができるのは,自分自身しかありません。親はそれを側面援助できるばかりです。本人の自助の努力に水を差すようなことをしなければいいのです。
自分の力を自分自身が信じることができれば,他人は怖くなくなるでしょう。学校へ行こうが行くまいが,他人が怖いという理由は排除されるでしょう。
悪しき依存は心の障害の欠かせない前提のようなものです。それは精神を試練に立たせます。克服して自立の方向へ向かうことができるか,さもなければ様々な形でつぶされてしまうか,あるいはいやな気分を紛らわせるために気晴らしの日々を送るか,人生を分けるものでもあるでしょう。
性格形成に与える母親の影響-その5
■見捨てられる恐怖
見捨てられる恐怖は,「境界性人格障害」に固有の病理といわれることがありますが、この問題は、むしろすべての乳児が経験する心理特性であるというべきです。つまり、いうならば、人間が人間以前の存在形態から、人間存在へと移行する過程での通過儀礼ともいえるものです。
人間は誕生という形で、あるとき、いきなり個の人間として世界に登場するのですが、人間存在の著しい特徴は、生の個的な開拓者として、既に死を背負う宿命の下にあるということです。後にも述べることになりますが、死は無意味の代名詞ではなく、生の欠かせない対立軸と考えることができます。
つまり力強く生きるためには、意志によって限定化された可能性と、それを阻み、空無化しようとする不可能性とが対立し、せめぎ合う必要が欠かせません。
喩えていえば、算数の苦手な小学三年生にやる気を出させるには、容易に解ける二年生の問題をさせつづけるのも、初めから無理と分かる六年生の問題をさせるのも愚かしく、出来るか、出来ないかというところでせめぎ合わせることに意味があるのとおなじです。
この意味で、生を受けた者の必然として死を背負うので、赤ん坊にしてもその矛盾に満ちた現実に立たされるのです。
そして母親は、赤ん坊にとって‘全’の役割を担っています。
赤ん坊は、次のような気分的なメッセージを母親に向けて発するでしょう。
「あなたは完全な満足と完全な安心とを与えてくれる力を持っているはずです。そうでなければ私の存在は成り立ちません」
ある意味での臨床場面では全員に共通して見られる根本問題の一つです。診療に訪れる患者さんが直接この恐怖を意識していること はむしろ稀ですが,症状的なものが表面化する理由の根本のところにこの問題が関与しているのです。もっとも,この問題は心の病理的なものに悩むことになってしまった一部の人にだけあるのではなく,心の成長過程の最早期に,この恐怖を経験しない乳幼児はないといえる性格のものだろうと思います。ですから人間に普遍的にある心性といって間違いではないと思います。
一般的にも,日常心理のいたるところにこの恐怖は顔を出します。人に会うときの緊張もそうです。親しく信頼のできる人に会うときは,あまり緊張はしないでしょうが,目上の人,密かに思いを寄せる異性,嫌いな人,あるいは自分が嫌われている人などなどに会うときは,たいていは緊張を強いられます。
自分が愛されているか,受け入れられているかということに,多くの人がこだわりを持つものです。
この問題の基本概念を,E.Hエリクソンが「基本的信頼感」と呼んで提唱しています。エリクソンは,この概念は大人の精神病理学から学んだものだと述べております。その論旨は次のようです。
他人や自分自身とうまくいかなくなると,自分の中に閉じこもってしまう。自分の部屋のドアを閉め,食事や慰めを拒否し,交友関係を没却してしまう。彼らが根底的に欠如しているもの,それは,彼らに精神療法を施すときにはっきりしてくる。つまり,我々は彼らを信頼していることを信じてよいのだということ,および自分自身を信頼してもよいのだということを確信させる意図を持って彼らに接近しなければならない・・・そのように退行している患者の最も幼児的な深層部に接しているうちに,我々は基本的信頼というものを,活力的なパーソナリティの隅石とみなすようになった・・・そういう観点から逆照射して,病的に退行している人の心が,基本的信頼の根底において損傷しており,基本的不信感に陥っている・・・。
基本的信頼感は,赤ん坊が生まれて間もない原初の段階で,母親とのあいだで,母親主導で確立されることになるものです。安心と満足とを貪欲に求める赤ん坊とのあいだで十分な信頼感が醸成されるためには,母親の安定した愛情が頼りです。育児にかかわるこの過程で,母親の愛情に不安定なものがあれば,あるいは赤ん坊の側に特別に過敏で混乱し易い生物学的な事情があれば,赤ん坊の満足と安心は脅威にさらされることになるでしょう。見捨てられる恐怖が体験されるのはこのような母子の関係においてですが,完璧な母親があり得ない以上は,多かれ少なかれすべての赤ん坊が脅威にさらされることにならざるを得ないと考えられます。
ですから基本的信頼感といっても,その程度は個々にさまざまなのはいうまでもないことです。
人と自分とを信頼し,愛することができるための一定の礎の上に,人は成人として社会の一員に足りるように両親に躾けられ,学校で集団的な訓練を受けます。社会の中でときどきの集団の一員としての地歩を占めることができるためには,なかんずく他者との関係を円滑に営める能力の開発が必要です。他者愛と他者を信じる能力が一定程度そなわっていれば,更に重要な意味を持つ自己愛と自己を信じる力も,ひとまずは,それなりにそなわっていると考えてよいと思います。
いま述べた世間向けの顔ともいうべきものは,ペルソナと呼ばれているものです。ペルソナという対人的な一種のテクニックを身につけるための基礎が,基本的信頼感であるといえるのでしょう。
ペルソナの命名者であるC.Gユングは,このことについて次のように述べております。
非常な苦労の末にようやく実現されるこの集合的心(個人の特徴を離れた一般的,普遍的に見られる心)の一切を,私はペルソナと名づけた。・・・ペルソナは,もともと役者がつける仮面で,役者が演ずる役を表している。・・・個人と社会とのあいだに結ばれた一種の妥協である・・・。
つまりペルソナという仮面を身につけることと,それを形成する礎である基本的信頼との確かな醸成がなければ,人は社会的存在として危ういものになるのですが,一方ではそれは本音を隠すものでもあります。その意味での本音とは,社会性とは相反する性格を持つものに違いありません。
おびえ,ひるみ,恐怖,不安,怒り,敵意,妬み,恨みなどなどの感情は,ペルソナによって覆い隠されることになるものですが,これらの対人関係を不安定にさせる感情の根底に見捨てられる恐怖があると考えられます。この恐怖には強い怒りも伴いますので,仮に日常的に’本音で’人と対さなければならないとすると,いわば血みどろの闘争の日々になることでしょう。それでは人間社会そのものが成立しなくなってしまいます。
ペルソナは建前であり,本音を隠すものでもあるのですが,本音は滅多なことでは人に明かせませんし,滅多なことでは明かしてはいならないものでもあります。
見捨てられる恐怖が母親との早期の関係で緩和されていなければ,ペルソナによって装われた自己は内側から脅かされ,自己を保つことが危うくされかねないのです。そうなると自我は防衛のためにペルソナの仮面性を過度に強化し,場合によってはいわゆる心の硬い人ということになるかもしれません。
ペルソナを身につけることの主要な意味は,一般的な人々に受け入れられ,それなりに愛されるに値する性格の形成です。「私は社会でのしかじかの役割と責任を負っています。それをまっとうする力を培った人間です」というメッセージがペルソナに彫琢されます。また彫琢されるべく日常生活を励む必要があります。それは社会の一角に自分を位置させるために不可欠な努力であり,人を安心させるためのものです。しかしペルソナの出来栄えに神経質すぎる人は,ペルソナの仮面性が逆に面に表われてしまうでしょう。それは仮面が心を隠すという意味があるからです。感情を過度に押し殺すと,「能面のような顔」になってしまいます。そこには自己というものの表出が見えなくなっているのです。人に見せられない自己というものは誰にでもあります。意識下に抑圧されている影の分身たちはそういう性格のものです。しかし他人が,なぜそんなことが人に知られたくないのかといぶかしむようなものまで影の分身としてしまっている人は,「何を考えているのか分からない人」,「感情のない人」として敬遠されることになりがちです。ペルソナの彫琢が神経的に過度にわたると,魂が見えない顔になってしまいます。
ペルソナの完成は,自己の完成ではありません。それはまったく別な次元の話になります。それは人を安心させるため,見ようによっては人を欺くための仮面ですが,自分自身を本来的に満たしていく心の作業は,仮面の影に隠れているものを自らあばきたてることによって可能となるのです。いわば仮面の持っている嘘にあきたらず,あるいは偽りの自分であることに不安をかき立てられる人には,真実の自己の探索へと向けた心の旅が現実の目標になるかもしれません。これは大きな行為です。この心の作業,あるいは行為をまっとうするには,強い自我が要求されます。自我が弱ければ,あるいは自我の機能が衰弱すれば,自己と人生とを見失う危険がはらまれています。ですからペルソナに安住している大方の人は,見て見ぬふりをすることになるものです。その意味でペルソナの達人は,ごまかしの達人でもあるのです。
心の病は,いわば偽りの自己と真実の自己とのあいだの矛盾,葛藤の緊張に耐えられず,心にほころびが生じたものといえなくもありません。自己を創出するための演出者は自我ですから,自我が,演出者としての能力を無意識界にある身内から批判されて立ち往生してしまった図ともいえます。そして真実の自己を追究する心の旅に出る人にとっても,その先導者はやはり自我ということになります。この大仕事をするためには,自我が十分に力をつけていなければ出来ない相談です。
また,心の病に悩む人はペルソナの達人とはいえない人たちです。自我が強いとはいえず,ごまかしが利かない人が心の病に陥る危険があるといえると思います。
心が病んでいるとき,必ず自我が機能不全に陥っています。両者はほとんど同義語です。これといった外部的な理由が見当たらず,いわば平地で遭難してしまったかのように発病する場合,自我が自己欺瞞に陥って見るべきものを見ようとしないか,衰弱した別種の様態に陥っているかということになると思います。それとの相対関係で,勢力を強めている無意識界の分身(影と呼ばれるものです)たちによって,機能不全化して無気力になっている自我が実質的に支配されるのです。
健康な精神では,自我が常に主導力を保持しています。悪を働く心は悪人にだけあるのではありません。人間であればだれにでもないわけがありません。悪人と善人とを分けるのは,前者の自我が無意識界にある悪なる影の支配を受けているのに対して,後者の自我は影の上位者であることができていることの違いです。
PTSDといわれる心の病気の場合は,事件として扱われるほどの外的できごとの下で,平均的な強さを持つ自我が機能不全化する心的病理現象です。この場合は大方の人の理解と同情が容易に得られます。この場合も機能不全に陥っている自我との相対関係で,無意識の心が荒れるのです。自我にとっては外的な負荷という前門の虎と,荒れる無意識という後門の狼とに対処が迫られるという事態です。
このように心を病むにいたった人の自我の機能が,自然に回復することも稀にはあるでしょうが,それはかなり難しいことです。ですから一般には,心理治療が必要になりますが,心理的な治療者は,心を病んでいる人の自我がひとり立ちできるほどに回復するまでのあいだの,指導的な伴侶ということになります。
心をいったん病んだ人に,ペルソナ,ないしは自我の強化策を勧めるのが,いうならば認知療法といわれているものです。これに対して自我の機能の不全化に伴って勢いを強めている無意識界の影たちを扱い,影たちの存在を捉え,そのいい分に耳を傾け,いずれはそれらを意識に統合する(影たちを救い出すといっていいでしょう)作業の試みが,精神分析的なアプローチということになります。この試みも自我の仕事ですから,治療者に支えられつつ,機能不全に陥っている自我の強化が図られることになるといえます。認知療法が自我の強化を目指すことによって,無意識の世界のものを相対的に改変させる試みといえるのに対して,分析的な試みは直接無意識を操作することによって,自我の姿勢の本来化を目指すということもできると思います。
繰り返しになりますが,心の病理的な現象は,幼児心性が意識の表舞台に顔を出している側面が色濃くあるといえます。自我を支配するほどの勢力を失うことなく,病理的な意味を持つほどのものである幼児心性が認められる背景には,原初の他者である母親との関係がからんでいる可能性が高いのです。そしてそれが自我の自律性を混乱させ,劣等化させるという連鎖があります。
これらの一連の病理的な連鎖の淵源にあるのが見捨てられる恐怖です。
このように,日常にある対他心理の根本のところに潜んでいる見捨てられる恐怖と呼ばれる幼児心性が,どのように克服されていくかがそれぞれの自己の課題であり,克服の仕方がそれぞれの自己の性格の上に反映されていきます。その克服に向けた最初の努力目標は,まずは両親,なかんずく養育の中心である母親によって掲げられることになります。人間の集団の最小単位であり,人間関係の基本を修練する場所でもある家庭の中が,最初の重要な人生の演習と実践の舞台となります。ここでは指導者としての母親の能力,そして当然父親の能力とがまずは問われることになります。その指導能力は,結論的にいえば愛情と信頼との質にかかっているといえます。そしてそのことがいかに難問であるかということも,精神科の臨床という窓口に立てば痛感させられることです。愛情と信頼が誰が見ても欠落している家庭がたくさんあるわけではないと思います。むしろ傍目にはもちろん,当の両親と子供たちの多くでさえ,自分たち親子のあいだで本物の愛情と信頼とが機動しているか正確な認識を持つことが困難なのです。それは人の心がそれぞれの無意識の心の影響を強く受けるために,自分の認識力が歪曲されていても気がつかないか,気がつきたくないということが起こるからです。
煎じ詰めれば心の病は対人関係に行き着き,その原型は親子関係に行き着くといっても過言ではありません。ここに問題がなければ,機能的な精神障害の過半は問題化されることはないでしょう。
家庭という人生の最初の舞台の上で修練されるものの中で,最も重視されるべきものは他人の心が分かる心の育成ではないかと思います。しかしこれは大きな問題です。人の心が分かるということは,自分の心が分かるということであり,人間について,ひいては人生について分かるという広がり方をする性格のものでもあるように思われます。そうなるとそれが十分に出来ている人は,少ないどころではなくなります。無論,私自身もよく分かっていない一人です。問題が大きく,たいていの大人にも手に負えないほどのものであるので,たじろぎもしますが,しかしやはり子供の心の育成上,大切な問題です。
人の心は,ある意味では分かるわけがないものです。そして,ある意味では一挙に分かることができるものです。これらは互いに矛盾していますが,矛盾こそがこの問題の特質なのです。
それは自我の機構に拠っていると思われる,自己の構造に由来するのです。他者は犬や猫とおなじように,他なるものとして意識にとって外部に存在しています。赤ん坊が成長していく過程で,犬や猫をしだいに認識していきます。それらは物と違って動くもの,命があるものとして,生物体である自分との類縁性において理解をすすめていきます。そしてそれらが何を感じ,何を考えているのか,そういうことも理解できるようになっていきます。そしてそれらの理解や認識は,外部からの学習と研究によって獲得されるのです。それは人間の心と絶えず比較されながらの理解ということになるでしょう。人間の理解とは,人間的な理解以上ではあり得ないのです。
ところで他者はこれらの動物たちとは違った認識のされ方をします。
生まれたばかりの赤ん坊について,M.Sマーラーは,「乳児はあたかも自分と母親とが全能の組織(共通した境界を持つ二者単一体)であるかのように行動し,機能する。・・・母子単一体という共生球を形成している」と述べております。
このように生まれたばかりの赤ん坊は,原初の他者である母親を,他なるものとして捉えていないのです。この段階の赤ん坊の自我はまだ機能を開始しはじめたところで,いたって未熟で自律性がありません。ですから母親の自我に絶対的,全面的に依存しています。人間には,あるいは自我には,絶対とか全部という存在形態はなく,赤ん坊のこの段階での母親依存が特別の例外といえるでしょう。
対自意識と対他意識とが渾然として一体になっていると考えられる生まれたばかりの赤ん坊は,簡単にいうとすべてが主観的である世界の住人なのです。そうした状態にある意識の黎明期にあっては,赤ん坊は誇大感と万能感の中にあると考えられております。つまりあらゆることが可能な力を持っているという感覚的意識と,大きな力によって護られているという感覚的意識の中にいるということです。
それは赤ん坊が人間になる以前の存在形態を暗示しているようであり,自我に拠る人間存在への最初の移行を安全に遂行させる役目を持つものであると思われます。
生まれたばかりの赤ん坊は,自然の中にまだまどろんでいるかのように思われますが,意識活動が開始される以前の沈黙の様相がうかがえます。そして沈黙は自然の特性の一つです。自然の特性は全ないしは完全というふうに考えられます。そして人間は,というよりは自我の能力はいうまでもなく不完全です。
人間は自我に拠る存在です。その活動がまだ不十分な意識の黎明期にある赤ん坊の自我機能は,母子一体の機能的な空間の中で,すべてが可能であるという幻想の中に保護されているようです。そして,また,その自我機能は,完全なもので護られているという幻想の中にもあるようです。つまり自我機能の能動性と受動性とがもろともに完全であるという幻想の中に,赤ん坊はまどろんでいるだろうと想像されます。しかしそれらは分離しており,従ってそのどちらもが不完全であるという不安があればこその誇大感と万能感の共存であるといえると思います。かつ,その存在形態は自然にかぎりなく近く,しかし自然から決定的に分離しているのです。つまり未成熟とはいえ自我の機能は最初の活動を開始しているのす。ということは自我の活動によって光(生)を意識し,従って闇(死)を感覚的に意識しないわけにはいかないはずなのです。
マーラーによれば,生後3ヶ月までの赤ん坊は,「正常な自閉」の中にあります。それはフロイトの,「閉じられた精神体系の見事な例としての鳥の卵」に相応するものです。その状態にある赤ん坊は,「刺激防衛壁に護られて外部刺激に対して反応しない」のです。そのように胎児期に近い状態で,過度な刺激から,活動を開始したばかりの未熟な自我の機構を護っているのです。
もっとも自我心理学の立場に立つマーラーのこの見解に対して,D.Nスターンが独自の乳児観察の経験に基づき,根本から否定的な見解を述べています。マーラーが,生後間もなくのあいだは,刺激防護壁に守られながら恒常的な平衡状態を維持する生物学的過程が優勢であると述べたのに対して,スターンは母子相互の関係性を無視してはならないという趣旨のことを主張しています。この対立は,本家フロイトに端を発する古典的精神分析を受け継ぐ自我心理学と,コフート以降の自我心理学への異議申し立ての一連の流れとの対立に伴うものです。
自我心理学の立場は,他なるもの,外なるものとの関係を考慮することなく,専ら病者個人の内的空間のみに限局して,起こっている歪曲を問題化しようとします。分析者は,自身をまったくの客観的立場に位置させ,あたかも外科医が外側から患部を調べ,病巣を摘出しようとするのに似て,治療者と病者との関係性は問題外なのです。これに対して,コフート以降の流れをくむスターン他の分析医たちは,それぞれ別個に存在する自己と自己とのあいだの関係性において問題を捉えようとします。
スターン他が主張する,関係性の視点で問題を捉えるべきであるというのは,改めて主張するのが奇妙に感じられるほどに当然のことと思われます。それはアメリカの地に根をおろした古典的精神分析の発展の歴史が,いかに重たいものであったかということの裏返しになるのでしょう。いまや教条主義に陥っているというしかないものに対する挑戦が,コフートの勇気と決断によって口火が切られたという形になっているのです。
スターンの主張によれば,生まれたての赤ん坊が専ら生物学的な過程の中にいるわけではないということですが,とはいえマーラーの観察が無意味だったということにはならないと思います。そこで観察されていることの理解と解釈の立場の相違はあるでしょうし,スターンの主張にその意味では分があるように思われますが,赤ん坊が生物学的な保護を必要としていることに異議を申し立てる根拠はあまりないようにも思われます。
スターンがいうように,生後間もなくから母子相互の関係で何かの感覚的意識のうごめきがあるとしてもまったく不思議はないでしょうし,大いにありそうなことです。であればこそ,赤ん坊の感覚的な意識は大きな脅威の中にあると考えないわけにはいかないのです。何らかの意識が活動するということは,繰り返しになりますが,闇の圧倒的な脅威を意識しないではすまないはずのものです。その脅威に対抗するために,赤ん坊の自我は,母親の自我とほとんど一体化するほどに密着している生物学的な理由を必要としていると思います。つまり生まれたての赤ん坊の自我は,母親の自我の中にまどろむように一体化して守られているのでなければ,無化する闇の脅威の前にひとたまりもなく粉砕されてしまうだろうと想像されるのです。
人間は人間以前の全なるものから,自我に拠る存在として生誕することに伴って,意識という光の世界と無意識という闇の世界に二分割された存在者であり,それら二つの存在形式のあいだに横たわる埋め得ない非連続的な深淵を,赤ん坊は前経験的な感覚的意識において通過しなければなりません。この経過の原初の存在形態として赤ん坊の自我は,他者なる母親の自我とほとんど渾然として一体であると考えるのが合理的であるだろうと思われます。
以上に述べたことによっても,自己は構造的に他者を内に含んでいると考えることができるのではないでしょうか。従って,他者は内なるものと外なるものとがあることになります。ここに犬や猫との関係と,人間相互の関係との存在形態が根本的に異なっている理由があります。
外部にある他者は,他性として結局は不可知の存在であり,しかし内なる他者との関連において一挙に会得されることが可能な存在でもあるという両面を持っているといえます。
そしてしだいに赤ん坊の自我が機能を進化させていく過程で,母親を他なるものとして認識することができていくのです。このことは,生まれたばかりの赤ん坊の自我が未熟すぎて,他なる存在である母親を他者として認識できないと考えることも可能だと思いますが,とはいえ,母親を自分の一部,内なるものとして捉えている事実を否定する理由にはなりません。赤ん坊の未熟な自我が,母親の自我をほとんど自分自身のものであるとする存在構造上の理由があって,はじめて母子一体の共生球が存在できると考えるのが合理的ではないでしょうか。それは赤ん坊の錯覚というようなものではなく,母親が内なる他者として自己と一体で区別がつかないところから,赤ん坊の自我の機能の進化に伴って,おもむろに外部にある他なる母親を認識的に捉えることができるようになっていくと考えられるのです。
犬や猫は学習と研究によって,いわば外部から認識できるのですが,他者についてはあらかじめ内的な会得があり,その投影が外部にある他者におよぶので,あらゆる存在者の中でも,他者は特別に親和的な存在であるといえます。外部にある他者は,外的な自己でもあるのです。
見捨てられる恐怖が根源的な意味を持つ理由は,以上のような人間に宿命づけられている存在構造にあると思います。
つまり自然の一部であったものが,どういう理由によってかあるとき自然から乖離され,自我に拠る特殊な存在として人間の生誕があったと考えるのは,なんら突飛なことではないと思います。人間以前の存在形態が何であるかは不可知ですが,不可知であることが,既に人間の知性,認識力を超越したものの存在を指し示しているのです。そのような超越的な存在をどのように命名するかは個々によるでしょうが,ここではそれを自然と呼んでおきたいと思います。
自然の特性は,一つには全または無といえます。これは矛盾したいい方のようですが,自我の能力が有限であることからくる必然です。全も無も,自我が捉え得ないものです。自我はかぎりなく全を目指すが全にいたることはなく,究極において自我の消滅という無に帰するのです。
人間の精神の内部にある自然が無意識の領域です。その領域には自我の光は限定的にしか届きません。そして人間を人間たらしめている自我は,無意識の世界,無意識の力とのあいだに有機的な関連を持っています。いうならば内なる自然である無意識の力を拠り所とする自我は,無意識の意向を受けているはずです。しかし無意識の意向をそのまま実践するだけのものであるのなら,あえて自我が存在する意味があるとは考えられません。自我は無意識に拠りつつ,無意識から独立したものでもあると考えるのが妥当だろうと思います。
自我の無意識との関係でのそのような依存性と独立性が,人の一生を,個々に大きく分ける理由だろうと考えられます。
いわゆる自己実現とか真の自己と呼ばれる人生行路をたどる人は,特別に恵まれたたくましい自我の持ち主ということになると思いますが,彼らの自我は,自然に通じる無意識の力の意向に忠実に即して人生の舵取りをすることができるのだろうと思います。
そして大方の人間の自我は,広大無辺である上にしばしば荒れ狂う海を,いわば自力で小舟を操って航海し通す自信と勇気とを持てません。危険に満ちた,なにが起こるか分からない人生という海路を,人と助け合って航海するにしくはないのです。
無意識という自然から独立しているものでもある自我の能力の寄る辺なさが,特別に親和的な関係にあるもの,他者の存在を必要とし,事実,他者を自己の構造の内に含み,’全’の性格に一歩近づいた存在形態となっています。そうすることで,恐ろしい孤独を慰めることが可能となっていると考えることができるように思います。
しかし一方で他者は外なるものです。他者とのあいだの親和性は,単に有力な可能性にとどまります。他者は頼りになりますが,人間の常として絶対の保証はありません。それは自我に拠る人間の宿命です。
赤ん坊のとりわけ寄る辺のない自我は,寄る辺がないだけに貪欲に安心と安全の保証を要求します。それに母親がどう応えるかが,いわば赤ん坊の一生の命運を担っています。赤ん坊は内なる母親との一体感の中にあり,それを拠り所にして万能感と誇大感が存在しているのだろうと考えられます。これら二つの誇大な感情は,赤ん坊が自我を付与される以前の全である自然に匹敵する代理的な防具としての意味があると思います。その幻想的な感情は生得的なものに基づくものに違いありません。そしてその原基の所在は,赤ん坊の自我の機構以外には考えられないと思います。いうならば赤ん坊を,自然のものから自我に拠る人間存在へと,ソフトランディングさせるための装置として原基があるのだろうと想像されます。
しかしながら先ほど述べたことと関連しますが,内なる母親との一体感の中にある赤ん坊といえども,母親の他性は感覚的意識に映じないわけにはいかないだろうと思います。内なる母親との関係で成立している全を要求する赤ん坊の貪欲さに,他なるものである母親が応えることができる能力は,いうまでもなく限定的です。自然の中にまどろむようにして存在していた赤ん坊の全的な安心と満足への期待と要求と,現実の母親の能力とのあいだには,埋めきれない深淵があるのです。この深淵は無を予感させます。これが見捨てられる恐怖が存在する根源的理由であり,人間には等しく避け難いものである理由です。この恐怖の深淵性が,あるとき母親の表情に投影されて映し出される瞬間がいくらでもあるだろうと思います。そういうときの母親体験は,母親が冷酷な他人に匹敵するほど遠方に感じられ,無の深淵の渦中にただ一人取り残された恐怖を感じる体験でもあるのではないかと想像されます。母親との関係でのその種の恐怖体験は,一種の外傷体験として刻印されることでしょう。それはさまざまな程度で,おそらくはすべての赤ん坊が体験するに違いないと思われます。
成人してからの病理性である完全癖,’全か無か思考’の心的傾向は,この幼児心性が克服されず,自我を支配し脅かしている様相です。人間の人間らしいところは,ほどほどの満足で自足することです。それをもたらすためには,先にも述べたように母親が一貫した愛情で応える必要があります。赤ん坊が求める,不安と恐怖と怒りに裏打ちされた全的な安心と満足への要求に対して,母親にできることはこの程度のことでしかないということを,精一杯,身をもって教えることが必要です。全的な要求をする赤ん坊は,しばしば不満と怒りで一杯になることでしょう。しかしやがては一貫した愛情を示す母親に,感謝の感情を持つようになります。それは現実を認め,受け入れる気になったということです。全的な安心と満足を要求する心から,現実的なほどほどの安心と満足で我慢する心に移行することで,母親との関係が落ち着くことができるのです。母親としては首尾一貫した愛情を,精一杯示してあげるのが,真の愛情ということになります。
母親の気分が不安定であったり,病気で入院するなどして愛情の剥奪,中断があったりすると,赤ん坊は大いに混乱するでしょう。幻想的な主観世界の中にある赤ん坊は,当然のこととして客観的にできごとを捉えることができません。混乱させられ,不安と恐怖とを鎮めてもらえない心的環境にあっては,いつまでも全的な安心と満足とをもとめつづけることになるのです。そういう折に強く叱られるなどすると,赤ん坊によっては更なる恐怖で沈黙するでしょう。そのときもとめつづけていた全的な要求は引っ込められますが,それは母親の怒りを恐れての非常手段であり,問題が解決したわけでは勿論ありません。問題は自我によって抑圧,封印されて,意識下で幼児心性としてのエネルギーをいつまでも温存されることになります。この抑圧する自我は,怖い親の自我に密着して傀儡化すると共に,自己の自然な欲求を不当に扱ったことになります。親との関係において無力であるしかなかった自我は,恐怖をもたらした親に怒りを向けることができません。
心的なエネルギーは大きく分けて,生の方向に作動するか,死の方向に作動するかだと思われます。自我が主導的に機能しているかぎり,エネルギーは原則的に前者のものであり,機能不全化すると後者のものになると思います。そして後者のそれは,怒りの形で表われます。幼い子が親に恐怖をいだいたために満足をもとめる欲求を抑圧するとき,自我が主導する力を示せなかったことになります。主体性を欠いた自我は親の自我の支配を受けて傀儡化してしまいます。その自我によって,親に向けられるはずであった怒りが抑圧されます。満足を求める欲求は,本来は自然のものとして自我によって受け入れられ,生の方向に自己を発展させていくものであり,かつ発展させていく力を増強するはずのものです。それができるためには,自我が親のしたことへの反応として生じた適応的な怒りの正当性を認め,自我の主導の下で親に対してアピールをする必要があります。ところが生へのエネルギーが,やむを得ずとはいえ自我によって阻まれ,そぎ落とされることになるときは,親に向けられて然るべきであった怒りもまた,自我によって抑圧されることになります。生の世界に羽ばたくはずであったそれらのエネルギーは,一転して心の闇に内向して怒りのエネルギーに姿を換えるのです。このときの怒りは,最初に親に対して向けられるべきであった適応的な怒りとは違う性格を持ちます。それは生の世界の開拓者である自我に対して,自己の中の異分子となった抑圧された分身たちと共に異議申し立てをし,やがては自我の世界の破壊者になる可能性を持っています。自我は不自然な,無理のある解決策を講じてしまったことになります。それに伴ってエネルギー論的にも自我は弱く,抑圧を蒙っている分身たちは強い負のエネルギーを抱え持つという歪んだ配分となります。そして歪んだ自己の構造に基づく圧力を,たえず無意識から受けることになる弱い自我は,ますます親の自我の傀儡でありつづけることで機能を守るしかなくなるのです。こういう自己の構造の下にある自我は,親の自我の支えを失うと無意識の圧力に抗し切れない不安を強く持つことになります。
H.コフートが次のように述べております。
・・・女性性器を目にした少年が見せる戦慄は,体験全体のうちで最も深い層ではない。その背後に,それに隠されてさらに深く,もっと恐ろしい体験が横たわっている。それは顔のない母親の体験,我が子を見てもその顔の輝くことがない母親を体験することである・・・。
生まれて早々に,あるいは生まれて早々であるからこそ,このように激しい他者への恐怖と不信との基になりかねない過酷な体験を強いられる赤ん坊を,両親,なかんずく母親は,人の心が分かる子供に躾けていかなければならないのです。それは何といっても,原初の他者である母親自身とのあいだで,根源的であるこの恐怖を癒していく心の交流がもとめられるのです。その決め手は母親の愛情と信頼が,真正のものにどれだけ近いかということです。いわばごまかしの愛情,愛情に似た母親の欲求充足などは,赤ん坊には通じないと考えるべきです。そのような偽りの愛情は,母親には理解できない形で赤ん坊の心をいびつにさせてしまうと考えなければなりません。赤ん坊も,成人となってからも,自分にそういう問題が起こっているという認識を持てません。たとえていえば,気がつかないうちに何らかの被害にあい,しかし実際にはその事実は知らないままでいるのにいくらか似ているかもしれません。これらのことについては,母親自身がその母親からどの程度質の良い愛情を注がれていたかに,かなりの程度左右されることになると思います。そういう前提の上に立って,いずれにせよ母親自身が自我の姿勢を好ましく整えていなければ,母親の自我は無意識の潜勢力の悪しき影響を受けることになるのは必至で,それが育児に反映されるのも避け難いでしょう。よい母親であろうと知性的にいくら注意を払っても,盲点はできてしまうと思います。
賢い母親とは知性的に高い人ということではなく,赤ん坊という自然のものであるが故に無垢である存在者に,母親自身も母性の自然の発露で応じることができている人ということになるのではないでしょうか。そういう母親であれば,赤ん坊と一体となって自然的な心の充足感の中にいると感得し,至福の感情にひたることがことができるのだろうと思われます。それは母親にだけ与えられた特権です。そういう役割と立場を与えられていることを喜べる母親は,賢いという名に値するのではないでしょうか。
母親である人が母性的でないことは不幸なことです。神経症に類する心の不自然化の表れであると考えることもできます。しかし他人がとやかくいうことではないかもしれませんし,人がさまざまに神経症的であるといわれていることでもあり,何も母性だけが問題でないのも確かです。
しかしながらここでのテーマは,性格の形成の基盤に当たる乳児期の問題に関してです。赤ん坊の命運を母親が担っているというのは,大げさないい方ではないと思います。問題の性格から母親の責任論という側面があり,母親によっては不愉快かもしれません。しかしそのことは,見方と受け取り方を少し変えれば,母親が赤ん坊にとって余人には変えがたい,唯一最大の拠り所であるという名誉ある問題についての議論です。一人の人生を左右するほどに大きな役割を与えられた立場に置かれて,それを誇りと感じない精神は貧困であり,不幸です。そしてそれは母性の欠落を即座に意味するものです。ですからこのテーマは母親の仕合せ論でもあると思います。人の問題について,特に不幸かどうかについて,他人がいうことではないのも確かですが,そういう客観的な性格を持っています。また母性に関しては母親個人の問題にはとどまらないことなので,別格なものとして議論されてしかるべきです。ともあれ大きな役割を与えられるときに,それを名誉であり,誇りであると捉える精神は豊穣であるといえます。しかし物事にはすべて裏と面があるように,母親が余人には味わえない豊穣と至福の感情を持つことができる立場にあるということは,逆に一転してストレスと被害感の源泉にもなる可能性があるということになるでしょう。母親が子供に対して愛情の名を借りて過干渉になるのは,後者の精神においてです。
それにしても人の心を知るというのは大きなことです。生易しいことではないと思います。そしてそれは,自分自身の心をどのくらい深く知ることができているかということと,パラレルな関係にあると思います。自己を知ることは,他者を知ることであり,人との関係性を知ることです。それはそれぞれの自己の世界を知ることであり,ひいては人生や人間についての理解を深めていくということでもあると思います。
汝の敵を愛せという言葉があります。この言葉の内に含まれている精神は上質すぎて,大方の人の笑いものになりかねないほどのものです。だれにもそんなことが出来るわけがない,言葉だけだ,偽善者のたわ言だということになりかねない言葉です。
端的に,「あなたの子供が殺されたとして,犯人を愛せますか」という反問があるときに,「愛せます」という心境になるのはほとんど困難です。偽善的な響きになりそうなそういうことより,「犯人を殺したいと思うかもしれない」と感情を表す方が共感を呼ぶのかもしれません。
問題は理念と実際との違いということだと思います。’汝の敵を愛する’精神は理念です。その極致にまで到達するのはおそらく困難でしょうが,実践が困難なほどのものでなければ理念にはなりません。
理念は自我がおのれに課す,到達されることのない到達目標です。理念は,自我がそれに向けて現実的な行為を編み出す力をもたらします。ですから理念は自我に内在するものではなく,自我を超越するものです。従ってそれは無意識に係属するものであり,自我がそれによって啓発されおのれに課したものという正確を持っています。理念はいわば自我に提示された光であり,その光の照射を受けて,自我が心の内外の暗部をあからさまにしていく力を得るのです。
人に向かってこれ見よがしにする’善行’の実践はいただけません。それはほとんど愚行です。人から揶揄され,謗られても仕方がないでしょう。しかし’汝の敵をどこまで愛せるか’と密かに自己に沈潜する精神は,理念によって照らし出されるものに向けて,可能なかぎり自分の暗部を探り,最奥にまで至ろうとする行為を導きます。その沈潜する行為の過程で,他者への激しい怒り,憎しみに遭遇するかもしれません。というより遭遇しないわけがありません。心の内部の闇の帝王の手先である怒りに遭遇したとき,自我がそれをどう受け止めるかは,自我の器の大きさが試される正念場です。早々に蓋をして退散しなければ,自我が粉砕されかねないほどのものであるかもしれません。怒りは弱気の自我にとっては,自我が演出者として構築する,自己の世界を世界たらしめている心の内外の諸対象との関係を破壊しかねない,悪なるものです。しかし立ち向かい,受け止める自我にとっては,怒り,憎しみは,もはや闇の帝王の手先ではありません。闇の帝王として自我を脅かすかぎりは悪として潜行するものですが,自我の手の中にあり,既に光の中に取り出されたそれは,善に衣替えしたのも同然のものです。
怒り,憎しみの力を恐れ,自我がそれによって支配されているとき,それらの感情は自我を傀儡化して悪性の働きをします。心の外にあっては他人に対してさまざまな形態の悪を働きますし,内にあっては健康をさまざまに害します。しかし自我が怒りの上位に立ち,それを従えているとき,怒りは悪の牙を抜かれたも同然です。場合によっては人に向けて怒りを露わにすることもあるでしょうが,それは防衛的,適応的な怒りで,自我が怒りを利用したことになり,つまりは自我に主体性があるのです。
自分を深く知るということは,自分の暗部にある悪をより深く知ることです。自分の内部の悪をおそれず捉えたとき,悪は既に悪ではありません。もっとも,それで心の深部に潜む悪の全貌を捉えたことにはなりません。人が善であろうとすること,自己自身であろうとすることを心がけるかぎりは,その前進を阻む力である悪は立ちはだかりつづけるでしょう。つまり悪の存在がなければ善もないのです。
自我が下位にあるものを捉えることは,常に可能です。捉えたかぎりで自我は上位に立ちます。まだ正体のはっきりしない怒りについては,自我は上位にはありません。それを意識し,捉えようという意志があれば,少なくても自我は下位にはありませんが,その意欲を失くしている自我は,本来は下位のものとしなければならないものの下位につくことになります。そのような状況にある怒りは悪の性格を持ちます。これは病理的な心的状況といえます。
怒りは悪の手先です。自我は怒りと,怒りをもたらしたものを捉えてその上位に立たなければなりません。それをあきらめて自我が怒りの下位に甘んじるとき,怒りの根源にあり悪の支配下に置かれます。悪は闇の帝王であり,自我の姿勢によっては自我の世界の破壊,回収を使命とするものであるように思われます。
自我はより上位にあるものは捉えることができません。怒りは自我がその上位に立たなければならないものですが,怒りの根源(悪)は捉えることができません。つまり怒りは必ず無意識の中に存在し,悪性のものとなる可能性を持っています。そしてそれらの根源となっている悪そのものにまでは,自我の追求が及ぶことができません。従って根源にある悪は上位に立つものです。そしてそれは善と区別がつかないものでもあると思います。つまり自我の上位者は一つであり,自我の姿勢によって悪が現前化するのでしょう。悪の尻尾を捕らえようと極限まで追求することができるとすれば,そこには善と区別がつかないものの存在があったということになりそうです。つまり善と悪は二律背反の関係にあるのだと思います。
以上のように自己に沈潜する行為を揶揄したり,非難したりする者はないはずです。第一,最初から他人の眼は問題外なのです。自己自身との関係で悪は真に問題とされることが可能であり,’汝の敵を愛せ’という設問が意味を持つのです。ですから悪をなす者は,自分の悪を知らない者のすることです。あるいは自我が悪によって支配しつくされた者のすることです。「俺は悪人だ,それがどうした」と,そのとき彼らはいうでしょう。
パニック障害を病むある女性が,次の内容の夢を報告してくれました。
どこかのホテルのロビーにいる。私がパニック障害で悩んでいるのを知っているらしい女性が,それを治す方法を教えてくれるという。別室に連れて行かれ,しつらえてある仏像に向かって鈴を振れば治るという。鈴を振ると,脇のところから大きな身体の相撲取りが出てきて,私の方に向かってくる。その眼がとてもこわい。たちまち投げ飛ばされる・・・。
そして,「私を案内していた女性に,力士の身体を押さないといけないといわれていたように思う」という補足がありました。しかし相手が大きすぎて押すどころではありません。
彼女は薬の助けもあって,症状的なものは一応は収まっています。しかし薬に頼っているかぎりは,ふつうの人ではない,と感じています。はたして薬をやめることができるのかという不安もあります。占いや祈祷の類に関心を持っている彼女は,魔術的に治ることはできないかというほのかな希望を持ってもいるようです。
夢に現れた巨大な身体と力を持つ力士は,彼女のパニック障害をもたらしている何ものかのようです。
夢によるかぎり,たちどころに投げ飛ばされる無力な彼女の自我が,巨大な怒りでもあり,彼女にとっての悪でもあるらしい力士に対抗する力を持つのは,現時点では到底無理なようです。一見すると案内した女性は,彼女をだましたことになります。何か悪辣な意図をいだいて彼女に接近したように見えます。これは夢の特性のようです。つまり立ち向かう意志を持っていない自我に対しては,このようにいいかげんなことをいってあしらうのです。しかし,夢の意図はそれにとどまらないものがあります。この夢では,夢を見ている主人公に,その夢舞台に現れた女性が,「力士の身体を押しなさい」といっているようです。つまり自我が対抗するようにといっているのです。ところが端からそんな力が自分にあるとは信じていない本人は,祈祷によるマジックを期待するしかない気分なのかと思われます。そういう意味合いでいえば,案内した女性はいい加減なことをいっていることになります。
この場合,本人の自我は自分の問題と対決する勇気も意志もないかぎり,夢舞台の女性は,本人にとっての悪の手先であるらしい力士と一連の者であるようです。しかし本人が夢の意味するところに気がついて,力士と対決する姿勢を見せれば,一転して夢の舞台の演出者の真の意図が汲み取れるのです。そのように自分の問題と正対しようとする自我に対しては,演出者が差し向けた女性は悪の手先ではなく,問題を解決する方法を教えようとするものの使いということになります。つまり夢の演出者は本人にとって善をほどこすものでもあり,悪をなすものでもあり,それは自我の姿勢によって変わるということになります。
この女性の母親は,結婚したときから夫の実家に住み,気難しい舅,姑に黙々と仕えてきました。夫は自分の両親に頭が上がらない人で,妻の苦労を見てみぬふりをしていたようです。そして夫自身が妻に依存的な性格です。母親の辛そうな顔をいつも見ながら女性は成長しました。祖父母や父親には,強い不快感を持っています。外出しようとすると後ろから黙って見ている視線をしばしば感じ,気味の悪い思いをしてきました。このごろでこそ,「何か,用?」と怒りを表すことができますが,最近まで何もいえずにいたのです。
女性の夢に現れた力士は,祖父母,父親,母親などとの関係があるようです。
案内した女性が,「力士を押すように」ということに促されて夢のイメージを見据えると,それらの家族の人たちとの関係が表われてくるかもしれません。夢のイメージを解剖してそれらの人たちを客観的に捉えることができれば,彼らに対して嫌悪感はあるかもしれませんが,もはや恐れるに足らないものになるでしょう。そうして見ると,彼女の夢に現れた力士の恐ろしげなイメージは,彼女の感情の彩色によるものが大きかったということになると思います。人が恐怖するイメージを持つときは,大いに主観的になっているものです。
夢は多重構造になっていて,一見すると卑近な日常の些事が現れているのに過ぎないように見えても,掘り下げていくと日常の意識のおよばない叡智が現れてくることがあります。夢というイメージは,現実の世界にあるものから無意識の深部にあるものにまでおよぶ広がりを持ちます。
童話には元型的なものが表われているといわれますが,「眠れる森の美女」というドラマは童話をもとにして創られています。このドラマでは王子が,悪魔によって100年の眠りに就かされているお姫様を救い出すことになっています。その過程では悪魔の手先と戦わなければなりません。このドラマを夢の舞台に置き換えると,王子は夢を見ている神経症的な苦悩を持つ本人の自我であり,それを癒すためには無意識下に我知らず追いやってしまった命の源泉であるお姫様を救い出さなければなりません。お姫様は心に生気をもたらす力です。そのお姫様を100年の眠りに就かせてしまったのは,王子自身の臆病だったでしょう。悪魔の存在を忘れてしまった父王の臆病が悪魔を怒らせたということになっていますが,王子にはその父王との関係でそれと類似の臆病があったために,かけがえのないお姫様を失ってしまったのです。王子である自我は,発奮して死を恐れずに悪魔と戦う気構えを見せました。その勇気があるかぎり勝利は王子のものです。王子は次々と繰り出してくる悪魔の手先を撃退し,最後には悪魔自身と戦い勝利を収めます。
自我の臆病は,してはならない抑圧をして無意識下に分身たちをとじこめます。それら分身たちは自我の価値規範に合わないということですから,自我に敵対するもの,つまり怒りと一体となった悪という性格を帯びることになります。ドラマではかけがえのないお姫様を意識の地下に幽閉してしまいました。悪魔とその手先たちは,お姫さまの怒りと悲しみとを受けて自我に敵対するのです。自我は不始末をしてしまった理由である不安や恐怖に改めて立ち向かわなければなりません。その不安は,基本的には母親や父親との関係で生じてくるものでしょう。そういう不安に負けてかけがえのないお姫様を抑圧してしまったのです。
王子である自我に起死回生の勇気を与えたのは,イメージの際深奥にある内在する主体です。先の女性の夢で,女性にパニック障害の治し方を教えようとした女性は,もしかするとこの主体に使わされた者かもしれません。彼女が王子のような勇気を持てば,悪である力士と戦って勝利することができるでしょう。
イメージの最深奥には,このように,自我の世界の歪みをただしたり,指針を与えたり,叡智を示したりという可能性をたたえて自我の様子を見守っている,無意識の世界の王である主体の存在があると思われるのです。
Sさんは,他人との意志の疎通がしばしばうまくいかない悩みを持っています。彼女は母親に大変依存的です。母親が少しでも自分が望んでいるような対応をしていないと感じると,大いに感情が乱れます。
彼女は,「関係のあるあらゆる人を大事に思っており,そのように対している」と自分では信じています。
しかし彼女は,家族や他人の言葉や態度を受け止めることがしばしばできないのです。自分が望んでいるような反応がないと,「どうして!」と動揺します。「私がよかれと思って出来る限りのことをしてきたのに,どうしてなの?」と思うばかりです。
この心を要約すると,私はあなたが大事なので,しかじかの努力をしてきました,ですからあなたも私を同等に大事に扱ってくださいということになるかと思います。この姿勢は相手側から見ると,私を大事にしてくださいというところに主眼があり,その心が満たされないかぎり不満を持たれることになります。そんな不満を持つのなら,あなたに気を使ってもらう必要がありませんということになりがちで,相手が去っていく十分な理由になり得ます。事実,友人たちが次々と去っていくのです。彼女にはその理由が分からず,不安が募ります。去って行った友人たちは,彼女の気遣いをむしろ要求がましく,自分本位と取っていることになるのでしょう。そういうことでは人との関係を大事にしていることにはならないのですが,その分,その理由が分からない彼女の心には大きな盲点があることになります。
子供は親の助けを必要とします。基本的に親の支持があって安心できます。大人は,大人といえる心は,自分を支える力は基本的に自分自身であるのが前提です。そういう意味での大人でない人は,一般的にいって少なくないように思います。Sさんも,本当の意味で自分を助けることができるのは自分自身でしかないということが理解できません。「私はとても寂しく,一人で居られる人間ではありません,だから分かってください,私を助けてください・・・」という心が切実すぎて,他人のことが念頭になくなるのです。一人ではいられないほどに孤独感と寂しさが強い彼女は,人の心が分からなくなるのはもとより,被害的な気分にすらとらわれがちになります。それはほとんど幼い子供の心です。安心と満足の全的な要求を持つ赤ん坊の心性が,そっくり残っているといえるようです。無意識下に強く布置していると思われるその幼児心性のほかに,見捨てられる恐怖もそれと並存していると考えられます。彼女の自我はそれらの力に支配され,自我としての自律性,主体性がほとんど奪われているのです。そのために人との関係を安定して保つ主体が不在であるに等しく,必死に人にしがみつこうとしては疎んじられることを繰り返しているように思われます。
幼児心性に支配されている彼女には,人から疎んじられ,陰口をたたかれる現実的な理由が皆目見当がつかず,しばしば死にたくなるほど落ち込みます。
では彼女はどうすればよいのでしょうか?
うつ状態に落ち込んでいる人に,私は,「私は元気になりたいの?と自問してみてください」と問いかけてみています。この問いかけは一見愚問です。元気でいたくない人があるはずがないと,誰もが思って当然です。通院するという行為は,元気になりたい心があってこそといえるでしょう。
しかし実際はそれほど単純ではありません。少なからぬ患者さんが,「そういわれてみると・・・」と首をかしげるのです。遷延しているうつ状態の患者さんには,決してこれが愚問でないことが珍しくありません。
この問いが意味を持つとすれば,それによって自我の自律機能が賦活され,活性化しはじめたときです。首をかしげるとき,自我はうなだえたまま立ち上がる力を感じていないことになると思います。自我の機能が途絶えたはずはないのですが,幼児心性が活性化してその支配を受けつづけている自我は,他の助けによってこれまで’元気でいれた’ために,苦境をはね返す力が自分自身の内部にあるとは信じられないでいるのです。他の圧倒的な助けがなければ立ち上がれないという気分は,幼児心性の支配を受けている姿そのものですが,そのことは自我が自律性を抑圧しつづけてきた性格形成のプロセスを物語っているのです。
発病という形で露呈した性格形成上の大きな問題に,自律性を欠いた自我は対処の仕様がないと感じているのだと思います。
繰り返し,「私は元気になりたいの?」と問いかけることによって,自我の自律性を鼓舞したいところですが,人生の重たい問題に押しつぶされそうになっているときに,自我の奮起よりはあきらめの方が先に立つことになりがちのように思います。
初診以来長期にわたってしまっているある主婦は,反復的に再発を繰り返しています。結果としての病状はうつ病の相ですが,根本の問題は,’自分の問題’として問題をとらえることができない性格的な特性が関与しています。再発すると常に焦っています。子供をせかし,家事に急き立てられる思いがし,病気を即座に治してほしいと焦ります。
通院をはじめて間もないころに,人の勧めもあって祈祷師にみてもらったことがあります。魔術的な解決を期待できないと分かっていながら,常に望んでいるところがあります。
この方の場合,「元気になりたいですか」という自問は,二重に意味をなしません。一つには「元気になりたい」と常に焦っているので,それはいうまでもなく,愚問です。一つには「治してほしい」という意識が強すぎるように,自分の問題としてとらえるという意味がどうしても理解できないのです。といっても知的な問題があるわけではありません。心の盲点がそうさせているのです。
彼女は自分の苦しみは親の悪影響の結果であると考え,恨んでいます。受容的な義母を頼りにし,常にそれと比較して実の両親に攻撃的な気分を持ち,実際に電話等で怒りをぶつけるのです。おそらくはこの被害的気分が,’自分の問題’としてとらえることを阻んでいるのです。病状が悪化するといつもそうであるように,子供を急かし,時間に追われ,家事をふつうにやっていれば問題がないと分かっていながら気がかりで仕方がなく,結局は何もしないで寝てしまいます。そして自己嫌悪に陥ります。
「治してほしい」という被害者心理をはらんだ要求的な気分は,大人の心性とはいえません。自我の力の一つが受け止めることであり,責任を持つことです。病的になったときに,そういうものが影を潜め,幼児心性が自我を支配するようです。
治療者に治してほしいという希望があるのは当然のこととして,患者さん本人の中に治りたい意志がなければ心理的な治療は空転します。もっとも幸いにして薬が奏効してくれれば話は少々別になりますが。
ユング派の論客であるJ.ヒルマんは次のような意味のことを述べています。
「治療者と病者との双方の心の無意識層に,癒す心と病む心とがある。治療者は自分の心に潜む病む心によって病者の心を共感的に理解することができ,病者は自分の中にある癒す心で癒し手である治療者に反応する・・・この無意識にある病む心と癒す心とは元型である・・・」
元型とは生得的なものであり,個人的に経験によって体得したものではないというような意味です。
いま述べた,「元気になりたいですか?」という質問に対して,「そういわれてみると疑問がある」とする場合,遷延しているうつ状態の患者さんには重要な意味が含まれているのです。つまり,「元気になりたい」ということの中には,いま述べたように,患者さんの無意識にある癒されたい心がある程度は活性化されていることになり,自分を助ける意志があるという意味が含まれているのです。そういう意志があれば,治療者との協力関係がより進展するはずですし,日常の生活の中の工夫や,考え方の転換などの対策も心に浮上してくる下地ができていると考えてよいと思います。
もっともそうした意志がしっかりしていれば健常の心であるわけで,何らかの程度にその意志が薄弱化しているのも明白ではあると思います。その薄弱な意志を掘り起こし,励ますことが大切なのだと思います。
私は,「仮に,そうは思わないという反応が心内から返ってくるようであれば,いまの状態はつづくと思ってください」ということにしています。そのように伝えて,「突き放された」と感じる人はいないようです。
Sさんの場合も,「元気になりたいですか」という問いに,「私はよくなりたいと思っていないかもしれません」という返事が返ってきました。彼女の説明によれば,「よくなると心配してもらえなくなるから」ということでした。彼女の自我は,幼児のようにしがみつく自我なのです。無意識下に強力に布置していると考えられる見捨てられる恐怖に支配されて,自我はほとんど自由に活動できていないように思われます。人に見放されないようにとしがみつく自我は,この恐怖の虜になっているのです。
彼女が,「私は人の助けを当てにしすぎていたようだ」という反省をすることができるまでは,苦境から抜け出ることは難しいのではないでしょうか。現状の心理構造で’元気になる’というのは,彼女が望む通りに周囲の人たちが応えてくれるのでなければ難しいのです。そういうことは不可能です。
彼女が時間をかけてでも,ある意味であきらめて(ほどほどの満足を受け入れて),人を当てにすることの間違いに気づいたときに,自我の機能が動き出すことになると思います。心内の手ごわい恐怖が彼女の自我を圧倒しているあいだは,彼女は幼い社会人として社会恐怖の心を免れることができないでしょうが,恐怖をともかくも従えることができたときに,彼女は自己の回復と,社会人としての新たな出発がはじまることになります。
問題は受け止められたときに,解決への第一歩を踏み出したことになります。いわば人にしがみつく自我から,受け止める自我への変貌は,それだけで子供の心から大人のそれへと脱皮しはじめたことを意味します。受け止める自我は大人のものです。そしてしがみつく自我は子供のものです。
自我がそのように本来化して自律性を回復すれば,人の気持ちをも捉えることが可能になっていきます。いたずらに主観的に問題を捉えるのは,幼児の心の世界でのことです。大人の自律的な自我は,客観的に存在しているものとの関係が確かなものとしてあるのです。
人の心が分かるというのは,このように自己の世界の関係性が豊かに保たれているという総体的な枠組みの中にあるときに,自ずから可能になるといえるだろうと思います。それが可能であるためには,自我の力が十分に強いということが必要であり,かなりの程度素質が要求されるかもしれません。一般的には性格発達の早期に,乳児の自我を好ましく守り育てることで過重な負荷がかからないようにすることが望まれます。資質として強い自我であれば,負荷(主に母親の愛情提供に何らかの問題,歪みによって生じるものです)によって苦しみながらはね返すことも可能でしょうが,資質として弱い自我であれば負荷によって機能不全化します。いうならば前者の自我は鍛えられて更に強くなることも可能ですが,後者の自我はさまざまにつぶされてしまいます。
要するに一般論としては,両親が子供の心の自然な成長(それは親自身とは独立した個の確立を目指す心の成長ということになります)を望み,喜べるという意味で,真実の愛情と信頼とに値する育児姿勢の中から,子供の自我の歪みの少ない発達が得られるといえます。逆にいえば,子供の心の自然な成長を喜べない親が,さまざまに介入して子供の自我の自律性を混乱させるのです。
しかしながら穏やかに成長した自我は,無意識との相克に悩まされない分,おおむね日常の生活に満たされるので,創造的な大きな仕事をするには向いていないようです。
このあたりのことを比喩的に説明すると,以下のようになります。
人生を無意識という海の上を行く自我という小舟の船頭になぞらえると,次のようにいえるかと思います。
いわゆる健康な心の人の場合は,暗黙のうちにどことなく定められている海路の航海です。そこかしこに小舟の姿があり,みな一様におなじ方向に進んでいます。海はおおむねおだやかで,空はたいていは晴れています。ときに空模様が怪しくなると波が荒くなりますが,仲間のベテランの船頭が小舟の操り方を教えてくれるので安心していられます。
一方,混乱しがちな自我なる船頭に操られている小舟は,いわば安全海域を離れてしまった海路を進むのを余儀なくさせられます。そういう海路を選んだ理由は,海なる無意識にあります。無意識の力が,船頭に安全な海路を取ることを許さなかったのです。そのために船頭は,自分が船団を組むようにして航海する多くのものたちの仲間の異分子であると感じるのです。船団を組む者たちによって,その仲間になる資格がないと拒絶されているように感じられるのです。いつの間にかはぐれたしまった海路は,独自のものです。天候はおおむねわるく,海はしばしば荒れ出します。操船術を授けてくれる信頼できる人もありません。暗い空の下の,荒れる海の,どこへ向かおうとしているのかも分からない果てしない航海を,無事にしとおせる見通しを持てません。なんとか確保した入り江に避難したとしても,人生は航海です。ひと休みはいずれ航海に乗り出すためにのみ許されるのです。入り江でのひと休みは,それなりに安心で気楽ではあっても,多くの仲間たちからはぐれてしまった,それに匹敵する独自色を出すことは不可能だという船頭の気持ちは自分を助ける力を持てません。人とのあいだで信頼関係を築けなかったからには,自分で自分を助ける以外には道はないのですが。
本当は船団を組む者たちにとっても,どこへ向かおうとしているのかは謎なのです。それを考え出すと船団の一員であることが怪しくなるので,考えない方が身のためともいえます。ともかくも天気は晴朗で,波は静かで,仲間たちと共にある安心は保証されています。
一方,独自の海路を取らざるを得なかった人の中には,あえてその独自の人生を引き受けようとする人も出てきます。そういう人は,船団を組む人たちが難路にさしかかったときに相談するだれかがいるわけではないので,いわば自分自身に相談する以外にありません。自分で自分を助ける以外にありません。そういう力を発揮できた人は,いわば人生の開拓者としての立場に立ち,一種の英雄として船団を組む人たちに対しても指導的な立場に立つことになります。いうならば一旦は船団を組むものたちからはぐれ,改めてそこへ別格な形で回帰したことになります。
ボクサーはハングリーでないと強くなれないといいます。作家は日常に満足してしまうと作家である理由がなくなるといいます。そういえばドストエフスキーや太宰治は,いつも金に困り借金をしていたということです。
人間は自我に拠る存在として,最も特徴づけられています。自我は人生を切り開き,自己を形成していく上での拠り所です。自我は自己と人生の光の世界の演出者といえます。そしてそれは話の半分です。残りの半分は(半分以上です),自己と人生の闇の世界の話になります。闇は,無,沈黙,死に通じるものです。光の世界のものである自我ないしは意識の力がとうてい及ばない世界です。
人間は光を知ることになった者として,必然的に闇を意識する者となったということでもあるのです。闇がなければ光もないのです。闇は光を無化する力を持っています。自我が力強く機能しているかぎりは,自己と人生は自我のものですが,機能が不全化すると自己と人生に翳りがさしていきます。
人が自我に拠って光の世界を切り開くことができているかぎりにおいては,人生は喜びです。自己は誇りに値するものです。そして自我の衰弱に伴って光の世界が翳りはじめると,不安,暗鬱,無力などの重苦しい気分に傾き,それは闇の無化作用が意識に及んでいる証拠です。自我がなんとか力の回復をはかれないかぎり,自己と人生は絶望とあきらめの境地に追い込まれていきます。
それらの意味で人生は過酷です。生まれたばかりの赤ん坊は,自然のものから自我に拠る人間への移行形として,自然の特徴といえる全ないしは完全の様相に準じるものを身にまとっているかのようであり,その具体的な防具が誇大感と万能感といわれているものであるようです。赤ん坊は母親との共生関係(母親と共に「共生球」の中に自閉するが,母親を他として意識しない)を機軸にして,おもむろに自我の機能が活動していくことになりますが,しばらくのあいだは誇大感と万能感とで移行期の不安が生物学的に保護され,緩和されると考えられるのです。
赤ん坊の自我は未熟とはいえ光の世界のものです。その発光体の存在根拠であり,後見人でもある無意識は闇の世界のものです(意識の力がおよばないという意味です)。闇にすっかり捉えられると光のものである自我は消滅するように,闇には無化作用があります。生まれたばかりの赤ん坊の心もとない自我が闇を意識するときに(意識しないわけにはいかないはずです),その無化作用によって粉砕されかねないほどの怯えを持つと思われます。ですからとりわけ時間をかけて,慎重に馴化させる必要があるでしょう。しばらくのあいだは,生物学的な装置によって,本能のレベルで自分で自分を護らなければなりません。そしておもむろに母親の助けを借りて自我の活動がはじまっていくことになりますが,心の発達,成長の過程で,誇大感や万能感の基となる心の防護装置は取り除かれていかなければなりません。成人になってもそういう心理が色濃く残っていれば,明らかに病的です。
病的な心は空虚感や無価値感に悩まされますが,誇大と万能の幼児心性の支配を受けていると,怒りと羨望と被害者意識とに捉えられます。自分は誉められてしかるべきだという気分があり,一方ではそんな人間は一人も居ないという絶望感と被害感と怒り,憎しみを覚えるのです。
被害感,怒り,憎しみは,周囲の人たちが,自分の中にある誇大感を認めようとしない,するわけがないという感情と,それと関連しますが自分が賞賛に値する人間であることを認めようとしない,するわけがないという感情に端を発するものです。どことなくそれが満たされることを当てにする気分の中にいるために,あたかも周囲の者が当然のものを自分に与えてくれないという被害者意識になってしまうのです。
自我を支配するほどの勢力を持つ幼児心性は,病的な心の孵卵器なのです。それらは対人関係を損なうもとになるものです。
万能感に応える立場にあるのが母親です。母親に課せられている役割は,赤ん坊の欲求の高さと母親が現実に応えることができる能力とのあいだの落差を埋めることです。赤ん坊が母親の助けによって,誇大感と万能感とを要求することが現実的でないことを体得し,それらの旗を撤去する気になったときに,一定の安心感と共に母親の現実的な愛情を受け止め,感謝する心が形成されていきます。それは母性が十分に機能したことを意味します。しかし貪欲な要求をする赤ん坊に対応しようとする代わりに,母親が自分の都合に赤ん坊を従わせようとするときに,赤ん坊の自我の形成は危機的な状況に置かれることになります。
このような意味で赤ん坊の期待と母親の受容力とのあいだに隔たりがあれば,赤ん坊は大いに混乱することになると思います。赤ん坊の自我はしがみつく自我になり,自律機能を自然的に発達させることができません。そして赤ん坊は,誇大欲求と万能欲求とを手放せず,いつまでもそれらを要求しつづける子であるか,表面はおとなしく,しかしながら無意識の中にこれらの欲求を保持したまま大人になってしまうということが起きるのです。
このように大人になって心の病気に苦しむときに,その人の幼いころの問題が表面化していると考えられる具体的な事例が大変多く,それは少なくても機能的な心の病気については,一般的にいえると考えてほぼ間違いがないように思われます。大人が人に見捨てられる恐怖を持つというのは,どこか不可思議な感じを与えるかもしれません。見捨てられるという言葉には,人間の上下の関係が込められており,生殺与奪の権力を持つ者によって人生を切断されるというふうな強い表現があります。この言葉は,幼い子と親の関係にこそふさわしいのです。乳幼児にとって,親に見捨てられるというのは,生死に関わる恐怖です。子を守る力を持っているはずの親と,その親の力を当てにする子との関係は,一方的なものです。ですから子供の立場では,いうならば絶対的に確かな信頼感がなければ,危ないのです。信頼の感覚が怪しくなったときに,この恐怖感情に強力に見舞われることになると思います。
実際に親に嫌われた幼い子は,悲惨なことになります。どこにも助けを求めようもありません。捨てられたり,虐待されたりということも現実に起こります。それほどでなくても,幼い子が愛されず,嫌われると感じると,精神的に抹殺される恐怖を持つと思います。
Tさんは50歳を過ぎた主婦です。子供はありません。高校を卒業してすぐに結婚しました。夫は,学校で相談に乗ってもらっていた教師です。家庭の事情をよく知っている男性と,助けを求める形で結婚しました。
夫は大変優しく,よくできた方です。Tさんにはこの上もない伴侶といえるでしょう。
結婚して十年ほど経ったころに,うつ状態を伴う強迫性障害を発症しました。入院も経験しました。私のクリニックに転じてきたのは,発症して15年ほど経ったころです。火の元,鍵などの確認行為や,トイレに一度入ると10分ほども手洗いをするなどの強迫行為があり,家事は夫の手助けなしには不可能でした。「料理,洗濯,掃除などは苦手という以上に,嫌なものは嫌なんです」と強い口調でいいます。一人でいることの寂しさに耐えられず。といって出かけるところもあまりありません。荒れる無意識と無力な自我の反映として,無為に寝て過ごす日々がつづきました。
一番の問題は以前からあった買い物依存でした。安い物には関心がなく,高価な洋服を買いつづけ,一室が洋服で一杯になっているということでした。「欲しいものは必ず買ってしまう。我慢することはできない。お金がなくなると万引きするかもしれない。いつもは家にこもっているが,外出すると必ず買ってしまう」といっています。そのときの心理は,「駄々をこねている子供とおなじ。後でまずいと思うが,そのときは家計のことは考えない」ともいっています。一方では老後のことも含め不安で一杯といい,死にたい気持ちが波のように襲ってくるといいます。夜中にパジャマのまま飛び出したことがあります。車に当たって死ねばいいと考えていたそうです。薬を過量に飲み,救急車で運ばれても胃洗浄を拒否するということもありました。
ある時期夫に対して攻撃的になり,「この人(と傍らにいる夫をそう呼びます)と一緒にいると我慢しなければならない,それを脅かされる,逃げるしかない・・・」などといいます。後々落ち着いてからのTさんには信じられない口の利き方ですが,当時は夫に何か不満があるのかという雰囲気でした。やがて幻覚,妄想が現れ,夜中に雨の中を戸外に飛び出し,連れ帰ろうとする夫から逃れようと大声を出すなどするようになりました。夫と別れたいともいいます。しかし夫はいかなるときも冷静に対処しているようでした。
Tさんは親子関係に大変問題がある家庭で育ちました。幼いころに,母親と外出すると,母親はどんどん先に行ってしまうのが当たり前のようでした。学生のころには鞄の中をチェックされたり,何かと干渉されたと思っています。「母親が死んだときに涙が出なかった,義母のときは泣いたけど」といいます。
父親のことは自分勝手,嘘つきといいます。両親は喧嘩ばかりしていたそうで,早く家を出たい一心で結婚したといいます。
一方,夫はゆるぎなく受け止める人でした。それに助けられて,Tさんは最悪の危機からしだいしだいに脱していきました。初診のころは生理的に無理といっていた家事全般も,ほぼこなせるようになっています。夫としばしば旅行を楽しみ,旅先で知り合った人の生き方に接して心を動かされたり,自宅を訊ねてくる夫の友人たちとの語らいを楽しんだりしています。
そういう現在でも,夫が毎朝仕事に出かけるときは不安になります。毎朝,毎朝,「今夜は帰って来ないのではないか」という不安と猜疑に悩みます。理性の上ではそんなことはないと分かっているのですが,どこか信じ切れないのです。夫に,「今夜,帰ってくる?」と何度となく訊いてしまいます。夫は,「他に行くところがないよ」とその都度返事をします。
夫は教師としての仕事のほかに,講演やボランティアなどで忙しい人です。自宅でも何かと仕事をしています。Tさんはそういう夫が羨ましく思います。夫と比較して,自分には何にもないという気持ちになり,しばしば落ち込みます。焦りも感じます。羨望し,僻む心が夫との関係にひびを入れかねないという客観的事実があり,それが更に夫に見捨てられるのではないかという不安を増幅するのです。そのように最も信頼し,頼りとする夫にすら,関係破壊的な心がしばしば頭をもたげます。関係を切断しかねないのは潜在する強い怒りですが,その原点は,母親に見捨てられるのではないかと怯えていた幼児心性にあります。その恐怖が強い分怒りも強いのですが,Tさんは直接的に怒りを表す性格ではありません。怒りは意識の奥深くに潜行して,吐き気,過食,買い物依存などを,抑えがたく引き起こす動力となっています。
人を信じることの基本のところで,身をもって教えられるものが希薄だったTさんの心を,支え,励ました夫の助けによって,Tさん自身の心に癒す力がすこしづつ賦活してきたといえると思います。
人を信じる能力は自我のものです。Tさんの自我は,人を信じるという一点においても,発育不全だったといえるのでしょう。荒れる海に打ち破られる防波堤のように,発育不全の弱い自我が,無意識の圧力に抗しきれずに破壊された様相が,Tさんの統合失調症に類似した心の病理現象です。この上もない支え人である夫にすら怒りと不信感を露わにしたのは,そういう事態においてでした。そのような強い怒りと不信を抱え持つ無意識の圧力の下で,自我の力は相対的に心許ないものがあります。ずいぶん穏やかになった現在でも,夫が帰ってこない(見捨てられる)のではないかという不安が拭い切れないのは,そのような事情に基づいています。
正月に実父の家に行きました。実家には父親が一人で住んでいます。Tさんは父親から父親らしいことは何もしてもらっていないと思っています。それなのに父親は,当然のように世話をやいてほしがるのです。高齢とはいえ,自分でできることがいくらでもあるのに,子供たちを呼び寄せようとします。姉を通じて声がかかると,できるだけ断るようにしていますが,いつもというわけにもいきません。なんといっても父親だから,できることはしてあげないといけないとも思っています。しかし父の所へ行くたびに,嘔吐感に悩むのです。
正月の集まりは,四人の姉妹とその家族も含むので,かなりの大人数になりました。きつい性格という妹二人は途中で帰り,姉もしばらくは他用がありました。一人で山となった汚れた食器を洗っているうちに,ひどい吐き気に襲われました。Tさんには,こころに障害を持っている事情を姉が知らないわけではないのにという怒りがあります(この姉と会って話しをしたいという私の申し出は,「親でもない私が何のために行かなければならないの?」と拒否されました)。夫が口添えをしてくれなかったことにも怒りを覚えます。無意識に潜行する怒りがそもそも相当なエネルギーを持っていると思われ,いわば火薬庫に点火されたような心的状況が生まれてしまいました。
翌日から過食と買い物依存が激しくなりました。過食はふだんもあります。買い物依存もときどき起こります。しかしこの正月のあとは,なりふり構わずといった買い物依存になってしまいました。夫への不満,怒りも,意識にのぼってくるのです。
そういう折に,「無性に母親が欲しいんです」といいます。そしていまは亡き母親を求めているという意味ではないと,あえてつけ加えるのです。それを夫に求めているように思うといいます。
この言葉からは,過食も買い物依存も,幼いときの情緒的に満たされなかった心と密接な関係がある様子が窺われます。
信頼と愛情との観点から,ほとんど唯一といえるほどに重要な夫との関係は,夫のふところの深い愛情によって保たれているといえるでしょう。しかしいま述べたように,心が怒りで荒れると,その夫との関係も不確かになってしまいます。そういうときに心を繋ぎとめるのが,過食であり,買い物への依存なのです。
これらの病理的な心理現象は,対他者関係が自己を正常に保つ上でいかに重要であるかを示しています。Tさんの例を通じても窺われるように,病的な心理と行動化が表われるのは,対他者関係が危殆に瀕しているときです。最も重要である夫との関係さえもがTさんの心を現実世界に繋ぎとめる力を失いかけたときに,無意識なる海は波高く荒れ,自我なる海に浮かぶ小舟の船長は,自己と人生とを支え,かつ創出する操船術に著しい困難を覚える状況に置かれるのです。漂流しかねない小舟を操る能力(自我の機能)が凝固し,不全化したときに,満足と安心とを激しい怒りを込めて求め,無意識なる荒れる海の破壊的な圧力を前にして,自我がせめても自己を現実世界に繋ぎとめようとする窮余の策が,過食であり,買い物依存であったと思われます。
TさんをTさんの世界に繋ぎとめておくのは,ふだんはなかんずく夫との関係です。一般に安定した心情でいる人の心の世界では,両親をはじめとした重要な人たちとの関係がゆるぎなく成立しているといえます。Tさんの場合,人格発達の早い時期に,両親との関係が不確かでした。典型的な悪しき依存の関係でした。見方を換えると,見捨てられる恐怖が和らげられることがないまま成長し,その強力なものは無意識の世界に布置しつづけたことになります。それは自我が,心を世界に繋ぎとめるための最大の拠り所を欠いたがために,世界から転落し,あるいは世界を粉々に砕かれてしまいかねない脅威を内に抱え込んでしまったということを意味します。そしてそれは,無化される意識,闇の恐怖,死の恐怖といったものにつながるものでもあります。
実家での正月の集まりでのTさんの経験は,見捨てられる恐怖を活性化させるものでした。たった一人で山と積まれた汚れた食器を洗う作業は,そういう経験でした。受け入れ難い父親のための集まりで,Tさんは孤立無援の心的状況に置かれたといえるのでしょう。幼児心性が一気に賦活したTさんの心は,小児的,主観的な世界に埋没してしまったのです。夫さえもTさんを刺激したことになるほどに強力な怒りは,Tさんの客観世界とのあらゆる関係を破壊しかねないほどのものでした。それはTさんを発病に導くことになった,心の原風景(幼児心性)であったといえると思います。
活性化した見捨てられる恐怖は激しい怒りを伴い,Tさんの心的世界を粉砕しかねないものであり,世界を保持するために自我が取った窮余の策が,過食であり,買い物依存であるといいましたが,それらのものに必死に助けを求めなければ,世界は粉々に砕けそうな恐怖,一切のものとの関係が失せる恐怖(統合失調症に見られる世界崩壊への恐怖),あるいは無化する闇へとまっさかさまに転落していく恐怖といったものに対処できなかったといえるのでしょう。
依存の対象へのTさんの激しい没入は,母親を強く求めているというTさんの言葉とも符号するものです。Tさんは,実際の母親を求めているという意味ではないとわざわざいうのですが,母なるものの不在形として実際の母親との関係があったということであり,それは見捨てられる恐怖と直結するものです。そして夫がいくら母親的な存在であっても,母なるものへの欲求が夫によって満たされるのは無理というものです。そうしてみると,Tさんの心が望ましく満たされることは相当に難しいといわざるを得ないことにもなります。ですから唯一,最大の良い依存の対象である夫にさえ怒りを向けたのです。これまでに,夫に助けられて徐々に自己の回復がはかられてきたといういきさつもありますが,Tさんの心の飢えが活性化すると,夫の存在すらが無意味化する危機に立たされるのです。
いま述べたような耐え難い心的状況では,心の飢えを封じられていた幼児心性が,強い怒りとともに意識の表面に浮上してくることによって,客観世界との関係が粉砕されかねない恐怖を持つことになると思います。それはまた,それによって心の病理現象の原点を明らかにするという意味合いを持っています。それは幼い時代の自我の自律性の根の保護を,当然してもらえるべきであった両親によってしてもらえなかった強い怒り,悲しみ,口惜しさ,虚しさなどが抑えようもなく表明されているということでもあります。
Tさんは家庭から逃れるように,高校を卒業すると同時に結婚しました。家庭がTさんには安心できる場所でなかったのは明らかですが,見捨てられる恐怖から逃れるための結婚というのとは,少し違う側面もあるようです。
乳幼児が母親の愛情を期待し,要求するのは自然なことです。それが適えられなければ怒りを覚えて当然です。赤ん坊の怒りは自然的,適応的なものと考えられるので,見捨てられる恐怖に捉えられ,それが母親の愛情によって緩和されなければ,その怒りは撤回され,意識の上から引っ込められることになると考えられます。それが生存本能に即した適応的な心の動きといえるからです。それは自分の,生存にかかわる正当な主張を犠牲にし,母親に取り入ったことを意味します。自我は自律性を犠牲にし,母親の自我の支配の下に入るのが安全という選択をしたことになります。
見捨てられる恐怖という強力な脅威の下で,そのような策を講じた自我は,母親の自我にしがみつくことになるのです。それは母親にとっても,かなりの程度望むところだろうと思われます。赤ん坊がおとなしくなり,聞き分けの良い子になるのは,家事や育児に追い回される母親にとっては悪いことではないだろうからです。更に,それ以上に,半ば意図的に赤ん坊の怒りを緩和せず,沈黙させた母親は,母親自身が脅かされつづけてきただろう見捨てられる恐怖を抱え持っている可能性があります。そうであれば母親自身が心の奥深く,情緒的に満たされない思いを持つ分身を抱え持っていることになります。そしてそういう場合には,もう一つの分身である赤ん坊によって情緒的に満たされ,見捨てられる恐怖を緩和させたいという強い要求を,内々で正当化させる理由を持つことになるのです。
赤ん坊が自己の自然に即して成長していくことは,母親の下から離れていくことを意味します。それを喜べる母親であれば,赤ん坊の怒りを受け止める愛情を持つことができるのでしょうが,それを喜ばない母親もいて不思議はありません。そのような母親は,赤ん坊をいわば道具にして,母親自身の見捨てられる恐怖を恒久的に緩和させようと無意識的な意図を持つことになります。そのような母親の下で,母親から容易には離れられなくなった幼児の心は,母親が望むように機能するしかなくなります。両者は分離しがたい一対の心となり,場合によっては大変仲睦まじく見えさえするのです。
Tさんの場合は,親にしがみつく自我ではありませんでした。内在する強い怒りと共に,Tさんに親元から逃れるように促した心の動力は,別種の恐怖でした。それは母親ないしは父親に呑み込まれる恐怖だったようです。親の都合のいいように利用され,自由が奪われ,呑み込まれてしまう恐怖から逃れたのです。自己が失われる恐怖でもあったと思います。
良い子の姿勢は親の一定の評価が得られて,親子関係がそれなりに安定するのに比べて,呑み込まれる恐怖をも併せ持つ子供の場合には,親の暗黙の要求を拒否する心理力動が働くことになると思われます。それは自主独立の心にも見えますが,内在する強い怒りの支配を受けています。それを克服できていない以上は,怒りと恐怖に支配された行動になり,親から独立した心には程遠いのです。これもまた悪しき依存の一つの形です。つまりTさんの自我は,母親に甘えたい強い欲求と,それを強く拒否する心とを無意識下に潜め,その支配を受けている幼児心性の様態にあるといえるのです。
さきほど述べた父親との関係で生じた感情の乱れと過食と買い物依存とは,Tさんの怒りが,自分を自分の世界に繋ぎとめておくはずの,客観的なもろもろのものとの関係を破壊してしまいかねないほどに強力だった心的状況で起こったことです。これ以上にない伴侶と思われる夫との関係さえ粉砕されかねないほどの,怒りと対人不信が一気に浮上したのです。
彼女を現実世界に健康的に繋ぎとめることができるかぎり,Tさんは大人の心を保つことができます。つまり自我がそれなりに機能しているのですが,父親と姉妹たちとの関係で味わわされた疎外感は,彼らによいように扱われる(呑み込まれる)ことへの強い怒りを浮上させました。それは自我を恐怖させるものでもあり,本来は自我の力の下で,意識の地下にあって人目に触れてはならないはずのものをも浮上させることになりました。信頼と愛情とで与えてくれるはずの安心を,誰もが保証しようとしないことへの怒りに駆られて,なりふり構わずに満足を求めて過食と買い物に走ることになりました。誰もが自分を助けず,見捨てようとしていると被害的な怒りに駆られたときに,Tさんを世界に繋ぎとめることができるのはそのようにしてでしたが,それは幼児の世界への退行という様相になりました。
それは自我の世界で起こることではなく,いわば裏の自我の世界でのできごとです。裏の自我の営為では破壊的な怒りが発動します。そこでは社会性がまったく配慮されることがありません。おもむろに自我の機能が回復されるまでは,他者の支配を被害感に駆られて拒否するTさんは,裏の自我の支配を受けることになるのです。そして時間の経過と共に自我の機能が回復していくことができるためには,夫の動じることのない母親的な愛情が不可欠です。仮に夫がTさんに愛想尽かしをしてしまったとすれば,Tさんの自我の機能の回復のために必要な,現実的な拠り所を見出せなくなる危険性が高くなるでしょう。
呑み込まれる恐怖については,逆に相手を呑み込もうとする甚だしい例がかつてありました。自分の要求をあくまでも押し通そうとするので,地域でのトラブルが絶えないのです。両親は耐え切れずに,行方が分からなくなってしまいました。治療者に対しても,幼児的な万能欲求に裏打ちされているかと思われる期待感を持っているらしく,何かと要求をしてきます。幼児的な誇大欲求を満たすべく,相手を呑み込み,支配しつくそうとする姿勢は,相手にとってこの上もなく厄介で迷惑なものですが,その心理の背景にあるのは,大きな不安と恐怖と怒りです。その幼児心性の根底には見捨てられる恐怖があり,和らげられることのなかった赤ん坊の誇大欲求と万能欲求とに裏打ちされた被害感が,相手を支配しつくす(呑み込む)ことによって,それらの欲求をなにが何でも手に入れようとするのです。その被害感と過大な権利の要求は甚だしく現実感を欠いており,反社会的な行動になってしまいます。
この種の反社会的行動に走る精神病質者について,J.Fマスターソンは次のように指摘しています。
「幼いころに愛情剥奪を経験している子供たちは,対象からすべての情動投資を引き上げ,感情を持たなくなる,病的な自己愛を満たすために,治療者を操ろうとする」と。
40代の男性会社員Yさんの例です。
Yさんは一人っ子です。父親はYさんが十代のときに病死しています。2児の父で,妻と実母との5人家族です。会社には在勤10年になりますが,大学までの学校生活も含め,最近までほとんど元気に過ごしてきました。初診の一ヶ月ほど前から会社をしばしば休むようになり,受診にいたりました。欠勤の理由は,不眠,気分の乱調,食欲不振などですが,その他に会社の上司や同僚への不信感の増幅があり,それがストレスになっているようでした。背景として会社の再編問題があります。一部上場企業に就職したのですが,Yさんの職場は切り離されて別会社に移行することが決まり,本社に残りたければ遠方へ移住しなければならないことになりました。他の多くの同僚が選んだように,Yさんも今までどおりの職場に残ることに決め,受診した半年ほど前に再出発という形になりました。Yさんは社会的な名聞にこだわる傾向がありますので,一部上場企業に見切りをつけるのは,苦渋の決断でした。
診療が始まってしばらくは,会社の問題にだけ目が向き,家族間の葛藤が語られることはありませんでした。そのことに気がつかなかったということになりますが,気がつきにくい心理的な事情もしだいに明らかになっていきます。
初診の数ヶ月前に,母親の名義になっている土地にYさんの金策で家を建て,母親と同居する計画が決まりました。そして実際に同居することになったのは初診の2ヶ月ほど後のことですが,そのころから急激に精神状態が不安定になりました。
診療を重ねるにつれ,母親の問題が主題になっていきました。母親が孫であるYさんの子供に接する様子を見ていて,自分の幼かったころの記憶が蘇りました。母親によく叱られ,勉強を強制され,何かと干渉されたのです。しかし子供のころはそういうことに殊更な意識を持たず,一貫して母親に従う良い子だったといいます。
同居してからは母親の声を耳にするだけで怒りがこみ上げてきます。しばしば衝突もします。荒れ狂うような怒りの他に,母親にそういう態度を取ってしまう自分への怒りも強く,罪悪感に悩まされます。
母親との同居問題が浮上し,現実化することに伴ってYさんの不調がはじまっているのが明白であり,病状の改善には母親と一定の距離を取る必要があると判断されました。妻をもまじえてこの問題を話し合い,母親に近くのマンションに移ってもらうことになりました。このことをYさんが理解し,実行に移すまで相当な逡巡がありました。「母親と一緒に暮らしながら解決できることだし,母親があまりに気の毒だし,世間がどう見るかということもあるし・・・」と抵抗感が強かったのです。しかしなんとか納得して自分で母親に別居を申し出るということになり,実際にそのように行動しました。しばらくはYさん自身は母親と会わないほうがよいと思われ,母親とうまくつき合っている妻が,母親とのあいだの仲介役をすることになりました。
それでもしばらくは気分の動揺がつづきましたが,しだいに落ち着いてきて会社にも行けるようになりました。
しかし妻がしだいに疲れてきました。妻は事情を理解していましたし,姑とのあいだは悪くはなく,気さくな人柄でもありました。しかし本心ではまったく理解していない義母の相手をするのが苦痛になってきたのです。妻はYさんが長期の休職中にも動揺する素振りを見せず,Yさんを支えてきました。その妻の憔悴,苛立ちは新たな難題でした。
妻から伝え聞くかぎり,母親は不満で一杯のようです。「なぜ自分が家を追い出されなければならないのか」と母親は思っているようです。古い土地柄ということもあり,母親は近所の目を気にするのですが,その点はYさんもおなじです。「母親は,自慢の孝行息子となぜ別々に暮らさなければならないのか,近所の人が理解できないだろうと考えていると思う」とYさんはいいます。Yさん自身もそう思うのです。想像される近所の人の目で自分を見,「自分はなんてひどいことをしているんだ」という罪悪感に,しばしば責め苛まれます。「自分がしっかりしていれば,同居しながら母親を困らせるようなことをしないですんだ」とも思います。依存関係にある両者は,一般になにかと似てしまうものです。しかしYさんは,一方では母親が身勝手だとも思うのです。果てしない堂々巡りになってしまいます。
母親はYさんを,「とてもよい子です。しかし心の底がよく分かりません」と評しています。その母親は息子の深刻な事態を前にして,表面的には理解を示して別居生活に踏み切りました。しかし心の底では理解も納得もできずに,強い不満のままでいたようです。そういう母親をYさんの立場でいえば,「母親はよく理解して別居に応じてくれました。しかし心の底ではよく分かっていないと思います」ということになり,両者の関係は相似形になっています。
母親がいう「とてもよい子」というのは,子供時代のYさんのことであり,いまもそういう側面があるということだと思います。そして「心の底が分からない」というのは,結婚してからの息子の様子が少年時代とは違うといっているのだと思われます。それは結婚によって,Yさんの自我が幾分か自由を回復させたということなのでしょう。
一方,少年時代のYさんは,自分自身が「心の底が分からなかった」のです。それは母親に気兼ねをしない,自分自身の自由な感情,思考であり,母親への恐怖によって強く抑圧されていたのです。そのような形で昔からあったものです。そのように抑圧された心の要素は,母親が受け入れるはずのものではなかったので,Yさん自身が幼いころから習慣的に,無意識的に,いわば見捨ててきたのに違いないのです。
母親が「分からない」といっている「Yさんの心の底」は,元々はYさん自身にも「分からない」形になっており,いわば見捨てられる恐怖を仲立ちにして,「良好な親子関係」があったのだろうと想像されます。いうならば母親から見捨てられないために,Yさんはかけがえのない自分自身の重要な分子を見捨てたといえるのでしょう。その意味で依存する母と子は共犯関係にあったといえます。両者の犯意が何に対するものかといえば,無垢なる自然のものであるYさんの分身に対してです。母親に向けた良い子の顔は,一方で,自分自身に対しては無慈悲な顔を持っていたことになります。
Yさんの父親は会社が忙しく,家庭は妻にまかせきりだったようです。母と子の関係は密接になる状況がありました。母親に「心の底が分からない」といわせるようになった現在のYさんには,幼いころは叱られ,何かと強制された思い出だけが残っています。ずっと良い子だったと思うとYさん自身もいっており,怖い母親に取り入るしかなかったことに,今は気がついています。それらのいきさつから,いわば母親の自我に憑依された自我の形成があったと思われます。
極論すれば,母親を安心させ,母親の心を満たすためだけに存在を許されたともいえる幼いYさんは,良い子であることによって安心を手にすることができていたのです。それは一方では情緒的な満足を犠牲にされた分身たちを,無意識下に閉じ込める必要をもたらしたのですが,Yさんが手にした安心は,そこからの圧力に脅威を受けることなく,すっかり意識から遠ざけていられるほどの力を持っていたようです。しかし意識下には強力な恐怖心と満足を求めて怒っている心が潜在していたのです。それらのことは結婚をして,母親から独立した生活をするあいだに,少しずつYさんの意識に上るようになったと思われます。改めて母親との同居問題が持ち上がったときに,Yさんが大いに混乱しはじめたのが,その証拠です。
一方の母親は,半ば無意識ででしょうが,幼い時代のYさんの,そういう弱みを存分に利用してきたといっても過言ではないと思います。自分自身の安心,満足をもとめて息子を巧みに操作してきたといえば,酷ないい方になるでしょうか。しかし「心の底が分からない」という不満は,Yさんの心の一部が,自分が望み,求めてきたものではないという意味以外の何ものでもないだろうと思います。
Yさんを何がなんでも自分に従うように仕向けたと思われる母親の心も,たぶん無意識的な力に操られていたと思われます。無意識下に布置する大きな力の支配を受け,母親の自我は自由ではなかったと見なければ,かけがえのない息子への支配的で身勝手な心のあり方の説明がつきません。自由な自我であれば,他でもない自分の大切な息子に対して,より余裕のある柔軟な心でいられないわけがないのです。そういうふうに考えれば,母親の自我も無意識下にある大きな力に捕捉され,なにものかに憑依されていたということになります。そうであれば自由な自分自身の立場,考えを持つのが困難だったと思います。Yさんの母親は,彼女自身が,おそらく見捨てられる恐怖とそれに伴う怒りとを,強く持っていた人ではないかと思われます。悪しき依存関係にある親子は,互いに似たもの同士という側面を持つのです。
実際に母親に会ったときに,ある種の威圧感と怒りをたたえた表情が感じ取られました。もしかするとそのときの母親の心には,大切な息子を奪い取られる怒りがあったのかもしれません。そのときに感じた迫力は,幼い子を怯えさせ,威圧し,望むように従えるには十分なものでした。
怯えを持った幼い自我が,いわば保護色で身を守るように,母親に取り入るのが安全と感じただろうことが理解できるよう思われました。
母親の支配を受け,憑依された自我にとって,憑依しているものは守り神でもあります。幼い息子の怯える心を利用したのが母親なら,怯える心を鎮めるために幼い子は母親を利用しました。つまり母親を安心させ,少しでも母親の心を満たすように心をくだけば母親の庇護をもらえるのです。まだ子供といえる時代には,母親を必要とする公然の理由もあり,問題は表面化しないのです。
結婚し,頼りにできるよい妻に恵まれ,しばらく母親とは離れた生活がつづきました。この間に,妻との関係でよい依存を体験したことになります。
Yさんの心が荒れ出したのは,母親との同居問題が持ち上がった時期に重なります。従来は無意識だった母親への依存が,こんなにも強かったのかと,Yさんは驚きを込めて何度か語っております。そして制御し難い怒りと罪悪感とが交互に現われ,心の沼が激しく揺れる日々がつづきました。
人間は何ものかに依存しないではいられない存在です。前章でも述べましたが,依存にはよい形とわるい形とがあります。一人一人の中でそれらは入り混じっていると思います。見捨てられる恐怖は,わるい形の依存へと発展していく素地となるものです。わるい依存の形が顕著になると,自我の自律性が育たず,主体性と責任意識も未発達になります。
悪しき依存関係にある親子は,二人組みの内部にあるかぎり問題はないかもしれませんが,共に社会的な自立を果たせない未熟な自我の姿でもあるので,それ自体が心の病理現象といわなければなりません。
Yさんは心理的に紆余曲折しながらも,会社での左遷をも経験しながらも,それにめげない自我の主体性の確保と,社会的な立場の確保とをほぼ自分のものとしています。今後は母親との同居が現実の課題になるでしょうが,自分の心の内部に拠り所を得たYさんは,母親から自由になった主体者としての自己を確立しつつあり,かつてのような混乱に陥ることはないだろうと思われます。
以下は長期にわたり規則的な通院をしているにもかかわらず,病状がまったく改善しない中年女性Wさんの例です。
Wさんは夫とふたり暮らしで子供はありません。もともと仕事や習い事でずいぶん頑張る人です。気力をふるって精一杯励んでいるときは,生きている実感があります。しかし,一段落つくと落ち込みます。そういうことが繰り返されてきました。やれることはやってきたという思いがあり,これ以上はどうすればいいのか,とても虚しいということで受診にいたりました。
両親はWさんが幼いころに別居しています。母親が家を出て行こうとしたときに,夫がとめてくれるかと思っていたのが,別居するのもいいかもしれないといわれて別居になってしまったと,母親から聞かされたといいます。Wさんにとっては,その以前から母親には捨てられたに等しい心理状況だったといいます。それでも後に正式に離婚になったときには,冷静ではいられなかったそうです。離婚をするような夫婦であれば,自分は生まれてくるべきではなかったと改めて考えるのです。
Wさんは父の元に残りました。Wさんは「母親に捨てられたと思っている」といったり,「母親と一緒になるのを拒否した」といったり,「拒否ではなく,どうせ父親が許してくれないと思ったから」といいかけて,「それでは父親に愛情があったことになりますね・・・」と自分で首をかしげていたり,「母子家庭がいやだった」,あるいは「父には経済力があり,自分を扶養する義務がある。将来は大学へ行きたいという計算が働いた」といいます。そのときどきでいい方が変わり,混乱しがちです。
別居後,近くに住む母親のところにしばしば行っていました。母親を求めてではないそうです。義務感からのように思うとも,行くと物や金をくれたからともいいます。いずれにせよ母親は愛情深い人ではないといいます。母親が近所に住んでおり,生殺しにされていると感じていたともいいます。
父親は自分中心の人だったといいます。自分のためにだけお金を使い,母親には十分なお金を渡さなかったのも離婚の理由だったともいっています。
両親は母親がしている仕事が縁で結婚しましたが,Wさんは母親がしている仕事を軽蔑しています。それは母が死んだ今も受け入れ難いといいます。
父親のイメージを絵に描けば般若の顔になるといます。体罰もあったが,それ以上に精神的に怖かったそうです。自分の意見が認められなかったということですが,両親に対する怒り,憎しみ,恨みの感情が激しくあるように見える一方で,具体的に訊いていくと,説明が一貫しない様子がうかがわれます。
母親については,何かのことで自分が有名になったときに,母親がしている仕事が恥ずかしいと一貫して思ってきました。
母親が死んで十数年になります。母が死んだとき落ち込み,立ち直るまで二,三年かかりました。Wさんがいうには,「ふつうの親子関係では母親が死ねば素直に悲しみ,そして悲しみから立ち直るまでにそんなには時間がかからないと思うが,私の場合ははるかに屈折したものだった。母の死後に見た日記で,それまでは自分とまったく性格が違うと思っていたのが,意外と似ているのに気づいた」といいます。
母親が家を出たのは,同居していた父親の妹にそれを促されたからである,あの人に家庭を壊されたともいいます。そして父親と二人の父方の叔母は,それぞれに問題のある性格で,そういう子供を育てた父方の祖父母には会ったことがないが,誰よりも憎しみを覚えるといいます。
父親については,絶対に再婚させてやらないと考えていました。自分だけ仕合せになるのは許せないと思ったそうです。父親への激しい羨望がうかがわれます。父親が肺疾患で死んで数年になります。病床にある父親の様子は苦しそうでした。看病をつづけ死を見取って父親への怒りが和らぎました。そして父親にも認められるものがあると思うようになりました。読書家であること,音楽や絵画への造詣が深いこと,頭がいいことなどです。そして頭がいいのは母親もおなじとつけ加えます。
両親が好きだと思ったことは一度もないといいます。母親に抱かれた記憶がまったくないといい,しかし一人っ子だし,実際にはそんなはずはないとも思っています。
あるとき受診したWさんが沈み込んでいるように見えました。理由を訊ねたところ,「意識にはないのですが,もしかすると両親が死んだことと関係があるかもしれない」といっております。両親はたまたまおなじ月に亡くなっています。
Wさんには生まれてきたことへの根強い恨みがあります。どうしてもその気持ちを払拭できないといいます。初めのころはその理由はなんといっても両親にあるといっていましたが,ある時期からは,死んでしまった両親を恨んでも仕方ない,神様を恨みたい気分といい方に変化がみられます。
小学生のころから,死にたいと思っていました。大人になると,何かの犯罪を犯すことになるかもしれないと考えたこともあります。この時代を振り返っても,信じることができた人の顔も,尊敬できる人の顔も浮かびません。しかし明るく元気に,人に嫌われないようにと心がけていました。同年代の子には,気が強いためか疎んじられるところがあったのですが,大人好きがする子だったと思うといいます。
高校生のときに,夫となった人と知り合いました。Wさんがいうには夫は自己中心の人で,友人がいなかったそうです。「私がいないと彼は人と接点を持てなかった,私によって彼は生きる楽しみ,喜びを知ることができた,その彼が一生かかってでも償えないほど,私を傷つけることをいった,彼はそういうことをよくよく分かって結婚した」といいます。
夫は会社員ですが,自分の世界を大事にし,会社の仕事の犠牲になりたくない人だといいます。Wさんは自分の方をだけ向いていてほしいと思い,夫が会社員として成功してほしいとは望んでいません。二人でしみじみと人生を語って暮らすことができれば,それで満足なのです。その夫がときに,「自分の世界に閉じこもってしまう」のです。Wさんは取り残されてさめざめと泣いてしまいます。夫は見かねて傍に寄り添ってくれます。
そういうところを見ると,「名もなく,貧しく,美しく・・・」といった類の仕合せな生活があってもよさそうに思われますが,隣の空き地に家が建つと分かってから,その種の平和が脅かされ,同時にWさんの不穏な心が表に表われてきます。
Wさんはあふれるばかりの陽光を何よりも大事に思っていました。それが隣の家の建築で奪われることになるのです。まだ会ったことがない隣人に激しい敵意を感じます。建築がはじまるととても大きな家と分かりました。相当な金持ちだろうと思われます。建築中の家を一家で見に来たときに,幼い子供たちの騒ぎ立てる声が聞こえてきます。
Wさんは苦労をして手に入れた我が家が,「この程度のものでしかない」と改めて落胆します。自分たちは子供を望んだことはないが,子供がいるふつうの仕合せを羨む心があるのは否定しません。隣家への怒りは,太陽を奪われたこともさることながら,物心両面での羨望があるのも否めないのです。周りの平凡に生きる人を軽蔑してきたのが,一転して自分が誰よりも惨めで,認めるべきものがなにもないという心に転落してしまうのです。
最近になって夫に変化が生じました。会社での責任が重くなったのです。それに伴って帰る時間が遅くなり,その分,「二人だけの語らい」が犠牲を蒙るのです。遅くまで話したがるWさんに,夫が苛立つようにもなってきました。帰りが遅い夫を詰問して(Wさんには詰問しているつもりはありませんが),夫が怒り出すということもあります。夫を会社に奪われた,夫に裏切られたという思いが,Wさんの理性をしばしば圧倒し,混乱させます。
夫が楽器を手に入れました。元からその種の楽器が好きでした。夫が目をつけたそれは音が外に漏れないように細工してあるもので,インターネット・オークションに出品されていたのです。「金額の提示は高くできないのでたぶん無理と思うが,入札してみたい,どうか」と,事前にWさんの了解を取ってありました。夫にもそういう気晴らしが要るのは分かると思っていたので反対はしませんでした。そして落札はきっと無理だろうという気持ちもありました。
ところが落札してしまったのです。Wさんは,楽器に夫を奪われたと思いました。怒りがこみあげて夫に当り散らしました。自分が理不尽なことをしているのは分かっています。しかし,「私を放っておいてそんなことをしていいのか,許されるのか」という怒りがどうしようもなく立ち上がってくるのです。夫を会社に奪われたという焦りもあったので,怒りに火がつきやすい状況もありました。
夫は唯一理解のある人とWさんはいいます。夫との良好な関係が唯一生きる支えになっているといいます。しかし交際のある友人たちも含め,一人として信頼できないという思いが強く,夫も例外ではないいいます。自分には人を愛する心がないともいいます。Wさんは,表情などから受ける印象は,決して冷淡には見えない人なのですが。
両親を頼りにできなかったWさんは,怒りをこめて両親を心から排除し,幼いころから自分を恃む心が強かったようです。明るく,活発にと心がけ,人に負けないように,人に認めてもらえる(見捨てられない)ようにと,精一杯頑張って大人になりました。一息入れると自分には認めるべきものは何ひとつない,生きている資格も意味もないという気持ちに苦しめられます。ちょっとひと休みというわけにはいかなかったのです。より強く,より正しく,より好ましくと自分自身に鞭打って自己形成に励んできたのですが,その様子には,どこか追いすがろうとする影から逃れようと懸命になっている姿が感じられます。Wさんもそういう捉えかたを否定しません。
生活の中に小さな楽しみ,喜びを見出せるように,いろいろな提案をしましたが,無益です。家事がまったく苦手といって,実際にも夫まかせのようです。なにか大掛かりなことが必要で,「小さなことでは動けない」人なのです。
あるとき,「先生が提案してくれることが,小さなことなのにできない。自分は病気ではないのではないか。ただの怠け者ではないか。こんなことでは通院する意味があるのか,疑問に思うときがあるんです」といいます。このときに,「自分を恃む気持ちが強すぎて,問題を医者に託していないということはないですか」と訊いてみました。彼女はしばらく黙っていました。無言の肯定のように思われました。そして,「人を信じきれないというのは確かにあります。だれであっても私の病気は治せないだろうという気持ちがあるように思います。・・・・・それと,こんなことをいうと見捨てられるのではないかと怖いのです」といいます。
治りたい心がないわけがありません。現に長期にわたり規則的に通院しているのです。しかし一方では,治りたいと本当に思っているのか疑問だといいます。むしろ,この世から消えてしまいたいのだといいます。彼女によると,治ってしまうと怠けている口実がなくなるのです。Wさんは,怠けるという言葉が誰よりも当てはまらない人なのですが,なにかの目標に向かってまっしぐらに進んでいないと,怠けているように感じてしまうようです。いわゆる「全か無か」の人で,「ほどほどの満足」ができません。
実際にWさんもいっておりますが,治療者に自分を委ね切れないのは,見捨てられる恐怖が一因になっているようです。自己不信が強く,しかしおのれを恃む心もそれに劣らず強い彼女は,人を信じることが怖いのです。自分の本心をさらけ出すと(信じると),相手は受け止めかねるほどの厄介な荷物と感じるに違いないという恐怖が湧いてくるようです。彼女自身が,自分の内面には受け止めかねるほどのものがあると感じていることの裏面です。
また根拠のはっきりしない自負心が人一倍強く,一方では現実が伴わないので,逆にそれが無能感を呼び込んでいるようです。おそらく根拠のはっきりしない何らかの能力への感覚があると思われます。そしてそれだけの根拠が,無意識の領域には実際にあるのだろうと思います。
自分の力をそれなりに発揮できていれば,人は自分に納得できるものです。自分はだめな人間だ,何一つ取り柄がないと思っている人は,いわば持てる力をほとんど発揮できていないのです。そして評価の基準点が自己自身にはなく,何らか他なるものにあるのです。
それにしても何を基準にして自分を評価するのでしょう?人の価値を計る客観的な基準が何かあるでしょうか。
個々の価値は人さまざまでしょうが,結局は自分らしく生きているかということになると思います。それはなかなか困難な課題ですが。
Wさんが自分には価値がないと考えるのは,価値の基準点が,万人が感心し,賛美するものという甚だしく高いものだからであるといえるようです。その心理の背景にあるのは,幼児的な誇大欲求です。もう一つの幼児の幻想的欲求である万能感が,現実の両親などによって満たされることがなかったので,いわば万人が認めるほどの大きな価値を手に入れないかぎり,くつろぐのに耐える安心,安全もまた手に入らないという意識が働いたのではないかと思われます。それは両親から見捨てられた感覚と,逆に両親を拒絶した感覚とに起因する幼すぎる自立の試みだったように思われます。
Wさんが隣家に羨望の眼を向けたように,金持ちか,貧乏かということは一般的に小さな問題ではありません。お金はあるに越したことがないと思うのがふつうでしょう。本当にそういうことに恬淡としていられる人は,よほどの人物といえるのでしょう。そういう人であれば,おそらく自分らしく生きている人に違いありません。
Wさんは,お金にとらわれるのは愚かなことだという意識の強い人です。そのWさんがはからずも隣家の住人によって,富への羨望が強いことが暴露されています。しかしだからといってWさんの心が,実際に富によって満たされるものでもないだろうと思われます。Wさんには他人を見下ろす心があります。「その辺にごろごろしている人」といういい方をしてはばかりません。そういう自分を傲慢と認め,たとえようもなく醜い自分といいます。おそらくは富に恵まれているらしい隣人を蔑む心があり,その蔑む理由が精神的な豊かさに関連するものであり,しかしながらその隣人が少なくても自分より富において勝っている,自分にはそれすらないという心が働くのです。Wさんが精神的に満たされていれば,おそらくそういう羨望からは免れることができているはずです。実際にはWさんには,「自分には何もない」感覚があります。全力を出して目標にまっすぐ向かっている自分以外は認められない,という要求を自ら突きつけている人です。自然の意志の発動を喜び,楽しむ精神はなく,誰よりも高く,遠くへという精神性への要求があります。まるで誰かに命じられてそうしているかのように見えます。
自分が掲げた目標であれば,自分の力と相談した目標設定になるでしょう。途中で間違っていることに気がつけば,訂正することもできるでしょう。うまく進まないときに悩むこともできると思います。それは自己の責任において機能している自我の姿です。
Wさんの自我は,何ものかに憑かれた自我です。自我を強いて一途の前進を要求する他なるものがあるのです。
Wさんは人を信じることができないと自分でいいますが,人の評価を大変気にする人でもあります。その一つが母親の仕事を認め難いという,不可解なほどのこだわりように表われています。彼女の自我が自由であり,自律的であれば,好悪はともかく,より柔軟な姿勢でいられるのではないかと思われます。そういうことも含めて,人の全幅の承認を得たいというのが,Wさんが躍起となって自己を飛翔へと駆り立てているように思われます。
ある日,次のような内容の夢を見ました。いま述べたことが象徴的に表われているように思います。
カラフルな玩具のような自転車で,ある家の屋根から空を飛ぼうとしている。周りに人が一杯いて期待して見ている。しょっちゅうトイレに行く。
客観性を著しく欠いた無謀な内容です。Wさんの世界が,いかに客観的なものとの関係が育たないままでいるかということの表れのようです。Wさんはしばしば赤ん坊のように夫に甘えたがるといいます。玩具のような自転車というのは,その心と関係がありそうです。空を飛ぶ,周りで大勢が期待して見ているというのも現実的ではなく,退行的,小児的心性の表れのように思われます。この「期待している大勢の者」というのが,彼女の自我に憑依しているものに通じるように思われます。それによって自我肥大を起こしているようです。心の成長過程で,何らかの無理な心理力動が働いたことに伴うものに違いありません。
この夢からも,Wさんの無意識の領域に,自我を支配するほどの勢力を持つ小児心性が潜んでいることがうかがわれます。それは幼いころの親子関係に端を発するのはいうまでもないことです。
Wさんは幼いころから両親に怒りを持ったようです。「母親は別居をはじめる以前から私を捨てていた,だから別居とその後の離婚によって決定的に確認できたということであって,その流れは一貫している,だからそもそも私は生まれてくるべき者ではなかった」と考えています。おそらく見捨てられる恐怖とそれと関連する誇大感,万能感などが母親によって和らげられる体験を持たなかったのではないかと想像されます。それは愛される体験,信頼される体験の不在の感覚と,そうしたものを求めることへの警戒心とを招いたと思われます。
愛し,愛されること,信じ,信じられることを母親との関係で達成することをWさんは拒否し,空想的な母親に託しました。それらの感情のほかに,和らげられることなく持ち越された誇大欲求,万能欲求なども母親との関係からは怒りをこめて撤収し,空想上の母親に託しました。そのような感情と欲求の撤収と移動の主な動因は怒りでした。
彼女の自我に憑依したものとは,怒りによって呼び出された空想上の母親とその人に託した二大欲求です。憑依され肥大化した自我は,誇大欲求という全的なものに引きずりまわされ,元気で,明るく,正しく,だれもが認める蜃気楼のような人物像に向かって休むことなく疾駆しつづけました。疾駆しているかぎり,彼女は見捨てられる恐怖に端を発する,もろもろの恐怖や空虚感などを意識しないで済むのです。
万能欲求は夫に託されました。この欲求は現実的な対象が必要です。夫は楽器で遊ぶことさえ許されない,完璧な受け手の役割を担わせられています。いつか夫が同席しているときに,「まるでご主人は奴隷のようですね」といったことがあります。後でWさんは,そのことを,「夫はやけに気に入ったみたいです」という形で,半ばその意味を認めながらも不満をいっておりました。
自分としては精一杯頑張ってきた,これ以上どうすればいいのか分からないとWさんは思っています。疲弊した精神を跳ね返す気力がわかない日がつづいています。いくら頑張ってもだめだ,自分にはなんの価値もないという気持ちが支配しています。
Wさんの負の依存は,なにか絶対的なものを追い求めるという形になって現われています。それは両親への依存を拒否する心の裏面です。同時にそれは両親をもとめる心が未処理だということです。人一倍大人であろうと背伸びした子供でしたが,その自我は,本来依存するべきものを見出せず,怒りをこめて拒否し,目に見えない自分の力を信じようとしたように思われます。そこにおのれを恃む心の病理性があります。まだ甘えを必要としている時期にその欲求を封じたことに,心理発達上の無理があったのではないでしょうか。
治療者に自分を託すことができるとすれば,よい依存の対象にかけてみる気になれたということになるでしょう。それは確かに冒険です。治療者が本当によい依存の対象であるか未知であるかぎり,期待が失望に変わる危険への感覚があって当然です。その意識がWさんには人より大きいのでしょう。恃むにあたいしないと分かったときの失望は,Wさんをして自らの意志で治療者を見切らせるように促すのではなく,自分が見放されたと感じさせる人なのです。未発達な自我は再びまずい判断をしたことになります。
性格形成に与える母親の影響-その6
■怒り
怒りは明確に生物学的な根拠を持っています。本能をつかさどる中枢は大脳辺縁系にあり,怒りの中枢もここにあります。動物実験で特定の箇所に電気刺激を与えると,動物はたちまち激しい怒りを表します。そして電流を切ると即座に怒りは鎮まります。いうならば機械仕掛けで怒りは発動します。
動物は,本能的に安心(安全)と満足とを求めようとします。安心を求めて巣を作る場所を選び,あるいはテリトリーを守ろうとします。満足を求めて獲物を捕らえ,異性を得ようとします。安心を脅かし,満足の追求を妨害する相手には,怒りを向けます。ただし動物の場合,同じ種族の中での闘争では,力の優劣がはっきりした時点で,弱いほうは恐れを持ち,尻尾を巻いて引き下がるのです。そうすると強いほうはそれ以上相手を攻撃し,息の根を止めるようなことはしないようです。大脳辺縁系の怒りの座のすぐそばに恐怖の座があります。怒りと恐怖とは,現象的にも相互に素早く入れ替わる類縁関係にありますが,それらはそれぞれ生物学的に個別の根拠を持ちながら近縁関係にあるのは興味深いことです。種の保存が本能的にはかられている動物の世界では,怒りと恐怖とがいわばセットになって,役割を果たしているのが分かります。
種の保存の生物学的な原則を越えて相手に攻撃を加えるのは,動物の中では人間ばかりのようです。怒りは極めて原始的な情緒ですが,人間の怒りは単に本能的,生物学的な現象とはいえません。原始的であることに特有の強力なエネルギーを保持しつつ,人間にあっては,怒りは高度な精神性に寄与する側面と,最も凶悪な忌むべき行為に関与する側面とを持っています。怒りによる攻撃行動は動物一般に認められることですが,相手を殺すこと自体が目標になる凶悪な行為は,人間に固有のものといえます。
動物の世界で見られる怒りは,生きていくために必要な,あるいは種の保存のために必要な適応的なものといえます。人間においても,この意味の適応的な怒りはあります。
動物にとっては,怒りは単純に怒りであり,自然そのものといえます。動物では怒りは他の動物に向かい,自分自身には向かいません。ここでは怒りが持つ意味は関係の破壊ではありません。そもそも動物では関係というものが,人間のようにはっきりしたものではありません。人間になついている動物は人間との関係ができているといえなくもないのでしょうが,そこにあるのは,動物の立場では,人間によって安全と満足とが満たされているということです。それは不快が退けられ,快が確保される動物的な適応的な行動の域を出ないでしょう。動物の行動に’人間的な’情趣を感じ取るのは,大部分が人間の思い入れというものではないでしょうか。
一方,人間の怒りには喜びの反意という性格があります。動物との違いは,人間では他者との,あるいは自己自身との関係の上に怒りが生じるという点です。それはおなじことを角度を変えて見れば,自我を持たないものと持っているものとの違いといえます。人間にあっては動物と違って,怒りには不快への反応にとどまらず,喜びの対極にある感情でもあります。つまり喜びがそうであるように,怒りもまた,精神的な現象です。そしてそれらの精神性の根拠は自我にあり,自我に拠って自己と他者との関係,および自己と自己自身との関係が,人間においては特徴的,かつ重要な意味を持つものとして生じています。
このように怒りの本質的な意味は,人間の場合,関係の破壊です。怒りは他者との関係,あるいは,それとの関連で自己自身との関係で生じます。適応的な怒りでは,怒りによって旧来の悪しき関係を破壊し,新たな関係を再構築する意味を持ちます。
動物の場合は怒りが他へ向かうことがあっても,自分自身へ向かうことがありません。そこが自我に拠らない動物と人間とでは,関係概念が根本的に異な
る所以です。
反抗期にある子が親に怒りを向けるのは,ひとまず適応的です。これまでの親子関係が,子にとっては支配され,抑圧される関係だと子が感じはじめたあるとき,一定のエネルギーの高まりがあって反抗が面に表われるのです。
長年にわたって培われてきた親子の関係は,それなりに強固ですが,親子の関係は,暗黙の合意,暗黙の契約によると考えることができます。そして親と子は,しばしば共犯関係にある,あらざるを得ないともいえます。それは暗黙の合意とはいえ,親の主導によるものなので,子供の立場では多かれ少なかれ不満があっても従わざるを得ない事情に関連します。親は権力的になりやすく,子供は親の権力を恐れるということを前提とした合意ですが,その上に成り立つ親子関係によって,そのかぎりで親子の安心と満足が保証されるのです。しかし親の権力,親の主導ということから明らかなように,親にとっての満足,安心が優位に傾くのは避け難いところです。そういうことを前提に,何に対する犯意かといえば,子供の心の自然的なものに関してであるといえます。これは,しかしながら,なかなか難しい問題です。子供の自然な心といっても,親の関わりがない放任された環境というものは,むしろ不自然なものであるからです。親の保護の下にある子の心の自然というものは,親の介入を人工的と捉えれば,どうしても人工的な心的環境の下でのものになります。たとえば我がままの度が過ぎる場合,あるいは逆に行儀の良い子の場合など,子供の心の自然が何であり,どこまで許容されるべきかというのは,そう簡単なことではありません。しかしながら自然の知恵というのは無視し難く,子供の心の自然の中に,自ずから自己規制を促す能力があるのではないでしょうか。大人の介入が,この自然の自己規制力を混乱させるときに問題が生じ,また,多かれ少なかれ問題が生じざるを得ないのが,人間的な現実であると考えるべきであるように思われます。ここで問われるのは,またしても親の愛情の深さと質とであろうと思います。
親の子に対する愛情は,二つの方向性を持っています。つまり親が子によって自分自身の安心と満足とを得ようとする心と,子供自身がみずから安心と満足とを得ていくのを喜ぶ心とです。前者の比重が高ければ子供の自由はさまざまに阻害され,後者のそれが高ければ子供の自立心と自由とは望ましいものになるでしょう。子供の自由を最大限に尊重する親を一方の極とし,その精神が劣悪な親を他方の極として,親子の共犯関係はそれらの両極のあいだのどこかに位置することになるといえます。その程度に応じて親子の関係は強制的合意,あるいは合意の不在となり,最も望ましくは信頼に裏打ちされた自由の契約ということになるでしょう。
次に上げる女性の夢は,母と子の共犯関係を示しているように思われます。
この女性は母親と性格が似ているそうで,両者の関係はよいという認識を持っています。
第一の夢は,「6歳ぐらいの女の子が施設にいる。母親の面会があり,女の子が喜んでいる。しかし母親は,まだしばらくは引き取れないという」といった内容です。そして,この子は私ではないと思いますとつけ加えました。
この女性は仕事の上では人に当てにされ,自信も持っています。しかし家庭では,しばしば幼い子(男子,2歳)に当たってしまいます。受診を思い立った直接の理由はその問題でしたが,夫の浮気に悩まされてもいるのです。夫は子供の世話はよくやき,子供は父親になついているそうです。彼女は経済的には自立できる自信を持っています。しかし一人で子供を育てていける自信がありません。何日間も家に帰って来ない夫に対して,別居,離婚に踏み切ることも辞さないという強い姿勢を取れないかぎり,彼女の将来は暗澹たるものと思われるのですが,元々争いを嫌う性格のせいもあって,彼女は我慢するしかないと思っているのです。そのような気弱さのために,公然と浮気をし,それがなぜ妻にはストレスなのか分からないという不可思議な感性の持ち主である夫の行動は,黙認されたままでいます。
夢に登場した女の子を,「私ではないと思います」と,質問を受ける前から自分でいっていますが,逆にそのことは,半ば自分と関係があるといっているようなもののように思われます。夢に出てきた施設については,女性の弟が肢体不自由者であるという現実があり,それと関係がありそうです。そして主観面では,女性と母親とのあいだの共犯関係の犠牲となった心内の幼い分身が,いわば心の内部の施設に預けられているというイメージが提示されているように,私には思われます。
第二の夢は,「地震が起こり家が倒壊する。両親と弟が押しつぶされ,私が泣き叫んでいる」というものです。
女性の連想が得られず,夢も断片しか記憶されていないので確かなことはいえません。しかし女性が置かれている状況と,第一の夢とを照らし合わせて,次のように読み取ることが出来るのではないかと思います。
第一の夢に現れた,心内の女の子を救い出すには,女の子の持つ怒り,悲しみ,絶望を,女性が認め,受け止めることができなければなりません。それは共犯関係にある母親への怒りの存在を,彼女が認め,受け入れることとおなじ意味を持ちます。心内の女の子は,肢体不自由者である弟のためもあって,幼い時代の女性が,母親に我がままをいい,自由に甘える心を抑圧し,’健気な大人’であったことに伴う犠牲者として(心内に)幽閉されている,というふうに考えられます。彼女の無意識的な怒りは,家という自我を倒壊させる力を持っています。彼女の心内に幽閉されている幼い子が望んでいるように,彼女自身が母親に甘えたい心を隠し持ち,我慢しているのです。だから現実の我が子を一人で育てるだけの母性がなく,頼りない夫への依存を断ち切る勇気が湧きません。夫は彼女にとっては,母親の代理という意味を持ちます。彼女は母親に依存する心を強く持ちながら,意識上では否定しています。そういう歪んだ意識と無意識との関係が,現実生活の上で夫との不可解な依存関係を生じさせています。
女性は怒りを面に表さない性格ですが,心内には大きな怒りが内向していると思われます。夫によって悩まされることに耐えつづけているのですが,ここにも怒りが内向する大きな理由があります。その怒りが夢の舞台で家を倒壊させたようです。彼女の現在の自我は母親への依存が強いので(意識上では独立しているつもりですが),母親が倒れれば,自我もまた崩壊すると感じているのでしょう。
この解釈がまったくの当て推量で,治療者である私の一人合点に終わるのであれば,私がこうした解釈をもてあそぶことは許されないでしょう。しかし治療関係の上の直感としては,かなりの確度で実態を捉えているように思われるのです。それは今後の治療過程で実証されるものであれば,この解釈は意味を持つことになります。
いま私がここで試みたのは,母と子の共犯関係と,その裏で犠牲となる分身のことと,それを救い出すのが治療上の要点になることと,そのためには怒りが重要な意味を持っていることとを例示することです。
ある父親が次のように語っています。
「息子に,幾つかの学習塾を探してやったが,息子は態度を決めかねている。ふと気がついて,もう息子に任せよう,余計な先回りはやめようと思った。そうするとずいぶん気が楽になった。思えば,これまでいろいろと無意識的に先回りして手を貸してきた。年齢から仕方がない面もあったと思うが,息子のためにも私のためにも良いことだったとは思えない・・・」と。
この父親自身がその母親から浸入的,束縛的な養育を受け,自己の姿勢を正すために多大の時間と苦労とを重ねてきたのです。
親が子を躾けるときに重要な役割を果たすのは怒りです。
心には表舞台と裏舞台とがあります。表舞台とは自我に拠る世界です。裏舞台とはいわゆる無意識の世界ということになりますが,無意識には自我がそこから生まれ出てきた,自我の拠り所となる領域と,自我の価値規範外のものとして抑圧,排除された領域とがあります。そしていずれにせよ,自我の基本姿勢は,それら一切を引き受けるということです。無意識の世界は自我の能力から見れば無限大のものであり,であればこそ自我が拠り所とするに値するのですが,それをも引き受けるのが自我の使命という大いなる矛盾があります。自我に拠る人間は,どうしたって矛盾を生きる宿命の下にあるのです。
自我に拠る心の表舞台は生を志向します。そして心の裏舞台は死を志向します。人の心には日常的に生と死とが入り乱れて表われます。一途に,永遠に生を生きることができない人間は,睡眠という形で死を日ごと経験します。目覚めと睡眠とは,生は単なる生ではなく,死をも含むことの一端であると考えられます。そして健やかな心は,睡眠によって一日の生を閉ざし,翌日,健やかな目覚めとともに再生するのです。
怒りは裏舞台に所属するものです。怒りの指し示すベクトルの最奥にあるのは死であろうと思われます。
動物が怒りを表すのは,生に適応するためでしょうが,怒りを露わに攻撃すれば自分が殺されるかもしれないのです。しかし闘うしかないのです。怒りを表すときに,動物は死を計るようです。勝ち目がないと分かると,怒りに代わって恐れを表し,降伏する自然の知恵を持っています。
親が子を叱るときはどうでしょう。叱るというのは,分別のある態度です。親の権威を背景にして教え諭すのが叱るということです。しかし叱るということと怒るということとは,見分けがつけにくいものです。叱ることは,抑制された怒りであるといえるように思われます。その証拠に,叱っているつもりでも,子供が思い通りにならなければ,いつの間にか怒りそのものに代わってしまうことも,むしろ一般といえるだろうからです。
人間にとって怒りが動物と根本的に違うのは,怒りを自我が加工するということです。子供が怒りのはけ口になっているように見えても,躾けのためだといえなくもありませんし,正義のために命がけで闘うこともありますし,理不尽な相手を黙らせることもできる等々です。
人間をも含めた動物の生を促す動力は,満足と安心との追求ではないかと思われます。本能的な心の要求に自我の加工が入る人間においては,動物よりは複雑ですが,煎じ詰めるとおなじところに落ち着くように思われます。
親が子を躾ける場合にも,親が満足と安心とを追求する基本姿勢に従っているといえます。どんなに愛他的精神に富んだ親でも,子を躾けるときに親自身の満足も追求されないわけにはいきません。親が子について描く期待イメージが,子の心の自然の要求に即したものであれば,素直に子によって受け入れられ,親も子も満足できるでしょうが,子供が反発して親が描くイメージが脅かされると,何らかの怒りが生じるでしょう。そのときに親がその怒りをどのように表現するかは一定の傾向があるものなので,親子関係に強い影響を与えるに違いありません。親たるもの,そのようなときには自分自身の心にある怒りを見つめ,それが与える自他への影響を計らなければなりませんが,実際には簡単なことではありません。気の強い親,気まぐれな親,頑固な親,気弱な親など,さまざまに異なった表現になるのはいうまでもないことですが,怒りの持つ破壊力に親の自我が翻弄されなければ幸いです。子にとって一番ありがたい親の姿勢は,いろいろあっても引き受ける精神が根底にあることではないでしょうか。それがあれば要するに正直な心でいられますし,何よりもそれ自体が親自身にとって満足と安心との源泉になるので,子の助けに依存する度合いも最小にできるからです。
親の価値観の事実上の強制を,子は多かれ少なかれ不満を抑圧して受け入れ,両者の無意識的な暗黙の契約が成立します。それに伴って子供は親によって安心と満足とを与えられることになるのですが,そこには,親に従わなければ安全を保証しないという隠れた威嚇に,子供が多かれ少なかれ屈せざるを得なかったという事情が潜んでいるのです。これらのことには親と子の双方ともに,一般的には無意識だと思います。ここには親と子の共犯関係という意味があります。この関係によって子供の自我が,子供本来の満足への要求,自分の心の自然的なもの(甘える心,羽目を外した遊び,いたずらなど,子供にとってはそれらの満足を満たすことは,その後の成長に大きな意味を持ちます)の要求を抑圧(いわば心の牢屋に拘束する)し,犠牲に供することになります。共犯と呼んだ意味は,これら抑圧され,犠牲となったものを生み出すということです。それらは心の表舞台の価値規範に合わないものとして裏舞台に回されたというふうにも考えられます。それらのものたちは,しだいに影の分身といえるほどの勢力を持つことになります。それは自我が偽りの自己を作り出すことに直接的に関連しますが,これらのことは人間には避け得ないものでもあります。
また生きることの拠点である自我によって受け入れを拒否され,裏舞台に回されたものたちは,生きることの反面である死を志向する性格を持つといえます。自我がこれらの影の分身たちを改めて自己に再統合することができれば,それは自己の成長ということになります。人生の重要な意味の一つは,そのように影の分身たちを再統合しつつ自己の発展を模索することであるということができると思います。
逆に裏舞台のものたちに対して無関心,無気力でいれば,影の分身たちは勢力を強める一方で,相対的に生きるエネルギーは衰微せざるを得ないでしょう。そういう状況では,裏舞台の極北の首座にあるといえる死の影がもたらす極風が,人の心を戦慄させるでしょう。心の諸々の病気は,この戦慄させる極風に吹きさらされることによってもたらされるといえるように思われますが,しばしば心の病気の諸症状は,その戦慄させる北風から身を守る手段ともいえるように思います。
人は何らかの満足と安全とを求めないではいられない存在です。心の表舞台で思うようなそれらが得られないときに,裏舞台のものたちが,いわば凍え死なないように病気というせめてもの隠れ家に身を潜めるという側面があるようです。いうまでもなくそのせめてもの満足は,症状といわれる苦痛に身を切られる思いと引き換えに得られるものです。
一例を上げれば,拒食症は,身体が痩せ細っていくことにのみ満足感が得られるのです。衰弱して死が切迫していると分かっていても,その満足の追求をやめることができません。
心の表舞台と裏舞台とは一定量のエネルギーを分かち持っていると思われます。表舞台が活力を持っていれば相対的に裏舞台が沈静化され,要するに元気でいられます。表舞台を活性化するエネルギーは,満足感によってもたらされ,その根本的な由来は内在する主体にあるものと想像されます。また裏舞台に注がれるエネルギーは怒りによってもたらされ,その根本的な由来は死界(内在する裏の主体)にあると想像されます。
これら表と裏の主体は,結局は一体のものであり,前者を全と呼べば,後者は無と呼ばれるべきもののように思われます。すべてを分割してでなければ認識的に把握できない自我にとっては,生と死とも正対するものとして表れるしかありませんが,いずれもが自我を超越した存在です。それらについて自我に拠る認識を敢えてほどこせば,以上のような意味を見て取ることが可能だというふうに考えるのです。
このように考えることを単なる暇つぶしに終わらせないために必要なのは,ここでは心の領域での臨床上の問題に寄与できるかどうか,臨床上のできごとに符号するかどうかということです。
心身症を病むものの多くが,もともと良い子といわれてきた人たちです。人生の最早期の幼いころに,心根を震撼させる何らかの怯え(死の極風に関連するでしょう)があると,親に捨てられないように(捨てられると生きていけないという心理が働くと思われます),親に満足されるように専心します。それは一方では,子供自身が自らの意志で,本来望んでいた,情緒的に満足したいとする心を断念することになります。それによってそれらの心は,心の暗部に幽閉されることになるのです。言葉を換えれば,自然的には受け入れられて然るべきものが,自我によって不当な拒絶を受けたことを意味します。
以上のことを敷衍すると,子の心根にある怯えが親の介入に対して自我を無気力にさせ,引き受ける精神を放擲させるのです。その結果自我によって裏切られたのも同然の自然の心たちは,心の裏舞台に回されることになります。人生の最早期にそのような心の動きがあれば,その後の心の成長過程において,親の価値観に同調しつづける自我になります。そしていうならば同じ過ちを繰り返すことになり,雪だるま式に増大する影の分身を抱え込むことになります。それらの勢力が増大するにつれ,分身たちの怒りのエネルギーもまた増大していきます。
それら分身たちの怒りの圧力に突き動かされて,子供の自我はそれに同調しないでは済まなくなるか,あくまでも畏怖する自我がそれらの分身たちの圧力を強力に抑圧しつづける(この場合は分身たちの怒りがほとんど意識されません)かということになります。後者は大きな問題を残したまま成長しますが,前者は,これまでの親子関係に異議を申し立てなければ済まなくなります。その心の動きは,旧来の親子の共犯関係を破棄し,分身たちの要求を受け入れた形で改めて契約を結び直そうとするものです。
これらのことを実行に移すには,それ相応のエネルギーの高まりを必要とし,覚悟が要ります。反抗期の反抗は,人間として成長し,力をつけてきた証拠でもあります。そのように,反抗期での怒りは,親との関係で子供自身もその関係維持に加担し,恩恵を蒙ってきた旧来の関係が,一方では自分自身との関係での軋轢が耐え難いほどに大きくなったことに伴うものです。
しかしながら関係の破壊には,それなりの危険は避けられません。それはある意味では忘恩なのです。共犯関係とはいえ,そういう形で親の恩を受けてきたのは事実ですから,世話になってきた親に弓を引く罪悪感も伴います。そして必ずしもその後の保証はありません。関係を破壊しようとすることの重要な意味を,親が理解すれば子の勇気は価値のあるものになります。困難な人生に適応するために,勇気と信頼と愛情とが踏み絵にかけられることになります。
20代の女性,Lさんの例です。
Lさんはしばらく休んでいた仕事に出ることにしました。Lさんは,「心の中にもう一人の子供の私がいる感じがしている」といいます。これは先に述べた’分身’が,自我に脅威を与えるほどに成長し,乖離した存在として意識にのぼり,自己の一体感,統一感が危機に瀕していることを示しています。
この幼い分身が表に出ると,頭がボーっとして思考力がなくなるそうです。しかし,「会社に出れば大人の私がしっかりするので,仕事はこなせる」のです。それが今回はいつもと違い,しばらくぶりに職場に復帰したところ,分身に邪魔をされて,思ったようには仕事をこなせなかったのです。帰宅して,情けなくて号泣しました。そして幼い分身を殺す気持ちで,胸に刃物を向けました。その夜,幼い分身に仕返しをされました。実際には,自分で自分の首を絞めました。その後二日間にわたり手首に傷を負わせました。
このことがあった前日,母親と雑談していた折に,自分の病気のこと,幼い分身のことを母に聞いてもらいました。母親は,「そんな話は私には分からない」といいました。また,「病院に一緒に行って・・・」と頼みましたが断られました。Lさんは,「母親が理解しないだろうということは,期待する部分もあったけれど私には見当がついていた。しかし幼い子供はそのことで傷つき,怒ったみたいだ」といいます。
この話は,要約すると以下のようになります。
母親に認めてほしいと願いつづけているLさんは,母親の願いどおりの子でいようと努めるのが習いでした。それで母親との表面の関係は平和に保たれてきました。しかしLさんの本当の願いは,(二人の関係の犠牲者として)存在が明らかになっている’幼い分身’をも含めた,全身的なLさんの存在の容認です。そのためにLさんは,母親に’幼い分身’について説明し,一緒に病院へ行ってもらいたいと頼みました。それが聞き入れられれば,乖離している分身との和合が可能となり,乖離の解消と自己の統合とが図られると考えたのです。ところが母親はその願いを拒否しました。母親との関係を手放せないLさんは,逆に分身の怒りを活性化させてしまったことになります。自我は混乱に陥り,仕事に支障をきたしてしまいました。従来は,「仕事に出れば大人の自分でいられる」と思い,それが一つの支えになっていたので,このことは二重に心に打撃を与えました。そしてLさんは母親にではなく分身に怒りを向けました。分身が消えれば乖離は消滅するのです。しかしそれはお門違いというものでした。分身を作り出したのは他でもなく,Lさん自身なのです。分身の仕返しにあったとLさんはいいますが,それは起こるべくして起こったといえる出来事です。分身はLさんと一体のものなので,Lさんが引き受ける以外にないものです。分身の立場からすると,Lさんの自我が分身の存在を容認し,自我に統合する意志を持つか,あるいはその可能性があくまでも閉ざされ,もろともに滅びる道を選ぶか,ということになるのです。いうならば母親を取るか,分身を取るかは,死ぬか生きるかということに等しいのです。
このように,生死を賭けてでも手放したくない母親との共犯関係を支えるものは,Lさんの心根にあるだろう,根源的といえるほどの恐怖以外には考え難いことです。
Rさんは男子大学生です。
初診の半年ほど前から,これといった外的な理由がなく,無気力感に囚われるようになり,母親に促されて受診しました。
Rさんの成育史で重要なのは,母親が入院を含む精神科受診歴を持っていることです。
母親はそのことを,自分の病気が子供たちに迷惑をかけたと大変気にかけています。母親自身は最近は一日の中の一定の時間,睡魔に襲われる(そのことを,眠りに逃げ込むように,と表現します)ものの,それ以外は健常状態と変わらず,残遺症候はありません。
Rさんは,小学校以前の記憶はあまりありません。小学校のころが一番楽しかったといいます。家では母親が怖いのでおとなしくしていたといいますが,外では先頭に立って,(幼い子としては)過激ないたずらをしていたということです。
5年生になってから,母親に命じられて塾通いがはじまります。勉強がいやで仕方がなかったそうです。しかし母親には絶対服従でした。目標の学校は中高一貫の有名校で,母親のいうなりに決まりました。受験勉強をはじめてから,2年間にわたり,身体への暴力を含むいじめにあいました。
受験は成功しました。しかし,自分から進んで入った学校ではなく,強制されるばかりだったという思いがありました。合格してしまうと,「もう勉強はしなくていいんだ」と思いました。勉強を怠けているので,成績は下がる一方でした。中学2年のとき,進級が難しいことになりました。そのころ両親の喧嘩が絶えなかったといいます。母親が独断で,学校に行き,退学を決めてきました。Rさんは勉強はいやだと思っていましたが,自分で勝ち取った学校という思いはあり,また学校が嫌いなわけではないという気持ちもありました。この学校に入ったのは母親主導でしたが,やめるときも同様でした。Rさんは逆らえませんでした。
公立中学に転じたあとも’やる気’は起きず,欠席が多かったということです。それでも友人には恵まれました。高校は管理的に行き過ぎていたそうで,1年で中退したRさんは,現在にいたるまで引きこもりがちの生活ですが,遊びに誘い出してくれるのは,そのころの友人たちです。
大学への進学希望は特にはありませんでしたが,通院後,大検を受け某大学に入学しました。Rさんには興味がある学問分野があり,そこを選んだものの,入学が決まったときに何の感動も覚えませんでした。疲労感が絶えずあり,講義への幻滅感もあり,いつか通学の意欲を失くしてしまいました。いまは休学中です。
通院後は,いわば一進一退です。気分がよいときと,乱気流に巻き込まれたように不安定になるときとが交互にやってきます。死を待望する気分にしばしば陥ります。生きようとする心と,死にたいという心と,二つの心が綱を引き合うように交互に表われるのです。
通院をはじめて1年半ほど経ったある日,いつになく険しい表情で受診しました。
母親に,「生んでほしくなかった」とはじめて口に出したといいます。そのあと自殺も考えました。「いままでいわなかったが,物心ついたころから,死にたい,生きていたくないと思ってきた。元気にしているときも,その気持ちを隠していただけだった。口にしなかったのは,そうすることで家庭が壊れるのを心配したからだった」といいます。
深刻な事態であり,深刻な告白です。しかし,新たに困難な局面にさしかかったというよりは,元からあった心の問題が告白されたのです。そのような苦しい胸のうちを明かしてくれたのは,むしろ注目され,評価されてよい局面です。いわば生きようとする心が勝ってきたからこそ,口にすることが出来たといえます。
評価してよいもう一つは,これまで抑圧してきた怒りを,母親に向けて表現したことです。そしてその怒りが,母親のみならずRさん自身にも向けられたものであることを,Rさんはすぐに気がつきました。
従来,母親とのあいだには,母親の意向には逆らわないという暗黙の合意がありました。母親の病気に伴う不安定,怒りっぽさ,入院による不在等々は,幼い幼いRさんには脅威だっただろうと容易に想像されます。幼いRさんは,母親の気持ちに迎合することで母親の怒りを鎮め,母親が(多くは心理的に)遠くへ去ってしまわないように心を砕いただろうことも,容易に想像されます。このように,母親の意向には決して逆らわないという暗黙の合意は,母親を恐れる心を背景にしたものであるのは明らかです。その暗黙の契約は,幼いRさんが自分の内部にある自然の心の要求を無視し,黙らせることなしには済まないものなので,共犯関係といえる性格のものです。
Rさんが母親に向けた怒りは,その関係の不条理性を問い質すものです。怒りを込めた異議申し立ては,両者の関係の犠牲となっている分身たちに端を発するものですが,それをRさんが受け入れたことになります。
一般に怒りは自我に所属するものではありませんが,自我がそれを受け止め,みずからの責任において怒りを利用するときに,怒りは適応的な意味を持ちます。
Rさんの異議申し立ては,「生んで欲しくなかった,無(死)を望む」ということです。「生んで欲しくなかった」というのは母親に向けられたものであり,「無を望む」というのはRさん自身に向けられたものです。
怒りは関係の破壊を志向します。母親との旧来の関係を破壊しようとするRさんの怒りが適応的なものになるかどうかは,一つには母親の姿勢にかかっています。つまり母親が冷静に受け止めることができるかどうかですが,「子供に迷惑をかけて申し訳ない」気持ちで一杯の母親は,悩みながらも受け止めることの意義をよく理解しています。またRさん自身も,自分の中にあるはずの怒りの正当性を認めたからこそ,無意識層深くに潜んでいた怒りを意識の上に浮上することを許したといえるのでしょう。ある程度はそれを口に出しても,母親の病気は悪化しない,親子の関係が破壊されることはないという計算も働いただろうと思われます。いわばそれなりの心理的な準備が整って,かつては考えられなかった自己主張をしたのです。
評価できるもう一つは,治療者に,「いままでいわなかったがずっと死にたいと思っていた・・・」という’告白’です。これは重い荷物を治療者に預けても大丈夫だろうという心理があってのことです。ある意味では治療者へのプレゼントです。また,その告白の意図の重要な要素は,「死にたい気持ちがあるのは事実だが,それを共有してほしい,何とかなるものなら方法を教えて欲しい」という気持ちが無意識的に働いているだろうと思います。ですからこのことは,治療的な展開といえるのです。
これまでにRさんは,「自分が最も望むのは無です,消えることです。一人になることは何とも思わない。友達は要らない・・・」と繰り返しいっていました。その都度そのことについて話し合われてきました。この’告白’は,そのやり取りの延長線上にあるといえます。
その後何度か母親に向かって,「生んで欲しくなかった・・・」という怒りの表明をしています。そして,母親への怒りの表明が繰り返されることに伴って,乱気流に巻き込まれたかのような気分の乱調は,目に見えて収まってきています。
Rさんが怒りの存在に気がついたのは通院後のことです。それまでは怒りは自我によって強く抑圧され,無意識下に潜行していたのです。それは母親を恐れる自我が,母親の自我に同調したことによるものでしょう。抑圧が強かった分,恐れも強かったと考えるのが合理的だと思います。
(30代のある主婦は,「結婚するまで母親のいうことに疑問を持ったことがなく,ましてや怒りを覚えたことがなかった」のです。ところが結婚してから,夫の家庭や育ち方などが,自分とあまりに違うのでびっくりしました。夫は寒い日に外出しようとすると,「温かくして行けよ」といいます。ところが母親は,「みっともないから一枚脱いで行きなさい」といいます。一事が万事この調子でしたが,「世の中こんなもの」と思っていました。母親は世間体が常に気になる人だといいます。しだいに怒りが収まらなくなりました。いままで溜まっていた怒りが,堰を切ったように意識に上ってくるようになったのです。あるときから電話の連絡も断っています。母親を「心の貧しい人」といってはばかりません。些細なことで苛立ちを覚えると収まりがつかなくなり,しばしば落ち込みもします。そういうことで受診にいたりました。この方の場合は怒りの存在を,幼いときから自分でも気がつかないように抑圧し,その存在を消していたのでしょう。それはいうならば親子の共犯関係に基づくものです。いまは心の中を飛び交うようにして表われる怒りの処理に窮していますが,怒りの存在を過度に抑圧する自我から,その存在を受け入れた自我に移行したということなので,差し当たりは苦しくても彼女の自己の回復過程では重要なことが起こっているのです)
Rさんがうつ状態に陥ったのは,高校を中退してコンピューター関連の仕事を目指していたころです。ある時期からそのことへの意欲を失ったのがきっかけでした。そのことに特別な外的事情があったわけではなく,いわば内的に閉塞状況に陥ったようです。そのころから,いわゆる引きこもりの生活になりました。心のベクトルが生よりも死の方に傾いたといえる状況です。見方を変えれば,心の舞台の重心が表から裏に移行したともいえるでしょう。
通院後,まる2年ほど経ったころに,次の内容の夢の報告がありました。
パラシュートで降下する。綱が切れる。死の恐怖と安堵。しかし山の頂上に落ちてたすかる。「たすかった」と思った。苦労して自力で山を下りる。
Rさんの内的世界では,生きようとする心と滅びようとする心の綱引きが長期にわたってつづいています。夢の内容もそういうことを表しています。パラシュートでの降下は,この夢では生と死を賭けたものです。もし綱が切れなければ死はありません。危険ではあっても,ただのスポーツです。しかしここでは綱が切れてしまいました。そして生きようとする意志がはたらいて,山の頂上に落ちることになります。仮に夢の中で激突死していれば,近い将来に実際に死の危険が迫っていると考えなければならなかったかもしれません。
この夢によって,Rさんの生きようとする心が死を望む心に勝ったことが窺えるのですが,現実にはすぐにはその意志が強化されていく様子が見えません。あるとき自殺を考えて外出し,しかし恐怖心から果たせなかったということも起こっております。それは夢の内容に符号するものです。母親(父親にも)への怒りの爆発はその後も見られました。そしてそれが母と子の旧来の関係を破壊する上で必要であり,有意味でもあったのです。その証拠に,しだいしだいに気分の安定が図られております。
Rさんから,「自分の仕合せを問い詰めていくと,どうしても無を望むことになる。それがなぜ問題なのか,その自由はあると思うが・・・」という問いかけがしばしば見られていました。そして気分の安定化に伴ってそうした問いかけが見られなくなっています。
Rさんの問いかけに,私は,自我に拠るのが人間である所以だから,というふうにこたえております。
自由と死のテーマは,他の方からも提出されています。その方は自死について言及することが多いのですが,次のような夢を見ました。
だれかがステージに立って,「自由を勝ち取ろう!」と演説している。そのとき私自身が空から落ちて行く。
この男性の問いは,自死と自由とは同等だろうかという問いでした。
自由は心の表舞台のものです。死は裏舞台の最奥にあるものです。前者は自我の世界のものであり,後者は自我の範疇の外にあるものです。もし自死が自由に選べる性格のものであれば,それは自我の世界に所属することになるのですが,そうではありません。自死は自我の力の行使ではなく,自由な選択の不能として起こることではないでしょうか。
ここで検討に値するのは,ソクラテスの死です。
ソクラテスは,「悪事をなす者で,若者を堕落させ,国家の神を信じず,自らの何か新しい心霊を奉じている」というかどで告発されたといわれています。彼は刑罰を免れるための一切の弁明をせず,亡命のすすめも拒否して,毒杯をあおって刑死しました。
ソクラテスが裁判にかけられ,死刑の宣告までされるにいたったのは,(「ソクラテスの弁明」におけるソクラテス自身の説明によれば)次のごとくです。
それはソクラテスが自分自身に課した’奇妙な使命’から生じました。あるとき,カフェレオンという彼を信奉する親友の一人がデルフォイへおもむき,ソクラテスより知恵のある人がいるかどうかと,神託を訊ねました。その答えは,ソクラテスより知恵のある人はいないというものでした。
ソクラテスは,それは何を意味するのか知りたいという使命感に駆られたのです。というのは彼自身は,善美のことや徳(それらは魂を世話することを何よりも重視するソクラテスにとって,最深奥にある課題でした)について,自分はむしろ何も知らないと考えていたからです。そうすると神託は,何も知らないことを知っていることが知恵のある者であるといっているのだろうかと考え,それを確かめたいと思ったのです。この答えを知るために,自分より知恵のありそうな者を探し出す必要を感じました。これはと思う者に会って,彼らの知恵に耳を傾け,それを論駁できるだろうかと考えました。結局,彼らの誰一人としてソクラテスより知っている者はいないというのが結論でした。何ほどかすぐれたところがあっても,自惚れることでそれを帳消しにしているということが明らかになるばかりでした。彼らはほとんど知らないか,何も知らないのに,すべてを知っていると思い込んでいるのです。ソクラテスは,結果的には,自惚れる者たちに問いを持ちかけ,自己矛盾に陥らせることで,見せかけの知恵を暴き立てる仕事にのめり込むことになりました。こうして恥をかかされた者たちの激しい敵意を呼び込み,知識の教師を自認する者たちから,「詭弁を弄してアテナイ市が認める神々を認めず,別の新しい神を信じるように促し,若者を堕落させる不埒者」呼ばわりされることになったのです。
こうした問題になった背景には,当時のアテナイ市が国家の存亡をかけた政治的状況にあり,アテナイ市民に与えるソクラテスの立場と影響力の大きさ,加えて多くの市民が彼をソフィスト(神を否定するもの,弱小の問題を強弁して世を惑わす者)と混同していた,などの事情があるようです。
ソクラテスは人類の教師と讃えられていますが,ソクラテス自身は神に仕える者という使命感を持っていたようです。彼は合理的な精神を誰よりも尊重し,身につけてもいた人といえるのでしょうが,一方では親しい関係にある者にとっても,神秘的で不可思議な人という側面を持っていました。それは,「子供のときから何か神からの知らせとか,鬼人からの合図とかいったようなものがよく起こった」と彼自身が述べていたと伝えられているように,’心内の声’に聞き入っている姿がしばしば見られたからです。
当時は,神の定めた圧倒的な運命の前に,人間はいかんとも抗し難く,神託,予言,前兆,夢などを通じて自分たちの運命をさぐり,悪しき運命をできるだけ避けようとする時代精神から,一方で,そのような運命的な必然に対して,人間の自由を主張する合理的な精神の方向へと時代が動いていました。特にアテナイ市民は自由を何よりも誇りとしていました。彼ら市民たちが自由と合理性を謳歌しようとした背景には,神々がまだ生きていた時代であったということがあるでしょう。一方では神々の威力を畏怖し,一方ではそれを非合理なものとする合理的な精神が台頭し,しだいに後者が時代をリードしつつあったといえます。
神々への畏怖を背景として,掟や部族の宗教に縛られる古代人に較べると,アテナイ市民たちは大きな自由を謳歌しつつありました。しかし宗教的な戒律に代わって,今度は市民たちは,ポリスへの全的な服従という戒律に従わなければならなかったのです。いずれにせよ自由という高度な精神は,人間はどう扱ってよいものか分からないものになりがちです。ソクラテスが,「身体は一切の災いの素である・・・・・・魂(精神)ができるだけすぐれたものになるように気を使わなければならない・・・・・・そのことよりも先に,もしくは同程度にでも,身体や金銭のことを気にしてはならない」というように,身体性を持つ人間には,純一の魂と同義であるらしい真正の自由というものは,永遠に理念でありつづけるばかりです。ですから戒律がなければ,人間がそれぞれに勝手なことをはじめる混乱は避け難いことです。
神々の名の下であろうとなかろうと,戒律を定めるのは人間です。自由を与えられると勝手なことをはじめる愚かしさが人間のものであるなら,本当にはその権利も資格もないのに,市民に戒律を押しつけて自由を奪う愚か者もまた人間です。自由を真には謳歌できない人間は,どうしても愚か者以上にはなれないというべきでしょうか。
ソクラテスは,自分自身がそのような意味での愚か者であることを誰よりも承知していました。そして真の賢者は神であると認め,自分は神の助手として,自分の愚かしさをかぎりなく煎じ詰めることによって,人間の分としての賢者でありたいと熱望した人です。そして神の助手であるという自負心と使命感とを持って,アテナイ市民たちを少しでも有徳で謙遜であるように仕向けようとしました。彼は自分自身が神の助手としての資格を本当に持っているのかということを確かめるためにも,世の中の権威者と考えられている人間たちと,ある意味での知恵比べをしたのです。
ソクラテスは自分の使命を,「(神が私を)虻のようなものとして,このポリスに付着させたのではないかと思われる・・・」という比喩を使って表現しています。「・・・ポリスという馬は,素性がよくて大きいが,そのために却ってふつうより鈍いところがあって,目を覚ましているのには,何か虻のようなものが必要だ・・・(諸君は)目を覚まされて怒っているのだろうが,そのような(虻である私のような)人間を軽々に殺してしまうと,後は(諸君は)ずっと眠ってしまうことになるのだから,困るのは自分ではなく諸君の方だろう・・・」といいます。
神の助手を自認するソクラテスを理解するには,内心の声に聞き入った特異の体験の持ち主であることを抜きにしてはできないでしょうが,神々がまだ生きていた時代であればこそ,その特異さが彼を神々しく色づけることに益したのでしょう。彼の時代であれば,「神からの知らせに聞き入っていた」といっても,「それは幻聴というものです」としたり顔にいって聞かせる者などはいなかったのは幸いでした。もっとも内心の声に従ったといっても,声が彼を突き動かしたのではなく,何か間違った考えが浮かぶと声がそこに介入してきたという意味のことを,ソクラテス自身の言葉としてプラトンが伝えています。つまり彼は憑かれた者ではなかったということです。
ソクラテスは一方の足を神の世界にかけ,もう一方の足を人間界にかけていたといえなくはないように思われます。ソクラテスの信奉者たちはそういう彼に神々しいものを見たようです(プラトンは「饗宴」の中で,アルギビアデスの名を借りて次のように語らせています。・・・ソクラテスの話は女,男,少年の区別なく,みな驚嘆してそれに魅入られてしまうようなものであり,・・・ソクラテスと接することで,心臓は激しく動悸を打ち,涙が流れ,奴隷のような状態になって恥じ入るという体験をした)。神の世界に片足をかける存在が許容される時代でなければ,ソクラテスのように,あれこれの誇り高い人物のところにおもむき,その思想の迷妄を確かめ,正そうなどというお節介は,決してまともに相手にされることではなく,許されることでもないでしょう。その意味では現代は神々に対する人間の自由は,完全な勝利を得ています。そしてアテナイ市よりは,社会を律する掟もずっと洗練されたものになっているに違いありません。しかしながら真の自由を謳歌できるほどに人間が洗練され,愚か者であることからも自由になりつつあるかといえば,それは設問自体が愚かしいことになるでしょう。
私がソクラテスに見る最大のものは,引き受ける精神の具現者であるということです。何を引き受けるのかといえば,神命ということになります。つまりソクラテス流に考えれば,自我に拠って人間であるようにというのが神命であり,彼はそれを潔く引き受けたことになります。
自我はまさしく引き受けることを使命としています。そしてソクラテスが耳を傾けた内心の声の発信者こそ,先の章で問題にした「内在する主体」であると考えられます。
これは非科学的な考えでしょうか?
思うに人生とは,ソクラテスが内なる声に耳を傾けたように,内在する主体の意向に耳を傾け,それに即してそれぞれの自分の心の姿勢を整えていくことにより,自己自身になろうとする行為過程であろうというものです。ここでいう自分自身とは,ソクラテスに従っていえば,純一なる魂に到ること,換言すると’囲いの外’へ超え出ることによって神の意志そのものと合一すること,という意味合いになると思います。こうした人間的な知性,認識力を超越したものもまた人間存在の構成要件になっている以上は,想像的に人間的に解釈し,人間的な言葉に置き換える努力は,目下の問題に答える上で欠かせません。問題は全体を包括的に見る視野の上に立たなければ,いかなる理解も本来的なものに近づくことはできないでしょう。
具体的に主体者の意向をどう捉えるのかというのは難題ですが,ソクラテスの愛知の精神,常に最上のものを知りたいとする精神はそういうものです。また我々の日常に即していえば,一つには,’心の障害’といえるほどの心の苦境からどのように脱するのかということに手がかりを与えるものがそういうものである,と考えることができます。実際,「内在する主体」というのは,机上の空論を弄んだ結果の産物ではなく,患者の皆さんとの関わりを通じて経験的に浮上してきた産物であるのは確かです。
ではギリシア時代の神はどこへ行ってしまったのでしょう?宇宙的規模で森羅万象をつかさどる神を擬人的に描いたさまざまな神話は,それが生き生きとた感動を人々に与えていた時代にあっては,それに呼応し,活性化される心の内部の状況があったのでしょう。現代では神話はくだらないお話の域を出ません。それに呼応する心がほとんど死んでしまっているのです。言葉を換えれば自我が至上のものとなり,非合理的なものが意識からほとんど排除されてしまった現代では,神が云々されることは困難になりました。しかし神を征服し,至上者の位置についたかのような自我に拠る現代の人間は,ソクラテスの時代に較べて一段と成長し,賢くなったとも思えません。物質文明が栄え,心が砂漠化している現代は,ソクラテスが魂の世話をせよ,金品や身体を魂に従えさせよと警告を発しつづけていたことに学ぼうとしなかったために,精神の貧困化を必然的に招き寄せたといっても過言ではないでしょう。そしておなじ理由によって,神や自然を畏れる時代には豊かにあっただろう謙遜の心が,現代ではあやしいものになっています。人間にとって自我は最上位のものではないという自明のことから,謙遜の精神は人間にとって最も意味のあるものに違いないのです。
ソクラテスがしたように,内心の声に耳を傾けることは現代でも大きな意味があります。それは人間が拠って立つ自我がその上位のものに依拠しているのは論を待たず,その上位者を内在する主体と位置づけるときに,この主体の意向に耳を傾ける必要があるからです。自我を通じて我々がするべきことは主体の意向を模索することです。C.Gユングは,夢は意識の補償作用の意味を持つといっております。自我が主体の意向の軸に即するように活動しているときに,自我の働きはいわば補償される必要がありません。そして心の障害という事態にあっては,自我の活動の方向性と主体の意向の方向性とが甚だしく合い隔たってしまっているといえ,補償作業が必要になるのです。
内在する主体の意向に耳を傾けるのは,ソクラテス流にいえば,「神からの声」に耳を傾けるのとおなじ意味になると考えられます。現代の神は,内在する主体であるということが可能であり,そのように考えることによって臨床的な問題の理解と,治療上の工夫と有効性とが確かめられていると私は考えています。また,そのような意味のある思考の連鎖を,私は科学的であると主張できると考えます。
ところでソクラテスは,死刑の判決を逃れるための画策や,あるいは,まだ幼い年齢の子供たちを含む家族の苦境も考えて欲しいという弟子達の声に耳を貸そうとしませんでした。彼にとっては最も正しいと考えることを,いかなる理由によっても捻じ曲げることは許されないことでした。神の助手としての自分の崇高な使命を翻し,地上の汚濁にまみれている者たちに媚びるなどは,彼には考慮に値しないことでした。神を信じるソクラテスには,この世で善を生きようとする者は,囲いの外である彼の国ではますます善が喜ばしく遂行されるはずのものでした。
引き受ける精神の具現者であるソクラテスにとっては,死は雄雄しく引き受けるべきものでした。
死に関して彼は次のようにも述べています。
人間というものは,囲いの中に入れられ,その囲いを監視するものにいつも見張られている動物のようなものである。その動物が勝手に自分の命を絶つようなことをすれば,監視するものは当然腹を立てるに違いない。一方,哲学者は無知な大衆によって’死んだ者’と馬鹿にされるが,真の哲学者とはいわば死の練習を日夜しているようなものである。死とは一切の災厄の元である身体を去って,魂そのものとなることなので,それこそ真の哲学者の望むところである。(死は)知の探求の究極の姿である・・・。
ソクラテスにとって哲学者とは知の探究者であり,知を探求することは,人間にとって最も重要な徳や善,美を求めようとするかぎり必須のことです。そして知を極めた者が死を正当にまっとうできると考えているようです。ソクラテスにとっては,知の探求は人間が魂を最高,最善なものになるように世話をするための王道です。その道は囲いからの解放と,監視者の監視からの解放への道でもあります。それが達成されたとき,人は既に人間存在ではなく,それを超越した存在です。人はそのような死を理想的な目標と考えることが可能で,哲学者たるもの,日夜そのための練習をしているというわけです。
一方で,人間は身体的存在であるのを免れず,それはどうしても災厄の素になるので監視者が要る,とソクラテスが述べているのも頷けることです。いわば煩悩から解脱しないかぎり人は災厄から逃れるわけにはいかないが,解脱をもとめる心があるかぎり,彼方に理想としての死が微笑んでいるということでしょうか。
ソクラテス流に考えると,魂はこの世を超越した世界のものです。そして身体はこの世のものです。この世を超越した性格のものと,この世的なものそのものの性格のものとが混交しているのが人間存在に他ならない,ということになるようです。
魂はこの世のものであるかぎり身体と連れ添うしかない羽目にあるのですが,それらの関係から不可避的である矛盾,葛藤に耐え,超克していく強い自我があれば,やがては対立的な諸矛盾の最終的な止揚という形態で究極の境地に到ることができる,そのようなものとして死は求められるべきものであるというふうに考えることができるようです。そして自我のそのような仕事に,内在する主体が暗黙の内に指針を与えていると考えることは何かと有益です。
死へと到るこの道は,いうまでもなく容易なものではありません。だから我々は日夜死の練習をしているのだよと,ソクラテスはほくそ笑むようにいっているように見えますが,’哲学者’ならざる我々は死の練習をするほどの余裕はありません。絶えず煩悩にさらされ,傍目からは日常の平坦な道と見える路上で遭難しかけることも珍しくはありません。この世的な煩悩を超克して純一な魂の完成に到る,などという大層なことなどはおぼつかないことであり,荷厄介な身体を捨て去りたいというほどに疲れ果てることも起こります。
我々一般にとって,死は囲いの中から覗き見る非日常的な問題です。それは到底手に負えるものではないものとして,ふつうは寿命がつきる,病に落ちるという形で訪れます。それは囲いの中で迎える死といえるかもしれません。
そしてソクラテスが述べる死は,囲いの外へ出ようとする意志を持った者に訪れる死です。そのような意味での死は,生きることが確かに「死ぬ練習」といえるのでしょう。ソクラテスが人生の道半ばで死を甘受したのは,監獄という囲いの監視者の目よりも,人間存在のあり方そのものの監視者の目の方を躊躇なく尊重したことによります。
死はいずれにしても訪れるとして,彼我を分ける決定的なものは,生きる姿勢ということになるのでしょうか。より良く生きたものは,死を自ら引き受けることができるということなのでしょう。
先にあげたRさんの問いは,身体を捨て去ることによる死と,人生をかけた葛藤を超克して純一な魂になり得たのと,一体どこが違うのかという問題であるように見えます。
死に関する問いは重いものなので,どのように答えても安易の謗りは免れないように思いますが,自我が十分に引き受ける精神をまっとうした意味を持つソクラテス的な死は,この問題を考える基準を与えているように思われます。
魂と身体という二極分化は,人間が自我に拠るものであることに伴う必然です。自我そのものが矛盾し,対立しあうものの交点です。先に,ソクラテスは一方の足を魂のふるさとの世界にかけ,一方の足を身体の存在理由となっているこの世的な世界にかけているといいましたが,自我についても同様なことがいえます。つまり自我の機構は生物学的な根拠を持っていると思われますが,これと名指しするのは不可能でしょう。仮にそれが可能であるとすると,生物学的なという限定によって,自我は明瞭に’この世的なもの’以上のものではなくなります。しかし自我に拠るのが人間であるという前提が正しければ(他のものを前提としたとしても,結局おなじことになります),人間に関する一切の問題を自我は引き受けなければなりません。つまり自我は,’この世的なもの’以上のものも自己の課題とすることを含んでいます。換言すれば自我は,人間が’この世的に’存在する理由であり,かつ’この世的なもの’を超えたものをも引き受ける使命を持っているということになるだろうと思います。ソクラテス流にいえば,自我は神意を受けてこの世のものであるべく存在しているということになるだろうと思います。
自我は光の世界のものです。人間が何を目指して生きるのかといえば,ソクラテスに従えば,純一の魂を目指してということになります。この場合の魂とは,真の自己,自己自身,自己実現といった概念と等しく,実際には到達できない理念としての自己の目標,あるいは超越的自己の存在様態ということができます。ソクラテスは,純一の魂となることは身体から自由になることであり,哲学者がそうありたいと努めてきた理想の実現であるといっております。つまり人間が生きているかぎり手中に収めることは決してできないが,死という到達点に向けて,満足の行く自己形成の歴史を追及するにあたっての目標であるということになると思います。
具体的には,ソクラテスに従えば,身体性を歩一歩克服していく心的なプロセスということになるでしょうか。
しかし克服するべき身体性とは,どういうことでしょうか?
人間の心には,光(正)の世界と影(負)の世界とがあるといえます。その心の負性のものは,心の自然的な発展過程というものを想定したときに,他者によって歪められることになった心たちによって構成されるといえると思います。
例えばAという人物が3歳のときに次のような経験をしたとします。
まだ1歳に満たない弟を,母親がまたとない慈愛に満ちた顔をしてあやしています。Aはそれが羨ましいと思っています。母親が寝ついた弟をベビーベットに寝かせています。Aは母親の膝の上に乗りたくてたまりません。先ほど弟にしていたように,慈愛に満ちた顔で抱いて欲しいと思っています。しかしつい先日も含めこれまでに何度も,母親の膝に乗ろうとしたら厳しい声で叱られたのを思い出します。
Aは母親に甘えるのをあきらめました。ぼくは(わたしは)お兄ちゃん(お姉ちゃん)だから,そんなことをしてはいけないんだと思いつつ。
この例によると,母親に甘えたい心は自然のものです。そして母親との関係で,その自然のものを歪めたということになります。
いうまでもなく,こうしたことは誰の場合でも多かれ少なかれ起こることです。つまり自然の心を歪めないですませることは不可能なのが人間です。
この例のAの場合,甘えられなかった甘えたい心が負性のものです。
Aが純一の魂を目指す使命を持つとして,長じてこの負性のものをどのように扱えばよいのでしょう。また,Aのこの負性と身体性とはどんな関係にあるのでしょう。
このように心を不自然に歪めるときに働くエネルギーは主に怒りです。Aがいわゆる良い子であるとすれば,怒りを抑圧して自分では気がつかないことになるでしょう。可能なら怒りを母親に向けて抗議するとよかったかもしれません。母親がその正当性を認めてくれれば,Aは甘えたい心を抑圧する必要がありません。つまりAの自我は,心の自然を護ることができたことになります。この場合の怒りは,Aの自我によって適応的に作用したといえます。
長じて,Aがこの問題を解くことができるとすると,Aが幼いころのこれらの経験を意識が探り当てたときです。言葉を変えると自我がかつては抑圧したものを,改めて自我の表舞台に引き上げ,再統合を図ることが出来たときです。このあたりの自我の作業を,フロイトは遺跡の発掘作業になぞらえています。
こうした心の作業を困難にさせる理由の一つは,強力な怒りの存在です。怒りは元はといえば,甘えたい欲求が理不尽に満たされなかったことに伴うものですが,それが理不尽であればあるほど,抑圧しなければならなかった母親との関係の問題が大きかったことになるでしょう。それとの相対的な関係で,自我が気弱にならざるを得なかったのです。意識下の闇に葬ったものに長年にわたり悩まされて,長じて改めて意識の光を当てる気になった自我は,既に気弱ではないことを証明したことになります。そしてこのときに,暗々裏に感じていた怒りのエネルギーに恐れをなしていた心に,打ち克ったことを意味するでしょう。その怒りのエネルギーは,抑圧されていた体験群と共にあっただろうと思われます。そして心に屈するものを解決する決意を持った自我が無意識界を探索し始めるとき,自我は怒りと共にある過去の体験群を受け入れる気になっているのです。その心の作業に伴って怒りが意識の上に浮上してきて,自我を脅かします。しばらくのあいだは心は不安定であることを免れないでしょう。しかしやがては怒りのエネルギーは,自我の意味のある仕事によって心の表舞台を支えるエネルギーに姿を変えることになります。裏舞台のものであった怒りのエネルギーは,表舞台のものである生のエネルギーに変換されたのです。
この場合,ソクラテス流に見れば,’災いの素である身体的側面’を,魂の世話をすることで克服したということになりますが,それを具体的に見てみます。
Aが羨望したのは母親の愛情のことです。
母親の愛情は身体の愛撫を通じて表現されます。母親に愛されなかった自分とは,愛されるに値しない身体を持つ自分といっても過言ではないでしょう。怒りも介在して母親を怖れたAは,母親の怒りを招かないために,本来は心の表舞台にあるべきものとして認知しなければならなかったもの(甘えたい心)を,裏舞台に回してしまいました。その自我の汚点は,自分の身体が認めるに値しないという歪んだ認知を招きます(思春期にある者が,身体に病的なこだわりを持つことはしばしばありますが,その由来はこのようなものであると思われます)。
このように人間の悩みは,総じて身体的なものへのこだわりであるといえるようですが,それは身体に発するさまざまな欲望,欲求といったものが満たされていないところに帰着し,人間の宿命としてそれらのものがことごとく満たされることは不可能であるというところに帰着します。
これら本能に由来する身体的な諸欲求のエネルギーが強力であることが,’地を這うもの(鳥は空を飛びますが)’である動物たち一切が,たくましく生存していく上で不可欠といえるでしょう。そして動物達の中で人間だけが,魂を持っています。ソクラテス流にいえば,身体に由来する強力なエネルギーによって確固として’地上のもの(この世のもの)’であるが,一方で神の直系である魂によって,この世的であることからの超越的飛翔(身体から離脱し,自由になる)を目指すものであるといえるように思われます。
Aが後々,先ほどのように意識下に埋没させていた自分の分身を救い出したことは,それ自体が自我が有意義な仕事をしたという満足感につながります。そして甘えたい,身体的に愛撫されたいという潜在欲求が,それなりに解決し,解放されることになります。その分密かにあった母親への依存心からも自由になり,ある意味で母親を許すことになるでしょう。身体に発する欲求に制縛されていた心が,そこから解放されることに応じて,魂はその分の飛翔を果たしたといえます。
この種の満足はいわば白い満足です。言葉を換えれば魂が飛翔する感覚の満足です。それは内在する主体の意向を捉えた心の動きといえ,その分の自我の勝利です。
一方,自我が相変わらず気弱なままであれば,甘えたかった心は依然として怒りと共に心の裏舞台に据えられたままです。そうした折々に,これらの心たちは,例えば過食という問題を起こします。これはいわば黒い満足です。つまり魂の飛翔のない満足です。見方を換えれば,’地を這いずる満足’ということになり,動物的なレベルでの満足です。いずれにしても満足の追求はしないわけにはいかないのが人間です。そして魂性を欠いた黒い満足は,結局は人間としての満足としては虚しいのです。過食など,黒い満足に束の間の愉楽をもとめる者は,それと引き換えに人間としての尊厳,満足という点からは見放されているのです。
人間の人間たる所以である自我の機構的な構造は自然のプロセスの中にあると考えるべきですが,自我の機能はその自律性によって,人間独自の反自然的な世界を切り開く能力を持っているように思われます。その自律性は自然からの乖離,魂の飛翔という特性があるようですが,しかし絶えず自然の支配の中にあると考えられます。自然の大きなプロセスの中にありながら,反自然的な世界を構築するべく宿命づけられているのが,人間の偉大と卑小,あるいは幸福と地獄の理由といえるのかもしれません。人間は自我によって特別な存在者となったといえるもののようであり,一方で自然の全的な大きさの前に,しばしば震撼させられる存在でもあります。その自然の大きさに包囲されているかのような自我は,例えていえば無限の宇宙に浮かぶ一個の星のような存在に見えます。宇宙の大きさの前では,星に例えられる人間はほとんど無に等しく,事実人間の心は絶えず自然の無化作用に脅かされるのです。しかし星が強い光に満ちているかぎりは,自身が無限大の闇に包囲されていることは忘れていられるのです。それほどの光を放つ力を人間は持っています。
こうした人間的特性が,他者との関係,そして自己自身との関係を,欠かせない存在要件としています。つまり自我はそれ自身で自足するものではなく,全的な存在であろうとする可能性を生きるべく宿命づけられています。他者との関係,自己自身との関係は,既に自我の機構の内部に自然そのもののプロセスとして所持していると考えられます。言葉を換えれば,現実の他者および自己自身との関係の可能態を,それぞれの自我は既にあらかじめ所持しているのです。それらを根拠として,現実の他者との関係を生き,あるいは自己自身との関係を模索すると考えることができます。
自我の自己自身との関係とは,言葉を換えれば自我と無意識的自己との関係ということになるでしょう。しかし生まれて間もない自我は,その成長のためには他者の助けを必須のものとしています。とりわけ特別な他者である母親とは,全面依存という関係です。赤ん坊と母親とは全面的に助けられ,助けるという依存関係であり,しかしながら人間の能力として完全な相互依存ではありません。原初的な関係において,赤ん坊のもとめる絶対的な依存欲求が不完全にしか適えられないということの中に,自己は自己自身との関係が確立されていかなければならない理由の根本があります。赤ん坊の自我は母親に全面的に依存しつつ,しかし不完全であり,不完全であればこその依存なのです。この不安定な依存関係が,赤ん坊の心に,信頼と不信,満足と不満足,安心と不安という満たし尽くされない空隙をもたらし,それが自我の発達を促す原動力になります。それらのこともまた,自我の機構的な構造に含まれていると考えてよいと思います。しかし他なる他者としての母親が母性を欠いている場合は,信頼よりは不信,満足よりは不満足,安心よりは不安ということになり,いわば後天的に自我の機構に破壊的な影響を与えると思われます。逆に母親の愛情がいかにも自然的に子に注がれれば,一般の動物とおなじように人間の心もまた自然な発達をしていくに違いありません。しかしご承知のように,人間の心はどうしてもさまざまに自然から遠ざかり,その観点からすると個々に歪んでいるのです。こうした他者による介入,なかんずく母親の介入は人間の精神を反自然的にさまざまに歪めさせるのは必定です。それを改めて自我が引き受けることがもとめられています。歪められた心を引き受ける雄雄しい自我が,その歪みを徐々に解除しつつ,本来もとめられているであろう自己の姿勢を追求していく自己の回復のプロセスが,いわば人生です。
以下は,両親の理想的な愛情の下にあったと思われる方の例です。
患者さんは70代後半の女性です。うつ状態が長くつづき,涙にくれる日々ということで受診しました。うつ病の発症は,初診の1年ほど前になりますが,かつての恋人の訃報に接したことがきっかけとなりました。その男性と別れたのは,50数年も昔のことになります。
彼女の父親は名のある政治家でしたが,歴史的に著名な何人もの学者たちと懇意にしていた人でもあったそうです。その父親は,家庭にあっては自由の精神を尊重し,音楽,絵画などの素養を持ち,子供たちにもそうした素養を身につけることができるように,時間を惜しまず機会を与えました。
子供時代は第二次大戦前のことであり,海外の統治国で過ごしました。大きな邸宅に大勢の男女の使用人が同居して,身の回りの世話をやいてくれました。母親は,「大和撫子の鑑といわれていた」といいます。あらゆる人に分け隔てなく愛情を注いだそうです。
彼女は女子の入学が許された草創期に大学に入りました。「夢子ちゃんといわれていました」というように,「本があれば何も要らない」といったふうでしたが,一方ではダンス,テニスなどのスポーツを好み,ピアノの練習,料理など多方面にわたって生活を楽しみました。留学も経験しています。
大学を卒業するころ,同窓の恋人から,突然,「これ以上つきあえない」といわれたそうです。理由は何も知らされず,また,「訊いてみようとさえしない子供でした」ということです。いわば何不自由のない生活をしてきた彼女は,生活臭といったものがない人です。「二人でいさえすればどんな暮らしでもよかった」という言葉に嘘はなかったでしょう。どんなに貧乏をしたとしても,それを嘆く姿が想像しにくい方です。どういう生活状況であれ,いわば自然に生きていたのではないかという印象があります。彼女の伴侶となるべき人はその彼氏以外には考えらないといい,実際にもその通りでした。何故そう思うのか,言葉で表現するのはほとんど困難でしたが,彼氏が常識的な意味での生活力があるかどうかは問題外のようです。彼女がそのようにいい,実際にその通りだろうとうなづくしかないのですが,そのことは彼女の伴侶となるべき人が,客観的に語れる人格の持ち主というものではなく,彼女自身のもう一つの半分の像をその男性に投射して見ているように思われました。いわば彼女は自分自身に恋したと考えて,ようやく理解がいくのです。
彼女の失恋は周囲の者たちには知れ渡っていたようで,その一人の男性が恋人としての名乗りを上げたのです。彼女はまったくの受身で交際していたようで,「気がついたら結婚していた」のです。
この夫も一流大学で然るべき地位にあった方です。しかし学者然として人を近づけないという感じの人ではなく,浮世離れをした妻の忠実な伴侶といった雰囲気を持っています。この夫なしには,浮世を渡るのがはなはだ難しいように思われるのですが,いつかな夫との結婚を肯定的には見ようとはしないのです。夫を見下しているともいえるのですが,彼女は決して高慢ではなく,自分の感情に単に自然に従っているだけなのです。夫もまた,妻のそうした態度を不快にも,不満にも思わないようで,常に笑みを浮かべながら妻の心情を観察して私に伝えてくれるのでした。
彼女が心を許せるのは,今は亡き両親と,子供たち,孫たちと兄など,血縁関係にある人ばかりのようです。そして肉親以外の唯一の例外は,50数年前に分かれたかつての恋人なのです。
子供たちを育てているあいだは,一途に育児に打ち込みました。そしてそれぞれが独立し,両親も他界したあとは,過去の恋人との思い出だけが心を支えているかのようでした。その男性の訃報に接したあとは,まるで昨今分かれたばかりの恋人の死を嘆くように,時空を超越して涙に暮れるのです。そして生きる理由のほとんどが失われたという気配です。
一日の生活は,「本さえあれば何も困らない」というように,手許にある馴染みのある本を繰り返し読むことで費やされているようです。それは読書三昧というものではなく,既に生きる実質的な理由を失って,形式化されたものであるように思われます。そしてときに縁側に座って庭の樹木や花に見取れます。食欲があるときは,「食べ過ぎて太ってしまった」と気にすることはありますが,食事も気分のおもむくままです。
通院はしていますが,意志的に元気になりたいなどとはまったく考えません。仮に薬などによって元気になったとすれば,それもまた拒むものではないでしょうし,辛い人生という意識も殊更にはありません。自殺という意志的な考えも起こりません。人生の終焉として死が訪れるのであれば,それもまた自然に従おうとする心があるばかりです。
ことごとくに自然の感情に従い,それに逆らうという様子が,この方には見えません。彼女を気遣う夫や子供たちに応えて,少しは生きる努力をして安心させようとする心の動きもありません。それはしかし頑固というものには程遠いのです。外国に住む子供たちから,毎日のように電話がかかるのですが,彼女から電話をかけることは決してありません。しかし子供たちを何よりも愛しています。
生きるため,生活するために,意志的な努力をしない彼女に対して,夫は忠実なしもべのように黙々と必要な役割を果たしています。かなり長期にわたる通院になりましたが,必ず夫が付き添っていました。うつ状態のためということ以上に,電車を乗り継いでの通院が,一人ではほぼ不可能でした。どの駅で降り,どの電車に乗り換えるのか,夫の助けがないと不可能なのです。
この症例の方は,現実にはあり得ない,おとぎ話の世界の主人公のような印象を受けます。子供のころから不安とか不満とかの感情に悩まされた記憶がなく,いわば何一つ不自由のない育ち方をしているといってよいように思われます。それは甘やかされたとか,過保護だったとかという以上に,両親の稀有な愛情の下で成長したというべきことのようです。そしてこの方の心のありようは,考えられるかぎりの自然流というふうに見えます。
この方は両親の保護が物心両面にわたり理想的に行き届いていたために,自然的に生きることが可能だったという稀な例のように思われます。そして一方では,社会性という観点からすると著しく欠けるものがあるといわなければなりませんが,それを意識し,問題視しようとする心の動きはありません。
自然的に生きていくしかないこの方は,確かな関係を持ち得る具体的な他者の存在が失せてしまってからは,ほとんど生きる理由を失ってしまったかのように見えます。両親の死後,両親の霊魂のようなものが彼女の周辺に絶えず漂っているといいます。それは実態的な雰囲気を持つ,守護者です。そうしたことが客観的に実在するものか,それとも主観的,心霊的な現象なのかなどということは,彼女には問題ではありません。単にそういう事実があるばかりなのです。
稀に見る自然流の心を持つこの方には,自我の確立,自立心の涵養といったこととも無縁のようです。
このことから考えると,たくましく自己であろうとすると,他者の歪んだ介入をむしろ必要としているといわなければならないように思います。その他者の歪んだ介入は,まさしく,先ほど述べた偽りの自己の源流となる影の領域の心を作り出すものでもありますが,社会的人格を形成するためには,心内での対立,葛藤が欠かせないもののようです。
いかにも自然流の心でいるこの女性には,影の自己といったものが希薄です。彼女の無意識を探ると第二の自己が表われて問題が回復に向かう,ということはほとんど信じ難いことです。何よりも抑圧されている個人的無意識といったものがあまり問題にならないことが,彼女の場合,むしろ稀有な特徴になるのではないでしょうか。
そのように考えると,影の自己の存在は人間にはむしろ欠けてはならないといえます。そういうものがあるために,それを解決する自我の責任意識のごときものが必要とされるのです。自己が当面している(心の)内外の問題を引き受けるのが自我の本分です。影の自己は他者(特に人生最早期の,最も重要であり,原初的な他者である母親)の介入によって生起するとはいえ,その不可避的に関与してしまっているものを,自我は己の課題として引き受けていかなければなりません。それら影の分身たちによって悩まされながらも,それを引き受ける雄雄しい自我だけが自己を助ける力を持つのです。
影の分身たちを引き受ける雄々しい自我がある一方には,引き受けない自我もあります。影の分身に悩まされていることを意識したがらない自我は,分身たちが存在しないかのような不誠実な姿勢に終始します。そうした欺瞞化する自我を持つ自己を,偽りの自己と呼ぶことは妥当だろうと思います。
逆に真のあり方を志向する自己とは,自分自身が作り出した分身たちの存在に悩まされながら,意を決してそれらの分身たちを引き受けようとし,責任を持とうとする自我に拠る場合といえます。
このあたりの問題は次に上げる男性の例に端的に表われています。
男性は30代です。身分保障に恵まれた職場で専門的な仕事をしています。いわゆる’現場’で対人的な関わりをするのが本来の職分ですが,請われる形で現在の事務職に就いています。彼を招いた先輩が転勤で去り,新しく上司となった人との関係がうつ病を発症したきっかけとなりました。その上司は,彼によればよく怒鳴るのだそうです。男性は上司に認められるとよく仕事ができる人ですが,高圧的な上司の下では怒りが内向して,気力が萎えてしまう傾向があります。職場の問題の他に家庭の問題も重なり,長期間の休職となっています。
男性は旅行を好みます。海外にも何度も行っています。最近,十日ほどの予定で計画を立てましたが,出発の直前まで無気力でほとんど自宅から出られない日々でした(彼は一人暮らしです)。そういう状態で海外旅行など出来るだろうかと思いましたが,何とか飛行機に乗り込みました。そして旅行中はいつになく元気でいられたのです。
男性によれば,十日のあいだに七カ国を回ったのですが,それらの旅行の計画や,不自由な言葉の問題などを,当然のことながら自分一人の責任でやらなければなりません。誰かを当てにすることができず,一切を自分が引き受けなければなりません。何が起こっても自分の責任において解決を図らなければなりません。そういうことが元気を取り戻すことができた理由のように思うといいます。
それでは,そのあたりのことがふだんはどうなっているのか,なぜ不調なのかという問いに対して,職場を含めた生活全般に,誰かが何とかしてくれるだろうといった甘えが,どことなくあると思うといいます。
男性のこの経験は,私流に解釈すると次のようになります。
外国旅行中は,男性がいうように,自分以外の誰をも当てにできない生活状況に自ら身を置くことになります。そういう状況では,自我が一切を引き受ける以外にありません。自我が自己に関わるすべてを引き受ける姿勢に入ることにより,彼が所有しているエネルギーを十分に動員することができたと考えることができます。
一方,日常はどことなしの依存があり,漠然と誰かのたすけによって意欲が保たれ,あるいはたすけがないときは意欲が阻喪されてしまうと考えられるのです。言葉を換えれば自我が自己と生活全般を引き受ける意志を持たず,だれかのたすけを漠然と当てにしているのです。そういうときには,自我は必要な仕事をしていないので,エネルギーは自我の負債ともいえる意識下の分身たちに取られてしまうのです。これら分身たちは自我の力によって救い上げられるのを待っているのですが,自我は当事者意識が希薄で,分身たちを引き受ける心になれないのです。
また別の男性の例では,もともと他に気を使う性格で,与えられた仕事を断ることができず,人一倍頑張る方です。うつ状態で休職になり,やがて復職しました。会社は鷹揚なところがあり,本人が望む限り負荷はかけてこないので,しばらくは人より負担の軽い仕事をしています。会社からの圧力は何もないのですが,男性が仕事をふやさないと申し訳ないと気にします。しかし,「しばしば心にもやもやしたものを感じる」という形で分身たちがその存在を誇示しているのです。この方の場合も,他に気を使うことも大事とはいえ,引き受ける(気を使う)べきものは第一に分身でなければなりません。そうでなければしばらくは持ちこたえることができても,やがてうつ状態が高じる懸念を否定できません。
これらの男性の例に見たように,光の世界を切り開く使命を持つ自我は,不可避的に影の世界(意識下の分身たち)をも作り出す宿命の下にあります。自我はいわば自ら作り出した影に怯え,悩まされつつ,それを超克していく使命を持っています。全的な存在ではないという性格のものである自我は,影ないしは闇をその内に持ちつつ,それらによって自我自身を超えたものの存在を意識します。そのことは,自我が畏怖の念を抱くことができるための内的で根源的理由にもなっています。それは不安と恐怖の根源となるものですが,永遠なるものに対して畏敬の念を持つことを可能にするものでもあります。
偽りの自己と真の自己とを考えるために,万引きを例にしてみます。万引き行為は悪に違いないとはいえ,精神科の臨床で問題にされることが珍しくありません。これは犯罪の中でも悪性度が比較的低く,その問題を治療者と共有できる自我の健全性がそれなりに保たれていることが多いからだと思います。この他者と共有できる自我の健全性の程度が,犯罪の悪性度に大いに関係があると考えてよいでしょう。そして悪性度の低い犯罪は,悪しき依存の一つの形として精神科の臨床の問題となり得るのです。
依存の心の病的な表現である万引きが,悪そのものであるのは論を待ちません。その論拠は法律にあり,また常識的な倫理観にあるとひとまずはいえると思います。しかしそのような人為的な取り決めごとにとどまるものでもありません。そこに更に人為的なものを超越した理由がなければ,説得力も不確かなものになるでしょう。
その超人為的な論拠は,少なくても一つには,自我の境界機能に求められます。この機能の一つに,自己と他者とのあいだに一線を画すということがあると思われます。それが自他を弁別し,それぞれの自己を独立したものとして保証する原理的な理由であると考えられます。(したがって親,特に母親が自分の子の世界に干渉,侵入するのは,誇張的にいえば人権侵犯になります。一般に母親がこの過ちを侵しがちなのは,子が赤ん坊のころに母子密着の時期を経験するからでしょう)
自我機能の基盤をなすと考えられる自我機構は,自然のプロセスの内部にあると考えられます。法律という公共的な規則,規制が揺るぎのないものであるためには,人間の知性が超知性的な根拠の上に成立することが必要ですが,自我機構にはそのような性格があると仮定的に考えることができます。
このように考えると,万引きという行為が悪であるのは,自我がその本分に基づいた仕事をしていないところに問題の一端があることになります。
偽りの自己についても,これとおなじことがいえるでしょう。つまり偽りの自己とは,自我が影の分身たちに対して,本来あるべき役割を果たそうとしていない場合といえます。そのように見ていけば,悪の問題と偽りの自己の問題とは近縁の関係にあることが分かります。
悪性度の低い段階での万引き行為では,人の目を盗む一方で,場合によっては人の目に触れることを望んでいるように見受けられます。そこには,悪性の行為とはいえ,何らかの意味のあるメッセージが込められていると考えられます。
悪の特性に即したメッセージということになれば,望ましい形の否定,いやがらせ,挑戦,脅しなどなどの影の自己の要求を受け入れた行動の形を取ることになるでしょう。それは従来の自己が偽りのものであること,その自己が「(親である)あなたとの関係で生じている」ことを暗に主張しているということになると思われます。
「私はあなたが望んでいるような良い子ではありません。むしろ悪い子です」,「私が家のお金を盗むのは,私がもらうべきものだったもの(愛情,信頼など)をもらっていないからです」,「みんなが一家の主として私を尊敬しないのであれば,私は盗人となって転落します。そうするとみんなは私の存在を少しは認識することになるかもしれない」,「あなたは会社で偉い人かもしれませんが,夫として私のことを疎かにし過ぎていませんか。私が転落するとあなたはうれしいですか,それとも私に少しでも目を向けるつもりがありますか」等々・・・。
メッセージ性のある悪性の行為では,健全な関係が,歪んではいても壊れてはいないことが認められます。そのときに自我の意識は,半ばは関係者に向けられ,半ばは分身たちに向けられています。分身たちのたくらみは,目先の利得,満足の要求です。自我の意図は,分身たちの意向を行動に移すとすれば,関係者との関係に与える影響がどの程度破壊的であるかを計ることです。その程度には分身たちの力に押され,その程度には分身たちを抑える力を残しています。強力な力を持たない自我は,分身たちが求める目先の欲求充足に身を任せる責任回避と,そのような事態をもたらしたと考える関係者を窮地に追いやることの意趣返しとで,暗く危険な愉楽にふけるという側面も持ちつつ,関係者に助けを求めているのです。やがて自我が目を覚ますときは,関係者への愛情と信頼とが回復されているでしょう。そのときに危険な愉楽の試みは,一定の成果を手にしたことになります。
このように,悪は,自我が社会的責任を回避することと,刹那の愉楽に身を任せようとする無責任とで,社会的な位置を危うくさせることになりますが,重要な位置にある関係者に助けを求めているかぎり自我の力が回復する可能性があるといえると思います。そのかぎりでは治療的な介入が意味を持ちますが,刹那の愉楽をもとめて止まない心が大きな障害になります。一般に犯罪は,悪性の依存的行為であるといえる所以です。
幼い心としては,たとえ他人の物であれ自分の物としたい心があって当然です。それを考えると幼い心が盗みを働くのが,なぜ真実の自己の行為とはいえないのかということにもなるかもしれません。その点は先に述べたように,他者との関係で相互の境界が自我の機能に内在しているからというのが根本的な理由といえるでしょう。つまり盗みはいけないという指導は,内的な自然のプロセスに即した理由を持っているといえるのです。
ここに表われているのは二つの側面です。一つは親(という他者)との関係であり,もう一つは自然のプロセスの中にある無意識的自己との関係です。欲しい物を自分の手許に置きたいというのは,そもそもは本能的な自然のプロセスによるものです。そして他者の介入により,その行為の善悪が問題になります。その根拠は介入する他者の恣意によるものであってはならないでしょう。つまり自我の機構に内在すると思われる境界機能に即した他者の介入であれば,恣意によるものではありません。それは正しい指導であり,納得がいくはずのものです。
この自然のプロセスに基づく二つの要求は互いに矛盾します。子供は葛藤に悩むことになります。そして親との関係は幼い子にとっては何ものにも優先させなければなりません。子供は原則的に親に従うしかありませんが,親子の関係が愛情と信頼とで満足できるものであれば,その葛藤の解消は一般に困難ではないでしょう。
ところが親が体罰を加えるなど,度の過ぎた育児指導をしたり,両親の不和,母親の神経質や病気,等々によって,乳幼児期に過度に不安や怯えを経験したりすると,子供の心は親への不満,反感を密かに強めるのは避け難いでしょう。そのような心理にあるとき,他者とのあいだの境界を侵してはならないという自然の心に従うよりも,満足を得たいという自然の心に従おうとするとしても不思議はありません。このような場合にはいずれにせよ幼い心には,満たされない思いの分身たちが大きな勢力を占め,それに伴って強い怒りが内向していると考えなければなりません。
強い怒りが内向するときには,必然的に,不当に満たされるべきものを満たされなかったという思いと,護られるべき安全が不当に無視されたという思いが交錯して内在すると思います。それらは自己が自己らしく生きる上で,是非とも適えられなければならない思いといっていいでしょう。それを果たさなければならないのは自我です。自我がこの苦境を引き受ける雄雄しい態度を取るときが来ないかぎり,分身たちの怒りと不満とによって内側から蝕まれていくことになります。蝕まれかけた心が悪を表現します。それは表の心の営為の中心である自我が不甲斐なく,裏の心の営為に主導権が渡りつつあることの表現です。
この険悪な心的状況をはね返すには,強い自我の力が必要です。
私が,「盗みはしない」と意識し,行動するように努めているかぎり,私は光(正)の世界の住人です。しかしそれは私の正を保証するものではありません。負があればこそ正があるのです。私が行動として負に落ちないためには,自分の正を信じるよりは負の存在について深く思いを馳せる必要があるでしょう。もしかすると,盗みを働いた人に憎しみの情を持つことは,まだまだ心が負に傾く危険があることを知らなければならないのかもしれません。自分の内面に潜む盗人の心を一掃することは不可能である以上(人間である以上は不可能です),盗人を憎むことは自分を憎むことです。考えの中にあることと実際に行動することとは,まったく次元が違うともいえますが,「絶対に私は人の物を盗みません」と断言できる理由にはなりません。むしろ,「その可能性を一掃できないので,よくよく注意したいと思います」という方が自分に忠実といえるのかもしれません。そう考えることで盗みという悪行を許す理由にはなり得ないでしょうし,盗みという犯罪に対して,人間的な態度を取ることができるかもしれません。
盗みはともかく,自己の負性に苦しめられることは多かれ少なかれ避けられず,それを克服するべく引き受けるか,気晴らしをして問題を回避するかということになります。一般的には,そういう意識に囚われていると日常の生活に支障をきたすでしょうから,回避的態度になると思います。
ここでいう偽りの自己に悩まされる意識というのは,それを引き受けたときに意味のある問題になり得るのです。それは人間が何を目指して生きるのかという問いを,自分に対して立てるのとおなじ意味を持ちます。
偽りの自己とは,自我の臆病ないしは自我の欺瞞の犠牲になっているものたちの存在をかかえる自己といえます。
光の世界のものである自我によって影の世界に追いやられたものたちに対する自我の態度には,二通りあります。
一つは雄雄しく引き受ける自我です。一つは女々しく,引き受けない自我です。
前者と後者との自我の営為に対する評価は,自己自身との関係に与える影響如何ということになります。つまり前者への評価は自己の充足感,生気感情の高揚という結果をもたらします。後者への評価は,それとは逆に,自己の不充足感,生気感情の低落という結果をもたらします。
自我の仕事を評価する力を持つのは,自我を超越したものでなければならず,従ってそれは無意識界に内在するはずの超越者といえるものです。それは仮説の域を出ることがない問題ですが,精神現象を論理的に理解しようとすれば,自ずからそれが指し示されているともいえるのです。
偽りの自己とは,その本分に基づいた仕事をしない自我によって影の世界に追いやられたものたちの存在が生じ,なおかつそれらの存在に自我が目を向けようとしないままでいる自己のことです。それは仮説的に述べた内在する主体によって,評価されることがない自我に拠る自己です。そして人間は常に何ほどか偽りの自己であり,そうあらざるを得ない存在であるといえます。人間のあるべき姿は,そのことを絶えず悩み,絶えず問い,そしてそれを克服することといえます。そうすることで一歩ずつ真実の自己へ近づくのです。しかしまた,最終的に真実の自己に合一するところまで自己を克服するのは不可能なのも人間です。そのような自己を人間は生きているといえると考えられますが,自我は’真実なる自己という絶対的な光’に向けて,時々の偽りの自己を克服していく根拠となるものです。そのように,光の世界の演出者という性格を持つ自我が,あえて死を志向するということは考えられないことです。死は自我の無力化,無効化に伴って姿を表すものです。自我は無限または無,あるいは絶対という性格を持つ自然によって無化されるものです。それが死の意味であると考えられます。
敷衍すると,自我が無力化するにつれ,相対的に個人的無意識(C.Gユングによる)が勢力を強めます。個人的無意識は,自然そのものが心に及んでいると考えられる普遍的無意識(ユングによる)と,相互に交流していると仮定的に考えられます。自我が衰弱していくと,自我の負性の特徴を持つ個人的無意識を介して,場合によっては自然の無化作用が自我に及ぶと考えられるのです。
自然自我ととの関係は,宇宙の無限空間とそこに浮かぶ星体に比してみると分かり易いように思います。自我なる星体は,自然なる無限空間の中で,マクロ的に見ればいかにも頼りなげで,ミクロ的に見れば,無限の深みを持つ周囲の暗黒をはね返すほどに力強い光を持っている,というふうに見えます。自我なる星体と自然なる宇宙とは,対立して相互に交わることがないというものではなく,自我の生物学的根拠と仮定される自我機構の中に,自然そのものの特性が及んでいると考えられます。
生まれたばかりの赤ん坊の心は,自然そのものである普遍的無意識と,自然そのものの中にあって自然から乖離する方向性を持った,萌芽的な自我とから成ると仮定的に考えられます。萌芽の状態にある自我は,母親の自我との協働でしだいに機能を高めていきます。この母親との関係は,明確に自然から乖離した次元の上に成り立ちます。母親との関係を最優先とする乳幼児の自我が,無意識から生起する自然のものである心たちを抑圧,排除して,母親が望むような自己形成に励むことになりますが,この抑圧,排除された無垢の心たちが個人的無意識の層を作っていくことになります。
また自我と無意識の関係について,私はしばしば次のような比喩を引き合いにして説明を試みています。
無意識は海であり,自我は小舟の船頭です。日常がとりたてて問題がない人の場合,天気晴朗で,海は凪いでいます。近くには多くの小舟が浮かんでいるのが見えます。天候が怪しくなり,海が荒れても,仲間同士で励まし合い,助け合ってなんとか乗り切れます。仲間たちとの関係で支えられている自我なる船頭は,孤独になったときに容赦なく突きつけてくる’航海の意味’という難題に悩まされることがなく,念頭に浮かべる必要がなく,目前の困難を仲間と共に乗り切ることだけを考えていればいいのです。それは自我の力で何とか乗り切れる見通しの下での困難といえます。こういう自我の下では,海は過激な荒れ方はしないものです。
しかし死が問題となっている自我の下では,天候は不良で,海は荒れがちで,あたりに仲間の船影がありません。荒れる海にもまれて,どこへ向かうとも知れない航海になんの意味があるのかという懐疑が船頭を捉えます。その種の懐疑はもっともなものでもありますが,心細いかぎりの思いでいる船頭が,孤独に船を操る意味を悟るのは至難の業です。実人生のさ中での問いは絶望をもたらすだけです。そういう問いは,実人生から距離を置いた哲学的,心理学的なものでなければならないでしょう。
そのような意味不明の難儀な航海に耐えるよりは,いっそのこと海に飛び込んで航海を終わりにしたいと考えるのも,無理からぬことです。しかしそうすることが船頭の自由かといえば,そうはいえません。それが船頭の意志であるといえるためには,自我がそれなりに自由であり,健全であることが前提になります。つまり航海について創意工夫をこらす自由はあっても,航海そのものをやめるのは,自我が自由にできる範疇の問題ではありません。死は自我の終焉,自我の最終的な挫折です。自我を超えた力,海なる無限,全,あるいは無という性格のものによって,自我は終焉に導かれる可能性を持っています。つまり力尽きた自我が終焉を向かえたときに,死があるのです。死は自我の終焉と同義です。そして無限,または無という性格を持つ自然によって,自我は無化され,回収されます。それは自我が自ら意志してではなく,自我の無効に伴ってはじまる回収作業です。死は自我の意志,自我の決定により自由に選べるというものではなく,抗し得ない成り行きというものです。「死にたい,なぜそうしてはいけないのか?」と問いかける人は,そのような回収作業に取り込まれかけているのかもしれませんが,むしろ生きる意志を持っており,助かる可能性はあるだろうかと反問しているように思われます。より深刻な事態に陥って,死が避けられないと感じている場合は,むしろこのような問いは向けてこないのではないでしょうか。
それでは死を志向する心の中心には何があるのでしょう。
Lさんの例では,首を絞めたり,刃物を突きつけたり,手首に傷を負わせたりしていますが,そこにはもちろん怒りが絡んでいます。首を絞めたのと手首に傷を負わせたのとは,Lさんの言葉によれば,「子供の仕返し」です。子供というのは先に説明したように,母親とのあいだのいわば共犯関係によって犠牲にされ,抑圧された自然的な心たちです。それは理不尽な目にあっている分,当然,怒りと共にあります。内向する怒りに火がついて,自分たちの存在の元凶ともいえる自我に襲いかかったといえます。また自分の胸に刃物を当てることで,「子供を殺そうとした」のは,混乱に陥っている自我の仕業です。
Lさんの取るべき唯一の方法は,怒りを母親との関係に向けることです。それは自我が分身の怒りを受け止めることをも意味します。それが果たされないかぎり幼い分身は,自我によって受け入れられる見込みを持てないのです。自我はまた,それらの分身を受け入れることで,本来もとめられている力を発揮できたことになります。逆に母親との共犯関係を手放そうとしない自我は,怒りと共にある分身を意識下に封じ込めるために多大のエネルギーを費やし,かつ分身が意識下で暗躍するために,多大なエネルギーを奪われることになります。その結果,自我が自己の世界を拡大,発展させていくエネルギーが削がれることになります。
それだけの犠牲を払ってでも旧来の母親との関係を失いたくない自我は,そもそもがよほど怯えているのです。それは見捨てられる恐怖に由来する怯えだと思います。怯える自我はしがみつく自我です。このような事情がありますので,母親との強固な関係の下にあるLさんにはかなり困難な課題ですが,それでもその関係を破壊し,清算しなければ,幼い分身を救い出す手立てがありません。些細といえる刺激で混乱する自我の下では,人生は多難を極めます。どうしても困難な内外の心的状況を,ともかくも自我が引き受ける気勢を示すことは,人生の軌道をただすためには必須です。
このあたりの問題の解決の鍵は,治療者との関係がしっかりとした信頼でつながれるかどうかにあります。それができれば,自我はその姿勢をただすためのひとまずの根拠を得ることができます。
Lさんの母親との関係が現状のままであれば,幼い分身は救われません。自我が勇気を出して内外の状況を引き受けることがないまま,やがて母親との関係も活力を失うと,事態は更に悪化します。自我が更に無気力となると,人間そのものが内部から蝕まれることにもなりかねかせん。そのような成り行きになると,幼い分身が心の主導権を握ることになると思います。自我に分身を引き受ける力も意志もないのがはっきりすると,影の存在である分身たちは闇の世界のもの,死の世界のものの性格を強めていくことでしょう。それは社会性を引き受ける自我が,もはや機能しなくなっているに等しいということでもあります。人生の意味が見失われ,直接に死が志向されるか,闇のものの特徴として悪の色合いを深めていくかということになるでしょう。
その闇のものの中心にあるのは,自我が光の世界の中核であるのと正反対に,裏の自我ともいうべきものです。それは悪をなすものです。悪とは破壊そのものが目的である破壊です。非適応的な破壊ともいえます。他者との関係での一途の破壊は,暴力ないしは犯罪です。自己自身との関係での破壊は,自死が志向されます。
現実的な心の中心である自我が力を失えば,幼い分身たちは生きる方向で日の目を見る機会が永遠に奪われてしまいます。そうなると闇の世界のものである分身たちに,エネルギーの過半が移行します。強力なエネルギーを持った幼い分身たちは,自我を傀儡化して目先の欲求を満たすために自我をあやつり,他者との関係を毀損して傷む心を持たないことにもなっていきます。
この人格全体の主導権を握った闇のものは,社会的に未熟で,対人配慮に欠け,いたって自己本位になります。生きる方向での希望を絶たれたものが持つ恨み,怒り,絶望,羨望といった黒い感情を身にまとい,人品を著しく欠いたものになります。
自我が分身たちとの好ましくない長期にわたる相対関係で衰弱し,分身たちが自我に統合される可能性が事実上絶たれてしまうと,怒りを蓄えた分身たちが悪の性格を帯びるようになり得るのです。そこにあるのは,自己と他者との関係の,そして自己と自己自身との関係の実質的な破壊です。いわば人に迷惑をかけることなど眼中になく,その悪行に悩む自己がありません。
(付言すると,Lさんは彼女を慕っていた年下の女性の死という事態に直面しました。その死は避け難く,予期されたものでした。しかしLさんは,その悲報によって雄雄しい精神になることができました。「彼女はもっと生きていたかったに違いありません。それを思うと私が死を云々することは許されないと思います」とLさんはいいます。人によっては,更に落ち込むこともある状況です。死によってかけがえのない友人を失うという状況で,Lさんの自我はむしろ決然と生きる意志を確かめたのです)
いま述べたように自我が自己形成の表舞台の演出家であるとすれば,挫折した自我の下では,自我のネガである悪の様相を帯びた裏舞台の演出家もあることになります。前者が生または光を志向し,後者は死を志向します。そして後者は,本来は表の自我によって表舞台への登場が見込まれていたものたちを統合するものです。
自己の表舞台の演出家である本来の自我を表の自我と呼び,悪の性格を持つ裏舞台の演出家を裏の自我と呼んで区別したいと思います。裏の自我は,表の自我の衰弱に伴って,永遠に表舞台への登場が阻まれてしまったものたちの怨念を携えて,影の世界での暗躍を画策します。
表の自我と裏の自我とは,ポジとネガの関係にあります。前者が生きることの肯定系であり,後者は否定系といえます。
このように性格形成に関して,二つの首座があると考えるのは,日常の臨床を通じて表われてきた病理的現象に導かれたものです。ですからそれは病理的現象の理解にとって有用なのはいうまでもなく,治療的な手がかりとなるものでもあります。患者さんにそのような理解を伝えることで,患者さんが自分を悩ませていた問題に一定の見通しを持つことができれば,不安のかなりの部分が解消されることになります。またそのことにより,治療者との信頼関係もより安定したものになり,その後の診療を進めやすくなります。
多重人格という病理現象は,裏の自我の演出によると考えられる具体的な例です。明確に多重人格を語る患者さんは,一も二もなく以上の見解に理解と同意を示します。またそれ以外の大方の患者さんも,自分の心の深部でうごめく何ものかの感覚があり,以上のような説明に対して,直感的な理解を示すことが多いのです。
70代のある女性は,神経質症の気味があります。軽度の抑うつ感があり,アモキサンという抗うつ剤をごく少量使って改善しました。本人の判断で,ある時期からは気分が不安定になりそうなときだけ,10ミリグラムを服用しています。それでほとんど問題はありませんでした。
ある受診時に,「アモキサンはたくさん残っているから,今回は不用・・・」ということで処方はしませんでした。ところが家に帰ってみると,いくらもないことに気がつきました。律儀な性格のためか,決められた受信日以外に薬をもらいに行くことにためらいがあったそうです。この間,「うつ病がひどくなって入院することになるのではないか,一生だめになるのではないか」というふうに,良からぬことばかり考えてしまいました。そして明るく考えるよりは,暗く考えるほうがなぜか楽なのだといいます。
アモキサンは,薬理作用としては,たまに服用することで効果が得られるとは考え難く,おそらく気分的な効果だったと思われます。薬が手許にないということで,気持ちが動揺し,抑うつ感にかられたのだと想像されます。「暗く考えるほうがなぜか楽だった」というのは,どう解釈すればいいのか安易にはいえませんが,裏の自我の力に従うのが自然だったというふうに,私には思われました。葛藤に耐え,それに打ち克つのは相当なエネルギーを要しますので,この方は,そんなことよりも自然に従ったほうが楽だったと感じたのではないでしょうか。
Rさんの例に即して考えれば,怒りが母親(との関係)に向けられたことに大きな意味がありました。しかしそれは,一般に怒りが外に向けられることが有意義であるということではありません。Rさんの場合は,自我が怒りを受け入れる準備ができていたので有意味だったのです。怒りは母親に向けられましたが,本人は無自覚だったものの,Rさん自身にも向けられました。Rさんの自我は,自分自身がその怒りによって粉砕される恐怖に耐えることができると踏んだのでしょうし,母親の自我もその怒りによって粉砕されることはないだろうと踏んだのに違いありません。事実Rさんは,「自分の人生を目茶目茶にしておいて,母親面をして欲しくない・・・」と怒りを込めて語っておりましたが,やがては,「その一方では,母親を恋い慕う気持ちもある・・・」と述べております。
この怒りがRさんの意識にのぼる以前は,Rさんにとって怒りは存在しないも同然でした。しかし実際には無意識の世界に潜行していたのはいうまでもありません。そしてRさんが,「ものごころが着いたころから,死を望んでいた」といいます。そのことは裏の自我という’反自我連合’を統合する中核が早々と形成され,勢力を強めていたことを意味すると思います。Rさんの幼いころに母親の気分は特に不安定で,気分まかせに(理不尽に)怒鳴られることがあったようです。手厚い保護が必要であった年代の幼い自我は,母親の自我に必死にしがみつくことで精一杯だったのではないかと推測されます。安全感と情緒的な満足とが保証されることが特に必要な年代で,他でもなくそれらを保証する立場であるはずの母親によって脅かされ,剥奪されつづければ,脅威にさらされる幼い自我は,何を頼りにすればいいのか分からないでしょう。過酷で悲惨な心的状況だったと思います。年端のいかない年齢では,幼い心を引き受けるのは,幼い自我ではなく,主に母親なのです。引き受けられないと感じている幼い心が死を待望するとしても,何の不思議もありません。それでも幼い心は親とのあいだで密着した依存関係にあるので,自我はまだ未発達で,死を志向するほどには分身たちが勢力を強めていないといえるでしょう。幼い子の自死が比較的少ないのは,そのためではないかと考えられます。
これらの表と裏の自我の綱の引き合い(生きるか死ぬか)は,Rさんにとどまらず,臨床場面の随所に見て取れます。
これらのことをエネルギー論の観点から見ると,次のような仮説が考えられます。精神エネルギーの問題は,実証的に証明することは不可能なので,精神科の臨床をはじめ我々の日常の体験を合理的に考えればこのようになるという仮説にとどまるしかありません。そのような仮説を立てることは,精神の構造を措定する作業を補完する意味を持ちます。精神構造についても,自然科学的な意味での実証は不可能です。いわば一つのことを二つの局面から,可能なかぎりで合理的に考察するとこのようになると仮定的に考えることができるということです。
各人の精神的なエネルギーは定量であると思われる。言い換えると,集合的無意識に属するエネルギーと自我に属するエネルギーとはそれぞれ一定量である。前者は身体的なエネルギー,ないしは本能に属するエネルギーと相互に交流をはかりつつ,定量のエネルギーを保っていると推定される。また後者と前者とのあいだにもエネルギーの交流がはかられつつ,それぞれに定量のエネルギーが保持されていると推測される。
自我に属するエネルギーは,個人的無意識を養うために分与されると思われるが,個人的無意識層と普遍的無意識層とのあいだにもエネルギーの相互的な交流があると考えられる。しかしながら個人的無意識層のエネルギーは,本来は自我に留まるべきものであると想定される。つまり自我と個人的無意識層とのエネルギーの総和は定量であると考えられる。そのエネルギーは自我の活動いかんによって,双方に容易に移動すると推測される。
日常的には,自我に付与されているエネルギーが自我によっていわば運用されるが,特別な心的状況では,集合的無意識層にあるエネルギーが一時的に自我に向かって流れ込むことがあると思われる。
たとえば研究者や芸術家のインスピレーションがそういうものであり,いわゆる’火事場の馬鹿力’といわれている危急時の興奮のときにそういうことが起こる。あるいは統合失調症の病的な興奮や躁的興奮状態などの精神病性興奮,もしくは境界性人格障害などの興奮状態などのときにも,そのようなことが起こる。
前者のいわば適合的なエネルギーの移動は,強い感動をもたらします。それは自我が十二分に活動していることに伴うことのように思われます。逆に後者の病的興奮でのそのような現象は,自我に回るエネルギーが極端に少ない状態がつづいているときに起こるように思われます。そうした心的状況では自我が必要な働きができていず,相対的に無意識層の活動が活発化するために,ますます自我は破壊的な圧力を受けることになるのです。そのような状況で自我機構に非日常的な圧力がかかり,何らかの機能的,あるいは器質的な不具合が生じるのではないかと推測されます。それに伴って,自我と集合的無意識層とのあいだの境界機能が一時的にダメージを受け,後者のエネルギーが前者へとなだれ込むのではないかと想定されます。
統合失調症の中核群では,自我の機構に何らかの器質的欠陥が生じていると考えられます。そのために自我の境界機能に不都合が生じ,エネルギーの適量を確保する能力自体に問題が生じていると推測されます。
また統合失調症の中にもさまざまな移行形があります。健常な心とのあいだ,うつ病,神経症,人格障害などとのあいだにも相互に移行する病態があります。
それらすべての問題の中心にあるのは自我であるといえます。自我こそ人間の標章であり,自我の機能的,器質的なざまざまなレベルの様態が,さまざまな病的様態を惹き起こすといえます。
このあたりの問題を二つの例に見てみます。
Mさんは40代の主婦です。
診断名は「うつ病」で,通院歴は10年ほどになります。発病のきっかけの一つは,転居した先の主婦たちが,どれも賢そうに見えたことといいます。私のところには5年ほど通院していますが,初診の半年前に急性妄想状態で入院しております。
Mさんは女ばかりのきょうだいの次女で,一児の母です。彼女は夫を頼りにしており,娘が生まれたときに夫を取られると思ったといいます。子供に愛情を感じず,子煩悩な夫に不満を持ち,夫婦仲は険悪になりました。離婚の危機もあったようです。そもそもMさんは子供を持たないキャリアウーマンが理想と考えていました。実際,子を生まずに海外旅行などを楽しんでいる女性が羨ましくてなりません。結婚後に妊娠したときに,子供よりも仕事を取りたかったといいます。しかしそのことで夫との仲がおかしくなり,やむを得ず退職しました。
Mさんによれば,父親がことあるごとに,もっと勉強してキャリアウーマンになりなさいといっていたそうですが,その父親の一番のお気に入りは,’一番できの良い’妹だといいます。妹は研究者です。両親は将来この妹と一緒に暮らしたいと思っているそうです。長女である姉は,父親とおなじ医療系の専門職についています。姉と妹は頭が良く,美人で,子供のころから仲が良かったそうです。Mさんは孤独感をかみしめていました。家族全員が集まる席で,父が,「お前だけが母親似で,うまくいっていない」といったといいます。しかし両親の仲は大変よいといい,父親が母親を蔑視している節が感じられません。父親がいったというこの言葉がどこまで客観性があるのか疑問があります。
Mさんは仕事を持っていないことに異常に劣等感を持っていました。
娘が6歳になったころに,子供が誘拐される夢を見ました。夢の舞台のRさんは,誘拐されても構わないと思い,娘を捨てて家を出ました。いつかヤクザの世界に迷い込んでいました。その朝,気を失っているのを夫に発見されました。覚醒したMさんは,妄想の世界にいました。興奮が収まらず緊急の入院となりました。妄想の内容は,妹夫婦が加入している某宗教団体に家を乗っ取られる,義弟は学歴詐称をしているというものでした。義弟は国内の有名大学を卒業し,外国の有名大学に留学しています。ちなみに夫も,世間的に有名という意味では弟以上の大学の出身者です。Rさん自身は,私立の有名大学の出身です。Rさんも留学を望んでいました。姉妹たちは共におなじ高校(進学校として有名)を卒業しています。Mさんと母親とは資質的に文系で,他のきょうだいは父親とおなじ理系の大学を卒業したことを,Mさんは偶然以上のものとしてこだわりを持っていました。母親の家系には,知的で自由な職業についている人が多いそうです。そして母親自身は大学を出ていません。Mさんによれば大変頭が良い人で,全国的に有名な進学校の卒業生です。大学に進学しなかったのは,「女に学問は要らない」という父親の考えのためといいます。母親の学歴コンプレックスの犠牲にされたと考え,子供時代を,「下らない受験勉強に終始した」ことを悔やんでいる様子を垣間見せたこともあります。しかし別な機会には,母親は物事に囚われず,明朗闊達でスポーツを好み,感性が豊か・・・と称揚します。Mさんが語る父親,母親像には,一貫性が欠けているように感じられます。Mさんはむしろ聡明な人のように思われますので,このような混乱は無意識下のコンプレックスの影響を受けているのだろうかと想像されます。自分の子にも,下らないといって憚らないMさんの過去の人生の軌跡を,そのままたどらせようと躍起になっているところがありました。この矛盾については,父親の意向に抗せなかったと説明します。また,子供のころは父親を疎んじていたが,母方の親族の女性問題を軽蔑し,父親を高く評価するようになったといいます。また別な機会には,父親の生活姿勢には,何一つ問題のないしっかりした人と子供のころから思っていた,ともいいます。
Mさんの娘は,「私と対照的な能天気で,勉強などは気にかけずに,テレビを見て笑い転げるような性格」です。ある時期までは,「受験勉強に打ち込もうとしない・・・成績が伸びないのに平気な顔をしている・・・」と苛立ち,落ち込んで,娘の成績に振りまわされている様子が顕著にありました。しかしその様子に変化が見られ,受験に駆り立てる母親に,「おかあさんは,どうしてそんなに心配するの?私は何にも心配していないのに」と不思議そうにいうと,娘の立場を理解する様子が見えてきました。
Mさんが自分で嫌っている人生コースに,躍起となって幼い娘をはめ込もうとしている様子からは,Mさん自身の子供時代の母子関係が表れているように思われます。Mさんがいうように娘は能天気であるらしく,それは娘とMさんのために,喜ばしいことといってよいでしょう。またMさんの夫は,「お前みたいな下らん奴が出た学校に,娘を入れようとするな」というそうです。それをMさんは忌々しいとは捉えていない様子です。
結局は娘は公立の学校に進むことになりました。私立校への強かったこだわりを捨てることができたのは,一つには母親の苛立ちを一向に気にかけずに,’能天気’であるらしい娘に助けられたといえるのかもしれません。そしてこのごろのMさんは,キャリアウーマンへのこだわりも少なくなったといい,さばさばしているように見えます。日常の生活が結構楽しいと,かつては聞かれなかった感想をもらします。
先に上げた夢は,Mさんの葛藤を表現しています。
Mさんは他を羨み,自分にないものにあこがれる傾向が顕著でした。母親とは,「きょうだいのような仲」といいます。これは一見すると微笑ましい親子関係の表現のように見えますが,母親とのあいだに強い相互的な依存関係があることを暗示しているように思われます。言葉を換えれば母親を母性豊かなものとして尊重していない表現のように見えます。母親にMさんと共通するものがあるのは確かかもしれませんが,Mさんの自律的でない自我は,母親に同一視する(母親の自我にしがみつく)ことで平衡を保っているように見えます。
「きょうだいのように(母親と)仲がよい」というのは,若い女性からしばしば聞かれる言葉です。ここに共通しているのは,母親から独立し,自由になっていない心です。そしてそれが問題であるとは考えたくない様子が見えます。いわば母親にしがみつき,それを手放すと自分が立ち行かないという気分であるように思われますが,そういう認識の言葉を聞いた記憶が希薄です。このことには母親自身も一役買っているように思われます。そこにはかつて幼いころに得られなかった母親との蜜月関係がようやく実現できたという気配があります。(一般に,摂食障害や自傷行為が仲立ちになって,このような母親との蜜月関係が形成されることが珍しくありません)
母親に同一視(自律性を欠いた自我が母親の自我にしがみつく)するMさんの心を支配するのは,父性原理とでもいうべきもののようです。「父親は非の打ち所がなかったので,父親のいうことに逆らうことができなかった」といいますが,Mさんがイメージとして描いている父親からは,父性としての豊かさが感じられません。むしろひどく幼稚な身勝手な父親に感じられます。Mさんには懲罰的で恐ろしく,到底逆らえないものとして父親イメージが屹立しているようです。そのイメージの父親は,Mさんに怒りを持っていて,子供たちの中で最低位に価値づけされ(ということは無価値に等しい感覚になります),駄目な奴と思われているというふうなものです。それへの反作用として,それに相応してMさんの心にも強い怒りがあると考えられますが,父親を美化して心を護っているMさんにはそういう認識はありません。その父に認められることは到達困難な理想という形で,父親に拝跪する姿勢で内外の怒りを和らげようとしているように見えます。
客観的に父親は暴力的でもなければ威嚇的でもなかったようです。Mさんが自我の自律性を捨てざるを得なかったのは,記憶の届かない早期に体験した恐怖があったからに違いありませんが,それはむしろ母親との関係でのことではなかろうかと想像されます。幼い時代のMさんの自我がとった防衛的戦略は,一方では母親との同一視で,一方では父親の理想化ではなかったかと思われます。何を防衛したのかといえば,むしろMさん自身にある強い怒りと,それと恐らくは関連するだろう見捨てられる恐怖とに対してではなかろうかと推量されます。そのように内在する強い恐怖と怒りとの投影をまじえて,畏怖する父親像が生じ,「きょうだいのように仲のよい」母親像が生まれたのではないかと思われます。このようにMさんの自我は,父親と母親の自我のまったくの支配を受けています。子供のころは父親に反抗的な気分を持ったといいますが,ある時期から自我は自立と自由への途を断念し,父親に迎合する方向に転換しました。主体性を放棄した自我は,自分を助けるものを他に求めなければならなかったのです。
助けを求めたのは,一つには母親です。「きょうだいのように仲がよい」という形で,母親との依存関係を絶えず確かめる途を進んできました。それが,「勉強に明け暮れして,他の楽しみを知らない下らない人生」を選んだ理由の一つで,一方では,「母親の学歴コンプレックスの犠牲にされた」という密かな思いです。これも母親との関係を壊すわけにはいかないので,声高には叫ぶことができません。感性を共有すると信じているMさんは母親をコンサートに誘うなどしますが,そういう折に母親がMさんの姉妹たちのことを話題にするとたちまち不安に駆られます。
一つには夫です。夫にはMさんが描いている理想を託しているところがあります。しかし夫は実家の方に心が斜傾しているようで,Mさんには少々遠い存在です。Mさんが自分の両親と一緒に暮らしてくれる気があるかと訊いたときに,断られました。夫は世間的に有名な学歴の持ち主です。しかし義弟は留学をしているので,そちらの方が一等高いものとしてMさんを脅かします。そして義弟の妻であるMさんの妹は,「美人で,頭が良くて,羨ましい職に就いていて,父親の大のお気に入り」なので,Mさんにとっては何から何まで敵わない人なのです。義弟は学歴詐称ではないかと妄想の中でこき下ろしにかかっています。そして密かに第一等でありたいという野心を抱いている(Mさんは,「白雪姫」のお妃に自分はそっくりだといっています)Mさんの自我は,かれら夫妻への羨望で破壊されそうなのです。それが義弟たちが入っている宗教団体に家を乗っ取られるという妄想になって表れています。
一つには娘です。Mさんは母親の特権をふるって,娘を自分の写し絵にしようとしました。娘を自由に支配することは,支配を受けないでは立ち行かない自我の歪んだ戦略といえます。歪ませたのは無意識界に膨れ上がっている負の分身たち(コンプレックス)といえるでしょう。自律性と主体性を欠いた自我は,外では父,母の自我の傀儡となり,内では怒れる分身たちの傀儡にならざるを得ないのです。分身たちによって傀儡とされた自我は,娘に対しては黒く彩られています。それは父,母に対しては拝跪する姿勢(よい子)で,あくまでも白い彩を演出(黒い欲求を隠す)しているのと好一対です。
自我を傀儡化している分身たちの要求は,「世界で一番美しい(女性として価値がある)のは私であるべきだ」というものかと思われます。それは自己愛が怒りと恐怖によって病的に肥大化して,意識下の潜勢力となったものです。人に認められるものは私には何もないというのが表の意識ですが,誰よりも高い価値を持っていると認められないのは不当だ,というのが裏の意識です。自律性と自由とを欠いている自我が描く理想的な自己像は,Mさんがたどった人生の軌跡の正確な再現でしかないのです。意識下の潜勢力が,傀儡化した自我を操って,そのように自分が果たせなかった(父親の)期待通りの人生コースを娘によって実現させようと企てたのです。それは娘の人格と人権とを無視した冷酷で,愚かしく,悲しいイメージ図に娘をはめ込もうとしたのです。
一般に自我の自律性と自由とが失われて,無意識の潜勢力の傀儡となっているときの特徴は,社会性と精神性の欠落です。
Mさんを助けたのは夫と娘だったでしょう。娘はMさんが躍起になって従属させようとしても,一向にへこたれない’能天気な’強さを持っていたようです。そしてその娘を夫が支えています。娘に対してあまり無理なことをすると,夫との関係にひびが入りかねません。夫に対しても理想化要求があるのですが,元は他人であるという事情のために父親に対してのような理想化には至ることはありません。頼りにしつつ現実的な距離があるので,Mさんの自我は夫との関係では自由になるのです。また思い通りにいかなかった娘に対しても,結局,一個の独立した人格として認めざるを得ませんでした。娘の自我を自分の自我の傀儡に仕立てようと躍起となったのですが,幸いにして娘は自由になりませんでした。結果的に娘に対しても,娘の助けによってMさんの自我は自由になることができたのです。
かつて妄想状態に直結した夢を見たころのMさんの自我は,このように自由ではありませんでした。
夢の世界で,誘拐された娘を捨てて家を出たのは,自由を求めるという意味があったと思われます。しかし夢が提示するMさんの自由とは,到底その名に値しないものでした。粗野で暴力的なカオスの中に身を投じる映像が,夢が提示したMさんの自由のイメージでした。それはMさんの自我が到底受け入れることができる代物ではありません。傀儡化したまま固化した自我には,自由を描く術がありません。自由という高度な精神性は,自我が自由であることと一対のものであるだろうからです。Mさんの自我が夫と娘とに助けられて,おもむろに自由を回復させていく過程で,Mさんの精神の自由が現実のものになるでしょう。そのときに夢が提示する自由のイメージは,まったく別種の,Mさんの目を開かせるプレゼントといったものになるのではないでしょうか。
中年の主婦であるNさんは,両親への依存心,攻撃心を強く内向させている人です。夫の両親である義父母は,Nさんを終始温かく見守っているようで,特に義母を頼りにしております。不安に駆られると,毎日でも義母に電話をしているようです。Nさんの話を聞いていて,義母の根気のよさには頭が下がる思いがします。そして義父母と絶えず比較して,実父母への怒りを抑えきれなくなるのです。
あるときに憑き物が落ちたように平静になり,一定期間,それが保たれます。
繰り返しうつ状態が訪れ,そして一定期間それが回復します。その過程で,統合失調症と区別がつかない状態になり,それが長期化するということも一度ならずありました。
彼女は,「すぐに治してほしい・・・」という姿勢を一貫して変えられません。心の治療は外科医のようにはいかない,本人が自分を助けるのを助けるのが,われわれ心の治療者の役目ですと,いくら説明しても,「先生のいうことは難しくて分からない」とうまく理解してもらえません。Nさんが望むのは,魔術的な治療なのです。実際,祈祷師を訪れたことがあったようです。
「こんなに辛い気持ちで長年通ってきているのに,いつまで経っても治らない,ここに来るのがいやになる」と焦る彼女は口癖のようにいいもします。実際,長年にわたり堂々巡りが繰り返されているので,何度か転医を勧めました。しかしそれに応じることもありません。
ようやく回復が確かなものとなったように見えたあるとき,「自分の力を信じるということがどういうことか,やっと分かりました。先生のおかげです」というのです。彼女は,「夫に,おれは精も根も尽き果てた,離婚したいといわれた,それがきっかけだった」と明るくいうのです。
「離婚のことはしょっちゅういわれていたが,どこか高を括っていた。しかし今度はヤバイと思った」といいます。つまり他の力を当てにしつづけてきたが,今度こそは自分が引き受ける以外にないと決意したというのです。
Nさんのこの他の力を当てにする基本性格は,心に潜む幼児性の影響を受けたもののように思われます。これはごく幼いころに,満足感を得られなかった何らかの心的状況があったことに起因していると予想されます。そのような小児心性は,乳児期の幻想的な全能感,全能要求に由来し,それらの約束を母親(父親も)が履行していないという怒りと不満とがあっただろうこと,しかしそれを上回る恐怖心が働いて,幼い自我がそれらを意識下に抑圧し,潜在させたまま成長したことによるのではないかと想像されます。母親(父親)への不満,怒りよりも恐怖感が優先するときに,幼い自我は親の自我に迎合して共犯関係に入るので,満たされなかった自然的な欲求が,怒りや不満と共に抑圧,排除されて心の裏舞台に追いやられることになります。
それらの全能幻想は乳児の自我に内属していると,仮定的に考えることができます。それは母親の胎内にあるときの充足性と,出生後の不充足性との落差を埋めるものです。
出産に伴ういま述べた落差は,’1000メートルの降下’と比喩的に考えてみると分かり易いように思います。つまり赤ん坊が生まれるときに経験するのは,まったくの充足である母親の胎内という洞窟から出るように促されて,1000メートルの高みに立たされるようなものではないかと想像されます。まともに落ちればショック死があるのみなので,それを回避するためには,現実を引き受け,直視する力が身に着くまでのあいだ,何らかの幻想的なクッションが不可欠であろうということです。その幻想は,十分な満足感と安心感とが与えられると約束された感覚であるように思われます。それは母親の胎内にあるときの充足感に匹敵するものを保証するものです。
満足感の追求は動物一般に認められる本能的な欲求(フロイトをはじめ精神分析的には欲求という言葉は使われず,欲動といわれることが多いようです。欲動の方がより身体的であり,欲求には精神的ニュアンスが込められているからかと思いますが,あまり厳密に言葉に捉われる意味はないようにも思われ,日常見慣れた欲求をここでは使います)ですが,人間の場合も同様です。人間が動物と違うのは,’自己満足’という言葉があるように,他者と共有できる満足,換言すると精神性と社会性とを携えた満足の追求がもとめられることです。それが自我の主要な仕事であり,かつ人生の主題であるといっても間違いではないでしょう。このように他者とのあいだで共有できる満足の追及が重要であることは,逆に他者によってその追求が困難にされるということでもあります。
他者は自我が仕事をしていく上での欠かせないパートナーです。しかし他者の介在を不可欠とすることが,自我が自分の仕事を遂行することを混乱させる要因です。
このことを敷衍すると,以下のように考えることができます。
生まれたばかりのときは,心の全体が自然のものです。自我の役目は,これら自然の心たちをいかに護っていくかということです。しかし一個の自我が独立して機能することは不可能なのが人間の現実で,自我が機能していく上で,他者の関わりを不可欠なものとしています。それは外部的な他者の助けを必要としているという以上に,自我の機構に他者および異性が内属していて,自己の無意識層に内なる他者または異性を構造的に含んでいると考えられます。そのために自己の内と外とで,他者または異性が呼応し合える関係にあります。そして一方で外なる他者は,自己と異なる存在であり,いわば何を考えているのか計り知れない存在でもあります。ですから他者はいかに善意の持ち主であっても別個の存在であり,当人の自我が自己のために最善を尽くすような意味では,当人のために他者が最善を尽くすのは不可能です。自己の内と外の他者の呼応性というかぎりで,他者は頼りになりますが,外なる他者が不可知であるかぎり,時によっては悪意の他者でもあり得ることになります。そのような他者の意向を受けて,とりわけ幼い自我は葛藤し,混乱するのを避けることはできません。つまり自我が自分の内部の自然な心たちを自然のものとして護り切ることは不可能です。
以上のような事情から,自我は心の自然な欲求を護ることができたときには,いわば白い子を生み出し,護り切れなかったときには,いわば黒い子を生み出します。黒い子を生み出すのは,自我の不始末ということになります。
このあたりのことを以下の例によって見てみます。
ある家にぶどう棚があるとします。秋になると美味しいぶどうがなります。その家の幼い子(A)が友達を連れてきてぶどうをご馳走します。Aは友達に満足を与え,自分も満足します。それが得意でもあります。ところがあるとき母親に見つかり,叱られます。Aは友達の前で叱られて恥をかき,自分の威厳が下がったような気がします。
母親に見つかる前は,Aは美味しいぶどうを友達と分かち合う楽しみを味わいます。そのとき一人で食べるよりも,更に大きな満足を得られたに違いありません。Aはその場の主人公であり,ぶどうという満足をもたらす力を自分のものとしています。この場合Aは小さな権力者です。ところが母親に見つかってしまえば,ぶどうの本当の持ち主は自分ではないことが暴露されてしまいました。権力者の座から失墜したのです。このときからAは少々元気がなくなりました。
母親の関与がある前は,Aは美味しいぶどうを友達と分かち合う満足を得ました。ここには社会性を帯びた白い満足を,幼い自我が引き出した意味があります。しかし母親の関与により,本来は自分のものではないものを自分のものとしたことが暴露されました。そのとたんにAがしたことは,社会性を失い,黒い満足になってしまいました。
Aの自我が試みた仕事は,美味しいぶどうを仲間と食べたいというかぎりで,自然な欲求を充足しようとしたことです。しかし人間社会の掟では,他者(ここでは母親)への配慮を抜きにすることは許されないという理由で,Aは心を護ることに失敗したのです。
これが自我が単独で機能することができないという具体的な例です。そして敢えてそれを試みると,未熟な自我という汚点を残すことになります。つまり自我が社会性を帯びた成熟性を発揮するためには,他者の関与を踏まえないわけにはいかないのですが,それは自然の心の欲求との激突を避けられないものでもあります。
それではAはどうすればよいのでしょうか?
Aのテーマはぶどうを仲間に振る舞い,喜んでもらいたいということです。そしてそれとは別の意図が入っていた可能性があります。Aは功を焦るあまり,自分のものではないものを自分のものであるように振る舞ってしまったように見えます。Aの目論見は,「自分の力によって仲間たちと共に満足することを演出する」ということのようです。Aは自分の力を示したい,人に認めさせたいと,少々権力的になってしまっているようです。Aが内心で望んでいるのは,母親にもっと認められるべきだという不満足の解消だったかもしれません。「ぶどうを好きなように食べていいよ,ぶどうはAのものだよ」,と母親にいってもらいたかったのかもしれません。その心はもっと幼いころに母親に十分に甘え,自分が愛される価値があることを母親に認めて欲しかったという不充足感に発したのかもしれません。母親に十分に甘えることは,その後のあらゆる満足感の源泉であり,基礎になることのように思われます。Aはそういう意味で母親に不満があり,ぶどうは僕の物だという隠れた意識を持っていたかもしれません。そうであればぶどうを仲間に振舞ったのは,母親への挑戦であったという面を持つことになります。Aは母親に叱られ,ぶどうはAの物ではないといわれました。権力者の座を目指したAの面目は丸つぶれです。Aは口惜しい思いをし,腹を立てたことでしょう。
このように見てみると,Aはこれでよかったのだということもできます。何故ならAは,自分の分身である母親に甘えたい心を見捨てなかった(抑圧しなかった)からです。幼い時代に甘えたい心が満たされなかった不満をいだき,改めてその不満の表明と解消とをもとめる心が,仲間とぶどうを食べるという行動の隠れた意味ではなかったかと考えることが可能です。そして再びその目論見を母なる他者によって封じられたことは,自我の不始末ということになります。しかし自我は常に即座に成功を収めることは無理であり,必要でもありません。いつか成功を収める機会を得ればよいのです。怒りと共に心に内在している満たされなかった甘える心が自我を圧迫し,苦しめるでしょうが,それを持ちこたえる強さが自我にあれば,いまは負であるそのエネルギーは,機が満ちたときに一気に自我の仕事を支える正のエネルギーに変換されるのです。そのときに意識の下部で自我に圧力をかけて催促していた欲求が,自我によって満たされることになります。母親によって失墜させられたAの野心は,その後のAの人生への取り組み方しだいによって,むしろ使えるエネルギーなのです。大きな負荷をかけられて撓んだバネが,あるとき一気に反撥するように。
以上のように,自我の目論見が他者によって退けられたときに,自我は無意識からの圧力を受けることになります。自我はその圧力に耐えなければなりませんが,耐え難く傀儡化する自我と耐える自我との差は小さくありません。無意識の力の傀儡となった自我は,未熟で社会性を欠いた思考や行動になることが避けられません。耐える力を維持することができる自我は,次の機会に備える能力を温存しているといえます。
いまの例でいえば,幼い自我が母親をおそれて甘えたい心を満たせなかったとき,自我は二つのものに捕捉される,あるいは傀儡化されてしまう可能性があります。一つは母親で,一つは無意識の世界に抑圧,排除した分身たちです。母親をおそれて取り入る自我は,いわば傀儡自我であり,主体的,自立的であることをあきらめています。傀儡自我の下では,自然のものである心の諸欲求(白い子)を護りとおすことは困難で,引き受けを拒んで無意識の世界に抑圧,排除することになりがちです。自我が護ってあげられなかった無垢の欲求は,自我によって死の宣告を受けたのに等しいことになります。言葉を換えれば,白い子を黒い子にしてしまったことになります。黒い子を作り出したのは自我の不始末ということになり,黒い子たちをおびただしく作り出してしまった自我の下では,自ずから不甲斐ない,自分は駄目な人間だという思いにかられがちになると思います。そして黒い子たちが強力化すると,自我はそれらの勢力に捕捉されて,再び主体性と自立性を放棄するしかなくなります。このような事情にある自我の下では,Aのように仲間を集めてぶどうを食べるよりは,人目を盗んで一人で食べることになるでしょう。
人に認められる,愛される,信頼される,受け入れられる等々のことは,他者との関係での要点ですが,その原型となるのは(主に母親によって)甘えが十分に満たされることではないかと思われます。精神の未発達な赤ん坊が母親との関係を通して得られる満足感は,身体的なものです。甘えることの原型は,抱かれる,愛撫されるなどの身体的な接触を通じた満足感です。それへの欲求は身体的なものであるだけに,強いエネルギーを秘めたものであるといえるでしょう。そういうことが基礎になり,長じて愛される,信頼される,認められる,受け入れられる等々の,より精神性の高い満足をもとめることになります。
甘えることの原型は,身体的な満足感(フロイトの快感原則)をAがBに求め,Bがそれを満たしてあげるという関係で成立します。それが本能的なものである証拠の一つに,動物も人に甘えることを上げることができます。
動物の場合は,心地よさを人に求め,満たしてもらうという身体的な次元での満足に留まっているように見えます。しかし動物の側で人を信じることがなければ,甘えることはありません。人間の側でも噛まれるなどの怖れを持たないので甘えを受け入れることができます。人は動物を可愛いと感じ,もしかすると可愛がられているという感じが動物の側にもあるかもしれません。このように人と動物とのあいだでも信頼とか愛とかの精神性の萌芽があるように思われます。
母親と赤ん坊の場合も,甘えの原型としては本能レベルで赤ん坊が身体的な接触を求め,母親も半ば本能的に赤ん坊の身体を抱き,愛撫します。両者はその身体的な触れ合いの満足感に没頭します。イギリスの精神分析医であるW・ウイニコットは,このことをマターナル・プレオキュペーションと呼んでいます。この両者の関係で,母親の助けの下に赤ん坊は甘えを満たすことができます。すべての満足感の基礎と思われる甘える満足は,母子の特別な二者関係において成立し,そこには両者のあいだに,身体的な強い満足感と信頼と愛情という精神的な強い満足感とが体験され,それは母子共々に至福のときではないかと思われます。動物も人に甘えることがあるようですが,赤ん坊が動物と決定的に異なるのは,自我に拠るものとそうでないものとの違いです。赤ん坊の甘えも,生まれて間もないころは動物と同じように身体的なレベルに限局したものです。それが自我の機能の発達に伴い,徐々に精神的な様相を深めていきます。そのことは甘えを求め,それを受け入れられ,満たされるという受身的に見える満足追求の行動が,実は主体的なものであるという意味につながっていくことでもあります。母親によって身体的に心地よい満足感を与えられることが,実は赤ん坊の心の親ともいえる幼い自我が,母親の協力を取りつけることに成功し,自分で心の子である甘えを求める欲求を満たすことができたといえるのが重要であるように思われます。つまり満足感を得たのは,赤ん坊自身の自我によってであるという意味が大切であると思います。母親は欠かすことが出来ない重要な役割を果たしていますが,赤ん坊の甘えるという満足感を獲得する主体者ではなく協力者に過ぎないのです。つまり赤ん坊が母親に十分に甘えることができたということは,人間の満足感の追求が身体レベルにとどまらず,精神的な満足への広がりをみせ,それは他者との関係での満足感と密接不可分であり,将来,一切の満足感を得る上での基礎になります。
赤ん坊が甘える満足を満たされたとき,母親によって自分が価値ある者,大切な者等々として受け止められているという満足感を諸共に経験することになります。そのとき両者のあいだには,信頼と愛情が共有されています。
赤ん坊が母親から信頼され,愛されているのを体得するのは大変重要なことですが,それは幼い自我が甘えるという満足感を自分の力で得る上で欠かせないことであったからともいえます。この重要な心の作業を(母親が)理解し,協力してくれたのは,信頼と愛情とによってであるに違いないからです。仮に母親にネグレクトされるなどのことがあれば,赤ん坊は恐怖と不満足感とで恐慌状態に陥るでしょう。何よりも母親の助けを得られないと甘える欲求を満たす術がありません。ここには愛情と信頼との欠落があります。最も頼りとする母親から何がしか見捨てられた体験を持つと,その後の人間関係に強い影響を与えます。自分は人に受け入れられないかもしれないという怯えが生じやすく,自我は心の子であるさまざまな欲求を無意識的に,自動的に抑圧することになるでしょう。当然それは性格形成の上で大きな問題を残すことになります。
心の親である赤ん坊が,心の子であり,自然のものである甘えたい欲求(白い子)を満たすことができれば,白い子を白い子として護り通すことができたことになります。そして母親の協力が得られず,甘えるのを断念したとすれば,幼い自我は白い子を護れず,意識の裏舞台に追いやったことになります。自我は心の子である甘えを求める欲求を護ることができず,いわば死の宣告を与え,黒い子にしてしまったことになります。
母親に愛されていない(幼い心は,きょうだいたちの中で,第一等の愛を要求します。それが得られていないと感じると,愛されていないのに等しい感じを抱くのです)と感じる子は,甘えを満たすことが更に難しくなるでしょう。それは母親への不信感に直結するでしょうし,一般に対人不信に陥る十分な理由になります。愛されていないと感じている子の一番の問題は,対人不信に陥りがちであるために,自我が甘えを満たす術を失うところにあります。それは自我が不始末を繰り返す意味を持つ上に,自分が愛され,信頼される価値がなく,人に認められない駄目な人間であるのを絶えず確認していくことにもなり,心が転落していく理由になります。
幼い時代に甘える欲求が満たされる体験をしていれば,自我は白い子を護ってきたという自負心を持つことができているので,後々,対人的にストレスに見舞われても回復は速やかでしょうが,甘える満足に欠けるものがあれば,次々と黒い子を生み出してしまう悪循環に陥ることになるかもしれません。
このように人間も含めて動物一般の基本的な欲求は満足感の追求です。動物と異なって人間は,本能的,身体的なものの他に精神的な満足の追求が欠かせません。動物体としての人間が,動物としていわば地に根を張った存在でありつづける上で,肉体的,本能的な満足への欲求は強力である必要があり,事実そのとおりです。そして一方では,成長するにつれ精神的な満足の追求が不可欠の要請になっていきます。身体性と精神性とのあいだでの相克,葛藤は,とりわけ思春期にあって甚だしく,しばしば内的に深刻な問題になります。
いずれにしても自我の役割は,身体的,本能的欲求と精神的な満足との相克に悩まされながらも,身体的な満足からしだいに精神的な満足へと比重を変えていくところにあるでしょう。
自我は満足感の追求の履行者の立場にあります。何であれ行為するときは自我が方針を決め,欲求の協力を促します。両者の協力関係の下に意志が確かめられます。意志の根底には欲求があり,何かを始めようとするとき,自我は自動的に欲求に呼びかけると考えることができます。欲求はその都度新たに生まれるものです。そういうふうに考えると,いわば心の親である自我が,子供である欲求を大切に護っていくことが重要です。邪念に駆られていったん始めようとしたことを中断するようなことになれば,欲求の立場からすると,要請されたり不要とされたり,いわば迷惑な話になります。このような頼りない自我の下では,自我自身が自信を失くしているでしょうし,気まぐれにもなるでしょう。欲求もまた,容易には生じにくい状況といえ,要するに無気力になっていきます。
ソクラテスは,身体の心配をするよりは魂の世話をすることが肝心だといっています。また愛知の精神を尊ぶ彼にとって,哲学は人間の仕事の最上位にあるものですが,「我々は日夜死ぬための練習のために哲学をしているようなものだ・・・」といっています。また,「人間は囲いの中に囲われているようなもので,当然,囲いの番人はいる。人間の究極の目標は身体を去ることで囲いを超えることだが,囲いの中で勝手に死ぬようなことは,番人にとっては許し難いことだろう・・・」といいます。
この考えに組するかどうかはともかく,人間の存在様態を端的に捉えている一つの典型といえるのではないでしょうか。
そのことを煎じ詰めると次のようになるかと思います。
人間が生まれたときは,満足感の源泉は身体的なものにある。しだいに成長するにつれて精神的なものに比重が移り,身体と精神との満足追求の対立が激しくなっていく。自我がうまく成長するときには,この対立を止揚して新たな統合を達成していくことができる。見方を換えると,対立に伴う強いエネルギーに一定の意味のある方向性を与えることに成功する。そして最終局面に達して死を向かえるときに,身体が滅び精神のみの存在となる。それはソクラテスのいう囲いを越えることであるが,囲いの向こうに何があるのかは,人間の窺い知れない問題である。
精神的に満たされることが人間の場合は決定的に重要ですが,身体性の裏づけを欠いた精神性というものはありません。身体的に満たされる体験を,乳幼児期にしているかどうかは重要です。自我の未発達な赤ん坊の安心と満足とは,母親とのボデイコンタクトを通じて得られます。それに従って,愛されるという精神的な満足を受動的に経験します。愛されるに値する自分とは,まずは身体的に満たしてもらうという経験に由来します。そういうことを経験して,自我の機能が発達していきます。
以上のような意味で自我が健全な発達をしていないと,過食症やアルコール症のような黒い満足の追求に向かうことになるかもしれません。心の病的な現象は,大多数が幼いころに満たされなかった心に由来しており,それは同時に身体を通じて愛された体験が希薄であることを意味しているように見えます。
過食症は,満たされない心を代理的に食べ物で満たそうとする病的心理現象です。これは乳幼児期に甘えが満たされなかったことに関係があるようです。幼い自我が母親との関係で何らかの恐怖心を抱き,甘える心を護れなかったことに起因すると思われます。この幼児心性がことごとく過食に向うというものではありませんが,自我によって抑圧された甘える欲求は,いわば見捨てられて死の宣告を受けたことになります。自我に護られることで心の表舞台に乗せられ,精神性と社会性とを備えることになります(白い子)が,護られなかった欲求は心の裏舞台に退けられて(黒い子),精神性と社会性とに無縁となります。怒りのエネルギーを蓄えている黒い子が一定以上の勢力になると,自我を捕捉し傀儡化するようにもなります。何らかの満足を求めないわけにはいかないのが人間であり,そういう心の状況では黒い満足の追求になります。それが食物に向うとき,黒い満足は小児心性ということでもあり,虚しい心を埋めるために怒りを込めて貪り食うことになります。黒い満足としての食事は,自我の関与を欠き,精神性と社会性とを欠いているので,いくら食べても虚しいのです。また拒食症者にとっては,食べずにやせることが満足の一切です。身体性を否定し,精神性だけの存在になろうとしているように見えます。それは幼いころに身体を通じて満たされる体験が希薄だったことの,過食とは違った一つの表現です。食べ物を貪るのは身体への固執であり,食べ物を拒否するのは身体性の拒否ということになります。両者は両極に分かれていますが,共通するのは幼い時代に心が不十分にしか満たされなかったこと,恐らくは甘える満足が十分に満たされなかったことが主因となって,心の成長過程にあっても内心の空虚さが満たされないままでいたのです。過食症者は,太っていることをとても恥じます。それは精神性を欠いているが故の食行動の結果だからでしょうし,激しいエネルギーの黒い子の下で無力だった自我が,我に返って,情けなさに打ちひしがれている姿でもあるのでしょう。また骸骨のようにやせ細っても,ある意味では恥じない拒食症者は,身体性を拒否することに精神性を見出そうとしているように見えます。いずれにしてもそれらは心の裏舞台にある黒い子たちが求める満足で,生きる方向での行動ではなく,死の方向での行動なのです。ですから常識的な意見は通用しません。
ある女性は次のように述べております。「健康な心が健康な身体を望むというのは分かる。私の中にもそれがなかったとはいえない。しかしずっと以前から私にとっての美とは,死に化粧だった。グロテスクといわれると思うが,そのようなメイクをし,痩せこけるのが私のもとめる本来の美だった。そこには悪魔がいて,私を誘っていた・・・」
人の不幸を喜ぶ心も黒い満足です。犯罪も然りです。黒い満足を演出する究極には,影の帝王ともいえる死があるといえるでしょう。その手先が先の女性が述べているような悪魔の誘惑といったものです。死は恐るべきものである一方で,魅惑するものでもあります。
ちなみに人間の誕生は,O.ランクが出産外傷と表現し,後々の不安反応の原型となるといっています。
人間が生まれるということは,無限定なものから限定されたものへの移行であると考えられます。それは母親の胎内以前のものから,以後のものに移行するというのとおなじ意味です。生きることは限定されているということ,つまり’囲いの中’に限定されて満足を享受する自由が与えられているといえます。その生の享受は,限定されているが故の不安を排除できません。囲いの中が生の世界であれば,外は死の世界に違いありません。
無限定なものから生という限定されたものへ移行し,再び無限定なものへと移行する宿命の下にあることの無意味感は,我々にとって厄介過ぎる問題ですが,それは,所詮,生という囲いの中のもののボヤキに過ぎません。ソクラテスのように,人知を超えたものの意志に対してひたすら服従する精神があれば,ボヤク無意味から一転して,謙遜の精神を手に入れることになるように思われます。謙遜の精神とは,引き受ける精神と表裏一体の関係にあるものです。
母親の胎内から出て,そこへと回帰するというふうにも取れる人生の道筋を,人間的に生きる主要な手がかりが満足感の追求ではないでしょうか。いわば全の世界からこの世という限定の世界へと突き落とされて,全に匹敵する満足感を飽きることなく追求することをやめるわけにいかない人間は,どこか蟻に似ていなくもありません。満足感の追求が不首尾に終われば,たちまち生の世界に翳りが生じます。生は自我による光の世界であり,光の源泉は有限の彼方である全であろうかと思われます。そして翳りは無であるものといえるだろう死の気配です。それら全と無とは無意識の世界にいわば存在し,自我に光と影をもたらすようです。自我が上首尾に自己を導きとおすことができれば,限りなく全に向けて飛翔するようであり(ソクラテスのいう囲いを越えること),自我が不始末の悪循環に陥れば光の世界にあって翳りの色を強めることになるのでしょう。
とりわけ生まれて間もない赤ん坊は,全を要求します。母親の胎内にあって,人間となるどんな修行を積んできたのか知る術もありませんが,限定された世界であるが故に死を含み持つ生を,赤ん坊単独の力で引き受けることはできません。幸か不幸か,母親は赤ん坊の絶大な期待に応える義務を帯びた立場にあります。母親に誰がそのような義務を負わせたのか,母親自身が不満を持つことも可能な状況です。母親はソクラテス流の引き受ける精神が要求されています。であればこそ,母性豊かな母親は祝福された人といえるのでしょう。
母親の大きな役割は,全を要求してやまない赤ん坊に,生きる上での欠かせない知恵である,この世の限定のことを身をもって教えることです。つまり,ほどほどの満足が人間の分というものであることを分からせるのが,母親にできる最上の愛情です。この大仕事を委ねられた母親の名誉は,どんなに頑張っても,全を求めてやまない赤ん坊によって悪魔の烙印を押される不名誉に転落する怖れを内に持っています。赤ん坊が全を求めてやまないのは,この世のものになったがために,宿命として死を垣間見ることが避けられないからです。その恐怖は,全を提供してくれるはずの母親と一体のものとして映じるでしょう。つまり母親は,赤ん坊にとって,死をもたらす存在でもあり得ることが不可避なのです。この母親の全と無のイメージが,大母と魔女とに他ならないといえるでしょう。
そのようにして,全ならざる人間は,飽きることなく,蟻のように満足を求めて生きつづける宿命の下にあります。
しかしいずれにしても赤ん坊の心は,全の世界から全ならざる世界へ移行していくのでなければなりません。言葉を換えれば幻想的世界から,現実的,客観的世界に移行していかなければなりません。
以上のような事情の下で,生まれたばかりの赤ん坊が母親から心理的に分離して,独自の個として生きていく上での拠り所となる自我の機能が,ひとまずは確保される(3歳ごろ)までのあいだは,いわば’1000メートルの下降’が穏やかに果たされる必要があります。この危険な下降,着地が理想的に穏やかに果たされたとしても,人間は絶対的な受身として存在が開始されたという事実は否定できません。つまり危険を賭して’1000メートルの下降’を強いられるということの意味は不明であり,絶対的な不条理を生きる宿命の下にあります。この不条理性を余儀ないものとする人間は,光のものであり,意味を紡ぎ出すものである自我によって存在可能となるのですが,それは同時に,人間の心は自我による光がおよび得ない闇と無意味の領域とを併せ持つことになります。かつまたこの闇の領域は,自我の価値規範によって否定され,隔絶,排除された意味を持つ領域と,自我が拠り所とする領域とを併せ持つものです。
自我に拠る光の領域を白の世界とすると,自我の価値規範によって否定された領域は黒の世界ということになります。そして白の世界の帝王は前章で述べた内在する主体ということになると考えられます。一方黒の世界の帝王は,死であると考えられます。しかしながらこのように両極に分離して現象を捉えるのは,自我の機能の宿命的特性です。白と黒のそれぞれの主体そのものは全であり,かつ無であるといったものであるだろうと考えられます。そしてその一者の観点からは,白と黒との分離はなく,白でもなく黒でもなく,あるいは白であり同時に黒であるといったことになるのではないでしょうか。
いずれにせよ,自我に拠る人間の理解がおよぶのは,主観と客観の総合である現象的世界にかぎられます。それは「意識という光が及ぶ限りの世界」と同義であり,つまりいうまでもないことですが有限の世界です。そのことは必然的に意識の光が及び得ない「無限界が存在する」ことを含んでいます。いうならば「無限の世界」は現象的世界とおなじように,「その存在}は明証的で,疑いようがありません。
自我は意識に拠る現象的世界の中心にあり,その世界を司っています。しかし自我が存在するにいたった理由は,自我の能力を超えています。そのことは一見すると合理的理解が不可能であるということになりそうですが,しかし自我が存在する理由はいま述べたように明証的です。そのことを結論的に言い表せば,次のようになるかと思います。
人間にとって明証的なのは意識が捉えるかぎりの世界(現象的世界)についてである。意識は自我に拠るものである。しかし自我自身の存在理由を自我は知らない。それは自我が一切の最上位にあるものではないことと同義である。つまり自我の上位にあるものに拠って自我が存在するにいたったことは疑いようがない。その上位にあるものを,現象界にあるものとおなじような意味で実体的に理解することは不可能であるが,それと名指しできないにせよその存在自体は疑いようがない。現象とは意識がそれと指し示すものの存在のことであり,その意識の連鎖を認証することが合理性ということである。このように,自我の存在理由となったものの存在を認めることは合理的である。
自我の上位にあるものは原則的に無限界に属するものです。ですから具体的に現象的実体として捉えることは不可能で,自我の能力を超えた問題です。「それは存在する,しかしどのような様態で存在するかは知り得ない」ということになります。
個々の自己が自分にも知り尽くせない自己であるのは,改めていうまでもないことです。それは自己が自我に拠りつつ,自我を超えたものの存在(「無限界に属する存在」ということになります)にも拠っていることを,明証的に示しています。そのことを敢えて考慮する必要があるのは,精神科の診療で心の問題を考えるときです。人間が絶えざる可能態として存在していることは,希望の源泉を確認することになるからです。自我の上位にあるものの存在様態は,現象的実体として捉えることはできないのですが,だからといって煙のごときもののように漠然としたままでいるのでは説得性が希薄です。それをともかくも措定する必要があります。それはどうしても擬似有限態として仮説的に措定するしか手がありません。
そのような試みは,心の治療の体験から自ずから導き出され,その有用性を診療の上で訂正されつつ確かめられることで容認され,意味を持つだろうと思います。
自我の存在と存在様態の問題は,生と死という人間の最も根源的なものと直接関わるものです。この問題を不問にして人間の心の問題を考えることは不可能です。
生は自我の誕生と共にあり,死は自我の終焉と共にあります。自我の存在以前には生も死もありません。つまり生と死とは,有限と無限の問題でもあります。
それにしても死とは何でしょうか?現象としては物化した屍体がそこにあります。それは死の動かし難い事実の一面です。しかしそれが死でしょうか?精神は,魂はどうなったのでしょうか。
死によって我々の前で明らかなのは,物化した身体ばかりです。精神は煙のように消えてしまい,それがそもそもどこに帰属するものなのか,手がかりがありません。生きているあいだは身体と精神とは一体のものであり,精神の活動は身体性と切り離すことができません。
人間の一生をたどれば,幼いころは身体に傾き,年をとるにつれ精神に傾くのが理想のようでもあります。生涯に3度結婚したソクラテスは,60歳を過ぎて再婚し,子供をもうけました。そして幼い子を残し,その気があれば免れることができた死刑を甘受して死を選びました。そのソクラテスは,身体に固執する愚を説き,魂を磨くことを説いています。
身体は成熟のピークを向えた後は,時間を経るにつれて衰えていきます。最後に物化して死を向えます。滅び行く伴侶と共にある精神は,共に滅びるのか,遊離するのか不明です。ソクラテスは,哲学は死の練習だといいます。哲学する精神は,滅び行く身体を慮り,自分自身の行く末を慮るという意味かも知れません。
死は精神の所在を謎に包みます。差し当たりは無に帰したというしかありません。身体もまた物化して残りますが,やがては腐敗して無に帰します。いずれにしても死によって人間は無に帰するので,ここでも厳然と「有限態であったもの」と「無の存在」とが明らかになっているようです。
自我が自我以上のものによって存在可能となったと考えるしかないのとおなじ理由で,死によって無に帰した精神は,そもそも「無の世界のもの」であると考えるのは可能であるように思います。有限態である自我の観点から,有限の彼方にあるのは無限に違いありませんが,無限即ち全は無と区別がつきません。
自我至上主義は虚無の精神に他なりません。それは死は本人の自由に扱ってよいものかという問いに対して,いうまでもなく本人の自由であるという結論を導きます。またそれは,謙遜である根本理由を欠くことになるので,ドストエフスキィーの「罪と罰」の主人公が考えたように,場合によっては他殺も許されることになります。更に自然破壊,環境破壊など人類の危機をもたらしているのもおなじ理由によります。
自我の機能は,第一に自由で自立的な自我,第二に社会的な自我,第三に非社会的な自我と,便宜的に三つの階層に分けて考えることができます。そして存在するものは必ず滅びます。自我の機能もまた崩壊する可能性を秘め,実際に崩壊します。その様態が統合失調症と呼ばれているものです。です。
自由で自立的な自我が保たれていれば,病的な心理に陥ることはないといえます。芸術家や研究者など,創造的な仕事に携わる人,あるいは人間の身体能力の限界に挑戦する才能のあるスポーツマンなどは,このレベルが最も望ましく機能している必要があります。このレベルでは内在する主体との関係が良好に保たれていると考えられます。何にせよ行為するためには意志が働きます。意志というのは,心の親である自我が働きかけ,それに即応する欲求が心の子として生まれ出て,両者が協働することで形作られます。自由な自我の機能のレベルにあっては,自我とそれに即応する欲求とがいわば阿吽の呼吸の関係にあり,同時にそれは内在する主体との関係も良好に保たれていると考えることができると思います。
この機能レベルは,下位レベルにある社会的自我機能を,監視し調整する役目があります。ですからこのレベルがそれなりに活発でなければ,考えが窮屈で,融通の利かない人ということになります。
第二の社会的な自我機能は社会的な存在である人間が是非とも身につけていなければならないものです。
第二のレベルを保つことができなくなったときに,第三の非社会的機能のレベルに後退します。このレベルでは自我は無意識の黒い分身たちに対して優位の立場を保てず,それらに支配されることになります。この場合,何らかの心身の不調は避けられません。
第四に自我が崩壊した場合,決定的な異常心理である統合失調症の世界に陥ります。このレベルには機能的なものと器質的なものがあります。器質的なものでは,人格の何らかの欠損状態が永続的なものとなります。
例として上げたMさん,Nさんに即していえば,自我の自由な機能は活発ではなく,第二と第三の階層を行き来していると考えることができます。そしてあるときに自我の機能的崩壊が一時的に起こったと考えられるます。
自我の自由で自律的な機能が失われて,固化した状態が長期にわたっていたことが第一に問題になると思いますが,二つの例に共通していて,しかし対照的なのは怒りの存在です。Mさんの場合は怒りの所在についてはむしろ無意識です。その存在は子供に対する支配的態度から容易にうかがえるのですが,Mさんにはそういう自覚もありません。それを明確化,直面化させようとしても,するりと交わされてしまいます。仮に無理にそれを迫るとすると,激しい怒りが噴出する怖れがあります。治療関係の破綻はもとより,自我の崩壊をもたらす怖れもあります。Nさんの場合は,逆に絶えず怒りが意識に上り,Nさんを苦しめます。
両者ともに怒りのエネルギーが大きいと考えられますが,怒りは自我が本来の機能を果たしているときには問題になることはありません。怒りの布置は自我の機能が弱体化している証拠なのです。それは分別のある人の怒りも同様です。思わず怒りを顕わにして,周囲の者にもその理由が十分に分かるとしても,自我がうまく機能しない隙をついて怒りが顕わになったのです。いかなる場合でも決して怒りを表さない人格円満な人は,自我の機能が常に安定しているのでしょう。
Mさんの自我は怒りを強く抑圧しているために,無意識からの圧力にひたすら耐えることで精一杯のように見えます。Nさんの自我は怒りを含む影の分身たち(黒い子)に取り囲まれ,支配されているように見えます。両者に共通しているのは,それぞれの自我が自立性と自由とに欠け,引き受ける能力を失っていることです。
無意識界に大きな勢力となっていたと思われる負の分身たちによって,Mさんの自我は固化され傀儡化されていたと考えられますが,Mさんが急性精神病状態に陥ったとき,潜勢力のエネルギーがついに自我の耐用力を凌駕して崩壊させたと思われます。このとき崩壊しつつも,自我は二つの対案を示しているように見えます。一つは置かれている客観的な状況から逃れて自由になること,もう一つは義弟は実は学歴を詐称していて留学はしていないと合理化することです。両者共に自我が無意識の力をある意味で利用しているともいえます。
しかし崩壊に瀕している自我には,現状況を再建的に克服する力を示すことはできず,非現実的で,機能を失っていることが明らかになるばかりであることに変わりはありません。
自我が機能を発揮するとき,生の方向にエネルギーが動きます。何らかの活力のある現実策が展開されるのです。そして機能を発揮できないとき,死の方向にエネルギーが動きます。Mさんの場合は,悪夢となって表れたように,暴力と無秩序のカオスの世界に突き進むしかなく,あるいは実の妹にあらぬ疑いをかけることにより,姉妹の関係を破壊するしかなく,それらはいずれもMさんを自滅の方向に向かわせるものです。
Nさんについてはどうでしょうか?
Nさんの生活状況は,むしろ恵まれたものです。夫と小学生の子供との3人家族ですが,夫は特に不理解でもなく,自分本位ということもないようです。何かと不調を訴える妻を,夫は病気というよりは性格の問題とみていたようで,突き放すような態度があったようですが,Nさんが精神病状態に陥った時には,よく世話を焼いてくれています。会社員としては高収入ではないかと思われ,経済問題もありません。さきほども述べたように,夫の母親はNさんをよく助け,嫁姑問題については大変恵まれています。
Nさんは一日の家事の手順に,強いこだわりがます。そのために絶えず時間に追われ焦っています。掃除,洗濯,買い物など,すべて決められた時間に済ませたいのです。夕食を作る時間,子供を入浴させる時間,食事させる時間,寝かせる時間なども然りです。そこへ夫から電話が入り,迎えの車を頼まれたりすると,それらが乱されることになります。夫はゴルフ好きで,休日には出かけることが多いのは仕方がないとしても,車を持っていかれるのが不便です。そういうことでも小競り合いが絶えず,日常的に波風が立っているのは確かです。それらのことは家族関係に起因するというよりは,Nさんの性格的特性に端を発しているといわなければならないようです。言葉を換えると,会社の仕事がある夫にもストレスの解消策が必要でしょうし,もっと奥さんの身にもなってと要求するとすれば,夫のストレスが更に高くなる危険があります。
Nさんによれば,夫は,「お前のは病気でないよ・・・」としばしばいっているようです。それは言外で性格の問題だといっているのでしょう。それに間違いはないのです。Nさんが性格を変えて行くつもりにならなければ,繰り返されている発病に歯止めをかけられません。
先にも述べたように,Nさんの治療者への姿勢は,「治してください」というものです。これは他を当てにする以上に,問題の一切を外部に預けることになります。これは外科医の治療を求めるのとおなじです。心の問題は,どんな医者であれ,「外側から治す」のは不可能です。Nさんの心の問題はNさんにしか分かり得ないのは,いうまでもないことです。そのことをどうしても理解できないNさんの心は,それ自体がどこか病的といってよいでしょう。心の病気の治療には,{頭が良い」ことが決定力を握っていますが,それは知能の良し悪しの問題ではありません。
Nさんが取るべき望ましい姿勢は,「これは私が引き受けるべき問題ですが,どう考えていけばよいのか見当がつきません。このことに治療者として協力してもらえますか?」といったことです。このような心の姿勢になれることが,心理治療の上では「頭がいい」ということになります。やはり問題は引き受ける精神に行き着きます。一般に,引き受ける精神になれる人が,「頭がいい」と言い換えても間違いではないでしょう。
この意味では残念ながらNさんは,心が硬かった,固化した自我の下にあった,といえます。
Nさんの自我を固化させていた主役は怒りです。Mさんの場合も同様ですが,Mさんの自我は怒りをひたすら封じ込め,表面では,「親に逆らわない良い子」というのが意識の構えです。自我が影の分身たちを引き受ける気配を見せないので,影のものたちからすると救いがありません。それで影の者たちの怒りのエネルギーは無視し難いものになってたと思われ,自我は必然的にその圧力を受けつづけています。そしてそのエネルギーのはけ口が娘に向かったことになったのです。怒りを込めた黒い分身たちを引き受ける気のない自我は,娘に問題を転嫁しようとしました。仮にそれが上首尾に運んだとすると,得られたのは黒い満足ということになります。そして娘はその犠牲者に供されることになります。
NさんはMさんとは逆に,怒りを両親に向けつづけました。義母に模範的な良い母親像を見出した一方では,まるで義母が焚きつけたかのように実の母親(父親にも)への怒りが収まりません。Nさんの自我が引き受ける精神を機能させていれば,事情は変わっていたでしょう。そのときには義母の優しさによって得られる満足は,自我が獲得した白い満足ということになるのです。ところが自我が引き受ける意志を持てないままでの義母の優しさは,Nさんの実の親への怒りを助長させることになりました。その黒い分身たちの怒りは,Nさんの自我が黒い分身たちを生み出した原状況である幼い時代の親子関係に問題が持ち込まれ,実父母への怒り,攻撃がとどまることがないのです。
Nさんの固化した自我は,日常の問題に対応できずに機能的崩壊(精神病の発病)を何度か来たしました。その度に夫の優しさ,頼もしさを経験しました。結果的にそれは夫を試すことになりました。うがち過ぎかもしれませんが,発病は,自我が夫の力を図る無意図的意図の一面もなくはなかったかもしれません。何度も離婚問題が取りざたされながら高を括っていたといい,しかし,「今度はヤバイと思った」と笑顔交じりでいうNさんの様子から,そういう印象も持つのです。自我が,「今こそ引き受ける気にならなければ離婚はあり得る」と踏んだともいえ,それが,自我が自律性と自由とを回復させるきっかけになったと思われるのです。それはMさんの自我が,動かし難い夫と娘の独立性によって,(ある意味であきらめて)自律と自由とを回復させたように見えるのと似ています。
(このあたりのことに共通するものとして,50代の主婦の例を上げておきます。この方は,幼いころから気分や行動が乱調だった息子さんの世話をやいてきました。ところが息子さんが,心霊的なあるセミナーで知り合った女性と懇意になり,いわゆる洗脳された気配になりました。そして,突然,激しい別離の言葉を浴びせられ,息子さんは家を出て行きました。連絡は一方的な形で金銭等の依頼があるものの,母親から連絡を取ることはできません。それから年余の歳月が経っております。夫は以前からそうであったように,連夜のように飲酒して深夜に帰宅します。夫のサポートもなく,孤独感と寂しさに悩まされておりました。そういう折に,老いた母親の入院の知らせを受けました。高齢なので覚悟はできていました,「しっかりしなくちゃ」と思いました。それを機に,本当にしっかりして心が屈することがなくなっております)
エネルギー論的に見ていくと,自我と無意識との関係は次のように考えられます。
自我は海のような無意識から浮かび出てくる小島のように見えます。生まれて間もなくは,代理自我ともいえる母親の全面的な助けを必要とします。母親の愛と信頼とに助けられて,赤ん坊はしだいに自分に固有の小島が大海のただ中に生み出ていく喜びを,大きな不安を持ちながらも知っていきます。それは母親が与えてくれた愛と信頼とを,赤ん坊自身が自分に与えることでもあり,同時にそれは母親への愛と信頼との印でもあります。やがて生まれつつある小島が自分のものであり,それを経営していく喜びが将来を保証しているように感じられます。いつか囲んでいる大海が怖れるに足らないもののように思われていきます。そして,いつか大海は姿を消し,小島は既に小島ではなく,揺るぎない大地の感覚になっていきます。
海は小島を呑み込む怖れを持っていますが,敵対するものではありません。それは母親が護り,助けてくれた大きな力によって,自分の小島を経営していく喜びと自信とが大きくなるにつれ,身についていきます。
海はいつか小島の内部に身を隠します。
このように比喩的に見ていくと(自我や無意識は現象的実体ではないので,我々が通常しているように,見たまま,聞いたまま伝えるというようなわけにはいきません。そういう形に似せて語る以外にないのです),自我が小島を未知なる大地に向けて発展させていくためには,自ら計画を立てるほかに,無限に通じる海のエネルギーの助けが必要です。
どうやら海は二層に分かれているようです。一つは小島に固有の海,もう一つはいわば人類のものであり,いうならば公海です。自我も含めてそれら三者は互いに境を隔て,かつ交流をはかっていると思われます。
これら三層のうち,自我と自我に固有の無意識層とでは,それぞれ一定量のエネルギーが固定されていると思われます。そして公海にあたる無意識のエネルギーは,いわば無限定です。
これら三層のあいだに境界があり,機能的な定めに従ってエネルギーの移動があると思われます。それは日常の心理の動きから推測すると,次のようではないかと思われます。
自我が使用可能のエネルギーはおおむね一定量と思われます。それは大よそ,自我が無意識層に対して上位に立ち,自由で自律的であるのを保つためです。
何かの行為をするときに,自我は自我固有の無意識に働きかけをして,それに応える形で欲動,あるいは欲求と呼ばれているエネルギーの供与を受けます。それは精神活動の一つの形式となり,必要に応じてパターン化して活動します。それが意志と呼ばれているものです。このときに自我に向けて,自我に固有の無意識から一定のエネルギーが移動します。自我が本来的な機能を果たせば,自我の子ともいえる欲求を護りとおすことができます。それは一定の満足感となり,供与されたエネルギーが適正に消費されたことになります。そして自我の機能の自由と自律性とが護られ,自我は活気のある状態を保つことができます。それに伴い自我に固有の無意識層に向けて,消費されたエネルギーが公海に当たる無意識層から補給されます。これら三層の一方向的なエネルギーの移動が起こっているかぎり,精神状態は健全です。
このことを,母親に甘える子を例にして見てみると次のようになります。
母親の助けによって甘えることができた場合は,幼い子の心の親である自我が,生まれてきた心の子である甘える欲求を護ることができたことになります。甘えを満たすことができたのは,母親によってというよりは幼い心の親である自我によってです。当然,母親の助けはなくてはならないものです。本来の役目を果たすことができた幼い子の自我は,エネルギーを蓄えて生まれてきた心の子である甘える欲求から,そのエネルギーを受け取ることになります。そのときに甘えが満たされた満足感を味わうことができます。その満足感は,母親から愛されている,信頼されているという喜びと共にあり,自分が価値ある存在であるという喜びと共にあるのです。そしてそのような体験を重ね,自信を得た幼い自我は,次々と生まれてくる欲求を押し殺さずに護り通そうとすると意志を持つことになるでしょう。それは自我の成長であり,活気のある自己の育成につながります。自我がエネルギーをうまく消費し,無意識の海から自我へと向けたエネルギーの移動が,滞りなく進んでいることになります。
一方,母親に甘えるのが難しい何らかの状況で甘えを断念したとき,次のようになると推測できます。
幼い自我は,心の海から生まれ出てきた自然のものである欲求(白い子)を護れず,見捨てることになります(黒い子を生み出す)。このとき自我は移動してきたエネルギーをもう一度押し返すことになります。それは自我が,生まれてきた欲求が蓄えているエネルギーを受け取ることができないばかりか,逆にそのエネルギーを自我に固有の無意識層に押し返すことによって,反自我の勢力(黒い子たち)を作り出すことになります。それに伴って,自我へと向う無意識層からのエネルギーの流れに,混乱と停滞が惹き起こされます。
そのようにして自我は不活性化し,かつ無意識層にある黒い子のエネルギーである怒りの圧力を受けることになり,二重に自我の活動を鈍らせることになります。
治療的な関わりが必要になるのは,以上のように自我の負債が増大したときといえます。治療的な介入がうまく進み,再び活性化しはじめた自我によって,黒い子の存在が改めて認められ,受け入れられるようになれば,それは既に黒い子ではなく,自我へと向けたエネルギーの移動が正常化することになります。
上に述べたことを別のいい方をすれば,次のようになります。
心には表舞台と裏舞台とがあります。表舞台には自我が仕事をした成果が乗せられ,生きる方向を指向しています。裏舞台には自我によって受け入れを拒否されたものが乗せられています。それら受け入れを拒まれた影の分身たちは,本来は自然のものであり,理不尽な目に合わされていることになります。また,人が人として生を開拓していく拠り所である自我が受け入れを拒否し,表舞台に上げるのを拒んだのですから,それは死の宣告に等しい意味があります。つまりそのようにして裏舞台に回された影の分身たちが志向するのは生ではなく,従って死ということになります。そのようなことが起きるのは,自我が機能する上で他者との関係を不可欠なものとしているからです。他者の助けがなければ,とりわけ幼い自我は立ち行くことができません。そして他者の助けは,幼い自我が真に必要としているものとは異なる宿命の下にあります。そのような事情から,自我の不始末(影の分身たちを心の裏舞台に回してしまう)が雪だるま式に拡大してしまうのは,多かれ少なかれ避けられません。自分を助けてくれるはずの他者によって,自我が不始末をはたらくのを余儀なくされ,結果として他者によって心が貧困化していくことは,大いにあり得ることといえます。
これら裏舞台の分身たちは死を志向するので,その勢力を一定程度以上作り出した自我は,作り出したことの不甲斐なさで力を衰弱させることに加えて,作り出された影の分身たちに取り囲まれ,支配を受けることになるかもしれません。そうなると主体性を失った自我の機能は固化して本来の生を志向する働きが鈍くなり,心全体が死の影に覆われることにもなるのです。
「死にたい」,「死んだ方がましだ」と考えるのは,自我が受け入れを拒否した心の分身たちの支配を受け,自由と自律性とを失ったことの表れです。
自我は,敢えて心の親であると意志的に意識する必要と責任とがあります。親であればこういう折に,「一緒に死のう」ではなく,「一緒に死ぬわけにはいかないよ,いまは助けてあげる力がないけれど,そのうちに助けてあげることができるようになるから・・・」というべきです。
このように心の裏舞台にある分身たちに言明するのは意味のあることです。そもそも自我の本分は,自己と人生とを引き受けることであり,いかに生きるかというところにあります。死を引き受けることはあっても,死を選択する余地は自我にはないのです。その本分に立ち返って,死への要求を排除していくことは,理にかなったことです。
ちなみに精神医療では,患者さんが死にたがっているときに,「死なないと約束してください」と提起するのが治療者が試みる定石です。その約束は,自殺を防ぐ有効性を持っています。この場合,衰弱している病者の自我を,治療者の自我が代理して補っているといえるでしょう。
なにはともあれ心の問題に解決が求められたときに,自我の介入が必須です。怒りは裏の自我に仕えるものです。
何であれ行為するときは意志に基づきます。意志は自我が相応する欲求(欲動)に呼びかけ,欲求が無意識の領域から生まれて来ることで成立します。その欲求はエネルギーを蓄えており,自我と協調して行為の達成を図ります。自我がしっかりと欲求を護り,励ますことができていれば,自我は活性化され意欲的に取り組むことになります。それは自我の呼びかけと相応する欲求の生起とが,いわば阿吽の呼吸の関係にあることになり,自由な機能が活発である自我の下に,次なる行為が速やかに展開され易い状況であるといえます。
一方,挫折を繰り返してきた自我は,呼び出した欲求を中途で無意識界に追い返すことを繰り返すことになります。自我によって見捨てられた形の欲求は,エネルギーを蓄えたまま生まれてきた心の海に押し返されて,いわば黒い子となります。それらは怒りと共にあります。自我に反逆するものとなり,死への志向を持つことになります。
以上のことを心の全体の整合性において考えると,以下のように描くことが可能ではないかと思います。
まず心の真の主体は何かという問題があります。意識的心の主体は自我と呼ばれています。自我は人間的なあらゆる営みの中心です。自我は意識活動の拠り所で,意識が及ぶかぎり知性的理解が精密に行われることができます。それが極限にまで推し進められたのが自然科学的なアプローチです。自然科学的達成に関しては,人は一切の上位に立つ支配者です。しかしながら自然科学以外の科学については,簡単ではなくなります。たとえば人の心理に関する学問は,自然科学のようには一様でありません。自然科学の威力は,意識の光が隈なく行き渡るので,ほぼ完璧に因果律的な論理の下に対象を従えることができることです。そしてその限界は,物的な対象に厳密に限られるところにあります。心理学は当然その範疇に収まりません。そこでは意識の光が隈なく及ぶことができないものを対象とします。つまり生きている全体を合理的に理解しようとすれば,意識の光が届き得ないものをも対象化することになり,その対象には無意識のものが入り込んでいることになります。ところで無意識と合理性とは全く相容れない関係にあります。合理的理解は意識化が可能であるのが前提になるからです。自然科学は合理的理解の究極のものであるので,心の科学もそれを援用することになりますが,意識が物的な実体として捉えることが不可能であるものを飛び越える形で,意識を繋ぎ合わせることになります。ですから推理や仮説は不可欠になります。仮説は物的な実体に凝らして行われるしかありません。
このように,そしていうまでもなく意識可能の世界が心の全体ではありません。つまり無意識の世界があり,これを大海になぞらえると,意識の世界は大海に浮かぶ小舟の船頭以上に頼りなげです。というよりは両者はそもそもそうした比較が不可能なのです。
心には無意識の世界があるのは疑えません。しかし意識の光が及ぶのはそこまでです。「それは疑いもなく存在する。しかしどのような様態で存在するのかは不可知である」ということになります。
意識できないものの存在を何故意識できるのかといえば,意識の光が届く世界が有限であるのが明らかだからです。しかしどこまでと限定すること自体が不可能です。たとえば100メートル走の世界記録を考えてみると,人間の能力に限界があるのは疑いありません。しかし世界新記録が限界に到達することもないでしょう。それは必ず新たな記録で破られるためにあるようなものです。それでも5秒以内で走るのは不可能に違いありません。「限界は必ずある。しかし人間の能力でそれをあらかじめ知るのは不可能である」ということになります。明らかにある限界に向けて,無限に近づくというのが実際です。このように明らかな有限性の中にも無限性が入り込んでいるのです。
つまり有限性は無限性があって初めて成り立つのです。そしてその両者のどちらが上位にあるかは論を待ちません。
そのことを定式化していえば,「我々は人間のことを意識できるかぎりで知っている。そのかぎりで人間は一切である。その拠り所を自我と呼んでいるが,それでは自我は何に拠っているのか?そのことを意識が捉えることは不可能である。しかし自我が存在する以上はそれをあらしめた存在もまた存在しているのは明らかである。その存在が自我の上位にあるのは論を待たない」ということになります。
自然科学の呪縛の下にあると,例えば,「死は一切の消滅である。それ以上の存在仮説を弄ぶのは愚かなことである」と考えます。しかしこの考えもまた,自然科学に論拠を置いた仮説に過ぎません。死の問題には無の問題があり,全の問題があります。それは無意識に通じるものでもあります。これらの問題が厳然としてあるかぎり,人はそれを問わなければ生きている全体を問うことができません。「死は無である。ただそれだけのことだ。それ以上のことを考えるのは無意味なことだ」と悟りすますのは,一見は謙遜に見えます。しかし真の謙遜は,自分の上位者の存在を認めることです。そうであれば,「死について,身体が無に帰する以上のことは,私には何も分からない」となるべきです。そしてその留保の態度が謙遜であるとすれば,暗黙の内に「何も分からないものの存在」を認めていることになるのです。「私には何も分からないのだから,それは存在しないということだ」といっているに等しい唯物論者の論は,粗暴に過ぎるというべきでしょう。
ここでその上位者を,内在する主体と呼んでおきます。この主体が心全体の上位者であり,統括者です。それは自我という有限の能力からは無限のものです。
自我という限定されたものには,それ自体を養う力はありません。言葉を換えると,自我が有限体である以上は,自我が抱えるエネルギーは有限のものです。つまり他から補給されなければ枯渇することになり,他というのは無意識の世界以外にはありません。このエネルギーは行動(行為)に伴ってもたらされると考えられます。何か行動(行為)を起こすとき,自我は計画を立てます。そして行動のエネルギーをもたらすものを呼び出す必要があります。その呼びかけに応じて内在する主体が,エネルギーを抱えた,いうならば神の子を送り出してきます。神の子は自然から生まれたばかりの無垢のものです。いわば白い子です。大変傷つき易くもあるでしょう。
呼び出した神の子を自我は護る義務があります。それは何といっても神の子で,送り出した子を自我がどのように扱うか,主体は見守っているともいえるでしょう(それぞれの個はどのように生きようが自由でしょうか。地獄化する人生があります。創造的な人生を送る人があります。それぞれの個が自分らしく生きていくのは,誰もが等しく願っていることではないでしょうか。それがどのようにしてというのが困難なのです。それを予め知っている人はいないというべきでしょう。しかしながら道を間違えると人生は地獄化します。やはり道はあるのです。我々には予め分からないが,それぞれの道は必ずあるということになるのだと思います。そうであればそれを知っているのは自我の上位者以外にはありません。自分らしく人格形成をしていく上での青写真は,主体にあると考えることができると思います。我々は手探りで自分の筋を辿っていくことになりますが,それは送り出された神の子を自我がどのように扱うかにかかっているように思われます。そしてその筋を曲げざるを得なくなり,自己を見失うことになる最大の理由は,他者との関係を必須のものとしているところにあります。換言すると他者の介入にあります)。
自我が神の子をどのように護るかといえば,目的(希望)に向って進む上での欠かせないパートナーですから,第一に呼びかけに応じてくれたことを感謝すること,そして第二に共に行動することを喜ぶことによってです。その行動のあいだ他のことに気をとられるようであれば,白い子は傷つくと考えるべきです。それで首尾よく目的を果たせば(自我が白い子を守り通せば),自我は白い子が抱えていたエネルギーを受け取ることになります。そのように逐一の行動を通じて,自我はエネルギーの補給を受けていると考えられます。
仮に予定された行動が,気が変わって取り止めになると,求めに応じた神の子は無用のものとされます。捨てられた神の子は怒りでいわば黒い子になります。自我に渡されることがなかったエネルギーを抱えたまま,黒い子は行き先を失います。送り出された主体の元に戻ることはなく,自我の世界の一隅にうずくまることになります。それは自我と無意識との中間領域で,ユングが命名した個人的無意識の世界です。この世界のものは,ふだんは意識の光が届かないので無意識ですが,自我がその気を出せば意識化が可能です。
このようにして元々は神の子であったこの黒い子たちは,悪魔の手先になっていきます。
これら黒い子たちを作り出す自我は,特有の状況でおなじことを繰り返す傾向を持つものです。それで黒い子は雪だるま式に肥大化します。それら黒い子たちの中核にあるのを,仮定的に裏の自我と呼んでおきます。
黒い子たちの抱えている怒りのエネルギーは自我に見捨てられたことによるので,怒りは,本来,自我に向けられたものです。それを受け止める気勢を示さない自我が,そもそも黒い子たちを作り出してきたのです。そういうときには,表の自我が裏の自我に支配されたまま無力でいるので,怒りは外的な状況に向けられるのです。黒い子をおびただしく作り出した自我の下では,人生そのものが面白くなく,道で石につまずくと腹を立てて石を蹴飛ばしたりといったことになります。
機能を回復した自我が与えられた使命をめざましく果たすことになれば,自我は裏の自我に仕える怒りのエネルギーを引き上げ,生へのエネルギーに転換する可能性があります。表の自我が力を回復させると精神のエネルギーは自我に集まり,力が衰弱すると,精神のエネルギーは裏の自我の方へ移行し,怒りを蓄えることになります。精神のエネルギーは無定形であり,生(光)への方向と死(闇)への方向といずれのものにも姿を換えるもののようです。一切を破壊するほどに蓄積された怒りは,死そのものと一体化します。死は一切の破壊であり,心の裏舞台の首座にあると考えられます。
Rさんの例で見れば,分身たちを抑圧しつづけてきた自我は,母親の自我の支配を受け,母親との共犯関係に囚われていました。その様子があるとき変わり,母親に怒りを向けることになりました。それはRさんの自我が母親の自我から距離を取り始めることに伴って起こったことです。それは同時に影の分身たちの存在に目を向け始めたことを意味します。母親の自我にへばりつくように依存していたRさんの自我は,おびただしく黒い子を作り出すことが避けられなかったはずです。そして怒りが意識に上ってきたことは,自我が本分に目覚める力を回復した兆しが表に表れたことを意味します。しかしまだ十分に機能を回復していないRさんの自我は,強力な怒りのエネルギーを蓄えている影の分身たちに捉えられたということができます。自我が機能を回復した分,母親から離れる自由を得たものの,今度は分身たちに捕捉されてしまったのです。その分身たちは,母親と共犯関係にあるあいだに,自我が心の表舞台に乗せることを拒否し,見捨ててきた(死の宣告に等しい扱いになります)ものたちです。
そのような局面を向えて,Rさんは大変困難な状況に身を置くことになったといえます。母親の自我の代わりに影の分身たちの支配を受けるかぎり,自我は傀儡の立場であることを免れません。それは死を賭した自立の希求という意味を持ちますが,自我が影の分身たちの上位に立ち,自由と自立とを確かめることができるまでは,自傷,自死を含めたあらゆる黒い満足の危険の只中にあることになります。いつか気がつくと自我が上位に立ち,影の分身たちの支配から自由になることができるでしょう,しかし裏の自我が蓄えていた怒りのエネルギーの総量は大きなものと予測され,自我によるそのエネルギーの回収作業はゆっくりとしたものである必要があります。慎重を欠けば,自我が粉砕される怖れがあるからです。その後の人生上の節目において,自我が衰弱するときもあるに違いなく,その度に分身たちのエネルギーが活発化して気分が不安定になり,あるいは屈するときもあることでしょう。それでもめげずにいるかぎり,やがて自我は引き受ける力を回復するでしょう。
怒りは身を守るものでもあり,身を滅ぼすものでもあります。身を守る怒りは,自我の後ろ盾を必要とします。身を滅ぼす怒りは,自我のそれを欠いています。
怒りは他者との関係,あるいは自己自身との関係を破壊しようとするものです。自我によって正当に支えられた怒りが他者に向かうのは適応的で,自己を護り,助けようとするものです。自我の支えを欠いた怒りが他者に向かうとき,対人関係を損なう危険が高まります。また自我の支えを欠いた怒りが自己自身に向かうとき,心と身体の健康を損ねる理由になります。
ある小学生は,夜,寝るときに,母親がいなくなる恐怖で眠れなくなります。母親が死ぬのではないかという恐れもあります。母親に叱られると,自分は嫌われているのか,可愛がってもらえていないのかと思います。年の離れた弟がいますが,弟ばかりが可愛がられると思い,怒りを覚えます。
弟はまだ1歳半ほどですが,小学生の兄が寝ているときに,いきなり頭を叩くなどします。小学生は,みんながいる居間で寝たいのですが,危険な弟がいるので,仕方なく別室で一人で寝ます。弟は宵っ張りで,夜中の1時ごろまで起きています。兄は不安と不満と怒りを胸に,眠りに入れません。兄も弟に仕返しをしたいのですが,なんといっても1歳半なので我慢するしかありません。学校から帰ると笑顔を向けてくる弟が,可愛くもあるのです。
この子は,率直な様子で話をする明るくも見える性格です。屈折した感じが見られません。「そうなんだよ,腹が立ってたまらないんだよ」といわば明るく怒りを表現します。怒りを露わにするという感じではありません。しかしそれらは表面のことで,心の裏面は明るいはずはなく,相当に深刻だと思います。明るく語る表情の裏には,はちきれんばかりの口惜しさがうかがわれます。
この明るく表現する怒りは,少年の自我の精一杯の努力といえるようです。自我が成熟している大人であれば,自我の精一杯の仕事はそれだけで十分に報われる意味を持ちます。しかし年齢が幼すぎるために自我が未成熟であるあいだは,幼い自我の仕事は親の支えによって報われる必要があります。両親の姿勢から,少年の怒りはいかにももっともなものなのです。それだけに少年の自我がしている精一杯の努力は,両親によって受け止められる見込みがなく,無効化されるのです。自我の精一杯の仕事によっても報われることがないので怒りが溜まり,心の潜勢力になります。その内向する怒りが,チックや不慮の災害への過剰の恐れという問題を引き起こしているのです。
怒りが心に充満し,母親の死を願うことさえあるようです。そういう怒りを持つために,母親が自分を捨ててしまうのではないかと恐れているのです。通学路の行き帰りに,変質者に連れ去られる不安を持っていますが,変質者は怒り(自分が母親へ向けた,あるいは母親が自分に向けた)の投影でもあると思われます。
母親によれば夜鳴きの激しい子だったそうです。
この子の怒りが母親に向けられたとき,もっと自分に愛情を向けてほしいという欲求を従えています。それは正当な要求であり,自我の仕事に基づくものといえます。そのとき怒りは満たされない欲求の従者でもあり,護衛でもあります。
しかしほどほどにしないと危険です。母の怒りの反撃に遭うかもしれませんし,場合によっては怒りが母との関係そのものを破壊するかもしれません。
親との関係の改善をもとめ,身を守るために怒りが表現されていますが,少年への優しさが足りないように見受けられる両親は,その意味を知ろうとしないのです。自我は本来の働きを精一杯しているのに,それが無効であるのは恐るべき現実です。子にとって,その存在を正当に認めようとしない親の下にあるのは,この上もなく残酷なことです。幼い自我の仕事は,親の支持がなければ無効になるのです。意識下の分身たちにとっては,自我が無力であるのと区別がつかないのです。業を煮やした分身たちの護衛である怒りが,実力行使に走り,心身の症状をもたらしているといえるでしょう。
親子の関係,特に乳幼児期の関係は,性格形成に決定的な意味を持ちます。幼い子の自我は,親との関係を通じて自分の仕事の意味を確かめていきます。生まれて間もないあいだの幼い自我は,身体的,生物学的な欲求の充足をもとめます。自我の仕事であるそれらの要求を,母親が満たして上げることが必要不可欠ですが,本当は満たしているのは母親ではなく,幼い自我が自分の仕事の有効性を母親を通じて確かめているのです。母親のサポートが得られたときに,幼い自我は大いに満足し,それを母親と分かち合うことになります。ここに自我の重要な役目である満足の追求と,母なる他者との関係が良きものであることとが,分かち難い関係の中で確かめられたことになります。このような母子関係の下では,自我は安定した機能活動に確信を持つことができます。逆に母親のサポートが不十分であれば,赤ん坊の自我は混乱することになります。
このように,親に感謝をする理由も,不満や怒りを持つ理由も,恐れる理由も,かなりの程度に親しだいです。
幼い子の怒りは,親のサポートが不適切であるという表明であり,改めて適切に対処して欲しいという合図です。
怒りをあらわにする子に対しては,親が真剣に取り組まざるを得ないだけに,解決に向けた努力が払われ易いといえます(体質的に怒りの度が過ぎる場合もありますので,うまくいくかどうかは一概にいえませんが)が,怒りを表に現さず,従順に見える子は,その傾向が災いして周囲の大人たちも問題視し難くなりがちです。表の従順は裏の不従順の表れであるとすれば,それは親を恐れる心からであると知っておく必要があります。
親に従順な子の場合,その親密さは見せかけのものであり,欲求の不充足感と怒りとを幼い自我が抑圧している可能性があるのです。そうであれば性格形成の上で難点を残すことになります。親としてもそれで満足したり,場合によっては子供のそういう傾向に乗じたりするのですが,子供の心には,抑圧が生み出した影の勢力が増大している可能性のことを考えなければなりません。
後々,心に障害が生じて医療の介入が必要になったときに,怒りは問題の在り処を指し示すセンサーのような役目を果たします。この感情に注目することで,隠蔽されていた負の体験を明らかすることが可能です。怒りの所在に注目することは,心の障害を取り除く上でも重要なものです。
心の障害を,治療者が親子の関係の側面から見る必要は大いにあり,それは鉄則であるといっても間違いではありません。
親子の関係を問題にするにせよ,しないにせよ,目的とするところは,障害をかかえている本人の利益にあるのはいうまでもありません。それはその母親,父親についても同様で,親子関係に問題があるのではないかと疑われるのは親の立場では不愉快でしょうが,親に対しても利益が還元されないはずがありません。障害を受けている子供だけがその利益を受け,親はそうではないなどということはあり得ないことです。もしそう考えて不快に思う親があるとすれば,それは親としては大いに問題であることを自ずから示していることになるでしょう。
残念ながら,この種の問題提起に,不快,不満を持つ親は少なくないどころではありません。むしろ一般だといっても過言ではありません。
明快な拒否感を持つ親は,そもそも治療者の前に現われることがありません。一見は協力的な場合でも,問題の根にまで理解を深めることは容易ではありません。親子が負の依存でつながっているからだと思います。親子の負の依存関係は,元はといえば親の側に,自我が処理し切れなかった負債ともいえる分身を意識下に蓄えていることによる可能性があります。それらの分身が要求するものを,自我が引き受けなければならないのですが,引き受けない(弱い)自我が他によって分身の不満を満たさせようとするのです。そのような自我の下にある母親にとって,赤ん坊は恰好の相手になります。赤ん坊は母親にとってはある時期まで自分の一部のように相互に密着した関係にありますので,意識的にか無意識的にか赤ん坊が自分を助けるように仕向けることが可能です。そのようなことが母親に起こりやすいのは,赤ん坊に対して特権的な立場にあるからです。ですから無自覚でいると,母親は赤ん坊に依存し,赤ん坊を助けるよりは自分を助けるように仕向けることになりやすいのです。母親が抱える意識下の負債が大きければ大きいほどこのようなことになりがちで,その依存の対象にされた赤ん坊もまた,自我の自律性が損なわれて,いずれ意識下に負債を抱え込まざるを得なくなります。
Wさんは主婦です。子供はいません。初診は29歳の夏でした。過呼吸状態で一人では歩けず,父親に背負われての受診でした。一週間ほど微熱がつづき,胃に熱感があり,食べ物を口にすると吐いてしまい,内科で栄養失調といわれていました。
初診の3年ほど前に結婚しました。初診の数日前に,夫婦二人の生活から両親が住む実家へ住居を移しております。父親が,「子供はまだか」と気にするので,「家が狭いから」とかわしたつもりが,実家に引越しをする羽目になってしまいました。父親に家を改造するからといわれると断れなかったのです。Wさんは自分の意見,意志を明確に出来ず,相手がだれであっても,「いやです」といえない性格です。夫が気を使うだろう,自由がなくなり申し訳ないといいますが,その後の経過から,この心配はWさん自身のものでもあるのは明白です。受診の動機となった心身の不調は,この転居と大いに関係があります。
Wさんは一人っ子です。過呼吸発作が始まると,いつも父親が手を握ってくれます。母親は決してそういうことはしません。この一事からもうかがわれるように,母親は母性に問題があるようです。Wさんは,幼いころから母親に罵られながら大きくなりました。何事につけ,役立たず,お前にはできっこないよなど否定的な言葉を投げつけられ,ほめてもらった記憶は皆無です。あんたなんか生まなきゃよかったと何度となくいわれました。赤ちゃんのときお湯を使わせたことがなかったとか,泣いても放っておいたとかわざわざいって聞かせるのです。2歳ほどのとき食べものを喉につまらせて,吐いたものが母親の顔にかかりました。いきなり平手打ちされたのを覚えています。
そのように育てられたのですが,父方祖母(この人には可愛がられました)に母親のことを悪くいわれ,あんなふうになるんじゃないよなどといわれると,おかあさんが好きだと,母親を庇うように心でつぶやきました。母親が身体の具合をわるくしたり,悲しそうな顔をしていたり,そのようなことがしばしばありました。母親を,怖いと思うのと可哀想と思うのと両方の気持ちが交錯するといいます。また両親の仲がわるいので(母親が一方的にののしる),Wさんは意識して笑顔を作っていたといいます。実際,Wさんは笑顔を絶やさない人です。その表情からは推し量れませんが,こんなことをいっていいのかなとつぶやきながら,心の奥に潜んでいる殺意を打ち明けることもあります。対象は母親と夫です。夫のことは尊敬しているし愛してもいるのですが,いつも仕事で帰宅が遅いので,しばしば私がいやなのか,私が負担なのかと気になるのです。しかしながらWさんがそのような激しい心を打ち明けることができたのは,心が回復してきている証拠です。
友達にも,頼まれると断ることができませんでした。常に機嫌よく引き受けてしまいます。しかし自分の問題を客観的に見る力がついてくるにつれ,自分の意志を表すことができるようになってきました。相手がどういう態度に出ようが恐れないという気持が芽生えてきました。これまでの優しさが,見せかけの仮面であったこと,自分がほんとうは怒っていたことに気がついてきました。本当は好き勝手なことばかりいう友人など,友人ではないとひそかに思っていたのです。そういうこともいえるようになってきました。従来は,ひそかにあった怒りは醜い心で,あってはならないことに思えていました。そういう心が自分にあることを意識したくなかったのです。しかしいまは違います。怒るだけの理由があるので優しいふりをする必要がないのも分かってきました。
Wさんは人に優しくしていないと,自分が意地悪に思えて不安になります。しかし意地悪なところがあるとしても,それはそれで受け止めるしかありません。事実は事実です。知らないでいるよりは知っているほうがよほどましです。意地悪なところがない人などあるわけもありません。自分に意地悪なところがあると知っていることが,それを克服するための最良の態度ではないでしょうか。Wさんはそういうことを理解するようになってきています。それにつれて母親に対しても以前のようには気を使わなくなりました。
怒りは重要な感情です。つよいエネルギーをはらんでいるので,怒りが爆発すると人との関係を破壊しかねません。内向すると自分自身を打ち砕きかねません。そういう不安を覚えることは誰にでもあると思います。
怒りのエネルギーが強いと,自分に対しても(重要な)他人に対しても,要求の水準が高くなります。要求が高くなると,望ましいイメージどおりでなければ納得できず,苛立ちを隠せなくなります。
怒りは”心の沼“の守護者のような働きをするように思われます。”沼“は意識が受け入れなかったものの負の集積所といえるでしょう。自我が怒りの活動に応えるときに,怒りが守護者であった意味が現実のものとなります。しかし自我が怒りに対して恐れをなすようであれば,怒りは黄泉路の国からの使いになりかねません。強い怒りによって機能不全化された自我は,心全体の指揮を取り,自己を指導する資格がないのです。
負の活動は生まれたときからはじまります。思えば誕生という祝福されるはずの出来事が,そもそも負の体験そのものである節があります。母親の胎内という安楽境にまどろんでいるときに,いきなり外へ放り出されるのが出産です。新生児は驚きもし,怒り狂ってもいるようです。児童心理の研究者によってその種の指摘がされています。
赤ちゃんは安楽境に匹敵する大安心,大満足を要求して猛り立ち,時には満ち足りた気分にもなり,そういうことを繰り返しながら母親に助けられて,しだいに現実的な,ほどほどの満足を受け入れていくことになります。
人間の誕生は自我の授与でもあります。人間の人間たるゆえんは,自我に拠るということです。
自我は人間自身が自分の力で身につけたものではあり得ません。生まれるときに備えられたものです。それを授けたのは誰かといえば,あまりに人間的な問いということになるでしょう。しかしながらそれは不可知の力によって,人知のおよばない力によってというのは明らかです。その超越的な力を表す主体は,無意識の世界に内在して自我の後ろ盾になっていると仮定的に考えることができます。
それは科学的という観点から実証不能ということで,荒唐無稽であると考えることも可能でしょう。しかし歴然として人知を超えたものの存在をどう扱えばよいのでしょう。それは科学では証明できないから留保するしかないというのであれば,それはそれでよいでしょう。しかしそうした留保は,超越的なものの存在を認める姿勢と何ら変わりがありません。
また科学的に証明できるもの以外は認められないというのであれば,それは科学至上主義ということになります。いわば科学ないしは人間の理性を,最上位に据えることに他なりません。これがいかに謙遜を欠いた態度であるかは,地球環境をまるごと危機に追いやった現実を見れば明らかです。自我に拠る人間は,その上位に立つものの存在を認め,怖れを知るべきです。
このように考えると,自我に拠る人間の存在理由は,自我を授与した超越者の意志を引き受けるものということになります。
かつてソクラテスが実践したのは,このことでした。彼は神の助手を自認し,神の意志(彼によれば子供のころから,鬼人か何かからの合図があるといい,何事かに心を奪われ,没入する様子があったといいます。その様子は,彼を信奉する人にも神秘的,奇異と映ったようです。現代の科学万能の時代であれば,ソクラテスは幻聴に聞き入っていたということになりかねません。また時代が違うと一蹴されてしまいかねませんが,それはソクラテスを時代の迷妄の産物といってのけるのに等しいことです。人間を取り巻く状況は,今も昔もおなじです。ソクラテス的な神が,現代においてどのように扱われるかは重要です。その存在の実体が何であるかは,今も昔も,我々人間の認識能力を超えたものであることに変わりがありません)をアテナイ市民に伝えるのを使命としていました。ソクラテスの愛知というのは,神命を引き受ける精神というところに行き着きます。
それにしても,大満足をあきらめて小満足に甘んじる仕方を習得していくのが人生だとすれば,一体人間とはなんなのでしょうか。幸福の追求とはなんなのでしょう。
この問いに答えるには,幸いにして人の心には無意識という広大で,不可知な世界があるというところに行き着くでしょう。この世界も人間の持ち物です。そしてソクラテス的な神は,いわば主体として無意識の領域に内在すると考えることが可能です。それは自我に拠る人間に,測りがたい力を秘めた後ろ盾となっていると考えてよいように思われます。
赤ちゃんの大安心,大満足の現実の提供者は,主に母親です。自然な母性に従う母親は,赤ん坊に一体化して没入することでそれに応えているのです。そして母親にできるのは,大安心,大満足の提供ではなく,ほどほどのものでしかないのだということを,身をもって赤ちゃんに教えることです。赤ん坊の心に潜む大安心と大満足への要求とは,母親の胎内にあった充足に匹敵するものの要求と思われるので,この世の現実を生きるためには,ほどほどの満足,ほどほどの安心(安全)に甘んじる必要があると教えることは,何よりも大切なことです。言葉を換えれば,母親の愛情とはこの程度でしかないということを教えることができるのは,豊かな母性のみであるということです。母親がこの役割を良く果たすことができなければ,赤ん坊のこれらへの要求は,約束の不履行の感覚として,意識下にいつまでも残ることになるのです。それはこの世を地獄化する大きな理由になります。
たとえば授乳について,母親は赤ちゃんが望むときにするのではなく,決めた時間にするとき,赤ちゃんの感覚は混乱し,安全感が危うくなるとイギリスのウイニコットという児童精神科医が述べております。たとえていえばこのように,母親は,知識に拠ってではなく,自らの本能的な知恵で育児に当たらなければならないのでしょう。赤ちゃんの人生の生殺与奪の権限が,母親に託されているといっても過言ではないと思います。大きな責任と大きな喜びとが母親に特権的に与えられているといえますが,それを喜び,誇りに思うか,迷惑千万と思うかは,人間の幸福と不幸の問題です。
それはともかく乳幼児の負の体験は,のちのち記憶としてとどまることはないでしょうが,その事実は消滅することはなく,無意識が預かることになると思います。そのようにして,”心の沼“が形成されていくのです。沼を構成するものは,感情の面では,恐れ,おびえ,寂しさ,虚無感,抑うつ感,疎外感,孤独感などで,またそれらの感情の基となった体験群であろうと思います。そしてそれらの辛い体験は自ら望んでしたものではなく,押しつけられたと感じたものです。それは理不尽と感じられ,怒りを伴います。これらの問題を捉えて解決に当たるのが自我なのですが,問題が大きすぎると,自我は回避的な態度を取ります。そういうときに,怒りは,”沼”を構成するものの,いわば守護者のような動きをするようで,主君である自我を脅かす勢力になるのです。
母親に叱られたときの乳児の恐怖は,母親が意識するものを超えている場合があります。乳児に愛情と信頼とが十分に伝わっているときには,母親の叱責は彼女の意識するレベルにとどまるでしょう。しかし,彼女が意識する以上の恐ろしさを乳児が感じるとき,それは乳児自身が大きな怒りを持つていたためかもしれません。自分の怒りが母親の上に投影されて,母親が鬼のように恐ろしい顔で怒っていると感じられることはあり得ることです。
あるいは母親が持つ“心の沼”に潜む怒りが,赤ん坊に感じ取られることも起こり得るでしょう。怒りをはらんだ“沼”には元型的なエネルギーが入り込んでいると思います。それは常識的な理解を超えたエネルギーが怒りに蓄えられていることを意味します。そのために場合によっては鬼のような怒りになるのです。
無意識の根底に,動物でいえば本能に相当する心の元型があると,ユング心理学ではいわれております。これは人類の長大な歴史を越え,民族格差を越えて,だれもが経験し,あるいは経験し得るものとして,人から人へ受け継がれてきた普遍的な心理現象の基となっているものです。人が個別的に学習して獲得するための原基となるもの,学習以前の生得的なもの,本能のように刻印されているもの,そういうものが心の深層にあるとユングが確信して,命名したのです。この元型には強力なエネルギーが込められています。
元型の一つに悪元型があります。それは文字通り悪に通じるものですが,一般的には,古い心の体制を破壊して,新しく心の組織をよみがえらせる上で,大切な役割を果たすと考えられております。いわゆる死と再生に関わるのです。この悪元型には怒りのエネルギーが強力に布置されております。この元型が賦活された状態にある人を前にすると,おのずから緊張を強いられるかもしれません。
虚無や孤独や寂しさや恐れなどが,「底なしの」とか,「途方もない」とか,「奈落に落ちるような」とかの言葉で形容されるのが,“沼“を構成する感情の特徴といえます。それらの感情は,人間の言葉では捉えがたい無限定なもの(死にも通じると思います)に触れたために生じているようでもあります。つまり,人間は有限の存在ですが,それら限定できないものに包囲されている存在でもあることを,ふとしたときに感じ取ることがあるものです。
星の群れがきれいに輝いている夜空を見上げるとき,ふとめまいを覚えたことはないでしょうか。そのとき宇宙の無限に触れたといえるかもしれません。そういう折の,途方もない無限感覚が,日常のありふれた体験の中にも入り込むことがあると思います。どこか空恐ろしげな気分に悩まされるとき,”心の沼”が活性化していると考えられます。
性格形成に与える母親の影響-その7(Updated 07/10/06)
■自我の形成 その1
#1 心の指導者(主我と客我)
心が成長するためには指導者が必要です。
心にとっての指導者は、心の内と外に存在しています。
母親がほとんどすべてである乳児期においては,母親は絶対的な指導者の立場にあります。
心の指導者が心の内部に存在せず、外部にのみ存在する乳児期は、乳児と母親とは絶対依存の関係にあります。
それは乳児のみならず、母親もまた乳児に絶対的に依存しているというべきです。
何故なら、そうした状況での母親と乳児の関係は一体のものである上に、そもそも依存というものは、相互的な関係であるからです。
しだいに長じるにつれ、母親のみならず、父親や祖父母などなど、周辺の重要な関わりを持った大人たちが、躾や教育などの指導をします。
それらは外的な指導者です。
そして、それにつれてしだい次第に、心の内部にも指導者が育っていきます。
このように影響力のある他者を取り込みつつ、他者イメージが育成されていくのですが、それを可能とする根拠は自我にあります。
心の中核にある自我の機構には、内的な他者の原基があると思われます。
それが受け皿となって外的な他者と協働し、他者イメージが育成されていくのです。
その内的な他者が、内的な指導者になります。
この内的な他者も自我の構成員ですが、その指導を受け、かつ受けた指導を再構成しておのれ自身のものとする構成員もあり、こちらがいわば真の指導者の立場にあります。
これらの自我の二つの構成員を、それぞれ客我と主我と呼んでおきます。
客我は内的な集合的他者で、主我は自己本来の主張を導くものである、と想定されます。
この関係を画家を例にして図式的に示すと、以下のようになります。
幼いあいだは、心がおもむくままに「お絵描き」を楽しみます。
この場合、幼児の無意識の心から、欲動が生まれてきます。
この欲動を引き受けて、絵を描くという行為に導くのが幼児の自我です。
その自我は、心の自然の要求に従っているので、主我ということになります。
やがて、絵の教師が指導者として現れ、お絵描き(主我による描画)を批評します。
教師の批判的指導を受けて、独りよがりだったことに気がつき、受けた指導に従おうとします。
自我は、この外部にある指導者を心の内部に取り込み、外的な教師がいないときでも、教えられたとおりに絵を描こうとします。
心に取り込んだ、この内的な教師が、客我の構成員になります。
これら心の内外の指導者が、仮に過度に厳しいとしても、画家の名に値するものであれば、主我は常に客我に屈することはありません。
主我は、いかなる場合でも、客我の支配から自由でなければ、「自分の絵」は描けないのです。
従って、おなじ理由から、心の構造が、客我が主我を支配する形になっているのであれば、絵は模写の域を出ることはできません。
一般的な日常の生活では、客我が心を主導していると考えるのが実際的であるといえます。
日常の行動は、いちいち考えながら推し進めるのではなく、パターン化されています。
エネルギー効率の上でも、パターン化されている方が合理的ですし、日常の行動はそれで足りるのです。
仮に、日常の個々の生活で、逐一「独創を意識する」とすると、エネルギーのロスが大きい上に、「個性的」というよりは、「変わった人」の印象を人に与えるだけのことでしょう。
日常は、常に変わらない姿が、周囲の人に安心を与えます。
しかし、こうした客我にいかなる場合でも従っていると、「退屈な人」、「変わった人」、「融通が利かない人」などなどといわれかねません。
当の本人にとっても、マンネリ化した日常では、退屈に悩まされることになるので、主我はそれなりに自由(柔軟)でなければなりません。
だから、「日常の中の非日常」は必要です。
「日常の中の非日常」では、心の柔軟性が問われています。
それは、主我が客我から自由であるという意味を持ちます。
例えていえば、ふだんは「自動運行装置」に任せておき、ここぞというときに「手動」に切り替えるのに、いくらか似ているでしょう。
主我が客我に支配され、自由が極端に束縛されると、人の目が過剰に気になります。
客我は客観的な他者と連動するのです。
客我に支配され、自由を束縛されている主我の下にある心は、自己を評価する基準が抽象的、集合的他者になります。
それは、客観的な外部の他者に認められるかどうかが、自己の存在意義にかかわることになることを意味します。
こういう心の状況では、客我が威嚇的、高圧的になるので、いわば100点を取って当たり前になります。
仮に上司が高圧的であっても、それは具体的で客観的な他者との個別の関係なので、主我が自由であるかぎり心が屈することは滅多にはないでしょう。
しかし、客我が主我を凌駕する心の構造があれば、例え上司が理解のある人であっても、100人もの過酷な上司に囲まれているに等しい気分状態になります。
このような状況では、主我は無意識から立ち上がってくる恐怖に圧倒されます。
いわば恐怖の色眼鏡で外的な他者を見るので、個々人を個別に、客観的に見ることができなくなります。
個々人への対処ではなく、いうならば、周囲の100人が100人ともが恐怖の対象になるので、社会的な役割の全般にわたって、すべての他者から無理難題を押しつけられるのに等しくなります。 (主我が恐怖によって破壊的な影響を受けて機能不全に陥ると、周囲の者に迫害されたり、監視されたりという妄想、幻聴に発展します)
そういう心的状況では、常に100点満点を強迫的(脅迫的ともいえます)に要求されるに等しいことになるので、義務を果たすばかりの、喜びのない、頑張りつづけるしかない日常になります。
こうした状況が長期に渡れば、やがては弾性限界に達したバネのように、心の弾性がくず折れるとしても不思議はありません。
一般に、困難な状況に置かれると、主我の動きが鈍くなり、相対的に客我が心を支配します。
それは、いってみれば、伸るか反るかの分岐点に心が立たされることになり、不安の増大は避けられません。
不安の大素には、恐怖があります。
その状況を越えることができなければ、挫折という心の崩壊が待っています。
それを免れることができない予感が、恐怖をもたらします。
こういう状況では、動きの鈍い主我に対して、客我が威嚇的にもなるので、主我が試練にさらされることになります。
そして、置かれた状況が客観的にも困難なものであれば、主我が客我を凌駕する力強さがもとめられます。
それが力強く発揮されたとき、天才的であるということになるのでしょう。
一方で、発育不全(親の躾けなどに耳を貸さないのが、習い性になっているなどで)の客我と共にある主我の下では、天才気取りの自称芸術家か、いずれにしても独りよがりの人間になります。
この場合は、社会への適応が難しくなります。
主我は、客我の影響を受けつつ、刻々と無意識層から贈られてくる新しい生命(欲動)を引き受けて、行動化する使命を持っています。 (無意識界には二つの層があります。一つは意識化が可能なA層、もう一つは意識化することが不可能なB層で、このB層は大自然が心に及んでいるものです。欲動はB層から贈り出されてきます)
自己に固有の生命的世界は、そのように展開されていきます。
主我は、客我の意向と、このB層から送られてくる新たな生命の誕生(大自然の贈り物)とを引き受ける立場にあるので、両者の意向が矛盾するときに、主我は選択を迫られて葛藤します。
それは、例えば次のようになります。
友達と遊びに行く約束をして帰宅したところ、母親に、「遊んでいないで勉強しなさい」といわれたとすると、母親の意向と客我とが連動し、遊びに行くことの動因として生起している生命とのあいだで、主我は葛藤に苦しみます。
客我が有力で、母親の意向に逆らえないときには、新たに生起した生命は抑圧されます。抑圧されたその生命は、怒りと共にA層に留まります。
しかし、改めて母親の意向を客我の意向と連動させてその意義を認めなおすと、「勉強をする」ことは、新たに主我が引き受けたことになり、自分自身の問題とすることができます。
そして、それに相応してB層から新たな生命が送り出され、主我との協働で勉強をする確かな意志になります。
しかし、母親の意向を理不尽と感じながらも、母親と客我の権勢に押されて盲従するとき、主我は客我の傀儡となり、自分を護れない臆病者になります。
つまり、B層から生起しているもっともな生命の誕生を無視することになりますが、それは母親の意向を理不尽と捉える明確な心が欠落していたのと並行して、主我が自分自身に理不尽なことをすることになります。
主我が、正当にも、生起している生命を護ろうとすると、母親と衝突します。
客我は、それなりに強くなければなりません。
それは主我の独りよがりを補い、社会一般の常識を教えます。
その上で主我が客我に対して自由であるのが健全な心です。
主我と客我が対立し、しかし補い合い、その上で主我が心を主導するとき、心は自立しています。
その母親が気弱であれば、あるいは幼い子の怒りが強く、聞く耳を持とうとしないなどの傾向があれば、客我の育ちがわるくなるかもしれません。
気弱な客我の下では、主我は生起する新たな生命を無批判に受け入れるので、勝手気ままな幼稚な心になります。
その場合は、社会性が怪しいものになり、場当たり的な行動を繰り返すことになるかもしれません。
いずれにしても主我によって抑圧された生命たちは、A層に終結します。
A層に終結している生命たちは、主我に受け止められなかった恨み、虚しさ、寂しさ、悲しみなどなどと、そしてその理不尽さへの怒りと、それらの感情と共にあることになります。
客我に支配された主我の下では、A層の生命たちは、不当に抑圧されたことになり、逆に主我を支配、拘束することにもなります。
それは、治療を要する病的な心の状況です。
A層の生命たちは、いわば、生きる喜びのために生まれてきたものが、「受け取れない。死んでちょうだい」と、主我に拒絶されたものたちに等しいのです。
実際、A層の分身たちは、死の極を目指すことになります(心には、生命の極と死の極との対立があると考えられる合理的理由があります)。
大自然の力と人間の浅知恵との力較べは、本来は比較にならないことであるので、客我が主我を支配しつづけるほどに強大であるときは、心はいかにも不自然な状況になると共に、豊かな人間性から程遠いものになります。
乳幼児の主我が、必要以上に母親との関係を優先させざるを得ない何らかの事情の下に置かれれば、母親との関係を護ろうとしないわけにはいかない(見捨てられないように、母親に盲従しようする)ので、大自然からの贈り物を不当に拒否することになります。
そうしたことが起こりがちであれは、乳幼児は、自縄自縛に陥る途を選んでいるのに等しくなります。
それは、自らを窮地に追いやることになります。 (母親との関係を優先させざるを得ない事情が傾向的に大きくなるのは、次のような場合が考えられます。母親の健康に問題があるとき、父親が家庭を省みない何らかの事情があるとき、両親が不和であるとき、母親の心が未熟、幼稚であるとき、幼い子が過敏であるとき、などなど)
他者との依存関係を存在条件としている人間の心の構造の中心にあるのが自我ですが(唯一の中心ではありません。自己の中で、生命的世界を展開する心の中心です)、この自我を、先に述べたように客我と主我とに分けることは、精神の問題を理解する上で合理的な意味があります。
そして外部に存在する他者と連動する客我と、真の指導者の立場にある主我とが、対立し、補完し合う様相によって、性格のパターンが決まります。
依存は依存であっても、主我と客我とのそれぞれの強さの程度や、両者の相対関係によって、自己の自立性の程度に、違いが出てくるのです。
赤ん坊に最も必要なのは、安心と満足です。その両者は、それぞれが別なものではなく、共にあるものです。
安心がないところに、満足はなく、満足がないところに安心はありません。
そして、赤ん坊は無邪気に育っていくだけのものではなく、大安心と大満足とを母親に要求しつつ育っていくのです。
ということは、赤ん坊は、安心と満足とを脅かされがちであるということです。
赤ん坊は、安心が‘全’でなければ、いわば立命できない気分でいると思われますが、現実にそれが理想的に適えられることはありません。
母親が、赤ん坊に、安心、満足をもたらす役目を持っているのは当然として、何らかの事情で不安感、不満足感を与えてしまうのは避けられません。そういうときに、赤ん坊の疑いに、現実的な理由を示すことになります。
母親は、欠けることのない愛情を注ごうとするよりは、‘全的な存在’ではないことを伝えるのが、むしろ愛情であるのは明らかです。
母親が‘全的な存在’ではないのが明らかだからです。
自立心に欠ける母親の中には、赤ん坊に、「すべてを注ぎたい」と考える場合もあるかもしれません。
そういうときに、甘やかしすぎて赤ん坊の自立性を奪うことになるかもしれません。
それは愛情が大きいのではなく、母親の不安が大きいからに違いありません。
母親自身の満たされていない心を、赤ん坊をいわば利用して満たそうとするに等しいので、実質は愛情に似て非なる自己本位のものといわなければなりません。 (ある境界性人格障害の患者さんは、「母親が欲しいものを全てあたえてくれた。そういうふうにして、子供である自分を支配しようとしてきた」といいます)
良かれ悪しかれ、二心(ふたごころ)を持っているのが人間です。
どんなに優しい母親でも、赤ん坊に注ぐ愛情は、赤ん坊に対するものである一方で、母親自身の利得を無意識のうちに意図するものです。
それは良い、悪いの問題ではなく、人間の特徴であり、事実問題です。
この意味で無私の愛情はあり得ないので、‘全’を要求する赤ん坊に疑惑を与えるのは避け難く、不安、不満足を覚えさせないようにするのは不可能です。
‘全’であってほしいほどに頼りとする母親であるがために、その裏返しとして、母親は大不信の発信源になる理由を持っているのです。
そういう折々に、赤ん坊が、心を震撼させるような大きな恐怖経験に見舞われても不思議はありません。
それが全面依存の身である赤ん坊に不可避な、見捨てられることへの恐怖の意味です。
見捨てられる恐怖は、生死を賭けた恐怖です。
このように見捨てられる恐怖は、人間であるが故の根源的なものであり、あらゆる恐怖の起源です。
それは無意識的な恐怖であり、しばしば得体が知れない恐怖感をもたらします。
いうならば心理的な意味で、見捨てられる恐怖は「諸悪の根源」で、さまざまな、というよりはあらゆる病理的現象を惹起させます。
人前での過度の緊張、過度な明るいふるまい(無意識界にある恐怖、孤独感などを隠すふるまいです)、過食、拒食、買い物、アルコール、ギャンブル、自傷、盗み、等々の依存症などなどをはじめ、すべての精神疾患の根底に、見捨てられる恐怖が潜んでいます。
見捨てられる恐怖は、人間であれば誰であれ、例外なく意識の根底に存在していると考えなければなりませんが、その度合いが強いときに、主我は生きる本能を優先させて、母親を怒らせないように、迎合する戦略に走るのです。それは同時に、自動的にB層から生起してくる(大自然の贈り物である)新たな生命を抑圧することになります。そういう傾向が優勢になると、客我が主我を支配する構造が出来てしまいます。客我に依存する主我は、いわば自由を放擲して、よい子になります。
以上のような事情がありますが、最善の母親とは何かといえば、自然の心を豊かに保っている母親ということになると思います。
それは高学歴であるとか、知能指数が高いとかとは、直接の関係がありません。
むしろ、「頭でっかち」の母親は、自然の心の豊かさに問題があるかもしれません。そういう母親は、赤ん坊に(育児に)専心するのが難しいのではないかと思います。
前者の母親であれば、二心についても、自然に身についた知恵が働くでしょうが、育児に専心できない後者では、関心がそがれている分、知的に理解しようとするでしょう。そういう母親は、当然ながら、赤ん坊の心に敏感になるのが困難だろうと思います。
そういう事情があるので、母親は、自分が赤ん坊に愛情を注ぐのは、赤ん坊が可愛いからだけではなく、赤ん坊の成長によって母親自身が仕合せになりたくもあるからだということを、知っている必要があります。このことに鈍感な母親は、母親自身が無意識界に何らかのコンプレックスを持っているに違いありません。
見捨てられる恐怖は、精神の病理現象を招く元凶といっても過言ではないと思いますが、否定的な性格をしか持っていない、というものでもありません。
肯定的な意味は、まさにこの否定的な意味の隣にあります。
つまり、見捨てられないように、対他的な何らかの行為を試みることによって、他者との関係を計る理由があり、それは必要なことです。
そのことによって他者に認められ、他者に認められることを通じて、自分が自分自身を認めることができ、いつか自己肯定感が育っていきます。
いうならば不足感があるがために、充足をもとめる理由が生じることが可能になるのです。
見捨てられる恐怖は、心のさまざまな病気を招く諸悪の根源であるといういい方をしましたが、その恐怖の存在自体が問題なのではなく、それが過度にわたるときの話です。
先に、自我は心の中心であるが、唯一のものではないと述べました。
もう一つの中心は、B層にあります。
B層は大自然が心におよんでいる領域で、心の無限性を保証するものです。つまり、この層は、全であり、無であるという性格を持っていて、自我(と、それによる有限の世界)はここから生まれ出てきたとも考えられるのですが、いずれにせよ、自我を根底で支える拠り所です。
この層の存在と死(無)の存在とによって、自我の有限性は補完されています。
つまり、そのときどきの志向対象との関係で、そのつどの自己を刻々と超克し、生命的世界を展開する主体である自我は、そのときどきの志向対象との関係にかぎっていえば、有限のものであり、目的に到達するたびに潰えます。それは、そのつど無(死)の無化作用を受けるということです。
一仕事を終えて、その充足感の余韻に浸りつつひと休みしているうちに、虚無の気配が忍び込み、不安に駆られることになります。それは次なる行為を促します。自我が健全な状況にあれば、改めてB層から新たな生命が送り出されてくるので、自我はそれを受け止めて新たな志向対象へ向かうことになります。
そのように自我は、死に由来する無化作用と、B層に由来する大自然から生まれ出てくる生命との、二つの無限性のものとの関係において補完されています。
つまり有限のものである自我は、逐一の行為が(死の別名である)無の無化作用によってそのつど潰え、B層との関係によって、そのつど新たに蘇るのです。
いわば人の心は、日常的に、生まれ、そして死んでいるといっても過言ではありません。例えば、夜が来て眠りに着くのは死と区別がつけにくい面がありますし、健やかな気分で朝を向かえるのは、新たな生命の生起といってもおかしくありません。
結局、自我は有限のものですが、無限性のものである死とB層とによって補完され、いわば「生きているかぎり無限の性格を持っている」ことになります。
死は自我にとって超えることができない壁です。
しかしながら、死は、いま述べたように、生を単に阻むもの、無意味化するものではありません。
生を主宰する自我にとって、死は超克することができない壁である一方、生と死の相容れることのない対立が、希望を生み出す根拠になります。
希望が成立するためには無限性が必要ですが、それを保証するのが死と、B層にあたる無意識界です。
繰り返しになりますが、自我は、生命の誕生(B層からの贈り物)と死との狭間にあって、死の超え得ない壁に挑みつつ、B層からの新たな生命の誕生を受けて、いわば生と死とを日常的に演出していると考えることが可能です。そこには、明瞭に有限のものでありながら、内に無限性をはらんでいるという、自我の特有の性格がうかがえます。
自我は、そのつど何ものかを志向します。
疲れてぼんやりとしているときであっても、自我が放つ光りである意識は、虚空を無意味に漂うのではなく、志向されている何ものかをぼんやりとまさぐっていると考えるべきです。そして、志向され、課題化されている何ごとかを超克したときに、意識はふたたびぼんやりとした状況に置かれます。それは、しかしながら、課題を超克したことへの満足感の余韻と共にあるでしょう。そして、また、しだいに死に由来する無の無化作用を受けて、不安、寂寥、虚無などの感情に悩まされることになります。そのように(死に)挑発されて、次の志向対象へと向かう意志をしだいに明確にしていきます。
そのようにして、「生きているかぎり、可能態としての希望が保証されている」といえるのです。つまり自我による生命世界の展開は、明瞭に有限のものですが、しかしながら、内に無限性を潜ませているといえます。
「生きているかぎり無限性を生きる」というのは論理的に矛盾しているように見えますが、矛盾こそが人間の本質であり、可能態としての「生きる無限性」が生み出される理由です。
生命的世界、有限の現象的世界を主宰するのが自我であるのに相応して、人間の心の内なる大自然の中にも心を主宰するものがあると考える合理的理由があります。
その主宰者を、内在する主体と呼んでおきます。
内在する主体は、心全体の主宰者です。
自我は意味を紡ぎ出す役目を持っていますが、主体は、沈黙のうちに心全体を統括しています。
自我が、沈黙する主体の意向を探り当てる方向で世界を展開できるときに、揺るぎない充足感、「これでよいという安心感」が心全体を覆うでしょう。それが沈黙のうちに存在する主体の答えです。自我の仕事への肯定的評価です。
そのような心は、主我が主導性を確保できている自立的な心です。それはいわば自由な心なので、精神が病理性といえるほどの事態に陥ることは考えられません。
そうした主我の育成には、幼い時代に母親に甘える体験を十分にすることが大きな意味を持ちます。
それは内在する主体からの贈り物を、幼い主我が受け止めている姿だからです。
それは、躾の中心にいる母親が(不当な)介入をせずに、従って客我がいまだ未成熟なので、主我が存分に自分の力を楽しむことができているからです。また、それは、内在する主体との関係が純粋に近い形で営まれているので、それを尊重して見守っている母親の態度に大きな意味があります。そのことは、内在する主体との関係で幼い主我が活動することが、もう一方の主体である母親に是認されている意味を持ちます。それは、即ち、母親の愛と信頼とに他ならず、人間関係一般に重要な意味を持つそれらのものに、基礎を与えることでもあるのです。
以上、述べたように、赤ん坊が置かれている心理的状況を推察することから、人間の精神の重要な問題の一端が、垣間見えるように思われます。
それらを列挙すると,以下のようになります。
嬰児は,全なるものの世界から,全ならざる世界への移行を果たさなければならなかったらしいということが第一の要点です。換言すると,赤ん坊は生まれる以前は,全なる世界の住人であったと仮定されます。
母親に絶対的に依存し、全であることを要求しているらしいということから,逆に、母親が全なるものではない予感を持っていると思われるのが第二の要点です。
何らかの不快感にとらわれているときに示す激しい怒りの表出から、赤ん坊が母親を支配しようとしている様子が窺えます。そのことから,「欠けるものがある存在者」であるが故の不安の脅威から、「満たされている存在者」への移行を、「全なるものである母親」に要求しているという推論が成立するように思われます。そして、それと共に、「欠けるものがある存在者」であることを受け入れる準備をしているらしい、と推論することが可能です。
全ではない者が受ける脅威とは,「欠けるものがある存在者」が、既に部分的に、無の無化作用にさらされていることを示していること、その無化作用が存在の全面におよぶことの予感(死の脅威に直面することに他なりません)から来るのであろうということが第三の要点です。それは、母親に見捨てられる恐怖といい換えることができます。
補足 人間の誕生は、自我の誕生です。自我は生を展開する首座にありますが、生はその裏面に死を併せ持つことによって存在可能です。このことから、自我の誕生は二項対立の世界の誕生といえます。事実、心は、自己と他者、男と女、善と悪、愛と憎しみなどなど、いたるところに二項対立があり、その最奥に生と死の対立があります。 そして、自我が終焉を向かえて自己が無に帰するときに、二項対立の世界である現象的世界という舞台の照明が暗転し、唯一性の世界に入るということができます。
また、例えば、「純粋に白い(あるいは純粋に黒い)」ものは現象的実体としては存在しないが、かぎりなく白に近い黒、(あるいはかぎりなく黒に近い白)」は、現象的実体として存在するといえるので、純粋に白い、あるいは純粋に黒いという全なるもの、あるいは無なるものは、単に概念的に存在するだけではなく、現象的実体の内部に含まれている」といえます。
いずれにしても、現象的世界の諸問題を合理的に理解しようとすると、人間的な理解の範疇を超えた超現象的世界のことどもが視界に入ってきます。現象的世界が有限のものであるといっても、内に無限性の性格をも含み持っているので、両者を截然と区分することはできません。従って、超現象的性格のものについても命名し、概念化する必要が出てきます。それは実証性を持たないので、何らかの仮説を設ける以外にはありません。その仮説の作業は、現象的世界についての概念を援用し、かつ命名する以外には方法がありません。
嬰児は母親に「全であること」を要求しつつ,そうではない予感を現実のものとして受け入れていく必要があります。それは全という「満たされている存在者」、あるいは自己完結態ではないという現実を承認することに他なりませんが、そういうことが可能となるためには、それに準じる存在形態を不可欠の要点としているといえます。現実を受け入れるとは、全をあきらめ、不十全に甘んじる心になることに他なりません。
つまり個としての存在であるそれぞれの自己は,「欠けるものがある存在者」として、他者との依存関係を欠かせない要件としています。それによって、他者との望ましい関係が得られれば、「満たされている存在者」に準じること、つまり不十全に甘んじる心になる基礎を得ます。また、更には無限性を帯びた人生を歩みつつ、自己の発展的達成に向かうことを通じて、「満たされている存在者」に限りなく近づくことができます。そのように、「満たされている」心そのものに到達することはできないが、そこへかぎりなく近づくことに甘んじることが、有限の「欠けるものがある存在者」の分であるといえます。そして有限の「欠けるものがある存在者」であるが故に、限りなく有限性を越え、無限性に近づこうとすることが可能であり、そのような意味で人間は無限性を生きているといえます。
自己がそれ自体で完結しているのではなく、いわば自己と他者とに分裂している「欠けるものがある存在者」であって、それが改めて自己と他者との合体によって、「満たされている存在者」に準じるものとなることが可能であるための前提条件は、他者を予め自己の構造(その原基である自我の機構)の内部に含んでいることです。つまり、他者は自己の外部に客観的に存在すると同時に、自己の内部に主観的に存在することによって、自己は他者との関係性において、「満たされている存在者」に近づくことができるのです。恋愛と、それに伴う熱情とは、「満たされている存在者」であることが現実に適えられることはないものの、いわば瞬間的に類体験していると考えることができ、従ってそれは、人間存在がその可能態を内に含んでいることを証明していると考えることができます。
母親とのかかわりを通じて,乳児は自分の幻想的な欲求(生後2ヶ月ほどになると,母子一体の感覚が乳児に芽生えます。その時期,乳児の母親への愛情欲求は絶対的なものであるといわれます)が満たされたり,満たされなかったりしながら,しだいに自分とは別個の他者が存在することを知っていきます。
現実の母親は,乳児がもとめるような絶対的な存在ではないので,乳児の幻想は,始終やむを得ず破られないわけにはいきません。幻想が破られたときに味わう乳児の苦痛は,大変なもののようです。そういうときにはどんなに愛情深い母親も,悪い存在として激しい攻撃を向けられます。ある時期には,乳児はあらゆる人や物を我が物にしようと攻撃的になるのです。場合によっては、悪鬼に殺されるとでも感じるかのように激しく泣き叫ぶことも起こります。そのようにしてしだいに現実を受け入れていくのですが,その過程では激しい苦痛と恐怖を経験しないではすまないということなのでしょう。
この人は本当に自分を守る力を持っているのか,持っているとしても,自分にその力を与える気があるのかといった猜疑や疑惑の(認識ではなく感じ取る)虜になるときに,乳児の全能欲求が反転して,母親は悪いものをもたらす張本人に見え,欲求が満たされたときには,母親は願わしいものを具現する者になって見えるようです。人生の最早期のある時期までは、母親は、そのように良い母親と悪い母親とに分裂した別種の者として存在し、良い母親だけが母親であるという全能欲求が護られます。そしてやがては良い者も悪い者も,おなじ一人の母親として,統合的に捉えていくことができるようになります。絶対者ではない母親は,一貫し,安定した愛情を示しつづけることで,乳児が現実を受け入れていけるように手助けをしてあげなければなりません。
この世に生を受け,自己を形成していくにあたり,人は人生の入り口の段階で最初の,そして最大の関門に直面します。すでに容易ではない試練にさらされているといえます。母親の胎内で安らいでいるある時期までは,胎児は自然と一体です。それが誕生という形で自然から乖離され,自分の力で生きていく使命を負わされたのが人間です。その人間に,人生という難路を旅するために授けられた武器が,自我といわれているものです。自然から乖離されて,人間として人生を旅する第一歩が,どれほど不安に満ちたものか,いうまでもないことです。激しい不安や恐怖や怒りの渦をはらんだ闇夜の中に,人生の黎明が訪れます。自分の力でこの世を生きていく喜び,希望もしだいに芽生えていくことになります。
人生がどれほど過酷なものであるか,たとえばソクラテスが次のような趣旨で述べています。死刑の宣告を受け入れる心境の一端を語った言葉です。
「死は深い眠りと区別をつけ難く,深い眠りに勝る安らかな経験がはたしてあるだろうか」と。
この言葉は,人生に懐疑的というのではなく,死の否定的な意味をもういちど否定しているのだと思いますが,人類の教師ともいわれるソクラテスが,生きることの困難を語っているのが興味深いことです。
生まれる間もなく,過酷な苦痛が待ち構えている宿命のもとにあるのが人間です。それを耐え抜くためには,母親の安定した豊かな愛情による養育が不可欠です。
逆にそこに問題があれば,人生の第一歩にして,将来の多難が早くも予測されるといっても過言ではないでしょう。
人生は一幕の芝居であるといわれることがありますが,このたとえでいえば,人生の早期に台本を書き,演出するのは父親と母親です。そこには両親の願い,考え,感情,価値観などが込められています。成長するにつれ,両親以外の人が意図せずに台本に別の筋を書き加えます。そうした経験を重ね,両親が書いた台本や演出に疑問を持つようになります。そして,やがては自分の手で自分のために台本を書いてみたいと思うようになります。人生を自分の演出のもとにしたがえたいと考えるようになります。これは自然な願いです。
幼い心で考えたことですから,未熟なのは仕方がありません。両親の愛情のあり方に問題がなければ,幼い我が子の未熟な主張を成長の証ととらえ,その主張の中に無視してはならないものがあるのを見逃さないと思います。そういう余裕があれば,ひきつづき子供を正しく指導することができますし,実際にまだまだ指導が必要なのです。自分の手で台本を書きたい,演出したいという意識の芽生えは大切なことなので,それを育てるのは両親の重要な課題です。
心の指導者が,他者から自己自身へと移行する過程では反抗は必至であり,なくてはならないものです。
#2 自律機能と抑圧機能
幼く,未熟な自我の代行を母親が中心となってするに当たり,第一に重要なのは、幼ない自我の自律機能を護ることです。それは乳幼児の感情をコントロールするのではなく、感情を全面的に許容する心の姿勢を貫くことによって得られます。それにつづいて指示や禁止など、感情をコントロールすることで躾をすることになりますが、それは自我の抑圧機能に働きかけることを意味します。
「自我の自律機能」の提唱者であるハルトマンは,この機能を,「自我という生物学的ー心理学的構造体が,超自我,無意識,外界などとの相互的な葛藤,関係性から自由であるべく保証されている」という意味で用いています。 あ また抑圧機能は,フロイトによれば,例えば生物学的な本能のほしいままに任せるわけにはいかないため,などといった自己の防衛策ということになります。
ここではそれらのことをふまえた上で,自律機能を,生の欲動(フロイト)の一切を意識にもたらすものという意味で用いています。そして抑圧機能は,他者への配慮の無意識的態度という意味で用いています。
一例を上げると以下のとおりです。
欲しい物を獲得するのは,自律機能によります。他人の所有になるものを,欲しくても我慢するのは,抑圧機能によります。
従って,自律機能はより生得的であり,抑圧機能は後天的です。後者は,人間存在が他者との関係を必須のものとしていることと密接な関連があり、本能的、欲動的なものとのあいだを調整する役割を担っています。抑圧機能の発動は,他者への配慮,社会性の尊重という意味を持っているのです。従って、躾は抑圧機能の発動を促すことになりますので、たとえば母親が神経質で、注意を与えることが必要以上に多くなると、幼児は、却って身勝手な行動に走ったり、抑制的になって子供らしくなくなったりします。母親は、幼い子には十分に甘えさせることが重要です。それは、幼児が無意識の心の泉から湧き出てくる力を体験していることの邪魔をしない、という意味を持つからです。そしてそれは、幼児が母親に認められている、必要とされている、愛されているという肯定的な感情を育てていく上で重要な意味があります。
心の無意識層から生まれてくる欲動群は、すべて生命的なエネルギーを蓄えています。あらゆる行動は、これらの欲動に促されて可能になります。あらゆる行動には対象があり、これらの欲動は、目的とする対象をおのれのものとして関係づける動因になります。対象を自己化して所有し、それとの関係をいわば傘の骨として、自己の世界を発達させていきます。対象となるものが人の場合は、欲動は愛という性状になります。対象となるのが自己自身であれば、自己愛ということになります。自己愛というものが存在していることが、愛の性状を持つ欲動が自分の心の内部から生起し、自分の心の内部のどこか外的なものへ向かうことを示しています。自己は自己自身との関係でもあるのです。
これらの欲動群がどこから生起してくるのかは謎です。無意識層からには違いありませんが、それは、心の内部にあって我われには理解し得ないところから、という意味になります。従ってそれを生み出し、意識へともたらすものは、人間が意識できる範疇を超えているものによって、というしかありません。
人間であることの証明は、自我にあるといえます。人間は自我に拠って、自己を発展的に展開していくと考えることができます。では、この自我を授与したものは何かということになりますが、それもまた、解き得ない謎です。しかし自我を授与したものと、生命的である欲動を送り出すものとの主体者は同一であると考えるのは、精神の諸現象を統合的に考える上で有意味です。欲動群は生命の源であり、自我は生命を司るものです。欲動群は、自我の自律機能に即して生起し、それを受けて自我は、改めて抑圧機能によって他者との関係に配慮します。自我は、両者を調節し、統合する首座となるものです。
欲動群を送り出すものと、自我を授与したものを、ここでは内在する主体と呼んでおきます。それは自我の拠り所であり、心全体の首座をなすものです。
つまり自我は個々の自己の首座となるものであり、内在する主体は個々の自我の拠り所であると同時に、個々の人間存在を超えた普遍的なものです。それは心の内における無限性を保証するもので、全でもあり無でもあるという性格のものです。
自我の自律機能は,内在する主体との関係性において,欲動群が主体から送り出されてくることに直接関わるものであるのに対して,抑圧機能は多かれ少なかれ(意識的にか無意識的にか)自我の判断機能と密接な関係があります。
自我が自由で自立していれば,状況に応じた適切な判断が可能なので,自己を適切に護り,他者との関係も適切に護るために抑圧機能を発動させることができます。
しかし後の項で述べるように,集合的他者に従属させられている自我の下では,他者への配慮が優先されるので,過剰に抑圧機能を発動させることになります。言葉を換えれば,不当に自律機能を抑圧し,自己を護り,発展させる上で好ましくない心的状況が生まれます。
このような意味で,自律機能よりも抑圧機能の方が強力であるかぎりにおいて,自己は発展的であるよりは閉塞的になります。
心的状況がそのままに置かれると,自己の展開は困難になるので,自己否定の方向に傾くことになると思います。
再びそうした心の閉塞状況を打破するためには,心理的な治療の介入か,あるいは自律機能が自ずから発奮して巻き返しにかかるかすることが必要です。
結局,自我の抑圧機能の本来の役目は,自律機能を護ることにあります。
自律機能は動物一般に通じる自然のものですが,抑圧機能は人間に固有のものです。精神性と社会性とを要求されている人間は,他者の存在を尊重する上で自律機能がもたらしたものに修正を加える必要があります。
動物的な自然の要求と他者への配慮とを理想的に統合するのが,それぞれのあるべき自己の実現であると集約的にいえると思います。
自我はこの二つの主軸の機能を活動させるにあたり,思考,判断等の知性的な機能を駆使することになり,それらが精神性を自己にもたらすことになります。
他者との関係はすこぶる重要であり,取り分け原初の他者である母親は,乳幼児期には絶対依存の対象になるので,特別に重要な他者といえます。母親への絶対依存の関係にある自我の未成熟な時代の乳幼児は,客観世界の展開がまだ始まっていないので,まったくのイメージの世界の住人です。とはいえ客観世界の展開がそれとなくは予感されていないはずはなく,それを勘案すれば母親は絶対者であるのではなく,絶対者であることの要求であり,願望であると考えるべきです。
乳幼児の幻想的絶対者である母親が,実はそうではないかもしれないという予感は,受け入れ難い不安を伴うのではないかと推測されます。
赤ん坊が置かれている心的状況には,絶対性と非絶対性とのあいだの埋めることが出来ない懸隔が避け難く存在しています。その奈落への転落を免れるには,依存の対象である母親が,幻想としてであれ絶対者である必要があります。
この克服不能の懸隔が,赤ん坊をどうしても脅かします。その恐怖は,母親が絶対者ではないかもしれないという疑いがあってこそ生まれるでしょう。
その疑いは,母親が自分を見捨てるかもしれないという恐怖に直結するでしょう。それは,生死のかかった恐怖です。従って人間の根源にある恐怖です。そして,また,他者への不信の起源をなすものでもあると考えられます。
人はよりよく自分である以前に,自己の保全をはかる必要があります。
成人してからは,場合によっては両者の関係が逆転することもあるでしょう。
「肉体の自由は奪われても,精神の自由は渡さない」とか,「身体への拷問より精神的な拷問の方が耐えがたい」とかいわれます。
作家のドストエフスキーは著作の中で,労役刑の苦痛の中でも,Aの場所にある土砂の山をBに運び,再びAに戻し,果てしなくAからBへ,BからAへと無益に移動させつづける刑罰ほど耐え難いものはなかったと述べております。
しかしながら親の保護の下にある年齢では,精神よりも身体の保全の方が優先されて当然です。
そのような意味から,見捨てられる恐怖は,幼い子にとっては精神の問題というより全存在に関わる問題なので,親を怒らせないために自我の抑圧機能を活性化させる,強力な意味を持っていると思われます。
従って,しばしば抑圧機能は自律機能に優先するのです。
しかし「角を矯めて牛を殺す」の喩えのように,抑圧機能が自律機能を護るという本来の使命を超えてそれに優先するのが習いとなると,自己の発展はさまざまに阻害されます。
いずれにしても自律機能が健全に発展していける心の状況にならなければ,人生は「強いられた山登り」になります。
人生は無際限に高く,深い山を登るのに似ています。その時々に遭遇する人生の難所は,いわばその時々の難路です。その都度その難所を切り抜けることに山登りの喜び,希望があるように,置かれた状況がいかに困難であれ,そこに希望の光りの筋を見出して,その状況を克服していくところに人生の喜びがあります。そしてその中心に自我の自律性があります。
希望のない山登りは無意味です。自ら意志してはじめた山登りであれば,必ずそこに希望を見ているはずです。
人生という山登りは,自ら意志して開始されるわけではありません。その意味では強いられたものといっても過言ではないでしょう。
それを改めて自ら意志して,というふうな主体者意識を,まずは母親,そして父親が導き出すべく育てる必要があります。
何事も最初が肝心です。大人びた幼児のように,早すぎる社会性はむしろ弊害があります。抑圧機能を早々と活動させる以前に,努めて好きなようにさせておく(自律機能の発露を喜び,自己の力を知る)ことが,親の愛情というものです。それが十分であれば,この世も捨てたものではないという重要な意味を持ったウォーミングアップになります。
比喩的に登山と希望との関係を人生に当てはめてみると,次のようになります。
エベレストはいかに高い山であっても,それが客観世界のものであるかぎり,征服してしまえばそこで希望は潰えることになります。
その対比でいえば,人生の高山には限りがありません。つまり人生の山登りの山は,客観的ー主観的という性格を持っています。
この主観的性格には無限性があります。つまりこの山は,ここでお仕舞いという終点がありません。
「強いられた山登り」は希望のない山登りです。これほど虚しいものはなく,どこかで絶望するに決まっています。
子供のうちは親に認められ,褒められるという喜び,楽しみがあるので,「強いられた山登り」であっても,我慢をする理由があります。
しかし長じるにつれて,「強いる者」が外なる他者ではなく,内なる他者である集合的他者となると,自律機能が抑圧されつづけるので,人生という山登りは希望のない,強いられたものになります。それは,棒の先に括りつけられた鼻先の人参を追いかける馬のたとえに,どこか似ています。そこにも希望があるといえばあるのでしょうが。
フロイトはその欲動理論において,生と死の二大欲動の存在を仮定しています。生に関しては,その根源的な欲動の存在はうなずけるものです。しかし死については欲動といえるものかに疑問があります。
場合によっては死の衝動が存在しているのは厳然とした事実です。精神科医であれば,誰でも知っていることです。しかしそれが生への欲求とおなじレベルで,対抗的な欲求であることを意味するかどうかは別問題です。
死の衝動は一義的なものではなく,生への欲求が挫折したときに表面化する二義的なものとしては是認できます。
生へのエネルギーは,プラトンが述べているエロス的(身体的なレベルから高度に精神的なレベルにいたるもの)なものであり,それがすなわち生の欲動という大河に即していると考えられます。
別の箇所で述べた「表の自我」は,この生の大河の首座にあるものと考えることができます。従ってここでいう自我の自律機能は,この大河に即して機能する方向性を持っており,内発的であるが故にエネルギーを抱え持っている,といい換えることができます。
生の欲動というのは無目的に無闇に何らかの欲動が生起してくるというものではなく,一定の方向性があると考えるのが合理的です。
その方向性とは,心全体の主体(内在する主体)と生の大河の主体である自我とを軸にして,内在する主体が自我に向けて欲動を送り出してくるといったもので,それがここでいう自我の自律性です。
それは内発的で,心の自然な発露といえるもので,つまり生(エロス)のエネルギーをもたらすものです。
動物には一般に,このような内発的なエネルギーの発露があると考えられますが,人間には,この心の自然な発露に’待ったをかける’抑圧機能が備わっているのが動物一般と違うところです。
本能に従う動物の場合は,例えば縄張りを守るために生死をかけて戦うところを,人間は自我に内属する抑圧機能によって,他者の立場を配慮,尊重するのです。
繰り返し述べていることですが,人間の証明は自我にあります。人間には社会性と精神性とがあり,それらの根拠が自律機能と抑圧機能とにあり,それらが適正に運用されることで適正な自己の展開が可能となります。
動物一般は,いわば自然そのものを生きているのに対して,人間は自我によって,自然そのものを生きつつも,しかしながら自然から乖離している存在であるという特徴を持っています。
それは人間には克服不能の矛盾ですが,人間がその存在の根本において,あるいは存在構造として,そうした矛盾を抱え持っていることが特徴であり,それが人生の苦悩と希望との源泉でもあります。
このように,自我が生の有限の世界の主宰者でありながら,自我機構が存在する由来が自我を超えたもの,つまり無限の世界のものという性格でもあるということは,人間の存在構造は,「有限であり,しかしながら無限性の性格をも合わせ持っているという矛盾を内包させている」ということになります。
人間が,この甚だしく錯綜し,解き難い世界の住人であることが,人生のさ中で迷子のようになったり,絶望したり,希望を見出したりする理由です。
人生は希望に満ちているといえば安易すぎるいい方でしょうが,「人生は克服不能の高さと深さとを持つ山に登るようなものである。だからこそ希望は常にあり得る」というのは真実ではないでしょうか。
身近にいるかけがえのない人の死は,痛恨の極みでしょう。
我われ人間への要求,「いかに生きるか?」という問いは,しかしながらこのような状況でさえ,「そこから希望の光を見出せ」と要求しているように見えます。その難問の前に生きる希望を見出せないでいるのはもっともであるとしても,「立ちはだかる目前の絶壁」を登らないわけにはいかないのが人生です。
それは,「いまは無理だが,そのうちに登ってみせる」ということになるのでしょう。そう考えるとき,既にかすかであっても希望が見えているはずです。そして,’そのうち’がやって来たときには,そそり立っていた絶壁は,より穏やかな勾配に変わっているに違いありません。
究極の課題は,「死について希望を見出す」ということになるのかもしれません。生を生きる人間には,死は最大の難問です。死はすべてを無意味化しかねないものです。しかし,いま述べたように,この解き難い問いがあるからこそ,可能態としての希望の光が絶えることがないというのは確かでしょう。
人間が自我によって自然から乖離し,独自の途を進む宿命の下にありながら,自然に内包されたものでもあるために,自然の無化作用の脅威を受けています。
自我が自己の展開の主宰者であることは,他者との関係を不可欠のものとすることで成り立っているのは,その脅威に対抗する意味があると思われます。
抑圧機能は,エロス的エネルギーの源泉である自律機能の発動を抑圧します。それは「生のエネルギー」を「死のエネルギー」に変換する意味を持ちます。
他者との関係を不可欠の前提としている自己の存在は,こうしたエネルギーの変換を避けることができません。
変換されたエネルギーは,喜び,満足をもたらすものから,怒りをもたらすものになります。
死の衝動は,内向した怒りのをエネルギーの強さを物語っています。
自我は二分化して機能し,そのように現象を形成します。
自律と抑圧もその一つです。
自我によって,人生は喜びを追求します。しかし,怒りを背後に隠し持たない喜びはありません。
前章で取り上げた小学校2年の男子の例です。
少年は,はきはきと物をいい,素直な性格の子です。その年頃らしい可愛さも持っています。
少年にはチックがあります。通学路で,怖い男になにかされるのではないかという恐怖があります。学校は友達がたくさんいるし,楽しいそうです。しかしこのごろ学校に行きたくないといいます。不意に胸のあたりがもやもやして気持ちが悪くなるからです。
父親は職人です。野球が上手です。そういう父親をかっこいいと思っています。将来は父親とおなじ仕事もしたいが,それよりも整体士になりたいそうです。父親や母親の身体を楽にさせてやりたいのです。少年も野球チームに入っています。もと父親が入っていたのとおなじチームです。「君は親孝行をしたい,よい子なんだね」というと,「そうだよ,よい子なんだよ」と答えます。しかしよい子の心の底には,それとは矛盾した激しいものが渦巻いています。
最近見たという次の夢がそれを物語っています。
人間がロボットを作っている。うまくいかなくて爆発しそう。怖いので逃げた。
父親は,「別に怖くないじゃないか」といったそうですが,少年には怖い夢でした。
ロボットにされそうなのは少年自身です。ロボットに仕立てようとしているのは両親でしょう。爆発しかねないほどの怒りがたまっているようです。爆発するのは少年にとっては,勿論恐ろしいことです。大好きな父親や母親をひどい目に合わせてしまうからですし,どんな反撃をされるかも分かりません。自分の心が破壊されてしまう恐怖もあります。
少年には1歳の弟がいます。可愛い弟だよと彼はいいます。その言葉に嘘はありません。彼は大変素直で,率直な性格に見えるのです。当然のことながら,母親は弟にかかり切りです。弟が寝ると,「起きると困るから,外に行ってなさい」といわれます。祖父母が近くに住んでいて,「泊まりに行ってきなさい」といわれることがあります。それをいわれると不安になります。学校に行きたくないと言い出したのも,母親の姿を見ていないと不安にかられるからでもあるようです。
この不安は,少年の年齢からすると理解し難いものです。客観的に見て,母親が少年を捨ててしまうことは考えられません。少年にもそれは分かっています。
そうすると母親の側に絶えずいなければ,母親が自分の前から姿を消す(捨てる)のではないかという不安は,心理的なものに違いありません。ということは,少年は,無意識的な心によって脅かされていると考えてよいでしょう。つまり想起できないほどに強い恐怖体験があったか,あるいは記憶をたどるのが不可能な早期(誕生後,自我の活動が未成熟な時期)に,何らかの恐怖をもたらすエピソ-ドがあったかということになると思います。
見捨てられる恐怖に怯える少年の自我は,自分の意志を押さえてでも,両親に忠実な子になりなさいというイメージの支配を受けています。それに伴って,親孝行をするよい子でなければ,愛される資格もないし,価値を認められることもないという恐怖心にかられているようです。
少年が求めているのは,分け隔てのない安定した愛情です。両親の思いはともかく,チック等の”症状”は,少年の心の沼から立ち上がってくる叫びでもあるのです。少年の自我が両親の支配から脱するためには,夢に現われている爆発しそうな怒りに,言葉を与えることができるようにならなければなりません。それを助けるのが治療者です。治療者の介入と援助がなければ困難な心の作業です。そして,また,子供の幼さを考えると,それは両親,とりわけ母親の協力なくしては難しいテーマです。
幼い子なので女性カウンセラーにも協力してもらうことになり,診療が開始されました。本人に起こっていると思われることを母親に説明し,今後の方針を伝えました。母親は涙ながらに,「私が怒りすぎたものですから・・・」と問題を受け止めてくれました。
5回ほど面接を重ねたところで,母親の伝言が入りました。子供の習い事の関係で,次回の予約は取り消したい,また連絡するということでした。相談ではなく通告です。母親の不信を買ったとは思えない状況です。カウンセラーは50分ほどの時間を空けて待っているのですが,あまりにもあっさりしています。習い事以上に重要視してもらえなかったのは残念です。母親のセンスに不安を覚えることでもあります。子供はその母親の指導を受けなければならず,現に指導のまずさが,大きな怒りを蓄積させ,恐怖の虜にさせてしまっているのが問題なのです。特別な事情があるのかもしれませんが,この子が心を回復させるまで,母親が忍耐強く診療に協力できるのか,気になります。
この母親の場合はともかく,一般的に,親の”ちょっとした”配慮の欠落,子供の心への鈍感などが積み重なって,子供の自我の形成によからぬ影響を与えるのは論を待たないでしょう。そういうことが起こるのは,親の側の盲点でもあると思います。自然な心でさえいれば,どんな親にでも気がついて訂正する機会はいくらでもあるだろうと思います。それを考えると,親の側の盲点が意味するものは,恐らく親自身が,自然な自我の形成を歪められた生育過程の下にあったということだろうと思います。その影響で硬直した自我が,哀しみと怒りをたたえて,子供に対して独善的な構えを取るのです。それは当然,固執的になり,優しさとは無縁のものになるでしょう。親自身がその親から蒙ってきた有形無形の被害的なものを背景に,子を相手に復讐をしている趣さえどこか感じ取られる場合もあります。自分が不幸だったという思いがあれば,子供の幸福を無条件に望むのが,しばしば難しくなります。子の側でいえば,意識するかしないかは別としても,当然,不満,怒りがたまる理由になり,その処理に苦しむことになるのです。
まことに人は人によって,自然の心から遠ざけられるのです。
このように見てくると,少年の自我の形成は相当に歪められていると考えざるを得ないと思います。
集約していえば,親との関係で少年は,見捨てられる恐怖に支配されています。そのために少年の自我は抑圧機能を過度に作動させつづけるしかありません。それに伴い潜行する怒りのエネルギーが勢力を強めていきます。自我はそのために自縄自縛に陥る一方です。
母(父)と子の関係は,特に子供が幼いほど,同盟関係にある強国(P)と弱小国(S)のそれに似ています。
PとSは同盟を結んでその他の国(H)と外交交渉をし,あるいは戦います。そのかぎりでSにとってPは心強い存在です。
しかしPとSは対等ではありません。Pがよほど大らかであっても,自国の利益を優先させるのは自明でしょう。
このことに先ほどの用語を当てはめていえば,PとSとの自律機能と抑圧機能の関係は,Pは前者に偏り,Sは後者に偏ることになります。
P国の安定はS国の犠牲の上に成り立っているのだが,S国の安定のためにはP国の力を必要としているので,国王は自国が不利益を蒙っているとは考えない・・・S国は国民の不満を黙らせることでP国との友好を維持できる・・・不利益を蒙っているのを知っているのは,S国の市民たち(C)である等々ということになります。。
事例の少年にこれを当てはめると,S国王は少年の自我,P国は母(父)親で。S国王は善政を敷きたいと願いつつ,P国に従わなければ国が成り立たないので,涙を飲んで不満分子であるCたち(自律機能によるもの)を地下牢に幽閉(抑圧機能による)しているということになります。
横暴なPに依存するSは,国王として自立的でないので,意識の地下から突き上げてくるCの抗議の気配に脅かされ,ますますPに取りすがろうとします。Pはそれを疎ましく思い,Pは見捨てられまいとして更に取りすがろうとします。
Cの怒りは,無力な国王のために国づくりが怪しくされているS国を破壊しかねない(ロボットが爆発する)ほどですし,S国王を恐怖で痙攣させてもいる(チック)と考えることができます。また,無力な国王を捕捉する(暴漢に襲われ,拉致される恐怖)たくらみもあるようです。そしてその怒りをP国に察知されると見放される,という恐怖(母親の側を離れることができない)も強いようです。
#3 内なる他者
自己の存在にとって,他者の存在は欠かせない構成要件です。
それは自己の存在構造の内に他者が含まれていることを示しています。そしてそのことは,自己と他者はそれぞれに独立しつつ,相互に絶対依存の関係にもあることを意味しています。
精神医学は,人間関係の学であるといわれることがあるように,人間関係は重要です。それぞれの自己が他者と絶対依存の関係にあることは,ほぼ必然的に利害の上で矛盾,葛藤が生じる理由になります。
他者の存在は有り難く,多大の恩恵を受ける一方で,少なからず迷惑で,不利益を蒙ることになるのです。従って対人関係は,しばしば人を大いに悩ませ,時によっては心の病理現象を惹き起こす要因にもなります。
それらのことは,以上に述べた理由,自我に拠る人間に特有の解き難い矛盾に起因するといえます。
結論的にいえばこのように考えることができますが,しかしながら,人間嫌いや,孤独を好むもの,ジャングルに置き去りにされた旧兵士,動物に育てられた子供などなど,いわゆる人間関係と無縁に等しい境遇で生活している人もないわけではありません。
また例えば人と猫や犬との関係,あるいは猫同士,犬同士の関係,あるいは未知の異星人と遭遇したとしてそれとの関係などなどは,人間同士の関係と質的な相違はあるのかといった問題があるかと思います。
人間の証明は自我にあると述べましたが,犬や猫,あるいはチンパンジーに,自我に類するものはないのかという問いもあって当然でしょう。
ある女性(A)は,「ニュースなどの報道で,人が殺されたと見聞きしても何とも思わないが,動物が虐待されたときは許せない気持ちになる」といいます。
このことは人間には二心があるが,動物にはないことに関連しています。その意味では動物は純粋であり,悪の性格を持たない(罪がない)のです。
これを敷衍すると,悪は善と裏表の関係にあり,つまり自我に拠る人間の二心の問題であるということになります。
自己と他者とが絶対依存の関係にあるということは,心が二分割されていることに通じます。
つまり自己が存在するためには他者の存在が不可欠であるということは,男と女,愛と憎しみ,善と悪,正義と不義,表と裏,本音と建前,全と無,生と死等々とおなじように,全一なるものを自我が二分割して捉えるということを示しております。それが自我の一大特徴なのです。
Aさんは母親と二人で暮らしていますが,母親は重い悩みを持っているAさんに関心を示しません。人間関係に疲れ果てるAさんは,かつては職場に向かうのが容易なことではありませんでした。しかし仕事をしないでいると,母親は冷淡な態度になります。誰それとのことでの悩みを聞いて欲しくても,相手方の立場でAさんが批判されます。
そういう母親に対して,Aさんも批判的ないい方になりがちでした。
しかし,あるときAさんが母親を行楽地に誘い,そのときの様子を報告するAさんの表情には,ふだんは見せない明るさがありました。
その様子から,母親への日ごろの怒りは,Aさんが母親に認められたい,愛されたい心と裏腹の関係にあるのが分かります。
Aさんは乗馬の練習をしています。「馬さんに会いに行く」のは,何よりの楽しみです。
Aさんにとって,母親と馬とのそれぞれの関係の違いは,といえば奇妙な比較ともいえますが,結論的にいえば,前者には二心があり後者にはそれがないことといえます。
それを前提にいえば,Aさんが人間を憎むのは,人間(自己および他者)を愛したいがためであり,他者から愛されたいがためであると結論づけられるでしょう。また人間への正義の要求が満たされていないために,人間の悪に過敏であるともいえます。
一方,動物との関係では,動物には二心がないので,彼らを愛らしいと感じる心は純一であり,人間を襲う熊は悪ではないのです。むしろ熊を怒らせた人間の方に悪があることになります。
この比較から,自己と他者との関係と,人と動物との関係とのあいだには,決定的な違いがあるのは明らかです。
Bさんは不妊治療も受けましたが,子供がありません。それで養子(C女)をもらうことになりました。その数ヶ月後,実家が改築された折に両親に請われて同居することになりました。しかしBさんは,もともと両親に対して屈折した心を持っています。
C女はみんなに可愛がられています。Bさんは,可愛がるだけではいけないと思っているので厳しくもします。いつかC女はBさんになつかなくなってしまいました。
Bさんは母性に疑問も持っています。C女を可愛いと思えないのです。
両親は,C女を可愛がることのどこがいけないのかと,Bさんの不満,疑問を理解せず,受けつけません。
この問題はさまざまに深刻です。C女はペットになっているからです。養母であるBさんが両親に対して気が弱いだけではなく,養女に愛情を持てないからです。
この状況で,本気で養女に責任を持つ気があれば,両親の家から出る覚悟がいると思います。「私が母親なのだ,私が責任を持って育てる」という覚悟がBさんには必要です。
ペットであれば,家族のみんなが単純に可愛がってやればよいのです。
しかし(人間の)赤ん坊であれば,躾が要ります。
この両者を較べてみると,動物と人間との心の在りようの違いが見えてきます。
つまり動物にも心があると仮定すると,それは単一のもので,人間のそれは,いわば二心であるということです。
動物は可愛がるとなつきます。なつかれると悪い気はしません。飼い主が望む通りに,ほぼ応えてくれます。だからこそペットなのです。その心の状況は,母親が赤ん坊にしてあげ,赤ん坊が母親にそのお返しをするという状況に似ています。
どうやらペットを可愛がる人は,母親と赤ん坊との蜜月時代の心を感じ取っているように見えます。
自我の発達が未成熟な赤ん坊は,動物に似て二心がありません。
母性は赤ん坊の単一の心を包み込む心性であるといえます。
母性を感じられないというBさんは,養女が(Bさんの)両親に可愛がられているのを見て,嫉妬しているともいいます。このことはBさんが,幼い時代に両親にうまく甘えられなかった何らかの心的事情があったことを示していると思います。
つまりBさんが幼女を包み込む心を持てないのは,幼い時代のBさん自身が,思うようには母親に甘えられなかったからで,未済の感情があるのだろうということです。
ペットが人の心を癒すのは,甘えたい,甘えてほしいという心の葛藤をなぐさめてくれるからのように思われます。
母親が赤ん坊に甘えてほしい,甘えさせてあげたいと思うのは,母親自身が甘えたい心を持っているからに違いありません。仮に甘えたい心が充足しきっていれば(現実にはあり得ません),甘えさせてあげたいなどとは思わないでしょう。赤ん坊に甘えられて仕合せな気分でいる母親は,部分的に自分自身が赤ん坊の心でそれを分かち合っていると思われます。
赤ん坊が甘えるのをわずらわしいと感じる母親は,自分自身が幼いころに甘えを極端に封じられていた可能性があります。そういう心的状況では,甘えるという生へのエネルギーが怒りのエネルギーに変換されます。内向する怒りと共に,甘えたい心が意識の地下に封じ込められていると,「甘えたいー甘えさせてあげたい」という心の流れが阻まれてしまいます。
赤ん坊は動物に似て単一の心の状態であるとはいえ,やがて成長して二心の持ち主になるのが分かっているのが動物と違うところです。
そこにペットは可愛がることができても,母性が湧かない心の事情があると思われます。
躾は,単に可愛がるだけでは済まないことになります。
ペットのように扱われた子は,自分の責任において行動する主体者意識が育ちません。
結局,二心は自我の自律機能と抑圧機能に関連します。
#4 自我の傀儡化
自我の活動は意識の活動に他なりませんが,両者の関係は発電機と電気の関係に似ています。
自我は何もの(何ごと)かとの関係において機能します。それは意識は何もの(何ごと)かについての意識である,というのとおなじ意味になります。
自我は意識活動の中心であり,根拠です。何ものかについての意識であるというとき,その何ものかは自我との関係における対象ということになります。
これらの一切の対象との全関係を統合する位置にあるのが自我であり,統合された全関係が自己であるということになります。
意識がとらえた何ものかについて,統合された全関係に即して,合理的な意味の連鎖を探り当てる知的作業も自我の仕事です。
生後間もないころは,自我は組織体として未分化で,機能的に未熟です。
それを補う役目を,母親(そして父親)を中心とした,重要な関わりを持つ大人たちが負っています。
乳児の自我が最初にする重要な仕事の一つは,「よい乳房」と「わるい乳房」(メラニー・クライン)の存在に関して進められると考えられます。
赤ちゃんがお腹を空かしてむずかっているのを母親が的確に察知し,授乳することで赤ん坊が満足できれば,即ちそれは「よい乳房」です。
母親が何らかの事情で機敏な行動ができなかったり,母乳の出がわるかったりすると,それは「わるい乳房」になります
成熟した自我であれば,空腹を感じたときにどうするかを知っています。つまり自分の意志で空腹を満たす(必要なものを自分で獲りにいく)ことができます。
自我が未熟な赤ん坊は,自分から「よい乳房」を獲りに行くことができません。母親がそれを助けることになります。
自他の弁別がまだついていない赤ん坊にとっては,母親は自己の一部です。言葉を換えれば,この時期の赤ん坊は主観ー客観の融合した世界の住人です。そこでは全てが思い通りに運ばれなければならないのです。つまり万能感が支配する自己愛の世界の住人でもあります。
「よい乳房」がそこにあるとき,それは赤ん坊が魔法で呼び出したように,望みどおりに存在するので,万能感が満たされ,自己愛が満たされることになります。
そして「わるい乳房」によって赤ん坊の万能感と自己愛とが傷つくのです。
あるときは「よい乳房」によって満たされ,あるときは「わるい乳房」によって傷つけられることが,やがて自他の弁別がつきはじめることに重要な意味を持ちます。
そもそも自我が未熟であるとはいえ,「よい」と「わるい」とに二極分化していることが,赤ん坊の自我が活動している証拠です。混沌とした主観的世界にありながらも,他者の存在,客観的なものの存在が姿を現し始めていることの証なのです。
「よい」の’一極化’がいわば赤ん坊の理想でしょうが,「よい」と「わるい」との二極化が避け難いのがこの世の原理と知るのが,’自我に拠って生きる’のを受け入れることに通じます。
「わるい乳房」の存在は,万能感や自己愛に翳りをもたらします。そして,それは全的には肯定されていないという根源的な恐怖を生み出す理由になり,投げ出されたもの,という被害感の起源にもなるでしょう。そして,また,それは万能感や自己愛が完璧ではないことを受け入れるしかなく,自己の一部であった母親が,客観的に外界に存在する他者であることを自覚し,受け入れるしかないことを促しています。
自己意識は,次のような心の動的なプロセスを受け入れ,それに即することによって形成されていくと考えられます。
万能感と自己愛とを完璧に保証するはずのものであるがために,絶対的依存の対象であった母親は,自己に内属しているのでなければならなかった。しかしそのことに疑問があるので,繰り返し母親を支配しようと試みる必要があった。そういうことを必要としたこと自体が,既に問題を明らかにしているのだが,やがて,母親を支配し切れないことが明白になった。
支配し切れない以上,母親は相対的依存の対象に過ぎない。そしてそれは,自己に内属する存在ではなく,外部に,独立して存在するものであることを示している。つまり母親は,他者であると認め,受け入れるしかないことである。
そうであれば,結局は自己を肯定する根本原理は自己自身にしかないことになる。そして,そこにも絶対性はないので,繰り返し自己を自己自身にもたらすのが,自己形成と自己の自立化の原理になる。
このように生まれて間もないあいだの赤ん坊は,母親との一体化の中にある主観世界の住人です。そしてやがて母子分離を経験する時がやってきます。
別の見方をすれば,母親に絶対的に依存している赤ん坊は,やがて相対的依存の関係に移行していきます。それは母親なる他者が自己に内属するのではなく,自己とは別個に独立した外部的な存在であると認識していくことを示しています。
(更に別ないい方をすれば,いうならば一者の世界のものが,既にそうではない世界のものに変貌を遂げようとしている,ということもできそうです)
母子の一体化現象と呼ぶとき,あるいは絶対的依存というとき,そこには両者の分離が内包されています。つまりそこには動的,発展的な分離の動きが既に予定されているのです。
赤ん坊は,心のこの動きを単純に喜ぶことはできません。
母子の分離の気配を感じ取るときに,その動きに抵抗しようとしているように見えます。自分が魔法使いのように,母親を思い通りに動かそうとしているように見えます。
それがうまくいったときに,例えば「よい乳房」を手に入れることができたのです。しかし,「わるい乳房」が繰り返し表れます。
繰り返し,繰り返し,「よい乳房」が手に入ることを確かめながら,その合間に,これもまた繰り返し味合わされる「わるい乳房」の,不愉快で不安な存在に悩まされ,脅かされながら,やがてそれへの対処の仕方を覚えます。
つまり,赤ん坊にとって,本来は「よい乳房」のみが存在しているべきなのです。それが万能感の本来あるべき姿です。それが自己愛の本来の形です。
従って,不愉快な「わるい乳房」の存在は,万能感や自己愛に翳りを与え,それらを揺るがすものです。それは’一者の世界’にはあるまじきもの,であるに違いありません。
やがて赤ん坊は,一つの結節点に立ち会うことになり,未知の経験をすることになります。
それが他者の発見です。既に一者の世界の住人ではないことの発見です。
その他者は,よい乳房とわるい乳房の提供者です。
他者であれば,「よい」のも「わるい」のも,その理由が外部にあるので,気分がよくても,わるくても我慢しなければなりません。自分は既に万能の世界のものではなく,自己愛だけの世界のものではなく,他者愛と共存,共立させなければならないと感じ始める時が訪れるのです。
’一者の世界’といういい方をあえてしましたが,このような形而上学的なものを,精神医学という学問を論じる場所に持ち込むのは言語道断といわれる向きがあると思います。
確かに,論のための論であれば,これは虚しい議論になります。
しかし,ここでは精神科の病理現象の蓄積の上に立って問題を整理し,統合的に理解する可能性を探ることが唯一の関心事です。精神病理をどう理解し,治療的に有効な形でどう還元するかがすべてです。
「客観的な学問の体裁」が求められているのはいうまでもありません。
その客観性の理想的なモデルは自然科学にあります。しかしそれを心の現象に適応しようとすれば,いわば穴だらけになるのは避けようがありません。それを徹底排除して,自然科学に準じようとすれば,脳の科学になるでしょう。
心理的な議論では,幾つかの里程標のような事実問題があり,それら相互の間隙を繋ぐには推論以外にはありません。そしてその「科学性」とは,その推論の説得性,合理性にあります。
人間存在の問題は,生誕以前の世界と死後の世界とを含んでいます。これらの巨大な謎は,自然科学の手に負えるものではないのは論を俟ちません。
しかしそれらは厳然とした人間の事実問題です。
この超え難い謎は,人間の心理を’科学的に’理解しようとするときに立ち会う謎(里程標のような現象的諸事実のあいだに横たわる間隙,自然科学的な光が及ばない深淵)と連関するものです。ですからそれらのすべてを仮説をもって繋がなければ,統合的で合理的な理解を得ることはできません。
形而上学的であるといえば,人間存在はそうしたものなのです。
人間存在にかぎりませんが,問題は統合的な視野の下に置かなければ,それを問うことはできません。
この問題を,自我に内属する理性の支配下に置くことは不可能です。いわば人間の手に負えないものを学問的に理解しようとすれば,仮設を用いて,我われにも了解可能な一種の体系を仕立て上げる以外になく,その有用性は,治療的な還元によって確かめられることになります。
誕生以前の自我の存在様態は永遠の謎です。
一般に目下の謎を解いていくのは,理性とか知性などと呼ばれる能力によってですが,それらは自我に内属するものです。自我は自我自身について対象化することはできず,従って自我自身を問うことはできません。
換言すると,現象的世界に現れている現象的実体に関してはこれらの能力の範疇にありますが,自我そのものの存在様態,存在の由来などは,その能力の範疇外です。ということは自我の力が及ぶかぎりの現象的世界が有限界であるのに対して,及び得ない世界は無限界ということになります。それを自然界といい換えることができます。
自我は,以上の意味で,自然から乖離されたものであると考えることは許されると思います。つまり自我は自然に内属しながら,自然そのものではなくなったものという性格を持っています。自然そのものは全なるものであり,無限であり,無であり,それ自体で自足するものです。それらは自我に拠る人間の能力では捉え得ないものです。
その上で改めて自然を対象化することによって,自我は自然を我が物にすることが可能ですが,そのように対象化したものは,もはや自然そのものとはかけ離れたものです。人間である我々の前には,自然そのものは決して姿を表すことはありません。人間にできることは自然を限定化し,対象化することですが,その心的な作業は自我に拠ります。そして全である自然と,限定的な力をしか持たない自我とは,いうまでもありませんが対等の関係ではありません。
自我が捉え,自己のものとしようとする試みは,全であり無である自然の前に,絶えず無化の脅威にさらされているといえます。
とりわけ生まれて間もない未熟な自我は,「世界を自己化する」力はとうていありません。
人生の最早期の乳児の精神世界を,イギリスの児童精神科医であるメラニー・クラインは,妄想的,分裂的であると特徴づけました。クラインは,母親の乳房との関係を軸に,乳児が精神的な世界を切り開いていく煩悶,苦痛と至福,満足とのあいだを激しく揺れ動く心性について詳しく論じております。目の前に現れる母親をはじめ,さまざまな対象を統合的に捉えていくのは自我の役目ですが,生まれて間もない自我は,自然による無化作用という乱気流にもまれて,一貫した姿勢をとれません。
それを保護するのが,なによりも母親の愛情ということになりますが,母親の力でも補い切れないものがあります。しかしながら,赤ん坊のこうした激しい心の混乱も自然のプロセスの中にあります。母親にもまた,そういう赤ん坊にどう対処したらよいか,自然の力とでもいうべきものがあると思います。ですから良い母親というのは,言葉では捉え難い自然の情愛深さを,誰に教えられたわけではなくても身につけている人なのでしょう。このような意味での良い母親の保護の下であれば,多かれ少なかれ幼い自我が傷つけられるのは避け難いにしても,やがては自然的なプロセスの流れとして,赤ん坊の自我は統合機能を整えていくことになります。
このような流れの中にあって,赤ん坊の側に持って生まれた過敏なものがあれば,あるいは母親の側に何らかの不都合があれば,混乱は更に深みを増すことにもなるでしょう。この場合は母親の保護を十分に受けられず,最も重要な立場にある母親によって傷つけられ,混乱させられるに等しいことになります。
もともと傷つき易く,混乱しがちな赤ん坊の自我が,いわば不自然に母親によって何らかの恐怖体験をしたとすると,自我は自然のプロセスに従うことができず,身を避けるために生まれて初めての対人的な策を弄することになります。つまり,母親の自我の傀儡と化すことによって身を守り,心の自然を犠牲にするのです。その動機は恐怖と不信であったにもかかわらず,そうしたものを緩和するために,母親が大好きという偽装を凝らすことになる場合があります。疑いを持つことは危険なので,あくまでも友好の姿勢で取り入ろうとするのです。しかし,その根にある恐怖と不信は,対人不信と自己不信の核になるでしょう。その程度がはなはだしければ,将来,妄想的でさえある猜疑心に囚われる下地となるかもしれません。
自我は自己を形成していく中核ですが,いま述べたように,乳幼児の段階では母親の自我がその代理を勤めることになります。母親の愛情により至福の感情に浸されれば,赤ん坊の自我は母親のそれに助けられる形で,自己愛と他者愛とを同時に経験することになり,自我の成長に寄与することになるでしょう。また母親に恐怖を感じたとすると,怒りをもって応じるかもしれません。それが母親の愛情を改めて引き出す結果をもたらすことになれば,赤ん坊は,やはり自我の成長となる礎を得るかもしれません。しかし,恐怖の度が強ければ,赤ん坊の自我は母親のそれにしがみつき,恐怖をもたらしたものを懐柔しようとすることもあるでしょう。それらは本能的な自我の動きだろうと思いますが,後々の対人的な駆け引きにつながるものでもあると思われます。
このように(赤ん坊の)自己なる存在構造には,母なる他者が密接不可分に入り込んでおります。
そのようなことが可能であるのは,その存在構造に内なる他者が(構造的に)含まれているからであろうと想定されます。そして,また,自己の存在構造は,原基としての自我の機構に組み込まれいると考えられます。
生まれて間もない赤ん坊は,自他の区別がつきません。そして客観的には厳然として他者が存在します。赤ん坊は外なる他者である母親の世話を受けつつ,やがて自他の区別がつくようになります。
それに応じて外なる他者である母親とは別に,自己の内部に他者が生起してくると考えられます。つまり自我の機構に組み込まれていた自己の存在構造としてある内なる他者が,外なる他者である母親との関係に刺激されて機能を顕かにしていくと思われます。
この過程で重要なのは,境界機能です。自我に内属すると仮定される境界機能が,自己の内なる他者の生起に寄与していると思われます。
つまりこの意味での自己の内なる自己と,内なる他者とは関連しつつ独立しており,両者のあいだは境界機能によって隔てられていると仮定されます。
自我は全であり無である自然から乖離されたものです。自我に拠る光の世界は,無限定な闇に包囲された限定的なものです。人間はそれぞれの自己として存在し,意識の光によって世界を現象させます。その世界は意識と共にあり,意識の消滅と共に消滅します。そのような現象的な世界の演出者であり,住人であるそれぞれの自我は,包囲している闇といずれは一体化する宿命の下にあります。そしてそのときに限定的であった自己ならびにその世界は,無限の中に溶出します。その意味では,自己は自己自身の中に’全’を含んでいます。自己はそれだけでは全体の半分に過ぎず,他の半分を内に含むことにより’全’となるのです。そのように他者を自己の構造の中に,内なる自己として包含しています。そして同様に外部にある’半分に過ぎない’他人の内部に,他なる自己を包含しているのです。それは現実的な他者との関係にとどまらず,心的現実としてさまざまに現象されているのです。
自己と他者の関係は大変重要ですが,それはいま述べたような理由によるものです。ですから,たとえ嫌人癖が甚だしく,人里はなれて孤独に生活する人であっても,他者との関係から無縁になることはできません。
生まれたばかりの自然的な傷つき易い自我は,最重要の他者である母親が,基本的に自我の護り手であったか否かということに大きく左右されることになります。
自我の重要な機能の一つは自律性です。樹木の種が大地に落ち,しっかりと根を下ろせば,あとは種に組み込まれた自律性によって成長していくのとおなじように,自我の自律性の根は,母親の保護を受けて大地に根を下ろすことができるでしょう。根が伸びていくのは,心の大地である無意識の領域です。その領域の主体にまで根がおよび,しっかりとした接触が図られれば,自我の自律性はそれなりに健全性を保つことができるものと思われます。そのようにして,自己がおのずから自分らしい自己に向けて,成長していくことができるのだろうと考えられます。
逆に,原初の他者である母親によって自我が護られず,自律性が混乱させられる体験をすれば,自我の健全な自然性が傷つけられることになるのでしょう。
人間にとって他者が重要なのは,自然的な自我の機能を護る上で,他者が絶対的な前提となっているということです。しかし他者は,むしろしばしば脅威になります。絶対に必要な存在であることは自然的な要請ですが,現実の外なる他者は,むしろこの自然的なものに脅威を与えるものでもあります。
従って人間の最も大きな矛盾と困難は,自我の自然性を他者との関係でいかに護っていくかということにあり,それはしばしば難問であるということです。
母親への恐怖から,いわば母親の自我の傀儡と化した幼いそれは,自我本来の善導する姿勢から,一転して過酷なものに転身します。この幼い自我は,母親を怒らせる元凶が甘える心と認識するので,甘える心を片端から捉えて無意識の牢屋に封じ込める途をとることになるのです。そのようにして母親に媚を売り,よい子を無意識的に演出することで,母親の怒りをかわすことができると考えるのです。そして甘える心を封じたままでいるので,その後の心の成長に大きな難点を残すことになります。
なによりも自我が,傀儡化することによって,その自律性を犠牲にしたことが問題です。母なる他者への恐怖によって乱された自我の混乱は,長じて,一般的に他者に対して恐怖心や不信感を抱き易くなる可能性がありますし(不登校や対人恐怖症などの心の障害に関連します),自己不信のもとにもなるでしょう。更にそうした不安定な他者への感情のまま,他者へ依存しないではいられないということにもなります。何歳になっても,年齢とは無関係に依存心が心の大勢を占めることになるかもしれません。そして,それに相応して無意識の領域に,先の例に即していえば,「甘えられなかった分身たち」を抱え込むことになります。この分身たちは,悲しみ,虚しさ,恨み,怒りなどと共にあるでしょう。そして表の自我が生きる方向に向かうべく機能する性格を持つのに対して,この自我に受け入れを拒否された分身たちは,裏の自我とでもいうべきものを主柱とした勢力になり,表の自我への反逆を志向することにならざるを得なくなります。それは,やがては死へのエネルギーと一体化して,ただでさえ困難な人生をいっそう難しいものにしてしまうのです。
他者への度の過ぎた依存は大変危険です。他人しだいの人生に,満足も,充足も,安心も望めるはずがありません。おまけに他者への度を過ぎた依存を求める心は,表の自我が基本的に劣弱であるという事情があります。そういう心の状況であれば,日常の生活の諸々のストレスに対応が難しい上に,内側(無意識)にも意識を脅かす勢力を持つことになるのです。まさに前門の虎に,後門の狼という心的状況といえるでしょう。
#5 表の自我と裏の自我
40代後半のYさんが,「私の中に悪魔がいる」とあるときいっていました。
Yさんが10代のとき,母親が幻覚,妄想状態でした。Yさんの目の前で縊首自殺を試みようとしたこともありました。現在は,通院は継続していますが,いわば’健常人と変わらない’程度に回復しています。
Yさんの一人娘も,中学生のころに幻覚,妄想状態となりました。いまは大学生ですが,しばしば感情が嵐のように激しく揺れます。そういうときは母親を罵倒します。手に負えない幼児のような行動に走ります。
Yさん自身は,長女が発病したころに気分が不安定になり,通院が開始されました。
長女は祖母(Yさんの母親)に似ているので,病気がよくなるとしても祖母のような年齢になっているのではあまりに不憫だと,しばしば悲観的になります。そしていっそのこと自分の手で・・・と思いつめることがあります。実際に行動に出たこともあります。
「私の中に悪魔がいる」というのは,そういう状況でのことです。「もう,いいかな」と悪魔がしきりとそそのかすといいます。
Yさんの絶望は,長女の将来を悲観する気持ちと一体になっています。
長女は鬱屈した感情を激しく母親にぶつけますが,自分に手を掛けようとした母親の行動には,怒りも恐怖も覚えないように見えます。両者は密着した依存関係にあるように思われます。
30歳のWさんは二児の母親です。この夏に第二子を出産しました。
あるとき,「(4歳の)上の子の足をへし折ろうとするイメージが湧いてきて,怖くなった」といいます。
一年ほど前,状態のよくない日がつづいていました。
ある日,一人で帰すのが心配で母親に来てもらいました。ベッドに寝ているWさんの肩を抑えている母親の手を,「・・・るせーな・・・」といって払いのけようとします。「ハサミ・・・カッター・・・」とうめくようにいいます(自傷行為は数知れずといった過去があります)。動物そのもののような唸り声を発します。
いまにも暴れ出しかねない様子なので,弟にも来てもらいました(夫は仕事で,呼ぶのが困難でした)。
小一時間後,人が変わったように自分から起き上がり,きちんと挨拶をして帰って行きました。
20歳のZさんは,そのWさんの紹介で二年前に受診しました。
初診のとき,真夏ということもあり,無数の切創痕が露出された腕の全面に見えていました。
手首,腕への自傷行為は,高校に入学して間もなくからつづいています。始めは興味本位でしたが,やがては幻聴にそそのかされるようになりました。「切っちまえ」という声が聞こえ,切ると,「よくやった」と聞こえたりします。
外出中などに急に怖くなり,泣きたくなり,死にたくなり,身体を切りたくなることがあります。そういう折に,「死んだら」とか,「切ったら楽になるよ」とかいう声が聞こえたりします。
電車の中で,「切れ!・・・誰も見ていないから大丈夫だ」という声が,リアルに聞こえたこともあります。
初診のころに,「将来がとても不安・・・ちょっとしたことで無闇に涙があふれてくる・・・私は駄目だとすぐに思ってしまう・・・しばしば死にたくなる,そういうときに手を切る衝動が湧く・・・高校に入ったころから<自殺マニュアル>の本に興味がある・・・ゾンビーを殺すゲームに夢中になる・・・」と述べています。
「腕に目立っている傷痕は,人に見られるのが嬉しいと思う,何故か隠そうとするより誇りたい気分・・・」ともいいます。
鼻翼と口唇へのピアス,’ゴス調’の黒装束を好み,当然目立ちます。そういういでたちをしていると自信が湧いて,みんなに見て欲しいと思います。一方で,’ふつうの’服装をしていると,人の目が気になります。私がおかしいから見ているのかと思い勝ちです。
紹介者のWさんが,「様子がおかしい,いつもと違う,ある人と自殺の計画を立てている。そういうときの顔は怖い」と,相談に来たことがあります。
十代の患者さん(K)が,「犯罪者の気持ちって分かりますか?」と,あるとき訊いてきました。この質問は,昨今,十代の子の重大犯罪のニュースが続発していることに関していたと思いますが,実は彼自身の不安でもあるようでした。
彼は生い立ちに,ある事情があり,しかしながら母親を助けるよい子として成長しました。その’ある事情’が,彼の心に潜在している怒りをもたらしたと思われるのですが,彼自身はそのことに無意識でした。治療がはじまって,うつ状態が晴れるにつれて,制御し難い激しい怒りに苦しむことになったのです。
彼の自我は,怒れる分身たちを抑圧することで自己を保ってきました。彼が抑うつ感と無気力感に囚われることになったのは,母親を助けようとする心に無理があり,その一方で自分を押し殺さずにはすまなかったからです。
母親は強い人ではありません。幼い彼が母親を助けることに腐心したのは,心根の優しい彼としてはそれ以外にはできないことでした。そしてその代償をも背負わされることになったのです。
過度に抑圧された怒りは,憂鬱と無気力の十分な理由になります。
それは自己を切り開いていくはずのエネルギーが,自己を閉塞させる方向に流れているからです。
母親を助けることが何故このような意味を持つことになったかといえば,母親に大いに助けられなければならない年代に,幼い彼の怯える心は孤独に耐えるしかなかったということがあります。
また強い依存関係にある母親が危機的状況にあるので,母親を支え,助けることが自分を保つ上で,不可欠の要請でした。
それは,そうしたいというよりは,そうしなければならなかったのです。つまり自発的である意志に基づいたというより,他から強いられたという性格を持っているのです。
大人の分別で母親を何らか助ける場合には,どういう場合であれ一定の満足が得られるでしょう。それは強いられたものではなく,自ら意志してする行為だからです。しかし幼い子であれば,自分を助ける立場にある母親が窮地に陥っていること自体が一大事です。更に,母親の窮地を助けるのは,幼い自分ではなく,誰か大人,特に父親でなければなりません。しかし幼い彼は孤立無援に等しかったようです。大人たちからそれらが得られないときに,母親を助ける役割を,いわばそれら不在の大人たちによって強いられたに等しいことになるのです。
事実,殺意をも秘めた彼の怒りは,不特定の他者と父親とに向けられています。
これらの症例に共通しているのは,自我の世界の分裂が公然化することによって,社会性と精神性との活力が著しく低下するのと,それに反比例して破壊性を内に秘めた孤立性のさまざまな様相です。
以上の四例を上げた理由は,心の病理現象が,本来は影に隠れているはずの心の裏舞台のものたちが,表舞台に躍り出て公然化している(しようとしている)ことを示すためです。
心が裏舞台と表舞台の二重構造になっているのは一般的なことで,心とはそういうものです。
その二分化は,繰り返しになりますが,自我に拠るもの(つまり人間)の必然です。ですから潜在的に,人間は二重人格といえます。
心が健康であれば,社会的人格がしっかりと確立されているので,その人格の別称ともいえる表舞台が安定した活況を保っています。そして裏の世界は,影に回って縁の下を支えているといってよいでしょう。
この場合の表と裏の舞台の統括者,演出者が自我です。とはいえ,いま述べたように,心は裏と表に二分割されているので,それぞれの世界がそれなりに統合されていると考える方が理解を進める上で便利です。それでここでは,前者を統合するものを裏の自我と呼び,後者を統合するものを表の自我と呼んでおきます。
ちなみにC.Gユングは,心の全体をコンプレックスの複合体とみなしています。ユングによれば,自我はその気になれば意識化が容易な心の世界の中核であり,意識化が可能ではあるが,原則的に無意識である世界を個人的無意識と呼んでいます。また,この個人的無意識の世界は,多数のコンプレックスから構成されています。そして自我もまたその一つで,自我コンプレックスと呼ばれています。
ユングによれば,このように意識化が容易である心の領域の中核が自我であるので,彼がいう個人的無意識の領域は非自我の世界ということになります。
私が裏の自我と呼んでいる領域は,ユングの個人的無意識に相当しますが,なぜ敢て自我と呼ぶかといえば,ユングのいう個人的無意識の世界は,いわば自我の負の遺産だからです。自我の関与があってこその存在であるからです。
心の世界で自我の関与が及ばないのは,ユングがいう普遍的(または集合的)無意識の領域です。言葉を換えれば,この領域は自我を超越した世界です。時間的,空間的に,自我に拠る世界は有限性のそれですが,心の内なる普遍的無意識界は,無限性の性格を持っています。
人間が人間たるゆえんは,自我に拠ってです。つまり自我の領域こそが人間的世界ですが,人間を超越した世界をそれぞれの自己が心の内に抱え持っているところに,自己が永遠に現在の自己を否定的に超え出て,新たな地平を求めつづける時間的存在である理由があります。
そして普遍的無意識の存在は,人間が超人間的である自然に内包された存在であること,人間の存在由来をそれぞれの自己の心の内部に抱え持っていること,を暗黙の内に示していると考えることができます。
以上の意味での自然は純一であるのに対して,時間的性格を持っている自我は,果てしない自己否定の階梯をスパイラル状に上昇していくのを理想としています。つまりその都度の自己は否定を内に含んでいます。
純一なる善,正義,愛,公正などなどを追求するのは人間であればこそというわけですが,それは内に,悪,不義,憎しみ,不正などなどを常に抱え持っている証拠で,それが人間です。
敷衍すると,例えば純一なる善を追及するとして,それは理念としてのみの概念的存在で,実際には善の否定,つまり不善が尽きることなくついてまわればこその追求です。ここにもまた,人間が有限の存在でありながら無限性を生きている様が現れています。
人間は人生を追及しようとするかぎり,自我に拠って,以上のように人生の階梯をスパイラル状に登っていくことになりますが,それは別な角度から喩えていえば無限につづく負債の返却です。つまり自我は,仕事をすれば,必ず何らかの負債をも背負い込む宿命の下にあるといえるのです。
’追求する自我’であるかぎり,精神性と社会性との追求ということになるでしょうが,人間についてまわる身体性と他者性とがそこに干渉してきます。これらの属性があるかぎり,人間はたえず煩悩に引きずり込まれないわけにはいきません。
十歩前進,九歩後退といったところが,うまくいっても人間の現実ではないでしょうか。
まことに死によって,人間はようやく本物の自由になることができるようです。
解脱,悟り,などによって得られる解き放たれた感覚,真に自由であるという感覚は,その根拠を死から得ているように思われます。
このように自我は自己の開拓者であり,同時に,やむを得ず自己を貶めるものでもあります。
開拓された自己の全体の中核にあるものを表の自我,貶められて陰の領域に追いやられた自己の中核にあるものを裏の自我と,ここでは呼んでおきます。
ユングが述べているように,無意識の領域はいくつものコンプレックス群から成り立っています。その中で自我コンプレックスと呼ばれているものだけが,一定の恒常的体裁を保っています。そのために,誰それという固有名詞で呼ばれることが可能になります。つまり,それぞれの自分がそういう体裁で存在しています。
心のこの世界が自我の仕事の正のものです。そして正を生み出そうとする自我の仕事の背後に,負の遺産がいわば量産されていきます。
この負の遺産の中で問題になるのは,他者への過度の配慮から,その過度にわった分の自己犠牲です。それは簡略化していえば,外面がよすぎる自己における自我の不始末です。
これら無意識界に存在しているコンプレックス群のそれぞれには,自我コンプレックスのような恒常的体裁はありません。
それぞれのコンプレックスには,それを刺激する特定の体験があり,そういう折に思いがけない激しい感情状態に囚われることによって,その存在が顕かにされます。
例えばふだんは落ち着いている大人が,子供が騒ぐ声を耳にするときに限って,その場に居たたまれない強い不安に駆られるとすると,幼い時代に甘えを満たされなかった体験をしている可能性があります。
この場合のコンプレックスは,幼い時代に母親に甘えられなかった数々の体験群の無意識的記憶と,それに伴う悲しみ,寂しさ,虚しさ,怒りなどの強い感情群とから成り立っています。
(20代のある女性(S)が,退職した職場に用があって顔を出しました。元の同僚達に,「思ったより元気・・・」とか「綺麗になった・・・」といわれて悲しかったといいます。彼らは上辺だけを見て,心内にある強い悲しみ,寂しさに日夜悩まされているのを察してくれなかったからです。
幼いころに母親に甘えたいのに甘えられないでいる心を,母親に気づいてほしいという願いが元々あったと思われます。しかし,それは果たされないまま成長し,いわば未済のままでいるのです。その心が無意識的に他者に向かうとき,その他者は母親代理ということになります。虚しく期待してしまう様子がここに現れています。
何もいわなくても分かって欲しいという気持ちは,甘えの変形です。大人のいまでも,幼児のころと少しも変わらず,母親代理の他者が気づいてくれるのを虚しく待っている心が,ここに現われているのです。
中には,寂しがりやであるのを見抜いてくれた友人もありましたし,それなりに努力もしてくれましたが,彼女の心が癒されることはありません。「私は甘え方を知らないのかしら・・・確かに強がって甘えたりしないと思うけど・・・」といいます。しかしながら,彼女が望むように甘えると,幼児そのもののようになるに違いなく,それは手に負えない病的な行動になりかねません。
(このような行動化は,境界性人格障害に典型的にみられます)
心にある欲求を他者が気づき,解決を図ることができるのは,乳幼児と母親との関係における母親だけといってよいでしょう。この関係での両者は一体の関係にあり,未熟な乳幼児の自我を母親が代理しているからです。この関係においては,乳幼児の心の要求を,母親はほとんど自分の心の要求とおなじように扱うことになります。
成人においては,阿吽の呼吸とか,腹を探るとか,勘で分かるなどというように,人の心を直感で察することは可能であるにしても,乳幼児のように扱えば,ふつうは余計なお節介ということになります。
従って自分の内部問題であるこれらのことを解決できるのは,本人以外にはないのですが,人はしばしば,「黙っていても意を察してほしい」と思うものです。キリスト教文化の影響の下にある欧米人にくらべて,日本人にはこの傾向が強いのは,かねてからいわれていることです。それは屹立する自我と,より相互依存的である自我との違いといえるでしょう。そのことは集団行動を得手とすることや,公衆道徳のありようなどにも表れています。
たとえばかつての国家統制の行き渡っていた時代の日本では,二宮尊徳型の忠義者が公衆道徳を率先して黙々と実践すれば,社会の大勢が自然にそれに見習うことになるのがふつうです。
これがなぜ幼児心性かといえば,個々人の自我が,良かれ悪しかれ自立していないからです。この場合の主体的自我は,いわば外在する集合的他者ということになり,それは天皇を頂点とした権力機構であるといえます。個々人の自我は,幼い子が母親の自我に依存するように依存しているのです。
ですからこの権力機構が崩壊した’民主国家日本’では,自立していない個々の自我が解放されて,幼児のように’やりたいようにやる’人種がここかしこに見られるようになり,公衆道徳は一転して地に落ちることになるのです。
自立していない自我の下での個人主義は,幼児的自由がまかり通ります。それは真の自由とは似て非なるもので,いうならば’勝手にやる心’といったものです。そしてまじめな心の持ち主は,集団に依存します。かつての強力な国家的集合体ではなく,個々の大小の集合体に依存します。ここでは集団に帰依することによって,自我は主体者である困難(自由と責任等々)を免れる代わりに,自己自身を追及する機会をも捨て去ることになります。こうした状況では,責任の主体があいまいになり,欺瞞的精神に傾かざるを得ません。集団の秩序に従うのが前提になるので,秩序を乱すものは排除されます。そこでは,時として正義が踏みにじられ,偽善がまかり通ることになります。
土居健郎氏は,日本人の心理特性を甘えという鍵概念で捉えています。
本来,甘える心はまさしく小児のものです。それが日本人一般の心理的特性であるのは,キリスト教的な唯一神による民族の支配がなじまない何らかの風土的な事情があり,個々の自我が,より人間臭のただよう現実的な集合体に依存したからに違いありません。超越的なものへの依存であれば,それは個々の問題になるのですが,人間的な集合体への依存であれば,自我はさまざまに移ろうことになるのです。
先のK,Sの二例は,心の無意識にある幼児心性が強い勢力を持っていることを顕かにしているのです。
言葉を換えれば,心の表舞台を司る自我をおびやかすほどに裏舞台の勢力が大きいといえるのですが,冒頭に上げたY,W,Zの三例では,いうならば表に出てはならない裏舞台のものが表に出てしまっている様子が現れているといえます。
ここでは自我の統率力が破綻を来たし,心の表と裏の舞台がそれぞれ独立しているように,人格が二分裂している様相になっているのです。
三例に共通するのは,自我の統合力が衰微して破れが生じているという点です。そのために,裏舞台にあるはずのものたちが,自我の統率から逸脱して自律性を持ってしまっているのです。そのために自我の世界の二分裂が公然化したともいえ,分裂したそれぞれの世界の統合者を,一つには表の自我であり,そして一つには裏の自我であると呼ぶのが現実的であり,それなりに意味があるのです。
これまでに述べてきたことの繰り返しになりますが,自我に拠る現象的世界は,意識・光・生きる・有限・・・ということで特徴づけられるものです。そして無意識・闇・死・無限・・・といった世界が,それら現象界を包囲しています。
それは,心の表層はそれら光の世界のものであるが,闇の世界をも含み,両者は密接不可分の関係にあるということを,そしてまた,光の世界は独立を志向しながらも闇の世界に依存していることであると言い換えることができます。
つまり人間は自我に拠っているので,自我のものである前者の性格を持っているのはいうまでもないのですが,自我を超越している後者の
無数にあるともいえるコンプレックス群が正の意味を持つのは,自我がその存在に気づき,自我コンプレックスの一員と認め,表舞台に引き上げるときです。こういうときには,裏舞台に流れていた負のエネルギーが正のものに賦活されるので,一見して元気になります。さまざまな精神療法,心理療法がうまくいけば,必ずこのようなことが起こっているといってよいでしょう。
しかし自我との接触が図られないままでいると,それらのコンプレックスは,さまざまに負の力を現すことになります。
両者の利益の矛盾に直結するのです。
ところで自我はなにを拠り所に存在しているのでしょうか?
自我は,人間に固有のものです。人間は自我に拠るものです。人間の認識能力は,自我の機能に属します。自我は意識という光の世界の核であり,光は生きる意志と共にあります。
自我の誕生の由来,意味は,人間の理解を超越しています。つまり自我の光や認識能力のおよばない問題です。自我は意識という光の世界を演出しますが,自我が自我自身の根拠であることはできません。従って自我が存在する所以は,心の闇の領域,つまり無意識の世界以外にはありません。それは仮説以上のものです
ですから自我の実体的な根拠を名指しすることは不可能です。人間の身体をつぶさに調べても,自我の根拠についての具体的な答えは見つかりそうにありません。しかし身体のいたるところに,その兆候があるようでもあります。
繰り返しになりますが,自我は人間の意識活動が存在する根拠です。身体的,精神的な全ての現象は意識活動に伴うものです。自我を実体的な存在として名指しすることができず,自我に拠る意識活動として世界を現出させている人間には,世界は実体的にではなく,現象的なものとして存在します。
換言すると,もろもろの精神現象が存在する以上は,然々の原基的な起源がないはずはないが,それを実証することは不可能であるということになります。
自我はそういう性格のものです。それはいたるところに姿を現しているが,それ自体は決して意識に映じることはないといえます。
つまるところ,自我を拠り所に意識による光の世界を生きる人間は,意識の消滅によって世界は闇に溶け去ります。死は自我の終焉を意味します。
以上のように,「自我は,その存在様態を人間が知り得ないものの,何か原基的なものに拠って存在していると考えなければ,精神現象の一切が説明できない」というのは,合理的な仮定です。一定の仮説を立てて合理的な理解を目指すのは,必要なことです。
それはやがては実体的に証明することができるという性格のものではなく,永遠に仮説にとどまるでしょう。ですから,それぞれの分野でそれぞれの仮説を立てることになるのは当然です。そしてそれぞれの仮説は,それぞれの分野に現象として存在しているものを,合理的に説得する力を持つかという意味が問われることになります。
このように,自我のような,そもそもの存在根拠を,人間的な理性の及ばないところに求めるしかないものは,その実体性においてあいまい極まりないものです。そして精神の現象には,その類のことがずいぶん多いのです。
人間の理性的な理解を超越したものの全体を,仮に’自然’と呼ぶとすれば,自然の意志が人間の心の内部に及んでいるのが無意識の領域であると考えられます。意識界の首座にあるのは自我です。そしてそれに相応して,無意識界にも首座があると考えるのが合理的です。そうしたものが存在すると仮定することは,精神の病理現象を統合的に理解する上で意味があります。
その無意識界の首座にあるものを,ここでは「内在する主体」と呼んでおきます。それは自我の拠り所となるものです。自我がその意志を探り当てることによって,人間の精神を造形していくものと考えることができます。
自我は,喩えていえば大海を行く小舟の船長ですが,船長が操る羅針盤に映じるのが主体の意志です。あるいは星を読み取って航路を定めるのが船長であれば,星々の運行をつかさどるのが主体です。いずれにせよ船長の恣意で小舟を動かすことはできません。それは漂流に他なりません。
人生はどのように生きてもよいとはいえません。「自由に生きる」ことには,主体の意志を探り当てるという意味があるでしょう。これに対して,「どう生きようと勝手だろう」という考えは,自由とは似て非なるものです。それは自我が自分を引き受けようとしない姿です。ですから基本的なところで無責任なのです。たとえ漂流しようが構わないでほしいということは,確かに他人の与り知らぬこととはいえ,他人との関わりを欠いた行為というものはありません。いずれにせよ,主体の意志にお構いなしの生き方は,いわば心の内部の法廷で有罪判決を受けることになるのは必定です。それは他人に対しても,何らかの迷惑が及ばさないわけにはいかないでしょう。
以上のような考えは,人間が存在するのは何かの偶然に過ぎない,あるいは生物の進化の連鎖の過程にあるに過ぎない,等々という疑問ないし反論にあうのは必然でしょう。そうした疑問が起こるのは,自然科学的な合理的思考が行き渡っている現代ではもっともなことです。
しかし,それは自我を首座に置いた思考によるものです。いま,ここで述べてきたことは,自我を最上位に据えることは不可能であるということでした。
さまざまな観点から考察を加えることは必要なことであり,そうしなければ済まないものでもあります。それぞれの立場によって,現象の読み解き方がそれぞれに違ってくるのは避けられないことです。しかし,自我を最上位に置く自然科学的思考が,精神現象を統合的に解明することができると考えるのは不可能です。
これまでに述べてきたことがどういう意味を持つかということについては,臨床的な有用性がどの程度かということにかかっていると思います。事実,それらは診療を通じて自然的に浮かび上がってきた考えです。病気の成り立ちや自己が改善されていく様子などに考察を加え,それらは更に臨床の上で検証され,強化されてきたといういきさつがあります。それに伴って,その仮説に基づいて治療に当たることに,一定の確信を持つことができているということでもあります。
無意識界にあるとする人間の精神の直接的な母体を,内在する主体と呼ぶのは仮定の命名ですし,自我は,人間が自然そのものではない存在として乖離されたときに,この主体から生み出されたものであろうと想定するのも同様に仮定のことです。そうした前提の上に立って,臨床上の有用性がそれなりに確かめられたときに,それらの仮定は一定の意味を持つと考えるわけです。
結論的にいえば私が果たさなければならないのは,以下のことです。
治療者に対して患者の皆さんは問題を提起し,治療者としての私には,それを受け止め,有効性のある治療的な展開と還元とをもって応える義務と役割があるということです。更につけ加えれば,患者の皆さんは,教師としての性格の一面を持っています。教師が問いを出し,生徒である治療者がそれに対して一定の答えを出す,その当否を決めるのは教師であるというわけです。
この場合の教師の役割は患者さんの自我にではなく,内在する主体にあるといえます。患者さんが発する問いは自我によるものですが,治療者の自我がそれを受けて,双方の意志を通じ合うことになります。それらのやりとりの結果,患者さんが納得でき,それに伴って心に力が湧いてくるときに,生徒である治療者は,教師である双方の主体から合格通知を受け取ったことになるといってよいように思われます。
診療というものは,本来的にそのように展開されるものと考えてよいと思います。
幼い子の自我の自律性を守り育てる,唯一といっていい立場にある母親(と父親)の存在の重要性は,いくら強調されてもされ過ぎることはないでしょう。それはいうまでもないことですが,程度の差はあっても虐待する親が決して少なくないのが実情でもあります。子供は,親の前で逃れようがない立場にあるので,虐待される子供の絶望は察するに余りあります。それは,どんな犯罪よりも犯罪的であるといってもいい過ぎではないと思います。親から受けた心の傷は,一生を決定づけるほどのことなのですから。
虐待とまではいかなくても,子供は親から様々な干渉を受けるのが現実です。それは,人間の宿命といえるでしょう。他人の’要らぬ節介’は避け難い問題です。
赤の他人のお節介はともかく,親のそれは性格形成に大きな影響を与えます。
性格の健全な形成には自我の自律性が鍵を握ると思われます。その自律性が両親によって護られる必要があります。そのためには,親の自我の境界機能が確かなものである必要があります。そうでなければ,親は当然のように子の心の領域に侵入することになるでしょう。
自我の自律性は,境界機能と密接な関係があると想像されます。親が子の領域に無分別に侵入するのが当たり前になっていると,子供の自我の境界機能が混乱し易く,境界機能に護られない自律機能も混乱すると想定されるのです。
強い不安と硬直した自我を持った親ほど,子供への干渉が甚だしくなると思います。両親の干渉が過剰になれば,先に上げた少年の例のように,ロボットにされる恐怖を持つようなことも起こるのです。
以下は,甚だしい干渉をしてしまっている母親の例です。しかしこの母親は,劣等感が大変つよい人であるにもかかわらず,柔軟な心と子を思う優しさとを失ってはおらず,自分がおかした過ちをすぐに認めることができる人でもありました。
この方は,小学生の一人娘が,最近になって不登校になったという悩みを持っています。彼女は夫と離婚し,一人娘と実母と三人で暮らしています。娘が不登校になったことについて,甘やかせ過ぎがよくなかったのかという悔いを交えた反省をしています。愛情ならたっぷり与えている,むしろそれが行き過ぎているのではないかというのです。
しかし実際には,’愛情’の裏側には,大きな不安が潜んでいるのが明らかです。娘はごくごく幼いときから,喧嘩ばかりしている両親の仲裁役をしていたようです。母親が落ち込んで黙りこくっていると,「何か話して」といって母親を励ましました。「こんな駄目な親の私に,どうしてあんなよい子ができたのかと思ってきました」と彼女はいいます。勉強もできるし,手伝いもしてくれるし,申し分がなかったのだそうです。
この母親と幼い子の祖母(本人の実母)とは,良好な関係ではありませんでした。祖母が支配的,強権的で,母親に育児の自由さえ許さなかったようです。幼い子は,母親と祖母とのあいだの板ばさみにもあっていたと思われます。そして母親は,「こんな醜い私のような大人になってほしくない」というのです。けがらわしい大人になるくらいなら,ずっとこのまま子供でいてほしいと願ってきたそうです。テレビの番組や読書など,’大人のにおいがする’ものは,ことごとく規制し,排除しました。愛情と信じた過度の干渉が繰り返されてきたようです。このごろ,「なんでもお母さんには話をしてね」という母親の願いに応えてくれないことが多くなりました。母親は焦りと孤独感と不安を感じるのです。
これまでにも述べてきたように,自我の重要な機能の一つは自律性です。自然から乖離された人間は,自分の力で人生を切り開いていかなければなりません。それは小舟で大海を渡ろうとするような途方もないことです。そのための拠り所が自我の自律性です。先の比喩でいえば,自我は小舟の船長です。船長は自由に,主体的に操船しなければなりませんが,その自律性に根拠を与えているのが内在する主体です。船長が幼くて,操船術が未熟なあいだは親に依存して技術を見習います。そして,しだいに依存から脱して自由になり,直接に主体との関係を探り当てていきます。それが順調に進むときに,自我は自律性を発揮できます。
他者,とりわけ両親の望ましい援助と協力と指導があれば,または他者の干渉が自我の眼を眩ませなければ,その自律的な機能は,かなり自然に遂行されるのではないかと思われます。しかし実情は,両親を含めた他者の干渉が,無意識的なレベルをも含めると,無視し難いものがあるのが一般です。また,自我自身のそれぞれの能力の問題もあります。それらの事情から,自我が本来の自律性を保ち,適切に自己を導き抜くのは,むしろ困難だといわざるを得ないと思います。
幼い自我が自分のためになる仕事をしたいと思っているときに,権力者である親の干渉によってどのような影響を受けるか,先に述べたの二つの例に即して見てみたいと思います。
男児の例では,母親の愛情が弟に傾いていると感じ,母親に気に入られるように,活発にアピールしている様子がうかがわれます。しかし,その努力は一向に報われず,望むような反応が得られません。かえってうるさがられている印象もあります。父親はそのような母子関係と,息子の悩みに鈍感なようです。こういうときに少年はどうすればよいのでしょう?男児の自我は精一杯の仕事をしているように思われます。それが無効なので,怒りが充満しています。自我は役割を果たしているのですが,両親の協力が得られないので,結果としては無駄な努力になってしまっているのです。愛されたい,認められたいというもっとも過ぎる欲求には切実なものがあり,しかし,それらの欲求は,母親の協力を得られないので,自我はやむを得ず無意識の牢屋に押し込めるしかない(抑圧する)状況です。それは親の不理解,愛情の欠落によって,自我が無能力なのと何ら変わらないことになるのです。自我は大変に混乱しやすい状況です。不当な抑圧を強いられて,無意識の領域には怒りが充満しています。自我がそれらの不満の代弁者として,姿勢を変える必要があるのかもしれません。つまり反抗的な姿勢に転じるのです。しかし,よい子路線を取る少年の自我は,親に見捨てられる恐怖がもともと強かったと思われます。愛されたい,認められたいという自然で,当然の要求を,自我は精一杯すすめるのですが,両親には通じません。自我は両親の更に恐ろしい拒絶を回避するために,甘えたい心を涙を飲んで押さえ込まなければならない状況です。親の自我に迎合しなければ,存在そのものが危うく感じられるのです。押さえ込まれた甘えたい心たちは,傀儡化せざるを得なかった自我と両親に対して,悲しみや,虚しさや,恨みなどと共に怒りを充満させています。それら充満する怒りが,チックを呼び,夢の絵の中で,爆発しそうなロボットとして表現されています。ロボットの意味は,言葉によっても,行動によっても,意志を伝える力を持てないということかもしれません。
また,学校への通学路で,誘拐されるのではないかという恐怖があります。学校には友達がいて,学校生活そのものは問題がないようです。この恐怖は,母親との関係が遮断されてしまう不安のようです。母親が自分を捨てて,どこかへ行ってしまうという類の恐れは,意識上はありません。彼の自我は,母親がそんなことをするはずがないという認識を,精一杯保っているといえるでしょう。しかし内心の不安は打ち消し難く,無意識の世界にあるそれらの感情が,彼の自我を捕捉し,飲み込んでしまう恐怖を持つのでしょう。それが,誘拐という外部的な事件への恐れの形になって現れているようです。
彼は,将来,父親のような職人になるのもいいが,それ以上に整体師になりたいと考えています。その職業が両親の身体を癒して上げるのに役立つと思うからだといいます。もしかすると,その他に,両親の心にも整形を加えたいという隠れた願いがあるのかもしれません。
女児の母親の例では,女児はごく幼いときから,喧嘩の絶えない両親の関係と,自分をも含めた家族の関係との危機を救おうとしています。幼い自我の必死の願いと行動とに応えることができなかった両親は,少なくても子供の立場からは,幾重にも非難されても仕方がありません。女児の願いは叶えられなかったというべきか,半ばは叶えられたというべきか,両親は離婚しました。しかし離婚後,今度は母親と祖母とのあいだの板ばさみになりました。少女の自我は,本来は大人たちがするべきである関係の調整の役目を強いられました。幼いときから大人の自我の強さを求められたのです。親に愛されたい,励まされたい,甘えたいという子供本来の自然の欲求は,ここでも無意識の牢屋に押し込めるしかなかったのです。「私はなんで生まれたの?なぜ私を生んだの?」という疑問に応えるのが親の義務といえるでしょう。子供の側に,愛されている,信頼されている,大切にされているという肯定感があれば,それが答えです。
女児を母親は大切にし,愛情を傾けたつもりです。しかし母親自身に自己肯定感がなければ,それなりの健全な自己愛がなければ,子供に満足感を与えるのは,ほとんど難しいことでしょう。むしろ子供にそれとなく依存してしまうものだと思います。こういう依存は,穏やかな言葉や態度でカムフラージュされて,一見は仲のよい親子の図になるかもしれません。しかし,実質的に強制的な侵入になっていくと思われます。依存の対象になるのは,いわゆるよい子です。よい子というのは,そもそも(母親の)期待や要求に,無理をしてでも応えてくれるからです。「親が望むなら,そのようにして上げたい」と考えるよい子としては,母親が苦しむと分かっていながら,無視はできないのです。
母親の’苦しみ’にも,半ばは無意識的にでしょうが,よい子をそのように仕向けるための演技が入っているのではないかと想像されます。母親の半意識的な誘導によって,母親が悲しんだり,苦しんだりするのは,自分のせいと感じる癖が子供にはできていると思われます。そこには母親が,’愛情’を隠れ蓑に,もう一つの意図を隠し持っている姿が見え隠れしているように思われます。このあたりの事情は,子供もうすうすとは分かっていると思います。しかし,よい子であるかぎりは,母親の仮面を剥ぎ取ってしまうような考えは,到底できない相談でしょう。それは’愛情’の背後には,恐ろしい怒りが潜んでいる(母親が,幼い娘の気を引くために悲しそうな顔をするときにも,その心の奥には怒りが潜んでいます)のを感じ取っているからだと思われます。母親の怒りについては,どうすれば自分に向けて炸裂する(怒りの炸裂は,見捨てられる恐怖に直結します)のを防げるか,半ばは生存本能から分かっていると思います。恐らく,母親が大好きなのだという自己欺瞞にも陥っているのではないでしょうか。母親が愛情の仮面の裏に怒りを潜ませているのと,女児がつけている「お母さんが大好き」という仮面の裏に恐怖と不信とを潜ませているのと,母子それぞれが対をなして,演技的な関係にあると考えられるように思います。
こうした恐れを背景に,少女は母親に強く依存しているので,その関係が壊れることは,自己が破滅するに等しい恐怖感を持つのです。母親との間をつなぐ危うさをはらんだ絆を手放すと,無人の荒野に一人放り出されるのに等しい恐怖を持つのではないかと想像されます。
母親が望むように,という女児の自我の姿勢は,生きるための必死の戦略です。生存本能に駆られてのことといえると思います。そして一方では,自律性を犠牲にするという高価な代償を支払うことになったのです。それに伴い,’自分らしく生きようとする’意志のほとんど全てをあきらめるしかなくなります。それはかけがえのない人生を虚しいものにする,過酷な犠牲を強いることにもなるのです。
人間は自然から生まれ,自然に即することを最善とするものであるように見えます。それが損なわれるのは,他者との避けられない関係によってです。最も頼りとする母(そして父)なる他者によって,人生の塗炭の苦しみを味わいかねない不条理劇の幕が切って落とされるということが起こり得ます。そのように極端でなくても,子は親によってそれなりの被害を蒙らないわけにはいきません。それが人間です。人は,「親から受けた被害によって歪んだ心を,一生かけて自然的なものへ整え直す,それが人生である」という不可解な存在です。そして,それらの苦しみを招いてしまうのが自我であれば,改めてそこから脱出して自己を回復させるのも自我です。
この女児の幼い自我も,母親の愛情に守られているという安定した安全感が得られなかったと推測されます。おそらくそれとは正反対の母親への恐れ,恐怖,,不信感に,ごく幼いころに直面しただろうと思われます。それが自我の自律性を混乱させ,母親の自我への密着を促したと思われます。それらのことは,生死をかけたといえるほどの切迫した心理状況の下で起こることです。
幼い時代に経験したと思われる恐怖心や不信感などは,抑圧されて滅多には意識されることはないでしょう。それは年齢的に幼すぎるためではあるでしょう。しかし抑圧であるからには自我が関与し,抑圧されたものは無意識界にエネルギーを抱えたままいつまでも留まることになります。それは傷ましい心の出来事です。親が与えた心の傷ということになります。
このように幼い自我が自然の欲求を抑圧するのは,大人が何かを我慢するのとは比較にならないもので,いうならば心的外傷とでもいうべき出来事に直面したからであるに違いありません。それはよくよくの恐怖体験があったからに違いないのです。
それらの傾向,幼い自我が抑圧に走る傾向があるとすれば,その大元には,恐らく甘える心の抑圧があっただろうと想像されます。それは次のような事情によります。
乳幼児の幼い自我が,無意識界から送り出されてくる諸欲求を護るためには,母親との関係を抜きにしては考えられません。その最重要の他者とのあいだの関係が良好である証は,甘える心が満たされていることです。
母親への甘えが満たされている関係があれば,乳幼児は母親に受け入れられている,信頼されている,愛されているなどのことに確信を持て,満足感と安心感に浸ることができます。そういう関係であれば,何か不満足なことが生じたときには,恐れることなく不満や怒りも表現できるのです。そしてそういう関係の下では,それは基本的に,改めて母親によって受け入れられるはずです。
逆にいえば,母親への甘えを抑圧して満たされない思いをしている乳幼児の場合は,母親に受け入れられていない,愛されていない,信頼されていないという思いに駆られがちになるのは必然でしょう。そして子供の方も,母親への愛や信頼の確かさに自信を持てないことにならざるを得ません。そういう関係状況では,新たに不満が生じると,激しい怒りを向けるか,恐怖によって沈黙するかになりがちだろうと思います,それを受けて,母親の方が力で対抗したり,無関心になったり,悪循環に陥る可能性を否定できません。
甘える心が充足される度合いは,自己愛と他者愛との確かさの礎石に関わる問題なのです。
例示したこの女性の幼い子について見れば,底深い恐怖心がいわば仲立ちとなって,女児の自我は母親の自我に密着し,その上で母親への愛着という体裁に変質したのでしょう。換言すると,(自己の本心から見て)偽善的な装いをこらして自分をも母親をも欺くのです。母親を愛している,母親が大好きだというふうに信じ込むことで,母親との関係をはかろうとするのですが,一方で意識下に抑圧されている甘えられなかった分身たちは,その心の嘘にだまされることはありません。それらは表の自我と母親との一種の取引の犠牲になっているので,両者に対する怒りや恨みなどの感情と共にあります。ですから,どんなに表面上は母と子の関係が蜜月のように見えても,裏の自我に率いられる分身たちが心を許すことはありません。
(よい子の装いを偽善的というのは,代償として支払う自己犠牲が大きすぎるのを考えると酷な表現のようにも思いますが,非難をしてそのように呼ぶわけではないのはいうまでもありません。偽善というのは,悪意を隠し持って他人に親切を施すというようなことになると思います。よい子の仮面の裏には,一般的な意味での悪意があるわけではないのはいうまでもありません。しかし外側(親,他者)への配慮が過ぎて,内側(自己自身)を疎かにし過ぎるのは,自分自身に悪をなしていることになるのです。よい子がいじめに合うのは,そのような’嘘’が感じられるからかもしれません)
心から母と子の和解的な結合が起こるとすれば,唯一,表の自我が母親から距離を取り,無意識下に潜む分身たちの恨みや怒りに目を向けるときです。そうすることができるためには,表の自我が本来の力を回復させていることが前提になります。それは自我の自律性の回復をも意味します。
そのような心の転換を生じさせるのが,心理的な治療の目標になります。
これら二つの例に見られるように,自我の基本姿勢は,両親の影響を決定的に受けながら形成されます。生まれて間もない人生の最早期に情緒的に満たされることが,他者との関係を円満に保つことができる性格を形成する基礎になるはずです。
男児の例では,自我の自然的な機能が両親によって無効化されました。女児の例では無効化を恐れ,母親への盲従の途を選びました。両者とも,それぞれの自我は,いわば親の自我の傀儡になるしかなかったといえます。
幼い自我が脅威を受けてすくみ上がり,母親の自我に密着するのはやむを得ないことです。しかしながら,内在する主体との関わりから見れば,許し難い堕落という意味になる危険があるのです。自我の自然の機能を,自我自身が根本から歪める動きをしたことになるからです。これは幼い子の罪というわけには勿論いきません。しかし罪を犯したのに等しい罰のような人生が待っています。主体との関係をあやまたず確立することを目指すのが,何よりも自然的な要請だからです。
このことは,ダルマになるのが自己形成の理想といういい方で言い表すことができます。
心の軸が自己の中心にあれば,何かのストレスによって心がぐらつくとしても,過度にぶれることがなく,やがて心は平静を取り戻すことができます。しかし母親,あるいは母親代理の他者,あるいは(人間との関わりから脱落して)何ものかに,悪しき依存をしている自我の下では,心の軸は自己の中心から遠く離れるので,ストレスがかかって心がぐらつくと,態勢を容易には整えられないのです。それに加えてそういう心の状況では,自我がうまく機能しないので,心はしだいにエネルギーの枯渇感に囚われていきます。
ダルマ的な心の軸は,自我が主体としっかりと結合しているときに生じるといえます。そういう自己を目指すのが,それぞれの人生の理想的課題であると考えられます。
このように他者の介入によって,自我の主導性を損ねてしまう危険があります。母なる他者の影響が殊更に大きいのは,人生早期の未成熟な自我が,他者の保護を絶対的に必要としているからです。それを護る第一の立場に母親があるからです。あたかも神に対するかのように,赤ん坊は母親に全能者を要求するのです。
赤ん坊は人間の心の形成の歴史の中で,自己愛という自足態の中に満ち足りる,特別に理想的な時代にあるとする考えがあります。しかしそれは間違いであるように思われます。逆に,生を受けたが故に,必然的に死に怯えるものとなったのが赤ん坊であると思われます。そうであればこそ,幻想的な絶対者によって護られなければ存在できないのでしょう。わずかな闇の気配に怯えるだろう赤ん坊は,母なる全能者のふところにまどろむことを希求するのでしょう。そのふところは,つまり母親の愛情ということになり,そこには(広義の)性愛的な彩りがあるに違いありません。絶対的な上位者に護られていたいということは,言葉を換えれば甘えたいということになります。甘える欲求は,生死を賭けたものにふさわしい強力なエネルギーを持っていると考えられます。ところが,母親がこのようにかけがえのない立場にあるだけに,逆に,一転して恐怖をもたらす者になる危険性を払拭することはできません。全能幻想はいつかは綻びるのです。その綻びた隙間から垣間見る闇が与える恐怖が,赤ん坊に,母親への全能要求をためらわせるのではないかと考えられます。その恐怖は,母親その者への恐怖と区別がつかないだろうからです。生きるために母親に甘えることが重要ですが,垣間見た闇(死)の恐怖が更に大きなエネルギーを持っているために,その希求を制御するのです。母親への全能要求を恐怖によってあきらめ,現実的な関係の模索がはじまります。
人は巨大な矛盾の中に存在します。その最たるものが,生と死です。つまり,生とは究極のところ死の主題化である,という難題を人は負っています。赤ん坊にとって,全能要求は,生が主題であるかぎり死の存在を排除できないという現実原則が受け入れ難いという意味を持つのでしょう。そして赤ん坊にして,全生命の要求が,はからずも死の恐怖を否定し得ない現実によって打ち砕かれたときに,生と死とを本能的な知恵によって止揚しなければならなくなるのです。そしてそれが果たされたときに,人間存在として自立する第一歩を踏み出す基礎を得ることができます。
しかし,この激しい対立を止揚できないときには,母親への全能要求も,母親への恐怖(死の恐怖に通じます)も無意識下に収めて,いわばなかったことにしてしまうようです。それらの要求も恐怖も克服されないまま,いわば意識の地下に冷凍保存されることになります。
このように畏怖する自我は,自立を断念した自我でもあります。母親を畏怖する心は,死を畏怖する心に通じるものです。時によって母親は,半ばは意識して,半ばは無意識的に,幼い子のこうした畏怖する心に乗じます。時によって,巨大な不安を潜在させる母親は,子を自分を助ける道具にしようとします。
このようなことになれば,罪を問えないものに罪を科し,罰を受けているかのような多難な人生にしてしまいます。そうはならいように,親をはじめとした周辺の大人たちは,よくよく心をつくす必要があります。
母親の胎内にあり,まだ意識の活動が始まる以前には,心が存在していません。それは光もなく,従って闇もない世界です。それは全であり,かつ無でもある世界です。そして意識が芽生え,心が生まれることにより,光と闇の世界が始まります。赤ん坊は光を意識することにより,闇を知るのです。光は自我の世界のものであり,従って有限の世界のものです。闇は自我の光がおよばない世界のものであり,無限ないしは無の性格を持ちます。
言葉を換えれば,自我に拠る人間の世界は,それが存在する以前には全であり無であった世界が,いわば二分割されて現れます。つまり意識による光の世界のものとして存在することに伴って,生の世界が生じ,従って必然的に死の世界が生じたのです。生と死と,二極に分化した世界を生きるのが人間の宿命です。
生を受けたばかりの赤ん坊も例外ではありません。生まれる前には光も闇もない世界にあったものが,生を受けることにより,赤ん坊は,早速死におびえる者であらざるを得ないのです。生という光を意識するものにとって,闇という無限,無,死は絶大な脅威になります。赤ん坊は光の世界を享受するいとまもなく,怯えているのです。
闇に怯える赤ん坊の心の光を支え,育てる唯一最大のものは,母親の愛です。それに支えられて,赤ん坊の自我に備えられていると考えられる愛の原基に,ようやく活力が与えられるのです。しかしそれは圧倒的である無の感覚の前に怯えやすく,他でもない最も頼りとする他者なる母親によって怯えを刺激されたときに,著しい恐怖を味わうことになるだろうと想像されます。それに伴って,幼いとはいえ心の形態は既に備わっている赤ん坊は,襲い掛かる脅威に対抗するために母親の自我にとりすがるという原初の対人駆け引きを行い,かつ心を抑圧するという防衛手段を講じるだろうと思われます。必然的に,赤ん坊の無意識界には,自我の不当な抑圧を受けた無垢の心たちが集合体を作るのです。そこには不当な扱いを受けたものたちの怨嗟の声が満ちているといえるでしょう。それらの死の世界に追いやられたに等しい分身たちには,いつか自我によって改めて認められ,受け入れられる願いを持つもっともな理由があるのです。長期にわたってそれがかなえられないでいると(幼い子がこの作業をできるためには,両親の反省,手助けが欠かせないでしょう),これらの分身たちは,まとまりのある一つの勢力になります。それは心にできた怨嗟に満ちた沼のような趣があります。自我としては近づくと危険な雰囲気を持つのです。その沼の中心にあるのは,裏の自我と呼ばれるにふさわしいものです。表の自我と裏の自我の関係は,正と邪,善と悪,生と死,明と暗というふうに,真っ向から対立するものです。
表の自我は,生へと向かうエネルギーを司ります。裏の自我は死へと向かうそれを司ります。心には表層の生へと向かうエネルギーの河の流れがあり,深層には死へと向かう河の流れがあります。
人が何かの行為,行動をするときに,それに伴って無意識界からエネルギーが動員され(内在する主体によって送り出される),自我がそれを護ったかぎりで生へのエネルギーが受給され,護れなかったかぎりにおいてエネルギーは死への流れに合流します。一つの行為(行動)に伴って,二様のエネルギーの流れが生じると考えられます。
仕事で無理を重ねて心の病気になるのは,日ごとの仕事が自我に活力を与える(自我が引き受けているかぎり満足感が得られます)よりは,自我が受け入れ難く感じている度合いが甚だしいということになります。そのときに,仕事をするときに動員されたエネルギーは,より多く負の方に回ることになります。こういうときには休養が意味を持ちます。逆に無用に怠惰にしていると,自我はエネルギーを受給されないままになり,活力を失うばかりです。
自我が生まれてきたエネルギーを護り切れるとき,興奮に満ちた歓喜が起こるでしょう。科学者が待望の発見を目の当たりにしたとき,芸術家が霊感に触れたとき,競技者が力を出し切ったとき,恋する男女が恋を交わすときなどがそれに当たると思われます。
小学生のA君は,一時期,学校へ行けませんでした。最近は行けるようになっていますが,時には休みます。あるとき,学校で,広島の被爆者の戦争体験を聞く機会がありました。悲惨な話を聞いたあと,大好きだった肉を食べられなくなってしまいました。食べようとすると吐き気がするのです。
夜になると,お化けが怖くて一人で寝つけません。そんなものはいないと思っても,寝つくまで母親に傍にいてもらわないと安心できません。爆弾を投げつけられる悪夢に悩まされたりもします。
母親がやむを得ない会合があったとき,家で過ごすことができず,父親につきそってもらい,会合場所の近くで待つ必要がありました。
父親と母親が喧嘩をすると,母親に抗議します。父親にはできません。元々は,両親の口論が激しかったのですが,最近では母親も落ち着いて,自制することができるようになっています。
一般に,小学校に通うのは,まず社会から課せられた通過儀礼の一つという意味があります。課せられた学校状況を引き受けるのは,自我の役目です。自我が成熟して引き受ける意志を持つことができるようになれば,課せられたものという受身の姿勢から,自分が自分自身に課していくという能動的姿勢に転じていきます。このような心的状況であれば,母なる他者から与えられる満足感を,自分で自分自身にもたらすという重要な経験をすることになります。
自我が未熟な,より幼いレベルでは,幼児の満足感は主に遊びを通じて得られますが,それは(主に)母親によって補佐される必要があります。つまり未熟な自我は,母親のそれに依存して補強してもらう必要があります。無心に遊びに没頭しながらも,母親にその喜びを共有してもらうことが意味を持ちます。敢て母親を困らせることもするでしょうが,それは母親に喜んでもらう満足を求める要求と考えるべきです。それらのことは,母親への甘えの欲求を主軸とした行動といえます。原初の人間関係は,母親との関係であり,それは甘える満足をめぐってのことといえるでしょう。
小学生が学校に通うのは,自我がある程度成熟した年齢に達したときです。従って通学は欲求ではなく意志に基づきます。
欲求は無意識という心の内部の自然から送り出されてくるものです。自我がそれを受動的に受け入れるのです。一方,意志は,自我の主体性に力点があります。つまり自我がある計画を持ち,それに伴って個々の行動に必要な欲求(方向性を持ったエネルギー)を呼び出します。求めに応じて送り出されてきた欲求を,自我が護りとおすことで行為が成立します。それに伴って満足感が得られ,自我に活力が与えられると考えることができます。元気があるというのは,自我に(欲求を護ることにより)エネルギーが補充され,活力が保たれているということです。
意志に関して,ある行為の計画を立てるのは自我の役目ですが,いま述べたように幼い自我は両親をはじめとした大人たちの助けを必要とします。学校に通うことについては,本人の自我に任せるというわけにはいかないといえるでしょう。義務教育といわれるように,義務として課されたものであることが意味を持ちます。つまり多かれ少なかれ,意志的な心の仕事には苦痛が伴います。本人がしたいようにさせていたのでは,つまり意志の弱い子になってしまいます。天分も本人の気ままな欲求に任せていたのでは開花しないと思います。そのように他者によって義務として課されたものを,改めて積極的に引き受ける自我であれば,最も好ましいことになります。
躾けも含めて,教育には,以上のように,上位者である他者の関与が重要な意味を持ちます。
A君の不登校については,誰もが理解できるほどの問題が学校状況で発生したからというわけではありません。最近,午後から登校したときに,先生に,午前中は登校できなかった理由をきかれ,「鼻水が出たから」と返事をしました。すると先生に,「そんなことで休む子はいないよ」といわれました。A君としては,先生の言葉は心無いことになり,傷つきもし,怒りも覚えました。しかし,A君は答えに窮してそのような返事をしたのでしょうが,本当の理由はA君にも分からないのです。何か分からない理由で意志がくじけたのです。
これを先ほどの図式に当てはめてみると,学校へ行く意志を持つたのは表の自我です。そしてその意志を打ち砕いたのは裏の自我です。A君は裏の自我に引きずられて,心の沼に落ち込んだのです。
A君の夢からは,強いエネルギーを持った恐怖と怒りが,心の沼に渦巻いている気配が窺われます。母親から片時も離れられない不安の様子と重ね合わせると,それは見捨てられる恐怖に由来するもののようです。
(自我に拠って生きることを宿命とされる人間は,即座に闇(死)に怯えるものであることをも宿命づけられています。
心には生と死と,二つの極に向かうエネルギーの流れがあると考えられます。自我は専ら生の世界を切り開くものですが,その仕事を助けるために他者の関わりが不可欠です。そしてその欠かせない他者の介入が,自我が節を折る理由にもなるのです。
自我が正当に仕事をしたときには,生へのエネルギーが勢いを増し,他者の介入によって自我が節を折ったときに生へのエネルギーは供与されず,そのエネルギーは自我が護れなかった分身(黒い子)を作り出し,心の沼が広がります。この沼からは,死の極へと向かう流れがゆるゆると形成されることになるように考えられます)
A君は,自覚的には,母親がまさか自分を見捨てるなどとは考えていません。しかし内心では強く疑っているのです。その恐怖と不信とは,無意識界に抑圧されている幼児心性がもたらすものといえるでしょう。幼児心性としては,自己愛と自己を信じることとは母親を経由して可能になります。つまり未熟な自我は母親の自我を頼りにして,幼児的な判断をするのです。
幼児心性とは,ごく幼いころに,母親への恐怖心から自我が護れなかった欲求たちです。とりわけ満たされなかった甘えの欲求が,護ってもらえなかった不満,不信,悲しみ,虚しさ,恐怖などと共に,怒りと一体になって意識下に現に潜在しているものたちのことです。
それらは裏の自我とでもいえるものを首座として,強い勢力となって表の自我に圧力を加えます。その影響を受けて,生の世界を司る表の自我は機能不全に陥りがちになります。
見方を換えれば,傷ついた自己愛ということになります。自己愛という自我機構に内属すると考えられる(自己愛は習得されるものではなく,生まれ持ったものです。自己愛の健全な成長は,つまり心が健全に成長しているということです。しかし,生まれたばかりの自然のものは傷つき易いのです)ものが傷つけば,自己を正当に愛することができません。信頼する(自信を持つ)ことも困難になります。自己がそういう状況に置かれると,当然,他者愛も他者を信じることも難くなります。
先生に訊かれて,「鼻水・・・」の口実を考え,先生に,「そんなことで休む子はいない・・・」といわれて傷ついたのは,(表の)自我が引き受ける能力に欠けるものがあることを示しています。先生の自我は,その点,健全な状況にあるので,鼻水が出たくらいでは学校を休むとは信じ難いのです。一方,A君は,得体の知れないことに悩まされているのを察してほしいと思っているのでしょう。更にいえば,幼い子の自我が母親のそれに取りすがるように,先生の自我にも取りすがりたかったのだろうと想像されます。甘えといえば甘えですが,小児心性の支配を受けているのですから,ふつうの意味での甘えとはいえません。心の構造が病的になっている心的状況下での言葉にならない叫びが,甘えに似ていることのように思われます。
母親に十分には甘えることができなかったことに起因する幼児心性が,先生に母親代理の役を期待したようです。そこに介入できなかった自我は,先生の質問にあって,答えにならない答え方を探し出したということでしょう。それで引き受ける意志を示せず,頼りにならない自我を差し置いて,裏の自我に拠る幼児心性が怒りを表したのだと思われます。
A君が気になるのは,裏の自我が主宰する,不気味な’心の沼’の存在です。それは死の恐怖につながります。夜になると気になる幽霊は,その沼から立ち上がってくる名状し難い不気味なものが,イメージ化されたものといえるようです。
’心の沼’は死へと斜傾する心の川の流れにつながると考えると,病的な心理の理解に役立ちます。この沼の首座にあるものを裏の自我と呼ぶことは,同様に人間の心を理解する上で有意味です。
表の自我を彩る感情が生気感であるとすれば,裏の自我を彩るそれは怒りです。
たびたび述べてきたように,人の誕生は自我の誕生です。人は自我に拠って存在可能となるといえます。
誕生以前の世界を,自我に拠る人間が遠望するかぎり,全または無に見えると思います。そして自我に拠るかぎり,世界は生と死に二分されて現前します。自我は世界を二分法で捉えるのが特徴です。生と死をはじめ,全と無,自己と他者,男と女,条理と不条理,愛と憎しみなどなどというように。
自我の誕生によって生の方向が目指され,それは即座に死の方向が打ち出される必然の下に人はあります。このように心の川には,対立し,相互に相容れることなく矛盾し合うふた筋の流れができます。一つは生へと向かう流れで,一つは死へと向かう流れということになりますが,この川筋ができる心の形成の歴史の発端に母親が大きく関わっています。つまり甘える欲求を赤ん坊が満たされているかぎり,生の流れが勢いを持ちますが,それが満たされなかったかぎりで死への流れが形成されるのです。甘える欲求は生の方向での源流を形成するといえるようです。それだけにその欲求は強力なエネルギーを持っています。しかし二分法の原理の下にある人間の心には,それとは反対の流れができないわけにはいきません。それを形成するのは怒りと恐怖です。つまり心の川の死の流れがはじまる発端には,甘える欲求を上回るエネルギーを持った恐怖と怒りに竦み上がる体験があったに違いありません。それは甘える欲求を満たしてくれる母親その人によって惹き起こされるのです。それはつまり,見捨てられる恐怖です。この根源的な恐怖は,赤ん坊が全生命を要求することが,人間的な現実の原則に反することであるのを教える意味を持ちます。そして恐怖の陰にある怒りを抑圧することに伴って,死へと向かう川筋が形成されることになります。
このように人が生きる方向で可能性を切り開き,自己形成をはかろうとすれば,死へと向かう心の川の流路の存在を必要としているという甚だしい矛盾をも受け入れていかなければなりません。そしてその相容れ難い矛盾をもたらす源流のところに,原初の他者である母親が介在しています。それは心を形成していく上で,複雑に矛盾するものを抱え込む理由になり,悩み多き人生を作り出す理由となるものでもあります。人は単に優しくあることはできません。人が人と関わることによって,原初の恐怖と怒りとが刺激されるのは,いかなる場合でもむしろ避け難い話です。絶えざる矛盾,絶えざる葛藤を乗り越え,乗り越えしながらでなければ,人は人を深く愛することはできません。
心の病理的な諸現象は,表の自我の衰弱に伴ってのことであるのは論を待ちません。それは自我が白い子を護り切れなかった度合いの多寡と関係があり,死へと斜傾する心の川の流れが勢いを増していることを意味するでしょう。そしてついに表の自我が主導権を裏の自我に譲り渡すにいたったときに,心の病理現象が問題になります。その病理性は,社会性や精神性に欠けるものがある心の状況と同義です。いずれにしても人は,生きているかぎり表の自我に拠ります。裏の自我はこれを無視することはできません。社会性と精神性とを欠いている裏の自我は,表の自我を傀儡化して社会性の体裁を保つことになるといえます。
(犯罪者の心理となると,「人の衣装をまとった獣」といわれるように,裏の自我が積極的に表の自我を操っている様相と考えられます。そのようにして社会をあざむき,自己の欲得に積極的にかまける心の態勢が作り出されているのが,犯罪者の心理的特性といえるだろうと思います)
A君は,先生に,「鼻水が出たぐらいで休む子はいない」といわれて傷つきました。翌日,学校を休んだのはその証拠のようなものです。先生のこの言葉に,A君は怒りを覚えたに違いありません。その怒りは先生とA君自身とに向かったと思われます。先生に対しては,A君にも説明がつかない’本当の理由’を察知してもらえなかったためです。それは母親に分かって欲しいのに分かってもらえなかった,甘えたい欲求の存在がかつてあっただろうことをも暗示しています。また,答えにならない答えをした自分自身にも腹を立てたと考えて間違いはないでしょう。
結局,怒りは無力な自我に引き受けられることがなく,抑圧されたのです。そして自我によってまたしても引き受けられることがなかった怒り(それは,はるか昔,見捨てられる恐怖体験によって抑圧された怒りに淵源を持つものでしょう)が,改めて怒りの沼を刺激して,A君を押し流そうとしたのです。学校に行くというのは,生きる方向での心の川の流れに乗らなければなりませんが,逆の動きをする川に引きずられたといえるのです。
怒りをどう扱うかは,すこぶる重要な問題です。怒りは,いわば黒い子たちのものなので,自我の介入がなく表に出れば,つまり憤怒ということになります。対人関係を破壊する動きになります。抑圧すれば怒りの川の勢いをつけることになり,意気消沈することになります。
自我が介入(引き受ける)するのでなければ,いずれにしても自己を窮地に追いやることになります。自我が介入するということは,いうならば黒い子たちを代弁する意味を持ちます。つまり,その存在を自我が認めたことを意味します。それは自我がしなければならない仕事なのです。そして自我が仕事をするかぎり,心は健全であるといえます。
更にいえば,怒れる川が勢いを増している心の状況では,自我は,その流れの始原にある見捨てられる恐怖(と潜在する怒り)に怯えた記憶を蘇えさせたように,凝結してしまう傾向を持つようです。
A君に先んじて受診したのは母親でした。母親の両親の問題があり,そのころ母親は怒りに駆られる人でした。そのあおりで夫婦喧嘩がしばしばあったといいます。恐らく,幼い時代のA君は恐怖心に怯えていました。満足感と安心感が不足していたのに違いありません。それは甘えを通じた母と子の関係が望ましいものではなかったことを意味するでしょう。
表の自我は生を志向し,裏の自我は死を志向すると先に述べました。
A君についてこのことを見てみると,赤ちゃん時代の母との関係が第一に問題になります。持って生まれた気質はともかく,養育環境としては母親がすべての時期がしばらくつづきます。それは赤ちゃんといえども,人間として生を受けたからには,死の問題に無縁であり得ないということに関係します。
先にも述べたように,人間は自我に拠って存在可能であり,その自我は世界を二分割して捉える特徴を持っています。その淵源は,人間の存在以前の世界を,自我は生と死との二つに分割して現前化するところにあるように思われます。
赤ん坊は人間として生を受けたときに,死を垣間見て怯える者でもあらざるを得ません。そのために赤ん坊は,母親に全を要求するのです(生誕以前の状態への回帰の要求ともいえるのでしょう)。それは母親を支配しようとするのとおなじ意味を持ちます。赤ん坊は怒りくるって泣き叫び,母親に要求を呑ませようとすると思われます。そうすることによって,万全の安心を手に入れようとするのです。安心がなければ満足はありません。満足感と安心感とは一体のものです。
しかし母親は全なるものではありません。母親には赤ん坊にそれを教える役目もあります。それは無意識的にであれ,死の存在を教える意味を潜ませることになるのです。
意識的には母親は,赤ん坊に死の存在を理解させようなどとは夢にも思わないでしょう。一所懸命に赤ん坊に愛情を注ぎ,可能なかぎり赤ん坊を怯えから護り切りたいと願うと思います。しかし,母親は全なる存在であるのを教えるしかありません。それは母親が,赤ん坊に死の存在を教えないわけにはいかないのとおなじ意味になるのです。そのことは,むしろ母親にも意識されていないはずです。母親自身もそのようなおぞましいものは見たくもないのです。しかし,いわば心の自然のプロセスとして,思わずそれを教えてしまうのです。それは避けるわけにはいかないものであり,避けてはならないものでもあります。
死の存在を赤ん坊に教えるのは,母親の怒りによってです。全的な存在ならぬ母親が,赤ん坊に対してといえども,怒りを一掃してしまうことは不可能です。そしてそういうあるときに,全を要求する赤ん坊の激しい怒りが,母親の顔に投影されて跳ね返ってくることがあるだろうと想像されます。それを感じたときに赤ん坊は,死を垣間見ることになるだろうと思われます。そういう折に,母親の顔が悪鬼の表情に見えるのかもしれません。実際は悪鬼のように怒っているのは赤ん坊の方なのですが,母親の顔にそれが投影されるのです。赤ん坊が見捨てられる恐怖を持つのは,そのときだろうと推測されます。そうなると怒りが恐怖に変わり,今度は母親を怒らせないように要求を自制するようになるでしょう。全生命というものはない,従って生きることには死が含まれていると身をもって知ることはどうしても必要なのです。そのことは人間が人間の現実世界を生きる上では,どうしても受け入れなければならないのです。しかしこの恐怖の度合いが強いと,必要以上に甘えることを断念してしまうようになるかもしれません。恐怖の度が強ければ,幼い心の自我は母親を怒らせないために,生まれてくる諸欲求を抑圧する傾向を強めることになるでしょう。それはいうならば心の負債を大きすぎるものにしてしまう理由になります。誰であれ心の成長過程でこの意味での負債を負います。それは程度の差はあっても避けることはできません。そしてその心の負債を自我が返済していくことが,いわば人生の目標であるとさえいえます。そのようにして人は成長していくのです。しかし負った負債が甚だしいものであれば,よほど強靭な自我でなければ,返済は困難になります。返済が困難であるということは,その重荷に押しつぶされる可能性が高まるということでもあります。そのままでは自我が無力になり,生命感情を豊かに育てていく上で大きな困難を持つことになるだろうと推測されるのです。
甘えがどの程度満たされているかは,母親との関係の良し悪しを占う道標になります。そしてその後の人間関係をも占う道標となります。甘えられない母親との関係では,自分は愛されていない,嫌われている,価値がないといった考えに囚われることになり,それは自己愛が傷ついていることを意味します。そして他者についても疑い深くなり,愛情を持ち難くなると懸念されます。
幼児期には活発に欲求が生まれてきます。それは内在する主体が送り出してくる,いわば神の子と考えることができます。自我はそれを護る使命を帯びています。それらのことは自然のものとして起こるでしょう。しかし幼い自我が諸欲求を護るためには母親の協力を欠かせません。すべては乳幼児と母親との関係の基調である甘えに還元されるのです。つまり甘えが満たされている関係であれば,幼い子の心に生じたさまざまな欲求は,おおむね自我に受け入れられ,護られるでしょうが,満たされ方に問題があれば自我によって抑圧される傾向が強くなりがちでしょう。
いたずらなり何なり,幼い子が何かをするときは,母親に認めてほしい心が付随します。それは甘えに他なりません。自我が発達した年齢であれば,何らかの行為を楽しみ,評価するのは自己自身でなければなりませんが,自我が未発達な幼児としては,母なる他者によって支えてもらう必要があるのです。
このようにして,護られなかった神の子は,自我に生気感をもたらすはずだったエネルギーを,怒りのそれに換えて無意識の世界のものとなります。そういう影の分身たちが,無意識界に不気味な沼のようなものとなって勢力を張ります。それは自我によって受け入れを拒否されたものであり,従って生の世界のものとしては認められなかったものたちです。つまりそれらは死を志向する勢力です。そして生を志向する心の首座にあるものを表の自我と呼び,死を志向する心の首座にあるものを裏の自我と呼ぶことが,心の病理的現象を理解する上で有益です。
裏の自我は,既に証明されている脳中枢にある怒りの座に,一つの根拠を持つだろうと推測されます。
A君は,他人に対して過敏です。人と争うのを好まず,誰とでも仲良くしていたいと思っています。母親によれば,友達は男女を問わず大勢いるそうです。しかしA君は,’真の友達’はいないと思っているようです。
A君が望む’真の友達’とは,「揺るぎのない心の支えになってくれる友人」,といったもののように思われます。そのような友人に出会える可能性はあるでしょうか?ない,というのが私の答えです。
A君がもとめる’真の友人’というのは,恐らく’全’をもとめる乳幼児の心に通じるものです。つまり乳幼児が,母親に対して持つ支配欲求に通じる心性といってよいだろうと思います。その心性は乳幼児に特有のものです。言葉を換えれば,心の成長過程で克服していなければならない心性です。この支配欲求は,闇(死)への怯えを一掃したいという願いです。母親にはそれを可能とする力があるという幻想を,赤ん坊は持っているようです。つまり赤ん坊にとって,母親は’全なる者’なのです。誕生したばかりの自我は,生を引き受けるべきものですが,生(光)の裏面である闇(死)に過敏に脅かされると想像されます。赤ん坊の萌芽でしかない自我は,その脅威によって破壊されかねないので,防護装置として万能感が備えられていると想定されます。それは自我に拠って世界が二つに割れたこと(生の世界と死の世界),自我の誕生以前の世界が’全’であることを暗示しています。万能感とは,全的な存在への幻想であるということができます。
ところで母親と一体の関係にある赤ん坊には,自分に’全なる力’があるのと,母親に’全なる力’があるのと区別がつきません。赤ん坊に,自分が’全なる力の持ち主である’という大安心を保証してくれるのは,’全なる力’を持っているはずの母親です。そして一方では,闇に絶えず脅かされることによって,母親が自分を護る気がないのではないかという猜疑心に囚われると思われます。赤ん坊は怒りをこめて,母親を支配しようとすると想像されます。全面的な支配を欲するのは,それが可能であるとする幻想があるからに違いありません。そして全的な大安心を提供する力があると幻想するからこそ,’未だ与えられていない’ことに激しい怒りを持つのです。そしてまたそこには,相手方である母親にそういう力はないのかもしれないという予感もどこかしら働いているに違いありません。あるに違いない,あるはずだという要求は,既に半分は疑惑なのです。疑惑がなければ要求は起こりません。そしてその疑惑の一部は,(母親が)持っているはずなのにくれようとしないというものでもあるだろうと思われます。それは自分が大切に扱われていない,愛されていないということに直結します。生死がかかっているこの要求は,ほどほどのものでは満足されることはありません。ですからきょうだいの中でも,自分が第一等でなければならないのです。そして,それは相手方(母親)が全なるものではないという恐怖に満ちた予感と,一体感の破綻の予感とに脅かされてのことのようにも思われます。
いずれにしても相手(母親)を完璧に支配しないかぎり,真の安心はありません。そしてその大安心幻想があるかぎり,小安心に甘んじることができません。その幻想の下では,全部でなければ無に等しいのです。つまり人間は小安心に甘んじることができなければ,無の感覚に脅やかされることから逃れることができません。
これらの恐怖は,母子分離の恐怖でもあります。
小安心に甘んじることが出来るようになるには,大安心幻想を捨て去ることが不可欠です。それは母親が全的な存在ではないことを受け入れることによって可能となります。その意味のある諦めは,見捨てられる恐怖をうまく克服できたときに生じるでしょう。この根源的な恐怖は,人間が人間であろうとするときの最初で最大の関門です。それを克服できれば,母親を現実的なものとして受け入れることができます。つまり,互いに小安心に甘んじなければならない頼りない身分であること,従って互いに助け合うことが必要である(信頼と愛情とによって)こと,大安心はないと知ることによって,自分で自分に小安心を提供しつづけることが求められていること,母親と自分とは支配ー被支配によって全的に一体化するべきものではなく,相互に分離ー独立した存在であること,従ってそれぞれが人格という個的な存在であり,それぞれに自由であること,などなどが自然のものとして受け入れられることになります。
そして一方,この恐怖をうまく克服できなかったとすると,母親が永遠に全なる人であるとする幻想から逃れることができません。その幻想に依拠することによってのみ存在可能なので,もらえるはずの大安心を当てにして母親にしがみつくことになります。それは,当然,母親を信頼している姿ではありません。信頼しきれない姿です。その不信の根源にあるのは,見捨てられる恐怖です。
大安心を諦めきれないでいる心と,小安心に甘んじることができている心とを分けるのは,おそらく見捨てられる恐怖を幼い自我がどう扱ったかの問題です。前者の自我はこの恐怖を克服する術がなく,一途に抑圧したと仮定されます。そのとき母親は死に匹敵する巨大な恐怖をもたらすものです。その恐怖はそれに匹敵する怒りの存在(当然与えられるはずである大安心を与えられない怒り)に関連するでしょう。自分の怒りの巨大さに恐怖を持つともいえるだろうと思います。そしてその怒りの巨大さは,一対の相手である母親の怒りと区別がつかないのです。それらの恐怖と怒りは,無力な自我が引き受けられるものではないときに,強力にそれらを抑圧して母親の自我に拝跪するのです。そのようにして,巨大な恐怖をもたらすものの怒りを鎮めようとするのです。
大安心幻想は乳幼児のものです。長じてなおこの幻想の支配を受けている自我は,個の確立が不確かであることになります。その幼児心性の下では,勝手な行動は取っても,自由に行動することは困難になります。そもそも自由に生きるという意味が感覚的に分からないという人が珍しくありません。この幼児心性の下では,他者の自由は脅威でありつづけるのです。別ないい方をすると,どうしてみても闇の脅威におびやかされるのです。
自由の精神とは,自分自身の自由のみならず,あれこれの他者の存在をそれぞれの個として,それぞれに自由であると尊重することができているときに可能です。それは大安心幻想をあきらめ,小安心を受け入れることができている個性に対する別な呼び方といえます。
A君が友達たちの些細な悪意に脅威を覚えるのは,友達の自由を尊重することができないためといえます。人の自由を’真に尊重’できないかぎり,人を’真に信用する’ことはできないはずです。母親をさえ信用できません。というよりは母親との関係で個の確立が不確かであること,それは同時に母親の自由を尊重することができていないことに,この問題の核心があります。
母親が自分を捨てるとは考えられなくても,不慮の事故に遭わない保証はありません。病気で命を落とすことになる可能性を排除できません。それらの不安を一掃するためには,赤ん坊のように母親と一体化するしかありません。否,赤ん坊もこの不安から免れることはできません。赤ん坊以前,自我に拠る世界が現出する以前の世界のものになるしかありません。それは絶望して死を望む心に他なりません。
見捨てられる恐怖の克服に失敗して,完璧な他者,全なる他者を求める大安心幻想の支配を受けているかぎり,心の平穏は困難です。
A君の’すべての人と仲良くしていたい’という願いには,このような心理的な意味が隠れていると思われます。だからA君が心の平穏を獲得するためには,友達たちの個と自由とを容認することができなければなりません。それは,死の存在を容認できることとおなじ意味になると思います。つまり生の裏面は死であり,対立し相容れない矛盾である両者を共に許容できなければなりません。死という現実問題を受け入れることができるときに,ようやく生と死との矛盾を生きる力を得るのです。そのときに,相容れない矛盾を止揚する心のダイナミズムが生まれてくるのです。
人間の意識は有限のものです。しかし人間は無限性を生きる存在です。仮に有限性を生きるのが人間であるとすると,生きる意味はほとんど失われるでしょう。ある有限の時空にいたって人生が,あるいは自己の形成が,完成し,自足するという事態は想像できません。
無限性を生きるというのは,生と死という相容れることのない永遠の対立が,姿をさまざまに変えて現れ,そして超克されていく意識のダイナミズムを生きるということです。それは生があるかぎり死があり,それが対立し合うかぎり,無限定に上昇しつづけることが可能な意識のダイナミズムといえます。
ここにこそ人間精神の自由の実態があり,それは幾分か比喩をまじえていえば,人間精神が無限の時空間を縦横に飛翔する姿であるといえます。
精神の自由の問題は,次のように考えることが可能です。
赤ん坊の生みの親は,いうならば二人います。
一人はいうまでもなく母親です。そして’もう一人’は,人間に自我を授ける力を持ったものです。それは人間以上の存在と考えないわけにはいかないものです。自我を授与した人間の上位に立つものは,以下のような意向を示していると考えることができます。
「自我に拠って思うように生きてみよ」と。
そしてこの上位者は心の無意識界に鎮座(内在する主体)して,沈黙のうちに自我の活躍ぶりを注視していると考えられます。
一方,母親はこれに対して,「お母さんを安心させるような子になりなさい」という暗黙のメッセージをもって育児に当たるだろうと思います。そしてそれは愛情といえる面と,母親の私心といえる面とがあって当然でしょう。
自我は生に奉仕するものですが,赤ん坊が生まれて間もない早期の段階では,母なる他者の絶対の補佐を必要とします。自我の生誕は光の世界の幕開けです。しかし,赤ん坊の未熟な自我は自ら活動する力を持ちません。母親の補佐(愛情)を受けて,自我の原基が刺激され,徐々に自ら光を発する力をつけていくのです。このような光の黎明期(乳児期)では,闇(死)の存在に殊更に脅かされると思われます。自我が自律機能を活発化させて人生を切り開く力を得るまでは,母親の愛情によって保護されるのでなければ,自我は立ちすくみ,いわば凍りついてしまうことでしょう。
自我は自律機能によって生を志向しますが,抑圧機能によって自律性を阻害します。前者は主体の命に基づこうとする機能であり,後者は他者の意向を重んじようとするときに働く機能といえます。抑圧機能は他者を前提としたものです。つまり自我には他者への配慮が構造化されています。
自我がそれなりに成熟して自律機能が活動しはじめてからも,いうならば無化される脅威に対抗するために,自我は他者との関係を不可欠なものとしています。自我の機構には,他者のイメージを生み出す機能が内属していると考えられるのです。そのために,他者は客観的に外部に存在するだけではなく,内なる他者として自己の内部の無意識界にも存在しています。
ですから他者との関係を必須のものとしている自我には,抑圧機能は,(自己を護るために)欠かせないものです。それは生死を分ける問題に関わるものでもあるので,自律機能以上に重要ともいえます。しかし自律機能が不十分であれば,自己の好ましい育成は望めないことになります。自己は他者に見放されても,自己自身に見放されても立ち行かなくなるという難しい問題をかかえているのです。
自己の自己自身との関係が好ましい形になっていれば,それは主体との関係が良好ということになります。そのことは誰もが目指すべき理想でしょう。そしてその関係を混乱させる元凶は,他者の介入,他者への行き過ぎた配慮です。それは主体との関係を中心にしてみると,巧まざる自我の堕落といえるものがあります。幼い自我にそのような要求をするのは無意味ですけれど,心の内部の事情を主体の観点からするとそのような意味になるように思われます。それは自己形成の上で犯罪的ともいえる結果をもたらしかねないのです。心の内部の法廷で有罪判決を受けたかのように,人生が地獄化することは決して珍しくはありません。
自我は,あちらを立てればこちらが立たずという難しい舵取りをしなければなりません。生誕につづく原初の段階では,全面的な他者(母親)の補佐を必要としているといういきさつから,自我が不始末を起こす状況的素地は十分過ぎるほどにあるのです。それは避けることができない人間の宿命であるといえます。そしてその幼い自我の避けられない不始末によって,’心の沼’が生み出されるのです。
’心の沼’は,,破壊的な力を蓄えた影の分身たちが,いうならば跳梁跋扈する闇の世界です。自我に脅威を与えるほどに,怒りを伴う破壊的な力を蓄えてしまっている’心の沼’がそのままに放置されていれば,ストレスに大変弱くなります。場合によっては,さまざまに由々しい人間の不幸,悲惨を招き込む,心的事態に陥ることにもなります。
自然的な自我が,内在する主体との接触を妨げられ,節度が曲げられるのは他者の介入によってです。
主体との関係を見失うのは,他者の介入による自我の不始末といえる側面があります。しかし圧倒的な力を持つ闇(死,無限,無であるものに繋がるものです)に包囲されている自我は,あまりに頼りなげな存在です。たちどころに無の闇に飲み込まれ,無化されてしまいそうな脅威の前に,自我は他者の力を当てにするしかありません。このような事情があるので,人間を頽落させるのはしばしば人間自身であるという無残な悲喜劇が,人生のここかしこに見られるのです。
自我が抱える難題は以上のようですが,総括的にいえば次のような問題があります。
自我に拠って生の世界が始まり,それは同時に死の世界の始まりであると繰り返し述べました。それは,自我の使命が,「死を課題化せよ。死に向って希望の光を掲げつづけよ」という難解極まりないものであることを意味します。人間の常識では理解不能の課題を,自我は負っています。禅問答の極みのような話です。
患者さんはしばしば,「何のために生きていなければならないのか?何故死んではいけないのか」という問いを持ちます。
それに対する答えは,「人間は自我に拠る存在だから。自我は引き受けるのが使命だから」ということになるのでしょうが,難問であることには変わりありません。
自我の使命は人生を切り開くことであり,自己を形成することであり,生きていくことです。ですから死は自我の終焉とともにあります。死によって生が終わるという意味では生は有限です。しかし生は単純に生ではなく,絶えず死をはらんでいます。
失敗の危険のない試みはありません。必ず成功すると決まっている試みはありません。成功は自我の勝利,つまり生の世界での営為です。失敗は自我の不始末,つまり死の世界への斜傾ということになります。
大冒険は死の危険と隣り合わせの行為です。スポーツ選手の新記録は,身体を極限まで鍛え上げる(身体を壊しかねない)ことなしには得られません。芸術作品は心の闇の表現です。科学者の大発見は失敗すれば一切が瓦礫化する怖れと共にあります。
死を賭けない成功は大したものではありません。そして大成功があっても,すぐに虚無の影が忍び寄ってきます。
精神の充実は自我によってもたらされますが,それは死(無)による意識の無化作用を一時的に沈黙させることができたに過ぎないともいえるでしょう。それは永続するものではなく,充実の獲得と共にすぐさま無の無化作用に脅かされるので,自我はひと休みしたあとは次の仕事に取り掛からなければなりません。
癌に侵されるなど死期の迫った人については,先に述べた「死に向かって希望の光を掲げよ」という主題はどうなるでしょうか。しだいに優勢になっていく死の無化作用は,自我の回収作業ともいえ,自我自身は従容として身を任せるしかありません。それは最終的な生と死の合一に向かっての回収作業といえるのでしょう。
臨終に当たって,「これでいい,これでいい・・・」という言葉を残した偉人の逸話が伝えられています。「これでいい」かどうかの判定者は誰かという問題があります。仮につぶやいた人自身であるとすると,単なる自己満足の域を出ず,強がりと区別がつけられません。しかし内在する主体の支持にもとづくものであれば,それは人生の達成というものに等しいかもしれません。そしてそれは自我の回収作業に携わる主体でもあるかもしれません。
いずれにしても死は人間の手に負えるものではありません。そこから先は,人間の上位者に任せるしかないというのは自明のことです。死刑,自死,安楽死などの問題の根本にはこのことがあります。
人間が存在する根拠は人間自身にはありません。つまり人間が最上位者ではないのが明らかである以上は,最上位者の存在を認めないわけにはいかないでしょう。自我がその者の存在に拝跪するのは当然のことです。その姿勢が,つまり,引き受ける精神です。謙遜は引き受ける精神の別称といえます。
自我に拠らない人間の上位者が,自我に拠る人間に向けて立てた問いが,人間の眼には先に上げた究極の矛盾のようなものに映るといえるのでしょう。
また,この解き得ない矛盾のような問いを負うのでなければ,人生はひどく詰まらないものになるでしょう。解き得ない矛盾に見えるからこそ,人に与えられた可能性は無限なのです。矛盾し合う二つのものを止揚しつづけることが未来を開くのです。それは生きているかぎり終わりのない展開です。そういうものを想像するのも困難ですけれど,仮に一切が有限の世界であるとすると,人生は永遠の退屈になるしかありません。
自我は自立を理念としています。しかし自我は内在する主体に絶対的に依存しています。主体が自然の属性を色濃く持っているのに対して,自我は人間を人間たらしめるものであり,人間が自然から乖離され,独自の存在形式を許された象徴ともいえるものです。従って自我の自律性は,自己を保ち,世界を切り開くために欠かすことができないものですが,それが健全に機能するのは,主体との依存関係が良好に保たれていることがあってのことです。
また,自己は他者とのあいだでも絶対的な依存関係にあります。それぞれの自己は,現実界の他者を排除して孤独に生きることは可能ですが,心の構造には内なる他者が構成要件の一つとして存在しています。そうでなければ,他者は異星人のように不可解な存在であることになるでしょう。内なる他者が心の構造に生まれつき組み込まれているので,他者を外なる自己として,異星人に対してであれば感じないであろう親しみの情をもって容認し,理解することができるのです。
また,それぞれの自己は,そのときどきの対象との関係において存在しています。その関係の連鎖の先には,他者が介在してきます。
要するに自我に拠る自己は自立を目指しますが,それはなにものかとの依存関係においてであるというのが,人間存在の特徴です。人は,本質的に依存的な存在です。
依存には好はましいものと好ましくないものとがあります。好ましい依存は,主体との関係が良好であるというところに行きつきます。それがあれば,いわば自己の軸は心の中心を貫くことになり,いってみればダルマ的な存在になることができます。つまり,何かのストレスに負けて心がグラリと傾いても,速やかに心の姿勢を回復させることができます。そうであれば他者との関係も自由になります。主体との関係がしっかりしていれば,孤独であることが脅威にはならないからです。
好ましくない依存とは,逆に主体との関係が危うい場合です。先の比喩に従えば,心の軸が中心を大きく外していること,換言すると,(主に)母親への隠れた依存が無視し難いことを表しています。それに伴って’心の沼’が強いエネルギーを抱えていることを表しています。
自我の抑圧機能が過度に働けば,自律機能を歪めることになるので,’心の沼’が勢力を強めることになります。そうであれば他者への依存が過度になるか,逆に拒否的になるかということになるでしょう。他者にも,自己にも信頼がうすくなります。孤独であることに耐え難いか,シェルターに避難するかのような孤独になるか,いずれにしても他者に対して自由になれません。
そもそもが,表の自我による人格は精神性と社会性とを備えています。これに対立する形である裏の自我は死を志向します。表と裏との相対関係で前者が劣勢になれば,それに相応して,虚無感に囚われ,あるいは非社会的ないしは反社会的という性格が色濃くならざるを得ないといえます。
過食症は好ましくない依存の一つです。つまり裏の自我に支配された表の自我の依存的な営為です。こういう問題が起こるのは,人格形成の最早期に,情緒的な満足が得られなかった何らかの事情があったためではないかと推測されます。想起するのは不可能であるほどの人生の初期に何があったかは分からないのですが,情緒的な満足が得られなかった理由は,主に養育の中心である母親との関係に求められるだろうと考えるのが自然というものです。情緒的な満足は,自我の根が無意識という大地にしっかりと下りていない乳児には,欠かしてはならない大切な肥料です。それを求めるのは本能的なものと思われますが,一方で乳幼児には見捨てられる恐怖というものがあります。これは他者への絶対的な依存を必要とするかぎり,生き死ににかかわるもので,根源的といえるほどに強力なものだろうと思われます。
生まれたばかりの赤ん坊は,なにはともあれ人間の誕生です。その意味は,これからは自分の力で生きていきなさいということです。赤ん坊は極度に感覚的な存在だろうと思われますが,その意味は分からなくても感覚でそれを捉えるのではないでしょうか。母親のお腹の中にいるときの自然的な状況から,あるときいきなりお産という形でまったく異なる環境に放り出された驚愕は(大人の感覚での類推になりますが)並大抵のものではないだろうと思われ,その恐怖は甚だしいものだろうと推測されます。その恐怖を和らげるお守りが万能感と呼ばれているものです。それは母親のお腹の中にいたときの安全感覚を,保障しようというものでしょう。
万能感と呼ばれているものは,E・ノイマンが次のように述べていることに通じるものがあると思います。
「人類の生まれつつある自我意識の最初の何段階かは,ウロポロスの支配下にある。これは自我意識の幼児期であり,もはや胎児ではなく,すでに独自の存在となってはいるが,なお円の中にいて,まだ円から出ておらず,ようやく円から自らを区別しはじめた段階である。・・・世界は周りを取り囲んでいるものとして体験され,人間はその中でとぎれとぎれに,瞬間的にのみ自らを自らとして体験する。・・・幼児の自我が,ほんの一瞬無意識の薄明の中から小島のように浮かび上がったかと思うと再び無意識の中に沈んでしまうように・・・偉大な母なる自然に守られ,抱かれ,支えられ,あやしてもらい,そして善きにつけ悪しきにつけ彼女に身をまかせきっている。
・・・世界が保護し,養うのであって,彼・人間が意志し,行為することはほんの稀にしかない。無為,無意識の中に抱かれていること,すなわち必要なものがすべて偉大な養母(原母)から絶えずこんこんと湧き出してくるような尽きざる薄明の世界,これこそ原初の’至福’状態なのである。・・・ウロボロス近親相姦における一体化は心地よさと愛を特徴とするが,これは能動的なものではなく,むしろ溶け込み吸い込まれようとする試みである。・・・快楽の海と愛による死の中で消滅することである。・・・死は・・・すなわち母との一体化というウロボロス近親相姦の特徴をおびている。・・・人間の意識が自らをこの原深淵の子とみなすのは正しい。・・・そしてこの意識は毎晩眠りの中で太陽と共に死んで,母なる無意識の深淵へと沈み,帰っていく。そして翌朝再生し,昼の運行を新たに始めるのである]
胎児の段階と赤ん坊として生まれる段階とのあいだの落差には甚だしいものがあり,その激しさを和らげる何らかの機構がなければ生存に耐えないだろうと推測されます。その機構が万能感といわれるものであり,具体的にはE.ノイマンが記述するようなことではないかと思われます。
この万能感を具体的に保証する役割を担うのが母親です。しかしいうまでもなく母親は,ほどほどの満足をしか与えることができません。赤ん坊は,万能欲求をしばしば裏切られ,失望する宿命の下にあります。「この人は,本当に凄い力を持っているのだろうか」とか,「この人は凄い力を持っているのに,なぜ私にそれを与えてくれないのだろう」といった不信,疑惑に,怒りと共に囚われることでしょう。それらが見捨てられる恐怖の母体となるのだと想像されます。
そういう折も折,過敏な赤ん坊が,何らかの御し難い恐怖に捉えられるということがあれば,情緒的な満足を求める生きる本能(自律機能を育てるために重要です)よりは,捨てられることの死の恐怖の方に圧倒されるのではないかと思われます。赤ん坊は,いわば沈黙して,母親の自我にしがみつくことで,危機を回避しようとするのではないかと考えられます。母親の自我の傀儡となることで,見捨てられる恐怖を鎮めようとするのです。それに伴って情緒的な満足は抑圧されることになります。
これらのことは,あらゆる乳児に起こる心的過程だろうと思います。自然ならざる人間は,このようにして他者の介入を必要とし,それによって,程度の差はあれ自然性を歪められることになるのです。
あまりに幼いときは母親は絶対者ですから,乳幼児たちは服従する以外にありませんが,成長するにつれ,しだいに自己主張がはじまるのが自然です。それは親子の関係で蓄積されてきた,いうならば歪みエネルギーが,いずれどこかで放出されずには置かないという意味合いを持つ自己解放の動きです。それによって親子関係の是正,修復が目指されるのです。
これまでに述べたことから,人間の誕生にはいわば’二人の親’が関わっていると考えることが,精神構造を理解する上で有用です。第一の親は,自我を授ける力を持った’人間の上位にあるもの’です。そして第二の親は,ふつうの意味での母親です。このような考えが可能であるという前提に立てば,真の親は前者であるのはいうまでもなく,後者はいわば前者から仮託されていると考えることが可能です。
前者は,「自我に拠って自由に自己を導くように」という意向を示し,内在する主体として,無意識的な心の世界で沈黙のうちに自我の営みを見守っていると考えられます。
後者は,二つに分離,対立する特徴を持つ自我に拠るものの宿命として,二心を禁じ得ません。つまり,立派に成長してほしいという当然の願いを母親は持ったとして,そこにはそれが赤ん坊に対する愛情である一方,母親自身を安心させて助けるようにという私心も入らないわけにはいかないのです。
前者が沈黙のうちに見守るとすれば,後者は良くも悪くも有形無形の口出しをすると考えてよいと思います。無形の口出しというのは,超自我の関与ということになるでしょう。
先にも述べましたが,自我領域にはいわば三つの山(立場)があります。
中央に位置するべきものが自我です。この自我と重要な他者(性格形成の初期ほど重要な意味を持ちますので,この重要な他者とはほとんど母親であるといえます)との関係で,必然的に派生されてくるのが,一つには超自我の山であり,一つには黒い子たちの山ということになります。そして無意識界にある沈黙する主体の沈黙する関与があります。
(過度によい子と,非社会的,ないしは反社会的な行動を取る子とは,対照的な心の病理現象と考えることができます。前者は無力な自我が超自我に絶対的に服従する心的構造下にあると考えられます。一方,後者の自我も無力であるのは前者とおなじですが,違うのは超自我もまた不在であるかのように未発達でいるらしいということです。そして後者の自我は黒い子たちの支配を受けていると考えることができます。
このことは,両者の自我が共に主体の意向に即することができないままでいること,そのために自己形成が病的なレベルになっていることを示しており,前者の超自我がいびつに大きなエネルギーを持つに至っていること,後者では黒い子たちがいびつに大きなエネルギー持ってしまっていることを示しているように思われます。これらの三つの山のどれが勢力を持っているかが,人格構造の基本的枠組みを決定的にしているといえるでしょう)
前者の命に沿うときに自我の自律機能が機軸になり,後者の命に沿うときに自我の抑圧機能が作動することになります。
赤ん坊にとっては母親はいわば神に匹敵します。その神なる母親は,赤ん坊には,自分に向けられた愛情に関しては何よりも心強く,しかし母親の私心に関してはそむくことの許されない恐るべき者といえます。
そのような事情から,幼い子の自己形成は,主体による第一の命題(自由に生きる)から大いに遠ざけられることにならざるを得ません。それぞれの心は,大いに歪まされながら自己形成が進行する宿命の下にある,それが人間である,といえます。
Bさんは50代の主婦です。近くに80代の母親,妹,二児の親である別居中の一人娘がそれぞれ住んでおります。Bさんは癌に侵されている夫と二人で暮らしています。酒好きの夫はあまり家庭を顧みなかったようで,夫婦の関係は以前からうまくいっているとはいえません。夫が勤めていた会社は倒産しました。取締役であったために保証金を差し出してあり,それが返ってこない上に,当然ということになりますが退職金はありません。夫への不満が高い一方で,夫は病気のためもありかなりわがままで,愚痴も多く,その相手をすることは容易ではないようです。
長女は十代から我がままのし放題というふうでした。実はそもそもは,当時十代だったこの長女が私のところに通院しており,途中から母親も通院することになったいきさつがあります。
長女が夫と別居生活に入った当時は,Bさんは,母親(父親は既に他界しています)が暮らす実家の敷地にあった小さな古屋に住んでおりました。
Bさんは,最近にいたるまで,母親のいいなりになってきたようです。母親は世間体を重んじる人のようで,Bさんが自分の家を持っていないこと,婿が失職していること,貧困であること,長く通院をして薬を飲んでいること,長女が婚家から帰ってきていることなど,ことごとく気に入らないようです。次女も母親のいいなりのようで,母親の命を受けて何かと言い募ります。そしてしばしば母親自身が罵倒します。Bさんが顔を出さないからといって腹を立て,夕方に雨戸を閉めに行くと,余計なことをするなといって怒ります。夕食のおかずを持っていっても受け取ってくれず,持ち帰ることもしばしばです。
家を出て行けと何度もいわれました。しかしBさんは母親の側を離れるのが不安でした。自分が困るというのではなく,母親が心配だと思えたのです。それでもようやく母親と別れて暮らす決心をしました。夫がまた,そこを離れて住まいを探すことに反対しつづけていたのですが,何とか説得しました。
マンションの一室に移り住んで一息ついたころ,孫達が騒ぐのがうるさいと苦情がきました。また引越しをしました。長女は当然のように一緒に住むと決めていましたが,今度は部屋が狭くてとても無理でした。それに30歳に近い年齢で,親に寄りかかって気ままに暮らそうとするのを黙認するのも問題です。強くいって,可能な援助はして,住居を別にすることになりました。そして悪態をついていた長女も,何とか仕事をする気になりました。しかし幼い孫の面倒をみてあげなければなりません。長女にとってはそれは当たり前で,感謝することでは決してありません。機嫌がわるいと,手伝いに来ている母親を激しく罵倒します。
マンションに移ってからも,相変わらず母親と,母親の手先のようになっている妹に責め立てられます。長女が婚家に帰ろうとしないのは親の責任だから,何とかしろといわれます。
Bさんは,もともと依存的な性格の上に,まったくの孤立,無縁の状況に置かれて,何度も絶望的な気持ちになり,死を待望するかのような日々でした。
そういうBさんに残されている唯一の可能性は,自分自身との関係を強化することでした。Bさんはその意味を理解しました。
敢て自由ということを意識するように心がけました。母親の,妹の,長女の,夫の,そしてBさん自身の自由をです。母親がいかに支配的な人であろうと,母親が何を考えようと,何をいおうと,さしあたりそれは母親の自由といえます。そしてその母親はBさんの自由などまるで配慮しません。Bさんは自分自身の自由を護らなければなりません。そのような甚だしい性格の母親が相手では,関係を断ち切る覚悟がなければ自由は護れません。Bさんは,非難,攻撃する妹に静かに耳を貸し,そして静かに,「縁を切ってもらって結構です」といいました。
母親との依存関係が殊更に強かったBさんにとって,「縁を切る」というのはいかに困難な課題だったか察するに余りあります。しかしBさんはぎりぎりの状況でそれを果たしたのです。
あるとき,晴れ晴れとした顔で,Bさんが次のように述べてくれました。
先日,娘の所にいたときに妹が来た(長女の叔母である妹は,Bさんの孫に会いたいのです)。Bさんが,「私はできることは精一杯やったわ。自分を褒めてあげたい気分よ」といったところ,妹は,「ほんとにその通り。よくやったよ」といっていた,と。
無論,皮肉ではなかったようです。
Bさんが試みた自分自身との関係の強化というのは,逃れようのない厳しい現実状況を,敢て引き受けることが,重要で,欠かせない出発点になります。Bさんにとっての救いは,幼い命を護りたい願いが,理屈ぬきの使命感につながったことでした。幼い子は,二度,三度と肺炎を起こして入院しました。それを助けたいという願いには,自分の命と引き換えにしてでもという切なるものが篭っていました。
現実を引き受けたことにより,それは押しつけられた(厄介な)ものが,(他でもなく)自分自身のものであるという意味に変換されることになります。押しつけられた意識感覚のままであれば,解決の主体は自分自身にあるとはいえません。現在の辛い状況は誰かのせいという被害的気分の中にいることにもなり,当てに出来ない何者かを当てにしつづけることになります。その場合は,不承不承「頑張る」しかありません。
「頑張る」ことには,他から課せられた問題に向かうという意味が込められています。
一般に何か行為をするときに,内発的な欲求と他者から課されたものとの混淆によって動機と意志が形成されると考えられます。
それは自我の自律性が内在する主体との関係において生じること,その自律性に即して主体から送られてくるエネルギーが欲動といわれるものであること,そして自我は自足態ではなく不十全な存在であるために,他者によって補完されるのが不可欠の要件であること,自律性が自我の生命線でありながら,他者の厚い協力がなければ,(無の無化作用の脅威に絶えずさらされている)有限なる自我の機能が存立の危機に瀕すること,他者の補佐は避け難く二心に基づくために不十全であり,かつ脅威ともなること,そのために自我は抑圧機能を不可欠のものとしていること,それは自律機能に対して優先的に働くものであるので,自己の形成,成長にとって阻害的であることなどなどの問題をはらみつつ形作られます。
煎じ詰めると,他者の関与のそれぞれの様態と主体との関係の健全性とが,結論的に,課されたもの(本質的に他者性です)を自我が望ましく引き受けることができているか否かに直結するといえます。このような他者とは,元々は母親を中心とした具体的な個々の誰かですが,しだい次第に抽象化されて集合的他者という体裁になります。それは超自我と呼ばれているものに相当するものです。
幼い時代に家庭環境に恵まれ,母親の安定した愛情の下に育まれた子の自我にあっては,集合的他者との関係も穏やかで,それはいわば心内における先人の知恵者との関係といった趣のものになるのではないかと思われます。しかし母(父)親が自分の二心に無自覚で,子への愛情以上に自分自身の役に立つようにという無意識的意識が優勢であれば,子に対して支配的,浸入的な育児となります。そういう関係で育まれた集合的他者は,自我に対して威嚇的,支配的なものになるだろうと思われます。
以上のような事情から,いかなる行為にも他者の眼差しが入っています。そして内発的な欲求は,内在する主体と関係があると思われます。この文脈で集合的他者が,自我に対して威圧的,支配的なものであれば,後者との関係が不確実なものである傍証といえるものでもあるので,自我は,相対的に他者の眼差しに依存的になります。つまり人の目が気になるのです。
(個々の自由は,自我の自律性が健全であるのを前提とします。しかしこの機能の危うさが他者の補完を不可欠とするので,取り分け人生の早期(自我がまだ未成熟な時代)には,他者(母親が中心になります)への怖れが抑圧機能を自律機能に優先させることになります。その度が過ぎると,他者の支配,侵入を受けるに等しいことになるので,自己の自由は危機に立たされます。つまり他者の眼が殊更に気になり,脅威になります。自己の自由が失われた極致に,諸々の妄想があります)
他者に行為の評価の基準点があるともいえるこのような心理的状況では,かぎりのない疑念に囚われざるを得ません。他者が何を考えているのか,結局のところ分からないのです。そういう状況では,生真面目な性格の人は,’完璧’であろうとする以外にないという心理状況に陥りかねません。
他者不信は,自己への不信と並行する関係にあります。
自己への信頼が揺らいでいないということは,主体との関係がうまくいっていることを意味します。そうであれば自己を支える機軸は自己自身の内部にあるので,他者に対する自由が確保されています。いたずらに人の心を気にすることはないのです。
(以上のように,行為には,一つには他者との,一つには内在する主体との関係が欠かせない契機です。そのいずれもがあやふやな心的状況では,いわゆる’勝手な行動’になります。それは眼差しの中にある重要な他者に(悪しき)依存していながら,それを認めるのを拒否するというひねくれた意識の下にある行動です)
Bさんは,できることを精一杯やりつつ,「これでよいですか?」と尋ねました。尋ねる相手は自分自身,つまりBさんの意識を超えた力を持つ主体です。そういう行為は,一人だけの信仰ともいえることです。
Bさんは,いまもおなじ生活状況にありますが,一定程度の自信を持っています。それが表情に表れています。そういうふうであれば,やがては親子関係の修復も可能でしょう。そのときは過去への回帰ではありません。かつてのBさんは,支配的な母親に従う一方でした。Bさんの主体者は母親だったといっても過言ではありません。いまやBさん自身が自己の主体者であるという,当然のことを自覚しつつあります。そうであれば,母親が従来のように支配者として振舞おうとするかぎり,親子のあいだには断絶があるばかりです。
必要とあらば関係の断絶も辞さないという強く,揺るぎない心の姿勢があれば,自己の自由を護ることができます。それは関係の正常化をはかる基盤を得たことを意味します。やがては,母と子が対等の関係で,それぞれの自由を尊重することで成り立つ,しみじみとしたものに変わる可能性も出てきたといえるのです。
自由は当然のことながらそれぞれのものでなければなりません。そういう理屈は誰もが知っていますが,実際には,個人のレベルであれ,国家のレベルであれ,強者には弱者を支配する自由があるという暗黙の了解があるかのようです。
親が子を支配し,子が親に支配され,そういう関係に依存している親子がなんと多いことでしょう。
膠で貼り付けたように,この依存関係は実に強力です。それを何とかしないかぎり,「病気がよくなる」可能性がないのですが,当然のことながら依存し合う双方共にさまざまに無自覚です。治療者がことを急いで,無理に膠をはがしにかかると,それはいわば自由の侵害になり,治療関係の拒否に合うことになります。母親の方は怒りをもって,子供の方は怖れをもって,共々に治療者の下を去っていくことになります。
何はともあれ自由は尊重しなければならないのです。依存し合う両者が,内側から,不自由な自由に疑問を持つ力を蓄えるしかありません。
このような局面では,治療者も困難な立場に立たされます。
何故なら,「病気がよくならない」からです。そしてよくならない理由を説明することが困難だからです。無理に分からせようと試みると,たったいま述べたように膠をはがす作業になり,痛みに耐えかねるあまりに不信と不興を買うことになりがちだからです。
そういう事情の下にあるとはいえ,問題を解決に向かわせるには,問題が正当に受け止められたとき以外にはありません。
膠で貼り付けたようなと,少々度が過ぎたいい方になりましたが,親子の強固な(悪しき)依存関係の悪しき意味を受け止めなければならない立場にあるのは,いうまでもなく第一には親の方です。
親の姿勢に好ましい変化があれば,子供は自分が自由になることが許されるという,当然で,重要な意味を知るきっかけを得ることになります。しかしそれは不安に満ちたことでもあり,半信半疑でだろうと思います。
何故ならそれは重要であり,そうでなければならないとはいえ,心の組織の破壊でもあるからです。
変革のためには破壊が必要ですが,自分で克ち得たものでないかぎり,破壊はあくまでもしばらくは破壊に留まります。
親に従うことで親に護られていた自己組織を,急に本人自身の自由に任されても,どうしてよいのかすぐには分かりません。むしろ突き放された,見捨てられた,親を怒らせたという恐怖に耐え難い思いをするだろうと想像されます。
しかしながら親の側のそのような意味のある理解の仕方は,子への愛情に違いないでしょうから,それは子の心を安心させる大いなる理由になります。
愛情と信頼とに勝る贈り物はありません。今度は子供の方で,その素晴らしい贈り物に自然な心でお返しをすることになるでしょう。本物の愛情と信頼に応えない子はないはずです。そのように親子の心の交流が進展すれば,心の自然を歪めてしまった人間の介入が,改めて人間の介入によって是正され,修復されることになるでしょう。
■自我の形成 その2
#1 集合的他者
いわゆる良い子の多くは,以上に述べた自己の自由の意味を感覚的に理解できません。
それは心の中軸であるはずの自我が,自立性を保つことができていないからといえます。
自我が自立性に問題がある場合,それに換わって首座にあるのは集合的他者とでもいうべきものになります。
この心の内部の他者が中心的な位置を占めると,人の目が気になって仕方がないことになります。
ここでいう集合的他者というのは,個々の他者ではないだけに,この勢力が大きくなると,あらゆる他者のおめがねに叶おうとすることにもなります。そうなるといわゆる完璧主義者になるしかありません。常に100点を取りつづけないと許さない親のような心の内在化といえます。いわば全か無かということになり,80点を取っても零点と変わらなくなります。自我が健全に機能しているのであれば,「80点は零点ではない」と主張することができるのですが。
それを心の法廷に見立てると,鬼検事ばかりがいて弁護士不在のようになっています。そうであればいつも有罪宣告されるに等しい心的状況になるのです。
鬼検事ですから,攻撃性が強く,怒りのエネルギーを強力に蓄えています。自我によって不当に抑圧された心の分身たちの,潜行する怒りが,命令的,懲罰的な集合的他者を作り出すのです。
以上のことを,具体的な例で説明してみます。
友達(B)の家で遊んでいた二歳の子(A)が,玩具を家に持ち帰りました。その玩具を欲しい,自分の物にしたいというのは自然の欲求です。それは幼い子の端的な自己表現であるといえます。
言葉を変えると,この素朴な自己表現は,自我の自律機能によって促されたものであると考えることができます。
幼い子がこのような表現をすることは,決定的にといってよいほど重要です。
つまり自己表現は人間にとって基本的に重要なことですが,幼い子は他人の干渉を受けずに,素朴にそれを表現し,それができている自分を喜ぶ(遊ぶ)という経験ができる年代にあるからです。
そして幼い子の自己表現が親をはじめとした大人たちの干渉を受けないということは,幼児が自分の力を感じ取るのを大人(主に母親)が是認すること,つまり共に喜ぶことを意味します。
未熟な自我は,ひとしきり素朴に自我の自律性の発露を味わい,楽しむことにより,自己表現の原体験をすることになります。それは母親を中心とした重要な大人たちの愛情によって保護されることにより,豊かで意味深い経験になります。
その経験は,後々,必要とすることを自分で取りに行く意志を持つことが正当化されることに通じ,与えられた人生,ないしは自己を自ら引き受ける意志を持つことに通じるのです。
その表現の仕方は,しかしながら,いずれ母親によって否定されます。「それはBちゃんの物です」と。
Aは不快感を味わいます。しばらくは元気がなかったり,不機嫌だったりするでしょう。母親に認めてもらえないことは,一種の危機なのです。
自分がすることが母親に認められたり,認められなかったりしながら,やがて母親に叱られないように気をつけるようになります。母親が側にいなくてもいいつけを守ることができるのは,母親を無意識的に心に取り込む(内在化)ことによってです。それによって自我は,自律機能の他に抑圧機能を働かせることになります。
ある程度成熟した自我がこのように母親の介入を受けることになり,それによって,素朴な自己表現から,より高次のものが求められることになります。
換言すると,素朴なレベルでは,’あらゆることが許される’のですが,新たな次元では,他者との関係をも配慮に入れることが要求されます。
母親との関係が確かな信頼と愛情とで結ばれていれば,「人の物は取ってはいけない」という禁止は容易に内在化されるでしょう。心に内在化されるのは,この例に従えば母親ということになりますが,一般的には誰とは特定できない抽象的他者になります。
このように内在化された集合的他者との関係で,自我が時によっては抑圧機能を働かせて,自律機能に優先させるのです。それによって,勝手気ままな行動は慎まれることになり,社会性を身につけることになります。そしてそれに伴って,自己表現の喜びには,他者に認められる喜びが含まれていることが明らかになります。
しかし一方では,このような集合的他者が内在化され,心の指導者になっていくと,幼児に許されるような内発的な自己表現が貧困化していく理由になります。つまり発達した社会性は,自己表現の本来の喜びを奪う側面があります。
例えば幼稚園児の’お絵描き’はそれぞれの内発性によるもので,この場合の集合的他者は,「自由に描いてごらん」という姿勢になると思います。また大人たち(外的な集合的他者)も余計な干渉をしないので,’それぞれの絵’があり,優劣は問題になりません。しかし中学生,高校生になると,教師が指導的干渉をします。この場合の(内的な)集合的他者は,一定のあるべきイメージを提示します。これら集合的他者なる指導者に従っているかぎり,優劣の差ができることになります。つまり自己表現の喜びは大幅に減じ,集合的他者が提示するイメージに従って絵を描き,それを教師が等級をつけて評価することになります。
このように,(内的な)集合的他者に従うかぎりは,(外的な)集合的他者によって優劣の等級がつけられることになります。
(真の芸術家は,世に受け入れられなくても,集合的他者にではなく,幼児のように自己の内発性による自己表現にこだわるので,孤独の中でも自己を追求しつづけるのです。そして’真の芸術家’には,(幼稚園児のように)作品に優劣はなく,それぞれのものがあることになります)
一般的には,それぞれの人生はそれぞれのものというほどに個性的,独創的ではありません。むしろ集合的,没個性的といえるでしょう。洗練された芸術家の自我は自律機能に従おうとする一方,一般市民のそれは,抑圧機能を発達させていると思われます。それによって,自己自身であろうとするよりは,人間集団の中で確固とした立場を得ようとします。この場合の野心は,人に抜きん出ることです。
他人より秀でたいという野心によって社会的な成功者になることができた人は,一方では,本来の個性的自己からは遠ざかることになるかもしれません。内在化された集合的他者の下に成功した人は,仲間同士の語らいで時を忘れることができます。うまくいくと一生をそのようにして送ることもできるかもしれません。しかし,例えば会社を辞めたあとに,虚無感に陥る危険がないとはいえません。
また先に上げた例の母親が,心配性で,子供が不始末を仕出かしていないか,絶えず監視の眼を光らせるようであれば,子供の心に内在化された集合的他者もまた監視的,命令的になり,幼い自我は過度に抑圧機能を働かせることにならざるを得ず,子供らしい自己表現(いたずら,泥んこ遊び,喧嘩などの遊び)が封じられることになっても不思議はありません。
このような心的状況では,心の表舞台から封じられた幼児的な自己表現の欲求が,社会性を剥奪された裏舞台のものとして潜航しつつ勢力を蓄え(必ず強い怒りを伴います)ることになるでしょう。場合によっては長じてから,それらが自我の眼を盗んで,万引き,過食,買い物依存等々の黒い満足に走る独立した動きを起こすことがあります。
幼児の心を失わず,素朴な自己表現の欲求を失っていない芸術家たちは,いま述べた心の裏舞台を作品として表現することがあります。成功者が心の表舞台を描いても,それは下らない自慢話になるだけで人の共感は得られません。芸術家が作品の上に描き出すのは,世間的な達成から疎外されている生活者の不安,不幸,あるいは悪とされるものです。世間的な成功者の驕りの陰で虐げられているもの,世間が眉をひそめる性的なこと,人生の惑い,悲しみ,怒りなどの中に,より強く人間のにおいがあることなどが,人の共感を呼びます。それらは世間的な成功から疎外された心の叫びともいえます。それはあたかも,意識上の世界だけが心のすべてではなく,無意識の世界の中にこそ生命の源があることを教えているかのようです。
心に裏面が存在しているのは,人間の真実です。それを何らか表現することは極めて重要なことでもあります。
ある中年女性は,人前では過緊張で字が書けなかったり,歯科治療のときに喉をごくんと鳴らすのではないかということを過度に怖れたり,「人は人を殺すことがある」という強迫的観念に脅かされたりします。
もし彼女が芸術家であれば,これらの衝動をもたらす心の裏舞台にあるものを抑圧しつづける代わりに,作品に取り上げることができるかもしれません。そうするとそれらのものは自我が承認したことになり,もはや意識の地下活動で自我を脅かすことはなくなるはずです。
彼女がこれらの衝動の突き上げにあって悩むのは,彼女が過度に社会性を身につけて,いうならば不条理な抑圧をしつづけてきたからに違いありません。
集合的他者というのは,体験された他者たちといったものではありません。
生まれて間もない赤ん坊は,いわば純粋主観の世界の住人です。それは自我がまだ機能を開始していないか,未成熟な機能でしかない時代の話です。その時代では,母親が自我の代行をしていると考えてよいでしょう。
そして客観的,外的世界は,自我の成熟と共に乳幼児の世界に取り込まれていきます。
このように自我に拠る人間は,主観的ー客観的である現象的世界の存在者であるといえます。
そのために,確かに経験したはずのことが夢のようにも思われたりします。確かである保証が純粋客観に求められるのであれば,人間にはそういうものは存在しないことになります。
人間に純粋客観はないが,純粋主観はある,それは嬰児の世界であるといえるように思われます。
ただし,このことを経験的,実証的に確かめる術はありません。いわば理論的推測ということになります。
この,存在すると思われる純粋主観の心理的世界が,人類に普遍的な無意識の世界であり,自我の能力を超えているという意味で無限界であるといえます。
心理的なエネルギーの源泉は,所在不明です。
身体にエネルギーがあるのは,実証的に明らかですが,身体と精神とは密接不可分の関係にあるのもまた明らかです。しかし,最初に身体があって,ついで精神の方にエネルギーが移行するといったふうに割り切って考えることは困難です。それは「精神の原因は身体にある」といった類の考えが,割り切り過ぎて,説得性を持たないのと同様です。
このような筋で人間の問題を考えると,「人間の原因は人間である」という奇妙な,悪ふざけになってしまいかねません。
それではこの問いに何と答えればよいのかは,自明といえるほどのことのように思われます。
つまり人間の存在は,不可知の理由によるとしかいい様がありません。
その上で,身体にエネルギーがあるのは明らかなのと,精神的エネルギーの捉えどころのなさと,一人の人間が持っているエネルギーの総量が一定範囲の中にあるらしいのと,それらを拠り所に,次のように仮定的に考えることが可能です。
自我は,無限界へとつながる無意識界(純粋主観の世界)と,身体をも含む外的客観的世界(意識化可能の世界)との接点にあり,主観的ー客観的である現象的世界を演出する主宰者の位置にある。
自我の存在根拠は不可知である。従ってそれは,先に述べたような意味で純粋主観の世界に根拠を持っていると考えるしかないが,身体的な根拠をも持っていると考えられる。それによって,主観的ー客観的な世界の演出が可能となる。それぞれの人間存在は,まだ自我の機能が開始されていない嬰児の段階で,定められた定量のエネルギーが与えられている。それが精神と身体の未分化な純粋主観の世界と,機能開始以前の自我機構とを養っている。
そして自我の機能が開始されると,主観性に客観的側面の根拠を与え,客観的,身体的なものに主観性(精神性)をもたらし,心に外形と内実とをもたらして統合する・・・。
自我が健全に機能すれば,外的客観とこの純粋主観との円滑な協働が果たされることになります。エネルギーは順調に循環することになります。
ここで問題にしている集合的他者というのは,いま述べたような意味で,主観的ー客観的な性格のものです。意識と無意識との中間にあるものでもあるので,それはイメージとして存在するといえます。
過食症者の多くは’よい子’です。自分でそう思っている場合もあり,むしろよい子ではないと思っている場合もあります。後者の方が自己がより多く抑圧され,「完璧ではない」という意味でよい子ではないと感じているのです。
一般的によい子の路線を取っている過食症者は,表面はにこやかにしながら,内面では人間不信や激しい孤独感,虚しさ,寂しさに打ちひしがれています。それらの激しく,ネガティブな感情と共にある彼らは,他人がどんなに優しくしてくれても,容易には情緒的な満足に浸ることができません。
彼らの自我は,母親のそれに密着していわば傀儡化しています。
権力者である母親の自我に過剰にすがるとき,自我は自律機能よりは抑圧機能を優先させる傾向が顕著になります。そうすると子供らしく甘える心は,抑圧されつつ成長していくことになります。それは自律機能に関係する子供らしい諸欲求(内在する主体から送り出されてくるもので,一定の方向性を持ったエネルギーを帯びています。それを自我が受け止め,護ることによって生気感情が育まれていきます)が不当に抑圧されることを意味します。無意識の領域から生まれてきた分身たちが,自我に受け入れを拒否される(母親への怖れ,気兼ねなどから)ことに伴って,寂しさ,悲しさ,虚しさ,怒り,恨みなどと共に,裏の人格を形成していくことになるのです。それは表の自我の無力を意味します。いつまで経っても(無力な)自我に受容される見込みが立たないままでいると,いつか裏の人格が支配的となり,死を志向する力と一体化していくことにもなりかねません。
このような傾向がつよい自己の心の内界は,中心にあるべき自我が無力である代わりのように,集合的他者とでもいうべきもの(外界にある母親に対応するものでもあるでしょう)が支配的な力を持つことになります。
これは他人の眼を過度に気にする基となるものです。
そして,それに相応して自我によって受け入れを拒否されたものたちが,影の分身たちの勢力となります。
自我領域には,いうならば自我の山と集合的他者の山と影の分身たちの山があると考えると,心の病理現象を理解する上で有益です。
それらの山の中で自我の山が主力であれば,自我は自立していることになり,自己形成へと向けた心の体制が整っているといえるでしょう。
過食症者は,しばしば死を希求します。
それはいま述べたような事情によるのですが,表の自我が自立していないために,有益な仕事をして自分で自分に満足をもたらすことができない傾向があるからです。集合的他者の支配を受けている自我が,自分自身よりも母親(あるいはそれに準じるもの)が満足するように仕事をしようとする傾向があるからです。
それに伴い,自我が自律機能をよりは抑圧機能を優先させるために,無意識の領域から生起してくる諸欲求を自我が受け入れ,護ることができないために,得られるはずの生命的なエネルギーを,怒りのエネルギーに変換させてしまうからです。それは生命的な心の表舞台に活力を与える代わりに,死への志向を持つ裏舞台にエネルギーを注ぎ込むことになるのです。
自律機能を十分に働かせ,自己を表現することの喜びを十分に経験するべき時期に,母親の意識的,無意識的な干渉によって抑圧機能が発達すると,大人びた子供になるかもしれません。それはもしかすると,周囲の大人たちに,「よくできたお子さん」と見られるかもしれません。いわば早すぎた社会性を身につけた子供は,周囲の大人たちの目にはよい子に映る一方で「自己の無力」に苦しむことになる可能性があります。
しかしながら乳幼児の場合,目的は,いずれにせよ母親によって自分の全存在が認められることです。
乳幼児に特徴的な重要な心性の一つは,揺るぎない全存在の保全をもとめて,母親を支配しつくそうとすることです。
完全に母親に依存している乳幼児の段階では,母親は神のごとき存在であるといっても過言ではないでしょう。事実,乳幼児は,母親が全能であるという幻想を持っていると思われます。母親と一体の関係にある赤ん坊は,全能なる母親を支配することで自分自身が全能の者となれるのです。
それを裏返せば,赤ん坊はこの全能幻想に疑いを持っていることになり,だからこそそれを要求するのです。あるはずのもの,持っているはずのもの,それらが与えられていないという不安,不満,苛立ち,怒りをもって母親に要求する(これらの疑惑,不満足は,長じて,自分は愛されていない,愛される価値がない等々の自己否定感の源泉になります)ことが,即ち支配欲求です。
しかしその原始的で,強力な欲求は,強力であるがためにカウンターパンチをもらう理由になります。いま述べたように,その要求が強力である分,強い怒りをはらみます。現実に満たされることが不可能な欲求と,満たされないことへの怒りが,母親のカウンターパンチを招く理由になります。母親自身にはそのつもりがなくても,ふとしたときに赤ん坊は自分の怒りを母親の顔に投射して,恐怖を持つことになります。
その恐怖は,赤ん坊が幻想的な全能感を必要とする現実と,それを要求することの非現実性とのあいだの懸隔が,赤ん坊が生まれる以前と以後との存在形態のあいだに横たわる超え難い深淵そのものであるといえ,そのような事情に由来しているように思われます。
しかしながら,いずれにしても,人間の現実世界では通用しないこのような支配欲求は,取り下げられなければなりません。何はともあれ人間として生を受けたからには,この世の現実を受け入れなければなりません。
見捨てられる恐怖には,あきらめて人間的現実を受け入れさせるための役割もあります。
「そんな分からず屋は,おかあさんの子ではありません」というわけで,全の要求をあきらめて,ほどほどの満足と安心とに甘んじる気にさせなければならないのです。そうしなければ,頼りとする母親との関係が保てなくもあるのです。
乳幼児にとっては,母親に見捨てられないようにするのは最優先の課題です。
この見捨てられる恐怖は,母親が赤ん坊に対して持つ怒りではむしろありません。そうではなく,赤ん坊が持っている怒りの逆照射に主因があるといってよいでしょう。しかし母親側の問題も無論小さくはないと考えなければなりません。というのは,支配欲求というのは小児心性の特徴として強いエネルギーを持っているので,母親自身が満たされない思いを潜在させていると,赤ん坊に苛立ちをぶつける十分な理由になるからです。それどころか,苛立ち易い母親,支配的な母親でさえ,珍しいどころではありません。
良い子として抑圧機能を優先的に働かせるのは,自我の戦略としては勧められたものではありませんが,母親に認められたいという目的はそれなりに達成されます。それに相応して,自律機能も護られることにはなるのです。
このように,よい子という自己犠牲の精神で生き残りを図ろうとする問題が生じる発端には,人格形成の最早期での避け難く,宿命的な見捨てられる恐怖があると考えられます。
いかに生きるかという以前に,ともかくも生きようとするのが自然ともいえるでしょう。
根源的に二律背反の原則に従わされている人間存在にとって,見捨てられる恐怖は生と死の分水嶺となるものです。
生を受けた赤ん坊は,残酷にも早々に死の存在を突きつけられ,やがては受け入れていかなければならないのです。
死を,自我が引き受け難いものであるかぎり,生もまた耐え難いものになります。
20代前半のある女性(Cさん)は,姉が’おばあちゃん子’であったのに対して,「この子は私の子」と母親にいわれながら成長しました。大学を卒業後,勤めた会社で否定的に扱われたこともあって,職に就いていません。母親の観点からすると,「昔はよい子だった」ということになります。そのついででいえば,「今はわるい子」ということになりま
あるときCさんが冷蔵庫の中を見ていると,母親が,「やめなさい」といいました。
Cさんによれば,いまも太っている(さほどではありません)のだし,仕事もせずに家でごろごろしているのだから,間食をするともっと太るというのが理由だと思うということでした。Cさんも,その母親の考えに同感しています。
その直後,母親が出かけたときに,菓子パンを2個食べました。食べてから,大変なことになったと思いました。あわててゴミを捨てに外へ出たときに,帰ってきた母親に出会いました。「殺される!」と思い,走って逃げました。電車に乗って遠くまで逃げたそうです。
いくらなんでも実際に殺される心配は皆無です。
支配的なCさんの母親を怒らせると,Cさんは見捨てられると感じたのです。Cさんにとっては,母親が支配的であるということは,圧殺者ではなく護られている者という感覚です。恩義を与える者と受けている者との関係です。そういう意識の下で,圧殺される,侵入される,自由を認めてもらえないといった心と,それに伴っているに違いない怒りとを無意識下に封じているのです。
そのことは集合的他者の山が,自我の山よりも高いことを,従って母親との関係で,自律機能より抑圧機能を優先させていることを物語っています。
間食など許される身分か,というのが母親の気持ちであり,Cさんも同調しているのですが,この同調する考えが集合的他者によるものです。そして母親がいない隙に盗み食いをしたのは,影の分身たちの仕業です。
自我はといえば,いずれにしても主体性を示せないでいます。
集合的他者の山が自我の山よりも大きくなるのは,怒りによってです。
その怒りは影の分身たちの山のものでもあります。
つまり自我が母親の自我に傀儡化するようにして自律機能を抑え,抑圧機能を働かせることに伴って,自我に受け入れを拒否された諸欲求が,生命感情を育成するはずだったエネルギーを,怒りのエネルギーに転換させたといえるのです。その怒りのエネルギーは影の分身たちを養い,集合的他者をも大きくします。
見捨てられると生きていく術を失うのは,幼い子の問題です。Cさんの心の中でそうした幼児心性がつよい勢力を張っていたことを,このエピソードは如実に物語っています。
殺されると恐れたのは,部分的には,もしかすると圧殺されているCさんの怒りが自我を脅かしたからかもしれません。その怒りはCさん自身の心を破壊しかねない(自我に向けられた怒りに自我が耐え難く感じている)ものであろうと推測されます。また,その怖れは母親に向けられた無意識的怒りへのものであったかもしれません。
集合的他者はすべての人の心にあるものです。
幼いときからピアノの天分が認められた子に,その父親が極端なスパルタ教育をして,ついには人格破壊をもたらし,しかしピアノ演奏の才は大いに開花したという映画があります。
この場合は,内在化された集合的他者は命令的,懲罰的で,自我を打ち壊すほどの勢力を持っていますが,自我の自律機能は,ピアノによる自己表現に関するかぎり,それに抗する力を失わなかったと考えられます。
むしろ圧力を加えてくる集合的他者に押し潰される代わりに,それを凌駕するようにピアノに立ち向かう力を自我は持っていました。
一般には,集合的他者は,より穏やかなものです。それは自我と対立,拮抗するよりは,穏やかな教師のように忠告します。その忠告は,おおむね,世間的に認められた人生の途についてのものでしょう。創造的,個性的な途については,自我の自律性の役目になり,集合的他者はその意味では抑制的に自我に働きかけることになると思われます。
Cさんの集合的他者は,支配的,命令的,懲罰的なもので,自我はひたすら抑圧機能を働かせるしかなかったようです。
つまり集合的他者(その中核には母親,そして父親がいます)に圧倒され,従属させられている自我の下では,’自己否定の人’の人生を歩むことになるのが避けられません。こうした場合は,いわば人生レースの敗者になります。
画家を目指す者であれば,集合的他者の介入に抗する内発力を発揮できないかぎり,二流以下の凡庸な画家に甘んじるしかないでしょう。あるいはその道の敗者になれば,絵をあきらめればよいだけのことです。しかし人生そのものとなればそうもいきません。しかし絵と違って,それぞれの性格,それぞれの人生は,本来は出来の良し悪しではありません。自分らしいかどうかです。
問題は心の指導者の立場を,集合的他者が握っていることにあります。そのために自我の自律性が抑圧を受け,機能不全化するのが習いになっていると,人生レースの敗者となり,自己を見失い,虚無と絶望の淵に立たされることにもなります。
そういう心的状況では,改めて,「自由にやっていいのだよ」という’幼稚園児のお絵描き’の精神に立ち返ってみるのも一方でしょう。
「かくあらねばならない」という絵の(集合的他者としての)教師は極力排除して,「自由に描いてごらん」という教師に置き換える努力をするのです。途方に暮れ,打ち倒されるようにして無為に過ごすのではなく,「いまできる自由な絵は思い浮かばない,強いていえば寝ている絵しか描けない」というのであれば,「それでよい」とする精神です。
何をしてよいか分からず,途方に暮れて寝ているとしても,強いられた絵が描けなくて寝ているのと,自分の意志で描く絵がいまは寝ていることでしかないのとの違いは,大きいはずです。
前者であれば一日中でも寝て過ごすかもしれませんが,自分の意志でとなると一日中寝ているのは苦痛になるでしょう。苦痛は不足感でもあるので,たとえば「掃除をするという絵」を描こうという気が起こるかもしれません。
そのように,「かくあらねばならない」という精神から,「何が出来るか」という精神に移行していくこと,強いられた精神から自ら意志する精神へと換えていくことができれば,徐々に自分らしい生活が見えてくるかもしれません。
何もする気になれなくて一日中寝て過ごしたとしても,それがいま自由に描ける精一杯の絵であれば,良しとしてよいのです。それは,旧来の厳しいばかりの集合的他者の指導の下にあれば,「そんなものは作品であるものか」ということになるでしょう。そういう状況では,おなじ寝ているだけの生活にしても,「絵を描けない」という絶望と内向する怒りと共にあることになります。しかしそういう集合的他者の指導に従ってきたので,現在の無気力な姿があるのですから,いまは差し当たりそれでよいのです。寝ていることも,自由に描いてよいという指導者の下であれば,「いま描ける精一杯の絵」といえるのです。
要は,一日を精一杯生きるということになるでしょうか。
強力に支配的な母親に従属していたある女性は,近く家を出て一人暮らしをすると決意を固めています。彼女には,母とのあいだの依存関係を清算するのは容易ならぬことでした。そのように心の状況が変化していくにつれて,無力に見えていた表情が引き締まってきました。この女性が描いた「家を出る」という絵は,立派な作品です。
#2 二人の母親
自我の抑圧機能が過剰に働くのは,母親を核とした他者への過度の気遣いとパラレルな関係にあり,それは集合的他者と影の分身たちとの勢力を増大させ,自我の無力化を招くことになると述べました。そしてそれは死へと斜傾する方向性を持っています。
一方,生気感情を豊かにさせるのは,自我の自律機能によってです。
これまでに繰り返し述べてきたことですが,自我の誕生は光の世界の誕生です。そして自我の誕生は死の誕生でもあります。
自我の誕生以前の世界は,自我に拠るわれわれ人間にはうかがい知ることができません。
自我による世界は,誕生によってはじまり,死によって終焉する有限のものです。自我による意識という光が届く範囲は限られたもので,これを有の世界とすると,自我の誕生以前の世界は意識が届く範疇の外になるので,それは無(または無限,または全)の世界ということになります。
そして先に述べましたが,自我の機能開始の黎明期にある嬰児の世界には客観的な外形はいまだなく,主観と客観とが渾然と一体化している,いわば純粋主観の世界であるように思われます。それはユングのいう普遍的無意識の世界ともいえるかもしれません。外形によって限定化されていないその純粋主観の世界には,無限性の性格があるように思われます。
自己と人生とが,誕生と死によって外側から明瞭に限界化されていながら,それでもなおかつ自己と人生とが目標とするある到達点を持ち,そこに到ってそれらが終結するといったことはなく,その意味では無限性を生きているのが実態といえます。それは嬰児の世界である純粋主観が無限性の性格を持ち,それが他でもなく我われ人間の一大特性であることに関係があるのではなかろうかと思われます。
また,明瞭に有限のものである身体性と,無限性に通じる精神性との総合である人間存在は,永遠の二律背反(生と死の互いに相容れず,しかし相互に絶対依存の関係にあるのがその最たるものです)を生きているのを特徴としています。その永遠の矛盾の対立が新たな統合をもたらし,人間の精神の無限性が保証されていると考えることができます。
つまり,この論旨に従えば,自我の誕生以前の世界は全または無であり,誕生後の世界は,その主宰者である自我によって二分割され,不完全なものの複合体になるといえます。
自我に拠る世界は現象的世界です。つまり主観と客観とが総合された世界で,両者は独立して存在することがなく,相互に絶対的依存の関係にあります。
現象的世界にあって,諸現象を二つに分割して捉える(自己と他者,男と女,善と悪,愛と憎しみ等々は,相互に他を不可欠のものとしています)のが自我の特徴です。その根源には,相互に他の存在を不可欠なものとしつつ,しかし相反するものの関係にある生と死と,あるいは光と闇との分割された対立があると考えられます。
自我による生の世界は,死という終焉にいたる有限のものです。
しかし生と死の対立の永遠性が,生の無限性を生み出すのです。つまり希望は無限定なものでなければ希望の意味をなしませんが,生と死との終わりのない矛盾,対立があるかぎりは,その都度それらが止揚されることが可能であり,それは次々と新たな希望が生み出されることを意味します。そして死という終焉にいたって,人は人間存在としての役目をはたし,自分の全存在を,それをそもそも生み出した不可知の上位者に返還することになると考えることが可能です。
そのように考えると,限られた能力をしか持っていない我々ではあっても,日常の意識の中に無限性をも持ち込みつつ生きているといえます。
ところで,それぞれの私の母親はだれでしょうか?
それぞれの私を生み落としたのは,それぞれの母親,というよりは,父親との合作によってであるとひとまずはいえます。
しかしそれが全てでしょうか?
その答えは,たったいま述べたことの中に含まれていると思います。
常識的な意味での母親を地上の母と呼ぶとすると,もう一人の母親は上位者なる母ということになります。
人間が人間であるゆえんは自我にあるといえますが,自我を授けたのは父親でも母親でもないのは明らかです。その自我を授与する力を持ったものが上位者なる母です。人間は,人間に似せたロボットを作り出すことができますが,あるいは人間を生むことはできますが,人間そのものを作ることはできません。
自我を授ける力を持っているのは,人間以上のものであるのは明らかであっても,誰と名指しするのは不可能です。名指しはできないが,自我によって人間は存在可能であるという事実問題があるかぎり,上位者の存在もまた明白といわなければなりません。
自我至上主義者は,例えば次のようにいうかもしれません。
人間は生命連鎖の極致にある,動物が進化した究極の存在である・・・と。
それもまた一つの仮説です。
しかし動物の存在形態のあいだに進化論的移行系が見出されているにしても,それが単純に物質的ないしは生命科学的な発展であると証明するのは不可能です。簡単にいえば人間の知恵をいくらこらしても極めることができない難題であることに変わりはありません。
この論法によっても,つまりは我われには知り得ない理由によって動物間の進化があることになり,その知り得ない理由を知っているのは人間以上のものであるということになります。
結局,どのような仮説を立てようが,,自我を最上位に置くことが不可能なのは自明です。
そもそも知性は自我の僕であり,自我は有限の世界での自己の中核です。そして自己ないしは人間存在には,無限的世界も含まれています。自我はこの無限領域に関わる能力を持っていないのですから,知性が人間存在の全般を網羅的に究明し,理解するのはどだい無理な話です。
そのように考えると,以下のような仮説が可能です。
人間の誕生は,第一に自我の授与によってである。それを授ける力を持つものは,自我に拠ってはじめて存在可能となる人間自体ではありえない。それは人間には不可知の上位者であると考える以外にない。
不可知の上位者とは,意識による人間にとっては’全なるもの’と言い換えることができる。
そして全なるもの(天)を母とする赤ん坊は,天からの授かり者ということができる。
自我を授与された赤ん坊は,意識せずにそれを引き受けたものとなる。つまり不可知の上位者(主体と呼んでおきます)の命を引き受ける者として地上の者となったと考えることが可能である。
主体の命とは,「自我によって自由に自己を導け」というふうに考えることができる。
そして地上の者となった人間の無意識世界に,主体は鎮座して沈黙のうちに自我がいかに自己を導くかを見守る。自我が自己を導く道筋を,主体は沈黙の内に指し示している。
人間の誕生は,第二に(地上の)母親によっている。母親は意識せずに主体の命を受け,仮託されたと考えることが可能である。
いうならば父親と母親とはそれぞれに二分割された二分の一以下の存在で,その母親が新たに一人の人間の親であることができるためには,他の二分の一の存在である父親と合体して’完全’にならなければならない。そうなることで子供が二分の一の存在として生み落とされる。
有限の世界を生きるそれぞれの自己は,二分の一以下の存在として心の内に他者を構造化し,外なる他者との関係を不可欠なものとしている。そのようにして全に準じる存在形態となり,人間の現象世界を包囲している全(自我に拠る人間には無と区別がつかない)の無化作用に対抗している。
第二の母親が第一の母親と決定的に違うのは,前者には二心があり,後者にはそれがないことである。
第一の母は,無意識世界の主体となって,個々の人生,個々の自己の途を無言のうちに指し示している。
第二の母は,人間的な大道を志向する。つまり,この世的な達成を志向する。それは勢い,他に負けないことが要点になる。
二心というのは,例えば,子供の成長を親が喜ぶのは子供への愛情である,と同時に,親自身の安心,満足でもあるということです。
二心それ自体は良くも悪くもなく,人間に固有のものです。
善心と悪心もまた人間に固有のものであり,二心です。その存在自体にはよいも悪いもありません。しかし悪がどういうものかを知らない者はないので,この場合の二心はある意味ではあまり問題ではありません。
人間に善心があるかぎり悪心は必ずある,しかし社会性と精神性とが欠落している悪心は,裏の自我による世界のものであり,公然と心の表舞台に乗せることは許されない・・・ということになります。
育児上の二心は,子のためを思ってしているつもりの躾が,実は親自身の不安や不満の解消を子に求めていること,それが意識されることがないこと,という形で問題になります。
以上の仮説に基づくと,躾は,主体が指し示す自己の途を探り当てる自我の仕事を,親が助ける形が望ましいことになります。
しかし躾や教育は,人生の大道の歩き方といったものにならざるを得ません。
個々人の真に個性的な達成などというものは,もし分かる者があるとすれば本人以外にはあり得ません。しかも幼いうちからそういう道筋をたどろうとするのは,ごく稀な芸術的天才だけでしょう。一般的には社会性を身につけさせる努力以外には,躾であれ教育であれできない相談です。
「世間体を気にする親」といったこともいわれたりします。世間体を気にしない人間もまたいないはずですが,このようにいわれるときには,子供の方で親の二心に敏感になっているということなのでしょう。
Sさんが,父親が乱暴にドアを叩き続けている,といった内容の夢を見ました。
実際に父親は怒りっぽく,母親も負けていないので両親の口喧嘩が絶えません。非は父親の方にあるとSさんは思い,両親のあいだに立って家庭の空気を和らげる役目を負いつつ成長しました。しかしSさんが仕事をすぐに辞めてしまうので,それが両親の頭痛の種になってしまいました。
常々,Sさんは母親の意向に従っていましたが,この夢を見て,乱暴にドアを叩き続ける父親も可哀想だと思いました。夫を閉め出している母親の方が問題ではないかと思ったのです。
Sさんと両親の三者との何度目かの面談の席で,Sさんをはさんで両親が声高にいい合いをはじめました。母親が夫の態度を責め続ける状況で,私がこの夢の話を持ち出しました。「Sさんも,母親に対してこのような批判的な気持ちを暗に持っているようだ」といったことを伝えました。
これはかなり乱暴な介入だったと思います。事前にSさんの同意を取りつけないままにしてはならないことでした。しかしSさんと母親との強固な依存関係が変わらないかぎり,通院を必要としているSさんの問題は改善される見込みがないのも確かです。どの段階でかこうした介入は必要ですが,その場の成り行きで,いわば賭けのような介入をしてしまったのは危険なことでした。
果たせるかなSさんの足がしばらく遠のきました。そしてしばらくぶりで受診したSさんは,言葉が少なく,不満の様子が見て取れました。
しかしその後気を取り直した様子が見え,私は改めてSさんの基本問題の説明をした上で,「あなたの意志を伝えることができるようになるのが課題です。おかあさんに,今後はそのようにするつもりがあるといってみてはどうですか?治療上の必要があるのでそうするようにいわれたと,話されてもよいかと思いますが」と提案しました。
Sさんはうなずいていました。
その数日後に母親がやって来ました。
母親は,Sさんが「逆らいなさいといわれた」といっているが,どう対応したらよいものか相談に来たといいます。そして最近辞めた会社の元上司と個人的な交際をしていて,彼は父親ほどの歳だが何もいわない方がよいのかといいます。
「逆らいなさい」というのはSさんの取り違いと思います(「意志は伝えるように」というアドバイスをしてあります)が,年上の男性との交際は初耳でした。
母親の困惑は当然です。
恐らくは感情を抑圧しつつ成長してきたSさんは,情緒的なものに飢えていたのだろうと想像されます。
しかしこの交際が正しいかどうかには疑問があり,母親が心配するのはもっともなことです。しかしながら,良くも悪くもこれもまた母親の二心であることに違いないのもたしかです。
仮に母親の強い介入があり,二人が分かれることになったとして,やがてはSさんも自分の迷妄に気がつき母親に感謝をすることになったとして,母親は自分の二心をよく承知している必要があります。
本当のところはSさん自身の問題であるのはいうまでもないからです。Sさんが当事者能力を欠いているほどに幼いとすれば,その責任の過半は親が負うべきものだからです。この時点で未熟な心のSさんに代わって,母親が善処策に走るのも愛情の形でしょうが,両者の依存関係はSさんの未熟な心と共に手つかずになってしまうでしょう。
二心を母親が十分に理解すれば,容易には手出しができないはずです。
このように母親(に限りませんが)が子供を思ってすることが,子供の身を護るためだけではなく,親の安心のためでもあるのは当然なのです。そもそも親の安心がなく,子の満足だけがあるなどということはあまりないことでしょう。親と子は強い関係としてあるので,一方の幸福は他方の幸福です,一方の不幸は他方の不幸です。子供を虐げる親は,何らか不幸であるからに決まっています。親の安心が薄ければ,子を安心の道具としがちなのです。
先に上げたBさんの例のつづきです。
Bさんは,「自分の狭い部屋に一人いて,何か牢獄にでもいるような感じがしていました。自由って何だろうと考えましたが,どうしても分かりません」といいます。
Bさんは支配的な母親からも,その手先のような妹からも,怒りをぶちまけるようにして支配してかかる一人娘からも,いまは距離を取っています。Bさんが本気で怒っているのを知っているためと思われますが,母親からも娘からも連絡はありません。
Bさんはいまは怒りの存在と,それが蓄積されてきた長い心の形成の歴史と,母親のまったくの支配の下にあったこととをよく理解しています。だからこそ母親から距離を取ることができています。気に入らないと怒り,罵ることでBさんを従えて来た母親にとって,Bさんは手であり足であり,道具であるに過ぎなかったといえるようです。だから何も連絡を取ってこないというのは,怒りの表現とはいえません。むしろBさんの真剣な怒りに怖れをなしているのだろうと想像されます。
Bさんは幼い時代に,母親への強い恐怖を体験しているだろうと推測されます。
その恐怖心が,母親の二心に対する怒りを徹底して抑圧しただろうと思われます。そのために母親のいかなる態度も,子である自分への愛情に基づくものという意識態度が強固に形成されたのだろうと想像されます。
それは自我が怒りを抑圧することに伴って必然化された,意識の欺瞞化でもあります。
そのような意識構造の下では,母親はいわば全なるものです。
母親への絶対服従の呪縛から解かれるきっかけとなったのは,他でもなく母親自身の更に激しい怒りでした。
Bさんは母親が何といって罵ろうが,自分の使命は母親の側にいて下女のように仕えることでした。
しかし夫のことや娘のことも重なって,Bさんが打ちひしがれているときに母親が放った痛罵に,さすがに怒りを覚えました。そして,「ここ(実家の敷地の一角にある古家)を出て行け」といわれたときに,Bさんは転居の決心を固めました。
母親への怒りの存在を認めたBさんは,ようやく母親の二心に注意を向けることができたのです。いわば全なるものが,自分と等身大の哀れな存在に過ぎなくなりはじめたのです。
自由とは,自我に拠る自由と考えてよいと思います。換言すると自我の自律性に従うということになります。これはいわば自我を付与したもの,人間の上位にあるものの意志に基づくものと考えることができ,内在する主体との関係において展開される性格のものといえます。
一方,現実の母親は,全面依存する赤ん坊には事実上の神といえるほどの存在で,生殺与奪の権利が委ねられているといえます。
先にも述べたように,見捨てられる恐怖から,母親の自我に同一化することによって自我の自律性を犠牲にしたところにあると考えられます。自我が自律性を失い,抑圧性を手放せないままでの人格形成の歴史ということになり,自我は衰退し機能不全化していくのです。それは相対的に裏の自我が力を強めることを意味し,やがては衰退した自我を支配することになります。母親の自我の傀儡であった自我は,裏の自我の傀儡になるしかなくなる必然性をも持っているといえます。
裏の自我は社会性と精神性とを欠いています。その自我が求める満足とは身体的,刹那的であるのを特徴とします。
食物に代理満足を求めます。それは決して満たされることがない欲求であり,常軌を逸した激しさで,餓鬼そのものの姿になるのです。
自己を善導する役割を持つ表の自我に対して,死への志向性を持っている裏の自我は,目先の利欲にかまけたり,狡猾であったりということはあっても,自己の将来などはおよそ念頭にありません。
よい子であった彼らが,強く依存している母親に怒りを向けることがあります。’よい子’によっては決して怒りを人に向けないことも少なくありません。怒りの感情の存在さえないかのような人もあります。しかし怒りの感情がないなどということは考えられないことなので,抑圧の強さの問題と考えるべきです。怒りを向けないという意志的なことではなく,怒りを表出できないのが実情だと思います。いずれにしても,’よい子’は(恐怖心から)感情の抑圧をするのが習い性になっているということなので,怒りのエネルギーはむしろ意識の下層に蓄積されていると考えるべきです。
’よい子’が母親に向ける怒りは,悪しき依存の枠の中にいる衰退した自我が,怒りを強めている裏の自我の支配を受けてのことです。そうすることにより母親を支配してしまうこともあり,これも裏の自我の営為といえるでしょう。怒りを表現することは大切なことですが,彼らのこうした行動は,表の自我の無力を反映したものなので,たんなる怒りの奔出という現象にとどまり,心の成長にはつながりません。
それが表の自我の仕事であるなら,大いに意味を持つことになるでしょう。それは抑圧してきた意識下の分身たちの感情に自我が眼を向けたことを意味します。いわばそれらの分身たちを意識下から救出するという意味があるのです。
しかし裏の自我の営為であれば,単なるうっぷん晴らしの域を出ず,表の自我の無力が浮き彫りになるばかりです。感情が鎮まれば,更に落ち込むことにもなるのです。
不登校の子を持つある母親は,母親自身の子供時代の親子関係の反映もあって,子供に支配的,浸入的な育児をしてきました。それを反省した母親は,不登校に陥った子の理解者であるよう努めるようになりましたが,父親や学校の先生たちは,不登校の子をかばう母親が理解できません。あくまでも’よい子’を求めるのです。かつて母親自身がそうであったように,学校に行ったか,家でだらだら過ごしていないか,親のいうことを素直に聞くか,などなどといったことにばかり注目して,それを守らせるのが本人のためであると信じているのです。それができないのは悪い子なのです。
かつてはこの子も,これらの大人たちの基準によるよい子でした。そのよい子の自我は,親の基準に従う傀儡自我にほかならず,’悪い子’を抑圧してきたのです。その基準の下での’悪い子’は,実はそれほど悪くはなかったはずです。先にも上げたように,単に甘える心を持つことが,抑圧という形で悪い子にさせられてしまうということが起こります。子供らしいいたずら,わがまま,反抗は,いわば子供の自然といえる程度のものが大半でしょう。それを抑圧する’よい子’の傀儡自我は,本来はあってはならない抑圧をすることで,無駄なエネルギーを使いつづけることになります。
しかも自我の自律性が犠牲にされているので,主体との接触がうまくいかず,いわばエネルギーの元を自ら絶ってしまっていることになります。必要なエネルギーの供給を思うように受けられないでいると,表の自我は無気力のままでいるしかなく,悪循環になります。それはすべて傀儡自我が招いた災いです。社会的な存在であることに無気力になってしまった表の自我は,いまや裏の自我の傀儡になってしまったといえるでしょう。主導権はこちらに移った結果としての不登校なので,’悪い子’といえばいえるのです。しかし,その子に’よい子’を求めてどうなるというのでしょう。仮に学校へ行くということが目標であるとすれば,表の自我が,’悪い子’のいい分に耳を傾ける力をつける必要があります。そのためには,周りの大人たちが,この子の自我の仕事に協力していかなければなりません。つまり自我が親の自我の傀儡にならざるを得なかった事情を汲み取って上げる必要があります。そのためには,学校へ行けない事情を理解しないわけにはいかないでしょう。傀儡化してしまっている自我には,自らを省み,問いただす力はないのです。
そもそも’悪い子’が実は悪かったわけではなく,大人の態度にこそ子供の自我を無力化してしまった理由があるのだということを,大人たちが改めて理解しなければなりません。それが行き渡れば,いずれ子供の自我の自律性は息を吹き返すのではないでしょうか。
このようによい子というのは,見方を変えれば,情緒的な満足を断念した子ということになります。それはずいぶん理不尽な話です。幼い子らしく駄々をこねたり,甘えたりしたいと思う心が,母親への恐れを持つ自我によって,片端から意識下の牢屋に閉じ込められるという残酷なドラマが,幼い子の心の舞台で密かに起こっていたに違いありません。
これらのよい子たちの,母親や他人の前でするにこやかで礼儀正しい笑顔の演出は,傀儡自我によるものです。そしてその一方で表面化してくるのは,意識の暗部に閉じ込められてきた分身たちの侮れない勢力です。それらは裏の自我の下に,満たされなかった情緒的な満足を求めて,役に立たない表の自我に公然と反旗を翻すことになっていくのです。
自己を導き,社会的な顔を育成する使命を帯びている自我としては,裏の自我の支配を受けるのは,恥ずかしく,屈辱的な事態です。それは,そのまま自己の喪失,人生の形成の失敗という意味があるからでもあると思います。
過食症の治療の困難は,依存症一般がそうであるように,依存の対象を容易には手放したくないという強固な心理が働いているからです。そのような強い依存欲求の存在は,それだけで小児心性を表していることを証明しているだろうと思います。依存の方向を間違えているとはいえ,激しい力を秘めている裏の自我にいわば捕捉されている表の自我は,本来の依存対象に自らを引き戻す力は既にあきらめかけているようにも見受けられます。治療的に必要なのは,依存の対象を手放しても安心できるほどの治療関係ということになるでしょうが,依存症者の心を現に捉えているのは,悪魔的に魅了する力と破壊力とを併せ持った何ものかであるようです。
人前でのにこやかな笑顔を持つ人格と,一人で過ごすときのなりふり構わない人格と,表と裏に極端に分裂した姿は,表の自我の力の弱さの反映です。餓鬼と化したかのような圧倒的なエネルギーを,裏の心は秘めています。
自我は受け止める力を持つときに,機能の回復が開始されます。餓鬼と化したといえるほどの激しい力を持つ裏の心を受け止めるのは,容易なことではないでしょう。衰弱している自我は,母親との依存関係に殊更の愛着を持っています。それは愛着というよりは,恐怖を媒介とする同盟関係という方が当たっているかもしれません。愛は人と人とのあいだで緩やかな関係を保ち,恐怖は強固な関係を必要とするでしょう。
恐怖心が一役買っている母親とのあいだの強い依存関係に楔を打ち込むためには,どうしても治療的介入が必要だと思います。それができるためには,患者さんの側の’求める心’がそれなりに強くなければなりません。それがなければ,母親との関係にしがみつく患者さんは,治療関係を築く間もなくあきらめてしまうでしょう。治療者との関係がしっかりしていけば,恐怖が愛に置き換わる可能性が出てくると思います。治療関係とは,愛と信頼の一つの形です。それがある程度進行したときに,これは自分の問題だ,このままでは自分に申し訳が立たない,という自己への責任感と贖罪の気持が芽生えるかもしれません。
問題を受け止めることができれば,最初の第一歩が踏み出されたのに等しいといえます。そうすれば,過食行動をさしあたっては承認する気力が湧いてくるかもしれません。たとえ当面は太る恐怖があるとしても,治療関係を通じて愛と信頼との力が回復することができれば,’太っている自分’を許せるのではないでしょうか。自己愛が回復すればそれは可能です。そして他人を信じてよい気力も回復するはずです。他者愛が回復すれば,他人の眼もさほどには気にならなくなるはずです。そういう心が育っていけば,何よりも,心の成長という得がたいものを手にすることができるのです。
自我のもう一つの重要な機能は,境界です。とりわけ意識と無意識とのあいだと,自己と他者とのあいだを分ける境界が重要です。
自我は人間を特徴づける最たるものです。その自我の機構の中核的な位置にあるのが自律性であると考えられ,その機能が健全に保たれることが人間的な自由を謳歌する条件です。自我の機構には,境界機能も含まれていると想定されます。自律性が健全な状態にあれば,境界も健全に機能すると思われます。
境界が意識にとって外界にあるもの,とりわけ他者とのあいだで,そして意識にとっての内界である無意識とのあいだで,有効に機能しているかぎり,自我の自律性が保たれると想定され,これらは互いに相補的な関係にあると考えられます。
男子大学生の例です。
予備校生だったある時期に,幻聴と被害妄想がはじまりました。予備校に入って間もなく,見かけた女性に好意を持ち,接近を試みたことがあり,それが関連してのことです。受診したのは大学に入ってからですが,その大学に,かつて噂を流した’張本人’がいると信じています。’彼とその取り巻き’に恐怖を持ち,大学を辞めようかと思いつめました。薬が奏効したこともあり,危機を乗り越えることができました。しかし,ふとしたときに,妄想的な疑惑が頭をもたげます。その’噂’が核になって,他の人の耳に入ったのではないかというふうに拡充します。また,将来の進路について迷いに迷い,決められないこと,母親になんでも相談し,判断をしてもらうことなどが顕著なときもありましたが,そういうこともしだいに自分で解決できるようになっています。
本人の受診以前に,父親が会社の問題でうつ状態となり通院しておりました。その父親は会社の要職にある人でしたが,妻を大変頼りにしておりました。夫の診療が終結した後に,その妻が,「実は・・・」と長男の相談に訪れたのですが,彼女は自分の対応がまずいのではないかと気にしておりました。夫につきそって来ていたころは,頼もしい妻という印象でしたが,実は大変に不安と混乱に陥りやすい性格のようでした。
本人(大学生)の母親観は,「怒ると怖い。もともと神経質でヒステリックになる。顔色をうかがう癖がついてしまった。・・・こうしなさいと何でもパッパと決めてしまう。それに従ってきた・・・」ということです。唯一の同胞である姉は,対照的に,自分で考えて行動する性格ということです。
母親が長女よりも長男の方を,依存のターゲットにしてしまったという印象を受けます。心根が動揺し易く,不安に駆られ易い母親が,長男によって安定を図ろうとしたようです。自分を助けることができる大人になるように,むきになって仕向ける母親のイメージが浮かびます。それがどうやら仇になったという印象を受けます。どうすれば母親が望むような息子でいられるか,’怖い母親’に,いちいち確認しなければならないほど,自立性を欠いてしまったのでしょうか。
幻聴や妄想が活発な時期がありましたが,経過から見て,統合失調症ではありません。この病的な問題は,境界機能が混乱し易いことを示していると思います。境界機能には,内外の問題を受け止める役割があると考えられます。無意識の勢力を受け止め,意識の領域との境界を画然とすることで,心の秩序が保たれます。自我が心の秩序を保つために,自我のときどきの価値規範に合わないものを抑圧するのは,境界機能を利用していると考えられると思います。
幻聴,妄想に関連して,誰かが自分の悪口をいっているように感じられるとき,外界の他者と自己との境界を画然とさせる機能も混乱しています。(ある女性が,最近,母親が身勝手なことを言い出して父親を困らせるというエピソードを語っていました。一時的にそのことで憂鬱になりましたが,「私は,私だ,お母さんとは独立しているんだ」と思い返して心の安定を回復させることができました。もともとは,こういう状況では混乱して自分を失うことが受診の動機だったのを考えれば,自我の境界機能が有効に働くようになったといえるのです。それは成長の証です)
境界機能が混乱するときは,必ず自律機能も混乱します。この大学生の場合は,関係念慮に苦しんでいたときは,将来の進路を決められず,一途に混乱していました。彼の自我がこのように混乱し易いのは,たぶんに母親の影響があります。母親の自我の混乱の影響を受けつつ成長したためであろうと思われます。
なお,統合失調症の中核型は,人格が恒常的に後退してしまいますが,これは自我が機能不全のレベルを越えて,自我機構自体(生物学的な根拠があると思われます)が何らかの破壊を受け,不可逆的な変化が生じたと考えられます。
自我の破壊という意味では,先の大学生が述べていることが参考になります。病的体験が活発なころに,殺される夢を繰り返し見たというのですが,これは自我が無意識の高波を受けきれず,破壊されかけているという意味に取れるように思います。
心理的な治療では,全人格的なものが,あるいは人間そのものが問われる側面があります。それは,治療者は病者を診る立場ですが,病者の問題を通じて自分自身を問う姿勢が要求されるという意味を持ちます。この心の作業には,問題を解く方程式もあります。いろいろある中で,たとえばフロイトを始祖とする精神分析はその一つです。この’方程式’の価値が他を凌駕するのは,人間の心への洞察の深さにあるでしょう。しかし我々がするべきことは,フロイトの真似ではありません。学ぶべきことは,その精神です。目の前の患者さんにフロイトの方程式を当てはめようとする治療者があるとすれば,彼は反フロイト的な行為をしていることになります。生きている現実に,’方程式’を当てはめて検討してみるのは意味があるでしょうが,’方程式’に患者さんを押し込めようとするのは,治療者がすることではありません。’自分の眼’を持たない心理治療者は,その名に値しません。しかし,’方程式’を無視する無手勝流も排除されるべきです。心を白紙にして臨むことと,学ぶ精神とは別個のことではないからです。学ぶ精神と白紙で臨む精神とを共に持つことが,病める心を前にする治療者の,理想とするべき’方程式’です。
心の問題に,万人が納得する永遠の真理といったものはあり得ないことなので,先達に学ぶ心を持ちつつ,なおかつ心が白紙であるときに,新たな里程標のようなものが立ち上がって見えて来るかもしれません。
人間の心理の問題は果てしなく奥が深く,そこに分け入ろうとすると,終わりのない探索行為になります。心理的な治療はそうした土俵の上ですることになるので,これまた果てしなく深く,複雑で,難解です。そうした困難に耐えて探索行為が続けられるうちに,心的現象の連鎖として,里程標のごときものが自然に見えて来ることがあると思います。やがては,現象的なものを超越したものも視界に現れてくることがあると思います。それらは実証されることはなく,仮説にとどまりますが,一定の意味を持ち,探索行を続けていく上で,勇気をもたらします。症例を積み重ねることによって,それらが無効化されることもあるでしょうが,有用性が更に確信されることもあると思います。
そのようなことを前提にして,主体との好ましい接触が出来ているときに,自我の自律性が健全に機能するものと仮定的に考えることができます。逆に自律性が傷つけられたり,混乱させられたりしがちなときに,自我の主体への接触が不良であると考えられます。
そもそも自我の起源の胚種である段階で,機構的に自律性や境界などが組み込まれていると考えられます。育児の主力である母親によって,自然的な自我の機構がほどほどに保護されつつ成長すれば,いい方を変えれば母親によって著しく擾乱されなければ,自我の中核である自律機能を育てる根が,到達目標である主体にまで伸びていくと仮定的に考えられます。
このように自我の自律性の根が,心の発達,成長につれて主体に向かって伸びていくと想定されますが,主体との接触が好ましいものであれば,親からの自立は順調に進行するといえるでしょうし,接触が著しく不調であれば,何歳になっても幼児のように親の助けを必要とするでしょう。
20代のある女性は,一人でいる時の不安,恐怖が著しく,その心の様子を,「幼いままの自分が,まるで一人で荒野に取り残されている感じ・・・」と表現しております。
自我の自律性の根は自然的に成長していくのがよいはずですが,原初の段階では自我はそれ自身で機能する力はなく,母親による愛情で保護されることが,絶対的に必要です。このことが,人間の心を育てる上で大きな矛盾を引き起こすのです。他者の介入は,赤ん坊の自我の自然的な機能を護るには,’あまりに不自然’にならざるを得ません。自然が全的な存在であるとすれば,人間は能力的に二分の一以下的な存在です。どう転んでも赤ん坊の自我は混乱させられるのです。それに相応して,自我の主体との関係はなにがしか接触不良に陥るのが,人間存在の宿命的現実です。そして,その不良の程度に応じて自我の自律性に混乱が生じ,それに伴って裏の人格が勢力を持つことになります。裏の人格の中核にあるのは,主体との関係を欠いた裏の自我ともいえるものですが,こちらは死に関わるエネルギーと一体化します。死に関わるものの中核にあり,裏の自我の拠り所となるだろうものを,裏の主体と呼ぶことができるのではないかと思います。
表の自我の自律機能の主要な役割は,自己の善導にあるだろうと想定されるのに対して,裏の自我の機能は,自己の善導の破壊,否定という性格を持ちます。従って,悪という性格を帯びています。
これら表と裏の自我の拠り所もそれぞれに違うということですが,それは別個に存在するというよりは,一つの主体の中の二つの機構とでもいうべきものではないかと思われます。つまり生と死は,生命体にはすべて起こることですが,中でも自我を持つ人間の特徴は,
単に生物学的に生と死があるのにとどまらず,精神的な意味をも併せ持つというところにあります。
心の外界には自然がありますが,これは宇宙にもおよぶ無限大の広がりを持ちます。また限りある人の命という観点からすると,永遠の時間と共にあるといえます。これら無限というものは,人間には概念と感覚の対象としてのみあり,人の身体にも心にも実態としては存在しません。
心の内界にも同様の無限の属性を持つ無意識界があり,これも外界の自然と一体のものと考えて然るべきです。どうやら無限の属性を持たない人間の精神に特有なものとして,現象として現前する事実や観念は,二つの極性に分離して現れる傾向があるといえるようです。外界の自然と内界の’自然なる無意識界’もその一つです。それは自我に拠る人間存在ならではの現象的な事実です。そのような特性を持つ人間の自我に対応して,自我の母体である’自然なる無意識界’にも,生と死に関与する二つの機構が存在すると仮定することができます。それらは人間にこそ別種のものとして存在しているように見えるものの,自然の様態としては一体のものに違いありません。
生と死は本来は一体のものと思われますが,自我を持つ人間に特有のこととして二極に分化し,互いに逆方向のベクトルを持つものとして現前しています。生は自我の誕生であり,意識という光の世界のはじまりです。そして,それは自然からの乖離でもあります。死は,意識という光の消滅であり,世界の暗黒化です。それは同時に自我の終焉ないしはお役ご免を意味します。そして,それは自然への帰還です。生は明るい光の中にあり,死は暗黒の中にありますが,それはあくまでも意識の存在が前提となっていえることです。
人間の誕生は自我の誕生です。自我が生まれることによって光が生まれました。そして光が生まれたことによって闇が生まれたのです。光は生の世界です。そして闇は死の世界です。人間は生きながらにして,死を併せ持っているといえます。
自我の誕生と共に自然から乖離したのが人間です。自我は生きる方向に向けて光の世界を構築する拠り所です。そして光を得ることによって,生の対極に死が布置することになったのです。生きるという方向で自己を形成していくのが,いわば人間の自然的な使命であると思われますが,そのことの裏面である死は,生きる機能に不具合が生じれば生そのものを回収しようとするもののようです。
寿命がつきかけたときに,「これでいい,これでいい」とつぶやいたという哲学者の話がありますが,回収作業を開始した死に自己を差し出す心を語る言葉として,人間の生き様の理想を見る思いがします。つまり死もまた,人間にとっては一つの目標です。いかに生きるかということは,いかに死ぬかというのとほとんど同義です。死は,単なる生の否定ということではないと思います。死は生に既に内包されており,いかに死ぬかが人間の課題です。自我が人間的な事態そのものであるとすれば,死は自然そのものの人間的な事態です。そういう意味で,死は裏の主体といえるのだと思います。
身近な者の死が悲しいのは,生を否定する力としての死が,生きよう,行きたいとする人の心を日常的に脅かすものであり,その直接的な事実の現前に立ち会うからです。死は生の脅威です。生きるためには喜びが必要です。それは意識という光の下でくりひろげられる祭典です。その喜びを意識と共に永遠に回収されてしまうのが死です。それが悲しくないわけがありません。生きる喜びをそれなりに楽しんできたあるとき,「もう,そろそろいいだろう」と,意識という舞台上の照明を一挙に消されてしまうのは残酷な話です。回収する側は,「そんなことは初めから承知していたはずだ」というでしょう。それは確かにそうなのです。回収する側が,舞台の照明の点灯をも含め,一切の権限を握っているのですから,文句をいってもはじまりません。人間としては,いずれにせよ与えられたことを受け止める以外に手はありません。人の力を超越しているなにものかが,こういう意味不明の舞台を提供しているのですから,なにか我々には及びもつかない深い思慮が働いているのだろうと考えるのが関の山です。どうやら人間が第一等に偉いわけではないのは確かですから,そうであれば,安んじてその第一等者に身を任せるのが分というものです。
それとおなじ理由から,つまり第一等者によってよりよく生きよと命じられているのですから,あれこれいわずにおのれの分に従って,謙遜に,よかれと信じる日々の営みを大切にし,自分らしい人生の創出に励むのが最善ということになるのではないでしょうか。
ということで,自我と意識の光を頼りに生きる我々としては,意識の否定である死の影は大変な脅威ですが,死というものの存在も生と同じくらい重要であるのは疑いありません。ですから潔く死の意義を積極的に評価するに越したことはありません。
そういうわけですから,自然のものである死が人間の脅威であるにしても,人間の敵というわけではありません。人間の敵は他でもなく人間自身のようです。人間は人間によって,相互に自然的な素地を混乱させ合い,それぞれの自己が,自己ならざる自己に迷い込むように仕向けあっているかのようです。困難な人生を,共に生きるものとして相互に助け合うのが筋というものでしょうが,不幸の渦中にあるものがしばしば意地悪であるように,大小の意地悪を,かけがえのない我が子に対してさえしてしまうのが,残念ながら我々人間の愚かな性であるようです。そのように,悲喜劇を繰り返しつつ一生を過ごそうとしているかのように見えます。
迷妄の渦に巻き取られる程度が甚だしいときに,生よりも死が関心事になっていきます。つまり,よりよく自分自身でありつつあるとき,生は大きく途を開けてくれますが,自己ならざる自己に迷い込んでしまうと,死が手招きしはじめるのです。前者が表の主体と表の自我の蜜月がはかられているのに対して,後者は裏の自我が表のそれを圧倒する力を持ち,裏の主体との接触を深めてしまっていることの表れといえるでしょう。そうなると,いわば死の極北から吹きつける風が,心のさまざまな不調,病気をもたらし,あるいは悪化させ,あるいは生きる意欲を失わせたりということも起こるのです。
人間が,自己の存在条件に他者の存在を前提としていることは,自我に拠る人間の完全性(自然の属性)の欠如を表していると考えられます。それは先にも述べたように,もろもろの事実や観念が二極に分化して現前するのが,人間の認識機能の大きな特徴であり,その一つの表われということです。自己と他者が合体して完全になるのが,自然的完全を志向する人間の理念といえるようです。そのように考えるのは,人間には,自他が互いに相手を求め合う無意識的な心の叫びがあるように思われるからです。その心の叫びは自然的な合体を求め合うようであり,現実に恋愛関係にある男女において,そういうことが垣間見えているように思われます。それを志向する心は,純度の高いものなので,実際には,むしろ他者は幻滅を与えるだけになるのでしょう。
他者は,自己の存在にとって必要不可欠な存在です。それは外部にある他人との関係が不可欠ということでもありますが,それにとどまらず,その根拠として自己の存在構造に他者が組み込まれているということでもあります。
自己の存在構造は,自我機構を拠り所としていると思われます。従って自己の存在構造の原基は,自我機構にあると考えられます。それらを敷衍すると,自己の中に内なる他者があり,それは当然,他者の中に外なる自己があることを意味します。それがあるために,現実に外部に存在する他者への親しみを持つことが可能になるのです。しかし一方では,他者は自己ならざる者でもあるので,疎隔感を持つことにもなります。人は孤独であり,孤独でないという一見矛盾した存在ですが,それは人間が全ではない存在であることの一端といえるでしょう。
自己愛と他者愛は相互的なひと組の関係にあります。自己愛が健全であれば,他者愛も健全のはずです。自己を愛する心の原基は,自我機構に備わっていると考えられますが,それを賦活し,機能的に発達させるのは,他者の中の特別な他者である母親の愛情によってです。私なる乳児を愛情をもって認めてくれている母親の受容力が,乳児の自己愛を育みます。そして,そういう豊かなものを与えてくれている母親に愛情のお返しをするのです。そのような相互的な力動関係が自我の自律性の根を護り育て,内なる主体へと根が伸びていく素地を作るのです。
逆に,このような豊かな愛情の関係で結ばれなかった親子の場合,乳児の心の自己愛は屈折したものになり,他者に対しても屈折した心を持つことにならざるを得ません。
恵まれた自己愛を持つ心の持ち主が,他者の中に他なる自己を感じたときに,他者への愛情と信頼が生まれるでしょう。自己の内部の他者(内なる他者)と外部にある他者の内部の自己(外なる自己)とが,それぞれに活性化され,結合的になったと考えられるのです。そして他者が単なる他性であるに過ぎないとき,他者は無縁の存在です。それらは状況によっても違うはずです。異郷の地で心細い思いをしているときに同胞を見かけると,日常の世界では味わえない親愛の感情を持つこともあるでしょう。道端で転んで怪我をしたときに,かけつけてくれる人があれば,恩人のように感じられるでしょう。
また,屈折した自己愛の持ち主が,他者の中に自己を感じたとき,容易には心を開けないと思います。自己愛の光りがとばりの中にあるように感じられている人は,他者に対して一様に距離を保ち,周囲の人には冷淡に感じられることもあるでしょう。
孤独であることを,人は一般的に嫌います。実際,一人遊びが多い幼い子は,将来が案じられる理由があるのは確かでしょう。
子供の場合,遊びを楽しむことが大変重要です。子供は生のエネルギーにあふれているので,元気がふさわしいのです。そして遊びを通じて自分を全身で表現することができるからです。時には喧嘩もするでしょう。喧嘩にも自己主張,自己表現の重要な意味があります。動物は,仲間との戦いを通じて群の中の自分の力,位置を知ることができ,仲間とうまくやっていく知恵を得ます。人間もおなじです。遊びの中の喧嘩で,人との関係の中での自己調整をはかることができます。そこで何を会得するかは,個々の問題ではありますが。いずれにせよ喧嘩という真剣な行為を通じて,自分を知り,他者を知り,怒りを体験し,対立する緊張を知り,断裂を味わい,和解する感動を覚えます。それらは大人になっていく上で,得難い体験になることでしょう。
まだ自分で自分を支える力を持たない子供にとって,孤独には危険な厳しさがあると思います。というのは,孤独には,死の極北から吹きつける風にさらされるという意味があるように思われるからです。心を凍りつかせるほどの力を持つ孤独は,子供には耐え難いものがあるでしょう。それは心を育てるよりは,破壊する方向に仕向けるかもしれません。
また他の元気な子供たちは,これらの孤独な子の理解者になるよりは,迫害者になる可能性があります。生きるエネルギーにあふれている子に,死の北風に震えている仲間への同情を要求するのは,一般に無理なことだろうと思います。しかし,これらの元気にあふれた子供たちにも,死の予感がないとはいえないはずです。それがあるからこそ,その気配に憤りを覚え,叩き潰すか,無視するかしたくなるのではないでしょうか。もっとも大抵の元気にあふれた子供たちの口から,その通りだという言葉は得られそうにありませんが。
いじめられっ子たちを護るのは大人の役目です。生きるエネルギーにあふれた子達に,そういう役割は期待できないように思います。大人たちが役目を果たしている姿があれば,それでいいのではないでしょうか。
孤独な子供たちは危険な状況にあると考えるべきですが,注意を要するのは,彼らを危険に追いやるのは,”元気な子’たちの悪意です(それ以上に親の不理解が問題ですが)。それは無意識的なものかもしれませんが,悪意の根底には死への恐怖が潜んでいると思われます。’元気であること’は子供にとって大切ではあるでしょうが,そこには生の裏面である死を意識しないで済ませるという意味もあると思われます。’元気な子’の悪意は,恐らく元気を沮喪させる影を持つ子に向けられます。それは本能的なものだと思います。影は死の領域に属するものです。それは’元気’を挑発するのです。そして彼らの悪意によって疎外される孤独な子は,自分自身の中に新たに燃え上がる心の炎が生まれ出て,自分自身を励ます力となることができるのでなければ,更に一層,死の極風が心を凍りつかせることになる可能性があります。そうなると,著しい悪しき依存から抜け出すのは容易なことではなくなると思います。
幼い時に情緒的な満足を覚えることは,その後の性格形成に重要な意味がありますが,しかし,それだけでは足りない何かがあります。人とうまくやれるということは,集団の中で生活をしていくことになる子供たちにとって,是非とも身につけていなければならないものでしょう。’集団の中にいる仕合せ’といったものは,大多数の者が理想とするものだと思います。そこには,しかしながら,’集団への逃避’という別な側面があります。何からの逃避かといえば,死の脅威ということになると思います。そういうことは意識にのぼることがあまりないでしょうが,集団依存的な一般的な市民の盲点だと思います。そうであるとすれば,先に述べた乳幼児期の情緒的な満足が性格形成の上で重要だというのは,括弧つきでということになるのでしょう。つまり市民一般のもう一つの顔である集団依存は,守りの姿勢を変えるのを難しくさせる要因になります。この意味での保守性は,特に日本人では個性の否定に傾きます。世間体を気にするということにもつながると思います。これらは育児の上での干渉にも通じる問題です。
これは,いわゆるペルソナの問題です。
C.Gユングは,次のような意味のことをいっています。
人間は,誰もがしっかりとペルソナを身につけていなければならない,しかし,それは自己ならざる自己の世間向けの顔である,それが発達し過ぎると,自己の実体が形骸化するだろう,中年期以降に,それが問われることになるだろうと。
このことは,社会的な存在である人間は,社会の中で人と調和してやっていけるための人格的な修練を欠かすわけにはいかないが,しかしそれは自己本来のあるべき姿とはまったく別問題であるということです。
世間的な成功を収めた人は,会社なりの組織にいるかぎり他人から評価され,それに助けられて自分の価値を支えることができるでしょう。しかし定年退職になって会社を離れると,いわば支えを失うことになります。それをどこに求めるかが問われます。しかしどこにもそれが見当たらないとすると,晩年が過酷なものになります。
ペルソナを鍛える一方では,自己と人生について思いをめぐらせて,集団の中で調和していることの意味と限界を理解しているに越したことはありません。そうすることで,集団への依存から,ある程度自由でいられることが可能だと思います。それは自己自身との関係をしっかりさせ,重心の移動を図る心の用意をはかっておく意味を持ちます。
集団の中で平和に過ごすことができる穏やかな心は,何よりも人間にとっての極限的なものを回避していられるという意味があると思います。それはそれで必要なことでもあるでしょうが,回避という姿勢は問題をはらんでいるのは確かでしょう。後々,いま述べたような自己の実質の空洞化に悩むということもあるでしょうし,他者に対しては無意識的に同族的,均質的なものを求め,排他的にならざるを得ないという別の顔を持っているのも否定できません。どんなに’良い人’でも,疎外されて傷ついている部外者には,結局のところ冷淡,非情であるしかないのです。
人生を創造し,人生の大問題に取り組むことになるのは,’元気な子’たちに疎外され,辛い時代を過ごした子供たちであるように思われます。彼らには,死の極風にもまれ,’人生に遭難する’危険を切り抜けてきた力への自負があると思います。人生そのものを受け止め,直視しようとすることがなければ,芸術も思想も成立しません。彼らは孤独であることを恐れないと思いますし,’明るく群れる’ことに価値を求めることはないでしょう。孤独を恐れない者には嘘は通用しないのです。逆にいえば,一般には,人間にとって重たすぎるものは回避するという,一種の嘘があるといえると思います。
彼らにとっては,自己自身との関係が最も重要になるので,他者との関係は,それぞれの仕事を通じた間接系になるだろうと思います。偽りの関係は無意味なので,真の友人以外は不要なことかもしれません。彼らにふさわしいのは人類愛ということになるのでしょうか。主体との関係がしっかりしていれば,自我の自律性もしっかりしているので,極風にたじろぐこともないように思われます。
こうしたことを考慮に入れると,先ほど述べた乳幼児期の母子の好ましい愛情関係について,つけ加えなければならないものがあることになります。
母親の愛情が重要な意味を持つことは強調されて然るべきですが,これには例外があります。俗に,「天才と狂気は紙一重」というように,長じて大きな才能を個性的に開花させることができるのは,むしろ幼少時に母子関係に恵まれていたとはいい難く,何かと問題があった生い立ちの子であるようです。「艱難汝を玉にす」という諺があります。幼いころに集団になじめない’変わった子’が,孤独の中で極風にもまれて,創造的な自己を創出する場合があります。それは本来的な自己の達成ともいえることです。そういうことが可能であるためには,孤独に耐える強い自我に恵まれている必要があると思います。彼らは,人生の早い時期に自我の自律性が危機に瀕したものを,自力で取り戻すことができたといえるのでしょう。このような場合に,自我は主体と最も望ましい関係にあるといえると思います。
このことは人生の難しさを教えてくれます。いわば’人生に遭難しない’ために,幼いころに母親を中心とした近親者たちから,豊かな愛情を与えられることが望ましいのですが,それは一面では,’集団への依存’という日常のぬくもりの中に人を安住させがちです。それがいけないということもないでしょうが,人生を回避している姿といえるのも確かでしょう。人が自己を本来化させるためには,孤独を引き受ける力が必要です。
一般的な市民にとっては,隣人愛が最も価値があり,美しいものでもあります。極風にさらされることから身を守るために,他者は重要なパートナーです。愛情の親密な関係で結ばれた他者があれば,日常はどんなに救われ,励まされることでしょう。災厄や不幸に見舞われれば,みんなが協力して助けてもくれるでしょう。それで十分だともいえるのかもしれません。
平凡な市民と非凡な個性派を分けるのは,他者への依存の仕方の違いといえます。他者への依存の比重が高くなれば,その関係に縛られて自由度が低下せざるを得ません。その分,いわば自己の重心は自己自身の中にはなく,何かの都合で自己の軸が傾いたときに,態勢を回復させるのに難渋することもあると思います。
一方,非凡な個性派は,他者との関係が比較的ゆるやかで,それだけに自由度が高いと思います。自己の重心がいわば自分の中心にあるので,ストレスで軸が揺らいでもダルマのように容易に姿勢を回復させることができるようです。
それは,極風にもまれてきた人と,それを回避してきた人との違いともいえるでしょう。
しかしながら,場合によっては命がけで人を救おうとするのも,隣人愛に富んだ人たちのようです。人間の価値の基準は簡単にいえるものではありません。
隣人愛の性格の一つの例を,シェクスピアの戯曲,「オセロ」に見てみます。
ムーア人の将軍であるオセロ(黒人)は,貞淑な妻,デズデモーナ(白人)を大変愛しています。美しい妻に満足しているオセロは,仕合せな日々を送っています。ところが忠臣と信じている部下のイアーゴー(白人)が,デズデモーナが不貞を働いていると吹き込みます。妻を信じようとして懊悩するオセロにとどめを刺したのは,一枚のハンカチーフでした。それは二人のあいだを繋ぐ愛のしるしとして,オセロが妻に,「決して失くさないように」と念を押して渡したものでした。それをイアーゴーが盗み取り,動かぬ証拠としてオセロの心を揺さぶります。嫉妬の激情にかられたオセロは,ついに最愛の妻を殺してしまいます。そして,やがて真相を知り,自らも命を絶ちます。
オセロが妻を愛する心情は一途なものであり,生きる喜びそのものです。しかし当然のことながら,貞操を疑ったときに暗転します。そのように仕向けたのは,悪魔的な心を持つ者です。暗転したオセロの心は,死の方向になだれ込んでいきます。そして最愛の人を殺し,自らも絶望して死を選びます。
オセロにとってデズデモーナは生きる意味のすべてに等しいものでした。高い愛と信頼への代償のように,絶対的な貞淑を求めました。表の心がそのようなものであるとき,心の裏面がどうであったかといえば,悪魔であるイアーゴーがつけ入る隙があったということが証明しています。つまり心の闇には,猜疑,不信など非愛の心が拭い難く潜んでいたということです。山が高ければ谷も深いのです。デズデモーナの気高い心を信じようとした分,一方ではそれを疑う心が意識を悩ませていました。それ自身が悪魔と手を携えて出番を待っているといえます。イアーゴーは,この無意識の中に潜むもの,そのものです。そして悪魔は黄泉の国の住人です。
デズデモーナへの愛の光が,オセロに生きる喜びを与えていました。しかし愛という光を求める心が強すぎたことが,オセロの心の闇の深さを物語っています。この戯曲で,黒人であることが白人へのオセロのコンプレックスを,象徴的に表しているようです。
隣人愛は,オセロのように純度の高いものの要求であるとき,自ら崩れ去るしかないのです。デズデモーナは貞淑の化身として描かれています。このドラマは観念的に過ぎるきらいがあるのですが,デズデモーナが生きた魂の持ち主であれば,オセロ的な愛の要求に耐えられないでしょう。離別するか,浮気でもするしかなさそうに思われます。オセロは滅びるべくして滅びたのです。滅ぼすべく誘ったのは外部にあるイアーゴーですが,それを可能にさせるほどに,オセロの内なるイアーゴーは勢力を強めていたのです。
隣人愛は人類愛のように純度が高いものであっては,ある意味ではならないのです。それは戦略的でなければならないといっていいと思います。不貞や欺きや裏切りや不公平などが,少々のことなら認め合わなければ成り立たないと思います。程度の問題でしょうが,そういうものを内に秘めて,なおかつ仲間として肩を組み合えるのでなければ仲間にはなれないでしょう。愛は少々のことは許すということも含んでいます。
生と死,愛と非愛の二者関係の両極の中間にあるのが人間存在です。従って愛は自然発生的であり,かつ世俗的,打算的でもある相対関係の中にあるといえます。
生と死の両極は,しかしながら,同等,同格ではありません。人間は生の極と全的な結合をすることは決してありませんが,死の極への全的な結合は,必ず起こるのです。死には,生という意識の光を回収する役目があるようです。あたかも人生は一つの作品のようであり,魂のこもった作品の制作が見込めないと分かったときに,人生そのものを回収する作業が始まるかのようです。それは同時に,主体との関係がほぼ断たれたことを意味すると思います。その撤収作業の主役が悪魔的な力です。言葉を換えれば,この悪魔は裏の主体ということになるのでしょう。
人間は,死を決意して自死にいたることができるでしょうか?寿命がつきたような自然的な死は別として,死を決意したときに,悪魔の回収作業が最終段階まで進んでいるようにも思われます。ですから死は決意してできるというよりは,回収作業に身を任せるというほうが事実に近いのではないのでしょうか。自死の気配を強めている人に,人の愛がどうしても届かないときには,そのようなことが起こっているのかもしれません。
表と裏の心のあいだの境界は,いうならば関所のようなものと考えるのが合理的なように思われます。裏の心は無意識界に勢力を張っていることになるのですが,表の自我は関所を通じてそれとの交流をはかっているというふうに考えることができます。
無意識の世界では,最下層で身体との直接的な関わりを持っていると考えられます。精神のエネルギーの源泉は身体にあると思われますが,精神と身体の関係は相補的です。一方的に心が身体からエネルギーを補給されているということではなく,心が健全に機能していれば身体にも影響が及び,身体も健やかでいられるわけです。
身体と接する層を最下部に,自我の層を最上部に置くのが,心の機能的ー構造的なヒエラルヒーです。そのような構造が仮定的に想定されるので,境界もまた,それらのあいだにあると仮定するのが合理的ではないでしょうか。
C.Gユングによって,身体と接する無意識の最下層を普遍的(あるいは集合的)無意識と呼ばれ,その上層の自我の領域と接する無意識層を個人的無意識と呼ばれております。それらのことは十分に説得的だと思います。
精神の力動総体は,自我の働きに決定的な影響を受けます。自我は,自己を指導する立場にあります。そして社会的,対人的な関わりの直接的な責任者の立場にあります。しかし自我は心の全体の主体ではありません。自我の働きがどう評価されるかは,内在する主体を拠り所とするに足りる働きをしているかによって決定されるでしょう。自己に対して責任を負う自我が十分な働きをすれば,主体との関係が良好に保たれていることになるので,いわば全身にエネルギーが行き渡るのです。そのように自我が望ましい働きをしているとき,境界での検閲は柔軟であると考えていいと思います。つまり現状のままで殊更の問題はなく,仮に,たとえば夢を通じて無意識からの何らかのメッセージがあれば,それを受けて前向きに検討することができる等々という意味でです。
自我の検閲が厳しくなるときは,自我が何らかの脅威を受けているときでしょう。それが外部に問題があってのことであっても,無意識が活性化するので,緊張を強いられます。自我に余裕がなければ,無意識の圧力を受けることになりますので,不安やいらいら感などに苦しむかもしれません。そういうときは,一時的に無意識との関わりを停止しようとするのも自我の仕事です。
自我の機能が衰退していると,無意識の支配を受けます。社会との関わりを持つのは表の自我の役目なので,衰退した自我は相対的に勢力を強めている裏の自我の傀儡と化し易くなります。
また自我の混乱と衰弱が甚だしいと,裏の自我が表のそれを無視して,直接的な行動に出ることがあります。解離性障害といわれるのは,そういう心の現象です。
更に自我の機能が不全化すると,境界機能も不全化して,深い層の無意識の内容が意識の中に侵入するという事態にもなります。精神病といわれる諸相は,そのような問題です。
関所がまったく封鎖されることはないでしょう。そういうことが必要なほどに無意識の力が増大しているときは,自我の境界機能はむしろ破壊されてしまう危険が増大するだろうと思われます。統合失調症のような事態が,一時的に現実化することは,状況によっては誰にでもあり得ることです。いずれにしても自我が柔軟な強さを失うと,境界の検閲機能も頑なになり,無意識の圧力を封じようとすることはあると思います。そういう時は,感情が表に現われなくなります。
関所での検閲を厳重にする必要があるのは,個人的無意識層にあるものが,単なる過去の体験群の集積にとどまらないからです。抑圧という心的活動は自我の価値判断に伴うものですが,それは自我に与えられている能力が限定的であることに帰着します。自我が抑圧するものには一定の傾向があります。自我がいわば神経質になっているものが抑圧の対象になり,その傾向の原点は乳幼児期にあると思います。人間が自我に拠る存在であるということは,自然的に心を形成することが不可能であるという意味を持ちます。しかも自然的であることが常に目標になるという矛盾した性格を強いられております。自然的であることが不可能である最大の理由は,自己なる存在が他者の存在を前提として可能であるということです。他者の介入によって自然的な心の営為が混乱させられ,それを改めて自分の力で自然的な方向に自己を整え直す,それが人生の目標であるという観があります。ここに人生の意味と無意味が交錯しており,人間が存在する理由の不可解さがありますが,これらのことは,あくまでも我々人間が人間的に答えていく以外にないことです。そもそも,なんといっても人間が存在する理由を人間自身が持っていないのですから,その根本理由をいくら詮索してもどうなるものでもありません。
自我による抑圧という心的行為には,他者の介入によって強いられたという側面があります。その始原的なものの過半は,原初の他者であり,最も関わりの深い母親との関係において生じると考えていいと思います。
たとえば性的な行動は,動物ならば自然なものとしてあるのですが,人間は抑圧します。それは自我を持つものと,持たざるものとの違いのようです。それは少なくとも一つには,自我に係属していると考えられる自己と他者とのあいだの境界によるのではないでしょうか。性的行動には,攻撃という側面があります。人間は人格的な存在なので,性行動が人格への攻撃という側面を持つのは否めません。境界を護るということは,自他の人格を尊重する意味を持ちます。自我機構に係属すると思われる境界機能は,生物学的な根拠を持っていると思われるので,性行動の抑圧は単なる文化的なモラルの要請以上のものがあると思います。しかし強すぎる性への拒否感は,他者(多くは親)の何らかの介入による自我の反自然的な性格傾向によると思います。
性がタブーになりがちなのは,その欲動の強さと攻撃性に関係すると思います。それは他者との関係を結びつける力にもなり,関係を破壊する力にもなります。従って,その本能の無原則的な発動は自我によって制限されます。そのときに自我の境界機能が意味を持つのです。その欲動の強さは結びつける作用の強さでもあるので,愛し合う男女のあいだでは好都合にはたらく一方,男女それぞれが異性を支配する本能的な手段にもなります。他人の性行動が気がかりになったり,不快感を持ったりするのは,欲動の魔力を扱いかねる複雑な心の動きがあるからでしょうか。
乳幼児が甘えを抑圧するのは,性の問題とは異なった意味があります。幼い子の甘えが母親の怒りを誘うのは,どういうときでしょうか?母親が情緒的に満たされているときに,幼い子の甘えに不快感を持つということはなさそうに思います。むしろその逆に,満たされていない情緒が拒否感を持つ理由になるのだと思います。自分の幼い子の甘えに怒りを覚える母親は,特別な状況にいるのでなければ,自分自身がおそらく乳児のように甘えたいのです。幼いころに甘えを満たされなかったという感情が働くのです。無意識にある満たされなかった情緒的諸欲求が自我を支配して,我が子の甘えを拒否するように,怒りをこめて要求するのでしょう。母親自身が幼いころにその母親からされたのと同じことを,我が子にすることになります。
全面依存の身である幼い子の自我は,ときによっては生き死にに関わる恐怖で母親の怒りを恐れると思います。
幼い子の甘えが,性的な欲求のように,母親に対して攻撃的な側面を持つとは考えられないことなので,この問題に関して自我が境界機能を必要とする意味はなく,一般的に甘えがタブーになることはありません。
甘えなどの情緒的なものが母親によって満たされることは,健全な自己愛と他者愛の育成に重要です。自律性の涵養という意味でも同様です。それは自我の自然的な機能が,母親によって護られたことにもなります。甘えを封じられることは,これらの意味がまったく逆になります。自然的な自我の機能が母なる他者の介入によって混乱させられ,自我が自律的な機能を捨てて母親に取り入ったという心の動きが抑圧と呼ばれています。幼い者の自我がそのような非常手段を取らなければならなかったのは,必ず恐怖と不信が働いたからだろうと思います。間違っても,母親が大好きだから母親に取りすがったなどということではありません。
このとき自我は母親の怒りを恐れたと思います。そして,自分が大切なものではなく,愛情に値しないと考えているのではないかという恐れと不信を持ったと思います。乳児にはそれに対して怒りを持つ理由がありますが,母親に向けるわけにはいきません。その怒りは,母親を怒らせる理由になるとおそれた甘えたい心に向かうのです。怒りをこめて,甘えたがる心を抑圧するのです。
このように,抑圧には,抑圧を蒙る側からすると不当であるという性格があります。ですからこれらの分身たちは,怒りによって抑えられるのですが,怒りを蓄えつつ無意識下に抑圧されているともいえるでしょう。
抑圧には,自我による死の宣告という性格があります。それは,自我は生の方向で機能するものですが,その折々の自我の判断が,ある種の体験が受け入れ難いとして無意識の闇に葬ったということを意味するからです。怒りはそれに伴って生じる感情です。つまり怒りは,死の方向で活動するエネルギーです。
自我のよい働きは生の方向で,わるい働きは死の方向で,心を動作させるといえます。また自我は,どう頑張ってみても半分しかよいことをできないともいえます。それは,自我には自然的な機能を大切に護るようにという大命題があり,それを達成するために他者の介在を必須のことして与えられているというふうに見えるということです。しかし自己と他者は合わせて’全’となるのは理念の上でのことで,現実には’全’どころか,他者は自我の破壊要因にさえなりかねません。どう転んでも’全’になりようがない人間は,それは永遠に彼方にあり続ける命題です。そして現実には自我の仕事としてではなく,自我の終焉として,死という’全’の世界に回収されるのです。自我の仕事は永遠に未完であり,悔いを残すことなく終焉を向かえるのは,すこぶる難しい話です。しかし’第一等者’ではない人間は,人間の知恵のおよばない’第一等者’にすべてを委ねるのが分というものでしょう。
母親との関係で,甘える心が自我によって抑圧されるとすると,甘えを封じる力が怒りです。それは母親の怒りが自分に向けられるのを恐れる自我が,扱いの厄介な甘えに対して怒りを持つということでもあります。本来は甘える心を自我が受け入れることで情緒的に満たされ,生のエネルギーを増幅させることができるはずですが,いわば母親の怒りに迎合するように,怒りをもって無垢の分身たちを葬り去るのです。受け入れられなかった分身たちは,悲しみ,寂しさ,虚しさなどの感情と共にあるでしょうが,そのエネルギーが強いだけに,境界を超えて自我に圧力を加えてくることになります。更にそれを強く抑圧することによって,自我は硬直したものになっていきます。これらのことは,エネルギーの流れの自然法則に反した,人工的なともいえる動きです。他者が介入することによって,心の自然な流れが乱されるのです。
怒りは,この例に即していえば,甘えを封じるために動いたのですが,意識の地下に封じられているものたちに所属する感情ともいえるでしょう。
破壊的なエネルギーである怒りは,死の方向で奉仕するものです。そして意識の地下に葬られているものたちは,怒りによって地下に繋ぎとめられているといえます。これらの分身たちは,自我が自由になり,自律機能を回復させて,改めて救い出されるのを待っています(それを実践するのが,分析的精神療法です)。しかし救出されないでいる状態が長期化すると,分身たちは怒りのエネルギーと一体化して,理不尽,不当な目にあっているものらしい恨みや羨望の感情に変質していきます。
抑圧は,すべての人に起こる人間に必須の心的過程です。そして常になにがしか不当であり,自然の心的機能を歪めます。その矛盾は人間に苦悩を与えます。不当な抑圧の比重が高くなっていくとすると,それは自我の弱さの反面ということでもあり,ますます自我の衰弱を招きかねません。しかし自我に強さがあれば,自分が知らずにしてしまった過度の抑圧が招いた,いわば不祥事を悩む力を持つことも可能です。意識の地下の分身たちの反攻を受けて,矛盾と苦悩に耐えながら,いつか,それらのエネルギーを己のものとしてしまうことも可能です。芸術作品には,このような心の過程が働いていると考えていいと思います。
分析的治療の経過中に,不用意に抑圧が解除されると,封印されていた怒りが,意識の表面に躍り出てくるような混乱が起こります。それが治療者に向けられるとき,治療者が抑圧,迫害の張本人であるかのような一種の取り違えが起こるのですが,やがてその怒りが治療者によって受容されるときに,患者さんの自我が抑圧者から受容者に変貌することができるのです。自我は更に自由になり,自律性が回復することになります。こういうことも考え合わせると,怒りは封印のために機動しただけではなく,受け入れを拒否された無垢のものたちと共にあるという側面があるのが分かります。治療者に向けられた怒りも,破壊的に作動しています。治療者が思わぬ怒りを向けられてあわてるとすれば,治療者は怒りの犠牲になるかもしれません。具体的に暴力を受けるとまではいかなくても,治療関係の破壊の危機に立ち至っているといえます。治療者が治療者としての節度を護れない困難な状況では,治療者・患者の関係は,迫害者・被害者の関係に変貌します。
しかし治療者が冷静さを失わず,治療者の立場を護ることができれば,怒りをもって破壊的な動きをした分身たちが,自我に受容されたに等しいことになるのです。それに伴って患者さんの自我も,自律性を回復する方向で動くはずです。それは既に生の動きです。死への志向性を持つ怒りに充当されていたエネルギーは,生の方向に志向する自我の自律性に所を換えることになります。つまりエネルギー自体は同一のものであり,自我の動きに伴って生と死とどちらかの方向に動くのです。怒りは死への志向を持つものの,生への方向で自我が力を回復させたときに,お役御免になるのです。
このことを考え合わせれば,怒りには自我の姿勢を「どやしつける」意味があるのが分かると思います。自我に,「受けて立つ」気があれば,怒りによって自我がよい仕事をすることができるのです。
一般に,つよい感情を潜在させてしまっている抑圧する自我は,特定の人や物へのしがみつき的な依存が強くなっています。それは必ずよくない依存です。過食症もその一つですが,依存症一般にそういうことがいえます。
依存症の異常なところは,食べることなり,飲酒なりが,人生の関心事のほとんどすべてと化していることです。そういうことは一般の人には理解に苦しむことです。
それらはいうならば死をかけた依存ともいえます。そうすることで必死に生につながっているのです。それは自我が,裏の自我にまったく支配されている姿ともいえます。その依存の手を放すと,死の世界にまっさかさまという恐怖が支配しています。
過食地獄に長年のあいだ苦しんでいるある女性に,次のような意味の問いかけを試みました。
「過食は自我が著しく衰弱して,裏の自我に支配されていることに伴うものと考えられます。言葉を換えれば,過食は,死の世界に属しています。一方で,会社へ行っていることや,めげずに診療に通い続けていることなどは,生の世界に属しています。いわば生死をかけた戦いといえますが,死の世界に引きずられかけているといっても過言ではありません。だから,食べることがすべてであるかのような事態になっているのです。しかし,こういう話はなんのことか訳が分からないと感じますか?」」
それに対して,彼女は首を振って,「いいえ,よく分かります」と明快に答えてくれました。
彼女は,過食のために異様に腹が膨らんでいると信じています。それは,もちろん,そんなふうには見えないといって上げたところでなんの意味もないほど,激しい恐怖です。それを人が見ると,異常な人だと思うだろうと恐れます。
それで私は,つづけて次のように問いかけました。
「異常なのは太っていることではなく,事実を認めようとしない気持ちです。たとえ醜かろうが,どうだろうが,事実は事実です。それは認める以外にないことです。しかし,あなたはそれを認めようとしない。それができるまでは,あなたの地獄は止むことはできないでしょう。逆にいえば,それができたときに,克服するきっかけをつかめるのです。癌と宣告されたとすると,すぐには受け容れられないと思います。そして受け入れることができるまで,平穏はあり得ないでしょう。事故で視力を失った人が不幸であるかどうかは,その事実を受け止めることができるかどうかにかかっています。失明が即座に不幸を意味するものではないと思います。そういうことと同じことで,事実としてあることは認める以外にありません。しかし,認め難い問題に直面することはあります。そして,認めることができないあいだは心に平穏はないのです。ところで,あなたは過食と癌か失明か,どちらかと差し替えることがでえきるとすると,どうしますか?」
彼女は少しのあいだ考えて,小さな声で,「眼です」と答えました。私が,「しかし,失明は治りませんが,過食は治ることが可能ですよ?」といったところ,「そうですね」と答えてくれました。
過食と肥満の恐怖とは,自己愛(と他者愛)と自己不信(他者不信)と直接の関係にあります。醜い身体の私という恐怖は,ありのままの自己を受け入れられないという自己不信と恐怖に帰着すると思います。それは密接不可分の関係にある他者不信(と恐怖)にも直結するのはいうまでもありません。
克服の第一歩は,’醜い私の身体’を,’ありのままの事実’として認める勇気を持つことです。それができた後で,やはり「私は醜い身体をしている」と思うかどうかは疑問です。たぶん,そうは思わないでしょう。
繰り返しになりますが,過食という依存を手放せない背景に,死につながる強い恐怖があり,それは依存症一般にいえます。
アルコール依存症者は,しばしば,会社や家庭など,持っているもの一切を失います。命と引き換えにしてでも酒瓶を手放さない人も少なからずあります。普通に考えると理解しがたことですが,アルコールという依存の対象を手放すと死の世界にまっさかさまに転げ落ちる恐怖があるからといえるだろうと思います。アルコールを飲みつづけることで心も身体も蝕まれていくので矛盾しているようですけれど,いずれにしてもいわば死の影に捉えられている心的状況でのことで,身体が緩徐に蝕まれて受動的に死を向かえるのは仕方がないと思うのかもしれません。
抑圧されている分身たちの欲求不満が長期にわたると,それは自我が無気力で当てにならないということでもあり,怒りと一体化して,いわば自我の根がしだいに腐っていくかのような印象もしばしば受けます。
破壊的なエネルギーを持つ裏の主体と一体化するに至ったと考えられる犯罪者たちにも同様なことがいえるようですが,こちらは裏の自我が強力化して,生きる理由が悪であると,裏の自我に迎合する形で自我が完全に傀儡化してしまうことにより,ある意味で活性化している様相であるように思われます。
他者との関係を自己の存在要件としている人間には,他者が自然的な自我の機能にさまざまな程度に破壊的に作用し,自律的な機能を歪め,混乱させるおそらく唯一の理由なので,他者はある意味でおそるべき強敵です。そして最も頼りとする最重要の立場にある母親が,他者の脅威を左右する鍵を握っているといえるでしょう。
しかしながら,精神の涵養の問題を安易に定式化することはできません。それぞれの持って生まれた自我の性状にもよるので,他者の脅威を受けつつ,それをやがては跳ね返していく力を導き出す子もあるでしょう。
自我の自律性は,個々人を,真の意味で個性的で人間的な達成に導くために欠かせないものと考えられます。その独自の人生行路を歩もうとすれば,どうしても孤独であることを免れないでしょうし,それを引き受ける覚悟,勇気,自分自身を信じる強い力などを必要とするでしょう。また,自然にそのような人生行路を歩み出すというよりは,何らかの決意と共に始まるものだと思います。というのも,将来を保証してくれる具体的な手がかりは特にはなく,自己を信じる曇りのない眼だけが頼りだろうからです。芸は身を助けるという諺があります。この独自の途を進む人には,なんらかの’芸’が手がかりを与えてくれると思います。
このように考えるのは,人間が生涯かけてまっとうしようとするのは,人間に与えられた自然的な自我の機能が,なかんずく自律的な機能が,他者の介入によってさまざまに混乱させられ,自己を失い,それをもう一度自然的な機能に修復することであるらしく見えるからです。
他者の問題は,すこぶる重要です。人間が自然そのものから乖離し,自己という存在者として誕生したとき,感覚的な存在である赤ん坊は,恐らく強い驚愕と恐怖の中にあるのではないでしょうか。周囲の大人は目出度いこととして祝福しますが,赤ん坊自身が自分の誕生を喜ぶ気分になれるか,甚だ疑問です。そういうものが皆無ということもないでしょうが。
赤ん坊にとって,生まれてきたことが目出度いと感じられるとすれば,それは母親が自分の存在を慈しみ,喜んでくれるのを知り,改めて自分の存在を愛でる気になったときだと思います。そういうことが可能であるためには,赤ん坊自身の中に,誕生をよしとし,自己を肯定する心の原基がなければならないといえるでしょう。伸びる芽がなければ,何事も伸びようがないのです。
いずれにせよ,自分の存在を大いに喜んでくれる他者なる母親の存在は,心の成長のためには不可欠です。自然児ならぬ人間の子は,母親の愛情に最初に触れて最初の安堵を知り,それから先は,その母的な愛情に絶対的な安心を求めると思います。生の方向に向けて自己を導くためには,なくてはならないと思われる自我の自律機能が萌芽の状態にある赤ん坊は,自己の内部に自己を支える力を持っていません。そうした心的状況では,おそらく絶対孤独の不安にさらされることになると想像されます。それは死の不安に包囲される脅威といっていいだろうと思います。その赤ん坊に大いなる光りをもたらすのは,なんといっても母親の愛情に違いありません。
赤ん坊の母親との関係での原初的な愛情体験は,心の成長のためには欠かせないものですが,赤ん坊が希求する愛情への欲求は絶対的なものがある激しいものです。それは人間以前だった全的な存在から,人間という不完全な存在への移行に伴う恐怖と驚愕と怒りをまじえた希求,というふうに考えることも可能ではないかと思います。そうした全的なものへの要求は,どうしても現実の前に失望に変質せざるを得ません。
愛というものを感じ取ったときに,全能欲求への期待はふくらむと思われます。しかし,それが満たされることは決してありません。期待が高いレベルでつづくかぎり,現実は冷酷です。赤ん坊はどうしてもそのことに気づく必要があります。それができたときに,人間として生きていくための第一条件をクリアしたことになります。自我に拠る人間は,能力的にいわば二分の一以下の存在です。人間には完璧はなく,ほどほどの満足が分というものです。強迫性障害などに見られる完全への要求には,原初のこうした問題がからんでいるのかもしれません。乳児が’二分の一の存在’であることを体得できるためには,母親の安定し,一貫した愛情が欠かせないでしょう。絶対的というものではなくても,自分を護る力を持っていることを理解し,許容する気になれるときに,心が落ち着いていくと思います。そして愛されている自分に気がつき,それに値する自分の価値を知り,生きている喜びを味わうことができるでしょう。また,自分を慈しみ,大切に思っていてくれる他者なる母親に,感謝と共に愛情のお返しができるようになるのです。ただし繰り返しになりますが,これらの肯定的な満足感は限定的であり,つまり不満,不信,怒りなどが一掃されることは決してありません。それが自我に拠る人間が,’二分の一以下の存在’であるという意味です。心が光の面と影の面とを持つということでもあります。
それはそれとして,日常生活の一般的な特徴は,反復です。来る日も来る日も,おなじような生活が繰り返されます。退屈は平和の証でもあります。
それに対して,気慰めをしつつの人生を送っていいものか,それは人の頽落態ではないかという議論も起こるかもしれません。それはもっともな議論だと思います。しかし凡庸な精神をしか持っていない我々の大方にとっては,それは厳しすぎる,場合によっては危険な問いかけです。
反復的な退屈な日常に,不意に不安が顔を出すという経験を,誰もがしていると思います。そうしたときに,急いでなじみのある日常に逃げ込み,胸をなでおろすかもしれません。たとえ退屈であっても,なじみの深い日常はこうした得体の知れない不安から身を守ってくれるので,贅沢なことはいえないのです。
退屈だが平和だった日々のあるとき,得体の知れない強い不安に見舞われ,それが執拗につづくとき,心の病かもしれません。それは平和だった反復的,日常的な世界の相貌が,もはや親和的ではなくなったということでもあるでしょう。
反復的な日常世界に安住できるためには,安定した自己愛と他者愛とを備えていることが必要のようです。それは,繰り返し述べてきたように,乳幼児期の母親との関係で情緒的に満たされる体験をしている(E.Hエリクソンの「基本的信頼」に相当すると思います)ことが基盤になります。。それによって,ある意味でバランスのよい性格を身につけることができ,いわゆる隣人愛の精神を発達させることができるのです。これらは,いわば平均的な市民感覚が発達している人たちです。彼らは,著しい不安に悩まされることがあまりないと思います。しかし,それが人間の模範的なあり方かといえば,それは疑問です。そこには,死の脅威(無意識的な)に対抗する愛の同盟という趣があり,そのかぎりでは自分たちの’健全な’市民感覚にほとんど疑問を持たないのです。危なっかしい生き様に見える肌合いの異なる他人たちに,隣人として優しい気遣いを示すことがあっても,所詮は理解しがたい世界の住人の域を出ることはないでしょう。彼らは自分の眼差しの優しさに,かなりの程度自足するのです。そして,また彼らの心配と忠告どおりに,’危なっかしい連中’は,人生の泥沼にはまり込むことが多いのも確かでしょう。これら市民的な健全さをしっかりと身につけている人たちは,隣人への優しく,愛情のある眼差しを持ち,決して無理をせず,突然見舞われた災厄にも従容として従う謙虚さと穏やかさを失わず,持って生まれた美質のために人の支援を得やすくもあり,ある意味で生き方の手本といえるでしょう。しかし,それにもかかわらず,死の脅威から目をそらす欺瞞化の才に富んでいるという趣は否定できません。
これらの’才能のある市民感覚’の持ち主ほどには,その種の才に恵まれていないものたちには,不意に顔を出す不安は,時によっては御し難いものがあると思います。それは一気に孤独を突きつけられるということでもあるでしょう。拡大視すれば,そこには死の影が漂っているといえるように思います。
影があるということは,光があるということです。心にとって光は自我の力を示すものであり,影は自我の無力を示し,死に所属するものです。自我はどうしても影を一掃できないものでもあります。
影は,それに捉えられると自我の滅亡を招きかねません。その予感が不安となって現れるのです。不安に見舞われたときに,自我がどういう姿勢を取るかが問われます。自我の解決能力が問われているのです。最も望ましいのは,他者との関係の途絶の不安,一切を無化する恐怖,等々であるこの死の影に,恐れずに立ち向かう勇気を持つことです。それがあれば,人を日常への頽落から脱出させるきっかけになるかもしれません。真に個性的な独自の途を開拓しようとすれば,’死’との戦いを抜きにしてはできない相談であるといえるのではないでしょうか。
しかしそういうことが可能であるのは,強い自我の持ち主であることが条件になると思います。それは先に述べた’健全な市民感覚の才能’の人とは,別種の才能ということになるでしょう。これら真の意味で個性的な人生を送る人は,’才能のある市民感覚’ということを基準とすれば,いびつな,バランスの悪い人格の持ち主ということになるようです。
以上に述べたように,なじみのある日常世界は,’死’に包囲されている現実を忘れていることができるという効用があります。そうした日常の世界に自足することができるのは,’健全な市民感覚’を身につけている人たちです。当然,彼らが人間社会の中心にいることになりますが,その特徴は良くも悪くも世俗的ということです。これらの集団依存的な生き方がうまくいっている人たちは,どことなく人生の勝利者という顔を持っています。人があるところ,いたるところに様々な集団がありますが,リーダーとなるのは,当然といえば当然ですが,人を上手にまとめたり,操ったりする能力に長けた人です。そういう人を中心に,その力を当てにする多くの仲間が集まって集団が形成されますが,肌合いの異なる者は巧妙に排除されることにならざるを得ないでしょう。偏狭といえばそうなりますが,集団の輪というものが要の意味であれば,それはやむを得ないことです。ですから,どうしても世俗的です。
人と仲良く暮らすことができるのはいいことです。それに異論はありません。それができれば人生はひとまず安泰といえるのでしょう。しかし,一方では,諸々のクラブから,排除され,疎外された人たちも必ずいることになります。クラブとしては,そんなことは知ったことではないということになるでしょう。それはやむを得ないこととはいえ,人間の偏狭が人間の不幸を生み出すという側面は否定できません。
そういうわけですから,そうした性格を持つ集団を,小市民的であるとして忌避する人がいるのもうなずけることです。他者に対して不信と恐怖と猜疑を払拭できないでいる人たちは,そういう拒絶感を持つでしょう。そこには,元々がそれらのクラブ的な人間の偏狭さの犠牲になり,心に傷を負ったといういきさつもあるだろうと思われます。
それらの人の中で,なにか秀でる一芸があれば,それは確かに,「芸は身を助ける」ことになるのでしょう。それらの恵まれた人たちは,自分自身の中に拠り所を持ち,自己を評価する基準を持つことになるので,他人の直接的な助けを必要としません。それだけに欺瞞的なものに敏感でもあるでしょう。従って彼らは,集団に対して批判的,否定的になるでしょう。孤独でもあるかもしれません。しかし他者との関係は,自己との関係同様に,内的に安定しているといえます。それは主体との接触がうまく図られるているということでもあると思います。
これらの独自の途を行くのは,いうまでもありませんが生易しいことではありません。自我がよほどしっかりしていないと,集団から離れて暮らすのは,やはり危険です。自分では個性的に生きているつもりでも,いつか途が見えなくなり,自分を見失う危険は,むしろ高いでしょう。そのときに死の極北から吹きつける冷たい風にさらされ,人間がいわば立ち枯れてしまうということも起こり得ると思います。死につながる意味を持つ孤独の彩の濃い生活は,精神を蝕むことになる危険があります。独自の実りある途を行く少数の人間エリートと,世間のクラブ的な社会に安住する常識派とのはざまに置かれると,どうしても危険な状況にあるといわなければなりません。
自我の自律性が確固としたものであるとき,自我に内属すると思われる境界機能もしっかりとした礎を得るでしょう。そして不幸にして,その好ましい心の作業に乱れが生じると,自我の根の主体との関係が不安定になると考えられます。そうなると自我は混乱しやすく,境界機能も不安定になるのではないかと思われます。
親,特に母親は,子に対して,心の境界をしばしば無視して侵入します。その極端なものは虐待する親です。虐待する親の下では,子の自我の自律性は失われます。そして甚だしい依存の仕方をしがちです。脅威を与えている親から逃れようとするよりは,その親への依存を手放せなくなるのです。それは死(乳幼児にとっては,親に見捨てられると,死の脅威にさらされることを意味します)をかけた必死の依存になるのではないかと思われます。
親の虐待に関するテレビの報道番組がありました。虐待されて命さえ危ぶまれる状況で,第三者が援助の手を差し伸べようとしても,虐待される子の十人が十人とも,「構わないでほしい」と述べたという内容でした。
境界を甚だしく無視して子の心の領域に侵入する親の養育を受けた子は,親への甚だしい依存を手放すことができません。それは自我の境界機能の欠落と自律機能の欠落を意味します。
そのような親子関係にある十代の患者さんがありました。社会性が大変低く,未熟な人格の人で,自分の問題を適切に表現する力もありません。しかし診療には通いつづけておりました。手前味噌のようになりますが,「ここへ来るとほっとする。私の聖域です」といったことを口にしておりました。そして,あるとき母親が訪ねてきました。ごく普通の母親のように見えました。診療への協力をお願いしたところ,こころよく聞いてくれました。しかしそれを最後に,その患者さんはクリニックを訪れることはありません。そのまま通院しつづけたからといって,’良くなる’ということも難しいと思いますが,私は,「回収されてしまった」と感じました。私の勝手な思い込みで,実はどこか別の医療機関に母親が連れて行ったというのであればまだしもと思うのですが。
こうした甚だしい依存関係(そうしたものは必ず悪しき依存です)では,自我の主体との関係は極めてよくないはずです。
自我の境界の問題は,隣り合う二つの国の関係によく似ています。両者に力の差があれば,強国がもう一つの国の主権を尊重するのはむしろ難しい問題です。強国が浸入して併合したり,植民地支配したりというのが歴史的現実です。
それと似たような事情にあるのが,親と子,特に母親と子供の関係だと思います。母親は胎児を宿し,お産の後も母子一体の時期を経験するので,余人には計り難い特有の感情を子供に持つと思います。そういうことと関係があると思いますが,母親がおかす一般的な間違いは,子供の領域への侵入です。それは子供の心の成長を阻み,心の障害をもたらす要因となる危険性もはらむことになるのですが,母親には容易には理解しにくい問題でもあるようです。母親自身が多かれ少なかれ依存の対象を必要としているので,恰好の相手を手放したくないというのが,むしろ一般ではないかと思います。そこには隠れた悪意さえうかがわれることもあります。母親は,子供のためを思ってしていると考えがちですが,意識の欺瞞というべき側面があることが決して少なくないと考えるべきです。
国境と異なるのは,強いはずの侵入する親が,実は強くはないがための侵入であるという点です。そういう弱さを自覚し,見据えることで心が成長するのでしょうし,子供の心の成長も助けることになるはずです。弱さは,それを自覚するときに,もはや弱くはないのです。
心の境界は,自他の存在をそれぞれ別個のものとして承認し,尊重するという意味を持ちます。国境が,相互にそれぞれの独立を尊重するものであり,それを護らなければ紛争になるのと似ています。
余計なお節介をされると腹が立つのは,境界を無視されたと感じるからです。親子といえどもおなじことで,親は子の存在を独立したものとして承認し,尊重しなければなりません。親が子の領域に侵入的になりながらその自覚を持たないのは,かつては自分自身がその親からおなじことをされてきたためであるかもしれません。これは好ましくない依存につながり,悪循環に陥りがちです。そして心の沼を広げる理由になります。
親は,特に母親は子供に依存しがちです。依存には良い形のものと悪い形のものがあります。前者は相互の人格を独立したものとして,それなりに認め合い,尊重し合っている場合で,いわば対等の関係で信頼と愛情を分かち合えるのです。後者は,親の力を子に対して行使するという体裁になります。あからさまに,あるいは暗黙のうちに,子供を従えてしまうのです。子供のころに親にされたことを,無意識のうちに取り込んで性格の一部にしてしまうのが人間です。そして自分では意識せずに,当然のように,子に対して,自分自身が子供であった時代にされたことを押付けていくのです。人はそういうことを繰り返し,まずいことをしているという自覚を持たないのです。人間は,代々このように苦しみの元をつないでいく不思議な一面を持っています。
境界機能がしっかりしていれば,他人が脅威に感じられることもあまりないでしょう。逆に,他人の脅威におびえる人は,境界機能が不確実なのです。それは隣国の侵入を受けてきた小国のおびえに似ています。そのことをYさんの例に見てみます。
Yさんは30代の男性です。彼は父親を大変恐れています。家族のだれもが父親には逆らえず,母親も夫に従って,Yさんはいわば放置されて幼児期を過ごしたと思っています。それは問題の一端で,長じては,勉強,進学,就職,友人との交際など,一事が万事,父親は激しい罵声をまじえて干渉しました。
父親は家族の全員が覚えているそれら昔のことを,ほとんど想起できません。しかし治療に非協力というわけではありません。出来ることがあれば力を惜しまない姿勢が見えています。被害を蒙った家族が覚えていることを,与えたらしい本人は記憶していないというのは,被害を与えたつもりがなかったからでしょうか。それとも都合のわるいことは忘れてしまう心の知恵なのでしょうか。
Yさんは成人し,結婚もしてから発病しました。職場で配置換えがあり,しばらくして年上の女性上司に恐怖心をいだくようになりました(客観的には人を恐怖させるような人ではなさそうです)。Yさんは,年上のその女性に取り入ろうとしたようです。父親を取り込み,内的な支配を受けている彼の自我は,取り入ることで身の安全を図ろうとしたのかと想像されます。しかし人とのあいだの距離の取り方がよく分からない(人の心が分からないのとおなじことです)Yさんの試みは,逆効果になりました。相手の女性には,しつこくつきまとう困った人と映ったようです。強い口調でたしなめられたYさんの心は,一気に崩れてしまいました。そして女性上司に依存することでおのれを保とうとした自我が,対象を見失って混乱に陥りました。Yさんは上司への恐怖心から,自分の席に座っていることができなくなりました。当然,仕事を満足にできず,欠勤することも目立つようになりました。
表の自我の主要な役割の一つは,社会的な立場を築き上げることです。それは自我の自律機能と境界機能が成長,強化されることによって可能になります。境界機能の重要なものは,問題を受け止める力です。
上に述べたことは,Yさんの自我が役割を果たすことができていないことを示しています。それと平行して裏の自我が勢力を強めていることになるはずです。
Yさんは,女性上司におそらく母親的なものを求めたと思われますが,拒絶されたと感じたときに,女性は拒否的,威嚇的,浸入的な支配の人に変貌したのです。女性は父親と同列の人になったということだと思います。彼女が出張などで不在のときはまだしも,ふだんは五分と席に座っていられないのです。
Yさんには退行しやすい幼児心性が色濃くあります。それは一つには母親的なものに甘えたい,頼りたいということです。また,拒否的,威嚇的なものに怯えを持ちやすいということでもあります。それらのことは自我の自律性が混乱しやすく,頼りないということと,自己の主観世界が他者の客観世界との混同が生じやすく,境界機能の受け止める力,侵入的にならない力が未分化であることを示しています。
父親への恐れと共に怒りも持っているYさんには,自分がこうなったのは父親のせいだというつよい思いがあります。しかしその父親を取り込み内在化しているのは,父親に対抗する力がない自我が,取り入る道を選んだということだと思います。父親の内的な支配を許し,依存した無気力な自我は,父親が期待したような自分ではないことについて,常に罪悪感に責めさいなまれる代償を支払わされているのです。自分の意志は,父親によってことごとく踏みにじられてきたと思っている一方で,内的な父親と一体になって,自分を不甲斐ない奴と内心で罵っているのです。内在する父親に依存し,Yさん自身の自由意志が不在であるかぎりは,心が晴れる日がないのは,当然といえば当然です。
妻は優しい人です。夫を気の毒に思い,受容的,母親的な姿勢で助けようと努めています。しかしそれが仇となって,著しく退行的(いわゆる幼児がえり)になる時期がありました。その姿は,幼い子が保護者の下に安らごうとしているのに似ています。それに伴って自他の区別がつかなくなったように,仕事がある妻の心を気遣うこともなく,朝方まで時間かまわず心の内を語りつづけます。Yさんは,他者を客観的に見るのが難しく,極めて主観的に,主観世界を外界にある他者に投影して見てしまうのです。
これはまさしく乳幼児の世界で起こることです。それら幼いものたちと同じように,心の境界機能が極めて未発達なレベルに後退していると考えられます。幼いころに母親に甘えたかった心を剥奪されたと思われ,早々に自我が父親に取り入ったと想定されます。それによって幼い時代は,むしろ大人びたませた子であったかもしれません。そして,それに伴って情緒的な満足を求める心は,自我によって抑圧されたと思われます。それに相応して,自我の自律性は未発達に終わらざるを得なかったのではないでしょうか。
学生時代のある時期まで,Yさんは学業成績が優秀でした。そのころまでは父親の支配を受けているYさんの自我は,学校の成績を重視する父親との協調が出来ていたということだと思います。そして,子供とはいえない年齢にさしかかったころに,息切れがして,成績が振るわなくなりました。高校生のころに,Yさんは勉強をしなくなり,見た目には怠惰な生活をするようになったのです。自我の目覚めといったものでもあったのか,消極的ながら反抗の意識もあったようです。自我の自律性が問われる年頃になって,問題が表面化したということでしょう。
いずれにしても,父親の支配を受けてきた無気力な自我は,子供の時代のままの父子関係に耐えられなくなったのだと思います。とはいえ,自分の価値を自分自身で支える力がありません。反抗ということが親の自我の傀儡であることを意志的に拒否し,自己の独自性の宣言という意味であるとすれば,Yさんのそれは,曖昧なところがあったように思います。つまり自我が明瞭に無意識の分身たちと一体になろうとしたというよりは,その圧力に効し切れず,機能不全に陥ったという印象を受けます。その筋で見れば,父親の価値規範から見て失格という状況に立ち至ったということです。選んだ大学は,父親が望んでいる(と信じています。父親は,「そんなつもりはなかった」と否定しますが)’超一流’ではありませんでした。自己の主張の萌芽ともいえると思いますが,父親の期待に即せなかったことへの罪悪感も並大抵のものではなかったようです。’超一流’を目指すことをあきらめたのは,明快に反抗したというより,荷が重過ぎるという一面もあったのだろうと思います。それは単に学力的な問題という単純なものではなく,父親との関係の長年にわたる重圧に耐えられなくなったということでもあるのでしょう。
発病は結婚後のことです。それは結婚によって情緒的なものに触れたことと関係がありそうです。というのは,無意識界に潜んでいたと思われる情緒的なものへの欲求が活性化したと思われますが,Yさんの自我は,それを受け止めるだけの力がなかっただろうということです。自我がそれをできたのは,幼児的に退行すること,妻を母親に見立てることによってです。無意識下の欲求の強さは,乳幼児の貪欲なそれに等しいものだろうと想像されます。その分身たちの勢力に支配された自我は,客観的に妻を見る力はなく,分身たちの眼差しで,つまり投影によって妻を見ることになったのです。妻の受容的な人柄も,そういうものを助長させたのではないでしょうか。自我は,無意識の力に押されて,妻をほとんど母親と見立てたと思います。
退行せざるを得なかった弱い自我によって,自律と境界の機能においても幼児的に退行したと考えるのが妥当でしょう。従って,錯覚し,混乱してもいる退行した自我は,受容的な妻に対して感謝の気持ちを持つことはほとんどありません。むしろ当然のように,’わがままに甘える’ばかりです。
発病は,意識の姿勢が崩れるということでもあります。Yさんの自我は,もともとは情緒的なものを抑圧して父親と協調しようとするものでしたが,思春期にいたってその姿勢があやしくなり,結婚をしたことによって崩れたといえます。
崩れるということは一巻の終わりですが,新たな出発の始まりである可能性も秘めています。その破壊作業は,死につながる裏の自我の営為であると考えられますが,破壊の次に再生があるか,単なる崩壊かは,表の自我にどんな力が秘められているかにかかっているでしょう。
Yさんの自我は,少しずつですが,再構築の作業に取り組んでいます。その証拠に,最近はほとんど欠勤しなくなっており,同僚たちへの過度の恐怖も少なくなってきています。その背景には,妻の根気のいい支えと,会社の度量ある態度にも大いに助けられているということをつけ加えなければなりません。
自我の重要な機能のひとつは判断力です。未熟な自我は,自分ではどうすればいいのか分からないので,外部的な頼れるものに依存します。親や権力者や友人に依存します。
いま上げたYさんは,恐怖をもたらした父親に取り入り,依存しました。どこかミイラ取りがミイラになってしまった趣です。この過程で自我が主体性を保つことができていれば,何らかの判断が働いたことでしょう。判断の機能が生きていれば,その後のことに責任を持てます。ミイラ取りがミイラになることはないと思います。父親との関係で無気力なままでいる自我は,幼い子が母親にするように,外的なものに過度に依存するしかない状況に置かれているようです。
退行しているYさんには,妻が困っているのが理解できません。「どうして怒っているの?」と悲しそうに訊ね,すねるように黙り込んだりします。自分の気持ちでしか他人をはかれないのです。
ところで判断力は自我の機能として重要であるといいましたが,判断をするということは,当面している問題を,まずしっかりと受け止めるということが前提になります。その上で自立的に考えをめぐらし,一定の結論を出すということです。そのようなことですから,判断という心的活動を支えているのは,境界機能の’受け止める力’と自律機能であるといえます。これらの機能が,人間の心的活動には,基本的に重要であるのが分かると思います。
女子大生のIさんが,次のような夢を報告してくれました。Iさんはおかあさんが大好きなのですが,夢の中でそのおかあさんに追われ,殺されそうになったのです。
もちろん現実にはこういうことはあり得ません。夢の舞台でなぜこのようなことが起こっているのでしょうか。
Iさんの主訴は,パニック発作や人前での異常なほどの緊張でした。
この夢について,本人の連想から次のような意味が汲み取れました。
殺されるというのは,母親の望むように生きなければ見離される,そうすると自分は生きていけない,精神的に抹殺されるという恐れです。
実際の母親は,Iさんが必要な意見を臆せずいうようになったこともあって,最近ではあまり口出しをしません。しかし内心では何を望んでいるか,Iさんにはよく分かるような気がするのです。それは,やはり無視しがたい圧力になります。また,Iさんの場合,母親を取り込み内在化している度合いは人より強いといえます。その’内なる母’は,直接的にIさんの自我を監視しています。かつては傀儡自我といえるほどだったのが(パニック発作や,人前での過度の緊張の要因です。母親の仮想的な要求に完璧に即さなければならないという強迫観念と,ロボット化している自我による抑圧された怒りなどが,関与していたと思われます),このごろでは大分自由になったとはいえ,十分ではありません。このような内的状況で,自我の自由はしばしば脅威にさらされるということが,’母親に追われて殺されそうになるというふうに解釈できると思います。
Iさんはいわゆるよい子です。夢の舞台ででも,母親に対抗する怒りが見えていません。抑圧がずいぶん強いのでしょう。人前での過度の緊張は,侵入される恐怖だと思います。それは母親から侵入されてきた養育過程と,それに対抗するだけの自由な自我が育っていないこと,境界機能が不十分であることを意味していると思います。
母親の侵入,支配を受ける形の上に,母と子のあいだの強い依存関係が成り立っています。Iさんは知性的で,問題を理解する能力は基本的に高い人です。解決を要する基本的な問題への理解が進むにつれ,症状的なレベルのものはしだいに解消していきました。ということは,その分自我が力をつけてきているということです。事実,こういう夢を見て報告をする気になったのは,自我が成長した証です。診療に協力する姿勢の現われでもあると思います。
患者さんにとって無意識的だった問題を,治療者が感じ取って,タイミングよく解釈という形で還元してあげれば,患者さんの方では思いもよらぬ収穫を手にすることになります。それは患者さん自身が半ば気がついていたからこそ可能なのですが,本当に知ることには抵抗があったので,気がつかないままで済ませていたのです。治療者との信頼関係が進展すれば,自分の中の扱いが厄介だった問題を預ける気になれます。それに伴って抑圧して無意識だったものを,ようやく認める気になれるのです。
夢のこのメッセージに注意を向ける気になったのは,自我が,おそるおそるながら従来の母親への姿勢に懐疑を抱くようになったからですが,それでも,いままでの恐れが強力なので,自分が持っていた母親のイメージに異を唱えるのは,やはり容易ではないのです。
Iさんは薬をほとんど必要としなくなってきており,やめようと心に決めました。しかし,バイトに行くときなど,特別なときは服薬をしています。これが本人には問題なのです。薬は飲まないと決めた以上は,それをまっとうしたいのです。新たな混乱が生じました。
薬はやめるべきだということ,一度決めたことはまっとうしたいということは,母親への同一化を示しているようです。強迫的なこの不自由な思いは,’囚われている自我’の姿です。母親の思いとしては,Iさんが’心の弱い子’であってはならないのです。
「その葛藤は,お母さん的な考えから自由になっていないからですかね」という問いかけに,Iさんは,「そう思います」とすぐに肯定しました。そして実際に母親が,服薬を快く思っていないとつけ加えました。
母親の支配を受けているIさんの自我が,もがき苦しんでいるという様相です。
Iさんの心の世界と,Iさんが対処してきた様子を比喩的に述べると,次のようになります。
それぞれがそうであるように,Iさんは小舟の船長です。小舟には母親も乗っています。小舟は心の世界で,Iさんが自我です。小舟には他にも同船者がいますが,それらは常に姿が視界にあるわけではありません。しかし母親は絶えず視界の中にいます。それを考えると,母親は特別な同船者のようです。おそらく船長としてのIさんの腕前を信用してはいません。Iさんは母親が口を出さなくても,なにをいいたいか分かっています。常に傍にいるので一心同体も同然なのです。
海が荒れています。船長はパニックに陥りそうです。船長はまだ半人前の腕前なので自信がないのです。母親にどうしても頼りたくなります。いままで母親がいう通りに小舟を操ってきました。それなのに海の荒れ方がひどくなってきたのはどうしたことかと,分からなくなってきました。
このごろ少し分かってきたのは,自分の舟なのに,まるで母親自身が船長であるかのようになっているのと関係があるようだということです。そのために,知らず知らず荒れる海の方に舟を導いてしまっているのではないかと考えてみたのです。
しかし母親に舟から下りてもらうわけにはいきません。そんなことをいえば母親が怒るに決まっているし,下りられてしまえば舟をどう操ればいいのか見当がつきません。それで母親が眠っているときに,母親にいわれたことを無視して自分流にやってみることにしました。それなら危険な状態になったとしても母親に助けを求められるのです。いかしいざとなると動悸がします。それで病院で相談したときにもらった安定剤を利用してみました。医師がIさんの考えに賛成してくれたことも心の励みになります。薬を飲むと心が落ち着きます。しだいにそういうやり方に自信が出てきました。薬を飲むと安心することができ,自分が舟をどう操ればいいのか,落ち着いて考えることが多少はできます。
Iさんは友人達に,自分にパニック障害があるとはいえませんでした。うかつなことをいえば,自分がよほどおかしな人間であると思われるのではないか,彼女たちが遠ざかってしまうのではないかと恐れたのです。それはIさん自身がパニック障害という問題を,自分のこととして受け止めることができないでいることも意味しています。やがて彼女は,それはおかしいと気がつきました。それは辛い問題ではあっても,恥ずかしいこととはいえないと気づいたのです。思い切って友人たちに話してみたところ,彼女たちはあっさりと受け止めてくれました。理解し,共感してくれました。一番の問題ともいえることを友人たちと共有できたのは,大きな収穫でした。
これらのことは,自我の境界機能と自律機能の混乱と回復とを示しています。
あるとき,母親が口出しをしてきたときに,自分の意見をいえるようになりました。初めのうちは母親は怒っていました。それを見て恐れをなしたのも事実です。しかし,だんだん負けないようになりました。それにつれて,母親もむきになってIさんを服従させようとするのを控えるようになりました。一目置くようになったのです。
小舟に同船していたがる母親に,下りてもらう勇気はまだありません。一部は母親が可哀想だからです。Iさん自身が,独立した船長であるといえるだけの自信がついたとはいえないからでもあります。しかし,どういう問題があり,どうしなければならないかということは理解ができていると思っています。
小舟の運命は,船長にかかっています。どうしたらよいのか分からずに,右往左往しているようでは舟を守れません。ともかくも船長の自覚を持ち,船長としての仕事をすることです。自分のためによいと思うことを考え,それを実行に移すべく判断をすることが求められています。それが間違いであると気がつくこともあるでしょう。それはそれでいいのです。判断をすることが,船長が仕事をしたことになるのです。そうすれば責任を取れます。次にどうすればいいのかが見えてきます。
この舟の船長は私である,母親は相談の相手ではあっても,最終判断を下すのは船長である私だという自覚を持つことが大切です。
診療への協力云々ということを書きましたが,診療のために通っている現実があるのに,変ないい方だと思えたかもしれません。それは患者さんの側に,一般的に治療への抵抗が潜んでいるといえるからです。そのために,場合によっては,治療が成功するのを阻む無意識の心の動きさえあり得るのです。
ある人が次のようにいっておりました。
3ヶ月で治る・・・と書いてある本を見た。私は良くなっているのだろうかと疑問を持った。もしかして私は治りたくないのかもしれない。治るとお母さんが心配しなくなると思う・・・。
このように’心の病気’にはコミュニケーションの一つの形という面があります。自我が解決できないでいる問題を,病気が部分的に救う面があるのです。疾病利得といわれているのは,そういう意味です。’自爆テロ’と呼んだ人がありました。自宅で暴れたことや,薬の過量服用を指しているのですが,言葉でいくらいっても通じない両親への暴力的なアピールという意味です。
自我が無力である状態が長くつづいているとき,身体が答えを出してしまうことがあります。たとえば過眠症にはそういう意味があります。学校や会社に行きたくないときなどに,それを解決するのが自我の役目です。(自我が)判断をするという形が必要ですが,それをせずに気分まかせにしておくと,身体が答えを出してしまうのです。自我が責任を取らずに回避しているという図になるといっていいでしょう。
メラニー・クラインが,羨望の心理の強い患者さんの中には,治療者の成功を妬み,治療の成功を妨害する心理力動が見られると述べております。
患者さんは,誰にも話せないでいる自分の問題を,治療者であるがために打ち明ける気になれます。しかしそれも程度の問題です。意識的にもさることながら,本人にも気がつかないレベルで重要な問題を隠蔽してしまうのは,なんら不思議なことではありません。治療関係の信頼度には,現実にはさまざまな程度があるのはいうまでもありません。治療者の能力に足りないものがあれば,患者さんの方で,ある程度以上のものを打ち明ける気にはなれないでしょう。
相手が誰であれ,自分の心をさらけ出すに値しないという心を誇りにしている人もあります。それでも一般には,自分が理解されたい,心の地獄絵を解決に導きたいという心があるからこそ通院するのに違いありません。例外的には,心の回復をほとんど信じていないで,治療者に対する何らかの悪意から通院する場合もあり得ると思いますが。
心の根底に絶望的なものがあるからこその心の障害です。そうであるからこそ,治療者がその難解なものを解決する能力を持っているかどうか,容易には疑問を拭えないと思います。治療妨害,治療抵抗の一面は,治療者の力量をテストする心の動きともいえるでしょう。
治療者は,そうした治療的な難問をかかえていると感じられる患者さんを,自分の手に負えるかどうか判断しなければなりません。その上で引き受けることになった場合は,さまざまなレベルの治療抵抗を,むしろ治療的な手がかりにできるかどうかが鍵を握るでしょう。一つ一つそれらの関門を克服していくのは,心の治療そのものです。
自我は無意識の心に依存しつつ,なおかつ自立した,主体的な存在であることが求められています。実質的に,心全体の主体は,内なる自然である無意識に,言葉を換えれば内在する主体にあります。しかし自然界のものである主体自身は,人生を直接生きることはありません。その役割は自我に与えられているのです。
無意識の上層部は,人為的な手が加わることによって混乱させられた自然界であるといえるかと思います。その混乱の責任は自我にあり,しかし自我にはありません。自我が未熟すぎて,責任の取りようがない時代の話におよぶものがあるからです。その上で自我の責任において,これらの人為的に混乱させられた自然を,元の自然へ回復させる作業をしなければなりません。それは主体との関係を確立する方向で進められなければならないと思います。その作業が首尾よく進んでいるかどうかは,心の全体が充実し,豊かになっていく感覚が答えになると思います。
自我の機能は,便宜上三つに分けることができます。一つは自由な機能,一つは社会的な機能,一つは非社会的な機能です。
自由な機能は,なにものにも囚われない高度な自我のものです。この機能が活発なときは,内在する主体との関係がしっかりしているので,自分の価値を信じることができています。それだけに他者への依存から理想的に自由になっています。これが健全に機能しているときに,内外の状況に主体的,自立的に柔軟な対応ができるのです。自我は一個の組織体ですが,自由な機能は組織体を改善していく上で重要なものです。
非日常的な状況に置かれたとき,自由な機能の発動が必要になります。一例を挙げれば次のようになります。
小学校の一年生が交差点で信号を待っているとき,幼児が車道に入ったとします。小学生は先生に,「赤信号では止まりましょう」と教えられています。一年生はどうするでしょうか。
法規を守って信号で立ち止まるのが,社会的な機能に依ってということになります。幼児が車道に出たとき,とっさに車道に飛び出して(法規を無視する)幼児をたすけようとするのが,自由な機能の発動ということになります。
社会的な機能は,主に日常の行動に関するものです。いちいち考えながら行動するのでは,ぎくしゃくして,日常生活が円滑に営まれないでしょう。人間関係もぎこちないものになります。無駄なエネルギーを使うことになり,疲れもします。そういうことがないように,日常の生活行動は,組織的,自動的に行われるのが望ましいのです。またこの機能には,その人の社会的な顔という側面もあります。
非社会的な機能は,上にあげた二つの機能が固化して不全状態に陥ったときのものです。生活状況のストレスが耐え難いほどに感じられ,人間関係にうまく対応できないでいると,このレベルに後退する場合が出てきます。身を守るために人を避け,いわゆる引きこもりの生活に入ることになります。このレベルになると無意識の影響をつよく受けるようになります。心の沼の勢力が大きくなっているので過敏になり,ストレスを受け易くなります。それが活性化しないように刺激を避ける必要があり,他人との関係を遮断する方向に向かいます。
自我の以上の区分は,いうまでもなく便宜上のものです。実際には非社会的な機能といい,社会的な機能といっても固定的なものではなく相互に移行する関係にあります。それら自由な機能の下位にあるものは,日常の思考や行動をパターン化し,それぞれの個人の特徴を表すものです。そして自由な機能が随時,それらの下位の自我の営為を監視し,修正する指令を発します。自由の機能が活発であるときは,内在する自我との関係が望ましい状況にあり,自我は与えられているエネルギーを十分に駆使することができます。
自由な自我は,内在する主体との関係が保たれているかぎりにおいて機能すると考えられます。主体は超人間的な存在であり,自我は人間に固有のものです。両者が自我の機構において接点を持ち,主体の意志を自我が人間的に変換して一定の指令を発すると仮定的に考えることができるように思われます。そのかぎりでは人間の力の源泉が主体にあり,かつ無限な可能性が秘められているともいえるように思われます。人間の可能性が無限であるという感覚がなければ,人生はすべて自我の範疇に収まることになり,閉塞球の中に閉じ込められた存在であるしかありません。人間の有限性は現実問題ですけれど,不可知な無限感覚もまた人間のものです。
非社会的な機能に陥っている自我は,自由な自我の機能がほとんど見られなくなった心的環境に自己を置きますが,この状況では内在する主体の意志は,自我を通じて人間的に有意味のメッセージを伝えることができません。エネルギー的にも枯渇する自我である非社会的なそれは,生きる意味を紡ぎ出す根拠を欠いているに等しいといえるようです。
また,この自由の自我の活況如何が,自己感を表すと考えられるように思われます。
自我を騎手に,騎手がまたがる馬を無意識にたとえてみると,自由な機能が健全に働いているとき,両者の関係は良好です。そのとき騎手は馬の力を巧みに引き出して,いわば人馬一体の状況にあるといえます。馬である無意識には,内在する主体が存在します。賢明な騎手は,その意向を探り当てることができているといえます。
これに対して非社会的な機能のところまで後退するとき,騎手がまたがっている馬は気まぐれで,しばしば不機嫌です。おまけに騎手は自分の力を信じていないので,人生行路が二重に難しくなるのです。このとき騎手は,自分がどこへ行こうとしているのか,なにをすればいいのか見当がつきません。いわば馬まかせになってしまいます。自我の主体性は発揮されず,主従の関係は逆転してしまいます。
馬が不機嫌なのは,自我が自分の役割をきちんと果たしていないからと考えるべきです。
すべては主体との関係に帰着します。その関係に問題があれば,いわば自分の筋を離れて迷子になってしまいます。自分がなんだか分からないという気持ちに悩まされることになります。
状況に応じて,自我の様態は変化します。自由自我が健全であれば,状況に柔軟に対応できるので,人間性がますます豊かになっていくと思います。しかしそうでなければ,悪い形のさまざまなものに依存します。
非社会的なところまで自我が後退している状況では,自我は無力化し,それに反比例して裏の自我が勢力を拡大するという事態になります。強いエネルギーを蓄えた内向する怒りが,長期的に滞留することになります。主体性を失った自我は傀儡化され,いわば裏の自我の虜になってしまいます。裏の自我に率いられる無意識界の勢力は,いつしか悪魔的,破壊的な彩りを深めていくかもしれません。
人間が犯罪者になっていくのは,そうした心の変質が起こってのことだと思います。アルコールで身を滅ぼしていく姿も然りです。過食症者が過食にふけっているときも,拒食症者が命の危険を省みないのも同様です。そこには悪魔的な心に捉えられ,引きずられていく様相が表れていると思います。 拒食症の患者さんが,夢の報告をしてくれました。
暗い道を通って家に帰ると,見知らぬ中年男が来て,荷物を差し出す。「これはあなたのものだ」という。荷物を開いて中身を見ると,ミイラ化した死体が入っている。「これは私のではない」という。相手は自分の主張を繰り返し,私はむきになって否定する。
むきになるのは確かに変だ,自分のものでなければむきになることはないですからと,夢の報告者はいいます。
いうまでもなくミイラ化した死体は,患者さん自身でしょう。やせることに囚われていると,こういう結末が来るだろうということ,あるいは心が身体を否定しようとするかのような行為は,既に精神的な死をもたらしているということ,そういう意味が見て取れるように思います。
では荷物を突きつける見知らぬ男はどういう素性の者でしょうか?彼は実際には見たことのない男です。現実の人物ではないらしいということは,無意識の世界から浮上してきた,なんらかの使命を帯びた不気味な者と考えられると思います。死を予告する冥界からの悪魔的な使者のようでもあります。 患者さんがあくまでも受け取りを拒めば,使者は冥界にいざなう役目を帯びてやって来た危険なものの姿を剥き出しにするかもしれません。しかし荷物を自分の物と認め,受け止めれば,その危険を回避するのを助ける使命を帯びてやって来た者ということになるでしょう。
荷物の受け取りを拒んだ前者は,自我が機能しなかったことを,受け取った後者は,機能したことを意味します。
夢を見た人の受け取り方一つで,夢の意味が変わり,次に見る夢に影響を与えます。夢は無意識の世界にある意味を伝達する機能を持つことがあるので,それを正しく受け止めることができれば,それ自体が自我の力の証明になります。提出された問題を受け止めることは,常に重要な意味を持ちます。それは心の世界全体が好ましく変容していく上で欠かせないことです。
Updated 07/10/06
性格形成に与える母親の影響-その8
■終章
「院内通信」の当初の目的は,摂食障害の外国の症例に即して,私がこの問題をどう考えるかを提示することでした。そうすることで,診療を受けていただいている皆さまに少しでも益するものがあればよいと考えていました。ですから当初は,パンフレットの類の簡単な解説文のようなものを念頭に置いていたと思います。しかし始めてみると,簡単には済まないことになってしまいました。というのも,少し考えればいうまでもないことですが,改めて思い至ったのは,心の問題は大変に複雑で,奥が深く,我々のような専門的な立場にある者にとっても,容易に扱えるものではないことです。
心の問題は人間存在そのものに関わります。心の病気はそのことと無縁であるはずがありません。従って心の病気を考えるに当たっても,人間存在の全体を視野に置かなければ,「群盲象を評す」の喩えのとおりになってしまいます。
考えてみれば,いかなる場合でも「簡単な解説」というのはむしろ難しい作業です。その問題に精通している上位者でなければできないことです。
学問一般についてみると,問うものと問われるものとはひとまず分離しています。つまり研究者が,外在化されている何らかの対象について問いを立てます。どの研究分野であれ,学問的に解明されつくすという事態はほとんど考えられないことなので,誰が第一人者かというのはそう簡単な問題ではありません。しかし一般論でいえば人間の営為には違いないので,ある研究領域に最も精通している人といういい方は可能です。人間の営為というのは,問う者としての人は,問われている事象の外部に位置しているという体裁の下での行為という意味です。この体裁の下では,人は,問われている事象に対して,それらの全体を知ることが可能であるという原則の上に立っていることになります。
ところが人間が人間自身を問う場合,誰が上位者かという問いには,これとは別種の困難があります。
この場合は,問う者としての人は,問われているものの外部に位置していません。喩えていえば,自分の尻尾を噛んでいるウロポロスの蛇のように,問題に食らいついても,終わりのない円環から抜け出せないことになりかねません。つまりウロポロスの尻尾をつかもうとするのがウロポロスの頭であれば,出口のない迷路をさまようだけということにもなるのです。
かつて哲学者のソクラテスが,彼の信奉者が受けた「ソクラテスより賢い者はいない」という神託の真意を知りたいと考えました。彼は,人間が人間らしく生きるためには,その根本知が必要であるが,自分はそのことに関して無知であると自覚していました。当時のアテナイ市民は,成人はすべて立派な市民であるための徳を身につけていなければならないと考えていました。その徳は人間社会が作り出した規範的なもので,その意味ではソクラテスは,いうならば落ちこぼれでした。神託を受けてソクラテスは,当時の知者として名高い者を尋ね歩き,彼らの考える徳についての根拠である知を問い質しました。結論的には,ソクラテスの反問によって,彼らの全てが空虚な知にしがみついていたに過ぎないことが暴露されただけでした。それでソクラテスは,神託の意味する賢者とは,「無知であるのを自覚している者」ということであり,真の知者は神のみであるという結論を得ました。
この例は,人間の上位者は存在するかという問いに対する一つの答えを提示しています。つまり人間の問題を熟知している人間はあり得ない,人間の問題に関するかぎり,敢て上位者を名指しするなら神とでもいうしかないということになるかと思います。
ですから,心の問題を語ることは根本的に難解です。そういう事情を考えれば,心の病気についての「簡単な解説」などというのは初めから無謀なことでした。
とはいえ,心の病気の専門家はいますし,私もその端くれの一人です。この問題は難解すぎて何も分からないというのでは,笑い話になりかねません。ともかくもそういう仕事をしているのですから,責任もあります。それで,一旦始めた以上は止めるわけにはいかないのですが,私にできるのは,日ごろの診療を省みて,そこから意味がある(と思われる)糸筋を慎重に引き出してみることのように思われます。そういう思いで作業を試みているうちに,いつしか自己研鑽の場になっていきました。それを「院内通信」という形のままで敢えて残したのは,一つには私に関わりを持たれた方に私の考えをお伝えしたいということです。そしてもう一つには,どなたが読んだとしても読むに値するものでなければ意味がないので,公開という形で一定の緊張の持続が保たれるだろうと考えたことです。
気になるところを直し直ししているうちに,思いのほかに大きくなってしまいました。それどころか永遠の工事現場のような気配で,これでお終いということがないだろうという果てしもないことになっております。
また当初の’M子さんの症例’に即するつもりが,まったく変化してしまいました。自己研鑽ということですから,症例の検討が欠かせません。症例を通じて浮かび上がって来るものを,可能なかぎり論理の糸で繋いでいくのが生命線といえます。症例を記載するに当たっては,ご迷惑をお掛けしないように出来るだけの配慮をしているとはいえ,全くの作り物では客観性という観点からあやふやなものになると考えますので,どうしてもご本人の目に入れば自分のことだと分かると思います。そこで最も怖れたのは,不快感を持たれたり,抗議を受けたりすることです。いちいち予め了解をいただくのが筋ですが,それは大切とは承知していても,なにせ多数にわたり,全ての方のご了解をいただくのは現実的ではありませんでした。ご本人が読まれたとしてもご不快のないようにという姿勢には注意しました。ご本人から,「読んだ」といわれたことも少なくありませんが,幸いにして抗議の類はいまのところ一件もありません。
ここに上げる症例は,いうまでもなく興味本位ではなく,あくまでも問題を掘り下げて一般化していくための素材です。私自身の自己研鑽という意味があるものの,患者の皆さまに益するものと信じて作業を続けています。何かご不快があればお話いただきたくお願いいたしますが,趣旨をご理解いただけると有り難いことです。
いま述べたように,心の病気の問題は人間存在そのものと切り離すことができません。従って,問題の捉え方が人によって異なり,一様ではないのが当然といえます。
医学は自然科学の方法論で進歩,発展してきました。心の病気も医学の一分野ですが,自然科学をそのまま適用できるものではありません。自然科学は’物’を扱う方法論で,’生きている全体’から不透明なものを排除して,意識の光が隈なく行き渡るように物を純化していくことで成り立つものです。その方法は厳密で,科学であることの見本ではあります。心の科学も科学であるからは,それを手本にする必要があります。その際,取り分けて難点になるのは,心には無意識の世界があるという問題です。自然科学が隈なく意識の光を当てていくことであるという原理からすると,意識の光を当てることは不可能であればこその無意識に対して,自然科学は全く歯が立たないことになります。
それにしても無意識の世界があると分かる(意識できる)のは何故でしょうか?
その答えは,(自我に拠る)意識の世界が有限であるということです。つまり有限の世界があるということは,無限の世界があることが前提となって可能なのです。無意識の世界とは,自我の光が届かない心の領域があるということであり,その存在は自明であるといえます。
このことを定立化していえば,「無限の世界は存在する。心に関しては無意識の領域が無限の世界である。その存在は自明である。しかしその存在様態を意識が捉えるのは不可能である」ということになります。
あらゆる対象は意識に映じるかぎりで存在しています。つまりあらゆる対象は,現象として存在するのです。それが自我に拠って意識と共にある人間の実相です。たとえ物理学の対象が’純化された物’であるとしても,意識に映じているかぎりの存在(現象的存在)であることに変わりがありません。換言すると,「純粋の物とは何か」という類の問いは,人間にとっては何のことか分からないのです。そして客観性の保証は,我々が意識が正常であるかぎりは,誰もが同一の体験が可能であるというところにあります。物理学的に’純化された物’の純粋性は,意識が正常な者なら,万人がその対象についての体験を等しく共有できるのは勿論のこと,因果律という純粋論理として定式化が可能であるというところにあります。それは当の対象を見ている科学者の眼から,無意識的心を徹底排除することで成り立つものでもあります。対象に意識の光が隈なくおよぶというのは,そういう心の動きがあって可能なのです。
ところで心を自然科学者の真似をして捉えようとするとき,心のいたるところに無意識が入り込んでいるのが難点になります。
例えば100メートルの競争という単純な行為であっても,無意識が入り込んでいるのです。この競技の新記録の限界値をいい当てることができる科学者はいないでしょう。誰であれ5秒以内で走るのは無理だと思うでしょう。限界があるのは明らかなのです。しかし具体的な数字で予想するのは不可能です。現在の新記録は少しずつ破られていくに違いありません。つまり,意識の光が隈なくおよび,この問題に最終決着が与えられることはあり得ないでしょう。仮にそれが可能であるとすると,100メートルの新記録を狙う者などいなくなるでしょう。競争をすること自体がばかばかしいことになるに違いありません。無意識という無限定なものがあるからこそ,人間は絶えず目標を持ち,挑戦的に生きていけるのです。
このように自然科学者の思い通りにならないことが,この世を生きていく上で大切なことであるという皮肉が,学問的にはある意味では人間を悩ませます。この場合,「群盲象を評す」という喩えに即してみると,群盲は自然科学者であり,象は無限的なもの(無意識)ということになります。それで心を科学的に見ていく上で,自然科学の手法に見習いながらも,群盲であることから脱する試みが求められます。そのためには,心の全体を俯瞰する立場を求めなければなりません。それはどうしても心の上位者の措定という問題にならないわけにはいきません。
そういうことをふまえて,心の科学が自然科学者の真似をしようとすれば,意識が捉えることができたものを里程標のようにみなし,それらを繋ぎ合わせていくことになります。心の病気の場合,患者さんが苦痛な体験を語る言葉が里程標ということですが,さまざまな患者さんがさまざまな表現をするので,それらをどう解釈するかはそれぞれの治療者が自分の心に意識の光を当ててみる作業が不可欠です。確かなことがいえるとすれば,この作業を通じてです。そしてそれを再び患者さんの語るところとつき合わせて整合性を図るのです。それでも心の問題ですから不確かさが絶えず残るでしょう。継続的に患者さんの言葉に耳を傾けて訂正したり,確信したりすることになりますが,洞察が深ければ,そういう過程で旧来の確信がそのまま残ることになります。そして決定的に重要なのは,得られたものが治療の上に反映され,有効性が確かめられることです。
心についてのこうした作業を難しくもさせ,意味深くもさせているのは,心の内なる無意識の問題があればこそです。心という生きている人間の全体に関わるもののいたるところにあり,生きていることの源泉でもあるのが無意識です。これを避けて心を語ることはできません。その上に無意識の問題を語るとき,自然科学者の手法を借りて,可能なかぎりの科学的客観性を確保しなければなりません。科学的な説得性が内包されていなければ意味を持ちません。しかしながら無意識という海であるが故に,里程標はいたって不確かです。そういう状況でのこの作業では,人為的な里程標を打ち込んでいくしかありません。
その作業は以下のようになります。
現象世界に現れている心的事象を理解しようとするときに,無意識の世界の存在様態を知る必要がどうしても出てきます。しかし実際にはそれを確かめる手がかりが希薄なので,日常の現象的な実在になぞらえて,比喩的に,仮定的に命名し,仮に実在させる必要が生じます。それは我々が知りたいと考えている現象世界に生じている謎に,仮説を建てることで自然科学者に準じようとする作業と考えることができます。それらの仮説は,自然科学者がするようには実証する術がありません。それらは永遠に仮説の域を出ることはありませんが,是非とも知りたいと考えている現象的事実の謎に対して,それなりに首肯させる力を内包させていれば,ひとまずの収穫というべきです。そしてそれ以外には打つ手がないのです。
それらの仮定的な里程標の中で,最大のものが心の上位者の措定です。それを内在する主体と,ここでは呼んでおきます。内在する主体は,心的世界の,あるいは一切の現象的世界を統括するものです。また,自我がどのように自己を導けばよいのかを知っている唯一者です。自我は精神活動の中枢に位置します。換言すると精神活動の頭にあたります。そして精神活動が生じているかぎりは,いわば足となるものの力を借りなければなりません。それは主体が送り出してくる欲動といわれているものです。いわば神の子(白い子)を護りとおすことにより,自我は主体の意向を自ずから尊重し,実践する意味を持つと考えられます。
病的な心理現象を扱う上で,以上の仮説を掲げることの有効性は,心を悩ませている患者さんの大方に,いかに理解され,共感されるかにかかっています。そしてそれらの説明は,少なくはない患者さんの共感と理解とが得られており,自分を悩ませている問題への理解が進むことに伴って,かなりの治療的効果が認められています。
以上のことを前提として,私が描いている心の見取り図は,以下のようになります。
心には二つの中心があります。
C.Gユングは自我を意識の中心と呼び,自己(セルフ)をこころ全体(意識と無意識)の中心と呼んでいます。
自我は(人間的な)世界を切り開いていく拠り所であり,(現実的な)精神活動の一切の中心です。人間の活動には,いかに身体的なものであれ,精神性の関与をまったく欠いているものはないといえるでしょう。仮にあるとすれば,自我の機構に何らかの故障が生じたときです。このことは,裁判で責任能力が問われるのと関係があります。心神喪失と認定されるときには,自我機構の決定的な不具合が生じているのです。
摂食障害やアルコール依存など,依存症といわれるものが病的であるゆえんは,その行動に溺れながら精神性の欠落感に苦しむところにあります。苦しんでいるくらいですから,精神的に満たされることへの渇望があり,しかしそれが適えられる希望がまるで見えないのです。それは自我の機構的な不具合ではなく,自我が機能不全に陥っている姿です。
自我が超自我と無意識界にある分身たち(黒い子たち)から自由であり,自立しているかぎり,精神は健全です。そして自我が機能不全に陥っているときには,超自我が自我の上位に立ち,黒い子たちもそれに連動して自我の上位に立っています。それらの勢力の狭間に埋没する自我は,著しい苦境に置かれることになります。
このように自我が機能不全化するのは,次のような過程があってのことであろうと思われます。
幼い時代には,心にさまざまな欲求が生まれてきます。それらはすべて大切に扱わなければなりません。例えば2歳の子であれば,遊びに行った友達の家の玩具を黙って持ち帰ることもあるかもしれません。2歳の子がしたことであれば,それを泥棒と呼ぶ者はいないでしょう。しかし5歳の子が同じことをすると問題になります。だからといって2歳の子のそうした行動は咎められるべきではありません。むしろそうした行動は自然のことであると捉え,その上で事の善悪を教えていかなかればなりません。生まれてきた欲求自体は善悪の問題ではなく,自然のものです。その上で人が成長していくには,他人との関係を教える必要があります。善悪の問題は他者との関係が前提になって問題化するのです。他者との関係は,内なる他者として自我の機構に内在していると思われ,親が子に善悪の問題を教えるのは,そういう前提があってのことで,親の恣意による教育というわけにはいきません。
他者との関係を自我が課題化することにより,心は社会性と精神性を獲得していくことになります。それは人の心が豊かになっていくための要点になります。
他者との関係は決定的に重要な意味を持ちますが,無意識の自然から生起してくる白い子たちを,自我が護れなくなる理由になります。他者との関係において,白い子を自我がいかに護っていくかが問われることになり,そのことを教えてくれる立場の中心にあるのが,父親と母親です。しかし彼らは部分的に正しく,部分的に間違っているのが一般です。すべて正しい親はあり得ません。
親の指導が間違っているときに,子供の自我は白い子の扱いに失敗して,黒い子にしてしまいます。
親の指導は,正しいことも間違っていることもひっくるめて,子供の心に主観的に取り込まれ,一定のイメージとして内在化します。これが,超自我と呼ばれている自我の後見人ということになります。一方,自我が護ることができなかった黒い子たちも,心の一角を占めることになります。
心はこのように自我を中心として超自我と影の分身といえる黒い子たちによって,そして心の最奥に在る主体とによって構成されます。超自我と影の分身たちとは半ば無意識の世界にあり,主体は完全な無意識の世界のもので,我々にはその存在様態は知る術がありません。
そのような構成の中で,自我が自由と自立性とを保っているときには,主体との関係はうまくいっていると考えられます。このことを見方を換えて説明すると,以下のようになります。
自我が何かの行為を主導するときに(精神活動が営まれるときに),主体が行為の足となる白い子(神の子)を送り出してきます。その白い子を自我が護りとおせば,白い子が抱えていたエネルギーは自我に渡され,活力が高まります。それは主体のおめがねに叶ったことを意味するでしょう。
逆に親との関係で,幼い自我が白い子を護ることが出来なかったときに,白い子は怒りと共に黒い子に変化します。神の子は,一転して,いわば悪魔の手先に変わることになります。
白い子の中でも,取り分け甘える欲求が封じられる何らかの事情があるときに,この問題が重大化するでしょう。その欲求は強力なエネルギーをはらみ,諸欲求を満たす基礎ともなるものです。それだけに,それを封じる力を持つことができたのは,根源的な恐怖だけであろうと考えるべきです。
こういう状況では自我は怒りを抑圧しつづけることになります。抑圧された怒りは黒い子と共にあり,それは超自我とも連動します。いわば黒い子をおびただしく作るような自我に対しては,超自我も怒りを持つともいえます。怒りのエネルギーの蓄積が大きくなると,超自我は優しさを減じ,命令的で懲罰的になります。いわば怒れる後見人になります。自我は相対的に地盤の沈下を来たし,超自我と影の分身たちとが上位に立ちます。自我は物いえぬものとなり,絶えず超自我に威嚇され,責め立てられ,黒い子達の嘲りを受け,という事態になります。
(例えば強迫性障害といわれている病理的な現象では,とりわけ超自我は苛烈な懲罰者の姿を表しているように見えます。超自我は自我に,安全の完璧な確認を求めるかのごとくです。完全性を求められても応える術がないのが人間ですから,自我は確認行為という完璧の真似をしてみせることになります。それは内容を欠いた悲痛な演技のようであり,儀式以上の意味を持ちません。それは超自我の苛烈な要求に従って見せているようであり,懲罰を受けている姿のようでもあります)
自我に拠る世界は光の世界です。精神の活動には,無意識という暗闇のものの関与がさまざまにあるので,陰翳の彩りがありますが,自我の機能が活発なかぎりは光の強さは強力です。それは比喩的にいえば,無意識という暗黒は無限大の広がりがあると想像されるので,これを暗黒の宇宙とすると,自我はその宇宙に浮かぶ一片の星です。その星は,包囲している暗黒の無限からすると,いまにも呑み込まれてしまいそうな頼りない存在に見えます。しかし星が力強く光を放っているかぎり,圧倒的な闇は存在しないかのようです。そして闇の力をいずれ知らされることになります。一つには心の何らかの病のときに,そして決定的には死期が近づいたときに。
この光が満ちているとき,自我は一切の上に立つ勢いがあります。それは自然科学が大掛かりに実践してみせてくれました。自然科学の勝利は,自我に拠る人類の勝利です。人は光をもとめ,光の世界を切り開いて行くものなので,そのかぎりで自我は最上位のものです。そして心の内部の暗黒を探るのも,自我です。しかしこの世界を隈なく光で満たすのが不可能であるのは,最初から誰にも分かることです。自我には手に負えないものが確実にあると認めるしかありません。
自我の活動に限界があるのが明らかであるように,自我が存在している理由そのものも不可知の闇に包まれています。自我は自我自身を知ることはできません。
自我が我々が知ることができない事情によって,自らの存在を自らに与えるべく意志したのかもしれないと考える人があるでしょうか。あるいは自我が存在するのは単なる偶然だという人がいるでしょうか。あるいは自然のサイクルの中の説明できないいきさつがあってのことだという人があるでしょうか。そしていつか人間の科学する力が,それらの謎を解き明かす時が来ると信じている人があるでしょうか。
いっそのこと,人間が存在しているのは神の意志によるというふうに考える人はいないでしょうか。合理主義精神が隅々まで行き渡っている現代において,神の問題はどこかタブーの趣があります。信仰を持っている人たちは,仲間内ではともかく,どこか肩身が狭そうにしているように見えます。ですからこういうことを考える人がいるとしても,滅多には口に出せない時代的な雰囲気があると思います。実際,神が云々といい出せば,たいていは一笑にふされるだけでしょう。
しかし私にいわせれば,以上に挙げたどれもが五十歩百歩です。合理主義精神は自我の責任範囲に関しては有意味ですが,自我は無意識という海に浮かぶ小舟のような存在なので,無意識の世界のことを自我がどう捉えるかは手に余るとはいえ,そこを無視すると精神が干からびてしまいます。それなりに捉える工夫はむしろ欠かせないはずです。
そんな人はいるとも思えないのですが,人間の存在理由を科学的に証明できると信じている人がいるとすれば,それこそ笑いものという気がします。
自我が人間の心の最上位者ではあり得ないのは,厳然たる事実として認めるしかないはずです。言葉を換えれば,光のものである自我の力が及び得ないものがあるのは,改めていうのも気が引けるほどに明証的です。その最上位にあるものをどのように命名するかは,あまり問題ではありません。自我の存在が単なる偶然であるといってみたところで,それで何かを証明したことになるわけではありません。我々には何か分からない理由があるといっているのと同じことです。
我々には理解し得ないものがある,自我の存在理由もその一つであるというのは明証的なものであるにもかかわらず,それを敢えて認めようとしないことが,自然科学の影響に置かれている現代の迷妄というべきではないでしょうか。科学の言葉で捉えることができないという理由から,自我の上位にあるものの存在を認めないことに,どんな意味があるのでしょうか。
ここではこの最上位にあるものを,内在する主体と呼んでおきます。それは自我の光が届かない無意識の世界の最奥にあるものと,仮定的に里程標を打っておきます。
我々が知り得ない理由によって自我がもたらされ,人間の存在が可能になったと考えることに,何か重大な見当違いがあるでしょうか?
そのように考えると,自我の最も大きな使命は,引き受ける精神です。
私は以上のことの恰好の実例をソクラテスに見ます。
ソクラテスは神の助手を自認し,公言していました。つまり神の意志を引き受けることに最大の使命感を持った人のようです。彼の時代のアテナイ市民は,合理主義精神に活路を見出し,活気づいていましたから,ソクラテスが奇妙な神(ソクラテス自身が,「子供のときから鬼人の類からの合図があった」といい,ぶつぶつ独り言をいいながら心内の声に聞き入っていたといいます)を信奉し,世を惑わすことは,為政者には看過し難いことでした。彼は為政者などの権力者に媚びないという点で,傲慢な人物と見られました。彼は誰が何といおうと,自ら信じていること(神の助手としての勤め)を実行しつづけました。
権力者たちの前では傲慢だった彼は,神の前では敬虔であり,あくまでも謙遜であったといえるようです。それは彼が人間である自分の上位者の存在を認めていたからです。彼は神の声に一心に聞き入り,その意志を引き受けようとした人のように思われます。
自分の上位者を持たない者は謙遜である根本理由を欠きます。そして謙遜とは,人間の最も崇高な精神の一つだと私は思います。
自我を最上位に置く自然科学は,干からびた威力をもたらします。それは大きな仕事を成し遂げてきた一方で,救い難い傲慢の罪を犯してきたともいわなければならないようです。
魂に潤いを与えるのは無意識の力です。その力を自然科学が,自分の上位に置くことができていれば,人類はまったく別様の文明を持ったに違いありません。
ソクラテスが心内の声に聞き入っていたといわれますが,その声の主こそが内在する主体であると,私には思われます。このことは,C.Gユングが述べていることとも符号します。
彼は次のように述べています。
「いま自分(の心)に起こっているのは何か教えてほしいと,心内のアニマに向けて問いかけた。問いかけるその姿勢が不確かであれば,反応はいい加減なものだった。しかし真剣になればなるほど,意味深い反応があった・・・」
自我の役割の最大のものは,引き受ける精神だと思います。引き受けるというのは,ソクラテス流にいえば,’神の意志’をです。ここでは主体の意志をということになります。ソクラテスやユングのように,心の内奥に在る主体の声に聞き入ることが必要です。自己を形成するというのは,主体の意志を実践することであると考えることができます。主体は,自我がどのように人生を切り開き,自己の達成に向けて導く働きをしているか,沈黙のうちに見守っていると考えられるのです。
実際にどうすればそれが可能かというのが問題です。
このことの仮定的な考えの一つは以下のようです。
自我のエネルギーは自我の位置を保つためのものと考えられます。自我は心の司令塔の役割を担っています。いわば心の頭であり,行動を実践する力は持っていません。何か行為(行動)をするときに,自我は計画(目標)を立てます。それを実践するためには自我のほかに,行為の足となるものの協力が必要になります。
日常の精神活動は,その眼で見てみると,個々に何らかの目的を持った行為(行動)群から成り立っているのが分かると思います。それらの個々の行為(行動)について,自我は自動的に無意識に呼びかけると考えることができます。それに応じて主体が行為の足となるものを送り出してきます。それはいわば神の子です。自然から生まれてきたばかりの無垢の子(白い子)です。自我は必要があって呼び出したのですし,行為の欠かせないパートナーであり,無垢であるが故に傷つき易くもある白い子をしっかりと護りとおすことが大切です。何せ神の子ですから丁重に扱わなければならないということでもあります。
スポーツ選手や囲碁などの勝負師,あるいは思索している人,研究に打ち込んでいる人などが,心の集中に極力努めているのは,自我が白い子との協働作業に没頭しようとしている姿です。
我々はすべての行為(行動)をまっとうできるわけではありません。言葉を換えれば常に神の子を護ることは不可能です。それは人間が,動物的な自然を生きるのではないことに伴うものです。そういう意味では,刻々と黒い子を生み出しているとも考えられます。しかし行為の価値には軽重があります。それぞれの分に応じて,現実的,かつ意味深い仕事を自我が成し遂げることができれば,それで十分といえます。
精神の充実は,つまるところ自我がどの程度の仕事をしたかということにかかっています。幸いにして大きな充実感の中にいることができているとき,自我は大筋で神の子を護ったことを意味すると考えられます。それは主体の意向に即することができたという意味です。
白い子を護るためには,行動の目的を敢えて確認してみるとよいと思います。そうすることで,白い子に意志を伝え,共に行動してくれるのを感謝するのです。首尾よく予定の行動が終われば,白い子は抱えてきたエネルギーを親である自我に渡したことになります。自我はエネルギーの補給を受けることになり,一定の満足感や充足感を得ることができます。
逆にいえば無為に過ごしていると,自我のエネルギーはしだいに枯渇していきます。
以上に述べたように,心の病は自我が機構的にか機能的にか,何らかの不具合が生じたときに起こるといえます。つまり自由と自立性が損なわれている自我は,与えられた状況的な課題を担えない,引き受けられないということが起こっているのです。
最初に提示したM子さんの過食と拒食,自傷行為は,いずれも臨床場面で日常的に見られる病態です。
過食にふけっているときの様子は,餓鬼道に落ちた亡者を連想させるものがあります。人目を避けて一心不乱に獲物に向かう悲しい姿がそこにあります。そのことに関して自我は機能せず,いわば無意識の仕事を無気力に傍観するばかりです。
摂食障害の治療は,依存症一般がそうであるように,易しくありません。
人は何かに依存しつつ生きています。人はまったくの自由,まったくの自立を生きることはできません。いうならば何かに掴っていなければ,押し流されてしまうのです。どこへかといえば,死へです。不安の根源には死があります。しっかりとした拠り所に掴っているのでなければ,不安に脅かされます。その度合いがひどければ,頼りないものにすがっていることの意味が分からなくなります。いっそのこと,当てもなく耐えるよりは,すがる手を放してしまった方が楽になれると考えることにもなります。
食べることにこだわる(すがる)のは,彼方に死の影が見えるからともいえ,それを見たくないばかりの必死の行動ともいえるように思います。見方を変えると,自我がこれほどまでに無気力なのは,おびただしく黒い子を作り出してきたいきさつがあるからです。黒い子は,神の子(欲求ー白い子)として主体から送り出されてきたものを,自我が護れなかったものたちです。それは主体の意向に即せなかったことになります。引き受けるべきである自我がそれを拒否したことになり,白い子,あるいは主体の側からすると不当,不埒という意味を持ちます。
自我が引き受けず,見捨てることになった産物である黒い子は,怒りのエネルギーを抱えることになります。そのエネルギーは,元は白い子が抱えていた生きるためのものです。自我はそれを受け取らなければ,エネルギーの補給を受けることができないのです。
神の子であった白い子が,一転して怒れる黒い子に変じて,悪魔の手先になったと考えることが可能です。
とはいえ,黒い子もまた,自我の子です。その関係は非行少年と親とのそれに似ていると思います。黒い子はいつか親である自我によって,改めて引き受けられる時が来るのを待っています。
(全(無限)と無とは正反対のようですが,それは有限性を生きる人間にはそう思えるということです。全とは限りない広がりのイメージから来るものであり,無とは限りなくゼロに近づくというイメージから来るものです。そして全そのもの,無そのものは,現象的実在として捉えることは不可能です。それらは有限性を超えたものであるがために,人間の意識の光が遠く及ばないものです。そういうことから全が良きものの最高のもので,無が悪しきものの最悪のものというイメージを持つことになります。最高のものとは,例えば神であり,最悪のものとは,例えば悪魔というわけです。全(無限)と無との分離は,人間の能力を超えたものについての人間的な把握の仕方といえます。
自我は心に関して二分化して捉えるのが特徴です。心には内なる他者,内なる異性などがあり,それは外なる他者,外なる異性と合体して完全な一者ということの内的な意味のように思われます。有限性を生きる人間は,この意味で二分の一以下の不完全な存在です。実際には起こり得ない他者との合体は,永遠なる一者,完全な自立など,無限なるものへの憧憬としてあるのだと思われます。そのようなことが前提になって,現実世界の人間は,他者を深く愛するときに至福の感情に浸ることができるのではないでしょうか)
黒い子を作り出すのは,人間には避けられないことです。
たとえばこの黒い子の存在がなければ,芸術活動は成り立ちません。白い子たちのエネルギーを受け取ることができた証である心の表舞台を,芸術家が表現する意味はまったくありません。そんなことは下らない自慢話の域を出ないからです。芸術家が意欲を掻き立てられるのは,黒い子たちの要求があってのことなのです。心には人に見せられない裏舞台があります。そこは黒い子たちの世界です。黒い子の勢力が大きくなると人の目が気になるのは,自我が,それらの存在を人に気づかれるのは恥と捉えるからです。それはいわば自我の不始末(お粗末でもあります)の証拠であり,黒い子をたくさん作ってしまった自我は,怒れる超自我をも意図せずに作り出してしまっているからです。
芸術家が一般の人と違うのは,欺瞞を潔しとしない自我を持っていることでしょう。彼らは黒い子たちの存在主張から眼をそむけずに,それを取り上げようと意志する心を持っています。芸術家が黒い子の存在に眼を向け,自らを暴き立てようと意志したときに,黒い子は自我によって引き受けれらたことになります。それは自我が知らずに犯した不始末を,自ら意志して取り返したことを意味します。
このように意図して,あるいは意図せずに,黒い子を引き受ける自我が,独自の人生を創っていくのです。黒い子はそれぞれの人生の起爆剤でもあります。つまり黒い子たちをたくさん作り出してしまった自我は,それに押しつぶされるか,それともそれを起爆剤に変える力があるかということになります。
心の病気は自我の不全化と密接な関係がありますが,自我が黒い子をたくさん作り出す不始末を働くことになった根本には,人間の誕生の問題(出産外傷といわれることがあります)と,それを補う立場にある母親との関係(取り分け,生まれて間もない最早期の関係)があると考えなければなりません。
出産という人間の誕生は,「自我に拠って,限られた時空間を思うように生きてみよ」という意味を持っているように思われます。自我を付与したのは,当然,自我の上位者です。
限られた時空間を生きるということには,死の問題が必然的に付帯しています。元気に生きるというのは分かりますが,一歩踏み込むと死に向って元気に生きよという設問になります。死という巨大な壁に阻まれて,元気に生きるという設問は,難解極まりありません。
(誕生という)人生の出発点でも,死の問題は立ちはだかります。
生まれるということは,喩えていえば,無のまどろみから起こされて,1000メートルの高みに立たされるに等しいことのように見えます。原初の段階にある自我機構には,「大きな安心と大きな満足がもらえるから何も心配は要らない」という幻想をかもし出す装置が取り付けられているかのようです。それは無であった世界に準じるものを保証しようとするものであるように思われます。その幻想に基づいて,赤ん坊は完璧な安心と満足とを要求します。要求する相手は母親以外にはありません。
有限の時空間を生きる人間にとっては,全とか無とかは現象的実在ではありません。しかし生まれて間もない赤ん坊には,直接的に全と無とが問題になっているように思われます。というのは,赤ん坊が自我に拠って有の存在になったということは,全または無の存在があることを間接的に示していることになるからです。そして有の存在としてはあまりにも頼りない赤ん坊は,母親に全面的に依存するしかありません。つまり母親は,赤ん坊にとって全の存在に等しいのです。その対比において,赤ん坊は無の存在に等しいといえるでしょう。赤ん坊は無の感覚において全にすがるといえるでしょう。
赤ん坊が人間として存在する出発点の段階で,1000メートルの高みの恐怖に耐えて,いわば無事に着地するためには,心の緩衝装置が不可欠です。満足と安心との十全な供与を約束されている幻想は,そういう意味を持ちます。母親にはそんな大それた力はないという意味では,それはまやかしです。そもそも人間は,その存在理由が永遠の闇の中にあるという点からして,壮大なまやかしの中にいるといえなくもありません。赤ん坊が,巧妙なまやかしを甘受することから人間としての第一歩を踏み出すことになるのは,人間存在の宿命的な何かを暗示しているようでもあります。
このように,いわば全,あるいは無限,または無の世界から,有限の世界に降りる甚だしい不条理のドラマが開始されるのが,赤ん坊の誕生です。
不条理劇の存在理由は,永遠の謎です。しかしともかくも幕は上がったのです。赤ん坊は不承不承であれ何であれ,与えられた運命を引き受けるしかありません。およそ3年ほどの歳月をかけて,1000メートルの降下を,母親に助けられながら果たさなければなりません。3年ほど経てば,自分と人生とを引き受ける役目を帯びた自我のひとまずの基盤ができるのです。赤ん坊はこの間に,完璧な要求の旗を降ろし,ほどほどのもので我慢できるようにならなければなりません。ほどほどの満足,ほどほどの安心で妥協する気にさせるには,母親の愛情が鍵になります。それができたときに,ようやく,この世を生きていくのも満更ではないという喜びを知る基礎を手に入れたことになるのでしょう。
過食は意志と判断が働いて起こっている行動ではありません。つまり自我の仕事ではありません。自我が機能できなくなった原初的な理由があってのことです。自我が機能できなくなった裏には,黒い子たちがおびただしく作り出されてしまった事情があるはずです。黒い子は,自我が受け入れるのを拒否したために,精神性と社会性とから無縁となった存在です。黒い子をおびただしく作り出す自我は,幼いころの母親との関係に問題があったと考える理由があります。そのような自我は白い子を護ることができた満足が得られず,白い子が抱えているエネルギーの補給も受けられず衰弱します。一方で黒い子たちが自我を支配するほどに勢いを増すと,いわば黒い満足を取りにいきます。その黒い満足の一つが過食です。
人は,あるいは心は,何らかの満足を追求します。そこに自我の関与がないかぎり,満足の追求に精神性も社会性も望めません。それらが欠落したものが黒い満足で,それは決して心を満たすことはありません。
拒食と過食とを繰り返してきたある患者さんに,自我(親)と超自我(後見人)と(黒い)子とから成る心の見取り図を示してみました。その図では自我が上位に立たなければなりません。上位にある自我は自由と自立性とを確保できているのです。ところが黒い子たちをおびただしく作り出した自我の下では,抑圧された怒りが超自我を大きくさせます。怒りをはらんだ超自我は,命令的,支配的,懲罰的になります。これら超自我と黒い子たちとは,パラレルの関係にあり,一方が増大すると他方も増大するのです。そしてこれら二つの山に囲まれて埋没した自我は,自由と自立性とを失います。
そのような自我の下で,超自我が活発なときには拒食に走ります。懲罰的な超自我の支配下での食行動は,それが極端になると身体性が否定され,精神性のみの追求が要求される観があります。この患者さんは,瘠せの極限で,死んでも構わないと思いました。身体性の全否定は,当然,死につながります。しかしやがて生きたいという意志が発動して,食事を摂りはじめ,元気を回復しました。そしてひとしきり経って,今度は過食にふけるようになりました。それは黒い子の仕業です。
超自我の勢いが収まると,一旦は自我が力を回復したものの,やがて黒い子たちが勢いを増し,自我を支配したといえるようです。このとき自我は,黒い子の動きを傍観するばかりです。
この患者さんの例から窺えるように,自我の機能は固定されたものではなく,あるときは自由を得,あるときは超自我の支配を受け,あるときは影の分身である黒い子の支配を受けるといえるようです。
患者さんは,以上の仮定的な説明に,まったくの同意を示しています。
乳児の精神的な満足は,授乳を通じて得られます。
フロイトは生の本能と死の本能とに言及していますが,生の本能はエロスともいわれます。一方プラトンは,愛の形態には肉欲から始まってしだいに上昇していく諸段階があり,その最高位にあるのが純粋な愛,つまり美のイデアへの希求であるとしました。そして真善美に到達しようとする哲学的衝動を,エロスと呼びました。
このように,生きる喜び,満足には,高度に精神的なものも含めて,その機軸となるエネルギーが性的であるというニュアンスが多分にあります。そして精神分析では,このエロス的な満足の身体的根拠がいくつかあり,心の成長に伴ってそれらの発達段階をたどるとしています。そのプロセスを精神性的発達と呼び,その最初の拠点は口唇にあるといわれています。これらの身体的個所は,erogenousuzoneと呼ばれていますが,日本語では「性的に敏感な」という意味です。
つまり生後間もなくからおよそ1歳半までの口唇期は,最初の性本能が満たされる時期ということになります。欲求一般を受け止めて,護る,あるいは満たすという心の作業は,自我の重要な役目ですが,とりわけ性本能(広義の)は強い欲求で,それをどのように満たしたかということは,精神的発達に大きな影響を与えます。
母親による授乳には,赤ん坊に口唇によるエロス的な満足とそれに伴う安心とをもたらす特別な意味があります。それは栄養の補給に勝るとも劣らない意味を持つでしょう。
自我に拠って有限化され,二分の一以下の存在となって個々に孤立している自己なるものに,エロス的な満足は,他者との完全な結合によって一者となる幻想をもたらすもののように見えます(自己と他者とが一体化して一者となるのは,人間の情念的な理念であるように見えます)。それだけに,エロス的なエネルギーには強大なものが秘められているのです。
そうした意味を持つ授乳は,信頼と愛情とを保証する基になります。それらは相互的なので,授乳によって満足と安心とを保証された赤ん坊は,愛されている,信頼されていると感じると共に,母親を愛し,信頼する基盤を得ます。
逆に,強大なエネルギーを秘めたエロス的な満足であるがために,授乳による継続的な満足が欠落する何らかの事情があれば,赤ん坊の心は不満足と共に,不信,不安,恐怖,怒りなどによって脅かされることになるでしょう。それは愛されていないと感じる大きな理由になります。そして愛されていなければ,信頼されていないと感じるでしょう。そうであれば母親を愛し,信頼するのも難しくなります。
摂食障害は,この時期のそうした心が意識下に潜行していたのが,あるとき病理現象という装いで浮上したもののように思われます。
なぜ意識下に潜行することになったかといえば,見捨てられる恐怖からです。そして摂食障害の患者さんたちは総じて’良い子’なのです。つまり内心のネガティブな心を,自我が笑顔でカムフラージュするのです。その葛藤は容易に解けないほどに,自我は笑顔の欺瞞性を,滅多には自ら認めようとはしません。
これは自我が母親への強い恐怖心から,自分を捨てて母親の自我にしがみついた,あるいは傀儡化してしまったともいえます。
こうした人生を賭けた心の欺瞞化構造を招いた根本にあるのが,人間に根源的な見捨てられる恐怖です。それは以下のように考えることができます。
先ほど述べた1000メートルの降下は,有の存在となったがために無に怯える赤ん坊の心を,比喩的に描いたイメージです。この降下を助けるのが母親です。母親の助けは,絶対不可欠です。絶対というのは,有の存在が無に帰する怖れに遭遇したときに意味を持ちます。赤ん坊にとって母親は全に等しい存在です。赤ん坊は無に怯えるものであるがために,全なるものを必要とします。
つまり全なる母親は,場合によっては無をもたらすかもしれず,その可能性を否定する術はないのです。1000メートルの降下中に,母親が赤ん坊を支える手を放せば,それでお仕舞いです。
無論,それは身体的な虐待の話ではありません。心理的に見放されることへの恐怖の話です。乳児にとって母親から見放される感覚を覚えるのは,死に等しい恐怖につながるといえるでしょう。それが見捨てられる恐怖であり,この心性が根源的な恐怖である所以です。
摂食障害という心の病理の形成過程の端緒には,以上のような,本人も知り得ない人生の最早期の問題が潜んでいると思います。
この時代の乳児の要求は,大人の想像を絶した激しいものであるようです。生きるか死ぬか,そのぐらいの大きなものがかかっていると思います。心の成長の原初の段階で,生きるために欠けてはならないエロス的な強力な満足の要求が適えられなかったとすれば,その理由は,それを上回る恐怖があったからに違いありません。それが適えられなかったことへの不満と怒りとは,それだけに極めて大きなもののはずですが,それを上回る(見捨てられる)恐怖のために抑圧され,意識の上にのぼることはなかったと考えられます。問題は欺瞞化されたまま,一応は収められた形になります。しかし消えたわけではなく,ほとんど生涯にわたって心に影響をおよぼします。表面の明るい笑顔とは裏腹に,真の生きる喜びが欠けたまま年齢が重ねられていることも多いのです。
親子の関係は重要で,精神医療ではことあるごとに問題視されます。それだけのことがあるのは間違いないところですが,その他に,自然と人類という更に大きな問題があります。
胎児の段階までは,人間が自然の一部でいられた特別のものです。そして出生という新たな段階を向かえるのですが,おめでたいはずのこの出来事が,どこか楽園追放という趣もないではありません。誕生という形で胎児は自然から切り離されて,なんのためとも知れず,人として人生の難路を旅する宿命を負わされます。その際,自然が授けた人間への武器が,自我といわれるものです。自然から乖離され,胎児は人間として独自の道を切り開くことになります。その営為の中心的な役割は自我に委ねられています。そのように自我は人間になくてはならない特有のものですが,自我自体はいうまでもなく人間が自らの意志で手に入れたものではなく,授けられたものです。換言すると,それを授けたものの存在があるのが明白だということです。ですから人間は自然から独立した存在とはいえ,自然のしもべの立場でもあり,自然の支配を受けています。
比喩的にいえば,自我は海に浮かぶ小舟の船頭です。海はもちろん無意識の世界です。
心に障害といえるほどの問題が生じれば,しばしば激しい感情が自我を翻弄します。その様子は荒れる海に浮かぶ小舟のように危うく,時には,立ちすくむ自我を後目に,怒りに駆られた阿修羅のような行動に駆り立てます。
高校時代に不登校の経験を持ち,中途退学をしたK子さんは,難関の大学に入りました。失恋がきっかけで発病しました。診断は境界性人格障害です。ふとしたことで怒り,憎しみがこみ上げてくると,行動を抑制できません。時間かまわず相手の男性に電話をかけたり,直接押しかけたりしてしまいます。自殺衝動が強く,相手を殺すか,自殺するかしなければ収まらないという気持ちになります。過呼吸発作が頻繁に現われます。何日か気分が落ち着いている日もあります。しかし急に別人のように激しい感情が心を席巻します。自分から求めて入院となりました。
無意識の海が荒れると,小舟の船頭である自我はなす術がありません。エネルギーの中心には怒りがあります。阿修羅のようなその激しさが分別を打ち砕き,行動に駆り立てます。なぜ人生のこの時期に,この激しさで,怒り狂う感情が心を席巻するのか,共感を持って理解するのは困難です。人の心理としては共感も理解もできないという異常な事態は,心理的理解を越えた出生に伴うなんらかの障害ということになるのかもしれません。
せめて海が荒れてひどい事態にならないように,我々ができることは,子供に正しい操船術を教えることです。どうしてみても難しい場合もあると思いますが,できることをするしかありません。
ふつうは,親が子に正しい指導をすることで,心の海が不自然に荒れるのを防げるでしょう。自我がそれなりにしっかりとした操船術を身につけていれば,困難極まりない航海も,満更でもないものになります。
自我の操船術は,主に両親から教えられます。危険や困難を乗り切るための有能な先達が身近にいるのは,心強いものです。しかしそれでも遭難の危険はなくなりません。海が荒れれば,やはり自分の力で切り抜けるしかありません。人はどうしても孤独な存在なのです。
この比喩のついでにいえば,小舟には船長のほかに,その親(実際の親ではありません。内的な親です。超自我と呼ばれることがあります)と(黒い)子が同船しています。無難な航海をしている舟は,船長が中心的な役割を保っています。それでも黒い子(幼い自我が親との関係で引き受けることができなかった諸欲求=内在する主体が送り出してきた神の子=)たちは必ず同船しています。それは船長が自然の要求を完璧に護りとおすことが不可能なためです。同船している内的な親は何かと口を出し,それが船長を助けるよりは足を引っ張ることも少なくないからです。黒い子をたくさん作り出した船長は,内的な親との相対関係で,間違った操船を何かとしてしまったことになります。どこかで船長が反発して自由と責任とを取り戻す力を示さないかぎり,いつか内的な親が事実上の船長になってしまいます。そして扱いの厄介な黒い子たちがとかく騒ぎ立てます。小舟はあくまでも船長が責任を負うべきものなので,内的な親と黒い子たちとに主権が移ってしまった舟は,迷走し,大海の只中で目標を見失ってしまいます。それは死への漂流になりかねません。
操船術の本当の教師は,自然の摂理です。信頼できる人生の先達から受け取るべきものは,技術ではありません。精神です。自然の摂理を読み取る謙遜な無私の精神です。処世の技術は世俗的な意味があっても,人生の航海の目をくらまし,しばしば有害です。それは無私ではなく,謙遜でもないからです。目先の利得になにほどの意味があるでしょうか。処世の楽しみに飽き足らず,虚しさを覚える人があって当然です。生きる理由について,確かな手ごたえのある何事かを会得したいと考えるのであれば,海なる無意識そのものの力に注目する以外にありません。
乳児は,母親に全面的に依存する形で,人間としての第一歩を踏み出します。目標は母親からの自立です。
自立を妨げる要因は二つあります。怒りと恐怖です。これら二つの感情は,主に原初の他者である母親との関係で生じ,一種の外傷体験になります。そして黒い子を生み出す理由になります。母親との関係は原初の人間関係であり,そこで生じた外傷体験は,抑圧されて意識下に潜行することになります。それはいわばアキレス腱となって,後々,人間関係一般でそれに類似する体験状況の下で,新たに怒りと恐怖とを惹き起こしがちになります。そしてその都度,黒い子を生み出すことになります。
激しい怒りは,完璧な保全の要求をする乳児に特有のものと思われます。いわば人間であることを強いられたものが持つ,その要求と怒りは,自己を保存しようとするもので,本能に基づきます。それはその反面に,人間であることの拒否を含むといえます。自己保存の要求が本能に基づくように,その要求の裏面には死の本能があると考えるのが自然です。文字通り,生死を賭けた要求といえるほどの激しいものが,乳児にはあるのではないかと想像されます。
怒りと恐怖は双子のきょうだいです。
「人間として生きよ」と命じられたものが,生の反面に死があるのを意識せざるを得ず,それを大きな脅威と感じないわけにはいきません。その解き難く,超え難い矛盾は,怒りを持つ十分な理由になると思います。生きるという光の世界の温かさは,死の極風にさらされ,凍りつく裏面を持ちます。生へのエネルギーはエロス的な満足と共にありますが,死へのエネルギーは,その満足が剥奪される怖れと怒りです。
しかしいま述べたように,自己保存と死という形での二分法となっていることが,既に人間の特徴です。つまり,自我に拠って生を切り開くのが人間である一方には,その挫折もまた含まれており,それは死への斜傾ということになります。
人間が生まれる前の存在形態は永遠の謎です。それは人間の目には,現象的には実在しない無または全の性格を持つもの,とでもいうしかないようです。それは死後の存在についても同様です。
人は無から生じたのか,全から生じたのかという議論は意味をなしません。しかし自我に拠って有限の時空間を生きる人間には,自我を授与したものは無であるというのは,何だか妙な感じを受けます。やはり全によって授けられたという方がしっくりします。どこか偉い人に認められた,選別されたというような気分にもなります。人間には,赤ん坊の誕生はおめでたいことでもありますし,生まれるというのは喜ばしいことに間違いはありません。だからこそ死はかぎりなく不吉なものです。死によって人間の存在はどんなふうになるのかは闇の中ですが,人間の語感では全より無の方が死にはふさわしいようです。つまり人は全によって生を受け,やがては無に帰するということになるようですが,実際のところ,全と無との区別は人間にはつけられません。
貪婪な欲求の持ち主である乳児がひとしきり騒ぎ立てるのは仕方がありませんが,母親の愛情に支えられて,自我がしだいに人生を引き受ける力をつけていかなければなりません。
しかしながら自我は幾重にも自立を阻まれていると考えなければなりません。母親の愛情が鍵を握るといっても,母親を取り巻く内外の事情や,赤ん坊の側の過敏さなど,一様には論じられません。結果として幼い自我がどのように怒りを扱ったかが問題ですが,それは個々に複雑な心のプロセスとでもいうしかありません。
怒りを母親の助けによって鎮めることができず,母親への恐怖から抑圧するしかななかった幼い自我は,黒い子をたくさん作ってしまうことになります。そして黒い子をたくさん作ってしまった自我は,それに応じて依存的であらざるを得ないといえます。親にあからさまな怒りを持ち,家出同然に独立した生活をはじめたとしても,心が依存から脱したとはいえません。依存から脱した証は,心が親からどの程度自由になったかによるでしょう。それなりに自由である自我は,黒い子たちを引き受け,その怒りのエネルギーを回収すろことに成功しているはずです。ですから激しい怒りが潜在しているあいだは,自立に似て非なるものといえます。
依存に関して,問題は黒い子たちにあります。それが大きな勢力を持っているかぎり,自我はその支配を受けます。怒りに駆られて家出同然の独立をはかるのは,とりあえずは黒い子たちに促された行動と考えるべきです。黒い子に取り囲まれて,親から離れることができない依存する自我とは別種の,依存する自我の下での行動です。怒りを抑圧し,内向させている後者よりは,怒りを前面に出している前者の方が本格的な自立への可能性が高いかもしれません。しかしその後のことは本人しだいであり,予断は許されません。
乳児は,母親に向けて完璧な自己保存を求める,いわば生死を賭けた激しい戦いを挑むと考えることができると思います。言葉を換えれば,母親を支配しつくそうとする戦いということになるのでしょう。それが激しいものであればあるほど,母親の態度に過敏に反応し,反転して著しい恐怖に陥ることがあるのではないでしょうか。恐怖は死を垣間見るときに起こります。それが現れたときに,乳児は怒りの鉾を収めて沈黙するのでしょう。
まだ人間らしい中庸の精神が発達していない段階では,エロス的満足を求めて,あるときは天使の笑顔になり,あるときは悪鬼の相を顕わにし,至福と怒りの両極の間で激しく揺れるのです。そしてあるときに死の恐怖を垣間見たときに,幼い自我が怒りを強力に制して沈黙し,時によっては親の自我に取りすがるようにしてよい子の路線を取ることで,身を守ることになるのでしょう。
そのように母親を支配しつくそうとして,反転して母親の支配を受けることになったときに,依存の病理的な一つの形ができるのではないかと思われます。
(怒りは関係を破壊しようとする力であり,死と関係します。動物の怒りは専ら外へ向かい,何らかの脅威となるものを攻撃する力になります。人間の場合は外へ向うこともあれば,内へ向うこともあります。外へ向えば他者との関係を破壊しようとする動きになりますし,内へ向えば自己自身との関係が破壊される動きになります。赤ん坊の怒りは,不快を快に転換するように求める適応的なものでしょうが,その怒りには,それが適えられないのであれば相手の破壊をも辞さないという構えもあると思います。であればこそ,反転して相手(母親)に恐怖を抱き,沈黙することにもなるのでしょう。それは自分の怒りが,いわば逆照射された恐怖といえるでしょう。他に死をもたらす力を持つものは,自分にも死をもたらす力を持っています。
相手に向う怒りが相手への恐れによって撤収されるのは,自己保存の本能が発動してのことですが,収められた怒りは逆照射して自分自身に向けられ,相手への恐怖が更に強められます。それを自我が持ちこたえられないときは,強力に抑圧して表面上は問題が収められます。しかし問題は内向する怒りとなって,今度は自分自身との関係を破壊する力となります。それはそのまま拡大してしまえば,精神的に滅びてしまうことにもなりかねないものです。
そういう事情の下で何が必要かといえば,自我の介入です。怒りを引き受けて,適切に扱うのは自我の役目です。それがあれば怒りの持つ死をももたらすエネルギーは,いつか自我によって鎮められて,生へのエネルギーに転換されることになることが可能です)
完璧な自己保存の要求は,具体的には,愛情と信頼とで満たされることを求める欲球に基づくものだと思います。そしてそれを要求したばかりに味わわされた恐怖があまりに大きいと,一転してそれは撤収され,今度は母親の気分を損ねないことに全神経を使うことになるのです。そのときに支払わされる代償が,寂しさ,不安,孤独などの程度の強い感情です。そしてそれらの感情の奥には強い恐怖と怒りが潜んでいます。それでも母親によい子と認められるのが嬉しいので,子供である間はそれで満足できてもいるのだと思います。しかし支払わされた代償は,大人の年齢になりつつある過程で,しだいに制御し難いものになります。それにもかかわらず早期に経験した恐怖が著しいと,抑制の手が緩められることはありません。その内面の激しいドラマとは裏腹に,あくまでも明るく優しげな仮面は強固であるとすれば,それは人に見捨てられたくない恐怖が強いためといえるでしょう。そして,その一方では自我によって解放される見込みが立たない怒りのエネルギーが,内側から心を破壊することになります。もっとも,外傷体験のように外部からダメージを受ける経験をしたとしても,心が破壊されるのは内側からであるといえるのですが。いずれにせよ強力な見捨てられる恐怖のために,その仮面を取り去って素顔を面に出すのは,容易なことではありません。そのことに伴う潜行する恐怖と怒りとは,人の理解を越えた激しいものだと思われます。それらの強い感情の下では,自我はほとんど機能不全に陥ることになるでしょう。凍える自我の下での理性は,自分の心の問題を形式的に理解はできても,洞察といえるほどの能力を発揮することはほとんど望めません。本心を知るくらいなら死を望みさえするほどに慄く自我は,恐怖と怒りとを抑圧する手を緩めようとしないのです。
この慄く自我は,母親との授乳を媒介とした心の会話がうまくいかず,好ましい形の依存が封じられたままでいるあいだに,いつしか懲罰的な怒れる超自我と,受け入れを拒否された怒れる黒い子たちとの狭間で,無力化しているともいえます。
このように無力化した自我は,自由と自立性とを欠いているので,さまざまに依存する自我であることが避けられません。
拒食症者である女性(Aさん)が,妹さん(Bさん)を診てほしいと連れてきたことがあります。妹があまり食べなくなったというのです。Aさんは自分のことは心配しないのに,妹であるBさんの心配はするのです。Bさんは,「いまはいらいらし易く,食べたくないのは事実だが,そのうちに食べ出すと思っている。私は姉と違って,明るく,社交性があり,物をはっきりいう。割り切りもいいので,姉のようにはならないと思う」といいます。また,「両親と暮らしているあいだは気分が常に不安定で,しょっちゅう吐いていた。2年ほど前に家を出て,同棲をはじめた。それから吐かなくなった」といいます。Aさんの話では,酒乱だった父親によって,家の中の物が壊されて目茶目茶だったということですが,Bさんによれば父親の暴力は更に激しいものでした。Bさんは以下のように語ります。
「幼いころから殴る,蹴るという目に遭ってきた。姉は我慢してよい子でいようとするが,私は口ごたえするからだと思う。父親は酔っているときに暴力的になったが,素面のときでもあった。中学生のときに,父と二人になった。包丁で刺されそうになったが,理由がいまでも分からない。その他にも,包丁を持った父に追い回されたことがある。いつ殺されてもおかしくないと思っていた。父は勿論,庇おうとしなかった母も決して許せないと思う。その一方で,許さないと・・・という葛藤がある。姉と違うのは,私は両親とのあいだに境を置いたことと思う。私が両親に怒りを持つのを許し,その一方で,私と両親とは人格が別だと考えた。そうすると気が楽になった。姉は両親の前でよい子でいつづけたと思う。いつか両親の面倒を見ないといけないと思っている。どうしてもその心を変えられないでいる・・・」
ずっとよい子で,いずれ両親の世話をやかなければならないと考えているAさんは,Bさんより度の強い拒食症者です。Bさんは甚だしい暴力を受けながら成長しましたが,自分の心にある度の強い怒りをしっかりと受け止めています。その上で,怒りの扱いに腐心した様子がうかがえます。それは自由な自我にでなければできない仕事です。一方,Aさんは,暴力をふるいつづけてきた父親と,無力だった母親とを,ある意味ではあくまでも庇おうとしています。Bさんは,それはよくないことだという認識を持っていますが,Aさんの心には届きません。姉妹を較べると,Bさんの自我はかなり自由のようですが,Aさんの自我はまったくそうではありません。
Bさんは重要なことを自ら会得しています。
一つは度の強い怒りに自我が支配されず,介入する自由を保つことができたことです。もう一つは,心の境界を敢えて意識したことです。母子一体の関係の中にある母親と乳幼児とのあいだでは,心の境界が曖昧です。母親は,必要であれば自分自身にするように幼い子の心に介入できます。そして幼い子にはその助けが不可欠です。そして心(自我)の成長と共に,親子のあいだに心理的な境界が形成されていきます。それは幼い子が母親から自立していくために必要なことです。幼い心が成長していくことと,心の境界が明確に備わっていくこととは,パラレルな関係にあります。それによって心の自由と自立とが得られるのです。
人格障害の患者さんの中には,他者に完璧な助けを求める場合があることが珍しくありません。このことは境界機能の発達が不十分であることを示しています。乳児と母親との関係では,母親の心にも乳児のそれに対応して心の境界が取り払われていると考えられます。ところが大人の年齢になってしまえば,本人の心の境界が曖昧であっても,周囲の人の心には明確に境界があります。そのために,母親が乳児にするようには助けられないのです。比喩的にいえば,相手が乳児の場合は,母親は家の中に入って助けることができますが,大人になってしまえば,母親(あるいはそれに準じる立場の人)といえども,家の外から助けることができても,子供の家の中に入って助けるのは不可能です。
このように完璧な助けを求めるのは,得られないものを得ようとすることで,周囲の者も疲れ果ててしまいます。自我がこのことを理解する力を回復したときに,自分の問題として自ら引き受ける気になることが可能になります。そのときに問題は収束に向うのです。
Aさんは,自分のことより妹を心配する優しい心の持ち主です。Aさんの心の優しさ,穢れのなさには疑問の余地はありません。しかし両親の世話をやかなければならないと思っていることについては,姉思いのBさんが疑問を投げかけています。何よりもAさんの拒食の心には,死への志向が色濃く紛れ込んでいるのが問題です。これは親孝行というより,苛烈な要求をつきつけ,懲罰的な超自我の下で機能を破壊されかけている自我が,必死に両親に取りすがるのをやめられない(依存している)様相というべきものです。これらの心の深部には,内向する強い怒りがあるはずですが,Aさんは強力に抑圧してその存在に気がついていません。あるいは気がつくのを徹底して避けているともいえるでしょう。それはもしかすると,抑圧する手を放すと,制御し難い怒りが両親に襲い掛かると,意識できないレベルの心で感じているからかもしれません。それよりも,自己の死を選ぼうとしている無意識的な心の動きがあるのかもしれません。Aさんが妹さんのように,両親とのあいだに心の境界を置くことができれば,超自我に屈しない自我の自由があると思われます。そしてそのときに,必要であれば親孝行が可能になるのです。
Rさんは40代の主婦です。
20歳で結婚し,共働きをしていましたが,30歳のころに動悸と全身倦怠感などがあり,某クリニックを受診しました。強迫神経症とうつ状態と診断され,仕事を辞めるようにいわれました。その3ヵ月後に勧められて入院しました。家事から解放されて落ち着きましたが,家に帰ると’旧の木阿弥夫’で,入退院を4,5回繰り返しました。
私のところの初診は45歳のときです。その当時は不安が強く,家事をする意欲がなく,強迫行動(観念も)があり,過食と買い物依存がありました。「鍵があいて誰かが入ってくる」という夢を繰り返し見るといいます。「自由な身(お金に困らず,子供に束縛されず,何人かの友人がいるなど)なのに,ひどく不自由・・・」と述べています。
強迫行動は,手洗い,洗顔,歯磨き,入浴,洗濯物の取り込み,調理,食器洗い,火の元,鍵など多岐にわたります。買い物は,高価の衣類にかぎられ,「昨日は5万円,一昨日は12万円・・・」などと,欲しいと思うと我慢が効かないのです。家中に衣類があふれ,お金がなくなると万引きをするかもしれないともいいます。夫によれば,スーパーに入ると様子が変わる,駄々をこねる子供とおなじになるということです。
夫は高校時代に身の上相談をしていた人で,父親的な優しさと包容力のある方です。Rさんと夫とは一回り以上歳が離れています。子供はいません。Rさんは,初診のときに夫を評して,「こういう私と長年連れ添ったのだから,優しくて,辛抱強い,120点あげます」と述べております。
毎朝,夫が家を出るとき,「帰ってくるのかしら」と不安になります。夫は笑って,「他に行くところがないよ」といいます。分かっていても不安は取れず,繰り返しおなじことを夫にいってしまいます。
夫は専門の分野で幅広く活動をしています。それが羨ましくもあり,自分の虚しさを教えられる理由にもなります。それに較べると自分には価値がないと思えてしまいます。十分に夫を信じ,尊敬しているのですが,夫に置き去りにされる不安が根深くあります。
初診から間もないころに,パジャマのまま夜中に外へ飛び出したことがあります。車道に出てはねられて死のうと思ったといいます。その後,夜中に薬の過量服用をして救急入院しましたが,胃洗浄を拒みました。その際,夫が,「数ヶ月前から,私が出かけたあとに,人の気配があって刃物で追い回される,刃物で切れと命令する声が聞こえるといっていた」といいます。本人から離婚話が出たこともあるといいます。しかし夫は,「見捨てるつもりはありません」といっています。この時期は,統合失調症と区別がつかない状態でした。
父親が自分本位の人のようです。母親は仕事を持っていて,いつも忙しそうにしている人でした。日記を覗き見られたり,鞄の中を調べられたりしました。両親はいつも喧嘩ばかりしていたといいます。
母親と共に出かけたとき,「置いて行っちゃうよ」としばしばいわれました。あるとき,幼いRさんのはるか前(母親と出かけるときは,いつも母親が速足で,先へ,先へと行ってしまいます)を速足で歩いていた母親が,本当にバスに乗って行ってしまいました。置き去りにされたRさんは,「ああ,やっぱり」と思いました。
子供は欲しいとは決して思わないそうですが,母親のような母親には絶対にならないと思ってきました。母親は交通事故で亡くなりましたが,涙が出ませんでした。
父親も母親も,いまでもどうしても受け入れることができません。そして,寂しさ,虚しさ,孤独,怒りの感情が常に心を支配しています。
母親の行動は恐怖をもたらしました。幼いRさんは,叱られないように,見捨てられないように,認めてもらえるように,ひたすら母親に注意を奪われつつ成長しました。自分が存在する価値がなく,両親に必要とされていないという意識が,いつか心の支配原理になりました。自己本来のさまざまな欲求は,強い見捨てられる恐怖の下にある自我によって抑圧されつづけたと思われます。母親の傀儡となっている自我によって抑圧されたものは,無意識の世界で黒い子となって勢力を蓄えることになります。黒い子たちが大きな勢力になると,破壊的で悪魔的な力になっていきます。Rさんの買い物依存や過食はその現れの一つです。
また黒い子をおびただしく作り出した自我は,強い怒りを強力に抑圧することになり,内向する怒りが,超自我を支配的で威嚇的,懲罰的なものにしてしまいます。それが強迫行動を生み出します。
Rさんはふだんは怒りを面に出す人ではありません。しかし妄想の渦中で夜中に外へ飛び出し,追いかけてきた夫に激しい怒りを向けたことがあります。冷静になれば,Rさんにとって夫はほとんど非の打ち所がない人です。その夫にさえ,毎朝出かけるたびに,もう帰ってこない(見捨てられる)のではないかと,いわば不信を持つのです。
Rさんの結婚は,何としても家を出たいという気持ちに端を発し,夫がそれを理解し協力したという形だったようです。単なる愛情からの結婚ではなく,たぶんに同情心が働いてのことでした。愛情は相互的ですが,同情は上下の関係での一方向的な行為になるでしょう。それは同情される側から僻みを受ける可能性を,そもそも持っています。そこにも怒りが介在する余地があるのです。Rさんは夫を尊敬していますし,悲惨な境遇から救い出されて感謝もしていますが,負い目がどうしても残ります。
自我が比較的自由である状態のときは,Rさんは夫に感謝と尊敬の念を持つのですが,自我が力を弱めた状態のときに,夫に対する羨望の念に苦しみます。
羨望は,そもそもは幼いころに,母親などから当然もらえるはずの愛情と信頼とがもらえていないと感じる不満と怒りに端を発するのでしょう。乳幼児期の満足と安心とを求める心には,強いエネルギーが込められているので,これを更に強いエネルギーで抑圧する理由があるとすれば,それは見捨てられる恐怖以外には考えられません。この激しい不満と怒りとが,親代理でもある夫に向けられても不思議はありません。
羨望は激しく傷ついた自己愛の問題でもあります。自己への愛情と信頼とは,健全な自己愛の下に育まれます。それは人格形成の最早期に,母親との関係でその基礎が築かれなければならないものです。健全な自己愛と健全な他者愛とのあいだには,相関関係があります。Rさんの夫は,安定した自己愛の持ち主のように思われます。Rさんに対する父親的な愛情に,不信の眼を向ける余地がない人のように見えます。Rさんの夫としては,これ以上に望めない人のように思われ,Rさんもそのように考えております。それだけにその夫を怒りを込めて羨むことの葛藤,苦痛には深甚なものがあるでしょう。
自殺衝動,妄想などのことは,超自我と黒い子たちとの狭間で苦しみつづけた自我が,ついに機能麻痺に陥り,黒い子達が心を主導している様相といえるでしょう。
Rさんが夫に救いを求めて家を出た主要な理由の一部に,内向する怒りがあったと思われます。その怒りは自我が受け止めたのではなく,依存の対象を親から夫へと移し変える動力になっていたと思われるので,恩を受けた負い目の下に,怒りは相変わらず内向しつづけたのです。夫の助けは貴重なものではあっても,それに支えられてRさんの自我が自らを助ける仕事をして,夫と対等の立場に立たないかぎり解決できないものでした。最近は家事をこなしていますし,夫と旅行をしたり,生活をそれなりに楽しめるようになっていますが,寝る前の薬をのんだあとに過食にふけり,その記憶がまったくないなどのことは今もあります。人生の最早期に傷ついた病理的な自己愛の修復は,理想的なパートナーによっても容易なことではないのです。
このことには,先に述べた自我の境界機能が関係しているように思われます。
母親と赤ん坊との関係では,自我の境界機能は特殊な様相になるように思われます。つまり,繰り返しになりますが,赤ん坊の自我の境界が未成熟であることに相応して,赤ん坊との関係における母親の自我の境界機能もいわば撤去されると考えられます。それによって,赤ん坊と母親とは,いわば特殊な二人組みの関係になるように思われます。それがあって,母親が自分にするように直接的に赤ん坊の心の世話をやくことが可能になるのです。そして赤ん坊が成長すると,この境界が明確になっていくために,他者(母親も含めて)は母親が赤ん坊にするようにして直接に助けることはできないのです。
人格障害の患者さんの中には,幼い子が助けを求めるような激しい情動を示す人があります。このことからは,自我の境界の機能がしっかりしていないということが暗示されます。
冒頭に上げたM子さんの症例は,美人コンテストで成功する夢を母親に託された娘の問題でした。日本には子供のこうしたコンテストがないので,馬鹿げた,グロテスクな話に見えます。しかし,日本の現実には受験の問題があります。それが母親の理性をどれほどおかしくさせているか(父親も同列です),実例に事欠きません。そこにはM子さんの母親がしたことと,さほどの相違がないように思えます。
そもそも親が子を信じ,愛情にも確かなものがあるとき,幼い子を受験などに駆り立てるものでしょうか。
親の側に,自分の不安が強く,そのために子供の将来も不安になるのだという正直な認識があれば,害は少ないと思います。そうであれば,自分の心に潜む,悪辣なもののへとつながりかねない心の傾向を知っていることになるからです。そこに嘘が介在していないからです。辛く,苦しい気持ちを持つことはなんら罪ではありませんが,自分の問題を子供の問題に転嫁するときに,子供の領域への無反省な侵入が始まると思います。それは,国境を越えて侵入すると紛争になるのとおなじく,親子の間で紛争が始まったと考えなければなりません。
強い自我(境界機能がしっかりしている)を持った子であれば,親も無闇と子の領域に侵入できません。弱い自我(境界機能が不確か)の子がその種の被害を蒙ることになります。それを考えると,おかしなことをしようとしているのが,親自身もどこかで分かっているというべきなのでしょう。子の領域に侵入すれば,強い自我の子であれば親子のあいだでの紛争になります。しかし侵入しようとする自我は,本来的には弱い自我なので,そういう紛争は回避して,弱い子に向うのです。これは卑劣というものです。
元はといえば,親の心の中が紛争状態なのです。それを自分で解決するほどの強さがないので,弱い立場の子の心を支配する形で問題を収めようとするのだろうと思われます。弱い自我の子が,親に対してしっかりとした態度を取れないために,表立った問題が起きていないだけなのです。そして,親の心の内紛が転嫁された子供の心は,表面はともかく,内面での葛藤に苦しむことになるとしても不思議はありません。
不安に悩む母親が,子供を信じるという善を施せずに,不信という悪にかられるときに侵入が始まります。子供を信じることができている母親が,子供の領域に侵入する理由はありません。子供を信じられない母親は,自分自身も信じられないのです。
侵入する心には,常に怒りが護衛のように従えられているように思われます。「あなたのために良いことをしている」という思いが単なる正当化に過ぎないのは,’良い子’がそれに従わなかったときに,親の心が穏やかではないことがそれを証明しているでしょう。
親が自分本位の毒念を持ち,しかし無神経な心がそれをカムフラージュしたとき,子供は厄介な状況に置かれます。親の心の奥に潜む悪意を子は敏感に感じ取ると思います。怒りを覚えるだろうと思います。しかし(弱い自我の)子も親に似て,その心を隠して親を信じた気になります。そういう親子の関係ができているとき,子の固有の意志は,怒りとともに意識の奥深くに潜行し,心の破壊活動がやがて始まることになりかねません。
一児の母であるSさんが,子供が可愛いと思ったことがないと口を滑らせたようにいったことがあります。ふだん子供の受験問題にことさら熱心な人なのですが,そうならざるを得ない子供の側の問題を常々述べておりました。子供が受験勉強に不熱心なので口やかましくなることはあるが,それを別にすると親子の仲はとてもよいということでもありました。しかしそれはにわかには信じ難い思いがありました。そういう折に,冷酷な心が一瞬だけ表に現われてしまったように感じられ,それは注目に値することでした。というのは,心が本音を隠蔽したままでいるかぎり,Sさんの本格的な治療が望めないからです。
残念ながら,この折角の話は深められないままになってしまいました。私も瞬間的に息を呑み,タイミングを逸したということですが,いずれ問題にできると思っていました。しかしその周辺のことに話が及んでも,再びその心が語られることはないままです。
母親自身が幼いころは勉強一筋の人でした。そうすることで両親に取り入ってきました。裏を返すと,両親に認められない怯えを持つ子でした。自分の子供時代の不毛をしきりと悔やみながら,子供が望むので応援しているという口実で勉強を強いているのです。意識の表面では子供への愛情からということであっても,影に冷酷な心が潜んでいます。幼い娘が,母親であるSさん自身がかつて夢見たように,学校生活でも,社会人としても,誰にも自慢できるような赫々たる成功者になり,母親を助けなさい(それはSさんが,内的な親によって命じられていたことでもあります)という暗黙の意志が働いてのことであるのはほとんど明白です。母と子の関係が良好であるという認識に裏があるのと同様に,娘としての自分と母親との関係が良好であるという認識にも,裏があるのも明白です。つまりは自分がされたのとおなじことを(世の成功者にならないと娘として認められないという強迫的な観念),まるで復讐でもするように一人娘にしていながら,その自覚を持たないのです。
Sさんの場合,野心とその影に潜む冷酷さは一体のものです。野心が自分の力を当てにするのではなく,子供の力を当てにする形を取っているからです。だから子供を独立した人格と認めていません。それは冷酷な心です。そこには子供じみた強制が働いていると考えなければなりません。いうことをきかなければ,おかあさんは承知しないよというメッセージが込められているに違いないと思います。
冷酷な心は,自我が認知しないことによって,無意識の中で毒素となって暗躍します。しかし認知する気になったときに,もはや冷酷な心ではなくなる第一歩を踏み出しています。それが容易なことではないSさんは,内向する強い怒りを恐れていると思います。
悪意が善意に変われば,みんなが仕合せです。そういう自明のことが難しく,秘めた悪意を捨てようとしない心は奇妙なものですが,それはどこにでも見られるありふれた心の出来事です。その理由は,それだけ内向する怒りが強いからだと思います。強い怒りを秘めた心はしばしば怨念となります。場合によっては,無力な主人公である自我を傀儡化して,第二の人格を無意識の領域に仕立て上げようとします。それがさまざまな依存症を引き起こします。場合によっては周囲を驚かせるような危険な行動をも引き起こします。
自我が,自分の盲点となっていることに眼を向けていくのは,二重に困難な作業です。それはそもそも自我が引き受けることができなかった体験に発しています。いわば幼い心の外傷体験ともいえるものがあり,それに類似する体験に直面するたびに,自我は抑圧,排除する傾向を持ちます。いわば自我が最も苦手としている問題に,改めて眼を向け,立ち向かっていこうとするには,大きなエネルギーを必要とします。
自我はそういう認識姿勢を持つこと自体を,できれば避けようとするでしょう。そうであればこその盲点なのです。しかしそれを克服して自分の仕事という自覚を持つのが,本来の自我の使命です。
そういう事情がありますので,黒い子たちの勢力に悩む自我が,改めて黒い子たちを引き受ける力を回復させられるまでのあいだ,その自我を補助するのが,我々,心の治療者の役目です。
外科の病気のように,自分はベッドに横たわっているあいだに治れるものなら治してもらいたいでしょうが,心の病気はそうはいきません。治すための主役は本人自身であり,治療者の存在は重要ですが,協力者以上であることはできません。
このことは先に述べた自我の境界機能に関係します。つまり心を病む人の自我と治療者の自我との領域は,境界機能によって画然と隔てられています。治療者は病者の心の内部に入り込むことはできません。いわば境界の外から,患者さんの自助努力に協力するのが心の治療者の役目です。ですから患者さん本人が,自分に立ち向かっていく意志の強さが鍵を握っています。
「あなたは病気を治したいと思いますか?」というと,馬鹿な質問と思うかも知れません。しかし,心の治療に関しては馬鹿な質問とはいえません。
幼い時代に抑圧,排除されたものである黒い子たちは,心の深部で,凍りつくほどにおびえている幼い弟,あるいは妹(つまり過去の自分自身)と見なすことができます。
というのは,主体から送り出されて来た白い子を,幼い自我が護ることができた(母親の協力が不可欠です)ときに,自我がエネルギーを得,満足感と安心感とを心にもたらすことができるのです。そのとき,白い子は心の表舞台に上げられたといえます。そして心は力を得て,その分の成長を果たすことになります。
しかし自我がそうした仕事が出来ずに,白い子を黒い子にしてしまったときに,自我はエネルギーを受け取ることに失敗し,心は不満足と怒りと恐怖とを抱え持つものを心の裏舞台に留め置くことになると考えることができます。つまり黒い子たちは,その時々の年齢のレベルに,凍結されるように留め置かれるのです。
心の治療は,それらの分身たちを救出する作業という意味合いを持ちます。具体的にその仕事ができるのは自我ですが,治療者の補助を受けて,その意味での弟(妹)の存在に眼を向ける勇気を持ち,それらの分身たちの心を言葉で捉えるということです。現実にも,そういう弟(妹)がいれば,兄あるいは姉が,弟の心をよく分かってあげるのが,何よりの励みになると思ます。それとおなじことです。これは自己の回復のためには,是非とも必要なことですが,自我の仕事としては最大級の難作業です。
他人との関係は重要ではあっても,一般には周辺的な問題です。他人との関係も依存的なそれであり,関係に無理が生じると壊れます。心もそれなりのダメージを受けます。しかしそのときは大きな問題であっても,やがては癒されます。切れてしまえば,他人の場合は,多かれ少なかれそれで問題は終結するのです。
なかなか終結しないとすると,その背後で,より核心的ななにかが連動していると思います。それを探って行くと,心の形成の歴史をはるかに遡った親との関係にたどりつくことになるでしょう。
勇気を持って自分の本心に立ち向かおうとすると,必然的に(母親との)旧来の依存関係に波及するのは避けられません。自我のその仕事は,威嚇的な超自我に支配されている心の体制を破壊し,再構築する一種の革命です。心の体制が覆るのは恐ろしいことです。統合失調症の中に,世界没落体験という深刻な病的現象がありますが,それに見舞われるときは,恐怖に満ちた体験になると想像されます。いま述べた心の再編も,それに準ずるような恐怖を伴うと思います。そういう勇気を持てない理由は,幼児のときに母親を恐れたのと同じ心で恐れるからといえるでしょう。幼いときに大きな否定的感情を体験すると,自我は無力なままで,いつまでも成長できなくなることがあるのです。恐怖心の底にある怒りが激発するような事態には,自我はとうてい耐えられないと感じるのです。鍵を握るのは自我の強さです。治療者に助けられて,自我が徐々に力をつけていくことができるかどうかです。
人は何ものかに依存しつつ存在しています。
中には死に依存する人さえあります。いざとなれば死ねばいいと思いつつ現実に耐えている人は,決して珍しくはありません。このタイプの人は,自分自身を引き受ける覚悟を持てないのです。誰かの助けは欲しいと思っても,自分の力で生きていくのは途方もないことのように感じられるのです。
一部のうつ病は薬が奏効して比較的短期間に治癒にいたります。この場合は外科医のような治療ということになります。しかし,うつ病といっても個々に背景が違います。単純なうつ病は,薬によっていわば体質が改善され,治癒にいたるのですが,心の病気は,一般に性格の傾向と切り離して考えることはできません。そしてそれに関連して,人生問題を抜きにして考えることはできません。
生きるということの反面に,死の問題があります。治療者に,’治してほしい’と思い,自分の問題として捉えることができない人の場合には,背景にこの問題があるかもしれません。何故なら,引き受ける精神がそもそも薄弱であるとすれば,それは幼児的な依存する自我の下にあるといえるだろうからです。自己と人生とを自ら引き受ける意志を持つことができなかったのは,無意識的にであれ死の恐怖にさらされているために,他に取りすがるのを止められないのでしょう。そういうときは,治療は難航します。