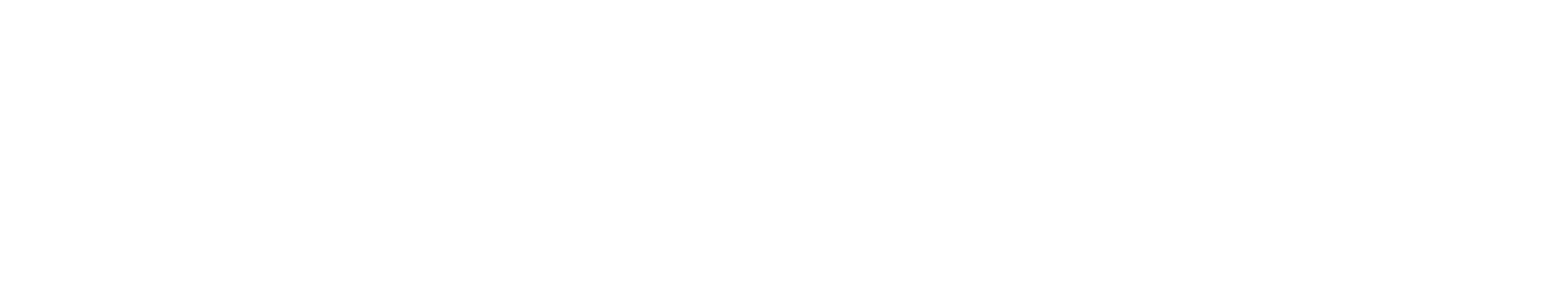院長 ご挨拶
Ⅰ 略歴
- 北海道立旭川東高校卒
- 東京大学医学部医学科卒
- 同大学病院神経科で研修。
- 医局長を経て、川崎市社会復帰医療センターに奉職。
- 1997年4月 現在地で開業
Ⅱ 私の履歴書
私の履歴書 1
私が産まれたのは、北海道旭川市の郊外です。
父親が教師だったので、田舎周りの転校が繰り返されました。
私は転校が好きでした。
新しいところに行けば、新しい出会いが待っているかもしれないからです。
幼い時代、ひととの関係がうまくいきませんでした。
幼いこころが、孤独に悩まされていました。
産まれつきの性格の問題もあるでしょうが、私への母親の愛情が薄かったことも、その理由です。
母親自身は人づき合いを好む性格です。
姉がふたり、兄がひとり、妹がひとりの五人きょうだいでしたが、母親の愛情のランキングでは私が最下位でした。
人間関係の原点にあるのは母親です。
幼いときから、母親に愛されなかった私はひととの関係で苦労しました。
それが人との関係に苦労した主な理由だと思っています。
もっとも、そうした経験が「ひとの気持ちが分かる」理由にもなっていると思っています。
そして、精神科医につながる理由にもなっているように思います。
母親の立場に立てば、やむを得ない事情もありました。
幼い妹が先天性の心臓弁膜症だったからです。
その妹に母親は、かかり切りでした。
妹は、5歳のときに亡くなりました。
幼い娘にこころが奪われている母親にとって、私はウルサイだけの存在でした。
しかし、子供である私としては、母親の愛情を要求する理由があります。
私をこの世にもたらした母親への不満から、しばしば、街角に立って大きな声で泣き叫びました。
どこかで仲間と遊んでいるに違いない母親を、「ひどい母親である」と世間に知らしめる意図がありました。
その声を聞きつけたのだろう母親が、遠くから小走りに帰って来る姿がしばしばありました。
その姿を見ながら、幼い私のことを気にかけたのではなく、お喋りをしていた友達への体裁だったに違いないと、こころのどこかで冷めた思いがありました。
そのことで母親が「眼を覚ます」こともありませんでした。
私の履歴書 2
こころには、いつも寒風が吹いていました。
見知らぬ所に行けば、新しい世界が開かれる秘かな期待がありました。
最初の転校は小学校4年生のときでした。
転校した先は山あいの「部落」でした。
子供の数が少ないので、ふた学年で一クラスの複式学級でした。
田んぼや畑に囲まれた小さな校舎でした。
その田舎の学校で、私はいっぱしの野球少年でした。
昼休みには、校庭で野球をして遊びました。
夜になると、地元の「名士」が集まってきました。
校長の住まい」が酒盛りの場になっていました。
酔っぱらった大人たちの様子を、部屋の片隅で見て過ごすのが習いでした。
私の履歴書 3
旭川市の高校に入学しました。
田舎で育った私にとって、旭川市は憧れの都会でした。
都会に行けば、新しい世界が開かれる期待を持っておりました。
しかし、高校に入学して間もなく、手ひどい洗礼を受けました。
入学して間もないころに、「実力試験」がありました。
成績順に、100番目までの名前が廊下に張り出されました。
そこに、私の名前がありませんでした。
それは、さすがにショッキングな出来事でした。
プライドが砕け散る想いがしました。
人生の坂道を転げ落ちるような思いでした。
それでも、一方で、巻き返しの思いが芽生えてもいたのを覚えています。
内心には、大学は東大という想いがひそかに立ち上がっていました。
当時の私には、東大だけがキラ星のように光って見えていました。
そこに入ることが、私の社会的自己を獲得する唯一の途に思われました。
現実には、卒業するまで「無名」のままでしたが。
東京に出て予備校に入りました。
そこでは「実力試験」が毎週ありました。
成績順に20人の名前が張り出されました。
その名簿には、聞きなれていた都内の有名校の名前が並んでいました。
それが身近にあることが励みになりました。
やがて、私の名前もそこに載るようになりました。
私の履歴書 4
一年の浪人生活を経て、目的の大学に入ることができました。
最初の2年間は教養学部でした。
何をするでもなく、無駄に時間が過ぎて行きました。
ボンヤリ過ごすのが、私のサガのようでもありました。
3年に上がるときに、専門学部を選ぶことになります。
しかし、行きたいところがありません。
成績がよければ、まだしも選びようもありましたが、成績がふるいませんでした。
そういう中で、医学部だけが選抜試験を行っていることに気がつきました。
他の学部とは違って、普段の成績とは無関係に、試験に受かれば入ることができました。
それをするしかありませんでした。
何とか医学生になりました。
そして4年間が過ぎて、医局を選ばなければならない時がきました。
しかし、行きたいところがありません。
そもそもが、医者になりたいわけでもありませんでした。
私の履歴書 5
ある役所に入ることになりました。
しかし、役人になりたかったわけではありません。
顰蹙を買うでしょうが、覗いてみようと思いました。
差し当たりの繋ぎの場、という想いでした。
最初から、3年で辞めると決めていました。
3年が過ぎて辞表を出したとき、意外なことに慰留されました。
バラ色の将来を語り聞かされました。
しかし、無能な役人のままで、そこに居座る意味はありませんでした。
私の履歴書 6
ある民間の精神病院の募集に応じました。
そこで数年間を過ごしました。
精神科医としてやっていくには、そのままではまずいか、と思うようになりました。
そこで仕事をしているうちに、精神科医としての自分に、あるべき姿を見たような気がしました。
母校の精神科教室の教授にお願いして、入局させていただくことになりました。
その教室には自由の気風がありました。
居れていただいで良かったと思いました。
やがて、医局長になりました。
しばらく経って、場所ふさぎになる、と思うようになりました。
「上に行くつもり」がなかったからです。
「外に出る」ことにしました。
私の履歴書 7
ある「医療センター」に職を得ました。
そこの施設長は、「患者思い」と聞いていました。
しばらく経って、施設の全体を巻き込む騒ぎを引き起こす事態になりました。
受け持ちの患者さん(Aさん)をめぐってのことでした。
Aさんに、職員に恐怖心を与える振る舞いがあったからです。
入院させよ、という騒ぎになりました。
しかし、私はそれに従う気にはなれませんでした。
入院は、自由の具体的な拘束です。
ひとの自由を拘束するのは、よくよくのことです。
Aさん自身が同意しないかぎり、入院させるわけにはいきません。
Aさんの代理人でもある私としては、下手な妥協は許されない問題でした。
数人のパラメディカルの職員の協力を得て、Aさんを「地域で支える」ことになりました。
日常の仕事が終わってから「現地」にかけつける、といった日々がつづきました。
ある夜、10時ごろに病院に帰ると、5人の医局員が待ち構えていました。
医局は、私とは異なる大学の出身者で固められていました。
私は異邦人の感じを味わっていました。
それらの人たちに、私の「愚行」をやめるように説得されました。
私には聞く耳がありませんでした。
組織としては厄介な人間だったと思います。
しかし、私としても、組織のいいなりになる理由がありませんでした。
しかしながら、ほどなく、Aさんがして欲しくないことをしてしまいました。
やむなく、「我われの手」で入院させる羽目になりました。
ことここに至っては、その職場に居座る鉄面皮はありませんでした。
私の履歴書 8
行き場を失って、医療刑務所に職を求めました。
そこは入ってみると、意外なほどの自由がありました。
それが、医療刑務所での生活が長くなった主な理由でした。
しかし、やがて、次を考えなければならない時がきました。
その居場所が捨てがたかったもう一つの理由は、当時の所長にありました。
見識のある所長でした。
共に居たいひとでした。
その所長の定年退職の日が近づきました。
所長が居ない場所には、居る意味がありません。
私も身の振り方を考える必要がありました。
ふと思いついたのが「開業」です。
それまでは、開業医というアイデアが浮かんだことはありませんでした。
思いついてみると、そのアイデアに魅了されました。
組織やひとに気を遣うことがなく、自分の責任において自由に仕事が出来る!
仕事と自由の両立!
そういう想念が頭をよぎりました。
頭に浮かんだその思いは、自由の極地のように感じられました。
開業資金の準備がありません。
自宅を処分してそれにあてました。
何の躊躇も不安もありませんでした。
いそいそとことを運んでおりました。
私の履歴書 9
開業医の身分は、なってみるとこの上もないものでした。
誰に気を遣うこともなく、すべてが自由に感じられました。
開放感がありました。
ここで経験した問題がふたつ思い出されます。
開業して間もなく、未知の男性から電話がかかってきました。
「医療刑務所に居たそうですが、・・・」と、電話口で、いきなりいわれました。
「精神科医はほかにも居るのか、内科や外科の患者も診るのか」といったことを訊かれました。
まるで‘身体検査’です。
何のために、未知の人物にそうしたことを問いただされなければならないのか、と内心で思いました。
その人も、ふだんは、そうしたことを人にいうはずがありません。
それが、あろうことか、見知らぬ男に詰問されました。
別のあるとき、実際に受診していた患者さんが、「私のお母さんが何かを渡していると思いますが」といいます。
その口調には、「賄賂をもらっているだろう」といった響きがありました。
そして、「ここはヤバいから」といって去って行きました。
図らずも、「刑務所の医者」を、世間がどう見ているのかということを実地に経験しました。
私は幸いにして、社会的地位にはあまり関心がありません。
経済的な保証があれば、関心と必要があれば、そこに身を寄せることに躊躇はありません。
「世間の眼」を気にするタチではないので、受刑者も人間であるという当然のことを単に受け入れていました。
私の履歴書 10
医療刑務所に在籍していたころ、「キミの野心はどこにあるのかね」と、ある教授にいわれました。
そのときに何と答えたかは覚えていませんが、「地位より立場です」といいたいところです。
社会的なポジションである地位は、自我の外向性がつかさどっています。
そこでは、ひととの関係が最重要の課題です。
教授がいわれる意味は、「社会的地位をどう思っているのか」、といったことかと思われます。
社会的地位は、「ひとに認められる」ことに繋がります。
我われ人間は、社会的地位がないわけにはいきません。
自我と呼ばれているものは無意識界を拠り処にすることで、生命的エネルギーを獲得します。
しかし、それが全てではありません。
むしろ、「ひとに認められる」よりも、「自分自身に認められる」ことの方が重要です。
「自分自身」というのは、自我の真の拠り所です。
他者は「私」のことを知っているというより、むしろ何も知りません。
そして、同様に、「私」自身も「私」のことを知っているより、むしろ何も知らないのが実情です。
そういう中で、自我が拠り処にしている無意識界は、自我の仕事の「すべて」を視ています。
自我の仕事をすべて視ている無意識界の眼は、真に畏れるべきものです。
人間のシンボルといわれている自我は、それぞれの「私」である自己の存在を造り出します。
無意識界を絶対の拠り所にしている自我は、「ヒトの眼」よりも、較べようもなく「無意識界の眼」に注意を払わなければなりません。
それを踏まえていえば、他者に気を取られていると、場合によっては無意識界から見離されることにもなりかねません。
私の履歴書 11
水曜日の休診日には、キックボクシングの個人レッスンを受けています。
電車を乗り継いで小一時間のところにあるジムに、2014年の4月から通っています。
先生は、総合格闘技の元世界チャンピオンです。
それに加えて、2021年の3月から柔道も教わっています。
格闘技への関心が強いのは、これまでの人生を徒手空拳で戦ってきたという思いがあり、それと繋がっているように思います。
私には完全性への欲求があります。
その分、幼児性と遊び心とが少なからずあります。
そのおかげで、体力と気力の強化と、気分転換が図られているので、休診日は貴重な時間です。
Ⅲ 精神医療の問題
執筆中 近日公開予定